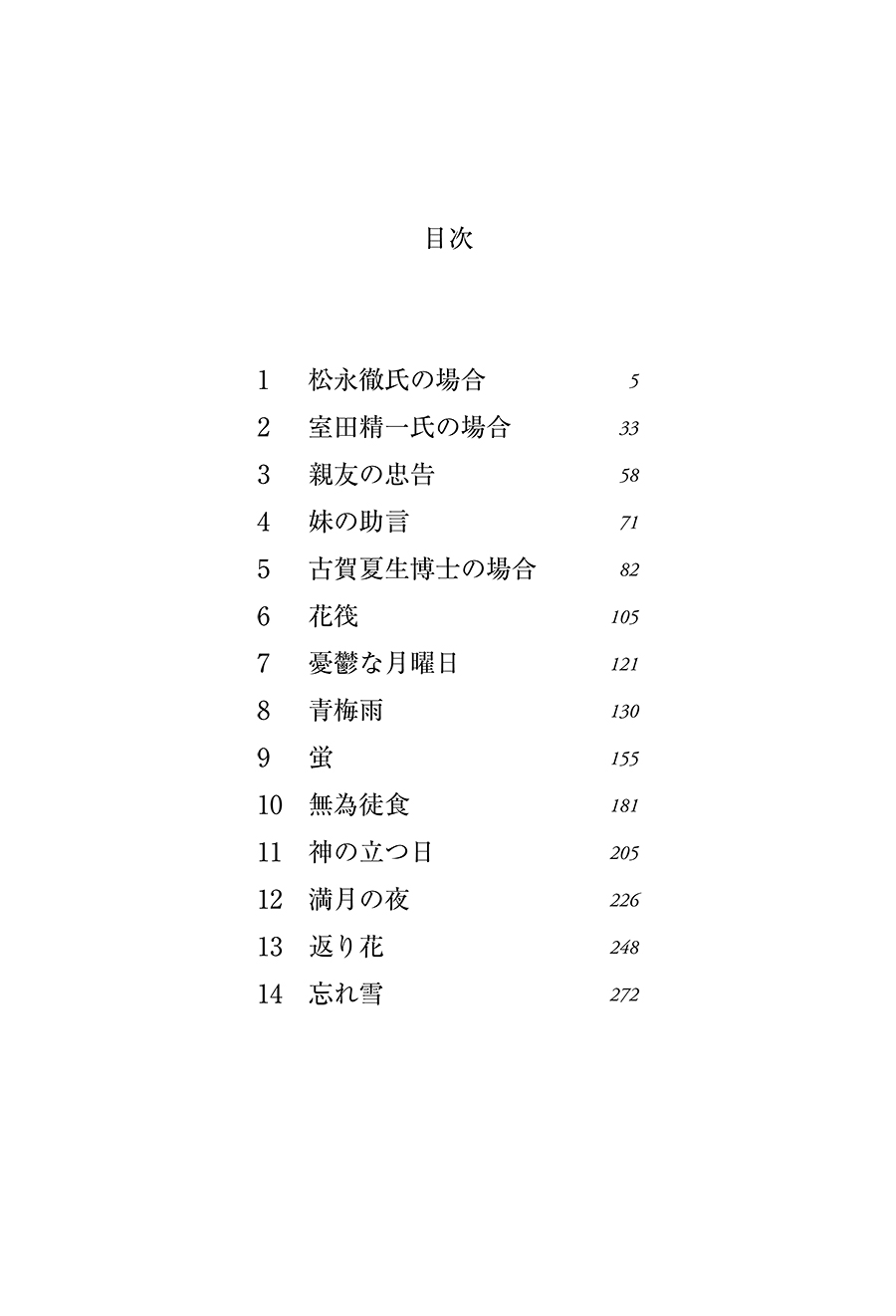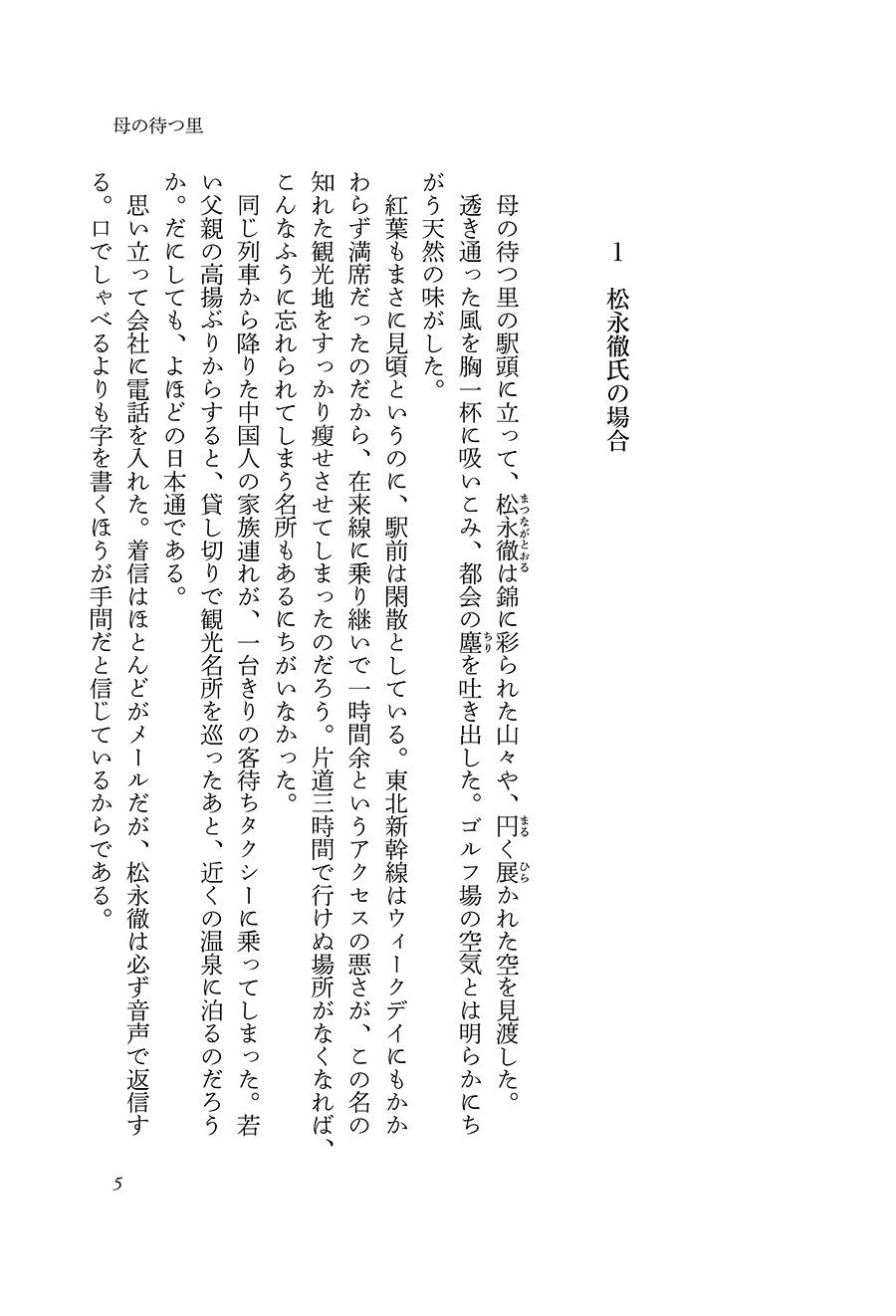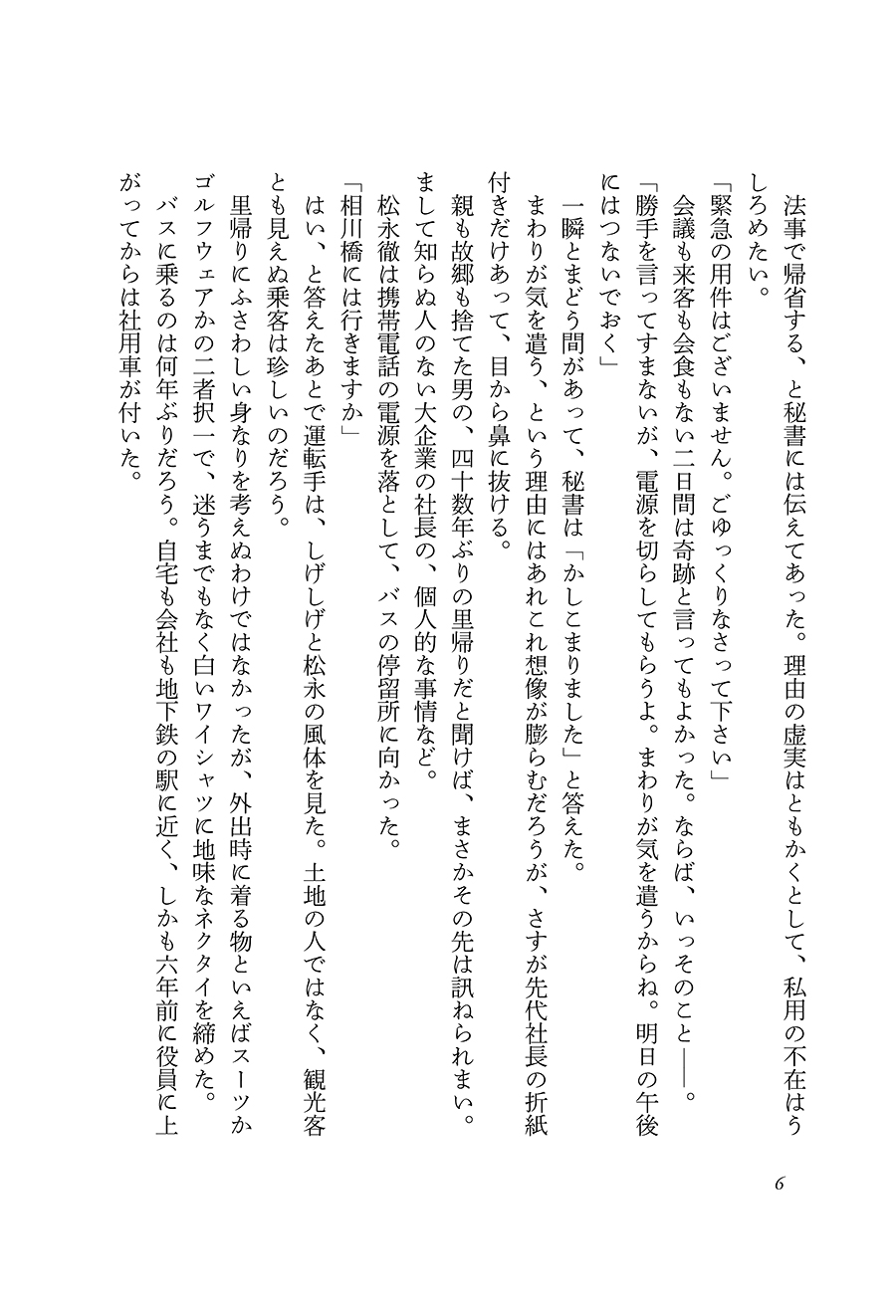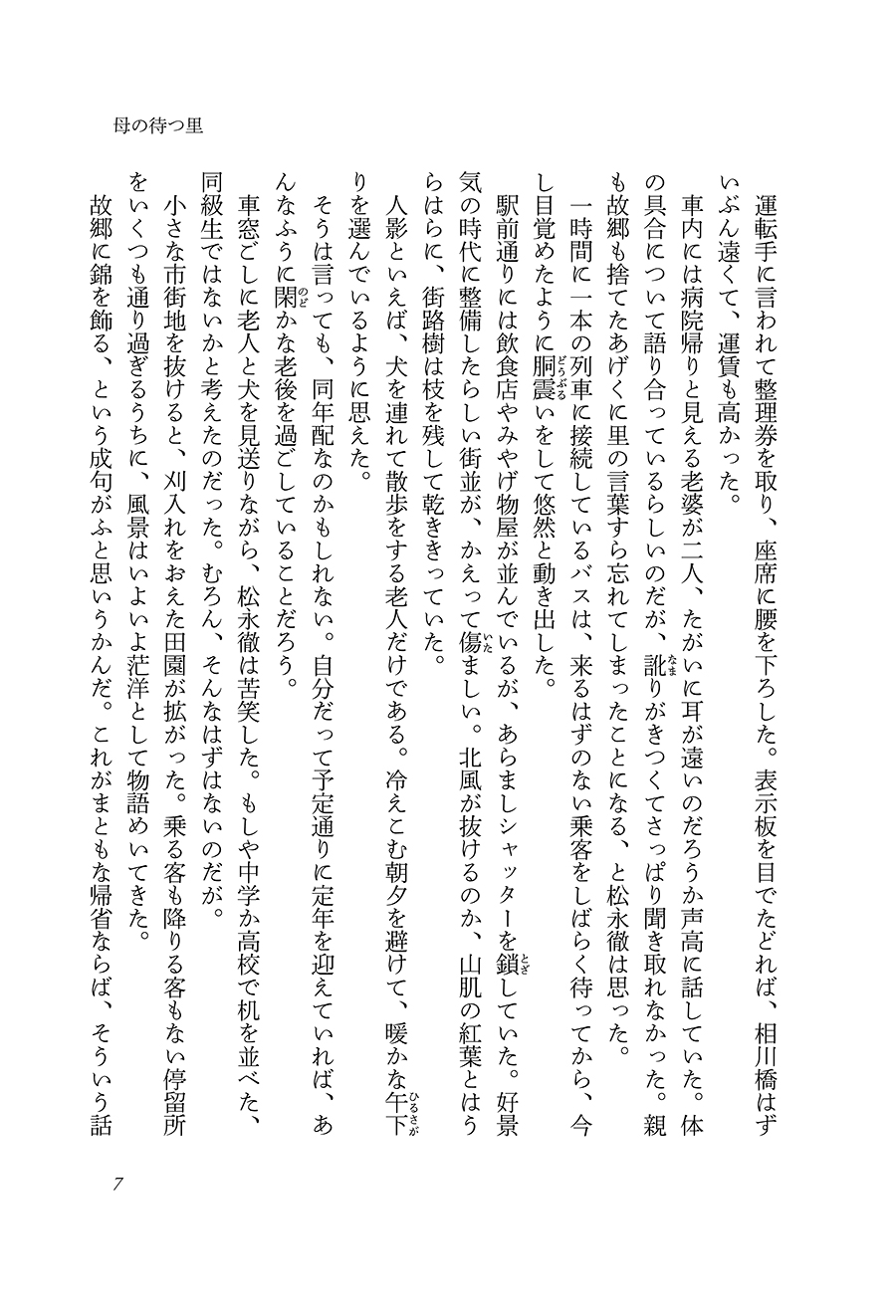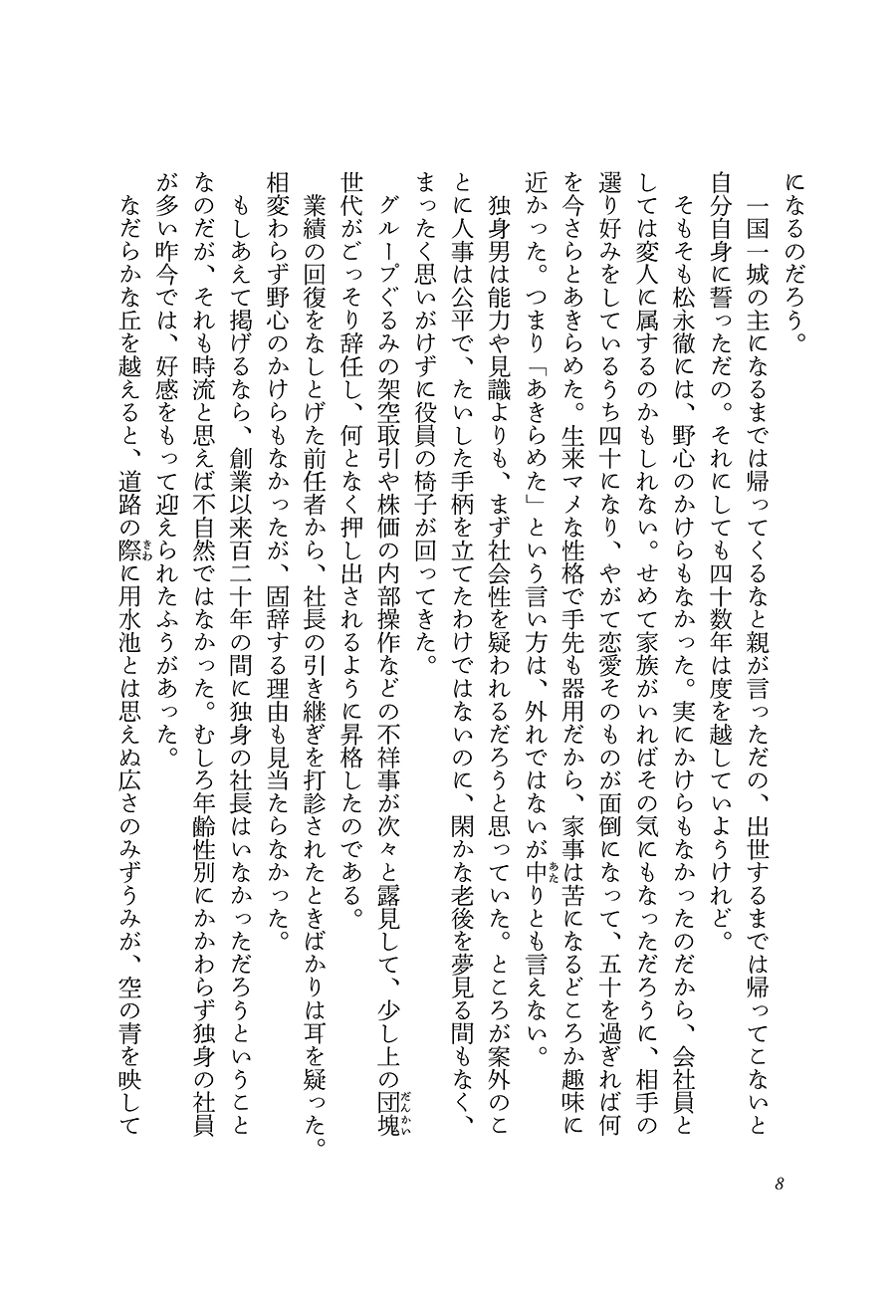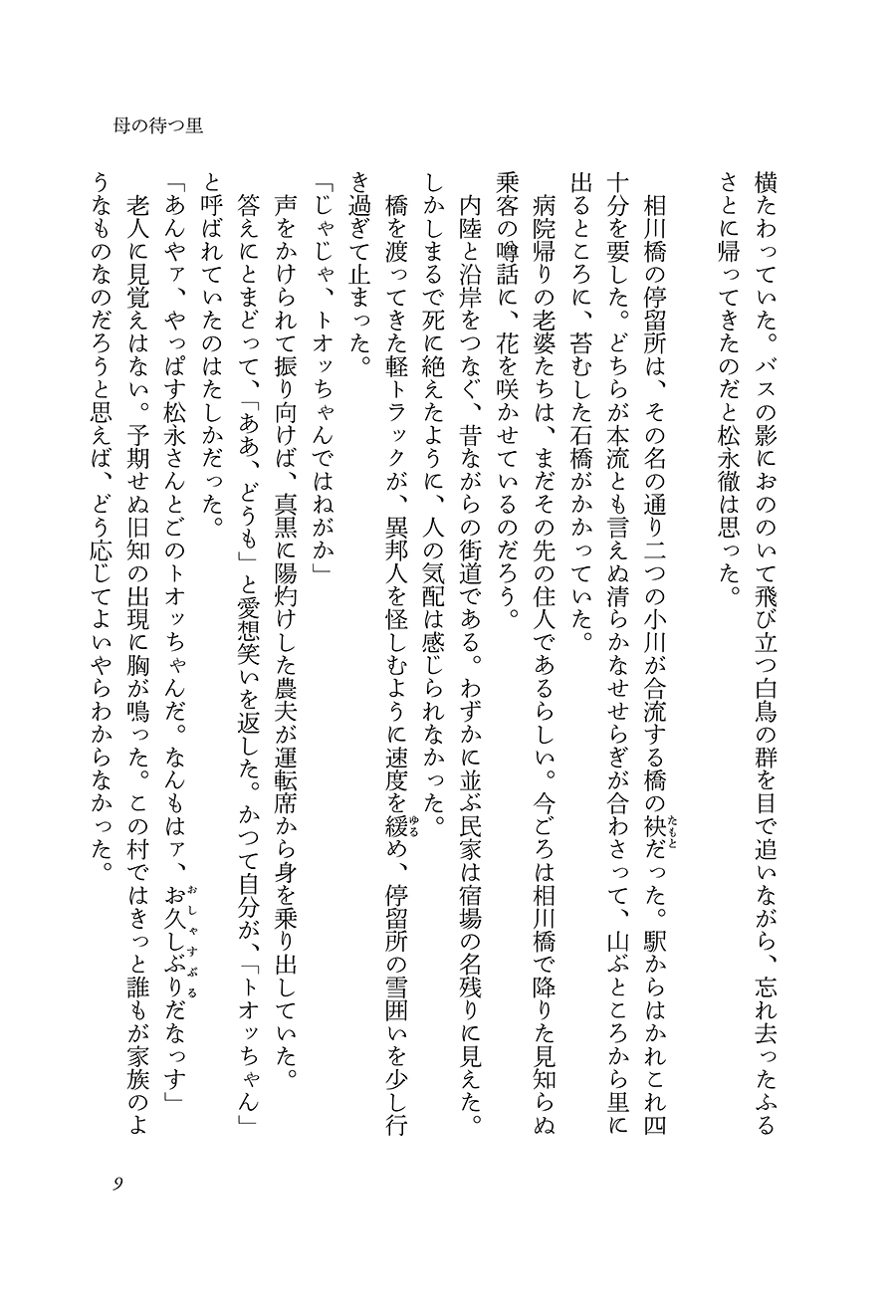1 松永徹氏の場合
母の待つ里の駅頭に立って、
透き通った風を胸一杯に吸いこみ、都会の
紅葉もまさに見頃というのに、駅前は閑散としている。東北新幹線はウィークデイにもかかわらず満席だったのだから、在来線に乗り継いで一時間余というアクセスの悪さが、この名の知れた観光地をすっかり痩せさせてしまったのだろう。片道三時間で行けぬ場所がなくなれば、こんなふうに忘れられてしまう名所もあるにちがいなかった。

同じ列車から降りた中国人の家族連れが、一台きりの客待ちタクシーに乗ってしまった。若い父親の高揚ぶりからすると、貸し切りで観光名所を巡ったあと、近くの温泉に泊るのだろうか。だにしても、よほどの日本通である。
思い立って会社に電話を入れた。着信はほとんどがメールだが、松永徹は必ず音声で返信する。口でしゃべるよりも字を書くほうが手間だと信じているからである。
法事で帰省する、と秘書には伝えてあった。理由の虚実はともかくとして、私用の不在はうしろめたい。
「緊急の用件はございません。ごゆっくりなさって下さい」
会議も来客も会食もない二日間は奇跡と言ってもよかった。ならば、いっそのこと――。
「勝手を言ってすまないが、電源を切らしてもらうよ。まわりが気を遣うからね。明日の午後にはつないでおく」
一瞬とまどう間があって、秘書は「かしこまりました」と答えた。
まわりが気を遣う、という理由にはあれこれ想像が膨らむだろうが、さすが先代社長の折紙付きだけあって、目から鼻に抜ける。
親も故郷も捨てた男の、四十数年ぶりの里帰りだと聞けば、まさかその先は訊ねられまい。まして知らぬ人のない大企業の社長の、個人的な事情など。
松永徹は携帯電話の電源を落として、バスの停留所に向かった。
「相川橋には行きますか」
はい、と答えたあとで運転手は、しげしげと松永の風体を見た。土地の人ではなく、観光客とも見えぬ乗客は珍しいのだろう。
里帰りにふさわしい身なりを考えぬわけではなかったが、外出時に着る物といえばスーツかゴルフウェアかの二者択一で、迷うまでもなく白いワイシャツに地味なネクタイを締めた。
バスに乗るのは何年ぶりだろう。自宅も会社も地下鉄の駅に近く、しかも六年前に役員に上がってからは社用車が付いた。
運転手に言われて整理券を取り、座席に腰を下ろした。表示板を目でたどれば、相川橋はずいぶん遠くて、運賃も高かった。
車内には病院帰りと見える老婆が二人、たがいに耳が遠いのだろうか声高に話していた。体の具合について語り合っているらしいのだが、
一時間に一本の列車に接続しているバスは、来るはずのない乗客をしばらく待ってから、今し目覚めたように
駅前通りには飲食店やみやげ物屋が並んでいるが、あらましシャッターを
人影といえば、犬を連れて散歩をする老人だけである。冷えこむ朝夕を避けて、暖かな
そうは言っても、同年配なのかもしれない。自分だって予定通りに定年を迎えていれば、あんなふうに
車窓ごしに老人と犬を見送りながら、松永徹は苦笑した。もしや中学か高校で机を並べた、同級生ではないかと考えたのだった。むろん、そんなはずはないのだが。
小さな市街地を抜けると、刈入れをおえた田園が拡がった。乗る客も降りる客もない停留所をいくつも通り過ぎるうちに、風景はいよいよ茫洋として物語めいてきた。
故郷に錦を飾る、という成句がふと思いうかんだ。これがまともな帰省ならば、そういう話になるのだろう。
一国一城の主になるまでは帰ってくるなと親が言っただの、出世するまでは帰ってこないと自分自身に誓っただの。それにしても四十数年は度を越していようけれど。
そもそも松永徹には、野心のかけらもなかった。実にかけらもなかったのだから、会社員としては変人に属するのかもしれない。せめて家族がいればその気にもなっただろうに、相手の選り好みをしているうち四十になり、やがて恋愛そのものが面倒になって、五十を過ぎれば何を今さらとあきらめた。生来マメな性格で手先も器用だから、家事は苦になるどころか趣味に近かった。つまり「あきらめた」という言い方は、外れではないが
独身男は能力や見識よりも、まず社会性を疑われるだろうと思っていた。ところが案外のことに人事は公平で、たいした手柄を立てたわけではないのに、閑かな老後を夢見る間もなく、まったく思いがけずに役員の椅子が回ってきた。
グループぐるみの架空取引や株価の内部操作などの不祥事が次々と露見して、少し上の
業績の回復をなしとげた前任者から、社長の引き継ぎを打診されたときばかりは耳を疑った。相変わらず野心のかけらもなかったが、固辞する理由も見当たらなかった。
もしあえて掲げるなら、創業以来百二十年の間に独身の社長はいなかっただろうということなのだが、それも時流と思えば不自然ではなかった。むしろ年齢性別にかかわらず独身の社員が多い昨今では、好感をもって迎えられたふうがあった。
なだらかな丘を越えると、道路の
相川橋の停留所は、その名の通り二つの小川が合流する橋の
病院帰りの老婆たちは、まだその先の住人であるらしい。今ごろは相川橋で降りた見知らぬ乗客の噂話に、花を咲かせているのだろう。
内陸と沿岸をつなぐ、昔ながらの街道である。わずかに並ぶ民家は宿場の名残りに見えた。しかしまるで死に絶えたように、人の気配は感じられなかった。
橋を渡ってきた軽トラックが、異邦人を怪しむように速度を
「じゃじゃ、トオッちゃんではねがか」
声をかけられて振り向けば、真黒に陽灼けした農夫が運転席から身を乗り出していた。
答えにとまどって、「ああ、どうも」と愛想笑いを返した。かつて自分が、「トオッちゃん」と呼ばれていたのはたしかだった。
「あんやァ、やっぱす松永さんとごのトオッちゃんだ。なんもはァ、
老人に見覚えはない。予期せぬ旧知の出現に胸が鳴った。この村ではきっと誰もが家族のようなものなのだろうと思えば、どう応じてよいやらわからなかった。
「バスに乗りおぐれた
「四十年ぶりですよ」と、松永徹は憮然として
老人は松永徹の顔色を窺ってから、窓を閉めかけて言った。
「お
松永徹はあたりを見渡して答えた。
「あやしいもんです」
「んだろうなあ。なぐなった
しまいには親不孝を
街道の北には山が迫っており、緩やかな
思い出すか。いや、やはり思い出せない。街道を少し戻ると、
石垣が高く組まれているのは、洪水の際の避難場所だったのだろうか。そう思って南に目を向ければ、川の行手には堤防が築かれ、左右は一面の低い
教えられた通りに、
何もかも忘れ去ってしまったけれど、松永徹が生まれ育った家であるらしい。
庭続きの小さな畑から母が立ち上がった。
「きたが、きたが、けえってきたが」
言葉の用意はなかった。松永徹は午後の光の中に
こんな人だったろうか。だが、四十年ぶりの帰郷を祝福してくれるのだから、人ちがいではあるまい。
まるで天から降り落ちてきたようなおふくろだと、松永徹は思った。
「道さ迷わねがったか」
「ちょうど通りすがった人に教えていただきました」
母は南に下る小径に
「何時のバスだかわがらねがったがら。迎えにも行がねで、お
古ぼけた毛糸の帽子を脱いで、母はていねいに頭を下げた。小さな人が余計に小さくなった。泥まみれの軍手には、掘り出したばかりの大根が握られたままだった。
居ても立ってもいられず、かと言ってバス停で迎える気にもなれずに、街道を見おろす畑に出ていたのだろうか。
手にした大根を恥じるように抱えて母は言った。
「もうはァ、八十六にもなって体も思うように動かねがら、下の
母の使う里言葉は、バスの中の老婆たちや家のありかを教えてくれた農夫のそれよりも、ずっとわかりやすかった。耳が慣れてきたのか、それとも母が気遣ってくれているのだろうか。
「さて、こんたなとごで立ち話も何だ、まんず、お
母が
「トオル。おめはん、
「いえ、まだです。乗り継ぎのとき食いそびれてしまって」
太陽と風が
「だば、ひっつみばこしェるべ。おめはんの好物だべァ」
それがどのような食べ物なのか、松永徹には思い及ばなかった。だが、好物なのだと母は言っている。
「それじゃ、遠慮なくごちそうになります」
母がスーツの袖をつんと引いた。
「なあ、トオル。そんたな他人行儀の物言いはやめてけろ。東京でなんぼ出世すたって、ここはおめの生まれた
そう言って見上げる母の肩を、松永徹は思わず抱き寄せた。
曲がり家。馬とともに暮らした、このあたりの民家建築だということぐらいは知っている。
玄関と呼ぶにはあまりに無造作な入口には、紛れもない「松永」の表札がかかっていた。
忘れたのか、何もかも。ならばどうして、こんなにも美しいふるさとと、やさしい母と
土間に足を踏み入れて、松永徹は高い天井を見上げた。茅葺きの大屋根を無数の木組が支えていた。
「なじょした、トオル。さあさ、中さ
生まれ育った家が珍しいわけはないのだ。松永徹はいっこうに戻らぬ記憶をそらとぼけて、導かれるまま母屋に入った。
「年寄りの独り暮らしにァ広すぎるだども、ここらの家はどごだりかごだり同じよなものだで」
たしかにこの広さは、民家というより屋敷である。母屋の土間だけでも二十畳ばかりもあって、上がりかまちの先には座敷が続いていた。
「どうだべ、トオル。昔のまんまじゃろ」
このあたりの家はどこも同じだと母は言ったが、それは年寄りばかりの村になってしまったという意味にちがいなかった。行方知れずになった一人息子がいつ帰ってきてもいいように、母は家の
そう思うと申し分けなさがつのって、靴を脱ぐことすらためらわれた。
「俺は、親不孝者だな」
母がかたわらに寄り添ってくれた。
「そんたなことはねえて。おめは大学ば出て、立派な会社さ入えって、もうはァこの上はねえて社長さんにまで出世すただど。お
松永徹はたまらずに顔を被った。捨ててきたものが多すぎる。忘れてしまったことが多すぎる。これほど非情で、あとさきかまわぬ人生ならば、努力も能力も関係なく誰だって成功できるはずだ。
「なんだけえな、大の男がべそべそすて、みっだくねえど。おらが泣ぐだばまだすも、ほれ、すっかどせえ、トオル」
母の腰手拭は陽なたの匂いがした。
「おどさん、か」
仏壇に線香を上げて、松永徹はひとりごちた。
モノクロームの遺影に見覚えはない。仏間の鴨居には祖父母と曽祖父母らしき人々に並んで、軍服姿の若者の写真があった。戦死した叔父だろうか。
目に憶えがないのなら、音や匂いはどうだろうと思い、松永徹は合掌したまま耳をそばだて、鼻から息を吸いこんだ。
鳥の
土と森の匂い。竈から漂い出る煙。線香と仏花の香り。母の
「トオルゥ、こっちゃこォ。腹へったべ」
六畳と八畳の座敷が四間、それぞれを隔てているのは
そう思いはしても、記憶にあるのはこの家ではない。松永徹の若かったころには、こうした間取りの家がいくらでもあった。たとえば、ビジネスホテルが普及する以前の商人宿。たとえば、スキー場や海辺にペンションが登場する前の民宿。
だから松永徹にとっては、
南向きの八畳間は居間であろうか。中央に囲炉裏が切られており、そのまわりだけがつややかな板敷になっていた。

「電話の一本もけれァ、こしェておいたんだが。さあ、たんと
大きな椀に
障子ごしに柔らかな午後の光が射し、
「ひっつみ」
「んだ、ひっつみ」
団子を指で引っ張って摘まむから、ひっつみなのだろうか。一口
二人はしばらく黙りこくって遅い昼食を摂った。母は
「お名前は」
熱い汁を啜りながら、さりげなく訊ねた。腹が落ちつくといくらか正気を取り戻したのだった。
「親の名前さ訊ぐ倅がどこさおる」
母は笑って答えた。
「いえ、忘れたわけじゃないんです。お名前ぐらいは――」
「そんたな他人行儀の物言いはやめてけろ」
松永徹は炉端に椀と箸を置き、改めて訊ねた。
「では、親不孝な息子が生まれ故郷を捨てたうえに、母親の名前まで忘れてしまったと思って下さい」
「ふうん」と母は
「もういっぺん
咳払いをして松永徹は言い直した。
「俺は四十年も勝手気ままに暮らして、この家もおふくろの名前も忘れちまったんだ。教えてくれよ」
今度は「ふん」と肯いてくれた。
「ちよ。松永ちよ」
「漢字の千代かな」
「うんにゃ。平仮名であんす。
「いつごろの話だろう」
「んだなァ。終戦の翌年のこって、駅までは馬ッこに引かれでな、汽車さ乗ってった」
母の
「おめ、うめえどがまずえどが、
「うまいよ。声をなくすぐらい」
「東京にァうめえものがなんぼでもあるすけ、お世辞じゃろの」
「そんなことはないって」
差し出した椀に、母はおかわりを盛ってくれた。
「のう、トオル。めんどくしェ話はそこまでにすてけろ。おらはおめの顔ば見るこどができただけで
母は松永徹の口を封じた。
鳥が囀り、薪が爆ぜる。誰もおらず、何もないところに来てしまったと、松永徹は思った。
「おめ、なじょすて嫁ッこ取らねんだ」
窓ごしに母が訊ねた。母屋から離れた裏庭に風呂場があるのは、防火のためなのだろう。
「東京じゃあ珍しい話じゃないよ」
「
「いや、男も女も独身が多いんだ」
「はァ、わげがわがらねな」
とうの昔に姿を消した木製の湯舟が、ここでは現役である。よほど手入れがよくてもこうまでは
母は風呂場の外で薪を
「もういいよ。熱いくらいだ」
「だば、おらも一緒に入えるべ」
エッ、と松永徹は声を出して驚いた。
「ハハッ。たまげるでねえ、冗談だわ」
何がそんなにおかしいのか、母はしばらく笑っていた。
そのうち枯葉を踏む足音が外を回って、たてつけの悪い引戸が開けられた。
「冗談だろ」
「んだがら、冗談だてば。
「いいって」
「良ぐねど。男やもめだば、背中も
湯気の中に顔をつき入れて、母はまたケタケタと笑った。
松永徹には子を持つ親の気持ちなどわからないが、ここは
松永徹は目を
「あややァ、とても六十過ぎた
特別のこととは、ジムだのエステだのを指しているのだろうか。居間にはひどく旧式のテレビが置かれていたから、当たり前の情報は入るのだろう。
世間の出来事を何もかも承知の上で、母が時間を止めているのだとしたら、それはとても幸福な暮らしだと松永徹は思った。
「一緒に入ってもいいよ」
母の手が止まった。
「ありがどがんす。だども、やっぱすお
「腹へったべ。じきに
「急がなくていいよ。ちびちび
土間の隅に湯沸器の付いた台所がある。竈には羽釜がかけられて、飯の炊き上がる匂いがした。

バスの窓から見た景色から察すれば、新米にちがいない。最も出来のいい米は、どこでも地元で費消すると聞いた。だとすると、きっとびっくりするような飯が食えるのだろう。
熾火は思いのほか暖かい。
面倒な話はしてくれるなと釘を刺されてから、松永徹の口は重くなった。つまり、この家の事情や母の暮らしについて、話材にしてはならないのだ。すると、母からの問いかけに応じるほかはないのだが、たまに帰郷した息子は誰だってそんなものだろうと思えば、それはそれで居心地がいい。
そもそも独り暮らしには慣れ切っている。若い時分から会社帰りの付き合いは避けてきたし、今も接待や会食のない日はさっさと帰宅して、テレビを相手に晩酌する。
山の鳴る音が聴こえた。風が出てきたのだろうか、
「こんたな
よっこらしょ、といちいち唸り声を上げて、母は土間と炉端を往き来する。串を打たれた川魚が囲炉裏に立てられた。
「
「うんにゃ、
日頃の買物はどうしているのだろう。相川橋のバス停にも店らしい店はなかったと思う。
「
「エッ、運転するの」
「あのなはん、年寄ったら運転すてはならねだの、七十過ぎたら免許証の自主返納だのて、そんたなこつ、都会の理屈だじゃ。だれだりかれだり、口ば揃えて
おっしゃる通りである。やはりこの箱形のテレビは、母にさまざまの情報を伝えてくれているらしい。ただし、都市生活の見識が全国的に通用するわけではあるまい。そのあたり、地方局の番組が世論を補ってくれているのだろうか。
「よっこらしょ」
どんぶりに盛った野菜の煮付け。このごろこういうものが好きになったが、さすがに一人前を作る気にはなれない。かと言って、コンビニの惣菜を買うのもためらわれる。
「やあ、これは何よりだ」
「んだんだ。四十年ぶりでも味付けァ変わらねど。思い出してくなんせや」
里芋を口に含んで、奥の知れぬ豊饒な味に溜息が洩れた。おふくろの味というよりも、この曲がり家の竈を代々守ってきた数知れぬ母たちが、
「なじょすた、トオル。口に合わねが」
とっさには答えられず、煙の抜ける天井を見上げた。
国内最大のシェアを誇り、世界規模のマーケットを持つ社業に、卑しさのようなものを感じたのだった。
「いや、うまい。こんなうまいものは初めて食べた」
母がほっと息をついた。
「初めてなわげあるめえ。どの口が
何という贅沢な夕食だろう。考えるまでもなく、「ごはん」と松永徹は言った。
夜が広い。
際限なく。
山の音も虫の
純潔の孤独が記憶どころかあらゆる想念まで奪ってしまうことを松永徹は知った。頭も心もからっぽだった。
日ごろ使い慣れた羽毛蒲団などではない、ぎっしりと綿の詰まった重みがここちよい。目に見えぬ力に護られているように思える。
こんな夜を重ねるうちに、やがてこの山里も深い雪に埋もれるのだろう。
「おお、寒ぶ寒ぶ。
座敷を隔てる板戸の向こうで、寝床に潜りこむ母の気配がした。
「何だよ。沸かさなかったのか」
「
ハラスメントどころか虐待だが、男を立てるならわしと火の用心を全うするなら、そういう話になるのだろう。
「一緒に寝ようか」
小さな母が、硬い蒲団の中でいっそうちぢこまっていると思えば、それも冗談ではなかった。
「なんぼなだって、ええ年の倅に
そう言って母はくぐもった声で笑った。
「
松永徹は
「おめ、眠れねがか」
「いや、眠るのがもったいなくって」
「
コンクリートで
「んだば、寝物語ば聞がせてやるべ。
答えあぐねていると、母は「どだや」と水を向けた。
「話の途中で眠っちまうかもしれないが」
「ほいでええよ。寝物語だべさ」
「なら、聞がせてけろ」
松永徹は母の口ぶりを真似て話をせがんだ。

むかしむかし、あったずもな。
相川宿さ
慈恩院の
ハテ、檀家でもねえし、遠ぐの長者殿の
すたっけえ、ちょこっと目ェはなしたすきに、もうは庚申様のあだりにァ影もかたちもねぐなっていたんだとさ。
宿場の衆に聞いたとごろが、たすかに婆様を見かけた人がなんぼもあった。そごらを
んだば、年食ってほろけたどこぞの御新造が、道さ迷ったんだか。そだったら探さねばならねと皆して出かかったんだが、話を聞いでお出えった村一番の
のう、トオル――そこで爺様が、なぬさ言ったがわがるが。
聞いたとたんに、だれだりかれだり悲鳴ば上げて逃げ出したんだど。
「やめるもしェ。あの婆様はの、娘ッこの時分に神隠しにあったんだじゃ。なんたら、
婆様がどっからお出えって、どこさへ
今でもこごらの
どんどはれ。
「寝だか、トオル」
松永徹は答えなかった。
「んだば、おやすみなんしェ」
寝物語の分だけわずかに開いていた板戸が、そっと鎖された。よもやと思うほどじきに、母の寝息が伝わってきた。
山家暮らしに飽きて、卒然と姿を消す若者は昔からいたと思う。間引きや
寝物語にかこつけて、自分もそう思い定めていたのだと、母は言ったのだろうか。少くとも松永徹には、その話が
神隠しにあった子供が年老いて、ふと里心がついたとする。だが、いざ足を向けてみれば、過ぎにし歳月の重みが、懐旧の情を圧し潰してしまうのではなかろうか。そして、すべてを忘れたことにする。ふるさとの山河も生まれ育った家のたたずまいも、母の顔すらも。
茫々たる夜の広さが、実はあるべきはずのものをなくした空洞であったことを、松永徹は知った。
「ようやっと
上がりかまちにちょこなんと座って、母は倅を見送った。
「またきてもいいですか」
「ええがって、おめの家でねか。だども、おらだってハァこんたな齢だがら、また何年も先の話ではわがねど」
母の用意してくれたみやげは、新米一升と炉端で燻した沢庵漬。朝食の味噌汁をうまいとほめたら、三年仕込みだという手作りの豆味噌も、どっさり包んでくれた。
ぴんと張りつめた朝である。竈の煙が土間に縞紋様を描いていた。
新幹線は午過ぎだが、一刻もいたたまれぬ気分がまさった。軽トラックで駅まで送るという申し出は、さすがに遠慮した。すると、いくらか
一時間に一本のバスを乗り逃がしてはならない。重い荷物をぎっしりと詰めこんだ鞄を肩にかけて、松永徹は立ち上がった。
「のう、トオル。ゆんべの話は気にするでねど。思いつぐまんま
いくらか気持ちが楽になった。
「俺は神隠しにあったわけじゃないよ」
「んだんだ。だば、お
え、と松永徹は訊き返した。
「気をつけで
美しい別れの言葉だ。
「せめてお
「また次の機会にね」
ずいぶんないいぐさだと思いながら、松永徹は重ねて母の願いを拒んだ。きのうのうちから何度も、母は慈恩院の墓参りを口にしたが、さすがにそればかりは気が進まなかった。
「ありがどがんす。またお出ってくなんせ」
背中に声をかけられて振り返れば、母は板敷に小さく丸まって両手をつかえていた。
山々はきのうよりも朱を増したように見えた。
冷たい風が街道から吹き上がってきた。空はどんよりと濁って、今にも雪が舞い落ちてきそうだった。
まるで夢の中のように足が進まない。枯草に被われた坂道は
慈恩院の築地塀に沿って街道に行き当たると、きのうは気にも留めなかったが、なるほど寝物語の通り、苔むした庚申様があった。
ふと、辻にぼんやりと佇む白髪の老婆が胸にうかんだ。
上等の着物を着ていたのだと母は語った。聞き流していたものの、思えばそこは話の肝なのかもしれない。人買いに連れられて村を去ったのか、それとも奉公に出たまま帰らなかったのか、しかし娘はそののち恵まれて紬を着る身分になった。だからこそ失われたふるさとを訪ねる気にもなったのだろうが、人生の浮沈にかかわりなく時は流れるのだと、物語は諭しているとも思えた。
「あんやァ、トオッちゃん。
落葉を掃く手も休めずに、石段の上から老いた僧が言った。
ようやく夢から覚めれば、また夢の中だったような気がして、松永徹は溜息をついた。
「こごらも年寄りばかりになってしまってなァ、おらほの倅もこんたな寺を継ぐ気はねがら、ハテどやすべえと御本山に相談すてるんだ」
聞く耳はない。墓参りもせずに帰るつもりかと、責めてでもいるような口ぶりだった。
「バスが来ます」
松永徹は門前をやり過ごした。
「ちよさんたら、大喜びで墓さ掃除すてたんだがなァ」
「申しわけない。バスが来ました」
振り向いて手を振った。
「ありがどがんす。またお出ってくなんせ」
母と同じ文句を口にしながら、老いた住職は合掌した。
バスの乗客はきのうと同じ病院通いの老婆たちだった。
まさかとは思ったが、二人そろって「あやあや」とたまげたのだから、偶然にはちがいない。
「おはよがんすゥ」
見知らぬ人にも挨拶をするのは、あたりまえの習慣なのだろう。松永徹も会釈を返して、奥のシートに座った。
慈恩院の
べつだんの感慨はない。ただ、ふしぎな体験をしたのはたしかで、夢ではない証拠には、米だの味噌だの漬物だのをぎっしりと詰めた鞄が、かたわらに置かれている。
ふるさとの景色が過ぎてゆく。あるいはふるさとと信じた景色が。
バスはきのうと同様に、乗降客の絶えてない停留所を通り過ぎて走った。

松永徹は携帯電話の電源を入れて、シートの蔭に身を屈めた。
「ユナイテッドカード・プレミアムクラブ、
四桁、六桁、五桁。つごう十五ものカード番号を押す。面倒なことこのうえないが、「世界最高のステータス」を自負するからには、当然のセキュリティーとも言える。
「松永徹様。失礼ですがご本人様でらっしゃいますか」
「そうです」
「かしこまりました。では生年月日を承ります」
答えたあとでいつもいくらか間が空くのは、たぶん声紋分析をしているのだろう。
「本日は、ユナイテッド・ホームタウン・サービスのご利用、ありがとうございました。少々お時間が早いようですが、何か不都合でもございましたでしょうか」
こうしてようやく対話が始まる。吉野という女性担当者は、さすが「世界最高のステータス」の名に恥じず、電話の受け答えにそつがない。
「いや、すばらしかったよ。何だか申しわけなくなって、早めに切り上げてきた」
「さようでございますか。ご満足なされましたか」
「もちろんさ」
「では、現在時刻十一月八日午前九時三十二分ですが、サービスは終了ということでよろしいでしょうか」
松永徹は座席の蔭から身を起こした。小声で話している分には、運転手に
「ところで、リピートはできるのかな」
「喜んで承ります。ただし、原則としてヴィレッジのチェンジ、ペアレンツのチェンジ等のご要望には添いかねます」
「それはそうだろうね。ふるさとが二つあるわけはないし、親が気に入らないというのはわがまますぎる」
「はい、おっしゃる通りでございます。リピートのご予定を伺えますか」
「いやいや、まだ日程は決められない。近々連絡します」
「かしこまりました、松永徹様。では、またのご利用をお待ちしております」
電話を切ると、ようやく心が落ちついた。あまりにもできすぎていて、虚実がわからなくなっていた。
白鳥の群れるみずうみが過ぎてゆく。これほど満ち足りた気分がかつてあっただろうか、と松永徹は思いたどった。年齢とともに、足るを知るどころか不満ばかりがつのるようになったと思う。
車窓に映る顔は
ふるさととは、そういうものなのかもしれないが。