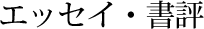本家アメリカにウィンクを
今もってホリー・ゴライトリーより恰好いい女を知らない。自由奔放で、とらえどころがなく、飼い猫にも名前をつけない、永遠に「旅行中」の彼女。15、6の時に映画版を先に観ていたから、原作を読んで180度違うラストを知った時には仰天した。こっちのホリーのほうが段違いに素敵じゃないか。映画の「ティファニー」は若いわたしを虜にしたが、小説の『ティファニー』はわたしの外国文学の読み方を変えたのだった。その思い出深い名作が、村上春樹の新訳で再登場する。これが興奮せずにいられようか。
ノーマン・メイラーはカポーティを「当代で最も完璧に近い作家」と評した。10代のカポーティが原稿運び(コピーボーイ)をしていた〈ニューヨーカー〉誌は最初、彼の短編を「ロマンチックの方向性がうちとは違う」とか言って掲載してくれなかったそうだが、不遇の時は長くなかった。しかも『ティファニー』はカポーティが小説家として一番幸福だった時代の作品だと思う。小説家の卵の「ぼく」には、作者の姿が色濃く投影されているらしい。かなり趣旨の違う映画版がヒットしたことは、この小説にとって大きな幸運でもあり不運でもあったろう(これは、「マイ・フェア・レディ」として映画化されたバーナード・ショウの『ピグマリオン』などにも言えることなのだが。おっと、これもオードリーの主演だ)。
もっとも、初の邦訳書が出た1960年ごろ、"ティファニーで朝食を"(Breakfast at Tiffany's)というフレーズの含意をぱっと理解できる日本語読者は限られていたと思う。わたしが初めて読んだ新潮文庫版(龍口直太郎訳)では、ホリーの決め台詞がこんな風に訳されていた。「ある晴れた朝、目をさまし、ティファニー(訳注 ニュー・ヨーク五番街にある有名な宝石屋で、食堂はない)で朝食を食べるようになっても、あたし自身というものは失いたくないのね」。ジョークの落ちを説明するような割注を見て、翻訳者の存在というものを初めて鮮明に意識した記憶がある。龍口氏はNYのティファニーまで行って、「食堂はありますか」と訊いたと言い、その訳者の翻訳と解説に接して日本語読者は漸くくすりと笑うことができた。しかし根無し草的な(じつは夫がいたりするが)ヒロインが口からでまかせに言う「ティファニーで朝食を」という台詞の妙味は、実体のないただひたすら綺麗なもののイメージが、陽炎のようにふわっと揺らめき立って消えるその刹那にある。同じ小説を読むにも、アメリカの読者とはいかんせん立つ位置が違っていたわけだ。
さて、待望の村上春樹訳ではこうだ。「いつの日か目覚めて、ティファニーで朝ごはんを食べるときにも、この自分のままでいたいの」。小さいことではあるが、わたしは「朝食」が「朝ごはん」になっているところにぐっときてしまう。なるほど、日本語の日常会話で「朝食」というと少々改まった感じになる。この場面のホリーの口調なら、「朝ごはん」のほうが自然ではないか。ふつうは超有名な邦訳タイトルに引きずられて、本文でも疑いなく「朝食」と訳してしまうだろう。こんな繊細な部分にも、わたしは村上氏の揺るぎない翻訳ヴィジョンを感じて信頼を増すのである。
要はセンシビリティだ。村上翻訳の技術の高さに触れると、「いや、翻訳は心なり」といった反論も出るかもしれない。しかしこうして細やかな感性が訳文の隅々まで行き届くのは、高度に洗練された技術の支えあってこそなのである。半世紀前の龍口訳はその当時の感性にぴったりくる名訳だった。そして、日本語読者の多くが「ティファニーで朝食を」というフレーズを聞いて、タイムラグなしに「にやり」とできるいま、村上春樹ほど新訳者にふさわしい人はいない。
スタート地点では遅れをとった(?)ものの、作品発表から半世紀を経た今日、小説家としても翻訳家としても第一級の人の手で味わいを更新した『ティファニー』を真新しい気持ちで読むことができる日本語読者の幸せ。これは翻訳物だけがもちうる豊かさなのだ。さあ、どう? と、本家アメリカにウィンクでも送りたい気分のわたしなのである。
(こうのす・ゆきこ 翻訳家)
波 2008年3月号より

単行本
ティファニーで朝食を
トルーマン・カポーティ/著、村上春樹/訳
発売日 2008年2月29日
1,540円(定価)