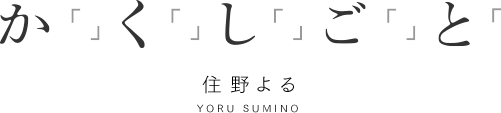我ながら女の子の匂いの違いに気がつくなんて大分キテると思うけれど、気づいちゃったものは仕方がない。今日は朝から
シャンプー変えたのかな。前にお気に入りのがあってボトルを常に持ち歩いてるくらいだと言ってた気がするけど、うん、もちろんそんなこと訊けるはずがない。そんなことしたら三木さんに気持ち悪がられて、嫌いな男子になってしまう。僕は今の好きでも嫌いでもない男子の座を守り抜きたい。もちろん本当は、嘘だけれど。
窓際最後方の席でぼうっとそんなことを考えていると、教室の前の方で三木さんに勢いよく抱きついた女の子の頭上にハテナマークが浮かんだ。
「ミッキー、シャンプー変えた? なんで?」
抱きつくのは論外だとしても、僕も意外とあんな風に普通に訊いてみたらよかったんだろうか。いやいや、僕だと痛々しい結果になるのは目に見えてる。ここは、代わりに訊いてくれたことに素直に感謝しよう。
そうやってこっそり様子をうかがっていると、三木さんは質問に対して「ははっ」と鼻にかかった笑い方をした後、「秘密」と、頭の上にびっくりマークを浮かべて言った。訊かれたことが嬉しかったのだ。
こういう時、僕ってやつは
彼氏でも、出来たのかな?
凄く寂しくて残念な気持ちになりながら、僕は八時半のチャイムを聞いた。
「いみじ、と、いと、の違い、ちゃんと分かる?」
古文の時間、先生の質問に僕から見えるほとんどのクラスメイトの頭の上にハテナが浮かぶ。自分のは見えないけれど、もちろん僕の頭の上に浮かぶのもハテナだ。
頭の上にびっくりマークや句点を
「はいっ」
元気よく手をあげた三木さんは、得意な古文の時間はいつもソワソワとしている。逆に数学の時間は頭の上にずっと読点を三つほど浮かべ、むにゃむにゃうなっている。後ろ姿ですら見ていて飽きない。けれど、あまり見ていて誰かに気付かれたら終わりなので、目の保養をするのは折を見て。とはいえ今日はその目の保養も、自分で思いついてしまった想像に邪魔されて暗い気分になった。きっと彼氏の前ではもっと色んな顔を見せているのだろう。
授業が終わって、机にうなだれていると隣の空いた席に誰かが座った音がした。
「次の英語、LL教室だってさ」
「あー、そうなんだ」
「大丈夫か? お前、授業中もぼうっとしてたろ」
「あー、そうなんだ」
「そうなんだって、お前のことだよ」
顔をあげると、ヅカは焼けた顔で明るく笑っていた。太陽の光でも吸収してるのか、
「体調でも悪いのか?」
「いいや、ただちょっと眠いだけ」
「そっか、俺も眠い」
そんな
「ほら、早く行かねえと英語で怒鳴られんぞ。今日俺、宿題忘れたし」
ヅカは楽しそうに笑うと、僕の肩を叩いて自分の席へと戻り英語の準備をしだした。僕も教科書とノート、そして筆記用具を持って廊下に出る。後ろからすぐにヅカの足音がした。
「昨日の夜中、日本代表が試合やってたろ。見てたら寝不足だ。見たか?」
「いや、見てない」
「んだよー、日本の代表だぞー」
正直、サッカーなのか野球なのかも分からなかった僕は「代表か、凄いね」と適当に返事をした。するとヅカが嬉しそうに「だろ?」と頷いてくれたのでよかった。
ヅカは、僕と仲が良いけれども僕とはまるで違うタイプの人だ。仲が良いのは音楽の趣味が似ているからで、それ以外に共通点なんてない。きっかけなんてそんなものだとも言えるけれども、ヅカは体育会系で明るくて外見もいい。知らない人が見たら身長差も含め、二人の仲を不釣り合いだと思うことだろう。僕だってちょっと気にしたりはする。だって僕達みたいなのは、いけてる子と一緒のものを身につけるのが恥ずかしかったりする、卑屈な生き物だから。
そう、きっと、ヅカの隣には彼と同じように体育会系で明るくて外見もいい人が似合う、なんて思ってしまう。
例えば、うちのクラスで言うなら。
「ねえ、ヅカ、私、なんか変わったと思わない?」
三木さんは僕と並ぶヅカの横に立って、突然そう言った。
「えー、分かんね。お前分かる?」
話を振られた僕。シャンプーの匂いだ、なんて言えるわけがなくて、でも三木さんを喜ばせる答えも見つからなかったので「いや……」とまるで興味がなさそうな答えをしてしまった。
「そゆことだミッキー、俺達は女子の一センチ髪切ったとか分かんねえの」
ヅカの軽口に三木さんは普段なら目をパチクリとさせて笑って応える。でも、今日は違った。三木さんの頭の上に句点が三つ浮かぶ。浮かぶマークと人の感情にはそれぞれに癖があるけれど、三木さんの句点三つは、不機嫌の時だ。
「んなんだから、先輩にふられんだよ」
三木さんはなかなかにひどいことを言って早足で行ってしまった。彼女の言う通り、ヅカは先日、付き合っていた先輩と別れた。音楽性の違いとか言って本当は色々とあったらしいけど、本人が気にしてないみたいだから僕も気にしないことにしている。
ヅカは普段のように「あいつひっでー」と笑った。頭の上に句点が浮かぶ。完全に三木さんを受け入れている証拠だ。
エアコンの効いた涼しいLL教室に入ってから僕とヅカは分かれて、教室での席順と同じ場所に座った。
LL教室では二人ずつ長方形の机に並んで座るようになっている。長方形の真ん中にはモニターが埋め込まれていて、このモニターで二人一緒に英語の教材を見ることになる。
今日も英語での挨拶をすませ、先生と互いの体調を気遣い合った後、僕らはリスニングの練習で映画を見ることになった。クラスの人数が偶数なうちのクラスでは、全ての席で二人がモニターを分かち合うことになる。きちんと見る為には、恥ずかしくなるくらい二人が接近しなければならず、僕なんかはそれだけで
うちのクラスには、いわゆる不登校生がいる。隣の席の
二年生になってから一ヶ月間、隣に座っていた僕としては、まさか自分が原因じゃなかろうなと時々怖くなるけれど確かめようはない。まるで心当たりがなければヅカを通じて誰かに聞いたり出来るかもしれないけれど、実はそうでもなかったりするから、僕は
三木さん以外の女子とはそこそこ話せる僕は、隣の席だった宮里さんとはそこそこ仲がよかったはずで、だったらもうちょっと彼女の不登校を心配して行動を起こしても良さそうなものだけれど、どんな形であれ気になっている人にはアクションを起こせなくなってしまうものなのだ。僕って奴は。どうでもいいことは言えるけど、肝心の話なんて出来やしない。
その点、三木さんっていうのは凄い。一年生の時、入学してすぐ好きになった先輩にアタックしまくっていたのは有名な話だ。身の回りの物、それこそシャンプーやスニーカーなんかをどうやってか調べた先輩の趣味に合わせたりしてたらしい。結果、先輩にはドン引きされて失敗に終わったようだけれど、そのガンガンいける姿勢を少しだけでも分けてほしい。と思ったけど、やっぱりいいや。三木さんの魅力を減らしてしまうわけにはいかないもの。
「だから、その女の子にガツガツした感じを少し分けてよ、ヅカ」
「だからって、その前の話なんなんだよ」
もちろん、三木さんをどう思ってるかなんて誰にも言えるわけないのでヅカには言ってない。これから言う気もない。
「いや、宮里さん、このままじゃ単位危ないんじゃないかなって」
「そっからどうやって俺のガツガツした感じの話になるんだよ。してねえよ! 宮里なぁ、確かにそろそろ危ねえかもな。どうせなら一緒に卒業出来りゃいいけど」
こういうことをきちんと口に出して言えるのが、僕がヅカを好きなところだ。英語と生物の授業を終え、昼食を食べた後、昼休み誰もいない音楽室でクーラーを全力稼働させて僕らは床に寝ころび天井を見上げていた。
「でも来なくなった奴を連れてくるって難しいぞ。それも長い間。部活も、来なくなっちまったら説得ってほとんど無理。大体辞めちまう」
「あー、そうなんだ」
「でも、部活仲間もクラスメイトもそうなっちまうって悔しいよな。なんかあったなら相談してくれりゃいいのにって思うけど、結局自分は相談相手になれるほどじゃないんだろうし、それで何も出来ないって情けねえなって思う」
「…………」
これだ。当事者意識の強さ。三木さんやヅカに共通の特性。つまりガツガツしているという部分だ。人のことも自分のことも、同じように考え強い感情を抱いて行動出来る。これが僕に少しでもあればいいのだけれど。ないから、天井を見上げて、「そうだね」なんて言うしかない。
「
いつの間にか音楽室に来ていたクラスメイトの声が足元から聞こえた。ヅカが自慢の腹筋を使って起きあがり、「おお、パラ」と言ったので誰だか分かる。僕も腕の力で起きて、二人が愉快なやり取りをしてるのを聞く。
やがてそれが終わると、ヅカは立ち上がりそれから足に力を込める僕を見下ろして言った。
「もしかして宮里にガツガツ行きたくて俺に分けてくれっつったのか? いや俺はしてねえけど」
ヅカの頭上にハテナが浮かぶ。彼は感情に正直で、きちんと言動と記号が一致している。
「いや、そういうわけじゃない。出て来たくない人にガツガツ行ったってもっと出て来てくれなくなるでしょ」
「そりゃそうだな、うん、でもまあ、お前は今のままの方がいいと思うよ。お前が隣の席ってのは宮里にとっていいことだと思う。人にはそれぞれ役割があるからな。お前は北風と太陽なら太陽の方だろ」
ヅカが冗談で言っているのではないこと、頭上のマークが教えてくれた。そして「俺は北風じゃねえぞ」と笑って僕の背中を叩いた。力が強くてちょっと痛かったけど、ヅカが底抜けに良い奴なことに免じて許してあげた。
今日もうちのクラスにいる二つの太陽は、僕のなんでもない生活を明るく照らしてくれているけれど、宮里さんにはそれがないのかもしれない。
そんなことを思った僕は何も分かっていなかった。