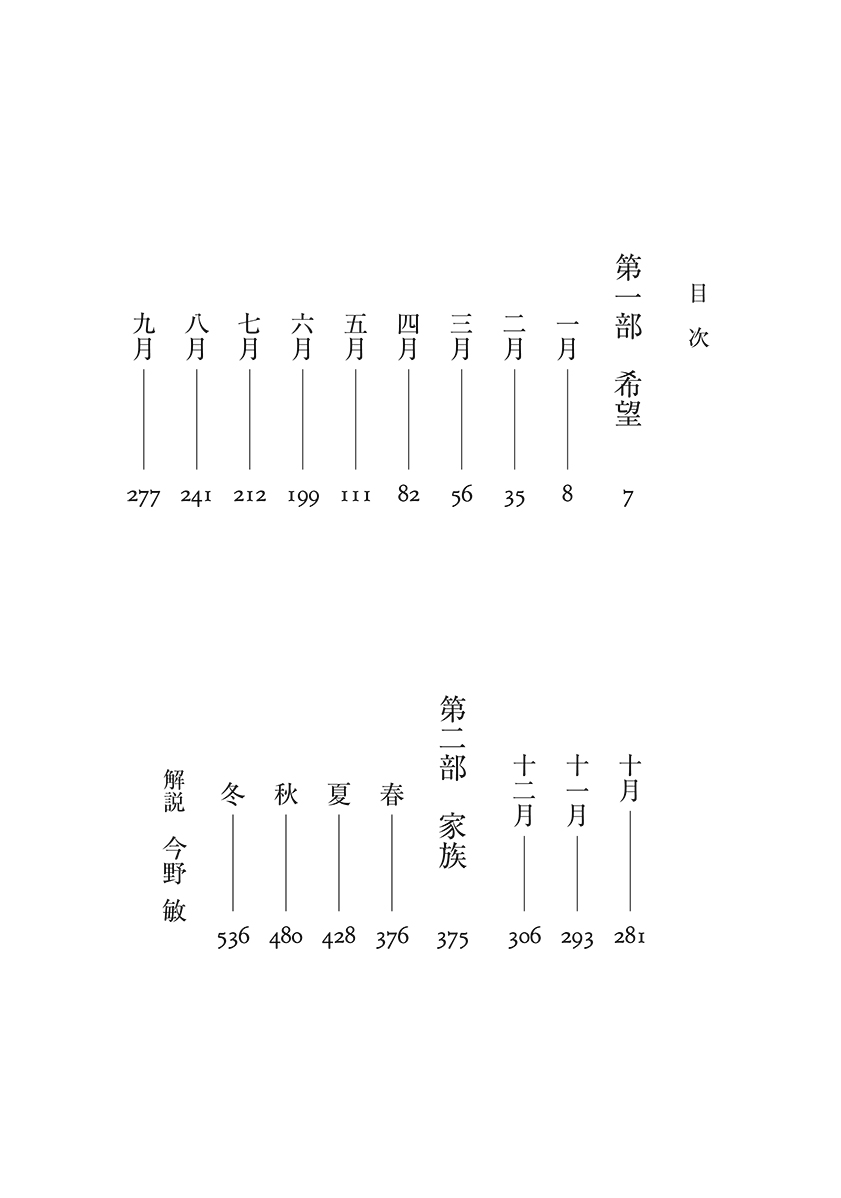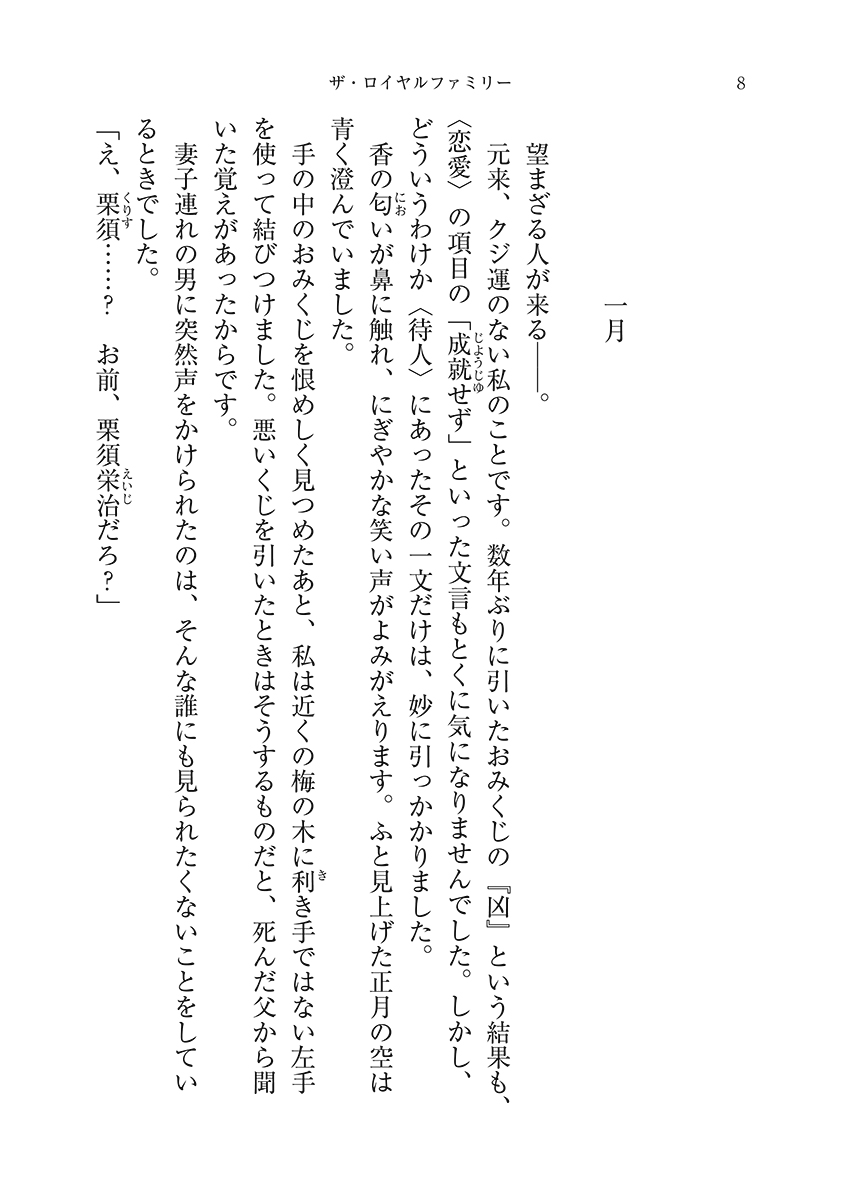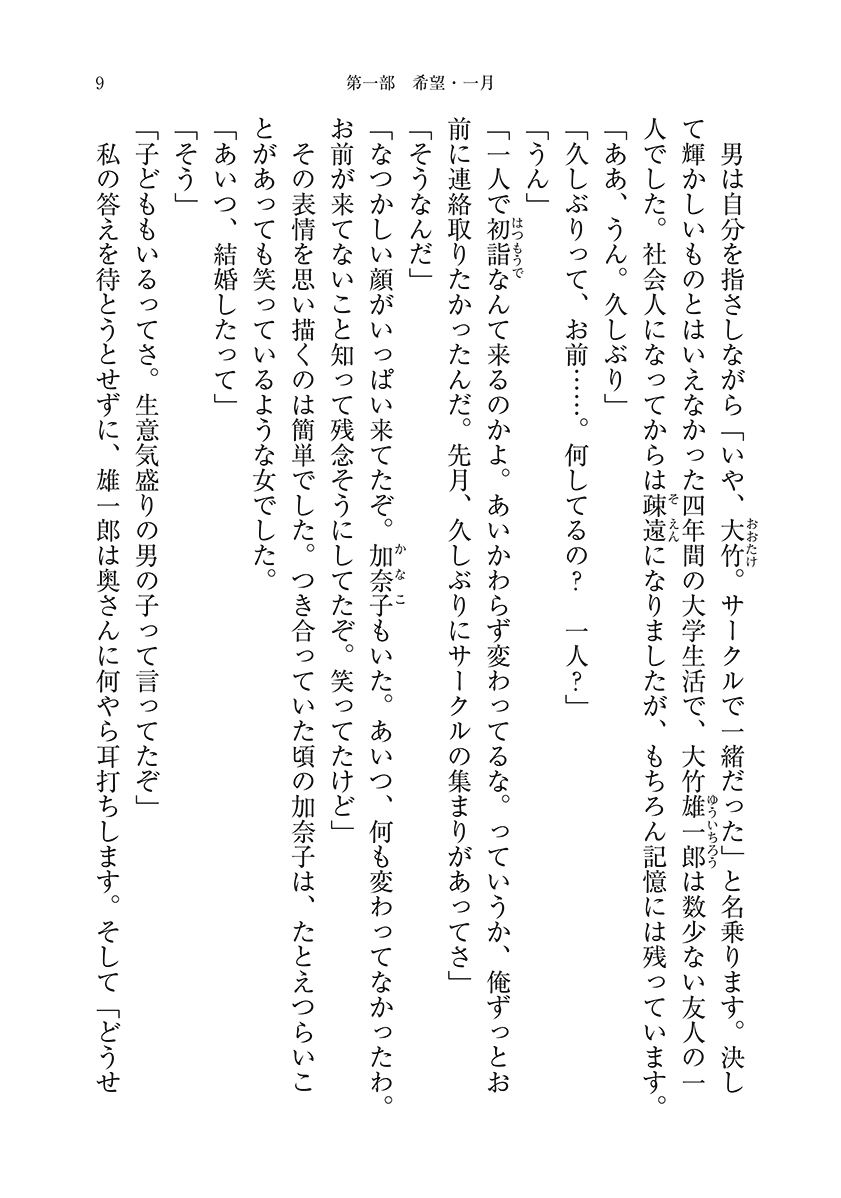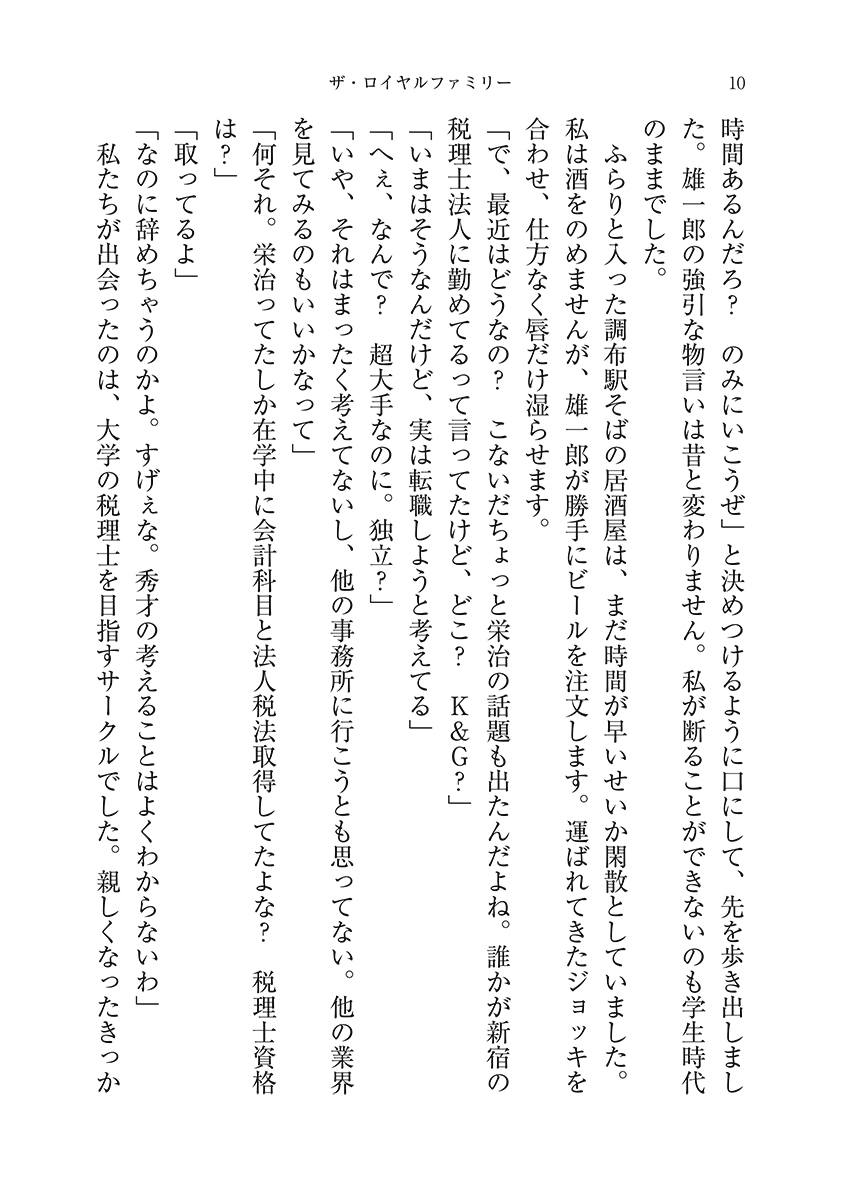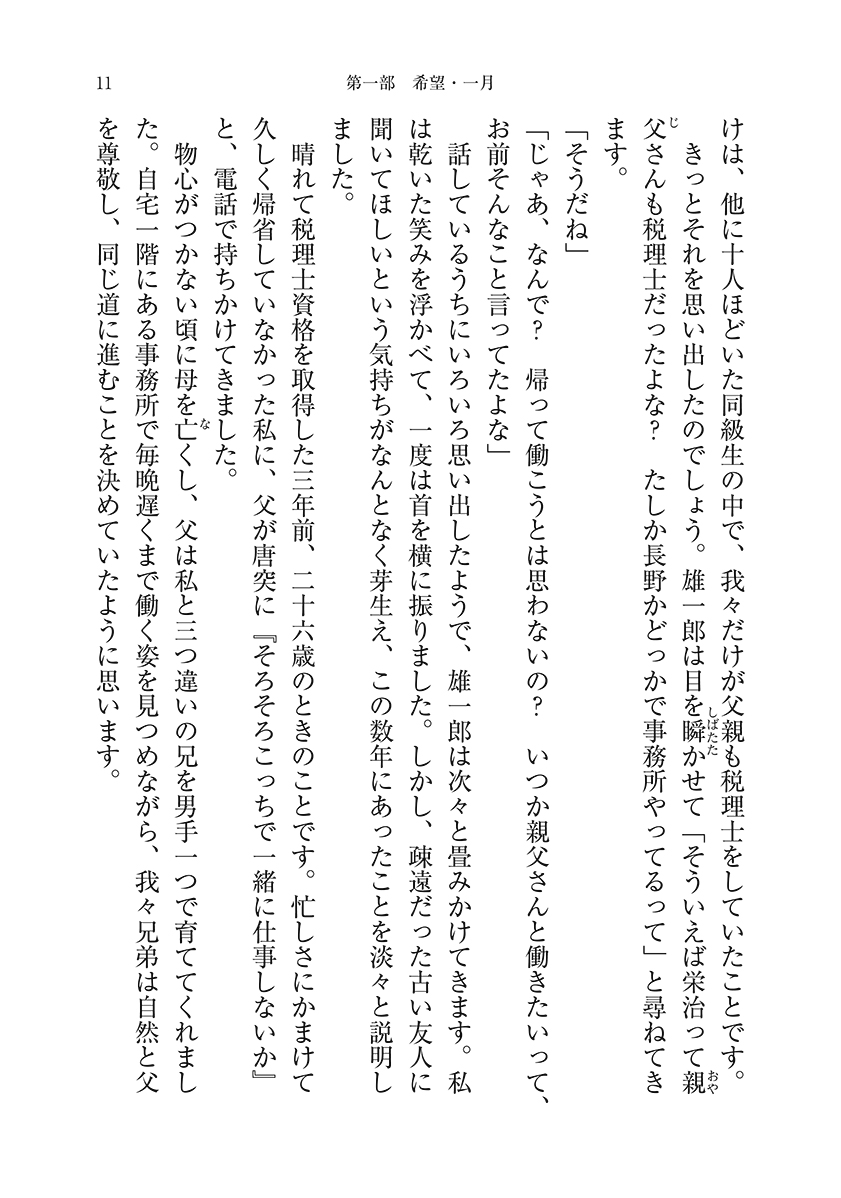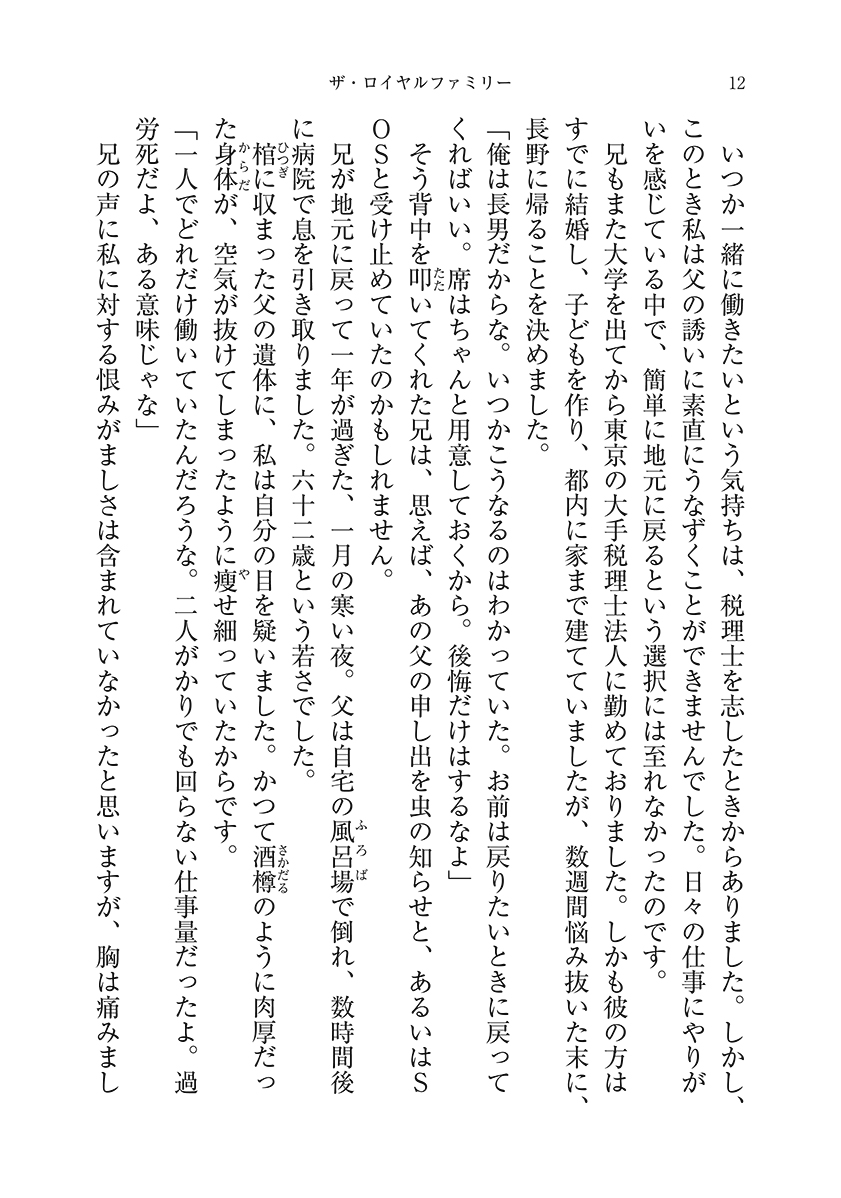第一部 希望
一月
望まざる人が来る──。
元来、クジ運のない私のことです。数年ぶりに引いたおみくじの『凶』という結果も、〈恋愛〉の項目の「
香の
手の中のおみくじを恨めしく見つめたあと、私は近くの梅の木に
妻子連れの男に突然声をかけられたのは、そんな誰にも見られたくないことをしているときでした。
「え、
男は自分を指さしながら「いや、
「ああ、うん。久しぶり」
「久しぶりって、お前……。何してるの? 一人?」
「うん」
「一人で
「そうなんだ」
「なつかしい顔がいっぱい来てたぞ。
その表情を思い描くのは簡単でした。つき合っていた頃の加奈子は、たとえつらいことがあっても笑っているような女でした。
「あいつ、結婚したって」
「そう」
「子どももいるってさ。生意気盛りの男の子って言ってたぞ」
私の答えを待とうとせずに、雄一郎は奥さんに何やら耳打ちします。そして「どうせ時間あるんだろ? のみにいこうぜ」と決めつけるように口にして、先を歩き出しました。雄一郎の強引な物言いは昔と変わりません。私が断ることができないのも学生時代のままでした。
ふらりと入った調布駅そばの居酒屋は、まだ時間が早いせいか閑散としていました。私は酒をのめませんが、雄一郎が勝手にビールを注文します。運ばれてきたジョッキを合わせ、仕方なく唇だけ湿らせます。
「で、最近はどうなの? こないだちょっと栄治の話題も出たんだよね。誰かが新宿の税理士法人に勤めてるって言ってたけど、どこ? K&G?」
「いまはそうなんだけど、実は転職しようと考えてる」
「へぇ、なんで? 超大手なのに。独立?」
「いや、それはまったく考えてないし、他の事務所に行こうとも思ってない。他の業界を見てみるのもいいかなって」
「何それ。栄治ってたしか在学中に会計科目と法人税法取得してたよな? 税理士資格は?」
「取ってるよ」
「なのに辞めちゃうのかよ。すげぇな。秀才の考えることはよくわからないわ」
私たちが出会ったのは、大学の税理士を目指すサークルでした。親しくなったきっかけは、他に十人ほどいた同級生の中で、我々だけが父親も税理士をしていたことです。
きっとそれを思い出したのでしょう。雄一郎は目を
「そうだね」
「じゃあ、なんで? 帰って働こうとは思わないの? いつか親父さんと働きたいって、お前そんなこと言ってたよな」
話しているうちにいろいろ思い出したようで、雄一郎は次々と畳みかけてきます。私は乾いた笑みを浮かべて、一度は首を横に振りました。しかし、疎遠だった古い友人に聞いてほしいという気持ちがなんとなく芽生え、この数年にあったことを淡々と説明しました。
晴れて税理士資格を取得した三年前、二十六歳のときのことです。忙しさにかまけて久しく帰省していなかった私に、父が唐突に『そろそろこっちで一緒に仕事しないか』と、電話で持ちかけてきました。
物心がつかない頃に母を
いつか一緒に働きたいという気持ちは、税理士を志したときからありました。しかし、このとき私は父の誘いに素直にうなずくことができませんでした。日々の仕事にやりがいを感じている中で、簡単に地元に戻るという選択には至れなかったのです。
兄もまた大学を出てから東京の大手税理士法人に勤めておりました。しかも彼の方はすでに結婚し、子どもを作り、都内に家まで建てていましたが、数週間悩み抜いた末に、長野に帰ることを決めました。
「俺は長男だからな。いつかこうなるのはわかっていた。お前は戻りたいときに戻ってくればいい。席はちゃんと用意しておくから。後悔だけはするなよ」
そう背中を
兄が地元に戻って一年が過ぎた、一月の寒い夜。父は自宅の
「一人でどれだけ働いていたんだろうな。二人がかりでも回らない仕事量だったよ。過労死だよ、ある意味じゃな」
兄の声に私に対する恨みがましさは含まれていなかったと思いますが、胸は痛みました。手を抜こうと思えばいくらでも抜くことのできる仕事です。反面、クライアントと関わろうと思えばどこまでも深く関われてしまう仕事でもあります。
父は典型的な後者でした。数年前にはなかった額の
兄の優しさに
私の中で突然異変が起きたのは、父を亡くしてちょうど一年後、昨年の一月のことです。仕事上のある案件について思い悩み、ふと父に質問したいと思ったとき、私はそれが二度と
深夜のデスクで、私は「あっ……」と口に手を当てました。自分はなんのためにここにいるのか、父と働きたくてこの仕事に就いたのではなかったのかと、
どうしてあのとき帰ってあげられなかったのか。
助けてあげようとしなかったのか。
それは罪悪感だったと思います。父を亡くしてから一年、私が必死に
年度末の繁忙期はなんとか乗り切ることができましたが、夏が過ぎ、秋を迎えても胸のしこりは消えませんでした。そして再び繁忙期を迎えようとしていた昨年末には、私はこれまでと同じ気持ちで仕事に取り組めなくなっていました。
たかが父親を失ったくらいで。それも二年も前のことを。誰かに相談すればそう言われることは明白です。他ならぬ私自身がそう感じているのです。しかし、父の死は私に想像もしていなかった喪失感をもたらしました。
たとえ会社からクビを言い渡されても、それほどショックは受けないでしょう。父と働く未来のないこの仕事に、私はどうしても未練を感じることができません。
雄一郎は神妙な面持ちで話を聞いてくれました。しかし、すがるような気持ちで引いたおみくじが『凶』だったという話には、身をよじって笑いました。
「いやぁ、でも、まぁ『凶』なんてなかなかお目にかかるものじゃないからな。そんな状況で神頼みっていうのも、栄治らしくてすごくいいよ」
雄一郎は目をこすりながら話題を変えます。
「そういえば、お前、明日ってまだ休み? なんか予定ってある?」
かつて何度同じように誘われたことがあったでしょう。用件を切り出す前に予定の有無を尋ねてくるのは雄一郎の
予定などありませんでしたが、私は口をつぐみました。雄一郎は気にする素振りも見せず、思わぬことを言ってきます。
「もしヒマなら一緒に競馬場に行かないか?」
「え、競馬?」
「俺の叔父さんが“ウマヌシ”だってお前に話したことあったっけ?」
雄一郎の言う「ウマヌシ」が「馬主」に変換されるまで、少し時間がかかりました。
「いや、たぶんないと思うけど」
「親父の妹の
「重賞レースって何?」
「『金杯』っていう大きいレースだ。なんか久しぶりの重賞らしくて、叔父さん張り切っちゃってるんだよね。お前も友だち連れてこいなんて言われちゃって」
「あの、ごめん。その“ウマヌシ”っていうのは“バヌシ”のことなんだよね?」
「ああ、あれ“ウマヌシ”って読むんだよ。俺もそんなこと知らなくて、いつだったか叔父さんにめちゃくちゃ説教されたことがある。どう? なかなか入れない馬主席だぞ」
「いやぁ、でもそれは──」
「加奈子も来るぞ、明日」
え、なんで……と、のど元まで出かかって、私は言葉をのみ込みました。かつての恋人、
雄一郎は
「あいつ、大学時代から牧場で経理をやりたいって言ってたもんな。結局、卒業しても北海道には戻らなかったらしいんだけど、競馬場には自分のとこの馬の応援に行ってるみたい。明日はあいつのとこの馬も『金杯』に出るんだ。牧場の将来がかかってる期待の
雄一郎はジーンズのポケットから携帯電話を取り出し、「とりあえずお前の連絡先を教えろよ」と早口で続けました。
普段、滅多に目にすることのない携帯電話を見つめながら、私はボンヤリと加奈子の姿を思い描きます。彼女と馬のことを話した記憶はそう多くありません。その数少ない一つは、ケンカをした思い出です。
そのときも牧場の生産馬がレースに出走するという日でした。日曜日の約束をキャンセルされて、私はふて腐れていたのだと思います。「一緒に競馬場に行こう」という誘いをかたくなに断ったのを覚えています。
不意におみくじのことが脳裏を
翌日、結局私は外出しませんでした。雄一郎は最後まで電話で誘ってくれましたが、万が一でも加奈子と顔を合わせるのも
それでも、レースの結果は気になりました。新聞を調べてみると、テレビで中継されることがわかりました。やはり“重賞”は大きいレースのようです。中山と京都の二つの競馬場で、同日に東西の“金杯”が開催されるとのことでした。
アナウンサーはしきりに『一年の計は金杯にあり』と説明しています。正月早々いったいどんな人たちが競馬など
そのうち「パドック」という場所がブラウン管に映し出されました。そこを、これからレースに出走する馬たちが歩いています。興奮して首を上げ下げしていたり、逆に
しばらくして「ロイヤルダンス」が登場してきました。十四頭出るレースで「2番人気」ということは、なかなか期待されているのでしょう。馬の見方などわかりませんが、コツコツという足音がいまにも聞こえてきそうで、他馬に比べて歩く姿に風格を感じさせます。
続いて「ラッキーチャンプ」も現れました。昨日、雄一郎から教えられた加奈子の実家で生産されたという馬です。こちらの方はその名前と同様、妙な
その元気の良さにかつての加奈子が重なり、私は笑ってしまいました。「9番人気」とあるのでそれほど支持はされていないようですが、毛づやなどはずいぶん映えて見えます。
歩いていた馬がいっせいに動きを止めたとき、画面の端に雄一郎が映りました。ダウンジャケットにジーンズという格好だった昨日とは異なり、スーツにアスコットタイで決めた姿はなかなか様になっています。
携帯電話を耳に当てている雄一郎のとなりで、中年の男が笑っていました。豆タンクのようにずんぐりむっくりした
何よりも品のない笑い顔が気になります。がさつな声が画面のこちら側にまで聞こえてきそうなほど、男は大口を開けています。
へぇ、この人が馬主さんか……。そんなことを思っているとき、家の電話が鳴りました。受話器を取ると、たったいまテレビに映っていた人間の声が耳を打ちました。
『ああ、栄治? ごめん、テレビ見てた?』
ボンヤリとブラウン管に目を戻しながら、私はこくりとうなずきます。
「うん。見てるけど」
『どう思った? ロイヤルダンス』
「どうって、どういう意味?」
『だからお前の目にはどう見えたか聞いてるんだよ』
雄一郎がなぜか
「いや、ダントツで強そうに見えたけど」
一瞬の沈黙のあと、嬉しそうな声が聞こえました。雄一郎はそばにいる誰かに、おそらくは馬主だという叔父さんに「ダントツで行けるとか言ってます」と伝え、すぐに『了解。で、どうする? 馬券は買っとく?』などと聞いてきます。
「馬券?」
『うん。ロイヤルダンスの単勝馬券』
「よくわからないけど、じゃあ、せっかくだから」
『いくら?』
「いくらって、そんなのわからないよ。千円くらい?」
『安っ! 学生じゃないんだからよ。まぁ、いいけど。じゃあ、買っとくわ。時間ないからまたあとで連絡する!』
そう言って電話を切ろうとした雄一郎を、私は思わず「あ、ごめん。あのさ──」と引き留めました。
『何?』
「いや、加奈子の馬も良く見えた」
『は?』
「パドックっていうところの映像。ロイヤルダンスほどじゃないけど、ラッキーチャンプもキレイに見えた」
雄一郎は『なんか身内びいきっていう気もするけど、オーケー。じゃあその二頭を応援しとけ。9番と10番だぞ。どっちも緑の帽子だからな!』と、今度こそ電話を切りました。
ジョッキーを乗せた馬たちがパドックを出ていって、競馬場のコースへと場所を移しました。広大な馬場に解き放たれ、どの馬たちも冬枯れした芝の上を気持ち良さそうに走っていきます。
スタートを告げるファンファーレが鳴り、馬たちが続々とゲートに収まりました。横並びになったロイヤルダンスとラッキーチャンプは、まるで旧知の間柄のようにゲート越しに見つめ合っています。
私にはやはりこの二頭が抜けて良く見えました。説明はつきませんが、どうしても強そうな気がしてならないのです。本当に「身内びいき」なのでしょうか。最後までそうとは思えませんでした。
音を立ててゲートが開き、馬たちがいっせいに飛び出します。快晴の中山競馬場、芝の二〇〇〇メートル戦。注目している二頭はまったく違うスタートを切りました。
ロイヤルダンスは最後方にぽつんと残され、のんびりと前を行く馬たちを追いかけます。一方のラッキーチャンプは最初から全速力で駆けていきます。
『さぁ、行った、行った。今日も行ったぞ、ラッキーチャンプ。十万の大観衆に見送られて、二馬身、三馬身……。今日も単騎先頭で駆けていきます』
アナウンサーがしきりに「今日も」ということは、これが戦法なのでしょう。それは理解できましたが、だとしても飛ばしすぎな気がしてなりません。この勢いが最後までもつようなら、ラッキーチャンプはダントツの「1番人気」であるはずです。現に二番手以降の騎手たちは誰も追いかけようとしません。
見えない何かに追われているかのように、ラッキーチャンプは向こう正面に入ってからも加速を続けます。一方のロイヤルダンスはあいかわらず最後方を走っています。何をあわてる必要があるのかと言わんばかりに、悠々と走る姿は王者の風格さえ感じさせます。
ちょうど半分の一〇〇〇メートルを通過した頃、先ほど隣り合わせになっていた二頭の間には数十メートルの差が開いていました。画面に収まりきらないほど離れた二頭を同時に応援する
最後の数百メートルの直線を迎えたとき、案の定、先頭を行くラッキーチャンプのスピードは鈍りました。しかし最後の気力を振り絞るかのように、他馬たちの追撃を許そうとはしません。
ラッキーチャンプに迫るのは一頭だけです。前を行く馬たちをごぼう抜きしたロイヤルダンスが、猛然とラッキーチャンプに迫っていきます。
私が注目した二頭による激しいデッドヒートが繰り広げられました。ロイヤルダンスに迫られたラッキーチャンプもさらなる粘り込みを見せ、二頭は後続の馬たちをどんどん突き放していきます。
私は
『さぁ、これはまったくわからない! ラッキーチャンプか、ロイヤルダンスか。9番か、10番か。どっちだ、どっちだ!』
スタート時と同じように、二頭は最後も横並びになって、ゴール板の前を駆け抜けていきました。絶叫するアナウンサーの声に、ようやく我に返る思いがします。
身体の
テレビでは写真判定の末、ロイヤルダンスがラッキーチャンプを最後に交わし、ハナの差で勝利したことを伝えています。私は笑みを浮かべ、電話の相手も確認せずに「おめでとう。良かったな」と伝えました。
思った通り、電話は雄一郎からのものでした。しかし、反応が想像と違います。
『うん、良かったのは良かったんだけどさ……』
「なんだよ、勝ったんだろ? 俺もすごく興奮したよ。競馬にハマる人の気持ちが少しわかった気がした」
くだけた調子で水を向けても、雄一郎の態度は煮え切りません。つかの間の沈黙のあと、雄一郎は覚悟を決めたように切り出しました。
『栄治、ごめん。悪いんだけど、これから新宿に出てきてくれないか』
「え、なんで?」
『馬主の叔父さんがさ……、
ほら、当たった馬券も渡したいしさ。そう続いた言葉を聞き流しながら、私はテレビに視線を戻しました。
勝ったロイヤルダンスが多くの人たちに囲まれています。表彰式の輪の中で、雄一郎の叔父は紅白の綱をがっちりと握り、一人で大はしゃぎしていました。あいかわらず田舎くさく、品のない笑顔に胸がざらつきます。もちろん会ったことはありませんが、不思議な既視感にとらわれました。
開けっ放しにしていた窓から強い風が吹き込みました。それは父を亡くしたときにも吹いていた、一月の鋭い風でした。
弱り切った雄一郎の顔を立てるためだけに、私はシャワーを浴び、髪をセットして、寒風の吹く外へ出ました。
私と同じように、明日から仕事始めという人が多いのでしょう。街も、新宿へと向かう電車の中も閑散としています。また忙しい毎日が始まろうとしているのに、なぜこんな時間に新宿になど向かっているのだろうと
礼を言われてしかるべき。心のどこかでは近い気持ちがあったのかもしれません。すし詰め状態の個室に案内され、まさか怒声をぶつけられるなどと夢にも思っていませんでした。
「遅い! どれだけ待たせるつもりだ!」
その声が自分に向けられていることにも気づかず、私は
「え?」
「お前が五分遅れたらこの部屋にいる人間は全部で五十分奪われたことになるんだよ。十分で百分、一時間で十時間だ! それだけあればここにいる人間がどれだけ稼げると思ってる!」
ブラウン管越しでは品のなさしか感じなかった顔には、強烈な精気が
「時は金なりっていう言葉があるだろうが。時間は金で買えるんだ。これからは呼ばれたらタクシーで来い、タクシーで」
山王耕造社長の野太い笑い声が響いたとき、部屋の空気が二つにわかれました。下座に座っていた雄一郎をはじめ、
後者の筆頭は、社長のとなりに腰を下ろした六十歳くらいの男性でした。髪の毛を真っ白に染めた男性はゆっくりと立ち上がり、「ま、そんなところにいないでこっちに座れ。社長に話があって来たんだろ」と言ってきます。
むろん、こちらから話があって来たわけではありませんが、仕方なく社長のそばに座り、名刺を出しました。社長は
その後は自然と私のことから話題が
きつかったのは周りから容赦なく酒をのまされ続けたことでした。雰囲気を壊してしまうことをおそれて、「のめない」とは切り出せません。
次々と注がれるビールを、私はなんとか胃に流し込みます。それでも少しでもペースが滞ると、社長はそれを目ざとく見つけ「おい、進んでないぞ」と
結局、ビールを三杯のみました。その間、私はトイレで二度戻しました。あまり長く苦しんでいたら不審に思われると、一気に吐けるだけ吐いて、急いで席に帰ります。
二回目のトイレから戻ったときでした。白髪の男性に「おーい、大丈夫か?」と意地悪そうに声をかけられ、目を丸くした社長からも「なんだよ、下戸か?」と尋ねられました。
大きく沸いた個室の中で、私は悔しくて肩を落としました。さらに大きくなった笑い声を、社長の声がかき消します。
「いやいや、だとしたらずいぶん根性あるじゃねぇか。お前、結構のんでたよな? うちの若い社員なんて平気でのめませんとか言ってくるぞ」
潮が引くように笑い声が消えていきます。社長はぎょろりとした目で私を見つめます。
「となりに座れ」
「あの、でも……」
「いいから来んか」
あごをしゃくるのがこの人のクセであるようです。社長は手を叩いて仲居を呼びつけ、冷たいウーロン茶を注文してくれました。私が一息にそれを飲み干すのを待って、さらに低い声で尋ねてきます。
「転職するって本当か?」
社長の視線は水気を帯びた名刺に向けられていました。なだめ、すかし、怒り、笑う……。それをわかりやすいアメとムチと見る人はいるでしょうが、私には意図してやっていることとは思えませんでした。
「どうなんだよ。転職するのか聞いてるんだ」
見えない力に導かれるように、私は力強くうなずきます。
「はい。しようと思っています」
「親父さんが亡くなったことが影響してるのか」
「そうなんだと思います」
「思いますってなんだよ。テメーのことだろうが。お前の言葉で言え」
「自分でも想像していなかったことですが、父が死んで一年ほど過ぎた頃から、ずっと気持ちが
「おい、栄治……」と、雄一郎の
死んだ父とは全然違います。そこに在りし日の姿を重ねたつもりはありませんが、手だけはよく似ていました。望むものすべてをつかみ取れそうなほど分厚い、それなのに弱々しく血管の浮き出た白い手だけは、父と社長は
「お前、栗須っていうのか」
あらためて
「はい。栗須栄治と申します」
「クリス……。おもしろいな。どっかの国の執事みたいだ。いま抱えている仕事にはきちんと決着をつけてこい。その上で、うちにはいつから来られるんだ?」
部屋の空気がふっと軽くなるのがわかりました。おもむろに差し出された社長の右手を、私は両手で握り返します。そこに血が通っていることに、それも驚くほど温度の高い血が流れていることに、どうしようもなく安堵しました。
鼻先がつんと熱くなりました。白髪の男性が「社長、例のものはいいんですか?」と口をはさんでくれていなければ、涙をこぼしていたかもしれません。
「ああ、そうか。すっかり忘れとった」
社長はいたずらっぽく目を細め、唐突に「おい、雄一郎!」と叫びました。
社長の手を経由して、それは私のもとにやって来ました。
「これは……?」
おずおずと尋ねた私に、社長はつまらなそうに鼻を鳴らします。
「馬券だ」
「それはわかりますが、でも──」
私はたしかに雄一郎に馬券の購入を依頼しました。ですが、それはロイヤルダンスの単勝馬券を、千円分であったはずです。それならば、馬券には「9」と、あるいは「ロイヤルダンス」とあって、「1000円」と記されているべきです。
しかし手渡された馬券にはなぜか「馬連」とあって、「9―10」と、そしてどういうわけか「30000円」と
「お前、2着のラッキーチャンプも予想してたんだろ?」
「それは……」
「ビギナーズラックっていうのは案外バカにできなくてな。あ、馬券代の千円は寄越せよ。そういうところはケジメだ」
社長は荒々しく笑ったあと、私の言葉を待たずに続けます。
「残りの二万九千円は俺からの入社祝いとして取っておけ。ま、せいぜいがんばってその分くらい稼いでくれよ。期待してるぞ」
そこで一度言葉を切って、社長は突然真顔になりました。
「その上で、お前に一つだけ伝えておく。絶対に俺を裏切るな。親父が死んで立ち直れなくなるような若い人間、俺は嫌いじゃないからよ」
この日の帰り道、酔い覚ましのために立ち寄った喫茶店で、雄一郎から社長が六十二歳であることを聞きました。
父が死んだのと同じ年齢であることを運命とは感じませんでしたが、一度は途切れた物語の糸が再び
「べつに本気にしなくていいからな」
温かいコーヒーに口をつけながら、雄一郎は疲れたように息を漏らします。私の方は不思議と疲れていませんでした。むしろ久しぶりに身体の
「とりあえずお礼も兼ねて近々話を聞きにいこうと思う」
「そうか。迷惑かけるな」
「ううん。なんか今日は楽しかった。重賞レースを勝つっていうのはすごいことなんだな。あんなふうに大人たちが大喜びしている姿、あんまり見ないもんね」
私に馬券が渡ったことをきっかけに、飲み会の話題は再び「中山金杯」を勝ったロイヤルダンスに集中しました。
みんながいかに“ダンス”が強かったかということを競うようにして語り合う中、社長はいきなり
立ち込めた静寂のあと、爆発するような声が個室の壁を震わせました。「有馬記念」というレースの格も、そこに「1番人気」で出走することの価値もわかりませんが、今日見たロイヤルダンスがそう簡単に負けるとは思えません。やはり酒に酔っていたのでしょう。私も気分が高揚して、みなさんと一緒になって拳を振り上げていました。
もらった馬券を手にしながら、そのことを思い出してついニヤけてしまった私を、雄一郎が
「ホントによ……。俺の方があのノリについていけなかったよ」
「たしかにね」
「栄治ってそんなタイプだったっけ? クリスとか呼ばれちゃって。なんか
「俺だって驚いてるよ」
「それ、大事にしまっとけよな。馬券。お金と一緒なんだから」
「ああ、そうそう。このことなんだけど──」
「ホントに、あのオッサンだけはよ。酔狂もほどほどにしとけっていうんだよな。そのうち破滅しちまうぞ、いい加減にしとかないと」
雄一郎は肩で息を
一月の冷たい小雪のちらつく中、事務所を出た足で私は新宿駅南口の場外馬券場へ向かいました。警備の人に教えられるまま馬券を機械に投入したところ、画面に『しばらくお待ちください』という案内が表示されました。
つき添ってくれた警備の人と目を見合わせ、小首をかしげたとき、機械の
私はたかが「3・8倍」の単勝に、千円を
『JRA』『WINS新宿』と緑色の文字が記された帯をほどき、言われるままお金の枚数を確認しようとしたとき、正月に引いたおみくじの「望まざる人が来る」の文言が脳裏を過ぎりました。
いまさらながら悔いる気持ちを抱きました。すでに事務所に退職する旨を伝えてしまったことをです。
きっと放心状態であったのでしょう。私の顔を
「あんまりハマっちゃダメだからね。ちょっと当たるとみんなすぐその気になるんだから。競馬で食べていけるなんて絶対に思っちゃダメ。ちゃんと
その日、私はタクシーで帰宅しました。時は金なりを実践したわけでも、大金を手にして気が大きくなったわけでもありません。四百万という大金を持って混んだ電車に乗るのがこわかったからです。
三十歳を迎えようとしていた年のことでした。ついに雪が本降りとなったこの日、流れゆく新宿のネオンを見つめながら、私は自らの将来についてボンヤリと思いを馳せておりました。
二月
会社設立十四年、社員数三百四十名、年間の売り上げ百六十億円。人材派遣業を主とする「株式会社ロイヤルヒューマン」に転職して、三年の月日が過ぎようとしています。
税理士資格を有していることから、当然、入社後は財務を任されるものと思っていました。実際、所属は「経理課」ではありましたが、必要とあれば営業も企画も、ときには販促用のチラシを徹夜で制作したこともありました。つまり「なんでも屋」というわけです。それくらい会社はまだ企業の
それを不満に思ったことはありません。この頃の会社には、私自身が税理士時代にたびたび目にしてきた、これから上っていこうという企業だけが持つ独特の勢いがあったからです。
社長との距離はむしろ遠ざかりました。同じ席で酒をのんだことが幻のように、一社員となってからはそのような機会はありません。
それでも、せまい会社の中でイヤでもその姿は目に入ります。社長は典型的なワンマンでありながら、経営者として業界の先行きを見通す力、とくに法律の本質を見抜く力に
「今年中に必ずある法改正によって、派遣禁止業務がほとんどなくなるはずだ。法が改正されてからじゃ遅い。いまのうちにあらゆる分野へ人材を送り込める準備をしておけ」
時は折しも平成大不況
小売業から転身し、社長がロイヤルヒューマン社を設立したのも、労働者派遣法が施行された一九八六年のことと聞いています。
この時期の派遣法は、直接雇用の社員が外部スタッフに置き換えられにくい専門性の高い十六種のみ派遣を認めるというもので、特別な理由でフルタイムの仕事に就けない人材をどうにか活用していこうという「労働者保護」の色彩が強いものとされていました。
しかし、社長はそれを早々に「建前」と見透かしていたようです。とくに一九九九年の法改正がパラダイムシフトになると踏んでいました。不景気にあえぐ多くの企業で大規模なリストラが敢行され、その空いた穴を埋めるために、これまで禁止されていた各職種においても派遣によって急場をしのごうとするという見立てです。
社長は指をくわえてそのときを待っているわけではありませんでした。派遣スタッフを大量に確保する一方で、ロイヤルヒューマン社の全社員に「コンサルタント」と刷られた名刺を新たに配り、クライアントに送り込みました。
社員はそこで積極的にリストラを提案しました。そしてその穴埋めに自社の派遣スタッフを当て込むことを勧めたのです。
完全なるマッチポンプではありましたが、少しでも人件費を削りたい企業側にとって、景気の変動によって調整弁として使い捨てできる、かつ雇用主としての義務や責任を負わなくて済む派遣スタッフへの切り替えは魅力的なものであったはずです。
企業は厳しい時代を生き抜く
よほどの場合に限りましたが、社長は前者の人間を自社に雇い入れました。後者に関しては、社員たちにいつもこんな発破をかけていました。
「あいつらにだってそれぞれの人生があることを忘れるな。クライアントが連中を使い捨てにしていいと考えていたとしても、俺たちはヤツらを大切に扱わないといけないんだ。すべてのスタッフがうちに登録して良かったと思えるよう尽力してやってくれ」
江戸時代から「人貸し」などと日陰の扱いを受けていた職業です。どれだけ聞こえのいい言葉を並べたとしても、我々が派遣スタッフからピンハネしている事実に変わりはありません。
一部の社員は社長の言葉をただのキレイ事と受け止めていたようです。しかし、私にはそこに社長の
社長の予見した通り、一九九九年は人材派遣業界にとって大きな転換の年となりました。会社はみるみる組織を大きくしていき、私が入社した頃には百名足らずだった社員数が、わずか三年で約三倍の三百名を超えました。また実務部門を桜木町の自社ビルからみなとみらい地区の高層ビル内に移し、そこを拠点に東京都内や関東近県にも次々と事務所を開設していきました。
不況になるほど業績が上がっていく業種です。皮肉な因果関係ではありましたが、この頃の会社はたしかに急激な成長のカーブを描いていました。
もちろん片方の面が輝くほどに、もう片面は影を色濃くしていくものです。やはり多かったのは内外からの不満の声でした。
何年も勤めた社員が
社内に難題も少なくありませんでした。もともと人材の流出入の少なくない業界ではありましたが、とくにこの時期のロイヤルヒューマン社は多くの社員が退社していきました。
戦力として未知数の十人を雇用している間に、三名のキーパーソンを手放していったという感覚です。引き継ぎもままならない場合も多く、責任の所在が常に
新宿の天ぷら屋ではじめて社長とあったときにとなりにいた白髪の男性、秘書課トップの
会社では目すら合わせようとしない社長とは異なり、金城氏は私をかわいがってくれました。社内で顔を合わせれば「少しは慣れたか?」と声をかけてくれ、ときには食事にも連れていってくれました。
そういう席で、金城氏は絶対に会社に対する不満を口にしませんでした。急激に成長していく組織のことも、きっと振り回されているはずの社長のことも、話題にすることさえほとんどなかったと記憶しています。
私はその
何よりも私は金城氏のある秘密を知っていました。二人で食事に出かけた晩のことです。いつもより酒に酔った金城氏は「さすがに気持ち悪いか?」とつぶやきながら、カードケースを開いて見せました。
名刺で膨れあがったケースの中に、写真が差し込まれていました。ロイヤルダンスが「中山金杯」を勝ったときの、口取り式と呼ばれる表彰式のものです。つぶらな
「いい写真ですね。とてもいい写真です」と、素直に口にした私に、金城氏は目を細めてうなずきました。
「たしかこの夜にはじめて君と会ったんだよな」
「そうでしたね。新宿の〈天八〉で」
「楽しかったよなぁ。みんな天下を獲ったみたいに騒いで。あの日の“ダンス”は本当に強かったし、みんな行けると思っちゃったんだよな。実にいい気なもんだった」
むろんビギナーズラックという自覚があって、私が競馬にハマることはありませんでした。それでも、私と社長をつないでくれたロイヤルダンスのことはずっと気にかけ、必ず単勝馬券を千円だけ購入しては、テレビで応援していました。
競馬のイロハも知らない私は、当然ロイヤルダンスはその後も勝ち続けていくのだろうと思っていました。しかし、どういうわけか“ダンス”は「中山金杯」以降、めっきり
社長が宣言した年末の「有馬記念」には出走さえできませんでした。そして翌年には華々しい引退式を開くわけでもなく、ひっそりと現役を退いたのです。
「難しいよなぁ。馬は本当に難しいよ」
金城氏はさびしそうにつぶやきました。
「難しい……ですか?」
「まったく自分の思い通りにならないから。思い描く未来図といつも違う。その意味では会社も競馬も同じかもしれない。裏切られてばっかりだ。俺の人生も思えばおかしなことになっちゃったもんな」
このときの金城氏に他意があったとは思いません。少なくとも写真を見つめていた
ですが、私は「裏切られてばっかり」という一言が妙に引っかかりました。
このとき思い出したのは、はじめて会った日に社長にかけられた「絶対に俺を裏切るな」という言葉でした。
金城氏がロイヤルヒューマン社を離れて一ヶ月、私が転職して三年が過ぎた二月の下旬。新年度を目前にして社内は混乱を極めておりました。
ある日の昼休み、私は同じ経理課の同僚とともに、ランチに出かけようとしていました。横浜の街側を見下ろせるオフィスとは異なり、二十七階のエレベーターホールからは海側が見渡せます。久しぶりの青空にベイブリッジがよく映え、横浜港には何
エレベーターの到着音が鳴り響いた瞬間、ホールの空気がかすかに重くなりました。同僚たちがいっせいに
普段は桜木町の本社ビルにいることが多く、社長がみなとみらいのオフィスに来ることは滅多にありません。私もあわてて壁際に寄って、声を上げました。
「おつかれさまです!」
社長は不意をつかれたように
一度はそのまま立ち去ろうとしましたが、廊下の角を曲がろうとしたとき、社長は何かを思い出したように足を止めました。
そして振り返り、私を凝視します。
「おい、クリス。お前、来週の水曜って空いてるか?」
飲み会での一件のせいでしょう。社長に呼びかけられるときは必ずカタカナで名前が変換されます。
「水曜ですか? はい、大丈夫かと思いますが」
「うん。じゃあ、久しぶりにメシでも食おう」
「は?」
「追って
となりの秘書がうやうやしく頭を下げます。社長はそれ以上何も言わずオフィスへ消えていきました。
同僚たちは何事かと目を見開いていましたが、私にはなんとなく理解できました。社長がいま何に困窮しているか想像すれば、
週が明けて、約束の水曜日。連絡を受けたのは当日の夜でした。社長から私の携帯に直接電話がかかってきて、まだオフィスにいる旨を伝えると、すぐにロータリーに降りてこいというのです。
果たして、そこには女神のエンブレムのついた漆黒の高級車が待ちかまえていました。
「クリスさまでいらっしゃいますね?」
白い手袋をはめたドライバーが語りかけてきました。「はい」とうなずいた私に目を細め、迷う素振りもなく社長の座る後部座席のドアを開きます。
「いや、それはまずいんじゃ……」
「社長から言われておりますので」
「そうですか、では」
仕方なく身をかがめ、社長のとなりに腰を下ろしました。「おつかれさまです」と声をかけても、反応はありません。私のことなど見えていないかのように、いつもとは違う黒縁の老眼鏡をかけ、頭上のライトに照らされた資料を熟読しています。
ドライバーは何も言わずに車を発進させました。音楽も流れておらず、エンジン音もやけに静かで、緊張感だけが増していきます。どこへ向かうのか見当もつかないまま、車は中華街を通り過ぎ、元町を左折して、山手の丘へと向かいます。
十分ほどで目的地に到着しました。ドライバーがリモコンで重厚な門を開いても、私はそこをフランス料理店か何かと勘違いしておりました。外壁がいくつもの照明で柔らかくライトアップされた、歴史を感じさせる西洋造りの建物です。
「社長、到着いたしました」
ドライバーは玄関前のスロープに車を停めると、後部座席のドアを開きました。社長は老眼鏡を外し、憂鬱そうに息を吐きます。
ドライバーはドア横のチャイムを鳴らすと、「では、私はここで」とお辞儀をして、当然のように運転席に戻りました。
間もなくしてドアが開きました。白いシャツを着た老年の男性が「お帰りなさいませ。お疲れになったでしょう」と口にし、社長から荷物を受け取ります。このときになって私はようやくここが社長の自宅と気づきました。
普段、社長は横浜駅近くのマンションに帰っているそうですし、東京支社に近い浜松町にも部屋があると聞いています。しかし、本宅は山手の豪邸だと、いつか古い社員から教えられたことがありました。
「
「クリスさん、ごぶさたしておりますね」
「え、お会いしたことがありましたか?」
「いつだったでしょうか。たしか新宿の天ぷら屋で。私もあの場におりました。お変わりなさそうで安心しました」
そう言う山田氏に案内されて、二階のリビングに向かいました。真っ先に大きな窓が視界に入ります。カーテンの掛かっていないその向こうに、冬の空気によく映える港の夜景が見えました。
「おかえりなさい。遅かったね」
社長にくだけた調子で声をかけたのは、二十代なかばの女性です。娘の
「あの、はじめまして。経理課の栗須栄治と申します」
その視線の強さに負けるように、私は腰を折りました。百合子さまは「クリス? 超ウケる。ハーフなの?」と言ったあと、煙を吹き出しながらあらためて私を見てきます。
山田氏にうながされて、私はテーブルにつきました。もう一人、すでに着席されている方がいらっしゃいます。社長の奥さまの
雄一郎の父親の妹と聞いていたことで、私は勝手にイメージを作り上げておりました。想像していたようなフランクさは
全員が着席したところで、山田氏が「お飲み物はいかがされますか?」と社長に問いかけました。社長は少し悩まれたあと、「シャトー・ラフィットでも開けようか」とつぶやかれます。
百合子さまが「ええ、すごいじゃん。景気いいね」と口にされて、私ははじめてそれが高級ワインなのだと知りました。当然、いつかと同じように「のめません」とは言えません。
みなさんとグラスを合わせたところで、社長が重そうに口を開きます。
「
私にはえぐみしか感じられないワインに表情を輝かせながら、百合子さまが応じます。
「さっきメールしたんだけどね。返事ないよ」
「何してるんだ、あいつは」
「仕事でしょ」
「今日は早く帰ってくるように伝えたんだろ」
「伝えたのは伝えたんだけどね。さすがに八時なんかには帰ってこられないんじゃない? お兄ちゃん、完全にお父さんの子どもだし」
「どういう意味だ」
「ワーカホリックっていう意味よ。働いてないと存在証明できない回遊魚」
長男の優太郎さまは、ロイヤルヒューマンの東京支社長を務めておられます。「二世」や「お坊ちゃん」という社内の色眼鏡をはね返すように
その後も百合子さまがしきりに話を振ってくれたこともあり、私も少しずつリラックスすることができました。
しかし、メインディッシュのステーキが運ばれてきたときでした。ずっと知りたかったこの日の本題は、それまでまったく口を開かなかった奥さまから切り出されました。
「で? あなたが主人の新しいマネージャーなの?」
一瞬、部屋の空気が
「あ、いえ、私は……」
「違うの? あなたかと思ったんだけど」
「なぜですか」
「前の金城さんが突然辞めちゃってからまだ誰もこの家に来てないもの。誰かと一緒じゃないとこの人ここに寄りつかないし、次に連れてくる人がきっと新しいマネージャーだろうって娘とも話していたんです」
それに……と、思わずといったふうに口にして、奥さまは鼻で笑いました。
「あなた、この人の好きそうな感じだもの」
「それはどういう──」
「従順そうっていう意味よ。最後は必ず痛い目を見させられるのに、バカみたいに」
「おい、京子。余計なことを言うな」と、社長がたしなめるように口にします。これまでも社長のいくつもの表情を目にしてきましたが、こんなふうに居心地が悪そうな姿ははじめてです。
「余計なことってどういう意味? 私たちはそのためにこうやって時間を割いているんじゃないんですか。食事を楽しむためだけにご招待したんですか?」
「優太郎が帰ったらきちんと話す」
奥さまは
「わかりました。じゃあ、これだけは言っておきます。栗須さんっていったかしら? もし、あなたが今後主人のマネージャーになるんだとしたら、申し訳ありませんがあまり競馬に熱を入れないように見張っておいてください」
「競馬ですか?」
「前の方はむしろ
「だから、もういいって言ってるだろ」
社長がわずかに声を荒らげたとき、奥さまの深いため息が部屋の中に漂いました。百合子さまは我関せずというふうに携帯電話をいじっています。
私は反応に困りました。ただ、暖色の家具であふれているはずのダイニングがひどく寒々しく見え、不思議でした。
結局、食事を終えても優太郎さまは戻らず、奥さまと百合子さまはそれぞれの部屋に戻られました。
「見苦しい場面を見せてすまなかったな。でも、まぁ、あいつの言う通りだ。お前に俺の専属のマネージャーになってもらいたいと思っている。経理の人間には話をつけておくから、タイミングのいいところで秘書課に移ってくれ」
一度部屋を離れ、数分で戻ってきた山田氏の手には直方体の小箱がありました。社長の手を経由して、それが私のもとにやってきます。
「金城とはもう十五年以上のつき合いだった。お前にすぐその代わりが務まるとは思っていないけどな。一つよろしく頼む」
「あの、社長」
「今日は遅いから俺も休む。山田さんにタクシーを呼んでもらいなさい」
そう一方的に言い残すと、社長は小箱の説明もないままダイニングをあとにしました。箱の中にはゴールドのロレックスが入っています。ワイン同様その価値はわかりませんが、どれだけ
いったいこれは何なのかと思っていると、山田氏から声をかけられました。
「ああ見えてとてもナイーブな方ですからね。絶対に口には出しませんが、金城さんが離れていったことはかなりダメージだったんですよ」
「いや、あの……」
「大丈夫ですよ。そんなものであなたの心を縛れないことは充分理解していますから。物に限らず、何か与えようとするのはあの方の病気です。むしろ心が離れていく要因になり得ることもわかっています。それでも、そうしていないと不安で仕方がないんです」
私はあらためて箱に収められた新品の時計に目を落としました。渡されたときの社長の白い手が脳裏を
父とは
「受け取れません」
私はそっと箱を閉じ、山田氏に突っ返そうとしました。山田氏は「私に言われましても」とおどけたように首をかしげ、
「耕造さまのおっしゃっていた通り、金城さんとはもう長いつき合いでした。いつも傍らにいらっしゃいましたし、マネージャーとして申し分なかったと思います。ですが、耕造さまはおそらく金城さんを信頼してはいませんでした。今回のこともきっと想像の
「今回のこと? あの、金城さんは何を」
「一言でいえば横領ということになるんですかね。かつてやられていた小売業の方でも、似たようなことがあったんです。そのときの方が規模が大きく、結局会社を畳まなければいけなくなってしまって。高い退職金だったって本人は笑っていましたが」
弱々しく
「馬主活動を始められたとき、耕造さまはポツリと『馬は俺を裏切らないから』とおっしゃっていたことがありましたよ」
「え?」
「私などには馬こそすぐに裏切るように思えるんですけどね。期待して、期待して、でも活躍しない馬ばかりですから」
山田氏がふっと視線を逸らしたとき、リビングの扉が音を立てて開きました。頰を赤くした優太郎さまが立っています。
「では、私はタクシーを呼んでまいります」
丁寧にお辞儀した山田氏と入れ替わるように、優太郎さまが入ってきました。あわてて立ち上がろうとした私を手で制し、優太郎さまは柔らかい笑みを浮かべます。
「煙いな、この部屋。百合子?」という質問に、どう応じていいか一瞬悩みました。優太郎さまは気にする様子もなく、近くの窓を少し開けます。
「ごめんね。すっかり遅くなっちゃった。なんの話だった? やっぱりマネージャーの件?」
「はい。そう伝えられました」
「おじいちゃんみたいだったでしょう? あの人」
「どういう意味でしょうか」
「根っからの仕事人間なんだよね。家にいるときのあの人の姿って、俺ちょっと見てられないんだ。こんなふうになったらおしまいだって、わりと小さい頃から思ってた」
優太郎さまは
「ま、そういうわけだからさ。クリスさん、よろしく頼むね。もうあと何年かであの人も引退すると思うから。せめて晩節だけは
「あの、優太郎さん──」と、私はきっと話を止めたい一心で呼びかけていました。
「何?」
「いえ、その……。競馬はどうしたらいいでしょう」
「競馬?」
「はい。先ほど奥さまからあまり入れあげさせないようにと命じられまして」
一瞬の沈黙のあと、優太郎さまは噴き出しました。
「俺はべつにいいと思うけどね。それこそ無趣味なあの人が持った数少ない仕事以外の生き
「優太郎さんもやはり競馬はお嫌いですか?」
「うーん、そうだなぁ──」と、優太郎さまは思案する素振りを見せ、ゆっくりと首をひねります。
「俺はべつに好きでも嫌いでもないかな。わりには合わないと思ってるけど。
優太郎さまはおもむろにネクタイをほどきました。これまでそんな印象はありませんでしたが、社長と目がよく似ています。そしてその言葉から、私とは種類の違う父親という存在に対する強い屈託を感じました。
社長の専属マネージャーとなることで、自分が失ってしまった何かを取り戻せるという思いがありました。後悔を晴らせるかもしれないという予感です。
しかし、それ以上に家族の長い物語に巻き込まれたという感覚があって、そのことが私をひどく憂鬱にさせました。
三月
経理課から秘書課に異動して、四年の月日が流れました。元いた部署の面々には無言で同情されましたし、私自身も容易な仕事ではないだろうと覚悟はしておりましたが、それをはるかに上回り、この間はなかなか厳しい日々だったと思います。
ロイヤルヒューマン社はますます大きくなりました。最大の要因は労働者派遣法のさらなる規制緩和です。二〇〇四年、最後の
ときの政府は「派遣スタッフにも職業選択の自由を」という、あたかも労働者の視点に立つかのような建前を
しかし、すでに「格差」が叫ばれ始めた時代において、私は胸に引っかかるものを感じ続けておりました。ひとたび景気のベクトルが下に向けば、真っ先にクビを切られるのは他ならぬ派遣スタッフです。「規制緩和」という耳ざわりのいい言葉に惑わされそうになりますが、工場に送られる彼らの将来に想像を巡らせてみても、明るい
そんな業界で、社長は「時代の
そういった質問に対し、社長は烈火のごとくやり返しました。
「俺たちは時代の要請にしたがってビジネスをしているだけだ。批判があるのならまずは政府に向けろよ。
いささか偽悪的ではありましたが、それは社長の本心だったと思います。それにどれだけ口悪く記者とやり合ったとしても、社長の派遣スタッフに向ける眼差しはあいかわらず優しいものでした。
とくにこの二〇〇四年以降の製造業のスタッフに対しては、社長はやり過ぎとも思える保護策を打ち出したのです。他業種からは平均して三割のマージンを取っていた中で、元値の安い製造業スタッフには一割減で還元したことなどはその最たる例でしょう。
そんな社長の独断的な行動に困惑する声は社内に根強くありました。当然、社外にはもっと多く存在していたはずです。
何度も話が出ていながら、それでも社長がかたくなに株式を上場しなかったのは、そういった点に理由があったのだと思います。
社内外の批判を一手に引き受け、私は常に厳しい立場に置かれていました。それに輪をかけて頭を痛めていたのは、競馬にまつわることでした。
普段は社長の口からほとんど競馬の話題は出てきません。「ロイヤル」の冠がついた馬が大きなレースに出走する週は、会社全体がどこか浮き足立ちます。ランチ時などに社員たちの話題に上ることもあるのですが、たとえそういう場面に出くわしたとしても、社長は「ほどほどにしとけよ」などと言うだけです。
しかし、ひとたび週末を迎えると、社長は目の色を変えました。平日に仕事から競馬が切り離されているのと同様に、週末になると今度は仕事の用件をいっさい受けつけてくれません。金曜の夜になると子どものように瞳を輝かせ、それを見ると私も気が引き締まりました。
ご自身の馬が出走するときは、北は札幌から、南は九州・小倉まで。社長は希望する社員や取引先の関係者、ホステスなどを引き連れ、全国に点在する競馬場へ繰り出しました。その来賓席で何かを誇示するように大きな笑い声を上げながら、喉がかれるまで愛馬たちに声援を送ります。
レースの大きさや賞金の
同日にいくつかの競馬場でご自身の馬が出走するということもありました。そんなときは、クラスの高いレースを選択することが多いのですが、社長にはあるルールがありました。たとえ他の競馬場でロイヤルの馬が重賞レースに出ていたとしても、新馬のデビュー戦だけはそちらを優先するというものです。
「これだけ馬の数が増えてしまうとな。なかなか顔を見てやることもできないから。デビュー戦だけはなんとか見てやろうって決めているんだ」
果たして馬たちがそれを望んでいるかは定かでありませんが、その気持ちは少しだけ理解できました。きっと出来のいい子どもと、出来の悪い子どもとの間に差がないのと同じように、どちらの馬もオーナーにとっては等しく
金城氏がいつかこぼしていたように、競馬は本当に難しいものです。高い馬が強いというわけではなく、かといって安い馬が勝ち進んでしまうようなサクセスストーリーもほとんど転がっていません。もっと言えば強い馬が勝つとも限らず、基本的には負けることが当然という世界なのです。
その意味では「中山金杯」を制したロイヤルダンスは、その後のレースはたしかに惨敗続きではありましたが、相当の運と実力を兼ね備えていたと言えるでしょう。馬主歴二十年の社長が重賞レースを制したのは、このロイヤルダンスを含めて三頭しかおりません。
「見張っておいてください」という奥さまの言葉は常に頭にありました。しかし、会社の勢いに比例するように、社長はどんどん競馬にのめり込んでいきました。ついていくのが精一杯で、私に止めることなどできません。
マネージャーに就いた頃から、社長は毎年十頭前後の馬を購入していきました。わずか四年で所有する現役馬の数は倍近くの五十頭にまで跳ね上がり、その中にはセリ市でどんどん値が上がり、一億を超えた馬も四頭います。
中でも社長がもっとも執着し、セリ前から「二億が三億になっても絶対に手に入れる」と息巻いていたのが、のちに「ロイヤルキング」と命名されたオス馬です。
最終的に一億八千万円で落札したその愛馬の骨折の一報は、私が受けました。彼が二歳になった夏の終わり。数ヶ月後に迫ったデビューを見据え、北海道でのトレーニングがいよいよ山場に入った頃のことです。
牧場関係者から報告を受けた夜、お供した桜木町の
税金や育成料を含めたら二億円以上かかった馬の故障です。私の声は震えていましたが、社長は
「状況は?」
「全治三ヶ月。復帰までに半年ほどと聞いています」
「どこの骨だって?」
「右前脚の第一指骨だそうです。レントゲンを見ても骨片が飛んでいるわけではないので、手術する必要はないだろうとのことでした」
競馬関連の予定や報告事項がびっちりと
「申し訳ありませんでした」と、私は
「何がだよ?」
「私がセール会場で止められなかったばかりに、余計な出費をさせてしまいました。まさか骨折するなんてあの日は夢にも思いませんでした」
「なんだよ、それは。最初から骨折すると思ってるヤツなんているかよ」
「そうかもしれませんが」
「なんだ? お前はもう“キング”が走らないと思ってるのか?」
「そういうわけではございません」
「だったらいちいち気に病むな。そんなことを気にしていたら競馬なんてやってられない。サラブレッドにケガはつきものだ。そんなことお前が気にするな」
セール会場ではあんなに屈強に見えた“キング”の脚は、実はガラス細工のように繊細なものでした。
それは“キング”に限らず、五〇〇キロという肉体を支えるのに、管囲二十センチ程度の彼らの四肢はあまりにも
私はあらためて手帳に『ケガはつきもの』と書き記しました。たった四年で何冊の手帳を使い切ったかわかりません。馬の入手法から、牧場での
デビュー後もレース選びやジョッキーの指定も馬主側ですることがありますし、勝ち進んでいったときには休養を挟むタイミングなどを指示する場合も出てきます。馬をいつまで走らせ、どの時期に引退させるかを見計らう必要もありますし、引退後の馬の身の振り方も考えてやらなければなりません。
たとえば、我々の想像を超えて走ってくれた「ロイヤルイザーニャ」という馬がいました。この馬は“キング”のときのようなセリ市でなく、一般に「庭先」と呼ばれる取引手法で購入した馬でした。
北海道
おもしろいのは、七月初旬に行われる豪華
派手好きの山王社長はセレクタリアセールが好みのようでしたが、他のセリにもなるべく参加するようにしておられました。
その理由を、社長は「そこでしか会えない牧場の人たちがいるから」といった言葉で説明されますが、当初、私は理解できませんでした。結局セールで馬を購入するのなら、牧場関係者と顔を合わせる必要などないと考えていたからです。社長の口にするのが「庭先」のためであると知るまでに、しばらく時間を要しました。
庭先取引はとにかくわかりにくいものでした。セールのように表立って値が公表されるものではなく、懇意にしている生産牧場と馬主との間で内々に行われる売買方法をそう言います。かつてはセリ市そのものが存在せず、大方の馬がこの手法で取引されていたそうで、その頃はなんとか良血馬を手に入れたい馬主側が必死に有力牧場とコネクションを作ろうとしていたと聞いています。
しかし時代は移ろい、金さえ出せばコネがなくともセールで良血馬を手に入れられるようになりました。不透明なやり方を嫌い、それこそ金の力にモノを言わせてセールで高額の馬を
「だってセレクタリアで一頭しか買えない値段で、何頭もの馬が買えちまうんだぞ。そんなお得な話はないだろ?」
社長は酒の席などではそう豪快に笑っていますが、そんな簡単な話ではございません。たとえ何頭もの馬を買えたとしても、当然そこにかかってくる維持費は
現役の競走馬一頭につき、月の維持費が平均して六十~七十万ほどかかるのです。そこに入手時にかかった金額の多寡は関係いたしません。元値が一億円の馬も、数百万円の馬も等しく六十~七十万円です。本当に儲けようと思うのなら、安馬を多く抱えるのは得策でないという話を聞いたこともあります。
では、なぜ社長は積極的に中小牧場とつき合い、決して良血とはいえない馬を定期的に購入するのでしょう。私にはある仮説がありました。
いつか桜木町の〈寿司大〉で二人きりだったとき、その
「ひょっとして社長は牧場を救済しようとしているんじゃないですか? ちゃんとお金が回るようにしてあげている。私にはそう思えてなりません」
圧倒的な資金力と情報量で、北陵ファームをはじめとする大牧場の占有が始まろうとしていました。かつて国策として農地を牧場に変え、一時代を築いた日高地区の中小牧場は、すでに大半がじり貧の状況に陥りつつあります。
社長はおかしそうに身体を揺すりました。
「俺がそんな聖人に見えるかよ。じゃあ聞くけど、お前にはセリに出てくる馬の善し
「善し悪し……ですか? それは、まぁ、なんとなく」
「本当かよ」と派手に笑い、社長は私の目を
「結局、俺たちはカタログに書かれてある父馬の競走成績や、母馬の繁殖実績くらいしか見てないと思うんだよな。いずれにしても、俺には馬の本質なんてわかってない。たとえば誰もいない会場で、すべての情報を
「あの、それは……」と言い
「しかも、俺たちが選ばなきゃいけないのは二億円の馬でさえないんだぞ。将来、二億円を稼ぎ出す馬なんだ。そんなのわかるわけねぇだろ。だったらプロを信用するしかない。こいつなら信用できるっていう人間と一人でも多く知り合って、そいつが『この馬はきっと走ります』って覚悟を持って言ってくるなら、俺はそれに投資する。馬に出資するんじゃない。その人間への信頼に
そんな社長の思いに競馬の神さまが
そもそも“イザーニャ”は値段さえつきませんでした。生産した
春とはいえ、北海道には多くの雪が残っていました。強い風の音しか聞こえない、うらぶれた牧場で我々は何頭かの馬を案内されました。
しかし、どの馬も似たり寄ったりで、母馬にさしたる繁殖実績もなければ、種馬も安さが取り柄というものばかりで、
「あの白毛の馬は?」
それが馬の、いや、生き物の習性なのでしょう。雄大な日高山脈を背景に、懸命に草を
社長が目をつけた白毛の仔馬もまた、美しい白さを誇る母馬に甘えています。
「いえ、社長。申し訳ございません。あの馬はもう……」と、牧場長は困惑したように言葉を濁しました。
社長の目の色が変わります。
「売れたのか?」
「そういうわけではないのですが。これから見てみたいとおっしゃっているオーナーさんがいらっしゃいまして」
「いくらだ?」
「は?」
「あの馬はいくらなら俺に譲ってくれるか聞いてるんだ」
仔馬の血統や、気性などを尋ねることもなく、社長は
少しの沈黙のあと、牧場長が口にした言葉は意外なものでした。
「その前に社長に見ていただきたい馬がいるのですが、よろしいですか?」
社長の顔を上目遣いに見つめ、牧場長は覚悟を決めたようにうなずきました。果たしてスタッフに母馬とともに連れてこられたのは、
社長は黒毛の仔馬を
「白毛の方の血統は?」
牧場長は少しムッとした様子を見せましたが、自分に言い聞かせるようにうなずきます。
「父親がダークシャドウズ、母馬がエンジェルレイナ。母の父がアイルランド産のボビーバウンズという馬です。二月生まれのオトコ馬で──」
ぶ然としている牧場長の説明に聞き耳を立てながら、私は持っていたリストにあわてて目を落とします。
優秀な馬のみがなれるとされている
社長は迷う素振りも見せずに言いました。
「じゃあ、二頭まとめて三千万でどうだ?」
牧場長に考える
「それでいいならいまここで即決する。今日中にもう何軒か牧場を回りたいから、あまり時間を割きたくない。いま決めてもらえるとありがたい」
「いや、ちょっと待ってください。社長」と、それまで無言を貫いておりましたが、私は口を挟みました。白毛の仔馬の見栄えがどれだけ素晴らしかったとしても、百二十万という父馬の種付け料からすれば三千万はあまりにも法外です。
社長は私になど目もくれません。牧場長は我に返ったように肩を震わせ、脚の曲がった仔馬に目を落とします。
「ですが、社長。こっちの馬の方も……」
「大丈夫だ。それも引き取る」
「いえ、ですが血統も何もまだ」
「関係ない」
そう制するように口にして、社長はようやく口もとに笑みを
「どうせ林田さんにとって思い入れのある馬なんだろ? それがわかるから、血統なんて関係ないんだ。安心してほしい。絶対に
母馬は子どもと引き離されるのを拒むかのように、荒々しく息を吐いています。その鼻先をそっと
「この母馬の名前は?」
「え……? あ、ああ、イザーニャです」
「イザーニャ? 意味は?」
「いえ、とくにはないんです。ただ──」
「ただ?」
「あの、すみません。縁起でもないって怒られるかもしれませんが、病気で死んだうちの
母馬の鼻からそっと手を離し、社長はあらためて脚の曲がった仔馬に目を落とします。
「こいつも
「ええ。そうです」
「じゃあ、ロイヤルイザーニャでいいな?」
「え?」
「山王の『王』から取ったうちの冠は背負ってもらうけど、悪くはないだろ? ロイヤルイザーニャ。ちょうど九文字で収まるし」
過去に大レースで優勝した馬の名や、企業の宣伝になるものが使えないなど、競走馬のネーミングにはいくつかの厳格なルールがありますが、その最たるものは「カタカナで二~九文字に収める」というものです。
牧場長の目はすでに
社長の口ぶりは、いつの間にか白毛の馬ではなく、脚の曲がった馬を欲しがっているようなものになっていました。社長が人助けとして中小牧場とつき合っていると感じるのは、こんな光景を目にするときです。少なくとも、これで向こう数年間は林田ファームは救われたことになるのです。
多くの人と出会うたびに、たくさんの人たちの人生を背負うたびに、社長の表情はいきいきとしていきます。
そばに仕えていた私は誰よりもその変化を見続けておりました。
ロイヤルファイトと名づけられた白毛の馬とともに、ロイヤルイザーニャが「ロイヤル」軍団の一員に加わりました。
そんなドラマがあったからといってその馬が走るほど、競馬は甘くありません。ましてや“イザーニャ”は脚に重大な欠陥を抱えた馬なのです。デビュー前は関係者の間で話題に上ることさえありませんでしたが、我々の予想を良い意味で裏切って、ロイヤルイザーニャはがんばってくれました。
二歳の九月に行われた「新馬戦」と翌月の「未勝利戦」こそ人気薄で、それぞれ11着、12着と
競馬は、基本的には勝ち上がるにつれてクラスが上がっていきます。「未勝利クラス」を勝ち上がれば「五〇〇万下」、そこを勝てば「一〇〇〇万下」「一六〇〇万下」、そして重賞レースにも出られる「オープンクラス」といった
どのクラスであっても「ロイヤル」の馬が出走するときは手に汗を握りますが、私がもっとも声を上げて応援したのは、この「未勝利戦」だったかもしれません。「未勝利戦」は三歳時の秋口までしかレースが組まれておらず、それまでに勝ち上がることができなければ、基本的にはJRAの主催するレースに出走することができなくなってしまうからです。
正直にいえば、ロイヤルイザーニャが八千頭ほどいる同期全体の六分の一ほどしか勝ち上がれないといわれている「未勝利戦」を突破するとは思っていませんでした。それほど「未勝利クラス」を勝ち上がることも難しいのです。
ですが一人だけ、最初から“イザーニャ”の可能性を指摘している方がいました。
「いやぁ、この馬いいですよ。たしかに脚は曲がってますけど、そんなに負担のかからない箇所ですし、何よりも背中が抜群に柔らかい。勝負根性もありそうだし、うまく育ててやれば化けるかもしれません」
透き通った笑みを浮かべて言っていたのは、ロイヤルイザーニャが所属した
JRAが管理する茨城県の
その中には大手牧場や有力馬主との関係が良好で、毎年「超」のつく良血馬を入れては、次々とGI馬を輩出する名トレーナーと呼ばれる方もいますし、馬集めさえままならない調教師もいます。かつては輝いていたのに落ち目と見られている方も、逆に新しく打ち出したトレーニング方法がうまくはまり、トレンド扱いされているような方もいらっしゃいます。
自分の愛馬をどの厩舎に、どの調教師に預けるかは、馬主にとって本来は愛馬の命運を握る重要な選択であるはずです。
しかし、社長は周囲から「先生」などと呼ばれる調教師という人間をあまり信頼しておりません。過去によほど不快な出来事があったのでしょう。二言目には「あいつらは馬のことなんて何もわかってない」と吐き捨てるように口にし、私が両者のケンカの仲裁に入ったこともありました。
広中調教師は、林田氏が紹介してくれた方でした。数年前に調教師資格を取得し、栗東のトレーニングセンターで開業したばかりの三十代で、まださしたる有力馬を抱えていないという状況でしたが、林田氏が「馬を見る目はたしかですし、いい馬を求めて一人でよく北海道を回ってます」と、強く推薦してきたのです。
その広中氏の前向きな言葉を、社長はやはり信じていませんでした。しかし、ロイヤルイザーニャは「未勝利クラス」を勝ち上がったあとも、「五〇〇万下」「一〇〇〇万下」と、三年という年月をかけてゆっくりと勝ち上がっていったのです。
加えて“イザーニャ”は馬券をもたらしてくれました。よほどのことがない限り、社長は競馬場に出向く際には愛馬の単勝馬券を最低十万円は購入します。そして“イザーニャ”が「未勝利戦」を勝った日は、幸運にも我々は競馬場に足を運んでおりましたし、そのオッズは「120倍」を超えていました。つまり“イザーニャ”が最初にレースで勝った時点で、千二百万円もの払い戻しがあったというわけです。
「なんだよ、もう馬代ほとんど取り返しちまったじゃねぇか」
多くの方に祝福の声をかけていただいて、気が大きくなっていたのでしょう。社長は拍子抜けというふうにつぶやいたあと、一千万円を超える価値のある馬券をひらひらさせながら、同伴していたホステスの耳もとで「これ、お前にやろうか」とささやきました。それを私が必死に
ホステスは恨みがましい視線をぶつけてきましたが、知ったことではありません。これから厩舎スタッフや牧場関係者にご
たった一頭が結果を出したくらいで調子に乗られては困ります。賞金の五百万円を含めた計千七百万円をどのように分配するべきか。
初対面のホステスの冷たい視線に
“イザーニャ”の勝ち上がりは数少ない成功例の一つだったと思います。そもそもの目的で購入した白毛のロイヤルファイトは「未勝利クラス」を勝ち抜くことができませんでしたし、二億円弱で購入したロイヤルキングに至っては、右脚の骨折が
こうなると、どれだけ“イザーニャ”が稼いだところで資金は回収できません。奥さまからイヤミをぶつけられるまでもなく、金の出入りをつぶさに見ていた私は、ことあるごとに社長に競馬を控えるよう進言していました。
「ああ、今年はもうそんなに使っちまってるか。さすがにやり過ぎだよなぁ」などと、社長も二人きりのときは殊勝な態度で耳を傾けてくれるのです。
しかし、ひとたびセール会場などに足を運べばすぐにまた気持ちが大きくなって、感情の抑制が
本業の好調もあいまって、社長に金に糸目をつけるという考えはありません。大枚を
息子の優太郎さまが吐き捨てるように言った「バカが手を出すもの」という言葉が、常に頭の片隅にありました。社長に限らず、馬主の方々がどうしてみなさんこれほど競馬に熱中するのか、正直、私にも理解しきれませんでした。
社長が馬主となった直接的な理由は、知人の会社経営者に勧められたことだったと聞いています。
「べつにその人が言っていた『節税対策』っていう言葉を信じたわけじゃないんだけどな。どれだけ節税になろうが、やらない方が金はかからないに決まってる。もちろん稼げるなんてちっとも思ってなかったよ」
社長はそこまでは口にしますが、ではどうして始められたかという肝心なことについてはハッキリ説明しません。
競馬が生まれたイギリスをはじめとするヨーロッパでは、馬主は何よりも尊敬を集めていると耳にします。
ロンドン郊外にあるアスコット競馬場では英国王室が主催する「ロイヤルアスコット」と呼ばれる競馬が開催され、エリザベス女王はいまもご自身名義の馬を所有し、出走時には観戦に訪れているそうです。
テレビで目にするヨーロッパの大レースのパドックには、華やかな社交の世界が存在しているように見受けられます。みなさん余裕のある笑みに満ちあふれ、色とりどりのファッションは見事に洗練されていて、画面に
では、日本のオーナーズサークルとはいかなるものなのでしょう。私がマネージャーとなってはじめてお供したのは、社長が馬主協会に所属している中山競馬場の馬主席でした。三月、とあるGIIレースがメインで開催された日のことです。
そこに一歩足を踏み入れたときのことを、私は生涯忘れません。ドレスアップが義務づけられ、たしかにそこには一般客席とはずいぶん違う顔ぶれが鎮座しておりました。しかし、イメージしていたヨーロッパの華やかさとはかけ離れ、率直にいえば私は失望しました。スリーピースの背広に
それ以上に残念だったのは、馬主席のみなさまがハッキリと分断されていたことでした。持ち馬同士が争っているわけですから、仲良く観戦というわけにはいかないのでしょう。それは理解できても、まずはこの雰囲気を楽しもうという、ヨーロッパ競馬に見られるような余裕が決定的に欠如していました。
みなさん顔では笑っています。同じ馬主協会の方同士、あるいは重賞の常連同士というふうに
本場の競馬にあるような威厳とはほど遠い、見栄っ張りしかいない世界に私の目には映りました。そうでなくても社長は悪目立ちする方です。知らないどなたかの好奇の視線に気がつくたびに、私は心身ともに疲弊します。
そうした馬主席にあって、ひときわ異彩を放っていたのが、
いえ、椎名さまを説明するのにそんな言葉はほとんど意味を
それぞれ距離と競馬場の異なる「
その中でもとくにダービー馬のオーナーとなることは「一国の宰相になるよりも難しい」という格言があるほどで、すべての馬主の
椎名氏に浴びせられた賞賛を
まるで何かに導かれるように、椎名氏とはセリ市でよくぶつかります。意地になった社長が競り勝つことが多いですが、このときは椎名氏に降りる気配がいっさいなく、最後は社長が白旗を揚げました。その馬がのちにダービー馬となるのです。
もちろん仮に社長が競り落としていたら「アキノリリー」は「ロイヤル○○○○」という名前だったでしょうし、所属するトレーニングセンターも、入る厩舎も、調教師も、トレーニング内容も違っていたでしょう。
そうなれば数々の栄光には至らなかったかもしれないと頭では理解していますが、そうした物理的な要因以上に、私はここに社長と椎名氏の決定的な
むろん、だからといって社長にツキがないわけではないのです。現に誰かと争うわけではない馬券などはよく当てます。
しかし、年間所得が二年連続で一八〇〇万円以上、総資産九〇〇〇万円以上でないとなることのできない馬主の、いわば全員が成功者で、全員が強運の持ち主というサークルの中では、率直にいって
勝てず、稼げず、賞賛もされず。ケンカをして、人が離れ、インターネットでは
それでも社長は何かに
椎名氏が大きなレースを勝つたびに、私は思うことがありました。
いつか社長にも同じ笑顔を──。
その思いもまた年月を重ねるたびに大きくなっている気がしてなりません。