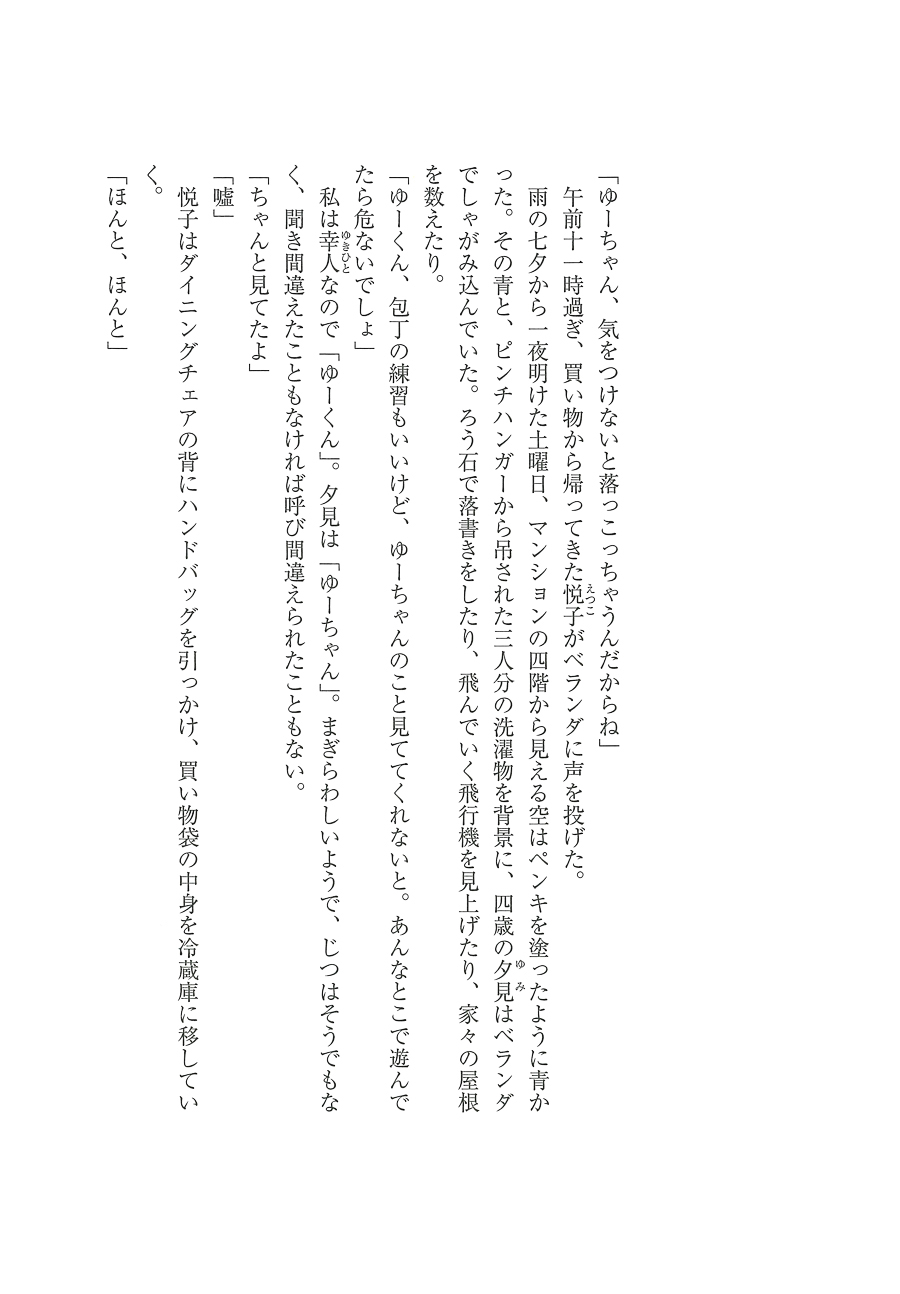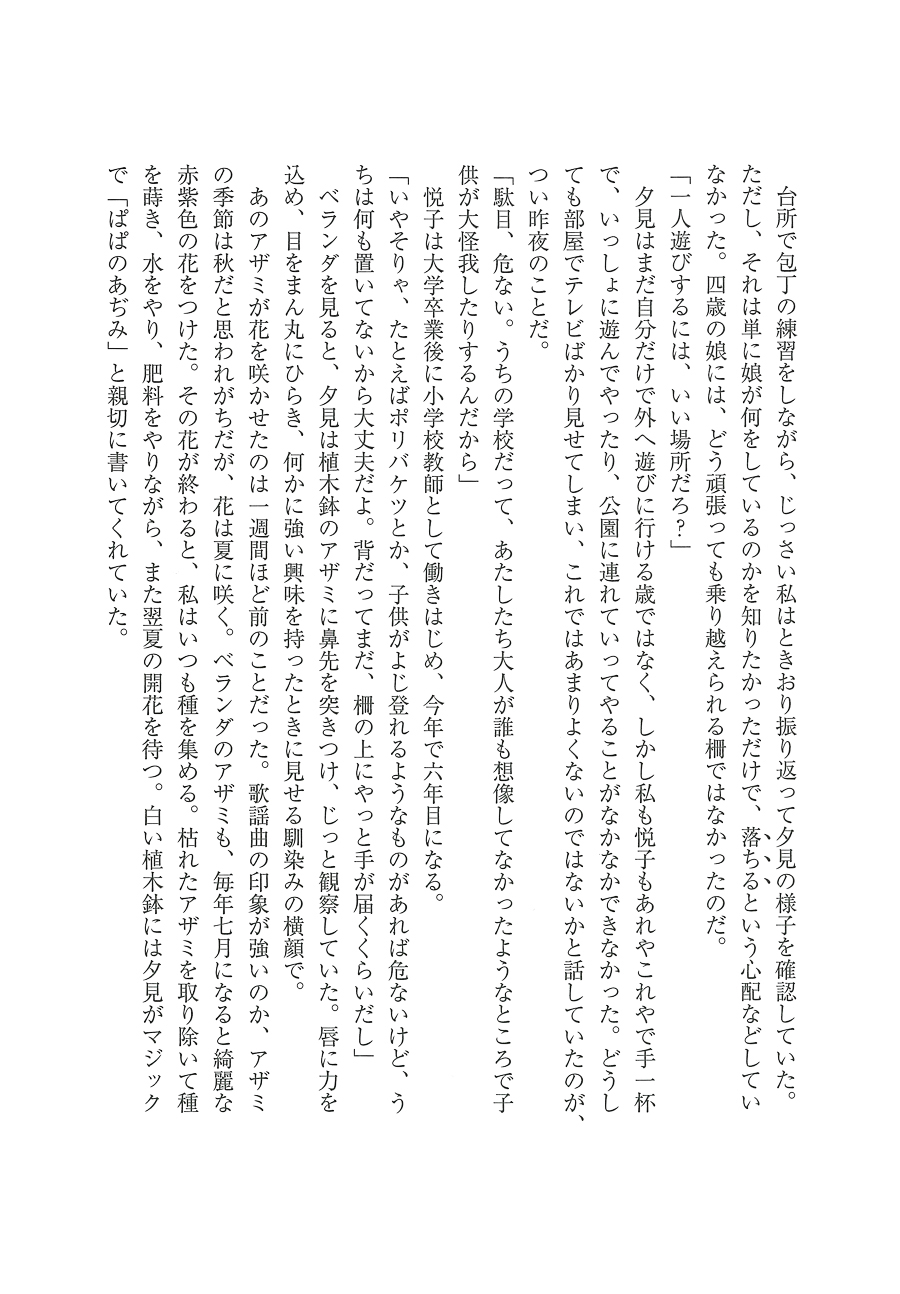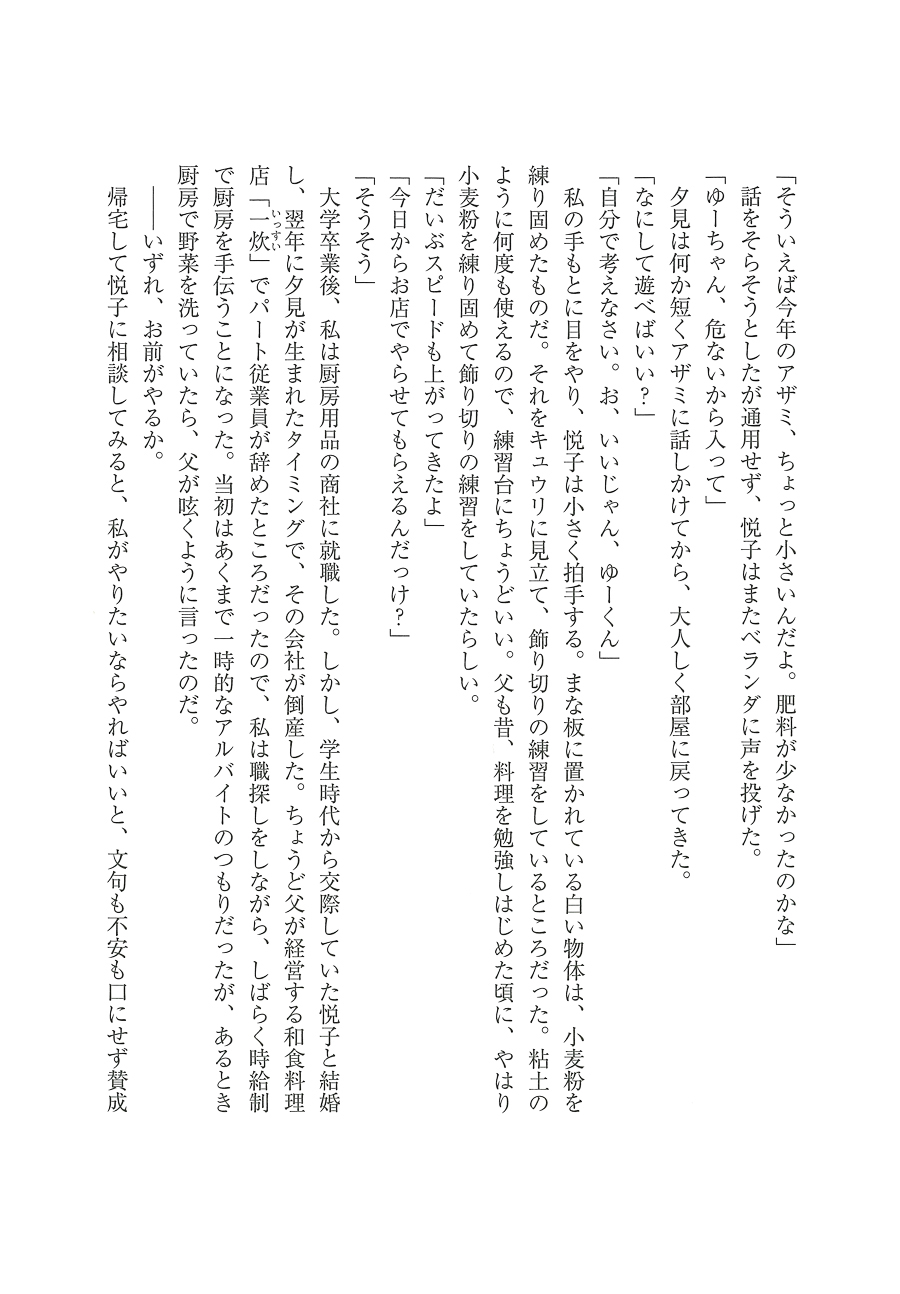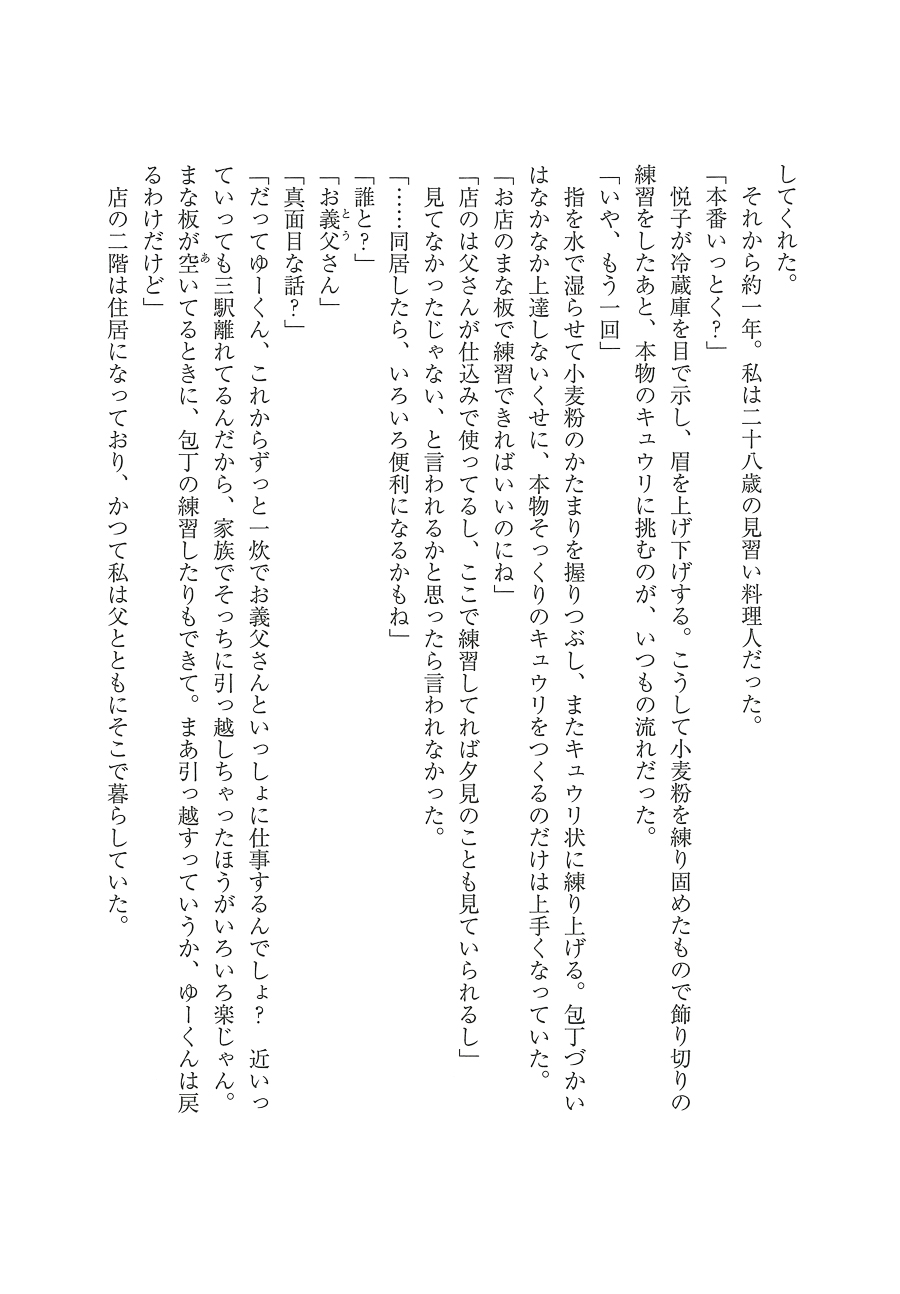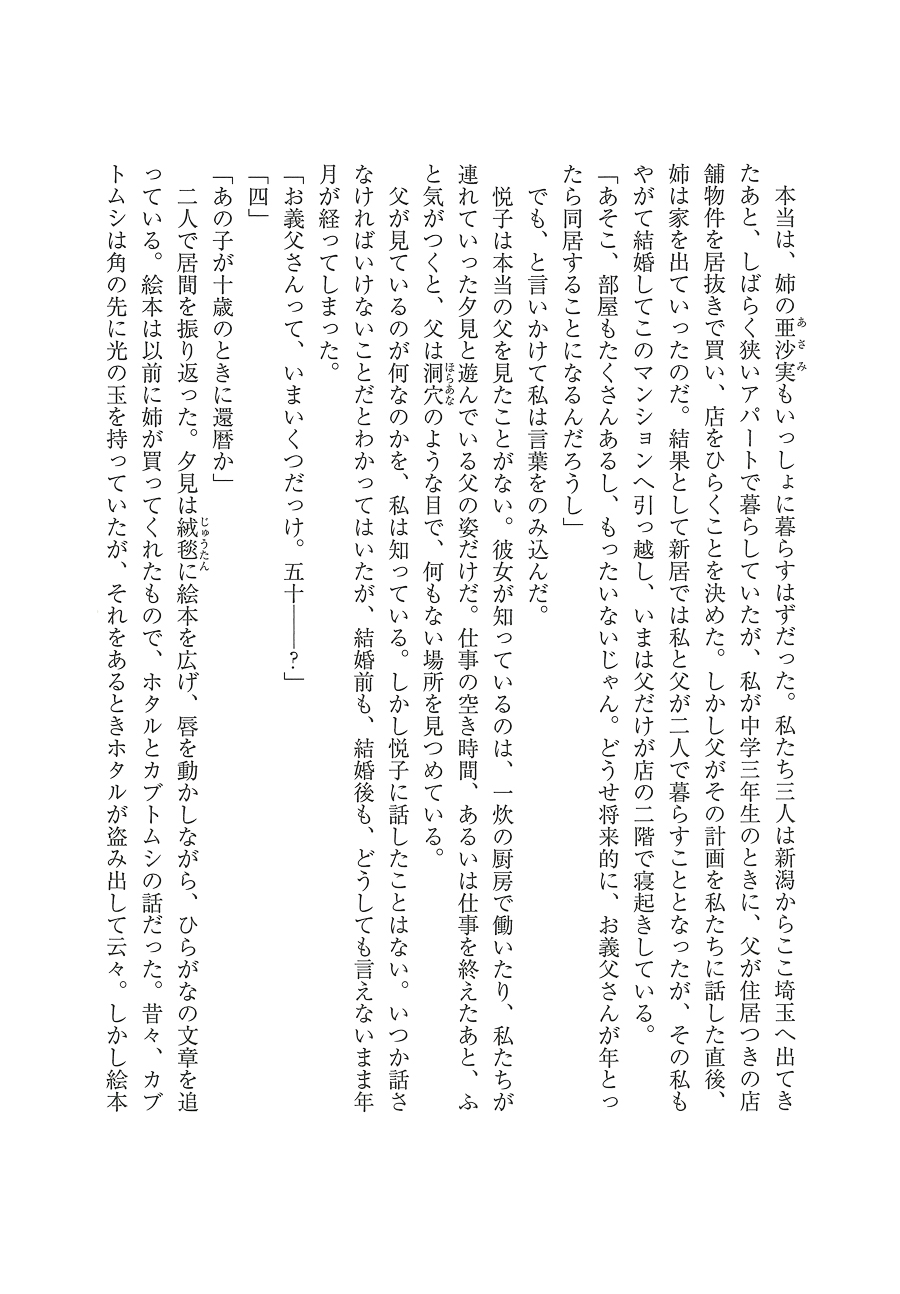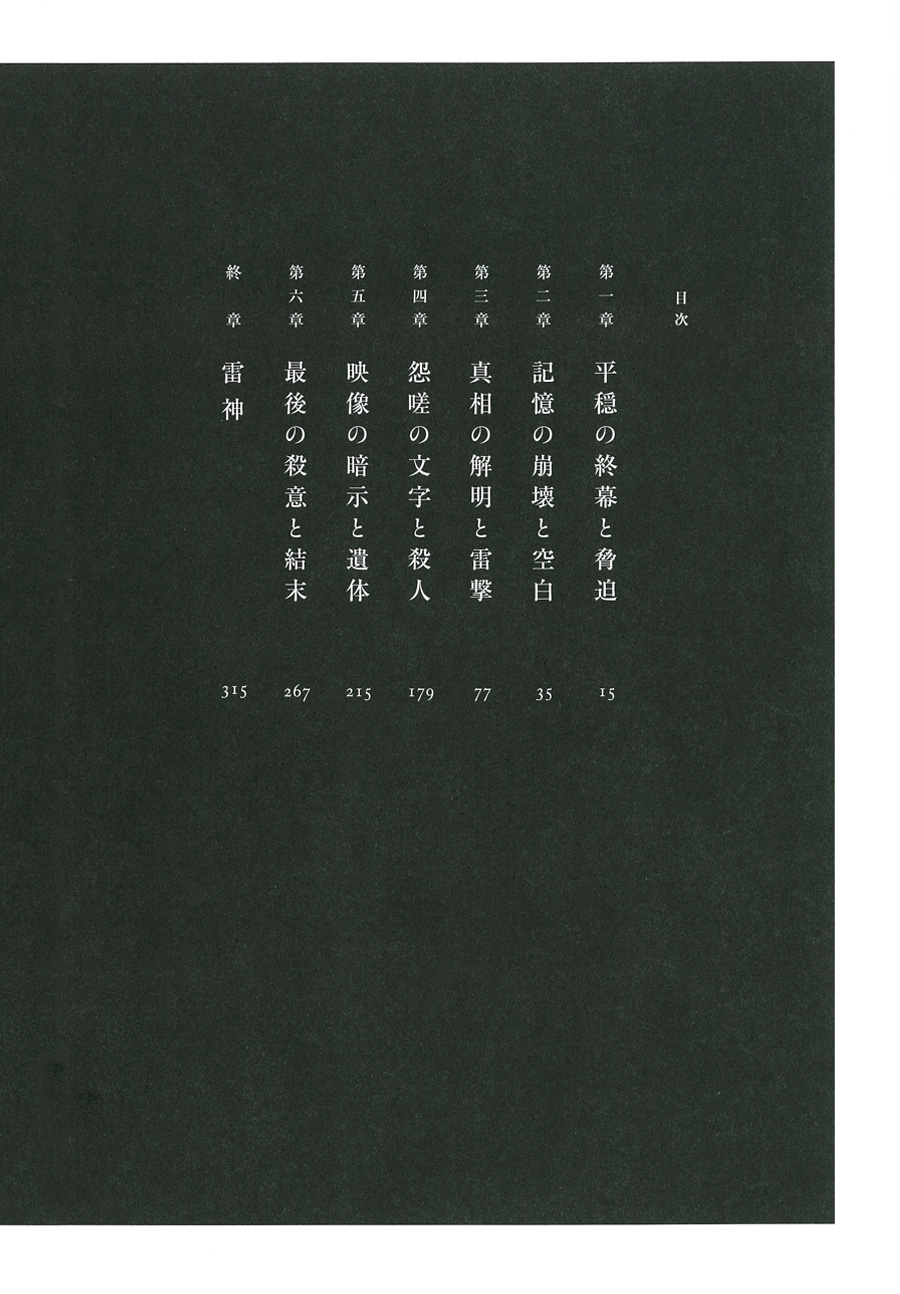「ゆーちゃん、気をつけないと落っこっちゃうんだからね」
午前十一時過ぎ、買い物から帰ってきた悦子がベランダに声を投げた。
雨の七夕から一夜明けた土曜日、マンションの四階から見える空はペンキを塗ったように青かった。その青と、ピンチハンガーから吊された三人分の洗濯物を背景に、四歳の夕見はベランダでしゃがみ込んでいた。ろう石で落書きをしたり、飛んでいく飛行機を見上げたり、家々の屋根を数えたり。
「ゆーくん、包丁の練習もいいけど、ゆーちゃんのこと見ててくれないと。あんなとこで遊んでたら危ないでしょ」
私は幸人なので「ゆーくん」。夕見は「ゆーちゃん」。まぎらわしいようで、じつはそうでもなく、聞き間違えたこともなければ呼び間違えられたこともない。
「ちゃんと見てたよ」
「嘘」
悦子はダイニングチェアの背にハンドバッグを引っかけ、買い物袋の中身を冷蔵庫に移していく。
「ほんと、ほんと」
台所で包丁の練習をしながら、じっさい私はときおり振り返って夕見の様子を確認していた。ただし、それは単に娘が何をしているのかを知りたかっただけで、落ちるという心配などしていなかった。四歳の娘には、どう頑張っても乗り越えられる柵ではなかったのだ。
「一人遊びするには、いい場所だろ?」
夕見はまだ自分だけで外へ遊びに行ける歳ではなく、しかし私も悦子もあれやこれやで手一杯で、いっしょに遊んでやったり、公園に連れていってやることがなかなかできなかった。どうしても部屋でテレビばかり見せてしまい、これではあまりよくないのではないかと話していたのが、つい昨夜のことだ。
「駄目、危ない。うちの学校だって、あたしたち大人が誰も想像してなかったようなところで子供が大怪我したりするんだから」
悦子は大学卒業後に小学校教師として働きはじめ、今年で六年目になる。
「いやそりゃ、たとえばポリバケツとか、子供がよじ登れるようなものがあれば危ないけど、うちは何も置いてないから大丈夫だよ。背だってまだ、柵の上にやっと手が届くくらいだし」
ベランダを見ると、夕見は植木鉢のアザミに鼻先を突きつけ、じっと観察していた。唇に力を込め、目をまん丸にひらき、何かに強い興味を持ったときに見せる馴染みの横顔で。
あのアザミが花を咲かせたのは一週間ほど前のことだった。歌謡曲の印象が強いのか、アザミの季節は秋だと思われがちだが、花は夏に咲く。ベランダのアザミも、毎年七月になると綺麗な赤紫色の花をつけた。その花が終わると、私はいつも種を集める。枯れたアザミを取り除いて種を蒔き、水をやり、肥料をやりながら、また翌夏の開花を待つ。白い植木鉢には夕見がマジックで「ぱぱのあぢみ」と親切に書いてくれていた。
「そういえば今年のアザミ、ちょっと小さいんだよ。肥料が少なかったのかな」
話をそらそうとしたが通用せず、悦子はまたベランダに声を投げた。
「ゆーちゃん、危ないから入って」
夕見は何か短くアザミに話しかけてから、大人しく部屋に戻ってきた。
「なにして遊べばいい?」
「自分で考えなさい。お、いいじゃん、ゆーくん」
私の手もとに目をやり、悦子は小さく拍手する。まな板に置かれている白い物体は、小麦粉を練り固めたものだ。それをキュウリに見立て、飾り切りの練習をしているところだった。粘土のように何度も使えるので、練習台にちょうどいい。父も昔、料理を勉強しはじめた頃に、やはり小麦粉を練り固めて飾り切りの練習をしていたらしい。
「だいぶスピードも上がってきたよ」
「今日からお店でやらせてもらえるんだっけ?」
「そうそう」
大学卒業後、私は厨房用品の商社に就職した。しかし、学生時代から交際していた悦子と結婚し、翌年に夕見が生まれたタイミングで、その会社が倒産した。ちょうど父が経営する和食料理店「一炊」でパート従業員が辞めたところだったので、私は職探しをしながら、しばらく時給制で厨房を手伝うことになった。当初はあくまで一時的なアルバイトのつもりだったが、あるとき厨房で野菜を洗っていたら、父が呟くように言ったのだ。
――いずれ、お前がやるか。
帰宅して悦子に相談してみると、私がやりたいならやればいいと、文句も不安も口にせず賛成してくれた。
それから約一年。私は二十八歳の見習い料理人だった。
「本番いっとく?」
悦子が冷蔵庫を目で示し、眉を上げ下げする。こうして小麦粉を練り固めたもので飾り切りの練習をしたあと、本物のキュウリに挑むのが、いつもの流れだった。
「いや、もう一回」
指を水で湿らせて小麦粉のかたまりを握りつぶし、またキュウリ状に練り上げる。包丁づかいはなかなか上達しないくせに、本物そっくりのキュウリをつくるのだけは上手くなっていた。
「お店のまな板で練習できればいいのにね」
「店のは父さんが仕込みで使ってるし、ここで練習してれば夕見のことも見ていられるし」
見てなかったじゃない、と言われるかと思ったら言われなかった。
「……同居したら、いろいろ便利になるかもね」
「誰と?」
「お義父さん」
「真面目な話?」
「だってゆーくん、これからずっと一炊でお義父さんといっしょに仕事するんでしょ? 近いっていっても三駅離れてるんだから、家族でそっちに引っ越しちゃったほうがいろいろ楽じゃん。まな板が空いてるときに、包丁の練習したりもできて。まあ引っ越すっていうか、ゆーくんは戻るわけだけど」
店の二階は住居になっており、かつて私は父とともにそこで暮らしていた。
本当は、姉の亜沙実もいっしょに暮らすはずだった。私たち三人は新潟からここ埼玉へ出てきたあと、しばらく狭いアパートで暮らしていたが、私が中学三年生のときに、父が住居つきの店舗物件を居抜きで買い、店をひらくことを決めた。しかし父がその計画を私たちに話した直後、姉は家を出ていったのだ。結果として新居では私と父が二人で暮らすこととなったが、その私もやがて結婚してこのマンションへ引っ越し、いまは父だけが店の二階で寝起きしている。
「あそこ、部屋もたくさんあるし、もったいないじゃん。どうせ将来的に、お義父さんが年とったら同居することになるんだろうし」
でも、と言いかけて私は言葉をのみ込んだ。
悦子は本当の父を見たことがない。彼女が知っているのは、一炊の厨房で働いたり、私たちが連れていった夕見と遊んでいる父の姿だけだ。仕事の空き時間、あるいは仕事を終えたあと、ふと気がつくと、父は洞穴のような目で、何もない場所を見つめている。
父が見ているのが何なのかを、私は知っている。しかし悦子に話したことはない。いつか話さなければいけないことだとわかってはいたが、結婚前も、結婚後も、どうしても言えないまま年月が経ってしまった。
「お義父さんって、いまいくつだっけ。五十――?」
「四」
「あの子が十歳のときに還暦か」
二人で居間を振り返った。夕見は絨毯に絵本を広げ、唇を動かしながら、ひらがなの文章を追っている。絵本は以前に姉が買ってくれたもので、ホタルとカブトムシの話だった。昔々、カブトムシは角の先に光の玉を持っていたが、それをあるときホタルが盗み出して云々。しかし絵本の中では、そのホタルやカブトムシよりも、夕見が赤いマジックで描き込んだ「ハートにんげん」のほうが目立っていた。何度も同じ絵本を読んで飽きてくると、夕見はいつもそうして独自のキャラクターを登場させる。はじめは注意していたが、自由にさせるのもいいのではないかと悦子に言われ、放っておくようになった。「角を矯める」という言葉は、そのとき悦子から聞いて初めて知った。
「あ、布」
悦子が急に私の肩をぱしんと叩く。
「うん?」
「布、買い忘れた。バッグの」
夕見が保育園への行き帰りに使う手提げバッグのことだ。
どこの保育園もそうなのか知らないが、通園用のバッグは親が手作りするという決まりがあり、入園時に悦子が深夜作業で完成させた。それが昨日、破れてしまったのだ。悦子が園まで夕見を迎えに行き、教室の奥にある棚でバッグを手に取ったとき、気づいたらしい。持ち手の付け根が、強く引かれたように破れ、その裂け目はバッグの本体まで走っていた。同じ園の子供が、遊んでいるうちに破いてしまったのか、あるいは悪戯でわざとやったのかはわからない。とにかく縫って直せる状態ではなく、土日のあいだに悦子がまた新しいものをつくることになっていた。
「ねえゆーちゃん、バッグの布、ママいまから買ってくるね」
夕見は絵本から顔を上げ、もうバッグが出来上がったような顔で、ピンク色の頬を持ち上げた。
「同じの」
「同じのね、探してみる」
破れたバッグを見たとき、夕見はすました顔をしていたらしい。しかし二人で家に帰ったあと、突然の大泣きが待っていた。悦子がバッグをゴミ袋に入れようとしたときのことで、捨てずに大事にとっておくからと言っても、なかなか泣き止まなかったらしい。バッグが破れたことが、本当はとても哀しかったけれど、ずっと我慢していたのだろうか。それとも、お別れすることが哀しかったのだろうか。一炊の仕事から戻り、悦子にその話を聞いたあと、私は娘の気持ちを思いながら寝顔を眺めた。小さな鼻の穴からすうすうと寝息が洩れ、忙しい夢でも見ているのか、薄い瞼の下で目玉がひっきりなしに動いていた。
「じゃ、ちょっと行って買ってくる。ゆーくん頑張って」
悦子はハンドバッグから財布だけ抜き出して玄関に向かう。ドアが押しひらかれると、ベランダからの風が室内を通り抜け、洗濯物が香った。
「……ベランダ、出るか?」
玄関のドアが閉じるのを待ってから、にやっと夕見に笑いかけた。
「いいの?」
娘の両目がふくらんだ。
「秘密、秘密。遊んでろ」
夕見はひたいを振り下ろすようにして頷くと、絵本を床に広げたまま、網戸に駆け寄ってガラッと開け放った。ベランダに出て赤いサンダルに足を突っ込み、さて何をしようかというように、きょろきょろと左右を見る。私はキュウリを出そうと冷蔵庫へ向かい、そのとき壁の時計が目に入った。この部屋に引っ越してきた最初の日、悦子と二人でホームセンターへ出かけ、蒲団や衣装ケースやアザミの種といっしょに買ってきた、月並みなアナログ時計だった。ほんの一瞬、視界に入り込んだだけなのに、そのとき針が示していた時刻を、私は十五年経ったいまでもはっきりと憶えている。時針は十一と十二のあいだにあり、分針は右斜め下を向いていた。そしてその時刻はいつも、十一時二十分ではなく、十二時まで残り四十分という印象で思い出される。死体検案書に書かれていた「12時0分」。それまでの四十分。
「……あれ」
冷蔵庫の野菜室を開けると、キュウリが入っていない。あると思っていたが勘違いだったらしい。布のついでに買ってきてもらおうと、私は携帯電話で悦子の番号にかけた。しかし着信音が聞こえたのは彼女が置いていったハンドバッグの中だった。ベランダに出れば、悦子の姿が見えるかもしれない。商店街に向かうとき、彼女はいつも真下の道を通っていくから、たぶん見える――が、さすがに上から大声で呼びかけられるのは恥ずかしいだろうか。
「ちょっと下まで行ってくる」
「なんで?」
「キュウリ、キュウリ。すぐ戻るから」
サンダルを突っかけ、鍵もかけずに玄関をあとにした。エレベーターを待っている余裕はないので、階段を一階まで駆け下りる。マンションの裏口を抜け、ベランダの真下の道に出ると、悦子の後ろ姿はやはりそこにあった。呼び止めようか、走って追いつこうか。短く迷ったあと、私が両手をメガホンにしたとき、すぐ右側を一台の白い軽自動車がゆっくりと追い越していった。
小さな影が、視界を縦によぎった。
何かが落ちてきたと理解したときにはもう、目の前を行く軽自動車のフロントガラスを、その物体が直撃していた。車が急加速し、弓状に軌跡を伸ばして遠ざかる。ドライバーが誤ってアクセルペダルを踏み込んだのは明らかだった。車は猛スピードで悦子の背後へ迫り、鈍い衝突音とともに彼女の身体が宙を舞った。そのときもまだ、私の両手は口もとに添えられたままだった。
以後の記憶は、前後がひどく入りまじっている。
通行人が呼んだ救急車。耳鳴りに邪魔されて聞き取れない声。奇妙なスローモーションで動く救急隊員たちの姿。姉に電話をかけたが、口が上手く動かせず、何度も訊き返されたこと。血まみれで地面に転がった悦子の身体。踊るように奇妙な方向へ投げ出された手足。軽自動車から降りてきた年老いた女性は、壊れた機械のように四肢を震わせていた。粉砕されたフロントガラス。そのフロントガラスを割った物体は、ばらばらになってアスファルトの上に散らばっていた。茶色い土。赤紫の花。白い陶器の欠片。その欠片の一つに、「あぢみ」の文字が見えていた。私が何ひとつ理解できないうちに救急車は走り去った。マンションの階段を駆け上がり、玄関に飛び込むと、夕見が顔中で笑いながら走り寄ってきた。
「パパのお花、おっきくなるよ」
自慢げに鼻をふくらませて。
「お花って、お日さまにあてたほうがおっきくなるんだよ」
しかしベランダに植木鉢はなかった。夕見は振り返ってそれに気づき、手すりの脇、コンクリート部分の上端あたりを不思議そうに指さした。
「あそこに置いといたのに……」
第一章 平穏の終幕と脅迫
(一)
「ブリしゃぶのブリってブリのどこ?」
暖簾を分けて、夕見がカウンターの向こうから厨房に顔を覗かせた。
「いま四卓さんで訊かれたんだけど。さっきブリしゃぶ出したテーブル」
「俺が行こうか?」
菜箸を置く私を、夕見は両手で押しとどめる。
「説明するの難しい?」
「いや簡単。ブリしゃぶに使うブリは腹身で、三枚におろした片身の、腹側のほう。背身を使う店もあるけど、やっぱりブリしゃぶは脂がのってるほうが美味いから」
「腹身、お腹、脂、うん」
「切り身になった状態での見分け方は、くっついてる皮が銀色なら腹身で、黒ければ背身。たいていの魚はほら、背中が黒くて腹が銀色だろ。水の中で、上からも下からも姿が見えにくいように」
「おお、なるほど」
「ほいこれいっしょに、隣の三卓さん。マグロと分葱のぬた」
小鉢にキュウリの飾り切りを添えて渡すと、夕見はそれを手に客席へ戻っていった。
腰を落とし、暖簾の下から客席を覗く。三卓で賑やかに飲んでいるのは、そばにある地方銀行で副支店長をやっている常連のエザワさんと、彼が連れてきたスーツ姿の若い男女三人。ブリしゃぶを食べている四卓は、私がこの一炊で料理の手伝いをはじめた頃から通ってくれている老夫婦。ほかのテーブルにも憶えのある顔が並んでいた。毎年十一月半ばを過ぎると、こうして客が増えてくれる。会社などの忘年会シーズンがはじまる前に、内輪で酒を飲もうという人が多いからだろうか。
あの事故が起きたあと、駆けつけてくれた姉に夕見を頼んで病院へ向かったとき、悦子はもう冷たくなっていた。母親の死を夕見に教えたのは、夜になってからのことだ。理解が染み込むまでに長い時間がかかった。しかしそのあとで、咽喉が壊れてしまうほどに娘は泣き叫んだ。
四歳の絶叫を聞きながら、私は真実を一生話さないと心に誓った。
それから十五年。
夕見は十九歳になり、大学に通いながら一炊の接客を手伝ってくれている。
――自宅の真下でバイトできるんだから、こんないいことないじゃん?
それまで家業にあまり関心を持っていなかった夕見が、急に手伝いを申し出てくれたのは、二ヶ月と少し前のことだ。
――いまのバイト先、やっぱりちょっと距離あるし、なんか社員さんも横柄な感じで居心地もよくないし。それに一炊ってバイトに晩ご飯出るんでしょ? お父さんも、わざわざあたしの晩ご飯つくって上に置きにくる必要なくなるじゃん。
訊ねてもいないのに、夕見は矢継ぎ早に理由を説明した。「いまのバイト先」というのはショッピングセンターの中にあるフォトスタジオで、それほど遠くもなければ、社員への愚痴も聞いたことがなかった。だいいち、写真学科に通う夕見には、得るものが多いバイト先だったに違いない。
たぶん、父の死がこたえている私を心配してくれたのだろう。
悦子の死後、私は四歳の夕見を連れてこの店の二階へと戻り、父とふたたび同居した。親を師匠に料理の修業をつづけ、なんとか一人で厨房の仕事をこなせるようになった頃、父は持病の関節痛を悪化させ、あまり厨房に立たなくなった。いまから半年ほど前には食道癌が見つかり、大がかりな手術はなんとか成功したのだが、久々に立った厨房で脳溢血を起こし、病院に運ばれた。蝉時雨に包まれた病室で、心電図の波形はその日のうちにあっけなく消えた。最期の言葉も言えないまま。ほんの三ヶ月ほど前――七十歳の誕生日まで、あと数日というときに。
夕見は週に六日、開店から十一時のラストオーダーまでホールに立って接客をしてくれている。いつも笑顔で、手際も客うけもよく、ときおり年配男性に酒をすすめられるようなこともあったが、未成年なのでもちろん断っていた。
「二卓さん、カワハギの肝和えと、それに合う日本酒だって」
夕見が注文シートを片手に暖簾をめくる。
「日本酒は冷や?」
「冷や」
「じゃ、酔鯨だな。片口とお猪口は、そっちの右端の、青いやつで」
酔鯨は高知でつくられるキレのいい酒で、かすかな酸味が舌を洗ってくれるので、濃厚な味の料理によく合う。
「今日、まだカメラ使ってないな」
カウンターの端を顎でしゃくった。そこには一眼レフカメラがぽつんと置いてある。大学で写真を学んでいる夕見は、市井の人を撮ることに興味を持っているらしく、それなら店にカメラを置いておいたらどうだと私が提案したのだ。常連さんなら気軽に撮らせてくれるだろうし、会話のきっかけにもなるのではないかと。なるほどいいねということでカメラをカウンターに置いてみたところ、はたしてそのとおりになってくれた。ホールで働きながら、夕見はしばしば客席で常連客の写真を撮らせてもらっている。私に写真の良し悪しなどわからないが、あとで見てみると、みんないかにもその人らしい顔をしていた。
「忙しいときは無理でしょ。余計なことしてないでお酒持ってきてくれって言われちゃうよ」
「まあな」
仕事仲間の苦笑を見せ合うと、私は冷蔵庫からカワハギを出し、夕見は片口に酔鯨を注いだ。
「写真のテーマは決まったのか?」
「キマ写? それが決まってないんだよね、迷っちゃって」
まだ十一月だが、夕見が通っている大学では期末試験がもう済んでいる。そのあとは授業がなくなるかわりに、作品の提出によって単位をもらうという仕組みだった。美術学科なら絵や彫刻、音楽学科なら楽曲、写真学科では写真を、年末までに提出することになっている。それが期末写真で、通称キマ写。一年生のときはテーマを「文化」とし、夕見は近所の寺を訪ね、僧侶とその家族が自宅でクリスマスを祝っている写真を撮らせてもらった。坊主頭にサンタ帽をかぶっているのは、少々わざとらしい感じもしたが、どれもコミカルで明るい、あとからまた見たくなるような写真だった。二年目の今年は、まったく違うテーマで撮りたいと言っていたが、そのテーマがなかなか決まらず悩んでいたのだ。
「大変だったら、休んでもいいからな」
夕見はここ数日、カメラ片手に出かけていき、六時前になると帰ってきて、てきぱきと開店準備をはじめてくれていた。
「大丈夫だっての。楽しみながらやれてるんだから。あたし思ったんだけど、小さいときにこの厨房の端っこで“お店ごっこ”やってたのも、そういうのが好きだったからかも。あれすごい楽しかったもんなあ」
小学生の頃、夕見はよく厨房の隅で、丸椅子をテーブルに見立てた「お店」をつくり、見えない客に見えない食べ物を売っていた。
「でもお前、それ憶えてないって言ってなかったか?」
「言ったっけ? わかんない。お父さんに言われて、憶えてるような気になっちゃったのかも」
まな板の上でカワハギの口先と鰭を落とし、皮を剥いでいく。全身タイツを脱がすように、つるりと皮が剥けるのは、名前の由来にもなっている特徴で、あっというまに透明感のある白い身が剥き出しになる。
「うっわ、グロ」
「綺麗だろ」
十五年前、悦子が死んだあの日から、私は事故の真相を胸に閉じ込めたまま生きてきた。何が起きたのかを知っているのは、警察と、軽自動車を運転していた古瀬幹恵という年配の女性だけだ。
悦子の死を告げられたあと、若い警察官が病院へやってきて事故についての説明をした。古瀬幹恵はマンション前の車道を法定速度内で走行していたが、突然上から落下してきた植木鉢がフロントガラスを粉砕し、取り乱した彼女はアクセルペダルを踏み込んでしまったのだという。そして車は暴走し、悦子の身体を背後から撥ね飛ばした。
現場を目撃していた私は証言を求められ、すべてを警察官に話した。妻が買い忘れた、バッグの布。アザミの植木鉢。それを娘が、ベランダの手すりの脇、コンクリート部分に置いたこと。花が大きくならないのを、私が気にしていたせいで。アザミを太陽にあててくれようとして。娘をベランダで遊ばせたのは私だ。アザミを育てていたのも私だ。後悔などという言葉では足りない、自分が内側からばらばらになってしまうような感覚に、いまも毎日のように襲われる。それがやってこない日など、きっと永遠に訪れないだろう。
――お願いがあります。
しかし、絶対に守らなければならないものがあった。
――このことを、娘の耳に入れずに暮らさせてやることはできないでしょうか。
途中から言葉も挟まずに話を聞いていた警察官は、しばらくしてから顔を上げ、相手方のドライバー次第ですと答えた。
――私らは、署内ですぐに協議して、報道関係にも洩らさないよう言っておきます。
軽自動車を運転していた古瀬幹恵にも、事情をすべて伝えてもらった。会って直接話がしたいと希望すると、先方は警察を通じて自宅住所を教えてくれ、後日、私はその場所を訪ねた。時代に取り残されたような、古い借家が並んだ中の一軒だった。駐車場はがらんとして、隅にアサガオのプランターが置かれていたが、完全にしおれ、土は水分を失くしてひび割れていた。室内で向き合った古瀬幹恵の顔には、何度も泣いた跡があった。その日だけではなく、来る日も来る日も涙を流してきたことがまざまざと見て取れる顔だった。彼女がこちらへ向けてくれた扇風機の風を受けながら、私が頭を下げると、相手もまた座卓の向こうで深く頭を垂れた。そして謝罪の言葉を繰り返した。震える肩口の先には仏壇があり、夫らしい男性の遺影が置かれていた。私は古瀬幹恵と、その遺影と、どちらにも頼み込むような思いで、あらためて夕見のことを話した。事故の真相を知らせずに暮らさせてやりたいと頼んだ。すでに警察から事情を聞いていた彼女は、迷いもなく承知してくれた。自分は一人暮らしで、子供もなく、地域に親しい関係の人もいないので、事故のこと自体を誰にも話さないと約束してくれた。
私が夕見を連れてこの店の二階へ引っ越してきたのは、娘に事故の真実を知られるのが恐かったからだ。あのマンションに住みつづけていたら、いつか何かの拍子に知ってしまうかもしれない。事故現場に落ちていた、白い植木鉢の欠片や、土や、アザミの花は、おそらく何人もの人が目にしている。マンションのベランダから落ちてきた植木鉢が事故の原因となったことは容易に想像がつくに違いない。それがどのベランダから落ちてきたのかは、誰も知らない。しかし夕見にはわかる。アザミの植木鉢という言葉を耳にしてしまったら、きっと娘はすべてを理解してしまう。だから私はあの場所を離れた。夕見をあの場所から引き離した。私たちはここで暮らし、この十五年間ずっと、何事も起こらずに時間は過ぎてくれた。これからだって何も起きないはずだった。なのに――。
「……え、何してんの?」
目を開けると、夕見が驚いた顔でこちらを見ていた。
私の身体は斜めに傾いでいた。片肘を調理台につき、危うい角度で自分の身体を支えていたのだ。たったいまカワハギの身をさばきながら、急激にやってきた怒り――頭が内側から爆発するような怒りに強く目を閉じたとき、平衡を失ってふらついたらしい。
「これ、油かな、滑った」
自分の足下を覗き込んでみたが、夕見のほうへ目を戻すと、まだ私を見ている。
「……ほんとに?」
「滑っただけだよ。いいから、それほら、早くお客さんに出して」
夕見は半信半疑といった顔でホールに戻っていったが、ちょうど新しい客が入ってきたらしく、「いらっしゃいませー」と元気な声を投げるのが聞こえた。私はまな板に目を戻し、肉があらわになったカワハギに包丁を入れた。怒りが不安に変わっていく。この四日間ずっと、懸命に抑え込んできた不安が、胸の中で冷たくふくらんでいく。
家の電話が鳴ったのは四日前の午後だった。
――藤原です。
――金を都合してもらいたくてね。
私の声にかぶせるようにして、相手は事前に用意していたことがわかる物言いで切り出した。最初に頭に浮かんだのは、電話を使った振り込め詐欺の類いで、私は何も言わずに受話器を置こうとした。しかし、つぎの言葉が耳に届いた瞬間、その手が止まった。
――秘密を知ってるんだ。
不安の先触れが胸を冷たくした。
――あんまり具体的に話すと俺の素性もばれちまうから、ごく簡単に言うけどな、あれをやったのはあんたの娘だ。あんたは、それを知っていながら隠してる。いままでずっと。
そして男は、まるで切り札のようにこうつづけた。
――アザミを育ててたことも……こっちは知ってるんだ。
言葉は途切れ、昂ぶりを抑え込んだ息づかいだけが聞こえてきた。恐怖に全身を絞り上げられながら、あらゆる疑念がいっせいにわき起こった。電話の向こうで呼吸しているのはいったい誰だ。古瀬幹恵は事故の真相を誰にも話さないと約束してくれたが、本当にその約束を守ってくれたのだろうか。少なくとも、警察を除けば、事故の真相を知っているのは彼女だけのはずだ。いや待て。私がベランダでアザミを育てていたことを知っている人間はいないか。もし知っていれば、事故現場を目にしたとき、それがどうして起きたのかを考え当てることができたのではないか。しかし植木鉢を落としたのが夕見だということまでわかるはずがないし、そもそも私はアザミを育てていることを誰にも話した記憶がない。事故の前もあとも。しかし悦子は? 妻が生前、話していた可能性はないか。誰かに。いま電話の向こう側にいる男に。
――あなたは――。
そのとき部屋の空気が動き、玄関で物音がした。期末写真のテーマを探しに出ていた夕見が帰宅したのだ。私は声を抑え、ほとんど息だけを聞かせるようにしてつづけた。
――あなたは誰です?
咽喉に引っかかった、軋むような笑いが返ってきた。
――正直に名乗る奴がいるか? とにかく俺は、あんたの娘がやっちまったことと、あんたがそれをいまだに隠しつづけてることを知ってる。
五十万円という金額を、男は提示した。
――近々、店まで受け取りに行くから、いつでも渡せるようにしといてくれ。
洗面所で夕見が手を洗っているらしく、壁の奥で水道管が鳴った。それと重なって、男の言葉が毒液のように右耳から入り込んだ。
――払わなきゃ、俺はあんたの娘にぜんぶ話す。
――あの子は何も知らないんです。何も憶えてないんです。
娘の名前は、毎日の夕暮れを幸せに眺めてほしいという思いを込め、悦子と二人で決めた。はじめは幸人の「幸」か悦子の「悦」を入れた名前を考えたのだが、あまり上手くいかず、紆余曲折を経たあとで夕見になった。毎日の夕暮れを眺めることができるだけでも、充分に幸せなのではないか。それだけでも悦びなのではないか。二人でそう話した。産まれたのは、若くして死んだ私の母の、命日が来る二日前だった。
――憶えてないから、教えてやるんだろうが。
その声を最後に、電話は切れた。
耳に届く不通音にまじって、背後で床が軋んだ。振り返ると、夕見が片手を顔の前に立てながら居間に入ってくるところだった。そばにある戸棚を探り、単三乾電池を一本取って出ていき、そのときになって私はようやく受話器を戻した。強く握った指は、いつまでも剥がれなかった。
夕刻、黙って家を出た。
車に乗り込み、十五年前に訪ねた古瀬幹恵の自宅へ向かったのだ。しかし、その一帯にあった借家はどれも姿を消し、整然と並んだ建売住宅の壁が夕陽を跳ね返していた。向かいの家の玄関から男性が出てきて郵便受けを覗いたので、私は以前あった借家のことを訊ねてみた。すると、五年ほど前に入居者がみんな出され、いっせいに建売住宅が建ったのだという。古瀬幹恵のことを確認したところ、彼女はそれよりも前に自宅で亡くなっていた。いわゆる孤独死で、においに気づいて家主が確認したときには、もう死んでからずいぶん経っていたらしい。
それから今日までの四日間、私は懸命に不安を遠ざけて過ごしてきた。店の厨房に立ちながら、家で過ごしながら、普段どおりに笑い、普段どおり夕見と会話をした。しかしあの脅迫の電話が、あの声が、蟻のように頭の中を這い回りつづけ、睡眠はほとんどとれていなかった。
「お父さん、あたしの心配ばっかりしてないで、自分の心配しなよ」
厨房に入ってきた夕見が、冷蔵庫からビールジョッキを出す。
「お祖父ちゃんが死んで、お父さんが倒れてなんて、冗談にもならないじゃん」
「お前の学費も、あと二年半あるしな」
「お金じゃないよ。お金もあるけど。お通し一つね」
怒ったように言いながら、夕見は生ビールを運んでいく。私は背後の食器棚からお通し用の三寸皿を取った。かぶらあんが入ったボールから、一人分をすくって小鍋に移す。それをあたためているあいだ、ふたたびカワハギの身に包丁を進めていると、客席で発せられた声が耳に届いた。
顔を上げる。
客席は、カウンターと暖簾とのあいだにわずかに覗く程度だ。そこに夕見の足と、背を向けて座っている男の尻が見える。作業ズボンのようなものを穿いている。
夕見の足がテーブルを離れて戻ってきた。
「このお通しは、そこに座ってるお客さんのか?」
「そう、いま来た人。何で?」
「俺が出す」
「知り合い?」
答えず、ぽつぽつと泡の立つ小鍋の火を止めた。中身を三寸皿に移し、それを手にカウンターを回り込んでホールに出る。銀行副支店長のエザワさんが、お、と口をあけて手のひらを斜めに立て、私はそちらに会釈を返してから、新客のテーブルにかぶらあんの皿を置いた。
「こちら、お通しです」
男の顔を見ることができず、しかし視界の端で、相手の目がくるりと私の顔に向けられたのがわかった。
「忙しそうだね」
低い、特徴を消そうとしているかのように平坦な声。私は初めて相手の顔を見た。日に焼けて皺の多い肌。鴉の嘴を思わせる、幅広で長い鼻。知らない男だ。しかしそれが意外なのかどうかも、私にはわからなかった。
「おかげさまで、忙しくやらせていただいてます」
男が口の中で何か呟くが、聞き取れない。なんとかがいいことだ、と言ったようだ。私が表情だけで訊ね返すと、男はビールをあおり、顎を引いて呻いてから、こちらを見ずに言い直した。
「儲かってくれるのは、いいことだ」
全身の血が音を立てて逆流し、かっと頭が熱くなり、沸騰した液体があふれるように言葉が口からこぼれ出た。
「うちに電話をしましたか?」
男はほんの一瞬だけ面食らったような表情を見せたあと、短い鼻息とともに下卑た顔つきになった。箸先で皿の中をつつき、小さく唇を動かす。
「……子供に話したのか?」
私は答えず、しかし内心で力強く首を横に振っていた。話すはずがない。話せるはずがない。
「このことは警察に相談します」
それだけ言ってテーブルを離れた。万一のときは――相手が本当に店へやってきたときは、そうしようと決めていたのだ。警察はきっと味方になってくれる。十五年前だって、夕見の人生を守るために協力してくれた。
「したきゃ、すればいいけどな――」
周囲に聞こえることをためらわない声が私を追いかけてきた。
「そうなりゃ、俺は本人にぜんぶ話すぞ」
頭に集まっていた血液が一瞬で逃げ出し、顔が冷たくなり、相手を振り返るのと同時に、店内の風景が白く掻き消えた。
(二)
「亜沙実さんって、もしかしてこの家に入るの初めて?」
私といっしょに車を降りながら、夕見が姉に訊く。
「そう、初めて。お店も家も。むかし夕見ちゃんを保育園に迎えに行ったあと、入り口までは何度も来てたけど」
「ぜったい上がっていかなかったもんね」
「夕見ちゃん、親とは仲良くしとかなきゃ駄目よ。わたしみたいに、家にも入れなくなっちゃうんだから」
「してる、してる」
三人で店内を抜け、二階の住居へとつづく階段を上がる。それだけの動作でも身体にこたえ、私は居間に入るなり座布団にへたり込んだ。夕見は台所でお茶の用意をしはじめ、姉は中途半端な場所に立ったまま、ぼんやりと家の中を見渡している。
「座りなよ」
「え?」
「座って」
「幸人ちゃん、もっとおっきな声で喋ってね。わたし耳が悪いんだから」
いまから三十年前、十七歳の冬に、姉は右耳の聴力を失った。
「いや亜沙実さん、病人だからその人」
「過労なんて、病気じゃなくてただの体調管理不足。気を遣う必要なんてないのよ」
「あたしより心配してたくせに。はい、お茶。亜沙実さんほら座って」
店で気を失ってから、ひと晩が経っていた。
病院で目を覚ましたのは今朝八時過ぎのことだ。眠っているあいだに採血をされたり、脳波をとられたり、腕に点滴の針を刺されたりしていたが、医者によると単なる過労とのことだった。ここ数日、睡眠が上手くとれていなかったことを伝えると、医者は食べ物や生活習慣についていくつかアドバイスしたあと、一ヶ月分の入眠剤を処方した。私は薬局でそれを受け取り、姉が運転する車に乗せられて家に戻ってきたところだった。
――あのとき店にいたお客さんたち、どうした?
ついさっき、走る車の中で夕見に訊いた。
もちろん本当に知りたかったのは、ただ一人、あの男のことだ。
――救急車が来るまでに、みんなちゃんとお金を置いていってくれた。エザワさんとか、多めにくれたりして。最後に来たお客さん、あのほら、お父さんの知り合いの人? あの人だけは、もうお父さんに払ったって言ってたから、もらわなかったけど。
私が黙って顔を見返していると、夕見は急に驚いた表情になった。
――もしかして、もらってない?
もらったと、私は嘘をついた。
――あの人は……何か言ってたか?
――また来るって。
夕見は屈託なくそう返した。
「幸人ちゃん、なんか顔が怖いんだけど」
気づけば、姉が座卓の向こうからまじまじと私を見ていた。
「過労じゃなくて、なんか悩みがあるとか? じゃなくて、悩みで眠れなくて過労とか?」
「そりゃまあ、店のこととか、いろいろね」
「考えるのはいいけど、幸人ちゃん、悩んだらおしまいよ。悩むのと考えるのとは大違い。立ち仕事なのに寝不足って、駄目よそんなの」
曖昧に頷くと、夕見がお茶を運んできて卓上に置いた。湯気の向こうの仏壇には、三つの遺影が並んでいる。静かに頬笑んでいる母。歯を見せて笑っている悦子。表情のない目でこちらを見ている父。
生まれてから三度、家族を亡くした。それでも五日前まで、世界はどうにか平衡を保ってきた。ぐらつきながらも壊れずにいた。しかしいま、その屋台骨に亀裂が入り、不穏な軋みを上げているのがはっきりと聞こえた。いや、軋んでいるのは私の世界ではない。夕見の世界だ。母親が死んだときから、娘はその現実と毎日のように闘い、やがて、なんとか折り合いをつけて生きられるようになった。保育園の卒園式でみんなが歌っているとき、母親ばかりが埋めた保護者席を前に最後まで口を動かさなかったのに、こうして笑顔で過ごせる新しい世界をつくり上げた。自分自身の力で。
「どっか……遠くに行ってみようか」
夕見や姉に言ったのか、遺影に話しかけたのか、自分にもわからなかった。
座卓の向こう側に座る二人が、表情だけで訊ね返す。私はつづける言葉を探しながら、この場所を離れたいという思いが――あの男から離れたいという思いが、いま急にわき起こったものではないことを意識した。
「なんか、いろいろ、疲れたから。少しのあいだだけでも」
「……ほんとに?」
夕見がぐっと眉を上げる。私が頷くと、娘は「だったら」と言うなり居間を飛び出し、片手に大きな本を持って戻ってきた。
「行ってみたい場所があるんだけどさ」
卓上に置かれたのは、古い写真集だ。表紙には「
「この人、あたしが一番尊敬してる写真家。もう亡くなってるけど」
「それで、夕見ちゃんが行ってみたい場所って?」
夕見は写真集を自分のほうへ引き寄せ、「ここ」と、ひらき癖のついたページを広げた。
奇妙な写真だった。
ほかのものと違い、被写体は人間ではない。全体的に真っ暗なので、夜に撮られたものだということはわかるが、いったい何を撮影したものなのだろう。下側の三分の一ほどは、黒く沈んでいる。上側には、白くて小さな花が大量に散っている。これは夜の草原を上空から撮ったもので、下側の黒い部分は、海か湖なのだろうか。草原の中央には、野生の動物が駆け抜けたような直線が斜めに走っている。――いや違う、これはページについた傷かもしれない。そう思い、私はその直線に指で触れてみたが、指先はスムーズにその上を行き過ぎた。
「……空か」
よくよく眺めてみると、それは夜空を写したものだった。下側の黒い部分は山影。その上に散っている白いものは無数の星。引っ掻き傷のように見えるのは流れ星。
「同じ場所で写真を撮って、それをキマ写で提出したいの」
「きましゃ?」
姉が訊き返したので、夕見は大学の期末写真について説明した。
「で、そのテーマがなかなか決まらなくて困ってたんだけど、ちょっと前に思いついて。尊敬する写真家が撮った写真と、同じものを撮るのはどうかって」
「……盗作?」
「違うよ。レベルの高いものをわざと目指して、自分がどこまで近づけるかを試すの。だから要するにテーマは、何だろ、いまの自分っていうか」
「いいじゃない、面白そう。場所ってどこなの?」
夕見は写真の下を指さした。ほかのページ同様、撮影された年、月、場所がそこに付記されている。
それに目をやった瞬間、私も姉も動けなくなった。
1981年 11月 新潟県羽田上村
地名にふりがなは振られていない。しかし私たちは「羽田上」を「はたがみ」と読むことを知っていた。その村が新潟県のどこにあるのかも。
「ごめん……じつは、半分くらい口実」
夕見が顔を上げて私たちを見る。
「お父さんも亜沙実さんも、死んだお祖父ちゃんも、自分たちが暮らしてた場所のこと、ぜんぜん話してくれないから、気になってたんだよね」
その村は、私と姉の生まれ故郷だった。
三十年前、父に連れられて逃げ出した場所だった。
かつて羽田上村で起きた出来事を、夕見は知らない。私も姉も父も、何ひとつ聞かせてこなかった。いや、私たち三人のあいだでさえ、あの事件については一切の言葉を交わさず、この埼玉県に移り住んでからずっと、忘れたふりをして生きてきたのだ。夕見が知っているのはただ一つ、姉の身体が三十年前の落雷によってこうなったことだけだ。
「ずっと前から、一度行ってみたいっていう気持ちがあって……だってほら、自分のルーツになった場所でしょ」
私の目はふたたび「羽田上村」という文字に吸い寄せられていた。子供の頃、この村名の由来を聞いたことがある。冬の寒い台所で、母が昼食のハタハタを焼いてくれているときだった。
――この魚の名前は、もともと“雷”っていう意味なの。
ハタハタは十一月から十二月に旬を迎える。それは日本海側でちょうど雷の季節にあたり、雷の音を表す古い言葉“ハタハタ”が、そのまま魚の名前となったのだという。
――この村は雷が多いから、“ハタハタが噛みつく村”っていう意味で、羽田上って名付けられたのよ。
第二章 記憶の崩壊と空白
(一)
三十一年前。
あの事件が起きる一年前。
羽田上村を東西に貫く幹線道路の裏手で、父と母は小さな居酒屋を経営していた。郷土料理と日本酒を中心とした店で、県内でとれた魚介や山菜、何より村の名産であるキノコを豊富に使った料理を出し、ちょうどいまの私や夕見のように、父が厨房に立ち、母が客席で働いていた。建物のつくりも似ていて、一階が店舗、奥にある階段を上ると二階の住居へとつながっていた。
地図で見ると、羽田上村の南には越後山脈から連なる山々が迫り、村の北側は後家山という山が大きな面積を占めている。山と山とのあいだにある、獣道のようなその隙間に、人々は集まって暮らしていたのだ。
海は近いが後家山の向こうだったので、漁業は発展せず、土地の産業基盤は鉄鋼業とキノコだった。社会科の授業で教えられた村の歴史によると、鉄鋼業がはじまるまで、人々の暮らしはほぼキノコのみによって支えられていたらしい。しかし明治時代に近隣の柏崎市で油田が発見されたことで、小さな羽田上村でも山沿いに製油所が軒を連ねるようになった。それと同時に鉄鋼業が盛んになり、村は好景気に沸き立ったが、やがて昭和に入ると海外から安価な石油が入ってきて、産業は急速に衰退してしまった。そうして羽田上村の好景気は終焉を迎え、私が暮らしていた当時は、もう製油所の姿などどこにもなく、生き残った鉄鋼業と、昔からのキノコ栽培が村を支えていたのだ。
羽田上村の旗や広報誌には、隆盛期につくられたという村章が入っていたが、思えばあれは皮肉なデザインだった。三角形の真ん中に逆三角形がはめ込まれ、つまり四つの小さな三角形が組み合わさったかたちをしているのだが、上の三角形は黒、左下の三角形は赤、右下は茶色に染められていた。それぞれの色が表しているのは、石油、製鉄、キノコ。真ん中の逆三角形だけは白く、未来の新しい産業を表していたのだという。しかし、昭和の時代に製油業が衰退し、上の三角形が意味をなくした。新しい産業が興ることもなく、四つめの三角形は何色にも塗られないまま、何十年も経っていたのだ。
両親が経営していた店は「英」といい、羽田上村にある唯一の居酒屋だった。私は家に出入りするたびいつもその看板を目にしていたし、何よりそれは母の名前でもあったので、「英」を「はな」と読むことに幼い頃から何の違和感も持っていなかった。むしろ、小学校の授業でその漢字を「英語」の「英」として教わったとき、別の読み方があったのかと驚いたのを憶えている。あのとき教室で、担任の男性教師は文字の由来について説明した。「央」に「美しいもの」という意味があるので、草冠をつけたとき「はな」と読まれるのだという。そう話しながら、教師は私の顔を見ていた。
――美人だもんね。
クラスの女の子が声を飛ばした。名前は忘れてしまったけれど、髪の短い、キツネ目の子だった。私はそのとき曖昧に首をひねってみせたが、自分の母親が綺麗な人であることは子供心にも理解していた。
店に来るほとんどの客は男性だった。当時の世の中がそうだったのか、羽田上村の女性が飲みに出かけることをしなかったのか、あるいは母の容姿のせいだったのか。
男性客たちはいつも母に、容姿を褒めるような言葉を投げた。その内容というよりも、口ぶりが私は嫌いだった。聞こえてくるたび、男たちの声がなまあたたかい感触で自分の肌を撫でるような気がした。店自体に対しても好ましい印象を持ったことはなく、人が粗暴で下品になるその場所が、家の真下にあることをみっともなく思っていた。
父も母も、もともと羽田上村の家系ではない。
父の名は藤原南人といい、群馬の生まれだった。四兄弟の下から二番目で、北栄、東馬という兄、西太郎という弟がいる。父方の祖父は、息子たちに日本中に散らばって名を成してほしいと願い、それぞれの名前を与えたのだという。しかし父以外の三人は地元の民間企業に勤め、父だけは地元を出たが、名前と逆に北へ向かい、山懐に抱かれた村で小さな店をひらいた。
母方の祖父母は、好景気だった時代に羽田上村へ移住したと聞くが、私が生まれたときにはどちらも病気で亡くなっていた。二人からの遺伝なのか、母も生まれつき身体が丈夫ではなく、小さい頃からしばしば寝込んで学校を休んでいたらしい。
――お花が好きになったの、そのせいかしらね。
店の定休日に、南向きの庭を眺めながら、いつだったか母はそう言った。意味が掴めなかったので訊ね返すと、子供のころ母が寝込むたび、祖母が花を摘んできて、枕元に置いてくれたのだという。
――ガラスのコップにお水を入れて、そこにお花を挿してくれたの。それが何の花でも、目をつぶると、いいにおいがしてね。
そのうち、枕元を見もしないで花の種類がわかるようになったのだと、母は笑っていた。細めた目の先には、色とりどりの花が植えられた庭があった。母が世話していたあの庭には、どんな季節でも花が咲いていた。眺めて愉しむばかりではなく、生薬というのだろうか、ときおり庭から何かの葉や花弁、種や根を取ってきては、母はそれらを乾燥させて茶封筒にためていた。それぞれの効能を一冊のノートにきちんとまとめ、自分自身の体調がすぐれないときはもちろん、私や姉が腹を壊したときや風邪をひいたとき、父が酒を飲み過ぎたとき、ノートを捲りながら、謎の乾燥片を煎じたり粉末にしたりして服ませるのだった。どれもひどく不味かったが、大人になってから服んだ薬で、あれほど効いたものは一つもない。
「祭り、やるってなあ」
事件を振り返るとき、朝食の卓袱台で父が口にしたその言葉が、いつも“発端”として想起される。
村の寒さが厳しさを増してきた十一月半ばだった。祭りというのは、毎年十一月最後の日曜日、後家山の中腹にある雷電神社で行われる神鳴講のことだ。
事実かどうかは知らないが、雷が落ちた場所にはキノコがよく生えると言われる。雷電神社にはその名の通り雷神が祀られ、昔から村の産業の守り神とされてきた。十一月下旬は、あの地域で雷の季節のはじまりであるとともに、キノコの季節の終わりでもある。神社では、大量のキノコを前もって干しておき、それらを使ってキノコ汁をつくる。そして祭りの当日、羽田上村の人々は、子供も老人も神社に集まってそのキノコ汁を食べ、収穫への感謝を捧げるとともに、翌年の豊作を祈願するのだ。毎年、神鳴講の準備がはじまると、密閉されたような村の空気が急に動き出し、その瞬間がいつも私は楽しみだった。
しかし三十一年前は、その年の九月に吐血した昭和天皇が闘病のさなかにあった。世の中は自粛ムードに包まれ、全国各地で伝統行事の中止や規模縮小が実施されていた。雷電神社でも、例年通り大量の干しキノコが用意されてはいたが、はたして神鳴講が開催されるのかどうかはっきりせず、村人たちはみんな神社の判断を待っていたのだ。境内にはいつものように露店が並ぶのだろうか。もらった小遣いで射的をやったり、クジを引いたり、祭りで行き会った友達と木々の中を走り回ったりできるのだろうか。父も毎年、神鳴講には趣味の一眼レフカメラを持参し、祭りの風景を写真におさめるのを楽しみにしていたので、しばらく前からずっと開催のことを気にかけていた。
「お祭りの汁、天皇が入院してる病院にも送ってあげればいいのに」
当時十二歳だった私の言葉に、父は声を上げて笑い、大きくひらいた口の中に朝日が差し込んだ。あの頃の父は、よく笑っていた。
「身体にはいいけどなあ、なにも病気が治るわけじゃねえ。遠くの村からコケ汁なんて送りつけられたところで、毒でも入ってんじゃねえかって、食わねえだろうしなあ」
あの地方ではキノコを「コケ」と呼び、キノコ汁は「コケ汁」だった。村の北側大部分を占める後家山も、昔からキノコが多く採れたことから、「コケ」が転訛して「後家」になったと聞く。
「あんた、自分じゃ食べないくせに、人には食べさせようとすんのね」
姉が私をからかった。羽田上村に生まれていながら、私はキノコが苦手で、まったく食べられなかったのだ。
「天皇は人じゃないんだよ」
「人だから病気になるんでしょ」
言い合いながらも、私たちの声ははずんでいた。
「お祭りって、いつもとおんなじふうにやるの?」
念のため父に確認してみると、心得顔で頷かれたので、私は箸を持ったまま拳を握った。
「開催すること、希恵ちゃんのお母さんが決めたのかな?」
姉が訊いた。太良部希恵は神社の一人娘で、姉の同級生だった。二人はよく放課後の時間をいっしょに過ごし、希恵が家に遊びに来るたび、私は恥ずかしくて外へ出た。希恵の肌はいつも日に焼けて、頬や腕はバターロールを連想させた。色白の姉と並ぶと、姉はより物静かに大人びて見え、希恵はより生き生きと活発に見えた。
その希恵の母親である太良部容子が、雷電神社の宮司だった。
女性宮司というのは全国でも少なく、大きな神社などでは女性が宮司になること自体、認められないことが多いと聞く。雷電神社でも代々男性が宮司を務めてきたが、先々代の宮司夫婦のもとに生まれたのが容子という娘のみだった。彼女の結婚相手が、婿入りというかたちでいったん宮司となったのだが、着任して間もなく病死し、彼女がその任を引き継いで、初の女性宮司となったのだ。
「もちろん最後にはそうだろうがよ、うちに来るしんしょもちさんらが、宮司さんにやれやれ言ったのかもしれねえなあ」
「しんしょもち」は「身上持ち」の意味だ。もともとは金持ちを表す方言だが、羽田上村においては、ある特定の四人を指した。英によく酒を飲みに来ていた四人。自分たちの存在を見せびらかすように、いつも大声で喋り、酒を飲んでは母の容姿について下卑た言葉を飛ばしていた。そして、相手が喜んでいることを確信したような笑い声を上げるのだった。
「来るじゃなくて、来てくれるでしょうが」
お茶を運んできた母にたしなめられ、父はぺろりと舌を出した。
「うちの売り上げもずいぶん支えてもらってるんだし、あの人らがいなきゃ、村だって神社だって危ないっていうんだから」
(二)
それから半月ほどが過ぎた。
神鳴講の開催が翌々日に迫った金曜日、母は雷電神社にいた。
村人に振る舞うためのコケ汁は大量につくらなければならず、事前に仕込む必要があるので、その作業にかり出されていたのだ。長いあいだ干されていたキノコにカビが生えていないかどうかなどを一つ一つ確かめ、布で丁寧に拭ったあと、三つの大鍋でそれを煮る。そうして出来上がったコケ汁が、寒い神社の中で一日半ほど寝かされ、味が馴染んだあと、当日の神鳴講で振る舞われる。毎年、何人かの女性が手伝いに呼ばれるのが慣例だったが、母はきまって彼女たちの中にいた。誰が選んでいたのかは知らない。
母が不在なので英は臨時休業となり、父は毎年その金曜日を店内の掃除や修繕に充てていた。私と姉も、学校から帰ると、酒器棚を空にして中を拭いたり、父が分解した換気扇の油を雑巾でこそぎ落としたりしながら夕方を過ごした。やがて母が神社から戻ってくると、私たちは二階にある自宅の卓袱台ではなく、客席のテーブルを囲み、父がつくった料理を食べる。年に一度、そうして店内で食事をすることに、私はいつも胸が躍った。父は毎年、徳利を四本用意し、自分のものには酒を、私と姉、そして下戸の母のものにはお茶を入れた。私たちはそれぞれの徳利から、自分のお猪口に中身を注ぎ、料理をつまみながら飲んだ。店で酒を飲む男たちが嫌いだったくせに、私は彼らの真似をして、お猪口を親指と人差し指で持ち、唇をすぼめてお茶をすすった。
しかしその年は、夕刻になっても母が戻らなかった。
帰りの遅い母を、私たちが心配しはじめたとき、店の電話が鳴った。屋外はもう暗く、時刻は午後六時前後だったと記憶している。父が受話器を取ると、電話は雷電神社にいる母からだった。コケ汁の仕込みが予定通り進まず、もうしばらくかかってしまう。子供たちには先に晩ご飯を食べさせてやってくれ。私は父の隣にくっついて聴き耳を立てていたので、母が話す言葉が聞こえた。そして、その後ろに響く男たちの笑い声にも気づいていた。
「準備が終わってないのに、何で騒いでたの?」
受話器を置いた父に訊くと、こちらを見ないで答えた。
「宵宮がはじまってるんだろ」
「よいみやって?」
「祭りの前にやる、小さな祭りだ」
そんなものが行われていたこと自体、初耳だった。しかし父によると、コケ汁の仕込みをする夜に、毎年やっているのだという。
「それって何するの?」
「しんしょもちさんらが集まって、お酒飲むだけ」
答えたのは床を掃除していた姉だった。モップの頭をバケツに突っ込み、いま拭いたばかりの床板に灰色の点を散らせたあと、ほとんど聞こえないほどの声でつづけた。
「希恵ちゃんが、嫌がってた」
「王様らを大事にしねえと、いろいろ上手いこといかねえからな」
村のしんしょもちというのは、黒澤、荒垣、篠林、長門の四人だった。
黒澤家はかつて製油で成功した油田長者であり、石油ブームの頃に所有した多くの土地建物のおかげで、ブームが去ったあとも多大な財産を維持していた。荒垣家は製鉄の技術を活かした金属加工業で大成功し、篠林家は村で最大のキノコ農家。そして長門家は、村内唯一の病院である長門総合病院を経営していた。村章を染める黒、赤、茶色――石油、製鉄、キノコは、そのまま黒澤家、荒垣家、篠林家のことであり、そこに大病院を経営する長門家が加わった四家が、村を経済的に支えていたのだ。当時それぞれの家で実権を握っていたのが、英にしばしばやってきていた黒澤宗吾、荒垣猛、篠林一雄、長門幸輔の四人。いずれも四十歳前後の、いま思えば脂ののりきった年齢の男たちだった。
以前に母が言ったように、雷電神社の経営も、四家からの寄付金に多くを頼っていたらしい。神社では宮司の手で「雷除」と書かれた小さなお守りを売り、村人たちは毎年それを買い換えるのが習わしだったが、いかんせん安いものなので、あまり足しにはなっていなかったに違いない。氏子費や賽銭箱からの収入も、ほんの微々たるものだっただろう。
「徳利、出す?」
姉がモップを仕舞って父を振り返った。
「母ちゃんもいねえし、今年はいいだろ」
父が簡単な料理をつくり、姉がそれを手伝うのを、私はただ憮然と眺めた。酔っ払った男たちの声を聞きながら働かされている母が可哀想だった。家族四人で店のテーブルを囲む楽しみを奪われた自分が可哀想だった。父はカレイの刺身と、野菜の味噌漬けと、カジカの半身を焼いたものを出してくれた。私と姉はそれぞれご飯をよそい、魚と漬け物を食べながら、グラスの水を飲んだ。父は母の帰りを待つと言って何も口にせず、一本のビールをのろのろと飲んでいた。私もまた母をできるだけ待つつもりで、最初はなるべくゆっくり箸を動かしていたのだが、腹が減っていたせいで、気づけば茶碗が空っぽになっていた。やがて姉も食事を終え、その頃にはもう、母が電話をかけてきてから一時間ほどが経っていた。
私と姉で洗い物をしたあと、姉は二階から学校の宿題を持ってきてテーブルに広げた。使っていた筆入れは太良部希恵とお揃いのもので、その年の春に上映された「となりのトトロ」の劇場グッズだった。私と三人で、バスと電車を乗り継いで行った映画館で買ったのだ。私も何かほしかったし、そのための小遣いも持っていったのだが、女の子たちが主人公の映画だったので、恥ずかしくて手ぶらで帰ってきた。
「お母さん、また体調悪くならないかな」
店の時計を見て私が心配すると、姉も頷いた。
「神社の作業場、寒いしね」
時刻はもう八時を過ぎていた。あまりに遅すぎた。時計を見上げていた私と姉の目は、やがて父のほうを向き、それに促されるようにして父は腰を上げた。
「神社に電話してみっか」
すると、ちょうど電話が鳴った。
「英です」
父が受話器を取ると、女の人の声が聞こえた。言葉までは聞き取れない。母かと思ったが違うようだ。
「いえ……戻ってませんが」
女の人はそのあと数秒、何も言わなかった。しかしやがて、途切れ途切れの声が受話器から聞こえはじめ、それが雷電神社の宮司、太良部容子のものであると私は気づいた。父は何も言葉を返さず、その顔はまるで難しいなぞなぞでも出されているようだった。私と姉は耳をすましたが、途中から父が受話器を強く耳に押しつけたので、相手の声は聞こえなくなった。
「――すぐ行きます」
父が電話を切り、まだなぞなぞのつづきを聞かされているような顔で私たちを振り返った。
「母ちゃんが、いねえんだって」
私たちが何か訊ねるよりも早く、父は椅子の背にかけてあった茶色い革のジャンパーを掴んだ。
「じき戻ってくるから、心配しねえで待ってろ」
店を出た父の姿を、引き戸の格子が縦に細かく切り分けていた。父は左手の駐車場へ向かいかけたが、母が神社へ行くのに車を使っていたのを思い出したらしく、ぐるりと身体を回して右手に消えた。物音のない夜で、靴音が速くなりながら遠ざかっていくのが、長いこと耳に届いた。
母がいなくなったというのは、いったいどういうことだろう。父にもわかっていないようだったし、私たちにはもっとわからず、二人してテーブルの脇に立ったまま引き戸の向こうを見つめていた。そこはただただ真っ暗だった。
何か大変なことが起きたという意識は、まだなかった。しかし、涙の先触れが目の裏側を熱くした。姉がそれを察し、私の頭にそっと手をのせた。その手の温度に引っぱられて涙が溢れた。両手を握って下へ突き出したまま、唇を真横に閉じ、鼻と目だけで、私は泣いた。不安はもちろんのこと、徳利でお茶を飲めなかった悔しさや、母の帰りを待たずに腹を満たしてしまった後悔や、それが何か母に不幸を飛ばしてしまったのではないかという思いも手伝い、泣きやもうとしても、できなかった。私は当時、小学六年生にしては背が高いほうで、小柄な父とほとんど変わらないほどだった。そんな身体なのに泣きやむことができないのが情けなくて、いっそう涙が出た。
「なじょも、なじょも」
私の頭に手をのせたまま姉が囁いた。新潟弁を聞きも話しもしなくなったいま、おまじないのように思い出される、「大丈夫」という言葉だった。
(三)
夜遅く、母は見つかった。
後家山の反対側、道もない斜面を下りきった場所にある川で、靴も履かず、冷たい水の中に倒れていたのだという。
見つけたのは村人たちとともに母を捜していた父だった。
山の斜面は急なので、意識のない母を運ぶには川沿いを行くしかなかった。父は母を背負い、数人の男たちとともに河原を歩き、やがていちばん近くの道路まで辿り着いた。一人がそれに先行し、民家の電話ですでに救急車を呼んであったので、母はすぐさま長門総合病院へと搬送された。
英で待っていた私と姉を病院まで連れていってくれたのは、富田さんという農協職員の男性だった。後部座席で手を繋ぎ合った私たちに、富田さんは事情を話して聞かせながら、真っ暗な夜道に車を走らせた。
――お母さんの靴が、最初に神社の近くで見っかってな。
川まではかなりの距離がある場所だったらしい。
――そっから山ん中を、ずっと裸足で……いってえ何があったんだか。
病室のベッドに寝かされていた母の顔は、血の気を失い、まるで白い紙で折られたもののように見えた。水滴で曇った酸素マスクがその顔にのせられていた光景を、私は一枚の写真のように鮮明に、いまも憶えている。母に対してできることはすべてやりつくされたあとだったのだろう、身体を覆う白い掛け蒲団には皺の一つもなかった。
私たちの直後に病院へやってきた太良部容子が、母が神社から消えたときの経緯を説明した。彼女によると、母は社務所に併設された作業場で、ほかの三人の女性たちとともにコケ汁を仕込んでいた。例年よりも作業に時間がかかってしまったので、どうしても夕刻に帰らなければならなかった一人だけが神社をあとにし、残りの三人は、それぞれ家に電話をかけて帰りが遅くなることを伝えた。
「ようやくコケ汁の仕込みが終わったのが七時過ぎで、英さんもほかのお二人も、荷物を持って作業場を出ていきました。わたしは本殿での準備が残っていたので、そちらへ行って――」
そこでの作業が一段落したとき、ふと駐車場を見ると、母の車がまだ停まっていることに気づいた。母が作業場をあとにしてから、もう一時間ほどが経っていたので、彼女は奇妙に思って母を捜した。
「作業場にも社務所にも、いませんでした」
社務所の奥にある和室では、しんしょもちの四人が例年のように宵宮の酒を飲んでおり、太良部容子はそこも覗いてみたが、やはり母はいない。四人に訊いてみても、姿を見ていないという。駐車場に車があることを話すと、男たちは腰を上げ、いっしょになって周囲を捜してくれたが、やはり母の姿はどこにもなかった。
「何かの理由で車を置いて帰宅したんじゃないかということで、わたしがご自宅に電話をかけてみたんです」
それが、父が受けた電話だった。
母が神社から姿を消した理由も、裸足の状態で川の中に倒れていた理由もわからなかった。冷たい水に浸かって衰弱していた母は、病院での手当も虚しく、その夜のうちに息を引き取った。命の糸は音もなく切れたので、医者が母の死を告げたあとも、私はそれを信じることができなかった。
翌日、私は村の葬祭場で、父や姉と並んで折りたたみ椅子に座っていた。
父は頭を垂れたまま石のように動かなかった。父と私のあいだに座った姉は、終始ハンカチを顔に押し当てて背中を震わせていた。私は生まれて初めて突きつけられた死という概念を受け止めきれず、前日には母が消えたと聞いただけで泣き出したというのに、涙がまったく出なかった。ただぼんやりと床を見つめ、弔問客たちの足音や、囁くような会話を、ひとつづきの長い音のように聞いていた。初めて涙が出たのは、翌日の神鳴講が通常どおり行われることを、村人たちの会話から知ったときのことだ。私はそれを、自分たち家族への裏切りのように思った。怒りが胸を満たし、その怒りに押し出されて涙が溢れた。姉が隣から頭を抱き寄せ、私はその胸にひたいを押しつけながら泣きつづけ、それに憐れを催した弔問客たちのすすり泣きが聞こえてくると、怒りがさらにふくらんで涙と嗚咽を押し出した。
(四)
ほどなく、村に雷がやってきた。
来る日も来る日も、雷雲は家々に腹をこすりそうなほど低く垂れ、村全体が一筆描きの絵のように奥行きをなくした。遠い都会の病院では昭和天皇の闘病がつづいており、年賀状に「おめでとう」という表現を使わないよう学校で注意された。この世からいなくなってしまった母よりも、いなくなりそうな人間のほうが重視されているようで、私の怒りと哀しみはさらに嵩を増した。母の命日が多くの人に知られることなどないのに、いつか天皇が死んだとき、その日付はきっと後々まで人の記憶に残るのだろう。そう思うと鼻の奥が熱くなり、涙で教室が眩しかった。
父は人が変わったように無口になっていた。私や姉が話しかけても、ほとんど声を返さず、ずっと前からそこに生えている木のように、いつまでも動かないこともあった。そうしたとき、父の両目は木の幹にあいた二つの穴に見え、しかしその奥に、何かがあるような気がした。何かがいるような気がした。店の営業は再開していたが、客足は遠のき、階下はいつも静かで、四人のしんしょもちたちも姿を見せなくなっていた。
家では姉が母にかわって掃除や洗濯をした。私が手伝おうとしても、まるで死んだ母の存在を自分の中で生かそうとしているように、頑なに一人でこなすのだった。庭仕事についても同様で、姉は時間を見つけては草花の世話をした。母が生薬の知識をまとめていたノートをすべて書き写し、自ら勉強したことを書き足し、私や父の体調を見ては、植物の種や根を服ませてくれた。
かつてと変わらず綺麗な部屋、庭の花々、私たちの洋服。具合が悪くなったときに服まされる苦い薬。姉のおかげで、表面的なものはみんな同じまま、ただ母だけがいない毎日だった。しかし私たちは、家族が減ってしまった家の、たとえようもない、不可逆的に変化した空気を吸いながら日々を生きていたのだ。そして、その空気の中、すべてがゆっくりと、取り返しのつかない爆発に向かってうねりつづけていた。
吹き抜ける風が冷たい棘を持ちはじめ、寒いときに使われる「さーめ」という言葉が飛び交い、雪が村を白く塗り替えた。どの家の屋根も同じに見えるその風景が、私は好きだったはずなのに、胸はまだ怒りと哀しみでふくれきったままだった。毎年の初雪をきまってカメラにおさめていた父も、もう居間の棚に置かれた一眼レフを手にすることさえなくなっていた。
母が眠っていたのは村内の寺にある墓地だった。藤原家の墓が遠い群馬県にあったので、父が新たに建てたのだ。放課後に一人でその墓へ足を向け、四角い姿になった母を見つめながら、私はどんなことがあってもこの村で大人になろうと思った。母のそばでいつまでも暮らそうと。
年が明け、一月七日に昭和天皇が崩御した。
平成という慣れない言葉を口にしつつ、世の中の自粛ムードはさらに色濃くなった。
しかし、やがてそれも雪解けとともに遠ざかり、夏が過ぎ、秋が来た。そのあいだ村は、母の死など忘れたように平穏で、ただ季節ごとに見慣れた景色が広がっているばかりだった。だが、いまにして思えば、あのとき村人たちは来たるべき事件への残り時間を過ごしていたのだ。
十一月になるとドイツでベルリンの壁が崩壊し、最後の土曜日には寺で母の一回忌が行われた。その日は朝早くに雪が降り、本堂から見える松の葉が薄白く染まっていた。あの村で雷よりも先に降雪があるのは珍しいことだが、一夜明けた神鳴講の当日には、先を越された雪に追いつくように、早朝から後家山に大きな落雷があった。ほんの数時間後に、私や姉から大事なものを奪い去り、人生を大きく変えることになる雷だった。