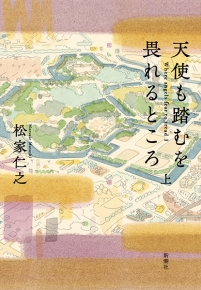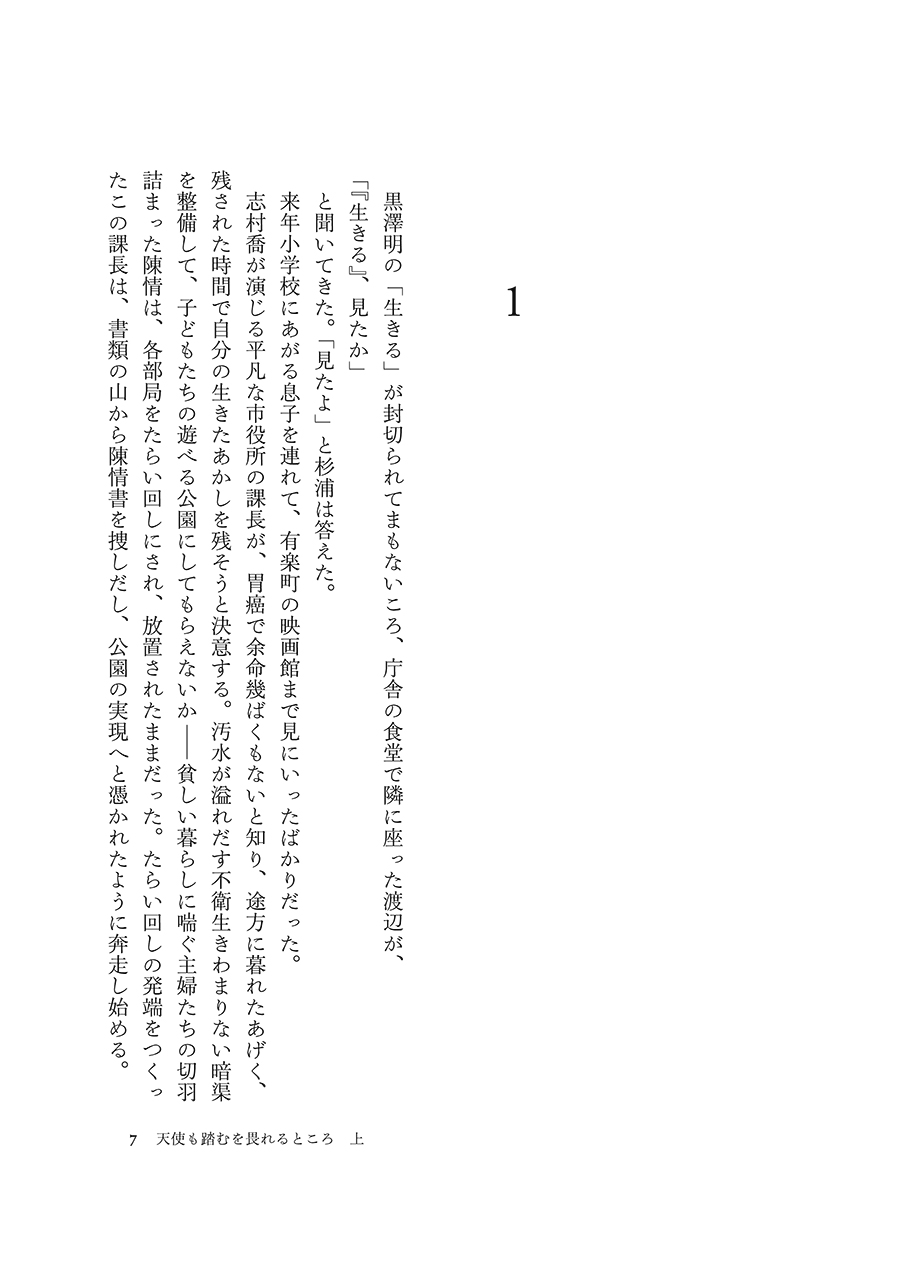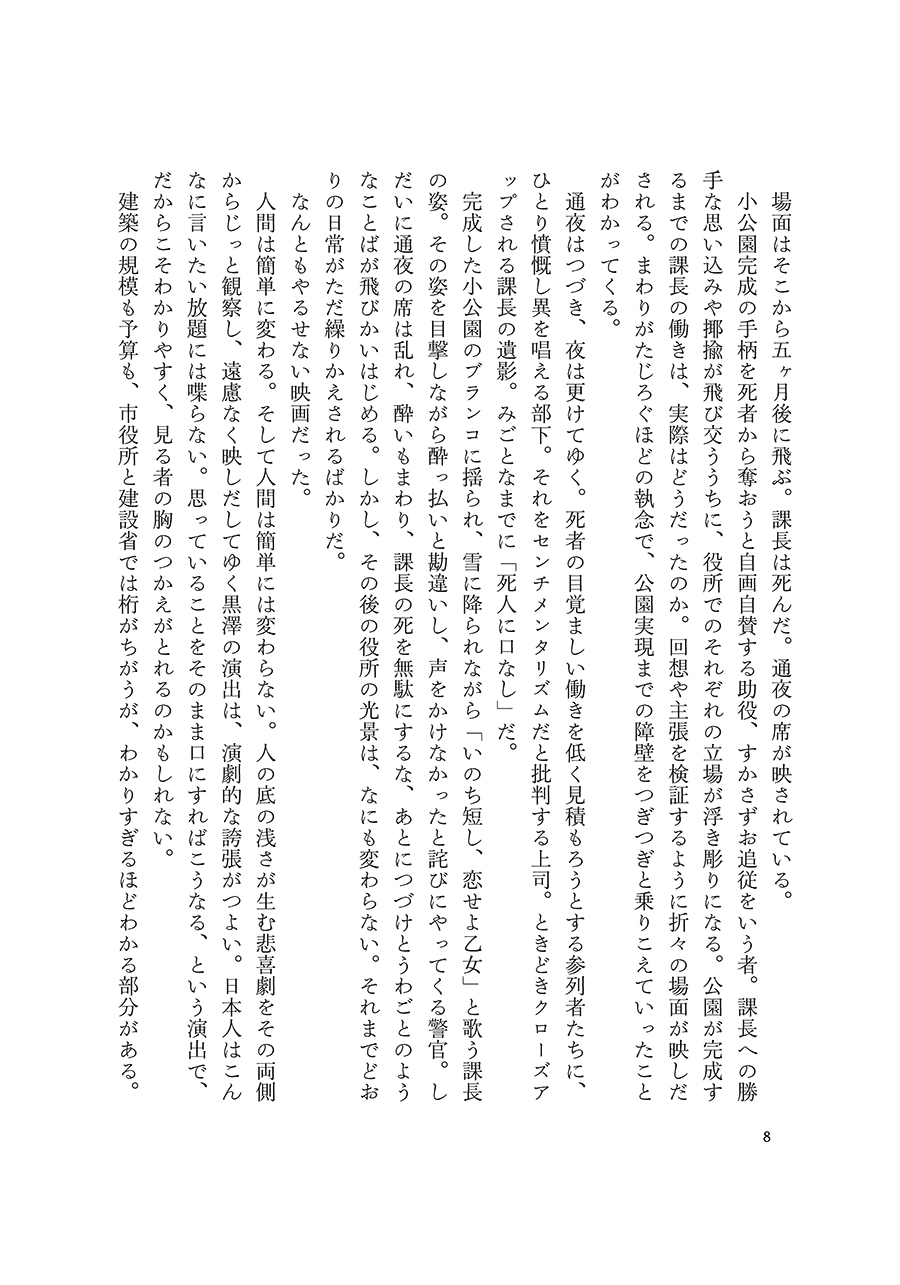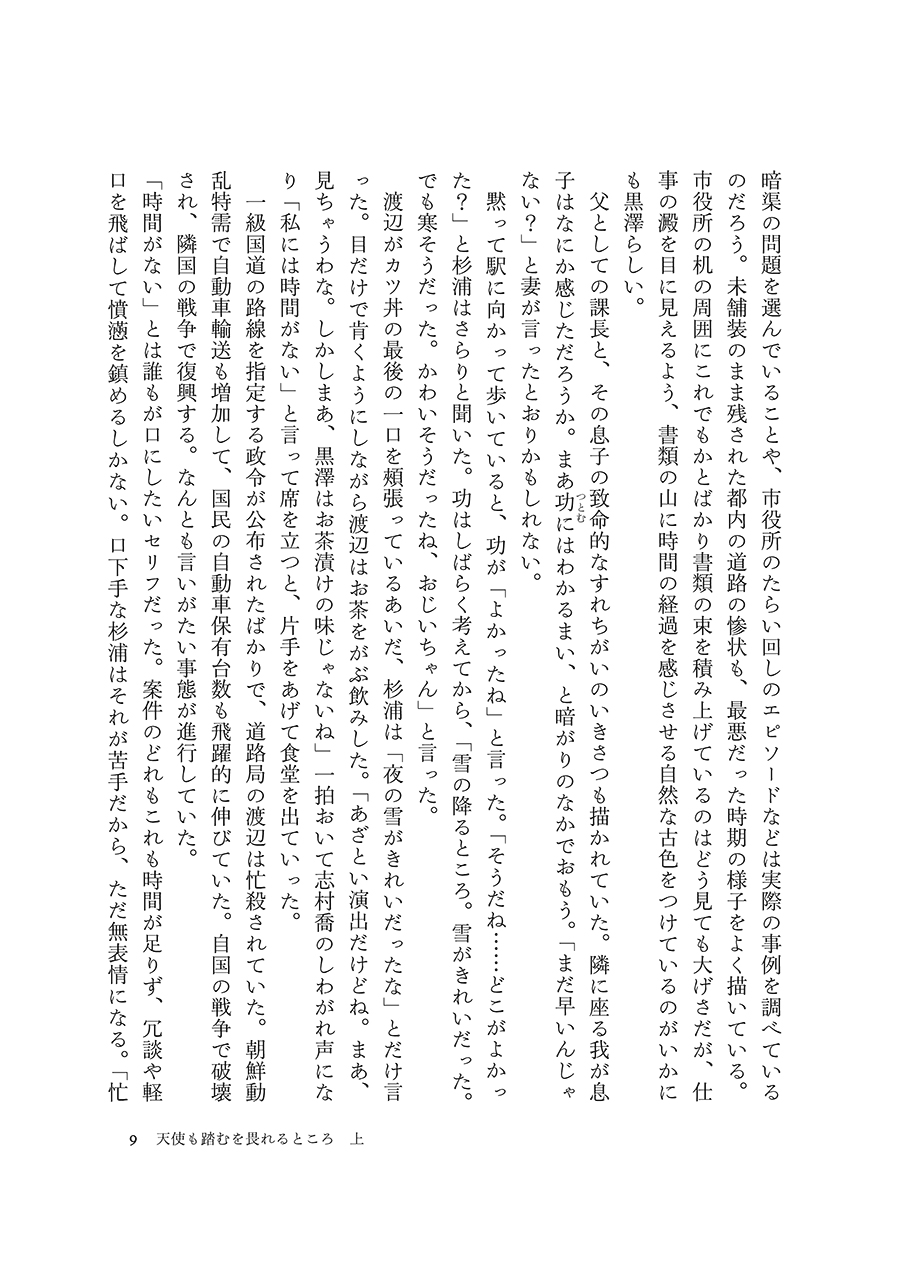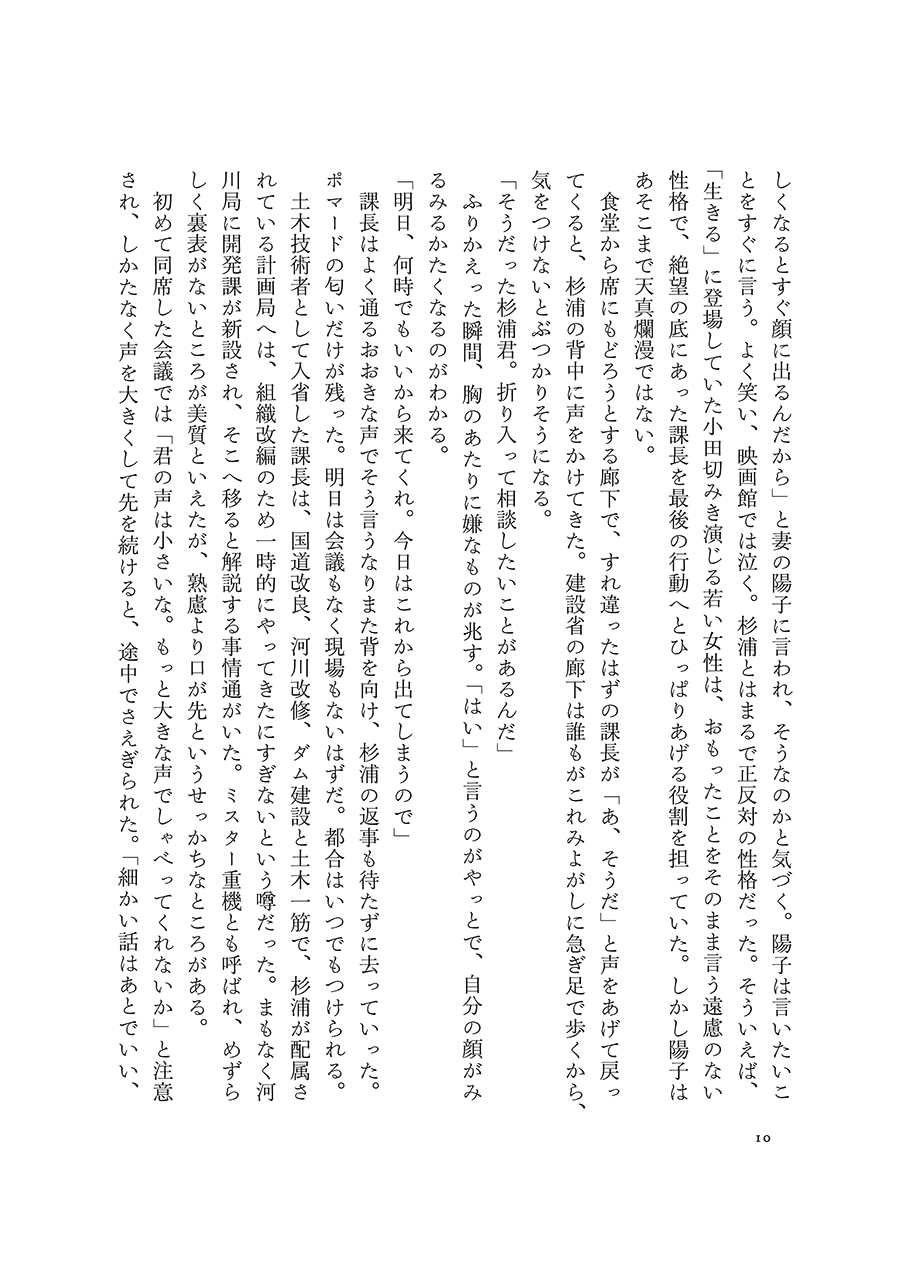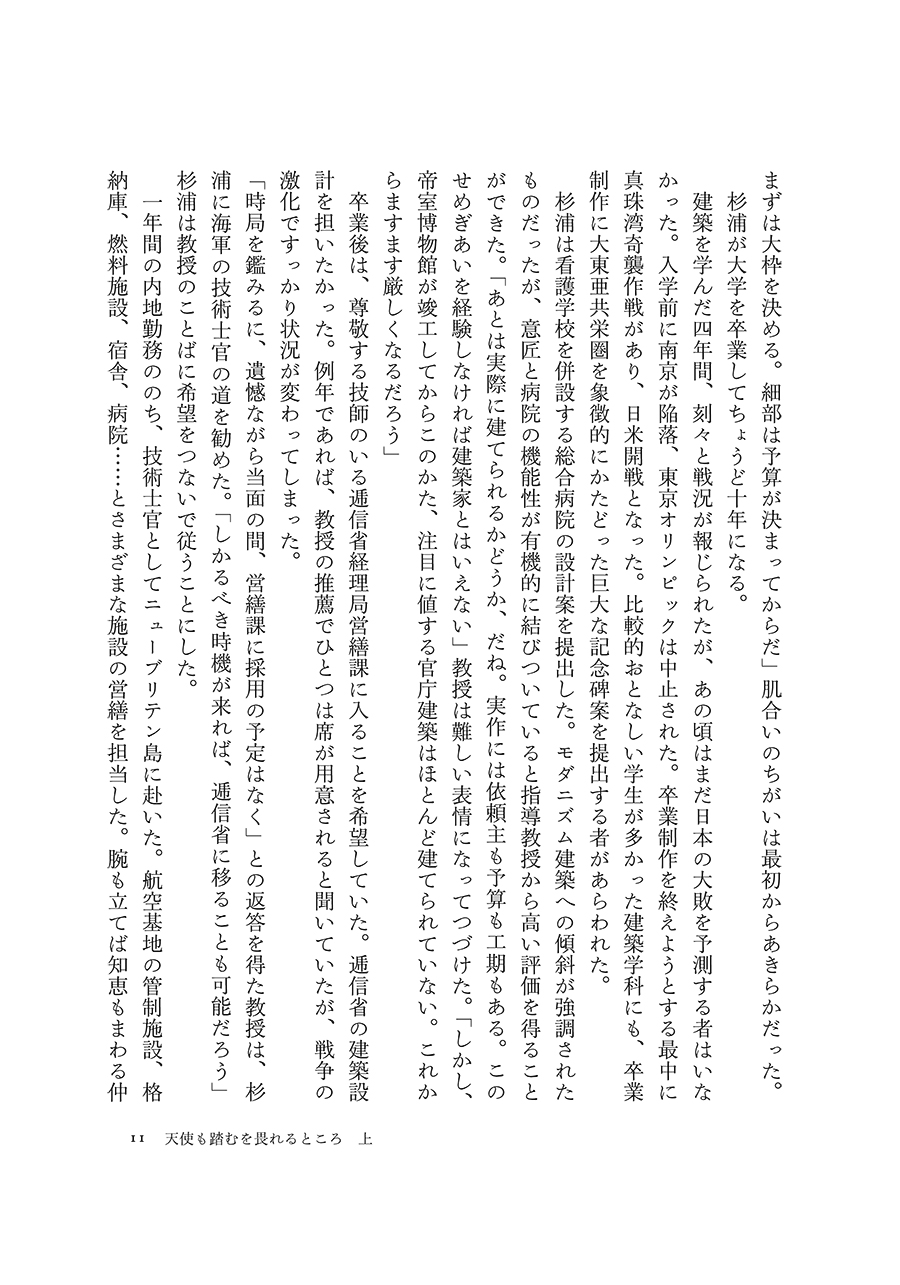1
黒澤明の「生きる」が封切られてまもないころ、庁舎の食堂で隣に座った渡辺が、
「『生きる』、見たか」
と聞いてきた。「見たよ」と杉浦は答えた。
小学校一年の息子を連れて、有楽町の映画館まで見にいったばかりだった。
志村喬が演じる平凡な市役所の課長が、胃癌で余命幾ばくもないと知り、途方に暮れたあげく、残された時間で自分の生きたあかしを残そうと唐突に決意する。汚水が溢れだし不衛生きわまりない暗渠を整備して、子どもたちの遊べる公園にしてもらえないか――貧しい暮らしに喘ぐ主婦たちの切羽詰まった陳情は、各部局をたらい回しにされ、放置されたままだった。たらい回しの発端をつくったこの課長は、書類の山から陳情書を捜しだし、公園の実現へと憑かれたように奔走し始め
る。
そこから場面は五ヶ月後に飛ぶ。課長は死んだ。その通夜の席が映されている。
小公園完成の手柄を死者から奪おうと自画自賛する助役、すかさずお追従をいう者。課長への勝手な思い込みや揶揄が飛び交ううちに、役所でのそれぞれの立場が浮き彫りになる。公園が完成するまでの課長の働きは、実際はどうだったのか。回想や主張を検証するように折々の場面が映しだされる。まわりがたじろぐほどの課長の執念が、公園実現までの障壁をつぎつぎに乗りこえていったことがわかってくる。
通夜はつづき、夜は更けてゆく。死者の目覚ましい働きを低く見積もろうとする参列者たちに、ひとり憤慨し異を唱える部下。それをセンチメンタリズムだと批判する上司。ときどきクローズアップされる課長の遺影は、みごとなまでに「死人に口なし」だ。
完成した小公園のブランコに揺られ、雪に降られながら「いのち短し、恋せよ乙女」と歌う課長の姿。その姿を目撃しながら酔っ払いと勘違いし、声をかけなかったと詫びにやってくる警官。しだいに通夜の席は乱れ、酔いもまわり、課長の死を無駄にするな、あとにつづけとうわごとのようなことばが飛びかいはじめる。しかし、その後の役所の光景は、なにも変わらない。それまでどおりの日常がただ繰りかえされるばかりだ。
なんともやるせない映画だった。
人間は簡単に変わる。そして人間は簡単には変わらない。人の底の浅さが生む悲喜劇をその両側からじっと観察し、遠慮なく映しだしてゆく黒澤の演出は、演劇的な誇張がつよい。日本人はこんなに言いたい放題には喋らない。思っていることをそのまま口にすればこうなる、という演出で、だからこそわかりやすく、見る者の胸のつかえがとれるのかもしれない。
建築の規模も予算も、市役所と建設省では桁がちがうが、わかりすぎるほどわかる部分がある。暗渠の問題を選んでいることや、市役所のたらい回しのエピソードなどは実際の事例を調べているのだろう。未舗装のまま残された都内の道路の惨状も、最悪だった時期の様子をよく描いている。市役所の机の周囲にこれでもかとばかり書類の束を積み上げているのはどう見ても誇張だが、仕事の澱を目に見えるようにするための大事な小道具で、書類の山に時間の経過を感じさせる自然な古色をつけているのがいかにも黒澤らしい。
父としての課長と、その息子の致命的なすれちがいのいきさつも描かれていた。隣に座る我が息子はなにか感じただろうか。まあ小学一年生にはわかるまい、と暗がりのなかでおもう。「まだ早いんじゃない?」と妻が言ったとおりかもしれない。
黙って駅に向かって歩いていると、息子の
渡辺がカツ丼定食の最後の一口を頬張っているあいだ、杉浦は「夜の雪がきれいだったな」とだけ言った。目だけで肯くようにしながら渡辺はお茶をがぶ飲みした。「あざとい演出だけどね。まあ、見ちゃうわな。しかしまあ、黒澤はお茶漬けの味じゃないね」一拍おいて志村喬のしわがれ声になり「私には時間がない」と言って席を立つと、片手をあげて食堂を出ていった。
一級国道の路線を指定する政令が公布されたばかりで、道路局の渡辺は忙殺されていた。朝鮮動乱特需で自動車輸送も増加して、国民の自動車保有台数も飛躍的に伸びていた。自国の戦争で破壊され、隣国の戦争で復興する。なんとも言いがたい事態が進行していた。
「時間がない」とは誰もが口にしたいセリフだった。案件のどれもこれも時間が足りず、冗談や軽口を飛ばして憤懣を鎮めるしかない。口下手な杉浦はそれが苦手だから、ただ無表情になる。「忙しくなるとすぐ顔に出るんだから」と妻の陽子に言われ、そうなのかと気づく。陽子は言いたいことをすぐに言う。よく笑い、映画館では泣く。杉浦とはまるで正反対の性格だった。そういえば、「生きる」に登場していた小田切みき演じる若い女性は、おもったことをそのまま言う遠慮のない性格で、絶望の底にあった課長を最後の行動へとひっぱりあげる役割を担っていた。しかし陽子はあそこまで天真爛漫ではない。
食堂から席にもどろうとする廊下で、すれ違ったはずの課長が「あ、そうだ」と声をあげて戻ってくると、杉浦の背中に声をかけてきた。建設省の廊下は誰もがこれみよがしに急ぎ足で歩くから、気をつけないとぶつかりそうになる。
「そうだった杉浦君。折り入って相談したいことがあるんだ」
ふりかえった瞬間、胸のあたりに嫌なものが兆す。「はい」と言うのがやっとで、自分の顔がみるみるかたくなるのがわかる。
「明日、何時でもいいから来てくれ。今日はこれから出てしまうので」
課長はよく通るおおきな声でそう言うなりまた背を向け、杉浦の返事も待たずに去っていった。ポマードの匂いだけが残った。明日は会議もなく現場もないはずだ。都合はいつでもつけられる。
課長は土木技術者として入省し、その後は国道改良、河川改修、ダム建設と土木一筋のはずだった。杉浦が配属されている計画局へは、組織改編のため一時的にやってきたにすぎないという噂だった。まもなく河川局に開発課が新設され、そこへ移ると解説する事情通がいた。ミスター重機とも呼ばれた課長は、めずらしく裏表がないところが美質といえたが、熟慮より口が先というせっかちなところがある。
初めて同席した会議では「君の声は小さいな。もっと大きな声でしゃべってくれないか」と注意され、しかたなく声を大きくして先を続けると、途中でさえぎられた。「細かい話はあとでいい、まずは大枠を決める。細部は予算が決まってからだ」肌合いのちがいは最初からあきらかだった。
杉浦が大学を卒業してちょうど十年になる。
建築を学んだ四年間、刻々と戦況が報じられたが、あの頃はまだ日本の大敗を予測する者はいなかった。入学前に南京が陥落、東京オリンピックは中止された。卒業制作を終えようとする最中に真珠湾奇襲作戦があり、日米開戦となった。比較的おとなしい学生が多かった建築科にも、卒業制作に大東亜共栄圏を象徴的にかたどった巨大な記念碑案を提出する者があらわれた。
杉浦は看護学校を併設する総合病院の設計案を提出した。モダニズム建築への傾斜が強調されたものだったが、意匠と病院の機能性が有機的に結びついていると指導教授から高い評価を得ることができた。「あとは実際に建てられるかどうか、だね。実作には依頼主も予算も工期もある。このせめぎあいを経験しなければ建築家とはいえない」難しい表情になって教授はつづけた。「しかし、帝室博物館が竣工してからこのかた、注目に値する官庁建築はほとんど建てられていない。これからますます厳しくなるだろう」
卒業後は、尊敬する技師のいる逓信省経理局営繕課に入ることを希望していた。逓信省の建築設計を担いたかった。例年であれば、教授の推薦でひとつは席が用意されると聞いていたが、戦争の激化ですっかり状況が変わってしまった。
「時局を鑑みるに、遺憾ながら当面の間、営繕課に採用の予定はなく」との返答を得た教授は、杉浦に海軍の技術士官の道を勧めた。「しかるべき時期が来れば、逓信省に移ることも可能だろう」杉浦は教授のことばに希望をつないで従うことにした。
一年間の内地勤務ののち、技術士官としてニューブリテン島に赴いた。航空基地の管制施設、格納庫、燃料施設、宿舎、病院……とさまざまな施設の営繕を担当した。腕も立てば知恵もまわる仲間は少なくなかった。しかし指揮系統は次第に迷走するようになり、精神主義が横行し、耳を疑う命令が聞こえてくるようになった。合理も道理も消滅し、やがていっさいの思考が停止すると、どこか遠くから「天皇陛下万歳」の声が聞こえてきた。これでは絶対に負けると肌身で感じるようになったのは、終戦の一年以上も前のことだった。
大本営は何を基準に判断し、国をどうしようとしているのか。南洋に取り残され、自分たちが何のために戦っているのか、もはやわからなくなりつつあった。俘虜になってでも生き残ってみせると望んでいたにせよ、もはやこれまでと覚悟した瞬間は一度ならずあった。栄養失調ではあったが、負傷はせずマラリアにもかからずに復員することができたとき、自分はこれですべての運を使い果たしたかもしれないとおもった。
焼けずに残っていた実家に戻り、父と母と兄に迎えられても、泣くことも笑うこともできなかった。大東亜共栄圏の記念碑設計案を出した男は北ビルマで死んだ。
復員すると休むまもなく内務省に呼びだされ、戦災復興院で働くことになった。
敗戦で時間が止まった、と感じたのは八月十五日の一日だけだった。
国は看板をかけ替え、動きつづけていた。
2
応接室のソファに座るなり、課長はすぐに話を切りだした。
「春から宮内庁に出向してもらいたい」
予想もしない内示に、杉浦の頭は追いつかない。
「宮内庁、ですか。私は何を」
「もちろん、管理部に技官として行ってもらう」
「それは……なにをする部署ですか」
課長は笑った。
「宮内省が宮内庁になったように、内匠寮は戦後まもなく主馬寮に統合されて、のちに主殿寮と名称が変わり、三年前管理部になったんだよ。回覧でも周知された話だよ君」
宮内省内匠寮はもちろん知っている。歴史ある営繕組織だ。管理部と名称を変えていたとは知らなかった。見ていたかもしれないが、関心の外だった。
「そうでしたか。知りませんでした」
旧逓信省、文部省、法務省、裁判所、国会、国鉄……それぞれが独自に営繕組織を持っていた。国費によってまかなわれる官庁営繕は建設大臣が掌握するのが建前だが、戦前からの慣例で、各省庁の営繕局が自立性を持って運営されていた。たとえば逓信省の営繕に所属しながら建築の世界で名を轟かせる建築家が生まれる背景には、この仕組みが貢献していた。杉浦が尊敬する技官、竹内尚久も逓信省の伝統に守られながら中央電信電話局の設計をした。竹内は戦争が始まってまもなく逓信省を辞め、故郷の札幌に帰ったと聞いたが、いまは東京に戻り大学で教えているらしい。竹内は大学の先輩でもあった。空襲の難を逃れた中央電信電話局は、日本におけるモダニズム建築の初期の傑作として、いまなお評価が高かった。
「まあ、そんなことはいいんだ」と言いながら、課長はめずらしく声を低くし、やや前屈みになって杉浦に顔を近づけてくる。
「これは単なる出向、というような話じゃない」
杉浦は顎を引いて距離をとろうとし、しだいに熱を帯びてくる課長の話をただ黙って聞いていた。
「今年はおおきな節目の年だった。講和条約が発効し、日本は独立を回復した。新憲法の五周年記念式典もあった。式典会場は皇居前広場だったな。しかしだ、問題は明仁親王の成年式と立太子の礼だよ。そうした大事な儀式がいったいどこで行われたか君、知ってるか」
先月、記事は新聞で見たが、場所の記憶はない。
「皇居内でのことかと」
課長はまた笑った。
「まあ、ほとんどの国民がそういう認識だろう。本来なら立太子の礼は、宮殿で行われるべき国事だよ。しかしだ、いま皇居宮殿はどこにあるんだね」
黙っている杉浦を見たまま課長はつづけた。「空襲の猛烈な火は濠を飛び越えて襲ってきた。明治宮殿は木造だからね、あっという間に火がまわった。決死の消火作業もむなしく宮殿は焼け落ちてしまった。以来、皇居に宮殿はないままだ」
杉浦はそのころ、遥か南洋の空の下にいた。宮殿が焼け落ちたことは大本営発表で知った。本土決戦という言葉が聞こえてきたが、そうなったら勝てる見込みはないと思ったのを覚えている。
課長はソファに深々と座りなおして言った。
「宮内庁庁舎の三階に、仮宮殿が設けられている。狭苦しいところだ。立太子の礼はそこで執り行われたんだよ」
課長はさらに声を低くした。
「吉田総理も立太子の礼を仮宮殿で執り行うしかなかったことに心を痛めていたらしい。宮殿造営は宮内庁の要望であると同時に、吉田総理のつよい意向でもある。宮内庁に待ったをかけているのはもはや天皇陛下おひとりだという噂もある」
土木一筋と思っていたが、いつから宮内庁の事情にこれほど詳しくなったのか。
「独立が回復して、天皇陛下は退位されないことが明確になった。遠回しな表現ながら、記念式典の『おことば』で明確に宣明されたからね。皇太子も立太子の礼を終えられた。皇居を正面から見据えていたGHQ総司令部も第一生命に返還された。日本が独立を回復してから、宮内庁の動きが活発になったのは当然のことだ。民間から抜擢された島崎宮内庁長官も、庁内の掌握に自信を深めているらしい」
杉浦はどう断ればいいかだけを考えていた。課長の話は聞いているようで聞いていないも同然だった。上の空の杉浦に気づいた課長は、ソファから立って中腰になり、ポケットをさぐってタバコをとりだすと、ふたたび腰をおろした。
「結論から言ったほうがよさそうだな。焼失した宮殿の再建計画が動き始めた。建設省からは杉浦君に出向してもらい、戦後最大の官庁建築としての……いや、国家的一大事業としての宮殿造営に尽力してもらいたい。と、こういうことなんだ」
タバコを箱からとりだしたものの、火をつける様子はない。
杉浦は膝のうえで両手を握るようにしてから口をひらき、ゆっくりと言った。
「たいへん僭越ながら、私ではなく、他の有能な技官にあたっていただけませんか」
ここで間違えるわけにいかない。海軍の技術士官の話を指導教授から打診されたとき、断れなかったことを後悔していた。いまここで宮内庁に出向してしまったら、建設省には戻れないだろう。戻ることができたとしても、早くて五年。いや、そんなわけにはいかないはずだ。計画が正式に決定し、調査が行われ、設計が始まり、予算が承認されるまでに数年がかかり、工期も数年、竣工まであわせて十年はかかるのではないか。四十代半ばになって建設省に戻っても、浦島太郎みたいなものだろう。
「そうか。それは困ったな」課長はタバコに火をつけた。
「君のような人物でないと、とても動かせない話なんだよ」ソファに背をあずけ、しばらく考える顔になった。君のような、とはどんな人物を指すのか。声の小さい、細かいことにこだわる人間でないと、ということか。
「初代宮内庁長官の島崎さんが民間から指名されてもう四年になる。たいへんな改革が進んでいるらしい。皇室もこれからさらに変わるだろう。国家元首から象徴になったことの意味が、あらゆる場面であきらかになってくるだろうし、あきらかにしなければいけない。その生まれ変わった皇室の、象徴となるのがあたらしい宮殿だ。人生を三回やり直したって、まずめぐりあえないような、おおきな仕事だぞ」
杉浦は表情を変えず、課長の話を黙って聞いていた。しかし決意は揺るがない。どうしても建設省に残れないのなら、辞表を提出するしかない――考えもしなかった選択肢がふいに頭に浮かんだ。
「黙ってるけど君、これは建設省として熟考の末の結論なんだよ」
「おことばを返すようですが、課長は相談だとおっしゃいました。相談であれば、私の意向も聞いていただけると思い、申し上げているまでです」
課長はタバコを灰皿におしつけて消した。
「わかった。ここですぐに諒解してもらえなくても仕方ない。まあよく考えてみてくれ。週が明けたらまた話そう」
課長は腕時計を見て、手帖を出し、次の予定を確認しているようだった。
「念のためだが、宮殿再建の話は大臣と官房長、それに局長、私の四人しか知らない。君を入れて五人だけだ。つまり極秘扱いと心得てほしい」
「承知しました」
頭を下げて応接室から廊下に出た杉浦を、慌ただしい空気がにわかに包みこんだ。廊下にはいつもと変わらない建設省の空気が流れている。しかしこの空気にはもはや自分は含まれていないのではないか。通りすぎる職員たちの声すらよそよそしく聞こえてくるのはどうしたことか。
もともと急ぎ足では歩かない。声も小さい。しかしこの空気のなかで働くことを心地よく感じていたと、いまさらのように自覚する。
宮内庁には同期入庁者はいない。いたとしても知らない。管理部がいかなる組織でどういう雰囲気なのかもわからない。そもそも宮内庁の採用には表には出ない独自の基準があると聞いたことがある。身元のたしかさを当然求められるだろう。つまり自分の身元はすでに調査済みということか。親族まで調べられ、安全無害とわかったとして、設計の実力とはなんの関係もない。調査済みの人間が集まる場所は、毒にも薬にもならない無菌室のようなものか。宮内庁長官がどんな改革をしたのか、あるいはしている途中なのかわからないが、長官ひとりの旗振りで、わずか数年でなにを変えられるというのだろう。いずれにしても、土ぼこりの立つ現場で職人と立ち話のできる建設省の風通しのよさが、濠に囲まれたやんごとない世界にも根付いているとは到底思えない。
席に戻っても、なぜ自分なのかという疑念はふくらむばかりだった。
(以下略)
3
一通の手紙が届いたのは、それから二週間後のことだった。再度の面談でも出向を固辞し、辞職願の下書きも用意しはじめていた。
厚みのある封筒の差出人の名前を見て、杉浦は目を疑った。竹内尚久と記してある。しかも住所は宮内庁の番地になっていた。
一度は会いたいとおもいながら、その機会がなかった元逓信省の建築家から、なぜ無名の一技官に手紙が届いたのか。しかも宮内庁の住所から。
鋏でゆっくりと封を切った。逓信省の便箋に、あかるいブルーブラックの万年筆。やや小ぶりの読みやすい楷書の文字がしたためられていた。
拝啓
突然の書状に驚かれたかと思いますが、貴殿の指導教授だった東恒雄は、私の大学時代の友人です。貴殿の住所は東に訊ねました。どうかご容赦下さい。
東は友人だった事に就いて、恐らく詳細を語っていないだろうと思いますから、この書き出しに成ったという次第です。
東から見せられた貴殿の卒業制作、看護学校併設の病院設計案は、今も記憶に鮮やかで、見事な作品でした。東から逓信省営繕課を希望されている事も聞いて居りましたが、私も逓信省を辞する相談を始めて居た時で、逓信省にもそもそもお迎えする余地が無く、今省みても心苦しい結果と成りました。南方での御苦労は如何程で有ったか、想像する事すら憚られますが、無事に復員なさって、戦後復興に寄与される仕事に就かれ、そのご活躍は建築雑誌でも拝見して居りました。逓信省は今や郵政省と電気通信省の二省に分離され、営繕課も二分されて力を削がれ、様変わりしてしまったと仄聞しています。
小生は大学の非常勤で建築史を教え乍ら、宮内庁の嘱託として勤めて居ります。与えられた課題は新宮殿造営の研究と計画です。間も無く日本語版が刊行される予定の拙著では原始時代から現代までの日本建築を歴史的に俯瞰し乍ら、皇居、公卿住宅、武家住宅、神社、仏寺等の特質を個別にも取り上げ、日本の風土、自然、或いは民族性と建築の関わりを明らかにしようと試みたもので、独逸で刊行された著作ですが、これを日本でも紹介したいと云う奇特な書肆が現れ、翻訳される事に成り、近く刊行の運びと成りました。この本の京都御所の調査の折にお世話になった方から、嘱託の声が掛けられたという成り行きでした。
宮内庁に席を戴き六年に成りますが、内匠寮の仕事を一通り総て見て回る事が出来たのは望外の喜びでした。敗戦という事態が無ければ、とても叶うことの無かった調査でした。
私はモダニズムの建築家と見られて居りますし、その通りではあるのですが、近年は日本建築の清浄な美しさにはモダニズムに通じるものが有る、という思いを強くして居ります。
経済成長の中、これからは鉄筋コンクリートとガラスで出来たビルディングが次々に建てられて行く事でしょう。其れに就いては当然の成り行きだと考えます。其の事態は進めば宜しいですし、機能と合理性をもった建築がこれまで以上に建てられ、使われる事は喜ばしい進展でも有ります。
しかし、日本建築の伝統が過去の無用の長物かと云えば、決して其の様な事は有りません。桂離宮がブルーノ・タウトに評価される事で世間に見直される、と云うのは考えてみれば恥ずべき事で、日本の伝統建築にも、これからの建築に多くの示唆を与え、モダニズム建築に寄与する所も、無限の可能性が有る筈と信じます。
敗戦後、内匠寮が管理部として再編されたのは、第一に宮内省の権限と規模の縮小に伴い、役割の整理が行われたと云う事です。私が嘱託で呼ばれた時、戦前は六千人を超えた宮内省の職員は千五百人弱、四分の一にまで削減されていました。
内匠寮が果たした役割は貴殿もご承知かと思いますが、宮殿、東宮御所を初めとして、全国に点在する離宮、御用邸、宮邸、帝室博物館、鴨場、御養蚕所、陵墓、等、多岐に亘るものでした。しかし、今後は、同じ規模、陣容で運営されて行く事は出来ません。宮殿や御所など建築物の設計は外注となり、その管理部門として、また維持、修理の監督部署として機能する事に成って行く筈です。
しかし乍ら、内匠寮の培って来た伝統と成果を踏まえて、新しい時代の建築物としての模索を続け、今の時代の建築としての宮殿を造営する事は国家としての責務だと考えています。国費を投じての建築には、国民に対する責任が有ります。海外からの賓客をどの様に迎え、持て成すか。国事としての儀式をどの様に執り行う事が可能なのか、象徴としての皇居宮殿とは如何なるものなのか。何れの課題も、これまでに無い開かれた場で議論され、検討され、実現しなければなりません。
貴殿の中には、天皇制という前近代的な制度への強い疑いが有るのではと拝察します。それは健全な疑問だと思います。民主主義と天皇制は両立出来無い概念です。そのように考える方が正しい。私もそう考える時が有ります。
しかし、国家と云うものは、政治的な制度だけで運営されて行くものかと云えば、そうでは無いだろう、と云うしかありません。好悪の問題を超えて、歴史や文化と云うものは、時代が変わったからといって、一掃し、消去出来るものでは無い。
私は政治の問題、民主主義の問題に就いて、ここで貴殿に聞いた風な事を書く立場では無いし、その力も有りません。私とて気持ちの揺らぐ時が有ります。天皇の存在に分かち難く残されている宗教性が、今後の日本の民主主義が根づいて行く中で、大きな矛盾として向き合わねばならない時が必ず来るでしょう。経済成長が進展するに連れ、国民の中に残された宗教的なものへの関心も、低下して行く筈です。一方で天皇の宗教行事はほぼ誰の目にも触れるものでは有りませんが、確実に、毎日続いています。戦争が終わった今、天皇の仕事は祈る事だけに集約して行くのかも知れない。そう考える事すら有ります。
逓信省で働いて居る時、郵便から電信へ、そして電話へと形式の大きな変化を見乍ら、共同体として共通の祈りを同じ土台で経験する事の価値が、これから大きく変わって行くのではないかと実感し、想像もしました。いずれ世界中が電信電話的なるもので繋がる時が来れば、国境と云うものも、架空の線に成るかも知れない。
そのような時代が果たして来るのかどうかは分かりません。しかし、その様な変化には、考えもしない落し穴が待っている筈です。得るものが大きければ、失うものも大きい。産業革命を見れば、容易に想像のつく話です。
そのような時代を迎えようとする時、総てが合理で動いている、と云うのでは無く、意味の分からないもの、目には見えないもの、誰にも「是れが其れだ」と指差す事の出来ないもの、謂わば理不尽なものを美しい形で残しておく事が、思わぬ働きをするかも知れない。小生はそう考えるように成りました。
桂離宮は日常的に使う建物としては、もはや無用の長物です。しかし、あの美しさから私は逃れる事が出来ません。何度訪ねても、其の度に発見があり、そこに立ち竦む気持ちに成ります。
皇居宮殿もやがて無用の長物となり、象徴天皇がいた時代に、この建物が機能していたらしい。しかし、この美しさは何処から来るのだろう。取り壊されようとする百年後、二百年後に、そう思い、考える人は必ず居るでしょう。
その様な建築物を遺す事が出来たなら、簡単には解く事の出来ない、其れを見るだけで、或いは其処に身を置くだけで、心の動く経験となる筈です。其れこそが芸術と云うものではないでしょうか。
私は来春に宮内庁の嘱託を辞する事に成りました。医師の診断に従いました。
管理部には私の調査研究の報告書、図面が残されます。内匠寮時代を経験して来た職員もまだ居ます。そして外注となるであろう宮殿造営を誰が担当するにしても、宮殿に必要不可欠な条件とは何か、設計条件の中に加え、成る可く合理的に且つ具体的に伝える役割を担う担当者がどうしても必要になります。その担当者は、現代建築の知識を持ち、巨大建築の為の資材の調達や、見積もりの正当性も判断、処理が出来、工期、現場の監理をする必要もある。建築家という個性ある個人と、やりとり出来る知性と柔軟性も必要です。
其のような条件を満たす人が果たしてどれ位居るか。貴殿が一番お分かりの事でしょう。
一度ならずお断りになったという事も伺いました。
この仕事は、二つ返事で引き受ける様な仕事では有りません。固辞する胆力もまた、この仕事には必要となる場面が出て来るでしょう。
象徴天皇と云う存在が、果たしてこの儘で良いものなのか、其の様な根本的な疑問を持つ人間こそが、この計画に関わる必要があります。
私は恐らく、完成した宮殿を見届ける事は出来無いでしょう。
本来なら、このような書状を突然送り付ける様な非礼は避けるべきではありますが、躊躇している時間は無いと考え、この書状をしたためる事に致しました。
三月末迄は管理部に居ります。
一度で終わるにしても、お目に掛かって、貴殿と建築の話が出来れば幸いです。
ご連絡を心よりお待ちして居ります。
杉浦恭彦様
一九五三年一月四日
宮内庁管理部嘱託 竹内尚久
一月末、杉浦は皇居に向かった。
坂下門を訪ね、あらかじめ郵送されていた書類を皇宮警察官に差しだすと、両手でうやうやしく受け取られ、ボックス内の内線電話で杉浦の名前が伝えられた。「ご案内いたします」と言われて皇居内に足を踏み入れると、右手奥にある宮内庁庁舎に向かって、ゆっくりとした歩調で導かれた。
正面玄関の手前に小柄で細身の人物が佇んでいた。濃紺のスーツを着た竹内尚久は、想像していたよりもだいぶ老いを感じさせる風貌だった。
(4~17略)
18
二月、三月とあたたかい日がつづいた。雨もよく降ったせいか、皇居の木々や草花が日毎に芽をふき、葉を伸ばしてゆくのが目に見えるようだった。
「今年の桜が早いのはどういうわけか、とお上のご下問がありましてね、気象庁に問い合わせたら、昭和十七年は三月二十五日だったと。十七年といえば初めて空襲警報が鳴った年ですよ。今年より一日早かったそうで」
管理部前の廊下で大きな声で野上と話しているのは西尾侍従だった。向こうから杉浦を認めると「杉浦さん、ちょうどよかった」と片手をあげた。
「図面ありがとうございました、天長節のお立ち台。これなら簡素でよい、とお上も仰せで……あれが宮殿跡に置かれるのはいつになりますか」
「一週間前までには一度、現地で組み立ててみようかと思っています。日にちはご都合に合わせます」
宮殿跡の広場に組み立て式のお立ち台を用意して、一般参賀者を迎えいれることになり、依頼を受けた杉浦が簡素で頑丈なものを新たに考え、線を引いたのだ。講和条約発効の式典でつくった横長のお立ち台は解体して保管してあるが、今回の式次第からすると横に長すぎるらしい。
「それはよかった。式次第のご説明を申し上げるときに、お立ち台がないと話になりませんから……じゃあ野上さん、またあらためて」
野上に軽く会釈した西尾が、杉浦を見て「いまお時間ありますか」と言った。
曖昧な表情の杉浦に「よかったらちょっと途中までいっしょに歩きませんか。こんなに気持ちのいい陽気で、小径も春の気配とくれば、歩いているだけで気が晴れますよ」
「行ってきたらいい。西尾さんは滅多にこんなこと言わないから」と野上は杉浦を見た。
「野上さんの顔ばっかり見ていても、気は晴れませんよ」
そう言って西尾は声をあげて笑った。野上は西尾に向かって手を振るようにしながら言った。「いちばん気が晴れないのはわたし。わたしですよ西尾さん」
屋外の空気は冷たくもなく暖かくもなく、すがすがしかった。シジュウカラが木の高いところで春の鳴き声をあげている。荻窪の庭にもよく姿を見せる機敏な鳥だ。
「紅葉山に寄り道しましょう。時間はありますから」という西尾にしたがい、内廷庁舎側の出口から紅葉山をめざして歩いた。竹内尚久に初めて案内されたのは冬枯れの紅葉山だった。春の森の木々を見上げると、あたりの様子をうかがう子どものように、小さな若葉が同じおおきさで一斉に顔を出している。どこか生々しい赤茶色にみえる若葉を繁らせている樹木もあった。
「あらわれましたよ」
西尾が指差すほうを見ると、なにかを探すような顔つきのキジが灌木のあいだを歩いていた。こちらを見向きもしない。
「あれはね、お上をも畏れぬキジです。このあたりが縄張り。陛下がこの小径を進んでいたら、あのキジが道にしゃがみこんだまま休んでいたときがありましてね、ずっと睨み合いをしているわけにもいかないとおっしゃって、そっと歩いていかれたら、キジ
「あのキジがそのキジですか」と尋ねると西尾は立ち止まって首をかしげ、「……ちょっと聞いてきましょうか」と言って目を丸くした。杉浦は笑った。
頭上で口笛を吹くような鳴き声がした。「あれはイカル」――離れた樹木のあたりから、おそらくまた別の種類の、鈴を転がすようなきれいな鳴き声が聞こえた。西尾は顔を向けずに立ち止まり、「あれはアカハラです――いや、久しぶりに聞いたな。杉浦さんお出ましのおかげかな」と呟く。
「野鳥にお詳しいですね」と言うと、「お上がお教えくださいますからね、いやでも憶えちまう。ふふふふ」
東京の中央とは思えない静けさだが、耳を澄ますと、たくさんの小さな音が重りあっている。葉ずれの音。なにかの鳴き声。落ち葉を踏んでゆくキジの軽い足音。
「空襲では十万人以上の方が亡くなられましたが、焼失したのは建物や人だけじゃありません。鳥が巣をかけ実をついばむ樹木もごっそり焼けちゃったわけです。かろうじて残ったのが神宮の森、新宿御苑、目黒の自然教育園、そしてここ。陛下は戦前から巣箱をかけておられた。いまもしかるべき場所に九十以上の巣箱がかけてあって現在満室です。雑草のケシ粒みたいなタネも鳥にとっては米櫃ですから、雑草もそのままにされているわけです」
西尾はまたこの話をしなければいけないか、という顔になってつづけた。「勤労奉仕のみなさんが道灌濠に沿って歩いていたら、あるとき、野草に埋もれかけた小径を見かけた。職員がサービスのつもりで余計なことを口走ったんです。ここを陛下が歩かれます、とね。次の日です。小径沿いの野草がぜんぶきれいに刈られちゃった。床屋にいってきたみたいな仕上がり。以後、勤労奉仕のみなさんへのお願いがひとつ増えちゃって――そりゃ言われなかったらわかりませんよ。野草も雑草も見分けがつかないのが普通です。お上は雑草というものはない、とおっしゃるし」
話しているうちに御養蚕所の前に着いた。職員が忙しそうに出入りしている。西尾を見かけると笑顔で頭をさげるが立ち止まりはしない。
「柳田先生が御進講で六月にお見えなんですが、御養蚕所はぜひ拝見したいとおっしゃってましてね」
「……柳田國男さん、ですか」
「はい、柳田先生。ただその頃はちょうど書き入れどき、室内はご案内できませんよとお断りしたんです。外からでじゅうぶんだからと。ずいぶんご熱心で」
御養蚕所の裏手にある網で囲われた畑にまわった。「あそこには
紅葉山をふたたび下って、道灌濠までもどった。キジは姿を見せなかった。
「皇居の森は武蔵野の森です。吹上御苑には秋になるとススキ原が広がる。それはそれは見事です。いわゆる雑木林もそろい踏みで、シイ、ケヤキ、モッコク、トチノキ、イイギリ、アカガシ、フウの大木がある。その下に、ヤブレガサ、ラショウモンカズラ、ヤマブキソウ、ホタルブクロ、リンドウ、イカリソウ……まだまだこの何倍もありますが、このへんにしときましょうか」と言って笑った。「ぜんぶ武蔵野の野草山草です。もともと生えていたものもあり、お上が採集して移植されたものもあります。いまの法制局長官の鈴木さんも野草一族でしてね、ときおり胴乱をさげて野草を献上にいらっしゃいます。お上が那須の御用邸からお持ち帰りになって、武蔵野の野草とは別の場所を選んで移植なさったものもあります。といっても二株かせいぜい三株だけ、もとの植生がこわれないようにずいぶん御注意をなさってます。ええとね、那須からは、アケボノソウ、サルトリイバラ、オトギリソウ、フシグロセンノウ、ノハナショウブ、サワギキョウ……あはは、ぜんぶ言えたな」
道灌濠を渡った先の道は、ゆるやかなのぼり勾配になっている。
「そういうわけですから、御文庫にかわる御所を設計して建てていただくにも、敷地はどこにも余ってない、というわけなんです。先住者の雑木林、野草山草でもういっぱいで」
杉浦はなんと答えていいかわからずに西尾の顔を真正面から見た。西尾はうれしそうにしている。
「しかもです。いまのあの湿ったコンクリの御文庫はそのままにせよ、とおっしゃる。武蔵野の森や野原もそのまま、御文庫も附属庫もそのまま。お気持ちは拝察するしかないのですが。……ところで今日も野上さんとその話をしたんですが、いくらなんでもそろそろお許しが出ることになろうかと感じています。御文庫、いや新しい御所はいわば私的なものですから、外の建築家に依頼するわけにいきません。杉浦さんを中心に管理部のみなさんにお願いすることになるでしょう。ただ、お上はまだわかったとおっしゃったわけではない。なので当面のあいだ内密に願います。しかしよろしいとなったら、すぐにとりかかっていただきたい」
野上が「まだまだだ」と言っていた御所の工事が意外と早く始まるかもしれないとわかり、杉浦はとたんに緊張を覚えた。
「この八月に北海道への行幸の予定があります。六日から二十三日の二週間強。この間はわたしもお供しますが残る侍従がおります。北海道行幸のあいだに御文庫をすみずみまでお調べいただきたい。侍従になんなりとお尋ねになって、腹案の参考にしていただければ――と、こういうわけです。野上さんが、西尾から伝えるようにとおっしゃるものですから、こうしてお誘いしました。杉浦は陛下とは直接やりとりできない、あんたが施主の代理人なんだからとおっしゃって」
杉浦は立ち止まり、どう答えていいかわからず「承知しました」とだけ言い、西尾に頭を下げた。西尾はふふふと笑って杉浦の肩をぽんと一度叩いた。
さらに五分ほど歩くと御文庫が目の前にあらわれた。竹内尚久に案内されて以来だ。
コンクリート造の簡素な佇まい。地下が二階まであるとはわからない。なにかの研究所と言われたら、そのようにも見える。よく見れば、壁にはあちこちヒビが入っている。
「とにかく華美であることは好まれない……餅に生えるやつも困りますがね。資材なども、謂れのある銘木でも使おうものなら、どんなお叱りを受けるか。そう、杉浦さんがいらした建設省で扱うような標準のものがいいんです。武蔵野の雑木林、野草山草の精神でお願いしたい――代理人としましては、そのように希望いたします」
西尾は突然、ふかぶかと頭をさげた。杉浦もあわてて頭をさげた。
近くの木の梢あたりから鳥の鳴き声が降りてくる。
「……ホオジロですな。
ピチュ、チュリ、キョロローという鳴き声は、たしかにそう聞こえなくもない。
「やはり江戸時代からの先住者なんでしょうな。つかまつるんだから」
西尾は腕時計を見た。「ではこのへんで。杉浦さん、お帰りはおわかりになりますね」
「はい」
「ではまた」西尾はそのまま大きな背中を見せて、御文庫のなかに入っていった。
続きは本書でお楽しみください。