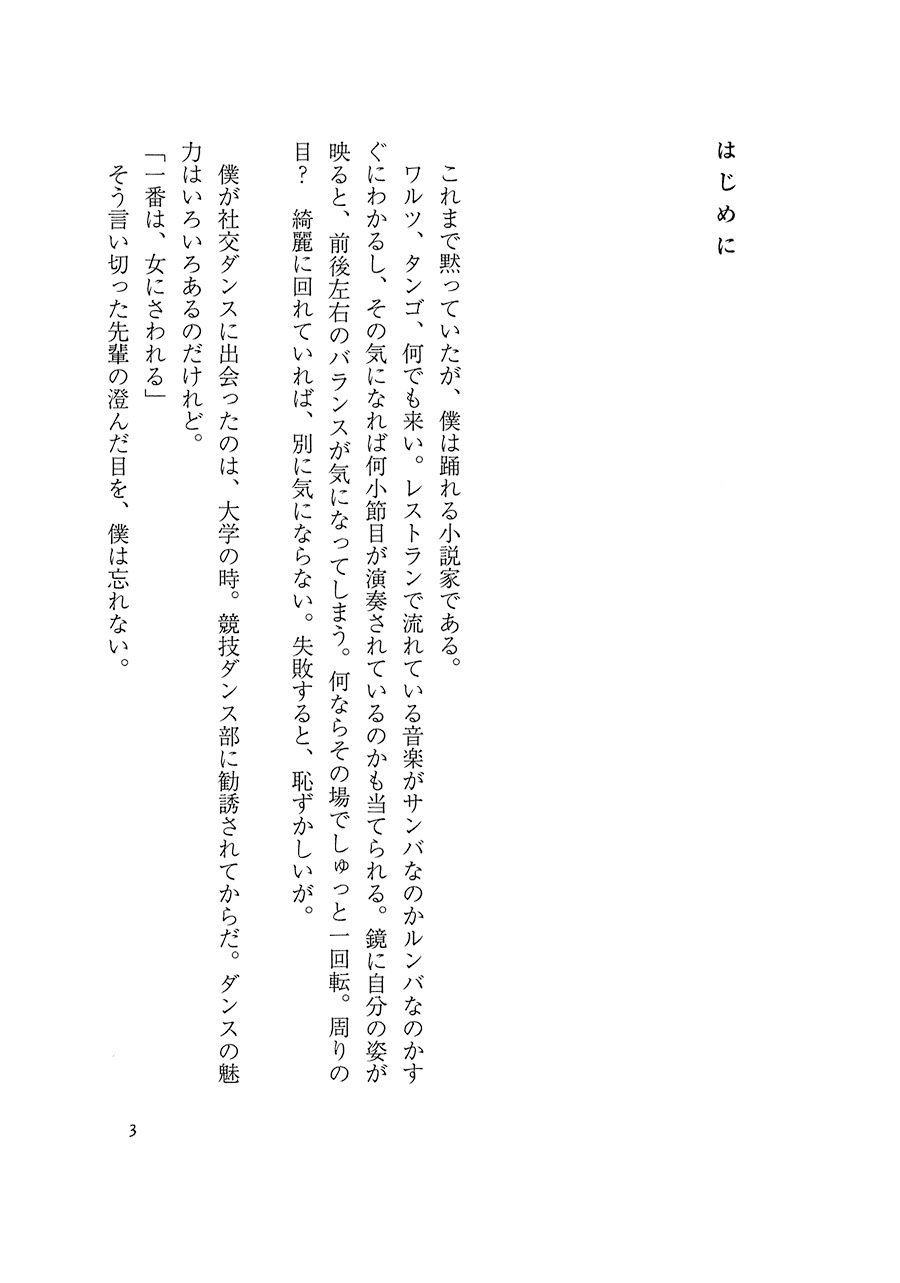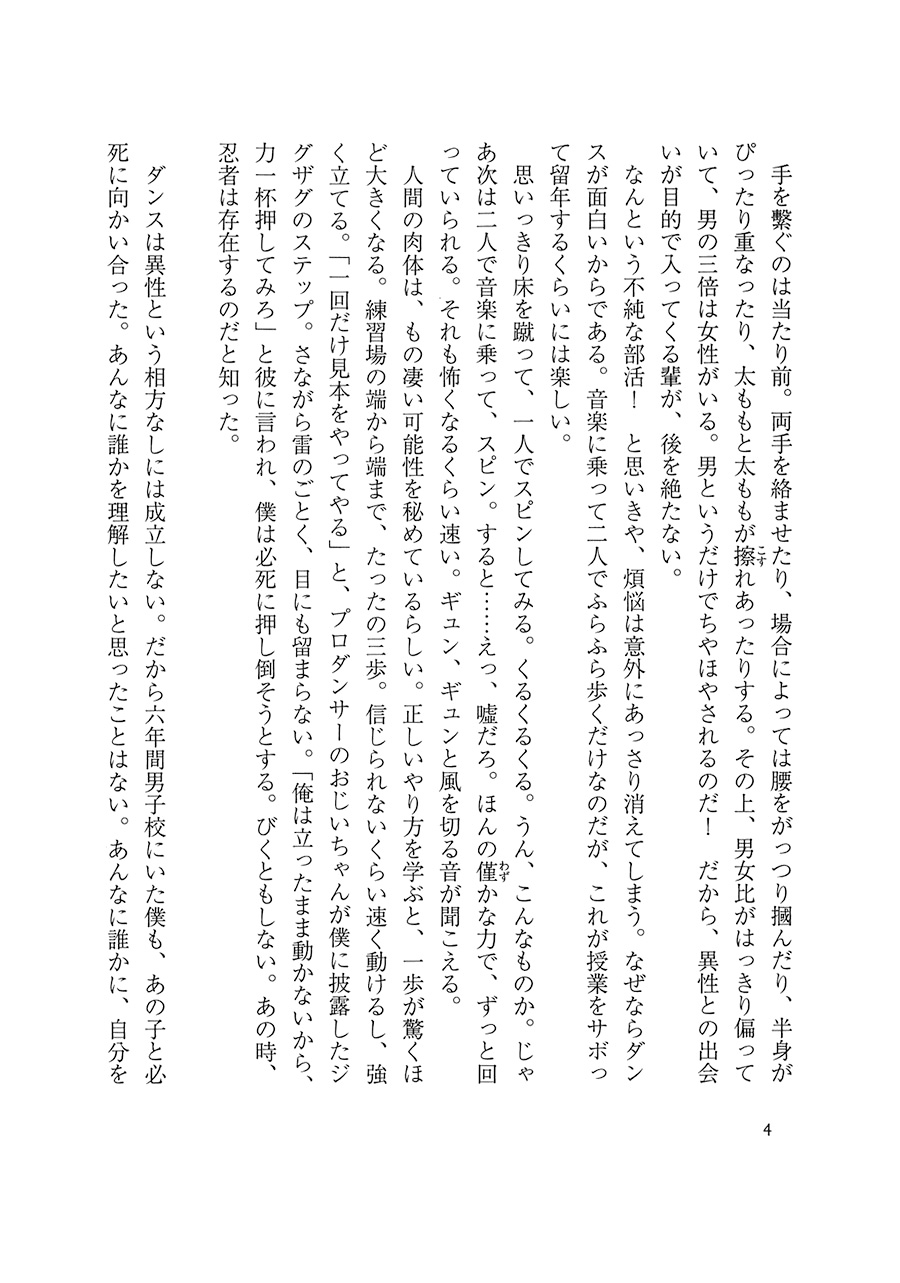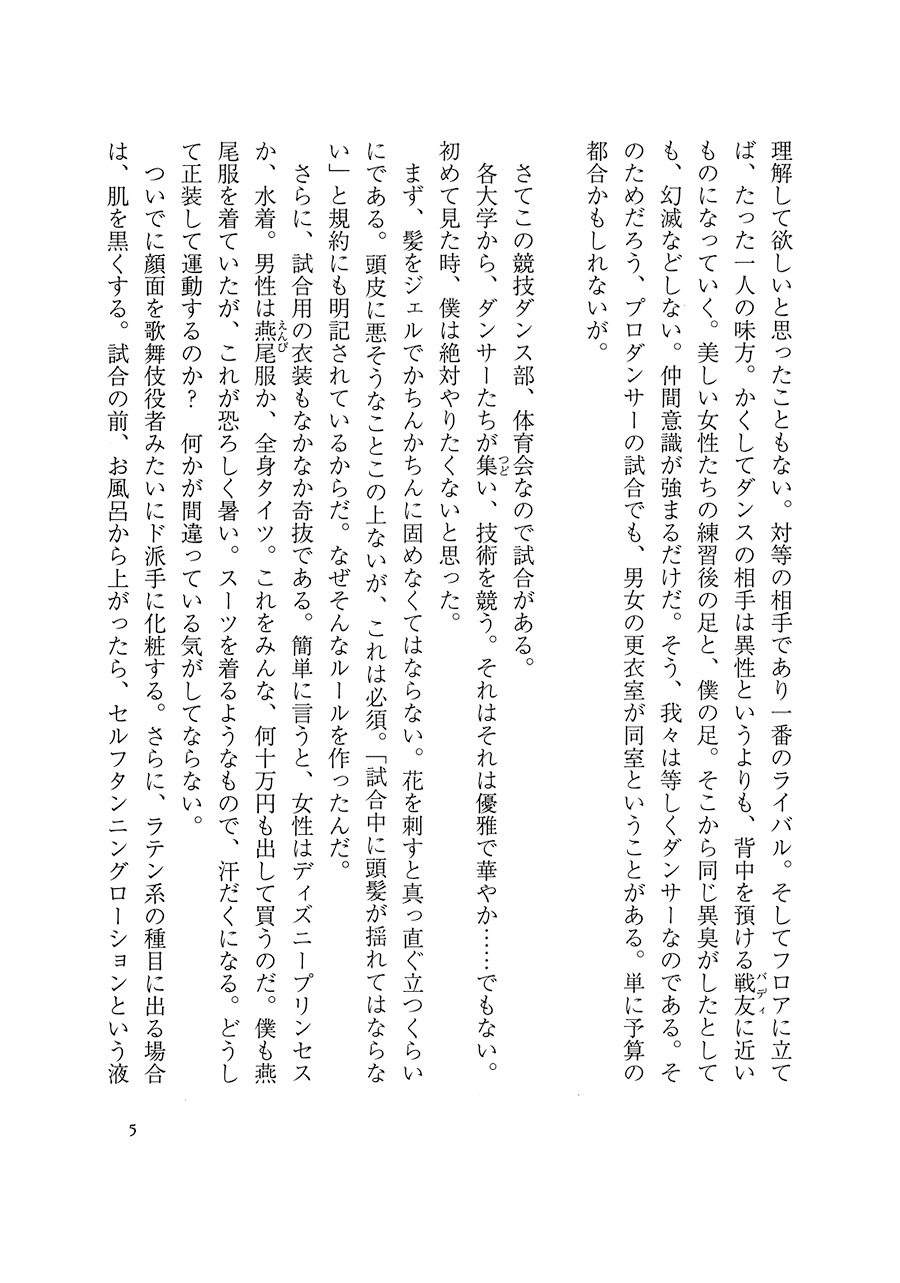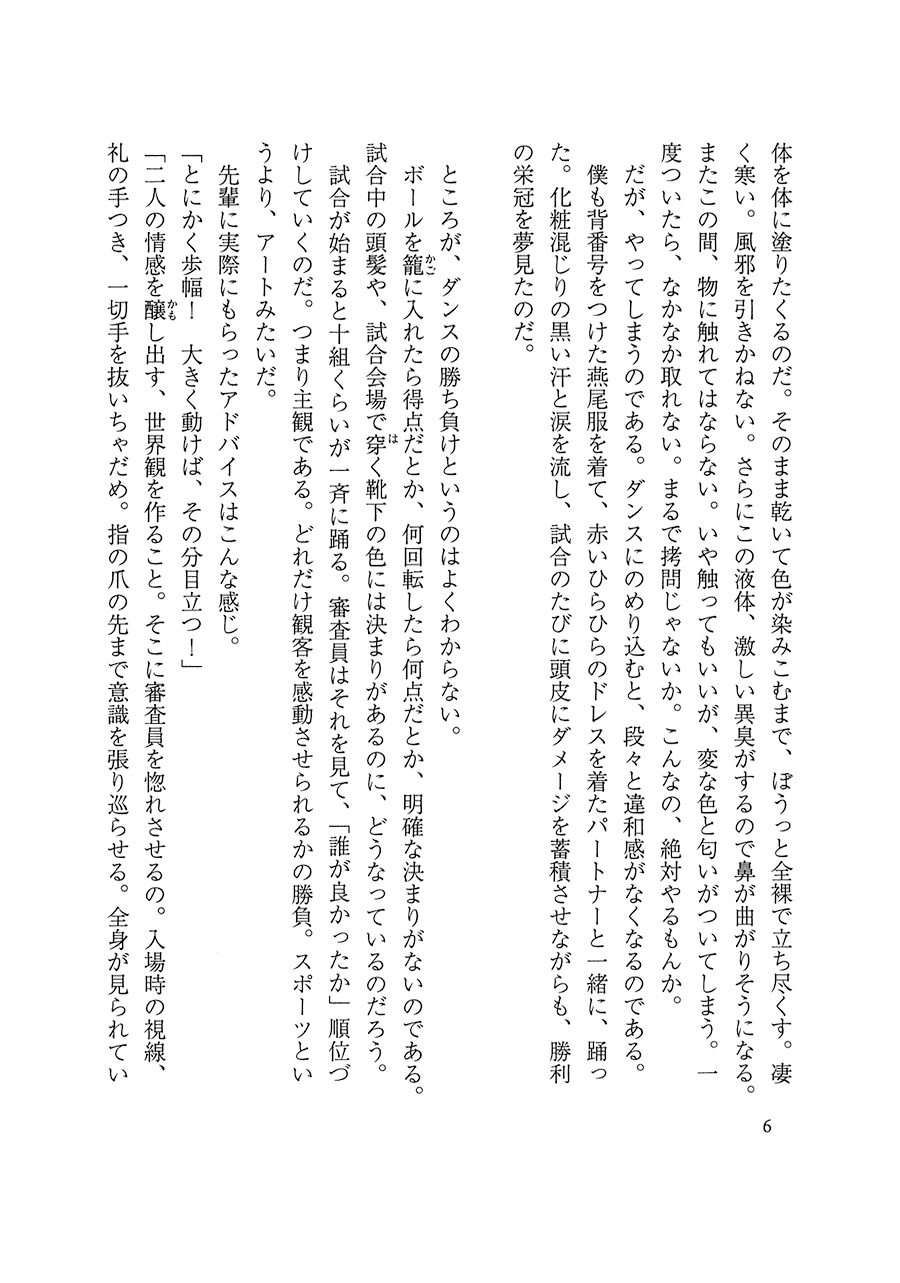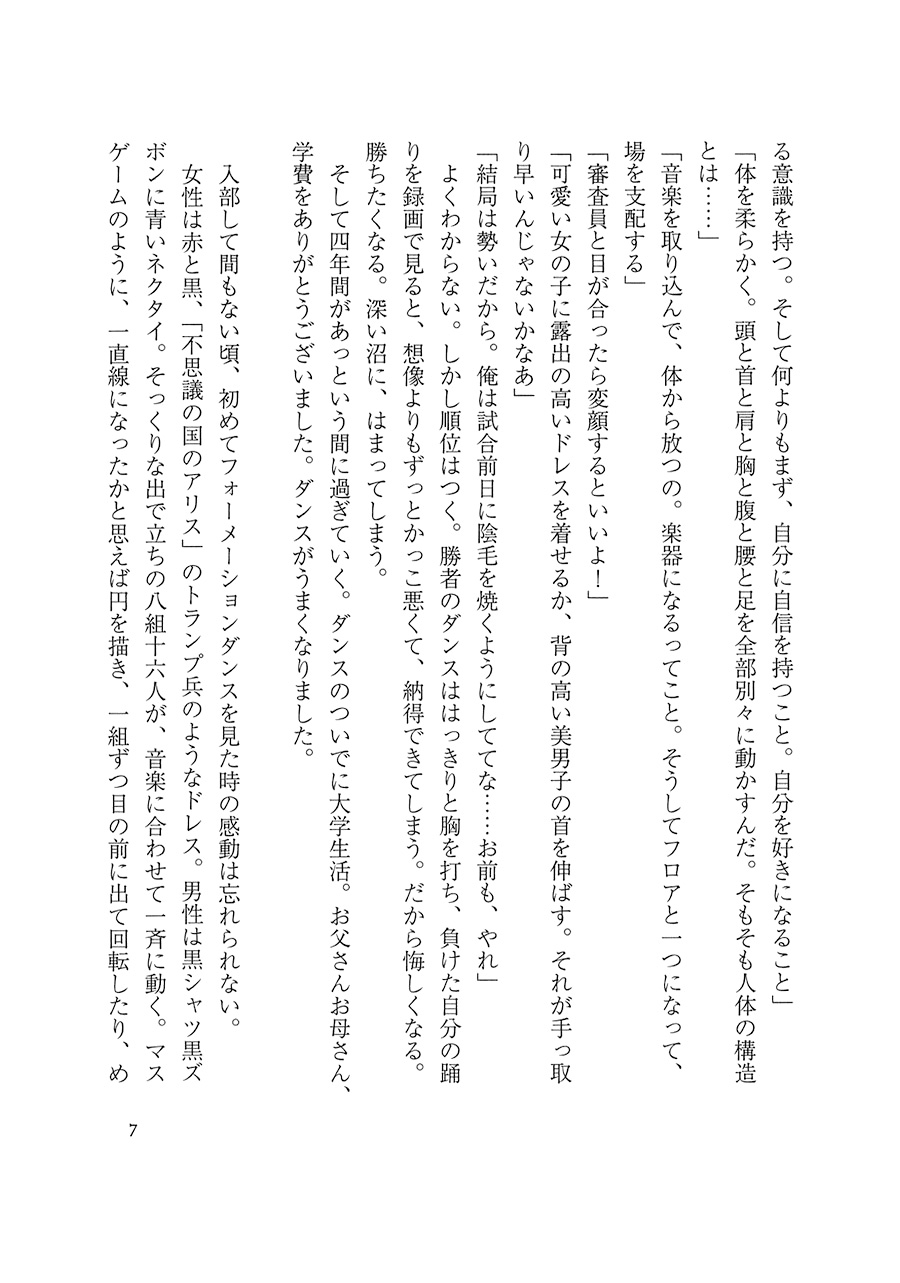試し読み 1
〔 page 1/4 〕

はじめに
これまで黙っていたが、僕は踊れる小説家である。
ワルツ、タンゴ、何でも来い。レストランで流れている音楽がサンバなのかルンバなのかすぐにわかるし、その気になれば何小節目が演奏されているのかも当てられる。鏡に自分の姿が映ると、前後左右のバランスが気になってしまう。何ならその場でしゅっと一回転。周りの目? 綺麗に回れていれば、別に気にならない。失敗すると、恥ずかしいが。
僕が社交ダンスに出会ったのは、大学の時。競技ダンス部に勧誘されてからだ。ダンスの魅力はいろいろあるのだけれど。
「一番は、女にさわれる」
そう言い切った先輩の澄んだ目を、僕は忘れない。
手を繋ぐのは当たり前。両手を絡ませたり、場合によっては腰をがっつり掴んだり、半身がぴったり重なったり、太ももと太ももが擦れあったりする。その上、男女比がはっきり偏っていて、男の三倍は女性がいる。男というだけでちやほやされるのだ! だから、異性との出会いが目的で入ってくる輩が、後を絶たない。
なんという不純な部活! と思いきや、煩悩は意外にあっさり消えてしまう。なぜならダンスが面白いからである。音楽に乗って二人でふらふら歩くだけなのだが、これが授業をサボって留年するくらいには楽しい。
思いっきり床を蹴って、一人でスピンしてみる。くるくるくる。うん、こんなものか。じゃあ次は二人で音楽に乗って、スピン。すると……えっ、嘘だろ。ほんの僅かな力で、ずっと回っていられる。それも怖くなるくらい速い。ギュン、ギュンと風を切る音が聞こえる。
人間の肉体は、もの凄い可能性を秘めているらしい。正しいやり方を学ぶと、一歩が驚くほど大きくなる。練習場の端から端まで、たったの三歩。信じられないくらい速く動けるし、強く立てる。「一回だけ見本をやってやる」と、プロダンサーのおじいちゃんが僕に披露したジグザグのステップ。さながら雷のごとく、目にも留まらない。「俺は立ったまま動かないから、力一杯押してみろ」と彼に言われ、僕は必死に押し倒そうとする。びくともしない。あの時、忍者は存在するのだと知った。
ダンスは異性という相方なしには成立しない。だから六年間男子校にいた僕も、あの子と必死に向かい合った。あんなに誰かを理解したいと思ったことはない。あんなに誰かに、自分を理解して欲しいと思ったこともない。対等の相手であり一番のライバル。そしてフロアに立てば、たった一人の味方。かくしてダンスの相手は異性というよりも、背中を預ける戦友に近いものになっていく。美しい女性たちの練習後の足と、僕の足。そこから同じ異臭がしたとしても、幻滅などしない。仲間意識が強まるだけだ。そう、我々は等しくダンサーなのである。そのためだろう、プロダンサーの試合でも、男女の更衣室が同室ということがある。単に予算の都合かもしれないが。
さてこの競技ダンス部、体育会なので試合がある。
各大学から、ダンサーたちが集い、技術を競う。それはそれは優雅で華やか……でもない。初めて見た時、僕は絶対やりたくないと思った。
まず、髪をジェルでかちんかちんに固めなくてはならない。花を刺すと真っ直ぐ立つくらいにである。頭皮に悪そうなことこの上ないが、これは必須。「試合中に頭髪が揺れてはならない」と規約にも明記されているからだ。なぜそんなルールを作ったんだ。
さらに、試合用の衣装もなかなか奇抜である。簡単に言うと、女性はディズニープリンセスか、水着。男性は燕尾服か、全身タイツ。これをみんな、何十万円も出して買うのだ。僕も燕尾服を着ていたが、これが恐ろしく暑い。スーツを着るようなもので、汗だくになる。どうして正装して運動するのか? 何かが間違っている気がしてならない。
ついでに顔面を歌舞伎役者みたいにド派手に化粧する。さらに、ラテン系の種目に出る場合は、肌を黒くする。試合の前、お風呂から上がったら、セルフタンニングローションという液体を体に塗りたくるのだ。そのまま乾いて色が染みこむまで、ぼうっと全裸で立ち尽くす。凄く寒い。風邪を引きかねない。さらにこの液体、激しい異臭がするので鼻が曲がりそうになる。またこの間、物に触れてはならない。いや触ってもいいが、変な色と匂いがついてしまう。一度ついたら、なかなか取れない。まるで拷問じゃないか。こんなの、絶対やるもんか。
だが、やってしまうのである。ダンスにのめり込むと、段々と違和感がなくなるのである。
僕も背番号をつけた燕尾服を着て、赤いひらひらのドレスを着たパートナーと一緒に、踊った。化粧混じりの黒い汗と涙を流し、試合のたびに頭皮にダメージを蓄積させながらも、勝利の栄冠を夢見たのだ。
ところが、ダンスの勝ち負けというのはよくわからない。
ボールを籠に入れたら得点だとか、何回転したら何点だとか、明確な決まりがないのである。試合中の頭髪や、試合会場で穿く靴下の色には決まりがあるのに、どうなっているのだろう。
試合が始まると十組くらいが一斉に踊る。審査員はそれを見て、「誰が良かったか」順位づけしていくのだ。つまり主観である。どれだけ観客を感動させられるかの勝負。スポーツというより、アートみたいだ。
先輩に実際にもらったアドバイスはこんな感じ。
「とにかく歩幅! 大きく動けば、その分目立つ!」
「二人の情感を醸し出す、世界観を作ること。そこに審査員を惚れさせるの。入場時の視線、礼の手つき、一切手を抜いちゃだめ。指の爪の先まで意識を張り巡らせる。全身が見られている意識を持つ。そして何よりもまず、自分に自信を持つこと。自分を好きになること」
「体を柔らかく。頭と首と肩と胸と腹と腰と足を全部別々に動かすんだ。そもそも人体の構造とは……」
「音楽を取り込んで、体から放つの。楽器になるってこと。そうしてフロアと一つになって、場を支配する」
「審査員と目が合ったら変顔するといいよ!」
「可愛い女の子に露出の高いドレスを着せるか、背の高い美男子の首を伸ばす。それが手っ取り早いんじゃないかなあ」
「結局は勢いだから。俺は試合前日に陰毛を焼くようにしててな……お前も、やれ」
よくわからない。しかし順位はつく。勝者のダンスははっきりと胸を打ち、負けた自分の踊りを録画で見ると、想像よりもずっとかっこ悪くて、納得できてしまう。だから悔しくなる。勝ちたくなる。深い沼に、はまってしまう。
そして四年間があっという間に過ぎていく。ダンスのついでに大学生活。お父さんお母さん、学費をありがとうございました。ダンスがうまくなりました。
入部して間もない頃、初めてフォーメーションダンスを見た時の感動は忘れられない。
女性は赤と黒、「不思議の国のアリス」のトランプ兵のようなドレス。男性は黒シャツ黒ズボンに青いネクタイ。そっくりな出で立ちの八組十六人が、音楽に合わせて一斉に動く。マスゲームのように、一直線になったかと思えば円を描き、一組ずつ目の前に出て回転したり、めまぐるしく隊列を入れ替えながら最後にはぴたりと揃う。先輩たちがまるで一つの生き物になったかのよう。今でも鮮やかに光景が蘇る。自分もこれをやりたい、と強く思った。
あの激動の世界を巣立って、十年が経つ。
すっかり社会人になった僕だが、ふと振り返ると、大事なことは全てダンスに教わったような気がする。夫婦生活の基本は、ダンスの基本、リード&フォローではないか。パートナーとの信頼関係に、男女問題を解決するヒントがあるのでは。読者に届く本の作り方は、審査員へのアピールに似ている。いい本と売れる本の違いについて考えるようなことを、試合のたびにしていなかったか。
ダンスは、社会の縮図。そんな気がするのである。
この感覚を何とか誰かに伝えたくて、僕はこれを書きました。「大船一太郎」という己の分身と共に、かつての仲間を訪ねながら辿り直した物語です。ちょっと長くて奇妙ですが、ダンス部、アツいんです。
page 1/4
試し読み 2
〔 page 2/4 〕 page 1

1 三歩でワルツ
コンパ? ダンパ!
三角屋根の駅を出ると、桜並木が延々と大学まで続いていた。心地の良い春の陽気が顔を撫でていく。受験勉強が終わり、新しい生活に一歩踏み出す実感がようやく湧いてきて、大船一太郎の心は浮き立った。
「おっす」
背中を叩かれて振り返ると、同じ高校だった寺尾慎吾が長い睫毛をぱちぱちさせていた。二人で視線を合わせてにやっとする。
「お、ちょうど」
「同じ電車だったかな。目星、つけた?」
「んー、だいたい」
大船は「部活&サークル紹介」と題されたパンフレットを開いた。いくつかのページに蛍光ペンで丸がついている。テニスサークル。バドミントンクラブ。文芸研究会。美術部。
「男女比率が同じくらいのところがいいよな」
カールのかかった髪をいじる寺尾の言葉に、頷いた。中高一貫の男子校で過ごした六年間は長かった。社会に出る前に華やかな思い出が欲しい。大学はそのラストチャンスである。
「ま、せっかくのサークル見学だし。いろいろ回ってみようよ」
二人は頷き合い、桜が満開のキャンパスの中へと足を踏み入れた。
しかし大学の新歓が、こんなに激しいものだとは知らなかった。願書を出しに来た時には閑散としていた守衛所前が、真っ直ぐ歩くのも難しいほどの混みよう。新入生一人に、様々な団体のユニフォームを着た上級生がわっと群がり、「ちょっと話だけでも!」だとか「今日、タダで飯が食えるよ!」だとか、声をかけるわ腕を掴んで引っ張るわのお祭り騒ぎ。
言われるままにブースに入ると、そこで説明を受けつつ、紙に電話番号やメールアドレスを記入させられる。「本サークルの新歓イベントのお誘いのため、電話をしてもいいですか?」という確認欄にチェックマーク。怪しい商売みたいだ。
ゆうに百を超える部活、サークル、同好会が、千人ほどの新入生を奪い合う。あちこちにノボリや看板が立ち、サンドイッチマンが歩き回る。ジャージを着た背の高い男が、携帯電話に向かって叫んでいる。
「こちら西班の武藤、状況は。え、法学部の女の子三人組? 絶対逃すなよ。時間を稼げ、予備部隊から応援を送る、どうぞ」
ここは戦場か。
唖然としつつも何とか人混みを抜け、大船と寺尾は噴水の横までやってきて、一息入れた。
「英語研究会にしようかな、俺」
寺尾が自販機でコーラを買いながら言う。
「留学して、世界を見て回りたいんだ。大船は? 高校では美術部だったよな」
「僕はちょっと迷ってる。運動系も気になってるんだけど……」
いくら「初心者歓迎」とポスターに書いていても、筋骨隆々のアメフト部員は大船に目もくれず、チラシも渡してこなかった。こっちだって戦力外だとわかってはいるが、切ない。
「美術部員の体力でもついていけて、面白くて、男女比率が同じくらいの競技がいいな」
「そんなのあるかなあ」
寺尾が嘆息する。我ながら贅沢を言っていると思いながら、ぼーっと空を見た。青い空に桜の花びらが泳いでいる。話しかけられたのは、そんな時だった。
「新入生の方ですかあ」
お揃いのジャンパーを着た、女性の二人組がチラシの束を手に立っていた。片方は背が低く、くりくりとした丸い目にショートカット。もう片方は長身で、切れ長の目にロングヘア。二人とも綺麗だったが、どこか不思議な気品があった。
「これからダンパがあるんですけど、来ませんか」
大船と寺尾は顔を見合わせる。飲み会の聞き間違いだろうか。
「すぐそこの生協でやるんで、良かったら」
手渡されたチラシには「新入生歓迎社交ダンスパーティー」とある。大船は目を疑った。そんなものがあるなんて、大学は凄いところだ。
「ワルツとかルンバを踊りながら、お酒を飲むの。ツマミもあるよ」
もう一人の女性が「楽しいよー」と後ろから囁く。
「ダンスなんて僕、やったことありません」
切れ長の目をした女性は、さっと髪をかきあげた。
「最初はみんな初心者だから。教えてあげる。ワルツとルンバくらいなら、すぐに踊れるようになるよ、私もそうだった」
嘘を言っている様子はない。しかし……ダンスか。この僕が、その、なんだ、踊るっていうのか? しかし女性陣に「ね、行こうよ」と腕を組まれると、もう抵抗できなかった。
「じゃあ、ちょっとだけ覗きます」
「オッケー。ついてきて」
女性に続き、大学の中をきょろきょろ見回しながら歩き始める。途中で女性二人が振り返った。
「言い忘れてた。私たち、これだから」
丸い目の女性のジャンパーを示し、その背中に書かれた文字をぱんぱんと叩いてみせる。
「ダンス部。よろしくね」
そこには、ALL一橋大学体育会競技ダンス部、とあった。
脇の下の筋肉を鍛える
「えっ大船さん、社交ダンスされてたんですか」
担当編集者の望月さんが目を丸くする。飲んでいたコーヒーが変なところに入ったらしく、ごほごほと咳き込んで「し、失礼」と坊主頭を撫でた。
「実はそうなんですよ」
困ったな、と思いながら曖昧な笑みを浮かべた。僕たちは企画を練る時、いろいろと雑談をする。今日はたまたま、大学時代に話題が及んでしまったのだ。
「社交ダンスって、あの、舞踏会のですよね。大船さんってもしかして、高貴な生まれだったりします?」
瞬きする望月さん。ユニクロの白いパーカーと大柄な体のせいで、シロクマみたいだ。
「いや、単に部活だったんですよ。競技ダンス部という体育会です」
「へえ、そんなものがあるんだ。楽しそう。小説の題材になりそうじゃないですか」
「いや。無理です」
僕はきっぱり言った。そういうことはあまりないので、望月さんが目を白黒させている。
「イメージするほど、楽しい部活じゃないですよ。しんどいことが一杯あって、あまり思い出したくないんです」
「ええー。優雅で、上品な感じなのになあ」
そこで僕は身を乗り出した。
「と、思うじゃないですか。あれ、意外と体力勝負なんです。クイックステップなんて、三分間、全力疾走するようなものですよ。全身汗だくのへとへと。それから、男女で組みますよね。ホールドと言うんですが、要するにずっと両手を上げてるわけです。その状態で、笑い続けなくちゃならない」
「え、笑う?」
「歯を食いしばって苦しげにしていると、それだけで下手に見えますからね。余裕たっぷりに微笑んでなきゃいけません。わかりますか。両手を上げて、足は凄い勢いでカサカサ動かしてるけど、顔だけはアフタヌーンティー」
「こわっ」
「だから顔面の筋肉を鍛えてる人もいましたよ。地味なところの筋肉、けっこう使うんです。脇の下から脇腹のあたりとか」
「そんな場所の筋肉、意識したこともなかったですね」
「僕も入部するまではそうでした。みんなで筋トレもしますが、きつかったですよ。ぶっ倒れて、泣いてる子もいましたね」
ふうむと、望月さんは唸った。
「つまり、体力的に辛いってことなんですかね」
「最初はそうです。でもうまくなると、どんどん楽になっていきますね。その過程は結構、面白いです。そうだ、望月さんもやってみたらどうですか? 猫背が治りますよ。ダンス教室ってあちこちにありますし」
「いや、あの、どうでしょう」
「緊張することはないですよ。社交ダンスの競技人口って、日本が世界一なんですって。百六十万人くらいだったかなあ。日本は、実はダンス大国なんです!」
望月さんは一つ瞬きしてから、僕をまじまじと見た。
「大船さん、ダンスが辛かったという割には、楽しそうに話しますね」
page 2/4
試し読み 3
〔 page 3/4 〕 page 2

アフリカとワサビ
大船と寺尾が連れてこられたのは学生生協の二階。普段は食堂だが、今日は机と椅子が隅に寄せられ、だだっ広い空間になっていた。いつもおばちゃんがランチを盛り付けてくれる窓口もシャッターが閉まり、貸し切り状態。音響機器から、ゆったりとした音楽が流れている。
「お。いらっしゃーい」
やはりお揃いのジャンパーを着た男性二人に迎え入れられ、四人に包囲される形で、大船と寺尾は席についた。
「何飲む? とりあえずビール?」
未成年です、と言っても無駄な雰囲気だった。大船は勧められるままに紙コップにビールを入れてもらい、口に運ぶ。苦い。
「まずは自己紹介しようか。俺は経済学部三年の佐藤っていうんだ。ワサビって呼んで」
突然、薬味を名乗った体格の良い眼鏡の男を前にきょとんとしていると、隣からニカッと白い歯を見せてもう一人の男が言った。
「俺、経済学部二年の北島。あだ名はアフリカ」
「ど、どうして、みなさん、そんなあだ名なんですか」
「何でだっけ? 俺もわかんない」
「ワサビさんは、一年生の時に緑色のTシャツ着てたからって聞きましたけど」
「アフリカは、子供の頃アフリカに住んでたからだよな」
「そうです。南アフリカです」
ひとしきり二人で頷きあってから、ワサビとアフリカは大船たちの方を向いた。
「お前らにもあだ名が必要だな」
いらない。大船は心からそう思った。
「ぐりこ、サマンサ、何かいい案ある?」
ワサビが女性二人に水を向ける。「そうねえ……」と切れ長の目の女性、ぐりこが考え始めた。どうやら女性といえども、このあだ名システムから逃れることはできないらしい。
変なあだ名をつけられたら、違う部活に入ろう。平静を装いつつ、大船はそう決意した。
「まずはワルツを踊ってみようか。ワンタローはサマンサと、タラオは私と」
大船一太郎という名前から、ワンタロー。寺尾慎吾は苗字をもじって、タラオ。かくして、この世にワンタローとタラオが生をうけた。五分くらいで。
「あの、僕、ほんとに何にもわからないんですけど」
「大丈夫、大丈夫」
にこにこ笑うサマンサ先輩に両手を掴まれ、フロアへと連れて行かれる。本名の相川夏樹から夏だけ取ってサマー、サマーが訛ってサマンサという由来らしい。
「ワルツは三拍子なのね。ちょうど今、流れてる曲がそう。ほら、一、二、三。一、二、三。カウント取れる?」
大船は耳を澄ませてみたが、よくわからない。アフリカ先輩が大船のすぐ横に立って、ステップを踏み始めた。
「拍子に合わせて一歩ずつ出せばいいんだよ。真似してみて。それ、一、二、三。次はこっちに向かって一、二、三。一、二、三……」
彼の足元を凝視しながら、大船は同じ動きを試みる。
「で、ここで最初に戻る。また一、二、三。一、二、三」
どうやらワルツのベーシックステップとやらは、三歩を四回、十二歩で構成されているらしい。あとはその繰り返し。つまり十二歩覚えればいいようなのだが……。
「覚えた?」
「すみません。もう一回、いいですか。ええと、一、二、三……」
「違う違う。そこはシャッセって言って、一回足を揃える」
「あ、はい。一、二、三……」
ちらりと横を見れば、タラオはもうぐりこ先輩と組み始めている。大船は焦った。が、なかなか頭に入らない。思えば小学校の出し物からこの方、振り付けを覚えるのは苦手だった。居残り練習の苦い思い出が蘇る。
「ワンタロー、もういいよ」
サマンサ先輩の言葉に、顔を上げる。
「とりあえず踊ってみよ」
「え? でも、まだうろ覚えなんですが」
「いや逆に、踊れば覚えるんじゃない?」
そんな馬鹿な。助けを求めてアフリカ先輩を見たが、彼も爽やかに笑う。
「そうだな、やってみようや。いけるいける」
あだ名の時から薄々感じていたが、この人たちはちょっと適当すぎるのではないか。
「左手は女子の右手を握る、そう。それで、右手は女子の肩甲骨あたりに当てる。半身で向き合って組む。互いに体の右半分が重なるように」
すぐ目の前に、サマンサ先輩のきらきら光る大きな瞳がある。上目遣いで、こちらを見ている。いい匂いがして、柔らかな感触と共に体温が伝わってきて、大船の動悸は一気に激しくなった。
「どうして半身で組むかっていうとね、貴族の踊りだからだよ。昔の紳士は左腰に剣を差していたから、それがぶつからないようにね」
言葉が頭に入ってこない。
「それじゃ、やってみようか。最初は左足で前進から」
前進って言ったって、前にはサマンサ先輩がいる。左足のすぐ先に、相手の右足があるのだ。どうすればいいんだ、これは。
「一、二、三、一、二、三、せーの」
「うわっ!」
大船は勢いよく蹴躓いた。組んでいた腕でサマンサ先輩を引っ張ってしまい、二人とも大きくよろめいた。やっぱり全然だめだ。せめて、ちゃんと一人でステップを踏めるようになってからじゃないと──
「ワンタロー。今、私の足を避けようとしたでしょう」
「え? はい。そうしないとぶつかるから」
「いや、ぶつかっていいよ」
良くないでしょ。
「あとね、ステップは意識しなくていいよ。思い出そうとして、下向いちゃってる」
「でも足元を見てないと、次に出す足を間違えそうで」
サマンサ先輩は、おかしそうに笑う。
「間違えるわけないじゃん。人間には二本しか足がないんだから。だから左を出したら、次は絶対に右しか出せないよ」
「あ、言われてみれば……」
「難しく考えなくていいよ。とりあえず左と右を交互に、足を出してみよう」
「はあ」
そんなものなのだろうか。何か騙されているような気がしたが、逆らっても仕方ないので大船は言う通りにすることにした。顔を上げて、足元を見ない。
怖い。
すぐ足元に障害物があるとわかっているのに、それを目で確認できないというのは、こんなにも恐ろしいことなのか。
「そう。左、右、左、右ね。ぶつかってくるんだよ。せーの」
うう、ままよ。
目を閉じ、歯を食いしばって、大船は左足を出す。相手の足に衝突する──
ぶつからなかった。
思わず目を見開く。
次は右。次は左。大船が左足を出せば、サマンサ先輩が右足を下げる。進んだ分だけ相手が下がり、向きを変えれば相手も向きを変える。一、二、三。自分の動きに、影のようにぴったりとサマンサ先輩がついてくる。
「上手! そのまま次の三歩も」
なぜだろう、ステップは覚えていないのに、次にどうするかがわかる。いつの間にか、自分も相手の影になっているようだ。サマンサ先輩はこちらに行くから、影である自分はこちらに行けばいい。一、二、三。一、二、三。
「そう、そこで最初に戻る。もう一回。そうだね、今度は曲に合わせてみよっか。一、二、三、このくらいのスピード、わかる?」
あ、結構速いんだな。
「でも、全然慌てなくていいよ。やることは今までと同じ、左右を交互に出すだけ」
その通りだった。大船はいつの間にか、口をあんぐり開けたまま足を動かしていた。
なんだこれ、凄いぞ。
一人では、足がついていかなかっただろう。しかし、先輩と一緒だと間に合う。むしろ余裕があるくらいだ。力は二倍になり、体重は半分になっている感じ。音楽に合わせて体を動かしているのではなく、音楽が自分の体を乗せて流れていくような──
「ふう、終わりー。だいぶ覚えたんじゃない?」
そこでサマンサ先輩が足を止め、大船ははっと我に返った。
「上手だったよ。練習すれば、次はもっとうまく踊れるはず」
サマンサ先輩は額にちょっと汗をかいていた。
「どうだった?」
アフリカ先輩に聞かれて、大船は考え込んだ。さっきまで、右も左もわからなかったのに。
「右と左だけわかれば、踊れるんですね」
「ハハ、まあそうだね。今度は違う人と組んで踊ってみる?」
「やってみたいです」
大船はずっと運動が苦手だった。ボールを追いかけたり、延々と走ったり、誰かを投げ飛ばしたりすることの、楽しさがわからないままだった。
でもダンスは面白い。三歩でそう思えたのだった。
page 3/4
試し読み 4
〔 page 4/4 〕 page 3

十秒のための数ヶ月
「いや、苦しいですよ、ダンスは苦しいです。本当に苦しかったんですから」
僕は慌てて口にした。望月さんが首を傾げる。
「でも、体力的に辛いのは最初だけだって……」
「僕らがやっていたのが競技ダンスだからでしょうね。社交ダンスで競技するんです。順位がつくし、勝ち負けがあるんですよ。ダンスの試合は、予選が二次くらいまであって、準決勝、決勝という流れになるんですが」
僕は喫茶店の四角いテーブルをダンスフロアに見立てた。
「フロアをぐるりと、審判員が取り囲んでいるんです。試合によるけれど、七人くらいかな。で、いっぺんに十組ほどが踊る。上げてもいいと思った組の背番号にだけ、ジャッジがチェックシートにチェックを入れていく」
ふむふむ、と頷く望月さんを見つめながら僕は続ける。
「予選のたびに半分くらいが落とされて、どんどん人数が減っていく。何百人と試合にエントリーしても、決勝戦を踊れるのは、六組十二人だけ」
「だいぶ減っちゃいますね」
「一次予選で落ちたら一回しか踊れないんですよ」
そこで相手がぎょっと目を剥いた。
「予選は、二分あるかないかです。何ヶ月も練習して臨んでも、それで終わり。高いお金を払って買った衣装も、靴も、セットした髪型も、全部パー。朝の九時くらいに会場に集まって、閉会式が終わるのは十九時くらい。だけど一次予選で落ちたら、十時には何もやることがなくなって。九時間、ライバルの応援だけして過ごすわけです」
「え、えぐいですね……」
「勝ち負けに納得がいかないこともあるんですよ。審査基準は、ジャッジの主観なので。フィギュアスケートだと、トリプルアクセルは基礎点八とか、はっきり決まってますよね。でもダンスはそうじゃない。何回転したって、かっこよくなかったらダメ。ただ立ってるだけでも、雰囲気が良ければチェックが入っちゃう。一瞬の印象が大事なんです。二分で十二カップルが踊ると、ジャッジは一カップルの踊りをどれくらい見られるか……単純計算しても、十秒ですよ。たったそれだけで判断されるのって、結構苦しいです」
まくしたててからはっと気づくと、やはり望月さんがじっと見つめていた。
「大船さん、思い出したくないという割には、細かく教えてくれますね」
「いやいや、本当に思い出したくないんですよ。たまたま今、記憶が蘇ってきちゃって、困ってるんです」
「でも、部活の友達とはご縁が続いていると、前に聞いたような」
「それはまあ。たまに飲んだりはします。でも、過去の話はほとんどしませんよ」
「そうですか……」
「はい。だから、ダンスは企画としては、なしです」
強引に結論づける。よほど僕は陰鬱な表情をしていたのだろう。望月さんも無理強いはしなかった。それから僕たちは、ああでもない、こうでもないと、別の企画について考え始めた。
美術部が有利なスポーツ
「ダンス部はめっちゃ楽しいよ!」
一通りダンス体験を終えた大船とタラオを前に、ぐりこ先輩がテーブルにアルバムを広げる。
「私がいいと思うのは、男女一緒に活躍できるところ。他の部だと男が選手で、女がマネージャーってところ多いじゃない? 女子ラクロス部なんかだと今度は男が肩身狭くなっちゃうし。でもダンスは男女ともに選手で、練習メニューも同じ。平等なわけ」
へーっとタラオが声を上げる。写真の中では、男女がごちゃ混ぜになって練習をしていた。サッカー部だった彼には、新鮮な光景なのかもしれない。
「だから遊ぶ時なんかも、雰囲気いいし。飲み会も楽しい」
ぐりこ先輩がぺらりと一枚めくる。川辺でキャンプしている写真も、遊園地でチュロスを手にしている写真も、ビールを片手に顔を赤くしている写真も……みな、笑顔だった。
「でも、体育会なんですよね。練習がきついのでは?」
大船は一番の不安を口にした。ぐりこ先輩が頷く。
「週に二回、参加必須の練習会がある。それから土日に自主練」
週に四回か。少なくはない。
「でも、女の子もついてこられる練習だからね。私は大学まで運動の経験なかったんだけど、こうして三年間続いてるし。大丈夫だと思うよ」
ワサビ先輩が横から言葉をかぶせた。
「俺がいいと思うのは、みんなゼロから始めるってとこ。大学からサッカーや野球始めたって、経験者にはかなわないじゃん。でもダンスは違う。経験者なんてほとんどいないから、努力すれば勝てる。あと、基本的に全員が試合に出られる」
「そうなんですか」
タラオが食いついた。彼は高校では補欠だったそうだ。
「一、二年のうちは絶対出られる。三、四年になっても基本的には出られる。事実、今の上級生は全員出てるから。それに勝ってる」
またぐりこ先輩がアルバムをめくった。真っ赤なマーカーでこう書かれている。「大学から始めて全国優勝が狙えます!」
「うちら、こないだの試合で団体優勝したの。私も勝ったし、ワサビも入賞した。というか、みんな勝ったから、総合得点で団体優勝なわけ。うち、強いんだよ」
写真には強烈な説得力があった。
金色に輝く巨大なトロフィー。その周りで笑顔を爆発させている、部員たちの集合写真だ。ぐりこ先輩は化粧をしたドレス姿、一方のワサビ先輩は漆黒の全身タイツ風の衣装。中央の背が高い男性が広げている賞状には、確かに「団体一位」と書いてあった。一位。一位って、凄いぞ。
「ダンスって運動神経だけじゃないんだよ。美的感覚が大事なの。要は見せ方?」
ぐりこ先輩の言葉に、ワサビ先輩が頷く。
「たとえばバスケなら、背が高い方が有利じゃん。でもダンスは八種目あるから、それぞれ売りが違ってくるんだ。ワルツだったら、背が高くて細い方が良く見える。タンゴだったら、背が低くて素早い方が映える。工夫次第でどんな個性も活かせる」
ぐりこ先輩は大船の目を真っ直ぐに見て、ダメ押しの一言を放った。
「ワンタローって、高校では美術部だって言ってたよね? そういう人、有利だと思うよ」
大船は心がぐらりと傾くのを感じていた。
スポーツでの優勝、トロフィー、賞状。そういったものとは無縁だったし、これからもそうだと思っていた。だが運動未経験だというぐりこ先輩が、トロフィーを掲げて笑っているのだ。
何も頂点を取りたいなどとは言わない。一桁の順位ですら望みすぎだ。だけど賞状の一枚でも、取ることができたら。あるいは日本一のチームの一員だったことがあると、思い出が残せたら。どれだけ素敵だろう。
「やってみようかな」
大船が口にすると、先輩たちが手を叩いて歓声を上げた。
「六月までに本入部してくれればいいから。まずは仮入部届を書いてってよ」
ワサビ先輩が差し出した紙に、大船は名前と学部を記入する。タラオに目をやると、まだ迷っているようだった。
「あの。俺、留学したいと思ってるんですけど」
「おお、留学。いいじゃん」
「二年生までダンスやって、その後辞めるとかできますかね」
「うーん、できれば続けて欲しい。でも、本人の希望次第だね。実際に途中で辞める人もいるから。無理強いはしないよ」
そう聞いたタラオは何度か頷くと「じゃあ俺も」と仮入部届に書き込み始めた。
ダンス部。考えもしなかった選択肢だったが、不思議としっくりくる。素敵な大学生活が始まる予感がした。
page 4/4
続きは本書、二宮敦人『紳士と淑女のコロシアム 「競技ダンス」へようこそ』でお楽しみください。