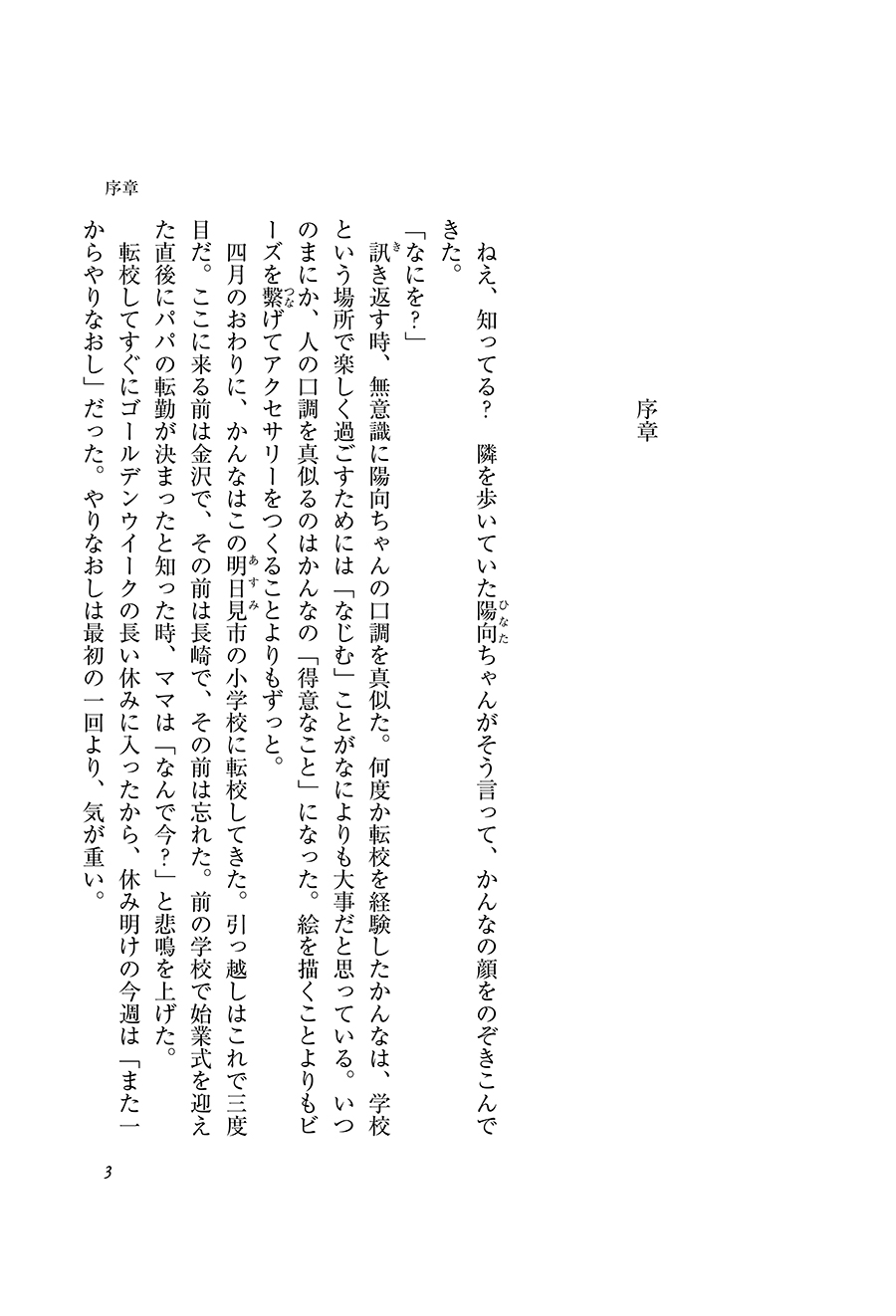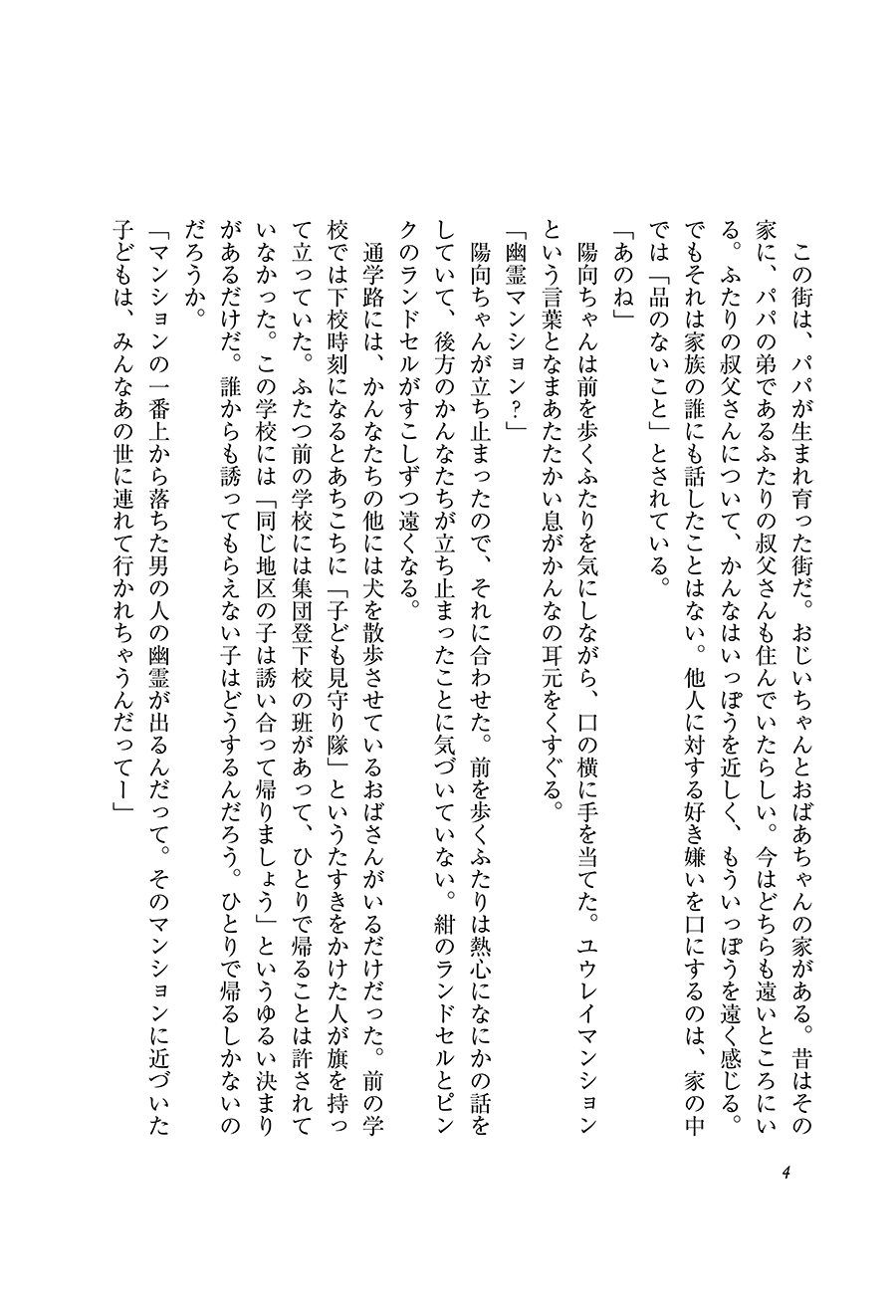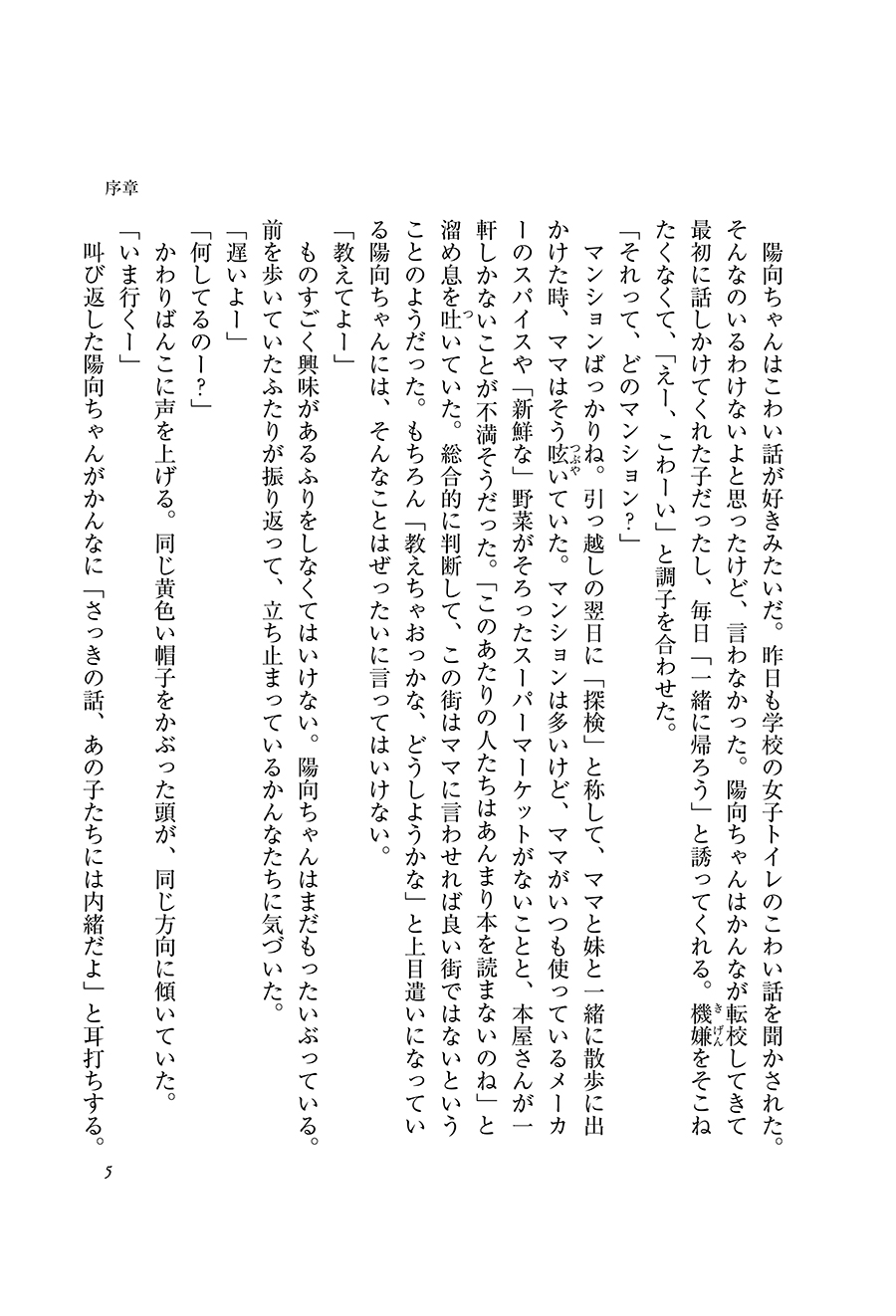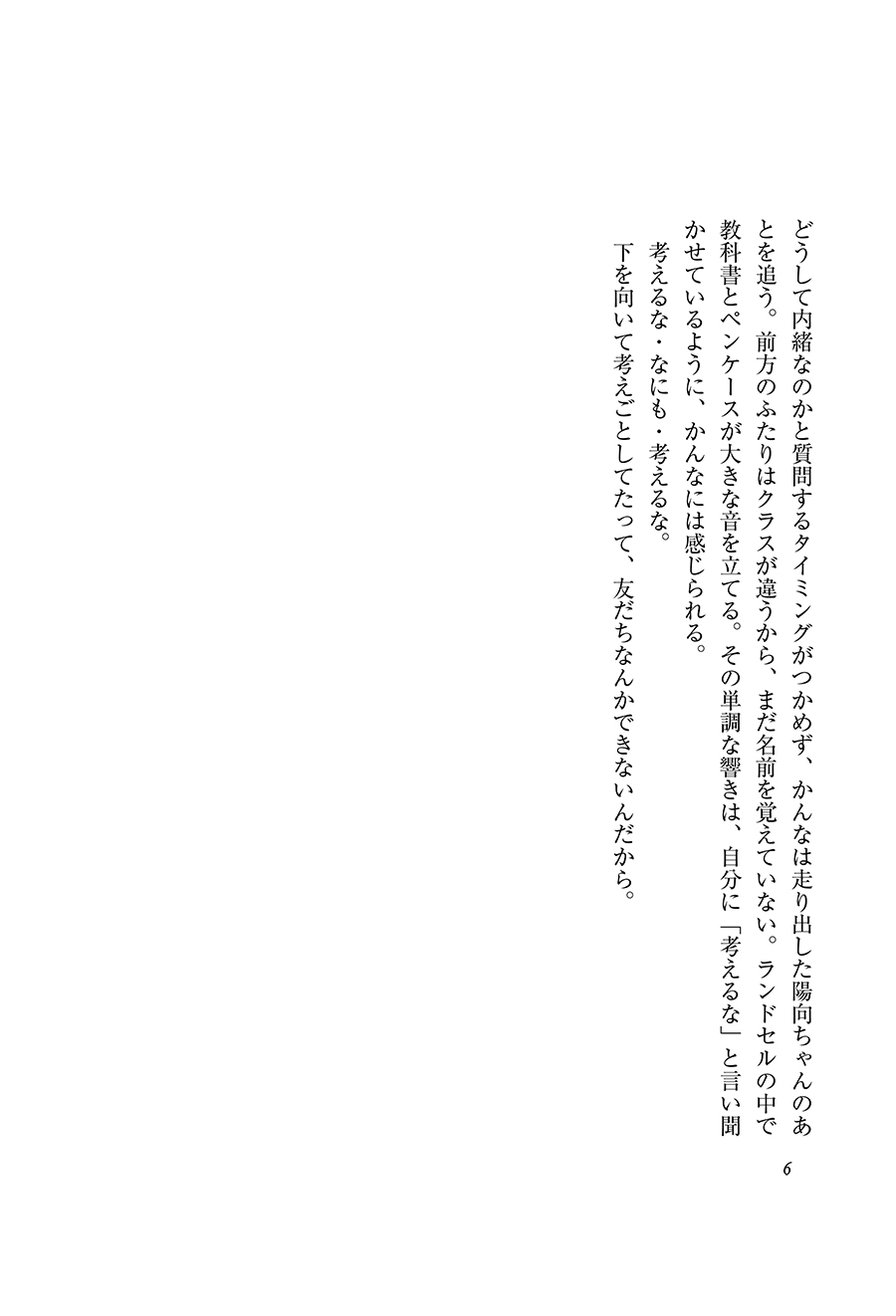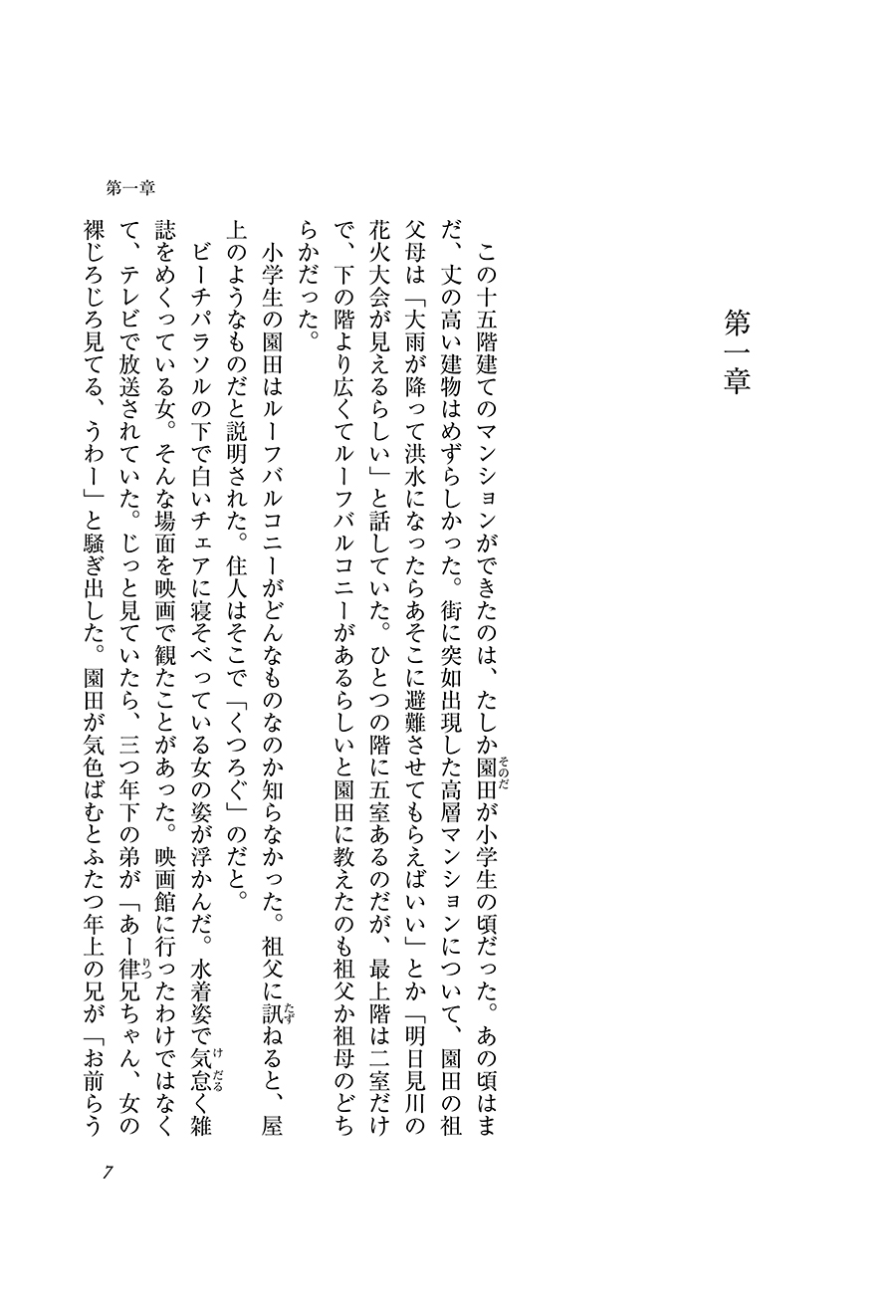第一章
この十五階建てのマンションができたのは、たしか
小学生の園田はルーフバルコニーがどんなものなのか知らなかった。祖父に
ビーチパラソルの下で白いチェアに寝そべっている女の姿が浮かんだ。水着姿で
恥ずかしかった。水着の女に目を奪われていた自分も「ルーフバルコニー」のない借家で母と、母の実父母である祖父母、兄と弟と自分がひしめきあうように暮らしていることも、兄と弟がさわいでいるあいだにいつも言葉を飲みこんでしまう自分も、ぜんぶ恥ずかしかった。
その後マンションの前を通るたびに、弟の「うわー」が耳の奥で聞こえた。もうじゅうぶんだろう、おれはこの件でじゅうぶん恥ずかしがっただろうと自分に言い聞かせても、羞恥心はしつこく
パルスのお膝元、と呼ばれるこの街で、園田は生まれ育った。このあたりに住む年寄りはみんなパルスの上に「世界の」をつける。世界のパルス。自分の会社でもないのに、誇らしげにその名を口にする。園田の祖父母もそうだった。

みなさん、大きな会社はぜんぶ東京にあると思っているでしょう、と言う担任の先生の声を今も覚えている。小学三年生の時だった。
「きみたちはパルスという、世界的に有名な電機メーカーの本社がある街に住んでいるんです。先生は高校生の時、アメリカのカリフォルニアというところで半年間ホームステイを経験しました。そのお家の居間には、パルスのテレビがありました。すごいことだと思いませんか?」
先生は「お父さん、お母さんがパルスに勤めている子、手を挙げてみてください」と言った。数名の手が挙がった。「じゃあ、お父さんやお母さんがパルスに関係のあるお仕事をしているという人」という質問にはさらに多くの手が挙がった。園田は自分が手を挙げていいのかどうかよくわからず、下を向いていた。
広大な敷地を持つパルスの本社は、地図で見ると市のちょうど中心部にある。それを取りかこむように、下請けや孫請けの会社や販売代理店が放射状に広がって位置している。そのうちのひとつが園田の父の勤め先で、やっていた仕事は「パルスに関係のある」といった
園田の実家は川沿いの町にある。町の中でもとりわけ古びた建物が建ち並ぶ、多くの人が「昭和っぽい」と表現する町で生まれ育った。二階建ての家や文化住宅がきゅうくつそうにひしめきあっていた。「○○銀座」と名づけられた商店街では、夏でも冬でもおかまいなしに桜の造花が風に吹かれていた。
隣の家には老夫婦が住んでいて、玄関にいくつもプランターを並べていた。母と隣人はそのプランターがこちらの敷地にはみ出したのはみ出さないのでしょっちゅう
母は隣家のプランターに植えられた花を
「どうせなら、食べられるものでも育てりゃいいのに」
母がなにかにつけて人のやることにケチをつけるのが恥ずかしかった。ほかにもたくさん恥ずかしいことがあった。クラスでいちばん背が小さいこと。二重とびがどうしてもできないこと。なんの授業だったかもう忘れたが、「カレーの材料を挙げよう」という授業でみんなが次々に、「たまねぎです」とか「お肉です」とか言うのに、園田だけ「ツナ」と答えてしまったことがあった。そのすこし前に母が「お肉買うの忘れちゃった」とツナを入れていたことが頭に残っていたせいだが、クラス全員から「カレーにそんなの入れるわけない」と馬鹿にされた。「先生もそれは食べたことないなー」と困ったように首を
両親の仲が悪くて、いつも隣近所に聞こえるような大声で言い争っているのが恥ずかしかった。運動会の時、観覧席がみょうに騒がしいと思ったら両親が怒鳴り合っていたこともあった。彼らが言い争う理由はおもに、父に言わせれば、母が父に「なめた態度をとる」こと。母に言わせれば父の稼ぎが少ないから母の実家に住まわせてもらっているというのに父に「感謝の心がない」ということ。
父の味方は、家の中にはひとりもいなかった。園田が七歳の時に両親が離婚し、父ひとりが家を出ていった。小学生の中途から中学卒業までは母方の姓である「
周囲の人びとに言わせれば、いつまでもひとつのことにこだわるのは「めめしい」ことらしい。「男の子ってひと晩たったらぜんぶ忘れちゃうよね」「うちなんか三歩歩いたら忘れちゃう」というような周囲の大人の会話を耳にするたび、「もしかして自分はほんとうは男ではないのかもしれない」と思っていた。
そんなことを思い出しながら「ルーフバルコニー」のあるマンションの十五階の外廊下に立っている園田の鼻先を、油でなにかを炒める匂いが
首を伸ばして、下の様子を
ここ十数年で似たようなマンションがいくつもできて、もうここは「このあたりにはめずらしい、丈の高い建物」ではなくなった。俗に言う駅近物件というやつで、売りに出るとすぐに買い手がつくマンションだったが、数年前、八階に住んでいた中学生がベランダから飛び降り自殺をして以来、その人気は下降気味だ。販売や管理にかかわる部署ではないが、マンション管理会社に勤めているのでそうした情報は耳に入ってくる。
マンションの向かいには背の低い、横長の賃貸アパートがある。三階のベランダで洗濯物がはためいているのが見えた。白いTシャツ、白いタオル。地上に視線を落とすと、植え込みには白いつつじが咲き乱れている。こんな清らかな色に囲まれて死ぬのも悪くない。
八階で死ねたのなら、最上階から飛び降りたら間違いなく死ねるだろう。だから、このマンションを自殺の場所に選んだ。こんな日中に人が死ぬなんて、みんな考えもしないだろう。ここの住人の多くが自分の死体を目にすることになる。かたい地面に叩きつけられ、
どうして彼は死んだのか。そんなふうに考えてくれる人が、ひとりぐらいはいるのだろうか。でも「どうして」なんて、園田自身にもわかっていない。億単位の借金を背負ったとか女にふられたとか、そういう明確なきっかけがあったわけではない。ただ今朝、目が覚めて「朝食に卵を焼こうかな」とか「雨が降りそうだな」とか思うように自然に「死んでもいいかな」と思いついてしまったのだ。

自分の人生でもっとも暗く過酷だった時期といえば、やはり中学生時代ということになるだろう。その時ですら「死にたい」とまでは思わなかった。でも今はこんなにも死にたい。状況の過酷さと死にたさが正比例するとは限らないと知った。ひとつ利口になった、と
どこからか姿を現したヘルメット姿の郵便局員がバイクにまたがり、走り去っていくのを見送る。
いよいよだ。銀色の手すりを乗り越えようとして、自分の手が震えていることに気がつく。以前は、「死にたい」と「死にたくない」は対極にあって、ぜったいに交わることのない感情なのだと思っていた。でも実際には、背中合わせにぴったりとくっついていて、テンポのはやい音楽に合わせてくるくる踊るように、かわりばんこにその顔をのぞかせる。死にたい。死にたくない。死にたい。死にたくない。
ダンスが一段落したところで園田は手すりから手を離し、乱れた呼吸を整えた。じっとりと汗ばんだ手のひらからは
*
つけっぱなしにしていたテレビから「クモを食べてるみたい」と聞こえてきて、爪を
蜘蛛を食べたことがあるのかと思った。でも空の雲だって食べられないのだから、どちらにせよこの女が言っていることはおかしい。画面の中の女。若いだけで格別に美しいというわけでもない女がきゃあきゃあと耳障りな声を上げ続ける。「うるさ」と呟いてテレビを消し、しばらく爪を塗る作業に専念した。
莉子は昔から聞き間違いや勘違いが多かった。父からはよく「話の前後で推測できるだろう」「人の話を聞く時は、しっかり頭を使いなさい」と小言を頂戴したが、すべて聞き流していた。だって母がそうしていたから。「女の子はかわいければいいの」が
成績なんかどうでもいいの。耳の奥で聞こえた母の言葉をきっかけに、「あの頃」がいくつも立ちのぼる。ダイニングテーブルに広げっぱなしのランドセルのカタログや夫の大樹がソファーの背に脱ぎ捨てたシャツが、遠くなる。教室のざわめきがすぐそばに迫ってきて、椅子と自分の足のあいだでごわつくプリーツスカートの感触すらも、なまなましく蘇った。
あの頃。大樹は王様だった。かっこいい男子は他にもたくさんいたけれども、場の空気を支配するのは常に大樹だと決まっていた。そして莉子は、王様から選ばれた女なのだ。
ファミリーレストランの野暮ったい花柄の壁にこめかみを押しつけるようにして、美南は座っていた。莉子が近づくと、小さく手を振る。栗色に染めた髪が、わずかに揺れた。
「あたし、これにする。期間限定だって。おいしそうじゃない?」
ブラッドオレンジの果肉の色に塗られた美南の爪が、ラミネート加工されたメニューの「さくらんぼのブリュレパフェ」という文字の上に落ちる。グラスの底の、あざやかな赤色のゼリーの上におなじ色をしたアイスクリーム。サイコロ状に切ったチョコレートケーキの上のブリュレのカラメリゼがいかにも甘そうだった。てっぺんに鎮座するさくらんぼは
「ドリンクバーだけでいいや」
メニューを押しやる。
「ダイエット?」
上目遣いで笑う美南に「そんなとこ」と笑い返した。ほんとうは、そもそも甘いものが好きではない。つきあいで食べているだけだ。みんなが好きなものを「きらい」と言うと場を白けさせる。
昼食の後、間違えて娘の
美南とは、中学まで一緒だった。高校で別れて
あたし、ほんとは働いてないの。何度目かに話した時、美南は声をひそめて莉子に打ち明けた。開業税理士である夫の事務所で就労証明書を発行してもらい、それで保育園の入園資格を得たという。
「莉子もそうでしょ?」
その通りだった。父の会社を手伝っていることになっている。虚偽の証明書発行から入園までの経緯は、美南とほぼ同じだ。父の会社、といっても、従業員はいない。父ひとりでやっている会社だ。建設会社の下請けの下請けの下請けみたいなことを、細々とやっているらしい。でもそのことは誰にも話していない。「父は会社を経営している」とだけ言うことにしている。
なんでわかるの、とたじろいだ莉子を見て、美南は薄く笑った。
「お勤めしてるママたち、みんなもっと余裕なさそうだから」
莉子の爪に視線を投げた美南はあの時、共犯者の顔をしていた。
芽愛はかわいい。それでも、四六時中一緒にいるのは耐え難い。だから二歳の頃から保育園に預けている。多くの女たちが、子どもを保育園に入れられずに苦労していることはもちろん、知っている。ずるをしているという自覚もある。だからなんなの、とひらきなおる気持ちも。両方を手のひらにのせたまま、莉子はファミリーレストランで、カフェで、夕方の五時までの時間を無為なおしゃべりに費やす。
「あーあ、あたしも
そうぼやいたばかりの美南の唇にブリュレをすくったスプーンが吸いこまれた。たしかに二の腕や腰回りにはもったりと肉がついている。
「え、ぜんぜん太ってないのに」
それでも、莉子はそう答える。十代の頃からかわらないやりとり。痩せたい。きれいな肌になりたい。もっと大きい目が良かった。もっと小顔になりたい。誰かが外見にまつわる愚痴をこぼすたびにべつの誰かが「ぜんぜんそんなことないよ」と言う。言わなければならないことになっている。それが社交だ。
教室には、層があった。さえない生徒はパフェグラスの底に沈むゼリーのように、いちばん下で息をひそめるしかない。でもてっぺんのさくらんぼになるのは、たぶんほんとうはそんなにむずかしいことじゃない。必要なのは「読む」こと。自分の置かれた状況を。真実ではなく、相手が言ってほしいと願う言葉を。てっぺんにいる生徒も底にいる生徒も目鼻立ちやスタイルだけで比べれば、たいした差はなかった。
それらの事実はすべて、言葉にされることなく莉子の中をただ、ふわふわと漂っている。昔から「読む」ことに
「あれほら、あの人じゃない?」
美南の視線が窓の外に注がれている。年中クラスの
自分で切っているのかな、と思うような野暮ったい髪形をした彼女は、今日も灰色のスーツを着ている。鈴音ちゃんのママがあれ以外のかっこうをしているところを見たことがない。鈴音ちゃんのパパは長身だが、背が高いというよりはひょろ長い感じで、かっこよくはない。ママのほうが極端に背が低いから、大人と子どもみたいに見える。鈴音ちゃんは眉が薄くて、色が白い。他の子にブロックや絵本を奪われても泣きもせず、のっそり立ちつくしているような地味な子。その程度の印象しかない。
「ほんとだ」
自転車のカゴに、鈴音ちゃんのママのものと思われる、くたびれたトートバッグが押しこまれている。彼らはよく保育園の送迎に夫婦そろって現れる。
「あそこのパパって、ひまなのかな」
大樹は、保育園のお迎えなんて一度も行ったことがない。以前、保育参観の後の懇談会で鈴音ちゃんのママは「小児科に連れていくのは夫の担当です」と話していた。家に帰ってそのことを話したら、大樹から「俺は残業あるし、到底無理だね」と
「そうなんじゃない? だって鈴音ちゃんのパパ、仕事できなさそうだもん」
外見が冴えない。なんか暗い。鈴音ちゃんのママを構成する要素に今日もうひとつ「仕事ができない旦那がいる」が追加された。実際に仕事ができるかどうかは関係ない。そう見えることが重要なのだ。
「そういえば鈴音ちゃんのママさ、このあいだ莉子のことしつこく訊いてきたよ、あたしに。お忙しいかたなんでしょうか、だって」
すごい忙しいと思いますよ、って答えといたよ、と美南が肩をすくめた。
「えー、なんでそんなこと訊くの?」
「さあ。莉子と仲良くなりたいんじゃない?」
その手のことには慣れている。昔からよくあの手の人たちが「仲間に入れて」とでもいうような、じっとりした視線を送ってきた。教室でもそうだったし、短大を出てから就職した会社でもそうだ。いつも気づかないふりをしてきたけれども。
「関係ないけど、鈴音ちゃんのママって雰囲気があの子に似てない? ほら、あの、なんだっけ、中学の時の、ほら」
美南はあーあー、と頷いて紙ナプキンを唇に押し当てた。
「あいつでしょ。松なんとか」
松尾だか松本だか、そんな名字だった気がする。ぺったりと
「松なんとか、結婚したらしいよ」
「へえ」
ひときわ地味だった彼女は東京の、莉子が知らない名の大学に入ってそのまま東京で就職したのだそうだ。同級生の誰かが出張先でぐうぜん再会したのだという。「別人みたいに痩せてきれいになってた」と言っていたと聞いて、莉子はわずかに鼻を鳴らす。
「ふーん」
よっぽどがんばったんだろうね、と続けてコーヒーカップに口をつける。旦那は歯医者だって、と美南が言った時、ホイップクリームで白く染まった唇の端が
「歯医者ってあんまり
返事になっていない気がした。でも、そう言うべきだという気もした。
「見てよこれ」
美南がスマホを取り出し、SNSの画面を開く。「興味本位で」、彼女のアカウントを検索し、繫がったらしい。インテリアにこだわりがあるらしく、自宅とおぼしき部屋の画像ばかりが並んでいた。リビングは莉子のマンションの倍ほども広く見える。でもそんなに広い家に住んでいるわけがないから、よほど写真の撮りかたがうまいのだろう。
「あ、この人も同じ中学じゃない?」
フォロワー一覧に、見覚えのある男子の名があった。彼の名を覚えていたのは学年で成績がいちばん良かったからだ。いつも度の強そうなメガネの奥から女子を盗み見ているような気味の悪い男子だった。アイコンは黒い大型犬の画像だ。本名で、しかもフルネームでSNSやってるんだ、と思う。有名人でもないくせに。

「ほんとだ……ちょっと見て、こいつニューヨークに住んでるらしいよ。似合わねー」
ぎゃはは。美南が天井を向いて笑う。奥歯の治療のあとがはっきり見えるほど大きく口を開けて。ニューヨークだって、と莉子も調子を合わせて手を叩いた。
東京。ニューヨーク。それらの土地は、莉子にとっては「テレビで見る場所」であって、自分がそこに行きたいとは一度も思ったことがない。
「中学とか高校で地味だった人にかぎって、外に出ていきたがるよね。なんでだろ」
言ってから、あわてて「美南とかは違うけど」とつけくわえた。あと大樹も、と、それは心の中で。美南は短大、大樹は四年制の大学という違いはあれど、一度この街を離れている。大樹は最初から「地元で就職するつもり」だと決めていた。遠距離恋愛になっちゃうけど、と言って、シルバーのリングをくれたことを思い出す。莉子はそれをずっと左手の薬指につけていた。それが結婚指輪にかわるまでずっと。
美南はフン、と鼻を鳴らす。鼻息で、テーブルの上の紙ナプキンが一瞬わずかに浮いた。
「そりゃやっぱ、仕切り直しだか逆転だか狙ってんでしょ。人生の」
「あー」
「あの人たち、地元じゃそれ以上上に行けないんだからさ」
「可能性、みたいなのを求めてるってこと?」
可能性とかチャンスとかという言葉を口にするのは抵抗がある。自分の話ではないが、とても気恥ずかしい。
「それそれ。『何歳からでも、人は変われるはず!』って期待しちゃってんの」
わざとらしく目を見開いて、美南は胸の前で両手をグーにする。ふたり同時に笑い声を上げると、すこし離れた席に座っている三人連れがこちらを見た。
「ださいよね、そういうの」
「ね。でも、ほんとわたしにはわかんないんだよね」
莉子は
「山奥の村とか離島とかさ、そういうところで生まれ育ったら、やっぱそりゃ都会に出たいだろうけど」
山奥の村と離島、と言っても、莉子にはその具体的な生活はイメージできていない。ただよく「田舎あるある」として語られる、靴を
「ここは地方だけど、ぜんぜん田舎じゃないし」
莉子は「ぜんぜん」に力をこめる。県内でいちばん有名な市ではないけれど、明日見市は人口二十万人で、けっして小さな市ではない。JRと私鉄と地下鉄の駅があり、車なんかなくてもどこへでも行ける。電車に十五分も揺られたら繁華街に出られる。莉子も高校生の頃まではよく洋服や雑貨を買いに行ったが、今はめったに行かない。大きなショッピングモールができて、そこでなんでも揃うからだ。映画だって観られる。
ショッピングモールは、以前は遊園地があった場所だ。家族でよく遊びに行った場所がなくなったのはすこし寂しい。でも観覧車など、いくつかの遊具は今も残っている。「全員知り合いか親戚」だなんていうのも考えられない話だ。明日見市には大学のキャンパスだっていくつかあって、便利で、開放的な土地だ。ここから出たいという願いが理解できないのは、それだけ自分が恵まれているということなのかもしれない、と思ったりもする。
田舎じゃない、と莉子が言った時、美南はかすかに笑った。ニューヨーク似合わねーと茶化した時よりは控えめな、でもたしかに同じ種類の笑いだった。莉子は、なにかおかしなことを言っただろうかと思い返してみたが、わからなかった。ただの思い出し笑いかもしれない。
美南が壁の時計に目をやり、「あーもうお迎えの時間だよ」と舌打ちする。莉子は「ねー」と同調して、口に運びかけていたコーヒーカップを置いた。
*
「じゃあ、気をつけて」
マンションの駐輪場で自転車を停めた
「元気で」
朱音がそう言っているにもかかわらず、宏明はまだぐずぐずと足元に視線を落とし、自転車の後ろに取り付けた子ども用シートに乗せられたままの鈴音に手を伸ばす。
「いいから、もう行って」
朱音は鈴音の安全ベルトを外してやる。地面に降りたった鈴音はそのまましゃがみこんで、アリを観察しはじめた。宏明が一緒になってアリを見ようと腰を
宏明とは、半年前から別居している。かつて夫の実家の敷地内に「建ててもらった」家から、朱音が鈴音を連れて出るかっこうではじまった。新しくうつり住んだのは十五階建ての分譲マンションだが、購入したわけではない。不動産屋が「訳ありですが、悪くない物件があります」と紹介してくれた、賃貸の部屋だ。数年前に男子中学生が飛び降り自殺をして以来、なかなか借り手がつかないのだという。家賃は相場より安い。人は遅かれ早かれ死ぬ。だから朱音は気にしないし、今のところ生活に支障はない。
離婚を前提に別居を決めた時、明日見市を出るという選択肢もあった。わざわざ宏明や彼の両親のいる街に住み続ける必要はない。その選択をしなかった理由は、父だ。病身でひとり住まいをしている父から、あまり離れるわけにはいかない。
父は朱音が二十歳の頃に一度、心筋梗塞で倒れた。以来、月に一度ではあるが通院する必要があり、朱音はそれに毎回付き添っている。
「やっと鈴音を認可保育園に入れられたのに」と、「職場への通勤も大変になるし」というのも、明日見市を出ない理由だ。父のことに比べれば
今日は宏明に「正式に離婚する前に最後に一度だけ、きみと一緒に鈴音のお迎えに行きたいんだ」とせがまれて、ふたりで保育園に行くことになった。思えば、以前からやたらと「一緒に」にこだわる人だった。洗濯物を干していると「手伝うよ」とやってくる。わたしが洗濯物を干しているあいだにあなたが
「それじゃあ」
「うん」
しゃがんだ鈴音の頭に視線を落としたまま、宏明はぐずぐずしていつまでも立ち去ろうとしない。まさかこの人、このまま部屋までついてくるつもりなんじゃないだろうか。「ほら、鈴音がさびしがってるから」とかなんとか言って図々しくあがりこんできて、あの家にいた頃のようにわたしがつくった夕飯を食べて「まだ、おれたち家族だよな?」なんて、離婚の話をうやむやにするつもりなんじゃないだろうか。冗談じゃない。
宏明は朱音がバイトをしていたコンビニの客だった。いつもハムとたまごのサンドイッチを買うので「ハムたまお」というあだ名をつけられていた。毎朝同じようなスーツに同じようなネクタイ。常連客にあだ名をつけるのは、パートの主婦と学生バイトの共通の娯楽だった。容姿のいい客は「王子」とか「姫」と呼ばれて、誰が接客をするかでひそかな争いがおこった。
ハムたまおは容姿がよくなかったのでバイトの女の子たちにとっては、たまにサンドイッチではなくゼリー飲料を買っていった日にだけ「具合でも悪いのかな」と話題にのぼる程度の存在だったが、朱音は好きだった。商品を受け取る時にちゃんと目を見て「ありがとうございます」と言う人だったから。かわいい女性店員だけでなく、朱音にもおじさんの店員にもひとしく、礼儀正しい態度をとる。「こんな人いるんだ」と驚嘆した。女の容姿を基準に、露骨に(あるいは微妙に)態度を変えない男がいるなんて、と。
あのコンビニはまもなくつぶれた。オーナーは従業員の教育だけでなく、いろんな面でゆるかったから。でも、なんだかんだであそこでバイトしてた頃は楽しかったな、と朱音は思いながら、自転車のカゴから通勤鞄を引っ張り出す。黒い
楽しいこともいっぱいあった。将来、夫になる人とも出会えたし。もう一度、そう思う。心からの気持ちというよりは、「たぶん、これが正解」と国語のテストの選択肢から答えを選びとるように、そう思った。夫になる人とも出会えたし。
離婚するけど。
離婚はするが、過去に戻れたとしてもやはり宏明と結婚すると思う。そうしなければ、鈴音に会えなくなってしまうから。
結婚以前の宏明は自称「子ども好き」だった。朱音は昔から子どもが苦手で、「子育てって楽しいに決まってるよ」と楽観的な宏明の説得に負けたかっこうで、子どもをつくることを決めた。
鈴音が生まれたのち、宏明は「子どもがこんなに手がかかるものだとは」と言うようになり、反対に朱音は日に日に「子どもがこんなにかわいいとは」という思いを強くしていった。宏明が好きだったのは「子ども」ではなく、「かわいくて機嫌の良い子どもとごく短時間だけ接すること」だ。その発見は離婚の直接原因ではなかったが、朱音の心をしぼませたことには違いなかった。
「そろそろおうちに入ろうか。鈴音、パパにバイバイして」

鈴音を立ち上がらせ、ズボンの膝についた砂を払う。鈴音はとくに