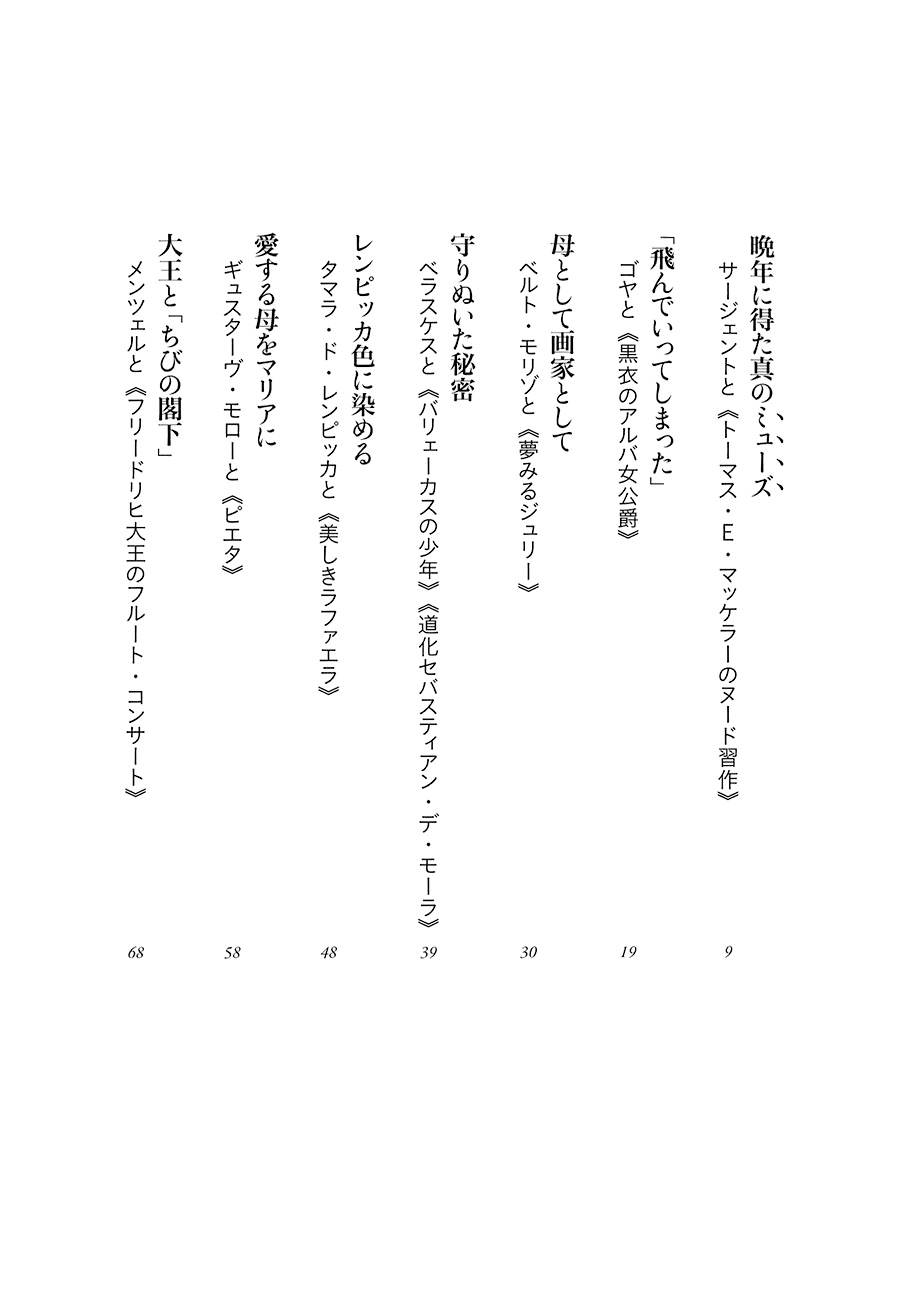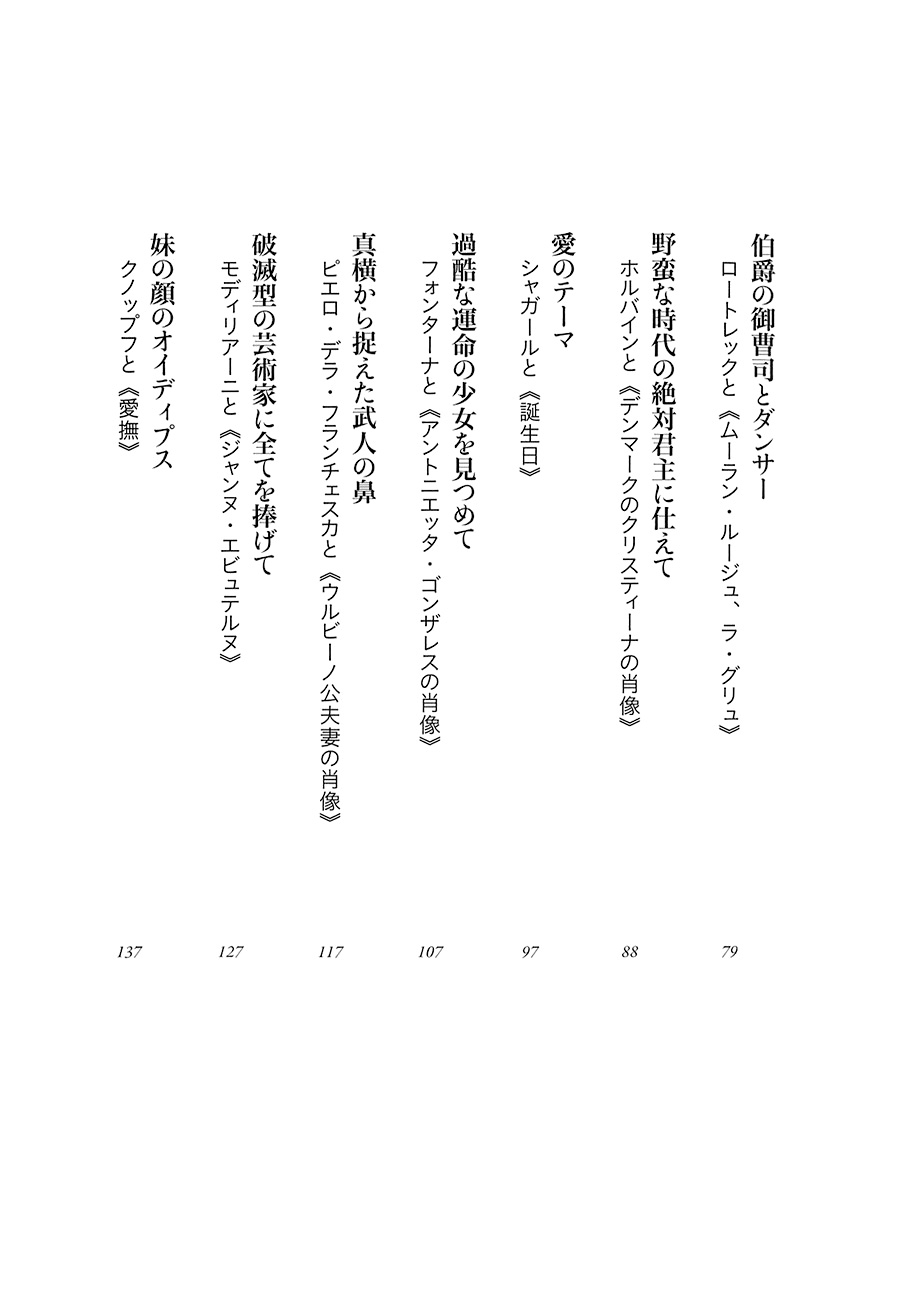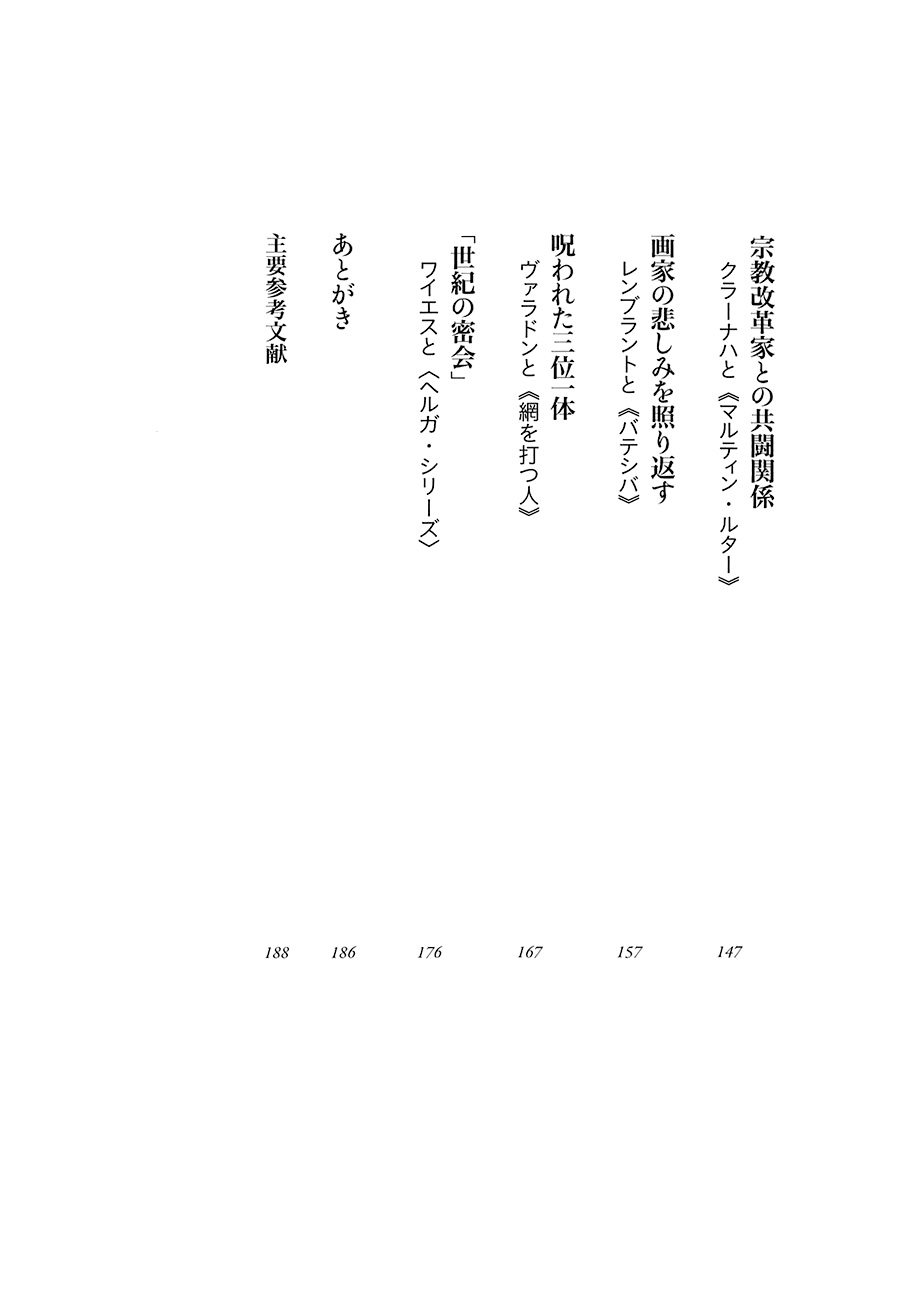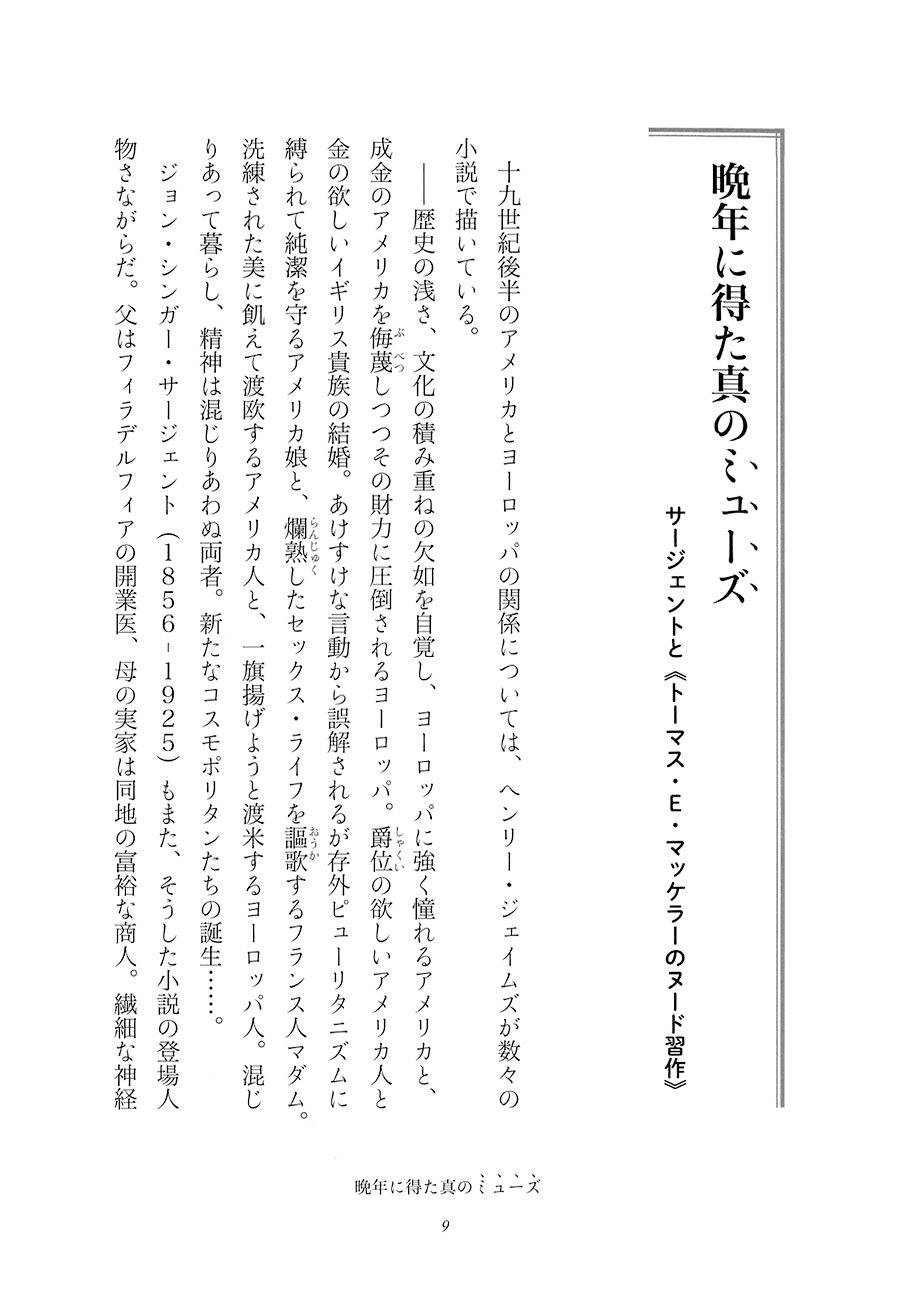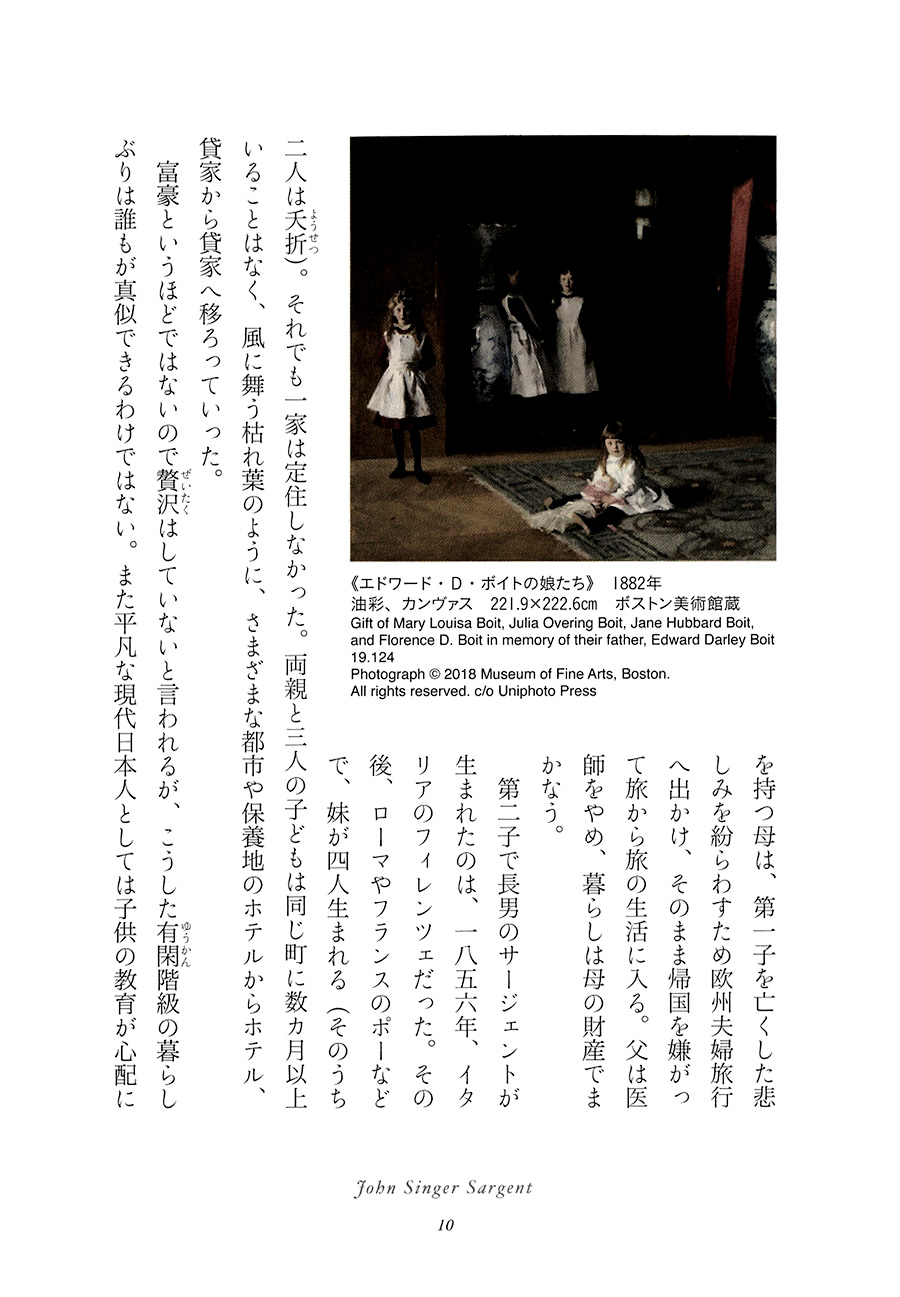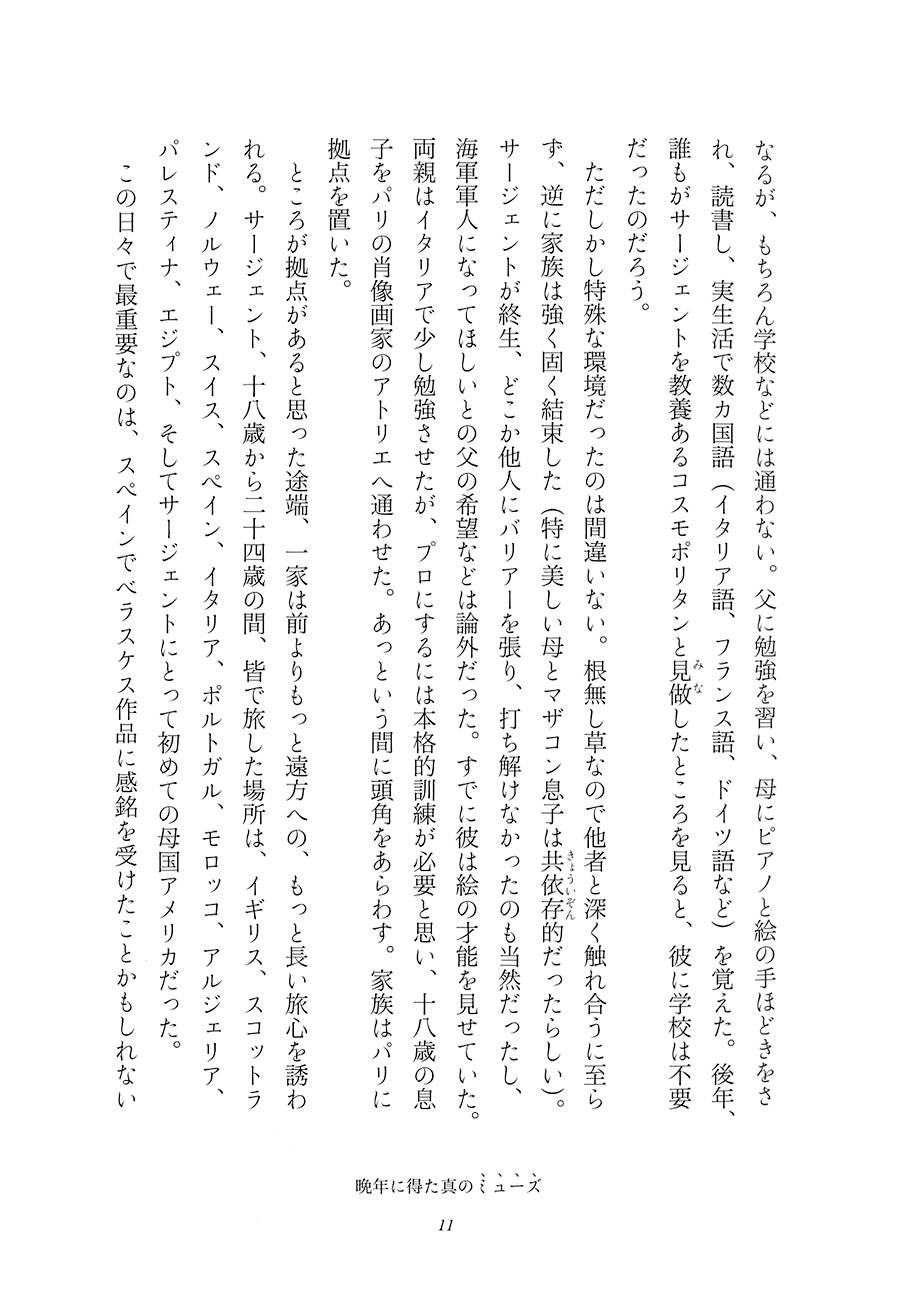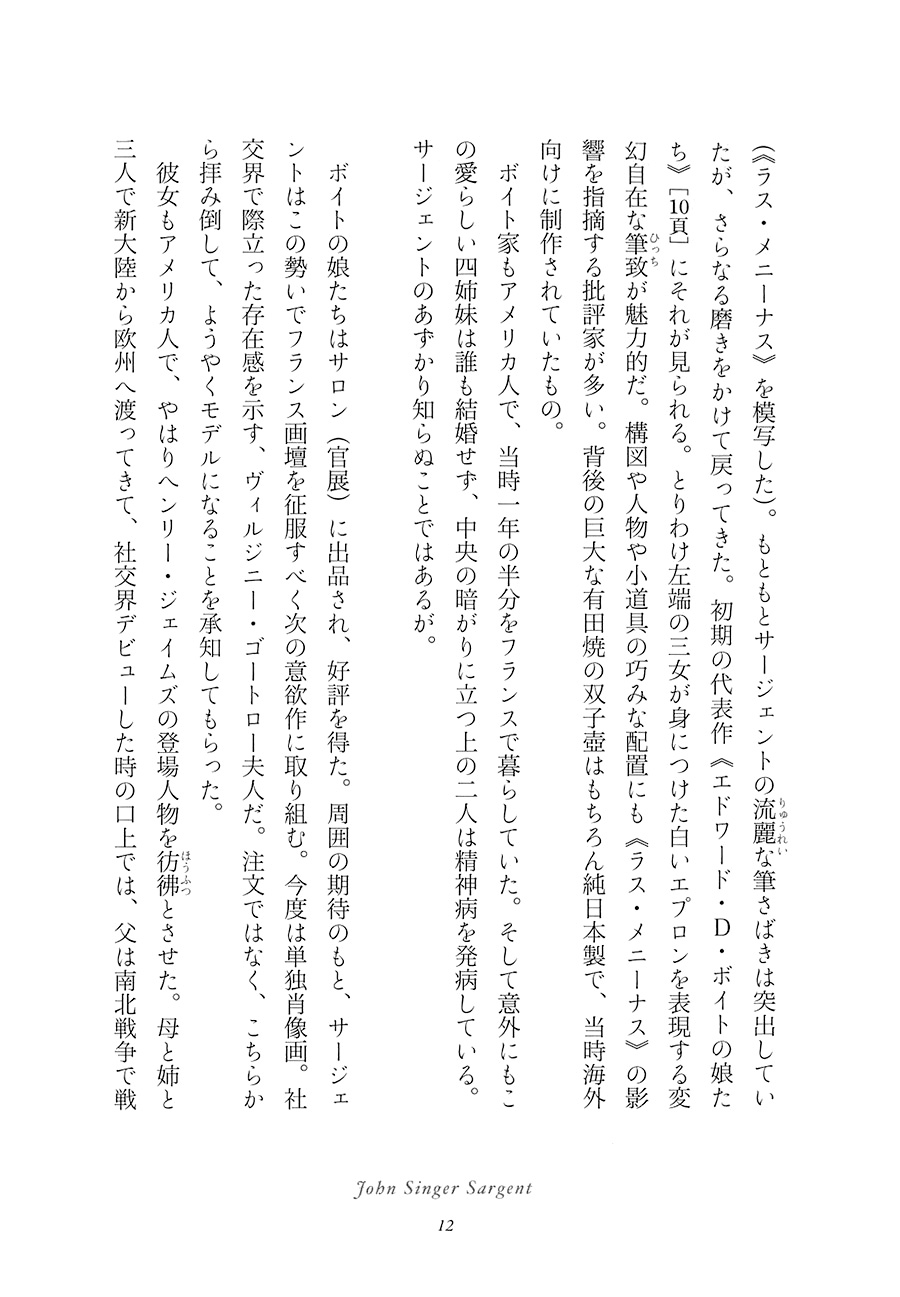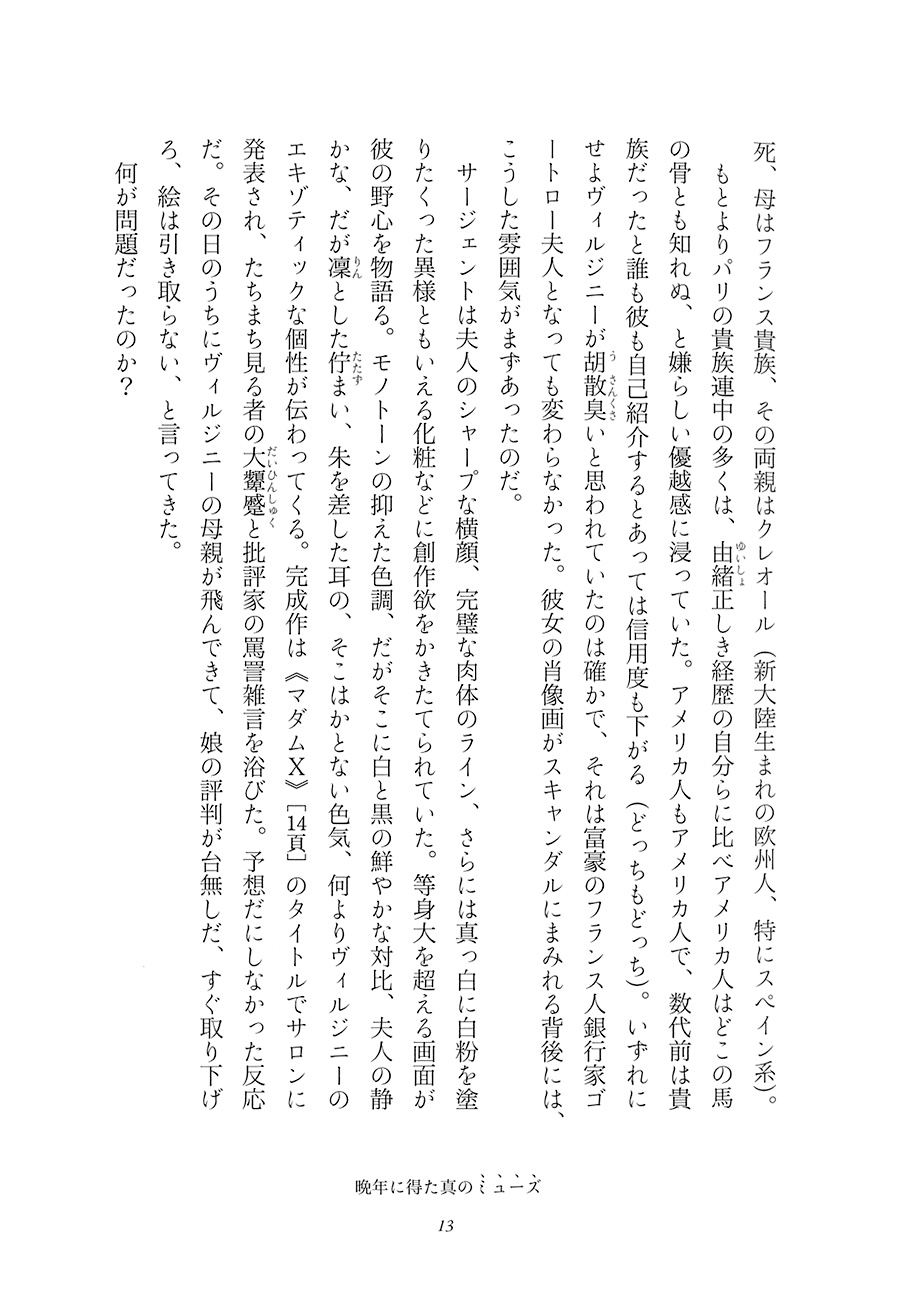特別試し読み 1

「飛んでいってしまった」
ゴヤと《黒衣のアルバ女公爵》
フランシスコ・デ・ゴヤ(1746–1828)がアルバ公爵家と親密になったのは、一七九五年、四十九歳の時だ。公爵邸に滞在し、対になる夫妻の肖像画を描きあげるよう、依頼を受けた。
この前後七、八年は、ゴヤの心身に烈風がまともに吹きつけた時期である。良きことも悪しきことも、幸も不幸も、歓喜も苦痛も、最大風速で襲ってきた。やがてそれが画業に大きく影響したのは言うまでもない。
ゴヤは同じスペイン出身のベラスケスやピカソと違い、早熟の天才ではなかった。世に出るのは遅く、出世の階段を上るテンポも遅く、王付き画家に任命されたのは四十歳だ(ベラスケスは二十四歳)。とはいえその頃にはもう王侯貴族や富裕層の人気肖像画家として多忙を極め、これ以上は誰もぼくのことなど思い出さないでほしい、と得意気に友人へ手紙を書いている。
頑健さを誇って働きづめに働き、猛烈な出世主義者ゆえに宮廷内闘争のストレスも加わったのだろう、疲労の積み重ねは予想以上に大きかったらしい。念願の宮廷画家の地位についてから三年後の四十六歳、旅先のアンダルシア(スペイン南部)で原因不明の病に倒れる。高熱、頭痛、平衡感覚麻痺……もう助かるまい、と一時は周囲も諦めたほどだ(病因は脳梅毒、鉛中毒、急性中枢神経系感染症など各説あるものの、未だ確定されていない)。
半年にわたる闘病の末、辛くもゴヤはこの世に留め置かれた。代償は聴覚の完全喪失。北欧神話の主神オーディンが、知恵の泉の水を飲むため片目を差し出したように、ゴヤは耳を差し出して全身これ透徹した眼の人と化す。全聾を受け入れるまでには、もちろん身を苛むほどの恐怖と煩悶があった。
宮廷に復帰した無音の住人は、だが職を解かれるどころか、アカデミー絵画教授の座まで得る。熱望していた画壇のトップ、首席宮廷画家の地位までは数年待たねばならないが、その前にまず、アルバ女公爵マリア・デル・ピラール・テレサ・カイエターナ・デ・シルバ・イ・アルバレス・デ・トレド(通称カイエターナ)との思いがけない交流が人生を輝かせた。
アルバ家はスペインの封建大貴族、それも名門中の名門だ(現在も続いている)。王族の前で帽子を脱ぐ必要のない「グランデ」という特権階級でもある。先祖には十字軍で名を馳せた武将を何人も輩出し、初代アルバ公の叙勲は一四二九年に遡る。
歴代もっとも有名なアルバ公は、三代目フェルナンド・アルバレス・デ・トレド。スペインを「陽の沈まぬ国」に押し上げたハプスブルク家出身のカール五世とフェリペ二世に仕えた。ただしこの三代目アルバ公が人々に記憶されたのは、「情け知らず」との悪評による。独立運動阻止の任務を帯びてネーデルラント総督として赴任し、おおぜいのプロテスタントを「血の審判所」と呼ばれた異端審問会にかけ、いともやすやすと処刑していったのだ。
犠牲者の中に、エフモント伯という貴族もいた。音楽好きはすぐピンときただろう。オランダ語のエフモントはドイツ語ではエグモント。ゲーテがこの高潔な英雄の自己犠牲を讃えた戯曲を書き、後にベートーヴェンが曲をつけた。苦難を経て救済へという『エグモント序曲』はコンサートの定番である。
ちなみにブリューゲル最晩年作《絞首台の上のかささぎ》も、ブリュッセルでのエフモント伯斬首がきっかけで制作されたと言われる(筆者もそう思う)。いろいろなことが網の目状に関連している。
さて、美女カイエターナ[21頁]は、そうした先祖を持つ十三代目のアルバ家当主だ。八歳で父公を亡くし、一人っ子のためアルバ公爵位を継いだ。夫のアルバ公は入り婿のようなものだから、彼女は公爵夫人ではなく、アルバ女公爵である。
代々積み上げ(簒奪し)てきた資産はうなるほどのもので、スペインを縦断するのに自領のみを通って行けたという。王宮と同規模のブエナビスタ宮殿(現陸軍司令部所有)やリリア宮殿、及びいくつもの別邸、田舎の別荘などを持ち、膨大な美術コレクションには、ベラスケスの《鏡のヴィーナス》も含まれていた(ベラスケスを心の師匠としたゴヤも見せてもらったろう)。階級が全てのこの時代、古い家柄を誇るアルバ家にとって、フランスからスペインへ横滑りしてきてまだ百年もたたないブルボン王家など、財産一つとっても何ほどのこともない。自由奔放なカイエターナは、ことあるごとにカルロス四世妃マリア・ルイサを小馬鹿にして反感を買った。
こうした対立には、それぞれ応援団がつくものだ。言語、作法、ファッションと、何から何までフランス風をきどるスペイン貴族は王家に、一方、生粋のスペイン文化復権を求め、よそ者たる王族を嫌うマハやマホら(スペイン版江戸っ子のようなもの)はアルバ女公爵に、熱い声援を送っていた(かつてのハプスブルク家と違い、ブルボン家はスペイン文化を頭から否定してフランス式を強引に押し付けたので民衆の反感が強かった)。
ゴヤは宮廷画家なので王家やその一派の肖像を多く描いてきたが、画家としての自由を制限されるものではない。先述したようにアルバ邸へ招かれ、しばし滞在して公爵夫妻それぞれの単独肖像を描いた。音楽愛好家で物静かな公爵はハイドンの楽譜を持った姿で室内に、闘牛好きで陽気な激情家の女公爵は豊かで真黒で長い縮れ毛と白いドレス姿で屋外に立つ。どちらの絵もゴヤとしては平凡な仕上がりである。
急展開はこの翌年。
公爵が病死した。三十三歳のカイエターナは子どものないまま寡婦となる。結婚生活は二十年ほどだが、もともと政略結婚で愛もない。喪に服すのが嫌だったのか、アンダルシアのサンルーカルにある別荘にこもり、五十歳のゴヤを呼びつけた。
招かれた画家は有頂天だったに違いない。田舎出の貧しい生い立ちを何とか粉飾しようと家系図に細工し、母方は下級貴族ということにしたゴヤだ。生まれながらのお姫様への憧れが抜きがたくある。しかも美しく魅力的で、スペイン女の典型たる火のような情熱の相手だ。お眼鏡にかなった喜びは、マゾヒスティックであれ何であれ望外と言えた。マドリッドから五百キロも離れたその別荘へ、ゴヤはすぐさま馳せ参じた。

好色で知られる画家と奔放で有名な大貴族は、数カ月をいっしょに過ごす。その間ゴヤはほぼ女性ばかりを走り描きした画帳を残し(「サンルーカル素描帖」[25頁])、短いが至福の時が流れていたことを示している。画帳の中のカイエターナは、癇癪玉を破裂させて髪をかきむしったり、女中頭に食ってかかり、逆に十字架を突きつけられている。スカートをめくりあげて裸の尻を向けているのも彼女だろうか、それはわからない。
再び《黒衣のアルバ女公爵》にもどろう。背景にアンダルシアの広々とした湿地が拡がるので、本作はこの時期にスケッチされたとわかる。ただし完成は翌一七九七年、マドリッドのゴヤのアトリエだ。はからずも苦い思い出の記録となった。
アルバ女公爵の黒衣は喪服ではない。みっしり黒い小花飾りを編み込んだ黒いスカート(みごとな描写)、黒いレースのマンティーリャをかぶり、茶色の胴衣は金糸で密に彩られ、真っ赤なサッシュが腰を締めるとともに画面全体をも引き締める。先細のハイヒールを履いた足は、バレエのポーズのような九十度の角度をとる。
顔は完全な卵型で、鼻筋が通り、黒々とした長い眉が特徴的だ。「スペインの新たなヴィーナス」と讃えられた美貌だが、現代日本人には必ずしもそう感じられないかもしれない。美貌の定義は時代と国でかなり違う。それは化粧にも言えることで、ロココを引きずった濃い頬紅はまだしも、当時の流行だった絹製の大きな付け黒子(右眉の先)の奇妙さに驚く。
肝心なのは絵に隠されたメッセージのほうだ。カイエターナは右手の人差し指と中指に指輪をはめており、象嵌された文字は「Goya(ゴヤ)」と「Alba(アルバ)」。さらに彼女の指さす足元の土の上には「Solo Goya(ゴヤひとり、ゴヤだけを)」という文字が、鑑賞者ではなくカイエターナの向きから読めるように記されている。しかも「Solo Goya」の「Solo(=only)」の文字は近年の画面洗浄で初めて浮かび出たのであり、同時代人には気づかれぬようゴヤ本人が薄く塗りつぶしたのは明らかだ。何よりこの作品はアルバ家所蔵ではなく、ゴヤが自分の家に秘匿していたのだった!
最初に構想した時、ゴヤは画家とモデルの熱い交感を伝えようとしたはずだ。だがそうはならなかった。画面全体から受ける印象は決して幸せなものではない。それはどこからくるのだろう? 眼だ。ゴヤに向けた彼女のまなざし。何も訴えかけてこない。かつてあった思いが失われ、今は無関心という残酷な現実があるばかり。そうだ。幸せな絵になるはずがない。なぜならゴヤの老いらくの恋は終わり、その終わりを受け入れた後に完成されたのだから。
ゴヤはリアリズムを追求し、カイエターナの自分への関心喪失という真実を描ききった。だがそれだけではあまりに切なすぎる。せめて指輪と「Solo Goya」を願望として描き込んだ……そんな気がする。

二人の関係がどこまでのものだったか、さまざまに想像されている。いまだ階級制を重んじる評論家に言わせれば、たかが画家ごときと愛だの恋だのは論外だと言う。カイエターナは王侯貴族が皆やっていたように、知恵遅れの少年やら黒人の幼女を「飼って」おり、聾のゴヤもその仲間だったと。
当時の大貴族の残酷さと非情を思えば、あり得ないことではない。しかしまた当時の大貴族の性的放縦を鑑みれば、身分など無関係の愛の形があったとして何の不思議があろう?
ゴヤはマドリッドの妻のもとへもどった。何度も妊娠出産しながら一人息子しか残せなかった、地味で存在感のない妻のもとへ。そしてこの絵を密かに完成させ、さらに銅版画集『ロス・カプリチョス(気まぐれ)』に取り組んで、そこにもカイエターナを登場させた。No.61の《飛んでいってしまった(彼女は飛び去った)》[28頁]がそれだ。例の特徴ある眉と黒いスカート、髪には蝶々を飾ったアルバ女公爵が、三人の醜い魔女の背中に乗り、黒いマンティーリャを翼のように拡げて飛んでゆく。振り返りもせず、ゴヤのもとから去ってゆく。
そのままこの世からも飛んでいってしまったのは、《黒衣のアルバ女公爵》が描かれた五年後の一八〇二年、四十歳の時だった。あまりに突然の死だったため、王家に毒殺されたのではと噂された。「スペイン史上最悪の王妃」と異名をとったマリア・ルイサとの確執が年々凄じくなっていたのは確かで、亡くなる直前にはマドリッドを所払いさせられている。その際のカイエターナの様子を、王妃は愛人ゴドイに宛てて「骨と皮になってしまっていた」「焼けつくように癎をたててまるで気違いみたいだった」(堀田善衞訳)と意地悪く書き送っている。
カイエターナの死後ブエナビスタ宮殿は宰相ゴドイが所有した後、王家に接収され、子どもがいなかったのでアルバ公爵位は親戚の者に渡された。ゴヤはかつて愛した女性の墓碑をデザインしたという。
「『飛んでいってしまった』 ゴヤと《黒衣のアルバ女公爵》」 了
特別試し読み 2

妹の顔のオイディプス
クノップフと《愛撫》
ベルギーが国家として独立したのは驚くほど遅く、一八三一年。かつてフランドルに属し、スペイン、オーストリア、フランス、オランダから立て続けに占領された末の独立宣言だ。民族の混成により、フラマン語(オランダ語の一方言)、ドイツ語、フランス語と言語も混成となるが(「ベルギー語」は存在しない)、アントウェルペン(=アントワープ)などの商業都市には資本蓄積があり、南部は石炭や鉄といった天然資源に恵まれて、イギリスに次ぐ速さで産業革命を達成した。
フェルナン・クノップフ(1858–1921)は、国家建国五十周年を二十二歳の時に祝っている。先祖はウィーン貴族で、十六世紀にはポルトガルの王族とも婚姻関係を結んだという。ただしベルギーにおけるクノップフ家は、上流階級とはいえ貴族ではなかった。
父親はアウデナールデ州司法官を経て、ブリュージュ裁判所判事、最終的には首都ブリュッセル裁判所判事となった。クノップフは一歳から六歳までブリュージュで過ごしたが、この地で妹マルグリットが生まれたことで、特別の思い入れを持ち、後年、《見捨てられた街》をはじめとした不思議な魅力のブリュージュ風景を何点も描くことになる(拙著『怖い絵』参照)。
十七歳でクノップフはブリュッセル自由大学法学部に入学した。父親の希望に沿っただけだったのだろう、学業に興味を持てず、入学翌年に早くも退学し、美術アカデミーへ通う。十九歳で最初のパリ旅行、二十一歳の第三回目では数カ月も滞在して大いに刺激を受けた。
両親との関係は良好だった。父親は彼が四十一歳、母親は四十八歳の時に亡くなるが、それまでずっと同居し続けた。このあたり、クノップフより一世代前の、同じ象徴主義の、都市隠遁画家ギュスターヴ・モローとよく似ている。ただクノップフには弟と妹がいたし、生前はモローよりはるかに人気画家だった。貴族や富裕層からの肖像依頼が多く、また国内だけでなくロンドン、ミュンヘン、ウィーンなどの展覧会に出品し、クリムトら新進画家たちから熱狂的に迎えられている。
では人づきあいが良かったかと言えば、そうでもない。モローとは別の意味でひどく変わっていた。いや、一家全員がどこか他人を拒む雰囲気だったと言ったほうがいいようだ。自身、ブリュージュ時代の一家は孤立していて弟以外に遊び相手がいなかった、と書いている。謹厳な判事の家族であり、物静かで冷ややかで、血筋を誇るブルジョワ一家だった。傍からはプライドが高すぎると思われたかもしれない。
クノップフは長身ですらりとした体つきを終生維持した。小さな鋭い目と尖り気味の顎、冷笑的な口元、赤毛。ダンディーな英国紳士風の写真が残されており、実際にいつもきちんとした服装で礼儀正しく振舞っていたという。特段ハンサムだとか魅力的だったとの証言はない。
貴族趣味、芸術至上主義、秘密主義、神秘学への傾倒、俗世間に対する侮蔑、そして妹マルグリットへの偏愛が、クノップフという人間を形作っていた。少なくとも形作っていると思われていた。
六歳下のマルグリットが彼のミューズだった。そのイメージは――モデルが別人の場合でさえ――画面に繰り返し立ち現れる。スリムな姿態や強い目力、真っ直ぐな鼻筋と薄い唇が、兄妹の外見に共通した点だ。しかしマルグリットの顔の大きな特徴は、鰓の張った、四角く、がっしりした顎で、それはクノップフのやや女性的な細い顎の線とは対極にある。
女性的な部分を持つ兄と、男性的な部分を持つ妹……補完関係にあるのだろうか?
それについては後述するとして、まずは二十三歳のマルグリット像[139頁]を見てみよう。高襟の、体にフィットした白いドレスを身につけ左腕を後ろにまわして右腕をつかむ。背筋がのび、高貴さが増す。背後の扉は祭壇めいた効果をもたらし、彼女を聖女のごとくイコン化する。
この作品をクノップフは死ぬまで大切にし、自ら設計した奇妙な自邸の「青の間」の壁に飾り続けた。つまり亡くなるまで三十年以上、彼は本作とともにあったのだ。彼の死後、マルグリットが本作を手に入れ、自分の家に「青の間」に似た部屋をわざわざ作って飾ったという。テニスのラケットも置いたかどうかは不明だが。
なぜラケットかと言えば、クノップフは本肖像画のそばにラケットも飾っていたからで、それは大型パステル画《記憶》と結びついている。
薄明りの緑の野で、女性七人が当時の角型テニスラケットを手に思い思いのポーズで佇んでいる。互いに無関心で、誰も目を合わせない。左端に肖像画と同じ白いドレスのマルグリットがいる。彼女だけが帽子をかぶっておらず、ラケットも持っていない。
だがよく見ると、他の女性たちも皆、同じ顔だ。つまり全員マルグリットだ。クノップフは妹にさまざまな服を着せ、さまざまなポーズを指定して、何枚も写真に撮った。それから画面上で複数の彼女を合成したのだ。きっと兄妹にとって、その日のテニスが何らかの強烈な「記憶」として残っていたのだろう。他人にはそれがどんなものか、想像もつかない。だがその時には、翌年マルグリットが結婚して遠くリエージュへ引っ越すことが決まっていた。彼はかなり落ち込んだので、もしかするとそのこととラケットは何か関わりがあるのかもしれない。
クノップフはある意味、夢の世界の住人だったから、マルグリットにいろんな仮装をさせ、シチュエーションを説明して沈黙劇を演じさせた。彼女もまた嬉々としてその夢に入り込んだのだろう。二人は秘密を共有し、ささやくような声で数少ない言葉を交わし、妹は要求を直ちに理解し表情を作り、ポーズを決め、兄は見つめて見つめて彼女を自分のものとする。
結婚した後も(たぶん里帰りした際に)、二人が新たな夢を紡いだことがわかっている。黒魔術の巫女めいた黒っぽいヴェールをかぶったマルグリットが、クノップフの制作した眠りの神ヒュプノスの仮面(実はこの顔もマルグリット)に手を触れる《秘密》という作品がそれだ。《記憶》と同じように、先立って撮られた写真が残されている。このころ三十代後半になっていた実際のマルグリットは頰がたるみ、少し太って、老けた印象だ。ところが絵の中の彼女は若き日の夢の女のまま。画家は見たいものしか見なかったのだ。
すでにもうクノップフには別のお気に入りのモデルができていた。ただ彼女らもやはり顎の四角い顔立ちで、どこかマルグリットの面影を宿し、彼女の呪縛からは抜け出せなかったのがうかがえる。
他の世紀末画家と同じように、クノップフも人間と動物のハイブリッド型怪物スフィンクスに惹かれていた。彼の代表作《愛撫》[142〜143頁]は、オリジナル・タイトルを《芸術(愛撫、もしくはスフィンクス)》と言った。もちろんここにもマルグリットの顔。

細長の画面に、赤土が拡がる。父を殺し、母を娶るとの神託を受けた王子オイディプスが、一人旅の途上、出会った怪物がスフィンクスだ。彼はスフィンクスの謎かけ(「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足の動物は何?」)に、正しく「人間」と即答して怪物退治をするわけだが、クノップフが表現した怪物との出会いは異様だ。頬ずりする両性具有のアンドロギュノス(andro=男、gyne=女)的スフィンクス、困惑するオイディプス。彼はスフィンクスの死の誘惑に、揺れているのか。
スフィンクスは通常、女の顔と胸、そこから下が獅子という姿だが、チーターへと変更された。これに関してはクノップフ自ら、チーターは蛇に最も近い、なぜなら這いつくばって襲う動物だから、と言っている。ファム・ファタールを喚起させる蛇(=チーター)とスフィンクスを重ねたわけだが、しかしこの顔は「男性化したマルグリット」(「クノップフとマルグリットの合体」との説あり)になっている。しかも青年オイディプスの身体に載っているその顔は、「本来の性である女性マルグリット」なのだ。
こういう捻れた性の変換は自然界では赦されないと無意識に感じているからか、画面に死の気配が漂う。オイディプスが握る杖は、二匹の蛇が巻きつき、上部に翼のついたカドゥケウス、つまりヘルメスの杖だ。ヘルメスは神々の使者であると同時に、死者を冥界へ導く神でもある。補強するように、背後には墓地の木、糸杉が林立している。その横の石の建造物も霊廟を思わせる。
クノップフはこうしたややこしい作品を描くことで、妹への愛は自己愛でもあることを吐露したのだろうか。彼は男に生まれたが女性的な面をもち、妹は女に生まれたがその相貌に男性的な面をもっていた。自分たちはアンドロギュノスのように本来は二つで一つのものだったのに、その理想の形は二つに割られてしまった。そう感じていたのだろうか。
もしそう感じていたのなら、マルグリットも同じだったろう。でなければどうして彼の死後に「青の間」を再現して自らの肖像画を飾るだろうか。
クノップフは四十九歳で、二人の子のいる未亡人と結婚したが三年後には別れた。死も突然だった。秘密主義を貫いていたので病名もわからない。入院して手術を受け、急死したという。六十三歳。精魂込めて建てた彼の神殿たる邸宅は、十数年後に解体されてしまった。もう少し長生きしていれば、モローのように個人美術館にできたかもしれないのに惜しまれる。
「妹の顔のオイディプス クノップフと《愛撫》」 了
密かに紡がれた愛情、過酷な運命の少女への温かな眼差し。
名画に刻印された知られざる関係と画家の想いを読み解く!