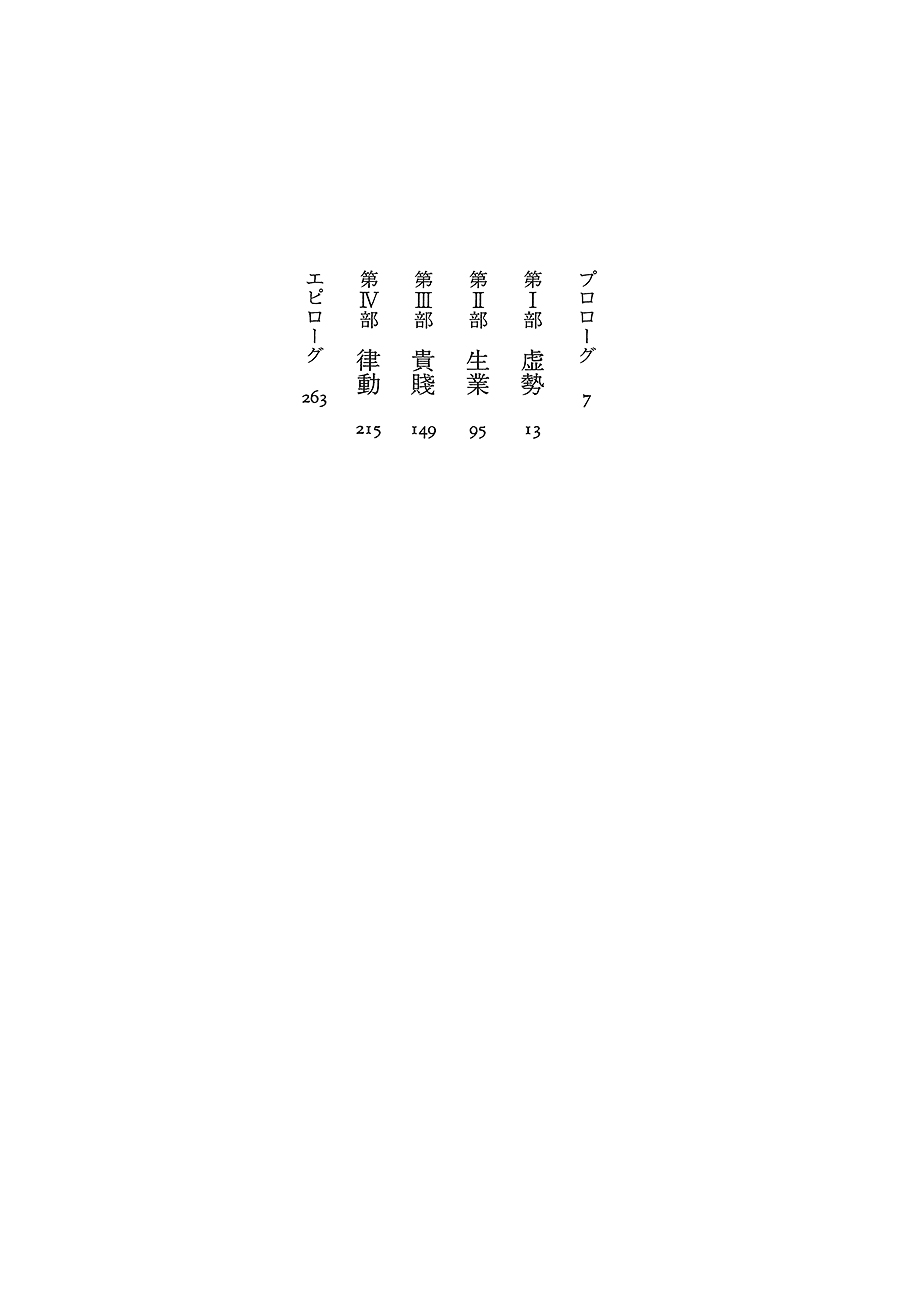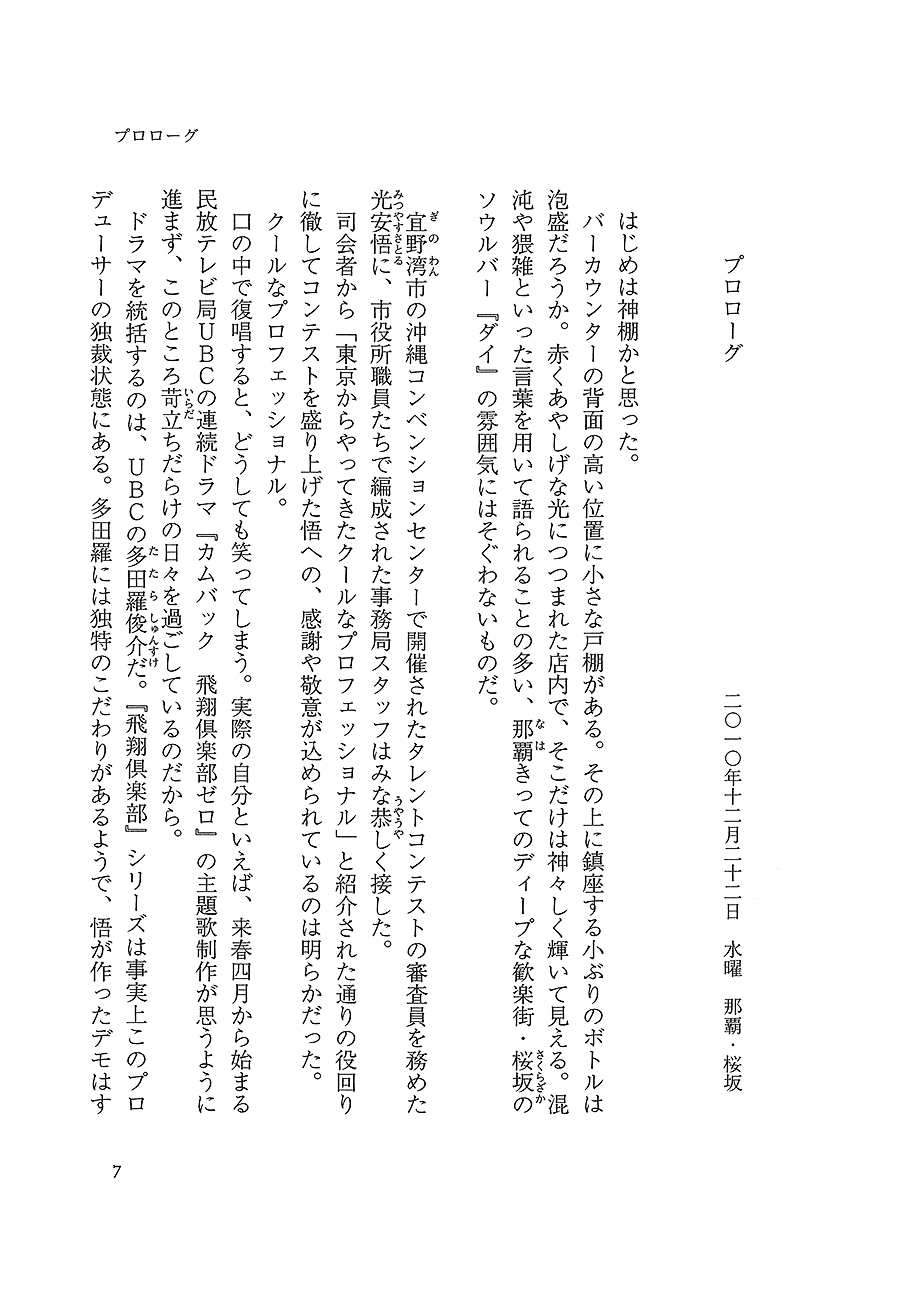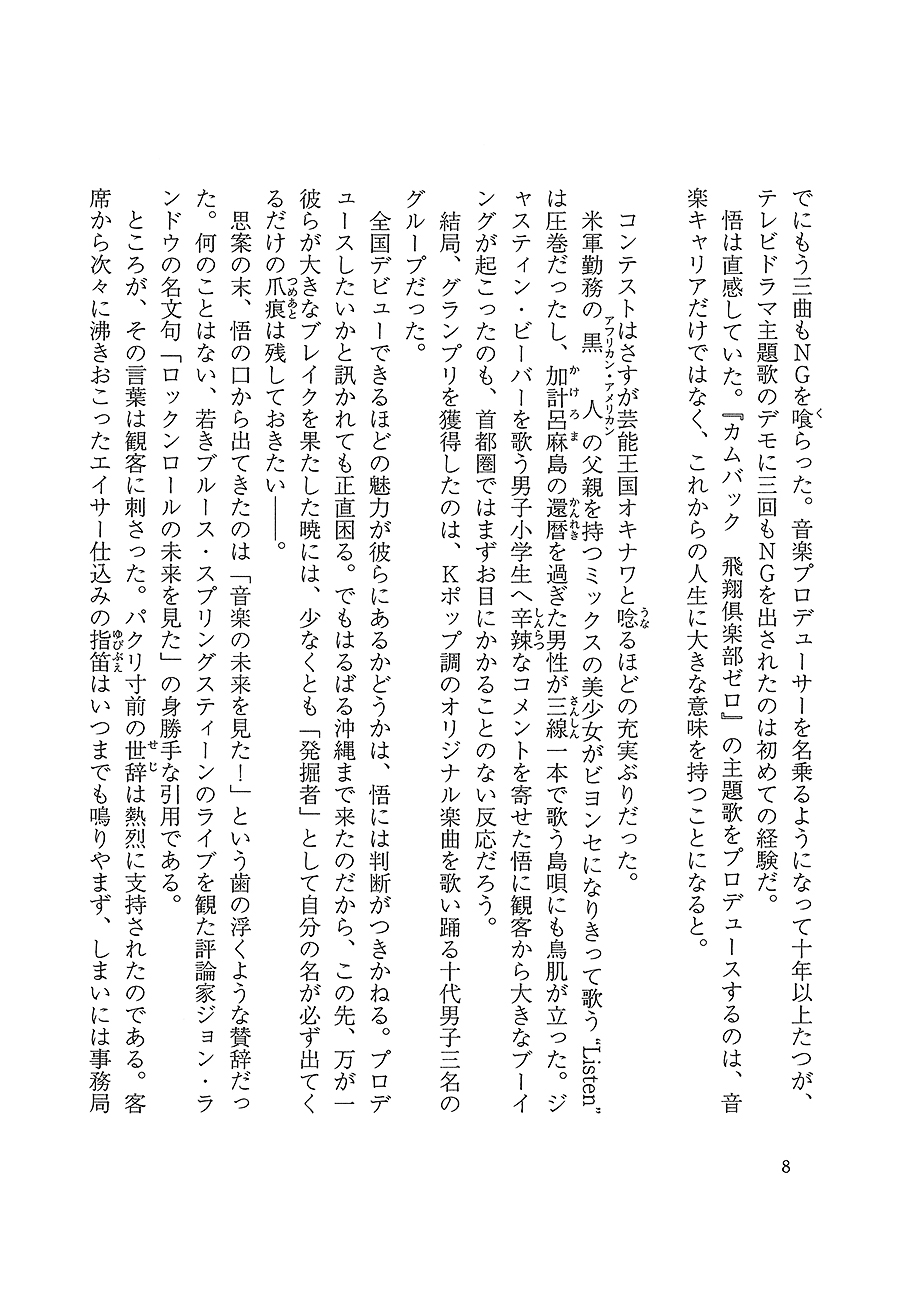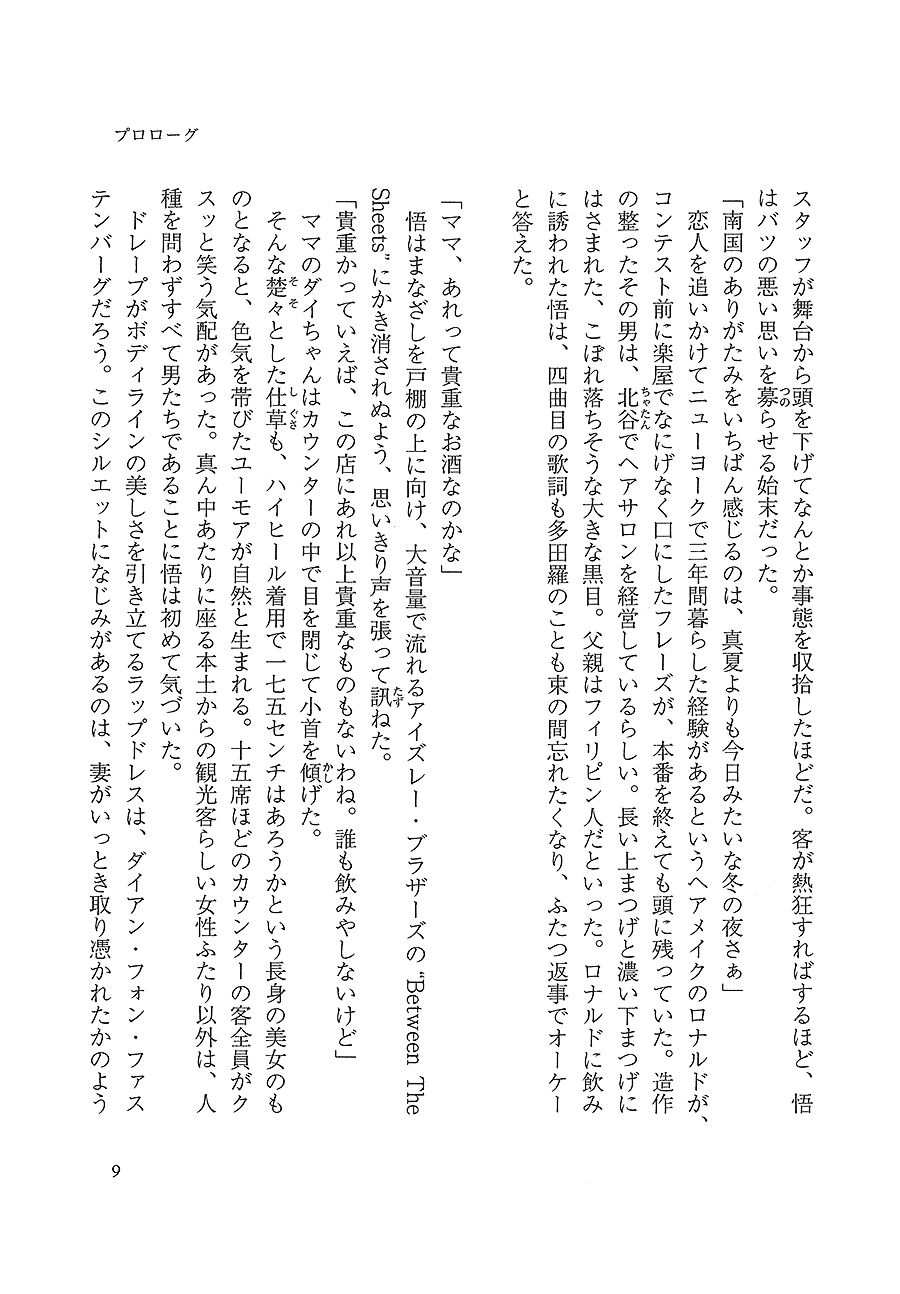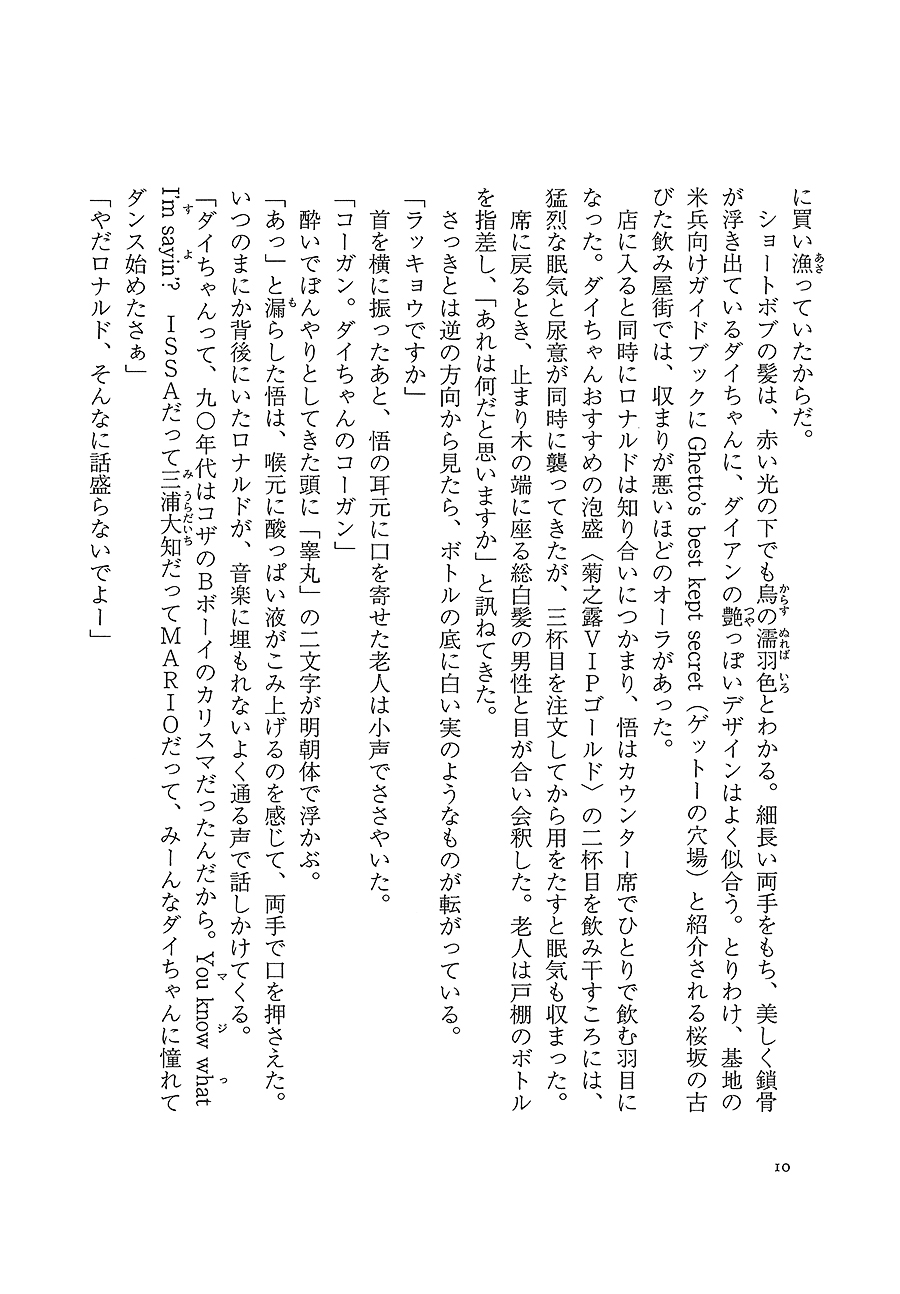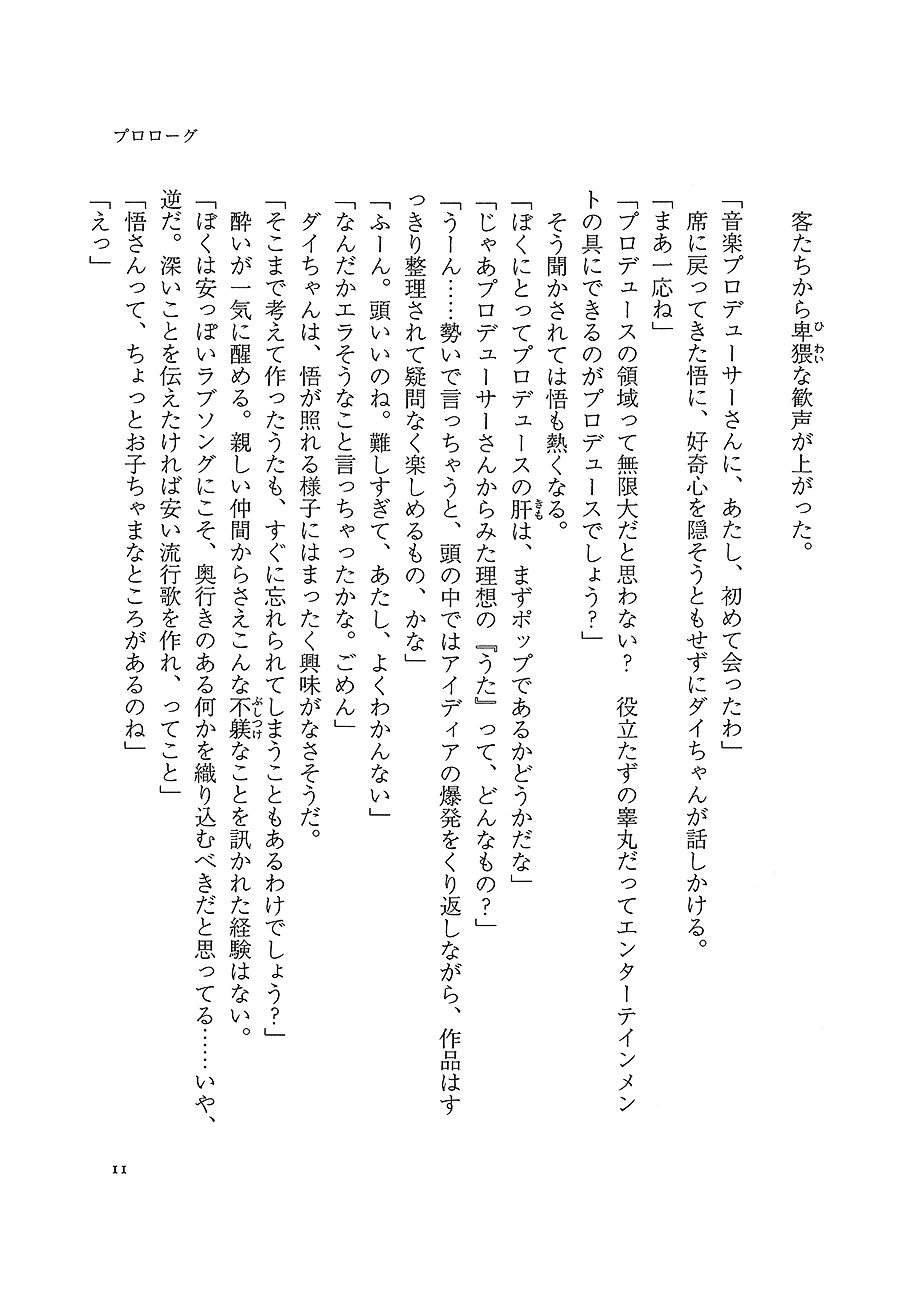プロローグ
二〇一〇年十二月二十二日 水曜 那覇・桜坂
はじめは神棚かと思った。
バーカウンターの背面の高い位置に小さな戸棚がある。その上に鎮座する小ぶりのボトルは泡盛だろうか。赤くあやしげな光につつまれた店内で、そこだけは神々しく輝いて見える。混沌や猥雑といった言葉を用いて語られることの多い、
司会者から「東京からやってきたクールなプロフェッショナル」と紹介された通りの役回りに徹してコンテストを盛り上げた悟への、感謝や敬意が込められているのは明らかだった。
クールなプロフェッショナル。
口の中で復唱すると、どうしても笑ってしまう。実際の自分といえば、来春四月から始まる民放テレビ局UBCの連続ドラマ『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』の主題歌制作が思うように進まず、このところ
ドラマを統括するのは、UBCの
悟は直感していた。『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』の主題歌をプロデュースするのは、音楽キャリアだけではなく、これからの人生に大きな意味を持つことになると。
コンテストはさすが芸能王国オキナワと
米軍勤務の
結局、グランプリを獲得したのは、Kポップ調のオリジナル楽曲を歌い踊る十代男子三名のグループだった。
全国デビューできるほどの魅力が彼らにあるかどうかは、悟には判断がつきかねる。プロデュースしたいかと訊かれても正直困る。でもはるばる沖縄まで来たのだから、この先、万が一彼らが大きなブレイクを果たした暁には、少なくとも「発掘者」として自分の名が必ず出てくるだけの
思案の末、悟の口から出てきたのは「音楽の未来を見た!」という歯の浮くような賛辞だった。何のことはない、若きブルース・スプリングスティーンのライブを観た評論家ジョン・ランドウの名文句「ロックンロールの未来を見た」の身勝手な引用である。
ところが、その言葉は観客に刺さった。パクリ寸前の
「南国のありがたみをいちばん感じるのは、真夏よりも今日みたいな冬の夜さぁ」
恋人を追いかけてニューヨークで三年間暮らした経験があるというヘアメイクのロナルドが、コンテスト前に楽屋でなにげなく口にしたフレーズが、本番を終えても頭に残っていた。造作の整ったその男は、
「ママ、あれって貴重なお酒なのかな」
悟はまなざしを戸棚の上に向け、大音量で流れるアイズレー・ブラザーズの“Between The Sheets”にかき消されぬよう、思いきり声を張って
「貴重かっていえば、この店にあれ以上貴重なものもないわね。誰も飲みやしないけど」
ママのダイちゃんはカウンターの中で目を閉じて小首を
そんな
ドレープがボディラインの美しさを引き立てるラップドレスは、ダイアン・フォン・ファステンバーグだろう。このシルエットになじみがあるのは、妻がいっとき取り憑かれたかのように買い
ショートボブの髪は、赤い光の下でも
店に入ると同時にロナルドは知り合いにつかまり、悟はカウンター席でひとりで飲む羽目になった。ダイちゃんおすすめの泡盛〈菊之露VIPゴールド〉の二杯目を飲み干すころには、猛烈な眠気と尿意が同時に襲ってきたが、三杯目を注文してから用をたすと眠気も収まった。
席に戻るとき、止まり木の端に座る総白髪の男性と目が合い会釈した。老人は戸棚のボトルを指差し、「あれは何だと思いますか」と訊ねてきた。
さっきとは逆の方向から見たら、ボトルの底に白い実のようなものが転がっている。
「ラッキョウですか」
首を横に振ったあと、悟の耳元に口を寄せた老人は小声でささやいた。
「コーガン。ダイちゃんのコーガン」
酔いでぼんやりとしてきた頭に「睾丸」の二文字が明朝体で浮かぶ。
「あっ」と
「ダイちゃんって、九〇年代はコザのBボーイのカリスマだったんだから。
「やだロナルド、そんなに話盛らないでよー」
客たちから
「音楽プロデューサーさんに、あたし、初めて会ったわ」
席に戻ってきた悟に、好奇心を隠そうともせずにダイちゃんが話しかける。
「まあ一応ね」
「プロデュースの領域って無限大だと思わない? 役立たずの睾丸だってエンターテインメントの具にできるのがプロデュースでしょう?」
そう聞かされては悟も熱くなる。
「ぼくにとってプロデュースの
「じゃあプロデューサーさんからみた理想の『うた』って、どんなもの?」
「うーん……勢いで言っちゃうと、頭の中ではアイディアの爆発をくり返しながら、作品はすっきり整理されて疑問なく楽しめるもの、かな」
「ふーん。頭いいのね。難しすぎて、あたし、よくわかんない」
「なんだかエラそうなこと言っちゃったかな。ごめん」
ダイちゃんは、悟が照れる様子にはまったく興味がなさそうだ。
「そこまで考えて作ったうたも、すぐに忘れられてしまうこともあるわけでしょう?」
酔いが一気に醒める。親しい仲間からさえこんな
「ぼくは安っぽいラブソングにこそ、奥行きのある何かを織り込むべきだと思ってる……いや、逆だ。深いことを伝えたければ安い流行歌を作れ、ってこと」
「悟さんって、ちょっとお子ちゃまなところがあるのね」
「えっ」
「おかしなものや場違いなものを見つけても、その場では口にしないのが大人でしょう。なのに悟さん、ぜーんぶ言葉で説明しようとしてるみたい」
「でも、炭鉱のカナリア的な機能だって必要だよ。声を上げなければ伝わらないことも多いのが、プロデュースの仕事なんだから」
疲れと酔いとダイちゃんへの緊張とで、やわらかい笑顔を作る余裕もない。悟の右目の周りの筋肉は
「ほーら、理屈っぽいのよ。あと、好きなものに対して潔癖すぎるんじゃない?」
「潔癖すぎる?」
「あたしもさんざん見てきたけど、潔癖性の人ほど不幸な人はいないって。不潔な世界にいるって嘆きながら一生を過ごすんだから。トイレに行って手も洗わないような人は、自分が不潔だなんてちっとも思ってない。こんな皮肉な話ってあると思う?」
さんざんな言われようだ。いっこうに収まらない右目周りの痙攣とあわせて、不愉快の虫が騒ぎ立てる。
「じゃあぼくが潔癖性だとしてだよ、それを治す特効薬はあるの?」
「さあどうでしょう。あたしは知らない」
そっけなく言い放ったダイちゃんは、女性ふたり客の追加注文を取り始めた。
言葉を失って、悟は気がついた。
水が飲みたい。無性に水が飲みたい──。
第I部 虚勢
第一章
二〇一一年三月九日 水曜 東京・鉢山町
喉が
洗面所に向かって歩いていたはずなのに、冷蔵庫の前にいる。扉に手を伸ばして、紙パックの牛乳を取りだす。
「ひと口ぶんしか残ってないなら、全部飲めばいいだろ。何度も言わせないでよ」
「あ、ごめーん」
テーブルから
たかが牛乳の話だ。朝の食卓につく前にここまでくどくど言う自分は、みっともないほど精神的な余裕が欠けている。わかっているけれど、言わずにはいられない。
渋谷区と目黒区の区境近くにある築二十年のビンテージマンションを購入して五年になる。
ローンも使わずにキャッシュで購入したことを旧友の公認会計士に言ったら、いちばん頭の悪いカネの使い途だとあきれられた。そんなことは百も承知だが、音楽人がそういうカネの使い方をしなくてどうする、と反発したい気持ちが悟にはいつもある。
入居にあたっては、紗和の理想をほぼ完璧にかなえる形でリノベーションを
アイランドキッチンをはさんだ先のソファに座る妻の紗和は、飲み残しの牛乳から始まった悟の小言を、iPadを手にずっと黙って聞いている。
自分が言葉を聞きたいときにかぎって紗和が口を開かないことが、最近とみに増えてきた。無言をつらぬくことで何かをアピールしているようにも感じられる。手先だけは動いているのが見えるから、夫の言葉は聞き流しているのかもしれない。
レコーディングスタジオでの作業は明け方にまでおよぶことが多い。結婚して九年、慣れっこのはずの紗和は、面と向かって悟に不平を言ったことはない。そのことに悟は心から感謝している。でも、徹夜明けの高揚感を共有できぬもどかしさを自分だけが抱えていることに気づくたび、夫婦も所詮は他人という
短い
注ぎ口を下の歯に当ててトントンと音をたてた。少しでも大きく聞こえるように。自分が身を削りながら音楽の仕事をして買った牛乳、その最後の一滴まで無駄にしてはならないと見せつけたい。
いつもなら悟に「朝ごはんは?」と訊ねる紗和だが、今朝はいっこうにその気配がない。どうやら自分は先にひとりで朝食を済ませたらしい。といっても手製のスムージーを飲んだだけだろう。iPadで読んでいるのは女友達とのメールかフェイスブックか。
結婚がきまったとき、紗和は悟にも家族にも相談することなく、すぐに退職届をしたためた。悟に事後報告する際に「だってほら、結婚と仕事の両立なんてあり得ないでしょう」とことも無げに言い添えた紗和が、「
生まれ育った仙台から結婚を機に上京してきた当初、東京に親しい友人がほとんどいなかった紗和の交友関係を大きく変えたのは、半年ほど経って通い始めた料理教室だった。悟と懇意の輸入車ディーラーの妻が紹介してくれた教室で、主宰者は長らくサンフランシスコで過ごした大手商社駐在員の妻である。帰国後に
教室に行くようになってからは、それまで縁もなかったグルテンフリーのファラフェルのような新しいメニューがテーブルに並ぶようになったし、夫には無理強いしないものの、紗和は一日に一度はローフードと呼ばれる非加熱食材の料理を口にしている。
料理だけではない。ファッションブランドやセレクトショップのファミリーセール招待にはじまり、ワインの試飲会、紹介制の高級洋菓子、高級マンションの新築計画、名門幼稚園の実態、ときには未公開株にいたるまで、いま紗和が持っている富裕層向けのさまざまな情報は、ほぼすべてこの教室のコミュニティを通して得たものである。特に気の合った生徒二名とは、ヨガのクラスにも一緒に通っているほどだ。
不必要な介入はしないと決めている悟だが、紗和が生徒仲間たちと毎日何かしらの連絡を取り合っていることを、苦々しく思うこともある。生徒仲間との付きあいの先に、大切な学びや有意義な時間があるようにはみえないのだ。とはいえ、自分が紹介したのである。まあ浮気しているわけでも散財しているわけでもないし、と考え直して心のバランスを取るのだが、炎が消えても
「大声だしてごめんね、紗和」
悟は極力やさしく言葉をかけた。だが自分がテーブルに着いても、真正面の紗和は生返事だけでiPadから顔を上げようとはしなかった。この無愛想な態度には我慢ならない。
「ちょっと、いいかげん、何か言ったらどう」
声を荒らげてしまった。無理して装ったやさしさの反動はいつも早い。だが紗和はさほど動じる気配もなく、ゆっくりと顔を上げた。堂々たるさまに
「悟さん、いまわたしの話を聞いてくれる?」
紗和は悟が拍子抜けするほど穏やかな笑みを浮かべ、やさしい声で言った。
「話って……」
会話をさえぎるように、悟の携帯電話がくぐもった振動音を発した。発信者の名前を確かめた悟は、紗和に聞こえるように「
電話をかけてきたのは、新ドラマ『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』の主題歌を歌う
十年前は音楽業界の頂点に君臨していた義人も、現在の位置づけを考えれば、メガヒットを記録したドラマ『飛翔倶楽部』の続編の主題歌を歌うのは、明らかに分不相応である。
裏を返せば、極上のタイアップ案件ともいえる。
ただ、これだけは言える。
この主題歌に義人はカムバックを賭けている。
ここ数ヶ月というもの、義人は毎日のように悟に電話かメールをよこしてくる。
そういうときに悟が心がけていることはただひとつ、いたずらに期待を抱かせるような内容を口にしないことだ。
「義人、ごめん。まだ反応が戻ってきてないんだ」
「そうですか。わかりました。オレに手伝えそうなことがあったら、どんなに小さいことでもいいんで、即教えてくださいよ」
「うん。わかってるって。ありがとう……あ、ごめん、キャッチ入っちゃった。じゃあここで切るから、またね」
キャッチホンは、UBC音楽出版、通称
「いつもお世話になっております。U音の澤口です。今、よろしかったでしょうか」
「はい」
「お取り込み中にすみません。一昨日いただいた新しいデモについて、お話しさせていただこうかと」
この種の連絡は、普段なら義人の所属レコード会社であるラッキーミュージックを介して悟のもとに届くようになっている。だが今日はその手順を
無理もないことだ。もう三月も上旬が終わろうとしているのに、主題歌がまだ決まっていない事態は、異常といっていい。
ましてやUBCの金看板である土曜夜十時からの名門ドラマ枠「サタジュウ」だ。今回のように四月スタートの場合、主題歌は遅くとも二月には仕上がっている。前年のうちに完成していることもめずらしくない。澤口が焦りを隠さないのも当然だろう。
『飛翔倶楽部』は、社会現象とまで言われた大ヒット作である。昭和二十三年に東大生によって起業された闇金融「光クラブ」をめぐる人間模様を描き、一昨年の春期にUBC開局以来最高の視聴率を記録した。人気に火がついたきっかけは、番組宣伝で使われた「世界よ、これがニッポンの実力だ」というコピーに、野党の四十代女性議員が
さえない俳優業から政界に転身して三期目の彼女は、金融犯罪集団を美化するものとしてこのコピーを問題視し、メディアのモラル欠如、またUBCの右傾化の象徴として国会で取り上げた。
メディアパフォーマンスであることは明らかだったが、ワイドショーのヒマネタとしてはちょうどよかったのだろう。ライバル局はこぞって彼女の国会発言を面白おかしく伝え、開始時十パーセント弱の視聴率は三週目にして一気に二十パーセント台まで上昇した。いったん上昇気流に乗った視聴率は、ストーリーが佳境に入った八週目以降は三十パーセント台を一度も割ることなく、最終話でついに四十四・四パーセントという異例の数字を叩き出したのだった。
続編『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』は、今春のテレビドラマ業界最大の話題だ。前作の視聴率が二十パーセントを超えたあたりから、続編が実現するかどうかに大きな注目が集まっていた。
主人公を演じる
マスコミがこの因縁に目をつけるなか、中里が「
ドラマ視聴の習慣がない悟は、『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』の主題歌プロデュースを依頼されるとすぐに、前シリーズ『飛翔倶楽部』全話のDVDを取り寄せた。類型的なギリシア悲劇に濃口醤油をジャブジャブふりかけたような安手の作劇術にうんざりしながらも、これも音楽プロデュース業務のうちと、何回もくり返し観た。
簡明な世界観や平面的な人物造形は、多田羅が視聴者の知性やリテラシーに一切の信頼を寄せていない証拠だと、悟には感じられた。一方で、そんな批判さえ百も承知と言わんばかりの
どんなにドラマのテーマやトーンに同意しかねるところがあっても、上質な主題歌を作ることで、何物にも代えがたい人生の
一昨日出したデモはすでに六曲目。神経を研ぎ澄ませて一ヶ月近くを費やした力作である。五年前にこの国で最も権威ある音楽賞とされる日本ミュージックアワードのグランプリを獲得し、悟の名声と評価を決定づけたストーリーテラーズのバラード「トゥルー・ロマンス」に、勝るとも劣らぬ強い手応えがあった。
だがドラマのプロデューサー多田羅は、またも首を縦に振らなかったらしい。
「私は今回はとりわけ大傑作だと思うんですけどねえ……UBCサイドがどこか違うって言うんですよ。今のまんまじゃドラマの絵も映えないし、歌詞のコトバも立っていないからぜんぜん入ってこないと。いや、あくまでドラマのトーンとのバランスって意味ですよ。個人的には光安さんプロデュースならではの珠玉のバラードだと思ってますから」
曲の不出来を責める澤口の
テレビ局系音楽出版会社の社員プロデューサーの業務は、悟のようなフリーランスの音楽プロデューサーと似て非なるものだ。とりわけ澤口の仕事は、UBCの番組や出資映画の主題歌や挿入歌の制作に特化している。
テレビドラマだと、番組プロデューサーと音楽家の中間でさまざまな調整を求められることが大半だ。もちろん音楽出版会社の社員プロデューサーにも、自発的なアイディアを次々に繰りだすタイプがいるにはいる。だが、ことドラマの音楽となると、ほとんどは番組プロデューサーの代弁者、いや伝令役であることも少なくない。理由はいたって単純。音楽出版会社はテレビ局の子会社だからである。ドラマの威光にすがりついてタイアップを欲しがるのは専ら音楽家のほう、という事情がそこに加わる。
テレビ局系音楽出版会社にとっては、ドラマの主題歌や挿入歌を新たに作ることで与えられる出版権で大きな利益を生みだすことが基本業務となる。この手順で作られた新曲は、ドラマで何度使おうとも著作権使用料は免除される。反対に、人気アーティストの既存曲をドラマに採用するとなると、楽曲権利者に
悟は語気を強めて訊ねる。
「
自分が声に出すことを避けてきた番組プロデューサーのフルネームを聞いた澤口が、あからさまに口ごもった。
去年十一月の第一回主題歌プレゼンテーションに、悟はデモを二曲提出した。タイトルはシンプルに「Comeback」とし、1と2のナンバリングを打った。いずれも義人が自ら
二曲ともかなりの完成度と断言できるもので、どちらが選ばれても驚かないほどの自信があった。先方から求められているのはあくまで主題歌一曲だが、残るもう一曲も挿入歌として採用を
ところが、多田羅は二曲の「Comeback」にOKを出さなかったどころか、どちらがいいとも、どちらが自分のイメージに近いとさえも答えなかった。悟が無理を言って転送させた澤口のメールには、権藤の「気を悪くしないでくださいよ」というメッセージとともに、多田羅の回答が記されていた。
二曲のデモを提出してきたところに、櫛田義人とスタッフのダメさ加減が象徴されている。これぞ自信作という決定的な一曲があれば、二曲も送ってくるなんて
腹が立った。多田羅がデモにNGを出してきたからではない。確かに残念ではあるが、それだけならばプロフェッショナル同士のやりとりとして、まだ受け止めることができる。
人気ドラマをプロデュースすることの
「うた」を作るには、すべてを出しきって、ほとんど捨てる。それでも残るものにこそ普遍的な価値がある。遠回りこそが王道だ。
だからこそ、自分に降りかかってくる無礼には全力で
「あ、ええ、ですから多田羅さんというより、UBCサイド全体の意向としてですね……」
澤口の
「あのね、澤口さん。ぼくは多田羅
「いや、何もってことは」
「じゃあそれもぼくに教えてくださいよ」
「……」
「要するに今回も多田羅PがNG出してるって理解で間違ってないですよね。よくわかりました」
「じつは今日、緊急ミーティングが」
「ほらやっぱり。多田羅Pも出席するんでしょう?」
「もちろんです」
そう話す澤口の語尾は消え入りそうに弱々しい。
「何時からですか」
「十四時からです」
「多田羅Pがぼくの参加をご希望なんですね」
「はい。いや、いいえ」
「どっちなんですか」
「おそらく希望してるんですが……ですから、UBCサイド全体の意向としてですね」
もうこれ以上この男と話しても
「わかりました。参加させていただきます。UBCに行けばいいですね」
「あ、はい。このあと詳細をメールで送ります。光安さんのお車の情報は以前に伺っておりますので、そのまま地下駐車場にいらしてください」
「スタジオに立ち寄るんで、十四時には少し遅れると思いますが、なる
電話を切った悟は、右の奥歯を強く噛みしめていることに気づいた。かかりつけの審美歯科医にいつも注意される悪い
自分が悪いんじゃない。仕事相手が悪すぎる。音楽のことなら自分がいちばん知っている。
「電話長くなっちゃってごめん」
紗和はさっきから
「それはいいの。悟さん、あのね」
とくだん責めるそぶりは感じられない。
「どうしたの?」
「お腹に赤ちゃんがいます」
言葉が出てこない。吸いつけられるように妻の顔を見る。
「お腹に赤ちゃんがいます」
「マジで」
悟はふだん滅多に使わない言葉を発している自分に羞恥を覚えた。
「マジです。やっとウチにも来てくれたみたい。うれしい?」
「うれしい、って?」
「……うれしくないの?」
「うれしい。うれしいよ。マジか。うれしいよ。超うれしい」
「大げさねえ……でも、うれしいって言ってくれて、わたしもうれしい」
「もう、牛乳パックはちゃんと捨ててよね」
どこまでも愉快という調子で悟を叱りつける。
「ま、今日は謝らなくていいけどね」
悟は両の手のひらを合わせた。温かさのなかにひんやりと湿った感覚があった。
第二章
二〇一一年三月九日 水曜 東京・鉢山町
リビングをつつみ込む香りで、紗和がコーヒーを
父親になる。この自分が父親になる。
幸せだ。幸せには違いない。
だが、心の視界は
その理由が、終わりの見えない主題歌制作であることは明らかだ。もし予定通り主題歌を作り終えたあとにこの吉報が届いたなら、どんなに晴れやかな気分が味わえたことだろう。
いや待てよ、それは
しかし──。
自分より確実に不幸な者を思い浮かべなければすんなりと受容できない「幸せ」なんて、本当の幸せと呼べるだろうか。
「朝ごはんは?」
「今日は大丈夫。このモカ、おいしかった。ごちそうさま」
コーヒーを飲み干した悟は、車のキーを手にして外に出た。
☆
オリガミ完全復活しましたね。たまにはパーコー麺どうですか。
レコード会社ラッキーミュージックの権藤雅樹から六年ぶりにメールが届いたのは、昨年十月下旬のことだ。
悟の心のうちに波が立った。だが、自分以外の誰も気づかない古い傷跡を
この十年の間に昇進を重ねた権藤は、今ではラッキーミュージックのナンバースリーの地位にいる。斜陽が叫ばれる音楽産業にあって、社内に自分の頭文字を
彼のサクセスストーリーの起点は、悟がプロデュースしたヴァイブ・トリックス、通称ヴァイブスというのはこの業界の常識である。A&R(エーアンドアール)と呼ばれる、制作と宣伝と販売促進を一手に担当する業務で権藤は名を上げた。
日本で最も多くのCDが売れたのは一九九八年である。その年をピークとして音楽市場が縮小傾向に入ってからリリースされたにもかかわらず、ヴァイブスが二〇〇一年に放ったデビューアルバム『ファースト・トリップ』は三百万枚を上回るセールスを記録、その年一番の大ヒットとなった。男性アーティストのデビューアルバムとして史上最高となるこの数字は、今後の音楽ソフトの行く末を考えてみれば、この先もまず塗り替えられることはない記録だろう。同様に、担当A&Rの権藤の名声が損なわれることもないはずだ。
アルバムのプロデューサーである自分の名声も、その数字の上に成り立っていることを、悟は自覚している。当時まだマニアックな存在だった悟に、アルバム丸ごとのプロデュースを託してくれたのは権藤だ。感謝の念を忘れたことはないが、この六年ただの一度も会っていないのには、それだけの理由がある。
その権藤が、たっての願いがあるという。待ち合わせに指定してきたのは、永田町にオープンしたばかりのザ・キャピトルホテル東急のダイニング『
ビートルズの一九六六年の初来日で宿泊先として選ばれたこと、あるいは人気絶頂時のマイケル・ジャクソンが愛猿バブルスと泊まったことでも知られるキャピトル東急は、音楽を生業にする者にとって特別の意味をもつ。深夜のオリガミで、ラーメンの上に
当時、オリガミの夜食によく付きあわせたのが権藤である。悟は自分のことは棚に上げて「睡眠不足だろ。
二〇〇六年にキャピトル東急ホテルが閉館したときには、すでに権藤とは縁遠くなっていた。その後赤坂見附の東急プラザで移転営業をしていたオリガミには、一度だけ行ったことがある。パーコー麺もナシゴレンもおいしかったが、店の雰囲気は別物で、場所も味のうちと痛感した悟の足は遠のいた。やはりオリガミは永田町でなければ。
権藤と再会を果たすには、今がよいタイミングなのかもしれない。その日の夜に、悟は早速会うことにした。
「店のレイアウト、すっかり変わっちゃいましたね」
久しぶりの再会なのに、権藤は目も合わさず挨拶の言葉もなく話し始めた。このそっけなさこそは照れの裏返しと思いあたると、悟の胸にはなつかしい感触がよみがえった。
「ここ
「隈研吾といえば、光安さん、去年できた新しい根津美術館はもう行きました? 庭園にカフェがあるんですけど、ランチで結構使えますよ。駐車場たいがい空いてるし。かわいい女の子も結構見かけます」
「相変わらずその手の情報に詳しいね。いくつになったんだっけ?」
「今年
権藤の口調に往時の軽薄なトーンが顔をのぞかせる。
パーコー麺とナシゴレンが運ばれてきた。
「ナシゴレンも頼んだっけ?」
「昔みたいに分けあいましょうよ」
ナシゴレンにのった目玉焼きをフォークとナイフを使って手際よく切りわける権藤を、悟はじっくり見つめた。六年の歳月なんて、あっという間だという気がしてくる。変わったのは体形と服の趣味くらいだろうか。
悟がヴァイブスをプロデュースしていたころ、権藤は太いデニムとティンバーランドのイエローブーツでスタジオに現れ、Bボーイの名残りを見せることがあった。神奈川のマンモス私大のダンスサークルで部長だったと聞いたことがある。
いまテーブルをはさんで目の前にいる四十男は、仕立ての良いエレガントなウールジャケットに身をつつんでいる。ピークドラペルのホールにフラワーをあしらったデザインは、昨年からセレクトショップでよく見かけるラルディーニだろう。社内でのポジションがめざましく上がったからといって、ハイブランドではなく、適度な現代性と高いコストパフォーマンスを両立した新しめのメーカーを選ぶあたりが、世知に
感傷を振りはらうように、悟はパーコー麺に手を伸ばした。スープを少し飲み、別添えの白ネギをたっぷり麺にのせる。権藤がなつかしそうに目を細める。
「そうだ、そうだった、光安さんってネギたっぷり派なんだよなあ」
呑気な反応にしびれを切らした悟は、たまらず本題を切りだした。
「で、権藤。たってのお願いって何だよ」
一瞬で笑みを消した権藤は、フォークとナイフを手に持ったまま訊きかえしてきた。
「光安さん、俺が去年社内に新しいレーベルを立ち上げたのはご存じですか」
「もちろん知ってるよ。Gストリートだろ。このご時世にすごいよなあ」
「光安さんのおかげです。けっしてお世辞じゃなく」
いつのまにか悟を
「また新人プロデュース?」
「違います。もっと大きな話です。『飛翔倶楽部』ってドラマ知ってますよね」
「そりゃあ知ってるよ」
「あのドラマの続編が春から始まるんです。その主題歌を……」
「ちょっと待って。誰が歌うんだよ。失礼な言い方になっちゃうけど、そんな大きなタイアップつけて歌う大物ってGストリートにいる? 新人ばかりじゃなかったっけ」
「じつは、このタイミングでGストリートに社内移籍するんです」
悟は自分の顔がにわかに火照り始めたのを感じる。激しくなる心臓の鼓動が権藤に聞こえはしないかと恐れながら、精いっぱい平静を装って訊ねる。
「誰だよ。権藤、まさか……」
「そのまさかです。櫛田義人です」
シンガーソングライター、櫛田義人。
ヴァイブ・トリックスの元メンバーである。悟にとっては今でもYOSHITOという表記がしっくりくる。ヴァイブスがデビューして三年後、人気絶頂時にグループ活動休止を発表してからはソロに転じて成功を収めた。
ヴァイブスは友情ありきで結成されたグループではない。帝都テレビの番組『スターサーチン』でボーイシンガー・オーディションの審査員だった悟が、最終審査に残った応募者四人のうち、敗者となった三人を束ねてデビューさせたR&Bボーカルトリオである。
審査員長は、「ミスターJポップ」と称される人気音楽プロデューサー
しかし、それこそが新たなサクセスストーリーの始まりとなった。本人いわく「最後の一手で」プロデュース業に転身した島崎と、「やむを得ず」彼の個人事務所の社長におさまったXYZのドラマー
吉野が見つけてきた歌手志望の
ぶっきらぼうに権藤が言う。
「まあ義人もピークは過ぎてるし、いまさら失敗しても失うものは何もないですから」
「何もない?」
「ええ。だから光安さんにご迷惑かけることもないんじゃないかと」
「やめてくんないかな、そんな言い方」
「すみません、生まれつき言葉が足りないもんで」
「歌手にとって傷を伴わない失敗なんてないよ。この歳になったら、たとえまわり道に見えたことにも意味があったと思わないか」
「まあ、おっしゃることはわかりますよ」
「この世に『無意味』ってものはない」
「
あのとき、自分は櫛田義人の発したある言葉にすさまじく
「エラそうなこと言える立場じゃないけど、ぼくだから言えることもある」
「なんですか」
悟は問いには答えず、権藤をまじまじと見つめかえした。目が慣れてきたせいか、いくぶん後退した生え際、やけに乾いた質感の頬骨付近、そして首との境目が
「やるよ。櫛田義人、やる」
権藤が両目を大きく見開いたのを確かめて、悟は言葉を続けた。
「やる前に、ひとつだけはっきり言っておきたい。これに失敗したら、すべてを失う」
「すべてを失うって、いくらなんでも、大げさじゃないですか」
にこりともしない悟に、権藤は茶化した口調をすぐに整えた。
「いや、それだけの大きなチャンスだよ、これは。少なくとも義人にはそう自覚してほしい。まあぼくに言われなくても、さすがに思ってるか」
「だといいんですけどね、あのバカ」
きつい言葉を放つのは、歌い手と近い距離をずっと維持してきた社員A&Rの自負からだろう。この男のプライドは自分とは違うかたちをしている。
「ぼくもその覚悟でやるよ」
「俺も言っておかなきゃいけないことがあるんですが」
「……なんだよ」
会話の主導権を奪われて不機嫌を
「ドラマのプロデューサーっていうのがちょっと
「厄介? そんなの関係あるもんか。音楽の力でねじ伏せてやるよ」
「言いましたね。戦線離脱も泣き言もなしって約束ですよ」
「そっちこそ、ぼくが作る義人の歌で泣くんじゃないぞ」
しばらく悟を注視していた権藤は、何かを観念するように息を長く
「光安さん、最近俺よく思うんっすよ。日本人って音楽聴かない民族だなって」
「大発見みたいに言うなよ、今ごろ。音楽なんて別に必要ないって連中だらけなことくらい、音楽を仕事にする前から知ってただろ。映画や絵画とおんなじだ」
「ま、そりゃそうなんですけど」
権藤もまた久しぶりの再会に感傷的になっているのかもしれない。
「人は音楽でお腹が
「いや、悪いなんて言ってません。すみません、余計なこと言いました。忘れてください。パーコー麺、いま食べるとかなりヘビーっすね」
「年相応だよ。若いころは食べ過ぎてただけ。音楽もね」
感傷過多なのは自分のほうか。悟はテーブルに両肘をつき、手を組み合わせた。
だが権藤は気にするふうでもなく、丼を抱え上げたかと思うと、「俺も歳くったな……今夜は特別だし、ま、いっか」とつぶやき、たっぷり残ったスープをひと息に飲み干した。
第三章
二〇一一年三月九日 水曜 東京・駒場
悟が代表をつとめる『有限会社 東京光安製作所』は、妻の紗和を形ばかりの社員に据えた夫婦だけの会社にすぎない。経営者としてただひとつだけ掲げる目標は、「光安悟」の単価を上げること。それ以外にはない。
若いアシスタントを
だから事務所の
車の運転は嫌いではない。二十代でカラダに染みついてしまった。そのころ出張を重ねたロサンゼルスやアトランタといったアメリカの都市では、空港に着いてまずレンタカーを借りないことには仕事が始まらなかったという事情もある。
社用車のトヨタ・プリウスのほかにも、個人名義の車を持っている。一九六八年製のジャガー420Gだ。七年前、ヴァイブスの仕事に自ら終止符を打ってラッキーミュージックの会議室を飛びだした三十分後に、駒沢通り沿いの中古車屋で衝動買いした。ビンテージカー愛好者の間で有名なその店の前を通るたびにいつも気になっていた、自分の生まれ年製の車だった。
ボディカラーは黒だ。それは
420Gが
重い防音扉を開き、調光スイッチをオンにし、エアコンやコンピュータに電源を入れる。アーロンチェアに腰をおろした悟は、
クラブミュージックのクリエイターに強く支持されるフィンランドのスピーカー、ジェネレックの小さなランプが、通電状態をしめす緑色の光を
自宅ほどではないがこの
その最上階、三階の南西角にミツスタはある。主にヴァイブスのヒット曲で得た印税で3LDKの物件を購入したのが七年前。ゆっくり一年間を費やして空間に手を加え、仕切り壁を取りはらい、ミツスタは完成した。
年配の職人たちが素朴さを残しながら丁寧に塗り上げた乳白色の内壁は、いつも穏やかな気分をもたらしてくれる。床に張った木材はもともと船舶用の耐水性に優れたもので、これも同じ職人たちが古代船を思わせる仕上げを施してくれた。
中央に配置したラグは、最後に会ったときに島崎がプレゼントしてくれたオールドキリムだ。半世紀前に作られたものと思えぬほどダメージも少なく、何より裸足で歩くときに指をつつみ込む感触がたまらない。
島崎によればプライベートスタジオの質感を決定するのはラグで、なかでもキリムがお奨めだという。理由を訊くと「誰かの受け売り」ととぼけた。彼がそう言う場合、まず十中八九ロックの
ミツスタには、悟が信頼を寄せるスタジオエンジニアが見さだめた機材をひと通り導入してはいる。だがデモの
きょうび、アマチュアや学生でも悟より高価な機材を揃えている音楽クリエイターはざらだ。でも自分には多くの機材は必要ないと割りきれるのは、実際にアレンジを作り込んでいくときは、チーム光安と呼ばれる親しいミュージシャンたちの協力を得る態勢が整っているからだ。悟にとっては統括的な意味でのプロデュースが本分なのである。
この仕事を始めたころは、打ち込み、つまり自らの手でサウンドをプログラミングする作業に、気の遠くなるような時間と体力を費やしていた。しかし、そもそも悟はミュージシャンやアレンジャーとしての達成感や名声を欲したことがなかった。自分よりアレンジやプログラミングに長けた人材がいることがわかっているなら、そして能力と実働にふさわしい対価を保証できるなら、彼らに打ち込みを
ここにある楽器らしい楽器といえば、作曲の頼もしい相棒、一九六八年製のヤマハのアップライトピアノU2Cだけだ。自分と同じ年に世に生みだされたこのU2Cは、幼稚園に入園したときに両親が倹約を重ねて中古で購入したものだ。
作曲のために弾くと、何かの拍子に幻想に襲われることがある。
つまりミツスタは本格的なレコーディングを目的としたスタジオではなく、悟が作詞と作曲を含むコンセプトづくりに専念するための
スタジオのシステムが立ち上がってから、まずやることは決まっている。前日までの作業分の最新音源データを小さな音量ですべて試聴するのだ。
どんな曲でも、大きな音で聴けばそれなりにいいものに聞こえてしまう。悪くはないと感じてしまう。これほど危険なことはない。
島崎直士が『スターサーチン』ボーイシンガー・オーディション優勝者へ提供したデビュー曲は、熱心な視聴者には酷評され、番組を知らぬ世間には黙殺された。楽曲制作の最終工程であるミキシングをチェックするときのモニタースピーカーの音量は、
本当に大切なことこそ、小さな声で伝えるべきではないのか。いや、小さな声でも伝わるものを「たいせつ」と呼ぶのではないか。
島崎にしても、プロデュースの仕事を始めた当初はきっと、複数のモニタースピーカーを使い、異なる音量で数えきれないほど試聴を重ね、微調整を加えていたに違いないのだ。
音楽プロデューサーを名乗って十年も経てば、誰もが感じるはずだ。この仕事の業務のなかで刺激的な部分はせいぜい二割か三割で、残りは単調とさえいえる地道な工程を根気よく積み重ねることだと。だがその工程なしには、くり返しの鑑賞に耐え得る楽曲なんて仕上がるわけがない。
おそらく、島崎は地道な工程の積み重ねに飽きてしまったのだろう。単調さから目をそらさないだけの辛抱強さを、もう放棄したくなったのかもしれない。生理に忠実にふるまった結果が音楽業界の最前線からの離脱であるなら、本人も納得済みということだ。周囲がどうこう言うことではない。
幸いなことに、四十代になった今もまだ、自分はそんな「飽き」に屈服することなくプロデュースを続けている。だが
そんなことをぼんやりと考えながら、悟は一昨日U音の澤口に提出した最新デモを、五回にわけて試聴した。初めの二回は小さな音で。三回目は少し音量を上げて。四回目は自分のため息がかき消される大きなボリュームで。そして五回目は最初の小さな音量に戻して。
義人の熱のある歌が入ったこの六曲目にたどり着くまで、いろんな経緯があった。だが今のところ、悟と義人の間に、権藤が心配していたような一触即発の事態は発生していない。権藤の細やかな配慮のおかげもあるが、デモにNGを連発する番組プロデューサーの多田羅を仮想敵として共有することで、義人との間に強い連帯感が芽生えているのだと悟は思う。
悟よりちょうど十歳下の義人は、ヴァイブ・トリックスがデビューしたときの悟と同じ三十三歳だ。義人が甘えたような口ぶりになると、悟はふたりの年齢差を思いだし、義人が
☆
「相変わらず光安流ですねえ。スタジオっていうより、ぶっちゃけ
昨年十月末のこと、ミツスタに足を踏み入れるなり、櫛田義人が言った。悟と義人の六年ぶりの再会の場所にここを指定したのは、ラッキーミュージックの権藤だ。
「シンガーの義人は俺なんかとは違って、『音』で光安さんとつながってる。ホテルや会議室なんかより、スタジオで会うのがいちばん自然でしょう」
権藤の言い分に理を認めた悟は、『カムバック 飛翔倶楽部ゼロ』の主題歌の制作に着手するにあたり、その場に義人を呼んだのである。
現場マネージャーも伴わず権藤とふたりだけでミツスタにやってきた義人の
久しぶりの再会にあたっては、義人がかつての輝きを失っていたとしても、けっして態度には出すまい……あらかじめ自分に説き聞かせていた悟は、それが
「さっき銀座の東映本社で打ち合わせがあったんで買ってきました。さあ食べましょう」
権藤はそう言うや、手土産の
「あっという間にふたりぼっちにされちゃったね」
悟がつぶやくと、義人が無防備な笑顔で言った。
「いいじゃないっすか。まあ主題歌打ち合わせも大切ですけど、今日は久しぶりに光安さんと音楽の話ができるの楽しみにして来たんです。なんでそんなにブラックミュージック好きになったのか、聞かせてもらっていいですか」
「ドラマチックな話があるわけじゃないよ」
「べつに話を盛る必要ないですから」
「親父がジャズ好きでね。福岡の普通のサラリーマンだったんだけど、日曜になると、晴れたら海釣り、雨が降ったら仏間で煙草吸いながらレコードをひたすら聴いてるわけ」
「お母さんもですか?」
「いや、母親はジャズにぜんぜん興味なし。だからこそ、ジャズに抗う気配がない息子のぼくを、親父はやたら可愛がってくれてさ」
「お父さん、家の中で派閥を増やしたかったんですかね」
「弟と妹は母親側についちゃったから、こっちは野党だったけどね。本当かどうかわからないけど、小学校に上がる前から、ぼくが反応するのはいつも黒人のジャズメンだったみたい。マックス・ローチとかソニー・ロリンズとか」
「シブいガキっすねえ。白人と黒人の音の違いなんてわかったんですか」
「だよねえ。で、ぼくも小学校二年か三年のころ、訊いたんだよ。『白人と黒人ってどう違うと?』って。そしたら親父は、なんと答えたと思う?」
「譜面で説明されたとか」
「腕組みしてひと言、『グッとくるとが黒人たい』って」
「やっべぇー」
「あのさ義人、こんな話を聞いてて面白いかな」
「はい。こんな話って言いますけど、昔はまったくしてくれなかったじゃないですか」
悟は苦笑しながら首を縦に小さく振った。
「けど、ほんと、やばいよね。こっちはガキだからね、もう舞い上がって勘違いしちゃったんだ。自分はグッとくるかどうかがわかる、特別な人間なんだって」
楽しい様子で話に耳を
「勘違いじゃないです。光安悟は特別な人間です。オレにとって、光安さんが特別じゃなかったことは一秒もありません」
「おいおい、大げさなこと言うなよ。重すぎるって」
「でしたか。すみません」
「謝ることでもないけど。じゃ、ありがとう。そんなことより、とりあえずのデモ作ったから聴いてみない? 一応ラフでメロディ入れてるけど、まだ固めてないから、気づいたことがあればどんどん言って」
「はい。じゃあ聴かせて……あ、ちょっと待ってください」
悟はマックブックの画面をクリックしかけた手を止めた。
「島崎直士さんって、いま何やってるんですか」
「ザッキーさんか。プロデュースの仕事はほぼリタイア状態みたい。一昨年XYZがシークレットで再結成ライブやったのは知ってる?」
「ほんとに? 知りませんでした」
「あれだけ人気のあったバンドだから、武道館とか国際フォーラムでやっても満員になるはずなんだけど、あえて町田の小さなハコでやったらしい。アマチュア時代のホームグラウンドで……喉が渇いたな。あ、ごめん、水も出してなかったね」
悟は立ち上がり、ハワイアンウォーターのサーバーに向かった。アンバーカラーのデュラレックス・ピカルディ二個に冷水をたっぷり注いで、ひとつを義人に差しだす。
「あ、いただきます。……最後にザッキーさんに会ったのはいつですか」
悟はピカルディをテーブルに置いて天井を見上げ、両腕を組んだ。
「ヴァイブスの『ファースト・トリップ』ができたとき、CDを持って事務所にお礼を言いに行ったんだ。ぼくを表舞台に引っ張りだしてくれたのはザッキーさんだから。ザッキーさんはニコニコしながら『悟、おめでとう。ヒット間違いないよ。おまえの時代だ』って言ってくれた……うん、あれが最後だった」
「じゃあオレと最後に会ってたころには、ザッキーさんとはもう会わなくなってた」
「ってことになるな」
「オレ、ザッキーさんが審査員だから『スターサーチン』に応募したんですよ。拾ってくれたのは光安さんでしたけど」
「ぼくで悪かったな」
やさぐれを装って悟が言う。
「いやいや、そんな意味じゃないです。誤解しないでください」
義人はまた真剣な表情に戻ると、まばたきもせずに悟を見て言った。
「あそこまでの人が、どうして急に表舞台から姿を消したんですか」
「ぼくは急だったとは思わない。オーディションがはじまる前から、ザッキーさんのモチベーションは下り坂だった」
「マジっすか。オレ、
「あのころのザッキーさんとぼくは、心が通じあっていたから」
「ふたりともイケイケだったから?」
「その逆。ぼくたちは、幸せじゃなくて悩みでつながっていた」
瞬間、義人は