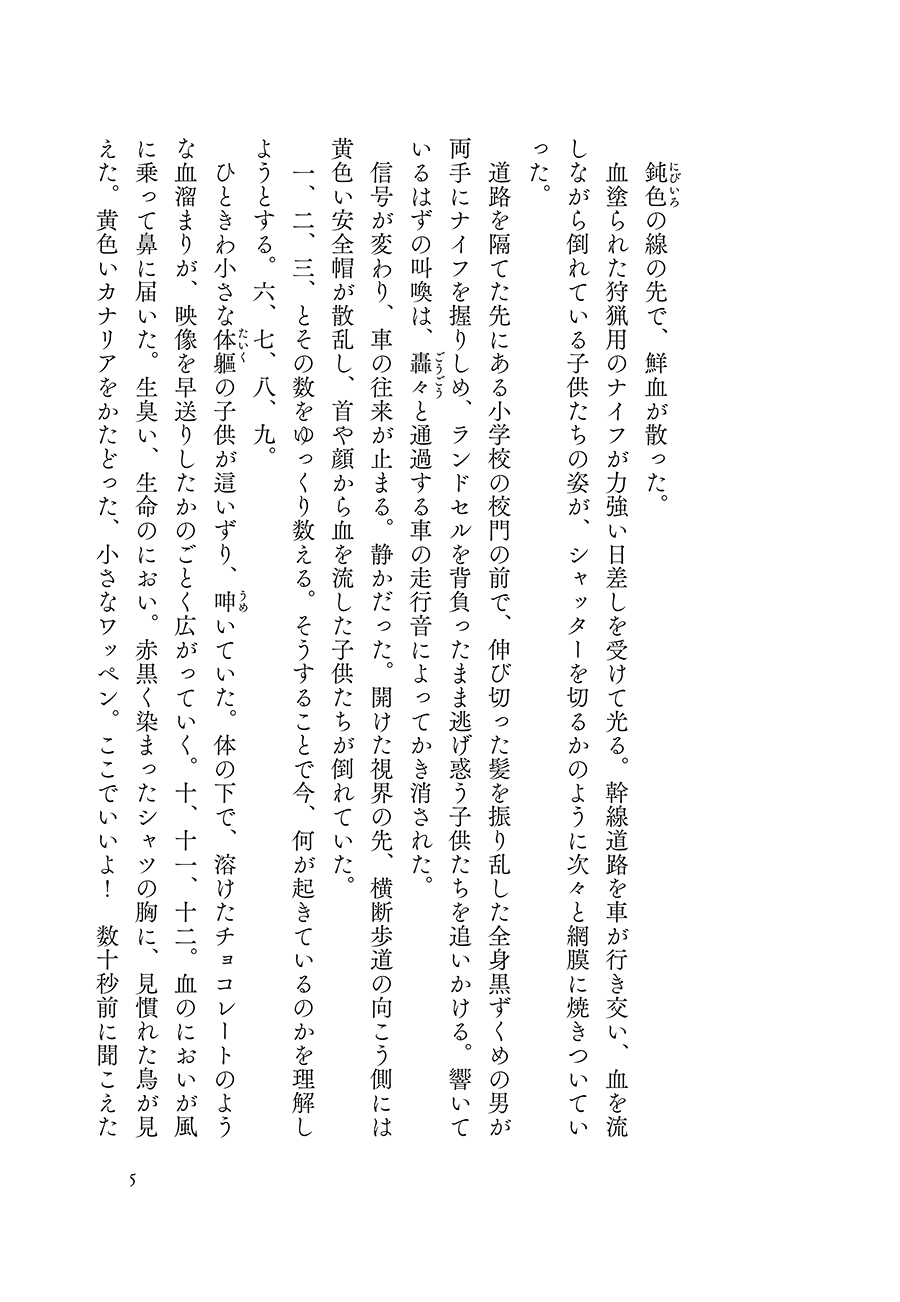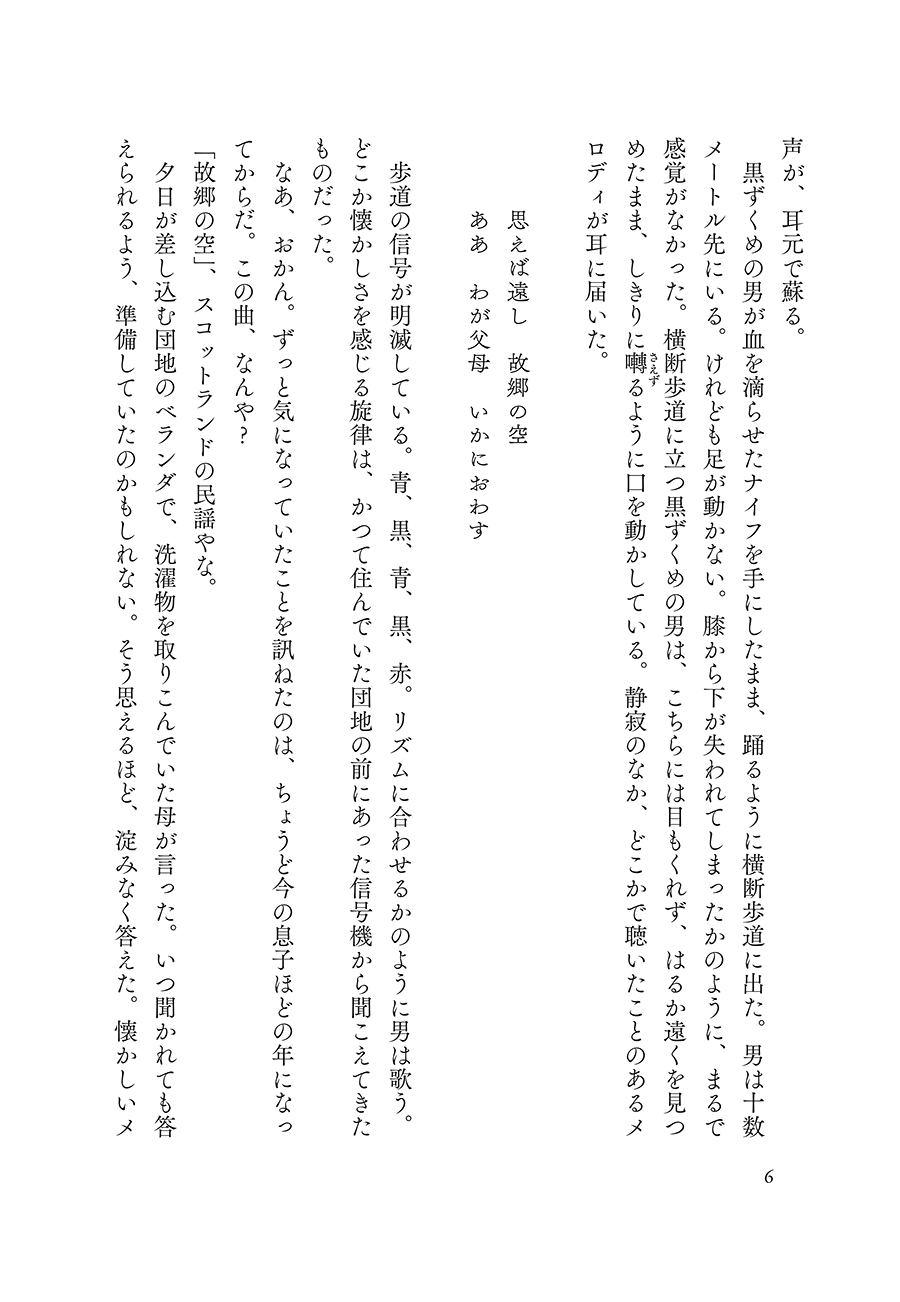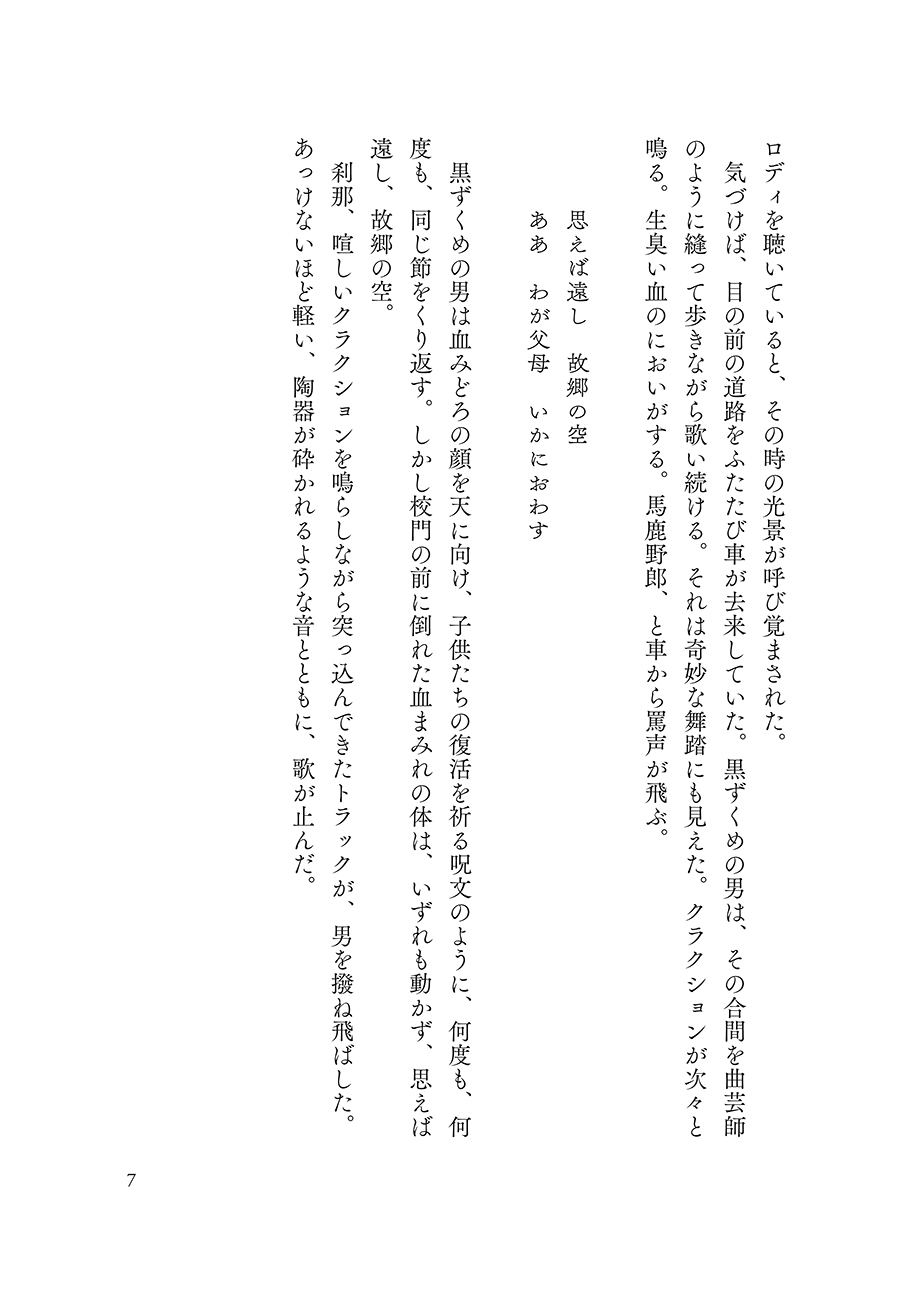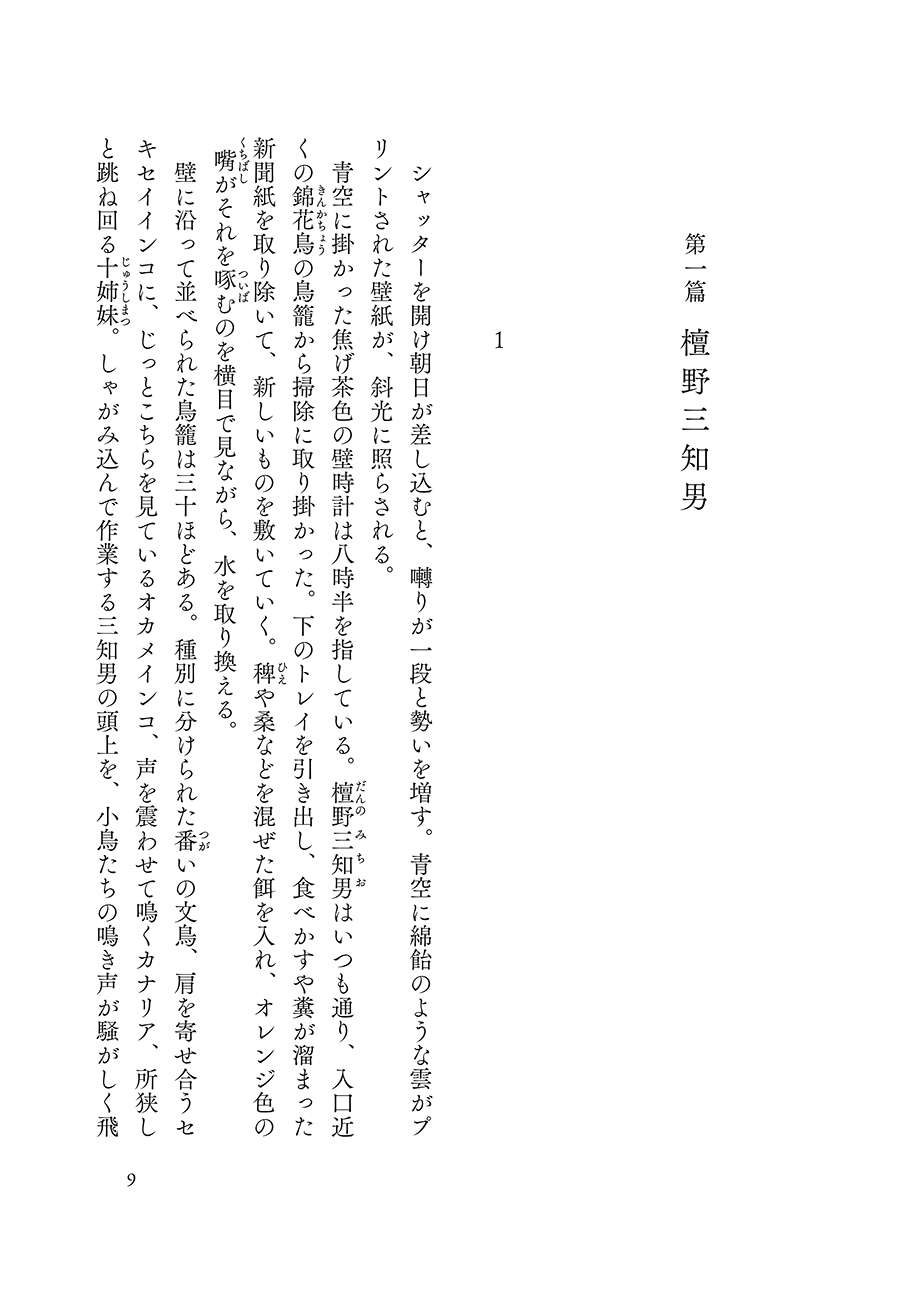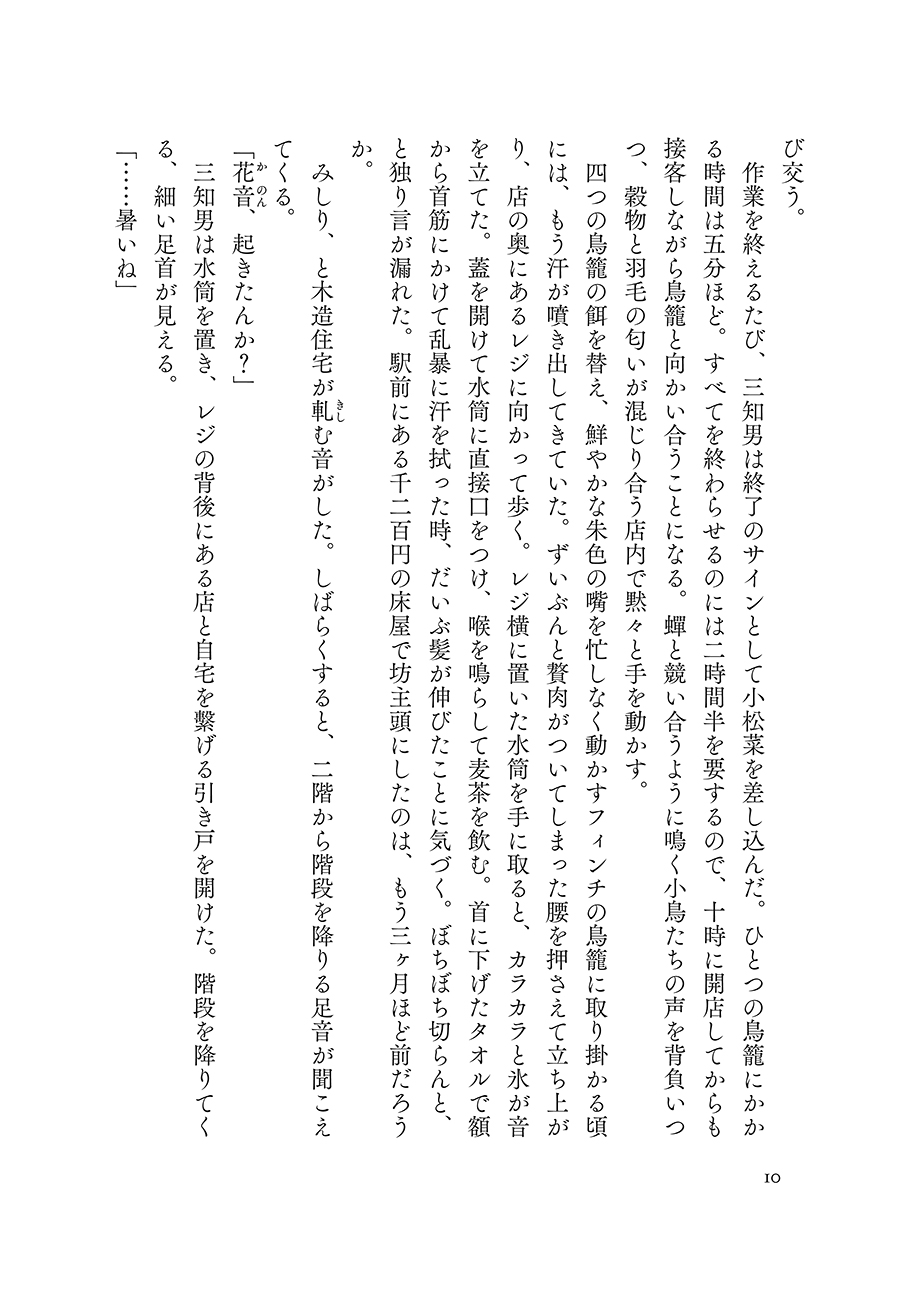鈍色の線の先で、鮮血が散った。
血塗られた狩猟用のナイフが力強い日差しを受けて光る。幹線道路を車が行き交い、血を流しながら倒れている子供たちの姿が、シャッターを切るかのように次々と網膜に焼きついていった。
道路を隔てた先にある小学校の校門の前で、伸び切った髪を振り乱した全身黒ずくめの男が両手にナイフを握りしめ、ランドセルを背負ったまま逃げ惑う子供たちを追いかける。響いているはずの叫喚は、轟々と通過する車の走行音によってかき消された。
信号が変わり、車の往来が止まる。静かだった。開けた視界の先、横断歩道の向こう側には黄色い安全帽が散乱し、首や顔から血を流した子供たちが倒れていた。
一、二、三、とその数をゆっくり数える。そうすることで今、何が起きているのかを理解しようとする。六、七、八、九。
ひときわ小さな体軀の子供が這いずり、呻いていた。体の下で、溶けたチョコレートのような血溜まりが、映像を早送りしたかのごとく広がっていく。十、十一、十二。血のにおいが風に乗って鼻に届いた。生臭い、生命のにおい。赤黒く染まったシャツの胸に、見慣れた鳥が見えた。黄色いカナリアをかたどった、小さなワッペン。ここでいいよ! 数十秒前に聞こえた声が、耳元で蘇る。
黒ずくめの男が血を滴らせたナイフを手にしたまま、踊るように横断歩道に出た。男は十数メートル先にいる。けれども足が動かない。膝から下が失われてしまったかのように、まるで感覚がなかった。横断歩道に立つ黒ずくめの男は、こちらには目もくれず、はるか遠くを見つめたまま、しきりに囀るように口を動かしている。静寂のなか、どこかで聴いたことのあるメロディが耳に届いた。
思えば遠し 故郷の空
ああ わが父母 いかにおわす
歩道の信号が明滅している。青、黒、青、黒、赤。リズムに合わせるかのように男は歌う。どこか懐かしさを感じる旋律は、かつて住んでいた団地の前にあった信号機から聞こえてきたものだった。
なあ、おかん。ずっと気になっていたことを訊ねたのは、ちょうど今の息子ほどの年になってからだ。この曲、なんや?
「故郷の空」、スコットランドの民謡やな。
夕日が差し込む団地のベランダで、洗濯物を取りこんでいた母が言った。いつ聞かれても答えられるよう、準備していたのかもしれない。そう思えるほど、淀みなく答えた。懐かしいメロディを聴いていると、その時の光景が呼び覚まされた。
気づけば、目の前の道路をふたたび車が去来していた。黒ずくめの男は、その合間を曲芸師のように縫って歩きながら歌い続ける。それは奇妙な舞踏にも見えた。クラクションが次々と鳴る。生臭い血のにおいがする。馬鹿野郎、と車から罵声が飛ぶ。
思えば遠し 故郷の空
ああ わが父母 いかにおわす
黒ずくめの男は血みどろの顔を天に向け、子供たちの復活を祈る呪文のように、何度も、何度も、同じ節をくり返す。しかし校門の前に倒れた血まみれの体は、いずれも動かず、思えば遠し、故郷の空。
刹那、喧しいクラクションを鳴らしながら突っ込んできたトラックが、男を撥ね飛ばした。あっけないほど軽い、陶器が砕かれるような音とともに、歌が止んだ。
第一篇 檀野三知男
1
シャッターを開け朝日が差し込むと、囀りが一段と勢いを増す。青空に綿飴のような雲がプリントされた壁紙が、斜光に照らされる。
青空に掛かった焦げ茶色の壁時計は八時半を指している。檀野三知男はいつも通り、入口近くの錦花鳥の鳥籠から掃除に取り掛かった。下のトレイを引き出し、食べかすや糞が溜まった新聞紙を取り除いて、新しいものを敷いていく。稗や桑などを混ぜた餌を入れ、オレンジ色の嘴がそれを啄むのを横目で見ながら、水を取り換える。
壁に沿って並べられた鳥籠は三十ほどある。種別に分けられた番いの文鳥、肩を寄せ合うセキセイインコに、じっとこちらを見ているオカメインコ、声を震わせて鳴くカナリア、所狭しと跳ね回る十姉妹。しゃがみ込んで作業する三知男の頭上を、小鳥たちの鳴き声が騒がしく飛び交う。
作業を終えるたび、三知男は終了のサインとして小松菜を差し込んだ。ひとつの鳥籠にかかる時間は五分ほど。すべてを終わらせるのには二時間半を要するので、十時に開店してからも接客しながら鳥籠と向かい合うことになる。蝉と競い合うように鳴く小鳥たちの声を背負いつつ、穀物と羽毛の匂いが混じり合う店内で黙々と手を動かす。
四つの鳥籠の餌を替え、鮮やかな朱色の嘴を忙しなく動かすフィンチの鳥籠に取り掛かる頃には、もう汗が噴き出してきていた。ずいぶんと贅肉がついてしまった腰を押さえて立ち上がり、店の奥にあるレジに向かって歩く。レジ横に置いた水筒を手に取ると、カラカラと氷が音を立てた。蓋を開けて水筒に直接口をつけ、喉を鳴らして麦茶を飲む。首に下げたタオルで額から首筋にかけて乱暴に汗を拭った時、だいぶ髪が伸びたことに気づく。ぼちぼち切らんと、と独り言が漏れた。駅前にある千二百円の床屋で坊主頭にしたのは、もう三ヶ月ほど前だろうか。
みしり、と木造住宅が軋む音がした。しばらくすると、二階から階段を降りる足音が聞こえてくる。
「花音、起きたんか?」
三知男は水筒を置き、レジの背後にある店と自宅を繋げる引き戸を開けた。階段を降りてくる、細い足首が見える。
「……暑いね」
寝起きの掠れた声で、響子が言った。サンダルをひっかけ店内に入ってきた妻を迎えるように、鳴き声が一段と大きくなる。小鳥たちはめいめいに声を響かせるが、それが不思議と美しいアンサンブルになっていた。この店の主人が誰であるのかを、鳥たちはよく知っている。
「どないしたん? まだ朝やで」
素っ頓狂な声が出た。三知男は慌ててエアコンのリモコンを手に取り、冷房のスイッチを入れる。まだ生温い空気が、エアコンの送風口から噴き出してくる。
「私、手伝う」
「え?」
三知男の答えを待たずに、響子は桜文鳥の鳥籠の掃除を始める。時計の針は、九時を五分ほど過ぎたことを示していた。三知男が隣に立ち、十姉妹の鳥籠に手をかけると、やっておく、と響子が言う。月曜だし、餌の発注とかあるでしょ。
この数ヶ月、響子は店に出ることはおろか、午前中に起きてくることもなかった。面喰らいつつも、ありがとう、と呟くと三知男はレジに入った。ノートパソコンを立ち上げて馴染みの問屋のサイトで餌を注文し、新しい小鳥の入荷情報を確認する。時折パソコン画面から目を上げ、妻の様子を観察した。ゆっくりと、しかし確かな手付きで小鳥に餌をやっている。母親の帰還を喜ぶように、文鳥たちが響子の指先を啄んでいた。
瓦屋根に覆われた古い一軒家の一階に、檀野小鳥店はある。
創業は七十年ほど前だと、響子の母から聞いた。戦後に近隣の農家が飼っている鶏の餌を販売するところから始め、その後うずらや伝書鳩などを扱っていた時代を経て、今は観賞用の小鳥の販売を細々と続けている。
八年前、婿入りというかたちで響子と結婚して、彼女の家業である小鳥店を継いだ。小鳥店の仕事をするまで、三知男は職が定まらなかった。
高校生の時に聴いていたパンクバンドの影響で始めたエレキベースに夢中になり、一浪して入った地元大阪の大学でも授業にはほとんど出席することなく、サークルでバンドを続けた。就職活動もせず、サークルの延長線上でギターボーカルとドラムスとのスリーピースバンドを結成し、親の反対を押し切って上京した。居酒屋やコンビニエンスストアのバイトを掛け持ちしつつ、都内のライブハウスで演奏し、CDを手売りして回る日々を送った。
ボーカルのルックスがそこそこ良かったこともあり、中堅のレコード会社から契約の話が来たが、新人開発部に預けられたきり、デビューのチャンスがないまま年月だけが過ぎていった。
二十代の半ばに、行きつけのバーで働いていたふたつ年下の女性と結婚したが、三年足らずで家を出ていかれてしまった。次第にメンバーとの仲も悪くなり、離婚とほぼ同時にバンドも解散。それからいくつかのインディーズバンドを渡り歩いたものの、作詞も作曲もできないベーシストでは生計を立てることは叶わず、音楽スタジオや楽器屋の契約社員をしながらの生活が続いた。
両親とは絶縁状態だったが、横浜に住む叔母だけはこまめに連絡をくれていた。三十歳を目前に控え、お節介焼きなその叔母の強引な勧めで見合いをすることになった。初めての見合いに渋々臨んだ時に、やってきたのが響子だった。
細身の体に、卵形の小さな顔が載っていた。その奥二重の中にある黒々とした瞳は、強い意志を感じさせた。思いがけず美しい女性がやってきたことに、三知男は戸惑った。なぜ彼女が、自分みたいな男と見合いをすることになったのか不思議だった。
「あとは若いお二人で……って仲人さん、ほんまに言うんやなあ」
ホテルのティールームで一通りの挨拶を終え、庭園をふたりで歩きながら響子に声を掛けた。
「私も……それちょっと思いました。台詞みたいでしたよね」響子が微笑を浮かべながら相槌を打つ。「最近のお見合いではそういうことはもう言わないって、聞いてたのに」
「誰にです?」
「友人に。私、初めてのお見合いだったので、いろいろ調べてから来たんです」
「そのお友達、日本庭園で鯉見ながら、てくてく散歩することもあらへんって言うとりませんでした? まさかこんなベタベタな……」
三知男は、締め慣れないネクタイを緩めながら池の水面に目をやった。そのままワイシャツの第一ボタンを外そうとしたが、硬くてうまくいかない。
「でもこんな体験ができただけでも、来た甲斐ありましたね」
「ちょっとお……それ、僕はどうでもいいってことですやん?」
苦笑いで返すと、響子は、あ、と頭を下げる。首元までで綺麗に刈り揃えられた髪を、小ぶりで形の良い耳に掛けた。
「ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんですけど、なんだか緊張しちゃって」
少し早口で弁明する響子の耳が、みるみる染まっていく。その赤を見ながら、彼女のことを好きになるのかもしれない、と思った。
錦鯉が泳ぐ池に架かる石橋の上で、売れないバンドを続けていることを三知男は伝えた。音楽が好きな人ならば一緒にいても楽しそう、と響子は言った。彼女は、音楽大学の声楽科を卒業したあと、プロの歌手を目指していたという。
「どうにも諦めがつかなくて、婚期もすっかり逃しました」
お互いの境遇が似ていることを確認したのち、響子は囁いた。静かな声で話していても、その声にはどこか惹き付けられるものがあった。
「でも、響子さんみたいなきれいな人なら、なんぼでも相手おるやろうに」
素直な感想を漏らすと、響子は俯いて口を開く。
「……小鳥は好きですか?」
「え? 子供の頃やけど……つがいのインコ飼うてました。ほんまは犬を飼いたかったんやけど団地やったから……二羽とも、大阪弁でよう喋る子でしたわ」
響子の唐突な質問で、昔飼っていた小鳥のことを思い出した。つがいのインコが大阪弁で話し出すと、まるで漫才をしているようだった。
「……条件があるんです」
条件、という言葉に三知男はすこし体を硬くした。何か訳ありなのか。それならば自分も人のことを言えた身ではない。
「小鳥店を、一緒に継いで欲しいんです」
「小鳥店?」
「はい。インコとか、文鳥とか」
「ひよことか」
「ひよこはニワトリになっちゃうので、扱ってないですけど」
響子は笑いながら、小鳥が羽ばたくように手を振った。三知男には小鳥店という仕事の想像が付かず、しばらく調子の外れたやりとりが続いた。
「正直、歌うことに今は疲れてしまって。しばらくは家族と小鳥たちとのんびり暮らしていく環境があればいいと思っているんです」
結婚などする気がなかったはずなのに、不思議と彼女の気分に同調していた。バンドを続けるのにも疲れていたし、狭いアパート暮らしにもうんざりしていた。ただ、自分の才能を見限ることができないだけだった。
「そういえば……もうひとつ友人から聞いたことがあるんです」
遠くから仲人がふたりを呼ぶ声が聞こえると、響子は呟いた。
「なんやの?」
「お見合いの時、石橋をふたりで渡ったら結婚するって」
「響子さん、そういうの信じはるんですか?」
「どうでしょうか……でも信じたい、と思っています」
半年後に三知男は響子と結婚し、小鳥店の二階で生活を始めた。響子の父親はすでに亡くなっており、ひとりで店を切り盛りしていた母親は体調があまりよくなかった。その母親も、店を譲ってから三年後に他界した。
結婚の挨拶に行った時、閉めてもいいのよ、と義母は言った。時勢的にも先細りするばかりの小鳥店を継ぐことは勧めない、と。実際、小鳥店の収入は楽器屋の契約社員の頃とさほど変わらなかった。家賃はかからなかったが、決して豊かとは言えない暮らしだった。
それでも響子は、この仕事にこだわっていた。初めは強がりだと思っていたが、小鳥店をふたりで切り盛りするうちに、彼女が本当に鳥を愛していることがわかった。響子は毎日、鳥籠にいる小鳥たち一羽一羽に声をかけ、時にはともにハミングし、買い手がついた時は笑みを浮かべつつも、どこか寂しげに見送った。
その姿を見て、三知男はさらに響子に惹かれていった。妻としても、子供の母としても、過分な女性と結婚できたと思っていた。
「なに見てるの?」
妻の声で、我に返った。ノートパソコンから目を上げると、オカメインコを手に乗せた響子が、こちらを見ていた。
「さっきから、ずっとにやにやしてるけど」
「え? ほんま?」
虚を突かれ、声が上ずる。ホンマ? と五年も売れ残ったままのオカメインコが真似をした。長居するうちに、三知男の口癖をすっかり覚えてしまっていた。
「なに見てるのよ」
響子が繰り返す。
「……逆立ちする猫の動画や」
観念して答えを明かす。数ヶ月ぶりに小鳥の世話をする妻の姿をレジからじっと観察していたが、そのうち直視することができなくなり動画サイトを見始めていた。
パソコンの画面の中では白猫が尻尾をぴんと伸ばし、逆立ち歩きをしている。スマートフォンで撮影された動画はやけにブレていて、滑稽な姿に堪えきれず笑う飼い主の声が入っている。
なにそれ? と苦笑し、響子が手に乗せていたオカメインコを鳥籠に戻す。また嘘ばっかり。
「いや、ほんまやって」
「信じられない」
「ほら、見てみ」
パソコン画面を響子に向けたが、妻はそれを無視して次の鳥籠に取り掛かる。ベルギーから取り寄せた珍しいフィンチが甲高い声で鳴いた。呼応するように、周りの小鳥たちが鳥籠の中で羽ばたく。
「他にもぎょうさんあるねん」
「どんなのが?」
「ピアノを弾く犬やろ、あと歌うキリンとか」
「どうせ、そういうのってCGとかで作ってるんでしょ? 前も石鹼で体を洗うネズミで大騒ぎしてたけど、あれも偽物だったし」
「あれはニセモンやったけど、ホンマモンもあるんやって」
三知男がクリックを繰り返すと、色とりどりの小鳥たちが先を急かすように鳴いた。スペイン、オーストラリア、メキシコにペルー。響子は様々な国の小鳥を仕入れるのが好きだった。
この小さな店に、いろんな国の息吹が入ってくる気がするの。海外から小鳥がやってくるたびに、妻は言った。輸入した小鳥は輸送や検疫のコストがかかるため値段が高く、五万円を超えるものもいる。郊外の小さな町でこんなに高い小鳥が売れるはずがない、と初めは困惑した。けれども、今では珍しい小鳥を求めて都外から檀野小鳥店に来る客も多い。
「そんな動画、どこで見つけるの?」
響子はフィンチの鳥籠に小松菜を差し込み、アルゼンチンから来たオキナインコの鳥籠を開ける。気づけば、手際がいつものペースに戻っている。子供の頃からこの店の手伝いをしていたと、妻が言っていたのを思い出した。
「次から次へと出てくんねん。人工知能が、あんたこれ好きやろ? って勧めてくれる。ほら、馬が涙流しとる動画も出てきた」
笑いながら響子を見るが、彼女は手に乗せたオキナインコの額を撫でていて、こちらを見ようとしない。信じられないよねえ、と灰色がかったブルーの羽で覆われたその小鳥に話しかけている。
「花音はどしたん?」
話題を変えるべきだと判断し、三知男は訊ねた。
「まだ寝てるんじゃない?」
檀野小鳥店の二階には、夫婦の寝室と子供部屋、台所と小さな居間が、ほぼ正方形のスペースに詰め込まれている。
「花音、朝ごはん食べへんのかな?」
響子からの返答はない。手に乗っていたオキナインコが飛び立ち、狭い店の中をばたばたと飛び回る。
「花音、降りてき!」
三知男は声を張った。
「朝ごはん作るで! 響子は? なに食べる?」
目をやると、響子はカナリアの鳥籠の前にしゃがみ込んでいた。飛んでいたオキナインコが、響子の足元に戻っていく。
「どないしたん?」
嫌な予感がして、三知男はレジの丸椅子から立ち上がる。響子の横にかがみ込んで鳥籠の中を覗くと、レモン色の小鳥が餌箱の裏で倒れて動かなくなっていた。
「あ、死んどる」
思わず口を滑らせたあと、それが特別な小鳥であることに気がついた。
「それだけ?」
響子の声が、震えている。
あ、いや、と三知男が口籠っていると、響子が続ける。
「この子、ピッピよ」
「せやな、ピッピちゃんや」
「……ちゃんと水取り換えてくれてた?」
「あたりまえやろ……」
「餌は?」
「もちろん……やっとった」
「ニガシード入れてた?」
「……忘れんようにしとったで」
スペインからやってきた珍しいカナリアは、レモンを思わせる鮮やかな黄色をしていた。細い喉を震わせて、フルートのような声で鳴いた。売り物だとわかりつつ、息子の奏汰はひそかに“ピッピ”と名付けてかわいがっていた。もしも半年間買い手がつかなければ、自分で飼っても良いと約束していた。以来このカナリアの世話だけは、奏汰が担当することになっていた。
「かわいそう」
ため息とともに呟くと、窓についた雨水のように、涙が響子の頬をまっすぐに伝い落ちた。同時に、花音が階段を降りてくる音が聞こえた。
「……花音、パン焼くか? 目玉焼き? 茹で卵? どっちや?」
階段の先にいるはずの娘に向かって声を張ると、YouTube の動画がちょうど切り替わったのか、ノートパソコンから呑気なカントリーミュージックが流れ出した。急いでレジに戻り画面を覗くと、バンジョーの音色に合わせて牧場で羊たちが踊っている。
「私なら……あなたみたいに見殺しにしなかった」
固まって動かなくなったカナリアを鳥籠から取り出しながら、響子が零した。
「ごめん……ちゃんと僕が面倒みるって約束しとったのに。でもピッピちゃんはもともと体も弱かったみたいやし……」
慌ててパソコンのマウスを触るが操作を誤り、カントリーミュージックのボリュームが上がる。突然の大音量に驚いたのか、小鳥たちが一斉に鳴き止んだ。
「あなたに任せなければよかった」
ようやく三知男が動画を停止させ、パソコン画面から目を上げると、レモン色を胸に抱きしめた妻が呻くように言った。何か声を掛けなければと焦れば焦るほど、言葉を継ぐことができない。カナリアを握る響子の華奢な手が、小刻みに震え出す。
「三十八度。たった三十八度の熱で、なんであなたなんかに任せたんだろう。入学してからずっと毎日私が送ってたのに。どうして、あの日に限って。奏汰、泣いてたでしょう? 苦しんでたでしょう? あなたに助けて欲しかったはずよね? 私なら車に撥ねられても、轢かれても、道を渡って助けてた。顔を切られようが、腹を刺されようが、あの男を殺してでも奏汰を守ってた。あなたなにやってたの? あの時なにやってたの? ぼーっと信号の前で突っ立って。そんなに自分の命が惜しかった? あなたそれでも父親なの?」
階段を降りてくる花音の足音が止まった。来たらあかん、そう声を掛けたかったが言葉にならなかった。響子の声が、娘の耳に届いていないことを祈った。
あの日、体調を崩した響子の代わりに、三知男が奏汰を小学校まで送った。
準備に手間取って家を出るのが遅れた。遅刻だ、遅刻だ。奏汰の手を握り、学校へと走った。校門を目前にして、横断歩道の信号が点滅し始めていた。お父さん、ここでいいよ! 信号が赤に変わる直前、奏汰が速度を上げ、道を渡った。
直後、車が勢いよく幹線道路を走り出した。横断歩道の向こうにいる息子に手を振っていると、黒ずくめの男が横から走りこんできて奏汰にぶつかった。
初めは、何が起きているのかわからなかった。男は倒れた奏汰の体から血みどろの狩猟用ナイフを引き抜くと、登校してくる子供たちを次々と刺した。奏汰も含めて死者は四人、重傷者は八人で、そのすべてが小学生だった。
「さんざん人殺してから死ぬ時に、あの男はどうしてた?」
響子の語気が強まる。
「怒ってた? 怖がってた? どうせ笑ってたんでしょう?」
歌っていた、とは言えなかった。伝えたら、妻が壊れてしまうと思った。スコットランド民謡「故郷の空」。今でもメロディがはっきりと蘇る。
あの時、彼は確かに歌っていた。そして三知男は、その旋律を懐かしんでいた。
「あなたは、全然泣かないよね」
響子がこちらを睨んでいるのがわかったが、目を合わせることができない。
三知男はただ、彼女の胸に抱かれたレモン色を見つめていた。生命が失われてもその色はまだ鮮やかなままだった。
「あなたがそういう人なの、わかってた。私だけがずっと悲しんでる。バカみたい。奏汰がかわいそう」
事件の後から響子は寝込み、花音は中学校に行かなくなった。三知男は葬式が終わるまでは枕を濡らし続けたが、その後は店を開け小鳥の世話を始めた。それは生活を守るためというよりむしろ、正気を保つためだった。目の前の仕事に没頭しない限り、すぐにあの日の血のにおいや、男が口ずさんだメロディが生々しく現れる。
どうしてあなたは辛いことから逃げようとするの? と響子はたびたび三知男を責めた。三知男が日常を変わらずに過ごしているように見えるのが、許せなかったのだろう。確かに、響子と同じだけの悲しみなのかと問われると、自分の感情がどういう質量を持ったものなのかわからなかった。
とはいえ三知男にも、小鳥の世話をしながら奏汰の声を思い出し、うずくまって動けなくなる時があった。小鳥の鳴き声のように繊細な声は母親に似て、いつもどこか震えていた。
通り魔の男については、しばらく名前を伏せたかたちで報道されていた。被害者遺族である三知男たちにも、情報はほとんど知らされなかった。けれどもインターネット上ではあっという間に名前や住所、学歴や家族構成が晒された。
男の名前は角倉正平。四十八歳、独身で、事件現場から二駅ほど離れた坂の上の一軒家で老齢の両親と同居していた。
二十年近く二階の自室に引きこもった生活を送っており、この数年は両親との会話すらなかったという。警察の捜査が入った時、自室の壁は真っ黒に塗りつぶされていた。ハイスペックのデスクトップパソコンと、三台のモニターのほかは何も置かれておらず、パソコンのデータもすべて消去されていた。
つんざくような鳴き声で我に返った。
檀野小鳥店の中で最も体の大きいボタンインコが鳴いていた。緑色の羽毛に覆われた太い喉を震わせ、絶叫し続ける。
「……音が聞こえない」
カナリアを抱いたまま、響子が呟いた。
「……え? なに言うてんねん響子。今もめっちゃ鳥鳴いとるやん」
話題が変わったことに安堵し、三知男は口角を上げてわざと明るく返した。
「そういうことじゃないの。音程がわからないのよ。メロディがないの。全部、ただの音の羅列なの」
三知男が言葉を失い視線を彷徨わせると、レジの背後にある引き戸を握りしめる花音の手が見えた。その細い指は震え、戸がカタカタと音を立てている。
弟の遺体を見た花音は、子供用の小さな棺桶にすがりついて体から水分を出し尽くすのではないかというほどずっと涙を流していた。そして、火葬されて粉々になった遺骨を目の当たりにしてからは、ほとんど言葉を発しなくなった。毎日涙を流す響子に、黙ってずっと寄り添っていた。
花音、と声が出た。娘は戸から顔を出して、制するような目で三知男を見る。その瞳からは、今にも涙が溢れ出しそうだった。震える手で口を押さえ、咽び声を漏らすまいとしていた。今の会話を聞いたことが、おかあさんに伝わってはいけない。なにも言わないで、と花音が目で訴えかけていた。
腹が熱くなり、心臓が鷲摑みにされているかのようだった。
その熱の正体が何かと考えてみたが、適切な言葉が見つからない。ただ、それがもうどこにも向けようがないものであることだけが、はっきりとわかった。