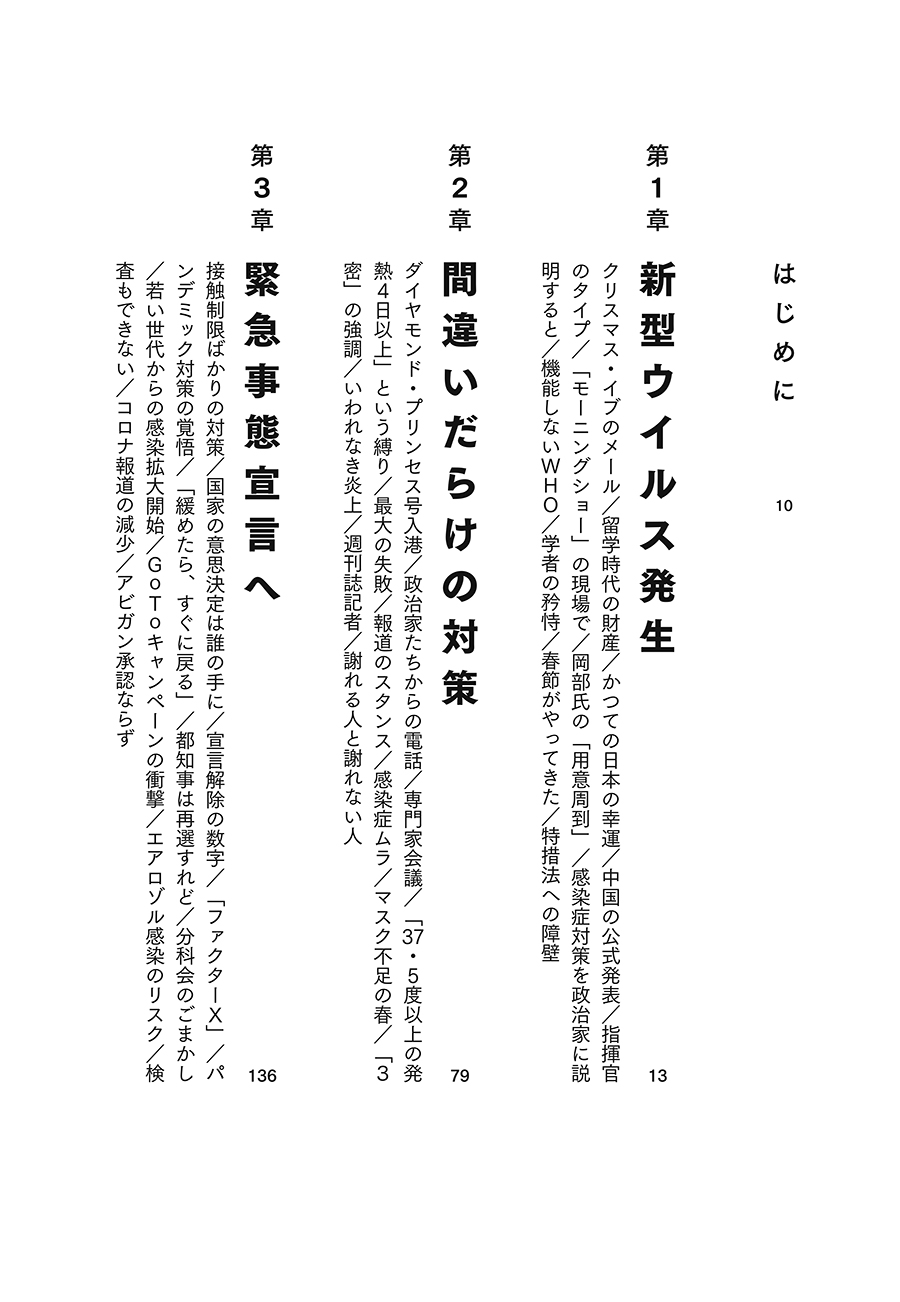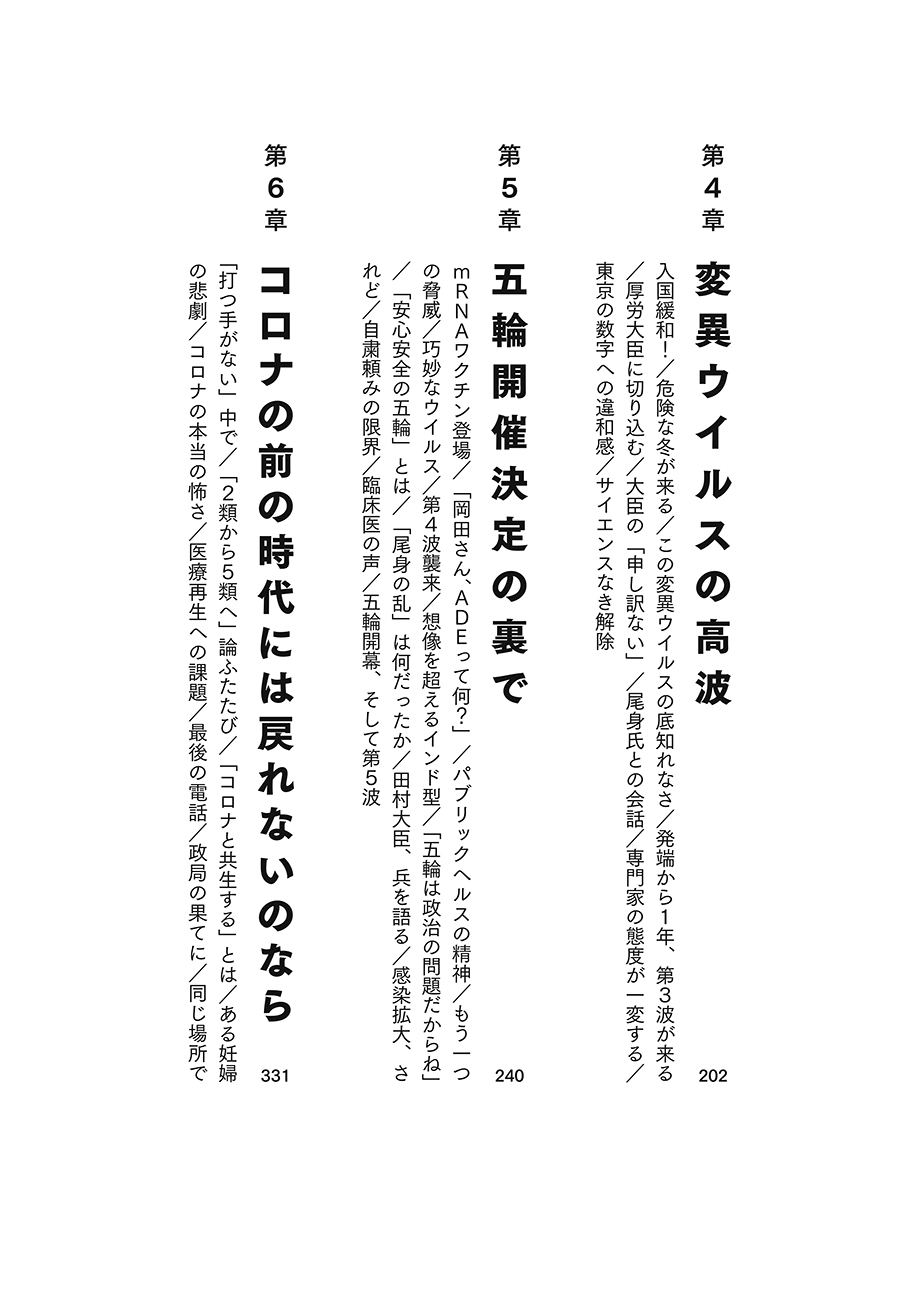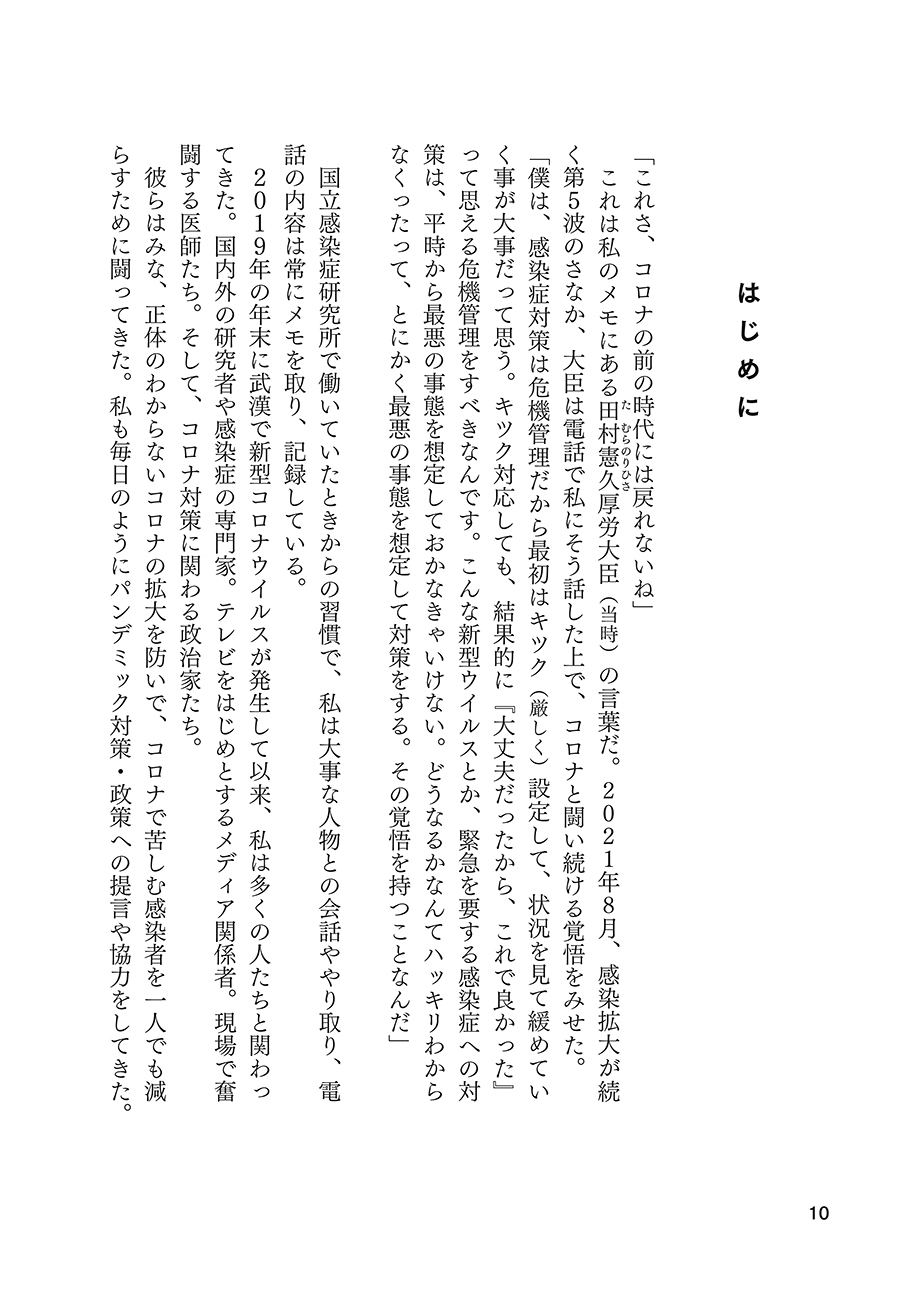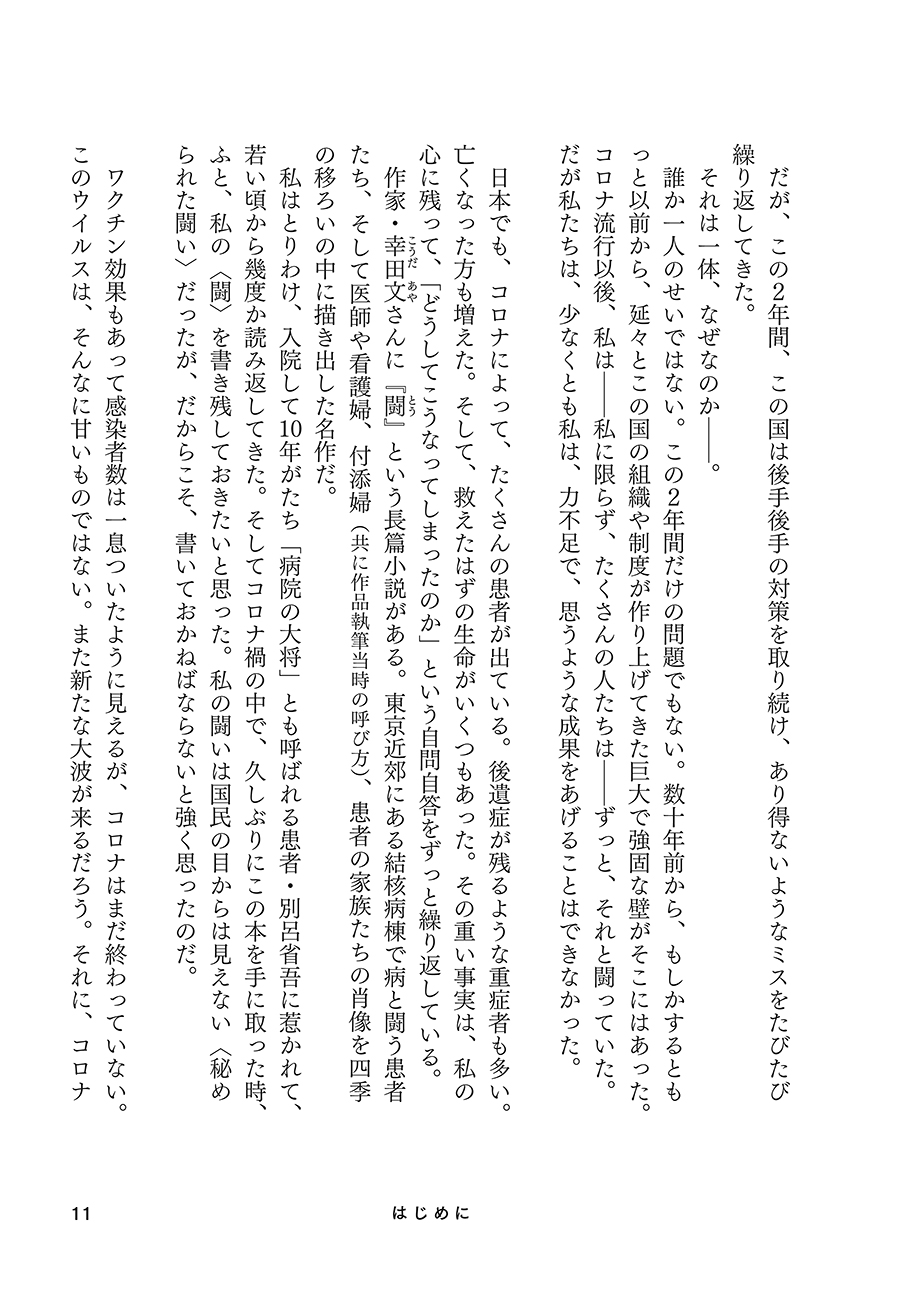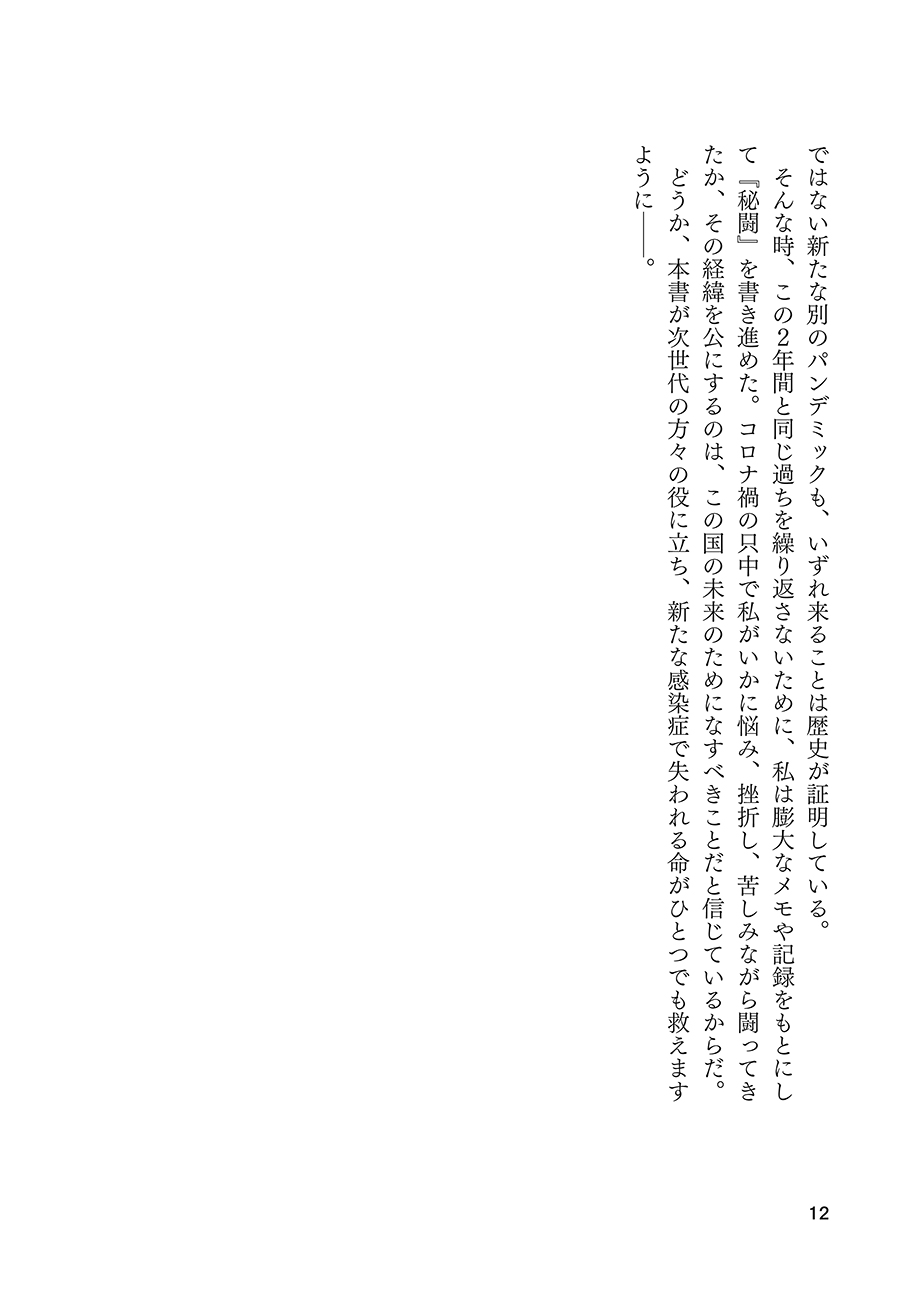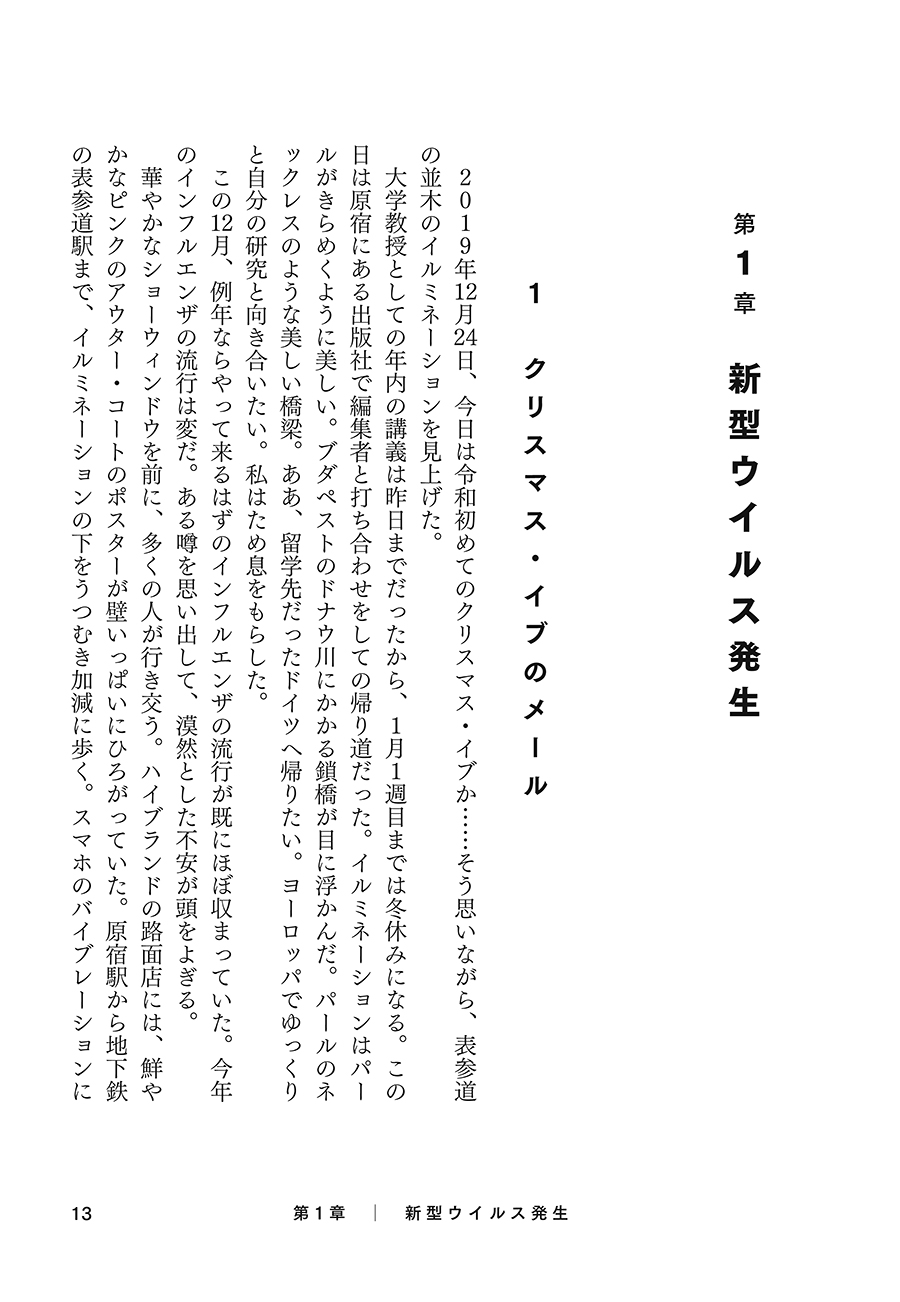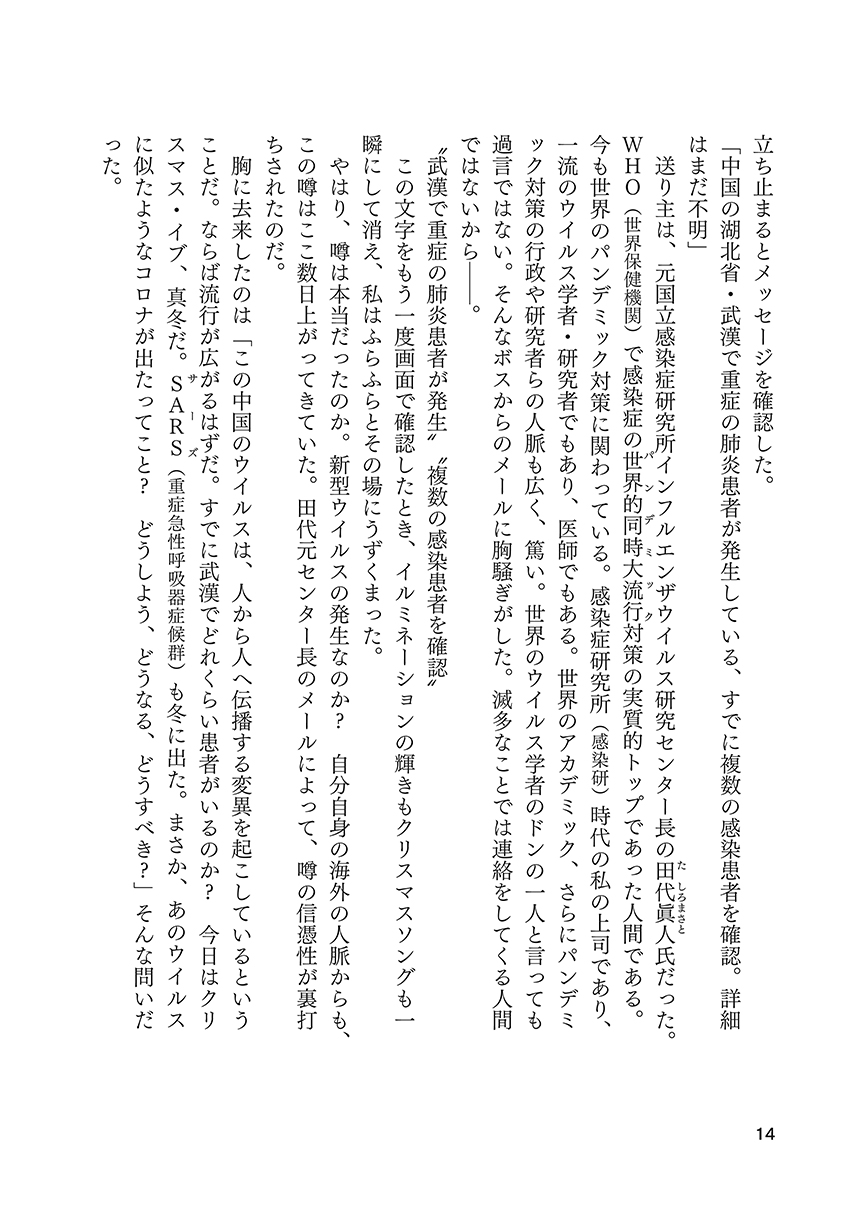はじめに
「これさ、コロナの前の時代には戻れないね」
これは私のメモにある田村憲久厚労大臣(当時)の言葉だ。2021年8月、感染拡大が続く第5波のさなか、大臣は電話で私にそう話した上で、コロナと闘い続ける覚悟をみせた。
「僕は、感染症対策は危機管理だから最初はキツク(厳しく)設定して、状況を見て緩めていく事が大事だって思う。キツク対応しても、結果的に『大丈夫だったから、これで良かった』って思える危機管理をすべきなんです。こんな新型ウイルスとか、緊急を要する感染症への対策は、平時から最悪の事態を想定しておかなきゃいけない。どうなるかなんてハッキリわからなくったって、とにかく最悪の事態を想定して対策をする。その覚悟を持つことなんだ」
国立感染症研究所で働いていたときからの習慣で、私は大事な人物との会話ややり取り、電話の内容は常にメモを取り、記録している。
2019年の年末に武漢で新型コロナウイルスが発生して以来、私は多くの人たちと関わってきた。国内外の研究者や感染症の専門家。テレビをはじめとするメディア関係者。現場で奮闘する医師たち。そして、コロナ対策に関わる政治家たち。
彼らはみな、正体のわからないコロナの拡大を防いで、コロナで苦しむ感染者を一人でも減らすために闘ってきた。私も毎日のようにパンデミック対策・政策への提言や協力をしてきた。
だが、この2年間、この国は後手後手の対策を取り続け、あり得ないようなミスをたびたび繰り返してきた。
それは一体、なぜなのか――。
誰か一人のせいではない。この2年間だけの問題でもない。数十年前から、もしかするともっと以前から、延々とこの国の組織や制度が作り上げてきた巨大で強固な壁がそこにはあった。コロナ流行以後、私は――私に限らず、たくさんの人たちは――ずっと、それと闘っていた。だが私たちは、少なくとも私は、力不足で、思うような成果をあげることはできなかった。
日本でも、コロナによって、たくさんの患者が出ている。後遺症が残るような重症者も多い。亡くなった方も増えた。そして、救えたはずの生命がいくつもあった。その重い事実は、私の心に残って、「どうしてこうなってしまったのか」という自問自答をずっと繰り返している。
作家・幸田文さんに『闘』という長篇小説がある。東京近郊にある結核病棟で病と闘う患者たち、そして医師や看護婦、付添婦(共に作品執筆当時の呼び方)、患者の家族たちの肖像を四季の移ろいの中に描き出した名作だ。
私はとりわけ、入院して10年がたち「病院の大将」とも呼ばれる患者・別呂省吾に惹かれて、若い頃から幾度か読み返してきた。そしてコロナ禍の中で、久しぶりにこの本を手に取った時、ふと、私の〈闘〉を書き残しておきたいと思った。私の闘いは国民の目からは見えない〈秘められた闘い〉だったが、だからこそ、書いておかねばならないと強く思ったのだ。
ワクチン効果もあって感染者数は一息ついたように見えるが、コロナはまだ終わっていない。このウイルスは、そんなに甘いものではない。また新たな大波が来るだろう。それに、コロナではない新たな別のパンデミックも、いずれ来ることは歴史が証明している。
そんな時、この2年間と同じ過ちを繰り返さないために、私は膨大なメモや記録をもとにして『秘闘』を書き進めた。コロナ禍の只中で私がいかに悩み、挫折し、苦しみながら闘ってきたか、その経緯を公にするのは、この国の未来のためになすべきことだと信じているからだ。
どうか、本書が次世代の方々の役に立ち、新たな感染症で失われる命がひとつでも救えますように――。
第1章 新型ウイルス発生
1 クリスマス・イブのメール
2019年12月24日、今日は令和初めてのクリスマス・イブか……そう思いながら、表参道の並木のイルミネーションを見上げた。
大学教授としての年内の講義は昨日までだったから、1月1週目までは冬休みになる。この日は原宿にある出版社で編集者と打ち合わせをしての帰り道だった。イルミネーションはパールがきらめくように美しい。ブダペストのドナウ川にかかる鎖橋が目に浮かんだ。パールのネックレスのような美しい橋梁。ああ、留学先だったドイツへ帰りたい。ヨーロッパでゆっくりと自分の研究と向き合いたい。私はため息をもらした。
この12月、例年ならやって来るはずのインフルエンザの流行が既にほぼ収まっていた。今年のインフルエンザの流行は変だ。ある噂を思い出して、漠然とした不安が頭をよぎる。
華やかなショーウィンドウを前に、多くの人が行き交う。ハイブランドの路面店には、鮮やかなピンクのアウター・コートのポスターが壁いっぱいにひろがっていた。原宿駅から地下鉄の表参道駅まで、イルミネーションの下をうつむき加減に歩く。スマホのバイブレーションに立ち止まるとメッセージを確認した。
「中国の湖北省・武漢で重症の肺炎患者が発生している、すでに複数の感染患者を確認。詳細はまだ不明」
送り主は、元国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長の田代眞人氏だった。WHO(世界保健機関)で感染症の世界的同時大流行対策の実質的トップであった人間である。今も世界のパンデミック対策に関わっている。感染症研究所(感染研)時代の私の上司であり、一流のウイルス学者・研究者でもあり、医師でもある。世界のアカデミック、さらにパンデミック対策の行政や研究者らの人脈も広く、篤い。世界のウイルス学者のドンの一人と言っても過言ではない。そんなボスからのメールに胸騒ぎがした。滅多なことでは連絡をしてくる人間ではないから――。
“武漢で重症の肺炎患者が発生”“複数の感染患者を確認”
この文字をもう一度画面で確認したとき、イルミネーションの輝きもクリスマスソングも一瞬にして消え、私はふらふらとその場にうずくまった。
やはり、噂は本当だったのか。新型ウイルスの発生なのか? 自分自身の海外の人脈からも、この噂はここ数日上がってきていた。田代元センター長のメールによって、噂の信憑性が裏打ちされたのだ。
胸に去来したのは「この中国のウイルスは、人から人へ伝播する変異を起こしているということだ。ならば流行が広がるはずだ。すでに武漢でどれくらい患者がいるのか? 今日はクリスマス・イブ、真冬だ。SARS(重症急性呼吸器症候群)も冬に出た。まさか、あのウイルスに似たようなコロナが出たってこと? どうしよう、どうなる、どうすべき?」そんな問いだった。
田代氏は定年退職後も、ジュネーブ(WHOなどの国際機関)や米国、ヨーロッパ、東南アジアを中心に、中国、台湾などの研究者、行政官にも強固なパイプを維持している。それは、過去の国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長、WHOインフルエンザ協力センター長、WHOパンデミック緊急会議委員などの役職によってもたらされたものだけでなく、より強いパーソナル・コミュニケーションによるネットワークが大きかった。
田代氏が感染研にいた頃は、それらのネットワークから、公式にはなっていない水面下の情報、ミステリアスな感染症発生や危惧すべき病原体など、さまざまな情報が日本へ即座にもたらされた。
彼は玉石混淆の情報の中から、重要かつ信憑性の高い事象を選び、厚労省の医系技官ら「それなりの人間」に送り、さらにリスク評価のアドバイスを入れ、対策も助言――というより、「こうすべきだ」と強く意見していた。
パンデミック対策は危機管理や災害対策にも匹敵する。国家の安全保障問題でもあるからだ。海外諸国との結びつきの強さのあまり、公安調査庁がやってきた、という話は部下の間では有名である。内閣情報調査室からも呼び出しがあった。
ただ、田代氏の要求する政策は、厚労省の想定するレベルを遥かに凌駕する強い対応であるため、医系技官ら担当部署の官僚らには煙たがられていたのも事実だった。平たく言えば、彼らはそんな大変なことはできないし、したくもないのだ。結果的に田代氏は定年延長もなく、本省(厚労省)から、はっきり「一切の委員会を辞めてくれ」と言われたという。
感染研の多くのOBは、定年後もなんだかんだと権力や地位にしがみついて、行政政府の顧問や参与の肩書を長く維持したり、地方自治体の衛生研究所などの所長のポジションについたりして、影響力を残そうとする。中でも、定年のない研究所の所長や理事長などのポジションは、感染研の部長職以上の職員たちの争奪戦になった。
東京エリアから近い「川崎市健康安全研究所所長」が一番人気のあるポジションだった。都心に通勤可能ということは、政府の主要委員会のメンバーにも残りやすい。ただし、そんな人事は厚労省の政策にうまくリンクした人にしか回ってこない。厚労省が政策的に使いやすい人間を、うまく双方の持ちつ持たれつで、定年後も維持するポジションである。
田代氏は定年と同時に、厚労省から「感染研だけでなく、感染症関連の委員会のメンバーも辞めてくれ」と言われたのだから、その対極だ。「ああ、そうですか」と、彼の引き際は鮮やかだった。65歳の定年と共に一切の国内の公職から潔く身を引いた。地位や名誉には興味のない人間だった。もっとも、国際的な仕事は厚労省に人事権がないので続く。だから彼の情報網は今なお健全に機能し、霞が関や感染研を離れても感染症情報のアンテナは高いままであり、パンデミック対策、危機管理に余念はなかった。
私は、まずは冷静に情報収集だ、と思った。そして、それらの情報を速やかに感染症対策に関わる人たちと共有する。今の私は一大学教授の身であり、国の政策決定と関わる立場にはいないが、感染研時代には散々パンデミック対策をやらされて来た。その経験から、条件反射のように思考が回り出した。
これが新型のウイルスならば、少しでも早く対策を打たないと、マズイことになるかもしれない……。厚労大臣経験者も含め、主要な政治家には情報を入れるべきだろう。クリスマス・イブの表参道で、元上司からのメールを受け取った私は直感的に動き出していた。
世界中の研究仲間から
武漢で重症の肺炎患者の集団発生――たぶん、ウイルス感染症だろう。ならば、寒い冬の時期のことだ。SARSまがいのコロナウイルスか? いや、最悪はH5型・H7型の鳥インフルエンザからの新型インフルエンザの発生だ……。
H5N1型鳥インフルエンザは1997年から2000年代にかけて大きな問題となった。さらにその後、H7N9型鳥インフルエンザが人にも感染し、弱毒型から強毒型への変異ウイルスも出現していた。この2つの鳥インフルエンザからの新型インフルエンザが出てきたら、極めて重大な脅威になる。しかし、中国政府が2017年に国内の家禽の90%以上にこの2つの鳥インフルエンザのワクチンを接種し、その後はうまくコントロールできているようにも見える。今、H5N8型などの鳥インフルエンザの野鳥や家禽での発生はあるが、人での感染事例はまだ少ない。それを考えれば、今回はコロナウイルスだろうか……。頭の中で2、3種類のウイルスの候補が消えては浮かぶ。どのみち、大変なことになる可能性は高い。
2002年の冬、SARSが発生した時の感染研での緊迫したやりとりを思い出した。中国から原因不明の、抗生物質が効かない非定型性肺炎(マイコプラズマやクラミジアなどの、ペニシリンが効かない特殊な肺炎)の流行が発生したのだ。あれより厄介なウイルスだったら――。私はふらふらと表参道のメインストリートから横道に入ると、人込みを避けてビルの前へ座り込んだ。ちょっと呼吸が苦しい。ストレス性の期外収縮、不整脈だった。感染研に居た頃から、急に過度なストレスがかかると不整脈が出た。息を整えて……そう、ここでパニックにならず、息を整えて……そうしたら、やり過ごせる。
かがみこんで上半身の体重を左腕で支え、胸を押さえて肩で息をしている私のそばで、コンビニの入ったビルから出てきた人が足をとめた。
「あのう、大丈夫ですか?」スーツ姿の男性だった。
「ええ、ちょっと低血圧で」と、曖昧に応えた。
「ここは寒いですし、前にスタバがあります。そこで休んだ方がいい」
男性は私の脇を支えるようにして立たせると荷物をもって、目の前のカフェに座らせた。「少し休めば落ち着くでしょう。何もなしに座っている訳にはいかないか」と途中から独り言のようにつぶやく。ほどなくテーブルにホットティーのカップが置かれた。
「スタバだから、本来はコーヒーなんですが、お茶の方がいいでしょう。ここで少し休んで。ああ、いいです。おごりです。誰ってわからないと不安ですか? 何かあったら、僕はさっきのビルで働いていますから」と名刺をおいて去っていった。
彼の親切に何度も頭を下げながら、落ち着きを取り戻していった。クリスマス・イブの混雑しているスターバックスの中で、呼吸を整え、お茶をひとくち飲んだあと、パソコンをとり出して、世界中の研究仲間からのメールを次々と開いていった。
“中国の武漢で肺炎の患者のアウトブレイクが起きている。患者を実際に診た医師によると非定型性肺炎だ。重症患者は急激に肺炎が増悪するということだ”
“急速に肺炎が増悪する、抗生物質が効かない。といえばSARSの発生の一報もそうだった。SARSウイルス類似のコロナは自然界には存在している。SARSの自然宿主のコウモリの中には、SARSコロナウイルスや似たようなウイルスが維持されているってことさ。今回の肺炎も、またあのSARSの再来? だとしたら嫌な情報だ”
“SARSが出たのは鳥インフルエンザからのパンデミック・フルー(新型インフルエンザの世界的流行)が一番の危機管理問題となっていた頃だな。だから、僕は重症肺炎の患者発生と聞いて、H5N1型鳥インフルエンザが新型インフルエンザになった!と思って戦慄した。H5N1型なら、もうスペイン・インフルエンザを遥かに凌駕する健康被害になるからな。でも違った、予想外にもコロナだった!”
“そうだよな、あの両肺、真っ白のレントゲン写真はインパクトが強かった。とんでもなく急激に増悪して、薬が効かない、ならH5でしょうってね”
“僕もそうさ、インフルエンザA型が検査でネガティブって出たときには、ラボで絶句したよ。ほっとした半面、正直ウソだろう?って。じゃあ何だ、この病原体は?って。何がこんな重症肺炎を起こすのか? どんなウイルスか? そしたらコロナ、あっけにとられた”
“現実にあの重症肺炎を起こしたのがSARSコロナウイルスだったのだから、事実はサイエンスとして受け入れるしかない。コロナの印象が180度かわったよな。あのSARSの肺炎像は凄かった。急激に悪化する。恐ろしいね。でも、逆に僕は医者としては興奮したね、挑んでやるって。これに立ち向かってやるってね”
“SARSウイルスについてはこっち(人間)は薬もワクチンもできていない。それが、今、武漢でもう一回やってきたのだとしたら、危ないな、拡がるかな?”
“患者が増えてくるかは注視しないといけない。まだ、人から人へ行っているのかはわからないんだろう? コロナじゃないかもしれないし。まあ、新型インフルエンザでもコロナでも最悪だが。冷静に議論しよう。拡大してくると非常にまずい”
“もう、中国では当然ウイルス分離をしているはず。だとしたら、この2、3日で病原体は確定できるな。どのみち年内にはわかるだろう。情報は共有しよう”
こんなメールのやりとりがあったのは5日ほど前からであったか。もちろん、友人たちの国とは時差があるが。田代氏の情報は確度が相当に高そうだ。ひとまず話を聞いてみるしかない。
ウイルスの正体は
私は心を落ち着かせてから、田代氏に電話を掛けた。余程の事でない限り、メールかラインで済ませる相手だ。また、余程の事でない限り、田代氏も電話に出ることはない。お互いに非常に忙しいので、電話は避けるのが、この上司に対する部下一同の現役時代からの了解事項であった。だがこの日はワンコールで電話に出た。
「田代先生、この肺炎、人から人への感染伝播はもう、行っていますか? 病原体、ウイルスは何でしょうか?」
早口で問う私の言葉を遮るように、田代氏はまくし立てた。
「調査は入っている、すでに、とっくに。人から人に行っている可能性は十分にある、ウイルスはまだわからない! が、僕はSARSウイルスか、その類似のコロナだろうと思っている。ゲノム(遺伝子全情報)を確認中だ。すぐにそのデータは出てくる、一両日内に」
怒鳴るような元上司の言葉が終わらぬうちに、さらに訊ねる。
「SARSってことは、これはコロナですか! 前もこの時期で、非定型性肺炎でしたね?」
「SARSウイルスは、そもそも同じようなウイルスがコウモリにいるからな。それが人に来たのかもしれない。どっちにせよ、シークエンス(遺伝子解析)待ちだ。人への伝播効率もまだはっきりしない」
それだけ伝えられ、電話はプツリと切れた。田代氏の「僕はSARSウイルスか、その類似のコロナだろうと思っている」という言葉は真実だろうと思った。すでにインフルエンザは否定されているのだろう。新型インフルではないってことだなと受け止めた。
問題は、どんなコロナウイルスかということだ。
コロナはもともと40種ほど見つかっており、動物が主体の病気だった。風邪コロナウイルスは4種あるが、人の風邪コロナは大した病気ではなかった。だから、SARSがコロナウイルスが原因だとわかったとき、ウイルス学者は驚愕したのだ。まさに想定外だった。あれが再来するというのか。
街はクリスマスムード一色だ。半地下のスターバックスのウィンドウから見上げる表参道の街路には、相変わらず多くの人が行き交う。とにかく、電話やメールの情報をとりまとめて残す。そんな記録の仕方は、厚労省感染研時代から染み付いた仕事の習慣だった。
レッドにグリーン、ゴールドの玉やリボンで彩られ、星とベルで飾られたツリーがクリスマスを演出するカフェの一角で、パソコンに情報を整理し記録していった。その内容をすぐに複数のサーバーに保存し、信頼できる人間にも即座に共有する。これもまた習慣だった。
今はSARSが流行した2003年当時とは全く違うレベルの解析能力のある装置、次世代シークエンサーがある。患者からウイルスのサンプルが採れれば、すぐにゲノム解析の結果は出るはずだ。この10年で中国の研究所も研究者もレベルが飛躍的に上がっている。米国など海外の一流の大学や研究所へ留学させた研究者らを破格の好待遇で呼び戻し、国内の研究機関ではハイレベルな研究成果を挙げ続けている。
それを思えば、この数日以内に結果が田代氏経由でやってくるのではないか? いや、もう現地では結果が出ているだろうし、彼の情報ネットワークなら明日にも知れるかもしれない。公式発表は政治的な思惑もあるから遅れるにしても。アンテナを高く張っているからこそ事前の対策が打てる。感染症対策はスピードが命だ。
それにしても、と改めて思う。SARSの再来は嫌だ。高速大量輸送時代の現代だから1ヵ月もすればパンデミックにもなり得る。田代氏の予測通り、SARSなのか? SARS類似のコロナウイルスか? これまで予測を外したことがない彼の鋭さも私を怖がらせた。
堂々巡りの思考を繰り返しながら、カフェの一角で深く息を吐き、過去に思いをはせた。
2 留学時代の財産
2000年前後、私はドイツのアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の奨励研究員として、ドイツ・マールブルク大学医学部ウイルス学研究所に留学していた。
国立感染症研究所の研究員は、その多くが2年程度の海外留学に派遣される。圧倒的に多い留学先は米国で、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)やNIH(アメリカ国立衛生研究所)や大学などだった。当初、私に提示された留学先も同様だった。
しかし、私はヨーロッパの大学への留学を強く希望した。もともと医学史や公衆衛生学の発祥の歴史などを学んでいたこともある。医療について長い歴史のあるヨーロッパ、その伝統や文化、そして公衆衛生学の原点などに触れることにも心を惹かれていた。フランスのパスツール、ドイツのロベルト・コッホらの足跡の残る大学や研究所に行きたいと思った。
感染研の上司らは難色を示した。「CDCやNIHのどこが不満か?」と言われた。確かに米国留学なら、行っただけでステイタスが上がる。ましてや、いずれも一流の研究所だ。イメージとしては垂直移動の留学先である。一方、ドイツ留学であるならば水平移動にしかならないだろう。しかし、結論として私は留学先にドイツの古い大学、マールブルク大学医学部ウイルス学研究所を希望した。この研究所のボスには、シドニーの国際学会で田代氏を通して紹介されていた。
帆船を連想させるような外観で知られるシドニーのオペラハウスで、学会のレセプションがあった。そのような場で田代氏は自分の若い部下らを海外の有名教授にどんどん紹介しては、プレゼンをさせた。若い研究者らにとっては、留学先を見つけるのに国際学会は恰好の場だった。上司たちにとっては、優秀な若い研究者をハンティングする場でもあったろう。
ドイツ留学を選んだ私に対して、田代氏は「それならば」と、ドイツのアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の奨励研究員に採用されることを留学の条件としてきた。フンボルト財団は別名ドイツのノーベル財団と呼ばれる難関だ。事実、フンボルトで留学を果たした研究者の中から毎年のようにノーベル賞受賞者も出ていたし、フンボルトに選ばれた研究者で大学教授以上にならなかった(なれなかった)人間はいないと言われる。
そのフンボルトに通るならドイツ留学を許すというのは、田代氏らしい非常に厳しい過酷な条件だった。実は、田代氏本人が20年ほど前にフンボルト財団の奨励研究員に通って、ドイツのギーセン大学に留学をしている。世界のウイルス学者から「偉大」と見なされる彼自身と同じレベルの条件を部下に課してくるのか。私は部長室の田代氏の前で直立不動のまま、床に目を落とした。怒鳴り声が響いた。
「トライしないで、書類も出さないで、初めっからダメだと決めてかかるのは、不戦敗だ。まずは出してみろ、しっかりしろ」
田代氏はよく怒鳴る。北里柴三郎のあだ名が「雷おやじ」だったのと同じかもしれない。思えば、北里柴三郎も内務省からドイツのロベルト・コッホの研究所へ留学した。日本の感染症研究の基礎は、もともとドイツなのだ。森鴎外もドイツ留学だった。志賀潔もそうだし、秦佐八郎もドイツでサルバルサンを開発したではないか、そんなことを矢継ぎ早に思い出した。しかしそれは明治時代のことだろう、今なら米国ではないのか? そんな声も聞こえてくるようだった。それらを振り払うように、不戦敗よりはマシだろう、フンボルトにトライしてみようと私は決意した。
さまざまな書類を提出すると、予想外にもすんなり合格することができた。こうしてアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の奨励研究員としてマールブルク大学医学部ウイルス学研究所に留学した。まず2ヵ月間ゲーテ・インスティトゥートに叩き込まれて、ドイツ語を徹底的に学ばされる。奨励研究員の採用にはドイツ語の審査もあったが、私は大学院の修士課程、博士課程の入学試験でともにドイツ語を選択しており、これが幸いしたのだろう。
この奨励研究員は世界中から採用され、給料も研究費も支給される。首相官邸に呼ばれ、首相と面会し、官邸でのパーティーもある。また、ドイツ国内を2週間、奨励研究員の仲間たちとバスでグループ旅行するという企画もあった。これはそれぞれの母国へ帰国した後もドイツ国家・国民との親善と交流を続けるために、ドイツをよく理解してもらおうという意図だった。
この留学で後のキャリアの財産となったものの1つが、フンボルト奨励研究員で知り合った世界中の研究者とのつながりだった。フンボルトでは医学やウイルス学だけではない、文系、理系のいろいろな分野から選ばれた業績ある研究者と交流することができた。帰国後、十数年を経て、それらの友人たちは母国で公職の高い地位につき、責任とともに大きな影響力、情報網も持つようになっていた。
私の留学時代は日本人は少なく、中国勢が多くを占めていたが、それは今後の世界の動きをドイツ国家が予見しての思惑もあるとささやかれていた。
フンボルトで非常に仲がよくなった女性研究者・チャンも中国人の農学の研究者であった。チャンの夫はウイルス学の研究者であるが、米国に留学中で、彼女はドイツ、子供は中国で夫の親族と暮らしていた。
彼女に小さな男の子の写真を見せてもらいながら、「なぜ、ドイツに連れて来なかったの?」とたずねると、
「今は、私はここで集中して業績を上げたいの。そうしたら、今度は米国に留学できるかもしれない。フンボルトだけでもポジションはもらえるけどね。でも、もっと上を目指すことも捨てたくない。結果として、この子も幸せになれるのよ」
この留学を為し遂げて帰ったら、中国で良いポジションが得られる。フンボルトでは貯金もたくさんできる。だから、この子にも十分な教育ができるのだと話していた。チャンは精力的に論文を書いていた。
彼女の研究室のあるボンからドイツ鉄道に乗っての帰り道、車窓に広がる異国の黒い森を遠くに望みながら、私は、自分にはないチャンの強烈なハングリー精神に匹敵するような情熱をもちたい、と思った。
感染症が起こした「国の不幸」
そんな思いを抱いたのは、ドイツの感染症の歴史を痛いほどに感じていたからかもしれない。地続きのヨーロッパでは、兵士が攻め込んでくるのと同様に病原体もやってくる。さらに、中世からペストの流行を10年から15年おきに繰り返してきたこの地域では、感染症に対する危機意識は日本人より、はるかに鋭敏だった。
私の働くマールブルク大学医学部の前には、ハンセン病患者の救済に力を尽くしたエリザベート王女ゆかりの教会がある。教会の先から旧市街へと向かう石畳を一緒に散歩しながら、同僚のドイツ人男性の研究者・ウォルフガングが言っていた。
「この石畳の下には、ペストの集団埋葬地がある。何万もの遺体が中世から近代までの歴史と共に埋まっている。決して石畳を掘り返してはいけない。悪魔が住んでいるから」
私が恐々と足元に目を落とすのを彼はちょっと気の毒そうに見ながら、「ペスト菌は死んでいるだろうけど魂は生きているよね。サイエンスではないけれど、そう思う。ペストという言葉には、ヨーロッパでは大量死という意味もあるんだ。流行したら、大きな壕を掘って遺体を入れる、少しだけ土をかける、その上にまた遺体が投げ込まれる。その繰り返し。ラザニアみたいな埋葬風景は戦争だけじゃないさ。ウイルスや細菌は人類の敵なんだ」と言った。
彼はインフルエンザの研究者だった。ドイツ人の朝は早い。早朝から研究室で実験をしている彼によく付き合った。私もまた、時間を惜しむかのように学んだ。研究のほかに、ドイツ語だけでなく、ロシア語にも手を出した。ベルリンの壁が崩壊した後で、ロシア人研究者も多く居た。だから、実践的にロシア語を学ぶには好都合だった。厚労省にはロシア語ができる人がいないからロシア語を学べと、田代氏からは露英辞典が送られて来た。
私は、ウォルフガングがインフルエンザウイルスに執着し、没頭するように研究するのを不思議に思った。この研究所ではエボラウイルスやマールブルクウイルス、麻疹ウイルスなどさまざまな病原体の研究が盛んなのに、彼はインフルエンザウイルスのみにある種、偏執的とも思えるほどに集中していた。もちろんインフルエンザの研究は主流ではあるけれど、エキサイティングな研究はもっとあるじゃない、そんな気持ちで訊ねたことがある。
「なぜ、そんなにインフルエンザだけに固執するの?」
ウォルフガングはレンガでできた実験台の上にピペットマンを置くと、即座に答えた。
「ドイツ、この国の不幸はインフルエンザウイルスが作ったからさ」
私はため息を漏らした。「了解、わかった、そうかもしれない」
1918年、第一次世界大戦のさなかに、スペイン・インフルエンザ(通称・スペイン風邪)が発生した。それは鳥インフルエンザが遺伝子変異を起こして、人から人に効率よく伝播する能力を持ち得た新型インフルエンザであった。このスペイン・インフルエンザが、パリを射程内に入れ、勝利を目前としていたドイツ軍に侵入した。燎原の火のごとく広がる新型ウイルスに、兵士が次々と倒れていった。補給線もずたずたに絶たれた中で、兵力を増した連合国軍にドイツ軍は敗れた。敗戦後、ドイツ国家は莫大な戦争賠償金を取られ、事実上、ドイツマルクは紙くずになった。
これらの問題を全て解決できるとして、台頭してきたのがヒトラー率いるナチ党であった。そのまま第二次世界大戦へと突っ走っていく。ウォルフガングにしたら、スペイン・インフルエンザさえなかったら、祖国の運命も違っていた、と思うのだろう。スペイン・インフルエンザが大きな歴史の転換点であったことは事実だ。
感染症の流行は時に世界史をも動かし、文化も政治も社会も芸術も変える。それが大陸では当たり前になっている。島国で鎖国も長かった日本は、感染症についてはラッキーな国だったのだ。「日本は地震には敏感だけど、感染症には不感症だよね」と笑うウォルフガングの言葉が胸に刺さった。そうかもしれない。でも、21世紀のグローバル化した社会ではそんな甘さは通用しない――。私が自分の研究対象としてパンデミック対策を考える、そのきっかけとなった会話だった。
ドイツの冬は寒い。マイナス20度になると研究所の脇を流れるラーン川は厚い氷に覆われた。そのラーン川を美しいフォルムでスケーティングしながら、ウォルフガングは通勤してきた。ドクターであった彼は、後にパンデミック対策で国の指揮を執るような重鎮になっていく。コロナウイルスをめぐるクリスマスのメールの送信者の一人は彼であった。
そして、中国からもたらされる情報の1つは、ボンの友人チャンの夫のドクターによるものだった。私にとって、中国の主要な研究者につながりが持てたことは、後にH5N1型やH7N9型鳥インフルエンザやSARSウイルスなど中国が主要な情報を握る感染症に対応する上で役立った。
マールブルク大学医学部ウイルス学研究所には、各国の研究者が集っていた。いろいろなウイルスの研究者仲間に出会った。“バイオセーフティーレベル4”という最高レベルの病原体封じ込め施設もあり、エボラウイルス始め、最も危険とされる病原体も扱っていた。エボラウイルスやマールブルクウイルスなどの出血熱の研究者はアフリカからもやって来ていたし、「ボンジュール」の挨拶で始まるフランス人グループの研究室もあった。まさに国際的な研究所であり、あらゆるジャンルのウイルスを扱う研究者がいたのは刺激的かつ有益だった。
やがて、ここを拠点にして複数のネットワークができあがり、留学後も情報交換が続いたのだ。特に12月のクリスマスシーズンは毎年、「メリークリスマス!」というメッセージも多くやってくる。ただ今年は、感染症関係の人間は誰もメリーとは書いてこない。中国湖北省武漢での“抗生物質の効かない原因不明の肺炎患者の発生”の情報が流れ始めたからだ。
3 かつての日本の幸運
どんなネットワークにせよ、情報というものは玉石混淆だ。全部の情報を盲目的に信じる訳ではない。だが、私は自分のネットワーク情報ですでに不安に苛まれていた。
それに加えて、田代氏が、彼の情報群から内容を精査した上で、武漢での肺炎患者の“集団発生”を部下であった自分に知らせてきたことで、不安が怯えに変わった。
田代氏は間違いなく本省、厚生労働省の感染症担当・医系技官にも連絡をして、緊急の対応を要請しているだろう。そして、論拠となる、もっと詳細なデータやメールを入手して本省へ転送しているだろう。そういう彼の行動を感染研時代から見てきた。
ただ、大丈夫だろうか? 腕時計を見た。私の時計は仕事柄、主要都市の時差も表示される国際時計だ。この時計で現地時間を確認して研究者へアポを入れる。
ちょうど、ヨーロッパはクリスマス休暇に入っている。さらに日本の役所はこれから年末年始の休みだ。いや、ことは危機管理だ。田代氏から連絡が入ったら、厚労省の担当者はすぐ応答するはずだ。きっと、つながらないなんてことはないはずだ。
感染研時代も現在も、感染症対策をやっている私は24時間、土日関係なく、仕事はONの状態にある。私にとって、感染症・ウイルスは単なる研究テーマではなく、流行を抑止する実践的な危機管理が本質である。ちゃんと危機意識を持って職務に臨んでいれば、国立感染症研究所でインフルエンザウイルス研究センター長を務める長谷川秀樹氏は対応するだろう。
メガネの奥の目がいつも笑みを浮かべている長谷川氏の温厚な顔を、私は思い出した。感染研のインフルエンザウイルス研究センター長という同じポジションであっても、激しさと厳しさとで、時に部下を怒鳴り散らしていた田代氏とは真逆の、穏やかな長谷川氏の顔を。
パンデミック、それも世界に拡大して同時大流行するとなれば、まさに国家の安全保障問題だ。長谷川センター長はこのコロナウイルスのパンデミックの可能性に対し、どういう初期対応をするだろうか。
長谷川氏は、SARSが発生した2002年11月、ウイルス分離や同定で緊迫した実験室の現場にはいなかった。当時は田代氏の部下ではなかったのだ。だから、田代氏が指揮した、中国や台湾などSARS発生諸国とのやりとりやWHOとの交渉の現場を見ていない。H5N1型鳥インフルエンザからの新型インフルエンザ、この強毒性(高病原性)鳥インフルエンザ問題のさなかにも現場にはいなかった。そもそも長谷川氏は“病理の人”なのだ。危機管理が叫ばれた1997年から2008年までの、パンデミック対策が本当に過酷な時期を、彼は経験していない。
田代氏はプロ中のプロであり、「世界の数億の命を背負う男」と国際的に言われてきた研究者だ。田代氏の直属の弟子であったことのない長谷川センター長に、その発言の重さが響けばいいのだが……。
まさか、「年明け、休み明けに本省と協議します」なんてことを田代氏に言ったりはしないだろうか。もしも、私がセンター長のポジションにいるなら、武蔵村山の研究所から霞が関まですっ飛んで行く。いや、大臣に電話を掛け、直接話をするだろう。トップに事態を伝え、役所の担当部局に降ろしてもらう。緊急事態時にはトップダウンで行かないと間に合わない。下から上げていったら、その間にウイルスが国内に入ってしまうからだ。
2003年、SARSウイルスは幸いにも日本には侵入しなかった。結果的には対岸の火事に終わり、日本人の多くに忘れ去られている。
当時の厚労省の医系技官も、もう、そのほとんどが別の部署に異動したり、退職して天下りしている。田代氏の主要な弟子たちも、多くは大学の教授職となって感染研を出ているか、定年退職をしているかだ。SARSの経験が、もはや現担当者に受け継がれていない可能性は高い。つまり霞が関からも、SARSのような新しい呼吸器感染症の侵入や流行に対する緊張感や危機意識が失われているのではないか。それは地方自治体の健康保健部局でも同様だろう。
しかし日本にSARSが入ってこなかったのは、紙一重の“幸運”に過ぎない。2015年、韓国では中東から帰った60代男性からMERS-CoVが国内に持ち込まれ、MERS(中東呼吸器症候群)の流行が発生した。それは病院、医療機関における大規模な院内感染に発展して大きな問題となった。このMERSも日本へは入ってこなかった。たまたまだ。韓国で起こったように、日本にMERSウイルスが侵入してパンデミックが起こってもおかしくはなかった。
さらに、2009年のH1N1型新型インフルエンザのパンデミックは、この新型インフルエンザウイルスにそもそも大した病原性がなかったので、健康被害も世界的に小さくて済んだ。それまで次なる新型インフルエンザと想定され、危機管理対策が取られていた高病原性(強毒型)のH5N1型鳥インフルエンザではなかったのだ。日本は、この「豚フル」とも呼ばれた新型インフルエンザでも、大事には至らなくて済んだ。最悪のシナリオを想定した対策準備ができていたことによって、犠牲者数を大幅に減らせたためでもある。こうした準備対応計画を練り、実行に寄与していたのも田代氏であった。
そんな直近3つの感染症流行をニアミスでやり過ごせた日本は、その幸運のために、感染症の危機管理の意識も緊張感も緩んでしまっている可能性がある。もしも、武漢の肺炎が人から人にどんどんうつる能力を獲得した新型ウイルスであったなら、そしてあの重症肺炎をもたらしたSARSの再来だったなら、日本は厳しい対策を取れるのであろうか。それが私の最大の不安だった。
かつての3つの幸運が、今のリスク評価の楽観視につながりはしないだろうか? 政治や政策は前例を重視する。特に霞が関では、前例がないことは実行し難い。さらに前例がこの程度であったとなると、それを踏襲しがちである。これまでの感染症対策を眺めてみれば、緩い政策に流れがちで、危機管理としての厳しい対応はでき難い……と私には見てとれた。
4 中国の公式発表
イブの夜から3日後の12月27日朝、ずっとメールの情報を注視していた私は、とうとう居た堪れない思いで田代氏に電話を掛けた。ヨーロッパは26日の夜であり、その日の情報が来ている時間帯ではないかと想像した。
この時も珍しく、田代氏はすぐに電話に出た。そして間髪いれずに発せられた言葉は、
「コロナウイルスだ! ゲノムシークエンスが出てきた。ただ、SARSではない」
「SARSではない、新しいコロナウイルスってことですか?」
「SARSウイルスとホモロジー(相同性)は高い、でも違うウイルスだ」
「病原性は? 人から人に連続的な伝播はあるんですか?」
「人から人は当然あるだろう、だが、どのくらいの効率で感染伝播するのか、市中で連続的に行くのかどうか、それはわからない。これからオフィシャルに中国政府から発表があるだろう」
それだけで電話は一方的に切られた。
その4日後の12月31日、やっと中国からの公式発表が出た。病原体のコロナウイルス分離、同定されたウイルスの遺伝子シークエンスの公表はさらに遅く、2020年1月10日であった。
厚労省は1月5日になって、次の内容を発表、ホームページに掲載した。中国政府の発表時点で報道の記事には出ていたが、年末年始の喧騒の中で、このニュースを注意深く見る国民は少なかったであろう。
「Disease outbreak news 2020年1月5日(厚労省検疫所掲載)
2019年12月31日、中国湖北省武漢市で検出された病因不明の肺炎(原因不明)の事例についてWHO中国事務所に通知されました。2020年1月3日現在、病因不明の肺炎患者、全部で44人が、中国の国家当局によってWHOに報告されています。報告された44例のうち、11例は重症であり残りの33症例は安定した状態です。報道によると、武漢にある関係する市場は環境衛生と消毒のために2020年1月1日に閉鎖されました。
原因物質はまだ特定または確認されていません。2020年1月1日にWHOはリスクを評価するために当局にさらなる情報を求めました。
当局はすべての患者が武漢の医療機関において、隔離されおり、治療を受けていると報告しています。臨床徴候と症状は主に発熱であり、呼吸困難の患者も数人います。胸部レントゲン写真では両側の肺の浸潤影を示しています。
当局によると、患者のなかには、華南海産物市場で店舗などを運営していた方がいるのこと。中国の調査チームからの予備的な情報によれば、ヒトからヒトへの伝播の重大な証拠は認められておらず、医療従事者の感染も報告されていません」(原文ママ)
2019年12月31日の中国政府の公式発表は、「ヒトからヒトへの伝播の重大な証拠は認められておらず、医療従事者の感染も報告されていません」というものだった。また、この時点の発表では病原体については触れていない。であるから、もちろん病原体ウイルスのゲノムシークエンスの情報は公開されなかった。SARSに近いが別のコロナウイルスであることも、いや、コロナウイルスであることすら公表されていなかった。
私は2002年に発生したSARSの時に、中国の徹底的とも感じられる隠蔽を感染研の現場で経験していたので、まずはこのくらいの発表であろうと思った。あのとき、中国の情報開示の遅れは世界各国から大きな非難を浴びた。今回は武漢での肺炎の集団感染は認めている。公式発表の翌日、2020年1月1日から肺炎患者の集団感染の起こった市場は閉鎖された。
さらに「重大な証拠は認められておらず」ということは、現象として人から人への感染はあるのだろう、と判断できた。感染が点であるのか、線となってつながっているのか、面で広がっているのか、その証拠はないが、集団感染が起こっていることが公式になった。
本当に海鮮市場からか?
ウイルスや細菌などの病原体は、人が動く距離だけ動き、感染症を拡げていく。感染者が体内に病原体、この場合はSARSと高い相同性のあるコロナウイルスを持ち、感染者が動くことで拡がるのだ。
武漢の街を思い浮かべた。1100万人の人口を持つ、東京並みの大都会。交通網の鉄道や道路のハブともいえる地理的な立地と役割を持つ要衝都市。人込み、喧騒、人と物の流動。遥か昔であるなら武漢の一地域で発生した風土病的な感染症で済んだとしても、今の武漢ではそれでは済まない。コロナウイルスはすぐに拡がるはずだ。私はすぐに武漢とその周辺の都市からの日本への直行便の数、移動人数を調べ始めた。在留邦人の数、さらに武漢はこれだけの大都市だ、進出している日本企業も多いはずだ。
田代氏は人から人へ行っている可能性を指摘していたが、公式には人から人への感染伝播の確証はないという言い方だ。微妙だが、このウイルスは、濃厚接触などの条件によっては人から人には伝播するのだろう。ただ、今は新型インフルエンザのようにどんどん連続伝播する能力を獲得している訳ではない――ということなのか。
もしくは、人での流行そのものをまだ公表していない、ということか。いずれにせよ、要警戒だ。コロナウイルスはそもそも動物のウイルスである。犬や豚や猫のコロナウイルスは獣医学の分野で研究されている。しかし、ときにコウモリなどの動物のコロナウイルスが、人に感染して病気を起こすことがある。動物や人への偶発的な感染を起こしているうちに、遺伝子の変異が起きる。遺伝子の変異はアトランダムに起こる訳だが、たまたま人に感染しやすい変化を起こしたウイルスが誕生すると厄介だ。
人に感染しやすいウイルスが発生して、ある人の体内で増える。ただ、そのウイルスはまだまだ人への伝播の効率は悪い。しかし、密な接触などで次の人間に感染することを繰り返すうちに、さらにウイルスが変異していく。人の体内で増えやすく、人への伝播力が強くなるような変異が起こった場合、偶発的な感染を繰り返していくうちに、さらに効率よく人から人への伝播をするウイルスが発生する。
こうして、動物のコロナウイルスが、人へ順化していく。こうなると人型ウイルスとして集団感染が起こる。さらに集団感染の規模はどんどん大きくなっていく。だから、新型ウイルス発生時は早期発見、そして完全なる封じ込め策を取ることが必要になるのだ。
現状、濃厚接触で長時間、密にいない限りは感染しないとなれば、まだ封じ込めもできるかもしれない。しかも、中国である。中国はSARSのときも北京を封鎖するという強硬な措置までとって、流行を収束させた経験がある。ただ、冬か……とひっかかる。
四季がある温帯地方の国では、冬はコロナウイルスが流行りやすい。逆に冬であるから、数が増えて感染者が見つかってきたのかもしれない。ある程度の人数の感染が出てこなければ、感染症を見つけることは難しい。肺炎はよくある疾患だ。それが集団であったからこそ、見えたということだろう。その集団の規模が問題なのだが。
もう一つ、海鮮市場ということにも、ひっかかっていた。ライブマーケットだ。海鮮というけれど、中国のライブマーケットはさまざまな動物が生きたまま売られている。この市場にも爬虫類、鳥類、哺乳類などが数多売られる一角があるのではないか?
SARS類似のウイルスというならば、自然宿主はキクガシラコウモリか? コウモリは中国、アフリカなどで広く食用にされる。コウモリが売られていることも想定される。ならば、そこで、コウモリから近くの檻に入った動物の糞尿等による飛沫感染・接触感染が起きて、まず偶発的な感染が起きたのかもしれない。これが繰り返されて、ウイルスがこの動物に感染しやすいように変異すると、中間宿主動物ができあがる。
さらにその中間動物を、人が調理にさばく。そして、最終的に食すというプロセスの中で、ウイルスに触れる、飛沫を吸い込む等をして、人が感染したのではないか。もちろん、自然宿主が強く疑われるコウモリ自体に触れる、さばく、食すためのプロセスで人が感染したことも十分考えられる。
ただ、「ライブマーケットで発生」という状況が、あまりにも出来すぎた設定のようにも感じられた。市場で感染者が出たという現象は、動物(野生動物の肉=ブッシュミート)から人への感染のイメージがわきやすい。動物から偶発的に人へ、それを早期に発見、対応という理屈がいかにも成立しやすい。本当なのだろうか? 短絡的にコウモリから人、あるいは中間動物から人への感染だと信じていいのか……と、引っかかっていたのだ。武漢の街中ですでに感染が起こっていて、その感染者がたまたま市場にやってきていた、ということもあるのではないか?
いや、ここで楽観視してはいけない。危機管理としては、すでに市中感染が起こっていて、寒い冬のこの時期にインフルエンザと誤診されながら、流行しているという可能性を考えるべきではないか。莫大な人口を抱える中国だ。たった20人や30人の肺炎クラスターで、WHOに報告などするものだろうか。
あの広大な大地、莫大な人口、混沌とした街。インフルエンザだと思っていた医者たちが、やっと異型肺炎に気がついた。それで病原体までを確認できたのが、まずは27人。背景には、もっと多くの患者がいるはずじゃないのか。いや、いると考えた方が自然だろう。呼吸器感染症の流行る冬の時期に、新しい肺炎がそんな少数例で見つかる訳はない。余程の事が起こっていて、だから表に出てきたと考えた方がいい。
田代氏からの情報は厚労省に入っているはずである。厚労省はこの武漢の肺炎にどんなリスク評価をするのだろうか? まずは武漢や湖北省からの直行便を止めるのか? 中国からの邦人帰国をどうするのか? とにかくそれらの準備をすぐ開始するべきだと思った。
厚労省の初期対応
田代氏は、武漢の肺炎をその症状などからSARSの再来か?と危惧した。しかし、ゲノム情報を詳細に見ればSARSではなかった。SARSコロナウイルスに非常に類似した別のウイルスであった。
もちろん、SARSでなくとも重大案件である。田代氏はそもそも政治を嫌い、自分から政治家に向けて動くことがなかった。だから、感染研在任中からその役回りは部下の私が担ってきた。そして必要とあれば面会や説明のセッティングもしていた。だから私はいろんな政治家の知遇を得ていたし、厚労族の田村憲久氏や川崎二郎氏など過去の大臣たちなら厚労省時代に仕えてきたので、信頼関係が築けており、すぐに電話して直接説明し、対策を進言することもできた。だが加藤勝信厚労大臣とは面識がなく、直接何かをできる手立ては、私にはなかった。
本来なら、米国CDCの情報もあるはずだった。しかし中国の北京にあったCIAのオフィスは、トランプ政権になって引き上げられていた。だから、CDCを通じて日本に入るはずの、CIAからの武漢の肺炎に関する情報もなかったのだ。結局、2019年12月31日の中国側からのオフィシャルな声明が第一報になってしまった。
中国・武漢当局がWHOに肺炎のクラスターが発生していることを報告したのを受け、2020年1月1日、WHOはこの肺炎を起こしている未知の病原体の流行に備えて対策本部を設置した。そして1月4日に、ようやくWHOはSNSで国際社会に発信、“武漢において肺炎のクラスター発生、死亡者なし、病因は分析中である”としたのだ。
1月6日、厚生労働省健康局結核感染症課は日本医師会に向け、「中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」という事務連絡を出した。
中国湖北省の武漢で、通常の抗生物質が効かない肺炎の集団発生の報告があった。詳しいことはわかっていない。武漢から帰国して肺炎などの呼吸器症状がある人を診る場合には、感染対策をしっかりやってほしい。さらに届出を義務付けられている医療機関においては、武漢滞在歴があって、このような原因不明の肺炎患者を診た場合には、速やかに保健所を通して報告してほしい。これは国立感染症研究所で調査を行う。
概略としては右のような内容で、田代氏や研究者仲間とのコミュニケーションで得られた情報以下の、通り一遍の内容でしかなかった。私は肩透かしをくらったような気持ちだった。患者についての報告を求める疑似症サーベイランス(定点機関)は、もともと東京五輪での海外からの輸入感染症対策として構築されたもので、それに乗っかったかたちだ。武漢の滞在歴があって変な肺炎を起こした患者が出たら、感染防御して診て、保健所を通じて報告してくれ、というだけでいいのか。
1月5日の厚労省検疫所からの発表でも「すべての患者が武漢の医療機関において、隔離されおり、治療を受けている」「臨床徴候と症状は主に発熱であり、呼吸困難の患者も数人います。胸部レントゲン写真では両側の肺の浸潤影を示し」「患者のなかには、華南海産物市場で店舗などを運営していた方がいるのこと。ヒトからヒトへの伝播の重大な証拠は認められておらず、医療従事者の感染も報告されていません」(原文ママ)というものだった。
報道の方が武漢の肺炎に対する反応は早かったが、この厚労省からの発表をもって、新聞やテレビ各局の報道が本格的に始まった。
5 指揮官のタイプ
勤務先である白鴎大学の広報を通じて、一通のメールが届いた。テレビ朝日系番組の出演依頼だった。テレビ朝日「ワイド!スクランブル」と「グッド!モーニング」がコロナ報道の口火を切ったのだが、私への依頼は当然ながら、「武漢の海鮮市場で集団発生したという原因不明の肺炎」についての解説であった。
コロナ報道における私の最初の生出演は2020年1月7日の「ワイド!スクランブル」となった。橋本大二郎キャスターの時代から何度も呼ばれている番組だ。私は後に「コロナの女王」と揶揄されるようになるのだが、元々15年前からテレビ等のメディアで感染症の解説を行っていた。感染研に在籍していた頃はNHKが多く、「ニュースウオッチ9」には何度も出演し、その時々で問題となっている感染症を説明した。感染研を辞めた後は民放が増え、中でも「ワイド!スクランブル」への出演は回数を多く重ねていた。抜群のアナウンス力を誇る大下容子アナが進行するこの番組は、かねてより自分にとって馴染みやすい番組だった。
そしてこの日から毎日、テレビの生放送に出ては、後に「新型コロナウイルス感染症」と呼ばれることになる、武漢発のウイルス性肺炎の感染症について解説し続けることになる。
コロナ報道の初出演の日、テレビ局からの車が迎えに来た。私は黒のワンピースを着て、パソコンを開いて研究者仲間からの最新のメールに目を通し、当然ながら新聞各紙、さらに海外の報道も確認する。しかし、2020年の年明けからのこの数日間、田代氏からの情報が届いていなかった。年末の「SARSコロナウイルスに似たゲノムシークエンス(遺伝子情報)を持つ新しいコロナウイルスだ」という情報で止まっていた。1月7日時点でも、中国はまだSARSに似ているというウイルスの遺伝子情報を公表していなかった。
田代氏に電話をしても出なかったが、着信記録は残るはずだ。田代氏は厚労省の医系技官に対して、武漢の新しいコロナウイルスについて説明し、そのリスク評価を詰めている段階ではないかと私は考えた。だから忙しくて電話に出られないのだろう。医系技官の仲介で、大臣への説明もあるのではないか。しかし、この予想はすぐに裏切られた。
というのは、どうやら厚労省でのリスク評価や政治家への説明は、田代氏ではなく、後に専門家会議や分科会の主要メンバーにもなる岡部信彦氏がその役を担っていたようだ。それはこの後、1月16日に出された厚生労働省感染症情報管理室からの「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について」というプレスリリースから類推できた。そこには「現時点では本疾患は、家族間などの限定的なヒトからヒトへの感染の可能性が否定できない事例が報告されているものの、持続的なヒトからヒトへの感染の明らかな証拠はありません」とあった。
「人から人への持続的な感染の明らかな証拠がない」という、遠回しながらも「人から人に連続してうつっているわけではない」と印象づけられる内容に、ホッとする国民は多かったであろう。
しかし、どこにそんな証拠がある? 中国側の説明をそのままに受け取って対応するならば、後で取り返しのつかないことになる可能性がある。感染症対策は、早期開始、徹底対応、短期決戦が鉄則である。田代氏であれば、こんな甘いコメントは出させない。彼はSARSの時も鳥インフルエンザ問題の時も、中国の情報隠蔽に煮え湯と泥水をさんざん飲まされてきた。この武漢での肺炎についても、「SARSが再来したのかと思った」という田代氏の言葉からして、人から人への伝播は当然あると思って備えろと主張したに違いない。
彼らは「調整型」を選んだ
要は、「新興感染症」「新型ウイルス」を危機管理と捉えられるか否か、なのだ。
岡部氏は調整型で、ネゴシエーションに長けた、平時の指揮官である。一方、田代氏はサイエンスに立脚した、緊急時に必要な指揮官である。2人は感染症研究所で同時期にセンター長を務めていた。
サイエンスよりも政治的落としどころを重視し、調整力に長けた人物と、サイエンスを信奉し、調整には関心を持たない人物という両極端のセンター長が、感染研には同時にいたのだ。この時代は長かった。私はその時代をずっと経験し、麻疹と風疹のワクチン問題でも、SARS対応でも鳥インフルエンザ問題の対応でも、極端な温度差の漂う現場を見てきた。特にH5N1型鳥インフルエンザからの新型インフルエンザ問題では、同じ感染研でセンター長の肩書を持つ公務員が真逆のリスク評価をしていた。
田代氏はウイルス学で最悪のシナリオまで想定して、健康被害をいかに小さくするかという対策を提言していたのに対し、岡部氏は「まあまあまあ、そういうこともあるかもしれないが、パンデミックはめったに起こりませんから」と、ウイルス学やサイエンスの論拠はないけれど、行政上の落としどころを心得て、田代氏の発言の火消しをしていた。結果、対策は行われないままになる。
厚労省は調整型の岡部氏を重用してきたのちに、定年のない川崎市健康安全研究所所長に据えた。最年長の岡部氏の意見は厚労行政に強く反映されてきたであろうし、裏を返せば、彼は厚労省の担当者の意に沿った意見を常に語るであろう。
岡部氏は運もよかった。すでに述べたように、SARSは日本には入らなかった。MERSも、韓国では帰国者がスーパースプレッダーとなって大変な騒ぎになったが、日本には入らないですんだ。2009年の新型インフルエンザも、危機管理として想定されていた「H5N1型強毒型新型インフルエンザウイルス」ではなく、病原性の極めて低いH1N1型であった。そのため、季節性インフルエンザよりも健康被害は少なくて済んだ。だが、繰り返しになるが、それは単なる「ラッキー」に過ぎない。
2014年に西アフリカ諸国でエボラウイルスが前代未聞の広がりを見せ、首都を含む各都市を巻き込んで大流行を起こした。WHOは緊急事態宣言を出し、国連も安保理決議を出すほどだった。感染者の数、死者の数はそれまでの平均的なエボラウイルスの流行より2桁も多い数となった。まさに桁違いの流行だ。このときも、ヨーロッパや米国には患者が入ったが、日本には入らなかった。これも「ラッキー」だった。
そのため、調整型の指揮官、岡部氏の対応でも乗り切れた。恐ろしいウイルスが国内侵入しなかったのだから、それで良かったのだ。だが、そのおかげで感染症の危機管理の意識は上がらなかった、いや、逆に薄れた。ウイルスに侵入された国では、それがトレーニングとなって感染症対策が再構築された。これまでのラッキーが、今回は日本の仇にならないだろうか? 現に、岡部氏の意見によるリスク評価の甘さがプレスリリースに現れているのではないか?
6 「モーニングショー」の現場で
2020年1月6日からの週、私はテレビで解説に呼ばれたが、「謎の肺炎が中国で発生しているらしい」という厚労省の発表の範囲に留まる内容であった。番組を観たのか、何人かの新聞記者がコメントを取りに来た。
1月初め、ProMEDという世界中の感染症関係の情報が流れてくるメーリングリストにも中国・武漢での肺炎の情報が流れ始めた。ウイルス感染症についてこのようなアウトブレイクの情報はよく流れてくるので、多くの研究者はあまり気に止めなかったかもしれない。だが、私は震えるような怖さを感じながら、それを見ていた。
そして中国は、世界でもっとも権威のある臨床医学雑誌である「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に、このウイルスの詳細を発表する。政府の公式な発表ではなく、科学論文が先行して世界にパンデミックウイルスの情報を発信するようになったのだ。SARSコロナから17年、サイエンスでも一流となった中国は、公表の仕方もドラスティックに変えた。
論文によると、1月3日から武漢において感染状況の調査、つまりウイルスがどの程度広まっているか、どのくらい感染者がいるか、という調査が行われていた。研究者が大勢送りこまれて調査を行っているということは、現地ではすでに大きな問題となっていたことの証明でもある。「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」電子版を私は一心に読んだ。
原因不明の肺炎の患者の集団が中国・武漢の海鮮市場で発生している。未知のコロナウイルスが分離された。中国疾病対策予防センターがそのウイルスのゲノムを解析し、全塩基配列を決定した。SARSコロナウイルスともMERSコロナウイルスとも異なる「新型コロナウイルス2019-nCoV」と名付けた(後に「SARS-CoV-2」に改名された)。それは極めて衝撃的な内容だった。
1月13日月曜日、テレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」に出演したのは、この日が初めてだった。私は1月3日から行われている武漢の現地調査をまだ知らなかった。
担当ディレクターは、いかにもベテランのテレビマンという印象で、数日前から電話でインタビューがあり、その後、出演依頼があった。前日、日曜の夜に入念な聞き取りがあって、テーマ内容についての意見を訊ねられる。コメント内容は自分の考えを述べる。“こう言ってください”という意見の指示や強要はまったくない。彼の話し方も紳士的で礼儀正しく、安堵感を覚えた。
当日、スタジオには「謎の肺炎で初の死者 新型ウイルス猛威 春節控え 日本も警戒」というテーマでパネルが組まれていた。
玉川徹氏の舌鋒はいつも鋭く、個性的なコメンテーターたちとの喧々諤々のやりとりを見て、「この番組は自分には荷が重いな」と以前から思っていた。それなのに「モーニングショー」の出演依頼を受けたのはどうしてか? その答えはシンプルだ。仕事は断ってはいけない、これが感染研のときの田代氏の教えだった。来た仕事は全て受けて、こなせ。そう言われ続けてきた。ここで解説をして、多くの視聴者の方に感染症の危険性を知ってもらうことが大事だと思った。そのスタンスはその後も続くことになる。
「モーニングショー」でも、ちゃんと想定外の質問にも発言できるように自分が成長するしかない、学ぼう、そう思って、この日はかなり緊張して臨んだはずだった。しかし、意外にもすんなりと本番生放送をこなせたのは、羽鳥アナの絶妙なバランス感覚と、私が答えやすいようにうまく質問を振ってくれた気遣いのおかげだろう。また、コメンテーター陣も、初めてのゲストとあって配慮をしてくれたかもしれない。
スタジオのテーブルの前に進むとき、羽鳥氏は必ず、笑顔で「お願いします!」と声を掛けて気合を入れてくれる。これは私が出演した初回から、200回を迎える出演回数に至っても変わらないことだった。本番前に一声かけて、ゲストを笑顔で迎える。重く暗い緊迫したテーマであっても欠かさず、そうしている。だからすっと番組に入っていけた。
70万人が訪日する中国の春節(1月24日〜30日)を前に、武漢で謎の肺炎が出た。ここは三国志の舞台「赤壁の戦い」のあった場所で、現在の主要産業は自動車。日系企業もホンダ、日産、ブリヂストン、イオンなど約150社ある。在住日本人は約460人に上る。
私はイオンの感染症対策の顧問を10年以上務めている。イオンは中国に複数の店舗を出店させている。鳥インフルエンザ問題でも、火薬庫であった中国での感染症危機管理を担当した。
2007年には、イオンから新型インフルエンザ行動計画の監修を依頼された。大陸を跨るウイルスの世界同時流行を想定しながら、イオンが国際的に展開する店舗、つまり不特定多数の来客が見込まれる店舗の運営と従業員の安全確保を目的とする、感染症対策マニュアルを作成した。それが私に託された初期のパンデミック対策のミッションだった。このとき、イオンが世界に展開する店舗数の多さに驚いた。まさに国際企業だった。
そのイオンが武漢に出店している。仕事を一緒にやってきた仲間が社内におり、今、武漢での新型コロナウイルスと対峙しているのだ。かつて作った新型インフルエンザ対策マニュアルは、同じ呼吸器感染症として稼働しているはずだ。そう思うと、胸が苦しくなった。
そして、この放送の本番中、ふと脳裏をかすめたのは、2007年、幕張にあるイオン本社の会議室で新型インフルエンザの対策を本社役員らの前で説明した時のことだった。最上階の会議室の窓の外にはきらめく青い海が見え、私の後ろには一緒にこの感染症対策を取りまとめたイオンの社員らがいた。
彼らは、武漢でどれほど大変な思いをしていることか……。私はベストを尽くして報道に臨む覚悟を決めた。
ウイルスが移動していく
初回の放送では、新型ウイルスでの症状、さらに動物のコロナウイルスが遺伝子の変異を起こして、人に感染できるウイルスに変異する可能性があることなどがパネルを使って説明された。私は「元々のウイルスの供給の起源として可能性が高いのはコウモリである」とした。
この新型コロナウイルスがSARSコロナウイルスと類似していることは1月10日の遺伝子ゲノムの公開ですでにわかっている。SARSコロナウイルスはキクガシラコウモリが自然宿主である。このコウモリのウイルスが遺伝子変異を起こして、ハクビシンにうつり、また人に感染するように変異を遂げた。
パネルには「新型ウイルス 発端は海鮮市場か?」とある。私は「?」がついていることに、ほっと息をついた。海鮮市場と断定されていないことに安堵したのだ。肺炎の患者発生が市場だけではない可能性は残しておくべきだ。私は、武漢の街中での人から人への市中感染の可能性を危惧していた。田代氏の情報、私のネットワーク情報でも人から人への流行が想定された。ただ、この時点では、厚労省やWHO、そしてWPRO(WHO西太平洋地域事務局)も、そうは認めていないし、その危険性も明確にしていなかった。
海鮮市場では、魚介だけではなく、ハリネズミやシカ、ハクビシン、コウモリなども食材として生きたまま売られている。中国の伝統的な食文化だ。そうした食文化と、動物と人との両方に感染する「人獣共通感染症」は関連性が濃い。市場が発端というのは、まずは、それらの食材となる動物から偶発的に人に感染したのではないか、と連想される。
「新型コロナウイルスで初の死者と確認された中国人男性は、海鮮市場に出入りしていた。市場の動物からの感染で、人から人に感染しているわけではない」厚労省からの発表がそうであるから、番組内のパネル解説もそうならざるを得ない。あくまで市場での偶発的感染に留まり、流行は武漢市内では起こっていないとするのか。やはりリスク評価が甘い、と思った。
1月9日に、東京医科大学の濱田篤郎教授が「何らかの動物のコロナウイルスが人に感染した可能性もある」とテレビの取材に答えている。濱田氏は輸入感染症、渡航医学の分野では日本でも屈指の医師であり、私も20年前から面識がある。濱田氏の発言は無難で、現時点のマスコミの質問への答えとしてはそうなるであろう、と私も思った。しかし、彼がそこから先、つまり「人から人へ」の感染状況をどの程度まで想定しているのかは不明だった。確固たるエビデンスが無いから、ここまでのコメントで留めたということだろう。この9日には、武漢で61歳の男性が新型コロナウイルスによって死亡している(公表されたのは2日後)。
10日、WHOは加盟各国に注意喚起を行った。注目すべきはその文面だった。そこには医療従事者への感染については特に注意することと付記されていたのだ。私はこの点を見逃さなかった。SARSやMERSにおいても、院内感染が集団感染・クラスターを形成して一大ウイルス伝播場所となったが、その経験からの院内感染への注意喚起と受け取れた。
それを今回も特に付記したということは、やはり、人から人への感染はあるのだな、と私は理解した。11日、新華社通信は「人から人への感染は未確認」と報道。さらに3日後の1月14日、WHOは報道関係者に「人から人への感染は家庭内感染に限られているが、SARS、MERSの経験から、人から人への感染があっても不思議ではない」と発表した。
WHOが家庭内感染を付記してきたということは、院内感染に留まらず、市中での感染も起こっている可能性があると読むべきだ。あとは、その伝播効率、つまり、このコロナウイルスがどれくらい人に順化しているかだ。
一方、春節前後の人の大移動よりも前に、武漢発の遠距離列車の片道切符が突然大量に買われている、との情報がカナダから入ってきた。この情報は大企業、中でも生命保険会社や投資会社などが契約して入手するサイトからのデータだった。この情報に基づいて、大勢の人が武漢から避難しつつあるとの憶測も流れた。
片道切符? 逃げ出すってこと? つまり、市民が危機を認知するほどに市中では流行しているってことだと戦慄する。一刻を争うように、着の身着のままに必要最低限の物だけ持って、片道切符を握りしめて満員の列車の隙間に身をくねらせるように乗り込む――そんな群衆の姿が脳裏に浮かんだ。
事実、この後、武漢の都市封鎖が現実のものとなるのだ。ギリギリに武漢駅発の遠距離列車で抜け出した日本人留学生の体験なども報道されることになった。実にこのとき、500万人もの市民が武漢から逃げ出していた。武漢の人口の約半分だ。
群衆が押し寄せたのならば、病院同様、駅も一大ウイルス伝播場所になる。そして、列車に乗り込んだ潜伏期の感染者(あるいは軽症者)の体内に乗って、ウイルスが中国のさまざまな地域に拡散していく……他に高速道路もある。そもそも中国大陸のど真ん中の都市なのだ。
私は凍り付くような不安に苛まれた。ウイルスは人の移動で運ばれる。太古の昔から、そうやって病原体は人と共に移動し、拡大してきた。そうなれば武漢だけの話ではない。中国と交流の多い日本でも、即刻に水際対策をすべきだ。当然、入国制限、禁止の措置が妥当であろう。
7 岡部氏の「用意周到」
こんな尋常ではない事態が武漢で起こっていたのにもかかわらず、日本のリスク評価はまだ楽観的であった。
日本の感染症対策の本丸は厚労省である。この厚労省の感染症対策を過去30年近くにわたって共にうまくやってきたのが、川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長であった。
岡部氏は「人から人への感染の可能性を排除できない」という1月14日の武漢市当局の発表を受けつつ、「仮に人から人への感染があったとしても、リスクはインフルエンザや麻疹などと比べても、とても低い」として、「現地に行く場合には手洗いなど衛生に気をつける」ことと述べた。これをなぞって、厚労省も16日に「現時点で人から人へと感染が拡大するリスクは低く、過度な心配は必要ない」としている。
私は、岡部氏のコメントの載った新聞を読んで、「先生、何をもってそう言い切るのですか? 単なる川崎市の研究所の所長だけでなく、今なお、さまざまな学会の理事、名誉会員や厚労省の委員会の委員等の肩書を背負っている先生の言葉は重いのです」と問いたくなった。内心で「この楽観視が対応の遅れにつながったら、日本でウイルスが広がります。広がってからでは、封じ込めはできません。岡部先生には、田代先生からの情報は、厚労省経由で当然入っていますよね。それを打ち消すデータやエビデンスがあるのなら、お示しください。でないと、私はこの国のことを思うと安心できません。国民を守れません。拡がったら、その痛みは国民が受けることになります。国民が受容できないほどの痛みとなった場合に、どうするおつもりでしょうか」と、大先輩の岡部氏に反論していた。
しかし、たとえ私が百万遍も反対意見を言ったところで、岡部氏の一言できれいに打ち消されるだろう。だいたい年齢が違う。年功序列の医学の世界では、およそ20年も年が下で、女の岡田ごときが、大先生に向かって何を反論する、となる。
岡部氏が73歳にして現役を退かないで現場にいることは、50代の現役世代の部長やセンター長たちが、この新型コロナ対策に口出しできないことを意味していた。何か言えるとしたら今の感染研所長の脇田隆字氏くらいか……。でも所長は肝炎ウイルスが専門だ。呼吸器感染症はわからないだろう。
それにしても、と少し冷静になった私は思う。岡部氏の「仮に人から人への感染があったとしても、リスクはインフルエンザや麻疹などと比べても、とても低い」という言い方はうまい。麻疹は空気感染をし、感染力が非常に強いウイルスだ。麻疹より伝播力の強い感染症は、思い浮かばない。だから、ワクチンで予防するしかない。ワクチンが無かった時代には、この麻疹が流行すると、罹ったことのない人間は、ほとんどが発症した。だから「お役」と呼んで、みんなが罹るものとされた。麻疹はハシカとして有名だが、その感染力と病原性の強さ、麻疹の怖さは、ワクチンで予防できるようになったため、今は認知されなくなったのだ。
岡部氏はそんな麻疹を引き合いに出して、それよりは弱いと言っているのだ。「インフルエンザより弱い」これはどうであろう? インフルエンザも毎年の季節性のものから新型インフルエンザまでいろいろある。普通のインフルエンザなら薬もワクチンもある。ここを曖昧にする、いかにも岡部氏らしい巧妙な言い方だ。素人の耳に心地よく、安心感を与える。しかもうそとは言い切れない。でも、と私は思う。新型コロナは、既に出てきている状況証拠からいって、とてもじゃないが大丈夫ではないだろう。
台湾のようにWHOより早くに動き、水際対策を最高レベルにし、先手先手で対策を打っているなら、国民は後になって実情を知ってもいいのかもしれない。だが、それは対策が適切に打たれていれば、だ。日本はまず楽観的な情報が流れ、その楽観視に乗っかって対策も甘く緩くなる。緩い対策のエクスキューズのように、また楽観的なコメントが流れる。本末転倒だ。まさにこの頃、武漢ではこの謎の肺炎の流行状況や病原体についての調査が行われていたのだ。
「モーニングショー」での私は、今の知見とエビデンスで「ここまでは言える、ここから先は予測となる」ということを、きちんと分けて話すことを意識した。予測で言うには世の中に与える影響、ハレーションが大きい内容は、口にすること自体を控えざるを得ない。さまざまなジレンマを抱え、いろいろ逡巡しながら、羽鳥アナから来る問いに返答していた。「モーニングショー」の視聴者のほとんどは一般人だ。だから、言い過ぎはいけない。でも、先を見通しながら、こういうことも十分に起こり得る、考えておくべきことだという範囲の内容は解説に入れることにしていた。
のちに、番組の注目度が上がるのに従って、国会議員や地方議員、首長など政治家の中でも「モーニングショー」を見てくれる人が増えていった。さらには、行政も見はじめた。玉川氏や私の発言が、内調(内閣情報調査室)から国の中枢に上がっていた、という報道もあった。国民がどういう報道を見て、どう理解しているかを調査、報告するのは、彼らのルーティンかもしれないが。
今まさに、現在進行形の感染症流行を説明しているのだ。不安を抱えてテレビの映像を見る人たちに、不安を煽るだけのような表現はできない。だから、今やるべき対策とセットで発言するように心がけた。しかし、時にどきっとするような事態を説明せねばならない時もあった。これはダメだろう、という政府の対応へきつい意見を言うべき時もあった。先行きは厳しいと言わなければならない、つらい質問もあった。
限界だらけの水際対策
ほんの数日の間に、番組では「アジア各地でも相次ぐ謎の肺炎」を取り上げるようになった。もう、この肺炎ウイルスは海鮮市場でもなく、武漢でもなく、中国だけでもなく、周辺諸国の問題になっていた。ウイルスは他国に確実に漏れ出していた。
香港では、武漢を訪問した60人が肺炎などの症状を呈しているが、その大半の人が海鮮市場に行っていないことが明らかになっていた。つまり市中で感染したのだ。
マカオで4人、台湾で3人が武漢訪問後に肺炎などを発症していた。もはや、武漢で人から人への感染が起こっていることは当然の想定となった。市場を閉めたところで済む問題ではない。武漢市内でインフルエンザのように市中感染が起こっていることを当たり前と考えて、日本も対応しなければならない。やはり、一刻も早く中国からの入国を止めることだ。もうすぐ春節で中国人観光客が大挙してやってくる。爆買いのインバウンドは日本経済を潤してきただろうが、今回はそうは言っていられない。
人から人への感染が強く疑われる中で、パネルは日本の水際対策、つまりウイルスの侵入をどうやって防ぐかに展開していった。私はもともと厚労省にいた。水際対策は厚労省の検疫所が担う。私自身、国立感染症研究所の研究員であったとき、成田の検疫所長に頼まれて検疫所で新型インフルエンザの水際対策の講演を行ったこともある。だから、呼吸器感染症の検疫の実情はよくわかっていた。検疫にもできることとできないことがある、つまり限界があるのだ。
感染していても、症状が出る前の“潜伏期間”の患者は見落とす可能性がある。それは、言わねばならない事実だった。水際対策は限界を承知で行うべきもので、これで病原体の侵入を完全に防げるという対策ではない。
新しい感染症が海外で発生すると、政治家や為政者はすぐに「水際対策の強化」を叫びながら会見をする。水際対策の強化は当たり前の措置ではあるが、それでもウイルスは入ってくる。特にダダ洩れになりかねないのがこのコロナウイルスだ。潜伏期間が長い、無症状者もいる、そんなウイルスを検疫で止めろと言っても無理がある。できるのは、ウイルスの侵入を遅らせることだけだ。
案の定、このときも関係閣僚の多くが「水際対策の強化」を強調し、国内侵入阻止のために万全の水際対策を取ることを表明した。国民を安心させたいのだろうな、とスタジオのVTRで流れる会見の映像を見ながら思った。ただ、それでも入ってくることを想定して、プラスアルファの対策をしないといけない、と私は解説で何度も念押しした。要は、対策がちゃんと準備されていればいいのだ。
問題は、水際で止められると思って、次の対策が遅れることだ。具体的には検査体制の強化と陽性者の保護・隔離施設。医療機関についても、専用病床の確保や、流行に備えた専門病院の選定なども、この時期に開始すべき対策だろう。それは厚労省や地方自治体が行い、国民の医療の多くを担う現場の医師会にも周到に根回ししておく必要がある。
政府に近い専門家からは、論拠がないままに、国民の不安を消し去り、安心感を与えるようなニュアンスの文言を盛り込みながら、とにかく大丈夫だよという楽観的な解説が流れていた。先の「仮に人から人への感染があったとしても、リスクはインフルエンザや麻疹などと比べても、とても低い」、「現地に行く場合には手洗いなど衛生に気をつける」という岡部氏のコメントはその典型だった。
この謎の肺炎が出ているときに、わざわざ武漢に行く人などいるものか。「現地に行く場合は手洗い励行」とは、武漢にいる人ですら、手洗い励行で乗り切っているという誤解を一般の人々に与えはしないか? ふと、まさかこの楽観論ときわめて甘いリスク評価で厚労省や大臣、政治家に説明をしているのではないか、と凍り付くような不安に囚われた。
過去の幸運がもたらした成功経験が、彼にこんなコメントを出させたのか。それとも、感染症流行など、この日本ならきっと乗り切れると本気で思っているのか。国民の生命と健康がかかっているのだ。裏付けとなる証拠をとって、危険度を評価すべきだ。
感染症の危機管理は甘いものではない。国民には良いことも悪いこともすべて開示して、「だから、こう対応する」と説明することが必要だ。専門家は「わかっていることはここまでで、ここから先は不明、だが危機管理としてこういう対応をする」と明確に話すべきだ。特に政治家、大臣レベルには全てを、正確に説明してほしい。安心だけを植え付けておくのは、いざ安全でなくなったとき、国民からも政治家からも「話が違うじゃないか」ということになる。
裏返して言えば、このような人間が「これは楽観視できませんね」などと態度を変化させたときは、本当にまずい、大変な事態のときなのだろう。
だが、そんなメルクマールとしても使えないことが後になってわかってくる。「この状況はまずい、大変だ」というときには、岡部氏は出て来ない。表舞台から消えるのだ。そして岡部氏よりは年下の尾身氏ばかりが会見した。まるで、平時から大事に至る前までは海月のように海中に漂って成長し、大事に至った時には二枚貝のように深く砂に潜る。海月と貝の比喩は、感染症研究所に居た頃に処世術の見本としてよく聞いた話だったと、思い出した。
8 感染症対策を政治家に説明すると
水際対策には限界があるのだから、当然、日本にもウイルスは入ってくる。他国のように中国からの入国を止めないのならば、新型コロナウイルスの“侵入は必然”としなければならない。ならば、国内侵入時のための対策も入れて、「モーニングショー」できちんと報道すべきだ。
1月13日に初出演した「モーニングショー」について、私は、番組スタッフの取材能力、理解力の高さに驚いていた。ディレクター、プロデューサー陣のレベルが高い。だからパネルの完成度が高い。さらに聞き取りによって、こちらの意図がちゃんと台本に反映されている。ディスカッションが無駄になっておらず、さらに内容が深掘りされている。また、MCの羽鳥慎一、コメンテーターの玉川徹の両氏は相当に勉強して本番に臨んでいた。
私の次の「モーニングショー」出演は同じ週の金曜、1月17日だった。その2日前、1月15日に、ついに日本初の感染者が出たことが確認された。中国籍の30代男性、武漢市に滞在歴があった。さらに武漢の家族が肺炎を発症しており、帰国まで家族と一緒に生活していることから、患者との濃厚接触者でもあった。
ある報道では、国立病院の有名な医師が「現時点ではSARSやMERSと比べて重症度は低い。むやみに恐れる必要はない」とコメントしていた。しかし、重症度が低いということは、軽症者が多いということでもある。それがかえって感染の広がりを助長することになる、という点をこの医師は見逃している。個人的レベルでは疾患が軽症であれば安堵するかもしれないが、社会やコミュニティーでは軽い疾患ほど広がりやすい。
SARSは、このウイルスに晒されればそのほとんどが発症し、さらにその多くが重症の肺炎を起こして、致死率は9・6%、約1割と高かった。感染者は重症だから動けない。つまり、うつす相手は看護する人や家族などの身近な人に限られる。だから、病原性の強い感染症は拡大速度が遅い。そして、重症者は見つけやすく隔離しやすいので、ウイルスの封じ込めがしやすい、つまり流行抑止対策が打ちやすい。
一方、軽症者が多い感染症の場合は、その軽い症状の感染者が、しばしば街に出て動きまわる。ウイルスを排出して、今度は患者自身が感染源となるのだ。もっとも怖いのは、感染しても無症状の感染者がいることだ。症状がないから自身も感染に気付くことはない。その無症状の感染者もまたウイルスを外に出す場合がある。本人も気が付かないままに、ウイルスを他者に伝播させていく。だから、無症状感染者がいる感染症対策は難航を極めるのだ。今、やれることは1つ。広範な人間に検査をして、感染者を割り出していくという手法しかない。
感染症をどうコントロールするかという視点で見れば、この新型コロナウイルスはSARSより賢い進化系のウイルスだった。
致死率は低くとも、感染者数、つまり分母が莫大になれば、犠牲者は途方もない数になっていく。ひろがってしまえば、流行抑止のための自粛やロックダウンなどによって経済活動へ甚大なる影響が出る。この手のウイルスは、最初に封じ込めを徹底することが肝心なのだ。
そんな思考をめぐらせていたとき、田代氏からメールがきた。英文で書かれたメールを訳せば以下になる。
「新型コロナウイルスCoV19の情報を送る。この新型コロナウイルスに楽観視は禁物である。そう思って対策を考えるべきだ。人から人への伝播が起こっている。以下のサイトを全部チェックするように」
WHOのサイトや海外の主要論文に飛べるようになっていた。私はそれを片っ端から読みながら、合点がいった。
田代氏は厚労省にこの情報を流し、新型コロナウイルスの危険性と対策の必要性を訴えたに違いない。しかし、本省は楽観的なリスク評価を選んだのだろう。それはここ一連の厚労省からの公式発表からも透けて見えた。
国の危機管理の中心は官邸が担い、その決断とリスク評価がものを言う。感染症対策も地震対策も原発事故の対策も同じだ。安倍政権になってから、官邸には経産省や警察庁出身の官僚が多くなり、厚労省は出る幕がなくなった。感染症対策の危機管理を官邸とうまく共有できないことに、以前から田代氏は強い憤りを感じていた。
厚労省の医系技官であれば、“腐っても医者”ではあるので、感染症対策の話もおおよそは通じる。だが、文系のまったく分野の異なる人間に、医療分野の病気・感染症の危機意識の共有の必要性を、サイエンスをかみ砕きながら説明し、理解してもらうのは難しい。それにはかなりのテクニック、労力、忍耐力、コミュニケーション力が問われる。
官邸で対応せねばならない他の案件を超えて、このウイルス対策が最優先課題の一つであるということを納得させ、事前実行に移させるには、かなりのエビデンスを揃え、相当の熱意をもって説得に当たらなければならない。情熱が相手を共鳴させるということもあるし、相手の感受性や想像力、そんな素地にも大きく影響される。つまり、流行したらどうなるかというイマジネーションを持たせられるかだ。しかし、何よりも国民の命、健康のために説明を繰り返す忍耐力が勘所である。田代氏一人にそれを求めるのは無理だろう。
2008年以前の鳥インフルエンザ問題の時には、その一端を私が担った。地方自治体にも政府にも、国会議員にも大臣にも、私が説明に行った。時には田代氏と共に出向いて、まず私が説明し、田代氏が質問に答えるという形式のレクもあった。
政治家に説明するのは困難を極める。族議員の利権や権力闘争、支援者からの要望、党内の人間関係などの、さまざまな因子・ファクターが政治家の頭の中には渦巻いている。説明以前に、“立場と利権”から政治家自身がすでに結論をもっていることも多い。
そんなとき、能力を発揮したのが岡部氏であったろう。ネゴシエーション能力とバランス感覚に長けた人物だ。政府や政治家への説明は彼の独壇場だったろう。
こうして対策は二進も三進も進まない……だから田代氏は腹も立ち、落胆もしたであろう。
もうひとつ、世界の急速なグローバリゼーションと野生動物の生息エリアに人が踏みこむような開発等を背景に、野生動物の病原体に人が暴露・感染する新たな感染症の発生と、それが一気に拡大する事態を田代氏は確信的に予見して、その危機管理を訴えていた。新型インフルエンザと新型コロナはまさにそれだ。
近年の人間社会のグローバル化は、もはや風土病を一地域に留まらせることを許さず、高速大量輸送によって瞬く間に病原体を大陸を越えて拡散させる。SARSが1週間で大陸越えをしたのは、航空機社会だったからだ。そんな時代だからこそ、田代氏は以前から、検査・隔離・医療体制の構築や感染症病床の確保、専門的な医療者の育成など、発生前からの感染症対策を主張していた。だが、事前準備に予算や人をつけるのは、そもそも難しい。
そこへ2011年の3・11東日本大震災とそれに続く福島第一原発事故の発生があった。感染症対策の危機管理から、首都直下型地震、南海トラフ地震をはじめとする震災対応、原発事故対応に大きく舵が切られた。さまざまな政策案件の中で、平時からの感染症対策は後回し案件になった。では、この後、日本の官邸、厚労省はどんな対策に出るのか?
9 機能しないWHO
日本の新型コロナウイルス対策も岡部氏を中心に対応していくことになるのが、はっきりと見えてきた。岡部氏自身は多少おっかなびっくりだったとしても、厚労省や国(官僚や官邸)の護送船団がついていることは、強力な自信と安心につながる。あとはリスクの分散化だ。仲間を増やして専門家の委員会等を組織することだ。これは厚労省、内閣府など、いろいろな組織に作る。この作業には役所は長けている。まずは、よく人選を相談しよう。それから各学会にも協力をお願いしよう。学会のメンバーをバランスよく配置して……。
1月30日には政府内に「対策本部」、2月7日には専門性をもった立場から感染症対策を考える「アドバイザリーボード」が設置された。尾身茂、押谷仁、そして岡部信彦の各氏が名を連ねた。押谷氏が60歳、尾身氏は70歳、岡部氏は73歳。いわば功なり名をとげた先生たちであり、現場で実務を担っている現職からは遥かに遠い人選だった。
このメンバーで本当に日本は大丈夫なのだろうか? 彼らを信じるしかないのか、と不安に駆られた。中国の肺炎患者が増え出したら、日本にどんどんウイルスが入ってくる。いや、武漢では患者が増えているから、感染者はすでに複数例、入国しているかもしれない。問題はそれが十分に把握しきれないことだ。現にマカオでも台湾でも香港でも、そして日本でも、すでに武漢帰りの発症者がいる。
私は私の持ち場でベストを尽くすしかない。大きな健康被害、大きな経済的損失が出たら、それは国民が受ける痛みになる。ならば、自分がテレビなり何なりでサイエンスに基づいた正論を言い続けるしかない、と私は腹をくくった。臨床現場の医師や保健所の職員、地方自治体で対策を担う人、もっと言えば感染のリスクを背負う国民に対して、現状と先の予測、そしてなされるべき対策を提言していくしかない。
もちろん、公共の電波で裏取りのできない情報を言うことはできない。私はこの時期、4つのテレビ局で生放送に出演していた。生放送にこだわったのは、感染研時代の所長の鉄の掟のためだ。収録は編集されるので、意図しない使われ方をされることがある。だから感染研の職員は基本的に生放送の出演しか許されなかった。感染研を辞めて11年経った今も、その所長の言葉は染み着いていた。
まずは、厚労省以上のアンテナをもつ田代氏から情報とエビデンスをもらうことが先決だった。いくら田代氏からの情報でも裏取りができない限り、オンエアでは口にできないが。
私は、武漢の人から人への感染の状況やその伝播効率、特に基本再生産数の詳細が知りたかった。厚労省が「人から人へと感染が拡大するリスクは低く、過度な心配は必要ない」とし、岡部氏が「現地に行くときには手洗い励行」と明言している以上、それを打ち消す情報・エビデンスが欲しかった。
新型ウイルスの呼吸器感染症は、冬場こそ流行が速い。ほんの数日、ほんの1週間の違いが冷酷なほどに後の流行の明暗を分けることがある。地域流行のアウトブレイクで済むのか、それとも世界的大流行となってしまうのか。
感染症の歴史が長い国
1月15日に日本で初の感染者が確認されたという情報を取り扱ったのが17日の「モーニングショー」。その後、事態は急激に動いた。
1月19日、SARS流行の際に陣頭指揮していた鍾南山教授が、武漢の新型コロナウイルス肺炎対策の専門家チームのトップとして着任。翌20日に鍾氏は、このウイルスは「人・人に感染する」と、ついに明言した。それまで中国政府系のメディアは、この新型コロナウイルスについて、「人・人への感染はない。予防も制御もできる」と言っていたのだ。厚労省のリスク評価も中国政府の公式発表に則したものであった。
恐れていたことが現実となった――。
すでに中国での感染者は500人、医療機関は患者でごった返している状況であった。この段階では、まだ中国以外の国での感染者数は数人である。そのためか、この感染症を抑え込めるという自信があったのだろう、中国政府はWHOを牽制するかのような動きを始める。
1月22日、WHOは世界各国から22人の専門家を招集して、新型コロナウイルス感染症についての緊急委員会を開いた。主たる目的は「公衆衛生上の緊急事態宣言」を出すのか否かということだった。このときの緊急委員会では、中国の委員が頻繁に発言し、「中国は緊急事態宣言を出すような状況にはない」ことを強調して、会議のほとんどの時間を費やした。WHOのテドロス・アダノム事務局長は、中国から巨額の資金援助を受けているエチオピアの出身である。ゆえに中国寄りであることは、かねてより指摘されていたし、緊急委員会のメンバーも当然、それは承知していたはずである。
21世紀になってから、WHOには中国出身の職員が多く採用されていた。中国はウイルスなどの感染症に強い海外の大学に多くの若い優秀な人材を送り込み、さらにWHOには多くの人材を採用させ、パンデミック対策に注力をしてきた。時代の先を読む中国政府は、21世紀は新型インフルエンザや新型コロナウイルスなどさまざまな感染症の脅威に晒されやすいグローバル化社会であることを認知し、先手で対応していたと言える。
一方、WHOには限界もあった。強制力がない。中国側に拒まれれば、WHOは現地調査に専門家を入れることもできない。中国側から円滑に情報がもたらされなければ、コロナの流行状況やウイルスの情報も入手できない。隠蔽されれば、その国の内情は公式には掴みにくい。
1月23日、テドロス事務局長は「まだ世界的な緊急事態宣言をするに至っていない」とし、緊急事態宣言を見送った。そしてこの日、中国政府は武漢という巨大都市、東京に匹敵する都市を丸ごと都市封鎖したのだ。感染者が激増した武漢に警察と軍を投入し、市内の地下鉄駅の電源は落とされて真っ暗になり、駅にも空港にも利用客は皆無となった。普段の雑踏が1日で完全な静寂になったのだ。
24日、私が出演した「モーニングショー」のパネルタイトルは「日本人感染か 春節前に封鎖拡大 発熱せず死亡も」だった。都市封鎖の中での武漢市民の生活も報道した。
武漢の住民からの情報では、市民全員が自宅待機となっている。スーパーマーケットには生活必需品を求める人が押し寄せ、新型コロナウイルスの流行で病院はどこに行ってもいっぱい。たとえ発病しても医療提供はない。それだけ多くの感染者が出ているということだ。
ほんの4日前、20日に日本政府(厚労省)から出ていた“人から人への感染は稀で限定的”だから大丈夫だという安心情報を信じていた日本人の多くは、この放送を見て驚愕したはずだ。人から人への感染は稀どころか、武漢の病院では人があふれているではないか! これで、このウイルスに対する国民の楽観視は消し飛んだ。日本になだれ込んでくる可能性だって高いのではないか?
すでに武漢の医療機関は事実上、患者を診られる状況ではなくなっていた。医療を受けられない、取り合ってももらえない患者は、発熱難民・医療難民となった。当然、自宅で重症化する人も多数出ていた。
肺炎が悪化しても医療を受けられず、血液中の酸素濃度が低下して呼吸が苦しくなっても、人工呼吸器などの医療機器の助けはない。そうなると、コロナウイルスは爆発的に増殖して、免疫暴走である「サイトカインストーム」が起こってくる。自分の免疫が自身の細胞を攻撃して、一気に肺炎が増悪する。こうなると患者は重篤化へ転げ落ちていく。
自宅で重症化し、重篤になって死んでも、犠牲者数にカウントされていない可能性も高い。検死のウイルス分離など、この医療状況でやれるはずはない。武漢の健康被害の実態も把握でき難くなっていた。
武漢は人口1100万人の巨大都市だ。長江とその支流漢江の合流する地点にある。さらに中国国内の交通網の中心地でもあり、ハブ的な位置づけである。飛行機なら北京へ2時間、上海、広州、重慶なら約1時間半で着く。
そんな交通の要衝たる都市での感染症の発生・流行に対しては、国内流行を止めるためにも徹底した封じ込め策を取るしかない。大きな痛みを伴っても都市封鎖だ。中国政府は、絶対に北京で感染者を出したくはない。北京を死守することはSARSの教訓、何としても武漢で封じ込める決意だ、と察した。
中国という国はユーラシア大陸にあって有史以来さまざまな感染症の大流行に晒され、甚大な被害も受けてきた歴史がある。ペストの大流行も天然痘も麻疹も、ユーラシア大陸を横断するシルクロードを通ってやってきた。そして、新型インフルエンザも繰り返し、発生してきた。新型インフルエンザは鳥インフルエンザが変異して発生する。鳥インフルエンザウイルスはカモなどの水禽を自然宿主とし、その腸内に生息する。夏はアラスカなどの営巣地で子育てし、冬季は南下する渡り鳥の一大飛来地域が中国大陸なのだ。度重なる伝染病流行は、この国の歴史に現在進行形で刻まれている。
結果として、感染症に対する危機意識はこの国土の人民のDNAに刷りこまれているはずだ。2002年の、同じコロナウイルスによるSARSの記憶はまだ鮮明に残っているだろう。だから、どんな巨大都市であっても、重要な交通網のハブであっても、封鎖を躊躇いなくやってのける。日本とは感染症対策へのそもそもの危機意識レベルが雲泥の差なのだ。
今や、武漢はホットスポット、湖北省はレッド・ゾーンという、危機管理の認識なのだろう。都市封鎖は住民に極めて厳しい生活を強いる。封鎖されれば、悪く言えばそのエリア内の人間は見殺しも同然なのが、感染症流行時の封鎖である。その状況を認知しているのもまた、この国の住民なのだ。封鎖前に武漢の地を逃げ出そうという人々が大勢出てくるのも当然なのだ。文字通り、死活問題だからだ。
そして、英国ランカスター大学などからの研究論文では、2月4日までに予測される武漢での感染者数は35万人と推計された。羽鳥アナから「岡田さん、これは?」とふられ、「感染率からみるとあり得ない数字ではない」と恐怖を覚えながら答えた。
10 学者の矜恃
1月28日、WHOのテドロス事務局長は北京で習近平国家主席と会談した。その模様は世界的に報道された。テドロス事務局長は習主席に対し、迅速に病原体を突き止め、公表したことへの賛辞を贈り、習主席は「WHOと国際社会が客観的で公正、冷静、理性的な評価をすることを信じる」と語った。
この頃、私は毎日番組を3つ4つと掛け持ちして解説をしていた。BS放送で大臣クラスの政治家と同席して、討論形式で行う報道番組もいくつかあった。このような番組であるなら、田代氏が意見を言っても違和感はないはずだ。なぜ、田代氏は自分が出ていって意見を表明しないのか。彼がテレビなどに出演して政策を提言すればよい、と私は思った。肩書きも重みも十分である。厚労省にとっても、田代氏の意見が公にされたら捨て置けまい。その方が、政策は圧倒的に受け入れられやすい。
彼にテレビに出て真実を語ってもらいたい。国民に実情を伝え、世論を形成できれば、行政が動きやすい。世論は内閣支持率に反映されるから、政治も動かせるかもしれない。
そんな思いで田代氏に電話すると、幸い、すぐに出た。
「先生が説明すれば、厚労省も放ってはおけないでしょう。あるいは、加藤大臣に直接、説明してはいかがでしょう、それならばなんとかセットを考えます。テレビできちんと討論するのもいかがでしょうか」
「もう、厚労省には言った! 年末休みで、電話に誰も出なかったが、メールでも年末にデータも説明も送ってある!」
「だから、再度、繰り返しご説明を……。メディアに出るという手もございます」
私の食い下がろうとする言葉を遮るように、
「厚労省には説明もした、ただ、やつらには通じなかった。ものわかりの悪い組織でほとほと呆れ果てた。それにもう、僕は引退した人間なんだ」
「でも、尾身さんも岡部さんもご年齢としては同じ、いや、岡部さんはもっとお年上です」
「彼らは引退はしていない、今も役所の肩書き背負って、厚労省と一緒にやっているだろう。僕にはあんな御用学者はできない。あいつらは学もなきゃ、ポリシーもない。だから、あんな無責任なことができるんだ」
そう言われると、反駁する言葉に窮した。田代氏の気持ちを斟酌しながらも、粘ってもう一度呼びかける。
「感染症対策は国民の生命の問題です。先生の肩には国民の生命がのっています。国民の健康被害を減弱させる必要があります。先生ほどの方がおっしゃるから説得力がある。どうぞご再考を」
「今、忙しい! 切るぞ!」
電話は切られてしまった。ああ、やってしまった。田代氏の怒りは相当強い。こう言い切られるとテレビ出演などは絶望的だ。
すでに私は、自分だけでは動かしきれない壁を感じていた。田代氏は何度も、今の私が持つような絶望感を味わってきたのだとは思う。これまで、新型インフルエンザ対策をはじめとする感染爆発に備える政策を提言しては、なおざりにされてきたのだ。
田代氏は極めて優秀で、世界的な評価も高いが、同時に人を寄せつけないところがある。さらに、誰にもわかりやすく物事を説明するのが不得意だった。噛み砕いて説明できないのだ。仕事上の交渉ごとでさえ、そうだった。だから、そんな面倒な役目はいつの間にか、部下だった私に集中していた。
しかし、今は多くの人命が危険にさらされようとしているのだから、彼ほどの人物こそ、たくさんの人に事態をわかってもらえるように言葉を尽くして説明して欲しい。なんと言っても、岡部氏や尾身氏などの大先輩の甘いリスク評価で対策が動きつつあるのだ。田代氏ならば、彼らを簡単に論破できるではないか。世界的な評価も、彼らとは雲泥の差で田代氏が勝る。国だって動かざるを得ない。
“田代氏をテレビへ”という願いは叶わなかったものの、その後も変わることなく、田代氏からはさまざまな情報が送られてきた。決して、国民を見捨てたりするような人ではない。
たいていが朝方だった。そのメールの送信履歴を見ながら、田代氏がヨーロッパ時間に合わせて仕事をしているのが感じられた。彼は彼なりに、今の立場で最善を尽くしているのだろう。私は深夜も仕事をし、早朝は田代氏からメールで送られてきた論文を片っ端から読む。さらに電話をすれば、田代氏はディスカッションには応じた。流行状況のリスクアセスメントをするとき、さらに対策に迷ったときは、彼の意見を聞いた。それだけでも有難かった。
11 春節がやってきた
コロナウイルスはこの間にもどんどん拡大を続けていた。武漢封鎖だけでは不十分で、1月末時点で中国全土22省、4直轄市、5自治区に感染が拡大。9000人あまりの感染者と200人以上の死亡者が確認され、北京だけでも100人以上の感染者がいた。
1月下旬には、世界各国は、次々と中国便の運航停止(あるいは大幅な減便)を打ち出し始めた。だが日本では運航停止措置は取られていなかった。日本の水際での検疫で新型ウイルスの検査は行われてはいたが、あまりに脆弱だった。その原因は以下の検査実施の条件にある。
実施条件は、(1)37・5度以上の発熱、(2)咳などの呼吸器症状、(3)直近2週間以内に武漢に滞在、もしくは(1)(2)がある武漢滞在者と接触がある人、とされていた。(3)は、のちに悪名高い「武漢縛り」として知られることになる。この緩さでは取りこぼしが出るのは火を見るより明らかであった。
水際対策の強化を謳いながらあまりに杜撰な検査体制に、テレビの解説でも、「これではウイルスが侵入してくるのは防げない」と言わざるを得なかった。うそは言えない。検査のキャパシティーが追い付いていないのだろうが、そもそも運航を停止すべきだ。そう言えば政府批判にはなるが、やってもらわなければならない政策なのだ。
実際に、広東省広州から帰国した男性が風邪症状や腹痛・下痢を空港で自己申告したケースでも、検疫の医師から問診だけで、「今のところ風邪の症状のみなので安静に過ごしてください」と帰宅を促されていた。これでは新型ウイルスがどんどん入ってきてしまう。
そして、1月初旬から中旬にかけて武漢から国内に入ったウイルスから、日本各地で集団感染・クラスターが発生し始めた。
海外でも同様の事案が発生した。1月8日、武漢からタイに入国した中国人女性がバンコクで発症した事例では、空港で発熱症状から見つかり、4日後にコロナウイルスゲノムが同定された。韓国でも20日には武漢から入国した女性のコロナウイルス感染が見つかった。このように1月中旬には武漢から近隣アジア諸国にウイルスが拡散し始めていた。
そして、とうとう無症状の感染者から他者への感染が起こることが証明される事案が出た。
1月19日、上海からミュンヘン行きの航空機に乗った中国人女性がドイツに到着後、彼女と接触した2名のドイツ人が感染したのだ。この中国人女性は「無症状」であった。
以降、1月28日から31日にフランス、イタリア、イギリスに中国人観光客がウイルスを持ち込み、スペインにはドイツ人旅行者が持ち込んだ。さらにイタリアからロシア、ブラジルへと飛び火していった。一挙にヨーロッパへ、そして大陸をさらに越えて広がったのだ。
無症状感染者が感染源となった――ここまで来たら、感染拡大を防ぐには感度の良い検査方法を早期に構築し、検査によって無症状感染者を見つけ出して、陽性者を隔離するしかない。水際対策は侵入の時間稼ぎにはなるが、無症状の感染者がいる以上、その効果は著しく低くなるだろう。いや、無症状感染者の感染者全体に占める割合が多いなら、それは無に等しくなるかもしれない。
中国便、停止せず
私は風疹や流行性耳下腺炎などのウイルス性感染症を思い出した。これらの疾患も咳やくしゃみで感染伝播していく。この疾患の無症状感染者は約3割だ。だから、これらの疾患はワクチンでしかコントロールできない。新型コロナウイルスでもサイレントキャリアが3割を占めるようなら、中国からの入国を閉じるしかない、と私は思った。ところが後に、無症状感染者は約5割にも及ぶことになるとわかり、先進国の多くは莫大な数のPCR検査で感染者を見つけ出し、隔離もしくは待機で感染者と非感染者を分ける政策を取っていくことになる。だが、日本はその世界の潮流とは正反対に検査体制を絞った。「検査を拡充すると医療が崩壊する」という論で突き進んだ。
さらに、感染してから発症までの潜伏期間が長いこともわかってきた。インフルエンザは1、2日の短期間で発症するが、このウイルスは10日もの長い潜伏期がある。これは、長距離の移動や国境を越えるには十分な日数だ。
今すぐ中国便は止めるべきだと、「モーニングショー」などの番組内で力説した。そんな意見は届かないまま、中国便はどんどん飛んできた。だが、厚労省には感染症対策ができる専門家が複数存在するのだ。いくら何でもこんな状況なのだから、岡部先生や尾身先生、押谷先生らが「中国便の運航は止めるべし」と進言しているだろう、と私は信じていた。
だが、進言がなされなかったのか、彼らの意見が聞き入れられなかったのかはわからないが、中国便の運航停止もないまま、そして新型ウイルスの検査実施も強化されないままに、中国の旧正月である春節がやってきた。中国では1月24日から30日まで7連休になる。日本への中国からの便数は、武漢が封鎖された翌日の1月24日からの1週間だけでも1600便以上に上る。上海580便、北京200便、天津80便、広東省広州60便、浙江省60便が運航されていた。
この“チャイニーズニューイヤー”の連休には、中国人観光客が日本に毎年大挙してやってくる。一番人気の渡航先が日本なのだ。また、日本側にも、中国観光客のインバウンドを経済の頼みの綱としている業界もあった。日本政府は中国からの団体観光客は止めたが、個人観光客やビジネス関係の往来は継続した。結果的に、大挙して中国人観光客はやってきた。
各局ワイドショーでは、盛んに中国人観光客の来日を取り上げた。銀座にも中継車を出し、カメラを回す。マスクを大量買いする中国人観光客がスタジオのモニターに映されるのを私は締め付けられるような思いで見つめていた。
なぜ、こんなに対策が甘いのか? ここでウイルスの侵入を積極的に止めなくてどうするのか? 後になって、いくら後悔しても、その頃には国内に飛び火したウイルスが流行を起こしている。無症状で感染させる事例も報告されている以上、この元気に買い物をしている観光客がウイルスをもってきていても何も不思議ではないのだ。「大した病気じゃない」「現地に行くなら手洗い励行」と同じ感覚の甘いリスク評価だ。無責任で、もっと本質的に言えば、人命を軽視しているのではないか、という思いを私は必死で打ち消した。
武漢の肺炎にすばやく対応したのは、韓国と台湾であった。台湾は、中国が公式発表した2019年12月31日には動き始め、1週間後にはその感染症対策を整えた。韓国は、国内で感染者が発生した2020年1月20日からわずか1週間で検査キットの開発と生産をメーカーに発注し、2週間後には1日あたり10万キットを生産することに成功していた。
武漢からの脱出
武漢が封鎖されると、政府は邦人救出を急ぎ、1月29日未明には日本人206人を乗せたANAのチャーター便が武漢空港を離陸した。
症状があるため入院した人を除いた197人が、千葉のホテルで2週間の隔離に入った。第2便で210人、第3便で149人が帰国、2月17日の第5便までで合わせて829人の邦人が武漢から帰国した。PCR検査の結果、1・7%が陽性、14人が感染していた。うち7人は肺炎症状があり、3人は発熱と咳、残る4人は無症状だった。無症状であったため、相部屋となってしまった事例も出た。
1月31日の「モーニングショー」では「帰国者 症状がなくても感染 ホテルの相部屋に波紋」として取り上げた。玉川氏はまず1・7%の陽性率が予想より高いとして、「この武漢からの帰国者、日本人ですよ。彼らは一般の武漢市民より注意して生活していたはずだと思うんです。それでも1・7%もの陽性者がいるってことは、武漢の人たちはもっと感染していることが推定される」と指摘した。私は頷いた。邦人は必死で感染しない対策を取っていただろうことは、自分の海外生活の経験からも容易に想像がつく。海外で、それも医療もままならない状況で、不気味な肺炎のウイルス感染症の流行があったら、彼らは籠城生活に徹したにちがいない。当然、武漢の一般市民の感染率は、これ以上に高いだろう。
この直後、中国政府は武漢にたった10日の突貫工事で、1000床のコロナ専門病院「火神山医院」を建設、稼働を始めた。2月8日には1500床の「雷神山医院」も完成した。それだけ多くの感染者がいて、大勢の重症者が発生しているということだ。テレビでは、この驚くべき短期間での巨大専門病院建設を可能とした中国の感染症対策の実行力も伝えていた。この後、中国政府は莫大な数の検査をして感染者を見つけては隔離し、国家プロジェクトとしてウイルスを封じ込めて行く。そうやって、震源地とされながらも、いち早く日常生活の正常化を可能としたのだ。
私は中国の対策が羨ましかった。「モーニングショー」では、「コロナ患者を集めて集中的に治療していくことは、他の医療機関を守るためにも必要であるし、診療も効率的になる、そして日本でもこのようなコロナ専門病院が必要となるのだろう」と力説した。そのためには、ウイルスが国内で拡散する前の今から、医師会と厚労省と都道府県などで話し合いを始める必要がある、もちろん予算取りもあるから、すぐにも準備を開始すべきであろう、とも述べた。
日本の中小の病院は、たいていが民間病院だ。市立病院や国立病院機構などの公的病院をコロナ専門病院とするにしても、そもそもそこに入院・通院している患者をどこの病院が受け入れるのか。「中国のことだ」と、今、視聴者はまだ対岸の火事としてこのコロナ専門病院を眺めているであろうが、私は数ヵ月先を見据えようとしていた。そこには時間軸のズレがあった。
武漢からの帰国者たちの2週間の隔離の状況、その食事や部屋割りなどの隔離生活がワイドショーでは取り上げられていた。房総の海辺にあるホテルが宿舎となったが、眼下に見下ろされる砂浜に蝋燭の火が灯され、ハートの形が浮かび上がった。隔離された人を励まそうという住民の優しい行動も報道された。
1月30日、WHOはようやく「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。しかし、このときすでに中国全土にウイルスは拡散、さらに世界中の18ヵ国で感染が発生していたにもかかわらず、パンデミック宣言は見送られた。結局、WHOがパンデミック宣言をしたのは3月11日、ここからさらに40日を経た後のことだった。テドロス事務局長の対応は、中国寄りであると叩かれ、WHOの限界を露呈した形となった。
WHOへの信用は地に落ちた。トランプ大統領はWHOへの拠出金を止めるとも表明し、私は、それまで愛用していたWHOのロゴの入ったスカーフや時計を捨てた。ジュネーブの出張のときに購入した記念品であり思い出の品でもあったが、最早、思い出したくもなかった。
12 特措法への障壁
1月中旬から、厚労省を中心に、この新型コロナウイルスを法的にどのように位置付けるかが問題となっていた。今後のコロナ対策の方向を決める重要案件である。
私は、TBSテレビのBS番組「報道1930」に渡航医学専門の濱田篤郎医師と自民党の国光あやの議員と共に出演した。国光氏は厚労省医系技官出身であり、厚労族だ。政府や党の方針はある程度把握しているだろう。
スタジオ入り前、廊下での立ち話で、さり気なく濱田医師が国光氏に核心的な質問を投げかけた。
「この新型コロナは『新感染症』には指定できないのですか?」
この問いに、私は思わず振り返って、国光氏の顔を見た。まさにこの新型コロナウイルス感染症を「新感染症」に指定し、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)で対応すべきと考えていたからだ。まだその性質が明らかになっていない感染症であるのだから、「新感染症」にして、既存の感染症法に縛られない柔軟な対応をとることで、円滑な対策が可能になる。
「新感染症」ならば、特措法の下で、省庁横断のオール日本態勢で事にあたれる利点も大きい。特措法ならば、有事の際、総理は「緊急事態宣言」を発出することもできる。
そもそも、このような新型ウイルス出現のために制定された法律なのだから、ここで動かさないという選択肢はない。新型コロナウイルスをまず「新感染症」に指定し、最悪の事態を想定して対応できるようにしておくべきだと、田代氏も私も考えていた。
しかし、なかなか政府が対策の方向性を打ち出さないのに業を煮やした田代氏から、珍しく電話が来て、「新感染症に指定して、特措法を動かせ」と言われた。怒っているような声だった。あまりに当たり前の政策であり、なぜ、そんな当然のことを電話してきたのかとわからずに、私は不思議な気持ちになった。
だが、田代氏から「そんな楽観視するんじゃない!」という罵声が電話の向こうから飛んできて、事態をすぐに理解した。
「厚労省マターの“指定感染症”にして、“感染症法”でやろうってことになりかねない。そんなことをしたら、すぐに法律に抵触して、何かある度に政令を連発しなきゃならなくなる。感染症対策が間に合わない。対策が後手後手になるぞ!」
それで電話は切れたが、田代氏の強い言葉は胸にぐさりと刺さった。古い記憶が、脳裏に浮かび上がった。
2012年、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が議案に上がっていたときだ。特措法についている「等」は、そもそもSARSのようなコロナウイルスの発生を想定して、わざわざ「等」を入れた経緯があった。私は内閣府に呼ばれ、大臣レクをした。あれは民主党政権時だった。
そうだ! 当時の民主党政権下で制定されたのが、特措法だ。あのとき、参議院では自民党は欠席のまま決議された。それを自民党政権下で、そのままで動かすだろうか。ぞっとするような思いが去来した。パソコンを開くと、自民党はあえて特措法を無視しているという主旨のメールが田代氏から来ていた。そんな政治的な理由で特措法の適用を本当に拒むのだろうか……。
感染症対策の肝はスピードだ。すばやい対策をするには特措法の運用が必須となる。対策が後手に回れば、流行は必至だ。大勢の人が感染し、医療が逼迫する、するとコロナ以外の医療にも甚大な影響が出る。コロナ患者も大変だが、他の病気の診療も大変なことになる。特措法なら、緊急事態宣言も出せるし、極端な話、中国のように巨大な病院を突貫工事で造ることも、既存の病院の病床を押さえることも可能なのだ。
田代氏に背中を押されるように、私は厚労族の議員、大臣経験者にも連絡をとり、「新感染症」に指定して特措法で対応すべきだと進言し、メディアでも同様の発言をし始めた。田代氏が動かない以上、私がやるしかない。
まさにそんなときだったから、「報道1930」のスタジオ入り前に濱田医師が「新感染症には指定できないのですか」と国光あやの議員に問うたとき、思わず振り返ったのだ。
「そうねえ、むずかしそうよねえ」と答えた国光氏に、私は言った。
「未知の部分もまだまだある、この新しい感染症に対しては、まずは新感染症として対応し、大きく網をかけて対策をする。そして、詳細が見えてリスク評価が正しくできるようになってから、徐々に対応を緩めていく。それが、国内流行を抑止することになるのではありませんか」
国光氏は「それがね、新感染症はむずかしいみたいなんだよねー。指定感染症にするんじゃないかなあ」と事も無げにつぶやいた。
「なんで指定感染症なんですか?」
私はすぐに聞き返した。本当に指定感染症にするなら、新型コロナウイルスの性質や実態が不明確な中で、何類の感染症に指定するのだろうか?
国光議員は「どーなんでしょうねえ」と言葉を濁した。
いつでも厳しい感染症対策の措置が取れる法的裏付けを得る必要性からも、「新感染症」に指定して、特措法を動かせる基盤を作っておくことが勘所のはずだ。
国光氏からはっきりとした返答をもらえなかった濱田医師は、がっかりしたように「新感染症にはならないのですか」とだけ、つぶやいた。
その日のBS生放送「報道1930」で、私は「まだ“未知の”ウイルスであるから、危機管理問題として新感染症に指定し、特措法の枠で対応できる道をつけておくべきだ。楽観的なリスク評価はすべきではない」と一貫して述べた。このような発言をする専門家はいなかったので、MCの松原耕二氏は驚いた表情をした。
明日は、自民党の新型コロナ対策本部長に就いた田村憲久議員と、また番組で一緒になる。これは彼と議論すべき問題だ、と私は判断した。田村議員は私が厚労省時代に仕えた大臣であり、面識もある。政治家としても「人間」としても尊敬できる、と感じていた人だ。
「名前がついちゃってるから」
翌日、田村議員は本番30分前に局入りしていた。簡単なメイクの後に、ディレクターが田村議員と私を前に、この日の番組の流れを説明し始めた。私はひそかに台本には無い、「新型コロナウイルスを新感染症に指定して、特措法での対応をすべきではないか」という問題を田村議員にぶつけるチャンスをうかがった。
もっとも、生放送の番組中に議論することは無理がある。本番中、この話題を提案という形で振ることもできないこともないが、与党の新型コロナ対策本部長から生放送で意見を引き出すのはリスクが高い、と考えた。尺が無い中で議論は深められないし、あまりよくわかっていない中で、ノーという言質を生放送で流されたらまずいことになる。特措法は民主党政権下で制定されているから、自民党の中でどれくらい議論が深まっているのか、その按配を読み切れていなかった。
だが、何としても田村議員とこの話題を詰めておきたいと思った。話すなら番組前かCM中、あるいは終了後だと、タイミングをはかっていたが、本番前には話題にできなかったので、CMに入ると口火を切った。
「田村先生、このコロナ、まずは新感染症に指定して、特別措置法で対応する、というのが円滑に対策を打つのに必要だと思いますが」
「新感染症ね、それってね、未知のウイルスってことだよね。このウイルスは、もうコビッド19って名前がついちゃっているから」
私は思ってもみなかった答えに驚いた。
「ゲノムは解析されて、名前はついてはいますが、それが新感染症に指定することの差し障りになるのでしょうか?」
「うん、正体がわかっちゃっているウイルスは新感染症には無理だって、役所は言っているんだよね」
「お言葉ですが、新感染症に致しませんと特措法は動かせません。有事の緊急事態には特措法での対応が円滑です。でないと、法的根拠を求めるために政令を次々と出さないといけない、という事態になります。感染症対策は一刻を争う場面もありますので、特措法運用のカードは残すべきです」
「うーん、そうねえ、でも正体がわかっちゃっているからねえ」
1分弱のCMは終わった。通信販売のサイト名が連呼される映像が目の前に流れている間の会話だった。
新感染症の定義は未知のウイルスと明記されていたにせよ、ゲノムがわかっていても、名前がついていても、ウイルスの挙動や性質、病原性やその成り立ちも不明な新しい感染症なのだから、新感染症に指定できるはずだ。法律ではそう読めるはずだ。
新感染症に指定しないということは、特措法を動かさないということか? やはり特措法は民主党政権下の立法だから、そのまま運用したくないのか? もっと言えば、田村議員の言及した「役所」とは当然厚労省だろう。省庁横断でなく、あくまで厚労省マターにしておきたいから、新感染症と特措法は無しにしておく、という推測もできた。SARSやMERSのように、この新型コロナも国内侵入や流行は起こらないとの楽観視があったのか?
CM中、私はこんな思考をめぐらした。ならば、番組終了後に徹底的に説明するまでだ。だが、「報道1930」の番組終了後に田村議員に説明をしたときには、もうすでに“指定感染症”2類相当の路線は決まっていて、動かしがたい状況であるとわかった。
1月28日、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」となる感染症法の2類感染症と閣議決定された。「2類相当」であるので、医師の届け出義務、感染症の発生・動向・原因の調査、入院、移送、健康診断、就労制限が課される。医療費は国がもつ。これらの業務はそのほとんどが保健所の仕事となり、全ての感染者を隔離する感染症病床が必要となる。危険度が2番目に高い2類ではあるが、無症状者も隔離対象となる等、一部は最も厳しい1類同様の措置となるため、2類相当と位置づけられた。