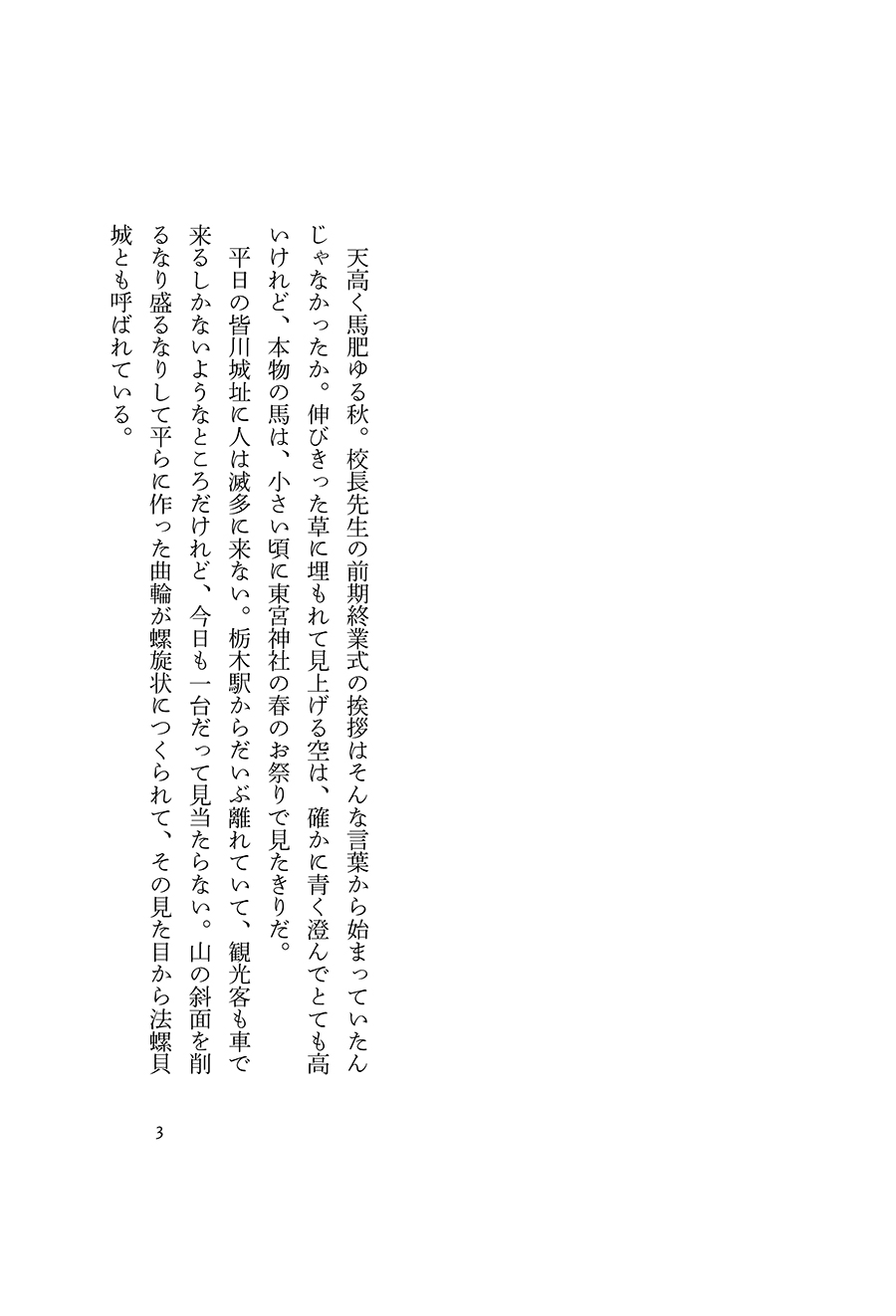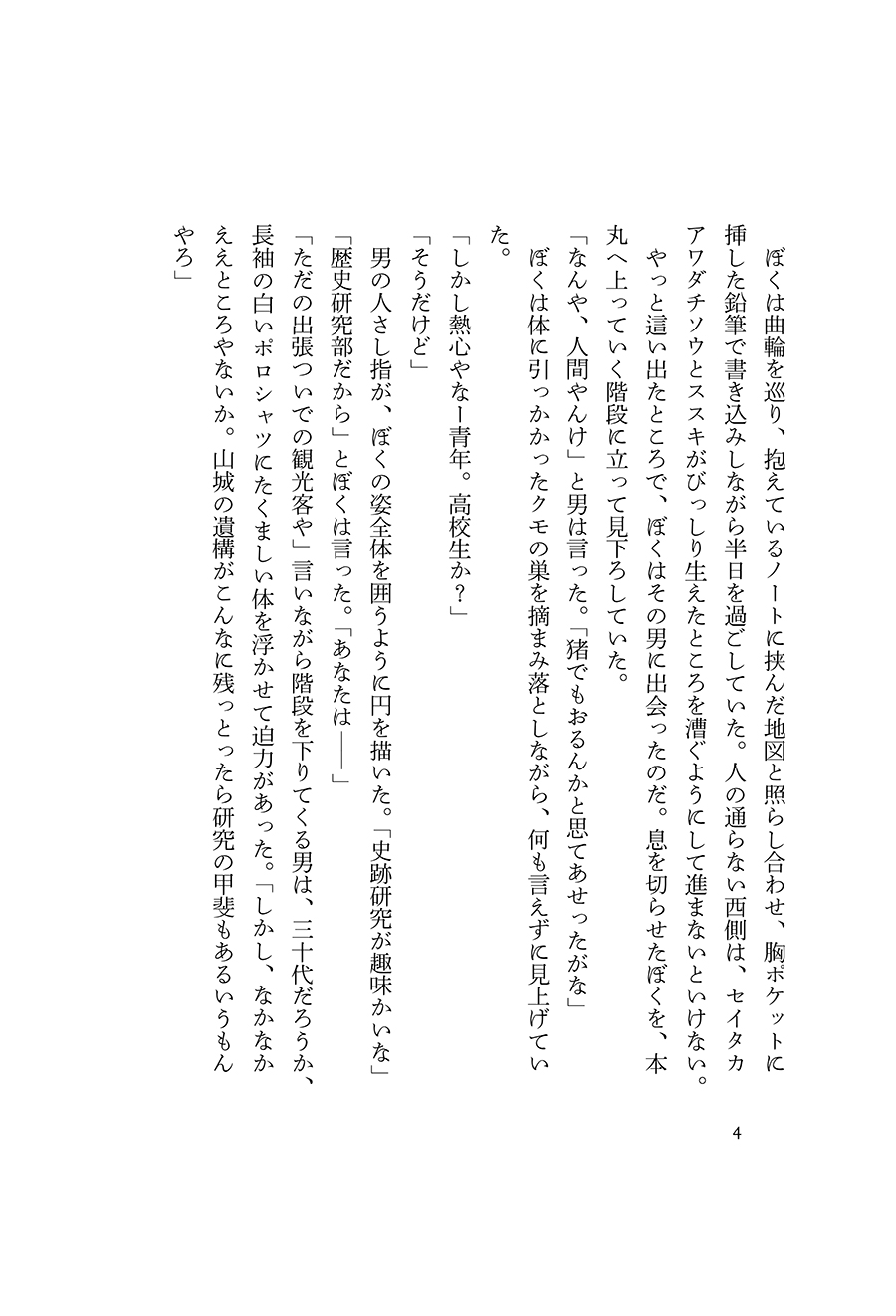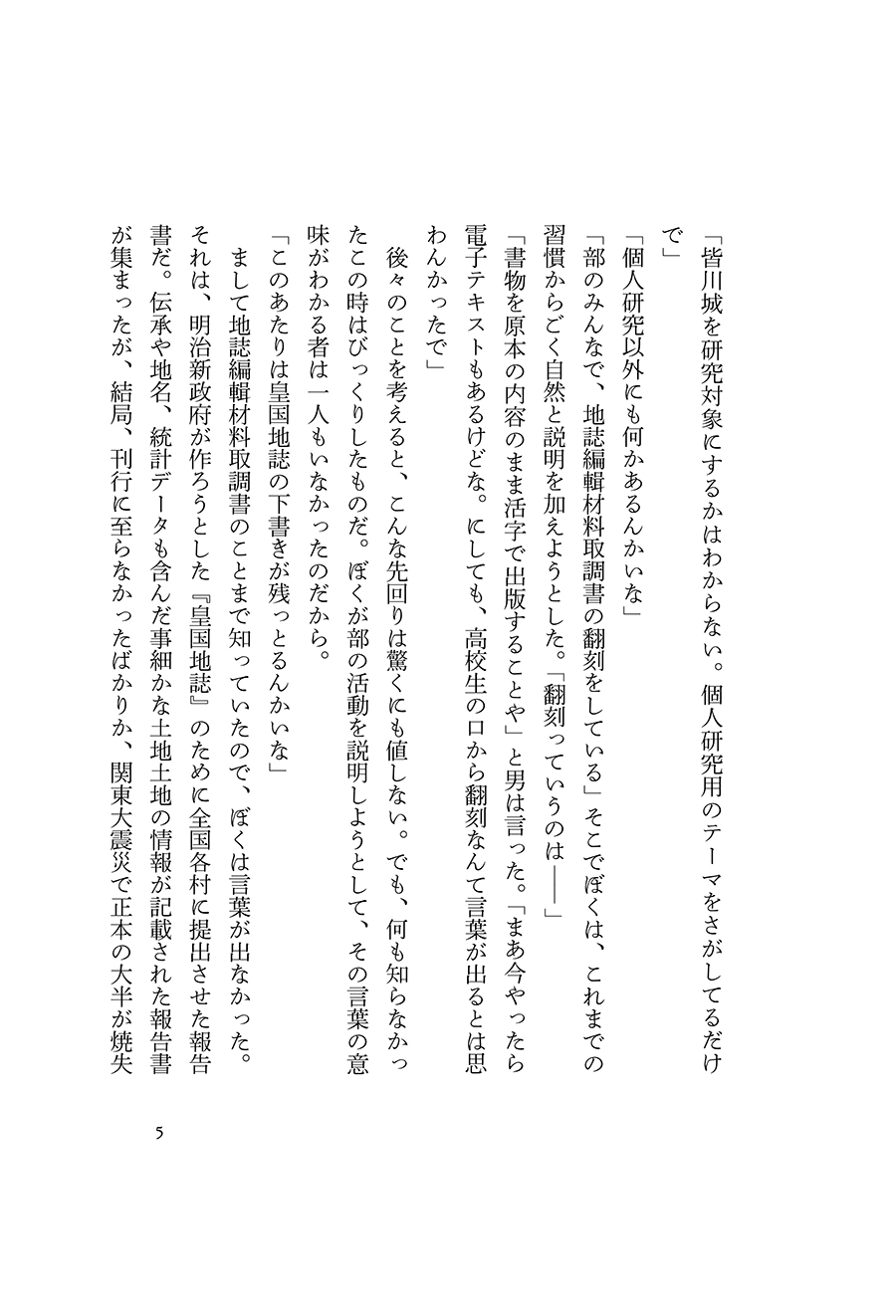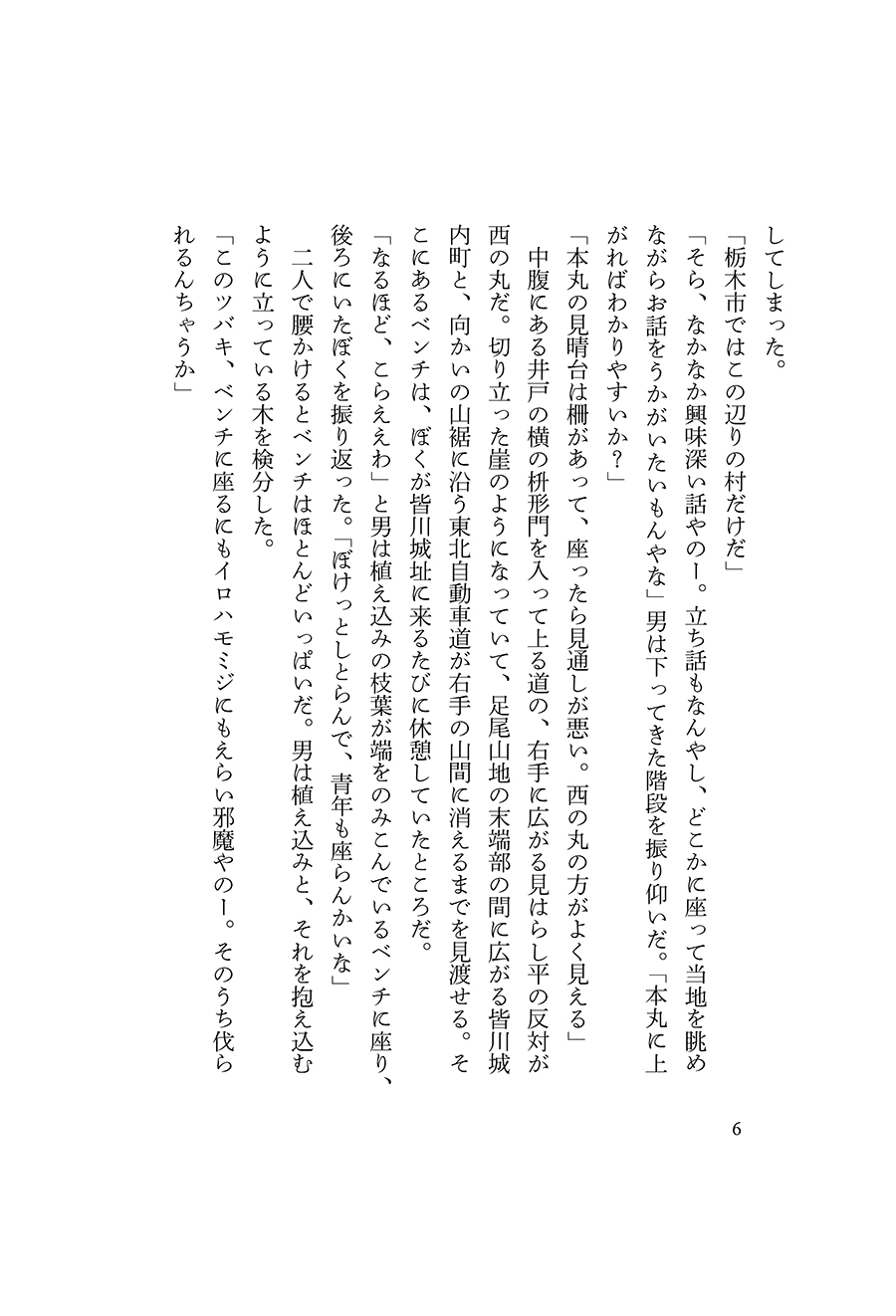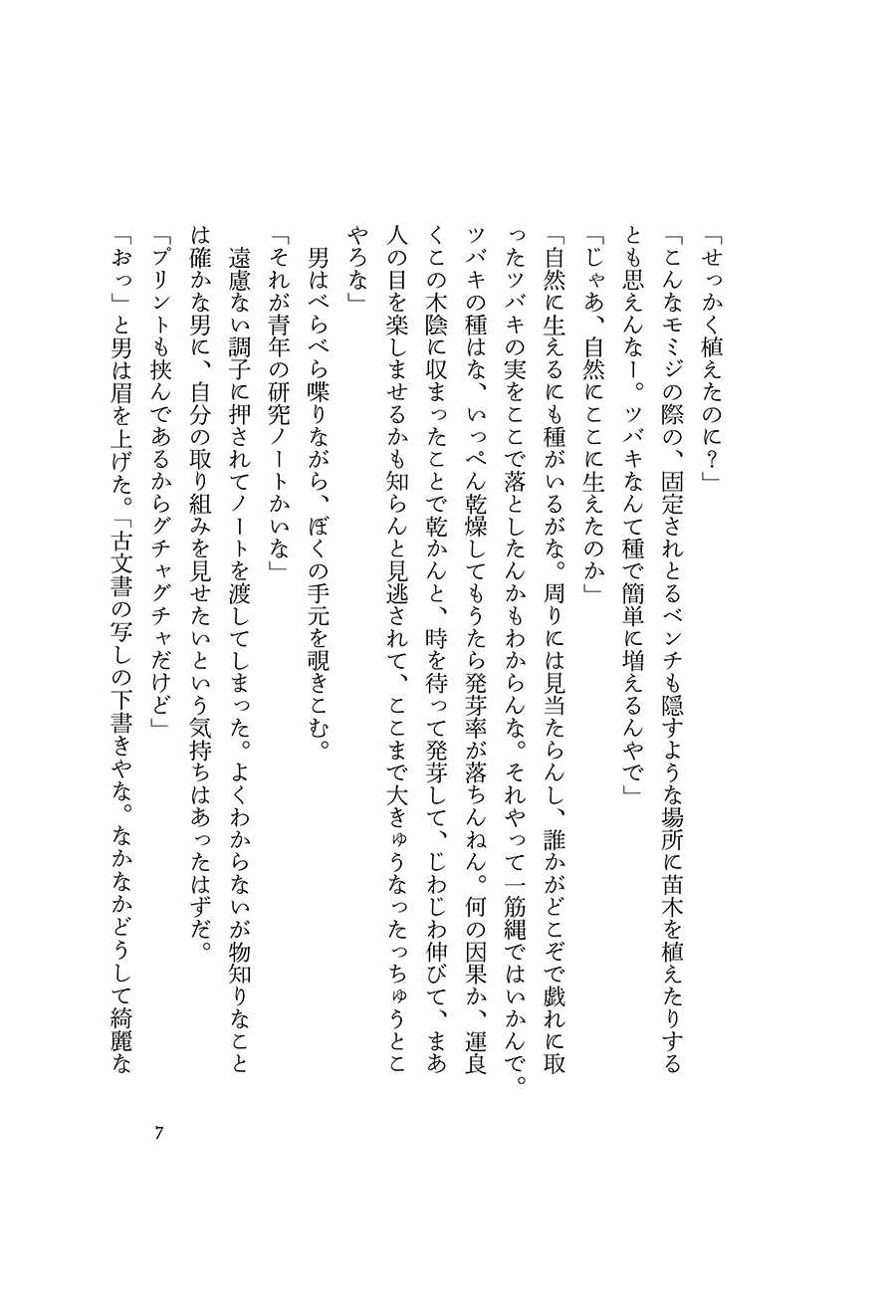天高く馬肥ゆる秋。校長先生の前期終業式の挨拶はそんな言葉から始まっていたんじゃなかったか。伸びきった草に埋もれて見上げる空は、確かに青く澄んでとても高いけれど、本物の馬は、小さい頃に東宮神社の春のお祭りで見たきりだ。
平日の皆川城址に人は滅多に来ない。栃木駅からだいぶ離れていて、観光客も車で来るしかないようなところだけれど、今日も一台だって見当たらない。山の斜面を削るなり盛るなりして平らに作った曲輪が螺旋状につくられて、その見た目から法螺貝城とも呼ばれている。
ぼくは曲輪を巡り、抱えているノートに挟んだ地図と照らし合わせ、胸ポケットに挿した鉛筆で書き込みしながら半日を過ごしていた。人の通らない西側は、セイタカアワダチソウとススキがびっしり生えたところを漕ぐようにして進まないといけない。
やっと這い出たところで、ぼくはその男に出会ったのだ。息を切らせたぼくを、本丸へ上っていく階段に立って見下ろしていた。
「なんや、人間やんけ」と男は言った。「猪でもおるんかと思てあせったがな」
ぼくは体に引っかかったクモの巣を摘まみ落としながら、何も言えずに見上げていた。
「しかし熱心やなー青年。高校生か?」
「そうだけど」
男の人さし指が、ぼくの姿全体を囲うように円を描いた。「史跡研究が趣味かいな」
「歴史研究部だから」とぼくは言った。「あなたは――」
「ただの出張ついでの観光客や」言いながら階段を下りてくる男は、三十代だろうか、長袖の白いポロシャツにたくましい体を浮かせて迫力があった。「しかし、なかなかええところやないか。山城の遺構がこんなに残っとったら研究の甲斐もあるいうもんやろ」
「皆川城を研究対象にするかはわからない。個人研究用のテーマをさがしてるだけで」
「個人研究以外にも何かあるんかいな」
「部のみんなで、地誌編輯材料取調書の翻刻をしている」そこでぼくは、これまでの習慣からごく自然と説明を加えようとした。「翻刻っていうのは――」
「書物を原本の内容のまま活字で出版することや」と男は言った。「まあ今やったら電子テキストもあるけどな。にしても、高校生の口から翻刻なんて言葉が出るとは思わんかったで」
後々のことを考えると、こんな先回りは驚くにも値しない。でも、何も知らなかったこの時はびっくりしたものだ。ぼくが部の活動を説明しようとして、その言葉の意味がわかる者は一人もいなかったのだから。
「このあたりは皇国地誌の下書きが残っとるんかいな」
まして地誌編輯材料取調書のことまで知っていたので、ぼくは言葉が出なかった。それは、明治新政府が作ろうとした『皇国地誌』のために全国各村に提出させた報告書だ。伝承や地名、統計データも含んだ事細かな土地土地の情報が記載された報告書が集まったが、結局、刊行に至らなかったばかりか、関東大震災で正本の大半が焼失してしまった。
「栃木市ではこの辺りの村だけだ」
「そら、なかなか興味深い話やのー。立ち話もなんやし、どこかに座って当地を眺めながらお話をうかがいたいもんやな」男は下ってきた階段を振り仰いだ。「本丸に上がればわかりやすいか?」
「本丸の見晴台は柵があって、座ったら見通しが悪い。西の丸の方がよく見える」
中腹にある井戸の横の枡形門を入って上る道の、右手に広がる見はらし平の反対が西の丸だ。切り立った崖のようになっていて、足尾山地の末端部の間に広がる皆川城内町と、向かいの山裾に沿う東北自動車道が右手の山間に消えるまでを見渡せる。そこにあるベンチは、ぼくが皆川城址に来るたびに休憩していたところだ。
「なるほど、こらええわ」と男は植え込みの枝葉が端をのみこんでいるベンチに座り、後ろにいたぼくを振り返った。「ぼけっとしとらんで、青年も座らんかいな」
二人で腰かけるとベンチはほとんどいっぱいだ。男は植え込みと、それを抱え込むように立っている木を検分した。
「このツバキ、ベンチに座るにもイロハモミジにもえらい邪魔やのー。そのうち伐られるんちゃうか」
「せっかく植えたのに?」
「こんなモミジの際の、固定されとるベンチも隠すような場所に苗木を植えたりするとも思えんなー。ツバキなんて種で簡単に増えるんやで」
「じゃあ、自然にここに生えたのか」
「自然に生えるにも種がいるがな。周りには見当たらんし、誰かがどこぞで戯れに取ったツバキの実をここで落としたんかもわからんな。それやって一筋縄ではいかんで。ツバキの種はな、いっぺん乾燥してもうたら発芽率が落ちんねん。何の因果か、運良くこの木陰に収まったことで乾かんと、時を待って発芽して、じわじわ伸びて、まあ人の目を楽しませるかも知らんと見逃されて、ここまで大きゅうなったっちゅうとこやろな」
男はべらべら喋りながら、ぼくの手元を覗きこむ。
「それが青年の研究ノートかいな」
遠慮ない調子に押されてノートを渡してしまった。よくわからないが物知りなことは確かな男に、自分の取り組みを見せたいという気持ちはあったはずだ。
「プリントも挟んであるからグチャグチャだけど」
「おっ」と男は眉を上げた。「古文書の写しの下書きやな。なかなかどうして綺麗な字やないか」
「そこにはぼくが担当してる皆川城内村のものしかないけど、村ごとに担当がいる」
興味深そうに資料をめくっていく男の手つきは慣れたもので、日頃から書類を扱う仕事をしているんだろうと思わせた。でも、あんまり素早くめくっていくものだから、内心がっかりした。やはり、こんな田舎の地誌などに興味はないのだろう。
男は数十秒ほどでノートを返してきた。「研究用に残そうっちゅうことやろうけど、顧問の先生がさぞ立派な人なんやろうなー」
それは間違いなかった。ぼくは、この出会いを先生に報告しようというさっきまで抱いていた思いをしぼませながら、それでも男の言葉を嬉しく思いながら、なんだか恥ずかしくなってきた。かがみこみ、足に挟んだリュックにノートをしまおうとした。
「おい、それはなんやねん」
リュックの口はほとんど開いていなかったので、そう言われた時は何のことかわからなかった。見上げてみると、男の鋭い視線は、上の方だけがわずかに覗いているばかりの、個人研究には関係のない資料を手当たり次第に突っ込んだクリアファイルに注がれていた。
「なんや、竹沢屋――」
それが一番上になっていることすら、ぼくは忘れていたのだ。
「蔵書目録。昔の皆川城内村の家のだ」
「おもろそうやんけ」男が上向きに開いて出した手は、かなり大きく見えた。
写真をプリントアウトしたものでかなりの量がある。どうせさっきと同じだろうと、ファイルごと渡してやった。案の定、次々めくっていく男の仕草は、さっきと何も変わらなかった。
「こんなところで余裕のある商家やったんやのー」
「酒屋だ」
「まあ、そうやろなー。さっきのノートの「民業」の項目にも、皆川城内村に一戸、生産額は二千や三千と書いてあったわ。下等酒とあったけど、道楽の学問に回すには十分な稼ぎやろ」
ぼくは驚いて何も言えず、資料に目を通している男を見た。
「なんや、間違っとるか?」
「いや」とぼくは首を振った。「さっきの一瞬でそこまで見たのか」
その時、男の目が資料の一点から動かなくなった。わずか数秒だったけれど、答えもなかったので、ぼくはもう一度、少し言葉を変えて訊き直した。
「ちょっと見ただけで、そんなに細かいところまで?」
「一瞬でもないがな」男はそのページをゆっくりめくると、顔を上げた。「酒屋なら宿場との取引もあるやろうし、文人交流も絡んで書物も手に入りやすいかもわからんな。ほんで、その酒屋は今も続いてるんかいな」
ぼくは少し考えて「いや」と言った。「家は続いてるけど、酒は造ってない」
「この辺りの名家ではあるんやろ、土地持ちの、でかい家の」
「そんな感じでもないと思うけど」
「蔵も蔵書も跡形もなしか」
「詳しくは知らないけど、たぶん。普通の家だ」
「そうかいな」
その瞬間、元通りにされたぶ厚いクリアファイルのまっすぐな底辺がぼくの喉元に突きつけられた。思わず身をすくめたぼくに顔を寄せて、男は「返すわ」とにやりと笑った。ぼくはクリアファイルを両手で受け取り、ゆっくりと首から離した。
「竹沢家はどの辺や」と言った男は、もう眼下に目をやっている。
「あの中学校の」ところどころ水のたまった広い校庭をぼくは指さしていた。「向こうのあたり」
「まだ明るいし、どや、その竹沢家まで案内してくれんか。ちらと覗いてみたいねん」
ぼくが口ごもったのを、この遠慮のない男が見逃すはずもない。
「なんや、迷惑か? 用事でもあるんかいな」
「そうじゃないけど、どうして行くんだ」
「単なる知的好奇心やがな。明治初期に酒造りをしとったんならまず有力者の家や。後に困窮して蔵書を売りに出したかも知らん。そんな没落の歴史の名残を目の当たりにして我が人生の教訓にできるかもわからんがな」
「そんな目的であなたと二人、近くをうろうろするのはぼくはいやだ」
「何を調子のいいこと抜かしとんねん。自分かて日頃からさんざんやっとることやろ。だいたい、知的好奇心を満たすためやろうと泥棒に入るためやろうと、公道歩いて後ろに手が回るようなことはないんやで」
男は無理やりぼくに案内させた。その家は、昨日の大雨でいつにも増して水を流している藤川沿いにある。生け垣に囲まれた竹沢家を一周して、小さな前庭が覗けるだけなのを確認すると、男はすぐそばにかかる橋の欄干から身を乗り出すようにして流れを見つめた。ぼくも安心して家を離れ、男の不可解な興味を見定めてやろうと背後に立っていた。
「わしからしたら広い土地やけどな。大都市とはさすがに土地の感覚が違うのー」
「あなたは大阪だろ?」
男は怪訝な顔でぼくを見た。「なんでそう思うねん」
低く押さえつけるような声に怒らせたかと心配しながら、「だって」と言った。「大阪弁だから」
男はぼくを見据えたまま何も答えない。何か濁すような言葉を付け足そうとしたところで、ふっと表情を和らげてうなずき、感心したように「なるほどなー」と言った。
胸をなで下ろすように血が流れていく。さっきの資料読みの速さと、威圧するような言動で、ぼくはこの男を少し恐れ始めているようだった。
「自分、コナン君みたいな名探偵になれるかもわからんで」男はぼくを指さし、おどけるようにへへへと笑った。「まあ、資料から昔を追うのも同じようなもんやろ」
「知らないけど」
男は身を翻し、透明な川の水をしみじみ眺め下ろした。「湧いて間もない流れやから、雨の後でも綺麗なもんやのー」それから藤川と書かれた橋の表示板を確認している。「さっきの資料やと、藤川はもっと下流の方だけを指しとったみたいやな。合流前のこの辺りは、もともと何ちゅう名前やったんや」
「五下川」
そのあたりのことは翻刻作業で頭に入っていた。でも、ざっと読んだだけの資料をもとに的確な質問をされるのはやはり不気味なものだ。写真を撮るように記憶ができる人間の話を聞いたことがあるけれど、その類なのだろうか。
「ほな、この五下川の水で酒造りをしとったわけや。源流はあっちの山かいな」
男は西に広がる山並みを指さした。
「川の流れからするとそうみたいだ」
「なんや、知らんのかいな」
「ぼくは城内村の担当だから。この辺から先は柏倉村だ」
男が鼻で笑うのがしゃくで、ぼくは慌てて地図を引っぱり出した。
「別に慌てて調べんでもええがな」と男は手が汚れるのも構わずに欄干に手を置き、軽やかに屈伸している。「見に行きたいわけでもあれへんし」
「川は鞍掛山まで続いてる」と半ば聞こえないふりですぐに言った。「琴平神社のあたりが源流みたいだ」
「コトヒラ神社やと」
しゃがんだ体勢で止まった男は、黙って山の方を仰いでしばらく見つめていた。
「鞍掛山の山頂にある、この辺りで一番栄えてた神社だ」
「なるほど、鞍掛山いうぐらいなら天辺はちょっとした平地や、でかい神社も造れるわな。栄えてたっちゅうのはどういうことやねん」
「火事でみんな焼けた」
「勧請はいつや」
「勧請って?」
「まあ、いつその社が建立されたかっちゅうことや」
「翻刻作業中のやつのコピーがある。確か、琴平神社のところまでは終えていたような気がするけど」
ぼくはリュックの中を探りながら、男の期待に応えようとしている自分に気付いた。なんとなく後ろめたい気がしたその時、覗きこもうとする気配を察して、思わず背中を丸めて遮った。
「なんや、けったいな奴やのー」
「琴平神社はぼくの担当じゃない。外の人間に、しかもあんたみたいな怪しい人間に見せていいかわからないからな」
「殊勝なことを言うやないか」にやにやしながら、わざとらしく一歩下がって言った。「ほんだら青年に任せるわ。なんて書いてあんねんな」
「安永元――」
「安永元年いうたら一七七二年やな」
ぼくの驚きといったらなかった。「あんたは元号から西暦に直せるのか」
「昔とった杵柄や。何を隠そうわしも、高校から大学と、青年と同じ歴史研究会に入っとったんやで。ラグビー部にも所属しとったけどちょっとした強豪でなー、兼部は無理な決まりやったけど、研究会ならええやないかとさんざんゴネたったんや。生徒手帳の校則に抜け穴があってのー」
「ラグビーと歴史研究会なんて、そんな兼部があるのか」
そう言いながらも、この男の体格や知識を目の当たりにしていると、嘘をついているようには思えなかった。資料を元に戻すぼくの背中に、男は喋り続けた。
「世の中、アホばっかりなんやで。考えてもみんかい、ラグビーで花園に行ったところで、大学でも続けてさらに実業団、今ならプロもやけど、そんな人生歩めんのは一握り、狭き門もええとこやがな。あきらめて職を選り好みする者は、頭がないと話にならんわ。その時、履歴書にラグビーで花園行って歴史研究会と兼部してましたと書いてみぃや。そんな奴おれへんがな」
「ハナゾノってなんだ」
「花園も知らんのかいな」思わず勢い込んだように言った男は、そんな素の反応を取り繕うように「まあ、まあ、無理もないわ」と自分の顎を撫でた。「花園ゆうたら高校ラグビーの聖地、花園ラグビー場のことやがな。野球でいう甲子園みたいなもんやな。さすがに、甲子園はわかるやろ」
「わかるよ」
縁遠い世界のことが話されるうちに、リュックを閉じて立ち上がる。
「就職の面接でな、わしは今まさに、青年が言うたような反応を受けたんや。そんな兼部があるのか言うてな。人間、新奇なもんに直面すると頭が鈍って判断が単純になんねん。大企業の人事部長かて一緒やで。こいつは運動だけが取り柄やないちょっと変わった切れ者やと勝手に思い込みよったわ」
「でも、あんたは実際にしっかり活動してたじゃないか。元号を西暦に直せるんだから」
「そこやがな。ただでさえそう考えてまうのに、ほんまにそうやったら、人を騙すも騙さんもないわ。相手の浅はかな早合点を確信に変えてやるまでをこっちで請け負うんは手間やけども、わしは努力を惜しまずそっちを選んだいうことやな。傾向と対策なんちゅうもんは、埒外の努力ができん凡人の悪あがきやで」
「歴史研究は就職のための努力だったのか」気に食わずぼくは言った。「あんたにとって」
いつの間にか腕を組んでいた男は、細い目をぎっと開いて口を結び、ぼくを見返してきた。しばらく見合っていると、口の端がわずかに開いて笑みをつくった。
「言うやないか、青年」と男は言って、ぼくの肩に手を置いた。「確かに、そないなことは好きやなかったらでけへんわなー。歴史研究をラグビーのついでのように語るっちゅうことは、わしも世間にすれて優劣をつけとるのかも知らんわ。青年のように自信をもって自分のやりたいことに邁進せんとあかん、反省や」
その手はぼくの肩を覆い尽くすほど大きい。自分勝手にうなずいている男から、ぼくは目を離さずにいた。
「しかし、そんなん言い返されたん初めてや。青年が面接官やなくて命拾いしたわ」
「ぼくも、あんたみたいな人に会うのは初めてだ」
「ほんまに口が減らんのー」
呆れたように言った男はぼくの肩から手を放した。やたらな会話がやむと川の流れの音が聞こえてくる。男はまた踵を返し、川面をじっと見下ろした。
「時に青年、明日は暇かいな」
ぼくは少し考えた後で「どうしてだ」と言った。
「すこしのことにも先達はあらまほしき事なりと授業でやったやろ。琴平神社に案内してくれやと言うとんねん。青年の方でも、個人研究のヒントがあるかも知らんで」
確かにそうだと思った。戯れに欄干へ片足をかけ、そこに肘をのせた男の背中を見ながら「別にいいけど」と答えた。
男はその体勢で勢いよく振り返った。「また明日の午前十時に、ここで待ち合わせようやないか」
「ここじゃなくたっていいだろ」
男は笑っているのか考え事をしているのかわからない顔でぼくをじっと見ている。ぼくは、これ以上ぼろは出すまいと、何も言い返さなかった。
「ほな、皆川城址の、二人並んで町を見下ろした、西の丸のあのベンチはどうや? 上り下りが面倒やけども、我々が初めてゆっくり思いを語らい合った思い出の場所やからなー」
「それでいいよ」とぼくは言った。「思い出の場所とは思ってないけど」
「なんでやねん。今度から待ち合わせは、あっこに決めようやないか」
「そんなに何度も待ち合わせるつもりなのか」
「当たり前やがな。エリートの長期出張ほど暇なもんはないんやで」男はやっと欄干から足を下ろして、今度は腰に手を当てて体を反らした。上を向いた顔が、ごろりとこちらを向いた。「青年とは長い付き合いになりそうやのー」
*
家からすぐの栃木駅を南口から北口へ抜けて、永野川に突き当たるまで西に歩いて、しばらく北上して、東北自動車道をくぐるまで一時間。やっと皆川城址の山が見える。このあたりが、かつて皆川城内村と呼ばれたところだ。
公民館の脇にある入口で見上げると、西の丸のベンチにすでに座っている男が見えた。目が合っても、腰を上げる気配がない。組んだ足の膝上に頬杖ついて、ぼくの方をじっと見ている。ぼくが自分の足元を指さすと、わざとらしく伸びをして視線を外し、手を庇にして遠く町を見下ろし始めた。太陽は雲に隠れていて、眩しいはずもないのに。
仕方なく登って行くと、男は座って腕時計を構えて待っていた。ベンチに缶コーヒーが置いてある。
「なんや、時間ちょうどやないか。待ち合わせは少なくとも五分前には着いとくんがマナーやで」
「どうせ下りるんだから、あんたが下りてきたらいいだろ」
「わしだけ上り下りしたら不公平やろがい」男は言って立ち上がった。「それに、ここ西の丸はわしらの思い出の場所やないか」と言って目の前の花を指さす。「彼岸花も綺麗に咲いとるがな」
「その思い出っていうのがよくわからないんだよ」
「青年がここの方がええと言うたんやで」
「あんな人の家の近くで待ち合わせができるわけないだろ。あんたみたいな怪しい男と」
「竹沢家もええ待ち合わせ場所やと思うんやけどなー」
反応をうかがうように見つめてくる男の言葉を無視して歩き出すと、慌ててついてきた。上着の中のポロシャツ以外は昨日と同じ格好で、靴も運動靴という感じではない。
「しゃあないやろ、仕事用の革靴以外はこれしか持って来とらんのやから。言うとくけど、ポロシャツは別のやで」
「何も言ってないじゃないか」
「そない気合の入った格好した奴に値踏みするようにじっくり見られたら気ぃ悪いがな」そう言って、男は飲みかけの缶コーヒーをぼくに差し出してきた。「結構な悪路なんか?」
男の言う通り、ぼくは昨日以上に動きやすい格好で、靴も父のトレッキング用のものを借りてきていた。缶コーヒーは受け取らなかった。
「ぼくも行ったことない」
「ガイドにしては頼りないのー」
男は残り少なかったらしい缶コーヒーを上を向くまで傾けて飲み干し、最後は下品に音を立てて啜ると、もう一度渡そうとしてきた。もちろん受け取るはずがない。
竹沢家の近くで県道75号から126号に外れ、琴平神社を目指して歩く。車通りがまったくないのは、126号は山間の葛生に出るだけの道だからだ。栄えた佐野へ出るには、東北自動車道と並んだ75号を利用する。
「せやから、こっちの峠道はサイクリストが多いんやで」
「なんでそんなこと知ってるんだ」
「調べたんや」と男は言った。「琴平神社のことは調べとらんから安心してな。せっかく連れがいてるのに、資料の確認に行くだけやといまいち興が乗らんからなー。どや、今日という日を心待ちにしとった様子が窺えるいうもんやろ」
確かに、草むらや小さな田畑の間を縫っていく川を時折またぐ広い道を何キロもまっすぐ歩く間も、上機嫌な口は減らなかった。だんだん細くなる道は傾斜がつくにつれて木々が取り巻き、急なカーブで峠道に入る。その手前、車道の脇に参道への入口があった。
「お、ここやここや」
石段を上って鳥居をくぐると、木々の間に狭い急坂の土道が続いている。道の真ん中はV字に削られていて雨水が流れるらしく、一昨日の雨もところどころに溜まっていた。
「なんや、かなり急やし水も残っとるのー。こんな格好ではかなわんわ」
木々が日を遮り土もまだ湿っているところを、それでも男は気にする様子もなく登って行く。岩盤が剥き出しになって段をつくっているところには、足を丁度かけられる形の窪みがあった。
「見てみぃ」と男はそこに足をぴったり嵌めてぼくを振り返った。「なかなか歴史を感じるやないか。確かに参拝者は多かったみたいやのー。先にまた石段もあるで」
かなり古めかしく、ほとんど土に埋もれている低い石段が見えた。
「あんたは、どうして琴平神社が気になったんだ」
「コトヒラいうたら、讃岐の金刀比羅宮、こんぴらさんから勧請したに決まっとるがな」
他の寺社から分霊を迎えることだ。琴平神社は、関口一郎左衛門らによって讃岐の金刀比羅宮から神璽を迎えて祀ったと資料にも書いてあった。男は、ぼくがそれらを調べてきたことすら承知しているようで、何も説明を加えなかった。
「だからって気になるのか」
「金刀比羅宮の大物主神は、水運の守護神なんやで。仕事の合間に、問屋町の名残を横目に巴波川沿い歩いとったら、点と点が繋がるやないか。きっと、江戸と結ぶ舟運をお守りくださいと、こんな山まで商人たちがせっせと足を運んだんや。遠い昔の同業者と同じ土を踏んどるんやと思たら感動するがな」
とてもじゃないが、その声色は感動しているようには聞こえなかった。古い枯れ葉に混じって石が撒かれた参道を、木の幹にくくりつけられた「あともう少し! がんばってネ」という札に「誰にぬかしとんねん」と茶化しながらじぐざぐに登って行く。
その斜面に捨てられていた空き缶を見て、男はふと立ち止まった。ずいぶん古いもので、ほとんど錆びている。わざわざ道を逸れてそっちに歩み寄りながら、ポケットから小さく畳まれた透明のビニール袋を出して広げた。
「何してるんだよ」
「見たらわかるやろ」缶を拾った男は、泥の塊を振り落としながらぼくを見た。「最近の若いもんはゴミ拾いも知らんのかいな」
「知ってるよ。なんでそんなことをするのかってことだ」
「心が痛んでたまらんねや」目を閉じて胸に手を置く。「ここまで何もなかったんで安心してたんやけど、不信心なもんはどこにでもおるんやなー」
「嘘つけ」
「なんとでも言うたらええわ」男は体を捻り、ビニール袋をボディバッグのストラップに結びつけている。「青年も見つけたら入れや」
核心をつけないまま先を急ぐ。倒れた木をくぐったところで足元にペットボトルの包装を見つけてしまった。ガサガサと音がして振り返ると、男がビニール袋を両手で持ち、口を結んだ厳しい顔で凝視している。仕方なく拾うと、両手を開いて袋の口をわずかに広げた。睨みつけられたまま近づくと、口はだんだん広がっていった。放り込むと、穏やかに微笑み、目をつぶって頭を下げた。
「あんたがやると茶番だ」
「茶番やない。作善いうねん」知らない言葉を口にしながら、男はビニール袋の口を握って閉じた。「茶番やとしても、それで参道がきれいになったらええがな」
やがて、両側を石垣に挟まれたひときわ長い石段が現れた。苔生して落ちた枝も散乱しているが、百段以上の立派なものだ。見上げた先にはぽっかりと青空が広がり、そこが頂上だとわかった。急で踏み面も狭い石段を上がって振り返ると、足がすくみそうになる。男はそこへ足をかけもせず、腕を組んでぼくを見上げている。
「上がらないのか」
「しんどそうやから、わしはこっちの迂回路で上がっていくわ」と奥の坂を指さした。「年やし、どうも靴が心許ないからのー」
「ちょっと急だけど、ただの石段だ」
「そうかいな」と視線を逸らして指をさす。「あの石垣の積み方、野面積と言うんやで」
その振る舞いを変に思って「もしかして、怖いのか?」と訊いた。
「何を言うねん」と鼻で笑うが、目は笑っていない。「アホちゃうか」
ぼくは思わず笑みを漏らした。昨日からずっと、男の弱みを探していたのだ。
「人々と同じ土を踏むんだろ」
「そこは土やない、石や。迂回路は土やと思うんやけど」
屁理屈ばかり言う男に背を向けて、ぼくは石段を上っていった。
「おいコラ、待たんかい」と男は言い、慌てて迂回路に入って行った。
上に着いたらバカにしてやろうと考えていたぼくの目論見はしかし、上りきって平らに均された頂上に出たところでまったく消え失せてしまった。一番奥、拝殿の前に誰かいると思った瞬間、ピンクのブルゾンの下に見慣れた学校指定ジャージの紫色が目に飛び込んできて、その人物が振り返ったからだ。
*
お互い呆気にとられたわずかな間に、男が石段を少し下ったところから出てきた。
「おい、ごっついでこっちの道、鹿のクソだらけで足の踏み場もないわ。玉砂利か思たがな」
何が嬉しいのか弾んだ声の男は、振り返ったぼくの様子を見て一転、怪訝そうに「なんやねん」とつぶやいた。「どないしてん」
「浮田先輩」
ぼくの後ろの遠くから澄んだ声がして、男の目がそっちを見やるのに合わせて顔を戻す。
「先輩も調査ですか?」続けて問いかける眼差しは、すぐにぼくを通り越した。「こんにちは」と、こんなに怪しい男にも笑顔で挨拶する。
「こんにちは」関西弁のイントネーションで返すと、男は案の定、明るい声で喋り始めた。「なんや、二人はお知り合いかいな。浮田くん、紹介してんか」
ぬけぬけと今初めて聞いた名を使う男に「同じ学校で、歴史研究部の後輩」と伝えた。
「竹沢です」
男は眉の根一つ動かすことなく、頭を軽く下げた上目遣いに微笑を返した。
「あの、お二人は……?」
ぼくが言葉を選ぼうとしたそばから、男がすぐ横に音もなく出てきた。
「観光で来たんやけども、さっき偶然、浮田くんと下で会ってのー」と肩に手を置いてくる。「わしもこういう史跡にはちょっとばかし興味があるんで、なんやえらい意気投合してしもたんや。そしたら、親切に案内役を買って出てくれるやないか」
「私たち、部でこの辺りの郷土史の研究してて」
「さっきちらっと聞いたで、なんや、明治時代の古い資料を出版し直そうとしてるんやって?」
どうして男が無学を装っているのかわからず黙っているうちに、二人の会話は弾んでしまった。さっきは男自らがした一通りの説明を、ずっとたどたどしく竹沢が説明し、男はしらじらしく初めて知ったとでも言うように感心しきりで相槌を打った。
「私がこの柏倉村の担当なんです。琴平神社の資料もありますよ」と竹沢は言った。「見ます? ここ、由緒とか、詳しい説明の看板も何もなくて不親切だから」
「そんな貴重なもん、部外者のわしが見せてもろてええんかいな」
「もちろん」竹沢は人当たりのいい満面の笑みでうなずく。「みんなで勉強しましょ」
はっはーと男はわざとらしく感嘆の声を響かせた。「好学の士はみな仲間やと言うわけかいな。大した心がけや、そうでないといかんわなー」そして、わざわざぼくの方を向いて言った。「ほんまに君たちはすばらしわ。日本も安泰やでほんまに」
竹沢は大袈裟な男の様子をけらけら笑い見ながら、石段脇にある大きな方柱形の石の上に地誌を入力し直した資料をのせて、傍らにしゃがみこんだ。ぼくが持っているのと同じものだ。
「この石、社号標なんですけど、倒れちゃってるからテーブルにしましょ」
「ほんまや」側面を覗きこんだ男が言う。「大正三年と書いてあるがな」
「多分、そっちの基礎石に立ってたんです。長さがぴったり同じだから」
そばに高さ三〇センチほどのロの字形の石枠がある。真ん中の凹みには、土が詰まっていた。
「山火事にあったと聞いたけど、その時かのー。火事で石は倒れへんか」
「どうでしょう。山火事は戦後間もなくのことらしいですけど」
地誌にある説明はこうだ。
琴平神社 無格社。社地東西三十間南北十一間、面積七畝二十六歩。官有地。村の酉の方字琴平鞍掛山の嶺上にあり。大物主命・崇徳天皇・大山祇命を祭る。安永元壬辰年三月創建す。地名を鞍掛と称す。天保九戊戌年十二月神祇官統領伯王殿公文所御勧遷の允司を乞へ倉掛山金刀毘羅宮と称し、明治元年戊辰年鞍掛山琴平神社と改め茲に信仰の諸人群詣す。祭日陽暦毎月十日。祠東向き縦二間横九尺樹木少なし。拝殿縦五間横二間、額殿縦八間横三間半、社務所縦八間横三間半、鳥居二棟、石燈籠五個、鉄製天水鉢四個あり。また石製玉垣及石階二十間あり。信徒戸数五百四十六戸、講社人員一万五千八百人、境外附属地三反三畝九歩。
「現代人には単位がようわからんくて敵わんわ。尺貫法っちゅうやつやろ」
わからないなんて嘘だろうと思いながら、資料に目を落とす男を見ていた。この間に、もう必要なことは覚えてしまったはずだ。
「一間は一・八二メートル。畝は九九平方メートル、歩が三・三平方メートルです」
「わかるんかいな、さすがやのー」
「ここにメモしてあるから」竹沢は左手で資料の端を指さし、右手を頭にやって笑った。
「なんやそれ」と鼻で笑った男は境内を見渡した。「ほんだら、この鞍掛山の頂上の平地は八〇〇平方メートル足らずいうことやな。鞍掛山というだけあるやないか」
奥に拝殿、本殿、社務所が配され、右手にいくつかの灯籠や記念碑、手水鉢が並んでいる。左手には小さな愛宕神社があった。
「この額殿いうのは何やねんな」資料に目を戻した男が訊く。
「石段の途中から、それを跨ぐみたいにかかる三階建ての建物があったんです。ほら」と言って石段の脇を指さす。「石段の横が大きく段をつくっているでしょ。あそこに額殿の脚が立ってたんです。あ、当時の絵もありますよ」
慌ただしく引っ張り出してきたプリントには、鞍掛山の鳥瞰図があった。石段や社屋が山上を埋め尽くして広がり、長い石段の頂上付近を覆うように門が立っている。
「なるほど、こんな山頂にえらい立派なもんを建てたもんやわ」男も興味深そうに顔を寄せた。「これがいつ頃の姿やって?」
「額殿の完成は明治十一年ですね」
「今じゃ見る影もないのー」男は石段を見下ろし、境内を振り返った。「まあ、参拝者の少なかった江戸時代の姿に近いっちゅうことか」
あははとおもしろそうに笑った竹沢は「確かにそうかも」と言って立ち上がった。
「しかし、さすが担当なだけあって何でも知っとるんやなー。浮田くんの出番があれへんがな」
「あ、すいません」竹沢は顔の前で手を合わせ、ぼくに謝る仕草を見せた。
「いいよ、別に」
「ここはかわいい後輩に花を持たせたらええがな」男は馴れ馴れしくぼくの首の根元に大きな手を置いた。そして竹沢に隠れて何か伝えるように、ぼくの首の肉を何度かつまみながら、竹沢に向かって言った。「実は、浮田くんとはこの後、担当の皆川城址を案内してもらう約束をしとるんや」
「わ、いいですね」と竹沢は言った。「そういえば先輩、個人研究って皆川城址にしたんですか?」
「まだ迷ってる。竹沢はここにするのか」
「はい、来週から資料を集めて、色んな人に聞き取り調査をしてみようと思ってます」
「おもしろそうだもんな」
男は、ぼくたちの顔を交互に見てにやりと笑った。
「そんなら、君ら一緒に琴平神社の研究をやったらええやんか」
ぼくは面食らったが、竹沢はすぐに「あ、いいですね」と言った。
「個人研究ゆうたって、同じことに興味を持ったらいかんなんちゅうことはないし、そうやったら協力し合うのが筋ちゅうもんや。君らの先生は、地誌の翻刻をしようなんちゅうこの世に資するとは何かをわかっとるえらい人や。共同研究はいかんなんて噴き上がるケツの穴の小さい人間ではないと思うで」
「ケツの穴」とウケながら竹沢がぼくを見る。「でも、それだと先輩がイヤじゃないですか?」
「ぼくは」イヤなわけがない。「別に」
「別にやなんて、素直やないのー」男が手をすりながらからんでくる。「はっきり言うてここはかなり興味深い場所やで。由緒も来歴も、明治になって急に栄えたんも気になるから栃木宿の商人連中との関連も見なあかん、調べなあかんことだらけや。わしが学生やったら嬉しい悲鳴あげてかじりつくとこやで」一気に言葉を並べたところで竹沢を見た。「おまけに、それをこんな優秀な研究者と一緒にできるなんてな?」
「ですよね?」
冗談にのせられておどけた竹沢が、男と顔を見合わせて何度もうなずく。身長差のせいで見上げる風になって、ややふくよかな首筋の白さに目がいった。
「男や女やいうご時世でもないけども、向き不向きはあるもんや。鹿も出入りしとるようやし、足場の悪いとこもあるわ。協力できるもんはせんとなー」
「竹沢がいいなら、先生に相談してみよう」
「そうしましょう」
「二人は互いの連絡先なんかは知っとるんかいな」
さすがに竹沢も口ごもり、ぼくも黙っていた。男は意に介さぬ態度でぼくたちのLINEを交換させて、何度もうなずいている。
「ほな、これからしっかり研究するんやで。出版されるんならわしもチェックできるがな、楽しみやなー」
午後から予備校だという竹沢と一緒に、ぼくたちも下りることにした。男は上機嫌で迂回路から先導し、あちこちで山を作っている鹿の糞を指さしたり、道々ゴミを拾ったりした。竹沢はそれに感動して、ぼくに向かって、私たちも今度からやりましょうと言った。
「そん時は、透明なビニール袋を使わんといかんで」
「どうして?」
「どうしてもやがな」とだけ男は言った。「時に、竹沢はんの家はこっから近いんかいな」
「はい」と戸惑いつつ答えた。「皆川城址の近くです」
「そらええわ」男はぼくの顔を見ながら愉快そうに笑った。「研究にも便利やのー」
竹沢は、参道入口のある道の奥に自転車を駐めていた。家族共用のママチャリらしく、荷台にもカゴがついている。
「じゃあ先輩、また連絡しますね」と言い、男には「またお会いできたらいいですね」と笑って握りこぶしを引いて見せた。「研究、がんばりますからね」
*
町へ戻るまっすぐ長い道を、竹沢は自転車に乗ったまま何度も振り返って小さく手を振ってきた。バランスを崩してすぐ前を向いてしまうから、竹沢はぼくたちが手を振り返したのを一度も見なかったかも知れない。
「ええ子やのー。心が洗われるようやないか」
「どういうつもりだよ」
「何の話や」
「ぼくが竹沢について黙っていたのを恨んでるのか」
男はにやにや笑って「何のことやらわからんわ」と言った。「わしは、さっきあの子が皆川城址の近くに家がある言うから、ようやっとそうかも知らんと思い至ったとこや。ちゅうことはなんや、やっぱりあの子は竹沢家の娘さんなんかいな。どえらい偶然があるもんやのー」
「白々しいよ」と男の方を見ないように言った。「また何か、変なことを企んでるだろ」
「それやったら、そっちはなんで竹沢家が知り合いの家やということを隠しとったんかっちゅう話になるで」
「見ず知らずの人間にそんなこと教えるはずないだろ」
ぼくたちの横をサイクリストが二人連なって抜けていった。その姿が小さくなってから、男はわざとらしく溜息を聞かせた。
「ほな、白状するしかないのー」急にしおらしく肩を落とした。「確かにわしは、名前を聞いてすぐに気付いたんや。そして、こんなに物怖じせず自分の意見を述べて歴史研究に邁進する立派な青年が、そんな些末な事実関係を隠すっちゅうことは、ひょっとしたら――ひょっとしたらやで? 青年が、あの子に好意を抱いてるんかと思ったんや。そうやとしても無理もないぐらいのええ子やしな」
「ぼくは一緒に研究したいなんて一言も言ってない」
「せやから、迷える子羊たちに手を差し伸べようという善意の第三者なんやからしょうがあれへんがな。わしにはお互いに、あの子の方でも好意を抱いとるように見えたんやけどなー」
答えようもなく黙っているぼくを、男は薄く口を開けたまま眺めていた。
「おっさんのいらんおせっかいやったんなら平謝りするしかないわ。恋のキューピッドに憧れとったんやけど、残念やのー。まあ、もしもわしの勘違いやったら、あれは一時の気の迷いやったと連絡したらそれでしまいやがな」
「そんなの向こうに悪いだろ」
「ほな、あのあと皆川城址に行って研究したいことが見つかったと言うんがええわ。自然やろ」
「そんなの」とまた同じ物言いになって口ごもった。「がっかりするだろ」
「そこやがな」男は体を寄せ、ぼくの肩に手を回してきた。「好きか嫌いかはともかく、いやまあ、わしの見立てでは嫌いゆうことはなさそうやけども、とにかくあの子は、ああこれから先輩といい研究ができる、頑張ろうと心に決めたんや。こんぴらさんの前でやで? その決意が台無しになってしもたら、さぞがっかりするやろなー」
がっかりする――自分で言ってしまったことが頭をぐるぐる回る。本当にそうなのだろうか。ぼくはこんな男に何を話しているのだろうか。
「あんなええ子を弄んで悲しませたら、青年」そこで言葉を切って肩を揺すぶってくる。ぼくが見るのを待って、小さく首を振りながら真顔で言った。「あかんで」
ますます元気のいい男に何を言い返す気力もなく、先の見えない長い道のわきに広がる田畑に目をやり、足を動かし続ける。今度は少し離れて横に首を差し出した男が、囃すような調子で話しかけてきた。
「へへ、今までとはずいぶん様子が違うやないか。さすがの青年も、ある面ではまだまだ人生経験が不足しとるっちゅうこっちゃなー。歴史ではこういう機微は学べんからのー。あ、ところで今、何時や? 今日は腕時計を置いてきたんや。百三十万の時計に傷がついたらかなわんからのー」
訊いてもないことをくっちゃべる男に「スマホぐらい持ってるだろ」と言いつつも、代わりにスマートフォンを確認してやる。
「仕事用の携帯しか持っとらんし、プライベートやからそれも置いてきとんねん。財布と名刺入れだけや。邪魔くさいからのー」
「今時、スマホも持ってないのか」
「昔気質の男でなー。せやけど、持ってたら青年の連絡先も聞けたやろ。昨日今日だけは、そんな自分が嫌やねん」
話半分に無視して「まだ一時過ぎだよ」と教えた。
「ほなさっき言った予定の通り、皆川城址に向かおうやないか。わしは十九時から会食があるよってに、時間頼むで。十五時には城址を出て、ホテルに戻ってひとっ風呂浴びて準備せんといかんわ。青年、見といてや」
返事はしないがもちろん気にしてもいない男は、またあのベンチまで上がろうと提案してきた。面倒だったけれど、歩きながらではしっかり問い詰めるのは難しそうだったから承諾した。
一時間近くかけて戻ってくる間に尿意をもよおし、ぼくは城址の入口にある公衆トイレに駆け込んだ。用を足す間、外から男の笑い声が聞こえた。
「仕方ないだろ、肌寒い中を長いこと歩いてるんだから」ぼくは出るなり言った。「あんたは行かないのか」
「わしは鍛えとるから屁でもないがな。いつでも他人を出し抜けるように、下手を打たんように、人間、あらゆる状況に備えとかなあかんやろ」
「こんなの鍛えられるもんじゃないだろ」
「尿道しめとんのは外尿道括約筋ゆう筋肉やから、鍛えられるがな。油断しとったらすぐに小便垂れ流すジジイになってまうで。わしはな、どんな状況やろうと、小便してきっかり十時間は我慢できる体になっとるわ」
「嘘だ」
「まあ、疑り深いのも学を志すには必要な性分や」男はしきりに頷きながら「よっしゃ」と声を張り上げた。「今日、青年と解散するまで小便行かんといたろ。そしたら納得するやろ」
そんなことはどうでもよかったが、溌剌と歩き出した男の足取りはここに来てなお軽い。ぼくの方はさすがに疲れて、急な階段で足が止まって息も切れる。軽口の一つも叩かれると思ったが、何も言わずに数段上、腕を組んで町を見下ろしている。見下ろしても、見上げても、標高一四七メートルの城山に人の姿は見当たらない。
ようやく西の丸のベンチに腰を下ろせた。男はボディバッグとビニール袋を置いて、その前に出ると、体操を始めた。
「ええ景色やなー」屈伸をしながらぼくをちらちら振り返る。「竹沢はんはあっこの中学校に通ってたんやろなー」
山間の狭い土地の真ん中、広い校庭に土のテニスコートを備えた中学校は、竹沢の家から目と鼻の先だ。ぼくは同じところに目を向けながら無視して座っていた。
「どうして竹沢の前ではあんな風に振る舞ったんだよ」
「どういうことや?」大きく腰をひねりながら言う。
「馬鹿の振りをしてたじゃないか」
「馬鹿ではないやろ。馬鹿に見えたんか?」今度は大きく体を後ろに反らせながら、逆さになった顔でぼくを見て、苦しげな声を出す。「あれでも世間では賢い方の部類に入るんやで。なんぼひどく言うても、最低限の教養と礼節をわきまえた気の良いお兄さんぐらいのもんや。むなしい世の中やのー」
「何のためにそんな演技をするんだよ」
ゆっくり体を戻した男は、ぼくから遠ざかって、さっき来た坂の方に歩いて行く。
「おい」その背中に「どこ行くんだ」と呼びかける。
「小便や」男は振り返り、あごを小さくしゃくり上げながら言った。「ぼちぼち我慢の限界でな」
ぼくは一拍置いて、火がついたように笑ってしまった。男は満足げに微笑みながら前を向くと、坂を下っていった。
当たり前だとぼくは少し安堵した。あの男は普通ではないけれど、人間には違いない。体操していたのも尿意を紛らわすためだと考えて、ぼくはくつくつ音を立ててしばらく笑っていた。でも、だからと言って不審な気持ちが消えるわけでもない。その他、やることなすことが何もわからないのだ。
リュックから水筒を出して下を見ると、竪堀脇の階段を下る男の頭が沈んでいくところだった。水筒を置くため、男のボディバッグを端に寄せようとした時、ぶつぶつした革の感触に手が止まった。楕円形の一番大きなところを閉じているメインのファスナーと、外側に薄いカードぐらいしか入らなそうな小さなファスナー。
財布と名刺入れだけや。男がそう言っていたのを思い出す。
もう一度、腰を上げて下を覗くように見ると、男の姿はさらに遠く、複雑に入り組んだ曲輪の向こうに消えた。あそこから入口のトイレまで二、三分はかかるだろう。戻ってくるまで少なくとも五分以上はある。ここに普通に座っていれば、男から見えることは絶対にない。
名刺は外側に入っているだろうか。こっちの名前は知られてしまったのだから、見たってお互い様だ。そう考えて指をかけたファスナーはひどく冷たくて、思わず一度、指を離した。
*
戻ってきた男は、照れ隠しなのか何なのかにやにや笑い、おかしなことには、幽霊のように手を垂らしていた。そして、ぼくの三メートルほど手前で止まった。
「青年、ハンカチ持っとるか?」
「持ってない」とぼくは言った。「服で拭けばいいだろ」
「それがどうもでけへんねん。こういう時に育ちの良さがアダになるんやなー」
「ハンカチも持ってないくせによく言うよ」
「いや、持っとるがな。朝、ゴミ拾いのビニールをポケットに入れる代わりにカバンへしまってもうたんや。取ってくれんか?」
「なんでぼくが」
「なんでて、さいぜん理由を言うたとこやがな」
「登ってくる間に弾き飛ばすなり手をこすり合わせるなり、乾かせるはずだ。実際、あんたの手はもう乾いてるんじゃないか?」ぼくは男を睨むようにして言った。「どうしてそんなに、ぼくにハンカチを取らせたいんだ」
男は手を前に下げたままにやにや笑い続けている。
「ぼくを試したんじゃないのか? そのためにわざと一人にさせたんだろ」
「どうやら、わしが気持ちよう小便しとる間にごちゃごちゃいらんこと考えとったみたいやのー。わしは、青年が他人の荷物に悪さをして名刺を見とらんことぐらい重々承知しとるがな」
「いや、少なくとも疑ってはいるはずだ。名刺のことだって、わざと口走ったんだろ。ぼくを試して、反応を見て楽しんで、今後に活かそうとしてる。あんたはそういう男だ」
「そんな男やとしても、疑っとるゆうのはちょっとちゃうなー」
「信用できない。信用できない人間とは一緒にいられない」
「おいおい、物騒なこと言うやないか」男はまるで拳銃で脅されているかのようにゆっくり手を頭の上に挙げた。まだ余裕があるようだ。「わかったわかった、わしが疑っとらん証拠があるわい」
「何だよ」
「弱ったことに、それもカバンの中やねん。堪忍やで」
ぼくは男をじっと見た。怯えたような細目をつくって手を一段と高く挙げ、顔を震わせながら逸らす。
「これでわしがカバンを開けてほしい理由はみな言うてしもたわ、弾切れや」上げた片方の口角をこっちに見せている。「あとは青年次第やなー」
ぼくは男のカバンを乱暴に持ち上げた。腿の間に挟むようにし、メインのファスナーに手をかけた。
「ここでいいのか」
「お、ようわかっとるやないか」
「うるさい」
「ほんでそれな、一気に引っ張らんとチャック噛んでまうねん。気ぃつけたってや。や、そんなことさえもう知っとるんかな?」
「知るはずないだろ!」
男の指示に従ったわけではなく、怒りにまかせてファスナーを一気に引いた。反対側までいって、まだ形を整えている口を開き、何かが引っかかっていると思って押し広げた瞬間、笛の鳴るような高い音と同時に、黒く長いものが勢いよく飛び出してきた。驚き、それを避けようとしてバランスを崩し、ベンチの後ろにもんどり打って倒れた。
わけもわからず頭を押さえ、やわらかな草の上で体を起こしかけたところで、男のいかにも嬉しげな声が聞こえた。
「よっしゃよっしゃ、大成功や」
男の挙げていた手は今や、万歳の形で指先まで伸びている。それからいそいそ弾むように走り出した先の地面には、黒く長いものが転がっていた。男はそれを拾って来ると、ぼくの前にしゃがみこんだ。
「いやー、ものの見事とはこのことやなー」こちらに向けて揺らしたその先端は、赤い舌を出した間抜けなヘビの顔だった。「ケッサクやったで。スマホ持ちやったら撮影もできたかも知れんのになー、口惜しわ」
何も言えずに呆然としているうちに、草の冷たさが手足や尻にじんわり伝わってきた。
「これでわかったやろ。こいつが外におらん限りは、青年がカバンをこっそり開けて中身を見とらんっちゅう証拠になるわけや。まあ、飛び出した時点で派手な音がするよう細工しとんねや、下にいても気付いたやろうけどもな」
ぼくは黙ってヘビの口の中を見つめていた。
「ほんで、ボケッとしとらんと早よハンカチ取ってくれや」
口答えする気もなく、ベンチの下に転がっていた男のバッグからハンカチを取って渡した。間近で見た男の手は本当に濡れていて、ヘビはぼくの方にぞんざいに放られた。
「これ、なんだよ」ぼくの口からはもう疑問しか出て来なかった。「朝からずっと入ってたのか?」
「はるばる栃木まで取り寄せたヘビやがな。けっこう仕込みが大変なんやで。ホテルを出る直前まで、何度もシミュレーションしたんや」
「なんでこんなことするんだ」
「さっき青年は試しとると言うたけどな、おっしゃる通りやわ」
男は次の言葉を待つぼくを焦らすように、たっぷり時間を取って手を拭いた。わざわざ綺麗に畳み直してポケットに入れる。
「ほんで青年は見事、採用試験に合格したわけや。わしを裏切ることのできひん、信頼に足る人間やとな」
「だから、なんで――」
「こんなタネ明かしをやっとるっちゅうことは、わしかて腹割る覚悟ができたいうことやないか。すぐ話したるから待っとれや。しかしまあ、今日のうちにヘビを出すことになるとは思わなんだで。万が一の準備やったんやけども、トントン拍子に事が運んでなー、特に、竹沢はんに偶然会ったんは大当たりや。それもこれも青年がいてこそやろ。ほんま、この出会いは一生の宝物やで」
うさんくさい言葉に喰らい付くには混乱しすぎていた。この男はいったい何者なのだろう。そんなぼくを弄ぶように、男はぼくが抱えたままにしていたバッグを取って、あれこれ大袈裟に確認した。
「こまいチャックだけ開けたとこを見ると、ある程度、危ない橋を渡る度胸もあるようやし、その上でわしに吹っ掛ける狡猾さと肝っ玉も備わっとるんやから、まあ上出来やな」
ぼくが外側のファスナーを開けたことをわかっている。驚きが「なんで」という声を漏らさせた。
「何から何までタネ明かししてどないすんねん」吐き捨てるように言ってベンチに座った男の背中は大きい。肩越しに、ぼくを見下ろす細い目が覗いた。「いつまでもぼさっと地べたにおらんと、隣に座らんかいな。大事な話があんねんから」