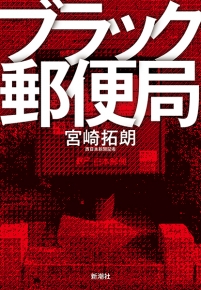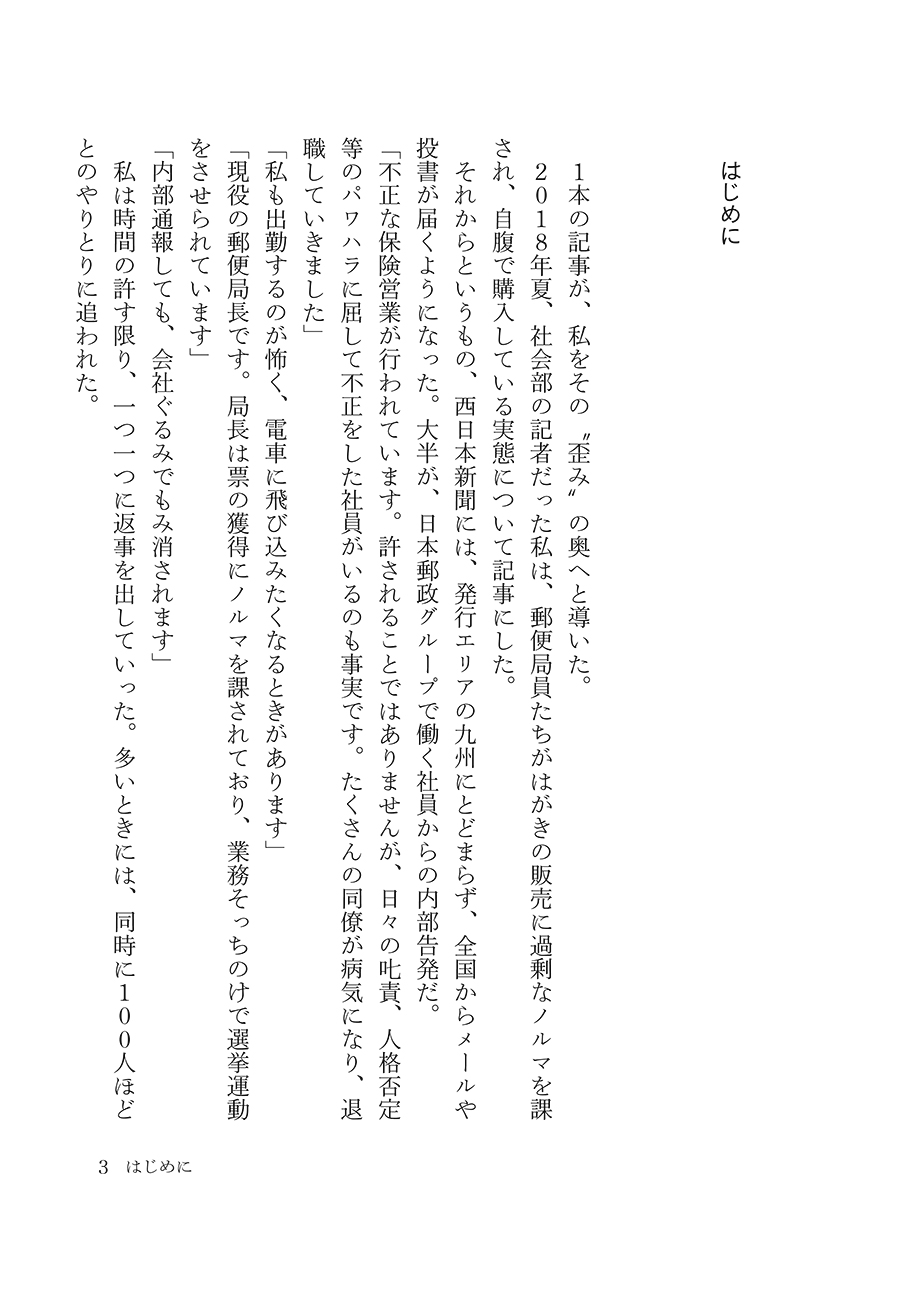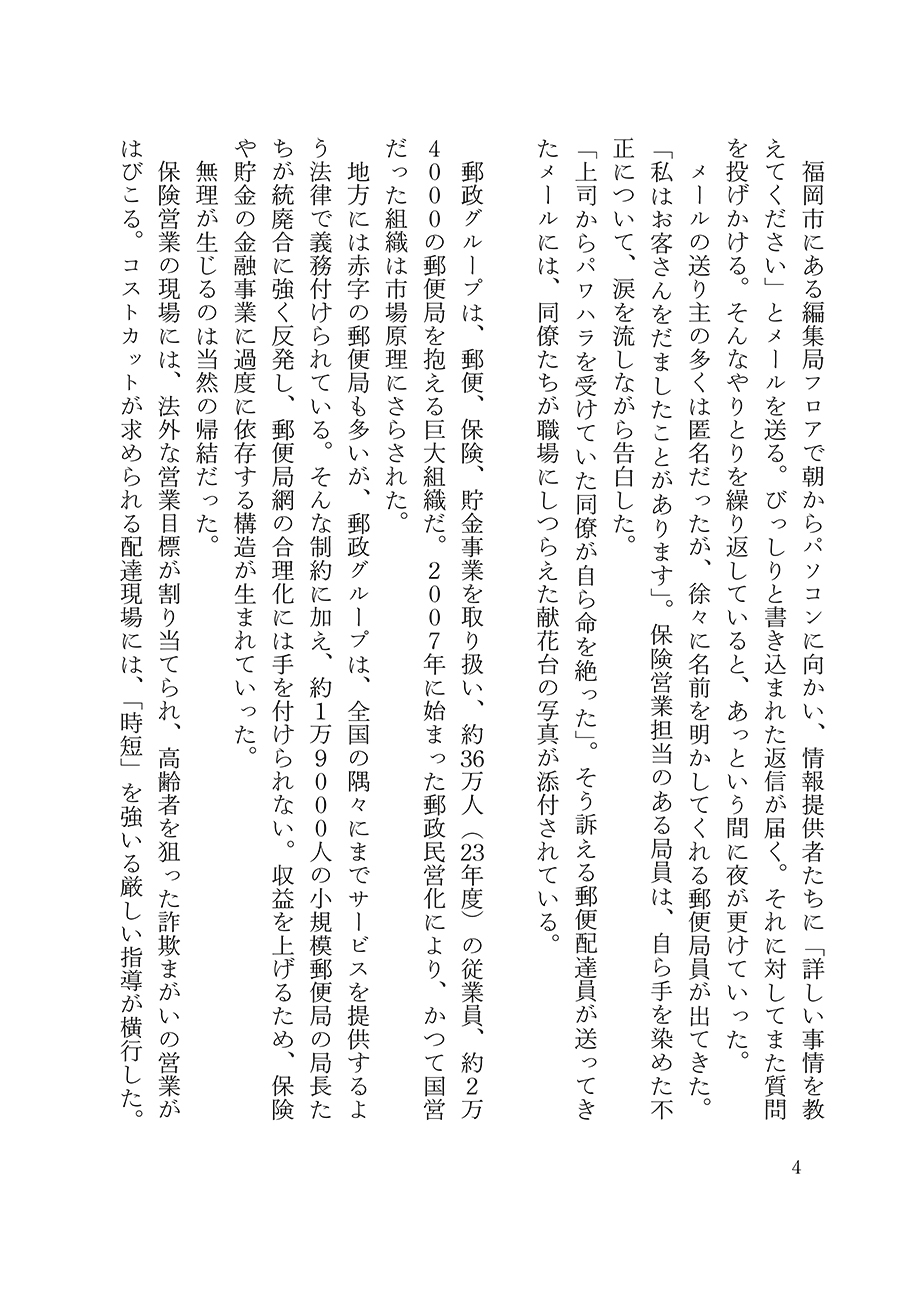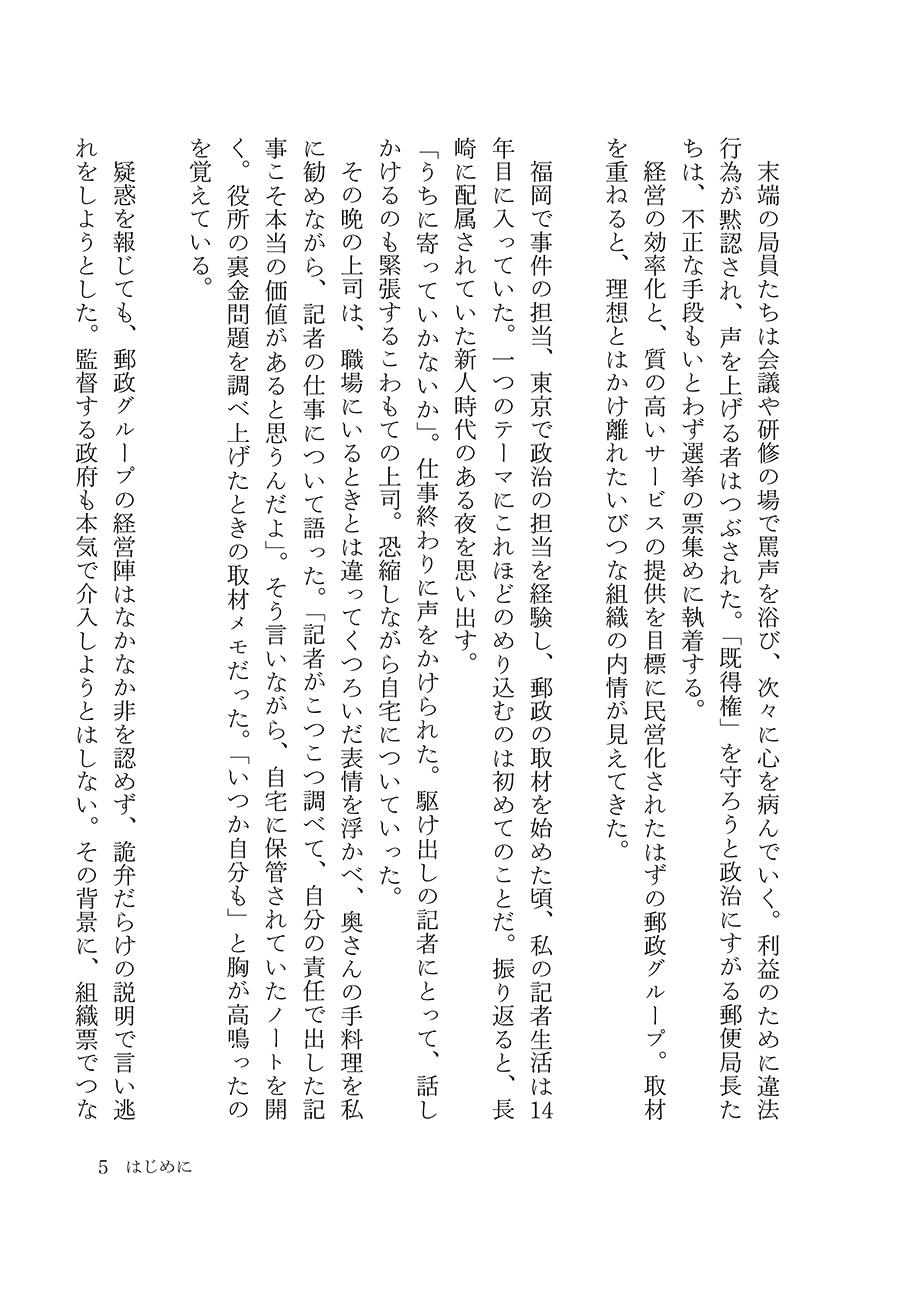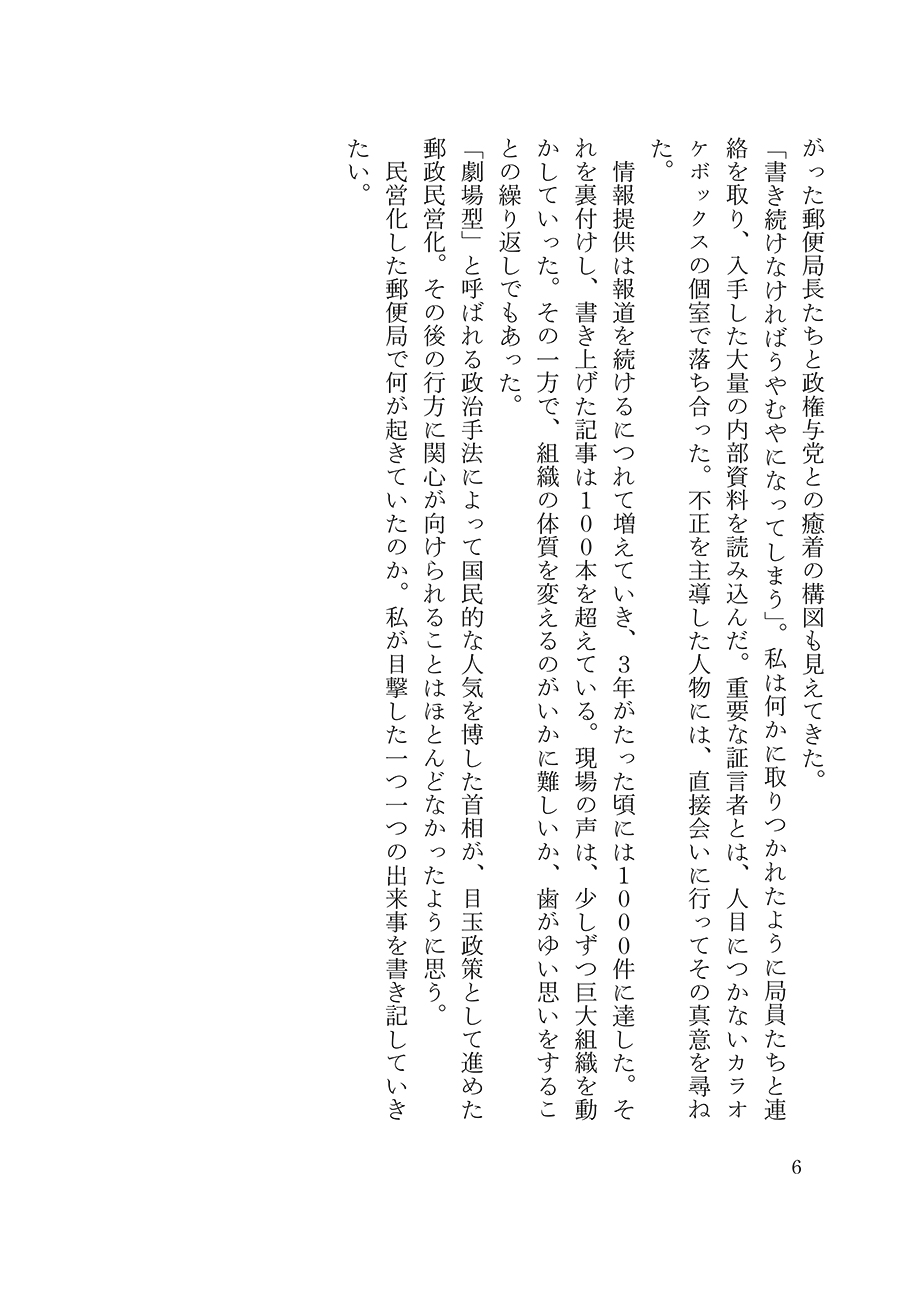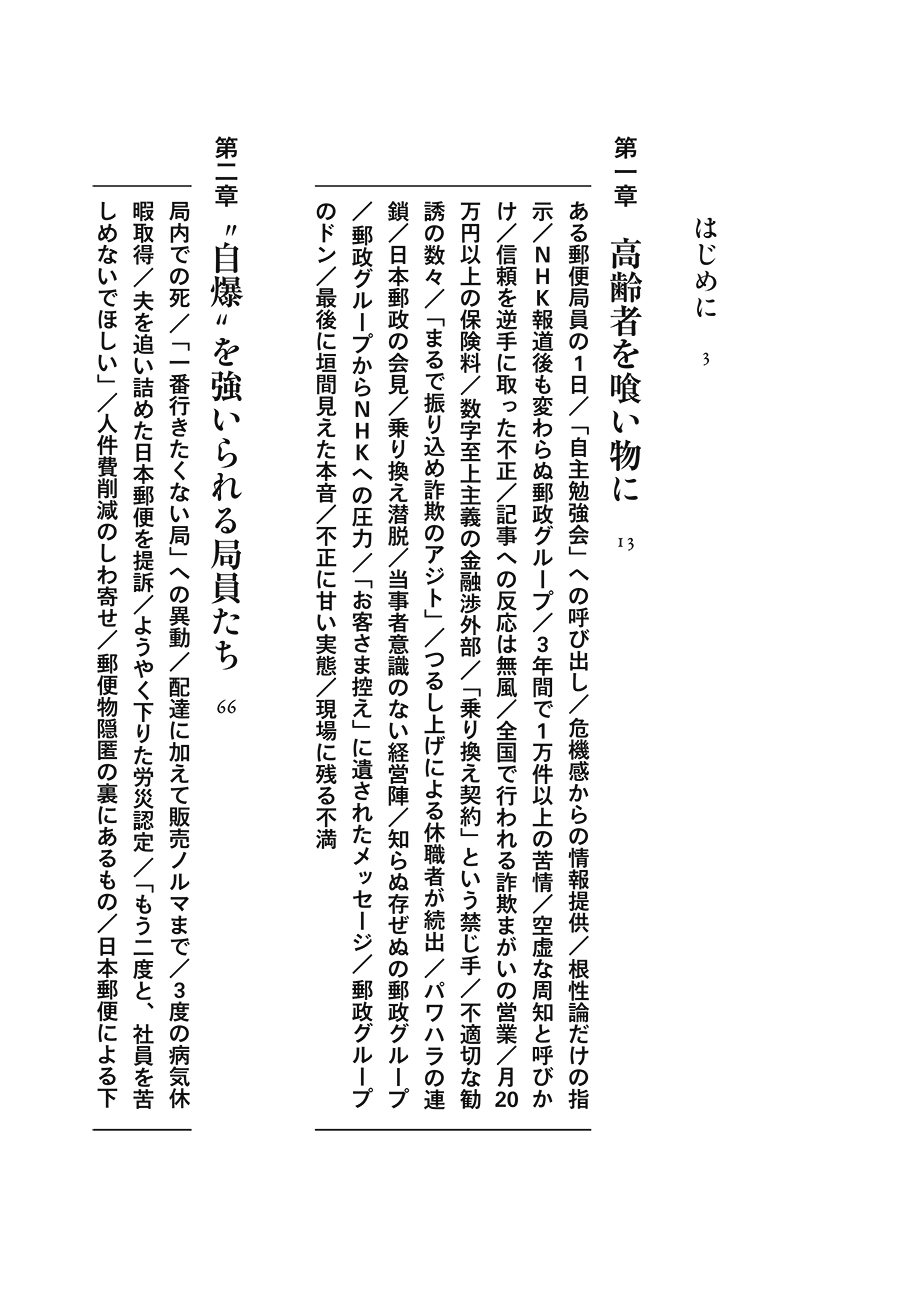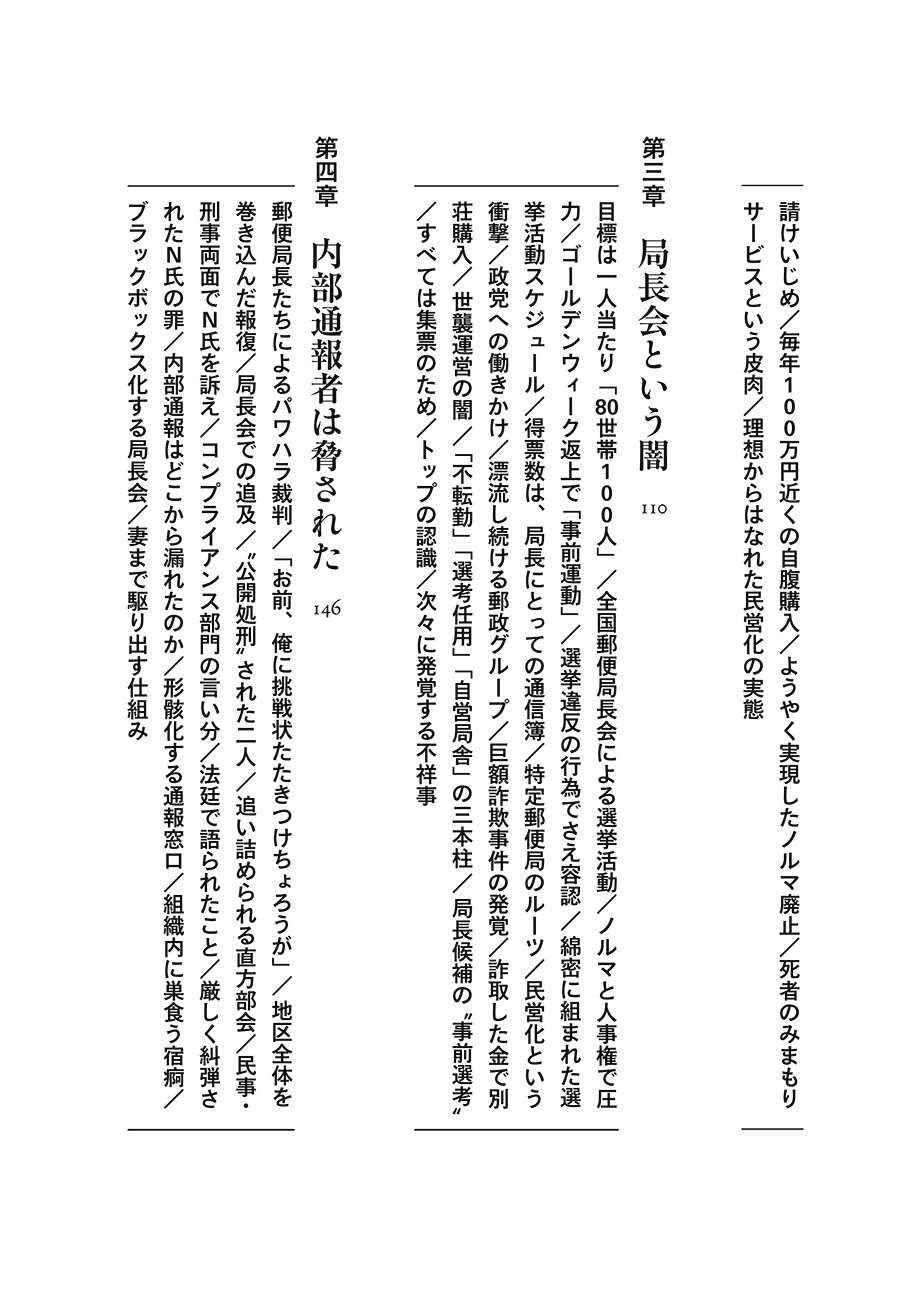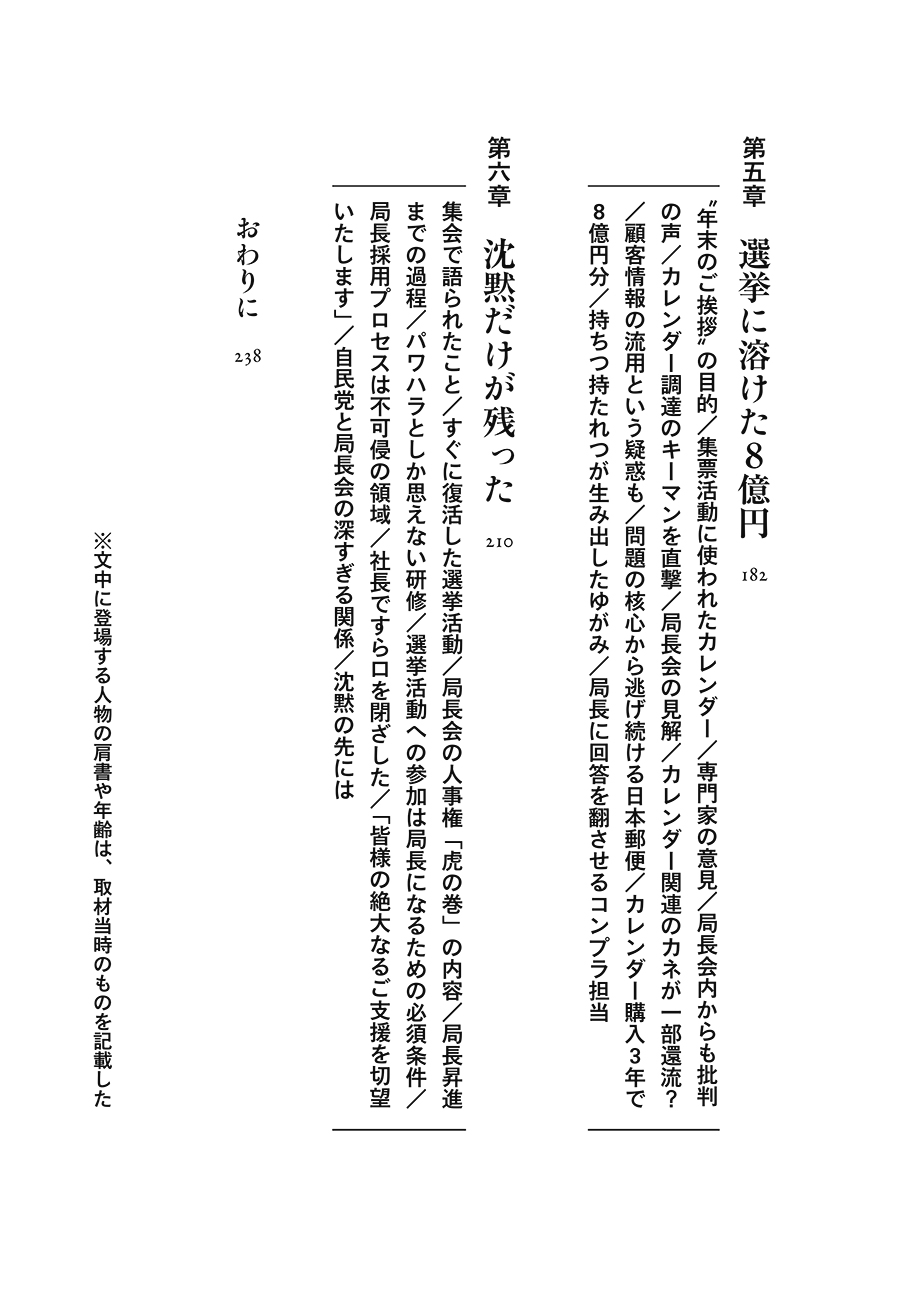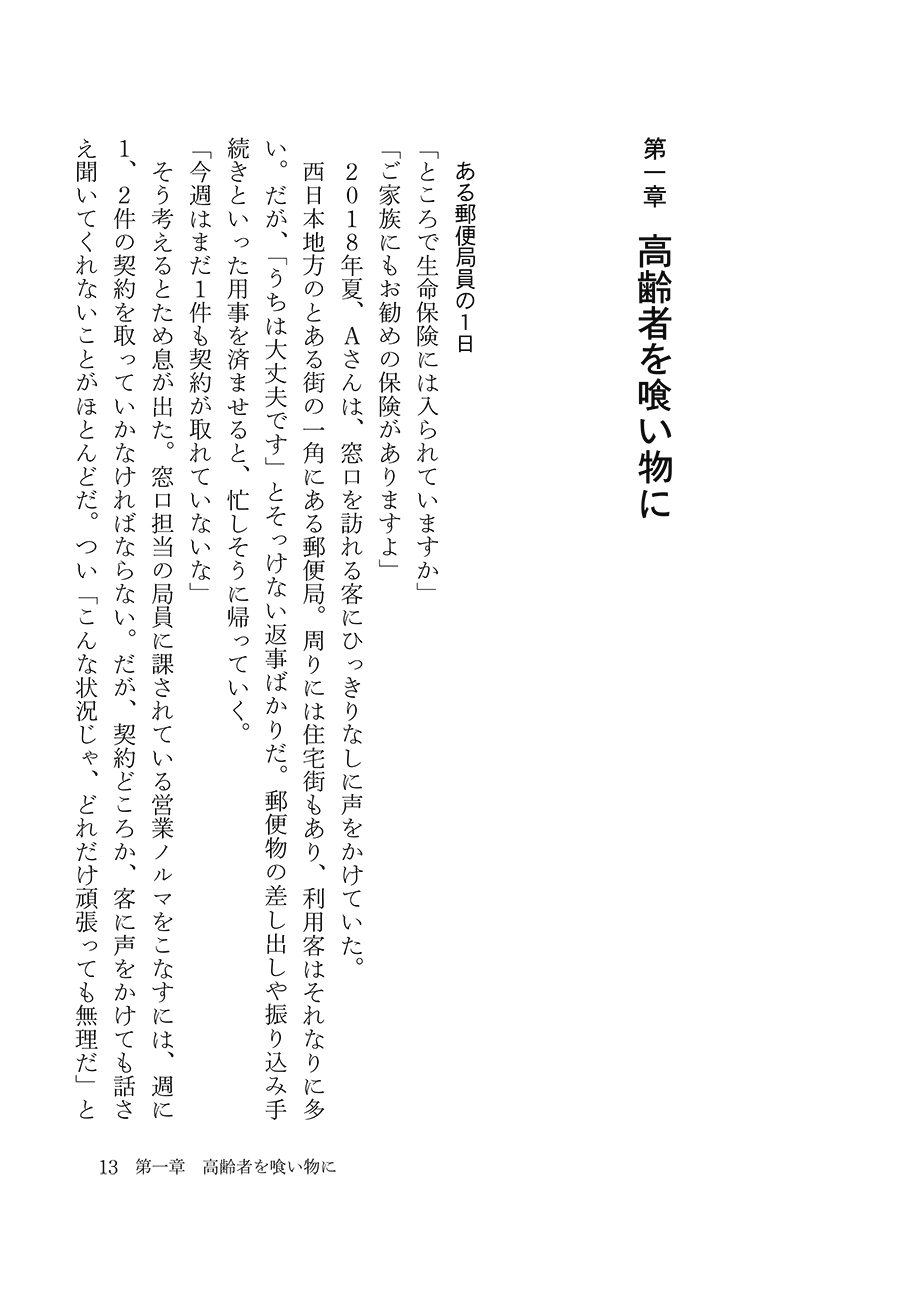はじめに
1本の記事が、私をその“歪み”の奥へと導いた。
2018年夏、社会部の記者だった私は、郵便局員たちがはがきの販売に過剰なノルマを課され、自腹で購入している実態について記事にした。
それからというもの、西日本新聞には、発行エリアの九州にとどまらず、全国からメールや投書が届くようになった。大半が、日本郵政グループで働く社員からの内部告発だ。
「不正な保険営業が行われています。許されることではありませんが、日々の叱責、人格否定等のパワハラに屈して不正をした社員がいるのも事実です。たくさんの同僚が病気になり、退職していきました」
「私も出勤するのが怖く、電車に飛び込みたくなるときがあります」
「現役の郵便局長です。局長は票の獲得にノルマを課されており、業務そっちのけで選挙運動をさせられています」
「内部通報しても、会社ぐるみでもみ消されます」
私は時間の許す限り、一つ一つに返事を出していった。多いときには、同時に100人ほどとのやりとりに追われた。
福岡市にある編集局フロアで朝からパソコンに向かい、情報提供者たちに「詳しい事情を教えてください」とメールを送る。びっしりと書き込まれた返信が届く。それに対してまた質問を投げかける。そんなやりとりを繰り返していると、あっという間に夜が更けていった。
メールの送り主の多くは匿名だったが、徐々に名前を明かしてくれる郵便局員が出てきた。
「私はお客さんをだましたことがあります」。保険営業担当のある局員は、自ら手を染めた不正について、涙を流しながら告白した。
「上司からパワハラを受けていた同僚が自ら命を絶った」。そう訴える郵便配達員が送ってきたメールには、同僚たちが職場にしつらえた献花台の写真が添付されている。
郵政グループは、郵便、保険、貯金事業を取り扱い、約36万人(23年度)の従業員、約2万4000の郵便局を抱える巨大組織だ。2007年に始まった郵政民営化により、かつて国営だった組織は市場原理にさらされた。
地方には赤字の郵便局も多いが、郵政グループは、全国の隅々にまでサービスを提供するよう法律で義務付けられている。そんな制約に加え、約1万9000人の小規模郵便局の局長たちが統廃合に強く反発し、郵便局網の合理化には手を付けられない。収益を上げるため、保険や貯金の金融事業に過度に依存する構造が生まれていった。
無理が生じるのは当然の帰結だった。
保険営業の現場には、法外な営業目標が割り当てられ、高齢者を狙った詐欺まがいの営業がはびこる。コストカットが求められる配達現場には、「時短」を強いる厳しい指導が横行した。
末端の局員たちは会議や研修の場で罵声を浴び、次々に心を病んでいく。利益のために違法行為が黙認され、声を上げる者はつぶされた。「既得権」を守ろうと政治にすがる郵便局長たちは、不正な手段もいとわず選挙の票集めに執着する。
経営の効率化と、質の高いサービスの提供を目標に民営化されたはずの郵政グループ。取材を重ねると、理想とはかけ離れたいびつな組織の内情が見えてきた。
福岡で事件の担当、東京で政治の担当を経験し、郵政の取材を始めた頃、私の記者生活は14年目に入っていた。一つのテーマにこれほどのめり込むのは初めてのことだ。振り返ると、長崎に配属されていた新人時代のある夜を思い出す。
「うちに寄っていかないか」。仕事終わりに声をかけられた。駆け出しの記者にとって、話しかけるのも緊張するこわもての上司。恐縮しながら自宅についていった。
その晩の上司は、職場にいるときとは違ってくつろいだ表情を浮かべ、奥さんの手料理を私に勧めながら、記者の仕事について語った。「記者がこつこつ調べて、自分の責任で出した記事こそ本当の価値があると思うんだよ」。そう言いながら、自宅に保管されていたノートを開く。役所の裏金問題を調べ上げたときの取材メモだった。「いつか自分も」と胸が高鳴ったのを覚えている。
疑惑を報じても、郵政グループの経営陣はなかなか非を認めず、詭弁だらけの説明で言い逃れをしようとした。監督する政府も本気で介入しようとはしない。その背景に、組織票でつながった郵便局長たちと政権与党との癒着の構図も見えてきた。
「書き続けなければうやむやになってしまう」。私は何かに取りつかれたように局員たちと連絡を取り、入手した大量の内部資料を読み込んだ。重要な証言者とは、人目につかないカラオケボックスの個室で落ち合った。不正を主導した人物には、直接会いに行ってその真意を尋ねた。
情報提供は報道を続けるにつれて増えていき、3年がたった頃には1000件に達した。それを裏付けし、書き上げた記事は100本を超えている。現場の声は、少しずつ巨大組織を動かしていった。その一方で、組織の体質を変えるのがいかに難しいか、歯がゆい思いをすることの繰り返しでもあった。
「劇場型」と呼ばれる政治手法によって国民的な人気を博した首相が、目玉政策として進めた郵政民営化。その後の行方に関心が向けられることはほとんどなかったように思う。
民営化した郵便局で何が起きていたのか。私が目撃した一つ一つの出来事を書き記していきたい。
続きは本書でお楽しみください。