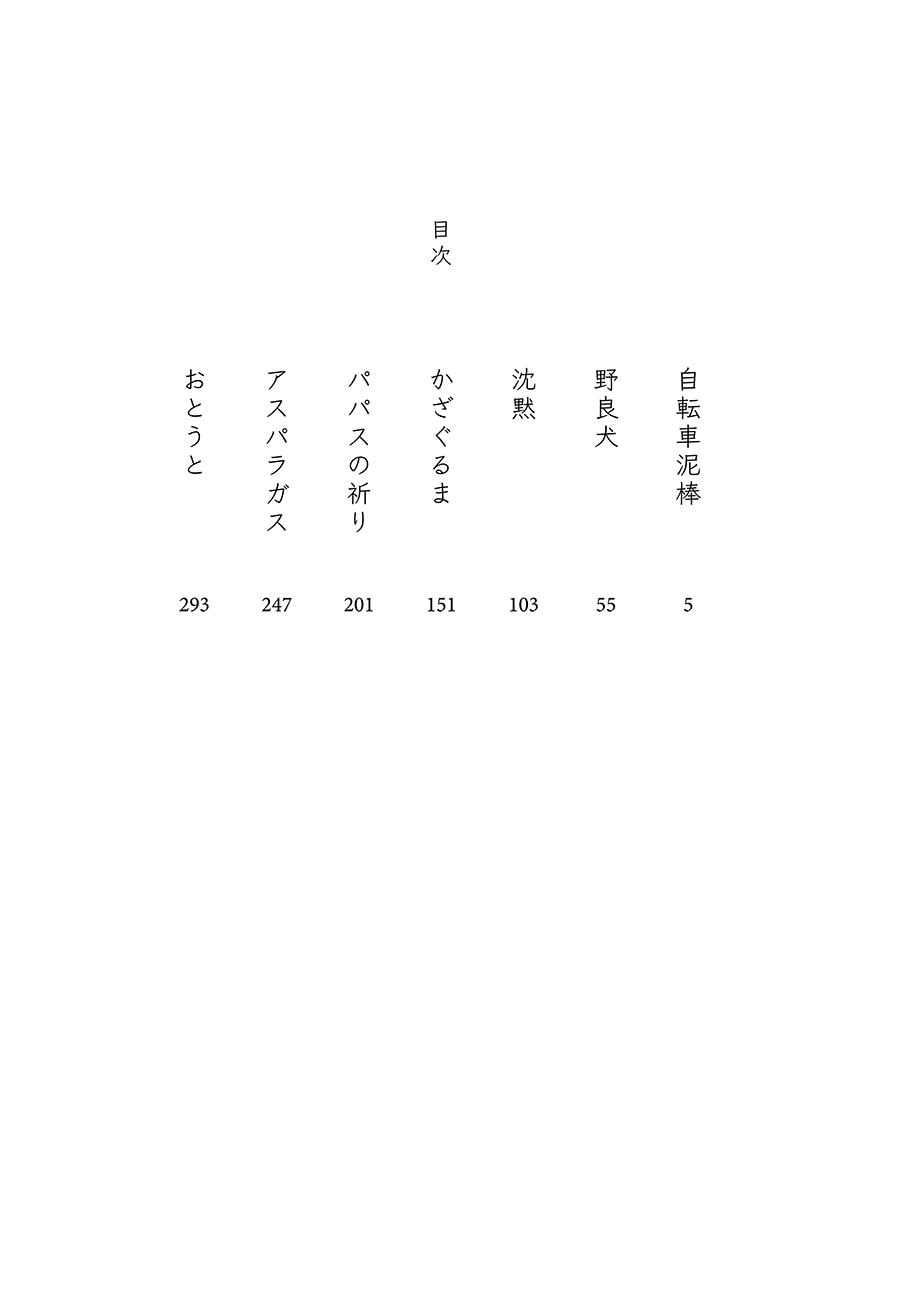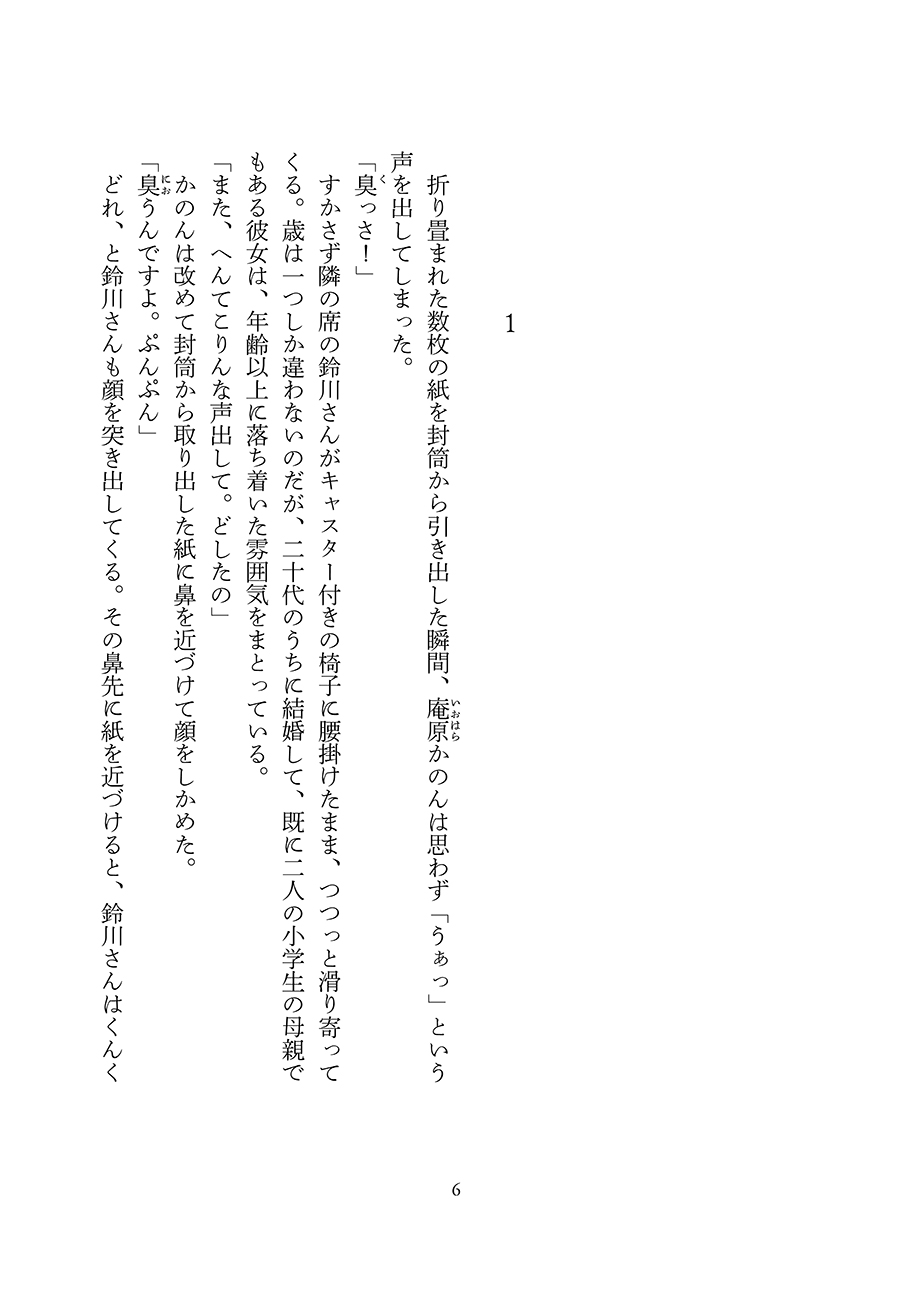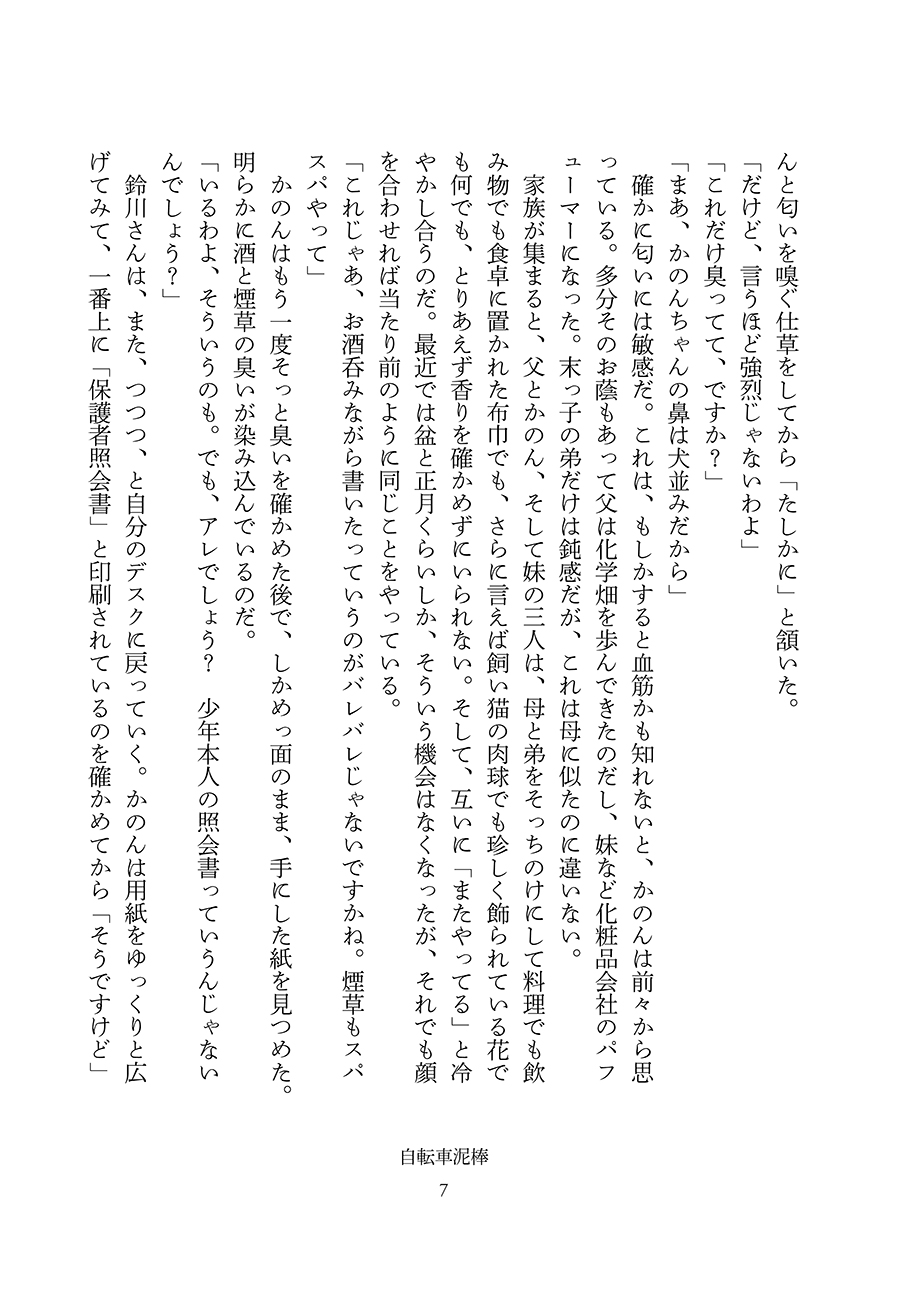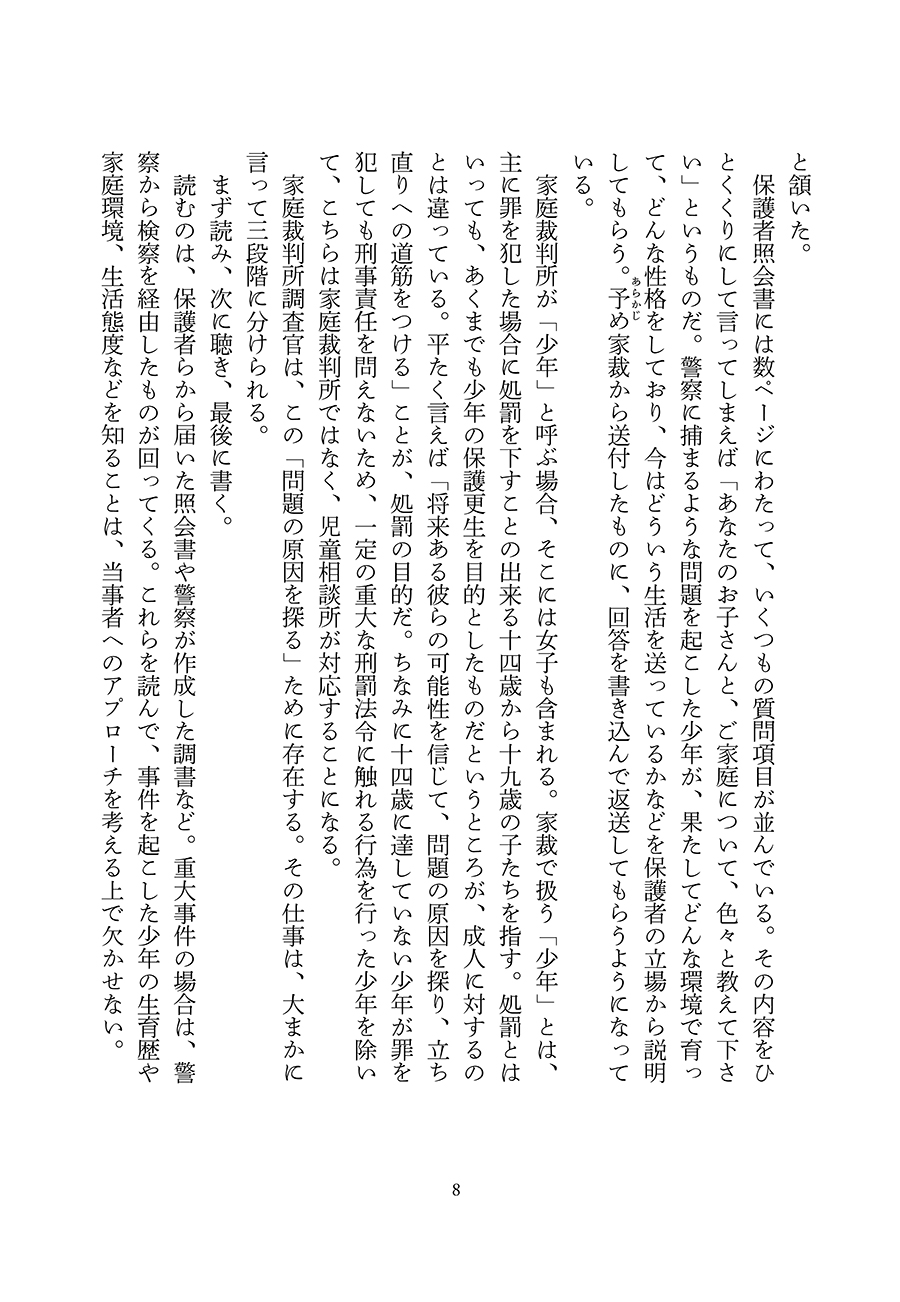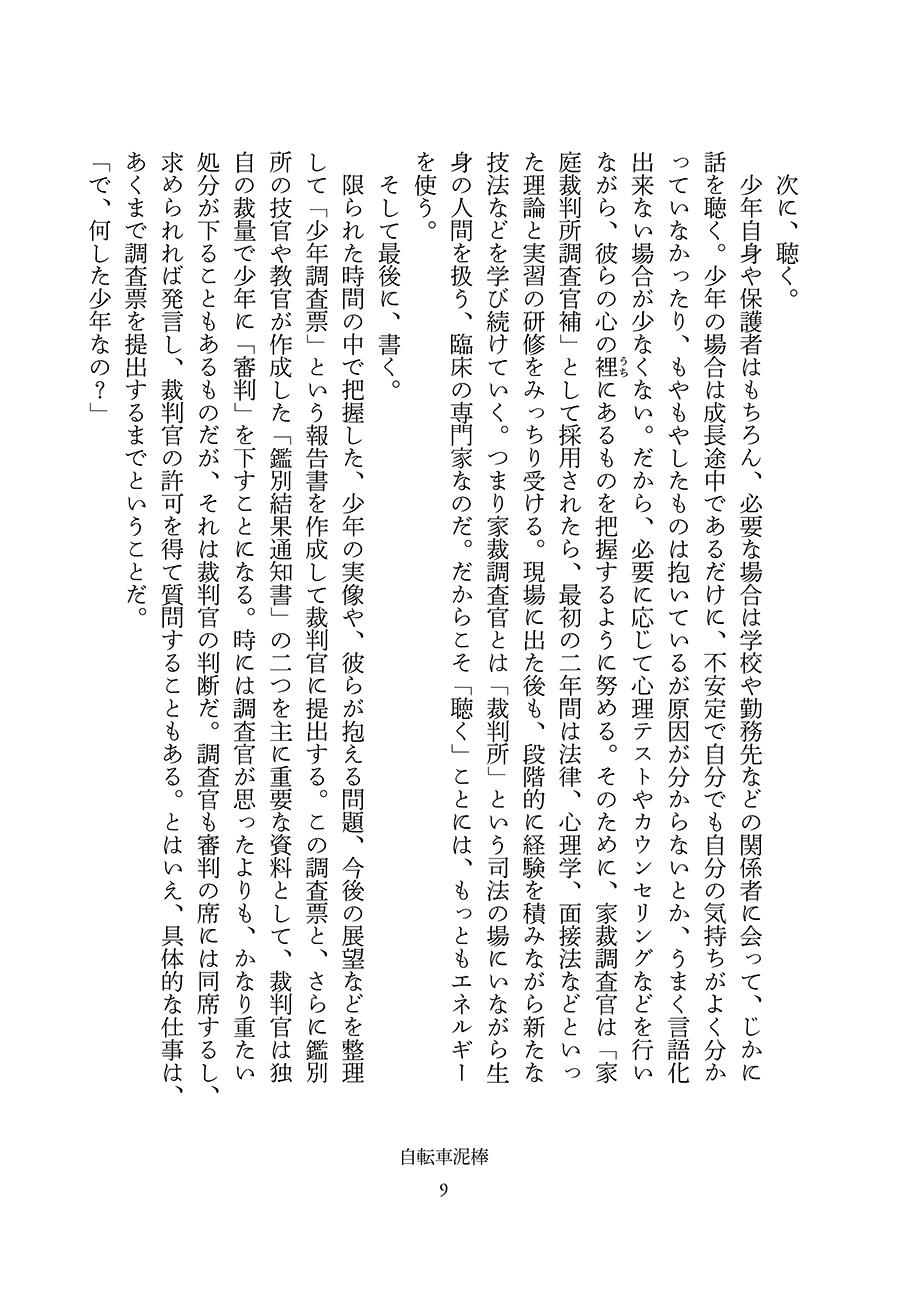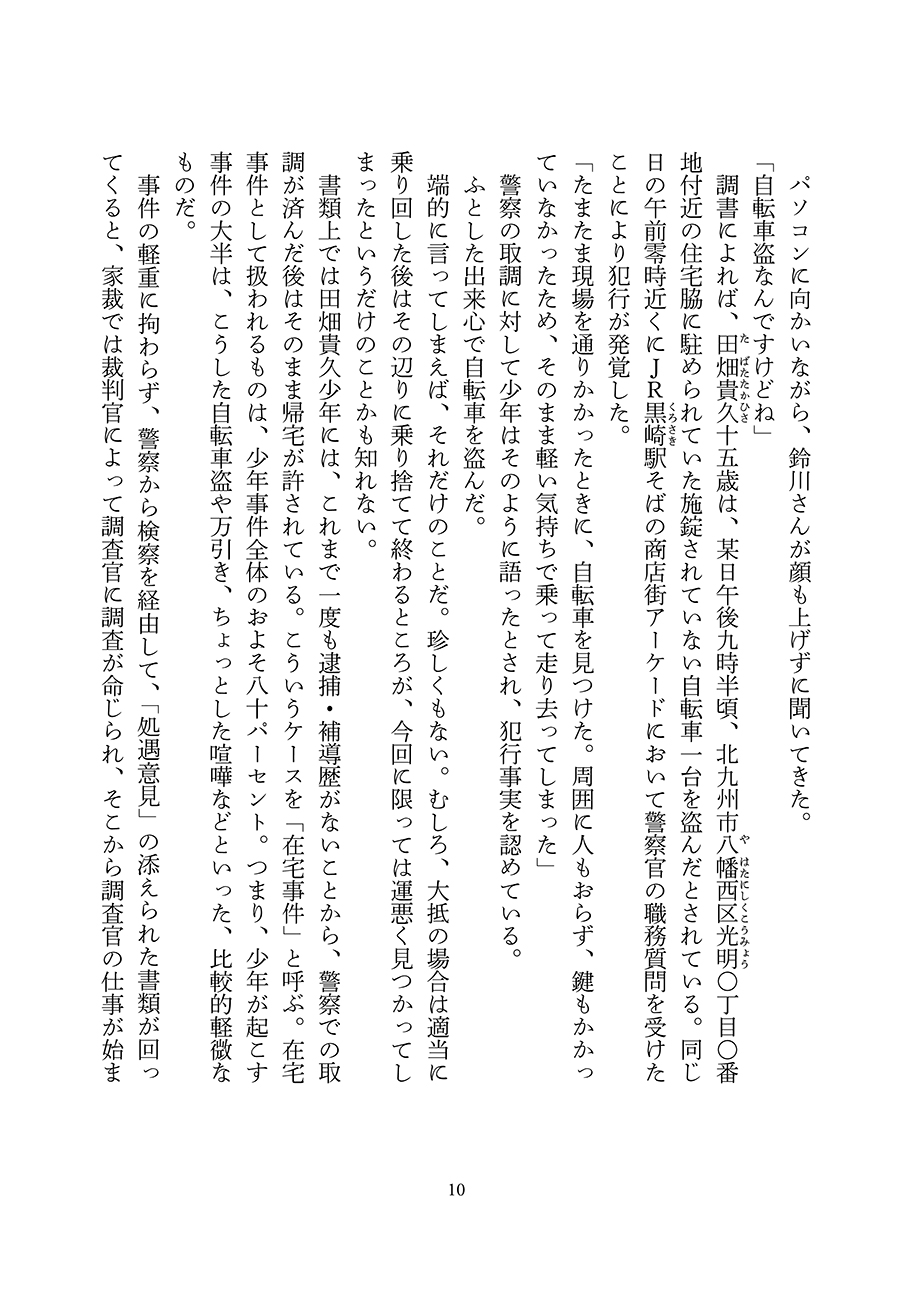自転車泥棒
1
折り畳まれた数枚の紙を封筒から引き出した瞬間、庵原かのんは思わず「うぁっ」という声を出してしまった。
「臭っさ!」
すかさず隣の席の鈴川さんがキャスター付きの椅子に腰掛けたまま、つつっと滑り寄ってくる。歳は一つしか違わないのだが、二十代のうちに結婚して、既に二人の小学生の母親でもある彼女は、年齢以上に落ち着いた雰囲気をまとっている。
「また、へんてこりんな声出して。どしたの」
かのんは改めて封筒から取り出した紙に鼻を近づけて顔をしかめた。
「臭うんですよ。ぷんぷん」
どれ、と鈴川さんも顔を突き出してくる。その鼻先に紙を近づけると、鈴川さんはくんくんと匂いを嗅ぐ仕草をしてから「たしかに」と頷いた。
「だけど、言うほど強烈じゃないわよ」
「これだけ臭ってて、ですか?」
「まあ、かのんちゃんの鼻は犬並みだから」
確かに匂いには敏感だ。これは、もしかすると血筋かも知れないと、かのんは前々から思っている。多分そのお蔭もあって父は化学畑を歩んできたのだし、妹など化粧品会社のパフューマーになった。末っ子の弟だけは鈍感だが、これは母に似たのに違いない。
家族が集まると、父とかのん、そして妹の三人は、母と弟をそっちのけにして料理でも飲み物でも食卓に置かれた布巾でも、さらに言えば飼い猫の肉球でも珍しく飾られている花でも何でも、とりあえず香りを確かめずにいられない。そして、互いに「またやってる」と冷やかし合うのだ。最近では盆と正月くらいしか、そういう機会はなくなったが、それでも顔を合わせれば当たり前のように同じことをやっている。
「これじゃあ、お酒呑みながら書いたっていうのがバレバレじゃないですかね。煙草もスパスパやって」
かのんはもう一度そっと臭いを確かめた後で、しかめっ面のまま、手にした紙を見つめた。明らかに酒と煙草の臭いが染み込んでいるのだ。
「いるわよ、そういうのも。でも、アレでしょう? 少年本人の照会書っていうんじゃないんでしょう?」
鈴川さんは、また、つつつ、と自分のデスクに戻っていく。かのんは用紙をゆっくりと広げてみて、一番上に「保護者照会書」と印刷されているのを確かめてから「そうですけど」と頷いた。
保護者照会書には数ページにわたって、いくつもの質問項目が並んでいる。その内容をひとくくりにして言ってしまえば「あなたのお子さんと、ご家庭について、色々と教えて下さい」というものだ。警察に捕まるような問題を起こした少年が、果たしてどんな環境で育って、どんな性格をしており、今はどういう生活を送っているかなどを保護者の立場から説明してもらう。予め家裁から送付したものに、回答を書き込んで返送してもらうようになっている。
家庭裁判所が「少年」と呼ぶ場合、そこには女子も含まれる。家裁で扱う「少年」とは、主に罪を犯した場合に処罰を下すことの出来る十四歳から十九歳の子たちを指す。処罰とはいっても、あくまでも少年の保護更生を目的としたものだというところが、成人に対するのとは違っている。平たく言えば「将来ある彼らの可能性を信じて、問題の原因を探り、立ち直りへの道筋をつける」ことが、処罰の目的だ。ちなみに十四歳に達していない少年が罪を犯しても刑事責任を問えないため、一定の重大な刑罰法令に触れる行為を行った少年を除いて、こちらは家庭裁判所ではなく、児童相談所が対応することになる。
家庭裁判所調査官は、この「問題の原因を探る」ために存在する。その仕事は、大まかに言って三段階に分けられる。
まず読み、次に聴き、最後に書く。
読むのは、保護者らから届いた照会書や警察が作成した調書など。重大事件の場合は、警察から検察を経由したものが回ってくる。これらを読んで、事件を起こした少年の生育歴や家庭環境、生活態度などを知ることは、当事者へのアプローチを考える上で欠かせない。
次に、聴く。
少年自身や保護者はもちろん、必要な場合は学校や勤務先などの関係者に会って、じかに話を聴く。少年の場合は成長途中であるだけに、不安定で自分でも自分の気持ちがよく分かっていなかったり、もやもやしたものは抱いているが原因が分からないとか、うまく言語化出来ない場合が少なくない。だから、必要に応じて心理テストやカウンセリングなどを行いながら、彼らの心の裡にあるものを把握するように努める。そのために、家裁調査官は「家庭裁判所調査官補」として採用されたら、最初の二年間は法律、心理学、面接法などといった理論と実習の研修をみっちり受ける。現場に出た後も、段階的に経験を積みながら新たな技法などを学び続けていく。つまり家裁調査官とは「裁判所」という司法の場にいながら生身の人間を扱う、臨床の専門家なのだ。だからこそ「聴く」ことには、もっともエネルギーを使う。
そして最後に、書く。
限られた時間の中で把握した、少年の実像や、彼らが抱える問題、今後の展望などを整理して「少年調査票」という報告書を作成して裁判官に提出する。この調査票と、さらに鑑別所の技官や教官が作成した「鑑別結果通知書」の二つを主に重要な資料として、裁判官は独自の裁量で少年に「審判」を下すことになる。時には調査官が思ったよりも、かなり重たい処分が下ることもあるものだが、それは裁判官の判断だ。調査官も審判の席には同席するし、求められれば発言し、裁判官の許可を得て質問することもある。とはいえ、具体的な仕事は、あくまで調査票を提出するまでということだ。
「で、何した少年なの?」
パソコンに向かいながら、鈴川さんが顔も上げずに聞いてきた。
「自転車盗なんですけどね」
調書によれば、田畑貴久十五歳は、某日午後九時半頃、北九州市八幡西区光明○丁目○番地付近の住宅脇に駐められていた施錠されていない自転車一台を盗んだとされている。同じ日の午前零時近くにJR黒崎駅そばの商店街アーケードにおいて警察官の職務質問を受けたことにより犯行が発覚した。
「たまたま現場を通りかかったときに、自転車を見つけた。周囲に人もおらず、鍵もかかっていなかったため、そのまま軽い気持ちで乗って走り去ってしまった」
警察の取調に対して少年はそのように語ったとされ、犯行事実を認めている。
ふとした出来心で自転車を盗んだ。
端的に言ってしまえば、それだけのことだ。珍しくもない。むしろ、大抵の場合は適当に乗り回した後はその辺りに乗り捨てて終わるところが、今回に限っては運悪く見つかってしまったというだけのことかも知れない。
書類上では田畑貴久少年には、これまで一度も逮捕・補導歴がないことから、警察での取調が済んだ後はそのまま帰宅が許されている。こういうケースを「在宅事件」と呼ぶ。在宅事件として扱われるものは、少年事件全体のおよそ八十パーセント。つまり、少年が起こす事件の大半は、こうした自転車盗や万引き、ちょっとした喧嘩などといった、比較的軽微なものだ。
事件の軽重に拘わらず、警察から検察を経由して、「処遇意見」の添えられた書類が回ってくると、家裁では裁判官によって調査官に調査が命じられ、そこから調査官の仕事が始まる。
調査官が「読む」作業を進める間、書記官が「照会書」や調査面接の期日を示した「呼出状」などを送付する作業を進めてくれる。それらの書面が先方に届くまでに、逮捕からおおよそ二、三週間。それだけの時間がたっていると、逮捕直後の緊張や興奮状態も醒めて、通常は当事者である少年も保護者も、かなり冷静に物事を考えられるようになっているものだ。そこで照会書には、少しでもいい印象を与えて軽い処分で済ませてもらえるように、優等生的な回答を書く場合が多い。
こうして事件から一カ月程度が経過した頃に、調査官はいよいよ「聴く」作業、つまり調査面接を行うことになる。この場合も自転車盗くらいなら、面接は一度限りで終わる。とりあえず、だとしても本人に反省の色がうかがえ、保護者も今後はきちんと少年を監督しますから、などと言えば、それでおしまいだ。わざわざ裁判官が「審判」の席を設けるというところまではいかない。こういう事件は「審判不開始」ということになる。または審判は開かれても「不処分」という決定が下される。調査官が扱う少年事件としては、数は多くても特に扱いが難しいということはない、淡々とこなしていけばいい類のものだ。
だけど。
改めて手元の保護者照会書に目を落として、かのんは口もとをきゅっと引き締めた。保護者の氏名欄には田畑里奈という名前が書き込まれている。文字は相当に乱れていた。
かなり酔っ払って書いたんだろうか。
名前からすると女性だろう。つまり、この家はひとり親の家庭なのかも知れない。その下から次ページへと目を通して、かのんは「そう来たか」と思わずにいられなかった。各質問に対して、それなりの回答スペースを確保しているにも拘わらず、すべての回答欄に「とくになし」というひと言しか書き込まれていなかったからだ。何カ所か、酒の染みらしい紙の毛羽立ちが見られるだけでなく、不規則な皺の跡までが残っている。保護者がこの照会書をかなり乱暴に扱ったか、下手をすれば一度は腹立ち紛れに捨ててしまおうとでもしたのかも知れないと想像がつく。そして極めつきが、この臭いだ。
ここから考えられるのは。
一つ。子どもが自転車を盗んだくらいで何を大げさなと腹立たしく思っている。
二つ。子どもが何をしようと自分には関係ないという姿勢の親である。
三つ。生活が荒れている。
いずれにせよ、あまりいい想像が浮かんでこない。
今度は同じ封筒からもう一通の用紙を取り出してみた。こちらは「少年照会書」というものだ。問題を起こした少年自身に、自分が起こしてしまった事件について、改めて認否を問うと共に、なぜそのようなことをしてしまったのか、今はどのように考えているかを書いてもらう。また、被害者に対して謝罪や弁償の気持ちはあるかなどということも尋ねる。少年自身が書けない場合には保護者が代わりに記入しても構わないものだが、今回そこに書かれている文字は、明らかに保護者のものとは違っていた。
「人の自てん車をとってすいませんでした」
保護者照会書の臭いがこちらにも少し移っていた。シャープペンで書かれているのは稚拙で頼りない筆跡の、その一文だけ。十五歳で自転車の「転」が書けないということ以外の情報が摑めない。
「ひょっとすると、多少の知的障がいがある可能性も考えられるかな」
コンビニ弁当ばかりでは飽きるから、ほぼ一週間ぶりに職場からほど近い食堂で昼食をとることにすると、かのんの説明に、同行した若月くんがトンカツをおかずに大盛りの高菜飯を頬張りながら視線だけ天井の方に向けた。高菜飯の上には、別注の温泉卵までのっている。すると、かのんと同じく肉ゴボウ天うどんを注文した巻さんが「考えすぎじゃない?」と、柔らかめのうどんの湯気を吹く。ここの肉ゴボウ天うどんは、とろとろに煮込んだ牛肉もゴボウの天ぷらも多めなうえに、おろし生姜がたっぷりのっていて、甘めの出汁の味を引き締めている。これに、テーブルに備えてある刻み青ネギを山盛りと、さらに柚子胡椒を加えると風味がぐんと増して、癖になる味だ。この土地で暮らすようになってからの、かのんの好物の一つになった。
「単なる不登校なだけかもよ」
巻先輩の言葉に、かのんと若月くんは同時に「たしかに」と頷いた。外でランチというと、このメンバーになることが多い。二十代の若月くんはかのんと同じく独身だし、巻さんは五十手前くらいだが「お弁当作りは卒業した」が口癖で、さらに最近では「いっそのこと主婦業も卒業しようかな」と、少しばかり穏やかではないことを言い出している。ちなみに、巻さんのご主人は裁判所の書記官をしていて、今は同じ福岡家庭裁判所の、別の支部に勤めている。大学生の一人息子は東京にいるということだ。
福岡家裁北九州支部の少年係調査官は、五十代の勝又主任調査官を筆頭に、鈴川さん、そしてここにいる三人の、計五人からなる。鈴川さんと勝又主任は常に弁当持参だから、外で昼食をとることはまずなかった。
「どっちにしても一回きりの面接で、そう突っ込んだことまで聞けるわけでもないですしね」
かのんの呟きに「そういうこと」とさらりと答える巻さんは、普段の仕事ぶりも淡々としているというか、かなり割り切っている印象だ。それがベテランというものなのかも知れないが、話を聞いている限り、かのんのように担当した少年との接し方やアプローチについて「あれでよかったんだろうか」と引きずることもない様子だし、その子の将来に思いを馳せるなどということもないらしい。
「その案件に関しては、僕は少年より保護者の方に興味があるなあ」
たっぷりした体格にふさわしく、いつでも旺盛な食欲を見せる若月くんが、眼鏡の奥の丸い目をぱちぱちとさせた。アザラシの赤ちゃんが眼鏡をかけているような、おじさん子ども的な顔立ちの彼は、表情も豊かで、何というか時代を超越した感じの愛嬌がある。その外見のお蔭で、調査官という仕事をする上ではかなり得をしていると、かのんは常々思っている。何しろ一目で相手の警戒心を解く雰囲気の持ち主なのだ。
「厄介な母親じゃなければいいんだけどね」
「それも、今から考えても仕方がないこと」
かのんの呟きを打ち消すように言って、巻さんは早々とうどんの汁を飲み干し、ふう、と息をついている。若月くんは「ですね」と楽しそうに笑いながら、小皿に残っていた漬物を口に放り込んだ。ポリポリといい音が、こちらまで聞こえてくる。
「若月くんは、これから鑑別所?」
巻さんが、早くも財布を取り出しているから、かのんも大急ぎで残りのうどんをすすり始めた。一人で喋っているつもりもないのだが、なぜかいつでも自分だけ、食べるのが遅くなる。二人のやり取りに口を挟んでいる余裕はなくなった。
「そうなんですけど、これがまた、悩ましい子なんですよね。犯罪事実も『あんたらがそう思うんならそれでいいんじゃね?』みたいな言い方をするし、テストも真剣に受けてくれないし」
「私の方は、返事だけはいいんだけどねえ。別の意味で、ちょっと厄介になりそうなんだ」
「鑑別所じゃないんですよね、どこまで行くんですか?」
「中間。入院してたお祖父ちゃんが帰ってきたもんで、父親がまたイライラし始めて、酔うと暴力を振るうらしいんだ。それで本人は、また夜中に外をうろついたり帰ってこなかったりになったらしいんだけど、母親がぼんやりした人で、電話で話してても埒があかないのよ」
福岡家裁北九州支部の管轄には、北九州市全域だけでなく、西に隣接する遠賀郡の四町と、中間市も含まれる。かのんたち少年係の調査官が、鑑別所でも学校でも児童相談所や自立支援施設でもなく、個人の家を訪ねるときは、ほとんどの場合が「試験観察」という状態にある少年に会いに行くのが目的だ。
単発的な窃盗や喧嘩などよりもさらに非行の度合いが進んでいたり、何かしら複雑な事情を抱えた少年が逮捕されると、もう「在宅事件」というわけにはいかなくなる。この場合は「身柄事件」と言って、少年は少年鑑別所で身柄を拘束された上で、心理テストや面接などといった「観護措置」を受け、最終的に裁判官による「審判」を受けなければならない。鑑別所で過ごすのは、通常なら四週間だ。少年が容疑を否認している場合は、最長で八週間に及ぶこともある。
ところで、こうして少年が最終的に審判を受けるまでの間に、一定期間、家裁調査官が様々な働きかけを行いながら少年と面接を繰り返し、彼の変化を見守ることがある。この期間を「試験観察」という。試験観察中に少年が自分の行いを反省出来るようになったり、自分の問題点に気づき、更生への足がかりが摑めそうだと判断されれば、その後の「審判」にも影響する。
この試験観察をするにあたって、再犯や逃走の恐れもなく保護者も協力的な場合は、身柄事件であっても、日常生活の中で学校や職場に通いながら生活のリズムを取り戻させる取り組みを行う。この場合でも、調査官はたとえば日記をつけさせたり、必要なカウンセリングを行うなど、相手の年齢や問題点に合った方法を駆使しながら、定期的に少年と保護者に家裁まで来てもらって面接を行う。ただし、事情があって来られない場合や、少年の家庭の状態や暮らしぶりを知るために家庭訪問をする場合もある。一方、家庭環境が整っていないとか、再犯・逃走する可能性が高い場合、また少年の社会への順応性などを調べ、一般常識を身につけさせるべきだと判断した場合には、少年は一般の篤志家に預けられることもある。これを「身柄付補導委託」という。期間はおおよそ六カ月。
この場合、調査官は定期的に委託先に出向いて少年と面接をするが、どれだけ強がっていてもまだ十代の彼らにとって、馴染みのない環境で他人に囲まれ、基本的な生活態度の一つ一つから叩き直される体験は、精神的にかなり厳しいようだ。そこで初めて現実の重たさに気づいて泣き出したり、心細さに脱走する少年もいる。そんな問題を起こせば、まず少年院に直行だ。
とにもかくにも、若月くんも巻さんも、今日の午後は身柄事件で観護措置中と、自宅での試験観察中の少年との面接があるということだ。
「ふう、ご馳走さまでした」
ようやく箸を置いたときには、額にうっすら汗が滲んでいた。だが、会計を済ませて店から出ると、途端に冷たい風が吹き抜けて、汗など簡単に引いてしまう。季節は確実に巡り、もう冬の気配が感じられるようになっていた。九州は暖かいとばかり思っていたが、北九州という土地は実際に住んでみると夏場はともかくとして、冬は日本海に面しているだけに季節風が強くて意外なほど寒い。近ごろは秋の深まりと共に、朝晩ずい分冷え込むようになってきた。
小倉駅に向かう巻さんたちと店の前で別れて、一人でのんびり歩きながら、かのんはふと、初めてこの土地で冬を迎えたときのことを思い出した。
午後から冷たい雨の降り出した日だった。出張からの帰り道、坂道を歩きながら何気なく空を見上げたら、無数に降り注いでいた雨粒が空中でふいに速度を落とし、次の瞬間、ふわりと雪に変わった。同時に、傘を叩く雨の音も遠ざかって、それからものの十分程度で、遠くに見えていた田畑や小高い山まで、すべてが水墨画の世界のようになるのを、かのんは半ば陶然と眺めたものだ。気がつけば身体が芯まで冷え切っていて、小倉まで戻ったところで駅に直結しているショッピングモールに飛び込み、大急ぎで厚手のマフラーを買ったことも思い出す。
今年もあのマフラーを出す頃だ。
そう考えると、年月の早さを改めて思う。調査官は、三年ごとに異動する。それぞれの土地のことが分かりかけたと思う頃には他の土地に移ってしまうから、本当の魅力はなかなか摑みきれないが、かのんはかのんなりに、赴任地の景色や食べ物を味わいたいと思っている。
この週末は自転車で少し遠出をしようと計画している。月に一、二回は東京に帰っていることもあって、土日や祝祭日でも、のんびりと自由に行動出来る日はそう多くない。このままでは、そうでなくても出番の多くないチェレステカラーのビアンキは、単なる飾り物になってしまいそうだ。
そういえば、芦屋町の方に、なみかけ遊歩道というサイクリングスポットがあると、書記官から聞いている。波が打ち寄せる岩場に沿ってぐるりと走れるのだそうだ。これからの季節は風も強いし、かなりの寒さだろうが、それでも行ってみるだけの価値があるという話だった。おそらく片道一時間半も見ておけば行けるのではないかということだ。
週末は、サイクリング。
それを思うと気持ちが弾む。家裁の昼休みは四十五分と決まっている。だから食事でも何でも急がなければならないのだが、とりあえず戻る前にいつものコンビニに寄って、何か甘いものを買っていくことを忘れてはならなかった。
2
朝倉陽太朗十六歳は某日午後四時半頃、高校の下校途中に同じ学校に通う友人二人と連れだって北九州市若松区二島にあるショッピングモールに立ち寄り、モール内の書店で漫画本十六冊を万引きした。店を出たところで巡回中の警備員に声をかけられ、逃走を図るが、友人二人は逃げ果せたものの、朝倉少年はその場で身柄を確保された。書店側の聞き取りに対して、本人は友人たちに誘われて犯行に及んだこと、万引きは今回が二度目であることを供述。だが、同店は以前から度重なる万引き被害に遭っており、これまでも防犯カメラの映像に朝倉少年らと似た背格好の少年たちが何度も映っていることに加え、二度目の犯行というにしては、いかにも手慣れた様子で、さらに盗んだ点数も多いことから、常習と判断して警察に通報し、少年は同日、逮捕となった。
目の前には、書類に添付されていた写真以上に色白で細面の、また年齢の割に小柄な少年が座っている。肩幅も狭くて、まだ中学生のような頼りない雰囲気だ。髪は黒く、髪型は普通。ピアスの穴も開いていない。服装はこざっぱりしていて乱れもなかった。
朝倉陽太朗は最初からほとんど顔を上げることがなかった。かのんが何を問いかけても返事をする声は小さい上に曖昧だ。一方の母親は、面接室に入ってきたときには少年の背に手を添え、少年が椅子を引いて腰掛けるときも一緒に椅子の背に触れる仕草を見せた。席についてからも、ことあるごとに隣で俯いたままの息子に視線をやる。かのんが話しかけたことに、朝倉少年が「ええと」などと口ごもると、すぐに「それはですね」と口を挟んできた。
濃いピンク色のニットアンサンブルに長めのチェーンペンダント。化粧もしっかりしているし、髪には軽くパーマをかけて、耳元にも光るものをつけている。派手とまでは言わないが、万引きした息子に付き添って家裁に来る格好としては、少しばかり場違いな感じがしなくもなかった。その母親が少年に替わって喋ってしまうたびに、かのんは「息子さんに答えていただきたいんです」と繰り返さなければならなかった。すると母親は「あ」とか「すみません」と肩をすくめるが、またすぐに口を挟む。
母親、過保護。過干渉。
手元のメモに、書き込んだ。そして、また少年の名を呼ぶ。
「繰り返しますが、これは取調ではありません。私の仕事は陽太朗さんを責めたり叱ったり、また罰したりするのが目的ではないんです。だから緊張しないで、思った通りのことを陽太朗さん自身の言葉で、そのまま話して下さいね」
面接の予定時間は二時間から二時間半。警察の調書をそのまま読み上げるようなことはしないが、本人の身元と犯罪事実を確認した上で、様々なことを尋ねていく。
「盗んだ本は、どうするつもりだったのかな。読みたかったの? それとも、売るつもりだったとか?」
朝倉陽太朗は会社員・朝倉亨と妻・菜々絵との間に長男として生まれた。現在四十六歳の亨は中堅食品会社の係長をしており、亨よりも一つ年上の菜々絵は専業主婦。陽太朗の三歳下に次男、さらにその二歳下に長女がいる。家族は若松区の新興住宅地に建つ戸建て住宅で暮らしているが、父親は営業職ということで出張も多く多忙。子どもの教育はすべて菜々絵が取り仕切っているようだ。
陽太朗は幼い頃、小児ぜんそくを患っていた。母親は体力をつけさせようと二歳頃から水泳を習わせ、幼稚園からはピアノ、英会話教室にも通わせた。小学生になるとこれに学習塾が加わる。成績は体育と図画工作を除いて中の上。学校の通知表には「やれば出来る」と書かれることが多かった。
「やれば出来る、ですか」
かのんの言葉に、母親が不満げに頷いた。
「そう書かれる度に私たちはずい分と悔しい思いをしよったんです。だって、やってるんですから。やらせとるんですから。だから、いつも『もっと頑張らないけんね』って、ずっと言い続けてきました」
かのんは「なるほど」と頷き、そのまま陽太朗に視線を移した。
「じゃあ、陽太朗さんもずっと頑張ってきたのかな。大変じゃなかった?」
陽太朗が一瞬、口もとに力を入れて何か言おうとする前に、またもや母親が「当たり前のことです」と胸を張る。
地元の中学に入学後は母親の反対を押し切ってサッカー部に入ったものの、もともと体育が苦手だった上に体力的にもついていかれず、すぐにやめてしまった。その後、部活はしていない。また、中学生からは、それまでの習い事の代わりに複数の学習塾に通うようになった。三年間を通して特に親しい友人は出来なかったが、一方でいじめ被害の経験などもない。ゲームが好きで、家で弟と遊ぶことが多かった。これも母親は「きちんと時間を決めて」遊ばせていたという。成績は相変わらず中の上だった。
「それだけ安定してるっていうことは、ずっと頑張ってきたっていうことですね」
母親が「もちろんよねえ」と息子を見るが、それにも少年は無反応だ。その後、高校受験に挑むが第一志望には合格出来ず、第二志望の現在の私立校に進む。この辺りでは中堅と言われる学校だ。
「では、これから先はお母さんには少し見守っていただいて、陽太朗さんに自分で答えてほしいんですが」
手元の時計をちらりと見てから、かのんは改めて、念を押すように母親と少年を見た。
「さっきも聞いたけど、盗んだ本はどうするつもりだったの?」
「――べつに、どうするとかは」
「じゃあ、これはどうかな。本屋さんでも、警察でも、陽太朗さんは友だちに誘われたということと、今回が二度目だと答えていますけど、それについては、どうかしら?」
「――誘われて――二回目で――」
「そう、二回目なのね。それなら、どうして本屋さんは『もっとやってるはずだ』って言ったのかな」
「――何か、間違ったか、人違いか――」
「人違いか、なるほど。それじゃあ、いつも仲間と三人でいるっていう、それについてはどうかな。誰がリーダー格だとか、そういうことはあるの?」
書店から逃げた他の少年二人も、朝倉少年の供述によって氏名が明らかにされたことから、翌日までに逮捕されている。実は、彼らは揃って、万引きは朝倉陽太朗に誘われたと語っているようだ。それも二回どころか、すでに五、六回も同じ店で万引きを繰り返してきたし、他の何店かでも万引きをしてきたという。かのんは担当していないが、書類はもう家裁に回ってきていて、鈴川さんと若月くんが、それぞれに動き始めている。
「大体いつもあいつらと一緒やけ――」
「そのことですけどね」
我慢しきれないというように、やはり母親が喋り出してしまう。
「要するに、この子は利用されたんですよ。おとなしくて人が好いもんだから」
母親はそれから堰を切ったように、自分の息子こそが被害者なのだということをまくし立て始めた。次第に声がうわずっていく。
母親から見た長男は真面目で几帳面な上に気が弱く、とてもではないが自分から悪事を働けるような子ではない。また十分な小遣いも与えているので、万引きなどする必要はまったくない。つまり、今回のことは単に悪い友人にそそのかされて万引きすることになったのに違いなく、その挙げ句に警察に捕まったのだから、迷惑以外の何ものでもない。親としては、その友人たちに詫びてもらったくらいでは気が済まない。何なら損害賠償して欲しいほどだという。
それだけのことを母親が滔々と述べる間、かのんはメモを取り続け、うん、うん、と頷きながら、一方で朝倉少年を観察していた。少年は何度か薄い肩を上下させ、時折、口もとを歪めた。微かな貧乏揺すりが伝わってくる。額にかかる前髪を振り払うように、顔を小さく左右に振ることもあった。とりあえず母と子を離さないと、少年から彼なりの言葉を引き出すことは難しそうだ。
「では、ここからは息子さんと二人でお話をさせていただきたいので、お母さんは外でお待ちいただけますか」
母親の話をひと通り聞いた後で、かのんが促すと、母親はまだ話し足りないといった表情だったが、それでも素直に面接室から出て行った。かのんと二人きりになると、少年はほんの小さな舌打ちをして、それから長いため息をついた。背中から力が抜けたらしいことが見て取れる。
「今お母さんが話したことと、朝倉さん自身の考えと、違うところはありますか? たとえば友だちのこととか、それから今回の万引きのこととか」
少年が、初めてちらりとこちらを見た。瞳が揺れる。
「――特に、ないです」
「ないかな。友だちについては、どう? お母さんの言う通り、悪い人たちだと思っている?」
「――それは――分からんです」
「じゃあ、一緒にいるときは、どんな感じなの? 楽しいとか、面白いとか」
「――そんなに面白いっちゅうことも、特にないんやけど」
「それなら、あの日は? 誰が本屋さんに行こうって言い出したんだろう。最初から万引きする目的だったのかな」
「――何となく『行こうか』っちゅって」
「誰が?」
「――何となく」
「そうか、何となく、そうなったのね。誰が言い出したっていうわけじゃなく?」
「――まあ」
「それで朝倉さんは、二人のうちのどっちかに命令されて万引きすることになったの? それとも、両方? 本当にあれが二回目だったのかな」
少年の貧乏揺すりが伝わってくる。何度か深呼吸を重ねる少年の顔を、かのんは首を傾げて覗き込むようにした。今ここで、少年が本当のことを話してくれたら、彼自身の気持ちも軽くなるだろうし、これから母親に伝えるべき話の内容も違ってくるはずだ。だが、しばらく待っても、少年は口を開こうとはしなかった。調査官の仕事にもう一つつけ加えることがあるとしたら、それは「待つ」ことかも知れない。それでも少年は口を開きそうにはなかった。かのんは再び話し始めた。
「分かってると思うけど、万引きって、要するに泥棒と同じなのね」
「――まあ」
「それに、被害に遭った本屋さんのことも、少し考えてみてほしいんだ。本が一冊売れたときの、本屋さんの儲けってどれくらいあるか知ってる?」
少年は、俯いたままで首を左右に振った。かのんは「定価の二割だって」と手にしたボールペンをくるりと回しながら言った。
「つまり、朝倉さんが盗った本でいえば、一冊の値段が四五〇円として、二割っていうことは――」
「九〇円」
「さすが、計算が速いね。それの十六冊分っていうことは」
横を向いたまま、それでも少年はさほど間を置かずに正確な金額を答えた。かのんは「そうね」と頷いた。
「十六冊売って、やっと一四四〇円。ちなみに、朝倉さんのお小遣いは月にいくら?」
少年は「五〇〇〇円くらい」と答えた。
「だとすると、朝倉さんの家が本屋さんなら、漫画の本を五十冊以上売らないと、それだけのお小遣いはあげられないことになるよね」
「――」
「その他にも、本屋さんは家賃とか光熱費とか、それから店員さんのお給料とか、自分や家族の生活費とか、色々と出していかなきゃならないよね?」
朝倉陽太朗は大きく息を吸い込み、わずかに顔を傾けたまま「だから」と呟いた。
「もう、やりませんから」
視線だけ上げたときの表情を見て、かのんはつい「本当に?」と言いたくなった。面差しは幼くても、どこかに投げやりなふてぶてしさが感じられる。本当に反省しているときの顔つきというのは、こんなものではない。
かのんは詰め寄る代わりに、では、迷惑をかけた書店に対してはどのように考えているかと尋ねた。照会書には「謝って弁償します」と書かれていたが、本人の口から直接、反省の弁を聞きたかった。すると少年は「かあさんが」と、ぼそりと呟いた。
「菓子か何か持って、謝ってくるっち」
「お母さんが? 朝倉さんは行かないの?」
「――かあさんが、行かんでいいって」
次第に姿勢が崩れてきて、椅子の背にもたれかかるような格好になり始めている。貧乏揺すりも止まっていなかった。少年が少しずつ苛立ちを募らせているらしいことが伝わってくる。何かしら、心にわだかまりがあることは確かだと思う。だが、たった一度の面接で、そこまで探り出すのは難しかった。最後に、今度は少年と入れ替わりに、母親に入ってきてもらった。
「お店へは、お母さんが謝罪に行かれるんだそうですね」
母親は、とにかく早く始末をつけてしまいたいのだと応えた。
「陽太朗さんと一緒には、行かれないんですか?」
「まだ高校一年生ですからね。『あれが万引きで捕まった奴だ』みたいな目で見られたら可哀想ですし、それが心の傷になって欲しくないんです」
「心の傷、ですか」
「だって、悪夢みたいなものやないですか。あんな引っ込み思案の子が、せっかく友だちが出来たち喜んどったのに、結局は利用されとっただけやなんて」
「息子さんは、本当に利用されたんでしょうか」
かのんの質問に、母親はいかにも心外なことを言われたという顔つきになり、「当たり前やないですか」とまなじりを決した。
「あの子には今後一切、彼らとは関わらんようにきつく言って聞かせました。もちろん、LINEや何かもやめるように、私の目の前でアカウントも何もかも全部、削除させました。自分の人生を台無しにするような相手とは、金輪際、関わったらいけんって。あちらに転校してもらいたいくらいです」
かのんは「そうですか」としか答えることが出来なかった。反論したところで、この母親は容易に納得しないに違いない。むしろ、話がこじれる一方だと思ったのだ。これは、あくまでも在宅事件だ。これに懲りて、あの気弱そうにしている少年が二度と馬鹿な真似さえしなければ、それで一段落ということになる。
朝倉母子を帰して調査官室に戻ると、かのんはまずコーヒーを淹れ、冷蔵庫で冷やしておいたコンビニのデザートを取り出した。このために、いつもおやつを欠かさない。甘いものが、かのんにとっては何よりの滋養強壮剤なのだ。
「おっ、今日のは何。栗か?」
頭の上から声が降ってきた。勝又主任が、眼鏡の奥の目を細めながら後ろに立っていた。
「お疲れさん。どうだった」
かのんは、スプーンを片手に「まあ、大体」と頷いて見せた。
「ずい分と過保護っていうか、子どもを支配している感じの母親でした」
「少年は?」
「年齢よりは幼い感じの割に、何となくふてぶてしい子でしたね」
勝又主任は「そうか」と頷いて自分の席へ戻っていく。
「で、庵原さん、今度の週末は帰るの?」
窓際のデスクに戻った勝又主任が、首を伸ばすようにしてこちらを見ている。若月くんも巻さんも、そして鈴川さんもまだ戻ってきていなかった。
「今週は帰りません」
主任はふうん、と首を傾げた。
「彼氏が淋しがるんじゃないのか」
「大丈夫です」
「先週も帰らなかったよな?」
うるさいな。
と、ちょっと思う。世話好きが高じて、勝又主任には少しばかり詮索し過ぎなところがある。
「あんまり彼を放っておくと――」
「主任」
スプーンをひとなめしたところで、かのんは首を巡らせて主任を見つめた。
「それ以上はセクハラになりかねませんよ」
すると主任は鼻白んだ表情になって「はいはい」と一度は首を引っ込め、だがすぐに「じゃあさ」と、また首を伸ばしてきた。
「今度の週末は、どうしてる?」
「こっちでやりたいことがありますから」
「よかったら、僕らと走らないかなあ」
かのんは薄めのコーヒーをひと口すすってから「またの機会に」と愛想笑いで答えた。勝又主任の趣味はジョギングだ。ことあるごとに走ることの素晴らしさを語り、何とかして仲間を増やそうとする。調査官という仕事は、人の人生や思いを受け止めるばかりだから、澱のようなストレスが溜まりやすい。だから暇を見つけてはストレスを発散し、気持ちを切り替える必要があった。それで、登山やバードウォッチング、囲碁将棋と、趣味に没頭しようとする人が多い。かのんにとってはそれがサイクリングなのだが、どういうわけか勝又主任はジョギングの方に引き込みたいらしかった。
「いいもんだよ、この、両方の足の裏で、じかに大地を感じるのは。チャリンコじゃあ、それは味わえないだろう?」
チャリンコなんて言わないで欲しい。それでは前カゴをつけたママチャリのようではないかと思いながら、かのんは愛想笑いを崩さずにスプーンを動かした。
「さて、と」
甘いものを食べ終えたら、スリープ状態になっていたパソコンを立ち上げる。朝倉陽太朗少年に対する調査面接の結果を、今日中に調査票にまとめてしまうつもりだ。これで、この事件に関してはおしまいということになる。
それにしても。
何となくすっきりしないものはあった。陽太朗本人の口からは結局、最後まで反省の弁らしいものは聞かれなかったし、母親の向いている方向も少しばかり見当違いだ。すべては友だちのせいだと言い切り、我が子を反省させようとは思っていない。少年は後半、ため息をついたり貧乏揺すりをしたりという苛立ちを見せていたが、あれはどういう心情を表していたのだろう。かのんの目には、母親に苛立っていたように見えなくもなかったが。
でも、まあ。
とにかくこれで普通の高校生に戻ってくれることを願うことにして、かのんはパソコンのキーボードを叩き始める。少しして、栗林からLINEが入った。
〈クチェカの腹が、まだ治らないよ〉
先週から、彼が飼育担当しているニシゴリラの雌、クチェカが体調を崩して、栗林は休日返上で動物園に詰めている。それもあったから先週も今週も、かのんは東京に帰らないことにしたのだった。もともと土日や祝日に休めるなんて、動物園の飼育員にはまず期待できないことだが、それでも、せっかく東京まで戻っても実家しか行くところがないか、またはひと晩中ゴリラ舎で過ごすのでは、あまりに味気ない。
〈正露丸は?〉
半分、冗談のつもりで返事を送った。するとすぐに、ゴリラが涙を流しているLINEスタンプだけが返ってきた。
3
一週間が飛ぶように過ぎていく。瞬く間に金曜日が来た。その日かのんは午前中から少年鑑別所に行って、暴行傷害容疑で逮捕された十八歳の少年と二度目の面接をし、続いて鑑別所の技官と話し合いの時間を持った。ベテラン技官は広くなった額を掻きながら「ダメですね、あいつは」と顔をしかめた。
「私の顔は当然、覚えておるんですが、最初のひと言が『まだおったんか』ですから」
つまり、そう簡単に更生の兆しは見られそうにないということだ。これまでも繰り返し暴れては逮捕されている少年は鑑別所にも慣れてしまっている。
「余計な時間をかけてないで、早く少年院に送ればいいじゃないかと、少年本人から言われました」
午後からは裁判官室を訪ねて午前中の面接について中間報告をした。かのんが何を話しても、自分の将来になどまるで希望を抱けないらしい少年は、うるさそうに顔をしかめてそっぽを向くばかりだった。こちらとしては、どこかに彼の気持ちを開かせる糸口があるのではないかと思っているのだが、それを見つけ出す手立てがない。
「家族は面会に行っているようですか?」
谷本判事の質問に、かのんは「いいえ」と首を横に振った。生い立ちが複雑な上に、現在の家庭環境もかなり悲惨な状況の少年だ。そういう意味では気の毒な点がたくさんある。
「実母は相変わらず居場所が分からないままですし、実父も少年にはまったく関心がないようです。少年は『手紙も来ん』と笑っていました」
「笑っていましたか。どんな風に?」
「『どうせろくに読めんのやけ、どっちみち同じやけど』って」
小学生の頃から不登校になったという少年は、文字の読み書きも満足に出来ない。最初の面接のときに、作文を書いて欲しいと提案したら、少年は「字なんか書けんちゃ」と拒否をした。知能指数をテストしたところでは境界領域と判断されている。つまり、明らかに知的障がいがあるというレベルではない。そういう少年にはまず、落ち着いて学べる環境が必要なのだと思う。今のままでは少年院送致は避けられそうにないが、それならそれで、少年院にいる間に読み書きを学んで、さらに新たな知識を得る楽しさを知ってほしい。暴力の裏にひそむ劣等感に打ち勝つためには、そこから始めるしかないからだ。
「調査官は、父親と会う予定はありますか」
「週明けに面接することになっていますし、別の日に家庭訪問も予定しています」
谷本判事は満足げに頷いて、「そのまますすめて下さい」と締めくくった。噂によれば、呑むと人が変わったように賑やかになるという判事だが、仕事中は極めて口数も少なく、実直そうに見える人だ。
その後は週明けに行われる「事例検討会議」に向けての準備をしなければならなかった。調査官がそれぞれ担当している少年事件について、アプローチの仕方や心理分析方法、処遇の見通しなどを互いに報告し、より適切と思われる方法を検討しあうものだ。これによって、調査官一人で事件を受け持つことで生じる偏りや不足点が解消されるし、ベテラン調査官から様々なことを学ぶ機会にもなる。かのんとしては今回は特に、さっき鑑別所で面接を行った少年について、他の人たちの意見を聞きたかった。
少年と面接出来る回数は残り一、二回。その中でどういうアプローチをすれば、少しでも彼の心に変化の種をまくことが出来るか、さらに来週予定している父親との面接では、息子に無関心な親の気持ちを、どうすれば動かせるか、先輩方の経験と知恵を借りたかった。そのための資料を揃えたら、今週はおしまいだ。
「どうだい、一杯やっていかないか」
帰り支度をしているときに、勝又主任が調査官たちに声をかけてきた。即座に「いいですね」と応じたのは若月くんだけだ。かのんも「今日はやめておきます」と控えめに会釈して鞄を肩にかけた。
「明日、早いんで」
それだけ言って、地裁と同居している家裁の建物を後にする。学生時代の友だちでも近くにいれば、カラオケくらい行きたいところだが、北九州にそういう友人はいない。結局、官舎で一人の夕食をとりながら缶ビールを二本空けて、その晩は早めに布団に入った。
翌朝は、車が雨水を跳ね飛ばして走り抜ける音で目が覚めた。手探りで枕もとに置いた眼鏡を探し、眼鏡をかけながらベランダに出てみると、ちょっと錆の浮いた手すりの向こうに、雨で煙る住宅街の景色が広がっている。驚くほど冷たい風と一緒に細かい雨粒が顔に当たった。
せっかく楽しみにしてたのに。
こんな天気では遠出は無理だ。部屋に戻って普段あまり使っていない方の和室を覗けば、綺麗に磨き上げたビアンキが、颯爽と走れる機会を心待ちにして、それこそ青空色の輝きを放って見える。だが、仕方がなかった。
〈おはよう。クチェカの様子は?〉
パジャマだけでベランダに出たお蔭で、あっという間に身体が冷えた。遠出が出来ないのならと再び布団に潜り込んで、かのんは身体を温めながら栗林にLINEを送った。しばらくして、うとうとしかかった頃に〈相変わらず〉という返事が来た。
〈眠ろうとしても眠れないのかな、何か変な姿勢をとるし、やっぱり痛いのかも知れない。もう二、三日しても治らないようなら、CT検査だ〉
〈それ、めちゃめちゃ大変そう!〉
〈麻酔かけなきゃならないからね〉
ゴリラという生き物は、あんなに大きくて立派な体格をしているのに、実は意外なほどデリケートで、ちょっとしたことでお腹をこわしたりするという。八歳のクチェカは中でも神経質なタイプらしく、栗林が勤める動物園で飼育されているニシゴリラの中でも一番の心配の種になっているらしい。
〈落ち着いたら連絡するよ。かのんも今朝は早いんだな〉
〈サイクリング行こうと思ったんだけど、雨だからやめた〉
〈そっちは雨か。じゃあ、のんびりすれば〉
〈そうする〉
スマートフォンを布団の脇に置いて眼鏡を外し、毛布を顎のそばまで引き上げる。時間を気にせずに布団の中で過ごすことが出来るのも、思えば貴重な贅沢だ。今ごろゴリラを眺めながら気を揉んでいるに違いない栗林のことを考えると少し申し訳ない気もするが、こればかりは仕方がなかった。
早く元気になるといいね、クチェカ。
そのまま目を閉じて、静かに自分の呼吸を聞いているうち、眠りに落ちたらしい。気がついたときには、もう十時を回っていた。改めて外を眺めると、雨も上がっている。
それならと、布団を畳みながら今日一日の過ごし方を組み立て始めた。今さら遠出する気にはなれないが、やっぱり自転車には乗りたい。それなら今日のところは近所を適当に走り回ることにしようと決めた。
久しぶりにビアンキを外に出して街を走り始めたのは昼近くなってからだ。天気は徐々に回復してきて、薄くきらめくような陽が射し始めていた。日頃は黒のパンプスに地味なスーツや、せいぜい無地のニットなどで過ごしているから、明るい色彩のカジュアルな服装にスニーカーで動き回れるだけでも気が晴れる。雨上がりの空気は湿り気を含んだいい香りがしていて、風を切って走ると、すぐに身体が温まってきた。
普段は通らない道を進み、目についた角を曲がってみる。特に目標など決めず、散歩でもするように走り回っていると、頭の中に少しずつ新しい地図が生まれていく感じがした。そうして見知らぬ住宅地を走っていくうち、ふと、歩道に真っ白いベンチを出している家が目にとまった。近づいていくと、普通の住宅の一階を改装して、テイクアウトの小さなサンドイッチ店になっている。ちょうど空腹を感じていたから、今日のランチはここで済ませようとひらめいた。
「ベンチで食べていってもいいですか?」
手描きの看板が掲げられている小さな窓を開けて声をかけると、かのんと同世代くらいに見える女性が「どうぞどうぞ」と笑顔を向けてくれた。店の横に自転車を立てかけて、注文したサンドイッチと飲み物を受け取り、ベンチに腰掛ける。秋の陽射しがまぶしくて、いかにも清々しい日になった。一方通行の車道は道幅も広くなく、車どころか人も滅多に通らないようだ。
サンドイッチは、バターがよくしみた食パンが軽くトーストしてあって、間に挟まっているシャキシャキとしたレタスやルッコラなどの歯ごたえとスクランブルエッグ、そしてハムの組合せが絶妙だった。陽射しを浴び、雲の流れる空を見上げながら、もぐ、もぐ、と無心でサンドイッチを頬張り、一緒に注文したハニーレモンを飲む。心が解き放たれていくのが実感できる。これは、いい店を見つけたと思った。スマホの地図に位置を記憶させておくことにする。
「美味しかった、また来ますね」
最後にそう声をかけて、また自転車に跨がった。しばらく走ると、いつの間にか到津の森公園の方まで来ていた。ここは小倉の街の中心地からも近い上に、小高い山の連なりの中に動物園があって、市民の憩いの場になっている。かのんも何度か訪れているし、以前、栗林が来たときには彼を案内したこともあった。あのとき、彼はフクロテナガザルがすっかり気に入ってしまって、展示スペースの前から動かなくなった。かのんはずい分長い間、フクロテナガザルの独特の鳴き声をぼんやりと聞き続けたものだ。
今日も、あのフクロテナガザルを見てみたい気がしたが、自転車では入ることが出来ないことを思い出した。駐輪場に預けて、可愛いビアンキが盗まれたりしては大変だ。あっさり諦めて、今度は近くを流れる川沿いの道を走ることにする。ほとんど歩行者専用のような細い道は、周囲の景色はさほどでもないものの、走るには快適だった。このまま下流まで行ったら海に出られるだろうかと期待したのに、頭上を線路が通る辺りで道がなくなった。地図アプリで確かめてみると、西小倉駅よりも、さらに西まで来ている。軽い散歩のつもりが、それなりに走ったようだ。その上さっきまで陽が射していたのに、いつの間にかまた灰色の雲が広がってきて、風も冷たくなってきている。
そろそろ戻った方がいいかな。
アプリで道を確かめながら、かのんはまたペダルを漕ぎ始めた。なるべく交通量の少ない裏道を選んだつもりが途中から広い通りに出てしまい、そのまま走っていくと、独特の屋根をしている松本清張記念館が見えてきた。ああ、この程度の距離なのかと、また頭の中の地図がつながる。ここまで来れば、もう分かる道だ。その先の市役所の横を通り抜けて、 紫川を渡る。直進して魚町銀天街に差し掛かる辺りで、一旦、自転車から降りた。この辺りは車の交通量も多い上に、歩道にも人が多かったからだ。すぐ先の横断歩道で道の反対側に渡ろうと、自転車を押しながら歩調を緩めたときだった。いきなり左側の路地から男が飛び出してきた。バタバタという足音に続いて「あっ」という声がしたから、かのんは反射的に自転車のある方に身体を傾けた。同時に向こうもかのんに気がついたらしく、身体を反転させようとしたらしい。だが、間に合わなかった。かのんの左肩に、どん、という衝撃があった。男がよろけて歩道に転がる。かのんの方は、自転車で身体を支える格好になったからよかったものの、下手をすれば完全に自転車ごと倒れていた。
「痛ってえちゃっ、このっ!」
自分からぶつかってきて自分で転んだ男が、派手な濁声をあげながらこちらを睨みつけてきた。垂れ気味の細い目に細い眉。ツーブロックの髪のてっぺんは金色で、ピアスをしている。どう見ても中学生だ。
「――そっちこそ」
反射的に言い返すと、男は、というより少年は、さっと立ち上がって、さらに忌々しげに首を傾け、顎を突き出すようにしてかのんを睨みつけてくる。いくら子どもだと思っても、ちょっと怖い。咄嗟にどうしようかと思ったとき、男は自分が飛び出してきた路地を一瞥したかと思うと、慌てたように走り出した。そのまま人混みの中に紛れていくのを、呆気にとられたまま、かのんは眺めていた。
「ちょっと、お姉さん、大丈夫やった? ぶつかられたん? 怪我は?」
知らないおばさんが慌てた様子で歩み寄ってきた。かのんの左肩には、確かに鈍い衝撃が残っている。腕を大きく前後に回してみてから「大丈夫です」と答えると、エプロン姿のおばさんは安心したように頷いた。
「以前はこの辺にも怖いお兄さんが結構、歩きまわっとったけ、ぶつかったとか目が合ったとか、色々あったもんやけどね」
「そうなんですか?」
「ああ、平和んなったんよ。やけど、ああいうのもおるけ、油断出来んもんやねえ。これで、もしも相手が年寄りやったら、骨の一本も簡単に折れとるよ」
北九州の人は概して親切だ。知らない相手にでも、こうして気さくに声をかけてくれる。かのんが「本当ですよね」と苦笑している間に、おばさんは「気をつけんとね」と言い残して離れていった。目の前の歩行者用信号がちょうど青だ。かのんは小走りに自転車を押しながら、横断歩道を渡った。何とも言えず胸がざわついている。
何だろう。これ。
何とも妙な感じがしてならなかった。頭の中がめまぐるしく動き始めている。これまでの経験から、記憶の中にある似た匂いを探そうとしているのだ。だが、見つからない。こんな匂いは嗅いだことがなかった。
何だろう。
間違いなく、さっきぶつかった少年から匂ったものだ。横断歩道を渡りきって、再び自転車に跨がってからも、かのんは自分の肩先に残る匂いを懸命に記憶の中で転がし、そして、脳裡に焼きつけた。
翌日も、肩にはまだ鈍い痛みが残っていた。痛みを感じる度に、あの匂いを思い出して、胸の中がざわめいた。それでも午前中は美容室で髪をカットしてもらい、帰りにスーパーマーケットに寄って、午後からは洗濯機を回しながら読んでおかなければならない本に目を通し、それからゆっくりと風呂に浸かった。
夕方には、クチェカの体調が戻ってきたと栗林からLINEが入った。少しずつ食欲も出てきたという。ずっと見守ってきた栗林は、さすがに徹夜続きで疲れたらしい。今夜は早めにマンションに戻ると言ってきたから、時間を決めて夕食をとりながらオンラインでお喋りをすることにした。
「今度、俺がそっち行くときには、フグにしような」
かのんはワイン、栗林は缶ビールについで湯飲み茶碗で焼酎のお湯割りを飲み始めている。疲れていると言う割に、帰宅してからポークジンジャーとツナポテトサラダを作ったのだそうで、風呂上がりのボサボサ頭で嬉しそうに箸を動かしている。かのんの方はトマトの輪切りにピーマン炒め、そして冷凍ハンバーグだ。
「そっちならフグ、安いもんな。刺身と白子も買ってさ、白子は網でじっくり焼いて、あとは鍋やろうよ。ぽん酢も作って」
「網なんか、ないよ。それに、ぽん酢まで作るの? 誰が?」
「そりゃ、俺でしょうねえ、やっぱり」
「でしょうねえ!」
正直に言うと、料理に関しては絶対にかのんはかなわない。栗林は、魚も自分でさばけるし、細かい下ごしらえも面倒くさがらない。出汁も取ればパスタソースも作るといった具合で、しかも盛りつけにもセンスがあるのだ。いくら普段からゴリラの餌やりで包丁を使い慣れているといっても、これは生まれつきの才能としか言いようがない。
「いつ、フグが食べられるかな」
「しばらく休み取れてないからなあ。出来るだけ早く、行けるようにするよ」
「クチェカ次第だね」
「そうなんだよなあ。あの子、今夜はちゃんと食べたかなあ」
結局、話はゴリラのことになる。そうして二時間ほども話した頃、栗林はタブレット端末の向こうで大きなあくびをし始めた。それが、そっくりそのまま、かのんにもうつった。
4
翌週の末、自転車を盗んで捕まった田畑貴久との調査面接が行われる日が来た。果たしてどんな母子がやってくるのだろうかと、かのんは朝から何となく落ち着かなかった。
「こっちの緊張は、向こうにも伝わるわよ」
昼食の時、巻さんに見抜かれた。かのんは「はい」と頷いて、深呼吸をしたり、痛みの引いた肩や首まで回して時計とにらめっこをして過ごした。すると、指定した時間の十五分ほど前に、母子がやってきた。
「あの、この子は少年院に入れられるんでしょうか」
面接室で向き合って椅子に腰掛けた途端、母親が口を開いた。照会書のすべての質問に「とくになし」と答えた田畑里奈という女性は、根もとの部分から大分、黒い地毛が伸びてきている茶色い髪を後ろで一つに束ねて、羽織っているジャケットこそ派手だが、化粧気のない顔には明らかに疲労の色が見て取れた。そんな母親の隣で、十五歳の田畑貴久は、口を真一文字に結んだまま、ただ物珍しげに殺風景な面接室の中を見回している。
「そのぅ、警察でもお願いしたんやけど、今回だけは、何とか――」
「ご心配なく、今回のことで息子さんが少年院に行くことはありません」
警察でも説明されているはずなのにと思いながらかのんが応えると、母親は驚いた様子で、戸惑ったように口もとに手をやる。その仕草や表情が、構わない髪型や疲れた顔と妙に釣り合いが取れていなかった。
「そうなんや――何や、よかった――ねえ、タカ、よかったね。少年院、行かんでいいっちょ」
息子が頷くのを確認して、それからも、母親はしきりに口もとを動かしたり、唇をなめたりしている。緊張で喉が渇いているのだろうか。
「お水か何か、持ってきましょうか?」
すると彼女は、今度はいやいやをするように細かく首を振る。もしかすると、この人は案外若いのかも知れないと、そのときに気がついた。十五歳になる子を持つ母親だし、ぱっと見はかのんよりも年上に見えるのだが、その割には仕草がどこか幼げだ。
「今日、来ていただいたのは、息子さんを少年院に送るための面接でも、警察のような取調でもないんです。ただ、今回どうして貴久さんが人の自転車を盗ってしまったのか、また同じことをしないためにはどうすればいいか、その辺りについて少しお話をうかがいたいと思って、来ていただきました」
十五歳の田畑貴久は、そのボサボサ髪をさっぱりさせて服装にも気をつければ、かなり女の子にモテそうな雰囲気の、凜々しい顔立ちをしていた。古びた黒いダウンジャケットを着て、特に悪びれた様子もなく、かのんの質問にも素直に受け答えをする。
「それでね、ちょっと不思議に思ったんだけど、あの日はどうしてそんな時間に光明の辺りを歩いてたの? 貴久さんの家とは離れてるよね。時間も午後九時半頃っていったら、中学生にとっては遅いんじゃない? 塾にでも行っていたのかな」
少年は口を真一文字に結んだままで何回か瞬きを繰り返していたが、やがて「あの日は」と口を開いた。
「何っちゅうか――ちょっと、時間つぶしっちゅうか、散歩しとったっちゅうか」
かのんは「時間つぶし」と、彼の言葉を繰り返した。
「そうなんだ。それじゃあ、あちこち色んなところを歩いてたの?」
自分の中で言葉を探しているのかも知れないが、見つからないらしい。少年はただ、こっくりと頷いた。
「何となく歩いてるうちに、あの辺りまで行って、それで、鍵のかかってない自転車を見つけたんで、乗っちゃった。そういうことかな」
「そんな感じ、です」
「なるほど。それで、行ったのが黒崎駅の近くの、繁華街だよね? それには、理由とかあったのかな。目的とか」
今度は少年は、ちらりと隣の母親に目をやってからわずかに言い淀んだ後で「姉ちゃんに会いに」と答えた。少年に姉がいるということは、警察の調書にも書かれていない。
「お姉さんがいるの?」
「いる――今は、一緒に住んどらんけど」
「そうなのね。そのお姉さんが、黒崎の駅の辺りにいるの?」
「あの辺で働いとるっち」
「それで会いに行ったんだ。なるほど、なるほど。でも、それにしても、ちょっと遅くない?」
「姉ちゃん――キャバ嬢やけ」
「あ、そっか。キャバクラにお勤めなのね。お姉さんて、何歳?」
「十七」
思わず「それは、まずいんじゃないの」という言葉を呑み込んだ。少年の言葉が本当なら、彼の姉は労働基準法違反で補導の対象になるし、働かせている店も風営法違反になる。それにしても、姉は十七歳でキャバ嬢として働き、弟はその姉を探して夜更けに自転車を盗んだという、それだけ聞いても、彼らの家庭が尋常でないらしいことがうかがえる。
「それで、お姉さんとは会えた?」
田畑貴久は「会えんやった」と残念そうに肩をすくめ、もともと、姉が勤めている店の名前も知らないのだと言った。
「分からないで探してたの? それじゃあ、見つからなくても仕方がないよね」
うん、と頷く少年は、長いまつげに縁取られた瞳を伏せていたが、すぐに目を上げて、「そうよね」と仕方なさそうに微笑んだ。この年頃の子特有の反抗的な雰囲気が見られない。むしろ、健気な感じの少年だ。
「それで、今は、自転車を盗っちゃったことについては、どう思ってる?」
少年は「うーん」と天井を見上げ、それからまた口を真一文字に結んだ。
「――あのときは、そんなん何も考えとらんで、後から返しとけばいいやかっち思ったんやけど、今はやっぱ、悪かったなっち」
「そうだよね。人のものだもんね。貴久さん、自分の自転車はないの?」
「――前は持っとったんやけど、盗まれて、そんまんま見つからんのよね」
「そんなこともあったんだ。でも、それなら余計に、盗られた人の気持ちも分かるよね」
少年は、うん、と大きく頷いた。これなら何の問題もなさそうだ。彼はおそらく、もう同じ過ちは犯さないだろう。
「ところで貴久さんは、学校は?」
少年が、また困ったように「うーん」と言って首を傾げた。
「行ったり、行かんかったり」
「あんまり行ってないのかな。きっかけとかあったの? いじめとか」
少年は「何となく」としか言わなかった。そのとき、ずっと隣で静かにしていた母親が、ふいにごそごそとバッグからタオルハンカチを取り出して、それを目に当てた。
「全部――私が悪いんです」
母親の口から絞り出すような声が聞こえた。少年が唇を引き結んだまま、瞳に何とも言えない表情を浮かべている。
「駄目な母親で――この子は、私を心配して学校に行かんくなっちゃって」
ちらちらと、かのんの方を見ては、この場をどう取り繕おうかと慌てているらしい少年が痛ましく見えた。
「貴久さん、ちょっと外で待っててくれるかな。お母さんと少し、お話ししたいから」
かのんが促すと、貴久はまだ心配そうな顔をしていたが、素直に部屋を出て行った。二人きりになると、少年の母親はまたハンカチを目元に当てて、ほとんど嗚咽を洩らすように泣き始めた。
「私――もう、どうすればいいか分からんで」
「じゃあ、順番にうかがいますね」
家庭裁判所は、少年事件とともに「家事事件」というものを扱う。離婚、遺産相続をはじめとする家庭内のあらゆる問題を扱うのだ。小さな家裁では、調査官は少年事件と家事事件の両方を担当することもあるし、かのんも家事事件を扱った経験がある。だから、こういう女性の話を聴くことも、何も特別なことではなかった。
田畑貴久の母親、里奈は北九州市より南に位置する筑豊の小さな町で生まれ育ったのだそうだ。かつては炭鉱で賑わった土地だが、とうの昔に当時の賑わいは失われた。両親は早くに土地を捨てて出ていき、彼女は祖母の手で育てられたという。十六歳で妊娠したのを機に高校を中退、結婚して長女を出産、二年後には長男の貴久が生まれた。三つ違いだった夫は土木作業員だったが、長女が四歳になる前のある日、理由も告げずに家を出ていってしまった。後日、夫の親が離婚届だけを持ってやってきたのだそうだ。理由は「自由になりたい」と言っていたと聞かされた。祖母は既に他界しており、突然、幼い子を二人抱えて途方に暮れた里奈は、とにかく母子三人で生きていくために北九州に出て、風俗店で働くようになった。
「他に三人で生きてくだけのお金がもらえる仕事が見つからんで」
ほとんど昼夜逆転の生活だったが、家のことは幼い長女が懸命にやってくれていた。
「でも、私って、強い女やないけ――やけん、早く再婚したかったんですよね」
独りは辛い。独りは淋しい。だから何とかして頼れる人が欲しかった。だが、どの男とつき合っても、相手は常に里奈のことを風俗嬢としか見てくれなかった。結局は遊ばれただけだと分かり、失意に沈むごとに酒を覚え、煙草も吸うようになった。小学生になった長女は「給食が食べられるから」と毎日、学校に行くようになったが、貴久の方は小学校に上がってからも、日中、泥酔する母親のことを心配して、学校を休む日が増えていったらしい。里奈は、新しい男とつき合っては捨てられてを繰り返し、そうこうするうち、現在の交際相手と知り合った。「世界が変わると思った」と、里奈は語った。
「だって、あの人、つき合い始めてすぐに言ってくれたんです。『風俗なんかやめろ』っち。そんなこと言ってくれる男は初めてやった」
今度こそ本物の相手と出会ったと信じた。そこで里奈は、男の言葉を聞き入れて風俗の仕事をきっぱり辞めて、ビル清掃会社で働き始めたのだそうだ。知り合った当初、男は電気工事会社に勤めていた。
最初のうちこそ、男は子どもたちを食事に連れていってくれたり、休日には貴久とサッカーをして遊んだりと、優しくしてくれた。子どもたちも男になついた。このまま、男と再婚出来ればいいと、里奈は本気で考えるようになったという。だが、そんな日々は長く続かなかった。男が、仕事中に怪我をしたことでしばらく働けなくなり、そのまま勤め先を辞めたのだ。それからというもの、男の様子が変わっていった。昼間からパチンコに通うようになり、里奈のアパートを訪ねてくるたび、少しずつ金を無心するようにもなったのだそうだ。
「もとはと言えば私が悪いんです。私もパチンコが好きやったけん、一緒に行ったときには私がお金を出したりして、それが当たり前みたいになっちゃって」
里奈としては、当初は男が新しい職に就くまでの辛抱だという気持ちがあった。だが男は怪我が完治してからも、いつまでたっても仕事を探す気配がなく、そればかりか、酔うと次第に里奈に暴言を吐き、子どもたちにも当たり散らすようになっていった。そしてあるとき、里奈が仕事から帰ってくると、今まさに長女にのしかかって、乱暴しようとしているところだったという。それが、今から四カ月ほど前のことだそうだ。
「そのまま、娘はアパートを飛び出していきました。何回電話しても出らんし、LINEも見てくれてなくて、高校にも行っとらんみたいやし――もう、どうしたらいいんやろうと思っとったら、やっと一週間くらいしてからLINEが来たんですよね。働き口を見つけたけって。『あいつがうちに来る間は、帰らん』って」
今年で三十五になるかのんより、一つか二つ若いはずの里奈の瞳からは、次から次へと新しい涙がこぼれ落ちてくる。結局、貴久が夜更けの町をさまよい歩くようになったのも、原因はその男だということだ。時間にかまわず酔ってアパートにやってきては、里奈だけでなく貴久にもからみ、時として手をあげ、しかも、子どもがいる前でも里奈に卑猥な言葉を投げかけたり求めてきたりするから、多感な年頃の少年がいたたまれなくなるのも無理もない話だった。
貴久少年にしてみれば、二歳違いの姉は幼い頃から母親以上に自分の面倒を見てくれた人だ。だからこそ、少年は姉を求めたのだろう。だが姉は、働いている店の名前を伝えていなかった。ただ、黒崎にいること、何かあったらすぐに駆けつけるから心配するなと言っていたらしい。
「今度のことで裁判所から書類が届いたときも、あの人は『こんなもん捨てちまえ』とかっち言って、そのまま私からもぎ取って、放り出したんですよね――それでまた、喧嘩になりました。そのときに初めて、息子が言ったんです。あの人に」
「何て、言ったんですか?」
「『出てけ』って。それはもう、恐ろしい顔をして――今にも殴りかかりそうな勢いでした」
あんなに真っ直ぐな眼差しを持っている少年が、実はそれほどまでのストレスを抱えていることに、かのんは衝撃を受けた。今のうちに何とかしなければ、彼はさらに傷つき、やがてはもっと大きな罪を犯してしまいかねない。それにしてもこの問題は、もはや少年係の調査官がどうこう出来るものではない。手元の時計を見ると、予定していた面接時間はとうに過ぎている。
「それで、お母さんは、今後はどうなさるおつもりですか。今のままでいいと思っていますか?」
かのんの質問に、泣き疲れた顔をして、田畑里奈は大きくゆっくり首を横に振った。
「――あの人と、別れようと思います。いくら私でも、さすがに分かります。あの人とは一緒におられん――私たち全員、駄目になるって」
「私も、そう思います。今は、何よりもまず、お子さんのことを大切に考えた方がいいんじゃないでしょうか。お話をうかがったところ、上のお嬢さんも心配です。十七歳ということは、本当はまだキャバクラで働いていい年齢ではないんですよ」
母親は「そうなんですか」と怯えたような顔になった。
「出来るだけ早く、母子三人がもとの生活を取り戻せるように、やってみませんか」
とにかく一人で悩まずに、色々なところに頼ってもいいのではないかと言うと、田畑里奈は、自分などの相談に乗ってくれるところがあるのだろうかと、さらに不安そうな表情になった。かのんは「ありますとも」と頷いた。
「私も出来るだけのことはします。今の状況から、抜け出しましょう。何としても」
母親が落ち着いたところで、最後にもう一度、貴久少年を部屋に呼んだ。少年は、明らかに警戒した様子で、おずおずと席につく。
「貴久さん、これから、お母さんの力になってあげてくれないかな」
少年は、泣き腫らした顔の母親を見てから、不安そうな顔になる。
「色々とお話を聞いたけど、お母さん、たくさん悲しい思いをしてるじゃない? だから何とかして、抜け出そう」
「抜け出す?」
「そう。これ以上、悲しい思いをしなくてすむように。だから貴久さんにも、また家族が三人で暮らせるように、手伝ってほしいんだ」
少年はまつげの長い目を何度も瞬かせ、考える表情になる。
「やけど、僕が出来ることっち――」
「まずは、お母さんに心配かけないことだよね。もう二度と、人のものを盗ったりしないで、それから、出来れば学校にも行って」
少しして、少年は「でも」と自信のなさそうな顔になった。
「小学校、あんまり行っとらんけ、勉強、分からんし」
「ああ、そうか――そのことも考えよう。きっと何とかなるよ」
すると、少年の顔がぱっと明るくなった。その笑顔があれば、この家は大丈夫だと思えるような笑顔だった。
モデルとかアイドルとかにもなれそうなんだけど。
ちらりと、そんなことも考えながら、とにかく出来るだけ早く、自分も動くようにする、だから貴久少年には、ぜひとも母親の支えになってあげて欲しいと念を押して、面接を終えることにした。
まさか、こんなことになるなんて。
思っていたのと全然違う展開になってしまった。まずは児童相談所と婦人保護施設に連絡を入れるのがいいだろうか、いずれにせよ勝又主任に相談した上で、一日も早く手を打たなければ、長女まで補導されては大変だなどと次々に考えながら、せかせかした気持ちで調査官室に戻る。すると、隣の席の鈴川さんが、待ってましたとばかり、つつっ、と椅子ごと近づいてきた。
「あ、鈴川さん、あのですね――」
「ちょっと、かのんちゃん、さっき警察から電話があったのよ」
まずは、かのんから田畑母子の件を相談したかったのに、鈴川さんはいつになく意気込んだ顔つきをしている。出鼻を挫かれた気分で首を傾げると、鈴川さんは「ですよね、主任!」と、勝又主任を呼んだ。すると主任までが「そうそう」と勢いづいて席から立ち上がって近づいてきた。
「あったんだ、警察から。庵原さんに」
「私に、ですか?」
主任は鈴川さんの隣まで来て、いかにも何か言いたげな顔つきになっている。だがその前に、鈴川さんが口を開いた。
「先週、かのんちゃんが面接した少年、朝倉陽太朗ね」
「朝倉――ああ、万引きの」
主任が腕組みをして眉根を寄せた。
「また逮捕されたんだそうだ」
「――えっ?」
先週、面接したばかりの少年の顔が思い浮かんだ。頭の中で一杯に膨らんでいた田畑母子の問題が、きゅっと押しやられる。かのんは頭が混乱しそうになりながら、とにかく鈴川さんと主任を交互に見た。
「何をやったんだと思う?」
「――また、万引きとか? それとも、もっと派手な――」
「ど派手も、ど派手ですよね、主任」
鈴川さんが主任を見上げる。主任は、今度は口もとを変な格好にねじ曲げながら、いつになく重々しく頷いた。
「派手なんていうものじゃないわなあ。何しろ、暴行傷害だ。それも、相手は肋骨二本と腕まで骨折して入院」
かのんは「あの子が?」と、絶句しそうになった。鈴川さんが、さらに顔を近づけてくる。
「誰をやったんだと思う?」
「例の、つるんでた友だちとか」
「違うちがう。あのね。は、は、お、や」
「――え」
「家の中で大暴れしたらしいわ。それで、ボコボコにされた母親が、自分で一一〇番したんだって。『助けて、殺される』って」
衝撃と同時に、心のどこかで「やっぱり」という思いが浮かんだ。あのときの少年の苛立ち、母親の様子が思い出される。
「要するに、この間の万引きが、危険水域だったのね」
鈴川さんが、やれやれといった表情で言った。
「――ということは、私の面接が駄目だったんでしょうか」
「いや、本当の問題が露呈するまでには、それなりの時間がかかるもんだ。あそこが危険水域だとしたら、その後、決壊したんだろう、少年の中で、何かが」
主任は肩をすくめながらゆっくりと自分のデスクに戻っていこうとする。かのんは慌てて「主任!」とその背中を追いかけた。
「私に担当させてください!」
「それを決めるのは、谷本判事だからなあ」
「でも、何とか!」
もう一度、あらためてあの少年と向き合いたい。母親とも話をしなければならない。そのとき、「それはそうと」と鈴川さんの声が聞こえた。
「今の面接、いやに長かったじゃない? 何か、大変なことでもあった?」
しまった、そのことがあるのだ。かのんは反射的に自分の頭を抱えるようにして「ああっ、もうっ!」と声を上げてしまった。
「それ、そのことなんですっ! そっちから動かなきゃいけないのにっ!」
だが、何から話したらいいものやら、もう頭がパンクしそうだ。淡々と処理すればいいはずだった二つの在宅事件が、まさかこんな展開を見せようとは、考えもしなかった。そのとき、ちょうど外から帰ってきたらしい若月くんの「たい焼き買ってきましたよぉ」というのんきな声が響いた。かのんは、飛び上がるようにして若月くんに駆け寄った。
「食べたい! ちょうだい!」
赤ちゃんアザラシ顔の彼が、「熱いですよぉ」と、にっこりと笑った。
「自転車泥棒」 了
続きは本書でお楽しみください。