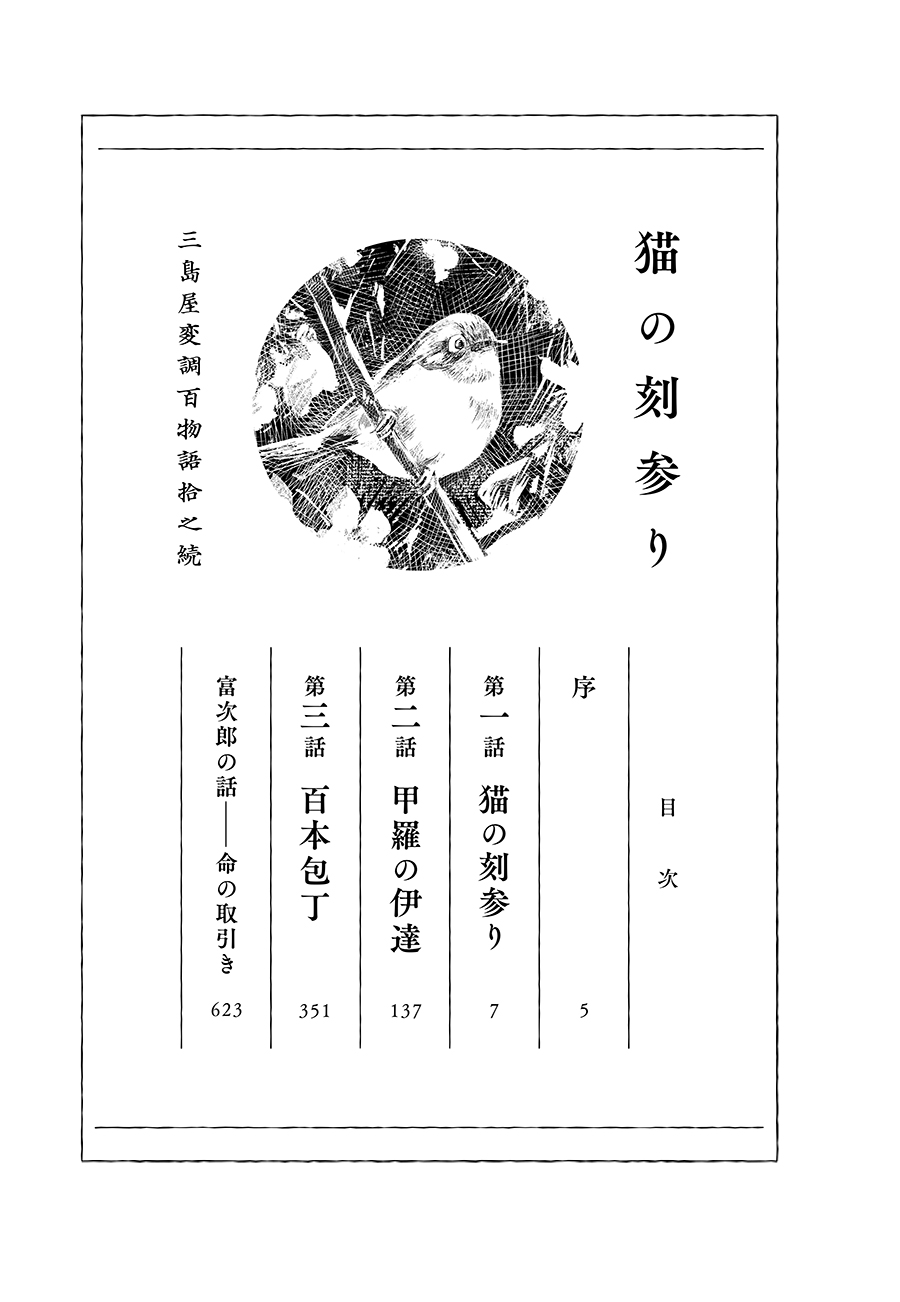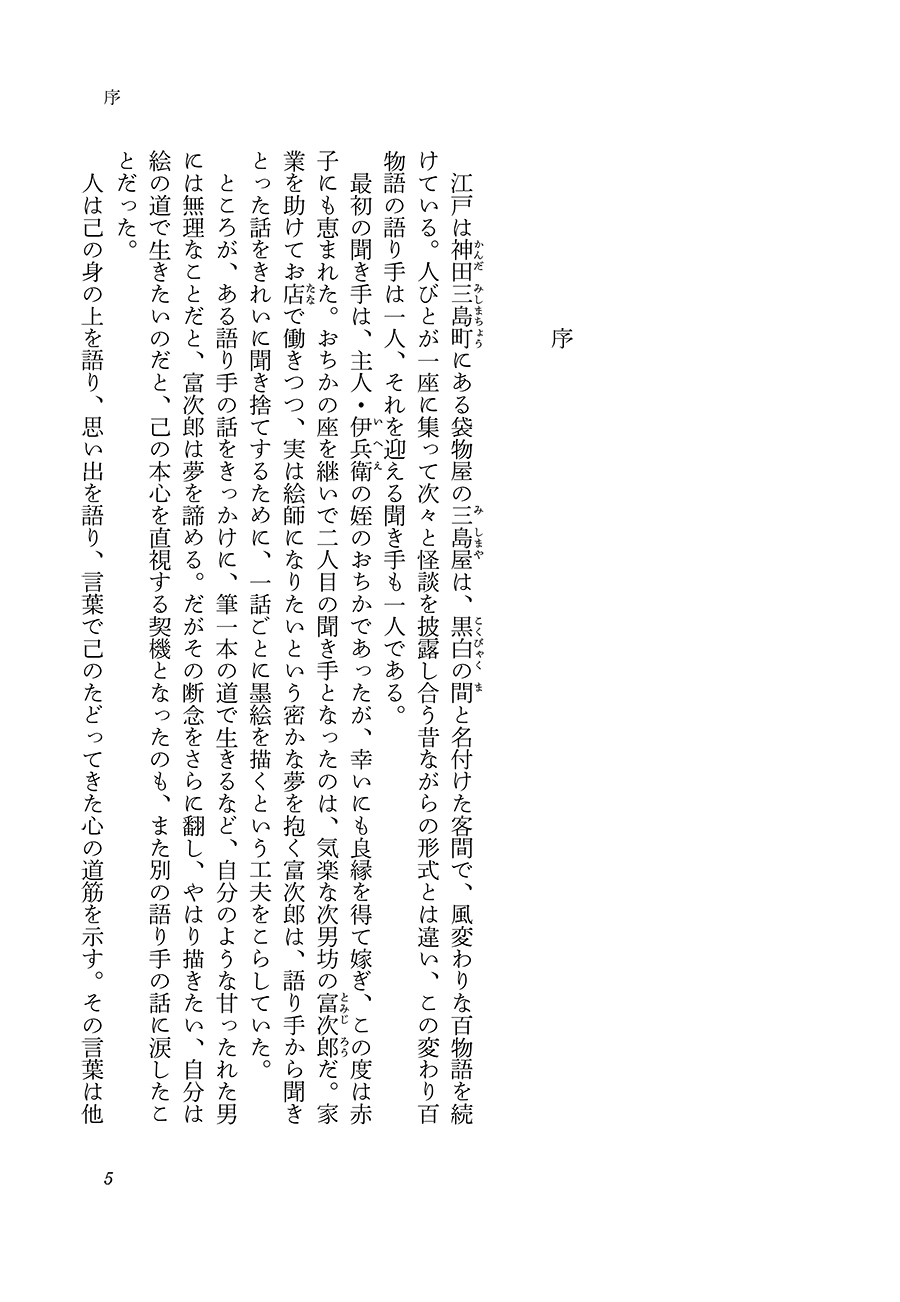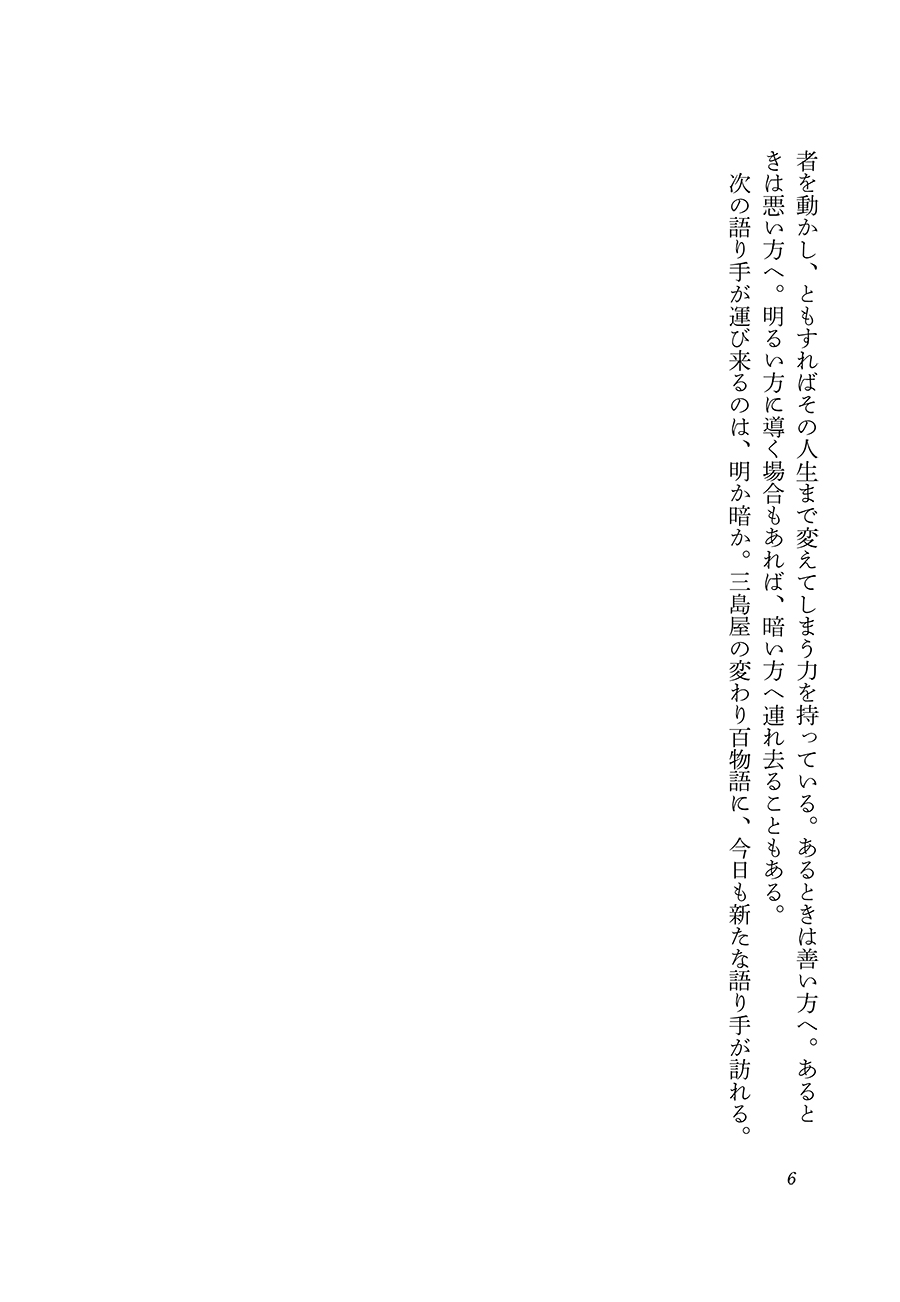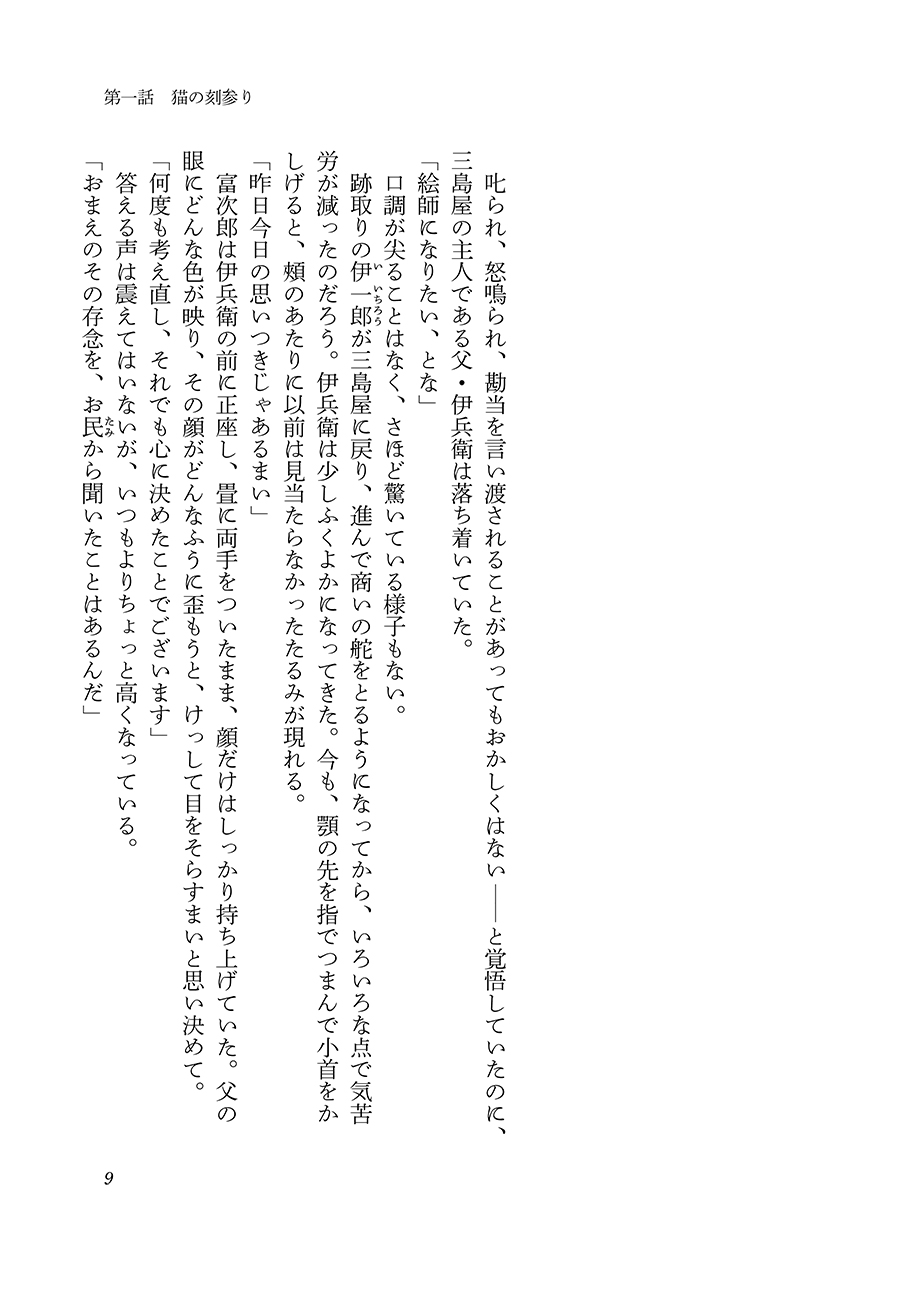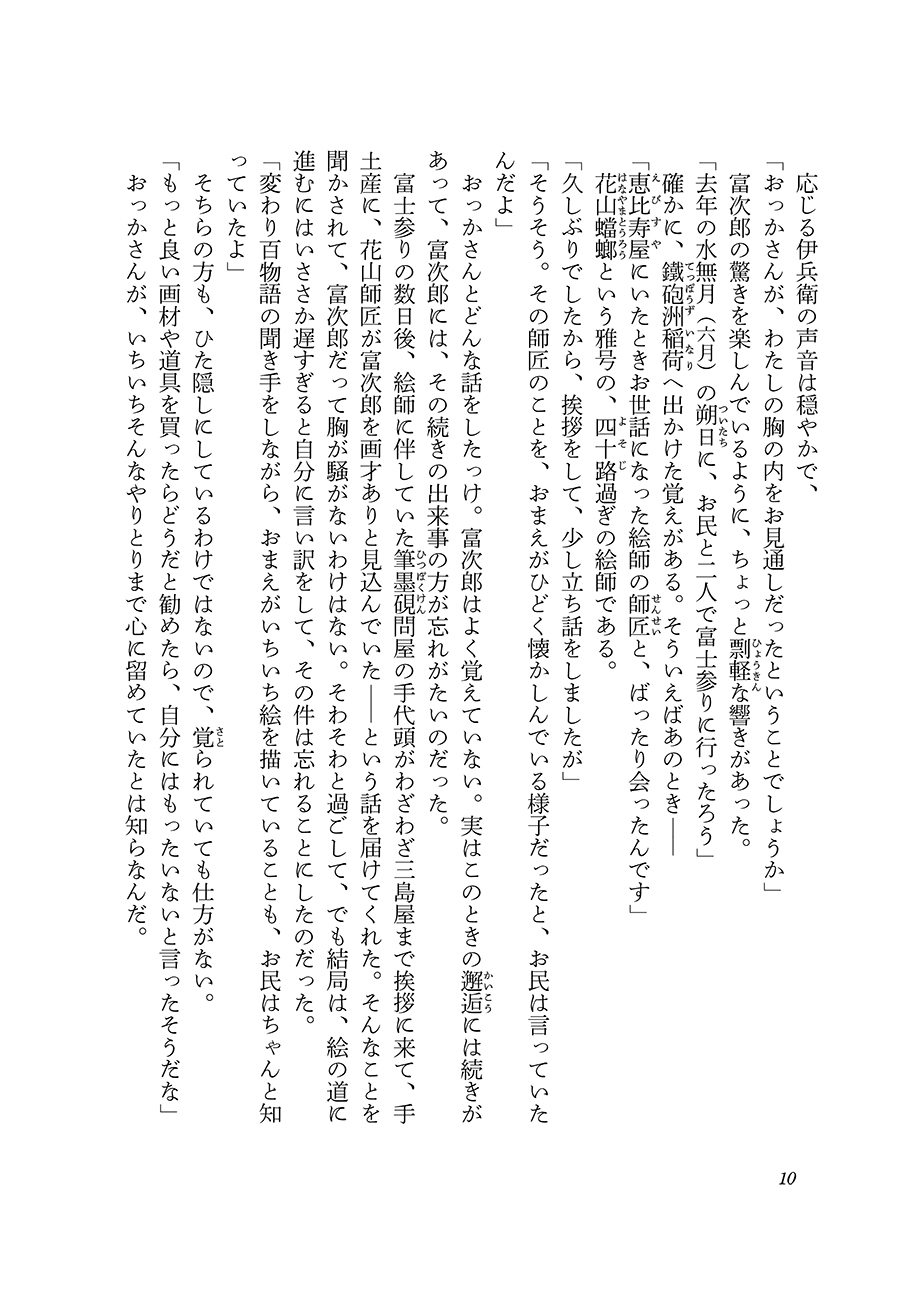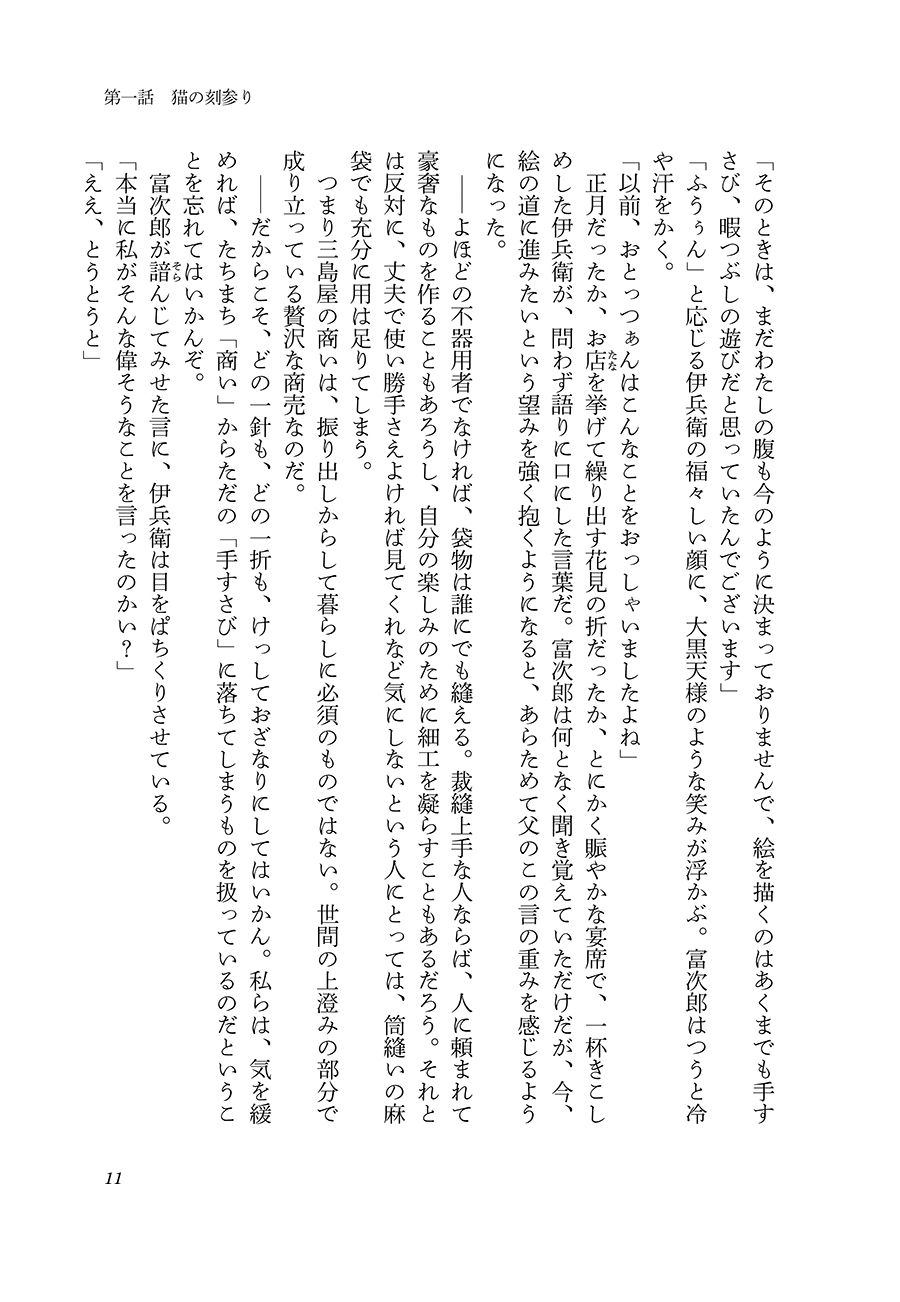序
江戸は
最初の聞き手は、主人・
ところが、ある語り手の話をきっかけに、筆一本の道で生きるなど、自分のような甘ったれた男には無理なことだと、富次郎は夢を諦める。だがその断念をさらに翻し、やはり描きたい、自分は絵の道で生きたいのだと、己の本心を直視する契機となったのも、また別の語り手の話に涙したことだった。
人は己の身の上を語り、思い出を語り、言葉で己のたどってきた心の道筋を示す。その言葉は他者を動かし、ともすればその人生まで変えてしまう力を持っている。あるときは善い方へ。あるときは悪い方へ。明るい方に導く場合もあれば、暗い方へ連れ去ることもある。
次の語り手が運び来るのは、明か暗か。三島屋の変わり百物語に、今日も新たな語り手が訪れる。
第一話 猫の刻参り
叱られ、怒鳴られ、勘当を言い渡されることがあってもおかしくはない――と覚悟していたのに、三島屋の主人である父・伊兵衛は落ち着いていた。
「絵師になりたい、とな」
口調が尖ることはなく、さほど驚いている様子もない。
跡取りの
「昨日今日の思いつきじゃあるまい」
富次郎は伊兵衛の前に正座し、畳に両手をついたまま、顔だけはしっかり持ち上げていた。父の眼にどんな色が映り、その顔がどんなふうに歪もうと、けっして目をそらすまいと思い決めて。
「何度も考え直し、それでも心に決めたことでございます」
答える声は震えてはいないが、いつもよりちょっと高くなっている。
「おまえのその存念を、お
応じる伊兵衛の声音は穏やかで、
「おっかさんが、わたしの胸の内をお見通しだったということでしょうか」
富次郎の驚きを楽しんでいるように、ちょっと
「去年の水無月(六月)の
確かに、
「
「久しぶりでしたから、挨拶をして、少し立ち話をしましたが」
「そうそう。その師匠のことを、おまえがひどく懐かしんでいる様子だったと、お民は言っていたんだよ」
おっかさんとどんな話をしたっけ。富次郎はよく覚えていない。実はこのときの
富士参りの数日後、絵師に伴していた
「変わり百物語の聞き手をしながら、おまえがいちいち絵を描いていることも、お民はちゃんと知っていたよ」
そちらの方も、ひた隠しにしているわけではないので、
「もっと良い画材や道具を買ったらどうだと勧めたら、自分にはもったいないと言ったそうだな」
おっかさんが、いちいちそんなやりとりまで心に留めていたとは知らなんだ。
「そのときは、まだわたしの腹も今のように決まっておりませんで、絵を描くのはあくまでも手すさび、暇つぶしの遊びだと思っていたんでございます」
「ふうぅん」と応じる伊兵衛の福々しい顔に、大黒天様のような笑みが浮かぶ。富次郎はつうと冷や汗をかく。
「以前、おとっつぁんはこんなことをおっしゃいましたよね」
正月だったか、お
――よほどの不器用者でなければ、袋物は誰にでも縫える。裁縫上手な人ならば、人に頼まれて豪奢なものを作ることもあろうし、自分の楽しみのために細工を凝らすこともあるだろう。それとは反対に、丈夫で使い勝手さえよければ見てくれなど気にしないという人にとっては、筒縫いの麻袋でも充分に用は足りてしまう。
つまり三島屋の商いは、振り出しからして暮らしに必須のものではない。世間の上澄みの部分で成り立っている贅沢な商売なのだ。
――だからこそ、どの一針も、どの一折も、けっしておざなりにしてはいかん。私らは、気を緩めれば、たちまち「商い」からただの「手すさび」に落ちてしまうものを扱っているのだということを忘れてはいかんぞ。
富次郎が
「本当に私がそんな偉そうなことを言ったのかい?」
「ええ、とうとうと」
「よっぽど酔っ払っていたんだなあ」
今ごろになって照れられても困る。
「おとっつぁん」
呼びかけて、富次郎は畳に指を揃え直す。
「日用品の袋物でさえそうであるならば、わたしが進みたいと望む絵の道など、もっと贅沢な遊びの道でございます」
多くの人びとが、趣味で絵を描く。富次郎が商いの修業で奉公していた恵比寿屋の主人もそうだった。けっして巧くはなかったし、蟷螂師匠から真面目に学ぶ気もなさそうだったが、短冊や扇子にちょいちょいと季節の草花を描いて芸者を喜ばすことぐらいは充分にできて、ご当人もそれで満足していた。
「他人様が遊興ですることを技として磨き、その技で世渡りしようという、それがどんなに図々しいことであるか、わたしなりに
だが、それでも、富次郎は絵筆と共に生きていきたい。
「どうぞ、わたしが蟷螂師匠に弟子入りすることをお許しください。このとおり、お願い申し上げます」
蛙みたいにぺったんこになる富次郎の前で、伊兵衛はまた目をぱちくりさせる。初めは本当に面食らっていたのだが、だんだんとこの場の雰囲気が面白くなってきて、わざとぱちくりを続けながら考えていた。
――この子もようやく本気を出したか。
長男の伊一郎は二十五歳、次男坊のこの富次郎は二十三歳。どちらももう「子」ではない。だが今は敢えて子供扱いしたいのだ。
伊一郎が万事に賢く、少し冷淡なところがあり、そのくせ人好きするという得な性分であることは、子供のころからわかっていた。手習所の師匠には「どんな大物になるやら空恐ろしい」と言われたし、得意先の一つである某旗本の養子に請われたこともある。商いの修業に行かせた小物商の
当の本人は、長男として「三島屋を継ぐ」という生き方に、一度も迷う様子がない。それも、伊兵衛とお民が築き上げたお店を守るだけではなく、伊一郎にはもっと大きな野心があるらしい。
もう三十数年も前のこと、夫婦で縫った袋物を笹竹に吊して振り売りを始めたとき、
――いつかは江戸市中で三番目に有名な袋物屋にしよう。
伊兵衛とお民はそういう夢を語っていた。三番目というのは、名店として知られている二軒の袋物屋、
真面目に商い、意匠に工夫を重ね、丁寧な縫い仕事を重ねて、今や三島屋は確かに市中で三番目の袋物屋の座にある。贅沢な古典意匠の多い越川や丸角よりも、三島屋の軽快な品柄が好ましいと
ところが跡継ぎの伊一郎は、そういう両親とはまったく違う夢を抱いている節がある。まだはっきりと言葉で説明してもらったことはないが、伊一郎は、三島屋の将来を先達の名店と比べてどうこう測る――という考え方そのものを捨てているようだ。まったく別の物差しを持って、三島屋の二代目として立とうとしている。ただ、単純に商売替えするということではなさそうなのが、また推し量りにくいところであった。
長男の野心は頼もしくもあるが、危なっかしくも感じられる。伊兵衛とお民は、伊一郎に向かって、これまで自分たちが歩んできた道筋を振り返り、その経験から得た学びをもとにして語ることしかできない。ここまで夫婦で築いてきた身代を潰し、お店のために身を粉にして働いてくれてきた奉公人たち、職人たちや縫い子たちを路頭に迷わせることがあってはならない、それだけは駄目だと意見することしかできない。
親なんて無力なものだと、ふと苦笑いを噛みしめることもある。だがこれは、跡取り息子が放蕩ばっかりしていて、どれほど説教してもどうしようもない――という嘆きではない。それとは逆の贅沢な悩みだ。思えば、伊一郎は子供のころから
伊兵衛とお民にとって、伊一郎はとんびが生んだ鷹だ。幸いに思う一方で、寂しさもあった。それを埋め合わせてくれるのが、次男の富次郎だった。歳は二つしか違わないが、いかにも弟らしい甘ったれのところがある。調子のいいところ、良い意味でまわりの人びとの顔色に敏感で、場の取り持ちが上手いこと、優しさと思いやりと、手間を惜しまず自分で動くまめなところも。
伊一郎は多くの人に熱心に好かれる一方で、ごく稀ではあるが、合わぬ人にはとことん疎まれたり避けられたりすることがある。富次郎は熱っぽく好かれることはないが、水のように誰にでも添える。水のように、強い匂いも味もない。相手に気を使わせぬ気配りと気遣いを身に着けている。
伊兵衛とお民が案じていたのも、まさにその点だった。あまりにも気配りに長けてしまったせいで、富次郎には彼自身の強い意志や希望がないのではないか。背骨となる気概や野心が育っていないのではないか。折に触れて、夫婦は小声で話し合ってきた。
幼いころから、あれがほしい、こうしたいと我を張る
――兄さんはどっちがいいの? おいらは、残った方でいいよ。
優しいし、控えめだ。それは長所ではある。だが、「自分から物事を選択しない、決定しない」というのは、胆力がない意気地なしの生き方でもある。
仮に富次郎が心の底から兄の右腕になりたい、伊一郎が目指す二代目三島屋の補佐役になりたいと願っているのだとしても、真の補佐役というものにもまた相応の器が要る。そして意気地なしはそんな器にはなり得ない。
――好きな娘さんでもできたら、富次郎にも我が出てくるかもしれないわ。
お民はそんなことを言っていたが、伊兵衛はその線には期待を抱いたことがない。
この
そういう次男坊である。いい奴だ。
――それじゃ毒にも薬にもならんのに。
その富次郎が、ようやく我を出してきた。親の商いを継がずに、絵師になりたいと。
先ほどから、やれ嬉しやと笑いがこみ上げてきそうになるのを、伊兵衛は苦労して噛み殺している。声音に喜色が混じってしまいそうで、なかなかしゃべることも難しい。喉声で唸っていると、駆込み訴えする
「おとっつぁん、どうなさいました?」
膝をにじらせて、富次郎が寄ってくる。その慌てぶりも可笑しくて、伊兵衛はますます笑いそうになり、何とか場を立て直そうと思案をめぐらせると、
「ひ、ひ、ひ」
「え? 肘がどうかしましたか」
「肘じゃない。ひ、ひゃく」
とうとう噴き出してしまいながら、伊兵衛は勢いよく問いかけた。
「百物語の聞き手はどうするつもりだ?」
今度は、富次郎が目をぱちくりさせる番であった。
「お、おとっつぁん」
この期に及んで、真っ先に変わり百物語のことを案ずるのか。
もちろん、富次郎にとって、黒白の間の聞き手であることは大きな意味があったから、絵師になろうという修練の道を選び、その大切な務めから離れざるを得なくなってしまうことについては、深く思い悩んでいた。
だが、伊兵衛もそれを心配するとは……。
――まさか思い入れがあったのか?
正直、おちかのために変わり百物語を始めた当時ならばいざ知らず、今の三島屋では、変わり百物語に熱を抱いているのは、富次郎自身と
「おまえの腹づもりとしては、蟷螂師匠に弟子入りするというのは、うちから出ていって、師匠の家に住み込んで、内弟子として働きながら絵を習うということなんだろう?」
問われて、富次郎は大きくうなずいた。
「だって、わたしは指南料を払うことができませんから、師匠のところで下働きするよりほかに
「みんな? 通いじゃ本気にならないと、誰が決めたんだ」
え。戸惑う富次郎の前で悠々と懐手をすると、伊兵衛はさらに問いかけてきた。「そもそも、どうしておまえは師匠に指南料を払うことができんのだ?」
え。え。え。大丈夫かな、おとっつぁん。そんなの当たり前の話じゃないか。
「絵の修業に打ち込めば、三島屋の商いを手伝うことができなくなります。お店の役に立たぬわたしは、これまでのように小遣いをもらうことも、衣食を面倒見ていただくこともできません」
「だったら、せめて変わり百物語の聞き手だけでも務めて、その分の給金をもらおうとは思わんのか」
打ち返すように真っ直ぐな伊兵衛の問いかけに、富次郎は、家にいながら
――このやりとり、おいらの都合のいい夢じゃないよなあ。
神無月(十月)二十日の恵比寿講をにぎやかに済ませ(一昨年はまだおちかがいたんだよねえと、皆と懐かしく語り合った)、あと数日で暦がめくれて霜月(十一月)が始まる。江戸の町に冬が訪れるのだ。伊兵衛の居室の長火鉢では炭火が燃え、五徳に載せた南部鉄瓶の口からほのかな湯気が立ちのぼっている。
心休まる六畳間。伊兵衛の居室は、主の人柄をそのまま映している。これまでずっと、お店の主人としても父親としても、どんなときでも
そういう父だとわかってはいたけれど、今度ばかりは話が別だから、富次郎は覚悟を固めていたのだ。兄を助けて三島屋をますます盛り立てるべき立場の自分が、いつ実を結ぶかわからぬ、一生浮かばれることなどないかもしれぬ画業の道を選ぼうとするなんて、お店と家族に対する裏切りだ。叱られぬわけがないし、父に泣かれてしまうかもしれない。
――それなのに。
「どうして」
富次郎は小さく呟き、自分が先に泣きそうになっていることに気づいて、慌てて拳骨を目元にあてた。
「おとっつぁんは、そんな甘いことを言ってくださるんでしょう。わたしはとんだ放蕩息子でございますよ。三島屋の将来に汚点をつける、できそこないでございますよ」
すると伊兵衛は言った。「そうとは限らない。おまえが絵師として名を揚げて、一代で財をなすことだってあるかもしれん」
鉄瓶の湯気が、伊兵衛の勢いのいい鼻息でふうと流された。
「……そんな……大甘すぎます」
富次郎はいよいよ涙が出てきた。
「私はむしろ、おまえがどうして悪い方にばかり考えるのか不思議でしょうがない」
自分の才に
「先回りして良くないことばかり言っておけば、本当に失敗したときに、大恥をかかずに済むとでも思っているのか」
どきりとした。富次郎にその了見はない。ないと思う。ないはずだ。自分の胸に問うてみると、手が震え始めた。
「私は袋物の商いのことしか知らんが、腕一本で何かを成そうというならば、失敗して恥をかくのも、金に困るのも、なかなか一人前になれずに世間で肩身が狭いのも、全て当たり前のことだ。その当たり前のことから逃げようとするのなら、おまえは絵師どころか何者にもなれないよ」
厳しい口調ではない。叱ってもいない。いつもの伊兵衛の声音だ。それでも富次郎は身体まで震えが回ってきて、膝の上に拳をおろしてうなだれた。
「いや、順番が違うな。こういう話はあとでいいんだ」
まずは変わり百物語のことなんだ――と、伊兵衛は懐手を解いて身を乗り出した。
「おまえ、
富次郎は蚊の鳴くような声で答えた。「おとっつぁんのお許しをいただけるならば、お勝に託すか……それが駄目ならば」
「取り止めにするしかないよな」
富次郎はがっくりと頭を下げた。
「おまえの他には、進んで聞き手を務めようという者は見当たらない」
「はい」
伊兵衛もお民も商いがいちばんだし、
「兄さんは、おちかが嫁ぐときに、変わり百物語など止めてしまえと言っていたくらいですから」
「うむ、あいつの存念は私も知っている」
顎の先をつまみ、伊兵衛はちょっと苦い顔をした。富次郎にとっては意外な表情だった。
「まあ、そっちは伊一郎の問題だから、おまえが案じることじゃない」
言って、伊兵衛は短い鼻息を吐いた。
「富次郎。おまえは望んで変わり百物語の聞き手を引き継いだはずだよな」
うなだれたまま、富次郎は大きくうなずいた。「最初は面白半分で、おちかが聞き手を務めているところを見物していたんですが、これはただ面白いだけのことではない、語り手の一生分の重みが詰まったお話を受け止めるのだと気がつくと」
恐ろしくもあり、楽しくもあり、学ぶことが多々あって、やりがいもある。ぜひ、自分が継ぎたいと思ったのだ。
「なのに今般は、それほど腹を決めて引き受けたことを諦めて……いや、途中で放り出して、画業に打ち込もうという」
放り出すとは人聞きが悪い。だけど、そういうことになるのか。言葉だけ好いように言い換えても、身勝手なふるまいは変わらない。
伊兵衛は思いっきり顔を歪め、口をへの字にひん曲げて、言った。
「私も浅学で知らなかったのだが、百物語には禁忌というものがあるそうだ」
富次郎は顔を上げて、父親の顔をそうっと窺い見た。「百話まで語ってはいけないのでございましょう?」
百話まで満たしてしまうと、その場で恐ろしい怪異が起こるから、九十九話で止めなければならぬ。
「それもそうだが、もう一つある」
伊兵衛は口の端から押し殺したような声を出した。
「ひとたび始めたからには、九十九話まで満たさずに止めてはいけない。さもないと、百話まで語ってしまったときよりもさらに恐ろしい凶事を招いてしまう、と」
え。そっちの禁忌は初耳である。
「おちかからもお勝からも、聞いたことがございませんが……」
歪んだ表情を保ったまま、伊兵衛はふんと鼻を鳴らし、ちょっと
「事の始めに、おちかのために変わり百物語の語り手を
となると、伊兵衛は最初から、一度百物語を始めてしまったら、半端に止めることはできぬと承知していたということになる。しかし、それでは少々割り切れぬ気がする富次郎だった。
――だって、そんなにもその禁忌を気にしていたのなら、おちかが瓢箪古堂に嫁ぐと決まったとき、誰か引き継ぐ者を決めておかないとまずいって、真っ先におとっつぁんが騒いでもよさそうなものだ。
ちょうど二年くらい前のことになるが、実際にはそんな騒ぎはなかった。とっとと止めてしまえと言い切る伊一郎ほど冷たくはなかったが、伊兵衛はおちかの祝い事で頭がいっぱいで、変わり百物語のことなどは、あとで何とでもやりようがあると、軽く考えている様子だった。富次郎はそれをよく覚えている。
――おとっつぁん、調子のいい作り話をしてるんじゃないの?
だからこそ、今はことさらに怖い表情をつくっているのじゃないのか。
富次郎はじいっと父の顔を見た。見つめられて、伊兵衛のへの字の口がゆるんできた。
「な、何だ、その顔は」
「おとっつぁんこそ」
喧嘩ではないから、睨み合っているのではない。にらめっこだ。どっちの眼力が強いか、勝負勝負。
「……喉が渇いた。熱いお茶を淹れてくれ」
先に目をそらしたのは伊兵衛の方だった。富次郎は素直に応じて、てきぱきと動いた。ここに備え付けの茶道具は、お民がどこかで見つけてきた
「手慣れているな」
茶筒から茶葉をすくい出し、急須に入れ、少し冷ました
――茶葉の埃を落とすんでございます。
客用の上等な煎茶はさておき、三島屋の人びとが好んで喫する番茶や棒茶、ほうじ茶では、こうするとえぐみが抜けるという。
「変わり百物語の語り手にも、おまえはこうやってお茶を淹れるのだろう」
「語り続けていると、喉が渇きますから」
聴き入っている富次郎も、手に汗を握り、心の臓がばくばくして喉が渇くことが多い。
「茶菓子も、毎度いろいろ趣向を考えて、わざわざ自分で買いに行くこともあるそうじゃないか」
「そんな話、誰がおとっつぁんの耳に入れているんですか」
「お勝と
新太は小僧、八十助は大番頭だ。
――小旦那さまが、黒白の間のお客様のために用意するお菓子は、いつもとびっきり旨いんだ!
――市中で評判のものだけでなく、これから評判になるものを見つける目もお持ちなんでございますわ。
この居室の茶筒に入っていたのは、濃い深緑色の大ぶりな茶葉だった。淹れると、野生の香りがたった。それを湯飲みにたっぷり満たし、伊兵衛の前に置く。
「いただきものの茶葉なんだ」
熱そうに指を立てて湯飲みをつかみながら、伊兵衛は言った。
「私が袋物の振り売りをしていたころからの付き合いのお茶屋さん、
お上の囚獄、通称・伝馬町の牢屋敷のある町筋である。
「昔、牢獄に繋がれている囚人たちの慰めに、せめていい茶葉を焙じる香りをかがせてやろうと、毎日大団扇で煙を送っていたら、騒々しいとお
肝を縮めた筋のいい仲卸問屋から取引きを切られてしまい、
「そして見つけたのがこの茶葉なのさ。
花川戸は大きな船着場が有り、江戸市中の水路を使った往来の要所の一つだ。さほどの田舎ではないのに、こんなにも野趣に富んだ茶葉が育つとは。
「ついでに言うと、牢屋敷のお役人にこっぴどく叱られて、大松屋さんが表戸を閉じて謹慎しているとき、私は串団子を山ほど買い込んで、差し入れに行ったよ」
大松屋は涙して喜び、お礼にと、伊兵衛が今も使っている茶盆をくれたのだという。
「素朴を通り越して、パッとしない品だと思うだろ? ところがどっこい、ざっと三十年使い込んだら、めったにない名品になるんだそうだ」
あと十年くらいかな、と楽しそうに呟き、熱い茶をすする父の姿に、富次郎の波立った心も静まってきた。
「……これまで聞いたことのないお話です」
「語ったことがないからね。今だって語るつもりはなかった。ひょっこり口から出てきてしまったんだ」
言って、伊兵衛はしげしげと富次郎の顔を見た。
「おまえは、いい聞き手なのさ」
やめてくださいよ。また胸が詰まる。だが、伊兵衛は穏やかな声音で続けた。
「商いだって絵の修業だって、道は一つじゃない。工夫次第なんだ。世間様がよくそうしているやり方に
独自の道を行こうじゃないか。
「おまえは変わり百物語を続ける。お店の仕事もできる限り手伝う。うちからは、おまえのその働きに見合う給金を払う。それで蟷螂師匠に指南料を払い、画材を買って、好きなだけ修業すればいい」
これまでよりも、うんと忙しい暮らしになる。画業の修業に励むには、文字通り、寝る間を惜しんで描くしかなくなるだろう。
「三島屋からはこの条件でのみ師匠につくことを許す、これが呑めぬなら勘当だと言い渡されたと、蟷螂師匠に相談してごらん。もともと、恵比寿屋の旦那に出稽古してらしたような先生なんだ。駄目だとは言うまいよ」
ここで伊兵衛はもう一度、へのへのもへじの落書きみたいに、口をへの字に曲げた。
「もしも師匠が、そんな甘い覚悟の弟子はとれませんと言ったなら、三島屋は師匠のおかげさまで変わり百物語が断たれ、お店もろとも一家が滅びます、ありがたくお恨み申し上げますと、私がご挨拶に伺うよ」
うへえ。それはどうかご勘弁ください!
続きは本書でお楽しみください。