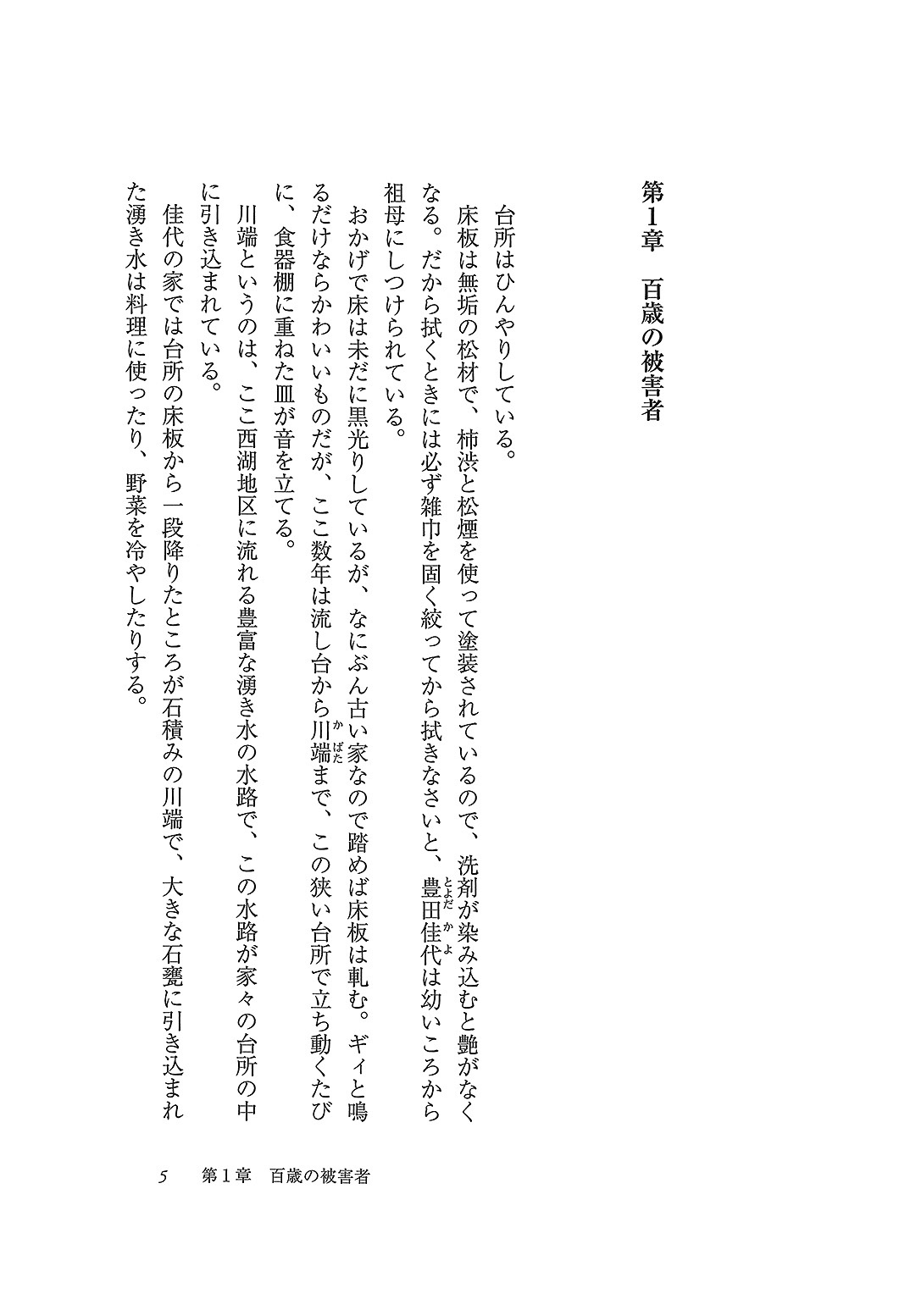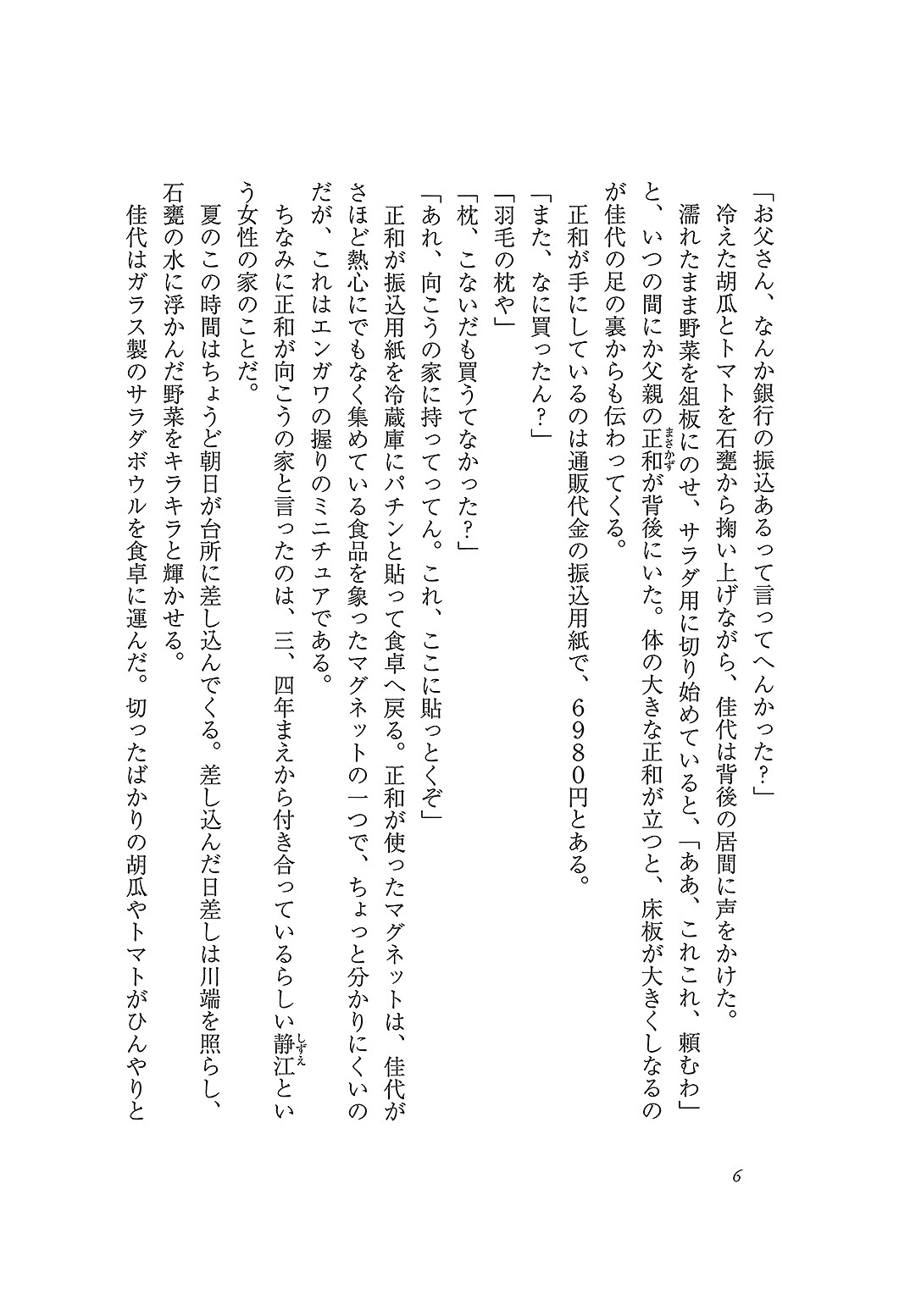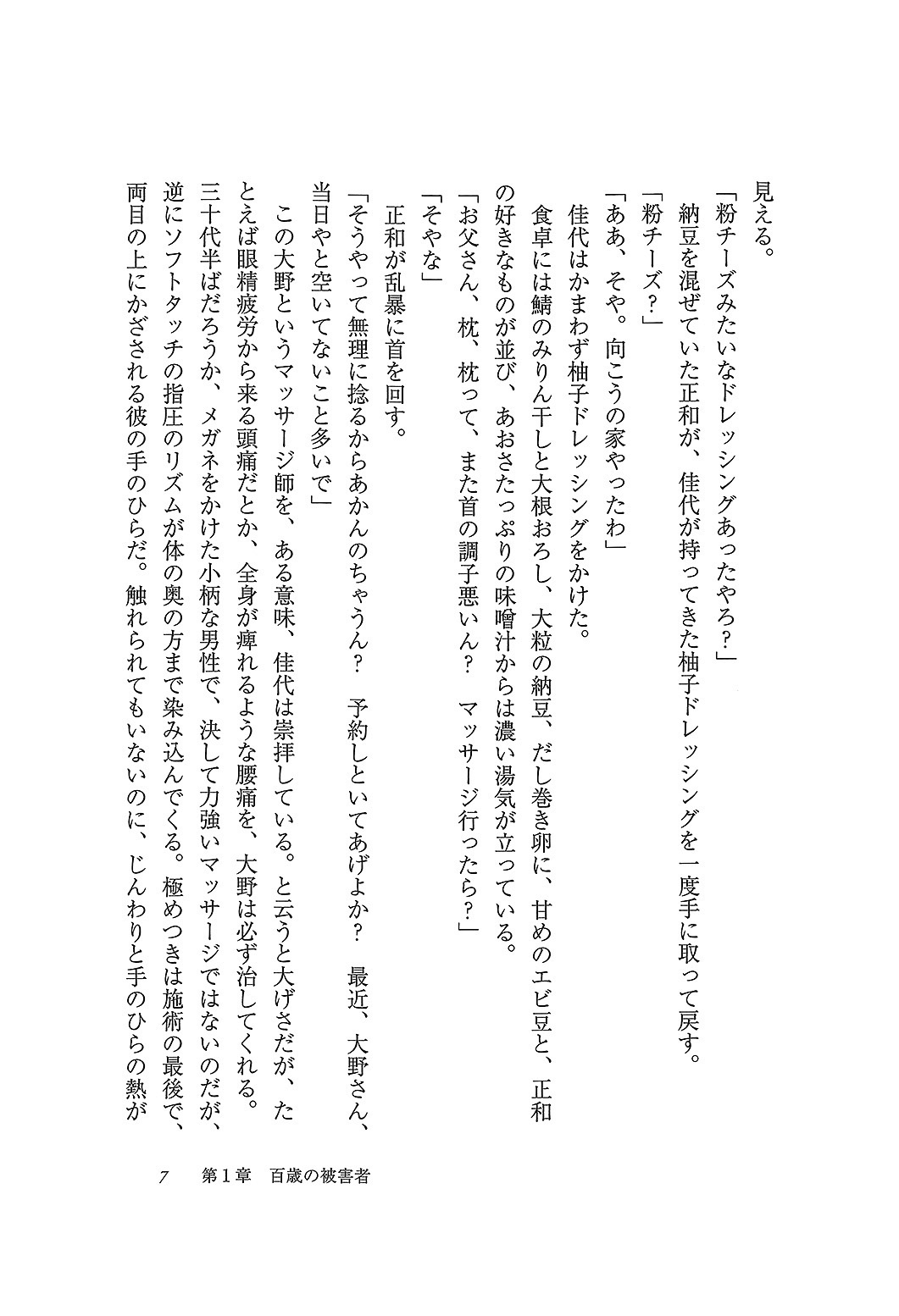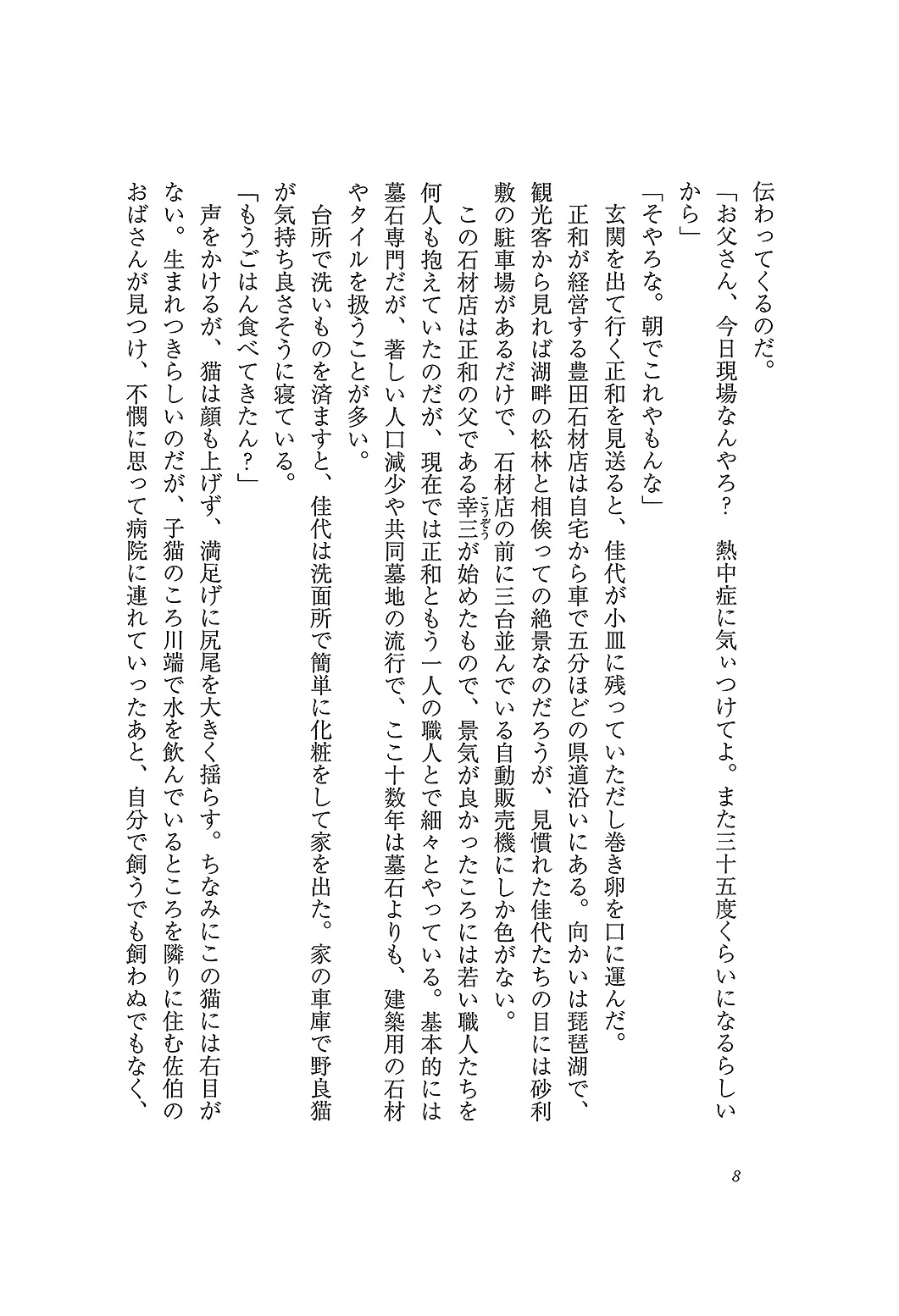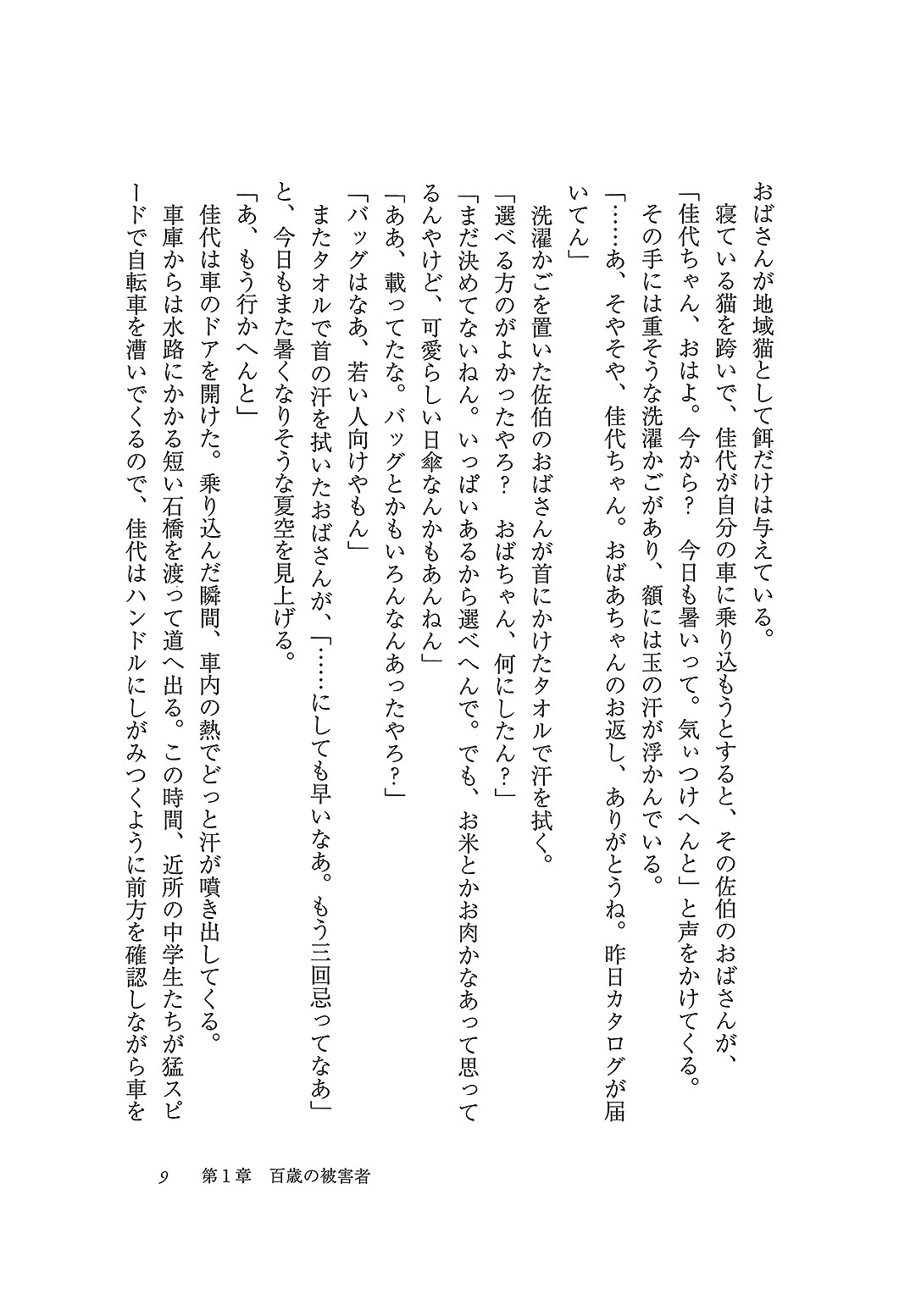第1章 百歳の被害者
台所はひんやりしている。
床板は無垢の松材で、柿渋と松煙を使って塗装されているので、洗剤が染み込むと艶がなくなる。だから拭くときには必ず雑巾を固く絞ってから拭きなさいと、豊田佳代は幼いころから祖母にしつけられている。
おかげで床は未だに黒光りしているが、なにぶん古い家なので踏めば床板は軋む。ギィと鳴るだけならかわいいものだが、ここ数年は流し台から川端まで、この狭い台所で立ち動くたびに、食器棚に重ねた皿が音を立てる。
川端というのは、ここ西湖地区に流れる豊富な湧き水の水路で、この水路が家々の台所の中に引き込まれている。
佳代の家では台所の床板から一段降りたところが石積みの川端で、大きな石甕に引き込まれた湧き水は料理に使ったり、野菜を冷やしたりする。
「お父さん、なんか銀行の振込あるって言ってへんかった?」
冷えた胡瓜とトマトを石甕から掬い上げながら、佳代は背後の居間に声をかけた。
濡れたまま野菜を俎板にのせ、サラダ用に切り始めていると、「ああ、これこれ、頼むわ」と、いつの間にか父親の正和が背後にいた。体の大きな正和が立つと、床板が大きくしなるのが佳代の足の裏からも伝わってくる。
正和が手にしているのは通販代金の振込用紙で、6980円とある。
「また、なに買ったん?」
「羽毛の枕や」
「枕、こないだも買うてなかった?」
「あれ、向こうの家に持ってってん。これ、ここに貼っとくぞ」
正和が振込用紙を冷蔵庫にパチンと貼って食卓へ戻る。正和が使ったマグネットは、佳代がさほど熱心にでもなく集めている食品を象ったマグネットの一つで、ちょっと分かりにくいのだが、これはエンガワの握りのミニチュアである。
ちなみに正和が向こうの家と言ったのは、三、四年まえから付き合っているらしい静江という女性の家のことだ。
夏のこの時間はちょうど朝日が台所に差し込んでくる。差し込んだ日差しは川端を照らし、石甕の水に浮かんだ野菜をキラキラと輝かせる。
佳代はガラス製のサラダボウルを食卓に運んだ。切ったばかりの胡瓜やトマトがひんやりと見える。
「粉チーズみたいなドレッシングあったやろ?」
納豆を混ぜていた正和が、佳代が持ってきた柚子ドレッシングを一度手に取って戻す。
「粉チーズ?」
「ああ、そや。向こうの家やったわ」
佳代はかまわず柚子ドレッシングをかけた。
食卓には鯖のみりん干しと大根おろし、大粒の納豆、だし巻き卵に、甘めのエビ豆と、正和の好きなものが並び、あおさたっぷりの味噌汁からは濃い湯気が立っている。
「お父さん、枕、枕って、また首の調子悪いん? マッサージ行ったら?」
「そやな」
正和が乱暴に首を回す。
「そうやって無理に捻るからあかんのちゃうん? 予約しといてあげよか? 最近、大野さん、当日やと空いてないこと多いで」
この大野というマッサージ師を、ある意味、佳代は崇拝している。と云うと大げさだが、たとえば眼精疲労から来る頭痛だとか、全身が痺れるような腰痛を、大野は必ず治してくれる。三十代半ばだろうか、メガネをかけた小柄な男性で、決して力強いマッサージではないのだが、逆にソフトタッチの指圧のリズムが体の奥の方まで染み込んでくる。極めつきは施術の最後で、両目の上にかざされる彼の手のひらだ。触れられてもいないのに、じんわりと手のひらの熱が伝わってくるのだ。
「お父さん、今日現場なんやろ? 熱中症に気ぃつけてよ。また三十五度くらいになるらしいから」
「そやろな。朝でこれやもんな」
玄関を出て行く正和を見送ると、佳代が小皿に残っていただし巻き卵を口に運んだ。
正和が経営する豊田石材店は自宅から車で五分ほどの県道沿いにある。向かいは琵琶湖で、観光客から見れば湖畔の松林と相俟っての絶景なのだろうが、見慣れた佳代たちの目には砂利敷の駐車場があるだけで、石材店の前に三台並んでいる自動販売機にしか色がない。
この石材店は正和の父である幸三が始めたもので、景気が良かったころには若い職人たちを何人も抱えていたのだが、現在では正和ともう一人の職人とで細々とやっている。基本的には墓石専門だが、著しい人口減少や共同墓地の流行で、ここ十数年は墓石よりも、建築用の石材やタイルを扱うことが多い。
台所で洗いものを済ますと、佳代は洗面所で簡単に化粧をして家を出た。家の車庫で野良猫が気持ち良さそうに寝ている。
「もうごはん食べてきたん?」
声をかけるが、猫は顔も上げず、満足げに尻尾を大きく揺らす。ちなみにこの猫には右目がない。生まれつきらしいのだが、子猫のころ川端で水を飲んでいるところを隣りに住む佐伯のおばさんが見つけ、不憫に思って病院に連れていったあと、自分で飼うでも飼わぬでもなく、おばさんが地域猫として餌だけは与えている。
寝ている猫を跨いで、佳代が自分の車に乗り込もうとすると、その佐伯のおばさんが、
「佳代ちゃん、おはよ。今から? 今日も暑いって。気ぃつけへんと」と声をかけてくる。
その手には重そうな洗濯かごがあり、額には玉の汗が浮かんでいる。
「……あ、そやそや、佳代ちゃん。おばあちゃんのお返し、ありがとうね。昨日カタログが届いてん」
洗濯かごを置いた佐伯のおばさんが首にかけたタオルで汗を拭く。
「選べる方のがよかったやろ? おばちゃん、何にしたん?」
「まだ決めてないねん。いっぱいあるから選べへんで。でも、お米とかお肉かなあって思ってるんやけど、可愛らしい日傘なんかもあんねん」
「ああ、載ってたな。バッグとかもいろんなんあったやろ?」
「バッグはなあ、若い人向けやもん」
またタオルで首の汗を拭いたおばさんが、「……にしても早いなあ。もう三回忌ってなあ」と、今日もまた暑くなりそうな夏空を見上げる。
「あ、もう行かへんと」
佳代は車のドアを開けた。乗り込んだ瞬間、車内の熱でどっと汗が噴き出してくる。
車庫からは水路にかかる短い石橋を渡って道へ出る。この時間、近所の中学生たちが猛スピードで自転車を漕いでくるので、佳代はハンドルにしがみつくように前方を確認しながら車を出す。
先日、祖母寿子の三回忌法要を臨済寺で済ませた。
亡くなる前日まで近所のスーパーに出かけていたほどで、とにかく急で呆気ない最期だった。あまりにも呆気なさすぎたせいもあるのか、通夜や告別式で佳代は一切泣かなかったのだが、なぜか先日の三回忌法要が終わった直後、自分でもどうしようもないほど涙が止まらず、境内の松の裏で泣きじゃくった。
悲しいとか寂しいとか、そういうことではなくて、祖母が亡くなってからの丸二年の間に溜まっていた、たとえば「なあ、おばあちゃん、タオルケット出そか?」とか「なあ、おばあちゃん、玄関の鍵閉めてくれた?」とか、「なあ、おばあちゃん、今日も暑いで」とか、そういった二年分の呼びかけが、「おばあちゃん! なあ、おばあちゃんって!」と、とつぜん体からあふれ出てきたようだった。
泣くだけ泣くと、子供のころ、祖母が話してくれた昔話が蘇った。有名な話もあれば、祖母の創作みたいな話もあったが、なかでも未だに鮮明に覚えているのは天狗の話だ。
あるとき、村の少女が神かくしに遭う。村人たちが必死に捜索するも少女は見つからない。そのころ、少女は森の中で目を覚ます。すでにとっぷりと日の暮れた森の中、少女は、走る誰かの腕に抱えられている。とても太い腕で、包み込まれるように柔らかい。しかし、暗くてその顔は見えない。
「あんたは誰?」
少女が尋ねると、ふと動きが止まった。
「わしは天狗じゃ」
そう言って、また森の中を走り出す。
車は県道へ出ると、正和の石材店とは逆方向に走る。湖沿いの片側一車線。平坦な一本道でスピードを出す車が多く、法定速度を守る佳代のようなドライバーは、あからさまに煽られてドキドキしたり、無理な追い越しにヒヤッとさせられる。
この県道を湖沿いに五キロほど北上したところに、佳代の勤務先である介護療養施設の「もみじ園」がある。
佳代たちスタッフが車を停めるのは、この正面玄関からさらに裏へ回った一角にあるスタッフ用駐車場で、その日来た順番に停めていくので、ここに停まっている車を見ただけで、今日は誰が夜勤で、日勤の誰がすでに出勤しているかが分かる。
車を降りた佳代はそんなスタッフたちの車を見渡し、一口に車と言ってもいろんな種類があるものだと改めて思う。
佳代のような女性スタッフたちは、ほぼ全員が軽自動車に乗っているが、それでもまだ若い梓ちゃんは淡いピンクのスズキ・アルトラパンというぬいぐるみのような車だし、シングルマザーである二谷さんは、室内が広く実用的な赤のダイハツ・タントで、旦那さんや孫と一緒にキャンプを楽しむというユニットリーダーの服部さんだけはキャンプ仕様に特注した迷彩柄のジープに乗っている。
この服部がキャンプ仕様の車に乗っているのには理由がある。孫娘に当たる三葉ちゃんという女の子を夫婦で育てているのだ。
服部から聞いた話によれば、服部の一人娘が離婚し、別の男と付き合うようになり、もちろん当初は娘の三葉もその男に会わせていたらしいのだが、次第にその男に対する三葉の態度が悪くなってしまったらしい。ただ、娘に男と別れる気はないどころか、三葉を置いて外出してしまうようなこともあり、見かねた服部たち夫妻が三葉を引き取って育てるようになったという。
塞ぎがちだった三葉を元気付けるために始めたのがキャンプだった。服部がアウトドア系に明るいのはそのせいだった。
つくづく、自分の車だけが特徴がないと佳代は思う。価格と燃費重視で選んだのは軽自動車の一番人気車で、乗り心地も良く不満はない。だが、無難にボディカラーを白にしたせいか、近所の大型スーパーやレイクモールの駐車場では似たような車がありすぎて探し出せないときがある。
佳代は施設に入るまえに背伸びした。少し高台にあるので、風通しも良さそうなものだが、あいにく風もない。以前担当していた入居者で、現役時代は建築家だったと言うおじいさんがいた。彼がまだ元気だったころに言っていたのだが、この「もみじ園」というのは琵琶湖からの湖風を遮るように建てられており、おまけに盛り土のような地形が風の流れを悪くしているらしい。
聞けば聞いたで、佳代もそんなものかと思う。ただ、風なんか隙間さえあれば通るのだから、そう関係ないようにも思う。
駐車場の強い照り返しから逃れるように、佳代は施設に向かった。程よい冷房が頬を撫でるが、すぐに介護療養施設特有の臭いがする。たまにしか来園しない入居者の家族や親戚には、この臭いに気づかない者が多いと聞いて、佳代は驚いたことがある。もちろん最新設備で園内の換気は完璧に行われているので、たまにしか来ない者には臭いがしないのかもしれないが、毎日をここで過ごす佳代たちスタッフ、そしてもちろん入居者たちは、どんなに最新の換気システムで空気を循環しようと、この生の人間の臭いを知っている。
「おはようございます」
受付の事務員たちに挨拶をして、佳代は更衣室に急いだ。その廊下には入居者たちで作る園芸サークルが育てた鉢植えのスイートピーが並んでいる。
更衣室では、夜勤明けの小野梓がスマホで動画を見ながらニヤニヤしていた。
「お疲れさま」
佳代が声をかけると、「お疲れさまです。ちょっと佳代さん、これ見てくださいよ」と、嬉しそうにスマホを突き出してくる。
見れば、YouTubeの動画で、「なによ、これ?」と、思わず佳代はその手を押し返した。
「流星たちの新作動画なんですけど、アホみたいでしょ? おちんちんに洗濯バサミつけて、お互いに引っ張り合ってんねんて」
「もういややッ」
佳代はさらにスマホを押しのけた。
「大丈夫ですって、ちゃんとボカシ入ってるから」
アホらしいとは思いながらも、動画から聞こえている男の子たちの笑い声が楽しそうで、つい佳代もまた動画に目を向ける。実際、何がそんなに楽しいのか分からないが、ユーチューバーの卵だという梓の彼氏たちは、本気で洗濯バサミのついた紐を引っ張り合っている。
自分で引くよりも、相手に引っ張られる方が痛いようで、へっぴり腰のまま、相手に近寄ったり離れたりする様子を見ていると、次第にそんな破廉恥な動画にも慣れてきて、少しだけ面白くなってくる。
「あ、そうや。佳代さんもチャンネル登録してあげてくださいよ。なかなか増えへんのやって」
「いややー、こんなことばっかりやってんねやろ?」
「たまには映画のレビューとかもやってるんですよ。でも、見なくてもいいですから、登録だけ。ね、お願いします。あとでLINEで送っときますから」
梓はまた動画に視線を戻して笑っている。佳代はロッカーを開けて着替え始めた。
流星という梓の彼氏の本職は型枠大工らしい。近いうちに同棲を始めるのだが、朝の六時まえには仕事に出かける彼氏に、夜勤も多い自分がどれくらいちゃんと尽くしてやれるかと、梓はそれが心配で仕方ないと悩んでいる。「梓ちゃんって、古風なんやね」と、佳代が驚くと、「え? 古風じゃなくて、今どきじゃないですか?」と逆に驚かれた。
◯
ナイロン製のウェーディングパンツで腰まで浸かった太ももを湖水が圧迫する。夏の日差しを浴びた湖面はキラキラと眩しく、湖岸の榛の木の木陰から釣竿を伸ばしているとはいえ、風が止めば背中を汗が流れる。
濱中圭介はいったん釣り糸を巻き上げると、ウェーディングベストから水筒を出し、妻の華子が作ってくれる自家製のポカリスエットを飲んだ。本物とはだいぶ味が違うのだが、逆に自家製の方がレモンの味が強くて、圭介は気に入っている。
湖岸に停めた車を振り返ると、日陰に停めておいたはずが、いつの間にかフロントガラスに日が当たりつつある。
圭介は改めて周囲を見渡した。琵琶湖のこの辺りは遠浅の湿地で、豊かな葦原が広がっている。湖面を渡ってくる微かな風に、葦がその葉を静かに揺らす。
葦原には赤芽柳や立柳などの大きな樹木も多く、太い幹が湖面から突き出すその様子は、熱帯雨林のジャングルを思わせもするが、ジャングルが原色の油絵だとすれば、こちらの湖は墨絵のように色がない。
非番の今日、圭介は朝からウェーディングにきていた。もう二ヶ月もまえ、華子とレイクモールに行った際、溜まっていたポイントを使おうと、アウトドア専門店に寄った。たまたま釣り用品のセールをやっており、古くて洗っても臭いが取れなくなっていたウェーディングウェア一式を買い替えた。以来、新しいウェアを着て湖に入ることを楽しみにしていたのだが、なかなか休暇も取れず、やっと取れても天気が悪かったりで、結局今日まで一度も使えずにいた。
その新しいウェアのお陰か、はたまた新調したヘビキャロの具合が良くて予想以上に遠投できたせいか、サイズは30から40のアベレージながら、傷一つないきれいなバスが面白いように釣れている。
圭介は遠い湖面を見つめた。
リグを落とす辺りに意識を集中すると、そこだけ静かに波打つように見える。圭介は竿を振った。思い描いた軌跡をなぞって、キラキラとラインが伸びていく。狙った場所に35グラムのシンカーが落ちた瞬間、静かな湖面に波紋が起こる。波紋は湖が静かであればあるほど大きく広がっていく。
いったん車に戻ったのは、仕掛けのワームがなぜか取れてしまったからで、ついでに車内で朝メシも済ませる。朝メシと言っても途中コンビニで買ったサーモンのクラブサンドで、ものの三分で食い終わる。胃が満たされると、日頃の寝不足がたたって眠気が襲う。早朝に出てきたので、まだ朝の八時まえだった。
圭介はシートを倒し、スマホに保存した動画を再生した。選んだのはプライベートに撮影されたらしいサディスティックなエロ動画で、急に女の喘ぎ声が漏れ出て慌ててボリュームを絞る。
車を停めているのは湖沿いの県道から水門脇の通路を抜け、さらに砂利道を進んだ湖岸で、密生したクヌギの木立が目隠しとなっている。
圭介は運転席で下着を下ろすと、乱暴に性器をしごいた。動画では性奴隷志願だという女が、パスポートで自身の本名を晒されながら男の性器を舐めさせられている。
圭介が果てたのと、このパスポートはきっと偽造だなと今さら気づいたのが同時だった。途端に女の媚態が演技に見えてくる。
白けた圭介はティッシュで汚れを拭い、水筒の自家製ポカリスエットを飲み干した。スマホが鳴ったのは車を降りてクヌギの枝に干していたウェーディングパンツにふたたび足を通そうとしたときだった。
部長の竹脇からで、非番とはいえ無視するわけにもいかずに出ると、「濱中か? すぐ来れるか? ……いや、直接現場に向かえるか?」と、いつになく切迫した声がする。
「事件ですか?」
「西湖地区に『もみじ園』っていう介護施設あるの知ってるか?」
「もみじ園……。いえ、知りません」
「湖沿いに野鳥センターがあるやろ? そこから駅の方に向かって……」
「ああ。……あの田んぼの中に建ってる? あれ、介護施設なんですか?」
「俺もずっと病院やと思てたけど、今朝あそこで入居者が死んだらしいわ。まだ様子はよう分からんのやけど、とにかくすぐ向かってくれ」
「分かりました。三十分以内には」
圭介は電話を切り、釣り道具をトランクに投げ入れた。
自宅まで十分で戻って五分で着替える。自宅から現場まで十五分……。頭の中で計算しながらも、前を走る車を次々に抜き去る。
自宅へ戻ると、夫の早い帰宅にベランダでハーブを摘んでいた華子が、「もう帰ってきたん?」と目を丸くする。
「急に仕事になった。すぐ出るわ」
圭介は服を脱ぎ捨てた。
慌ててベランダから戻った華子が、まずハーブを台所に置き、寝室のクローゼットからしゃがんでシャツを出そうとするので、「そんなバタバタ動いたらあかんて」と、圭介は臨月に近い華子を気遣った。
「遅くなるん?」
「まだ分からへん」
圭介は華子の腰を摩った。実際にはかなりの肉がついているのだが、不思議なもので、こうやって摩ると、ほっそりした本来の腰の線が感じられる。
「あ、せや。時間あるときでええから、義姉さんにお礼の電話入れといてくれへん? またオーガニックの高そうなおくるみ贈ってくれはって。ネットで調べたら一万二千円もすんねん」
華子が箱を開けようとする。
「おくるみって、何?」
乱暴にネクタイを締めながら圭介は訊いた。箱を開けた華子が、タオルのようなものを出し、「こうやって、赤ちゃんを『おくるみ』や」と自分の腹に巻いてみせる。
圭介は玄関で革靴に足を突っ込んだ。まだ下ろしたばかりで、新しい革が鳴る。
「あんまり高いもん、もらったらあかんで」
「そんなん、私がねだったわけちゃうもん」
圭介は玄関を飛び出した。
「いってらっしゃい」と言う華子の声が聞こえたのは、ドアが閉まったあとだった。
華子の実家は代々続く地元の歯科医で、現在では長男がその事業を継いでいる。この長男の嫁が、昔から圭介は苦手だった。もちろん表立った諍いがあるわけでもなく、会えば普通に付き合うのだが、こちらが何を言っても、その裏の意味を勘ぐられているような、そんなひんやりした空気が流れるのだ。
以前に一度だけ、その気持ちを華子に伝えたのだが、刑事の嫁にもかかわらず、世の中の悪意というものに無頓着な彼女にはピンと来ないようだった。自分の夫が陰湿な事件を扱っているというよりも、陰湿な事件を扱ったテレビドラマの刑事役でもやっているようなイメージらしく、華子が想像する事件現場には照明だけが強く、血や汗といった人間の臭いが一切ない。
高校時代、圭介はサッカー部に所属しており、おそらく女の子たちから人気があった。ある練習試合の帰り道、チームメイトたちと歩いていると、対戦相手だった学校の女子生徒たちから一緒に写真を撮らせてくれないか、などと頼まれた。嬉しいというよりも、チームメイトたちに冷やかされるのが嫌だった。しかしチームメイトたちは、「圭介、じゃ、俺ら、先に駅前のお好み焼き屋行ってるわ」と、まるで靴紐がほどけた友人をその場に残すように圭介を置いていく。
隣町の女子校に通っていた華子と付き合い始めたのがこのころだった。知り合ったのは両校共同で行われたチャリティーバザーの親睦会だったのだが、華子もまた、圭介の学校の男子生徒たちから一緒に写真を撮ってもらえないかと声をかけられていた。そして華子の友人たちもまた、まるで靴紐がほどけた友達を置いていくように、先にどこかへ行ってしまうのだ。
お互いにほどけてもいない靴紐を結び直して顔を上げた瞬間、お互いの顔がそこにあったような感じだった。
その後、互いに地元の大学へ進み、一人暮らしを始めた圭介のアパートで同棲の真似事のようなことをするようになった。長い休みには華子の両親が所有している北湖の別荘に学校の仲間たちを集めて過ごすのが恒例で、大学三年のときには、華子がミス琵琶湖に選ばれたこともあって、圭介もバイクで彼女が参加する全国キャンペーンについて回り、各地の旨いものを一緒に食べ歩いた。
大学卒業後、入学した警察学校の初任科のころ、結婚を意識するようになった。六ヶ月の在学中は文通以外の連絡手段がなく、週に一度交わす手紙の内容がいつの間にか将来の話になっていた。もちろん圭介は華子と一生を共にしたいと思っていた。華子とならば幸せになる自信もあったし、未だにある。実際、友人や上司たちはもちろん、互いの両親たちでさえ、見ていて気持ちいいくらい理想的なカップルだと手放しで褒めてくれる。
到着したもみじ園には、特に規制線が張られているわけでもなかった。報道関係者の車もまだ到着しておらず、駐車場はいたって平穏で、一台のワゴン車からひどく背中の曲がった老人が車椅子に乗せられて、やけにのんびりと降ろされている。竹脇部長の口調から、圭介はてっきり管轄内では珍しい殺しだと思っていた。
施設に入ると、さすがに内部は混乱しており、施設の職員や鑑識が慌ただしく立ち動いている。圭介は介護スタッフらしき女性に話を聞いている先輩の伊佐美の背後に立った。
「遅くなりました」
小声で挨拶した。伊佐美も小さく頷き、すぐにスタッフとの話を打ち切ると、早速現場となった個室に連れていく。
「状況、何か聞いてるか?」
伊佐美に訊かれ、「いえ、まだ何も」と圭介は首を振る。
「ガイシャは市島民男、百歳」
「百歳?」
圭介は思わず足を止めた。
「人工呼吸器をつけて療養中やったガイシャが、今朝方、心肺停止状態で発見されたんや。死因は低酸素脳症。駆けつけた家族が、施設側の説明とスタッフたちの態度を不審に思って通報した。今のところ、人工呼吸器の不具合かもしれんし、当直の看護師たちによる業務上過失があったのかもしれん……」
「発見したのは、当直やった看護師なんですか?」
「いや、看護師さんやなくて、介護士さんや。彼女がガイシャの異変に気づいたのが午前五時すぎらしいわ」
やけに磨き上げられた廊下を進むと、現場らしい個室を施設のスタッフたちが遠巻きに覗き込んでいた。おそらく、看護師は白、介護士が薄いピンク色の制服なのだろう。
その個室から竹脇部長がハンカチで額の汗を押さえながら出てくる。
「遅くなりました」と圭介は声をかけた。
「ちょっと出よか。ここは鑑識に譲って」
竹脇が圭介と伊佐美を押し戻す。
圭介は振り返った。なんの変哲もない病院の個室で、ベッドは一つ、サイドテーブルに花が飾られているわけでもない。
「ほな、改めて聞こか」
長い廊下が突き当たりで左に折れ、てっきりその先にもまた廊下が続くのだろうと思っていたが、折れた先が行き止まりで、四人掛けの硬そうなベンチがコの字に並んだ休憩所になっていた。
ベンチに座り込んだ竹脇の前に、圭介と伊佐美は立った。伊佐美がメモ帳を開く。
「昨晩の当直は看護師が二人。他に介護士が二人の体制やったようです」
伊佐美の話によれば、このもみじ園という施設は療養病床と老人性認知症疾患療養病棟に分かれており、当該のガイシャは療養病床の入居者ということになる。
「……まだ、詳しい調べはこれからですが、おそらくガイシャの死亡時刻前後、看護師は二人とも仮眠中で……」
「二人とも?」
竹脇が口を挟む。
「ええ。その代わり二名の介護士たちに仕事を任せたそうなんですが、介護士たちの方からは、正式な要請を受けていないという声も出ております」
「昨日が初めてか? その看護師が長い仮眠で介護士に任せるっていうのは」
「いえ、珍しいことやなくて、看護師の人数が足らんときは、いつもそういう体制やったそうです」
「よし、続けろ」
「はい。ですので、焦点は人工呼吸器に誤作動があったかどうか、もしないとすれば、施設側の業務上過失致死……」
伊佐美の報告を聞きながら、圭介は窓外へ目を向けた。高台に建つこの施設からは、防風林の先に夏の日差しを浴びた湖面が見える。
◯
浴槽の湯が汚れた泡と一緒に排水口に吸い込まれていく。佳代は入居者の体が冷えぬように、なるべく早くタオルで拭いてやりながら、「戌井さん、またゆっくりリフト上げますよ。お尻と背中はキャリーに移してから拭きますからね。気持ち悪いやろうけど、ちょっとだけ我慢しといてくださいね」と耳元に声をかける。
ペアを組んでいる二谷紀子がタイミングを見計らって頑丈な吊ベルトを椅子にかけ、リモコンを操作すると、ゆっくりと戌井の体が持ち上がる。入居してきたばかりのころに比べれば、戌井の体はすっかり細くなっているが、それでも吊ベルトの軋み音からは一人の男性の重みが伝わってくる。
佳代は、戌井の股間に乾いたタオルを置くと、安全のためとはいえ、あまりにも緩慢なリフトの動きが申しわけなくなる。局部にだけ小さなタオルを置かれた老人の裸体が、まるで見世物のようにゆっくりと浴槽からキャリーへと移動していく。
「恥ずかしいことじゃなくて、気持ちええことをしてあげてるって思わんと」
この仕事を始めたばかりのとき、先輩に言われた言葉だ。浴室のドアが開いたのは、そのように吊られたままゆっくりと移動する戌井の体を見守っていたときで、「入浴、まだ時間かかりそう?」と、ユニットリーダーの服部久美子が顔を出した。
「いえ、もう終わります。今日は戌井さん、お洋服脱ぐの、ぜんぜん嫌がらずにいてくれはったもんね。いつもとはお風呂の時間が違ったのにね」
二谷がリフトに吊られた戌井に微笑みかけるが反応はなく、佳代は戌井のその痩せた太腿に手を添えて、キャリーに降ろされるリフトの角度を調整した。
「ほんなら、戌井さんの入浴が終わったら、二人一緒に相談室行ってもらえるやろか。さっきは一人ずつて言われたんやけど、二人一緒でもええみたいやから」
服部はそれだけ伝えると、乱暴にドアを閉めた。廊下を走っていく忙しい足音が聞こえる。
「なんか緊張するな。一応、これ、正式な取り調べなんやろ?」
二谷がそう言って大げさに震える真似をしながらも、戌井の背中と尻を丁寧に拭く。佳代は、皮膚のたるんだ戌井の両腕を自分の首に回して抱きかかえ、拭きやすいようにその体をできるだけ持ち上げる。
「……でも、佳代ちゃんと一緒でよかったわ。心強いわ」
「私だってそうですよ。それこそ、学生のころから面談とか面接やのって言われると、心臓がキューッてなりますもん」
自分だけ蚊帳の外に置かれていることは分かるのか、入浴中には大人しかった戌井が佳代の腕から逃れようとする。
「……戌井さん、かんにんやで。もうすぐ終わるからね」
声をかけるが、戌井がさらに嫌がる。
「戌井さん、今日な、一〇八号室の市島民男さんが亡くならはってん。そんでな、どういう理由で亡くなったんか、警察がようけ来て捜査してんねん。別の班が担当してる入居者さんなんやけどね。それでも職員全員に昨日の夜のことを聞くんやて」
二谷の説明が理解できたとは思えないが、抗っていた戌井の体から力が抜けていく。
戌井を居室のベッドへ戻すと、佳代たちはその足で入居相談室へ向かった。取り調べを待つ長い列が廊下にできているのかと思っていたのだが、特に誰も待っていない。
「ノックした方がええんかな?」
ドアに耳を寄せる二谷に訊かれ、佳代も横から顔を近づけた。部屋の中からは人声もない。
「少し、そこで待ってみます?」と、佳代はベンチに目を向けた。
「そやね」
二谷と寄り添うように硬いベンチに腰掛けた途端、ちょっとそわそわしてくる。相談室のドアが開いたのはそのときだった。ぬっと顔を出した若い刑事が、「あれ、ここに婦警おりませんでした?」と訊く。
「いえ」
そう答えた二谷に、一拍遅れるように佳代も、「誰も」と続けた。若い刑事は爪先立ちになって廊下の奥を確かめる。日に灼けているせいか、ワイシャツが驚くほど白く見える。
「えっと……」
婦警を探すのを諦めたらしい刑事が、佳代たちに視線を戻す。
「ユニットリーダーの服部から、こちらに伺うように言われたんですけど」
答えたのは二谷だった。
「服部さんってことは……」
「二班です」
「ああ。じゃ、どうぞ」
そこで初めて佳代たちは立ち上がったのだが、自分たちが無遠慮に座り続けていたことに気づき、二人して照れるように互いを肘で突つき合った。しかし刑事は表情を変えることもない。
相談室内はいつもと変わらなかった。入居案内などのパンフレットもデスクの上にそのままで、窓際にはミッキーマウスとくまのプーさんのぬいぐるみが置いてある。
「西湖署の濱中と言います。お忙しいところ、ご苦労様です」
日ごろはスタッフが座る椅子にこの刑事が座り、佳代たちは来園者用の立派な椅子に腰かけた。
「お名前からお願いできますか?」
そこで初めて刑事が顔を上げた。顔を上げるというよりも、その目だけが動き、まっすぐに二谷を見つめている。
自分が見られているわけでもないのに、思わず佳代はその視線から目を逸らした。逸らした先に、刑事のものらしいメモ帳があった。これが例の警察手帳かな、と一瞬思ったが、そうではないらしく、スーパーなどでも見かける市販の帳面で、開かれたその紙面を、まるで黒蟻のような小さな文字が隙間なく埋めている。今にもその一匹が紙面から這い出てきて、日に灼けた刑事の指に上っていきそうだった。
「皆さんにお聞きしてるんですが、昨晩のお仕事の流れを一通り聞かせてもらえますか?」
濱中と名乗った刑事に訊かれ、「私は夜勤の遅番でしたので、出勤したのが夜の八時です……」と、二谷がすらすらと答える。
その横で佳代は慌てた。二谷が事前に答えを準備していると思った。昨夜のことを思い出そうとすると、さらに緊張してしまう。
本来なら昨日と今日は、両日とも朝の九時から夕方の六時までの日勤遅番シフトだった。ただ、前日からユニットリーダーの服部に相談されていた通り、ぎっくり腰で急遽休みを取っている沼田さんの代わりに、日勤遅番から続けて夜勤という二十四時間連続勤務になっていた。さらに今朝からの大騒ぎで、本来なら朝九時の終業時間を超え、こうやって昼近くまで二谷とともに働いている。
ただ、変則的なシフトのせいもあって、昨晩は五時間近くしっかりした仮眠の時間をもらえたので体力的には問題ない。
昨夜、夜勤の二谷とともに各室を回ってルーティンの作業を終えたのは平常通り午後十一時ごろだった。事務室へ戻り、手分けして日報を記入した。連続シフトで疲れているだろうからと二谷が声をかけてくれ、十二時前には仮眠室へ入った。
確認はしなかったが、おそらく窓側の二段ベッドでは看護師の中村たちが寝ていたはずだ。「今夜、一班は介護士スタッフだけで起きてるんやな」と思った記憶がある。
その後、一度トイレに起きただけで午前四時過ぎまでしっかりと眠った。身支度をして事務室へ戻ると、二谷が巡回から戻ったところで、「あれ、佳代ちゃん、もう起きたん? 五時までええよ」と言ってくれたが、もう目が覚めてしまったからと、ちょうど呼び出しのあった二〇五号室の白須さんのオムツ交換へ出向いた。
五時を過ぎると、入居者たちが目を覚まし始めるのでいつも通り忙しくなる。朝食前に入居者たちの投薬に最新の変更がないかチェックして、二谷と食事担当の分担を決めているときだったと思うが、一班が受け持つ一階がなにやら騒がしくなった。認知症の老人たちがいる施設なので小さな騒ぎなどよくあることで、今度は何だろうかと思う程度で静観していた。
朝食の準備などルーティンの仕事をこなしているうちに、騒ぎの原因が伝わってきた。なんでも一〇八号室の市島民男が今朝方亡くなっており、異常があれば本来なら鳴るはずの人工呼吸器のアラームが鳴らなかったらしかった。すぐに駆けつけた家族が患者の死因に不審な点があると警察に通報したという話が、佳代の耳に入ってきたのが、各室の朝食の片付けも終えたころだ。
さすがに気になり、佳代と二谷も一階へ降りてみた。ただ、予想した混乱はなく、一班のスタッフたちもすでに通常の仕事に戻っていた。
「お父さん、まだ焼酎飲むん? ごはん、まだいい?」
佳代は冷蔵庫から鰺茶漬けのパックを取り出し、茶碗半分ほどの白米の上に載せると、熱湯を注いだ。わざわざ通販で長崎から取り寄せている茶漬けパックで、真鰺に熱湯をかけると身が白くなり、鼻をくすぐるような風味が立つ。
祖母の寿子はあまり洋食を好まなかったが、この鰺茶漬けのパックで作ったパスタだけは好きで、一人分をペロリと食べた。
「お父さん、ごはんは?」
食卓に戻り、佳代は改めて訊いた。グラスに焼酎を注ぎ足していた父の正和が、「まだええわ」と首を振り、「……それより、その刑事もなんか頼りないな」と、話の続きを始める。
席を立つまえ、佳代は今日もみじ園で起こった出来事の顛末を正和に話していた。正和は百歳になる入居者の死因が自然死だったのか、はたまた医療ミスだったのかについては、さほど興味を持たなかったが、娘が刑事に取り調べを受けたことを面白がり、「へえ、警察手帳、見せへんの? アリバイ的なことは聞かれへんの?」と、佳代の短い話が終わったあとも質問を続けた。
「頼りないというか、その刑事さん、ものすごい疲れてはったわ。そりゃ、そうやで。同じ質問を二十人にも三十人にもするんやろうし」
佳代は鰺茶漬けを啜った。
「いうても、容疑者としての濃淡はあるやろ。おまえみたいにまったく別の班の者と、その死んだ爺さんを担当しとった人らとは調べ方もちゃうやろし」
「容疑者って……」と佳代は笑った。
焼酎を飲む父親と鰺茶漬けを啜る娘のいる食卓では、容疑者という言葉は馴染まない。
「お父さん、私、今日は連続勤務明けやから早よ寝るからな。グラスや皿、そのまま流しに置いといてくれたらいいから」
席を立とうとした佳代に、「あ、そや。引越しのことやねんけどな」と、正和がどこか言いにくそうに声をかけてくる。
「もう業者さんに頼んだん?」
「お父さん一人分の荷物なんて、わざわざ業者に頼むほどのもんちゃうやろ」
「それでも、自分たちでやるとなったら、また手間やで。この暑い最中に。……静江さん、なんて言うてんの? 一緒に暮らすって決めたんやったら、お父さんもちゃんとしてあげな。小学生の修学旅行ちゃうんやし、下着と歯ブラシだけってわけにもいかへんで」
「そんなん、分かってるわ」
正和がいつものように少し腹を立てたところで、佳代は自分の食器を流しに運んだ。
高校時代の同級生だという静江と正和が一緒にいるところを初めて佳代が見たのは、祖母の通夜の席だった。それまでにも正和の口から頻繁に彼女の名前は出ていたし、一緒に温泉旅行などにも行っていたので、ある程度のことは分かっていた。
祖母の葬儀では、元々世話好きらしい静江は、正和の喪服の支度から仕出しの手配まで何かと手伝ってくれた。佳代はそんな静江の少し出過ぎともいえる気遣いに嫌な気持ちになるどころか、「ああ、この人は本当にお父さんを大切に思ってくれてはるんやろな」と素直に思った。
「一緒に暮らしたらええのに」と、最初に口にしたのは実は佳代で、正和の方は、「そんなん、今更ええわ」と、ひどく照れていたのだが、実は静江からもその話はすでにあったらしく、「……もしそうしたら、お前はどうすんねん」とポツリと言う。
正直なところ、佳代はそこまで考えていなかった。だが、もしそうなるのであれば、正和がこの家を出て、どこかで静江と暮らすというイメージしかなかった。もちろんここは父の家だが、早世した母と祖母から受け継いだこの台所は紛れもなく佳代のものであり、静江がそこに立つ姿など想像できない。
「お父さんが静江さんのマンションに行けばいいやん」
佳代は当然とばかりにそう言った。すると、正和たちの方でも似たような話をしていたようで、「まあ、向こうもその方が気ぃ楽らしいわ」と答え、「……でも、お前はそれでええんか?」と佳代を心配する。
「本当は私が出ていくのが筋なんやろうけどな」と佳代は答えた。
「筋なんか、どうでもええねん」
「でも、静江さんもほんまにそっちの方が気ぃ楽やと思うわ。嫌やもん、人んちの台所に立つって」
もう二十年もまえに妻を亡くした男と十二年前に離婚した女が、還暦を前に新しい生活を始める。成人した娘がとやかく口出しする類のことではない。
八歳の時に母を亡くした佳代は祖母の寿子に深い愛情のもとで育てられた。幼いころから祖母と共に家事をこなしてきた佳代にとっては、正和というのは父でありながら、どこかこの家の一人息子という感じもあった。その一人息子が独り立ちして女性と暮らす。父を失うという感傷が一切ないのは、このためらしかった。
その夜、佳代はいつもより早くベッドに入った。仮眠が取れたとはいえ、連続勤務の疲れは重く、シャワーを浴びて髪を乾かしながらもすでに痺れるような眠気があった。暑さで目を覚ますのが嫌で、普段はつけないエアコンにタイマーをかけ、代わりに夏毛布を押入れから引っ張り出した。いくつか届いているLINEやショートメールも確認しなかった。
電気を消して目を閉じると、すぐに眠りに落ちそうだった。ただ、その瞬間、なぜか濱中と名乗った刑事の顔が浮かんだ。
入居相談室での取り調べのあと、思い出すこともなかった顔だった。正和に話しているときでさえ忘れていた。それが今になってなぜか鮮明に浮かび上がってくる。次の瞬間、佳代は急に体がゾクッとして、夏毛布を首筋まで引き上げた。自分があの刑事の顔を忘れていたのではなく、無理に思い出さないようにしていたことに、まるで他人事のように気づいたからだった。