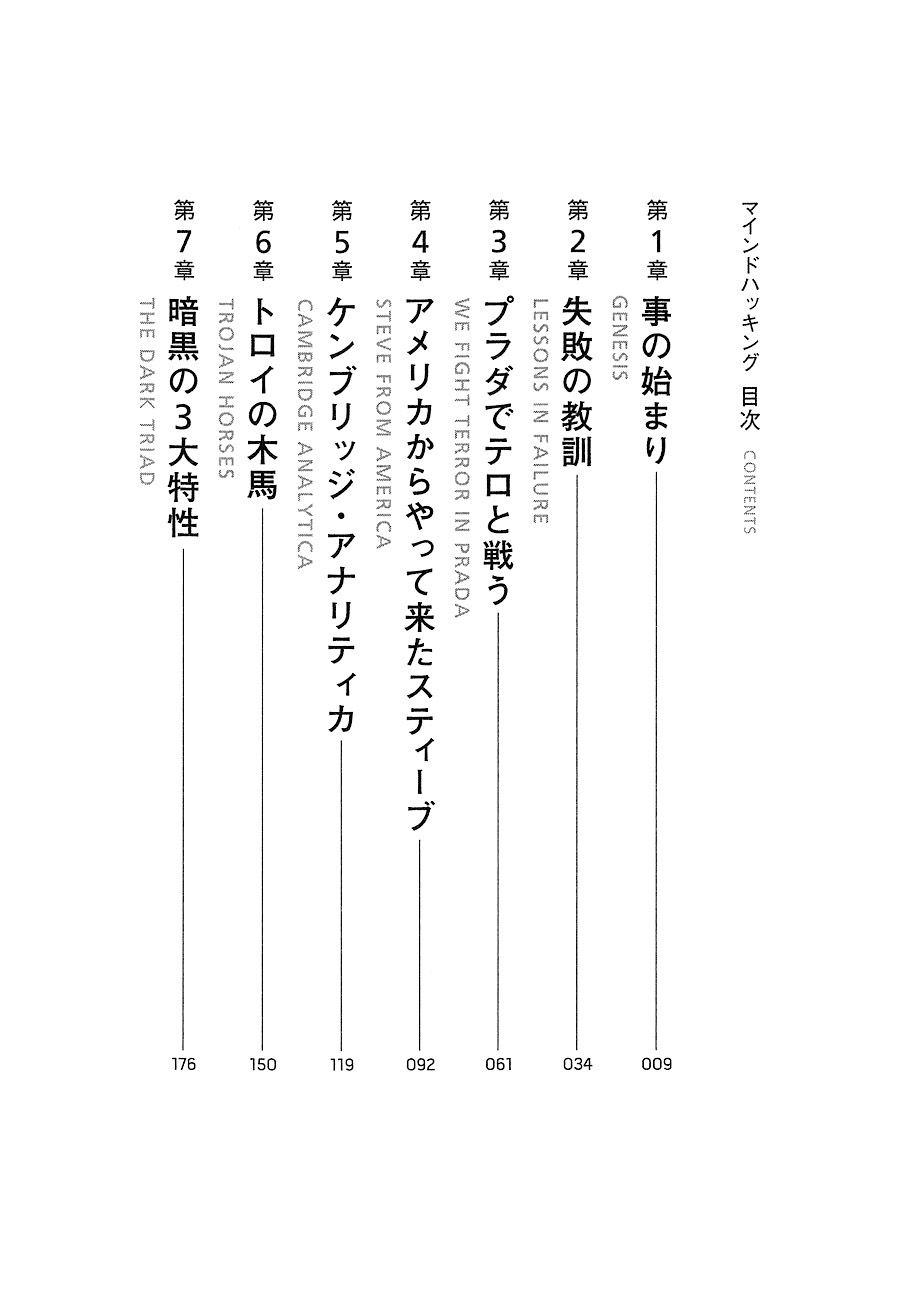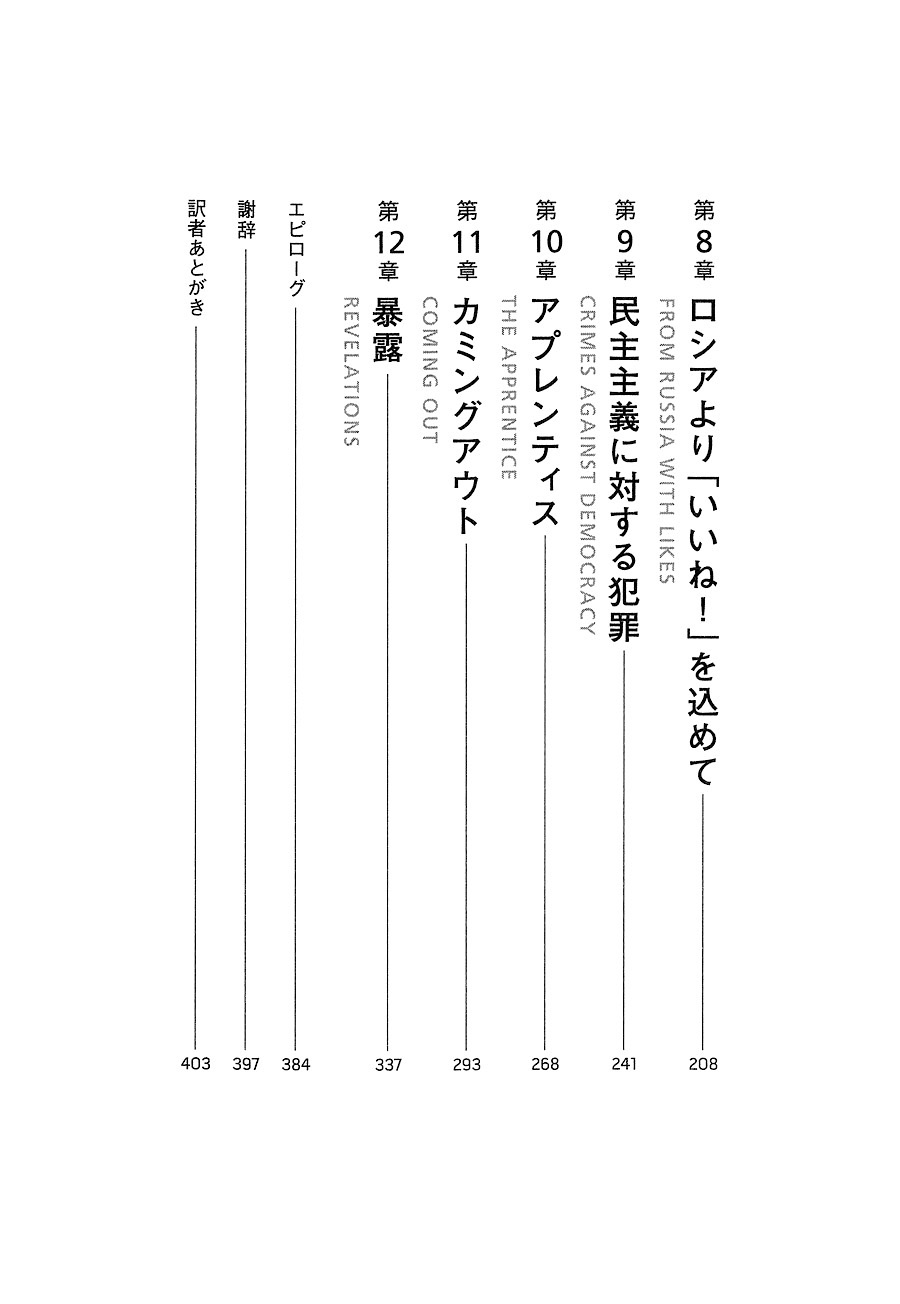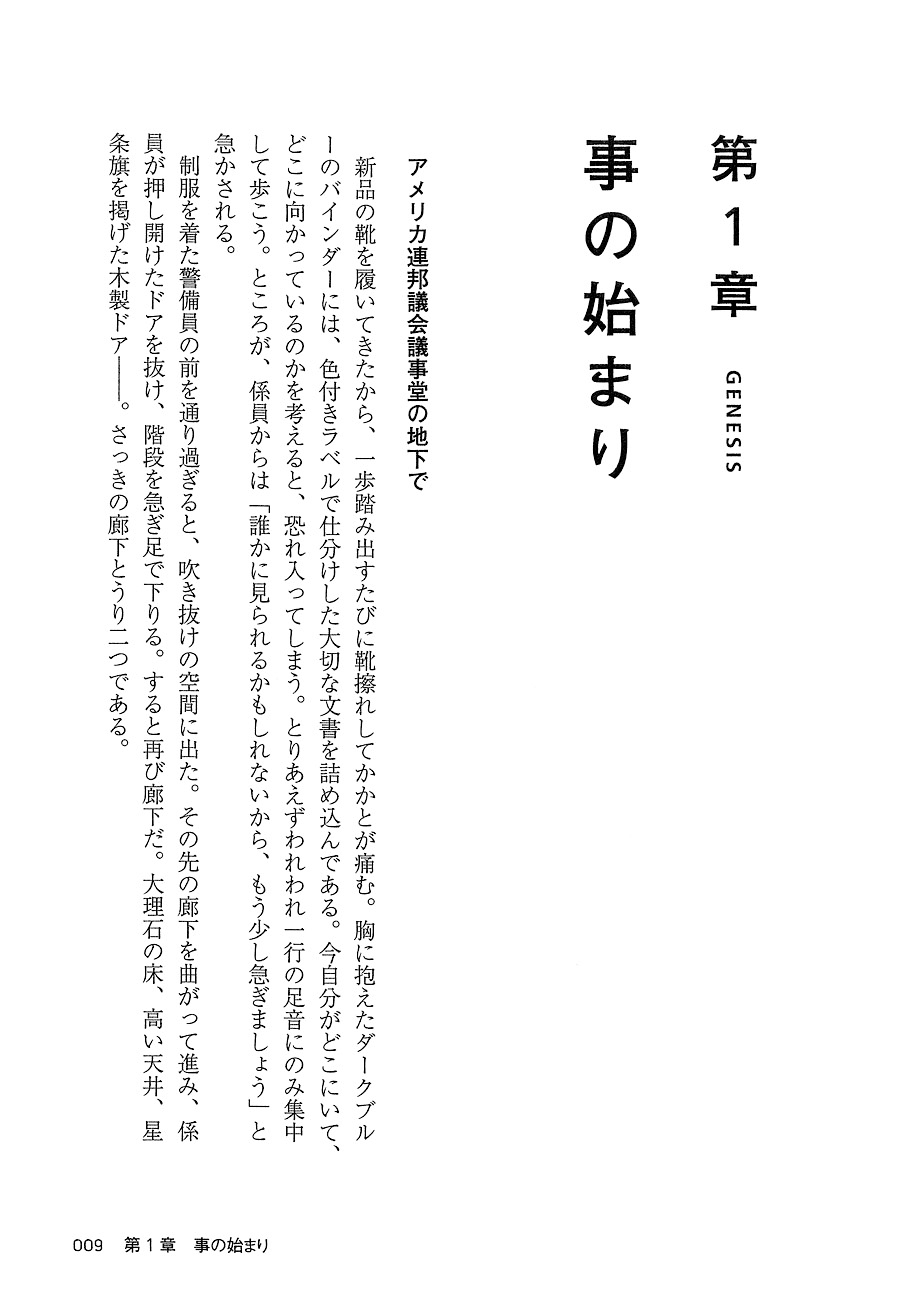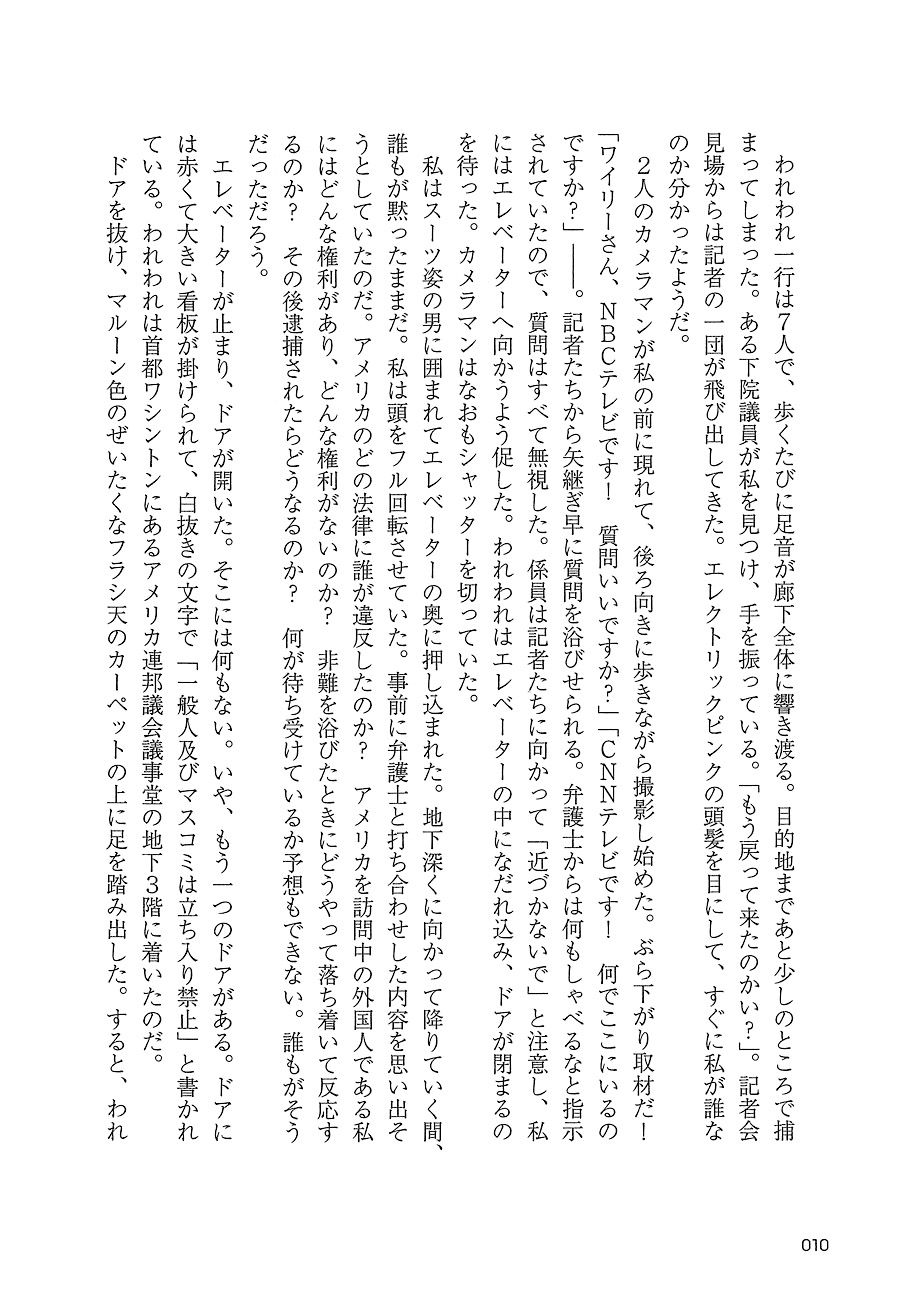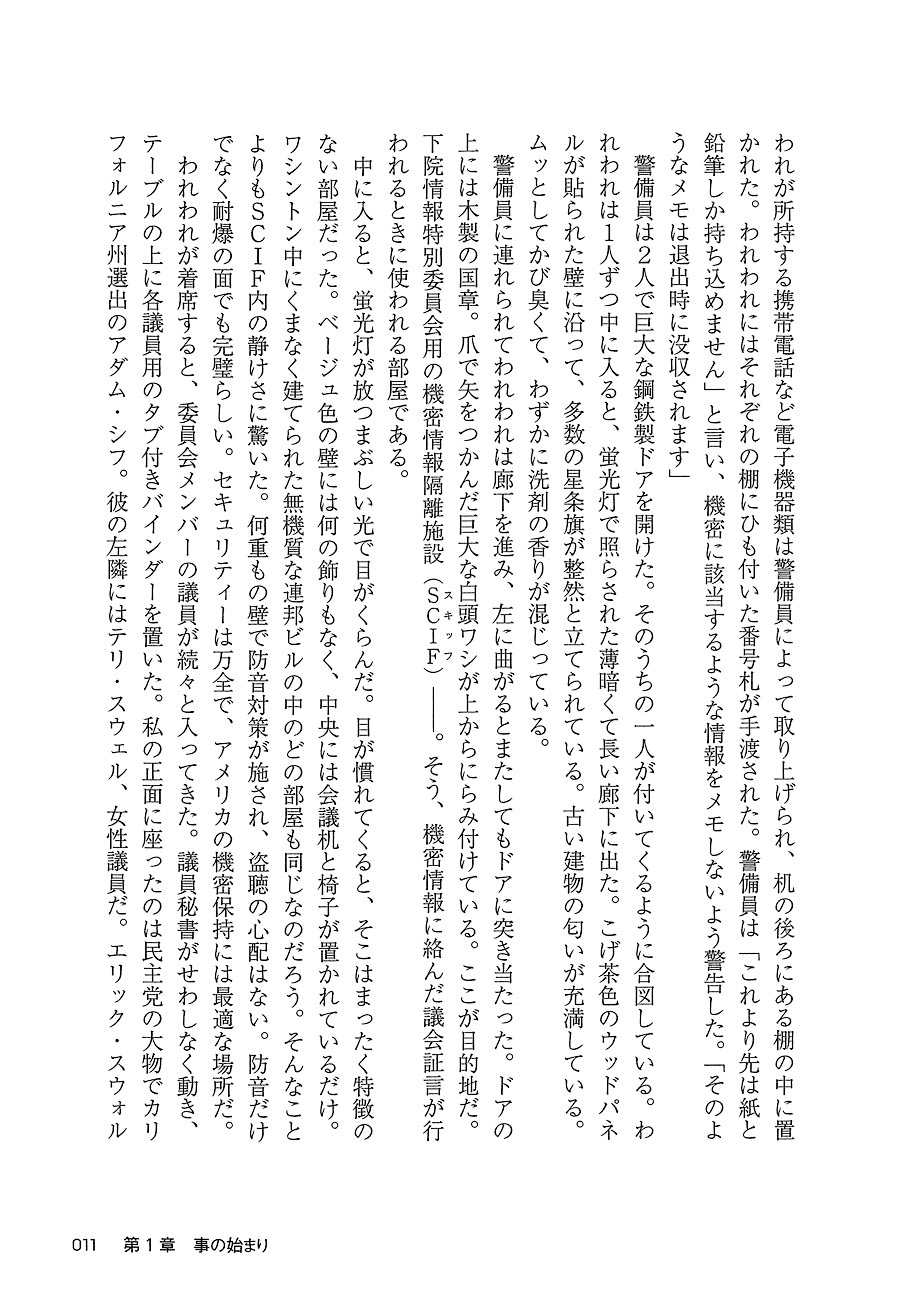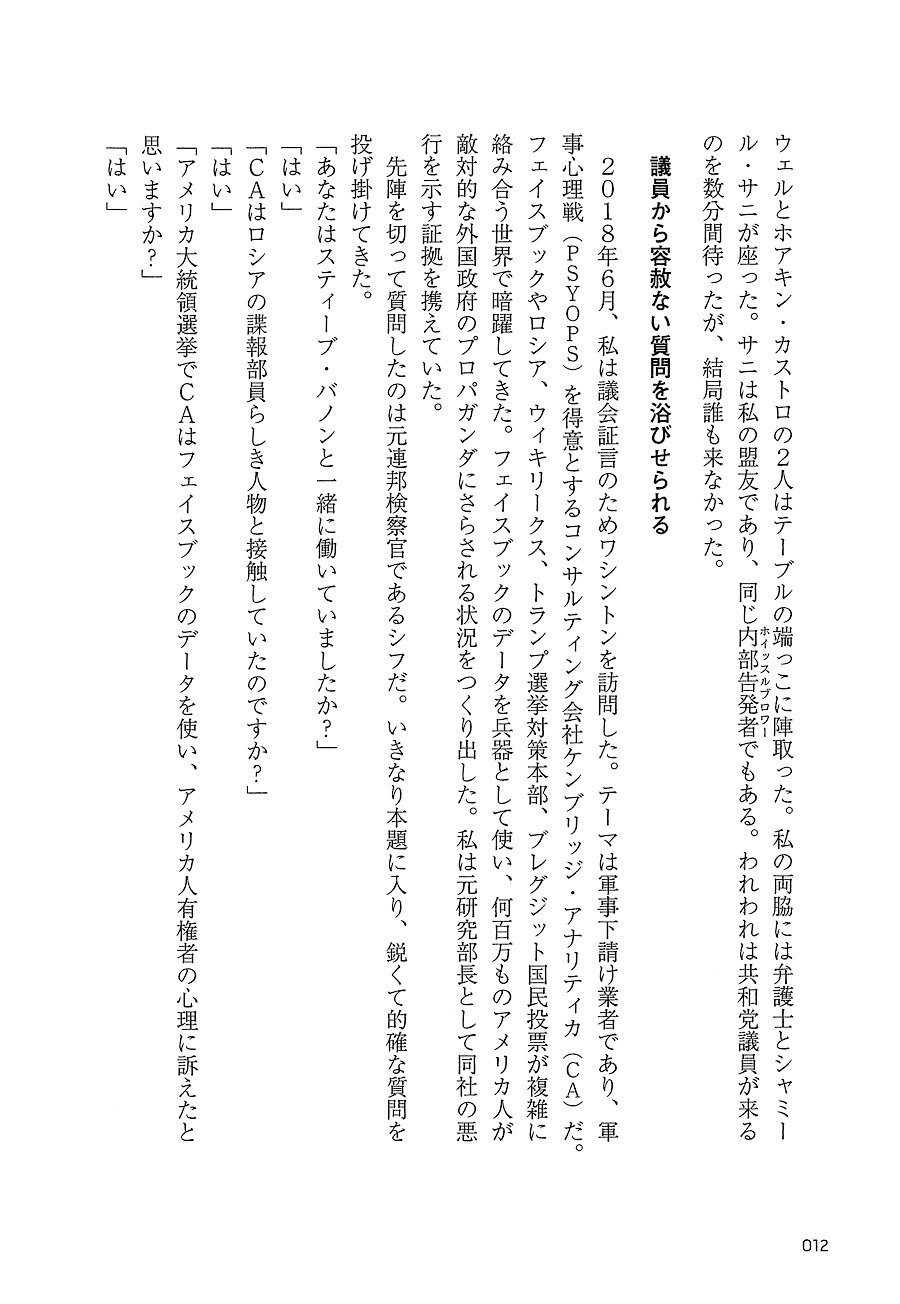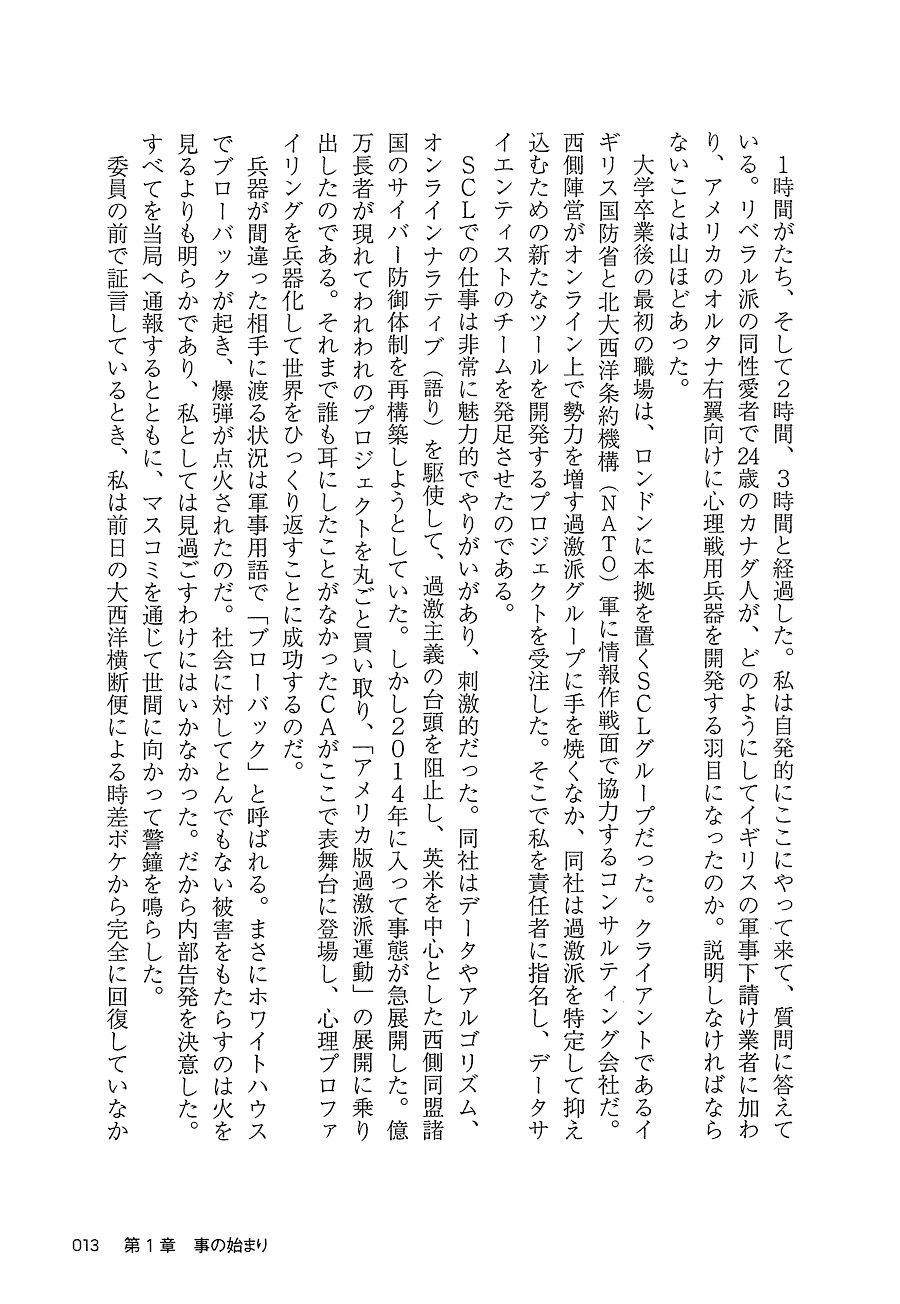軍隊の侵入は防げるが、思想の侵入は防げない
第1章 GENESIS
事の始まり
アメリカ連邦議会議事堂の地下で
新品の靴を履いてきたから、一歩踏み出すたびに靴擦れしてかかとが痛む。胸に抱えたダークブルーのバインダーには、色付きラベルで仕分けした大切な文書を詰め込んである。今自分がどこにいて、どこに向かっているのかを考えると、恐れ入ってしまう。とりあえずわれわれ一行の足音にのみ集中して歩こう。ところが、係員からは「誰かに見られるかもしれないから、もう少し急ぎましょう」と急かされる。
制服を着た警備員の前を通り過ぎると、吹き抜けの空間に出た。その先の廊下を曲がって進み、係員が押し開けたドアを抜け、階段を急ぎ足で下りる。すると再び廊下だ。大理石の床、高い天井、星条旗を掲げた木製ドア──。さっきの廊下とうり二つである。
われわれ一行は7人で、歩くたびに足音が廊下全体に響き渡る。目的地まであと少しのところで捕まってしまった。ある下院議員が私を見つけ、手を振っている。「もう戻って来たのかい?」。記者会見場からは記者の一団が飛び出してきた。エレクトリックピンクの頭髪を目にして、すぐに私が誰なのか分かったようだ。
2人のカメラマンが私の前に現れて、後ろ向きに歩きながら撮影し始めた。ぶら下がり取材だ!「ワイリーさん、NBCテレビです! 質問いいですか?」「CNNテレビです! 何でここにいるのですか?」──。記者たちから矢継ぎ早に質問を浴びせられる。弁護士からは何もしゃべるなと指示されていたので、質問はすべて無視した。係員は記者たちに向かって「近づかないで」と注意し、私にはエレベーターへ向かうよう促した。われわれはエレベーターの中になだれ込み、ドアが閉まるのを待った。カメラマンはなおもシャッターを切っていた。
私はスーツ姿の男に囲まれてエレベーターの奥に押し込まれた。地下深くに向かって降りていく間、誰もが黙ったままだ。私は頭をフル回転させていた。事前に弁護士と打ち合わせした内容を思い出そうとしていたのだ。アメリカのどの法律に誰が違反したのか? アメリカを訪問中の外国人である私にはどんな権利があり、どんな権利がないのか? 非難を浴びたときにどうやって落ち着いて反応するのか? その後逮捕されたらどうなるのか? 何が待ち受けているか予想もできない。誰もがそうだっただろう。
エレベーターが止まり、ドアが開いた。そこには何もない。いや、もう一つのドアがある。ドアには赤くて大きい看板が掛けられて、白抜きの文字で「一般人及びマスコミは立ち入り禁止」と書かれている。われわれは首都ワシントンにあるアメリカ連邦議会議事堂の地下3階に着いたのだ。
ドアを抜け、マルーン色のぜいたくなフラシ天のカーペットの上に足を踏み出した。すると、われわれが所持する携帯電話など電子機器類は警備員によって取り上げられ、机の後ろにある棚の中に置かれた。われわれにはそれぞれの棚にひも付いた番号札が手渡された。警備員は「これより先は紙と鉛筆しか持ち込めません」と言い、機密に該当するような情報をメモしないよう警告した。「そのようなメモは退出時に没収されます」
警備員は2人で巨大な鋼鉄製ドアを開けた。そのうちの一人が付いてくるように合図している。われわれは1人ずつ中に入ると、蛍光灯で照らされた薄暗くて長い廊下に出た。こげ茶色のウッドパネルが貼られた壁に沿って、多数の星条旗が整然と立てられている。古い建物の匂いが充満している。ムッとしてかび臭くて、わずかに洗剤の香りが混じっている。
警備員に連れられてわれわれは廊下を進み、左に曲がるとまたしてもドアに突き当たった。ドアの上には木製の国章。爪で矢をつかんだ巨大な白頭ワシが上からにらみ付けている。ここが目的地だ。下院情報特別委員会用の機密情報隔離施設(SCIF)──。そう、機密情報に絡んだ議会証言が行われるときに使われる部屋である。
中に入ると、蛍光灯が放つまぶしい光で目がくらんだ。目が慣れてくると、そこはまったく特徴のない部屋だった。ベージュ色の壁には何の飾りもなく、中央には会議机と椅子が置かれているだけ。ワシントン中にくまなく建てられた無機質な連邦ビルの中のどの部屋も同じなのだろう。そんなことよりもSCIF内の静けさに驚いた。何重もの壁で防音対策が施され、盗聴の心配はない。防音だけでなく耐爆の面でも完璧らしい。セキュリティーは万全で、アメリカの機密保持には最適な場所だ。
われわれが着席すると、委員会メンバーの議員が続々と入ってきた。議員秘書がせわしなく動き、テーブルの上に各議員用のタブ付きバインダーを置いた。私の正面に座ったのは民主党の大物でカリフォルニア州選出のアダム・シフ。彼の左隣にはテリ・スウェル、女性議員だ。エリック・スウォルウェルとホアキン・カストロの2人はテーブルの端っこに陣取った。私の両脇には弁護士とシャミール・サニが座った。サニは私の盟友であり、同じ内部告発者でもある。われわれは共和党議員が来るのを数分間待ったが、結局誰も来なかった。
議員から容赦ない質問を浴びせられる
2018年6月、私は議会証言のためワシントンを訪問した。テーマは軍事下請け業者であり、軍事心理戦(PSYOPS)を得意とするコンサルティング会社ケンブリッジ・アナリティカ(CA)だ。フェイスブックやロシア、ウィキリークス、トランプ選挙対策本部、ブレグジット国民投票が複雑に絡み合う世界で暗躍してきた。フェイスブックのデータを兵器として使い、何百万ものアメリカ人が敵対的な外国政府のプロパガンダにさらされる状況をつくり出した。私は元研究部長として同社の悪行を示す証拠を携えていた。
先陣を切って質問したのは元連邦検察官であるシフだ。いきなり本題に入り、鋭くて的確な質問を投げ掛けてきた。
「あなたはスティーブ・バノンと一緒に働いていましたか?」
「はい」
「CAはロシアの諜報部員らしき人物と接触していたのですか?」
「はい」
「アメリカ大統領選挙でCAはフェイスブックのデータを使い、アメリカ人有権者の心理に訴えたと思いますか?」
「はい」
1時間がたち、そして2時間、3時間と経過した。私は自発的にここにやって来て、質問に答えている。リベラル派の同性愛者で24歳のカナダ人が、どのようにしてイギリスの軍事下請け業者に加わり、アメリカのオルタナ右翼向けに心理戦用兵器を開発する羽目になったのか。説明しなければならないことは山ほどあった。
大学卒業後の最初の職場は、ロンドンに本拠を置くSCLグループだった。クライアントであるイギリス国防省と北大西洋条約機構(NATO)軍に情報作戦面で協力するコンサルティング会社だ。西側陣営がオンライン上で勢力を増す過激派グループに手を焼くなか、同社は過激派を特定して抑え込むための新たなツールを開発するプロジェクトを受注した。そこで私を責任者に指名し、データサイエンティストのチームを発足させたのである。
SCLでの仕事は非常に魅力的でやりがいがあり、刺激的だった。同社はデータやアルゴリズム、オンラインナラティブ(語り)を駆使して、過激主義の台頭を阻止し、英米を中心とした西側同盟諸国のサイバー防御体制を再構築しようとしていた。しかし2014年に入って事態が急展開した。億万長者が現れてわれわれのプロジェクトを丸ごと買い取り、「アメリカ版過激派運動」の展開に乗り出したのである。それまで誰も耳にしたことがなかったCAがここで表舞台に登場し、心理プロファイリングを兵器化して世界をひっくり返すことに成功するのだ。
兵器が間違った相手に渡る状況は軍事用語で「ブローバック」と呼ばれる。まさにホワイトハウスでブローバックが起き、爆弾が点火されたのだ。社会に対してとんでもない被害をもたらすのは火を見るよりも明らかであり、私としては見過ごすわけにはいかなかった。だから内部告発を決意した。すべてを当局へ通報するとともに、マスコミを通じて世間に向かって警鐘を鳴らした。
委員の前で証言しているとき、私は前日の大西洋横断便による時差ボケから完全に回復していなかった。容赦ない質問を浴びせられ、次第に混乱していった。複雑怪奇なCAの業務内容を細かく説明すると、議員団を困惑顔にさせるばかりだった。そこでバインダーを取り出して机の上に置き、議員団側へどんと押し出した。さあ、どうぞご自由に読んでください! もうここまで来てしまったのだから、すべてをさらけ出してもいいじゃないか、と思った。
証言中に休憩はない。背後のドアは閉められたまま。ここは地下空間で窓は一つもなく、空気がよどんでいる。正面に座る議員団を直視する以外、目のやり場もない。そんななか、議員団は自分たちの国に一体何が起きたのか、必死で理解しようとしている。
歴史的なデータ犯罪捜査始まる
SCIF内で行った議会証言の3カ月前、2018年3月17日のこと。英ガーディアン紙、米ニューヨーク・タイムズ紙、英公共テレビ「チャンネル4」の3メディアは1年に及ぶ共同取材の成果を一斉に特報した。起点は私の内部告発だ。私はCAとフェイスブックの内部で起きていたことについて真実を暴こうと決意し、マスコミの協力を得たのである。
これによって歴史的なデータ犯罪捜査が始まった。史上最大のスケールだ。イギリス側では国家犯罪対策庁(NCA)、MI5(諜報機関)、情報コミッショナー事務局(ICO)、選挙委員会、ロンドン警視庁、アメリカ側では連邦捜査局(FBI)、司法省、証券取引委員会(SEC)、連邦取引委員会(FTC)が捜査に加わった。
第一報が放たれる数週間前、アメリカでは特別検察官ロバート・モラーによる捜査が大詰めを迎えていた。この年の2月、アメリカ大統領選挙への介入で共謀したとして、モラーはロシア市民13人とロシア企業3社の起訴に踏み切っていた。1週間後にはトランプ陣営の選対本部長を務めたポール・マナフォートと側近のリック・ゲイツの2人を追起訴。一方、3月16日には司法長官ジェフ・セッションズがFBI副長官のアンドリュー・マケイブを解雇した。マケイブは年金受給資格を得られるまであと24時間ちょっとであったのに、である。
誰もがトランプ陣営とロシアの間で何が起きたのかを知りたがっていた。しかし、点と点を結んで全体像を描ける人は皆無だった。そんな状況で私は証拠を提出した。これによって、ドナルド・トランプやフェイスブック、ロシア諜報機関、国際ハッカー集団、イギリスの欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)がCAとつながった。得体の知れない外資系下請け業者でしかないCAが非合法活動に走って、トランプ陣営とブレグジット陣営に勝利をもたらす構図が浮き上がったのだ。
無数の電子メール、内部メモ、請求書、銀行取引明細、プロジェクト文書──。私が用意した証拠を点検すれば、トランプとブレグジットの両陣営が同じ戦略を取り、同じテクノロジーを使い、同じ人的ネットワークに依拠していたのは明白だ。しかも、背後ですべてを操っていたのはロシアの勢力だったのである。
第一報が出てから2日後、イギリス議会の下院は緊張した雰囲気に包まれ、異例の行動に出た。与党の主要大臣と野党の最高幹部が一致団結し、フェイスブックを糾弾したのだ。ガーディアンなど3メディアが明らかにしたのは、フェイスブックのプラットフォームが悪用され、敵対的なプロパガンダを展開するマシンと化していたということだ。結果として外部勢力が選挙に介入し、西側民主主義を危機に陥れた。
続報はブレグジットに焦点を合わせ、国民投票の正当性に疑問符を付けた。私が捜査当局へ提出した証拠書類によれば、ブレグジット陣営は国民投票に向けてCAの秘密子会社にカネを払い、フェイスブックとグーグル上で偽情報を拡散させた。イギリス選挙委員会の基準に照らし合わせれば、間違いなく違法行為であり、最終的にはイギリス史上最大かつ最悪の選挙法違反の一つとなった。
ブレグジット陣営の脱法行為を示す証拠が公になると、イギリス首相公邸があるダウニング街10番地は蜂の巣をつついたような騒ぎになった。国民投票期間中にブレグジット陣営がロシア大使館と直接接触していた事実が判明し、証拠書類がNCAとMI5へ送られた。1週間後、フェイスブックは18%の株安に見舞われ、総額800億ドルの株式時価総額を失った。アメリカ企業が1日で失った時価総額としては史上最大だった。
2週間ぶっ続けでテレビ出演
2018年3月27日、私はイギリス議会へ呼ばれて生中継の公聴会で証言した(このあと数カ月間、あちこちで引っ張りだこになり、公の場で語ることに何のためらいも感じなくなった)。CAによるハッカー集団の利用、フェイスブックの情報漏洩に絡んだ賄賂、ロシアの諜報活動──。話題は多岐にわたった。公聴会を受けてアメリカ側では捜査当局(FBI、司法省、SEC、FTC)が一斉に調査に乗り出した一方で、上下両院の各種委員会(下院情報特別委員会、下院司法委員会、上院情報特別委員会、上院司法委員会)が「話を聞きたい」と私に接触してきた。数週間以内にEUのほか世界20カ国以上がフェイスブックなどソーシャルメディアやフェイクニュースに対する調査を開始した。
私は全世界に向けて自分の物語を語っていた。そのうち、テレビ画面が自分自身の姿を映し出す鏡であるかのような錯覚を抱くようになった。無理もない。2週間ぶっ続けでテレビに出ずっぱりで、カオス状態だったのだ。ロンドン時間の早朝6時からヨーロッパ各国のテレビ番組に出演したのに続いて、アメリカのテレビ番組に舞台を移して深夜までインタビューに対応することもあった。どこに行ってもマスコミに追い掛け回され、そのうち脅しも受けるようになった。身の危険を感じ、公のイベントに出る際にはボディーガードを雇うようにした。開業医である私の両親も影響を受けた。大勢の記者がクリニックに押し寄せ、患者をおびえさせるので、一時的に閉院せざるを得なくなった。私は何カ月にもわたって目が回るほど翻弄され、お手上げ状態になった。でも分かっていた。警鐘を鳴らし続けなければならない。それができるのは自分だけなのだ。
どのようにして大衆のアイデンティティーと行動が商品化され、データ業界に大きな利益をもたらすようになったのか──これがCAの物語である。情報の流れを支配する企業は「世界最強企業」と呼んでもいい。秘密裏に構築したアルゴリズムを武器として使い、今まで誰も想像できなかったようなやり方で、世界中の人々の思考に影響を与えているのだ。
関心のあるテーマは人によってさまざまだ。銃規制や移民があり、言論の自由や宗教の自由がある。でも、テーマが何であっても「知覚危機の震源地」シリコンバレーから逃れられない。私がCA時代の仕事で明らかにしたのはシリコンバレー流イノベーションの暗部だ。CA、オルタナ右翼、ロシアの3勢力それぞれがイノベーションを起こし、世界に衝撃を与えた。では、3勢力のイノベーションを世の中に解き放ったのは誰なのか。フェイスブックである。そう、あなたが飲み会への誘いや赤ちゃんの写真をシェアするために使っているソーシャルメディアのことである。
12歳で車椅子生活
私がもし違う体に生まれていたら、テクノロジーに関心を持たなかったかもしれないし、CAへの就職も考えなかったかもしれない。子ども時代、コンピューター以外にやることがあまりなかったのだ。
生まれ育ったのは海と森と農場に囲まれたバンクーバー島。カナダ西部ブリティッシュコロンビア州の太平洋沖に浮かぶ島である。両親は開業医で、私は長男。2人の妹ジェイミーとローレンがいた。11歳の時、足がどんどん硬直していき、ほかの子どもと同じように走れなくなった。歩き方も変になり、いじめに遭うようになった。病院で診てもらうと、二つの奇病を患っていることが判明した。症状には極度の神経障害痛や筋衰弱、視力低下、聴力低下が含まれた。12歳になるころには車椅子生活を強いられた。ちょうど思春期を迎えようとしていたというのに、である。以後の学校生活ではずっと車椅子と一緒だった。
車椅子で生活していると、普通とは違うように扱われるものだ。時に人間というよりも物のように見られている気分になる。仕方がないのかもしれない。周囲の関心は、私がどうやって移動しているのかという一点に集中しがちだからだ。車椅子に乗っていれば、建物に入るときには常に特別な方法を見いださなければならない。どの入口なら入れるだろうか? 階段を避けながら目的地に到達できるだろうか? 普通の人ならば想像もしないようなことを考えなければならないのだ。
学校でコンピューター室を発見すると「これこそが自分の居場所だ」と思うようになった。コンピューター室に居る限りはもはや疎外感を味わわずに済んだ。ここから一歩外に出ればクラスメートにいじめられるか、恩着せがましい職員の相手をする羽目になるか、そのどちらかであった。教師は教室内で「クリスと仲良くしましょう」と呼び掛けていたが、義務感で生徒を指導しているにすぎなかった。私にとっては無視される以上にうっとうしかった。コンピューター室が自分の居場所になるのも当然の成り行きだった。
13歳になると自分でウェブページを作成するようになった。最初のウェブサイトは、ドジなクルーゾー警部に追い回されるピンク・パンサーの動画で、Flash形式のアニメーションだった。間もなくして、プログラミング言語JavaScriptで書かれたゲーム「三目並べ(〇×ゲーム)」のビデオを目にした。すごいと思った。3×3の升目に〇と×を並べていくゲームは至ってシンプルに見えるのに、背後にあるロジックを考えると実はそうでもない。コンピューターに適当に升目を選ばせると、ゲームが退屈になってしまう。面白くするためには一定のルールに従ってコンピューターを誘導しなければならない。例えば、「×の隣の升目に×を書き込め。ただし〇がすでに並べられている縦線と横線は回避しろ」と指示する。では、対角線上に並べられた×は? どのように説明したらいいのか。
結局、私は数百行に上るスパゲティコード(制作したプログラマー以外には解読困難なコード)を書き、「三目並べ」を完成させた。自分の創造物と最初にゲームをプレーしたときの感覚を今でも思い出せる。私が升目に〇を書き込むと、それに反応して自分の創造物が別の升目に×を書き込むのだ。まるで自分が魔法使いにでもなったかのような気分になれた。プログラミングの練習をすればするほど、自分の魔力を強くできるのだ。
コンピューター室の外に出ると、魔力を封じられてしまった。学校は生徒に対して「障害者ができないこと」と「障害者がやってはいけないこと」を教えていたし、「障害者が決してなれない人物」を理想像として示していた。15歳になるときに両親は心配して、私が居場所を見いだせるような学校を勧めてくれた。そこで2005年の夏、全寮制のインターナショナルスクール「ピアソンカレッジ」で過ごした。ブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアにある同校は、元首相レスター・B・ピアソンの名前を冠している。ピアソンは1950年代のスエズ動乱に際して世界初の国連平和維持軍を考案したとして、ノーベル平和賞を受賞した政治家だ。
ピアソンはエキサイティングだった。世界中から大勢の生徒が集まり、多様性に富んでいたからだ。私は生まれて初めて授業に真面目に出るようになったし、やはり生まれて初めてクラスメートの話を聞くようになった。例えば、ルワンダ虐殺の生き残りと友達になれた。ある晩に学生寮で彼の話に熱心に耳を傾けた。彼は子どものころに虐殺によって家族を失い、一人でウガンダの難民キャンプまで歩いたそうだ。衝撃的だった。
授業をサボってタウンホールミーティングに
本当の転機はその後に訪れた。学生食堂で夕食を終えると、パレスチナ人とアラブ人の生徒がイスラエル人の生徒と向き合い、祖国の未来について白熱した議論をしている光景を目にした。世界ではこんな大変なことが起きているというのに、これまでほとんど何も知らなかったことを痛感した。これをきっかけに一気に政治に興味を持つようになった。
新学期が始まると授業をサボって、地元政治家とのタウンホールミーティングに顔を出すようになった。学校内ではめったにしゃべらなかったのに、タウンホールミーティングでは自分の意見を表明することにためらいを感じなかった。授業とタウンホールミーティングは全然違う。前者は受動的だ。私は教室の後ろに座り、「こうやって考えなさい」「これを勉強しなさい」などと指導する教師に従うだけ。カリキュラムが事前に用意され、教育指導方法が決められているのだから仕方がない。後者は正反対だった。確かに政治家は教師と同様に壇上に立っている。でも、主役は聴衆であり、聴衆が政治家に対して「われわれはこう考える」と伝えるのである。これが信じられないほど面白かった。なので、地元政治家が「タウンホールミーティングを開催します」と発表すれば、私は必ず参加した。参加したら質問するだけでなく自分の考えを語った。
自分自身の「声」を発見すると、解放された気分になった。自分が誰であるのか知りたいという点では、普通のティーンエージャーと変わらなかったのだ。だが、ゲイであり車椅子で生活しているとなると、普通よりも高いハードルを越えなければならない。多くのタウンホールミーティングに参加して分かったことがある。これまでの人生で経験してきたことの大部分は、単なる「個人的問題」ではなく「政治的問題」でもあるということだ。
私が直面する試練も、私が送っている人生も、さらには私の存在そのものも政治的なのだ! となれば自分自身が政治的になるほかない。運良く元ソフトウエアエンジニアのジェフ・シルベスターが声を掛けてくれた。カナダ議会議員のアドバイザーを務めており、タウンホールミーティングに欠かさず参加して発言する青年──私のこと──に興味を抱いたのだ。結局、テクノロジーに明るい人材を探していたカナダ自由党(LPC)に私を紹介してくれた。私はすぐに正式に雇われ、夏の終わりから首都オタワのカナダ議会に通ってLPCの政治アシスタントとして働き始めた。
2007年の夏、私はモントリオールでハッカーのたまり場に足しげく通い、フランス系カナダ人のテクノアナーキストと交わるようになった。たまり場は工場跡地であり、床はコンクリートで壁はベニヤ板だった。部屋の中はアップルIIやコモドール64などレトロなテクノロジー製品で飾られていた。そのころには治療の効果もあり、私は車椅子なしで歩けるようになっていた(体の状態は改善に向かっていたとはいえ、内部告発に伴う激務に耐えられるほどではなかった。CAの暗部を暴く第一報が放たれる直前のことだ。私は発作を起こし、サウスロンドンの歩道で意識不明になって倒れ込んだ。ユニバーシティカレッジ病院へ運ばれ、腕に静脈注射を打たれる激痛で目覚めた)。どんな格好をしていても、あるいはどんなに奇妙な歩き方をしていても、誰からも変に思われなかった。ハッカーはテクノロジーへの情熱を仲間と共有し、手助けしたいだけだったのだ。
どんなシステムも絶対的ではない、難攻不落の存在はない、乗り越えられない障害はない──。私はハッカー集団と一時期を共に過ごしたことで、確固とした信念を持つようになった。自分の見方を変えれば、どんなシステムにも欠陥や脆弱性を見いだせると、ハッカー哲学は教えてくれた。コンピューターやネットワークはもちろん、たとえ社会そのものであっても。私は車椅子に座るゲイの若者として、人生の早い段階で権力のシステムを理解するようになった。そしてハッカー集団に加わったことでもう一つ学んだ。あらゆるシステムには弱点があり、いずれ食い物にされるのである。
新風吹き込むオバマ陣営に魅了される
私がカナダ議会で働き始めて間もないころ、LPCはカナダの南側──アメリカ──で起きている新たなイノベーションに関心を寄せた。フェイスブックが大衆の間で流行し、ツイッターが勢いに乗り始めるなど、ソーシャルメディアが勃興しつつあったのだ。ただし、選挙戦でどのようにソーシャルメディアを使ったらいいのかについては、誰も明確な考えを持っていなかった。そうしたなか、大統領選挙で人気急上昇中だった民主党候補バラク・オバマがソーシャルメディアの活用にアクセルを踏んだのだ。
候補者の多くがインターネットの活用に戸惑うばかりで、有効な戦略を打ち出せないでいるなか、オバマ陣営はウェブサイト「My.BarackObama.com」を立ち上げて草の根革命を起こし始めた。ヒラリー・クリントンをはじめ他候補もウェブサイトを持っていたものの、従来型の選挙広告に特化していた。対照的にオバマ陣営のウェブサイトは草の根団体向けのプラットフォームとして機能し、投票推進運動を盛り上げていた。オバマはイリノイ州選出の上院議員として1期目であり、他候補よりもずっと若くてテクノロジーに明るかった。ウェブサイトをテコに草の根レベルで熱狂を呼び起こし、リーダーとしてうってつけの人物に見えた。
私は自分の限界を思い知らされながら成長期を過ごした。それだけに、単純なメッセージ「イエス・ウィー・キャン!(やればできる!)」に込められた挑戦的楽観主義にすぐに魅了されてしまった。オバマ陣営は政治の世界に新風を吹き込んでいたのだ。そんなとき──私は18歳になっていた──LPCのアメリカ調査団に加わり、オバマ陣営の選挙戦略を見極める役割を担った。オバマ陣営から斬新な戦略を学び取り、カナダでの選挙に生かすのだ。
アメリカでは当初、ニューハンプシャー州など早期に予備選が行われる州を訪ねた。有権者に話し掛け、アメリカの文化を間近で見ようとした。楽しかったし、多くの発見もあった。同じ北米に属しながらアメリカ人とカナダ人がこれほど異なる感性を持ち合わせているとは、夢想だにしていなかった。例えば、「国民皆保険に反対」と主張するアメリカ人に出会い、非常に驚いた。カナダでは国民皆保険にほぼ毎月お世話になっていただけに、なぜなのかにわかには理解できなかった。もっとも、多くの有権者に会ううちに同じような話を100回も聞かされ、最後には大して驚かなくなった。
あちこちうろついて人々に話し掛けるのは楽しくて仕方がなかった。それだけに、「そろそろデータ班に加わってもらおうか」と言われたときにはあまり喜べなかった。でも、オバマ陣営のターゲティング責任者ケン・ストラスマを紹介され、すぐに考えを改めた。
オバマ陣営の戦略でとりわけ魅力的なのはブランディングだ。ユーチューブのような新メディアの利用もうまい。これは本当にカッコ良かった。ユーチューブは誕生して間もなかったから、オバマが登場するまで誰もビジュアルに訴える戦略を採用していなかった。これこそアメリカで見たかったものだ。ところがケンから「ビデオは忘れろ」と言われた。ケンによれば、ビジュアルだけではオバマ陣営のテクノロジー戦略の核心に迫れない。ではどうすればいいのか。大前提としてあるのは、何をテーマにして誰に話し掛けなければならないのかを正確に見極めることだという。
選挙運動にAI利用
言い換えると、オバマ陣営の核心にあるのはデータなのだ。ストラスマのチームが生み出した最大の成果はデータ分析モデルの構築である。このモデルを使えば、オバマ陣営はデータから意味を読み取って現実の広報戦略へ適用できる。つまり人工知能(AI)を導入していたのだ。ちょっと待ってくれ……選挙運動用のAI? 有権者に関する情報を貪欲に取り込み、ターゲティングの基準を教えてくれるロボットの誕生? SFの話ではないか? だが、現実に起きていた話だ。モデルが取り込んだ情報はオバマ陣営の上層部に届き、そこでどんなメッセージを使ってどんなブランディングを展開するのかが決まったのである。
データ処理のインフラはどうしていたのか。オバマ陣営が利用していたのは、ボストン出身の愉快な同性愛カップル──マーク・サリバンとジム・セントジョージ──が運営するコンピューターネットワーク「有権者活性化ネットワーク(VAN)」だった。2008年の大統領選挙が終わるころには、民主党全国委員会が保有する有権者データは04年の大統領選挙時の10倍に達していた。ひとえにVANのおかげである。民主党は膨大な有権者情報を蓄積したデータベースに加えて、データを分類して活用するツールを備えていた。そのため、民主党候補に投票してくれそうな有権者を投票所へ向かわせるうえで決定的に有利になったのである。
私は知れば知るほどオバマ陣営のデータ戦略に魅せられていった。あまりにも知りたいことが多く、マークとジムの2人を質問攻めにしなければならなかった。幸いにも2人は、若いカナダ人がアメリカにやって来てデータと政治について知りたがるのを面白いと思ったようで、快く対応してくれた。
ケン、マーク、ジムの3人に出会うまでは、選挙運動で数学やAIを使う状況を思い浮かべたこともなかった。実のところ、オバマ陣営の選対本部でコンピューターの前に並ぶ人々を最初に見たとき、「選挙に勝つために重要なのはメッセージと情熱であって、コンピューターと数字ではないはずだ」と思ったものだ。実際は違った。過去の大統領候補と比べてオバマが決定的に異なっていたのは、数字──それに予測アルゴリズム──を活用していた点だ。
オバマ陣営が効果的にアルゴリズムを利用してメッセージを発しているのを見て、私も自分でアルゴリズムを書きたいと思って勉強を始めた。自力で数値解析ソフト「MATLAB」や予測分析ソフト「SPSS」などの利用法を学び、データいじりに没頭するようになった。教科書には頼らなかった。統計を学ぶための古典的データセット「IRIS(アヤメ)」を使い、試行錯誤の独学から始めた。花びらの長さや色などさまざまなデータを操って、花の品種を予測するのだ。たちまちはまってしまった。
基本を理解し終わると、分析対象を花びらから人間へ切り替えた。VANは人間に関する情報の宝庫である。年齢、ジェンダー、所得、人種、持ち家の有無はもちろんのこと、雑誌の定期購読や航空会社のマイレージポイントまで分かる。正しいデータを入力すれば、当該人物が民主党と共和党のどちらに投票するのかを予測し、当該人物にとって最も重要そうなテーマを特定できる。そのうえで、当該人物の意見に影響を与えるための効果的なメッセージを考案することも可能になる。
データの活用によって、まったく新しい方法で選挙を理解できるようになる、と私は思った。データはオバマ陣営の選挙運動に力を与え、世の中を良くできる。疎外感を抱いている人々にメッセージを送り、投票所へ行くよう促せる。私は知れば知るほど「データは政治の救世主になる」との確信を深めた。そのうち一刻も早くカナダに戻って本部に出向き、次期アメリカ大統領から学んだ新たな知見を共有したいと思うようになった。
11月になってオバマは大統領選挙で共和党候補のジョン・マケインを破り、地滑り的勝利を収めた。それから2カ月後、オバマ陣営の友人からもらった大統領就任式への招待状を手にしてワシントンへ飛び、民主党支持者が結集するディナーパーティーに出席した(パーティー会場の受付ではちょっとしたトラブルに巻き込まれた。21歳未満であると告げると、うろたえたスタッフに制止されたのだ。会場内にはアルコール飲料が提供されるオープンバーがあるのが理由だった)。パーティーは信じられないほど楽しかった。ミュージシャンのジェニファー・ロペスやマーク・アンソニーとおしゃべりできたし、オバマ大統領夫妻の初ダンスも拝めた。リーダーにふさわしい人物がデータを活用して、近代的選挙戦に臨んだら何が起きるのか──。新しい時代の幕開けだ。祝杯を挙げないわけにはいかない。
プライベート空間で政治メッセージ
懸念材料もあった。オバマ陣営は特定の有権者に対して特定のメッセージを直接届けるマイクロターゲティングで成功した。マイクロターゲティングを全面展開すると、政治的メッセージを世の中に向かって広く発信するのではなく、プライベート空間に閉じ込める格好になる。プライベート空間で発せられる政治的メッセージという点では、古くからアメリカの選挙運動で使われてきたダイレクトメールも同じである。とはいえ、データを駆使したマイクロターゲティングは次元が違う。数千万人の有権者がいれば、数千万種類の政治的メッセージを作って送れる。個々の有権者はそれぞれの属性に合ったメッセージを受け取るわけだ。メッセージの内容は有権者によって千差万別であり、あなたが受け取るメッセージは隣人が受け取るメッセージと似ても似つかないかもしれない。だからといってどちらかが得するわけでもない。
選挙運動がプライベート空間で行われるとどうなるだろうか。政治家は公の場から姿を消し、監視されにくくなる。アメリカ民主主義の土台であるタウンホールミーティングは徐々に表舞台から退き、オンライン上を流れるデジタル広告に取って代わられる。監視がなくなれば、政治的メッセージはもはや政治的メッセージのように作られる必要もなくなる。オバマ陣営がお手本を示したように、ソーシャルメディアはまったく新しい環境を生み出した。われわれは友人から送られてくるメッセージを読むのと同じ感覚で、ソーシャルメディア経由の政治的メッセージを読む。送り主の正体や意図に気付かないままに、である。
ソーシャルメディア上で流れる選挙運動のメッセージは、ニュースサイトや大学、公的機関などからのメッセージと似てくるだろう。ソーシャルメディアの影響力が増すと、有権者は選挙広告に全幅の信頼を寄せてしまってもおかしくない。ここに問題が潜んでいる。ソーシャルメディアの中にあるプライベート広告ネットワークには、誤りを指摘してくれる第三者が存在しない。つまり、有権者はうそをつかれても簡単には気付けないのだ。
オバマ政権誕生の数年前から、シリコンバレーで新たなビジネスモデルが出現しつつあった。テクノロジー企業が蓄積する膨大なデータが利益を生み出し始めたのだ。このビジネスモデルの根幹にあるのが情報の非対称性だ。コンピューターはわれわれの行動について熟知しているというのに、われわれはコンピューターが何をしているのかほとんど何も知らない。
テクノロジー企業は情報サービスを提供し、見返りとしてより多くの情報──つまりデータ──を求めている。データの価値はますます高まっている。フェイスブックを見てみよう。1億7千万人に上るアメリカ人ユーザーから1人当たり平均で30ドルの利益を得ている。収集したデータを駆使して消費者行動に影響を与え、大きな利益を生み出しているのだ。われわれはテクノロジー企業の情報サービスをタダで利用しているわけではなく、自分自身の個人データを対価として払っている。
データが蓄積されるほど利益が増える。だから当然の成り行きとして、ユーザーにシェアを促す仕組みが導入された。フェイスブックなどのプラットフォーマーはカジノのまねをして、「無限スクロール」のようなイノベーションを起こしたり、脳内報酬系に作用する中毒性のある機能を導入したりした。グーグルの「Gメール」のようなサービスは、われわれのメールのやり取りをくまなく探り回るようになった。昔ながらの郵便配達人であったなら刑務所送りになるのは間違いない。われわれのスマートフォンにはGPS(全地球測位システム)装置が組み込まれた。GPS装置といえば、かつては罪人の足首に着けられたアンクレットと相場が決まっていた。さらには、現在普及している無数のアプリには、昔ならばおそらく「盗聴」と見なされた機能が標準で組み込まれている。
そんななか、われわれは何のためらいもなく、日常的に自分の個人情報をシェアするようになった。一つにはキャッチーな言葉に踊らされているからだろう。事実上の監視ネットワークとして運営されるソーシャルメディアは「コミュニティー」、ソーシャルメディア参加者は営利目的で利用される側だというのに「ユーザー」、中毒性の高い機能は「ユーザーエクスペリエンス」あるいは「エンゲージメント」と呼ばれる。一方で「パンくずリスト(ユーザーがウェブサイト内のどの位置にいるのかを示すリスト)」や「排気データ(デジタル活動の副産物として生まれるデータの痕跡)」によって、われわれのアイデンティティーがプロファイリングされている。
「素早く行動して破壊せよ」に踊らされる
過去数千年を振り返ると、人間社会はもっぱら天然資源を採掘して商品へ転換するビジネスモデルに依拠してきた。綿から糸を紡いで織物にする、鉱石を製錬して鉄鋼にする、森を伐採して木材にする──。ところが、インターネットの登場によってまったく新しいビジネスモデルが生まれた。われわれ自身──行動パターン、関心事、アイデンティティー──を商品へ転換するビジネスモデルだ。データと産業が合体した複合体の原材料は、われわれ自身なのである。
新時代の政治的ポテンシャルをいち早く見抜いた一人がスティーブ・バノンだ。知名度はいまひとつでありながらも、ニュースサイト「ブライトバート・ニュース」の編集長を務めていた。愛国主義者アンドリュー・ブライトバートの信条に従ってアメリカ文化の再構築を目指す同サイトを率い、「文化戦争」を自分の使命と考えていた。ただし──彼との初面会時に私は直接確認したのだが──自分たちが文化戦争遂行のための有効な兵器を備えていないということも理解していた。軍事指揮官が「砲撃力」と「空域制圧」に注力するように、「文化力」と「情報制圧」に注力する必要性を認識していた。新時代の戦場で人心をつかむためのデータ兵器庫を求めていたと言ってもいい。
新設のCAこそデータ兵器庫に相当した。同社は軍事心理戦のテクニックに磨きをかけることで、バノン流オルタナ右翼の反乱活動を大成功に導いた。文化戦争で犠牲になったのはターゲットにされたアメリカ人有権者だ。知らぬうちに惑わされ、操られ、だまされた。事実の代わりに「代替的事実」や「仮想現実」を見せられ、真実の代わりに「ポスト真実」を見せられたのである。
CAは最初の実験場所としてアフリカと南国諸島を選んだ。まずは選挙戦に介入してオンライン上で偽情報やフェイクニュースを大量に流すとともに、住民を対象に大規模なプロファイリングを実行。ロシアの諜報部員と協力関係を築く一方でハッカー集団を雇い入れ、対立陣営の電子メールアカウントにも侵入した。西側メディアの関心が及ばないような外国を舞台にして文化戦争のテクニックに磨きをかけたわけだ。
アフリカで部族対立をあおるのに成功すると、CAは次にアメリカに目を向けた。すると、「MAGA!(アメリカを再び偉大に!)」や「壁を建設しろ!」といった叫び声がこだまするなど、どこからともなく「アメリカ版部族対立」が起き始めた。大統領選挙では突如として政策論議は影を潜め、「本物のニュース」と「フェイクニュース」をめぐる奇妙な議論が幅を利かせるようになった。「心理戦版大量破壊兵器」が史上初めて大規模に使われた後遺症にアメリカは今も苦しんでいる。
CA創業メンバーの一人として、私は責任を感じている。これまで犯してきた過ちを正さなければならないという強い義務感を持っている。不覚にも、多くのテクノロジー業界関係者と同様に、フェイスブックのモットー「素早く行動して破壊せよ(ムーブ・ファスト・アンド・ブレーク・シングス)」に踊らされてしまった。これほど深く後悔したことは自分の人生では一度もなかった。素早く行動して強大な力を築き上げ、そして破壊したのである。何を破壊していたのかについて気付いたときには、すでに手遅れだった。
「FBIに逮捕されるかも」と懸念
話を2018年の初夏に戻そう。連邦議会議事堂の地下に設けられた機密情報隔離施設──SCIF──へ向かう途中、私は自分自身の身に起きていることが信じられず、茫然としていた。あまりにも多くの関係者を怒らせてしまったようなのだ。まずは与党・共和党。すでに独自調査を始め、私をおとしめる材料を探し回っていた。次にフェイスブック。PR会社と契約し、私を含めて批判勢力を中傷するのに忙しかった。そればかりか同社の法律顧問団は根拠を示さないまま私をサイバー犯罪者扱いし、FBIへ通報すると脅しをかけてきた。
そんななか、司法省はまったく頼りにならなかった。長年の法解釈を公然と無視するトランプ政権の影響下に置かれていたからだ。私の弁護団は懸念を強め、「クリス、あなたは最後にはFBIに逮捕されるかもしれません」と真顔で言った。安全策としてヨーロッパへの一時避難を提案する弁護士もいた。
安全上と法律上の理由から、私はワシントンでの議会証言を直接引用できない。はっきり言えるのは、SCIFの中へ足を踏み入れたとき、私は二つの大型バインダー──それぞれ数百ページ──を手にしていたということ。
一つ目は、CAが行った広範囲なデータ収集活動を示す電子メールやメモ、文書で構成されていた。これを読めば、同社がハッカー集団をリクルートしたり、ロシア諜報機関とパイプを持つ人物を雇ったり、賄賂や恐喝、偽情報拡散によって世界各地の選挙運動に介入したりしたことが分かる。ここには、法律顧問団がスティーブ・バノンに対して「われわれは外国代理人登録法(FARA)に違反しているかもしれない」と警告した秘密メモのほか、CAがどのようにフェイスブックを食い物にしていたかを示す一連の文書も含まれていた(CAは8700万人以上に上るフェイスブックユーザーのデータを不正に入手し、アフリカ系アメリカ人有権者を抑圧しようとした)。
二つ目は、一つ目以上に機密に触れる内容だった。この年の初めに私がCAのロンドン事務所からこっそり入手した数百ページの資料──電子メール、財務文書、音声データ起こし、テキストメッセージ──が入っていたからだ。これらはアメリカの諜報機関が探し求めていた資料であり、在英ロシア大使館がトランプとブレグジットの両陣営との間に築いた密接な関係を示していた。もっと詳しく言えば、イギリスのオルタナ右翼指導者がトランプ陣営関係者との会合前後にロシア大使館を訪ねていただけでなく、少なくとも3人がロシア鉱山株への投資に絡んだ儲け話──潜在価値数百万ドル──を持ち掛けられていた証拠も含んでいた。
ここで明らかになっていたのは、極めて早い段階でロシア政府は英米のオルタナ右翼ネットワークを特定したうえで内部協力者を育成し、ドナルド・トランプへの橋渡し役として利用していたということだ。オルタナ右翼の台頭、ブレグジット国民投票の可決、トランプ大統領の誕生──。16年の主要イベントは裏ですべてつながっていたのである。
200時間以上の証言、1万ページ以上の文書
SCIF内で4時間が過ぎて、5時間になろうとしていた。そのころには私はフェイスブックの役割と過失について詳細に語り始めていた。
「CAが入手・利用していたデータは、ロシア側スパイとみられる人物の手に渡ったのですか?」
「はい」
「ロシア政府は2016年にロンドンに秘密の活動拠点を置き、大統領選挙とブレグジット国民投票に影響を与えようとしていたのですか?」
「はい」
「CAとウィキリークスは連絡を取り合っていましたか?」
「はい」
ここまで話をして、委員会メンバーの目の中にようやく光明を見いだせた。ぼんやりとではあるものの、何が起きていたのかをやっと理解してもらえたようなのだ。フェイスブックはもはや単なる企業ではなく、アメリカ人の人心を操るためのマシンである、と私は指摘した。最高経営責任者(CEO)のマーク・ザッカーバーグはデータ金庫のドアを広く開け、CAやロシアに自由に使わせたのだ。フェイスブックは独占企業であるから独禁法の規制対象になる。しかし独占企業として規制されるだけでは不十分だ。あまりにも強大な力を得たことで安全保障上の脅威になっているし、民主主義を危機に陥れる恐れもある。
さまざまな国家組織──司法、諜報、議会、警察──に囲まれて難しいダンスを踊らされているうちに、私は累計で200時間以上の宣誓証言を行い、少なくとも1万ページに及ぶ文書を提出した。ワシントンやブリュッセルをはじめ世界各地へ飛んで指導者に会い、CAの悪行はもちろんのこと、ソーシャルメディアが選挙運動にもたらす脅威を説いて回った。
それでも問題山積のままである。私がどんなに長時間の証言を行ってどんなに大量の文書を提供したところで、関係者──警察、議会、規制当局、メディア──の誰もがどうしたらいいのか分からず戸惑うばかりだった。理由ははっきりしている。まず、物理的な場所ではなくオンライン上で起きた犯罪であるから、警察はどこの管轄なのかでもめてしまうのだ。次に、ソフトウエアとアルゴリズムに絡んだ事件であるため、多くの人が混乱してさじを投げてしまう。こんなこともあった。捜査官の一人から呼び出されて尋問されたときのことだ。テクノロジー犯罪の専門家を相手にしていたはずなのに、極めて基本的なコンピューターサイエンスの概念を教えてあげなければならなかった。分かりやすく説明するために紙の上に図表を走り書きすると、没収されてしまった。「厳密に言えば証拠押収に当たるのでは」と指摘したら、「アンチョコみたいなものですよ。何を捜査しているのかを知るうえで必要なんです」と冗談を言われた。LOL(大爆笑)。なんておかしなやつらだ。
われわれは社会的存在であり、政府や警察、学校、規制当局などの公共機関に信頼を置いている。だから、どの公共機関も秘密の専門家チームを抱えており、困った人がいればすぐに助っ人を派遣してくれると思いがちだ。助っ人はプランAが失敗すればプランBを用意してくれるし、プランBが失敗すればプランCを用意してくれる。いつもそばにいて面倒を見てくれる。だが現実は違う。そんな助っ人は存在しない。だから助っ人の登場を待ってはいけない。いつまでたっても誰もやって来ないのだ。
続きは本書にて
訳者あとがき
2016年、ポピュリズム旋風が吹き荒れるなかで、大きな話題を集めていたのがブレグジット国民投票とアメリカ大統領選挙だった。イギリスは欧州連合(EU)から離脱するのか、不動産王ドナルド・トランプ氏は大統領選挙で勝利するのか──。
多くの識者は「まさか」と思っていた。私もそう思っていた。だが、ふたを開けてみればブレグジット国民投票は可決され、トランプ氏は次期大統領に選ばれた。にわかには信じられなかった。
本書を読んで、「まさか」と思っていた自分の無知を思い知らされた。ロシアとオルタナ右翼勢力がソーシャルメディアを駆使して大規模な情報戦を展開し、何百万人もの有権者を「洗脳」したのだ。ここで中心的役割を果たしたのがケンブリッジ・アナリティカ(CA)と名乗る英系軍事下請け業者だった。
「洗脳」の手段が単なるフェイクニュースだと思ったら大間違いだ。確かにトランプ政権誕生に絡んでフェイクニュースは大きな話題になった。だが、フェイスブックから8700万人分ものユーザーデータが流出していた事実を忘れてはならない。結果として、フェイクニュースよりもはるかに強力な「心理戦版大量破壊兵器」が完成し、史上初めて使用されたのである。
だからこそ、原書は放送禁止用語をあえてタイトルに使ったのだ(そのままではなく1字伏せて「Mindf*ck」としてある)。そうしなければ「大量破壊兵器」のようなニュアンスを出せないとの判断があったのだろう。邦訳のタイトル「マインドハッキング」は原書のタイトルに引っ掛けてある。
本書の筆者は、CAを飛び出して内部告発者に転じたクリストファー・ワイリー氏。本人の言葉を借りれば、「リベラル派の同性愛者で24歳のカナダ人が、どのようにしてCAに加わり、オルタナ右翼向けに心理戦用兵器を開発する羽目になったのか」について詳述している。
渦中の当事者が自らの体験を赤裸々に振り返っているだけに、真に迫る内容であり読み応えがある。処女作でありながら文章力が光っており、飽きさせない。小説のようにすらすら読める。
CAがフェイスブックデータを使い、ロンドン本社内の役員室で実験する様子は生々しい。例えば、発表者がリクエストに応えて、同じ名前のネブラスカ市民の一覧をスクリーン上に映し出す。顔写真、勤務先、子どもの学校、自家用車、投票行動、好きなミュージシャン──。どの名前をクリックしてもあらゆる個人情報が即座に出てくる。
もっと驚きなのは、CA幹部がスクリーン上に表示されているネブラスカ市民に直接電話をかけ、個人情報が正しいかどうか確認する場面だ。もちろん、キッチンで電話を取って話をしているネブラスカ市民は、ロンドンとつながって監視されているとはつゆほども思っていない。
秘密裏に個人データが大規模に収集され、その実態を内部告発者が暴いたという点では、CA事件は13年のスノーデン事件と同じだ。しかし、世界を揺るがせたブレグジットとトランプ政権誕生に決定的影響を与えたのだとすれば、衝撃度ではスノーデン事件を上回っているといえよう(スノーデン事件を描いた『暴露』も臨場感あふれる良書)。
しかも、CAによって高度化した情報戦はブレグジットとトランプ政権誕生で終わったわけではない。むしろ、ますます先鋭化している。
20年に入って舞台は米中に移り、両国間の情報戦が激化の一途をたどっているのだ。象徴的なのが中国発アプリとして初めて世界を席巻した「TikTok」だ。若者の間でブームになっている動画共有アプリだというのに、フェイスブックと同じソーシャルメディアであることから脅威論が広がり、米国でやり玉に挙げられている。
同年7月末には米共和党の有力上院議員グループが書簡をまとめ、トランプ政権に対して強い対応を求めた。ティックトックは中国共産党の影響を排除できず、数カ月後の米大統領選挙に介入する可能性がある、と警戒しているのだ。ティックトックの大量破壊兵器化を懸念しているともいえる。
実際に、選挙介入の予兆を感じさせるニュースも飛び出した。上院議員グループが書簡をまとめる1カ月ほど前のことだ。トランプ大統領が久しぶりの選挙集会をオクラホマ州で開いたところ、当初予想とは裏腹に空席が目立った。韓国のKポップファンに加えて、ティックトック利用者が運動した結果との見方が出た(ソーシャルメディアの力を借りて4年前の大統領選挙に勝利したことを考えると、皮肉なものだ)。
19年暮れに新潮社から本書の翻訳について打診されたとき、私は二つ返事で引き受けた。17年夏に発足した非営利団体「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」の発起人の一人になり、一時期ファクトチェック活動に深く関わっていたからだ。
言うまでもなく、ファクトチェックはフェイクニュースと表裏一体の関係にある。フェイクニュースを見抜くためにファクトチェックが存在するのだ。
繰り返しになるが、ソーシャルメディアが事実上の社会インフラになった現在、フェイクニュースよりも格段に複雑で巧妙な情報戦が展開されるようになっている。本書を読んでいて分かったのだが、「ファクトチェック対フェイクニュース」という構図はすでに古い。
攻撃側は最先端の心理学や社会学、人類学で武装して利用者のアイデンティティーを操作し、社会に分断を引き起こした。実際、CAは超一流の心理学者を動員して心理戦版大量破壊兵器を開発したのだ。第2次大戦中にアメリカが超一流の物理学者を動員して原子爆弾の開発に取り組んだように。本書はワイリー氏の懺悔の記録でもある。
その意味では日本は心もとない。一部の大学では今も心理学科が文学部に置かれている状況が象徴しているように、社会科学分野で出遅れており無防備だ。高度な情報戦を仕掛けられたらひとたまりもない。ファクトチェックを進化させたり、新たなルールを設けたりして、社会インフラとしてのソーシャルメディアの安全性を高めなければならない。
日本は情報戦とは縁がないなどとのんきに構えていてはいけない。例えば、中国はいわゆる「戦狼(ウルフウォリアー)外交」と称して、世界各地で攻撃的なプロパガンダを展開中だ。自国内で禁止されているフェイスブックやツイッターも含めて、ソーシャルメディアを積極活用している。「第二のCA」と組んだらどうなるだろうか……。
本書に書いてある通り、現状ではソーシャルメディアは悪用されやすい。ソーシャルメディアを利用していると、悪意ある第三者によって知らぬ間に自分のアイデンティティーが操られていてもおかしくないということだ。誰もが「マインドハッキング」のリスクにさらされているのだ。
2020年8月 広島にて
牧野 洋