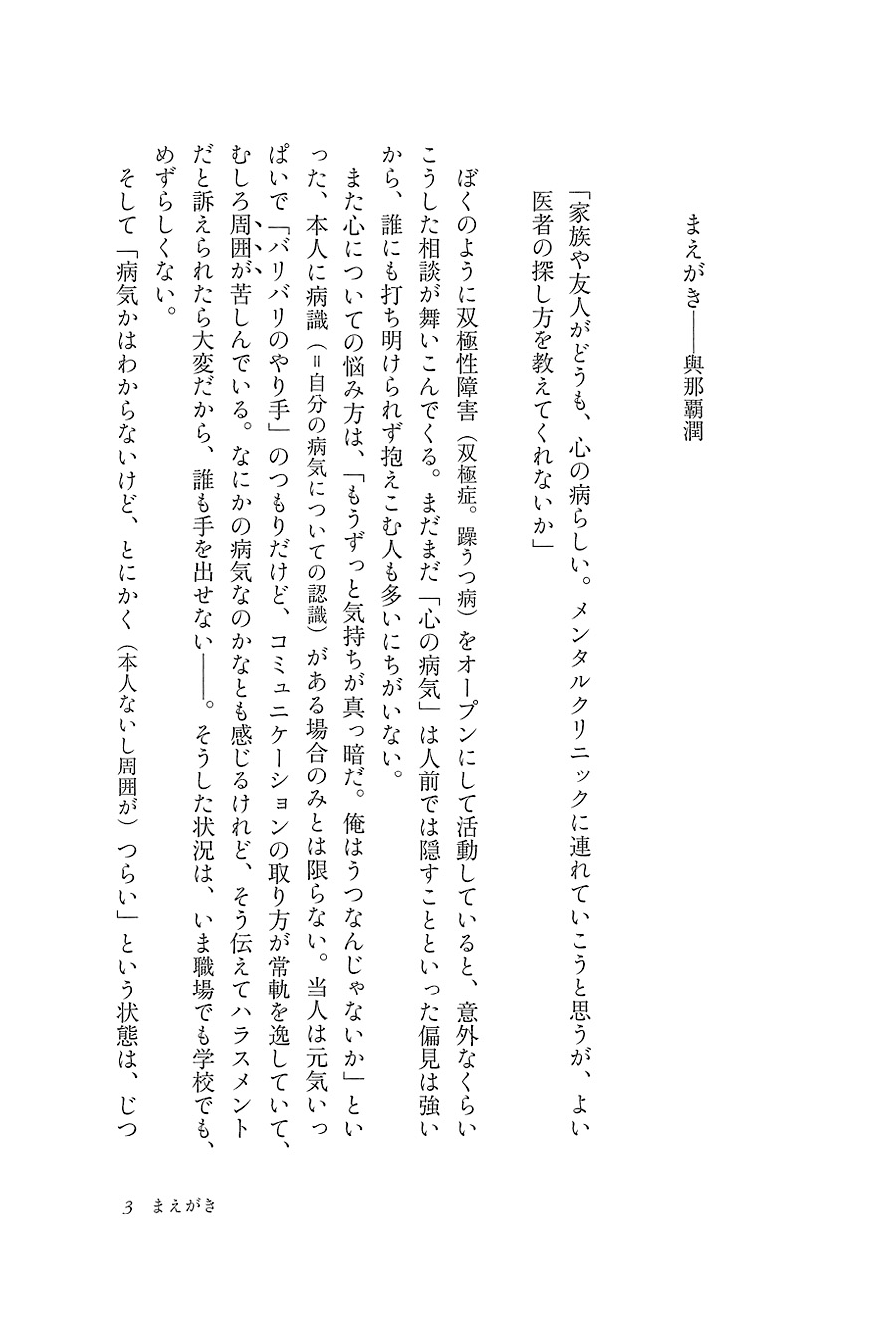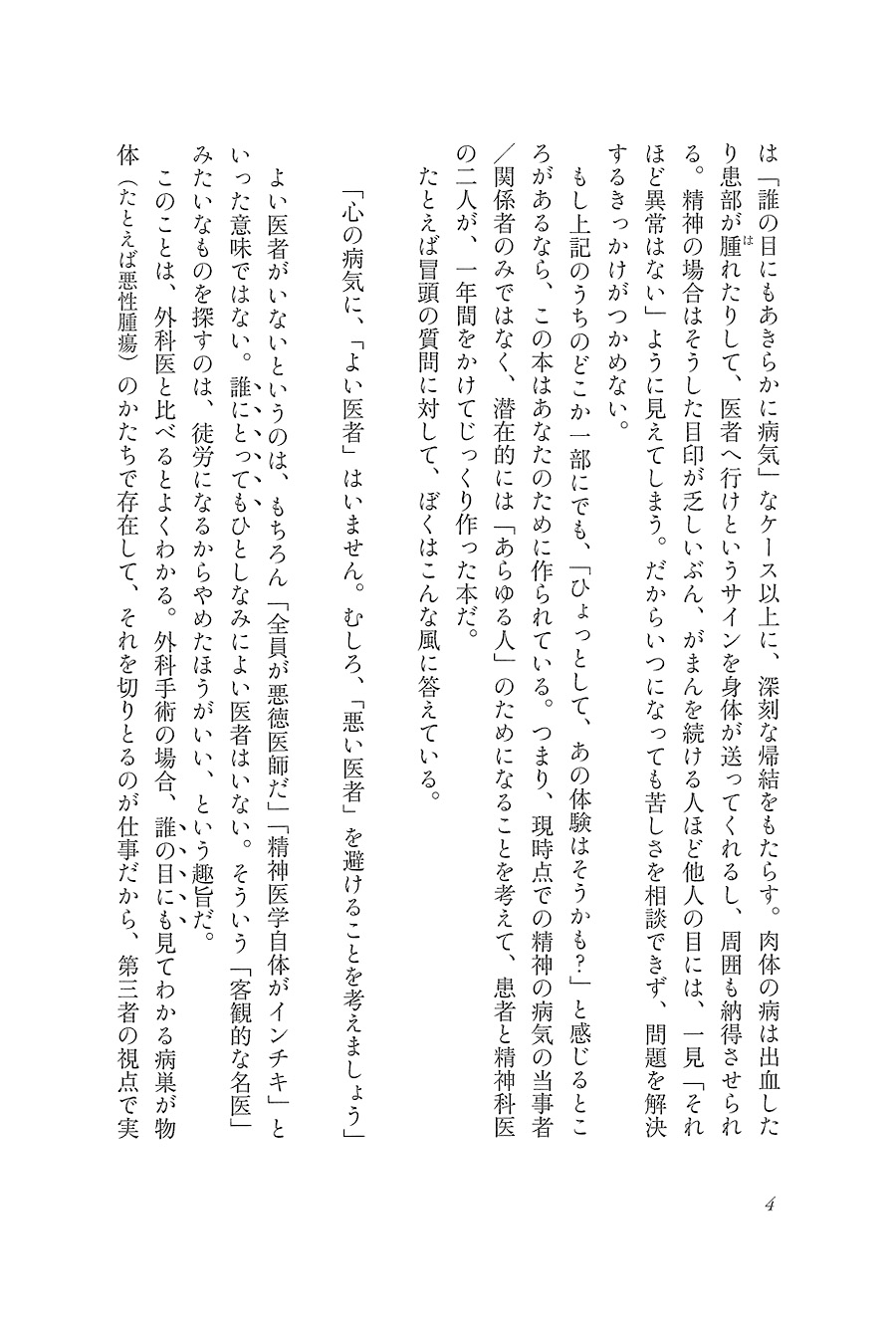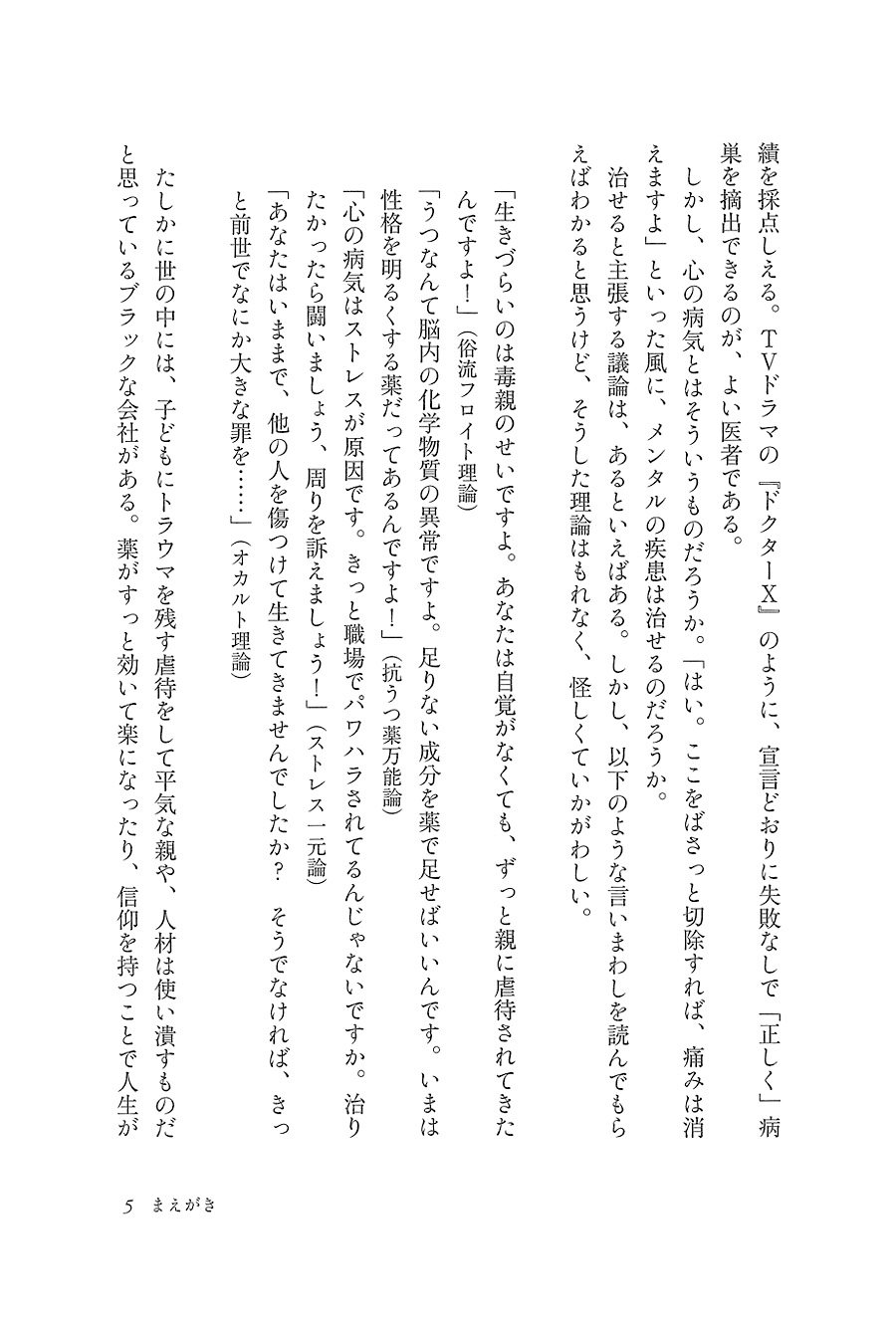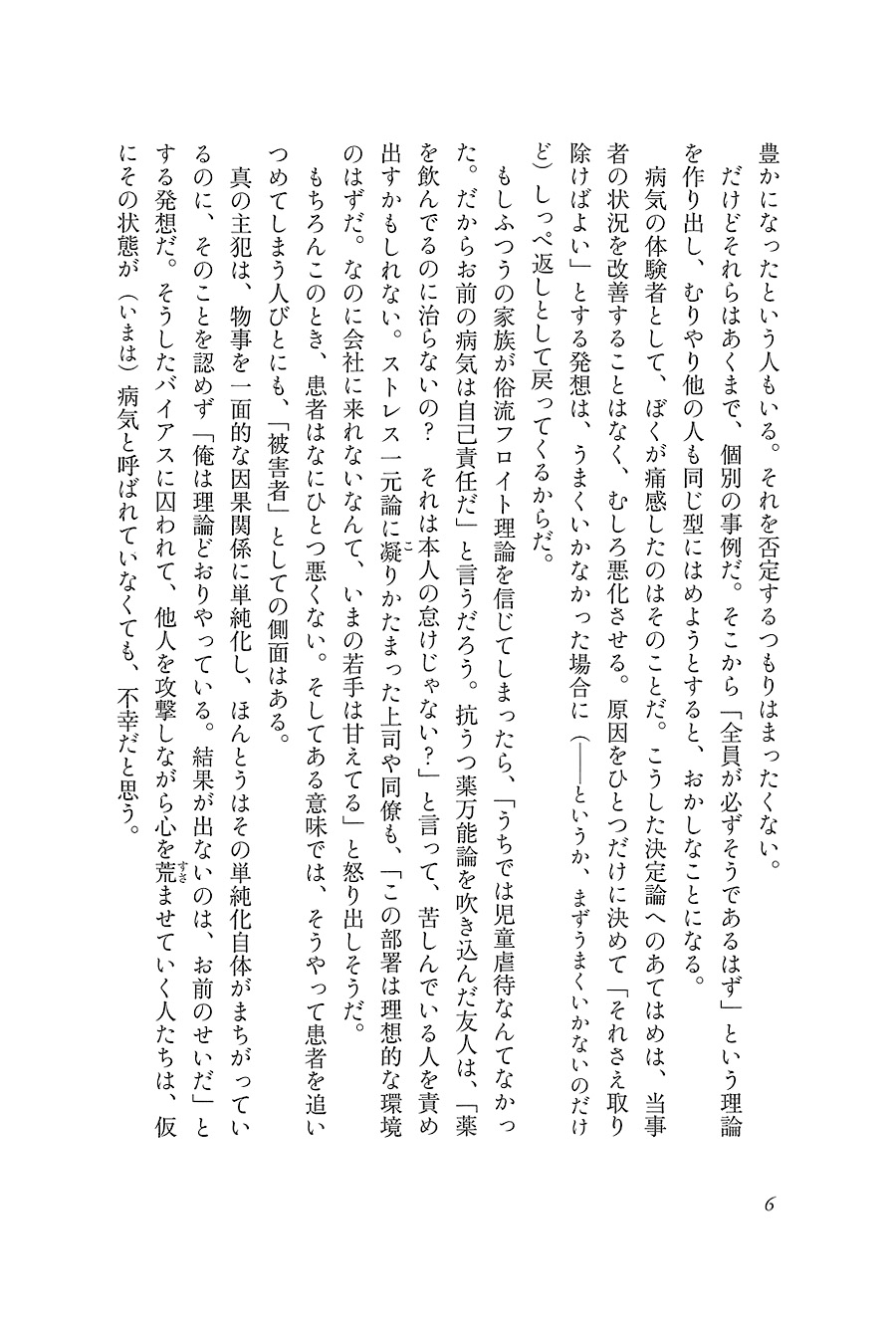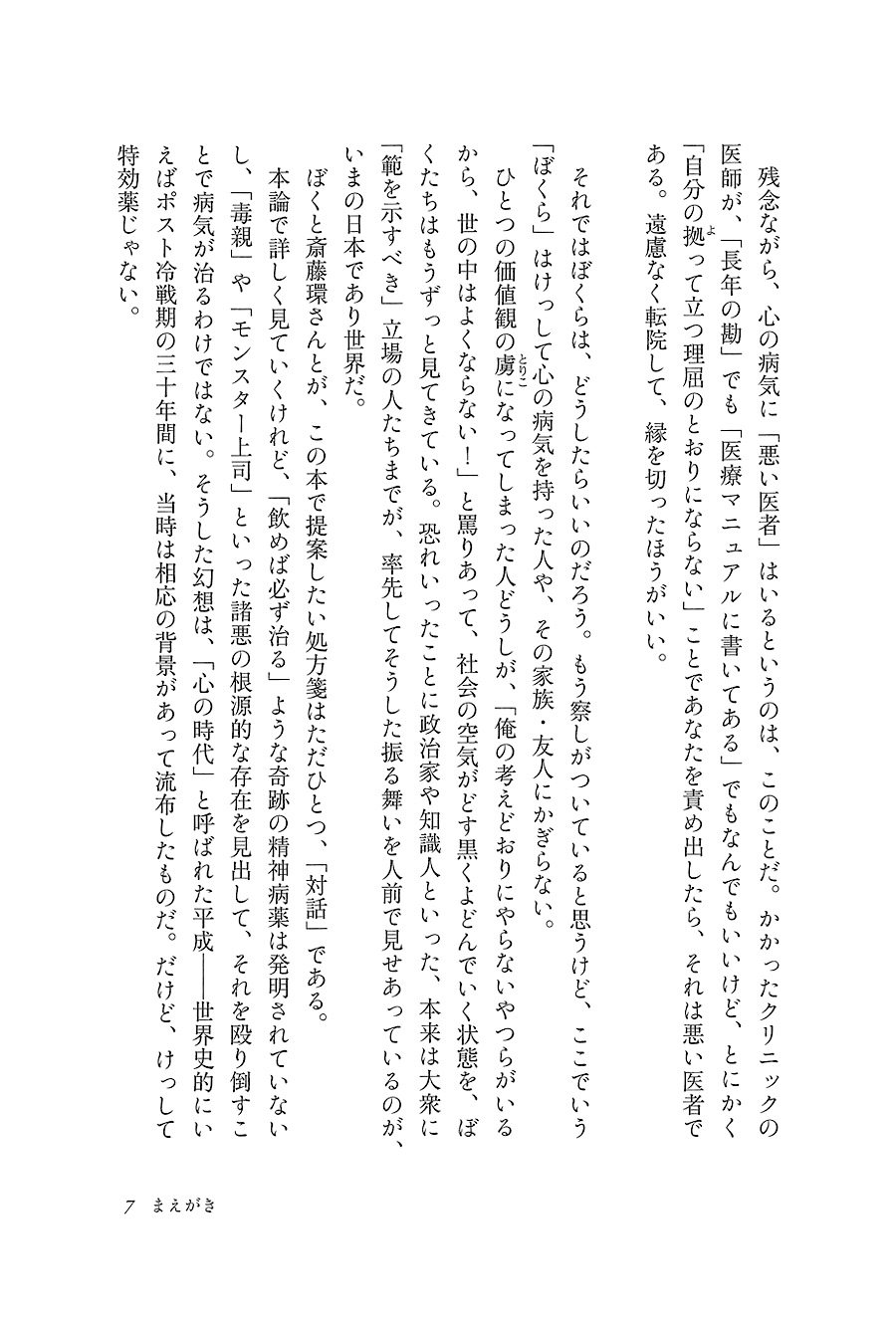まえがき――與那覇潤
「家族や友人がどうも、心の病らしい。メンタルクリニックに連れていこうと思うが、よい医者の探し方を教えてくれないか」
ぼくのように双極性障害(双極症。躁うつ病)をオープンにして活動していると、意外なくらいこうした相談が舞いこんでくる。まだまだ「心の病気」は人前では隠すことといった偏見は強いから、誰にも打ち明けられず抱えこむ人も多いにちがいない。
また心についての悩み方は、「もうずっと気持ちが真っ暗だ。俺はうつなんじゃないか」といった、本人に病識(=自分の病気についての認識)がある場合のみとは限らない。当人は元気いっぱいで「バリバリのやり手」のつもりだけど、コミュニケーションの取り方が常軌を逸していて、むしろ周囲が苦しんでいる。なにかの病気なのかなとも感じるけれど、そう伝えてハラスメントだと訴えられたら大変だから、誰も手を出せない——。そうした状況は、いま職場でも学校でも、めずらしくない。
そして「病気かはわからないけど、とにかく(本人ないし周囲が)つらい」という状態は、じつは「誰の目にもあきらかに病気」なケース以上に、深刻な帰結をもたらす。肉体の病は出血したり患部が腫れたりして、医者へ行けというサインを身体が送ってくれるし、周囲も納得させられる。精神の場合はそうした目印が乏しいぶん、がまんを続ける人ほど他人の目には、一見「それほど異常はない」ように見えてしまう。だからいつになっても苦しさを相談できず、問題を解決するきっかけがつかめない。
もし上記のうちのどこか一部にでも、「ひょっとして、あの体験はそうかも?」と感じるところがあるなら、この本はあなたのために作られている。つまり、現時点での精神の病気の当事者/関係者のみではなく、潜在的には「あらゆる人」のためになることを考えて、患者と精神科医の二人が、一年間をかけてじっくり作った本だ。
たとえば冒頭の質問に対して、ぼくはこんな風に答えている。
「心の病気に、「よい医者」はいません。むしろ、「悪い医者」を避けることを考えましょう」
よい医者がいないというのは、もちろん「全員が悪徳医師だ」「精神医学自体がインチキ」といった意味ではない。誰にとってもひとしなみによい医者はいない。そういう「客観的な名医」みたいなものを探すのは、徒労になるからやめたほうがいい、という趣旨だ。
このことは、外科医と比べるとよくわかる。外科手術の場合、誰の目にも見てわかる病巣が物体(たとえば悪性腫瘍)のかたちで存在して、それを切りとるのが仕事だから、第三者の視点で実績を採点しえる。TVドラマの『ドクターX』のように、宣言どおりに失敗なしで「正しく」病巣を摘出できるのが、よい医者である。
しかし、心の病気とはそういうものだろうか。「はい。ここをばさっと切除すれば、痛みは消えますよ」といった風に、メンタルの疾患は治せるのだろうか。
治せると主張する議論は、あるといえばある。しかし、以下のような言いまわしを読んでもらえばわかると思うけど、そうした理論はもれなく、怪しくていかがわしい。
「生きづらいのは毒親のせいですよ。あなたは自覚がなくても、ずっと親に虐待されてきたんですよ!」(俗流フロイト理論)
「うつなんて脳内の化学物質の異常ですよ。足りない成分を薬で足せばいいんです。いまは性格を明るくする薬だってあるんですよ!」(抗うつ薬万能論)
「心の病気はストレスが原因です。きっと職場でパワハラされてるんじゃないですか。治りたかったら闘いましょう、周りを訴えましょう!」(ストレス一元論)
「あなたはいままで、他の人を傷つけて生きてきませんでしたか? そうでなければ、きっと前世でなにか大きな罪を……」(オカルト理論)
たしかに世の中には、子どもにトラウマを残す虐待をして平気な親や、人材は使い潰すものだと思っているブラックな会社がある。薬がすっと効いて楽になったり、信仰を持つことで人生が豊かになったという人もいる。それを否定するつもりはまったくない。
だけどそれらはあくまで、個別の事例だ。そこから「全員が必ずそうであるはず」という理論を作り出し、むりやり他の人も同じ型にはめようとすると、おかしなことになる。
病気の体験者として、ぼくが痛感したのはそのことだ。こうした決定論へのあてはめは、当事者の状況を改善することはなく、むしろ悪化させる。原因をひとつだけに決めて「それさえ取り除けばよい」とする発想は、うまくいかなかった場合に(——というか、まずうまくいかないのだけど)しっぺ返しとして戻ってくるからだ。
もしふつうの家族が俗流フロイト理論を信じてしまったら、「うちでは児童虐待なんてなかった。だからお前の病気は自己責任だ」と言うだろう。抗うつ薬万能論を吹き込んだ友人は、「薬を飲んでるのに治らないの? それは本人の怠けじゃない?」と言って、苦しんでいる人を責め出すかもしれない。ストレス一元論に凝りかたまった上司や同僚も、「この部署は理想的な環境のはずだ。なのに会社に来れないなんて、いまの若手は甘えてる」と怒り出しそうだ。
もちろんこのとき、患者はなにひとつ悪くない。そしてある意味では、そうやって患者を追いつめてしまう人びとにも、「被害者」としての側面はある。
真の主犯は、物事を一面的な因果関係に単純化し、ほんとうはその単純化自体がまちがっているのに、そのことを認めず「俺は理論どおりやっている。結果が出ないのは、お前のせいだ」とする発想だ。そうしたバイアスに囚われて、他人を攻撃しながら心を荒ませていく人たちは、仮にその状態が(いまは)病気と呼ばれていなくても、不幸だと思う。
残念ながら、心の病気に「悪い医者」はいるというのは、このことだ。かかったクリニックの医師が、「長年の勘」でも「医療マニュアルに書いてある」でもなんでもいいけど、とにかく「自分の拠って立つ理屈のとおりにならない」ことであなたを責め出したら、それは悪い医者である。遠慮なく転院して、縁を切ったほうがいい。
それではぼくらは、どうしたらいいのだろう。もう察しがついていると思うけど、ここでいう「ぼくら」はけっして心の病気を持った人や、その家族・友人にかぎらない。
ひとつの価値観の虜になってしまった人どうしが、「俺の考えどおりにやらないやつらがいるから、世の中はよくならない!」と罵りあって、社会の空気がどす黒くよどんでいく状態を、ぼくたちはもうずっと見てきている。恐れいったことに政治家や知識人といった、本来は大衆に「範を示すべき」立場の人たちまでが、率先してそうした振る舞いを人前で見せあっているのが、いまの日本であり世界だ。
ぼくと斎藤環さんとが、この本で提案したい処方箋はただひとつ、「対話」である。
本論で詳しく見ていくけれど、「飲めば必ず治る」ような奇跡の精神病薬は発明されていないし、「毒親」や「モンスター上司」といった諸悪の根源的な存在を見出して、それを殴り倒すことで病気が治るわけではない。そうした幻想は、「心の時代」と呼ばれた平成——世界史的にいえばポスト冷戦期の三十年間に、当時は相応の背景があって流布したものだ。だけど、けっして特効薬じゃない。
だからぼく自身がそうだったように、心の病気でクリニックに通い出すと、かならず途中で後悔するタイミングがある。言われるとおりにしているのに、全然治らないじゃないか。むしろ副作用でもっとひどくなってるんじゃないか。安易に「医者に頼った」から、こんなことになったんじゃないか——といった具合だ。
そうなってしまったとき、どう乗り越えるのか。その手段が対話だと思う。疑問や違和感を言葉にし、ただしどちらも一方的に見解を押しつけることなく、コミュニケーションを続けること。問題が完全に解決しはしないけど、でも少なくとも一人で思考の堂々めぐりをしているよりは「楽」だから、もうちょっとこの関係を続けてみようと思えること。
そうした条件が整うことで、はじめて治療は継続できるし、結果としていつか「治る」。
どんな相手ならそう思えるかは、本人の性格や趣味しだいで違うだろう。だから客観的な意味での「よい医者」は存在しないが、でもあなたにとって「この人ともっと話してみたい」と思える相手が見つかったなら、それはよい医者に出会えたということなんだ。
こうした考え方こそが病気に限らず、いま生きることに悩む人の助けになると、ぼくは思っている。
本書で行われているのは対談であって、治療ではない。けれども斎藤環さんは上記した意味で、ほんとうに「よい医者」だった。とりあげる話題はうつ病や発達障害、ひきこもりといった疾患の治療のみならず、ふつうの日本の家庭や学校、職場、インターネットで広く生じている問題や、それを考察するツール(精神分析や現代思想)の長短にまで及んでいる。端緒となった令和の初月(二〇一九年五月)のゲンロンカフェでのイベントも含めて、ご多忙のなか計六回もの対話に応じてくださった、斎藤さんに心から感謝したい。
基になった対談は本書に掲載された順序どおりに行われたので、原則としてはそのとおりに読み進めるのがおすすめだけど、どうしてもいまのあなたの悩みに近くて「気になる章」があるなら、そこから先に読んでもらっても大丈夫なように工夫してある。ただし最終章は、できれば最後に読んで、そしてまたこの「まえがき」に戻ってきてくれたら嬉しい。
そのときたぶん、あなたは「対話」というものに、きっといまよりももう少し、期待をかけてみたくなっているはずだから。
あとがき――斎藤環
対談の仕事は無数に引き受けてきたし、対談本も何冊か作ってきた。それでも本書ほど濃密なものは前例がない。なにしろ一回あたり四時間あまりの対談を六回、それもずっと喋り通しだったのだ。すべてテキストに起こしたら、確実に本書の三~四倍の分量は喋っている。その内容をぐっと圧縮して、加筆修正をしたのが本書である。ひょっとしたら通常の単行本以上にさまざまなアイディアがつまっているかもしれない。
與那覇さんも「まえがき」に書いているように、本書は「対話」にはじまり「対話」に終わっている。ただし、ここでいう対話とは、合意や決定につながる対話ではない。自分と相手の違いをふまえて、それをさらに深掘りするようなやりとりを「対話」と呼んでいるからだ。與那覇さんが対談の冒頭で述べている「同意なき共感」も、対話の副産物として生ずるものである。
「対話」は合意を求めないが、共感は素直に口にしてよい。たとえば原発推進派と反対派がいたとして、両者の議論がずっと平行線のままだったとしよう。そんなときでも、推進派が反対派の不安に共感したり、反対派が推進派の挫折感に共感したりすることは十分に可能なはずだ。アタマが論争的になっている人は、相手を論破することしか考えていないから、どこまでも平行線になる。しかしひとたび「正しさ」へのこだわりを捨てられれば、対話はいつでも可能になるし、豊かな広がりを持ちうるだろう。本書のもくろみの一つは、そうした「結論の出ない対話」の価値を、対話を通じてさぐることだった。
本書に繰り返し出てくるキーワードに「人間教」がある。これは正確には、山本七平の「日本教」なのだが、あえて本書では人間教と呼んでいる。山本自身も、日本教とはつまるところ人間教であるとも述べているので、誤用ではない。
日本人は、なぜ無宗教と言われるのか。山本はその理由を、キリスト教や仏教、イスラム教すらも取り込んでしまうほど融通無碍な「日本教」信者であるからだと指摘する。山本=ベンダサンの「思想」は、政治的な部分も含め同意できないところが多々あるのだが、この「日本教」というアイディアについては、きわめて洗練された日本人論として、今なおその価値を失っていない。
ここでごく簡単に、私なりの「日本教」理解を述べておく。これは要するに、キリスト教的な意味での「超越性(=神)」や「他者性」なしで世界観を構築するための“信仰”だ。「日本教」が重視するのは「自然」や「人間」といった概念だが、これらもかなり独特のもので、西欧的な概念とはへだたりがある。たとえば「自然」とは、キリスト教的世界観におけるような、人間が支配し管理する自然ではない。「自己の内心の秩序と社会秩序と自然秩序」をひとまとめにした言葉だ。日本人にとっては、こうした自然がそのまま、あるべき規範になるという。この意味で自然は、いわゆる「空気」にも通ずる重要な概念なのだが、ここでは深く立ち入らない。
それでは「人間」とは何か。山本はよく天秤の喩えで「人間」を語る。人間そのものは定義できない存在だが、それは天秤の支点である。天秤の片側には「実体語」が、もう片側には「空体語」が乗っていて、人間が両者のバランスをとっている。実体語は現実を指し、空体語は概念を指す。「敗戦」という実体語が、「一億玉砕」という空体語を伴っていたように。
率直に言えば、この天秤の比喩はやや素朴すぎるきらいがある。ただ、私のヤンキー論を補足する上では、かなり役に立った。ヤンキーは現実的な行動力もあるが、同時に意外なほどロマン主義者で「夢」や「絆」を語りたがる。むしろ彼らの行動力の源泉こそがロマン主義であるとすれば、彼らは山本の言う「純粋な人間」に近い、とすら言いうるだろう。
人間教においては、「人間」は「自然」と調和した関係のもとに置かれることが望ましい。人間教には善悪を定めるような教義や規範はないので、極端に言えば、たとえその人間が悪事を働いても、それが自然な流れならば肯定される場合がある。いじめ加害が「武勇伝」になったり、暴力団の炊き出しが普通のボランティア活動以上に評価されたりするのもこの流れである。そこでは「自然に機能する人間」こそが称賛される。反面、「自然」の調和から外れた人間、それを見出す人間は罰せられ、排除される。山本が「抗空気罪」と呼んだような罪だ。不正や悪事と縁がなくても、コミュニケーションが不得手だったりひきこもったりしている人は、自然との調和を乱した罪の名のもとで、排除されてしまいかねない。
與那覇さんと私は、本書の中で、一貫してこの「自然」に抵抗している。人間教を延命させている「自然」が、いまなお至るところに浸透しており、非合理的でしばしば非倫理的ですらある「空気」として、しばしば個人を抑圧していること。この点が繰り返し指摘されている。
ただし、注意しなければならないのは、私たちの批判する人間教が、しばしば「同意なき共感」の見かけを持ちうるという点だ。人間教そのものは規範もなくタブーもない。そこで重視される「自然」とは、清濁併せ呑むかのような曖昧さをはらんでおり、「自然(=空気)」の共有は、しばしば共感と混同されやすい。その結果、「その場にいてはっきり反対を表明しなかった」ことが、共感=同意と見なされてしまう。つまり人間教における意思決定は、むしろ「共感なき同意」としてなされてしまうのだ。私たちが重視する「同意なき共感」とは真逆である。
この「同意なき共感」という言葉は、本書のもう一つのテーマである「価値規範なき人間主義」につながっている。どういうことだろうか。
価値の追求がテクノロジーと結びつくとき、「人間」は「価値付けられた部分」の集合ないし集積体となる。たとえば「情報」に価値を置いてみよう。このとき人間は、たやすく情報ネットワークのノードの一つとなり、無数のデータやピクセルの集積となり、非人称的なデータフローの一部とみなされるだろう。
ある種の価値を偏重し、人間をその価値が実現されるための道具や場所であると見なすこと。たとえば経済なら「ホモ・エコノミクス(経済人)」、言語なら「語る存在(ラカン)」といった側面に注目し、その機能を分析すること。こうした細分化は「科学」には欠かせない。人間を部分の集積と見る視点がなければ「人間の科学」は成立しないからだ。
あるいはエビデンス主義を支える統計解析は、人間を集団における匿名の一要素と割り切る視点がなければ不可能である。つまり、人間という存在を「部分の集積」と見なすことと「集合の一部」と見なすことは、匿名化という意味で表裏一体なのである。しかし注意しよう。こうした匿名化を要請するのは、あくまでも科学や工学のパラダイムであり、そこから「人間」の普遍的な原則は導かれない、ということを。
ここで「人間主義」にフォーカスしてみたい。これまで「人間主義」という言葉は、きわめて多義的に用いられてきた。共通するのは、価値基準の出発点を「人間」に置くということだ。そこから出発して、理性が、実存が、労働が価値付けられることになる。
人間主義は二十世紀前半までは流行したが、若い世代はそこにともなう文学的曖昧さ、鈍重さに飽き足りなくなっていた。彼らが歓迎したのは、構造主義でありポスト構造主義であり、これらの思想はフランスで学生運動がピークを迎える一九六八年を境に世界の思想地図を塗り替えていった。そのスローガンのひとつが「人間の終焉」だったのである。
しかし一九六八年から半世紀が過ぎても、われわれはいまだ「人間」のままだ。AIだ、ポストヒューマンだとの掛け声だけはかまびすしいが、われわれの日常は半世紀前とほとんど変わらぬ“人間的”な日常である。この当然と言えば当然の前提をふまえて、いったいどんな提言が可能になるだろう。
それが対談の後半に出てくるキーワード「価値判断抜きの人間主義」である。
理性や実存、まして「自然」といったキーワードは、価値基準としては強すぎる。こうした発想は、非理性的に見える障がい者などのマイノリティを排除してしまいかねない。本書でも述べているように、私は「価値判断抜きの人間主義」における人間の条件を「統合性」におきたい。「個人」という一つのまとまりを持つ存在を、人間と見なすということ。「言語」や「理性」といった能力や条件はいったんカッコに入れて、この「まとまり」をこそ重視すること。
誤解なきように言い添えておくが、ここでいう「統合」は、「統合失調症」の統合とは関係がない。むしろ統合失調症の患者であっても、まとまりを持った、統合された存在と見なすための言葉である。
実はこの考えは、医療倫理学ではつとに知られた「バルセロナ宣言」(一九九八年)からの引用である。ちなみにこの宣言は、尊重されるべき人間の価値として「自律 Autonomy」「尊厳 Dignity」「不可侵性・統合性 Integrity」「脆弱性 Vulnerability」を挙げており、いずれも現代における「人間主義」と深い関わりを持つ。
人間を個として「統合された存在」であると考えること。ただし統合性そのものに価値があるわけではない。統合それ自体は、良いものでも悪いものでもないし、統合から悪が生まれることもあり得る。しかし統合性から出発することで、私たちはさまざまな価値に気づくことができるはずだ。個人の尊厳や自由、権利や自発性の価値を担保しているのも、つまるところはこの「統合性」ではないだろうか。
私たちが他者と出会い、互いにそれぞれの統合性を尊重し合うためになされる行為。それこそが「対話」である。対話においては「議論」や「説得」、あるいは「アドバイス」はタブーとされる。それは相手の存在の「統合性」を否定し、自分と同一の存在であることを強いる行為になりかねないからだ。これと同じ意味で、「正しいこと」や「客観的事実」をめぐる対話は、しばしばどちらかの、あるいは双方の「統合性」を傷つける。
では何を話題にすべきか。それぞれの「主観」である。それが傍目にはどれほどいびつなものに見えようとも、対話の出発点は常に「主観」であるべきなのだ。その意味で対話とは、主観と主観の交換でもある。たとえ相手の“主観的”な意見に同意できなくとも、私が“主観的”に同意していないことを穏やかに伝えつつ、「共感」可能なポイントを探ること。これも対話の一部となる。たとえば「親を殺したい」という訴えには同意はできないが、そう思うに至った過程については共感できる、というように。
対話においては、合意や調和(ハーモニー)を目指す必要はない。むしろ「違っていること」こそが歓迎される。共感を大切にしながらも、自分と相手の「違い」を掘り下げること。異なった意見が対立しあわずに共存している状態を、対話実践では「ポリフォニー」と呼ぶ。個人の統合性を傷つけないポリフォニーの空間において、ほんとうの意味での個人の主体性がもたらされる。これが対話実践の思想となる。そしておおむね、「結論」や「解決」は、主体性の回復のあとに勝手についてくるものなのだ。まるで予想もしなかった形で。
本書で批判されたのは、たとえば欧米的な「エビデンス主義」や「操作主義」であり、それとはベクトルが異なる「日本教」であった。私自身、そのいずれに対しても批判的な意見を持ってはいたが、與那覇さんの鋭敏なアンテナ感覚と明晰な状況整理によって、かなりクリアに問題意識が共有できたと思う。名著『知性は死なない』からもうかがえるように、與那覇さんは病を得た経験から、ご自身の身体感覚も動員しつつ時代や社会のさまざまな徴候をとらえていくスタイルを確立されたのではないか。私からは主に対話実践の臨床から、「対話」こそがそうした問題に対する処方箋ではないか、というアイディアを提供したのだが、当初の予想以上にさまざまな可能性が見えてきた。診察室に閉じこもっているだけでは見えてこなかった対話の社会的意義に気づかせてくれた與那覇さんに感謝したい。
本書の企画を打診されたのは、およそ一年前の二〇一九年四月だった。『「社会的うつ病」の治し方』などでお世話になった三辺直太さんには、六回にわたる対談の設定から原稿のまとめに至るまで、ひとかたならぬお世話になった。ここに記して感謝したい。