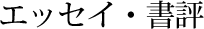『ペット・サウンズ』は音楽版『キャッチャー・イン・ザ・ライ』だ
このインタビューは、2005年5月末、本書『ペット・サウンズ』刊行直後に行なわれました。
――『ペット・サウンズ』に関する本を、どうして今書かれたのでしょうか?
コンティニューム(Continuum)社の33 1/3シリーズに、僕も本を書かせてもらえることになったんだ。このシリーズには、最高のロック本が収録されている。だから、このシリーズに、僕の本も加えてほしい、と願っていた。そして『ペット・サウンズ(Pet Sounds)』(1966年)は、僕の人生を完全に変えてしまった。だから33 1/3シリーズで何か1冊書かせてもらえるなら、『ペット・サウンズ』についての本しかない、と思っていたんだ。
――ベビーブーマー世代の人は、やはりそのように考えるでしょうか?
『ペット・サウンズ』は、ほんとうにすごいアルバムだった。ロックが勢いを持っていた時代の最高の1枚だ。だからその意味では、今の質問に対して、「イエス」と答えられると思う。でも、あのアルバムがほんとに理解されているかと言えば、そうとは思えない。『ペット・サウンズ』が好きな人たちも、このアルバムのすごさをほんとうに理解してはいないんじゃないかな。「素敵じゃないか(Wouldn't It Be Nice)」や「スループ・ジョン・B(Sloop John B)」や「神さましか知らない(God Only Knows)」が好きな人はもちろんいる。でも、そんな彼らも、『ペット・サウンズ』も、しょせんビーチ・ボーイズのごきげんな曲を集めただけのアルバムだ、と思っているんじゃないだろうか。『ペット・サウンズ』には、それ以上の何かがあるんだ。無垢な感情を失ってしまう複雑な気持ちや、人と違うために払わなくちゃいけない代償について、とても深いことが語られている。『ペット・サウンズ』を心から愛している人の多くは、ちゃんとそのことがわかっている。それがわかっている人は、アルバムに深くのめりこんでしまう。『ペット・サウンズ』における絶対的な存在は、何といっても、ブライアン・ウィルソンだ。ブライアンが言いたいことは、彼がトニー・アッシャーと一緒に書いた歌詞だけが伝えるわけじゃない。ブライアンの音楽とアレンジ、そしてプロデュースも、彼の言いたいことを伝えている。『ペット・サウンズ』は、ほんとにすごい芸術だ。
――芸術品ですか?
まさしく。どの基準で考えてもそうだ。『ペット・サウンズ』は、今生きている誰の人生より長持ちするだろう。ほんとにそうだ。僕ら全員がそれぞれの人生で経験する時間がここには凝縮されているし、社会学的に大衆に訴える力ももっている。まさに音楽版『キャッチャー・イン・ザ・ライ』だ。この音楽にはほんとに驚かされてしまう。ちょっとぎこちなく聞こえるけど、すっとメロディが流れてゆく。論理的じゃないけど、やっぱりすばらしいとしか言いようがない。まっすぐなんだけど、複雑。こんなのは、ポップ音楽の歴史になかった。そしてポップ音楽にないものをたくさん備えている。楽器のアレンジなんて、ハリー・パーチ(Harry Partch[1901-74]:独自の微分音音楽の記譜のために、1オクターブを従来の12音程ではなく43音程に分割する特殊な記譜法を考案した。作品は作者自身の発明になる特殊な楽器を使わなくては演奏できなかったので、広く注目されなかった)とジャック・ニッチェ(Jack Nitzsche[1937-2000]:ロックミュージシャン・作曲家・アレンジャー。フィル・スペクターやローリング・ストーンズ、ニール・ヤング、そしてマイルス・デイヴィスらと仕事をする。映画音楽も手がけ、映画『愛と青春の旅だち』[1982年]の主題歌でアカデミー賞受賞)が試みたようなことを、同時にやっているようだ。ヴォーカルのアレンジもすごい。ブライアンのようなヴォーカルのアレンジは、誰にもできないよ。
――ブライアン・ウィルソンに会いましたか?
会ったよ。でも、この本を書くために会ったわけじゃないんだ。この本はとても自伝的で、ちょっと変わっている。おかしな言い方かもしれないけど、悲しいけど、ちょっと変わっている。でも、ブライアンに会ったのは、本を書き上げた後だ。ブライアンはいい人だ。多くは話せなかったけど、彼に会えてほんとうにうれしかった。ミュージシャンの本を書くにあたっては、その人たちと何度も会うようにしている。でも、今回はそれをしようと思わなかった。
――ほかのビーチ・ボーイズのメンバーとは?
カール・ウィルソンとデニス・ウィルソンは亡くなっている。デニスにはずいぶん昔に会ったことがある。でも、今回はほかのメンバーには会わなかった。アル・ジャーディンとはLAタイムズ・ブック・フェスティバルで一緒になったけど、話をしようとは思わなかった。もちろん『ペット・サウンズ』に関しては、ほかのメンバーはほとんど何もしなかった、と言いたいわけじゃない。たとえばカールは、「神さましか知らない」で、ほんとうに見事なヴォーカルを聴かせてくれている。でも、『ペット・サウンズ』はやっぱりブライアンのプロジェクトだ。それは紛れもない事実だし、ブライアン自身もソロアルバムとして出そうとしたんだ。
――マイク・ラブについては、どう思われますか?
ほんとにびっくりしてしまったんだけど、ブライアンのファンは、マイクに対して、強い怒りの感情をいただいているようだ。ブライアンと親しい人たちもそうみたいだ。どうしてそんなことになってしまったのか、ほんとうのことはわからない。でも、マイクはブライアンに反対して、『ペット・サウンズ』と『スマイル(Smile)』の製作を手伝おうとしなかった、と人びとは考えているようだ。マイクは、ブライアンに、ビーチ・ボーイズはすでに大変な成功を収めているんだから、今まで同じような音楽を作りつづけるべきだ、と言いたかったんだと思う。でも、芸術家はそんなふうには考えない。ブライアンは今までなかったようなものを作り上げようとした。そしてそれを作ってしまった。ほかの人の援助は十分に得られなかったけど、『ペット・サウンズ』によって、今までなかったものを作り上げてしまった。そう、「駄目な僕(I Just Wasn't Made For These Times)」にも歌われているよね。「あてにならない友だちに見切りをつけられたら/僕はいったい誰に頼ればいい?」「いつまでも付き合えるような人たちと/何とかして知り合いたいと/僕は必死になっているんだ」。そんなふうに考えて、ブライアンは成長しようとしたんだ。あきらめることなく。
――ブライアン・ウィルソンは、今後ほかにも偉大な作品を残すと思われますか?
わからない。でも、彼ならきっとできると思う。大きなテーマが与えられて、彼もそれに挑戦したいと思う、そしてヴァン・ダイク・パークスやダリアン・サハナジャのような人たちがサポートしてくれる、というような状況になれば、きっとすごいものを作り上げるだろう。大きなテーマといっても、『スマイル』のように、アメリカを万華鏡のように映し出すものにする必要はないと思う。『スマイル』はまるでピカソの「ゲルニカ」のようだ。あまりにテーマが大きすぎて、時間や空間の設定がよくわからなくなってしまった。『ペット・サウンズ』も大きなテーマを扱っているけど、それを個人的に、そして内面的に解明しようとしている。ブライアンはそういうものをもう一度作ろうとするんじゃないかな。
でも、ブライアンにこれ以上望むのは気の毒かもしれない。ブライアンは『ペット・サウンズ』をはじめ、すばらしい曲をたくさん作っている。ブライアンが作った曲をよく聴いてみれば、それがどれだけすばらしくて、どれだけ内容の濃いものか、わかるはずだ。そして野心的な『スマイル』もついに完成させた。ブライアンの歌を聴けば、彼のヴォーカルのアレンジもいつまでも耳に残る。誰も『ペット・サウンズ』のようなレコードは作れないよ。彼はあんなすごいのをすでに作っているんだから......。
――今回の本は、今まで書かれたものとは違いますね。どうしてこのような書き方をされたのでしょうか?
書き方が違うということ? 純真さというか、若者が感じる驚きというようなものを伝えたいと思ったんだ。それは『ペット・サウンズ』の歌詞に読み取れる。でも、僕が初めて『ペット・サウンズ』を聞いたときの気持ちも盛り込みたかった。だから語り口が若干混沌としてしまっているところもあるかもしれない。僕の個人的な体験から始まって、『ペット・サウンズ』のレコーディング・セッションや、ブライアンの伝記的な事実にまで話が飛躍してしまうのだから。でも、それも意識してやったんだ。そうすることで、ブライアンの人生がどんなものであったか、浮かび上がらせようとしたんだ。ひょっとすると本書は音楽関連の本としては非常に実験的なものになったかもしれないし、そうでないかもしれない。でも、僕は作家だから、この本に小説の技法のようなものを持ち込みたかったんだ。
ずっと前にヴァン・モリソンに、彼が作った商業的な成功がおよそ期待できないアルバムについて、話を聞くことができた。彼に、そのアルバムは誰が聴いてくれると思うか、と訊ねてみたんだ。ヴァン・モリソンは正直に、「それがいいと思う人が聴いてくれるだろう」と答えてくれた。僕もそんな気持ちでこの本を書いたんだ。中には僕の語り口がしっくりして、僕と同じ視点で本を読んでくれる人もいると願っている。僕の狙いは、本書のエピローグを読んでいただければ、すべておわかりいただけると思う。著者はどこか傍らに押しやって、その語り口にだけ耳を傾けてほしい。
――『ペット・サウンズ』に収録されている曲のコード進行が本書には詳しく書かれているわけですが、それを知りたいために、この本を読む人たちがいると聞きました。ほんとうですか?
そう。この本には曲のコード進行などが詳しく書かれているから便利かもしれないし、それに目をつける人もいると思う。そのようにして読んでいただいても、うれしい。『ペット・サウンズ』の音楽が何といってもいちばん重要だ。それは認めないといけない。それが大切だ。『ペット・サウンズ』に入っているほとんどの曲の基本的なコード進行を、僕は書きこんだ。ベースの音程の取り方も少し書き加えた。もちろん、ブライアンが参加ミュージシャンに演奏させた曲は、ギターだけでは表現できない。少なくとも僕はそう思う。でも、本書を読んでくれた人たちから、僕はメールをもらうんだ。あなたがこの本で説明しているコード進行を元に、いろんなアレンジを加えて、ブライアンの音楽を演奏していますって。
――書店のリーディングで、実際に『ペット・サウンズ』の曲を何曲か演奏してみせたようですね。それはまたどうして?
ブライアンは、ちょっと変わっているけど、とても興味深いコードを使っている。だからベース・ラインと合わせて、そのコード進行を実際にみなさんに聴いてもらおうと思ったんだ。実際に演奏して聴かせることで、そのコードやベース・ラインがどれだけすばらしいハーモニーを作り出したか、みなさんに知ってもらおうと思ったんだ。さらに、ブライアンの音楽は「苦しみ」を含んでいる。その苦しみが見事なレコーディングや美しいヴォーカルによっていかに巧妙に隠されているか、それも知ってほしかったんだ。でも、僕はただお客さんの前に座って、何曲か演奏してみただけだよ。ごくごく小さなコンサートを開いただけだ。でも、僕は楽しかったし、お客さんも楽しんでくれたようだ。「神さましか知らない」を、みんなで一緒に歌ったりしたんだ。ほんとに楽しかったよ。お客さんもたくさん来てくれたし、予想以上の結果が出せたんじゃないかな。だって、お客さんは、ちょっと暗い顔で、「おいおい、この音楽評論家は、調子はずれの歌を歌って、安っぽいギターをジャカジャカかき鳴らしているぞ」とヒソヒソ話していたから(笑)。でも、ほんとに気持ちよかった。そんなことをしたのは一度だけだけどね。でも、版元のコンティニュームの人たちと、またやろうか、と話しているよ。
――ほかに音楽関連の本を書くご予定は?
特に予定はない。でも、きっと書くと思う。以前は、ポピュラー音楽に関する本やミュージシャンの伝記は書きたいと思わなかった。というのは、僕は小説家を目指していたし、小説家として自立したかった。でも、それはちょっと愚かな考え方だとわかったんだ。だって、それはたくさんの人たちが「ウォールストリート・ジャーナル」を読んで、ナショナル・パブリック・ラジオを聴いているんだから、小説だけ書いて食べていこうだなんて、なかなかむずかしいことだと思う。そして不愉快なことも一つある。ベビーブーマー世代の人たちは、ロックはすでに死んだ、1975年を境に死んでしまった、とどうやら思っているようだ。僕は以前、ロックの黄金時代の変遷について書いたことがあるけど、今なおロックは生きている。今のロックもイカしているよ。僕もいいロックをたくさん聴いているし、同じ世代の人たちにも聴いてほしいと思う。きっと楽しんでもらえるはずさ。だから、たぶん今のロックで何か書くと思うよ(笑)。
――以前から手掛けておられるテリー・オールが活躍する犯罪小説の新作はいかがですか?
僕は作家だから、次に何を書くかには、まだ話すべき段階じゃないと思う。来年(2006年)に刊行される予定の犯罪小説に、僕の作品も収録されるはずだ(オーディブル社が2007年9月25日から配信を開始したオーディオ・ダウンロード小説『ショパン・マニュスクリプト[The Chopin Manuscript]のこと。ジェフリー・ディーヴァー、リー・チャイルド、ジョセフ・ファインダー、リザ・スコットラインなど、15人の有名なスリラー小説の作家たちとともに、ジム・フジーリも1章を執筆している。)短篇小説とあわせて、ブライアン・ウィルソンとビーチ・ボーイズについての本を書くことで、僕は作家として成長できたと思う。だから次の作品には、僕が学んだことを生かしてみたい。
――ブライアン・ウィルソンが書いた曲の中で、一番悲しいものは何だと思いますか?
むずかしい質問だね。『サーフズ・アップ(Surf's Up)』(1971年)に収録された「ティル・アイ・ダイ('Till I Die)」だと僕は思う。精神の病の苦しみを痛切に歌った曲だ。「僕は大海に浮かぶ一片のコルク」「僕は風に揺れる一枚の葉/もうすぐ吹き飛ばされてしまうだろう」。そして最後に「こんな思いが頭から離れない。僕が死ぬまで」とブライアンは歌っている。
『ペット・サウンズ』の曲であれば、「キャロライン・ノー(Caroline, No)」の最後のフレーズを聴いてほしい。(「消え去ってしまったものを/僕らは再び取り戻すことができるだろうか?/ああ、キャロライン、だめだよ」)ほんとうにすばらしいよ。『ペット・サウンズ』は、アルバム全体が一つの曲と考えることができると思う。そのように考えれば、最初の「素敵じゃないか」のチャイムのような明るいギターから始まって、ブライアンの叫びとともに「キャロライン・ノー」が静かにフェード・アウトしてこの壮大な1曲は幕を閉じる、ととらえてみることができる。
――もう一つ、フジーリさんの無人島に持っていくCDのリストの中には、『ペット・サウンズ』が入っていませんね。どうしてですか?
『ペット・サウンズ』があまりに悲しいからだ。この本を読んでもらえれば、僕がそう考える理由がわかると思う。『ペット・サウンズ』は、とてもきれいなアルバムだけど、同時にあまりにも痛々しくて、僕は聴くのがとてもつらい。それを聴いてしまうと、僕は自分の人生でいちばんむずかしかった時期を思い出してしまう。自分は孤独だと感じていたあの時期のことが、頭によみがえるんだ。ブライアンの言葉と声と音楽とアレンジは、彼は一人ぼっちである、と僕らに教えてくれる。それと同じように、僕も自分は一人ぼっちだと感じてしまっていた時期がある。その時期を思い出してしまうんだ。だめだよ、誰かいてくれないと、『ペット・サウンズ』は聴けない。
(ジム・フジーリ 作家、上杉隼人/訳)
波 2008年3月号より

単行本
ペット・サウンズ
ジム・フジーリ/著、村上春樹/訳
発売日 2008年2月29日
1,760円(定価)