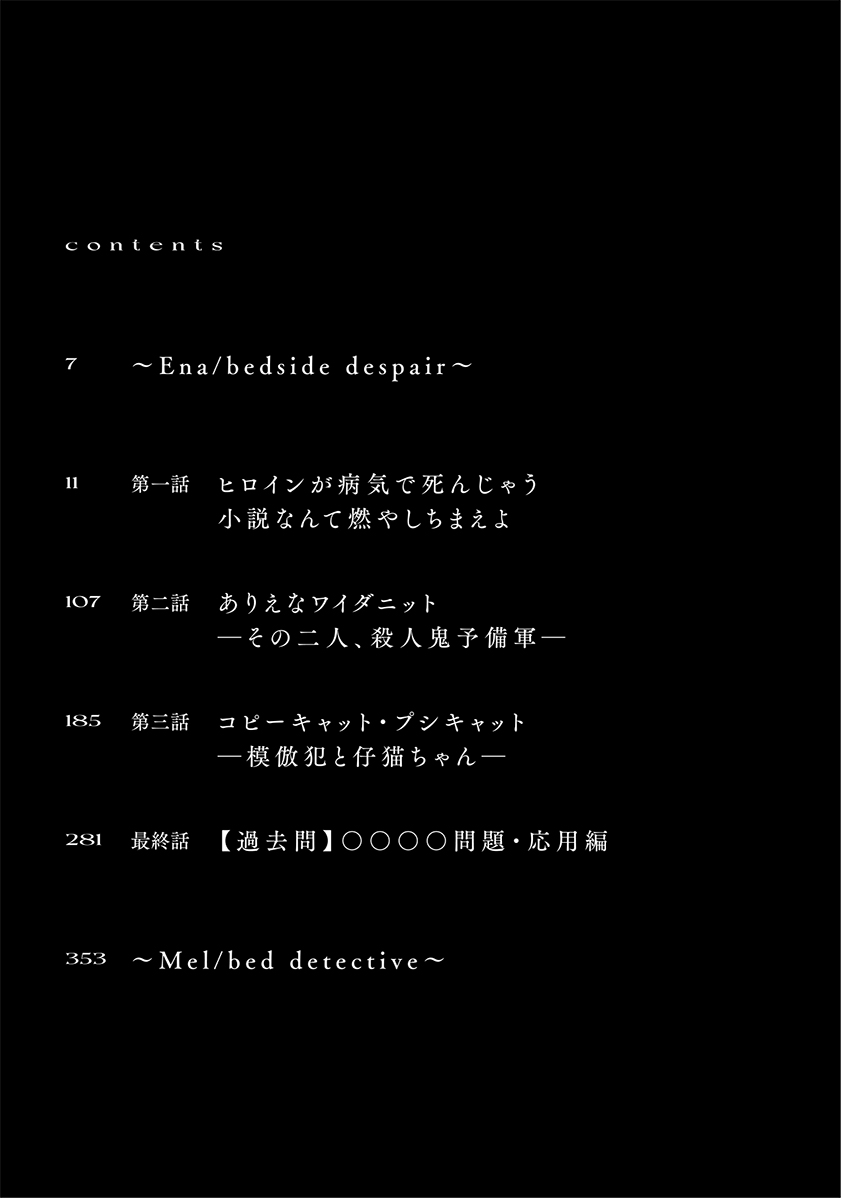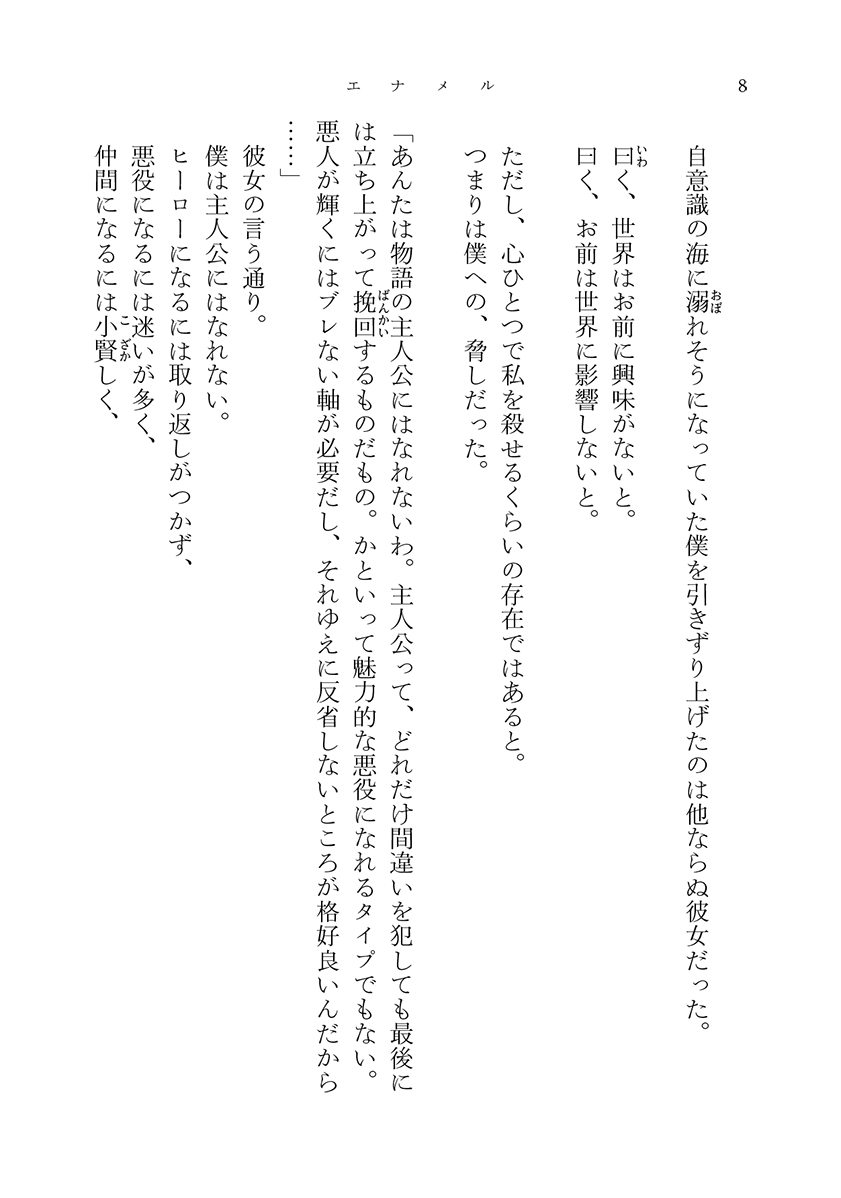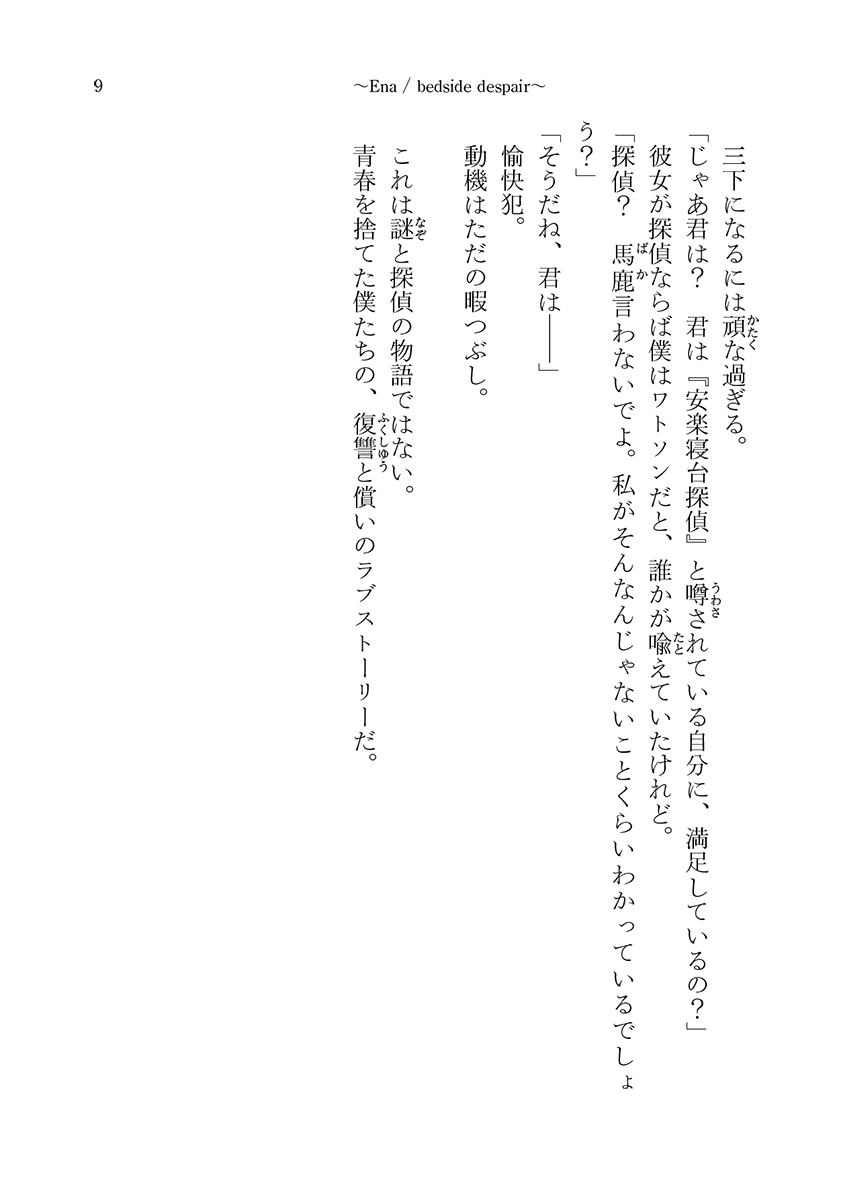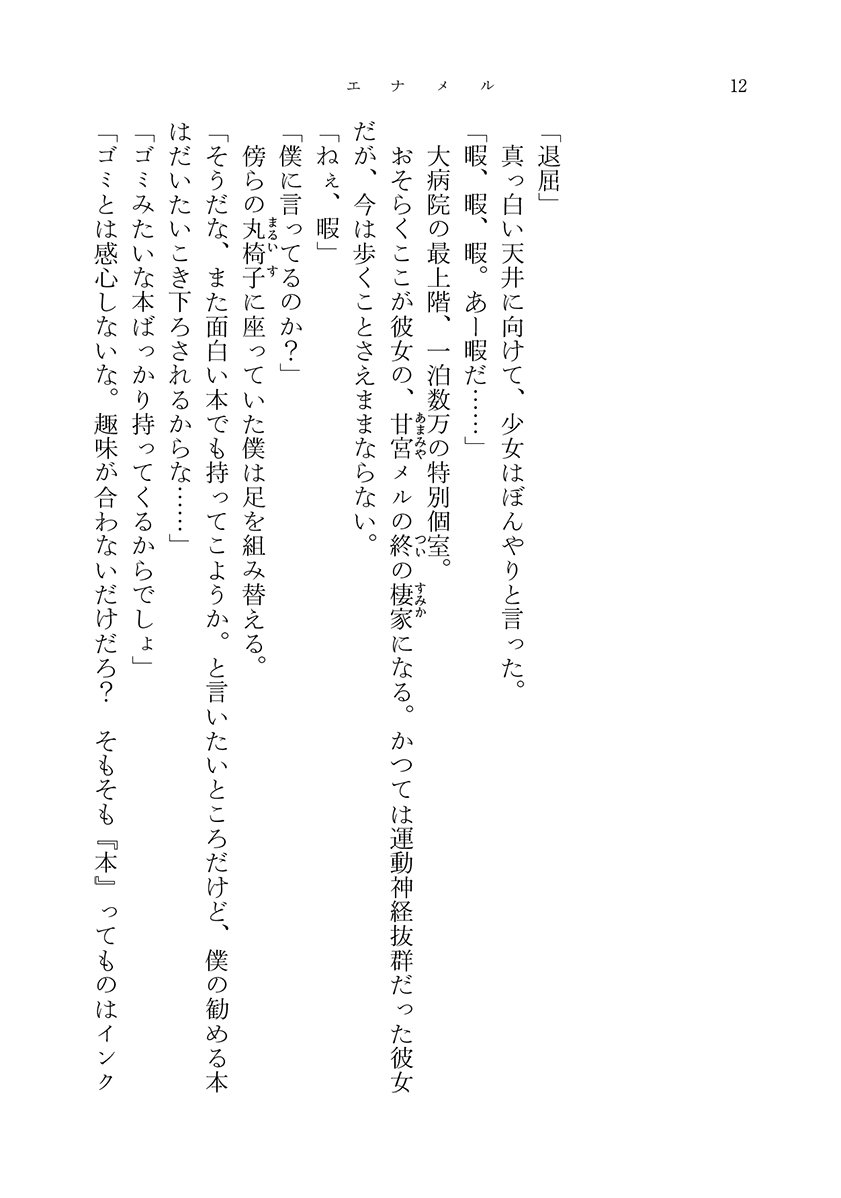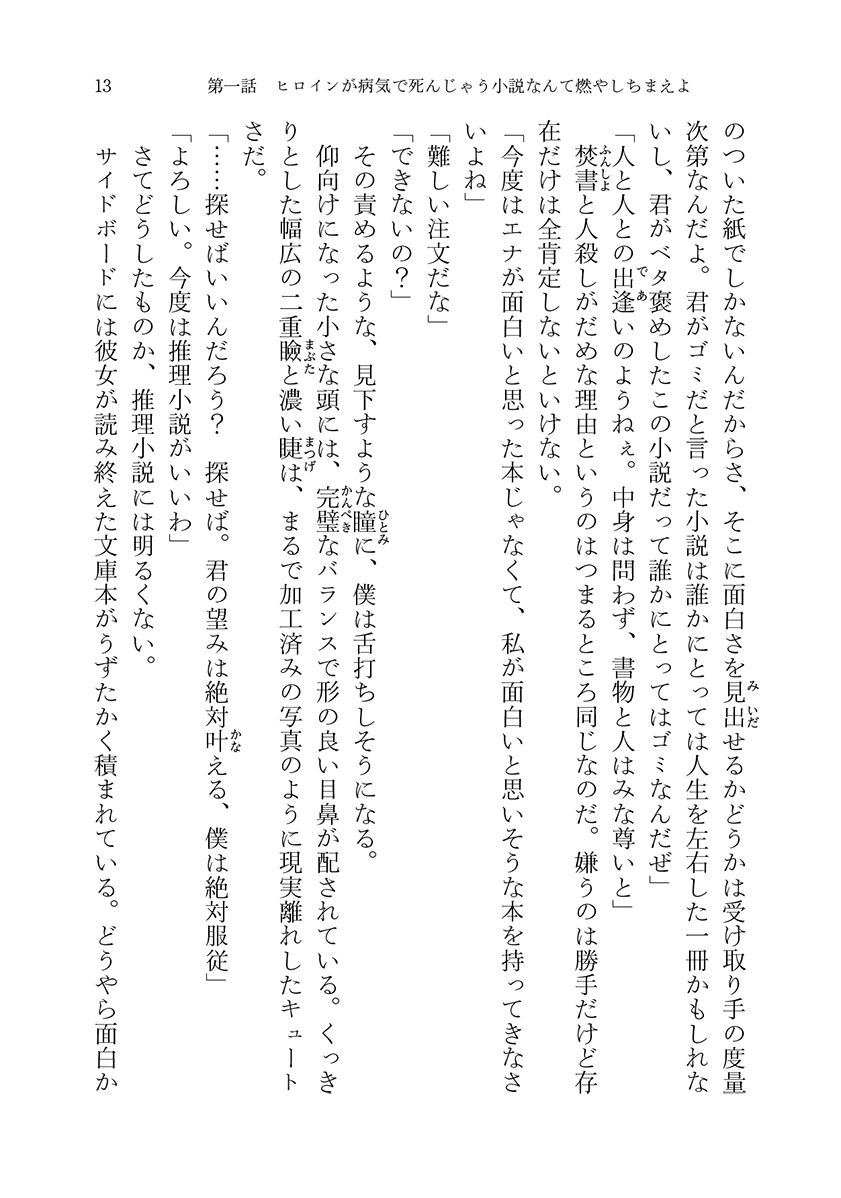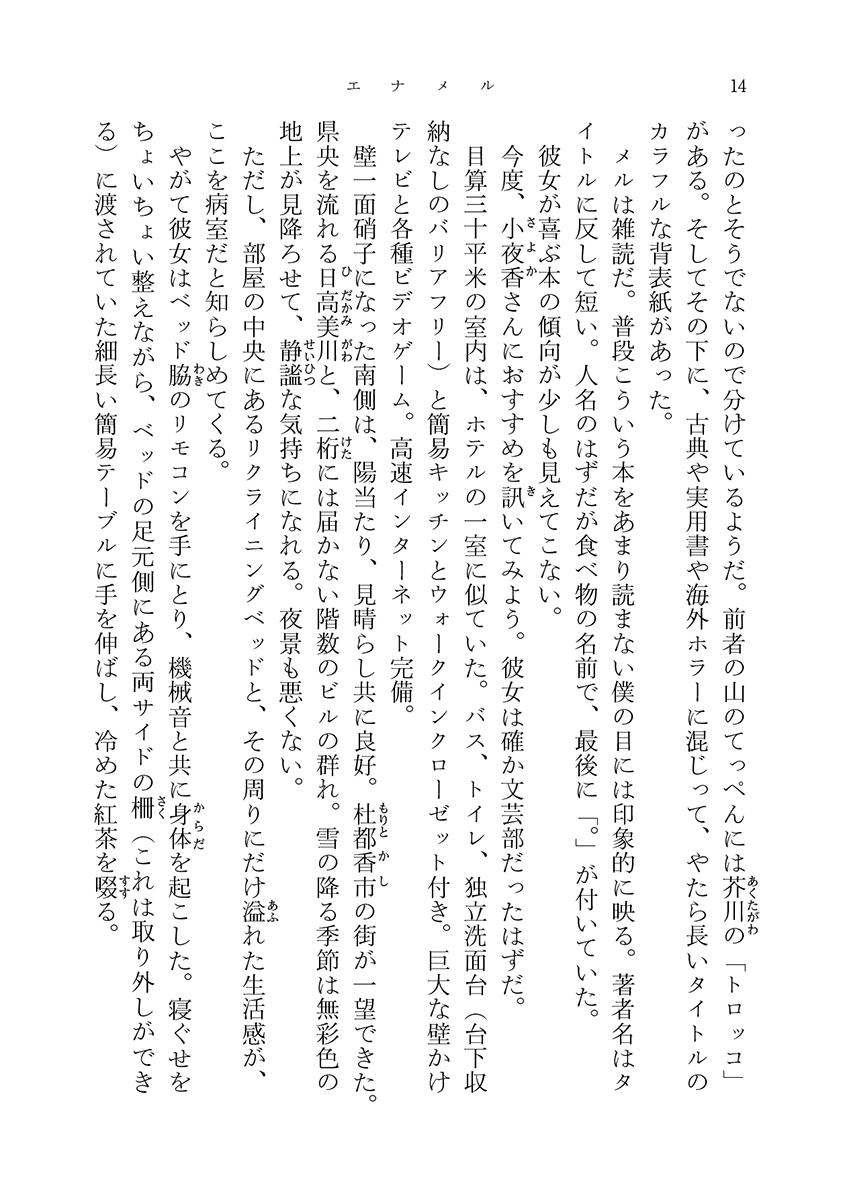~Ena/bedside despair~
自意識の海に溺れそうになっていた僕を引きずり上げたのは他ならぬ彼女だった。
曰く、世界はお前に興味がないと。
曰く、お前は世界に影響しないと。
ただし、心ひとつで私を殺せるくらいの存在ではあると。
つまりは僕への、脅しだった。
「あんたは物語の主人公にはなれないわ。主人公って、どれだけ間違いを犯しても最後には立ち上がって挽回するものだもの。かといって魅力的な悪役になれるタイプでもない。悪人が輝くにはブレない軸が必要だし、それゆえに反省しないところが格好良いんだから……」
彼女の言う通り。
僕は主人公にはなれない。
ヒーローになるには取り返しがつかず、
悪役になるには迷いが多く、
仲間になるには小賢しく、
三下になるには頑な過ぎる。
「じゃあ君は? 君は『安楽寝台探偵』と噂されている自分に、満足しているの?」
彼女が探偵ならば僕はワトソンだと、誰かが喩えていたけれど。
「探偵? 馬鹿言わないでよ。私がそんなんじゃないことくらいわかっているでしょう?」
「そうだね、君は――」
愉快犯。
動機はただの暇つぶし。
これは謎と探偵の物語ではない。
青春を捨てた僕たちの、復讐と償いのラブストーリーだ。
第一話
ヒロインが病気で
死んじゃう小説なんて
燃やしちまえよ
「退屈」
真っ白い天井に向けて、少女はぼんやりと言った。
「暇、暇、暇。あー暇だ……」
大病院の最上階、一泊数万の特別個室。
おそらくここが彼女の、甘宮メルの終の棲家になる。かつては運動神経抜群だった彼女だが、今は歩くことさえままならない。
「ねぇ、暇」
「僕に言ってるのか?」
傍らの丸椅子に座っていた僕は足を組み替える。
「そうだな、また面白い本でも持ってこようか。と言いたいところだけど、僕の勧める本はだいたいこき下ろされるからな……」
「ゴミみたいな本ばっかり持ってくるからでしょ」
「ゴミとは感心しないな。趣味が合わないだけだろ? そもそも『本』ってものはインクのついた紙でしかないんだからさ、そこに面白さを見出せるかどうかは受け取り手の度量次第なんだよ。君がゴミだと言った小説は誰かにとっては人生を左右した一冊かもしれないし、君がベタ褒めしたこの小説だって誰かにとってはゴミなんだぜ」
「人と人との出逢いのようねぇ。中身は問わず、書物と人はみな尊いと」
焚書と人殺しがだめな理由というのはつまるところ同じなのだ。嫌うのは勝手だけど存在だけは全肯定しないといけない。
「今度はエナが面白いと思った本じゃなくて、私が面白いと思いそうな本を持ってきなさいよね」
「難しい注文だな」
「できないの?」
その責めるような、見下すような瞳に、僕は舌打ちしそうになる。
仰向けになった小さな頭には、完璧なバランスで形の良い目鼻が配されている。くっきりとした幅広の二重瞼と濃い睫は、まるで加工済みの写真のように現実離れしたキュートさだ。
「……探せばいいんだろう? 探せば。君の望みは絶対叶える、僕は絶対服従」
「よろしい。今度は推理小説がいいわ」
さてどうしたものか、推理小説には明るくない。
サイドボードには彼女が読み終えた文庫本がうずたかく積まれている。どうやら面白かったのとそうでないので分けているようだ。前者の山のてっぺんには芥川の「トロッコ」がある。そしてその下に、古典や実用書や海外ホラーに混じって、やたら長いタイトルのカラフルな背表紙があった。
メルは雑読だ。普段こういう本をあまり読まない僕の目には印象的に映る。著者名はタイトルに反して短い。人名のはずだが食べ物の名前で、最後に「。」が付いていた。
彼女が喜ぶ本の傾向が少しも見えてこない。
今度、小夜香さんにおすすめを訊いてみよう。彼女は確か文芸部だったはずだ。
目算三十平米の室内は、ホテルの一室に似ていた。バス、トイレ、独立洗面台(台下収納なしのバリアフリー)と簡易キッチンとウォークインクローゼット付き。巨大な壁かけテレビと各種ビデオゲーム。高速インターネット完備。
壁一面硝子になった南側は、陽当たり、見晴らし共に良好。杜都香市の街が一望できた。県央を流れる日高美川と、二桁には届かない階数のビルの群れ。雪の降る季節は無彩色の地上が見降ろせて、静謐な気持ちになれる。夜景も悪くない。
ただし、部屋の中央にあるリクライニングベッドと、その周りにだけ溢れた生活感が、ここを病室だと知らしめてくる。
やがて彼女はベッド脇のリモコンを手にとり、機械音と共に身体を起こした。寝ぐせをちょいちょい整えながら、ベッドの足元側にある両サイドの柵(これは取り外しができる)に渡されていた細長い簡易テーブルに手を伸ばし、冷めた紅茶を啜る。
「……青春小説ってやっぱり好きになれないわ。エナが貸してくれたこの本も、全然面白くなかった」
彼女は先日僕が持ってきた「泣ける」と話題の文庫本をパラパラとめくった。売れているだけのことはある、という感想を僕は持ったのだけれど。
「私、病気ヒロインと、妹ヒロインに共通項を見出しちゃったのよね」
「共通項?」
「どれだけイチャコラしても、最後は責任を取らなくていいってとこよ。マニック・ピクシー・ドリーム・ガールからさらに『将来』っていう現実を取っ払った究極の理想的ヒロインなんだわ。死んじゃった人はそれまでだし、妹とは結婚できない。どっちも幸せにしてあげなくっていいの。まぁ今日び、男だけが責任を取るべきとは思わないけれど」
「なんだよそれ……」
少なくとも僕は自分の妹が結婚したあとも、妹の幸せのためなら、迷わず夫や家庭に口と手を出すぞ。
僕はベッドの端に座り直し、サイドボードの引き出しから櫛を取り出して、彼女の長い髪を丁寧に梳いてやることにした。
「青春で一番苦しいことってなんだと思う? 『何も起こらないこと』よ。手ひどい失恋のほうがまだマシ。『やっかいな少女に絡まれて苦労した』なんて経験、青春を味わえなかった成人男性から見たら羨望の的でしょうよ。それなのに青春小説の主人公は決まって不幸面しながら『やれやれ』って言うのよ。それを当の大人が書いてるんだから辟易するわ」
「そうかな。苦労するくらいなら、何も起こらないほうがいいと思うけれど」
「馬鹿ね。大人になったのに、友達いません恋愛経験ありません、部活で頑張ったこともなければ勉強しまくったわけでもなく、遊ぶのも下手……。そんな人間、目も当てられない。そういう人が社会に混じれないのって、なんとなく解るでしょう?」
「まぁね……、どこへ行っても肩身の狭い生き方をしそうだ」
「青春の内は、間違えても失敗してもいいのよ。だけどね……」
彼女は浅く息を吸う。
「青春小説に出てくるキャラクターたちには、死にたくなるレベルの『本当の失敗』なんて、そうそう降りかかってはこない。フィクションなんだもの」
痛いところをついてくる。
メルの髪は入院してからずっと伸ばしっぱなしだ。美容師を呼んで揃える程度に切ったりしているようだが、膝裏に届くくらいに伸びていた。あのまま高等部に進学していたら間違いなく校則違反だったであろうミルクティー色に染められている。
「ねぇ、エナ」
彼女は甘やかな声音で、僕にぽふんと寄りかかる。自然、後ろから抱きしめるような形になった。
「――エナはもう青春なんかに未練はないよね?」
街はずれに位置する「県立第一高等学校」、通称「県一」の歴史は旧い。
旧制中学を前身に戦後から共学になった、という地方都市ではありがちな沿革を持ち、偏差値と歴史の長さは県内で公立一だが、旧いだけあって校舎も設備も一番のボロさを誇っている。北国の田舎らしく、石油ストーブはあるがエアコンはない。
小、中と同じ学校だった僕と、幼馴染の小夜香さんはこつこつ勉強して県一へ入学したものの、一年次の夏休み明けである今は完全にだらけてしまい、安穏とした学生生活を送っていた。
「おすすめの推理小説かぁ……」
小夜香さんが、小首を傾げる。
「私もあんまり詳しくないんだよね、本自体あまり読まないし」
「あれ、小夜香さん文芸部じゃなかったっけ?」
「ううん、たまに遊びに行くけど部員じゃないよ。部員の友達に頼まれて有志として部誌の挿絵を書いたりしたことはあるけど、小説なんか書けないし……」
佐渡小夜香。「さやか」でも「さよこ」でもなく「さよか」。僕は完全に慣れきってしまったが、初対面の人は一瞬、舌先を迷わせる名前だ。
彼女はちょっと下を向いて左手に持った牛乳パックのストローをくわえた。右手には顔より長いあんバターコッペパン。毛量の多いロングヘアが緩く波打っている。重めな前髪の下で眼鏡越しに見える瞳が軽やかに動いた。
昼休みはいつも友達と過ごす彼女だが、今日は委員会だとかでいないらしく、嬉しいことに向こうから声をかけてくれた。彼女は常々、大人しい僕がぼっち飯なことを気にしているようでちょいちょいお菓子をくれたり、ようすを見に来てくれるのだ。
幸いこのクラスはいじめだのスクールカーストだのといった雰囲気とは無縁で、僕と小夜香さんが幼馴染なことも周知の事実なので、二人でお昼を食べていてもひやかされたりすることはない。
「そうだ、部長が推理小説好きだから、今聞いてみようかな。メルはどんなのが読みたいって言ってるの?」
小夜香さんはスマホでメッセージアプリを立ち上げた。
「えーと、何がいいっていうか、『あれが厭、これが厭』ってわがままばっかりなんだよな。とりあえず青春系と感動系は除外で」
「『せつなすぎるラスト!』とか『最後の一行であなたは絶対涙する!』とか?」
「あぁそれ……、そういうの絶対嫌いだな……」
ついでに言うと彼女は「洋画とロックにかぶれた小説」も「すぐ同性愛の話に持っていく女流作家」も「主人公が個性強くて浮いちゃう的な純文学小説」も嫌いだと言っていた。
逆に何なら満足なんだよ……。
ほどなく通知音がぴろんぴろんと連続で鳴った。送られてきた書名や著者名を読み上げてくれた小夜香さんだが、ふいに「えっ」と声を上げた。
「なんか、部室に置いてあった部誌が、大変だ、って……」
「ん?」
小夜香さんはスクロールして読み返し、送られてきた写真を見せてくれた。
「印刷会社から納品されたばかりの部誌が、いつの間にかこんなふうになってたんだって……」
映っていたのは机の上に積まれた冊子。
刷りたての部誌、三十部だそうだ。
しかしその側面はまだらに黒く汚れ、紙はぼそぼそと波打っていた。
「酷い……。なんだろうこれ、煤……?」
「煤ってなんだよ? まさか部室でボヤでもあったのか?」
と笑った僕の言葉に、彼女はパンを取り落としそうになる。僕はすかさず手を伸ばしてビニールの端を掴んだ。
「それ、かも……ええ、恐っ……」
「え、本当に?」
例の部員の友達から聞いたんだけど、と前置きして、彼女は言った。
「なんかね、一昨日二年生の先輩たちがちょっと、文学っていうか、小説論? みたいなので揉めちゃったんだって……」
「ほう、小説論と来たか」
「スプラッタとか好きな、籠目先輩って人がいるんだけど、その人がボーイミーツガールな感動小説を書いてる先輩に『ヒロインが死んじゃう青春小説なんて燃やしちまえ!』って、ぶちかまして喧嘩になったとか……」
「うわぁ」
くっだらねぇ。
僕は弁当の鰻巻玉子を齧った。弁当は毎日妹が作ってくれているのだけど、今日も最高に美味しい。食は大事だ。食は身体を作る。
それに比べ、学生のお遊び文芸部で文学だなんだと高邁ぶった思想を闘わせることは……、実りがないというか暑苦しいというか、なんというか……。
こういうのも「青春」って呼ぶのかな。
「……ふーん。『燃やしちまえ!』発言の直後に、こんなふうないたずらをされるってのは、確かに引っかかるな。そのスプラッタ先輩が腹いせに火で炙ったなんてことじゃないんだろう?」
「あんまり喋ったことないけど、流石に籠目先輩だって、いくら喧嘩を吹っかけたとはいえ、部誌を燃やすなんてことしないと思う……」
「ていうかこの黒いの、本当に煤なのか? 黴みたいにも見えるな。写真だと微妙にわかんないや」
「不気味……」
小夜香さんは困ったように呟いた。
昼休み終了五分前を告げる予鈴が鳴った。
「ねぇ小夜香さん。これ実物を見せてもらうことってできないかな?」
「気になるの?」
「まぁ、なんとなく」
「あ、わかった。メルの好きそうな事件だなーって思ったんでしょ」
ぎくっとした僕は目をそらす。小夜香さんは溜息をついたが、まんざらでもなさそうだった。
「しょうがないだろ、メルが暇だ暇だってうるさいんだから」
「いいよ。いつもみたいに、ついでで解決してくれるなら助かるし」
小夜香さんは薄墨色の睫を伏せる。
「入院しっぱなしのメルに何か面白い話をしてあげたいっていう気持ちは、私も同じだから」
「……うん」
と、僕は同志のように頷いて見せたけれど、小夜香さんの気持ちは友情からくる純粋な厚意だ。僕のそれとは大きく違う。
「面白い話と言えばね、副部長さんがプロのラノベ作家なんだよ。すごいよねー」
小夜香さんは憧れを滲ませた声で、いつもはじっとりしている双眸を光らせた。
「へぇ、それはすごいな。プロって、本とか出してるのか?」
「うん、デビュー作のシリーズがもう五巻目で、人気作家なんだよ。コミカライズとかしてて、そのうちアニメになるんじゃないかって言われてる。莉緒も――私の友達も、その人のファンで入部決めたんだって」
小夜香さんは嬉しそうに教えてくれた。
「『しかしにシリーズ』っていうんだけど……知ってる?」
「知らないな」
「『屍坂冥子は副業で死神をやってますが全然儲かりません』っていうタイトルで、巻数ごとにタイトルの最後が変わるの。『眠れません』とか『バフれません』とか。最新の五巻も今日発売なんだ。あ、その友達が『昨日フラゲできた』って言っててね……」
なんだか聞き覚えがあった。
やたらと長いタイトルの背表紙、絶対にどこかで見た。
「……! それ、作者の名前が食べ物みたいなやつか?」
「そうそれ! 『牛すじ。』先生!」
放課後。
僕は文芸部の見学希望者として部室に遊びに行くことになった。
《しにしかの牛すじ。って好きか?》
《「しかしに」ね。まぁまぁかな》
スマホでメルにメッセージを送ったら速攻で返って来た。けっこう好きってことだろう。
「見学っていう体だけど、本当は入る気ゼロなのはちょっと気が重いな……」
「別に大丈夫だよー。ゆるい感じの部だし」
校舎と部室棟を繋ぐ渡り廊下は、部活へ向かう生徒たちで騒がしい。
部室棟は二階建て。運動部はグラウンド脇のプレハブを部室にしているので、ここに部室を持つのは主に文化部だ。入口の詰め所には防犯のためか、管理人がいる。用務員を定年まで勤めあげ、退職後に再雇用になったという気の良いおじいちゃんだ。穴の開いたアクリル板の向こうにいつも置物みたいに座っている。
内装は校舎とあまり変わりなく、似たような部屋がいくつも並んでいた。廊下に面した側は教室と同じく、嵌め殺し窓が連なっていて、色んな部活のようすが窺えた。
廊下の中ほどに「文芸部」はあった。
引き戸の取っ手下にはあとから取り付けたと思われるナンバーロックがくっついていた。他の部室でもたまに見る、ホームセンターで売っているようなやつだ。
小夜香さんがノックする前に、僕は硝子の反射に目を眇め、中で読書していた少女を捉える。
窓際でレースのカーテンが大きく煽られた。陽光を受けて、その少女は溶けていきそうな儚さを湛えていた。彼女はノックの音に振り向き、まっすぐな黒髪のつやがさらりと照り返す。
こちらを向いた少女はページの間に指を挟んで「あぁ、こんにちは」と微笑んだ。抜けるように白く、華奢な美少女だった。
「今日来るって聞いてなかったからびっくりしちゃった。もしかして、正式に入部する気になった?」
「いえ、それはちょっと……。でも代わりと言ってはなんですが、見学希望者を連れて来ました。同じクラスの友達でエナっていいます」
改めて名乗った僕を、彼女は早速「エナくん」と呼んだ。
「初めまして、私は三年の秋月咲良。副部長です。よろしくね」
差し出された手は白魚のようで、強く握れば僕の握力でも潰れてしまいそうだった。
「副部長? じゃあ、あなたが牛すじ。さん……?」
「え、もう知ってるの? あはは、ちょっと恥ずかしいな」
副部長は名前の通りほんのりと桜色の唇を尖らせるが、すぐに笑顔に戻る。
ロの字に並べられた八つの机の一角に、僕と小夜香さんは座った。
「他のみんなは、まだですか?」
小夜香さんが尋ねる。
「あれ? 莉緒に聞いてない? 今学期は私以外みーんな委員会とか係になっちゃったから、授業が終わっても何かしらやることがあって、いつも遅れてくるの。一人で待つのは原稿がはかどるからいいんだけどね」
開いたポメラを指差しながら彼女がそう言った矢先、勢いよくドアが開いた。
「やぁ諸君! 原稿は進んでいるかね?」
鞄と制帽を小脇に抱えた眼鏡の男子生徒が堂々と入って来た。
学ランの襟についた組章は三年の緑色。足元は校内なのに下駄だった。というか制帽も、別に学校指定のものではない。県一は校則が緩いので染髪も可だし色んな格好の人がいる。
「部長、お邪魔してます。お昼は突然連絡しちゃったのに、ありがとうございました」
「おお小夜香くんか、久しぶりだな。なに、ミステリのことならいつでも頼ってくれてかまわんぞ。名作を布教できるのは嬉しいからな。ソムリエのように見繕って見せよう」
そこへ男子が二人と女子が一人、揃って入ってくる。女子生徒は例の小夜香さんの友達、早坂莉緒だった。
男子のほうは、覇気のない顔を直毛で半分隠した痩せ型の生徒と、むくむくした子熊のような生徒だった。組章は青。二人とも二年生だ。
「あー? 今日は大所帯だな」と半顔のほうが言う。
「彼は?」と子熊が僕を指さした。
文芸部の部員は全部で五人と聞いていた。
もしかして、彼らが一昨日「小説論」でぶつかり合った先輩たちじゃないだろうか。
三年が卒業したら廃部ぎりぎりの人数になってしまうとのことで、見学者は歓迎された。
僕たちは机にかけて、改めて自己紹介をすることになった。
ミステリマニアの部長。仙国万里。
ラノベ作家の「牛すじ。」こと黒髪美少女の副部長、秋月咲良。
小夜香さんを部に誘った友人で唯一の一年生、速読が得意な早坂莉緒。
スプラッタとホラーを愛する、半分顔を隠した陰気な二年、籠目先輩。
感動小説が大好きな、子熊のような作家志望の二年生、三雲先輩。
「しかしこんなときに見学希望者とはな……」
部長は顎に手を添えて難しい顔をした。
僕は内心の焦りを隠しつつも、チャンスを逃してはならないと思い「部誌のことなら、実は小夜香さんから聞いています」と話した。
籠目先輩の目が光る。
「エナくん、もしかしてその謎に惹かれてうちに来たの?」
「え?」
「部長と同じミステリマニア、とか? 汚された刷りたての部誌三十部。誰が? 何のために? みたいなさ」
彼はくくっと笑う。僕は話を合わせることにした。
「……バレましたか。そうなんです。僕は日常の謎ってやつに目がないんですよ」
「ぷっ、お前面白いな」
文芸部は思っていたよりもずっと和気あいあいとしていた。
しかも部長と副部長は付き合っているらしい。彼女だったら教室でもモテそうなものなのに、こんな変わり者を選ぶとは、やっぱり小説家だからだろうか?
驚いたことに副部長は檎林学園からの転入生だという。このことは小夜香さんも知らなかったようで、驚きの声を上げた。
「うわ、お嬢さまじゃないですか。どうりで……! 家でボルゾイ飼ってるって言ってましたもんね」
「あっれ? アラスカンマラミュートじゃありませんでしたっけ?」と籠目先輩。
「どっちも飼ってるの。籠目くんにはまだ言ってなかったっけ? ボルゾイは夏ごろに親が知り合いから貰って来てさ」
「すげー。エサ代だけでも馬鹿にならねーのに……」
副部長は「別にたいしたことないから」と片手をぴらぴら振った。
檎林学園とは、かつて甘宮メルも通っていた県内にある中高一貫の名門私立女子校だ。
小夜香さんの言う通り、学費と偏差値の高さは全国でも群を抜いており、寮もあるので東北中から選ばれた裕福な子女が集まってくる。定員は一学年たったの六十人だが、毎年一人はハーバードに入る、なんて言われているから、そのレベルは県一の比ではない。
ちなみにいうと、僕の妹も受験を検討している。せっかく自宅通学できる距離にあるのだからこれを活かさない手はない。幸いうちも経済的には豊かなほうだ。父に頼めば学費くらいぽんと出してくれるだろう。
「そんな良い学校からどうして……」と小夜香さんは驚いたようすで呟いた。
独りごとのつもりだっただろうに、聞こえてしまったらしく副部長は困ったように笑った。
「……作家活動がバレて、問題になっちゃって」
「立派なことなのに……」
小夜香さんは残念そうに言った。
「ライトノベルってところが良くなかったんだろうなぁ。作家辞めるか退学かって迫られて仕方なく、ね」
せつなげな横顔を見せたのは一瞬で、彼女は次の瞬間には笑っていた。
「それで転校か……辛かったですよね。しかし、こんな人って現実にいるんだな……」
頭が良くて裕福で、容姿も優れて、才能もあるが、悲しい過去を負っている。
まさしく青春小説のヒロインのようじゃないか。ドラマティックな人生が良く似合う。
「何もすごくないよ。やりたいことやってるだけ」
「副部長かっこいい!」と三雲先輩が調子よく言う。
「あぁ、俺もいつかデビューしたい! 羨ましいよなぁ」
部員たちは頷いた。部長は真剣に、早坂さんは目をそらし、籠目先輩はひねくれた笑みで。小夜香さんの顔には「ふーん」と書いてあった。
「やっぱり副部長みたいに新人賞に応募したほうがいいんですかね? 『ツヅリスタ』はなかなかPV増えないし、出版社から声がかかるなんて夢のまた夢……。たまに心折れそうになるんですよ」
「つづりすた?」と呟いた僕に、「大手の小説投稿サイトだよ」と小夜香さんが教えてくれた。
「投稿サイト……? え、三雲先輩の小説をそこで読めるんですか?」
「あぁ、IDは部誌の作者紹介にも書いてあるから、気が向いたら読んでみてよ。他のみんなもアカウント持ってるし、感想くれたら嬉しいなぁ」
すごいな。みんな本当に小説を書いているのか。
「部長だけは、絶っ対ID教えてくれないんだけどな」
籠目先輩が横目で彼を見やる。
「部誌に書いているものとは毛色が違うから見せられない、と言ってるだろうが。何度も言うがエロではないぞ」
「はいはい。まあ本気の小説ほど人には見せられないもんすよね。で、エナくんのIDは?」
「や……僕やってないです」
なんだー、とがっかりする部員たち。
副部長が嬉しそうに目を細めた。
「私、ここに転校して来てよかったな。こんなふうに創作好きの友達と話したりってこと、なかったし。県一なら目一杯執筆活動できるしね」
「ちょうど今日も、『しかしに』の新刊が出るんですよね」
小夜香さんが明るい声で言うと、一同が沸いた。
「莉緒の家は本屋だから、親に頼んで昨日フラゲしたって、すごい喜んでたよね。昇降口でも歩きながら読んでたし。もう読み終わった?」
水を向けられた早坂さんはぎこちなく返した。
「あ、あぁそれが……。一時間目にこっそり読んでたら没収されちゃって……、まだ途中までしか読めてないんだ」
どんまい。せっかく人より早く読めたのに、お気の毒に。
「そっか、残念だったね……。そだ、私も帰りに課金のカード買わないと……」
「む、小夜香くんは電子派だったな」
「はい。家が狭いので、あんまり物を増やしたくなくて……部長は圧倒的紙派、でしたね」
小夜香さんはくすくすと笑って、話題を変えた。
「四巻の最後、新キャラにやられて、また冥子が死ぬじゃないですか? 続きが気になる終わり方でしたよね」
「そうそう、またいつもの決め台詞と共に生き返るんでしょうけど、あそこからどうやって勝つのか想像もつかないですよ」
三雲先輩も同意して盛り上がると、副部長はわざとらしくウィンクした。
「それは読んでのお楽しみ」
何となく、早坂さんの顔色が気になったものの、みんなの話はどんどん流れていった。
「あの、例の部誌の件を詳しく聞かせてもらえませんか?」
お喋りが落ち着いたのを見計らって言ってみた。
みんなは少しだけ気まずそうな顔をしたが、やがて籠目先輩が立ち上がり、棚から冊子の束を持ってきて、部長の傍らに置いた。
部長はくるりと回し、冊子下側の側面をみんなに見えるようにした。
確かこの部分を本の「地」と呼ぶのだったか。上側の「天」と横側の「小口」は無傷のようだ。
「地」には、じわじわと広がるような黒い汚れが一冊一冊違う位置についていた。
「すでに連絡した通りだが、改めて全員で状況を確認しよう。昨日の放課後、印刷会社から届いたばかりの部誌、三十部すべてがご覧のとおり、汚されていたのが見つかった」
部長は一冊取り上げて冊子をパラパラ捲る。
部誌はB6サイズで五十ページほど、厚さは五ミリ程度だ。
僕はすぐに気が付く。
「……これ、焦げでも煤でもないですね」
紙はややよれているが、それは燃焼によるものではなく、何かを強くこすりつけたような歪み方だった。
「なんだ、燃やされたんじゃなかったんですね……」
小夜香さんがほっとした顔で言う。
「煤って?」「燃やされたぁ?」と部員たち。
「ええと、莉緒から聞いたんですけど、一昨日の部活中に『燃やしてやる』みたいな、論争が起きたって聞いて、私てっきり、本当に誰かが燃やそうとしたのかと……」
籠目先輩と三雲先輩は顔を見合わせて、笑った。
「ちょっ、どういうふうに伝わってんだよ? いつものことだろ、俺たちの趣味が合わな過ぎて罵り合うのは」
「そうそう、挨拶みたいのものだよ。僕だって、『悪趣味なだけのホラー小説なんか読んでも何も得るものない』ってよく言うし」
「んだと? お前本当わかってねーな」
言い合う先輩たちの姿に、小夜香さんはじっとりした目で下を向く。早坂さんも苦笑いしていた。
文字でのコミュニケーションは難しい。その辺は完全に僕たちの早とちりだったようだ。となると例の発言は無関係のようだ。
「でも、言霊ってのは侮れないからな。俺の発言が引き金になって何かの霊を呼び出した可能性も……」
「ないですって」
早坂さんが真顔で突っ込む。
「今回の論争には、珍しく部長も乗って来たんだよね」
三雲先輩が思い出したように天井を見上げる。
「あぁ、乗って来たっていうか、いつになく考え込んでましたよね。普段は『小説は面白ければいい』ってスタンスなのに。『本当に病気で長くない人が、これを読んだらどう思うだろうか……』って。びっくりしました。いえ、言いたいことは解りますけど……」
早坂さんの言葉に、部長は大きな手で眼鏡のブリッジを押し上げた。
「感動させるために、安易に病気を持ち出すのは考えものだ……と思っただけだ。三雲くんの小説を否定したいわけではない。良い作品だった」
部誌は年四回発行で、新刊は今週末の文芸イベントや、のちの文化祭で売る予定だったという。読むのに支障はない汚れだけれど、これでは売り物にはできないだろう。
詳しい事件のいきさつはこうだ。昨日の朝、顧問の先生が部長に「印刷会社から届いた部誌を部室に置いておいた」と教えてくれたそうな。
メッセージアプリの連絡でそれを知った部員たちは、放課後になるとわくわくしながら部室へ行ったという。
一番最初に部室に着いたのは、部長と籠目先輩だ。渡り廊下でばったり会い、そのまま一緒に部室棟へ来たそうだ。今学期はいつも一番乗りだった副部長は、その日は歯医者に行くので部を休んでいた。
「部誌が届く日にちょうど歯医者だったなんて、残念でしたね」
僕が言うと、副部長は唇を尖らせる。
「ね。部誌が届くって知ってたら、部室に寄って一冊貰うくらいしたんだけど、私、実はスマホ持ってないからトークルームも入ってなくて」
僕と小夜香さんは同時に驚きの声を上げる。
「親が厳しくてさ。ものすごーく心配性なんだよね……晩婚でネットに疎いし、もう『子どもにネット使わせると犯罪に巻き込まれる』くらいに思ってるの」
「それはなんとも……」
天然記念物レベルの価値観だ。
秋月家は僕が思ってる以上に古式ゆかしいお家なのかもしれない。
話は部長と籠目先輩の足取りに戻る。
「部室に入っても、しばらく気付かなかったんだよ。汚れた部分が窓側を向いてたから」
「うむ。いくら部誌を愛していても『地』なんてまじまじとは見ないしな。小夜香君の描いた表紙が美麗だったこともあり」
部長が肩を竦めた。
部誌を持ち上げようとした部長は、持った角度が悪かったせいで、部誌の束を滑らせ床にばらばらと落としてしまったらしい。二人で拾い集め、向きを揃えているときに、ようやく地が汚れているのに気が付いたという。
「最初は印刷会社のミスで何かの汚れが付いてしまったんじゃないかと思ったんだ」
部長は顧問を通して問い合わせようと思ったが、顧問は宅配業者から受け取ったときにしっかり確認しており「そんな汚れはついていなかった」と証言している。
僕は手を伸ばして部誌を一部掴む。もう一度近くで良く観察してみた。
「この汚れは、濃い鉛筆……? とも違うか、真っ黒だし、粉っぽいし、触ると指につくな」
「もしかして木炭じゃない? デッサンに使う」
副部長が言った。そして棚を漁り、古びた缶ペンケースを持ってきた。
「ここは昔、美術部の部室だったから、道具が残ってるんだ」
彼女はコピー用紙の束を持ってきて、木炭の欠片を側面に強くこすりつけた。すると、部誌についているのとそっくりな汚れができた。
「ビンゴだね……」
「『凶器』も部室にあったとなると……」
喋りながら僕は気付く。一同は浮かない顔をしていた。
「あの、この部室の鍵はどうなってるんですか?」
目をぱちくりする小夜香さんをよそに、みんなが渋い顔をした。やっぱりだ。
「そこなんだよ。エナくん」
副部長が理知的な瞳をつむる。
「出入口の引き戸はナンバーロックの電子錠を付けてるの」
「そういえば、来るときにも見ました」
僕は引き戸に視線をやる。
「うん、うちは締め切りまでに原稿を提出できれば、放課後の部活に顔を出すかどうかは自由なの。欠席の連絡もいらない。帰る時間も自由。私は毎日来るけどね。……だから誰かを鍵当番にするって方法だと色々不便でさ。顧問と正部員しか知らない暗証番号でロックすることにしたの」
「となると、顧問の先生が置いておいた部誌にいたずらできるのなんて、部室に入れる人だけ……ってことになりませんか?」
僕は念のために窓をチェックしに立ち上がった。ここは二階だ。外には木や配管など人が登って来られそうなものはない。
頭の後ろで手を組んだ籠目先輩が身体を反らして言う。
「ちなみに、汚れに気付いたときは窓の鍵はかかってた。それは俺と部長で確認してる」
意を決したように、副部長が立ち上がる。
「……この中に、やった人はいる? 怒らないから正直に話して」
「よせ、聞いても無駄だ」
「でも万里くん、何か理由があるかもしれないじゃない。みんな小説が大好きで、本気で原稿書いてる。全力で作ってる大事な部誌のはずなのに、ただのいたずらでこんなことするなんて、私には信じられない」
「咲良……」
確かに、犯人が部員だとしたら、何の得があってこんなことをするのかわからない。
部長は重い口を開く。
「過ぎたことはどうにもできん。幸い入稿データは残っているんだ、また作ればいい。今から刷り直しても週末の文芸イベントには間に合わないが……、既刊も沢山あるし、イベントはまたある」
そして彼は机の上で力強く両手を握りしめた。
「今回の号は、次のイベント……文化祭までに刷り直すとしよう。幸い部費は余っているからな。もう犯人捜しはやめにしよう。いい機会だ、せっかくだからもっと原稿をブラッシュアップしようじゃないか」
部長が力強く言う。
「熱いっすねぇ……しゃあない、頑張りますか」
シニカルな顔を崩さない籠目先輩だったが、みんなも、一人、また一人と明るい顔で頷いていった。
「エナくん、君も何か書いて来るといい。今号はページ数が少なかったから、短編小説一本分くらいならページを増やせるぞ」
「へ?」
部長は早速黒板に、かかっ! とチョークで締め切り日を書いた。達筆だった。
「いや僕、小説なんて書いたこと……」
「書いてみたいと思って我が部の門を叩いたんだろう? とにかく書いてみることだ。作法だの技術だのを勉強してから書こうと思ってると、いつまで経っても書き出せないものだぞ。まずは完成させろ。まさか此度の事件だけが目当てで来たわけじゃあるまい」
そのまさかです、とは言えない。
「最初は誰だって初めてだ。楽しみにしているぞ」
面倒な仕事が増えてしまった。
下校時刻を知らせるチャイムが鳴った。
僕たちは自分用に汚れた部誌を一部ずつ貰って帰ることになった。
校門を出てそれぞれの方向にばらけ――部長と副部長は恋人繋ぎで帰っていった――小夜香さんと二人きりになったとき、彼女は歩きながらスクールバッグのジッパーを開いた。
「これ、良かったらメルにあげて」
差し出された部誌に目を丸くする。
「入稿データ持ってるから、読めるし」と彼女はにべもなく言う。
「……いいの? 紙の部誌は思い出になるぞ?」
「いいの! 知ってるでしょ? 私、とにかく物を増やしたくないの」
「……そか。じゃあ貰うよ。ありがとう」
彼女は薄く微笑んで「こちらこそ」と後ろ手を組んだ。
それから、僕は小夜香さんに「教室に忘れ物をした」と言って、部室棟に戻った。
ちょうど文化部生があらかた帰って辺りはしんとしていた。
「お疲れさまです」
「はいどうも」
「ちょっと訊きたいことがあるんですが、いいですか?」
部室棟の管理人は「んん?」とアクリル板の穴に耳を押し付けてきた。
「昨日、部活の時間より前に部室棟に来た文芸部の生徒はいませんでしたか?」
管理人は電気を消しながら、脇のドアからのそのそと出て来た。
「文芸部? 生徒さん見ても誰が何部かはわかんねぇよ。名前もわからねぇしな。一日に何十人も通るし、昼休みに来る子もけっこう多いけども」
「そうですか。そうですよね……。じゃあ顧問の先生なら、覚えてますか?」
「先生はわかるよ。朝に谷町先生が来たな、本の束を持って。……ああ、あの先生が文芸部の顧問か。今年来た若い先生」
谷町先生は去年大学を卒業したばかりのちょっと綺麗な体育の先生だ。文芸部のみんなにさりげなく聞いたところ、彼女は幽霊顧問というやつで、部活のことは「部員の自主性」に任せているらしい。本当は運動部の顧問をやりたかったのだろう。
この情報からすると、たぶん彼女は「木炭のありか」もとい「部室内に木炭があること」すら知らない。容疑者からは外していいと思う。
「谷町先生、『部室の鍵が開かない』って困った顔でここへ戻ってきて、見に行ってやったら、番号押したあとに『えんたー』押すの忘れてただけでな」
管理人さんは、思い出し笑いした。
「そのあとは、どうしましたか?」
「先生は本を置きに来ただけだから、置いて、鍵かけて、一緒にここまで戻って来たよ」
「部誌のようす、覚えてませんか? どこか黒く汚れていたりしませんでした?」
「汚れ? そんなのなかった気がするけどなぁ」
彼は顎髭を撫でながら怪訝そうに目線を上げる。
ずっと管理人さんが一緒だったなら、谷町先生がその場で細工することはできなかっただろう。
おそらく、犯行はこのあとから放課後に部長と籠目先輩が部室に入るまでの間……昼休みに行われた線が濃厚だ。
僕は念のため、もう少し突っ込む。
「制帽に下駄を履いてる、声の大きい男子って、見たことあります?」
「あぁ、あの子はわかるよ! 部長って呼ばれてる三年生の子だろう。応援部かねぇ? いつもしっかり挨拶してくれる。昨日は珍しく二人で部活へ来てたな。もう一人の男子はどんな子だったか……」
籠目先輩はこれと言って特徴はないから、覚えられていないのだろう。昨日の一番乗りは二人というのも、本当のようだ。
「そうですか。教えてくれてありがとうございます」
僕はお辞儀して校門へ向かった。
このくらいで良しとしよう。当日のいきさつについては、多分誰も嘘をついてない。
《今から行く。「しかしに(5)」と文芸部の部誌を持ってく》
自動ドアの閉まる音を背に、通い慣れたエントランスを抜けていく。
真っ先に目に入るのは外来の会計と、その待合スペースにずらりと並んだ合皮のソファ。ディスプレイには次々と受付番号が点滅し、患者もスタッフもせわしなく廊下を行き交う。静かにしきれない独特のざわめきは、大病院特有の音だ。
もりとか総合病院は、目抜き通りから少し歩いた日高美川沿いに建っている、一族経営の私立病院だ。
僕が生まれて数年後に建て替えられた建物はまだ新しく、著名な建築デザイナーに依頼したとかで外観も内装も随分と洗練されていた。特に外来は開放的だ。南側の大きな窓から自然光が目一杯降り注ぎ、従来の大病院の「恐い」「堅い」といったイメージからは程遠い。
「あ、エナくん。いらっしゃい」
会計の反対にある総合受付から明るい声がした。すっかり顔見知りになった、受付係の椎名さんだ。
「こんにちは、今日もメルのお見舞いに来ました」
「健気だね……本当に」
僕は上手い返しが見つけられず、口ごもる。
「あぁ、ごめんね。私、メルちゃんのことは幼稚園のころから知ってるから、つい感情移入しちゃって。でもエナくんみたいな優しい彼氏がいて良かった。こうやってまめに通って、支えてくれてるんだもん……」
しんみりとした空気が流れ、僕は複雑そうに微笑んで見せるほかはなかった。奥から、別の顔見知りの受付嬢がやって来たので、足早に去る。
受付のほうから「純愛」とささやく声が背中に刺さった。
入院病棟へ通じる見舞客用のエレベーターは硝子張りで、吹き抜けのエスカレーターが隣接していた。まるで都会のオフィスビルのようだ。
ベルの音と共にエレベーターのドアが開く。最上階のボタンを押した僕は、遠ざかるリノリウムの床を見下ろして、呟いた。
「そんなんじゃねぇよ……」
深呼吸。ノック。返事のあと、引き戸を引く。
「や、メル。体調はどう?」
「普通」
サイドボードの上に「しかしに(5)」があった。
「もう買ってたのかよ」
「予約注文してたから昼間に届いた。あぁ、エナ買って来たとか言ってたっけ?」
メルは枕元のスマホ画面をつついた。未読のままのポップアップが映る。
「仕方ない、これは僕が読むとするよ。途中からでもだいたいわかるだろ。それよりさ、大ニュースがあるんだよ。なんと牛すじ。はうちの学校の文芸部員だったんだぜ」
はぁ? と返された。
僕は順を追って、今日のフィールドワークを報告して聞かせた。
十八時になった。時間ぴったりに運ばれてきた病院食を食べながら僕の話を聞いていた彼女は、ぱあっと頬を染めて、明らかに嬉しそうにした。
「世間は狭いのね。牛すじ。が現役女子高生なことは知ってたけど……」
「知ってたのか?」
「一巻のあとがきに書いてたもの。牛すじ。って、あとがきがはっちゃけてて笑えるのよね。時雨沢恵一の影響らしいけど、五巻のあとがきも笑ったわ。牛すじ。は献血が趣味なんだって。嫌がる弟に献血ルームの魅力を説きまくってむりやり連行したら、おじいちゃんがついてきたって話でね」
メルはふふっ、と思い出し笑いする。だいぶこの小説が好きらしい。
「ねぇどんな人だったの? その秋月咲良さんとやらは」
さてどう語ったものか。メルは断じて認めないけれど、小夜香さん以外の女性を褒めると機嫌が悪くなるので非常に面倒臭いのだ。僕と小夜香さんには幼馴染として強固な絆があるのだけれど、天地がひっくり返っても恋愛関係に至ることはない。詳しく語ったことはないもののメルは察しているようだった。
副部長はどんな人か……か。彼女には褒めるところしか見当たらないけれど……。
「そうだな、正統派ヒロインの要素を役満したみたいな、没個性的な子だったよ。作家なだけあって勉強できるっぽいし。『転校生』って属性まで付いてる。高校で転校生なんて珍しいだろ? 二年次に檎林から転入してきたんだって」
「えっ、檎林にいたの?」
「縁を感じるよな」
僕は肩を竦めて、メルが食べ終わった食器を廊下の配膳車に戻してきた。キッチンの電気ポットから湯を汲んで、ウォーターサーバーの水と混ぜ、飲み薬用のぬるま湯を作る。
「じゃあ私が中三のとき、高二? 嘘お! どこかですれ違ってたかもしれないじゃない。秋月、秋月……」
メルはますます興奮し、うさぎかくまか判らない白いぬいぐるみをぎゅうぎゅう抱きしめた。
「いたかなぁ、そんな人」
ぬいぐるみを脇に押しのけ、頬杖をついた。
「高等部と中等部だろ? そりゃ知らなくても……」
「ううん。私、中高と顔は広かったのよ。人気者だったもの」
彼女は臆面もなく言った。
「人間関係って一番面白いんだから。そんな情報、見逃すわけないでしょ」
僕は学園での彼女を知らない。
けれど、当時猫を被っていた彼女が異常なほどの人気者であったということは知っていた。彼女がここへ入院したばかりのころも、連日見舞客の生徒が通ってきて病室が千羽鶴で埋め尽くされたし。
あぁ、そうだ。
副部長は昔のメルに少し似ているかもしれない。
「しかも、作家デビューが問題になって退学。なんて、そんな大事件あったら私の耳に入らないわけないけど」
「その事件のときは、君はもう学園にいなかったんだぞ? 本人も学校もひた隠ししてたら、情報網に引っかからなくてもおかしくないんじゃないか」
「…………んー。まあ、そうか……。はぁ、私って本当に俗世を離れちゃったんだなぁ」
僕は鞄から部誌を取り出した。部室で撮った写真はすでに送ってあるので、おおよその状況は伝わっている。
「例の部誌の実物ね?」
「意外なほど面白いぞ。正直舐めてた」
受け取ったメルは早速「地」を見る。薄い冊子なので、重ねていたときに感じた派手さはないものの、しっかりと黒い汚れが付いていた。
「へぇ、結構面白そう……って」
メルが目次の中の一文に目を止める。
実録調査レポート「安楽寝台探偵考」 カゴマニア
ふっ、と失笑。
「私じゃない」
「な? 面白いだろ」
一年ほど前からこの街では「安楽寝台探偵」という都市伝説が囁かれ、ネット上でも広まっていた。
――とある病院の地下に、不思議な美少年ないしは美少女が入院している。そいつは不治の病で起き上がることもできないほど身体が弱いのだけれど、話をするだけでどんな謎も解いてしまう。しかし気まぐれなため相談内容が気に入ったときしか助けてくれないし、気に入らなければ寿命を吸い取られる。……というものだ。
ちなみにコンタクトを取る方法は、各種SNSで特定のハッシュタグをつけて投稿するとか、丑三つ時に「040-#4#4-****」に電話する、とか。様々なバリエーションがある——
もちろん甘宮メルにそんな超常的な力はないのだけれど、噂が広まった時期と内容からすると、十中八九、彼女が元ネタだろうと僕たちは結論していた。
「私、探偵なんてやったことないんだけど」
「ないね」
好奇心で面白そうな事件や謎を調べて、満足したら引き上げる。
僕たちがしているのは、それだけの暇つぶしだった。
メルは副部長の作品から目を通し始めた。
僕もぱらぱらと内容を見てみる。
部長の小説は「第五回」と書いてあった。本格的な孤島ものの推理小説を連載しているようだ。途中から読んだけど、なかなか硬派で面白そうだ。
副部長は「しかしに制作ノート」と題した裏話。主人公が「生き返る」ときのお決まりの台詞について。名台詞に多いと言われている「七五調」というものを採用しているらしい。なるほど「月に代わって、お仕置きよ」とか「海賊王に、俺はなる」とかか。敵に逆転する爽快感が読者に求められているので、毎巻必ずこれを言うシーンを入れることにこだわりがあるという。
三雲先輩は読み切りの恋愛小説だ。タイトルは「真夜中の君と彗星を探して」。これだけで切ない情景が浮かぶ。天体観測を通じて出会った男女の悲恋らしい。
籠目先輩が「安楽寝台探偵考」で、早坂さんは短歌を二十本くらい書いている。
僕は表紙イラストをまじまじと見返した。外国にある巨大な図書館のような、緻密な絵だった。小夜香さん自身は特に絵を描くのが趣味というわけでもないし、熱意もないようだけれど、スマホを使って指でちまちま描いているところを見たことがある。
どれから読もうか、とページを捲っていると、バサっという音に顔を上げる。
メルが自身の膝、布団の上に部誌を雑に置いていた。
「なんだよ?」
「……これ、刷り直してイベントで売るんだっけ?」
「あぁ、次の文化祭でな。部長がブラッシュアップしようって燃えてたから、ちょっとは変わると思うけど……」
僕の作品も載るかもしれないし。
「なるほどねぇ。それが動機かな」
「え?」
メルはスマホを操作する。横から覗くと、昼間僕が送った写真を見返していた。
「汚そうとして木炭を擦っただけにしては、なんだか複雑な形してるのよね……」
シャーペンの先をカリカリ鳴らしながら、僕は頭をひねっていた。
昼休みの図書室は、微かな物音と適度な人の気配が心地よかった。
小説は、死んだ母が好きだったらしく家に沢山あったから、平均的な男子高校生よりは読んでいるほうだと思う。けれど書くとなるとさっぱり勝手がわからない。「むかしむかし、あるところに」と書き出して手が止まる。欠伸を一つ。
昨晩、部誌を読み始めたらけっこう面白くて、いつのまにか読破してしまっていた。おかげですっかり寝不足だ。
特に「真夜中の君と彗星を探して」では不覚にもうるっと来た。
この小説は、典型的な「ヒロインが病気で死ぬ青春ストーリー」だった。試しに妹にも読ませてみたら、ぼろ泣きしてしまった。みゆは感受性が豊かなのだ。あんな心を締めつけるような話を思いつくなんて、僕にはとてもできないけれど、よく似た感情は痛いほど知っていた。
――むかしむかし、あるところに、中学三年生の少年少女がいた。
あぁ、するするとシャーペンが動く。
――少女は人気者だったが、それは猫かぶりで、それを見抜いた少年は……。
書いていくうちに心が凪ぐような、不思議な感覚に陥った。
「厭な気持ちや問題を書きだすと、心が整理される」のだと、メルの兄、甘宮明良も言っていた。最もその精神医学的見地からのアドバイスは、僕ではなくメルへ向けられたものであったけれど。
結局彼女は、過去のことなんて一文字も紙に書いたりはしなかった。
――そして少年は死にたくなったが、少女はそれを嘲笑った。
――彼は己が許せなかった。息をしていることさえ、厭で厭で厭で……。
「エーナくんっ」
ぽん、と両肩を叩かれた。
シャーペンの芯が音を立てて折れる。
振り向くと、副部長が小脇に本を挟んで立っていた。
「……ご、ごめん! 驚かせちゃった……?」
副部長のリアクションを見て、僕は自分がどんな顔をしていたのか悟る。原稿用紙は手汗でよれていた。
「……大丈夫?」
「あ、ああ、はい……」
笑顔を作ると、彼女は戸惑いながらも隣の椅子を引いて座った。彼女が持っていた本は「しかしに」の五巻、だった。
「それ、図書室にも置いてるんですか?」
「ううん、私物。静かなところで読みたくて」
「へぇ、本になったあとも読むんですね」
「作者だもん、チェックも兼ねて読み返すの。読むの遅いから全然進まないけど」
そういってこちらへ見せた栞の位置は、まだまだ序盤だった。
少しの沈黙のあと、副部長は僕の手元に視線を落とした。
「エナくんは……文芸部の原稿、書いてたの?」
「はい」
「どんな話?」
副部長は上目遣いに見上げて来た。
「……恋愛小説、です。学生が主人公だから、これも青春小説って言うのかな」
「へぇ、読んでいい?」
「まだ途中ですよ」
「途中でも。書き終わった原稿、これね」
僕の許可を待たずに副部長は原稿用紙を揃えて読み始めた。
小説の形になっているかどうかも怪しいけれど、副部長は本当に楽しそうな顔をしていた。僕は諦めて続きを書くことにした。
「エナくんみたいな子は何を書くのかと思ったら……、ずっと入院してる恋人を主人公が支える小説だなんて、まさかだったなー」
僕はかけていた消しゴムを落としそうになる。
「支える、とは違いますけどね」
恋人というのも、一緒にいる理由として便宜上そうしているだけだ。
「そうなの? 彼女のために身を粉にして頑張る少年って感じで、健気で胸が熱くなったけどな。エナくんもこういう話が好きなんだ、続き、楽しみにしてるね」
副部長が笑うと、ふわりと、シャンプーの香りが漂った。
「三雲くんの小説は読んだ?」
「はい。感動しましたよ。籠目先輩はああ言ってましたけど、僕は安易に病気を使ってるとは思いませんでした。妹もぼろ泣きしてましたしね」
「えっ、妹さんがいたんだ。ぼろ泣きって想像できない。エナくんの妹でしょ?」
「僕とは全然似てない、天使のような子なんですよ。『えなみゅ』って、知りません?」
「えなみゅ? クラスの子たちが話してたの聞いたことある……。写真とか動画投稿してる『東北一可愛い中二』だっけ?」
「あれ、僕の妹なんです」
僕はポケットからスマホを取り出して、写真投稿型のSNSを立ち上げた。
「この子? ふーん、すごいね、三万フォロワーか……」
「三万ってすごいんですか?」
というか大丈夫なのか。僕は基本「えなみゅ」のアカウントしか見ないので平均がわからない。
「個人のアカウントで三万はもう、インフルエンサーだよ」
猛烈に不安になって来た。妹が見も知らぬ三万人に無邪気に顔や声を晒しているなんて。みゆのことだから個人情報を特定されるようなヘマはしないと思うが。
頭を抱えていると「まぁ、私は五万人いるけど……」と副部長がさらりと言った。
そうなのか。じゃあ三万くらいは気に病む数字ではないのかもしれない。
「やっぱり人気作家は違いますね。SNSやってたの、知りませんでした」
「牛すじ。じゃなくて、私個人でやってるアカウントで! そっちでは作家なことは言ってない。パソコンからしかログインしないから、更新頻度もそれほど高くないしね。一女子高生としてのアカウントだよ」
牛すじ。のネームバリューがなくても、副部長もとても可愛い。顔写真を載せれば人気が出ても何ら不思議ではない。それに文才まであるのだから、些細なコメントだって人を惹きつけそうだ。
「やっぱり別格ですね、副部長は。あ、でも親御さんにバレたら、大目玉じゃないですか?」
「ふふ、そうだね。パソコンの履歴消すの、地味に大変」
僕は興味本位で聞いてみた。
「副部長のご両親って、何やってる人なんですか?」
「んーと、普通だよ? お父さんはもりとか総合病院の外科医で、お母さんは会社経営してる」
普通って何だっけな。
それにしても今の女の子ってみんなSNSやってるんだな……。
「そのアカウント、見たいです。教えてくださいよ」
「……恥ずかしいからダメ」
彼女は細く唸る。
「リアルの知り合いには知られたくないんだよね。牛すじ。でも秋月咲良でもない、本当の自分を解放できる場所が欲しいっていうか」
「はぁ。そういうもの、なんですか……?」
「そう……」
ふいに、秋風が窓硝子を揺らした。
「写真と日記を公開してるんだけど、元々、私が生きた記録みたいなものをちゃんと残したくて始めたの。だから知ってる人に見られてるとか、そういうことを変に意識しないまま、さいごまで自由に続けたいんだ」
副部長は、憂いを含んだ眼差しで、机を見つめた。
沈黙が下りる。
さいご、ってなんだ。
僕は違和感を隠さずに、視線で問いかけた。
誰かがページを捲る音がした。
「あのね……、部長が、珍しくあんなこと言ったのは、本当は私のせいなの……」
「どういう、ことですか?」
彼女と目が合う。
笑顔を作ろうと、強がる顔。
「……秘密だよ」
副部長は僕の耳にそっと唇を寄せた。
「私、本当はね――」
午後の授業はまるで身が入らなかった。
先生の声が耳をすり抜けていく。僕のノートには、塗りつぶした黒いぐちゃぐちゃばかりが増えていった。
――本当に病気で長くない人が、これを読んだらどう思うだろうか……。
部長が自問したのも無理はない。
副部長のどこか儚げな、眼差し。
「私、本当はね。心臓の病気で二十歳までは生きられないって、言われてるの」
彼女はなんてことないように、言った。
「……冗談、ですよね?」
「ふふ」
彼女はなおも微笑んで、胸に手を当てた。
「小さいころから、毎日薬飲まないと発作が起きちゃうんだ。でも、それも大人になるころには、身体に限界が来るんだって」
彼女は頬杖をついて、窓の外の真っ赤に色づいた紅葉を眺めた。
あと何回見られるのか、とでも言うように。
「どうして、そんなこと、突然……」
「部長にしか話してなかったんだけど……、なんとなく、ね? エナくんになら話してもいいかなって思ったの」
「僕なんか、昨日知り合ったばかりじゃないですか」
「過ごした時間の長さは関係ないよ。わかんないかな? 逆にクラスの友達とかには言えないの。みんなの楽しい学校生活に、こんな話題はいらないもん。でもエナくんって、私の病気のこと知っても特別扱いとかしなそうだし……」
目の前の少女と初めて会ったとき感じた。
折れそうに細くて、光に溶けそうだと。
それでも彼女はこうして、僕の目の前で呼吸をして、笑ったりまばたきしたりしているのだ。
あと二年かそこらで消えてしまうなんて。
そんなことって。
「……もっと小説書きたかったな」
絶句する僕をその場に残し、彼女は軽やかな足取りで図書室を出て行った。
青春小説のヒロインのようだと、ドラマティックな人生が似合うと、そう思っていたけれど。
僕は「しかしに(5)」をこっそり引き出しから取り出して、教科書の陰に隠して読み始めた。他の巻を読んでいないにもかかわらず、序盤から引き込まれた。
けれどどんなに面白くても、どうしたって彼女のことが頭に浮かぶ。胸に刺さる一文と出会うごとに哀しくなっていった。
五、六時間目、続けて読み通した。あっという間だった。
屍坂冥子はこれまでの戦いの中で、何度死んでも驚異的な再生能力で生き返って来た。
しかし後半で「命の残機」というものが明らかになる。実は彼女が生き返ることができる回数は、今まで死神として命を狩ってきた死者の人数と、イコールだったのだ。そして冥子自身も初めてその事実を知り、窮地に立たされてしまう。
一巻から読んでいたら、もっと驚いたに違いない。
その弱点を知った敵は、物量戦に持ち込んだ。間髪入れずに、冥子を何度も何度も何度も殺して、ついに残機をゼロにする。
最後のページで、彼女は仲間たちの叫びの中、血の海に沈んだ。
一度も決め台詞を言うことなく。
六巻へ続く。
「…………」
圧倒されて、溜息をつきながら本を閉じた。
牛すじ。は何を想ってこの展開を書いたのだろう。
今日の文芸部には全員が出席していた。小夜香さんも、僕に付き合って顔を出してくれている。
部員は各々好きなように活動していた。小夜香さんはスマホで、副部長は紙で「しかしに(5)」を読んでいたし、籠目先輩はタブレットで「SCP財団」を読んでいる。原稿を書いているのは部長と三雲先輩だけだ。早坂さんはスマホを横にしてゲームをしていた。
机に置いていた僕のスマホに通知が来る。メルからだった。
《報告ご苦労》
僕は午後の業間休みの間に、追加で得た情報をメルに送っていた。またぴろん、と通知音。
《もう飽きたから引き上げていいよ》
僕は画面をフリックする。
《何の説明もなしか?》
《説明いる? あんたもそろそろおかしいなって思ってるでしょう》
おかしい、ことなら、いくつかあるけれど……。
《部誌の地、もう一回ちゃんと見て。うちの病院のホームページも》
隣から「……っ?」と小さく息を飲む声が聞こえた。小夜香さんはスマホを両手で操作しだす。
「小夜香さん……? 新刊はもう読み終わったの?」
「うん、今……」と彼女は声を潜める。「エナは……、授業中に読んでたでしょ?」
小夜香さんの何か言いたげな瞳に戸惑う。
彼女がさりげなく角度を変えてスマホの画面を見せてきた。部誌の入稿データのPDFが映っていた。
同じ違和感を、感じているのだろう。
僕は頬杖をついて、硝子戸の戸棚に仕舞ってあった部誌を眺めた。
あれ?
これって、汚れというか――。
「…………っ!」
僕は立ち上がり、部誌の束を持ってきた。
「どうした?」籠目先輩が顔を上げる。
「みなさん、自分の分の部誌を持ってる人は、ちょっと貸してください」
ぴろんぴろんと通知音が鳴り続けるが、あと回しだ。
「部誌のことはもういいだろう」
部長が言うが、副部長は鞄から部誌を取り出した。
「私のあるよ」
「待て……!」
「エナくんっ、パス!」
捕まえようとした部長の手をすり抜け、副部長がからかうように無邪気に投げて寄こして来た。
「なんだ? ……あっ、そうか!」
籠目先輩が僕の動きを見ている途中で手を叩く。
僕は鞄から取り出した自分の分も足した部誌、計二十五部の重ねられた順番を並べ替えた。
汚れを縦に繋げるように合わせていくと、やがて三行のメッセージが浮かび上がって来た。
フクブチョウ
ギュウスジ。
ジャナイ
木炭に強く筆圧を込めて書いた文字。紙についたよれの方向も、綺麗に揃う。
「なにこれ?」
副部長は目をぱちくり、不思議そうな顔をしている。
僕はあれやこれやを思い出し、思考をフル回転させる。
メルはバラバラの順番で重なった写真を見ただけて、気付いたわけか。
僕は静かに彼を見下ろす。
「このメッセージ……いや、告発文をなかったことにしたのは、あなたですね?」
部長は大きく嘆息し、天井を仰いだ。
早坂さんがはっと口元を押さえる。
「あっ……、部誌を、落として床にばら撒いた……って」
「その通り。だけどアクシデントじゃなくわざとだったんでしょう。あの日、一番にこの文を発見した部長は、籠目先輩が気付く前に、落としたふりをして消したんです」
そして二人で拾い集めたときには、籠目先輩は「ただの汚れ」としか認識できなくなっていたというわけだ。
全員の視線が副部長に集まった。
「やだ、誰かの嫌がらせ……?」
彼女はむっとした顔になる。
「……みたいです」
三雲先輩と小夜香さんはショックを受けた顔で立ち尽くしている。
「……この中の誰かが書いたの?」
副部長はみんなに尋ねた。
ぴろんぴろんと僕のスマホが鳴る。
あぁ、引き上げていいって言われたのにな。
でももう遅い。思いつきだったとはいえ、僕はみんなの前で真実の端っこを捲ってしまったのだから。
「僕にも全貌がわかってるわけじゃないんですが……多分、事件が起きた一昨日の時点でこのことに気付けたのは、両方読破していた人だけです」
僕は部誌と、「しかしに」の最新刊をそれぞれ両手に掲げた。
「文芸部正部員のみなさんは、きっと部誌の入稿前の原稿データを読んでいましたよね」
「正確には、『読める環境にあった』ってだけだけどな。俺は本になってから読みたいから、三雲と自分のしか読んでない」
籠目先輩が言うと、三雲先輩が複雑な顔をした。結局この二人は仲が良いのだ。
「十分です。牛すじ。のファンでしたら、副部長の『しかしに制作ノート』はいち早く読みたいだろうという仮説が立てられます。けれど……」
僕は隣の彼女に尋ねた。
「小夜香さん、さっき『しかしに』の五巻を読み終わってすぐ、文芸誌のデータを読み始めたけど、どうして?」
「それは……、冥子が本当に、死んじゃったから……」
ネタバレを咎めるやつは誰もいない。
僕もついさっき読破したように、屍坂冥子は新刊で、今までの設定を大きく覆して本当に死んでしまうのである。
「毎巻必ず言わせる」とされていた、決め台詞も当然、言わずに。
副部長は呆れたように溜息をついた。
「それは書いた時期の問題。最初と設定が変わるなんてこと良くあるの。実際、一巻を書いた時点ではずーっと不死身設定でいくつもりだったし。五巻のラストは本当に締め切りぎりぎりに思いついたことだから」
「そうですね。最初に決めていた縛りをあえて破るっていうことも、ありえなくはないでしょう。けれど昨日発売の本の原稿の締め切りって、一体いつですか? 僕は出版業界のことは良くわかりませんが、遅くとも発売の一ヶ月くらい前には原稿が完成していないといけないんじゃないでしょうか? 誤字脱字のチェックを入れたり、表紙を決めたり、宣伝をしたり、何万部も刷ったりするにはどうしても時間が必要でしょう。それと比べて部活の文芸誌、つまり同人誌の締め切りっていうのは、それよりもっとあとなんじゃありませんか?」
僕が部長に視線を向けると、彼は苦い顔で答えた。
「今回の部誌の原稿締め切りは二週間前だ」
「……ですよね。決定的な矛盾ではないけれど、やっぱり物語の大きなターニングポイントである五巻の原稿を書いたあとに出す裏話としては、違和感があるんですよ。僕が作者だったらあんなふうには書かない」
「誤解だって。締め切りについては割と複雑なことがあるんだけど、書いた順番イコール締め切り順でもないからね? うーん、なんて説明したらいいかな……」
副部長は腕を組み、真剣な顔で思い悩む。そのようすを見て、僕は自分の考えが臆測でしかないことを思い知る。
一同が、訝しげな眼で僕を見て来た。三雲先輩なんか少し怒っているようだ。
「ごめんね。この件は一旦置いておこう? ……それで、エナくんの考えの続きは?」
副部長は、まるで子どもに言い含めるように言った。
ぴろん。とまた僕のスマホが鳴るが、誰も見向きもしなかった。
「……わかりました。つまりですね、落書きの犯人は、一昨日の時点で文芸誌と『しかしに(5)』を読破したから、『副部長が牛すじ。ではない』と思ってしまったんです。それでおそらく、嘘が書いてあるこの文芸誌を世に出したくなくなったんでしょう」
ぴろんぴろん、と通知音がうるさい。
そして間を置かず、軽快な着信音が鳴り響く。
「……ああ! もう!」
僕はイライラを抑えきれずに電話に出た。
『出るの遅すぎ。もう文字打つのめんどいから、喋っていい?』
辟易する僕の姿にみんなの冷たい視線が刺さる。
しかし、電話の相手はこちらの空気を敏感に察したのか、ワントーン低い声になった。
『……エナ、今部室でしょ? もしかして、汚れが文字だって気付いて入れ替えてみせたとか? ……あは。まさか今、解決編?』
「その、まさかだよ」
『へぇ』と愉しそうな声。『ビデオ通話でそっち見せてよ』
部長が僕に言う。
「電話、長引くようなら、廊下でやって来い」
僕はそれを無視して、ビデオ通話のボタンをタップした。
彼女の、花芯のようなうるうるの唇から下だけが映った。
寝間着にパステルピンクのカーディガン、ジェルで固められたきらきらの爪、コテで巻かれたミルクティー色の長い髪。清純派ヒロインとは真逆の、ガムシロップのような人工的な可愛いらしさ。
ただし、背景はリクライニングされた真っ白なベッド。
僕はその画面をみんなに向けた。
「……見えるか?」
『おっけ。……どうも、安楽寝台探偵です。事情は聞かせてもらいました』
全員が疑問符を顔に浮かべて固まった。小夜香さんは「メっ……!」と言いかけて堪える。
『カゴマニア。あんたのレポけっこう面白かったわよ』
「え……、本物……?」
『自分から名乗るのはこれが初めてなんだけどね』
可憐な声で、彼女は笑った。
『そっちの話どこまで進んでるかわかんないから、順を追って簡潔に話すわよ。
一昨日に新刊をフラゲした人が一人だけいたでしょう? 早坂莉緒。あんたは一時間目で没収されたと言っていたそうだけど、本当はその前に読み終えてたんじゃないの? 速読が特技だって聞いたわ。
そして、部誌の裏話との齟齬に気付いちゃったところ、連絡網で「部誌が届いた」という部長からの連絡を受けて、いてもたってもいられず、昼休みに部誌の中身を確認しに行った。そして汚した……どう?』
一息に、彼女は容赦なく語った。
「莉緒、あなたがやったの?」
副部長は、まっすぐに早坂さんに問いかけた。
こほん、と咳払いが聞こえ、僕はスピーカーの音量を上げる。
『牛すじ。は学生にも人気のラノベ作家。今までも部誌に裏話を書いていたみたいだけど、文芸イベントに出す以上、今回の部誌だって広く出回るわけで……、最新刊との違和感に気付く人が出てくるのは時間の問題でしょう。部員としては不名誉よね。同じ部に牛すじ。の名を騙る偽者がいるなんて』
みんな、いつの間にかメルの声に聞き入っていた。
『でも、いち早く気付いた早坂莉緒も、直接、秋月咲良を問い詰める勇気はなかったのよ。匿名でメールをするというのも駄目ね。彼女はスマホを持っていないんだもの。
早坂莉緒、あんたが一番に気に病んだのは“これを世に出すわけにはいかない”ってことじゃないかしら? そこでどうにかして“部誌を売れないようにしたかった”のね。汚すなり、破くなり、水をぶっかけるなりすればよかったのでしょうけれど……』
メルはまっすぐ前方を指さした。
彼女のカメラが映しているであろう光景は、廊下側の窓硝子。
『ここの部室は廊下から丸見えなのよね。昼休みも多くの生徒が出入りする。入口の管理人さんも覚えきれないほどに、ね。決定的瞬間を誰かに見られるわけにはいかないから、派手なことはできなかった。それに廊下から異常がわかるほどに部誌を大きく傷つけたら、外から発見されて犯行時刻が相当に絞られてしまう。
だからこそ、あんたは“廊下からはけして見えない窓側の側面、――結果的に《地》側になったわけだけど――に告発文を残す”という方法を思いついたのよ。だって今期は秋月咲良が部室に一番乗りなことが多かったらしいじゃない。早坂莉緒はそれを見越して“本人にだけ匿名でこの件を伝えられる”と思ったのよ』
話の切れ目に、僕は尋ねる。
「ちょっと待てよ、だからって側面に? わざわざ部誌を汚さなくてもメモを残して廊下から見えない位置に置くなりすればいいだろ」
『そうしたら、なかったことにされかねない。秋月咲良がメモを捨てて終わりよ。
だけど部誌の側面に書けば、順番を入れ替えてしまえば読めなくなってしまうから、告発を受けた秋月咲良は他の人が来る前にばらばらにしてしまうでしょう。こうすれば汚れた部誌だけが残る。で、部員たちは何らかの異常だけを察する。
犯人は“部誌が世に出なくなる”ことと“秋月咲良が内省して、嘘をやめてくれる”ことを望んでいたのじゃないかしら』
そしてできれば、自分から話して謝ってほしかったのかもしれない。
そう続けた彼女に、口を挟む者は誰もいなかった。
『……でも、その日に限って彼女が一番乗りじゃなかったのが、誤算だった。その日、副部長は歯医者で、一番最初に告発文に気付いたのは部長の仙国万里だったのよ。彼は部誌をばらまいて告発文を消した』
「でも、部長はどうしてそんなことを……」
三雲先輩のもっともな問いを、メルは鼻で笑う。
『咄嗟にそんな庇い方ができるとしたら、“元々知っていたから”っていうのが、濃厚だと思うけど? ……ねぇ、どうなの?』
部長の表情は動かない。
そういえば、彼はたびたび犯人捜しを止めようとしていた。「ブラッシュアップしよう」と言い出したのも彼だ。
やがて部長はゆっくりと椅子に座り直した。
「……見事だな。安楽寝台探偵、と言ったかい?」
『どーも。あんたとはエナよりかは小説の趣味が合いそうね』
「はは、江名くんは君のワトソンで……、一連の事件を全部彼女に報告していたというわけか」
小夜香さんが尋ねた。
「でも、副部長は、どうしてそんな嘘を?」
副部長は相変わらず平然としている。
「嘘じゃないって。私は本当に牛すじ。なの」
『牛すじ。は献血が趣味だそうね』
唐突に、メルは言った。
『エナから聞いたけど、あんた心臓が悪くて毎日薬を飲んでいるそうじゃない? 薬にもよるけど、服薬中の人間は基本、献血なんかできないものよ。まして命にかかわるような薬でしょう?』
「心臓が悪い?」と籠目先輩が繰り返す。
「それは……!」
はっとした顔になった彼女の腕を、部長が引いて自分の隣の椅子に座らせた。
「……もういい、いいんだよ、咲良」
全員がぎょっとする。
彼が、一筋の涙を流していたからだ。
「こんな嘘つかなくたって、みんなお前のことを忘れたりしない。全部話そう。いや、俺から話す。咲良はみんなを傷つけまいといつも明るく振舞ってばかりだから、今回のことだって、はぐらかして逃げるつもりだろうからな」
病気のことを言っているのだ。
察した瞬間、胸がギュッと締め付けられた。
みんなに打ち明けていいのか?
これ以上のショックを与えるのか。
いや、何考えてるんだ。
暴いたのは僕じゃないか。
部長はついに、言った。
「咲良は、心臓の病気でもう長くない」
誰もが言葉を失った。
長い間を経て、やっと三雲先輩が愕然とした顔で言う。
「な、何言ってるんですか、病気って……」
「もう時間がないんだ。みんななら痛いほどわかるだろう? 小説家になるのは、咲良の夢だったんだ。牛すじ。が現役女子高生だって知ったとき、咲良の中で色んな感情が渦巻いたはずだ。感動や悔しさ……そして憧れから、つい出てしまった嘘だったんだろう?」
部長はまっすぐに、副部長を見た。
「ちが……私は、本当に……!」
「ごめんな。俺は、君と二人でいる時間が長かったから、ちょっとした会話の中で気付いてしまったんだよ。本当はずっと前から、気付いていた」
「万里くん……」
「だけど俺も言えなかった。みんな、部の中にプロ作家がいるってだけで、あんなに盛り上がったじゃないか。あの楽しい時間を壊したくなかった。嘘は、確かに良くない。あの部誌は流石に世に出せない。でも書き直せばいい」
部長が深く頭を下げた。
「……ささやかな嘘だったんだ。だからみんな、咲良のことを、どうか許してやってくれ」
早坂さんは糸が切れたように床に膝を付いた。
「待って、長くないって……、嘘でしょう?」
小夜香さんが隣に駆け寄り、その肩を支える。
「そんなこと、今まで一言も……!」
薄幸の美少女は、憂いを帯びた顔で黙っていた。
しかし、機械越しの声が水を差す。
『……悪いけど、まだ話終わってないから』
部員たちはスマホに映った部外者を一斉に睨みつける。
当然だ。仲間がもうすぐ死んでしまうかもしれないなんて知らされて……、今それ以上に大事なトピックなんてあるものか。
『ねぇ秋月咲良。転校前は檎林学園にいたそうだけど、正門はどんなだったか覚えてる?』
いきなり何の話だ。
「どんな……って、大きい、門としか」
『あんなに特徴的なのに?』
「変わってはいるけど……、毎日通って見慣れちゃえば、細かいところまで覚えてられないよ。あなたは自分の家の玄関ドアの色や形をしっかり覚えてるわけ?」
『そういうことじゃないのよ。形の話をしているんじゃない』
メルはふっと笑う。
『檎林学園の正門は不審者対策のために自動改札機になっているの。守衛が常駐していて、学生証をかざさないと通れないようになってる。普通の学校じゃ、まずお目にかかれないシステムでしょう? 私は「正門はどんなだったか?」と聞いたのよ。どうして一言も「自動改札」という言葉が出て来ないのかしら。不自然じゃない?』
何が起きているのか、部員たちは固唾をのんで見守っていた。
『ていうか、檎林に在学中の友達に訊いたら、あんたを知っている人なんて誰もいなかった、中等部高等部、どっちもね』
じわりと、厭なしみが胸に広がっていく。
『もっと言うと、もりとか総合病院に「秋月」なんて外科医はいない』
メルの言葉は止まらない。
『それでなんだっけ? SNSのフォロワーが五万人いて、超大型犬を二匹も飼ってて、母親は会社経営者……? 改めて羅列すると怪しいこと、この上ないわね』
僕はたまらず語気を荒らげる。
「さっきから、何が言いたいんだよ……?」
『だから“嘘”なんでしょう。全部』
誰も、理解できないという顔をしていた。
『不治の病も、プロの小説家だっていうのも、全部全部、嘘』
甘宮メルはアンニュイに小首を傾げて、言った。
『――秋月咲良。あんた、重度の虚言癖があるみたいね』
愕然とする僕たちの耳に、廊下を行き交う生徒たちの靴音が響いた。
意外なことに、笑い出した人間がいたのだが、それは副部長ではなかった。
「くっ、……くくくくっ、ついにこういう日が来ましたか……」
籠目先輩はお腹をさすりながら、声をかみ殺している。
「お前、何がおかしいんだよ!?」
三雲先輩が彼の肩を掴んだ。
籠目先輩は冷静に、その手をそっと振り払った。
「……実は俺、けっこう前から気付いてたんすよね。この人、息するように嘘つくんですよ。しかもくだらないことで見栄張って。親がスマホ持たせてくれないってのもそれが理由じゃないですか? こんな人がスマホ持ったら、ネット上でトラブル起こすの目に見えてますもん」
副部長は、動じることなく彼を見ている。
「面白いから、黙ってましたけど」
籠目先輩は肩を竦めた。
「……なんで? なんでなんですか?」
早坂さんは胸を掻き毟り、悲痛な顔で副部長を見上げた。
「私、ずっと先輩が羨ましくて、すごい人だって、憧れてたんですよ? 牛すじ。じゃないってわかったとき、すごくショックでした。だからどうしてもちゃんと訊きたかった! それなのに、全部嘘って……? 全部って何!? 意味わかんない!」
副部長は、難しい顔で、はぁーと大きなため息をついた。
彼女は身体の前に両手を出し、早坂さんに「落ち着いて」とジェスチャーで促した。
「だからね、誤解なんだってば。こんな電話越しのわけわからない人の言うことを、簡単に信じないでよ」
彼女は僕の持ったスマホに向き直り、立ち上がる。
「私は本当に牛すじ。なの。逆にさ、嘘だって証拠あるの? 檎林の門のことだって、色々あって記憶が曖昧になってただけだから」
「あ、曖昧?」と、小夜香さんが繰り返す。
副部長は長い睫を伏せて、囁くように言った。
「……実は、あの学校にいたころね、作家業のことで学校と揉めたせいでストレスがかかりすぎて、記憶が抜け落ちちゃったところがあるの……。あんまり言いたくなかったんだけど、精神科にかかってて、診断書も貰ってる」
当然、この場に診断書はないのだろう。
『県一に来る前はどこの高校にいたか知らないけど、おおかた、この悪癖のせいでいじめられて転校してきた……ってところじゃないかしら?』
その言葉を聞いた瞬間、副部長はだん! と机を叩いた。
「私はいじめられたことなんかない!!」
全員が圧倒されて、長い沈黙が下りた。
部長は蒼白な顔で立ち上がり、彼女の両手を掴んだ。
「咲良……なぁ、本当のことを、言ってくれないか? 俺はもう、何を信じたらいいかわからなくなってしまいそうだ……!」
「私を疑ってるの!?」
副部長はさっきの言葉が契機だったかのように、乱暴に彼の手を振りほどいた。
「私のこと、好きって言ってくれたじゃない」
「言ったよ、だけど……!」
「わかった。もういいよ。好きって、結局その程度だったんでしょ」
おい、これどうしたらいいんだよ。
一体、何が正解なんだよ。
僕は小さな画面の中のメルを見やるが、彼女は我関せずとばかりにいちごポッキーを食べていた。
副部長に向けられた部員たちの視線が、彼女の分が悪いことを示していた。
彼女は急に心臓を押さえて、苦し気に呻いた。
「でも、覚えてて、……私は部長のこと、本当に好きだったよ」
せき込み、口元に手を当て、涙目になる。
もしかして、やっぱり本当に病気なんじゃないのか……?
狼狽えた僕の手は低く空を彷徨う。
「……ねぇ部長、私が死んだあとも……幸せになってね」
秋月咲良は部誌の束を抱えて教室を飛び出していった。
僕たちは副部長を追いかけた。
どこへ行ったかまるでわからず、手分けして校内を屋内外探し回った。メルとの通話は走り出すと同時に切っていた。
鞄はあるから戻ってくるだろう、という建前で、籠目先輩が呆然自失の早坂さんを部室に残したけれど、僕はこのまま副部長が鞄なんか放置してどこへ行ってしまってもおかしくないと思っていた。
部長は最悪の事態を考えて真っ先に屋上へ向かっていた。
夢中で走っていたら、いつの間にか一人になっていた。
落ち着け。僕は渡り廊下から上履きのまま外へ出る。
彼女は部誌を持ってったんだ。
県一の校舎は古く、設備も旧時代の遺物が残されている。
校舎裏の一角、ゴミ収集所のほうへ向かうと、綺麗な黒髪が風になびく後姿が見えた。
「……いた」
僕の声にちょっと振り返った副部長だけれど、手の動きを止めることはなく、流れるようにマッチを擦った。なんでそんなもん持ってるんだ。理科室から盗って来たのかな。
僕は一応走り出したけれど、彼女までの距離、約十五メートル。間に合うはずもなく、彼女が焼却炉の中にマッチを落として蓋をするのを見届けたあと、やっと会話のできる距離に来られた。
「エナくんか。……はぁ、なんで君が来るかな」
「不満でしたか? 僕たち図書室でフラグが立ってるじゃないですか」
人気者の美少女が、友達やボーイフレンドには言えない本当の気持ちを、優しいだけが取り柄の陰キャ少年に打ち明けるっていう、王道のやつをさ。
僕は焼却炉の蓋を開ける。白い煙が噴き出した。投げ入れられたマッチを起点に、部誌に火が燃え広がっている。
「やめて!」
「やめません」
僕はその中へ手を突っ込み、マッチを握りつぶして外へ投げ捨てた。
「やめてよ! もういらないんだよ! 部活だってやめるし、全部全部全部また壊れちゃったんだから! こんな部誌もう燃やし……!!」
僕は両手で燃えている部誌を数冊まとめて引っ張り上げ、足元のコンクリートに投げ落とす。まだ間に合う。
「やめてって言ってるでしょ! ふざけんなよ!」
ばん、ばん、ばん、と三回ほど往復したら、炉の中で燃えている物はなくなった。
「――っ……げっほ! えほっ……!」
煙を吸ってしまった。尻もちをついて目を擦りながら大きく深呼吸する。
副部長が、信じられない、という顔で僕を見下ろしていた。
「よかった、半分くらいは無事ですね。うわ……」
手を開いてみるとサーモンピンクに腫れあがっていた。
副部長がわなわなと慄える唇を開く。
「何やってんの……? こんな紙くずのために……!」
「みんなで作った大切な部誌じゃないですか。見過ごせませんよ。燃えちゃったら二度と元には戻らないんですよ」
そう、僕は二度と元に戻らないものの哀しさを知っている。
「世に出せないから、なんですか。もっと大事な思い出が詰まってる。何より、表紙は僕の大事な幼馴染が描いてるんでね」
「君おかしいよ」
「君もね」
痛みではない奇妙な感覚が手指に這って来た。あんまり触らないほうがいいだろう。
「君も私のこと馬鹿にしてるんでしょ」
副部長は両手を握りしめて、焼却炉を蹴った。
「本当のこと言ったら誰も見向きもしないくせにさぁ! 私は私がなりたい私になるの、何がいけないの? 誰も傷つけてないし、私が嘘ついたことで誰かが損しましたか? してないよね!? みんなお世辞だって言うし、男子ってみんな身長数センチサバ読むじゃん、それと一緒だよ。こんな今は本当の私の人生じゃないし本当はもっとすごくてきらきらしてるんだから!」
耳がわんわんする。
彼女は目を瞠って僕を見下ろすけど、僕のことなど見えていない。
「……部長、真っ先に屋上に向かったんですよ」
「……」
「解ります? 副部長の身を、本当に案じていたんですよ」
そのとき、遠くから「いたぞ!」と籠目先輩の声がして、複数の足音がした。
彼に続いて、部長と小夜香さんも走って来た。
「咲良!」
部長は僕の脇をすり抜けて、そのまま彼女を抱きしめた。
「万里くん」と、彼女が呟いた声を、確かに僕は聞いた気がしたのだけれど。
次の瞬間、秋月咲良は暴れだした。
「あああぁーーーーーーーーーーっ!!」
甲高い叫び声と共に、彼女は両手両足を振り回す。
後ろから押さえ込む部長に、僕と籠目先輩が両脇から加勢して、腕や顔をひっかかれたり噛まれたりしながら、なんとか彼女を取り押さえようとした。
騒ぎに気付かれたようで、校舎の窓が開き始める。
僕たちは彼女を引きずってその場から逃げ出したが、彼女はすでに電池が切れたように気を失っていた。
三雲先輩と早坂さんが、副部長の鞄を保健室まで持って来てくれた。
僕はさっきから水道の前に立ち、流水で手を冷やし続けていた。養護教諭は会議だとかで席を外していたが、大ごとにされたくないので助かった。誰かに患部を見られる前に退散したい。
「エナ、冷やし終わったら見せて」
「平気だよ。軽いもんだから、これで十分だ」
僕は小夜香さんから手を隠し、蛇口を閉めてベッドへ向かう。
カーテンを捲ると、寝かされた副部長を取り囲むように、部員たちが丸椅子に座っていた。
怪我はない。興奮しすぎただけだ。
案の定、彼女はしばらくすると目を開いた。
ほっとする一同の顔をぼんやりと見上げてくる。
「あれ……私、どうして……」
言いかけて彼女は息を飲む。
「そっか……思い出した。私が、牛すじ。じゃないって、バレちゃったんだっけ……」
彼女は酷く穏やかな顔で、目をつむった。
「迷惑、かけちゃった、ね……。ごめんね、嘘、ついて……」
みんな、黙り込んだままだった。
けれど部長だけは、力強く彼女の手を握りしめた。
「何も言うな。今はゆっくり休め」
「……ごめん、ね。…………ありがとう」
いつの間にか陽が暮れて、室内には夕日が差し込んでいた。
早坂さんも三雲先輩も落ち着きを取り戻し、籠目先輩も今度ばかりは神妙な顔をしていた。嘘に気付いていた彼も、彼女がこんなふうに追い込まれていたなんて、思いもしなかったんだろう。
彼女は息をするように嘘をつく、と彼は言った。
そのたとえは正しく、彼女自身、息ができなくなるほどの苦しさを抱えていたに違いない。
やがて夜の帳が下りて、秋月咲良はもうひと眠りした末に、落ち着いたようすを取り戻した。
いつもの、物語のヒロインのような微笑を、携えている。
「副部長も良くなったようですし、僕はそろそろお暇しますね」
この火傷を放置するのは良くないので、早く一人で処置のできるところに行きたい。
「……あ、待ってエナくん」
しかし副部長が呼び止めた。
「その前に、一つだけ話していい? ……みんなにも、どうか聞いて欲しい、です」
彼女は窓を背にして、それぞれの場所に座っていた部員たちを見渡した。
そして、勇気を振り絞るように口を開いた。
「みんな、私が『自分は牛すじ。だ』って言ったこと、どうしてそんなことしたんだろうって、不思議に思ってるでしょ……?」
誰ともなく、頷いた。
僕は引き戸にかけた手を下ろし、彼女を振り返った。
まっすぐな美しい黒髪がさらりと流れる。
――実はね、と彼女は上履きの爪先に視線を落とした。
「私、牛すじ。とは昔、友達だったの……」
え?
誰一人として予想だにしない、意外な言葉だった。
「私と牛すじ。は、昔ツヅリスタで出会って、共作をしていたの……」
懐かしそうに、彼女は目を細めた。
「私が主なストーリーやキャラを考えて、小説本文は分担して書くって感じで」
「そう、だったんですか……!?」
三雲先輩が椅子から腰を浮かした音が、やけに大きく響いた。
「うん……。色んな作品を書いたけど、その一つが『しかしに』シリーズだった」
初めて出会った日のように、細く開いた窓から吹き込んだ秋風が、美しい彼女の髪を揺らした。
「あれは……、小説も、ほとんど私が書いてたかな。うん。……でもね、ある日牛すじ。は私に黙ってアカウントを消しちゃって、それきり連絡が取れなくなっちゃったんだ」
風に乗って金木犀の香りがした。
その微笑は、あくまで自然で。
「……それで、どうなったんですか?」
僕は問いかける。
「数ヶ月後に、牛すじ。は、『しかしに』でデビューしてたの……」
「……つまり、『しかしに』は副部長の作品の盗作だと?」
「そう」
曇りのない瞳で、秋月咲良は言った。
とても嘘をついているようには見えなかった。
「会ったことはなかったけど、私は友達だと思ってた。でも流石にそんなことされたら悔しくて、つい『牛すじ。は私だ』って言っちゃったの。そしたらみんなが喜ぶから、今さら本当のこと言えなくて」
小夜香さんが、鞄の肩紐を震える両手でぎゅっと握りしめた。
「え? じゃあ、続きの巻は……?」
「あぁ……。完結分まで原稿のストックはあったから、二巻以降もそのまま使われてるみたい。だから牛すじ。は私だ、って言うのは、完全に嘘ってわけじゃないんだよね」
僕は質問を重ねる。
「……するとあの小説は、実質、全部副部長が書いたってことですか?」
「そうなの」
「あとがきは?」
「あとがきも」
室内は静まり返っていた。
僕は寒気を誤魔化すように微笑む。
息をするように、か。
彼女にとってそれは空気のようなもの。なくなれば呼吸が止まる。
副部長ははにかんだ笑顔で、唇の前に人差し指を立てた。
「秘密だよ。他の人には、言わないでね」
僕は小夜香さんのセーラー襟を、くいっと引っ張る。
「……了解です。それじゃ、僕たちはこれで失礼しますね。どうぞお大事に」
「あ、ちょっ、エナ……!」
と言った彼女も、次の瞬間には僕と同じように、足早に引き戸へ向かっていく。
だよね。それが賢明だ。早坂さんとは部の外で遊べばいい。
これ以上、刺激しては、いけない。
「「お疲れさまでした!」」
僕たちは元気よく挨拶して、保健室をあとにした。
小夜香さんと別れて家へ帰ると、エプロン姿でぱたぱたと出迎えてくれた妹は、すぐに僕の手の異常に気が付いた。
「お兄ちゃん、どうしたのそれ!」
「ちょっと化学の実験でね。十分冷やしといたから大丈夫」
「本当に? だいぶ広範囲だよ。しかも両手ってどういう状況?」
そして彼女は廊下を引き返し、居間へ向かった。僕は脱いだ靴を揃えてあとに続く。美味しそうなカレーの匂いがする。
「今すぐ病院、ってほど酷くはなさそうだけど、明日朝一で診て貰ったほうがいいよー」
「面倒だからいいよ。病院に行ったって適当な塗り薬塗られて終わりだろ? こういうのは風邪と一緒で自然治癒を待つのが一番なんだから、時間とお金の無駄だと思うぞ。庭のアロエでも塗っとけば治るさ。大して痛くもないし」
そう、僕は実は痛みに酷く鈍い。
痛くないからこそ病院にちゃんと行くべきだ、ということくらい理解しているのだけれど、これくらいは視覚情報だけでも軽傷だとわかる。
元来、僕の痛覚は正常だったし、神経にも何ら異常はない。けれどメルと僕の因縁が始まったあの日以来、明らかに鈍くなってしまっていた。
「原因は精神的なものだよ」と彼女の兄は言っていたから、そのうち治るかもしれない。
別に治らないならそれでもいい。
きっとそのほうが、僕にとっては気が楽だろう。
その日の食卓には予想通り、みゆ特製の無水カレーが出た。うちは父子家庭で、父は単身赴任で東京にいるから、この家には兄妹二人で暮らしている。
二人きりでは大きすぎる四人がけのダイニングテーブルにも、とっくの昔に慣れていた。僕たちはいつものように、テレビに飛ばした動画配信サービスの海外ドラマを見ながら食べ始めた。
「それで、本当は何したの? 腕にもひっかき傷とかあるけど、まさか喧嘩じゃないよねぇ?」
妹がスプーンの先を唇につけながら、まあるい瞳で見つめてくる。
「本当に何でもないって。兄ちゃんの言うことが信じられないのか?」
「さっき小夜香さんから、『エナの怪我どう?』って連絡来たんだけど」
思わずむせてカレーを吐き出しそうになった。
「……もしかして! お兄ちゃん、小夜香さんのために不良と闘ったとか……?」
お?
妹は両手を頬に当てて、困り眉にきらきらした目で見上げてくる。
みゆは少女漫画や恋愛ドラマが大好きなのだ。
「あれ? でもお兄ちゃん、他校の彼女がいるって言ってたよね? でも小夜香さんは初恋の人だし、うーん……?」
真剣に頭をひねる妹は、可愛らしかった。
「高校生にもなると、色々あるんだよ」
それから、文芸部には一度も顔を出していない。
小夜香さんから聞いたところによると、部は今まで通り活動しているらしい。
部長はショックのせいか三日も学校を休んでいたらしいのだけれど、復活したときはすっかり元の調子を取り戻し、すべてを受け入れたという。
すべて。秋月咲良のすべてをだ。
部長は彼女と別れることはしなかった。
「そりゃまた、奇特な」
「元々部長って変人だったもん」
「それもそうか」
昼休み、僕と小夜香さんは購買のそばにある自販機で飲み物を選びながら、あのときのことを振り返った。
「ていうか、部長はずっと『副部長は牛すじ。じゃない』ってわかってて付き合っていたんだろう? ずっと前から、僕たちとは違う視点で副部長の姿を見ていたんだよな、あの人だけは……」
そのうえで好きになった。
そのうえで両想いになった。
「籠目先輩もだけどね……。あの人は面白がって見守ってたって感じだからな……。ともかく付き合ってる本人たちがいいなら、周りがどうこう言う話じゃないよね」
と、小夜香さんがストローをパックに差しながら言った、そのときだった。
「その通り!」
廊下の向こうまで響きそうな声だった。
振り返った先には、部長と籠目先輩がいた。
僕たち四人は、購買から少し離れた廊下で立ち話をすることにした。
ちなみに部長と籠目先輩はたまたま購買前で会ったらしい。部長は腰に手を当てて梅おにぎりを齧っている。
「……副部長は、相変わらずですか?」
僕は言葉を濁しながら尋ねた。
「変わんない変わんない。今まで通り。あの日のことも、本人の中では都合のいいように改変されてるっぽい。あれはもう一種の才能だよ」
籠目先輩は笑いながら言う。部長は彼に尋ねた。
「籠目は、このまま活動していて本当にいいのか? 俺は部の解散もやむなしだと思っていたが……」
だろうな。三日も休んだくらいだ。
「いいじゃないですか。虚言癖、上等。元々濃ゆいメンバーの集まりだったんだから、奇人変人、大歓迎。それでこそ俺たちの文芸部ですよ」
不謹慎に面白がっているだけ、かと思いきや、意外にも籠目先輩は真面目な顔をしていた。
「正直、あそこまで重症とは思ってなかったんで、ビビりましたけど……、なんかトラブったときは俺たちが味方してあげましょうよ。副部長いないと、部活つまんないっすよ」
部長は、面食らったように唇を引き結んだ。
「……そうか。籠目、恩に着るぞ」
僕はほっとしたような、どこか落ち着かないような奇妙な気分になった。隣の小夜香さんもそんな顔をしている。
「部長は副部長のこと、変わらず、好きなんですよね?」
僕は尋ねてみた。少しだけ関係の似ている自分の恋人を思い浮かべながら。
「ん……まぁな。あまり言わせるんじゃない」
彼は照れたように制帽を被り直した。これは本当に惚れている顔だ。
「嘘つきでもいい。……いや、嘘つきだからこそいいんだ」
「「「え?」」」
三人は同時に怪訝な顔をした。
いや待て、嘘つきでも受け入れるって言うのはぎりぎりわかるけれども。
嘘つきだからいい、ってなんだよ?
「やっとわかったんだ、彼女の真の人間性ってものが。あれでこそ咲良なんだよ。かけがえのない個性だ。俺にはすごく、魅力的に映る」
僕は肯定も否定もせず「へぇ」と言うに留めておいた。
人にはわからなくても、彼らには彼らの絆があるのだから。
もりとか総合病院の一階には大手のコンビニが入っている。
僕はメルに頼まれたお菓子と雑誌をカゴに入れレジに並んだ。
「メルっていちご味好きだよね」
小夜香さんは新発売のチョコレート菓子を手に、斜め後ろからひょこっと現れて会計に滑り込ませた。自分もちょっと食べたいのだろう。
「そういうところばっかり乙女なんだよなぁ。小物も化粧品もピンクばっかりだし。読む本は血腥いのが多いのにな」
「傾向としては矛盾してはいないと思うけどな」
と言ったのは小夜香さんではなく、聞き覚えのある若い男の声だった。僕は密かに身体中の毛穴を開かせる。小夜香さんが僕の後ろへ向けて言った。
「あ、メルのお兄さん。こんにちは……」
どっちだ。どっちの兄だ……?
ゆっくりと身体をひねると、会いたくないほうの兄、つまりは長男の甘宮明良が、ゆで卵とサラダを手に後ろに並んでいた。
青い術衣に白衣、足元はクロックス。どれもくたびれていて、いかにも激務な臨床医という格好だ。メルによく似た端正な顔で、薄く笑みを浮かべている。
そして彼の後ろから、こぶし一つ背の低い男が「ちは~」と顔を出した。途端に安堵が押し寄せる。
「明也さんもいましたか……」
「はは、兄ちゃんデカいから見えなかったって」
「……いや大差ないだろ」
次男の明也さんは屈託のないのんびりとしたようすで明良さんを指さして笑った。雰囲気は対照的だが声はよく似ている。
「エナくん。話は戻るけど、残念ながら服装や持ち物の好みには、ある程度、性格や貧富、生活環境が表れるものだよ。そうじゃなきゃステレオタイプなんてものも生まれようがないからね」
メルをそのまんま雄化して縦に伸ばしたような明良さんは、やけに美形で医療ドラマに出てくる若手の医者のようにどこか嘘っぽいのだけれど、れっきとした精神科医だ。
「それにしたって、ピンクやきらきらの好きな子が、血腥い話にばかり興味を持つってのは、やっぱり違和感を感じますよ」
「違和感を感じる?」
「えと……だって、共通項が見当たらないじゃないですか」
そつのない微笑とゆっくりした話し方が、逆に癇に障る相手だった。人の話を絶対に遮らないところや、すぐ鸚鵡返ししてくるところは職業病なのだろう。そうと解ると余計に癪だ。
正直、本来の性格は良くわからない。僕にも未だに見えてこないのだ。
嫌われてんのだけは、わかるけどね。
小夜香さんがはぁっと溜息をついた。
「エナわかってないなぁ。女子の『ピンク』には種類があるんだよ。メルのは完全に自分のための、他人には上書きできないタイプのピンクでしょ。武器みたいなものだよ。殺傷力の高い魔法のステッキみたいな」
「はあぁ?」と僕が眉根を寄せると、明良さんは納得したように鼻で笑った。
……色味の話、ではないのだろう。
そのとき彼が首に下げていたPHSが鳴り、レジの列も進んだ。彼は通話しながら急いで会計を済ますと片手を上げて早歩きで去ってしまった。
「急患かな。忙しそうだね」
「明也さんは、もう仕事上がりですか?」
「うん。兄ちゃんとはたまたま会ったの。これから夜勤だから夜食買いに来たんだって。でもあれ、お腹空いちゃわないのかな……」
心配そうな甘宮明也は、ペールグリーンの作務衣のような格好で、お菓子とおにぎりの入ったカゴを持っていた。
彼はこの病院の作業療法士だった。伸びかけの髭がぱやぱやしている。明良さんとは年子らしいのだが「俺は医者にはなれなかったのよ」と、本人が以前あっけらかんと言っていた。
もりとか総合病院は、甘宮一族の創業した私立病院だ。
甘宮メルは、その家系図の末端にいる少女だった。
ゆえにあんなふうになってしまった今も、「自宅に帰るより、このままこの病院で暮らしたほうが、介護の手も家族の目も行き届きやすい」という理由で、最上階の特等個室に住むことになったのだ。
コンビニを出たとき、明也さんが「エナくん」と呼び止めて来た。
「妹があんまり手に負えないようだったら、いつでも言ってね。こう見えて大人だから、俺も」
シンプルな言葉がすっと染み込んで来る。
「はい。ありがとうございます」
すべてを知ったうえでのこの人の態度は、僕にとっては、周りが思うよりもずっと大きな拠りどころになっていた。
「ねぇ、エナ」
明也さんがいなくなったのを見計らい、小夜香さんが立ち止まる。
「エナ、は……明良さんが恐い?」
「恐い? そんなわけないだろ。急になんだよ」
「わかるよ、私には。十年以上一緒にいるんだよ? メルは私の友達でもあるから、力になりたいとか、退屈を紛らわせてあげたいのは、私も同じ。でもさ、エナはちょっと行き過ぎっていうか……」
小夜香さんは少しだけ真面目に、僕を見つめる。
「メルのためなら何でもしてあげるのは、どうして?」
彼女は疑っている。
「明良さんが恐いことと、関係ある?」
あの夜の真実を。
僕は目を細めて、曖昧な微笑を返した。
「――そんなんじゃあ、ないよ。惚れた弱みってやつさ」
歩き出した僕の背に、「気障だなぁ」と呟いた小夜香さんの溜息と足音が、遅れて追いついてきた。
深呼吸。ノック。返事のあと、引き戸を引く。
ベッドをリクライニングしてタブレットを見ていた甘宮メルは、画面から目を離さずに、こちらへ手を出した。お菓子を所望しているのだ。
「挨拶くらいしてくれよ」
「今忙しいの」
「メル、久しぶり」
「あっ、小夜香も来てたの。来るなら言ってよ」
「忙しい、って、何見てたんだ?」
答えてくれるとは期待していなかったのだけれど、彼女はにんまりとしながら僕たちにタブレットを見せてくれた。
「ツヅリスタのネット小説」
「メルもそういうの読むんだ」
「時間が有り余ってるもんですから。大半がゴミだけど、B級ホラー映画みたいな楽しさがあるのよね」
「ゴミ……」
小夜香さんは苦い顔をする。
「でもこれは悪くないわよ。最近完結したら、すぐ書籍化が決定してね」
メルが寄こしてきた千円札をありがたく貰いながら(彼女は、きっちり精算なんてことはしない。差額は駄賃だ)、タブレットを覗き込む。
タイトルは「桜降るころに、嘘つきな彼女は物語を紡いで」。
さくら、か。
「……いかにもな匂いだな。こういう感動小説は嫌いじゃなかったか?」
「この小説は一味違うのよ」
メルは軽快に画面をタップし、僕と小夜香さんのスマホが同時に鳴った。
「リンク送ったから、あらすじだけでも読んでみてよ」
そうして、彼女は小夜香さんが選んだ新作のいちごチョコレートの箱を開ける。
僕はのろのろと親指を動かしてページを開いた。
連載開始はちょうど一年前。
高校生の文芸部員、「僕」は転校生の少女が図書室で小説を書いているところに遭遇する。だが彼女は「自分は本当は人気作家なのだ」とバレバレの嘘をついてくる。最初は相手にしなかった「僕」だが、彼女の余命が少ないことを知り、彼女の嘘に付き合ってあげることを決意する……。
「……なっ……!?」
僕は思わず声を上げる。
「デジャブでしょ?」
「メル、君これどうやって見つけたんだ?」
「今回はたまたまよ。書籍化決定作品ってことで、ピックアップされてたから」
小夜香さんはスマホを食い入るように見ている。
最終話のレビューは膨大な数だった。「衝撃のどんでん返し!」と称賛されている。
だが僕は他の数字に注目した。
「メル、ラスト五話の更新日、気付いたか?」
「もちろん」
僕は流し読みで内容を軽くチェックする。
この小説は連載開始からきっちり三日置きに更新され続けてきた。しかしあるときから、三ヶ月も更新が止まっていたのだ。
そしてラスト五話は一週間前の、彼が休んだ三日間で集中的に連続更新されていた。
「もう完結はしないと思って諦めてたので、最後まで読めて嬉しいです!」という熱いレビューが躍っている。
怒濤のラストの内容は……読むまでもない。
「……わ、わかんない……! 私やっぱり、恋愛って良くわからない……!」
小夜香さんはスマホを伏せて頭を抱えた。僕にさえ理解しがたいのだ。元より恋愛に興味のない彼女からすれば当然の反応だろう。
「エナ」
メルがとろけそうな声音で呼びかける。
僕はなんだか心が憔悴してしまって、うんざりしながらそちらを向いたのだが、むっと唇に硬いものが押し付けられて、息を止めた。
「美味しいよ。分けてあげる」
甘ったるい、いちご味のチョコレートの匂い。
糖分が疲れた頭に染みわたるのを感じながら、僕は足を組み替えた。
部長はずっと、彼女をネタにしていた……。
なんて、そんないやらしい言葉で貶めるのは失礼だろう。
彼女を愛してないとか、そんな話じゃあないんだ。好きな人をモデルに小説を書くなんて、健気で甘酸っぱい、素敵なことじゃないか。
だけどこの、据わりの悪い気持ちは何だろう。
――やっとわかったんだ、彼女の真の人間性ってものが。
ありのままを受け入れることも一つの愛だろう。
じゃあ、止めないことも愛だというのか?
隣を歩くことなく、後ろからただそっと見つめて。相手が困っても、泣いても怒っても、何も言わずに行く末を眺めることも?
「……僕には、わかんねー領域だな」
独りごち、天井を仰ぐ。
僕は、恋人にはいつも機嫌よく笑っていて欲しいからね。
それから妹にも。この二つはどうしたって比べられない。
メルは小夜香さんに長い髪を三つ編みされながら、言った。
「それにしても、文芸部って本当にみんな小説書いてて偉いわよね。そこだけは評価できるわ。てっきり、口だけで書かないオタクの集まりだと思ってたのに」
「ふふ、県一の文芸部は特殊かもね。奇人変人、大歓迎だって」
そして小夜香さんは思い出したように言う。
「エナも部長に書いてみろって言われて、小説書いてたよね。できた?」
メルの目がきらりと光る。
「え? え? エナも書いたの? 見せて見せて!」
「やだよ!」
自分でもびっくりするほど大きな声が出た。
「見せてよ」
「書いてなんかないよ」
「嘘。さっきやだって言ったじゃない。できてるってことでしょ」
己の失言をどう思っているのか、小夜香さんはしれーっと目をそらす。
メルは手のひらを上にしてこちらへ差し出し、命じた。
「見せなさいってば」
この目、この声、この手。
僕は逆らうことができない。
「……ごめん、小夜香さんは席を外してくれるかな?」
ただならぬ気配を感じたのか、彼女は慌ててソファから立ち上がる。
「うん。私、ちょうどもう帰ろうと思ってたところだから……」
彼女は荷物を手に、病室を出て行った。
僕は鞄からクリアファイルを取り出す。消しゴムをかけた跡だらけの、鉛筆書きの原稿用紙が十数枚入っていた。
手渡すと、メルはすごい速さで読んでいく。
自分の頭ががんがんと鳴って、熱くなっていくのを感じた。
恥ずかしい、なんてもんじゃない。
消えたい。
読み終えたメルは深い溜息をついた。
「何これ、私小説?」
あらすじは至極シンプルだった。
中学生の男子が、同い年の他校の少女に出会い恋に落ちる。二人は互いにシンパシーを感じて急接近する。
けれど、少女は最後にあっけなく死んでしまうのだ。
「僕」は彼女が息を引き取った大病院の最上階にある特等個室をあとにし、青空を見上げて一人、彼女の死を悼む。
ぱさっと、音を立てて、ベッド柵に渡されたテーブルに原稿用紙の束が投げ出される。
「……これがあんたの理想の結末だったってわけ?」
僕は座ったまま、前傾姿勢で頭を抱えていた。
書いたのは気まぐれだ。
「怒るなよ、深い意味はないんだよ」
こうだったら僕たちはもっと、まっすぐに想い合えていたのかなっていう、夢想。
他でもない君に読まれるなんて、思ってもみなかったんだ。
「――悪かったわね、生きてて」
彼女はサイドボードの引き出しから百円ライターを取り出した。彼女は煙草なんか吸わないのだけれど、香りつきのキャンドルをよく使う。
原稿用紙の束をつまみ上げて、メルは角に火を点けた。
じわじわと炎が燃え広がっていく。
「……くっ、…………あはははっ!」
僕の気持ちなんかまるで考えていない。
いや、考えたうえで、より傷つける術を探している。
「あっつ……!」
僕は弾かれたように、風呂場から洗面器を持ってきた。
彼女の指先に炎が迫る前に、原稿を払い落とす。三角に燃え残った紙の端が、洗面器の中で灰になった。
「めちゃくちゃ熱かったんだけど」
「知らないよ……。僕が何とかする前提で危ないことするの、やめろよな」
甘宮メルは軽く握った手を口元に添えて、くすっと鼻で笑った。
「だって、助けてくれるでしょう? その命に代えても」
ふざけんなよ。
僕は知っている。
ちゃんと自覚している。
彼女が本当は、僕のことを殺したいくらいに憎んでいることくらい。