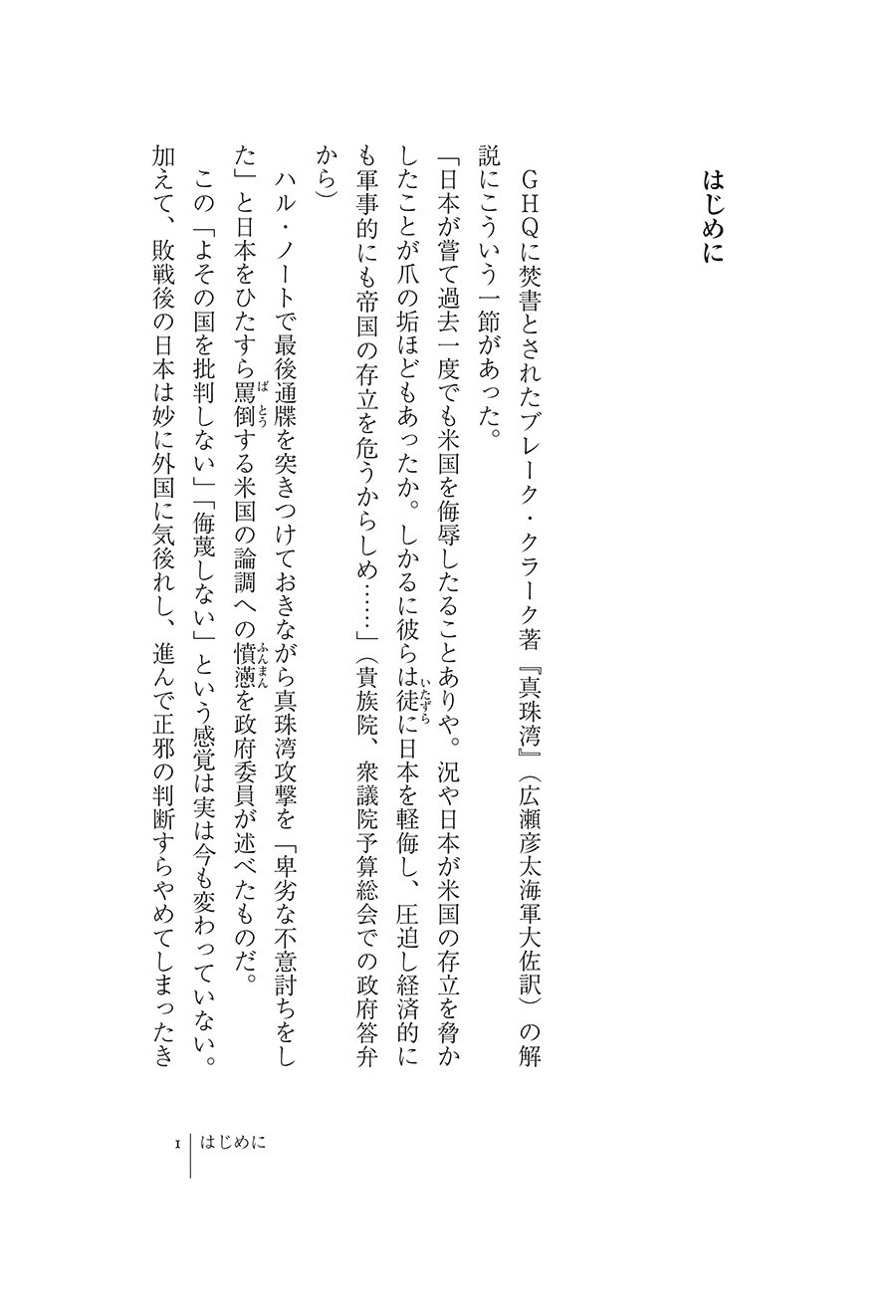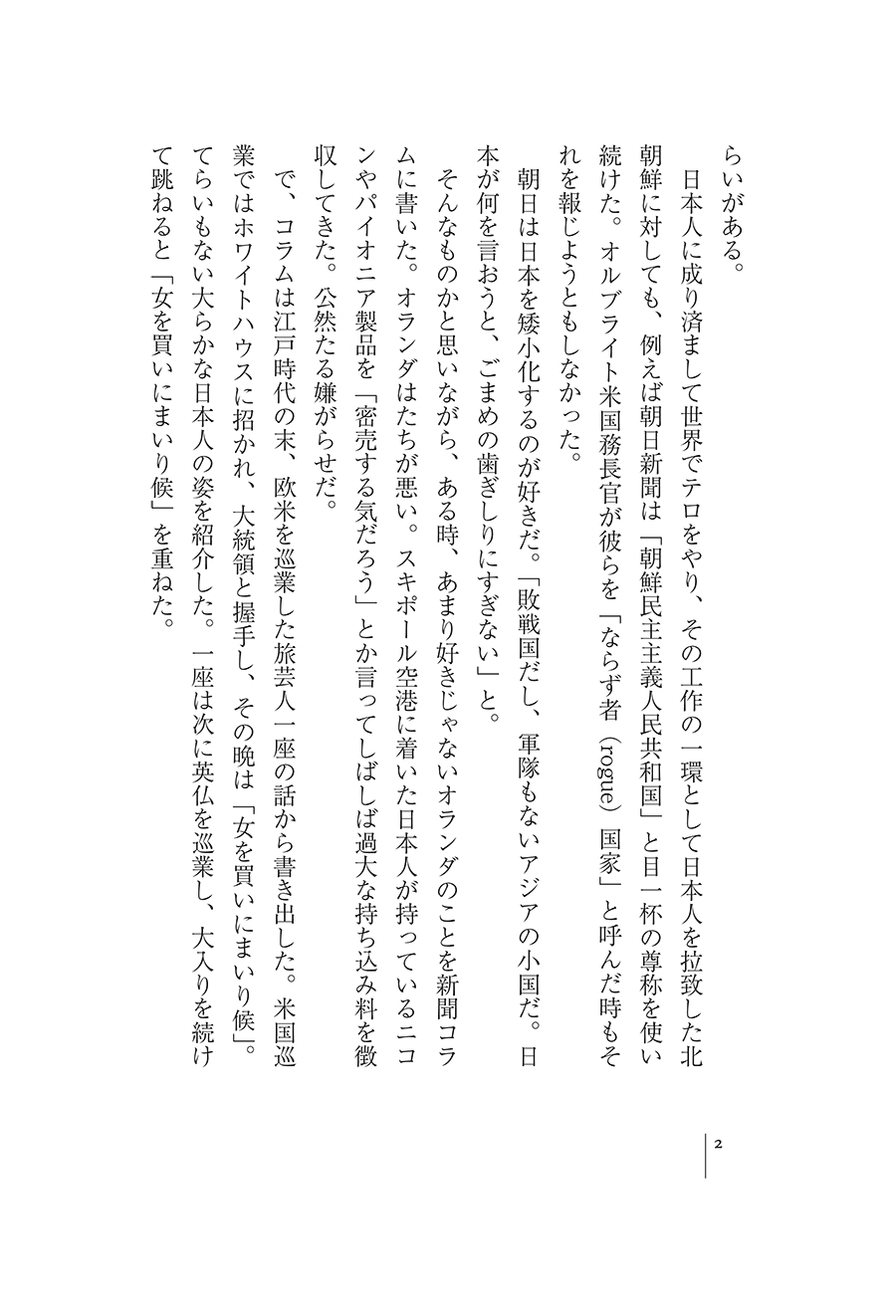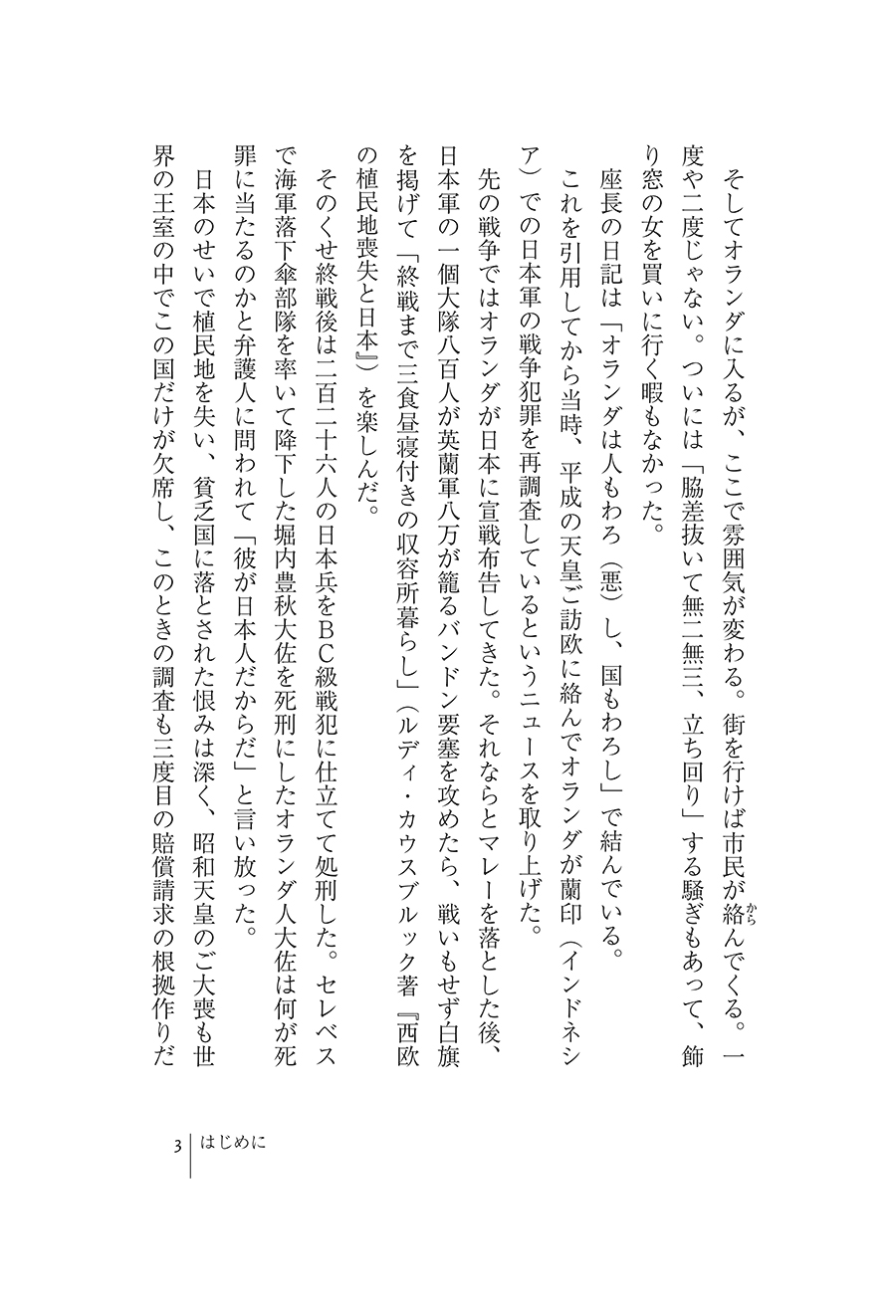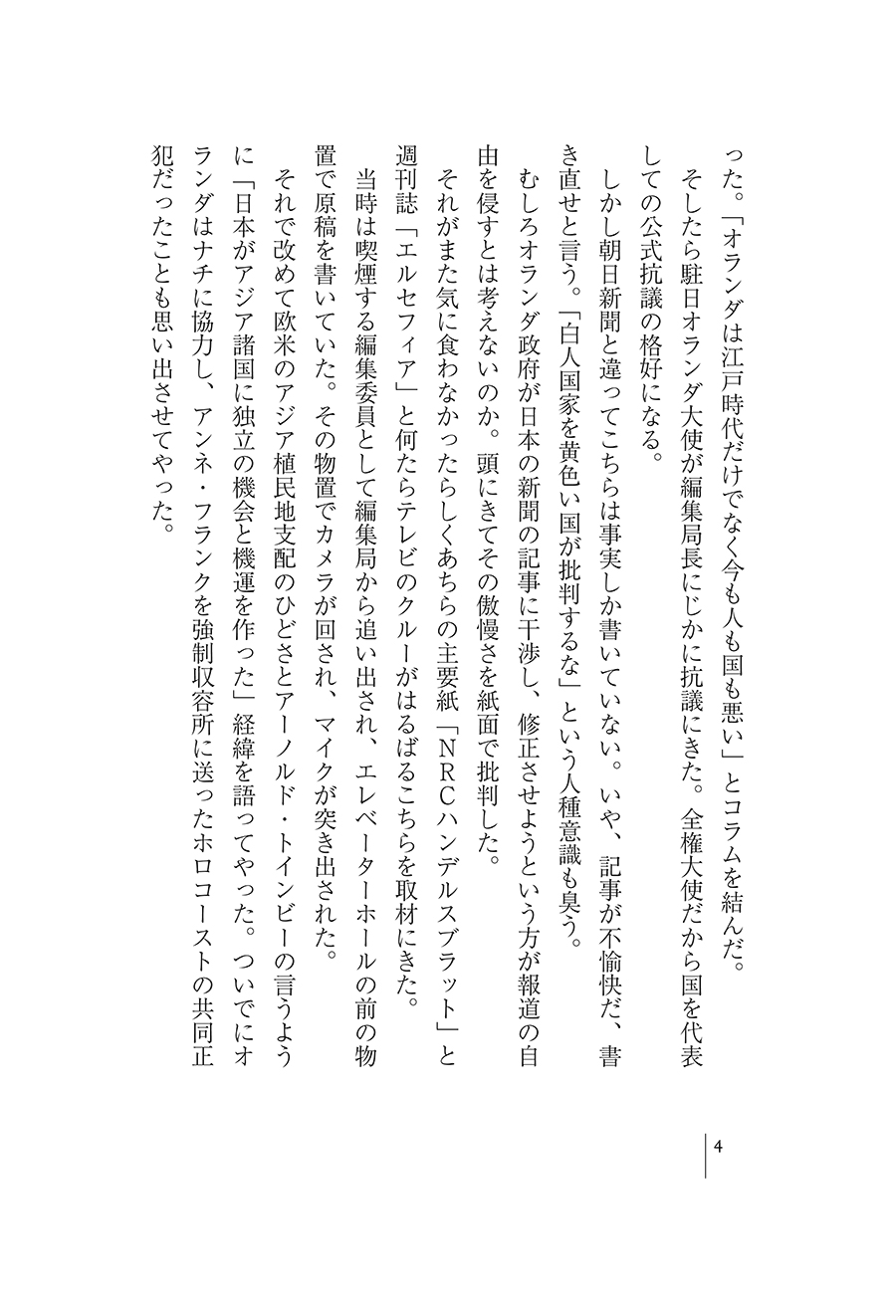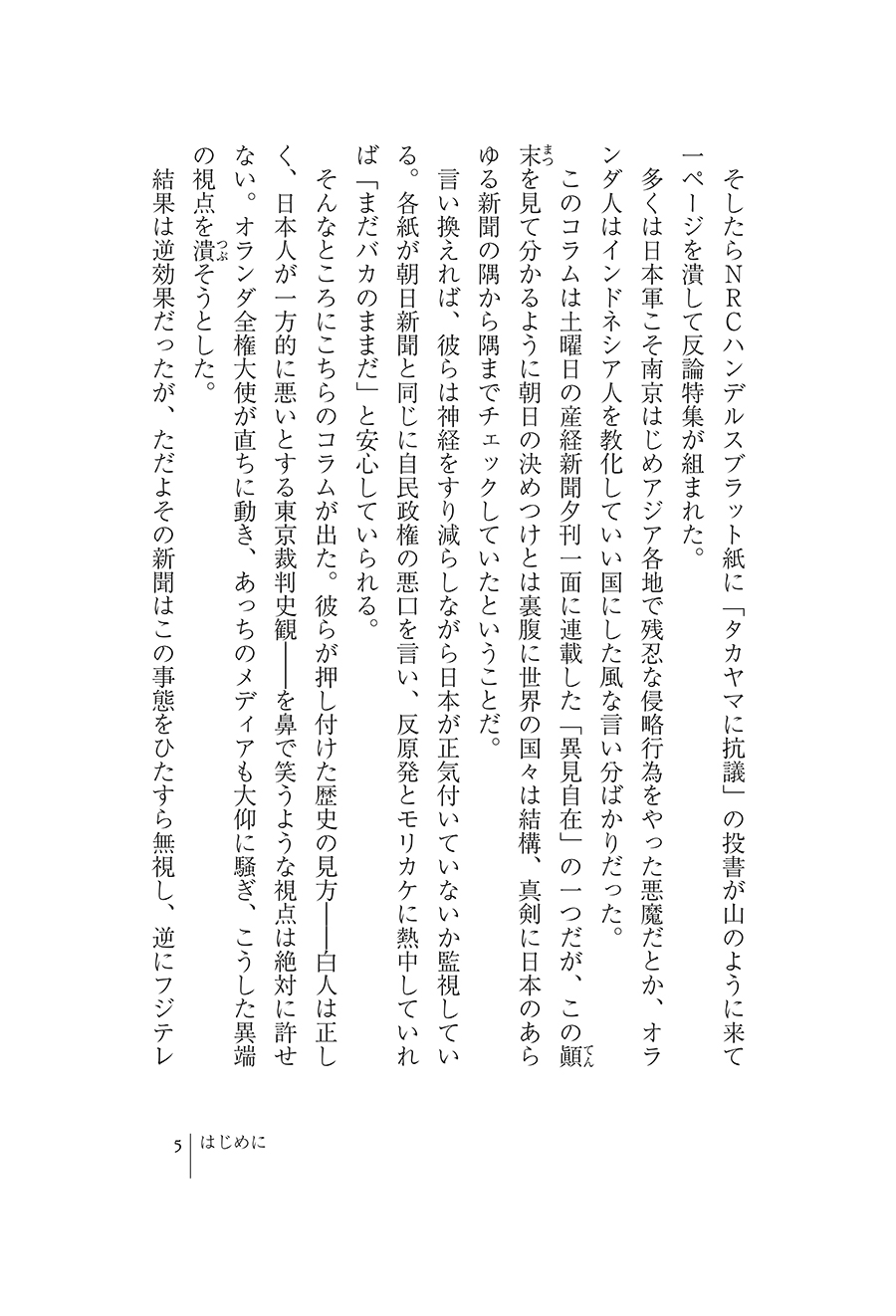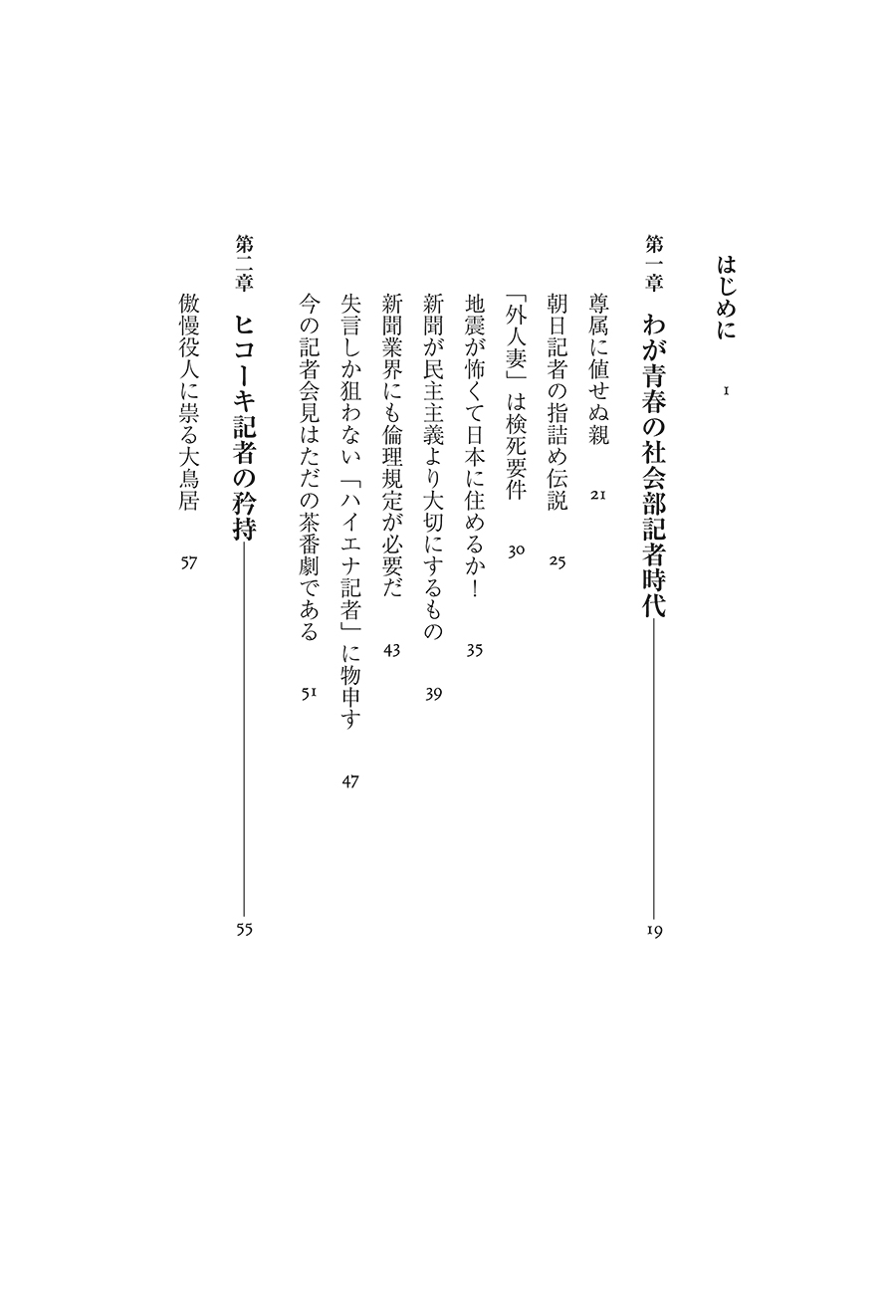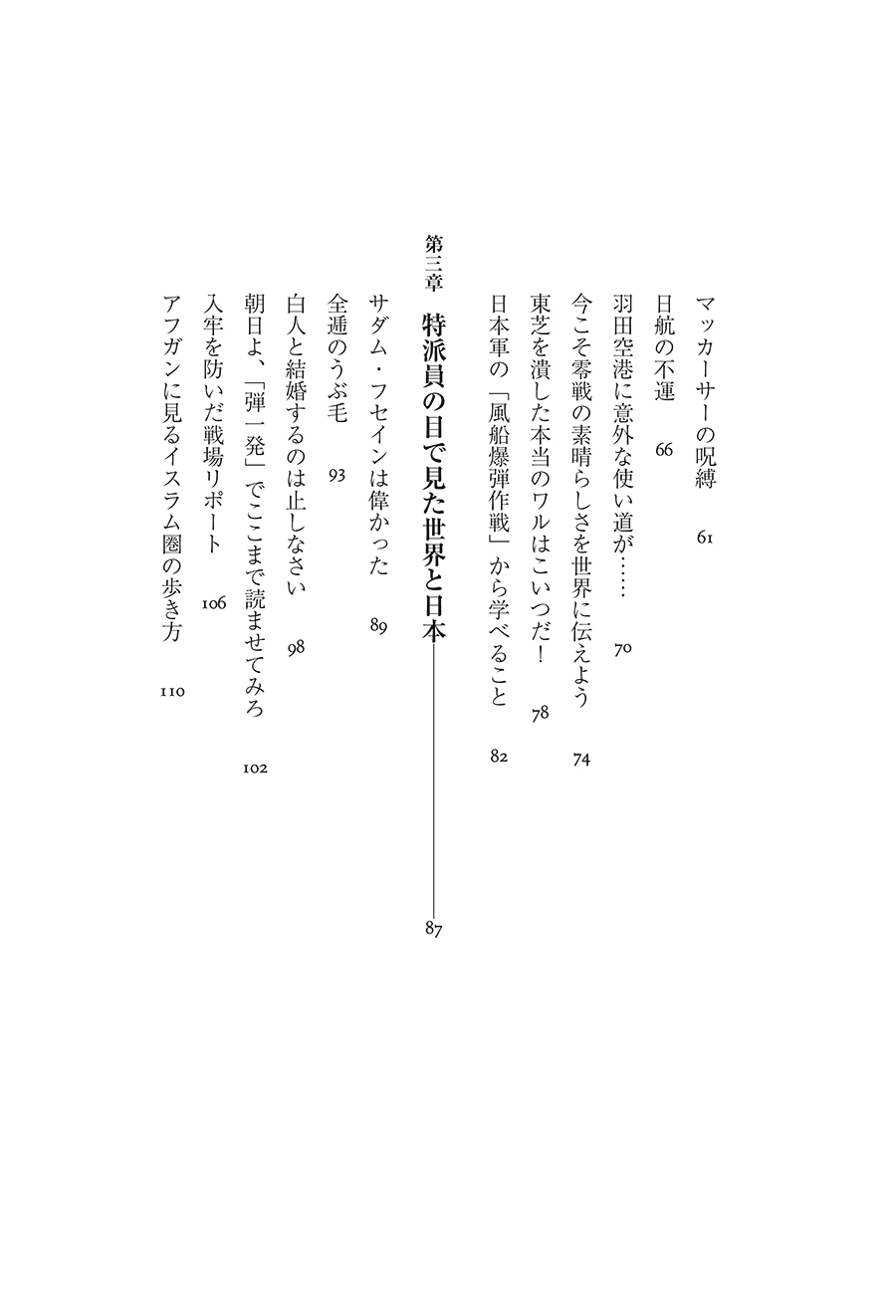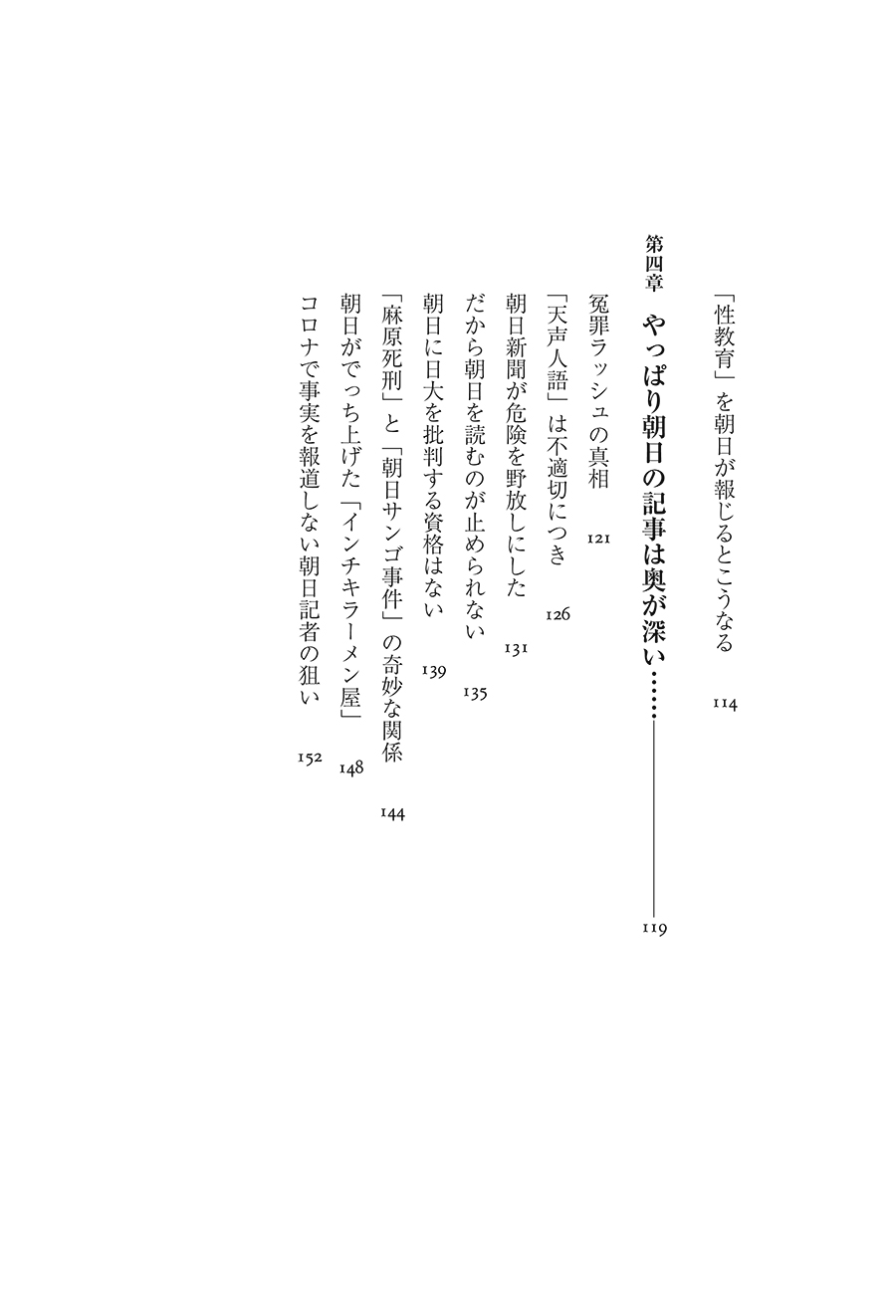はじめに
GHQに焚書とされたブレーク・クラーク著『真珠湾』(広瀬彦太海軍大佐訳)の解説にこういう一節があった。
「日本が嘗て過去一度でも米国を侮辱したることありや。況や日本が米国の存立を脅かしたことが爪の垢ほどもあったか。しかるに彼らは
ハル・ノートで最後通牒を突きつけておきながら真珠湾攻撃を「卑劣な不意討ちをした」と日本をひたすら
この「よその国を批判しない」「侮蔑しない」という感覚は実は今も変わっていない。加えて、敗戦後の日本は妙に外国に気後れし、進んで正邪の判断すらやめてしまったきらいがある。
日本人に成り済まして世界でテロをやり、その工作の一環として日本人を拉致した北朝鮮に対しても、例えば朝日新聞は「朝鮮民主主義人民共和国」と目一杯の尊称を使い続けた。オルブライト米国務長官が彼らを「ならず者(rogue)国家」と呼んだ時もそれを報じようともしなかった。
朝日は日本を矮小化するのが好きだ。「敗戦国だし、軍隊もないアジアの小国だ。日本が何を言おうと、ごまめの歯ぎしりにすぎない」と。
そんなものかと思いながら、ある時、あまり好きじゃないオランダのことを新聞コラムに書いた。オランダはたちが悪い。スキポール空港に着いた日本人が持っているニコンやパイオニア製品を「密売する気だろう」とか言ってしばしば過大な持ち込み料を徴収してきた。公然たる嫌がらせだ。
で、コラムは江戸時代の末、欧米を巡業した旅芸人一座の話から書き出した。米国巡業ではホワイトハウスに招かれ、大統領と握手し、その晩は「女を買いにまいり候」。てらいもない大らかな日本人の姿を紹介した。一座は次に英仏を巡業し、大入りを続けて跳ねると「女を買いにまいり候」を重ねた。
そしてオランダに入るが、ここで雰囲気が変わる。街を行けば市民が
座長の日記は「オランダは人もわろ(悪)し、国もわろし」で結んでいる。
これを引用してから当時、平成の天皇ご訪欧に絡んでオランダが蘭印(インドネシア)での日本軍の戦争犯罪を再調査しているというニュースを取り上げた。
先の戦争ではオランダが日本に宣戦布告してきた。それならとマレーを落とした後、日本軍の一個大隊八百人が英蘭軍八万が籠るバンドン要塞を攻めたら、戦いもせず白旗を掲げて「終戦まで三食昼寝付きの収容所暮らし」(ルディ・カウスブルック著『西欧の植民地喪失と日本』)を楽しんだ。
そのくせ終戦後は二百二十六人の日本兵をBC級戦犯に仕立てて処刑した。セレベスで海軍落下傘部隊を率いて降下した堀内豊秋大佐を死刑にしたオランダ人大佐は何が死罪に当たるのかと弁護人に問われて「彼が日本人だからだ」と言い放った。
日本のせいで植民地を失い、貧乏国に落とされた恨みは深く、昭和天皇のご大喪も世界の王室の中でこの国だけが欠席し、このときの調査も三度目の賠償請求の根拠作りだった。「オランダは江戸時代だけでなく今も人も国も悪い」とコラムを結んだ。
そしたら駐日オランダ大使が編集局長にじかに抗議にきた。全権大使だから国を代表しての公式抗議の格好になる。
しかし朝日新聞と違ってこちらは事実しか書いていない。いや、記事が不愉快だ、書き直せと言う。「白人国家を黄色い国が批判するな」という人種意識も臭う。
むしろオランダ政府が日本の新聞の記事に干渉し、修正させようという方が報道の自由を侵すとは考えないのか。頭にきてその傲慢さを紙面で批判した。
それがまた気に食わなかったらしくあちらの主要紙「NRCハンデルスブラット」と週刊誌「エルセフィア」と何たらテレビのクルーがはるばるこちらを取材にきた。
当時は喫煙する編集委員として編集局から追い出され、エレベーターホールの前の物置で原稿を書いていた。その物置でカメラが回され、マイクが突き出された。
それで改めて欧米のアジア植民地支配のひどさとアーノルド・トインビーの言うように「日本がアジア諸国に独立の機会と機運を作った」経緯を語ってやった。ついでにオランダはナチに協力し、アンネ・フランクを強制収容所に送ったホロコーストの共同正犯だったことも思い出させてやった。
そしたらNRCハンデルスブラット紙に「タカヤマに抗議」の投書が山のように来て一ページを潰して反論特集が組まれた。
多くは日本軍こそ南京はじめアジア各地で残忍な侵略行為をやった悪魔だとか、オランダ人はインドネシア人を教化していい国にした風な言い分ばかりだった。
このコラムは土曜日の産経新聞夕刊一面に連載した「異見自在」の一つだが、この
言い換えれば、彼らは神経をすり減らしながら日本が正気付いていないか監視している。各紙が朝日新聞と同じに自民政権の悪口を言い、反原発とモリカケに熱中していれば「まだバカのままだ」と安心していられる。
そんなところにこちらのコラムが出た。彼らが押し付けた歴史の見方――白人は正しく、日本人が一方的に悪いとする東京裁判史観――を鼻で笑うような視点は絶対に許せない。オランダ全権大使が直ちに動き、あっちのメディアも大仰に騒ぎ、こうした異端の視点を
結果は逆効果だったが、ただよその新聞はこの事態をひたすら無視し、逆にフジテレビ欧州特派員が「産経新聞がとんでもない記事を書いた。早急に善処せよ」と我が社に忠告してきたのが笑えた。ただそんな底の浅い特派員がいることに少し哀しくもなった。
もう一例をあげよう。沖縄返還を前に佐藤栄作首相が「返還後は米軍に核兵器の持ち込みを認めない」とするいわゆる「非核三原則」を語った。
背景には沖縄県民の抵抗で「ハワイ並み」(キャラウェイ高等弁務官)を目指した米国の沖縄経営の破綻があった。それでニクソンは必要な基地だけを取って、県民を日本に押し付ける施政権返還を決めた。
栄作は戦争で奪われた領土を戦争もしないで取り戻せる、人類史上稀な機会に巡り合った。ただ、それを理解しない馬鹿な野党と朝日新聞がいた。大事の前だ。政治的方便として核を「持たず」「作らず」「持ち込ませず」と言った。
これを米国が聞き逃さなかった。米国にとって一番怖いのは国際法違反の二発の原爆投下だ。彼らは日本が米国に対して二発の核報復権を持ち、それを必ず行使すると信じていた。
だからヘンな憲法を押し付け、日本の核保有を徹底的に警戒してきた。ケント・ギルバートは日本が中国に対し強力な軍隊を持つべきだと主張しながらも「日本は絶対に核を持ってはならない」と言った。米国人の本音だ。
そんなところに日本の首相が非核三原則を言った。よくぞ言った。米国はすぐノルウェーのノーベル委員会に命じて佐藤栄作にノーベル平和賞を出させた。日本は自ら核放棄を宣言したのだと。
米国のこの底の浅いペテンを大方は見抜いている。栄作自身も「非核なんていつでも捨てる」と言っている。それでノーベル委員会が「栄作に賞を与えたのは大間違いだった」と言ったとニュースにもなった。
ところが今になって岸田文雄首相が「非核三原則は日本の国是」とか言った。豆腐の角に頭をぶつけて考え直すべきだろう。
以上の二つのエピソードは何を語っているか。日本は十九世紀末、忽然として国際社会に登場した。そして例えば十四世紀以来、五世紀間、世界を恐怖に包んできた黒死病の正体ペスト菌をすぐに発見して、世界を安堵させた。
日本人はビタミンの存在も教え、死の病だった
日本人はまた日清、日露の戦争に勝ち、その戦いでギリシャ時代から続いた海戦の形もあっさり変えてしまった。
日本はまた植民地帝国主義という国ごと奴隷にする破廉恥な統治方法を批判し、人種平等を提唱した。
二十世紀、白人社会は結束して日本を叩き潰したが、世界はそれから大分経って日本人の言葉を理解し植民地は独立し人種平等社会に辿り着いた。
そんな空恐ろしい力を持つ日本を米国は戦後、あらゆる
今の日本はそういう状況にある。そんな環境にあることを国民に伝えるのが新聞記者の仕事だと思う。「いや、我々の仕事は権力の監視だ」と言う者がいる。それで閣僚の失言や言葉尻を追いまわす。それはちょっと違うように思う。日本の首相など権力者であるものか。現に新聞がでっち上げた疑惑だけで何度も潰しているじゃないか。
本当の「権力」とは全体主義国家、ジョージ・オーウェル『1984』の「ビッグブラザー」を思い描けばいい。毛沢東やスターリンでもいい。そう言えばスターリンは表敬に来た毛沢東を監禁し、「殺される」と毛を恐怖させた。
この二人は彼らの政策についての反論や非難を嫌う。そんな生意気な者は即座に排除する。人民を苦しめるだけだった「大躍進」について毛沢東に
外国特派員も同じ。スターリンは彼の提灯記事を書く米ニューヨークタイムズのウォルター・デュランティだけを認めた。毛沢東もまた朝日新聞の秋岡
今のプーチンも同じだ。ロシア人には誇らしい過去などない。一度だけ「共産主義はバラ色」と錯覚された時期、東側陣営のリーダーに立ったことがある。それを彼はロシアの強さだとダブルで錯覚した。
スターリンと似て背が低く、シークレットシューズを履くコンプレックスもあって、歯向かうものは容赦しなかった。プーチンの自作自演のテロを暴いたアレクサンドル・リトビネンコはポロニウムを盛られて三週間苦しみ続けて死んだ。同じ年、プーチンを批判した女性ジャーナリスト、アンナ・ポリトコフスカヤもモスクワのアパートで射殺された。
彼の恐怖政治を批判した産経新聞論説顧問、斎藤勉はウクライナ侵攻の騒ぎのさなかにロシア政府から無期限入国禁止処分を受けた。
このとき米英など自由陣営のジャーナリストも多数追放や入国禁止処分を受け、日本関係では斎藤勉のほか国際政治学者、袴田茂樹など計六十三人が無期限入国禁止とされた。
ただ、朝日新聞や毎日新聞の記者はだれ一人処分を受けなかった。ここの記者は例えば朝日の秋岡家栄のようにひたすら権力者に媚び、権力者の嫌がることは何も書かない。そのくせ朝日の主筆だった船橋洋一は「新聞記者は権力を持つものを監視し、徹底的に戦う」とか偉そうに言う。
それで今、何をしているか。例えば凶弾に倒れて逝った元首相が反論もできないのをいいことに「統一教会とずぶずぶ」とか下衆の勘繰りだけで中傷する。記者の名を
週刊新潮に連載のコラム「変見自在」はこの秋、連載開始から千回を迎えた。一度も休載しなかったこと、ネタの鮮度も何とか落とさず続けてこられたことが僅かな自慢だが、書いてみて分かったことの一つに新聞記者の役割がある。
新聞記者の仕事は楽しかった。英国のエリザベス女王が亡くなられたが、訪日のときに間近で取材させてもらった。チャールズ新国王とも米西海岸で取材の機会を得た。
ピーター・ドラッカーとは何度か食事もし、ベトナムの英雄、ボー・グエン・ザップ将軍にはパパイヤの食い方も教わった。
自衛隊ですら体験していない戦場にも前後六回出かけて砲煙弾雨に
この連載を続けられたのもそういう好奇心のおかげで拾い集められたネタが多かったからだ。
現役の記者は政治家の揚げ足を取ったり、ワシントンポストを翻訳したりするよりもっと他にやる事があると思う。その好奇心が今の日本を救うような気がしてならない。
では何にどう好奇心を持つか、二十年間、好奇心だけで書いたこの書がその参考になれば幸せだ。
二〇二二年十一月 高山正之