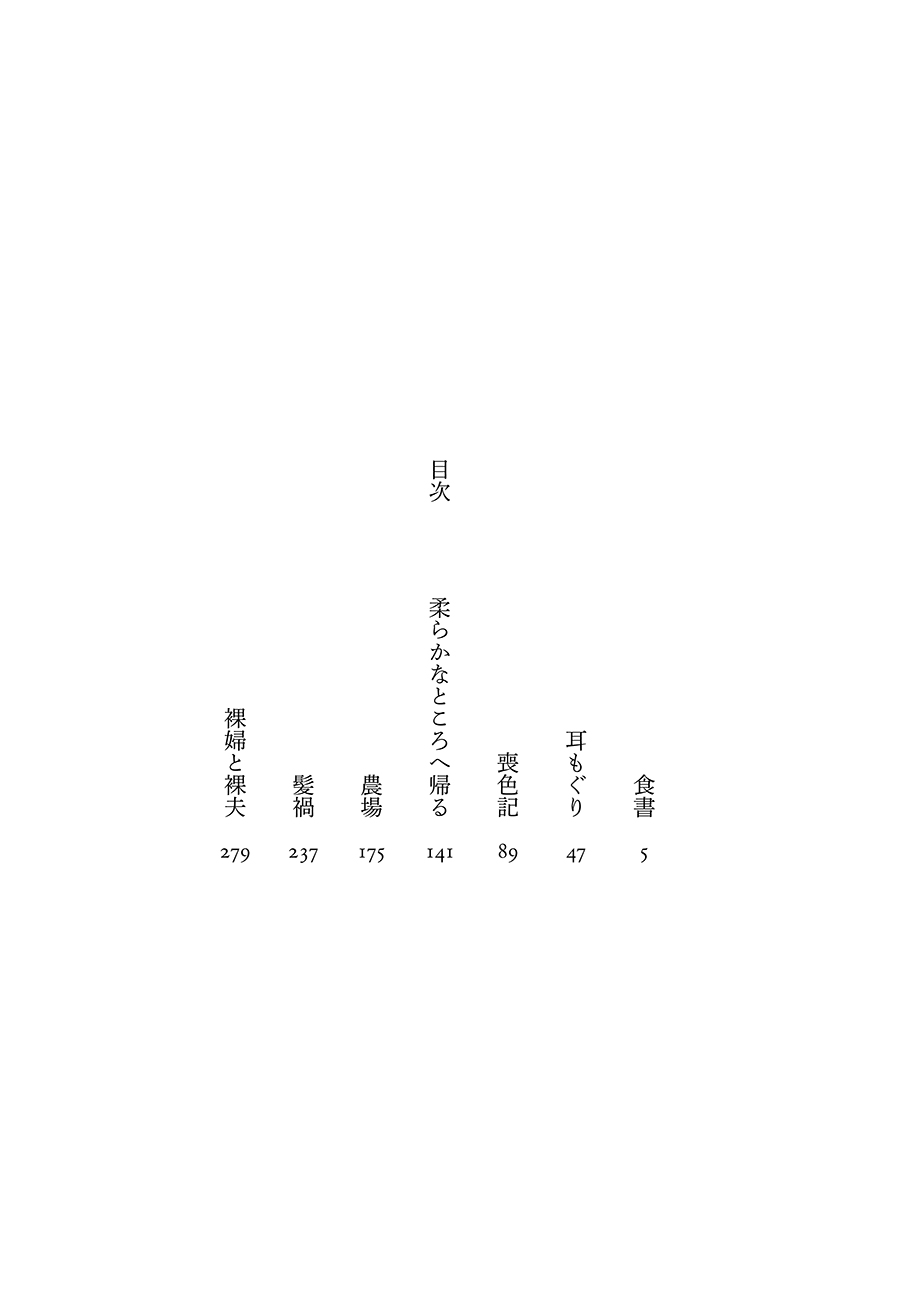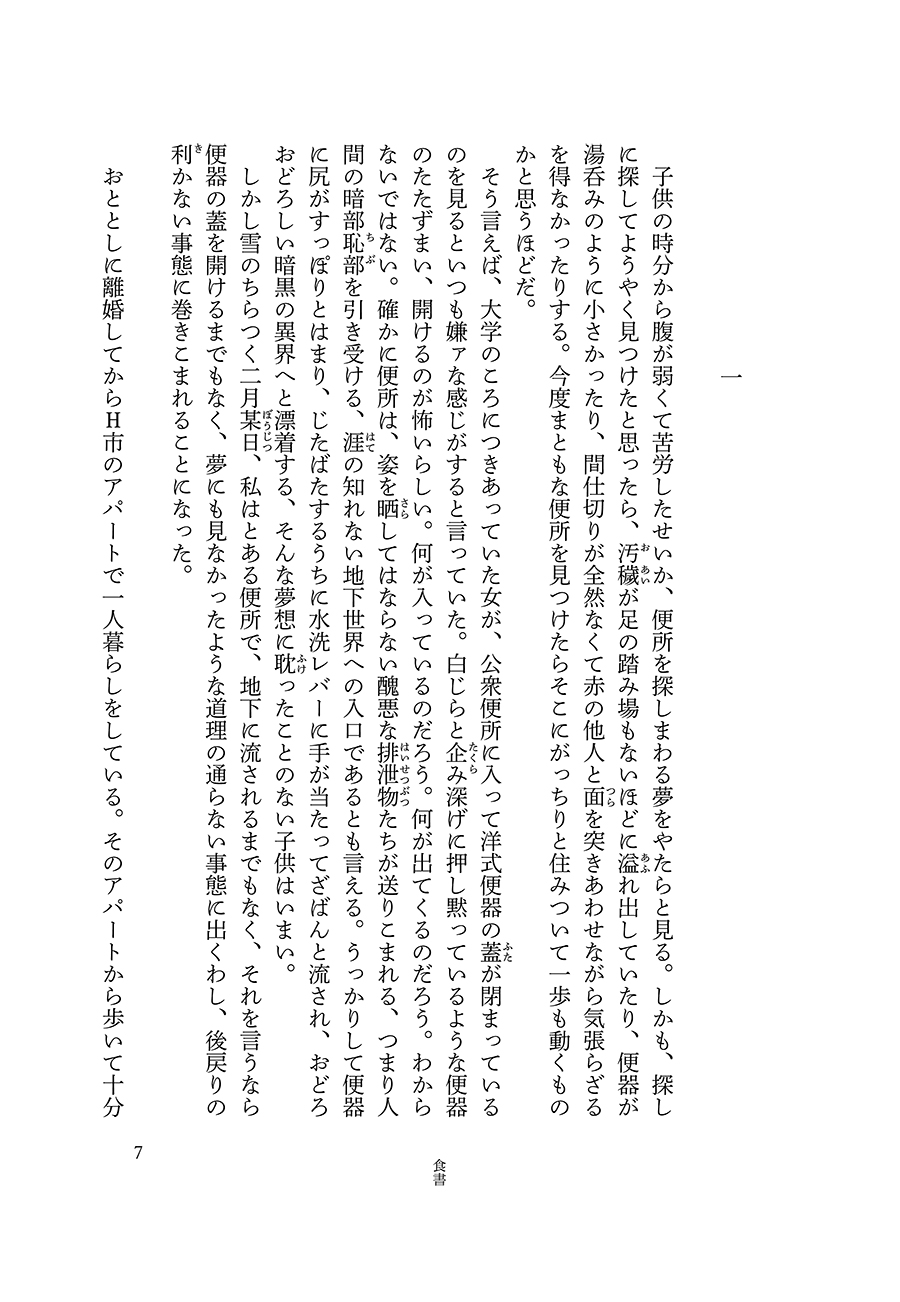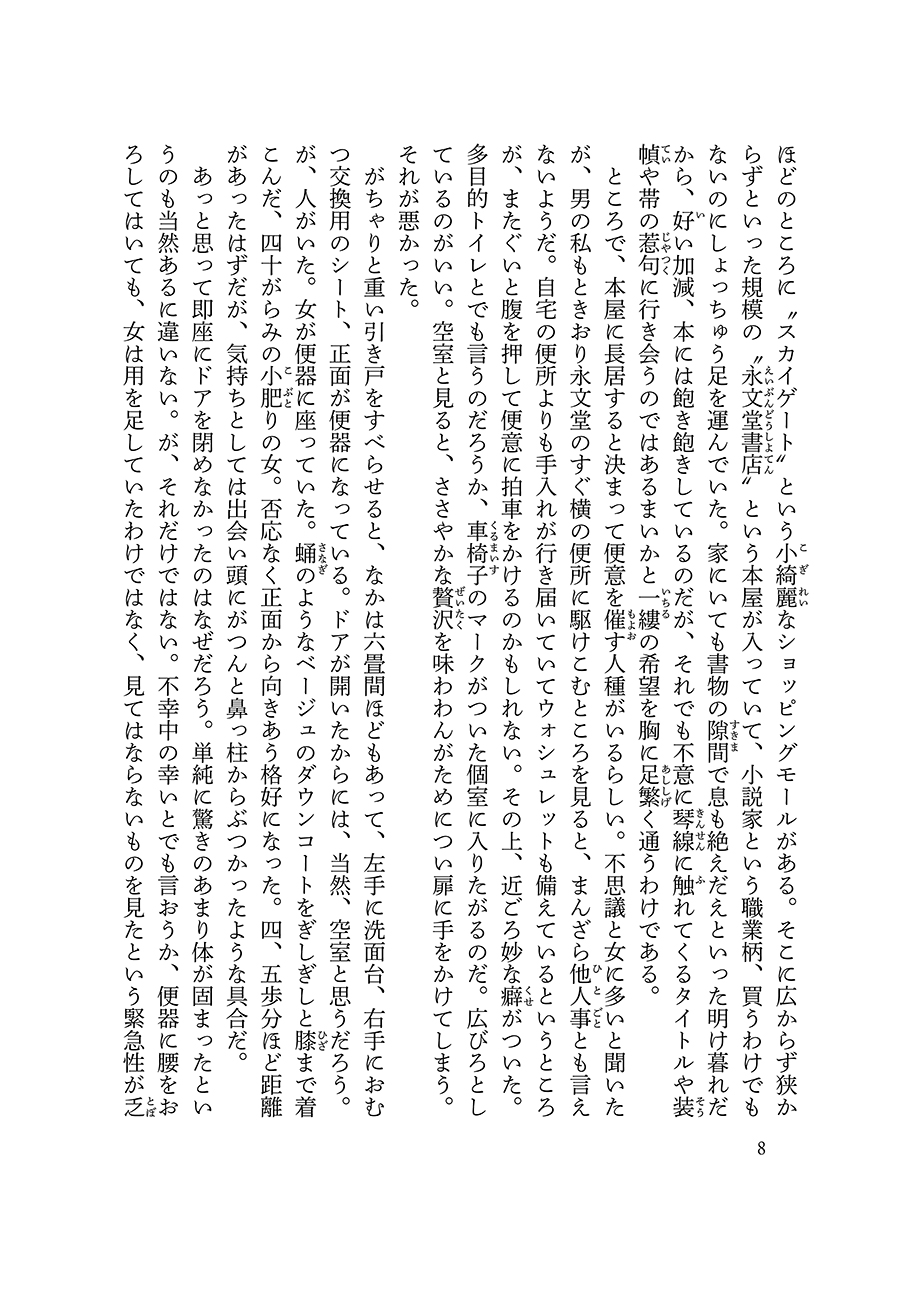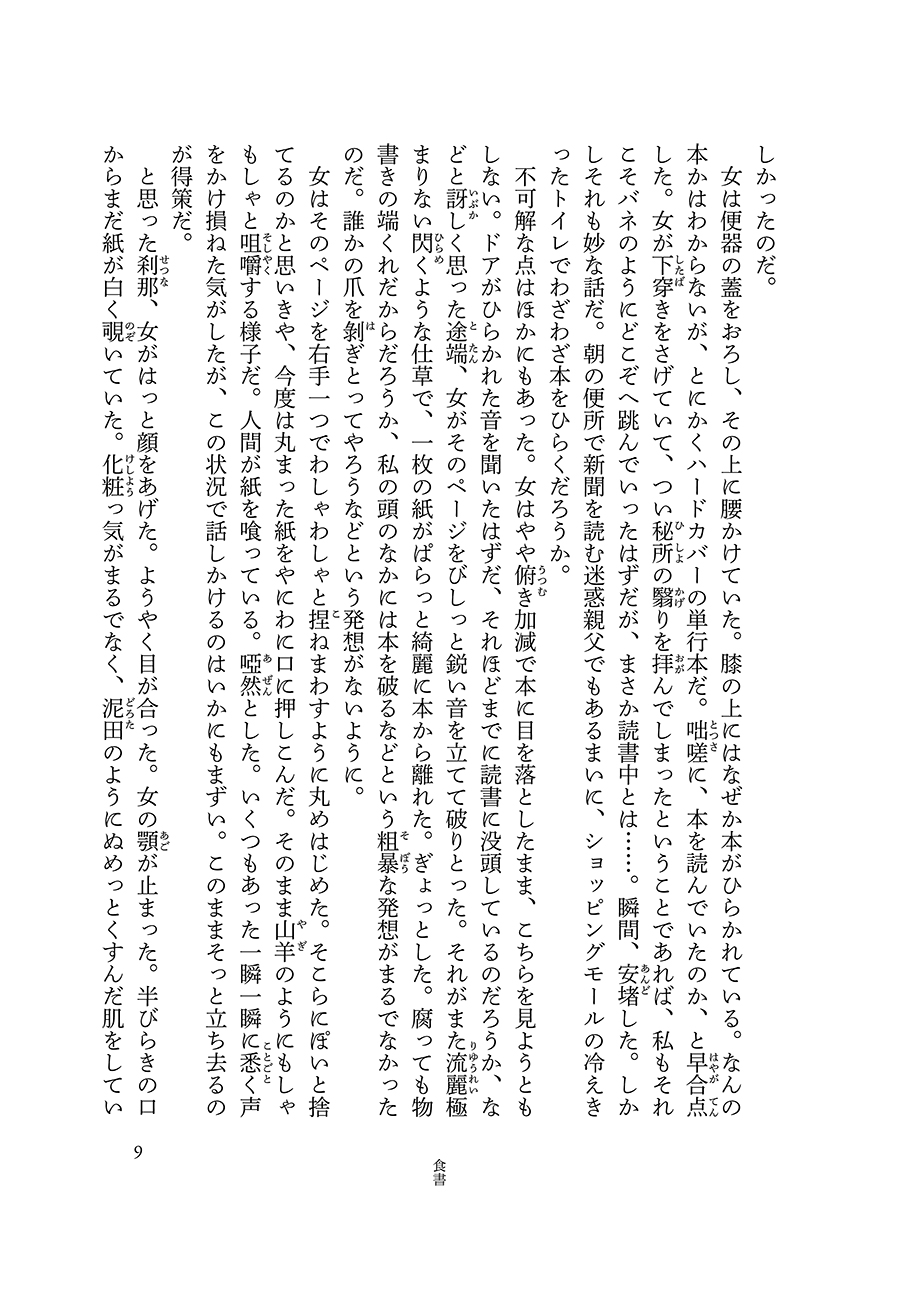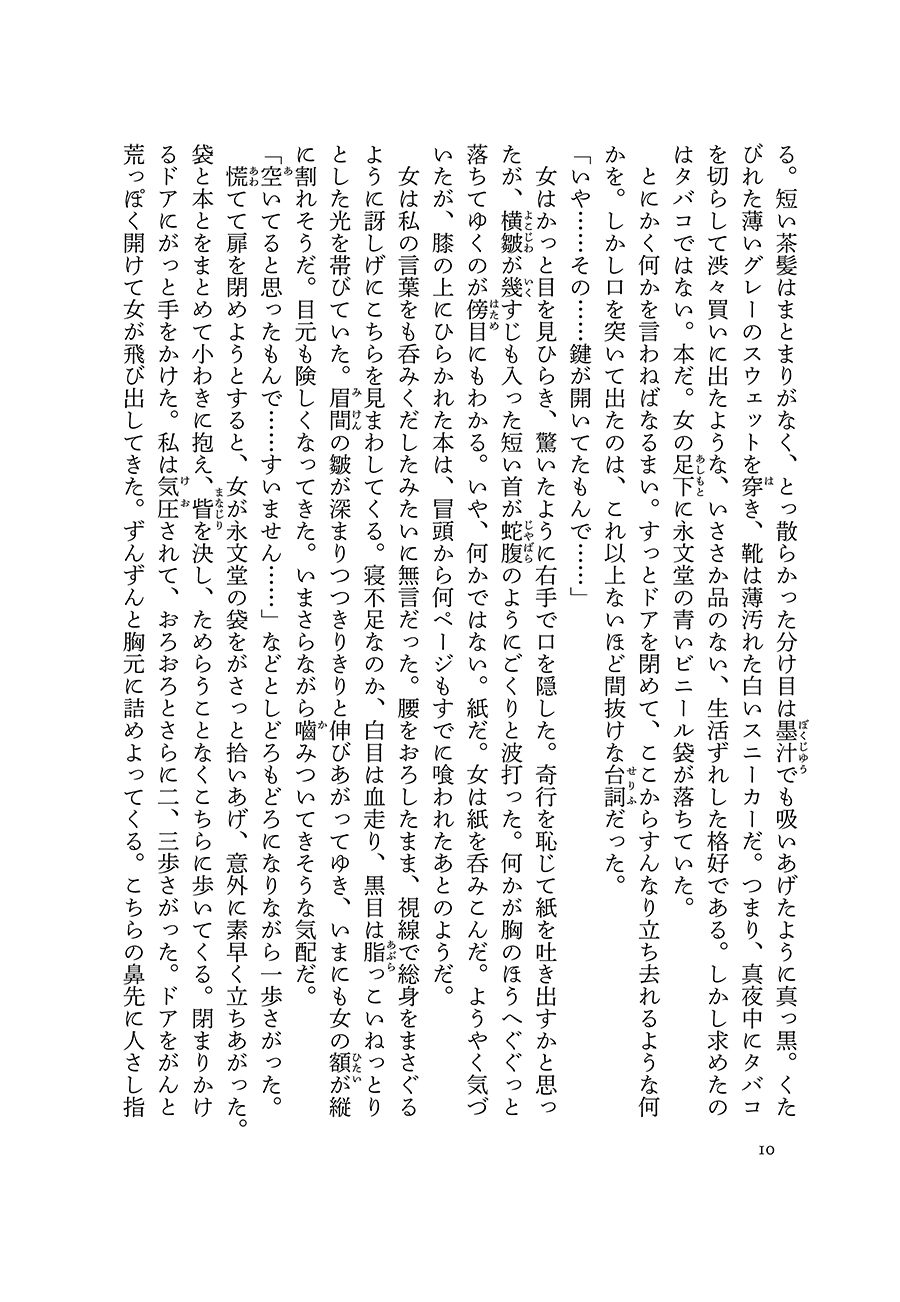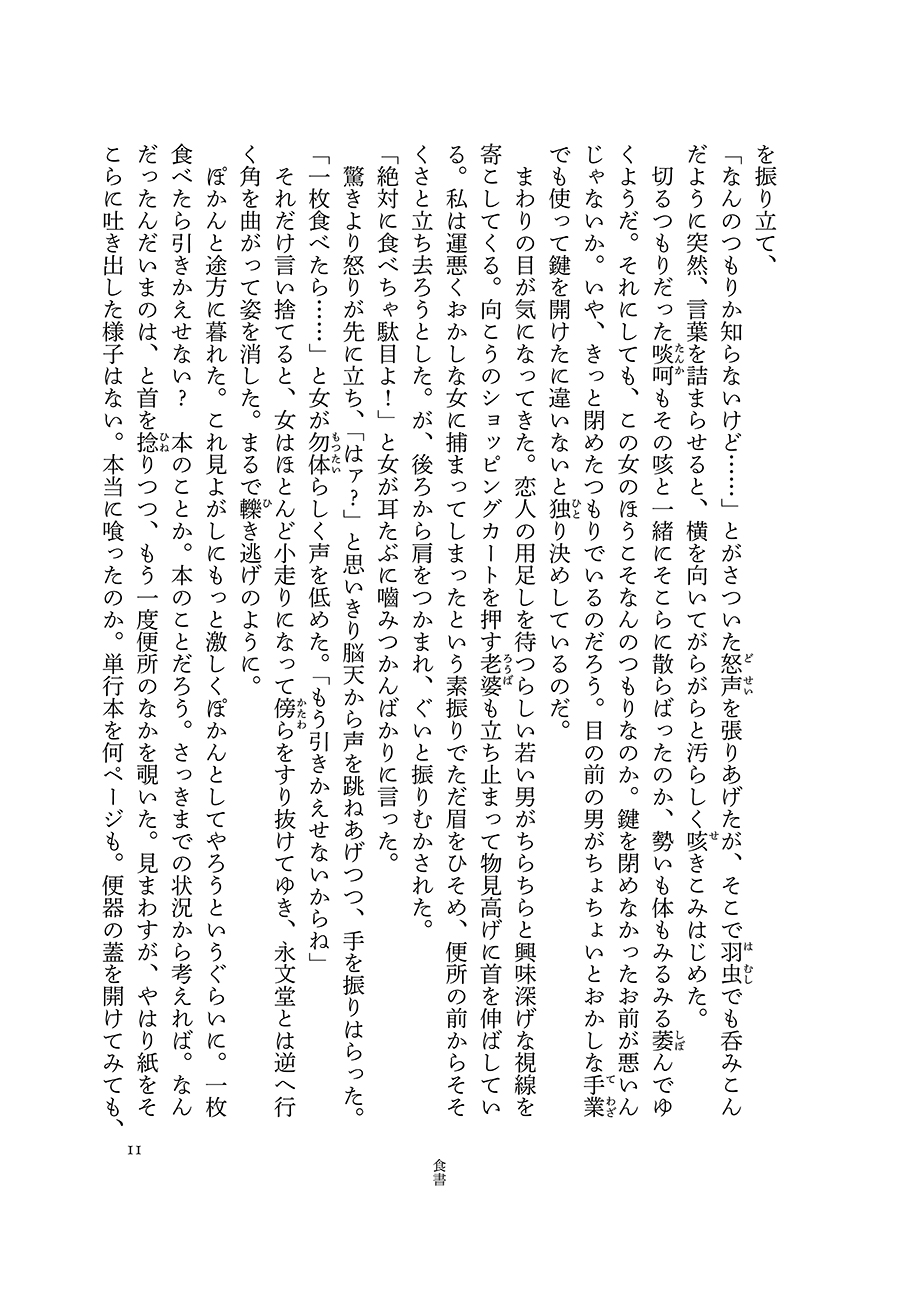耳もぐり
この手です。誰もが両腕の先に特段、不格好だとも不気味だとも思わずに平気でぶらさげている、まさにこれです。ほら、こうして目の前に
ああ、
ああ、そう言えば、あなたは本当に学者でしたね。まだ非常勤講師だけれど、東京の私立大学で社会学だの英語だのを教えている。そう、初めてお会いしましたけどね、あなたについては色々と知っているんですよ。あなたが思っているよりずっと多くのことをね。中原
いや、違うな。会うのは初めてじゃない。一度だけ、たった一度だけですが、三年ほど前にこのアパートの廊下ですれちがったことがありますね。
それはまあいいでしょう。とにかく手です。私がいまから話そうとしているのは、人間の手が長いあいだ隠し持ってきた、知られざる能力のことなんです。つまりそれが“耳もぐり”なんです。もちろん初めて聞く言葉でしょうね。耳もぐり、耳もぐり……なんとも
ああ、わかっていますとも。中原さん、あなたがなんのために私に会いに来たかは重々承知しています。香坂百合子のことでしょう? 聞きたいことは山ほどあると思います。しかしとにかくあなたは香坂百合子の
実を言いますとね、彼女がこのアパートから姿を消してからの三カ月間というもの、私はずっとあなたを待っていたんですよ。いや、本当です。いっそのことこちらから会いに行こうかと思ったことも一度や二度ではありません。しかし結局その勇気を持てなかった。怖かったんです。あなたと
ええ、私はあなたについてもいくらか知っていますが、彼女についてはもっと多くのことを知っているんです。彼女とはこのアパートの廊下や階段で何度すれちがったことでしょうね。彼女は女の一人暮らしですから、男の私をどこか警戒した様子でいつも目を伏せ、曲がらぬものを曲げるような固い
あなたがどう思っていたかはわかりませんが、彼女はあなたを本当に好きだったんですよ。もう何年も東京と大阪で別れて暮らし、たとえ月に一度しか会えなくとも、彼女はあなたを本当に好きだった。あなたもご存じのとおり彼女は器用な女じゃありませんでした。人生にわき道なんかないと思っているから、よっぽどのことがないとハンドルを切れないんです。あなたはあなたで自分が一人前になるのを長いあいだ待っていたんだろうと思いますが、彼女もあなたを待っていたんですよ、二十年もね。これは何十万年ものあいだ続いてきた、神話的なまでに古い、そして美しい物語じゃないでしょうか。男は狩りに出る。立派な
いや、それにしても私は
ああ、あの窓際の猫が気になりますか? このアパートは本来ペットを飼ってはいけないんですがね、実際はみんな色々飼っているらしいですよ。
そう言えば、香坂百合子も私が猫を飼っていることを知っていました。私がアニエスをベランダに出したとき、彼女は手すりから少し乗り出すようにして、間仕切り越しにあの子を見たんです。あ、と声を
実は、私が最後に彼女を見たのもここのベランダでなんですよ。彼女は見ているこっちが冷やひやするぐらいに手すりから身を乗り出し、この子を抱く私をじっと見て手招きしてきたんです。そして世界が耳をそばだてているのだというふうに小声で話しかけてきました。何と言ったと思いますか? 意外なことを言ったんですよ、彼女は。私にとっては実に意外なことを。まあその話はまたあとでするとしましょうか。言ってしまえば、付け足しのデザートのような話に過ぎませんからね。
ところで、あの子の目を見ていると、いつもある映画を思い出すんです。『殺し屋、あるいは
さて、その殺し屋ですが、おかしなことに、仕事をこなすたびにどこかから猫を一匹手に入れてきては、殺した相手の名前をつけて飼うんです。まるで自分が殺した人間はただ死んだわけではなく、すべて猫として生まれ変わったんだというように。誰一人殺してなどおらず、本来あるべき猫の姿に戻してやっただけだというように。でもそのせいで愛しはじめた女刑事に正体がばれてしまいます。そして最後は屋敷を警察に囲まれて、銃で全身を撃たれて死ぬんですがね。
なんと言っても結末がいい。
ああ、そうでした。耳もぐりの話でしたね。余談が過ぎました。私が初めて耳もぐりを目撃したのは二十六歳のとき、中原さん、あなたが生まれる以前の話です。昭和四十七年、
と言っても、私は旋盤に
あの日、夜遅く、私は
ここからが重要です。目を閉じてしばらくすると、誰かが隣の車両から移ってきたような足音が近づいてきました。コトン、コトン、という男物の硬い革靴のような足音でしたね。いや、実際は気配をぐっと押し殺して忍びよってくるような、普段なら聞き逃していたに違いない
しかし結局、足音の主は私には
薄目を開けたまま、私は息を殺して待ちました。男が女に触れるのを。財布を盗られるのは何も自分でなくても構いません。男が女の鞄を漁ろうものなら、バネのように飛び出していって正義の名のもとに腕を
ところで話は変わりますが、猿とタイプライターの話はご存じですか? 猿がタイプライターの前に座ってでたらめに打ちつづければ、いつかはシェイクスピアの作品ができあがる、という有名な話です。いやいや、実際にはできあがりませんよ。死なない猿も壊れないタイプライターも存在しませんから、単なる
まったく
もうおわかりでしょう? 男は“鍵”によって、“鍵穴”つまり女の耳をこじ開けました。私の見る前で、男は女の左耳に右手の中指を突っこんだかと思うと、ずるずるずるっと全身が吸いこまれてゆき、音もなく姿を消したんです。背広も革靴も残すことなく、頭のてっぺんから足の先まですっかり姿を消した。つまり、なんと言いますか、人間の形をした紙風船が中指の先からきつくしごかれて、つぶされながら小さな穴に吸いこまれてゆくような感じでした。時間にしてせいぜい二、三秒といったところでしょうか。それを目撃した私の驚きは想像がつくでしょう? 一人の人間が一人の人間の耳のなかに吸いこまれて消えたんです。その瞬間、女がびくりと身を震わせて目を覚ましました。何かこう、穴に落ちる夢でも見たような具合です。女は、やはり何か違和感を覚えたんでしょうね、男を吸いこんだ左耳にしきりに触れながら、どこか非難がましい視線を私のほうに向けてきました。離れたところに座る私が、ろくろ首のように
さて、これまた運命が私を
女の話を続けましょう。女は一人の男が丸ごと耳のなかに入っていることも知らぬげにひっそりと静まりかえった住宅街を歩いて行きました。ところどころにポツンポツンと肩身が狭そうに街灯が立っていて、弱々しい光で夜道を照らしていました。あたりを見まわしましたが、その道を歩いているのは私と女、二人きりです。女のほうもそれが気になったのか、一、二度後ろを振りかえり、離れてついてくる私にやや警戒しているようでした。なんの後ろめたいこともないときには男として
そのときです。突然、女がぴたっと立ち止まり、もう我慢がならないというふうにくるりとこちらを向きました。そして肩を怒らせ、巨大な目でまっすぐこちらを
街灯の下、五メートルほどの距離でしたでしょうか、私と女はしばし無言で向かいあいました。女の厚ぼったい
どんなふうに握りかえされたか、それをお話ししましょう。夜が背後から押しよせてくるような心持ちのままどうにか工場の寮の近くまでたどり着き、ほっと胸を撫でおろしたときでした。私はぎょっとして立ちすくみました。なぜか前方に、道の先に、さっきの女がいるんです。夜道をこっちに向かってふらふらと歩いてくるんですよ。しかも
そのときです。背後からあの男に声をかけられたのは。四十年も昔のことですが、いまだに耳のなかからそのしつこい残響を引っぱり出せそうですよ。男はこう言ったんです。
「見たんだろう」
私はびくりとして、本当にびくりとして、瞬時に振りかえりました。電車のなかで後ろ姿を見た男が立っていました。すぐそこに。手を伸ばせば届くところに。ぬるりとした撫で肩と背広姿ですぐにこいつだとわかりました。五十がらみのなんとも不快な顔立ちの男。べこんとこけた頰、
「おまえ、見たんだろう。これを……」
あっ、なんとかしなくては、と一瞬考えたのですが、もう手遅れでした。男は左手で私の左手首をぐっとつかみ、右手をすっと伸ばして、私の左耳に指を突き立ててきたんです。他人の指を耳に突っこまれるというのはどこか
どれぐらいの時間その場にいたかはっきりしません。一分か十分か、それとも三十分か一時間か、それすら言えない。とにかく気が動転していたんです。何度も左耳に自分の指を突っこみ、男を
寮は木造の二階建てで、私の部屋は二階の奥でした。三畳ひと間に押入一つ、独房のように狭い部屋です。暗い裸電球、
私は自分の部屋に飛びこむと、真っ先に鏡を手に取りました。鏡と言ってもメラミンの
しかしそう甘くはなかったんです。本番はそこからでした。突然、私の右手がぐいっと持ちあがり、手鏡を頭上に高だかと
「俺はここにいる」
一瞬、私は自分が
「俺はここにいると言ってるんだ。いないことになんかできねえよ」
恐ろしいことです。
私は割れた手鏡を握りしめたまま
「教えてくれ。それを俺にも教えてくれ」
私は、いや、私のなかの彼は笑いました。声もなく、大口を開け、
「ここから出ていきたいってわけか? この牢獄から?」
この牢獄、その言葉は彼が口にしたのですが、まるで私の魂に釣り糸を垂らして引きあげてきたかのようにしっくりと響きました。私は何も答えず、ただうなずきました。彼は、はっ、ともう一度だけ鋭く切るように笑い、言いました。
「牢獄の外は隣の牢獄……」
私の右手がおもむろに動きはじめたかと思うと、見たこともないような妙な形をつくり、その中指が右耳に突き立てられました。これはあとから知ったことですが、入るときの手の形とはまた違うんです。似ているようですが、確かに違う。これを間違うと大変なことになる、と彼からのちに教わりました。耳もぐりの第一のタブー、自分の耳にもぐってはならない、と。彼は“
さて、彼は私を引き起こすなり、
「ここは誰の頭のなかだ?」
これは彼の冗談なんです。彼だけに、でなければ耳もぐりをする人間にだけ通じる冗談なんです。実際、私がなおも
「お前じゃないとしたら、俺なんだろうな。え?」
そこで彼は私を見おろし、おどけたように片方の眉をひょいとあげ、そして自分の頭を人さし指でこつんこつんと叩きながら言いました。
「そんなことより……猫が見えた。大きな屋敷からたくさんの猫が……」
私は内心ぎくりとしました。彼が言った猫というのはもちろん夕方に見たばかりの映画のことです。私は耳もぐりがどんなものか独り決めしてはいませんでしたが、そういうものだとは思っていませんでした。もぐった相手の記憶にまで、そして心にまで触れるものだとは。しかしそのことについてはのちほどもう少し詳しく話すとしましょう。
彼は鈴木と名乗りました。もちろん偽名でしょうね。もっとも本当の名前がなんであれ偽名のほうがよほど似合うような
実際、鈴木は口数の少ない男でした。と言っても決して口下手というのではなく、かつて言葉がもっと正確に無駄なく使われていた輝かしい時代があったのだとでも言いたげに、ひと言ひと言を相手の胸に言葉を押しこんでいくように話すんです。抜き身の言葉とでも言いましょうか、実際に聞くとひどく不愉快なものですよ。鈴木にそう何度も何度も会ったわけではありませんが、いまでもあの独特の確信に満ちた語り口を忘れられません。いささか恥ずかしくもありますが、ちょっと
「耳もぐりをうまく使えば多くのつまらないものを手に入れられるが、お前が本当に欲しがっているものは何一つ手に入らない。俺たちは通りすぎるだけ。誰かの頭のなかを右から左へ、あるいは左から右へ、ただ通りすぎるだけ。本当の人生なんか俺たちにはないんだ」
終始こんな調子です。恐ろしく不自然でしょう? まともな人間の口調じゃない。こうも言っていました。
「明るいところへ出ようなんて思うなよ。俺たちは影みたいなもんだ。少しのあいだなら誰の影にだってなれるが、所詮、影は影だ」
何を話しても鈴木の口から出ると一切が結論じみていて、私はただそれを黙って聞くしかありませんでした。途中で何か異論を差し挟もうものなら、彼は巨大な沈黙を後ろ盾にじっと私を見かえしてくるんです。言葉で説明してわからないようならあとは沈黙と時間にまかせるだけだとでも言わんばかりに。だからでしょうね、私が鈴木を憎むようになったのは。いや、それだけじゃないな。この際、正直になりましょう。いったん誰かを憎むようになると、それは黒い雪玉を転がすようなものです。ありとあらゆるものが憎しみを引き起こす原因としてまとわりついてくる。私は結局、あの最初の出会いからすでに鈴木のことを深く憎んでいたんです。理屈ではなく、何かこう、肌のようなもので。
最初に会った夜以来、彼はときおり私の部屋にふらりと現れるようになりました。
私にとって鈴木の訪問はいつも重苦しいものでした。狭い三畳間で無口な男二人が膝を突きあわせて酒を飲みながらぼそりぼそりと話すのです。鈴木の青黒い顔は
ところで私が初めて耳もぐりをした相手は誰だと思いますか? 少し考えればわかることですよ。そう、もちろん鈴木です。私はあの最初の晩に初めて鈴木の耳にもぐったんです。彼は手短に私に“入り鍵”の形を教えると、子供をくすぐり殺すような薄ら笑いを浮かべて言いました。
「まず俺の耳にもぐってみろ」
私は
「大丈夫だ。すぐに引っぱり出してやるさ」
正直、余計にぞっとしました。自分から言い出したことなのですが、本当に本当にもぐるんか、この俺がこいつのなかに、と考えると、すうっと血の気が引くように感じたのです。しかも相手は会ったばかりのいかにも
しかし標的が進んで耳を貸してくれるとは言え、これがなかなか容易にはいきませんでした。瞬時に正確な手の形をつくり、
などと言いつつも、とうとうその瞬間が不意にやって来ました。初めて人の耳にもぐる瞬間が。どう表現したらいいでしょう、あの不思議な感覚を。ひと言で言えば、墜落感、とでもなるんでしょうか。意外なことに、相手の耳のなかに、落ちていく、という感覚なんです。まず、ふわっと体が持ちあげられるような浮遊感に襲われるんですが、次の瞬間にはもう相手の耳の穴と自分の入り鍵が
そう言えば、鈴木はもぐる相手のことを“耳主”と呼んでいました。いかにも鈴木らしい
言っておきますが、耳主の体を操るというのはたやすいことではありません。私もすぐに自由に動かせると思いこんでいたんですが、鈴木の腕を一本あげるだけでひどく骨が折れました。全身がすっかり
しかし始めたばかりのころは、もぐってから何時間もろくろく動けませんでした。出鍵を使って出るのに、夜になって耳主が眠るのを待っていたものですよ。ええ、相手が眠ってしまうともうこっちのものです。起こさないようにそっと耳主から出て、家じゅうを荒らしまわることだって朝飯前ですよ。実際にそれを
まあ、自分で言うのもなんですが、私もいまではもうこの道の
そう言えば、鈴木が結局どうなったのかをまだ話していませんでしたね。ひょっとしてあなたは私が鈴木を殺したと思ってはいませんか? いやいや、殺してはいませんよ。いや、どうでしょうね。私は彼を殺してしまったんでしょうかね。実を言うと、ずっと考えつづけているんです。彼がどうなってしまったのかを。まあ私の話を聞いてください。そしてあなたが判断をくだしてください。私が彼を殺してしまったのかどうか。
ある晩のことです。また鈴木が私の部屋を訪ねてきました。例によって、二人で酒を飲みながら、ぼそぼそと
私は夜中にはっと目を覚ましました。時計を見ると、明け方の四時になろうとしている。しかしあの夜はいたんです。鈴木がまだ私の部屋にいた。姿を消していなかった。私の横に、畳の上に、
「耳もぐりでいちばんやってはならないこと。それは自分の耳にもぐることだ。自分の耳に入り鍵を突っこむことだ」
もちろん私は
「さてね。知りたければ自分でやってみろ。それが嫌なら自分の爪先に喰らいついて、少しずつ全身を呑みこんでいくんだ。意地汚い
入り鍵をつくって眠りこける鈴木を見おろしたとき、何も自分で試すことはないのだと気づきました。誰かにやらせればいい。いや、こいつにやらせればいい。やはり一種の狂気に駆られていたのでしょうね。何かこう、思いついた
鈴木の右手は完璧な入り鍵をつくったまま何かの祈りのように胸に置かれていました。私はその手をそっと持ちあげ、息を殺し、少しずつ少しずつ彼の頭のほうへずらしていきました。緊張のあまり、どくりどくりと自分の鼓動が聞こえたほどです。途中で目を覚ましたら、鈴木はきっと私の企みに気づいたことでしょう。抜け目のない、ひどく察しのいい男でしたから。
しかし結論から言えば、私は成功しました。彼の右手の中指を彼の右耳に押しこんだ瞬間、鈴木はばかっと大きく目を見ひらきました。そして私を見あげ、「おまえ!」と声を発しました。いまでも私の頭蓋のなかを
ああ、あなたはこう考えていますね? 香坂百合子もまた同じようにして消えたのではないかと。私が彼女に耳もぐりを教え、私の
「連続してもぐってはならない。つまり一人の人間にもぐって、その肉体のまま別の人間にもぐるなってことだ」
どうなると思いますか? マトリョーシカ人形のように入れ子状に次々と耳もぐりをつないでゆく。一つの肉体にいくつもいくつも魂が入りこんでゆく。きっとそこらじゅうにいくつもハンドルのついた車に分別のかけらもない若者が大勢で乗りこむようなもので、さぞかし冷やひやすることでしょうね。さすがの私もそんな危なっかしい真似はしたことがありません。しかしそれに近いことならずっと続けてきましたよ。そこまで危なっかしくはないけれども、それに近いことを、若者のように性急にではなく、もっとゆっくりと四十年をかけて続けてきたんです。
そして三つ目のタブー。これが肝腎です。
「一人の人間に長くもぐるな。三日ももぐりつづけていると、だんだん混ざってくるぞ。自分と耳主の記憶が、感情が、何もかもが。そうなるともう、お前じゃなくなる。いや、お前でもあるが、結局は別の誰かだ。もう絶対に自分を引っぱり出せない。耳主の体はもうお前の体になってしまうんだ」
鈴木の言葉は完全に事実です。実を言うと、もぐった最初からその
しかしこれはある種の快楽なんです。いやそれどころか、人間精神が抱える根源的な快楽、もっとも人間らしい至高の快楽とすら言えるものなんです、他人と一つになるということは。中原さん、あなたは自分が自分でしかないことを
私が最初に溶けあってしまったのは一人の女でした。どこか堅い
しかしあるとき、夜道でばったり彼女に出くわしました。私は咄嗟に目を伏せそうになりましたが、彼女は、あ、と言って会釈してくれたんです。表情にこそ出しませんでしたが、喜びのあまり胸がとろけてゆくようでした。そして、もうこんな機会はないのではないか、この偶然の出会いはやれという徴ではないのか、そう思ったんです。となると、やはり我慢できませんでした。そのころにはもう何十回も耳もぐりを成功させていましたから、奥手の私もきっと大胆になっていたんでしょうね。チヨちゃんを呼び止め、出し抜けに耳に手を伸ばし、もぐってしまいました。そしてそのまま二日経ち、三日経ち、彼女の心が少しずつ染みとおってきたとき、もう出ていきたくない、このまま彼女と一つになりたい、そう思ったんです。誰かにもぐっていて、そんな気持ちになったのは初めてのことでした。もぐりすぎると自分が自分でなくなると鈴木から教わっていましたから、それまでは長くもぐってもせいぜい丸一日といったところでしたが、何日もかけて少しずつ彼女と溶けあってゆくのは、どんな快楽も遠く及ばないような比類なき経験でした。そして確かに私は別の人間として、まったく新しい両性具有の精神として生まれ変わったんです。しかし人間とはどこまでも足ることを知らないものですね、ひと月ほども経つと、精神に厚みを増した私は新たな肉体のなかでふたたび飢えを覚えはじめました。さらに新たな人間と融合したいという激しい飢えです。もう一度あの過程を経験したいという、ほかでは満たすことのできない飢えです。私はまた獲物を物色しはじめました。もはや、誰にもぐろうか、ではなく、誰と一つになろうか、と考えながら。そしていまここに至る私の長い遍歴が始まったんです。もぐっては溶けあい、もぐっては溶けあい、そのたびに肉体を変えつづけ、あたかも蛇が次から次へと脱皮をくりかえし、そのたびに精神のみが
私がいままで主に語ってきたのは、言ってみれば心の最下層に横たわっている、しがない旋盤工だった私の記憶です。いや、実際はいくらか間違っているかもしれませんね。『殺し屋、あるいは愛猫家』を映画館で見たのはまた別の私だったかもしれない。姫路で生まれたのも、物心つく以前に父親を失ったのも、本当は別の私だったかもしれない。奇妙に思われるかもしれませんが、いまとなってはこれがなかなか骨が折れるんですよ。たった一人の人間の記憶をほかから正確に
しかし私はなかなか優秀だとは思いませんか? いくらか正確さを欠くとは言え、四十年をかけて一つひとつ
最後になりますが、やはりあなたがわざわざ会いにきた二一三番目の私の話をすべきでしょうね。香坂百合子の隣人だった、この私の話を。もはやどうでもいいことかもしれませんが、二一三番目の私の名は
しかしあの日、香坂百合子を私が最後に目にした日ですが、私は私とベランダで初めてはっきりと言葉を交わしました。ああ、何だか話しているうちにひどく混乱してきました。こういうことがいまでもときどき特にもぐったばかりのころに起こるんです。自分の意識が波打ちながらもつれていくとでも言いましょうか、もつれながらずれていくとでも言いましょうか、ずれながら散らばっていくとでも言おうか、何しろいまやどちらも私でありすべては私なんですから私は。ああ、すでに私だった私は手すりから身を乗り出し、猫を抱いた私に手招きしました。私は思いがけない私の大胆な行動にぎょっとしたんだ。手招きした私は猫を抱いた私にわざと小声で言うたんよ。猫を抱いた私はその言葉がよく聞きとれず、え? と言って私に顔を近づけた。私は私と薄い間仕切り越しにベランダで肩を寄せあったんです。あのときの私たちをどこかから見ていた人がいたとしたら、陳腐な恋愛ドラマのようにお隣さん同士で恋が芽生えつつあると
猫を抱いた私は突然の奇妙な宣言に戸惑ってしまい、思わず私に聞きかえしたんだ。「どうやって?」。普通なら玄関から訪ねてくるだろうと考えるところです。しかし頭にふと浮かんだのは、ベランダの手すりにあがって間仕切りを
ああ、ほら、当のアニエスが私たちのほうをまたじっと見ています。金目と銀目をこれ以上ないほどにぴんと張りつめて私たちを見ていますよ。六年もともに暮らした主人がふっと姿を消したかと思うと、今度は見知らぬ男が主人のソファに居座って、ぶつぶつと独り言を言いつづける。それがよっぽど不気味なんやろな。
しかし中原さん、先ほどは大変失礼いたしました。部屋に招き入れるなり、突然あなたの耳に指を突き立てるような真似をして。私が自分の耳のほうへ姿を消したのを見て、さぞかし驚いたことだろうね。ああ、本当のことを言うと、あなたの耳にもぐるのではなく、まずあなたを抱きしめたかったんよ。香坂百合子として、あなたをきつく抱きしめたかったんよ。しかし私が、この私こそが香坂百合子なんだと、この私こそがあなたの捜している私なんだと、そう主張してもあなたは決して信じなかっただろうね。だからこれは必要なことだったんです。やむを得ないことやったんです。こうでもせんかったら、あなたは耳もぐりの話なんか狂人のたわ言と一蹴したに違いありませんから。でもこうなってしまうと、あなたは受け入れざるを得ない。どんな気分やろ? こうやって何者かがあなたの肉体を支配し、あなたの口を使って長々と話しつづけるんは。初めは恐ろしいことやろうね。私もときどき思い出すんだよ。初めて鈴木にもぐられたときのことを。初めて私にもぐられた、たくさんの驚愕の瞬間のことを。
そう言えば、いつのころからかふと思うようになったんよ。鈴木もまたいまの私のような存在やったんかもしれんと。いくつもの人間精神を太ぶとと束ねた巨樹のような存在やったんかもしれんと。それを私が殺してしもたんかもしれん。消してしもたんかもしれん。鈴木一人ではなく、何十人も何百人もの人間を同時に消してしもたんかもしれん。そう思うと、さすがの私も胸がきりきりと痛むんよ。いや、もちろんわかりませんよ。これはただの想像に過ぎへんから。でもそれが事実やったとしたら、彼らはいったいどうなってしもたんやろ? それを考えはじめると、いつも思い浮かぶんよ。映画のなかでルイ・カリエール
ああ中原さん、光太君怯えんといてくれ私は消えるつもりもないしあんたを傷つけるつもりもないんだから、それどころかあんたはこれから素晴らしい経験をするんだあなたはこれから私と出会う私のなかの香坂百合子とも出会う二一三の私と出会うそしてあなたは二一四番目の私となる、ああ光太君ほんまに会いたかったずっと会いたかったでもこれで私たちずっと一緒になれるんよ光太君に早く教えたりたいねんこれがどんなに素晴らしいことかでも教えられない言葉では絶対に教えられないんだよだから感じてほしいこれから起こることのすべてを隅から隅まで心の