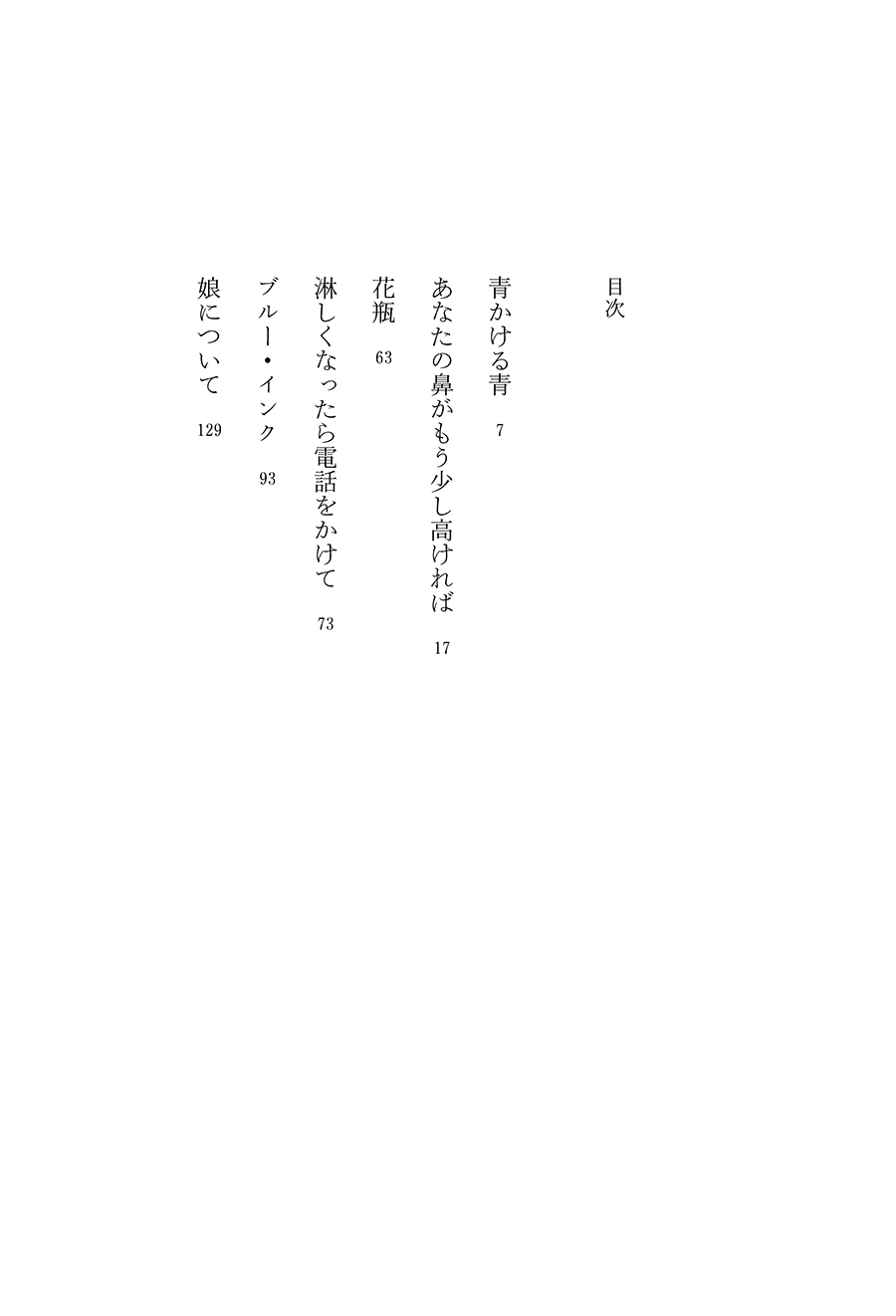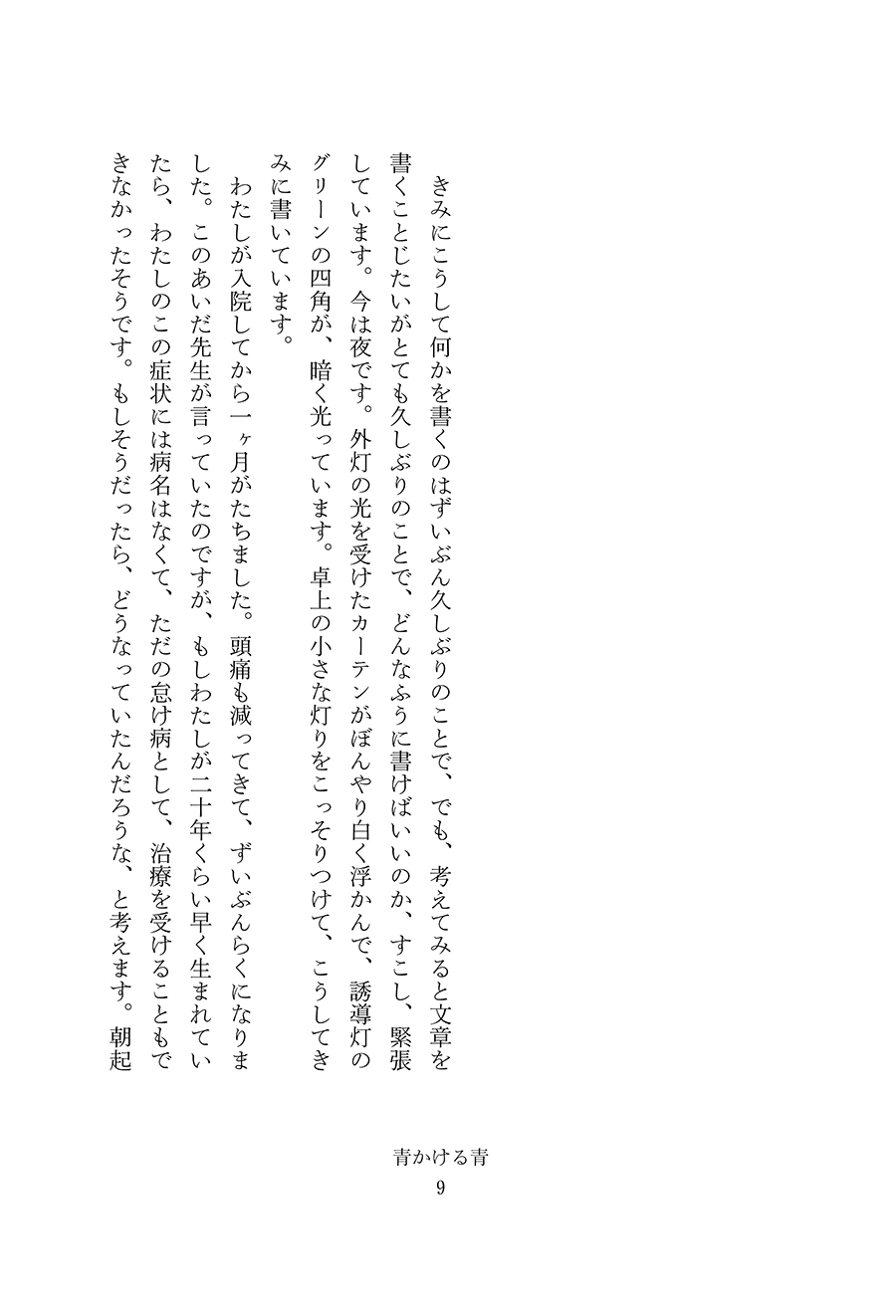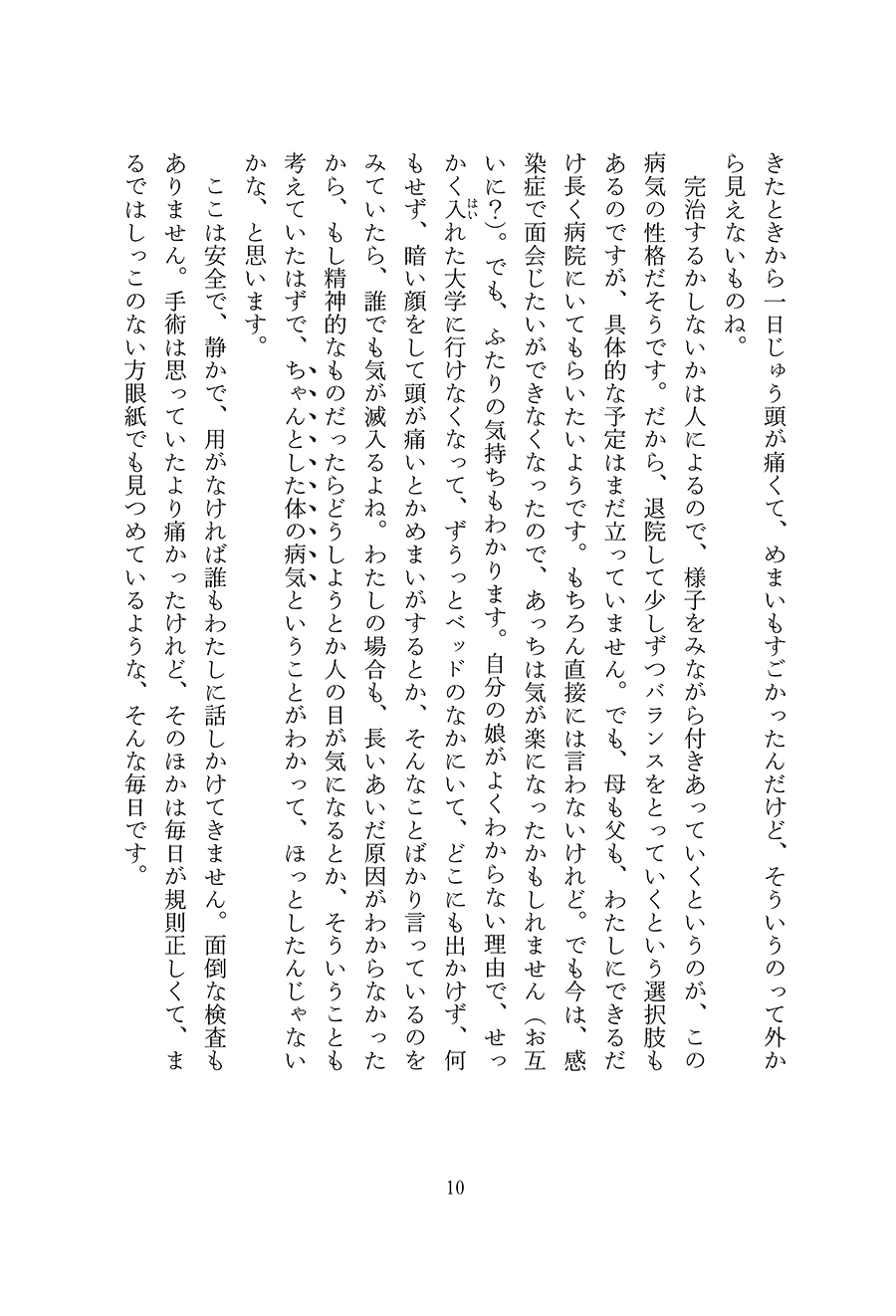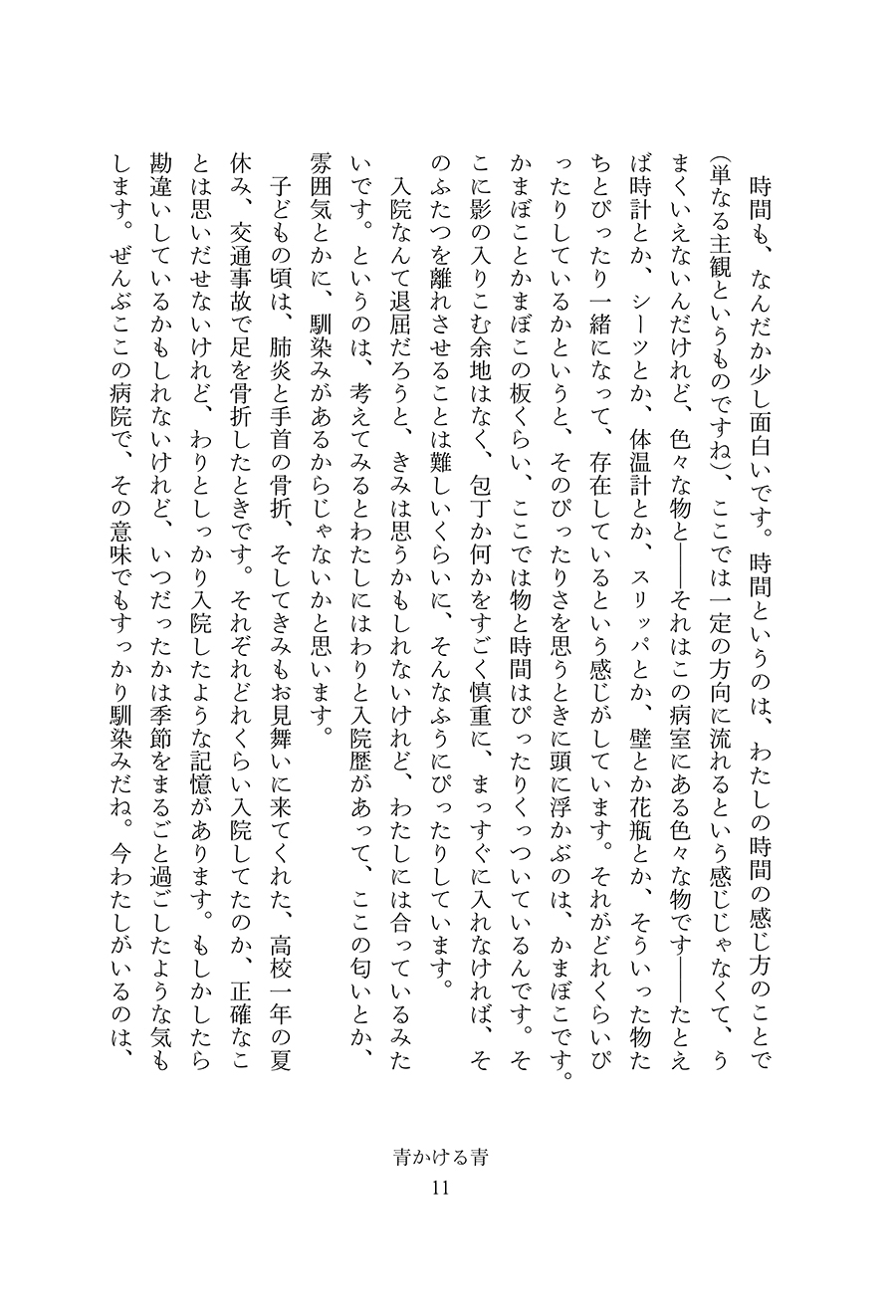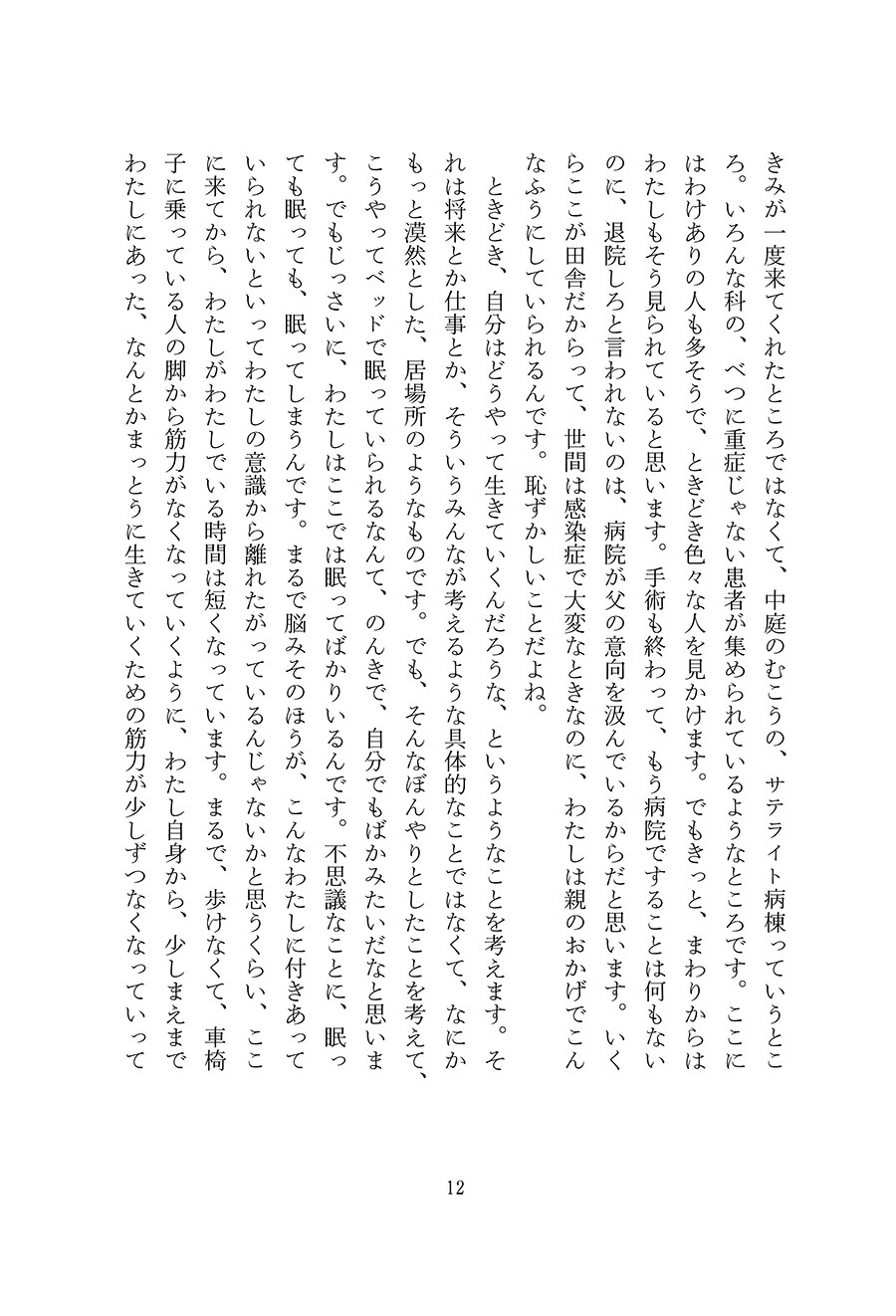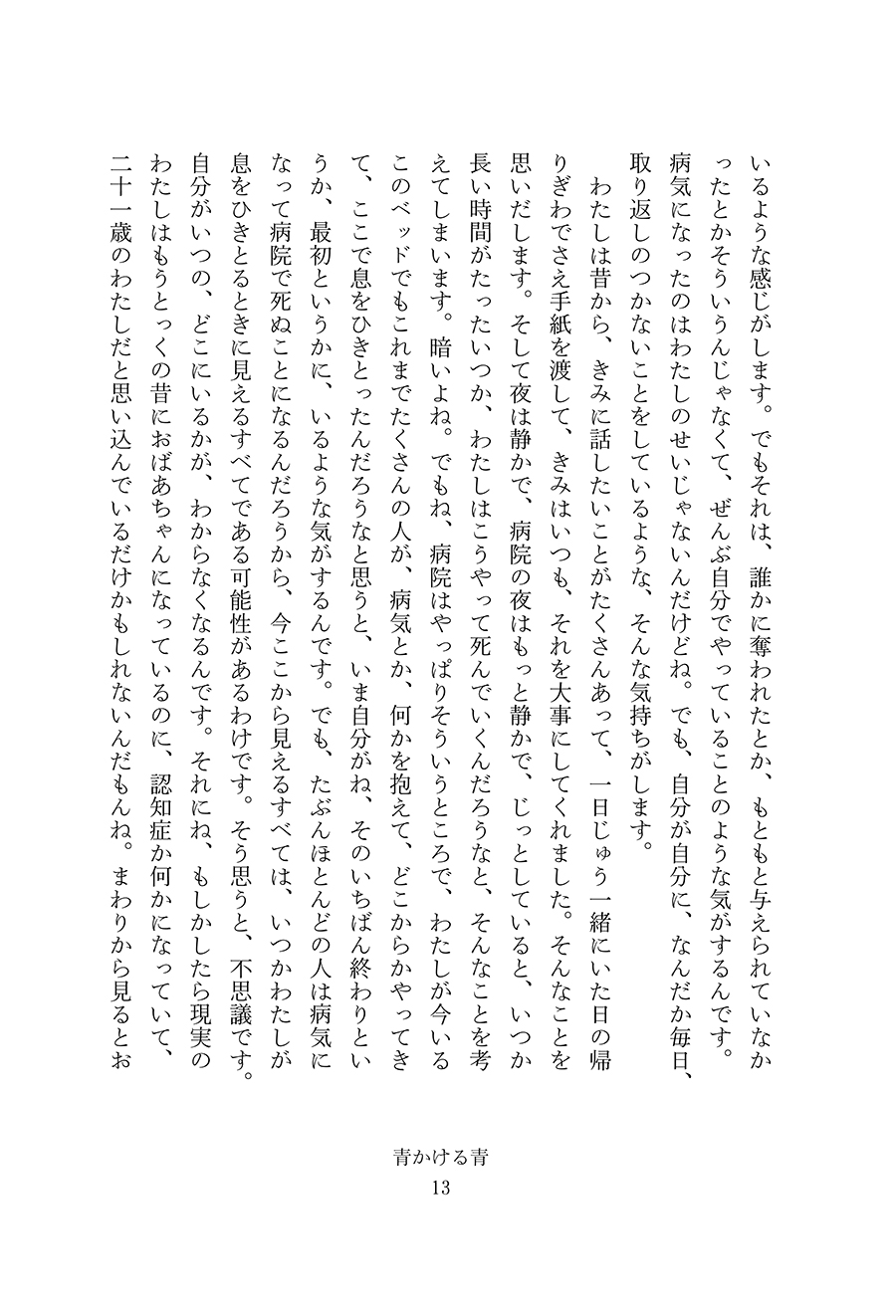あなたの鼻がもう少し高ければ
誰にも頼まれてなどいないのに、あるいは自分で自分に課しているわけでもないのに、感想というのは常にやってくるからしんどいものだ。
何かを食べてなにこれうまい。関係のない誰かの噂を仕入れて、信じらんない馬鹿じゃないの。ぱんぱんにむくんだ自分の脚をみてまじ終わってんなこれ。デパコスの新色をタップして最高すぎる。トヨを出入りする感想はいたって単純で、通過したあと大した痕は残さないけれど、何しろ量が多いので、自分でも気づかないうちに通路はみるみるすり減って、しかしどこに修理を頼めばいいのか、いつまでもつのかわからない。
朝、目をひらくと同時にトヨはスマートフォンでSNSをひらき、メンションとダイレクトメッセージをチェックして、フォローしているアカウントを巡回する。
気合の入っている写真がアップされていたら「天才♡可愛い♡顔面国宝♡」「ベリ可愛! 優勝! 似合い散らかしすぎだから!」みたいなことをえんえんリプライしてからライクボタンを押し、うっざ馬鹿じゃねありえないから、と知らない相手からのメンションに悪態をつきながら、布団のなかの時間はいいな、と思う。温かいし、動かないでいいし、一生ここから出たくないな。トヨはいつも心からそれを思う。
じゃあもう外に出なくていいように、死んでみるっていうのはどうか。
そんな考えがよぎらないこともないけれど、この心地よさを味わうことと、そこから出ることと死んでしまうということの関係がやっぱりさっぱりわからないし、すぐに面倒になって忘れてしまう。
それからゆっくり、モエシャンの、みっつのアカウントをチェックする。
モエシャンが何歳なのか、どこに住んでるのか、色々なことは謎。顔もいい感じに角度をつけて、ちらりとしか写さない。それだってきっと盛られてるだろうけど、まつげが長く、メイクが上手で、きれいな髪が印象的だ。そんなモエシャンには敵が多くて、彼女を面白く思わない、主に匿名アカウントが彼女についての色んな憶測をひんぱんに書き込んだりするけれど、ほんとのところはわからないし、モエシャンは相手にもしない。
トヨは、モエシャンのチームの女の子たちに憧れて、なんとか一員になってみたいその他大勢の女の子たちとおなじように、モエシャンのSNSのアカウントをフォローして、モエシャンがどんな一流店でどんな高級料理を食べて、どこのハイブランドで買い物をして、どんな服を着て、金持ちの男たちの金をどれくらい使ってどれくらい可愛い女の子たちと一緒に遊んでいるか、そうした情報を彼女の気まぐれなポストから摂取するだけ。
この二日間、つぶやきもないしストーリーズもあげてないし、取り巻きのアカウントにもどこにも登場していない。たぶんモエシャン、リアルが楽しすぎて忙しいんだろうなとトヨは思う。時計を見る。初めてモエシャンとその界隈の存在を知って半年。今日、じっさいに自分がモエシャンに会うのだと思うと、トヨのみぞおちはきゅうっと縮まり、死ぬほどどきどきする。いけんのかこれ。
でも、服もメイクも迷いに迷ってどれで行くかちゃんと決めたし、今さらびびってもしょうがない。トヨは自分を勇気づける。駅前にある評判のいい洋菓子店で手土産のフィナンシェ詰めあわせもちゃんと買って、用意してある。少し迷って五百円高いほうのセットにしたし、それにこの日のためにサラダチキンと冷奴だけを食べる生活を二週間つづけて体重をなんとか三キロ落として頑張った。見た目にもちょっとすっきりして、心なしかすっぴんの状態でも目が少し大きくなった気がする。じゃっかん達成感あるな……トヨは自分自身をからかうように鼓舞しようとするけれど、そんなことでは胸の底にはりついている緊張は剥がれず、無意識のうちに人指ゆびの爪で歯の隙間をひっきりなしに引っ掻いている。流れてきたアパレルの広告を反射的にタップする。セールか。こういうサイトあったんだ、なんかふつうにかわいくない? でもけっきょく骨格ストレートって限界あるんだよ、こういうフレア系とか全滅すぎて笑えるよな。まじ骨格ウェーブで優勝したい。だいたいなんでわたしはブルベ冬として生まれてこなかった人生なのか。どうでもいいけど黄色すぎるから顔。そんなふうに何秒間かがっかりして、またべつのページに飛ぶ。
学校は休校。授業はオンラインになるとかどうとか。田舎の親が学校に行かないぶんの授業料は返ってくるのか、そういう話はないのかと訊いてくる。知らないし、まだわからない、と答えても、少しするとまたおなじことを、おなじように訊いてくる。ひょっとしてこれがぼけの前兆なのかと思うとわりと切ない。年齢的にはまだ早いとは思うけど。それに戻ってくるかもしれない娘の学費を当てにしたいくらいにはうちってやっぱり金がないんだなと思うと、わかってはいても、なんともしょっぱい気持ちになる。そんな陰りを打ち消すように、トヨはスマートフォンの画面をスクロールしつづける。
関東近郊のしいたけ農家で生まれ育って、都内のなんてことない大学に進学したトヨの日常には、目立った困難も不満もとくになかった。けれどトヨには、昔からどうも何かを謳歌するということが、うまくできないところがあった。
それがはっきりしたのは思春期のころ。
いつからか彼女をじっと監視している視線の存在に気がついて、それ以来、トヨがちょっとでも浮かれたり、楽しいな、などと思ってうっかり心を弾ませるようなことがあると、それは即座に「身の程を知れ」と警告するようになったのだ。その視線がどこからやってきたのか、トヨにはわからない。けれど、鏡に映る自分の顔を見たり、仲の良い女の子たちと一緒に撮られた写真を見たり、布団の中で一日の出来事のあれこれをふりかえり、たとえば男子たちが自分にとった態度や無関心や表情なんかをふと思いだしたりするときに、その視線は一段と強く、鋭くトヨを睨みつけるような気がした。
トヨは美人というわけではなかったけれど、べつに醜いわけでもなかった。
ただ、圧倒的に人の印象に残らない顔というか、その雰囲気も含めて、人の明るい感情や、また会いたいな、みたいな、そういうポジティブなあれこれをほとんど喚起させない、そういう感じの顔をしていた。
ただ普通にしているだけなのに、親や友達から、どうしたの? 退屈なの? 怒ってるの? と訊かれつづけて、そんなことないよという正直な反応も、言い訳やある種の拗ねとして受けとられてゆくスパイラル。トヨに「身の程を知れ」と警告してくる視線と、そうした自分の容姿は何かしら密接な関係にあるのではないかとトヨは感じていた。
かといって、トヨは自分にまったく自信がないわけではなかった。というより、ふつふつとした野心すら秘めていると言ってもいいくらいで、トヨは自分の髪が美しいことを知っていたし、額の形を気に入っていたし、並行二重ではないけれど、いい感じに垂れた目には、ほんの少しだけ自信があった。
ただ上顎、上の歯茎が少し前に出ており、横から見ると口がもっさり厚くみえるのが嫌いだった。顎はふつうの角度なのでバランス的にはそんなに悪目立ちはしないけれど、鏡で横顔をチェックするたびに、自分の口元が美人の条件であるEラインからは程遠いことを思い知らされてがっくりきた。額も目も、パーツじたいは致命的という感じはしないのに、全体で見るとなんでこんな感じになるんだろう。なんでわたしは、ぱっとしないんだろう。自分自身が生まれてこのかた地味で凡庸な存在であると見られつづけていることに、トヨは慢性的な苛立ちを感じていた。
自分の本当の力を発揮することができる舞台はすでにいくつも存在しているのに、そこに行けないもどかしさ。
そして、本来の能力を発揮した自分を称賛してくれる人々はじつはもうたくさんいるっていうのに、そんな素敵なみんなにまだ出会うことのできない孤独な焦り。
自分という存在が、何かをじっと待機している状態そのものであるような、トヨはそんな感覚がずっとぬぐえなかった。小気味良い音をたてて何かがかちっと噛みあいさえすれば、オセロがずらっと裏返るみたいに、すべてが変わる気がするんだよなあ。それはたぶんちょっとしたことなのだ。わたしという存在を、もっと、くっきりさせなければ。早く本当の自分を発揮して、みんなのいるあの場所に行かなければ。ぎりぎりいっぱいに開かれたトヨの目は、常にスマートフォンに張りついていた。
そんなわけで、焦りと鬱屈が交互にやってきては少しずつ幅を利かせてゆく実生活もそこそこに、トヨはこの一年ほどSNSの美容アカウント、整形アカウントに入り浸るようになっていた。
整形手術が、ある種の惨めさとともに見世物であった時代は終わり、女の子たちの術後、術前の写真のせきららな公開や、ダウンタイムに耐える姿と詳細なレポートは輝かしい戦歴の証、そのものになった。トヨにとっては眩しさそのもの。理想の首根をつかんだら最後、文字通りの満身創痍で正々堂々とおのれと戦い、そして血まみれの勝利を手にして快哉を叫ぶ姿は憧れだった。
トヨは、そんな彼女たちにみるみる夢中になった。これだ。わたしが本当のわたしになるためにまず必要なのは、これなのだ。そんな彼女たちのサバイブと、それを可能にしている金の流れを目を赤くしながら追っているうちに、自然にモエシャンに辿り着いたのだった。
そう、整形と美容には、とにかく金がかかる。
自分とそう年の変わらない女の子たちが、どうやってそんな大金を工面しているのか、いちばんの疑問はそれだった。女の子たちの日々をつぶさに観察していると、背景は女の子の数だけあるにしても、そこにはいくつかのパターンがあるようだった。
まず実家が太い子。そして風俗などで稼いでいる子。それから水商売をしている子。あとは男と会って食事したりカラオケをしたりすることでお小遣いをもらうというようなことをしている子。ほかには、それのパーティーヴァージョンという感じで、ギャランティが発生する金まわりのいい飲み会で稼いでいる子たち。
モエシャンはそうしたことを希望する男たちに、女の子たちを適材適所、大量に紹介する元締めとして存在していた。そして、悪びれることなく自分のその斡旋業のことをSNSで公開していて、とにかく言葉遣いが辛辣なことでも有名だった。
「わたしに話しかけていいのは美人だけ」とか「ブスは貧乏のもと」だとか「金と顔と若さと人脈だけが女の人生を決める」みたいなことを言って憚らなかった。
彼女に群がるようにそれらを謳歌している女の子たちは、まるでモエシャンの価値観をそのまま体現しているかのように、みな若くて美しい艶に満ち、自分たちが参加したパーティーや飲み会の様子や、銀座や麻布なんかのミシュラン星つきのどこかで食べた何かとか、男に買ってもらったバッグや時計なんかを、堂々とアップしつづけていた。
整形していることを隠さずシェアする女の子たちにはトヨも慣れてはいたけれど、知らない男たちに――彼女たちがいったいどこまでのことをしているのかは実際にはわからないけれど、それでも一応、そうした男たちに媚び、いわゆる自分自身の一部を切り売りする的な行為全般にいっさいの後ろめたさを感じていない、モエシャンとそのまわりの女の子たちの様子に、トヨは鋭いノミか何かを前頭葉にカッと突きたてられたような衝撃を受けた。
そして何より、
〈心じゃない。顔と向きあえ〉
モエシャンのアカウントのプロフィール欄にただひとこと書かれてあったその文句に、トヨは痺れた。
トヨの大学のリアルの友達や知りあいは、最近は口をひらけば多様性とか自尊心とか、ルッキズムに反対しますとか、そんなことばかりを口にするようになっていた。人にはそれぞれの良さがあり、それは他人に決められるものではない。自分の価値は、自分で決める。トヨのリアルの友達がそういう感じのことを得意げに言ったりSNSに書き込んでいたりするのを目にするたびに、トヨは白けた。
だって、そんなの嘘じゃん。トヨはシンプルにそう思った。彼女たちの話をそのまま真に受ければ、ブスも美人も、この世界には存在しないことになる。
でも普通に考えて、そんなことはありえない。じっさいに、美人はいるしブスもいる。そんなの当たり前の話だった。自分で決められる価値もそりゃあるにはあるだろうけど、同時に他人が決める価値も、あるに決まってるじゃんか。得をするのはいつも美人で、損をするのはブスなのだ。だいたい美醜が個人の気の持ちようなんかでどうにかなるとか、本気で思ってんのかな。思いとか気合とかで、なんとかなるとか? もしそうなら、モデルとか芸能人とかどういう理由で成立するわけ? みんな何に金を払っているわけ? 美しさとかきれいさっていうのは、例えば、しあわせとか愛とかそういうなんかふわふわした適当なものとは根本的に違うんだよ。美っていうのは、どうしたってはっきりしていて、ぜったいに見間違えようのないものなんだから――ってま、あの子たちも、本当はわかってるんだろうけど。
そっち側にはなりたくないな、とトヨは思った。ただの弱さが、なんか気づき、みたいになってるのも気持ち悪いし、誰も傷つけない自分はえらいと信じることで自分を慰めるしかないような、そういうのはきっついな、と思った。
それに比べてモエシャンはどうよ。モエシャンは強い。嫌われることを恐れない。人の顔色を見ない。モエシャンは逞しい。自分の価値観を信じて突き進んで、モエシャンは今を生きている。そして何より、モエシャンは真実を言っている――こうしてトヨは、モエシャンとその仲間たちに心酔するようになっていった。
ある日、モエシャンが、
「今から二時間だけDMあけるんで、楽して稼ぎたい美人は写真を送ってくださーい。早いものガチ」
と書き込んだ。
モエシャンの本拠地は港区で、そこでは毎晩のように選りすぐりの一軍女子だけを集めた羽振りのいいパーティーが繰り広げられていた。
金持ちだけでなく、ときにはスポーツ選手や男性アイドルなんかも参加して夢のような時間を過ごしているというような匂わせポストもあったりして、モエシャンのチームに属したい女の子たち、あんなふうに楽しみながら稼ぎたい女の子たち、なんだかよくわからないけどちやほやされたい女の子たちが、年がら年じゅう色めきたっており、そんななかでかけられた、まさかの募集だった。
きた、とトヨは胸の中で叫び、心臓がどきどき音を立てた。
ものすごく迷ったけれど、駄目もとの勢いでダイレクトメッセージを送ってみた。するとすぐに募集受付専用ラインのアカウントが送られてきて、そっちに写真を送ってこいという。トヨは一瞬ひるんだけれど、これはわたしがくっきりするための、きれいに一皮むけるためのチャンスなんだと言い聞かせて、数ヶ月前にものすごい時間をかけて自撮りした奇跡の一枚に、さらにアプリの技術のすべてを投入して加工したものを、思い切って送信した。翌日、ライン審査をパスしたので、二週間後に渋谷に来いという返信があった。モエシャンが面接するという。それが今日というわけだった。
♡
指定されたのは渋谷のセルリアンホテル。名前を聞いたことはあったけれど、じっさいに行くのは初めてだった。渋谷駅に着いて、巨大な歩道橋を渡って数百メートル歩いたところに、その大きなホテルはあった。
空気は生ぬるくて、まっすぐ歩いてるだけなのに、なんか体がふわふわする。
三キロ痩せるとこんな感じなのか。それにまだ三月になったばっかで春なのになんかもう夏みたいじゃない? そう思うと腋にじわりと汗がにじんで、汗止めのジェルを塗り忘れてきたことに気がついて、トヨは心の中で舌打ちした。今日のはぜったい臭う汗だ。いやだなあ、っていうか、なんで臭う汗と、そうじゃない汗があるんだろ。臭うときと、臭わないときっていうか。食べ物? 体調? わかんない。そのへんのドラッグストアで汗止めを買って塗ったほうがいいんじゃないかといっしゅん迷ったけれど、来た道を戻ってもう一度あの巨大歩道橋を往復することを思うと億劫になって、もういっか、とため息をついた。久しぶりに履く厚底のローファーはすでにトヨの足を痛めつけており、こっちじゃないほう、べつのヒールを履いてきたほうがよかったかもと後悔した。そうすると、そもそもスカートともブラウスとも合ってないような気がし始めて、トヨはがぜん不安になった。ネットのセールで四千円、売れ筋ナンバーワンの、小さな金具のついた厚底ローファー。
そのとき、向こうから歩いてきた二十代くらいの女とすれ違いざまに目が合って、軽く睨まれたような気がした。早足で、細くて、顔が小さくて派手めな女だったから馬鹿にされたのかとトヨは思ったけれど、もしかしたら自分がマスクをつけてなかったからかもしれないと思い直した。
行き交う人々を見ると、マスクをつけている人とつけていない人の割合は半々という感じだった。この一ヶ月くらいテレビは感染症のことしかやっていないけど、やっぱたいしたことないのかもな、とトヨは思った。気温が上がったら自然消滅するって、どっかの偉い学者だか医者だかも言ってたしな。
こんなに騒いでも結局べつに何も変わらないんだな。そう思うと、頻繁に電話をかけてきては学費のことを何度も尋ねたり、感染におびえて暮らしている実家の祖母や母親や父親のことが頭に浮かんで、なんだか哀れに思えるのだった。知らないってのは損なことなんだな。ちゃんとした情報にありつけないっていうのは。負けつづけるっていうかさあ。狭い世界で取り残されていくっていうか。べつに感染症のことだけじゃなくて、生きていればなんでも。
ホテルは大きく、色んなところから人や車が出入りしていて、いったいどこからどう行って中に入ればいいのかトヨにはわからなかった。十秒くらいそうした人の行き来を観察すると、多くの人たちが外付けのエスカレーターに乗って移動していたので、トヨもその後についていくことにした。
エスカレーターを降りて、すぐ前を歩いている人とおなじ方向に進んでいくとホテルの内部に入り、そこがロビーになっているようだった。
人は多くもなく少なくもないといった感じで、きちんとしたスーツに硬そうな四角い鞄を持った男たちや、女も身なりのいい人が多く、カジュアルな格好をしているのは外国人だけで、そういえばあっちにもこっちにも外国人がいる。吹き抜けというのか天井というのか、壁も窓も何もかもが高くて大きくつるつるしており、むこうに見える階段も、目のまえにそびえている柱もなんだか当たり前に巨大って感じで、少なくない数の客がいるのに静かで、トヨがこれまで泊まったことのあるホテルとはレベルが違うように感じられて気後れがした。そして、こんな高級な感じのするところで女の子たちを面接するなんて、モエシャンはさすがだと思った。
約束の時間の午後二時まで、あと十五分あった。
トヨはきょろきょろしながらトイレのほうへ歩いていった。廊下の途中に雑貨店があり、ただでさえ光り輝いているガラスケースの飾り棚に、まるでグリッターフィルターをかけたみたいなアクセサリーや小物入れなんかが並べられていた。顔を近づけて値段を見ると、小さな髪留めが二万五千円とあった。
広々した石造り調のトイレはひんやりとし、手前のパウダールームの一番奥に女がひとり、座っているのが見えた。トヨは用を足したあと入って行き、ひとつ空けて又隣の席に腰を下ろした。鏡越しに見えた女の顔にトヨはぎょっとした。メイクがどうとかそういうレベルではなく、ひと目で整形であるとわかりすぎる感じの圧が凄かったのだ。トヨは日頃ネットで整形アカウントに慣れ親しんでいる自分はそういったことについてよく知っていると思い込んでいたのだけれど、考えてみればここまで気合の入った人物にリアルで会うというかお目にかかるというか、間近で目撃するのは、じっさい初めてなことに気づかされた。
両目とも、二重切開にプラス目頭プラス涙袋形成、鼻はプロテーゼと小鼻縮小、鼻先をクリップでつままれたようになっており、額はヒアルロン酸か脂肪注入でこんもりと盛りあがり、これが噂のコブダイか……とトヨは内心でどきどきした。フィラーの入れすぎで上下ともはちきれんばかりに膨らんだ唇は、まるで小人の尻のようだった。
じろじろ見ては失礼だとわかっていても、それぞれのパーツと、それが合わさったときに奏でるインパクトがすごすぎた。目も鼻も唇もすべてが飛びだす絵本の部品のようで、どこにピントを合わせていいのかわからないというか、逆に全部にピントが合っていてどこを見ていいのか、わからないというか。頭では駄目だとわかっているのに、メイク直しをしながらトヨはどうしても女のほうをちらちら意識してしまうのだった。
そうか、誰かが書いていたとおり、切開二重と目頭切開を同時にやるのはやっぱまずいんだなとか、蒙古ひだなしはいくら高さを後づけしても、日本人の基本的な平らな鼻筋とは食い合わせが悪いっていうのは本当なんだなとか、もしかしたらヒアルだけじゃなくて唇はM字形成してるのかもしれないなとか、鼻でも目でもやっぱり自前パーツはぜったいにひとつは残しておかなきゃいけないってのは間違いないなとか、頼まれてもいない答え合わせをしながら、鼻に浮いた脂をパウダーでおさえ、アイシャドウの締め色を目尻に重ねた。マスカラを塗り直しているとき、メイク直しを終えた女が席を立って、出て行った。黒い、フレアスカートのミニのちょっと透け感のあるワンピースで、年齢はわからなかった。
モエシャンが待つ部屋は、三二〇五号室。
菓子折りの入った黄色の紙袋をしっかりと握りしめ、トヨはパウダールームを出て歩きだした。初めての人に会うときは手土産を持っていくといい――それは田舎の母の教えだった。悪い気持ちになる人はいないから、というのがその理由で、こういう機会はほとんどないけれど、でも、トヨはこうした気遣いのできるわたしってちょっといいよね、と感じているところがあった。向こうから笑顔でやってきたホテルの制服姿の女性従業員に、三十二階の部屋に行きたい旨を伝えたら、親切にエレベーターホールまで連れていってくれた。トヨはぐっと明るい気持ちになって、弾むような気持ちで、素敵なホテルですね、と声をかけてみた。ありがとうございます、と従業員も優しく返事をした。
ホールに着くと、さっきパウダールームにいた女の姿が見えた。
従業員が笑顔で去ったあと、ちん、と涼しい音を立ててやってきたエレベーターに、女、トヨの順に乗り込んだ。女は黙って三十二階のボタンを押した。それを見たトヨは思わず声を出してしまうところだった。内なる驚きが伝わったのか、女もちらりとトヨを見た。っていうか、もしかしてこの人もモエシャンの面接とか? こんなに階数あるのにおなじ三十二階って、そういうことでしかなくない? まじで? ふたりはなんとも言えない沈黙とともに吸い上げられるように高層階に向かって上昇し、トヨの鼓膜はぷつんと小さな音を立てた。
三十二階に着くと、なんとなくお互いを気にしながら微妙な距離を保ちつつ、長い廊下を歩いていった。ドアの前でふたりは並ぶかっこうになり、そこで初めて目が合った。
近くで見ると、女の顔はさっき鏡越しに感じたものとは比べものにならないくらいの迫力に満ちていてトヨは面食らったけれど、女が少し微笑んだように見えたので、トヨも反射的に微笑んだ。女がベルを鳴らした。沈黙。十秒後にもう一度鳴らした。するとドアの向こうで人がこちらに移動してくる気配がし、がちゃりとドアが開いた。
「入ってー」
出てきたのはモエシャンではない女だった。
けれどトヨには、それがモエシャンの側近中の側近であるチャンリイであることがひと目でわかった。
チャンリイはインスタで見るより小柄で、目が倍くらいに大きく、全体に華奢で、そして何より目に飛び込んできたのは、そのめちゃくちゃな可愛さだった。
チャンリイは水色のふわふわした袖長ニットみたいなのを着て、白っぽいジーンズを合わせていた。死ぬほど脚が細いと思った。色素薄い系のメイクにブルーグレーのカラコンがきれいだった。というか、黒目の部分に反射する光のかけらの数が、人より多い気がする。それに肌が完璧にブルベ冬で、色んなところをいじってはいるはずなんだけれど、どれもやりすぎず盛りすぎずで自然だった。完璧だった。トヨの鼓動は激しく脈打ち、顔が赤くなるのがわかった。
女が先に入って、トヨが後につづいた。そのとき、トヨの胸がさっと陰った。自分はいまこのパウダールームの女とたまたま一緒にぐうぜん部屋に入ることになったけど、なんていうか、知りあいとか友達って感じに、思われたりしないよね? これが偶然だってこと、チャンリイちゃんとわかるよね……?
いや、うん、わかるはず。だって面接の受付っていうか、申込みは別なんだし、だいじょうぶだよね……そんな不安を打ち消しながら女の後ろ姿を見つめ、その足元に目をやったとき――女が、トヨの履いているのとおなじような厚底ローファーを履いていることに気がついた。
まじかよ。トヨは限界まで目を見ひらいてそれを見た。濃い茶色。ごつごつして、透け感のある黒のワンピとぜんぜん合ってない。いや、そんなことよりこれ、似てるんじゃなくて、ひょっとしておなじ靴なんじゃないの……? 金具、金具のところを見ればわかる、いや、でもこれって現実に、おなじじゃなくてもおなじっぽく見える、ってことがこの場合は問題で、この感じ、面接におそろいの靴を履いてきてる感じのこれ、チャンリイにいったいどう見えるの? センスおなじ感じにみえる感じなの?
何をどう考えればいいのか、トヨの頭の中はまだらに白くなった。
こっちでーす、というチャンリイの声にはっとして顔をあげると、一面に張り巡らされた大きなガラス窓のむこうに、東京の街が白っぽく霞んで見えた。手前に応接セットのあるリビング的なところがあり、その左奥に寝室部分がつづいているようで、べつの女の笑い声が聞こえてきた。電話で誰かと喋っているみたい。あの声は動画で何回も聞いたことのあるモエシャンだ、トヨはそう直感して耳がボッと熱くなった。
「すわってー」
チャンリイに促されるまま、トヨと女はソファに並んで腰かけた。
チャンリイは、ゆるく巻かれた金髪に近い、けれど全体に艶のある髪を何度もかきあげながらにっこり笑った。その仕草を見つめながら、トヨも無意識につられて自分の髪を触っていた。部屋は見事に散らかっていた。飲みかけのペットボトルとかグラスとか、皺だらけのショッパーや、床に丸められたバスタオルなんかが目についた。面接のためっていうより、普通に何日もここに泊まってるのだろうか。チャンリイはスマートフォンに目をやったまま独りごとを言いつつ、ふたりの向かいに座った。
「――えっと、どっちがマリリンちゃん?」
「わたしです。マリリンです」
女がいきなり、元気いっぱいの声で返事をした。その声のあまりの威勢の良さ、場違いな大きさと張りにトヨは驚き、思わず中腰になってしまい、あわてて座り直した。自分が空気を読まずに大声を出したわけでもないのに、何かとんでもない失敗をしでかしてしまったように、心臓がばくばくと連打した。
チャンリイは女の顔を二秒ほど凝視し、眼球を三ミリほど上下に動かすと口元だけで笑顔をつくり、無視することを決めたようだった。
「じゃ、そっちルナちゃん?」
「はい」
トヨは控えめに返事をした。
トヨの本名は登る世と書いてトヨと読む、まあまあ古風な名前だった。トヨが五歳のときに死んだ母方の祖父が「女だけどこれから世の中は変わるだろうし、出世するように」とつけてくれたものだった。その祖父心を知ってか知らずか、子どもの頃の
「ええっとー」
チャンリイが笑った。
「えっとー、ギャラ飲み希望なんだよね、うちにDMくれたってことは」
「はい」
普通に返事をしたら、女と――さっきマリリンと名乗った女と声が完璧に重なって、ユニゾンみたいになってしまった。
「えっとー」
チャンリイがまた笑った。
「えっとー、どこから何を言えばいいのかっていう」
せせら笑いのような表情でそう言うと、チャンリイはスマートフォンを触りだした。トヨはチャンリイが何か言うのをじっと待った。マリリンも黙ったまま、じっとチャンリイを見つめていた。でもチャンリイは、スマートフォンを持ったおなじ右手の親指で器用に画面をスクロールさせているだけで、つづきを話そうとはしなかった。半分ひらいた口から、ピアノの鍵盤みたいに真っ白な歯がみえていた。トヨとマリリンは黙ったまま、チャンリイがここにはいない誰かと、あるいはここには存在しない何かとやりとりしているのを見つめていた。チャンリイに案内されて部屋に入り、こうして彼女の目の前のソファに座っているのに、おかしなことにチャンリイはそのことにまるで気がついていないかのような、そんな感じがした。奥の部屋からも、まだ電話の話し声がつづいていた。
「あのー、ルナちゃんのほう」
しばらくして、チャンリイが画面に目をやったまま言った。
「ちなみに、整形ってしないんですかー」
えっ、と声が出て、トヨは打たれたように背筋を伸ばした。
「あっ、めちゃくちゃ興味はあります」
「どこ?」
「あっ、クリニックですか?」
「違う、顔のどこ?」
「あ」トヨは唇を舐めあわせた。「えと、理想っていうか、あの、それはあることはあるんですけど、まずクリニックに行って相談して、全体見てもらって、どこをするのがいいか一緒にまず決めるっていうか、そんなふうに考えてて……っていうのは、全体の費用感とかもあると思ってて」
「ふつう、それ終わってから来ない?」
「えっ」
「だから、来るなら、顔ちゃんとしてから、来てほしいんだけど」
チャンリイは目だけをちらっと動かしてトヨを見た。
「なんでブスのまま来てんの?」
トヨは、腹の奥のほうから恥ずかしさが熱の塊のようになって、体の内側をせりあがってくるのを感じた。
ここからは見えない、トヨ自身も見たことのないひだやおうとつや粘膜を、その熱がなめしながら覆っていくのを感じていた。これが胸を越えて首を通って頬や目のあたりに到達したら、そのまま顔面が爆発してしまうのではないかと思うくらいに、その恥ずかしさは熱かった。トヨは息を大きく吐いて、なんとか頭の中に浮かんだ言葉を繋げていった。
「えと、費用感っていうか、えっと、調べてはいるんですけど、かなりお金もかかるみたいで、そのために、えと、今回頑張らせてもらえたらいいなって、そんなふうに思って」
「いや、逆でしょそれ」
「えっ」
「それってさ、大学入る金がないから、まずグーグル入って稼ぎたーいとか言ってるのとおなじだよ。意味わかる?」
チャンリイは鼻で笑った。
「金がないなら借金するか、ブスでもできる仕事して稼いで、まず整形でしょ」
トヨはチャンリイの言葉に黙った。
「っていうか、それっきゃなくない? 芋ブスでも穴モテするとこ見つけてやるっきゃなくない? ぜんぶ順序が逆なんだよね。っていうかさ、クリニックで相談しますって、顔みたらどこやんなきゃいけないとか明らかだと思うんだけど? まず口ゴボ、それから鼻っしょ。そんなんわざわざ相談するまでもなくない?」
チャンリイは目の端っこをきれいにネイルされた小指で掻いた。
「インビザとかさ、なんでもあるじゃん、金ないなら、ないなりに。投資もしないで金稼ぎたいとかまじなくない? いるんだよなあ最近。ギャラ要らないから人脈つくれる場所に参加させてくださーいとか、金持ち紹介してくださーいとか言ってくるの。無理だっつうの。信用なくすし、ブスに人脈与えてうちらに何の得あると思ってるのかなあ? あんたの言ってることそれでしょ」
トヨはぴくりとも動かずに黙っていた。チャンリイの視界にすら入っていないマリリンも、膝のうえに手を載せたまま動かなかった。
「っていうか、ブスに来られると場が凍りつくの。ブスはトラブルのもとなの。っていうか写真がんばりすぎっしょ。盛ってるとかのレベルじゃないし。最近さあ、ほんと女の子から連絡すごく増えてて、ただでさえ忙しいのにさ、も、こういう営業妨害やめて?」
トヨは一言も言葉を返せず、ただ瞬きすることしかできなかった。
「はい、おつかれ」
チャンリイは髪をかきあげて立ち上がると、奥の部屋に入っていった。モエシャンはけっきょく、一度も姿を見せなかった。
♡
部屋を出たトヨとマリリンは、二十分まえとおなじようにエレベーターに乗り、薄暗い穴にでも吸い込まれるように下降していった。ちん、というやはりさっきとおなじように涼しい音がして扉がひらき、さきにトヨが、そしてマリリンの順で、ホールに出た。多くも少なくもない人々が談笑したり、歩いたり、誰かを待ったりしているロビーを横切り、なんとなく外に出た。湿っぽい、生暖かい風がぶわりと吹き抜けて、トヨは思わず目を細めた。
内臓が痛かった。いや、もちろん現実に内臓に損傷を受けたわけではなかったし、傷もあざもなかったけれど、しかしそうとしか言いようのないダメージを全身でひきずりながらトヨはふらふらとテラスを歩き、エスカレーターを目指した。吐く息が重く、つらく、体の重心をどこに預ければいいのかが、足を一歩踏みだすごとにわからなくなった。松葉杖とか、道でおばあちゃんとかが使ってるカートみたいなのが欲しいくらいだった。家にあるクイックルワイパーでもいい。体を支える何かが欲しい。
もたれかかるようにエスカレーターのてすりをつかみ、トヨは地上に運ばれていった。そしてベルトコンベアからどすんと落とされる荷物のようにアスファルトに降り立ち、ぽっくりぽっくり足を進めていると、ふいに視線を感じて、振り返った。
少し離れたところに、マリリンがいた。トヨとマリリンは何秒間か、見つめあう格好になった。トヨは、何か用ですか、とかなんとか言ってみようかと思ったけれど、その気力もなかった。
トヨは、自分とおなじ大きさ、重さのずだ袋をずるずる引きずるように歩き、なんとか巨大な歩道橋を乗り越えて、駅のほうへ進んでいった。階段とか、ちゃんと舗装された道を歩くのだけでもこんなにしんどいのに、登山とかわざわざする人ってすごいなとか、そんなことを思った。
山手線の渋谷駅南改札口は人で混雑しており、パスモの入っている財布を取りだしてはみたものの、あの人混みのなかに自分から入っていく気にはどうしてもなれなかった。よくわからないけど死ぬほど重いこの体と魂を、どこかで休ませないとやばい感じがする。トヨは横断歩道を渡って、雑多な飲食店が並ぶビルとビルのあいだの通りをゆき最初に目についたカフェに入った。
そんなに広くもない店は、がらがらだった。いい匂いなのかそうでもないのか、揚げ物とかルームフレグランスとかお香とかそういうのが混ざりあったような独特な匂いが充満していた。
顔が冗談みたいに小さくて、映えという映えが凝縮されたような、美しく若い女の店員がやってきて「お好きな席へどうぞ」と、無愛想ここに極まれりという具合で言った。トヨに一瞥もくれないその感じが、さらに美貌を引き立たせた。東京だよな、とトヨは力なく思った。こんなレベルの顔がごろごろしてる。美人であるだけで、その不機嫌も、わがままも、泣き言も失敗も、弱さも強さも、ぜんぶがそろって威光になる。ブスでは成立しないすべて。トヨは、沼にでも沈むようにソファに座って胸の中の息をぜんぶ吐きだした。少しして、がらんとドアの開く音がした。顔をあげると、逆光の中でマリリンが立っていた。細い光に縁どられたその影は軽く会釈のような動きをすると、トヨのほうへ歩いてきた。
トヨは生ビールを頼み、マリリンもおなじものを選んだ。きっちり三分後に、さっきの店員がこんもりとした泡を載せたグラスをふたつ持って戻ってきた。
トヨはグラスをにぎってかぶりつくようにビールを口に含んでから、喉に流し込んだ。苦味と冷気が胸の内側に一気に広がり、大きなため息をついた。
「やばかったですよね」
一息ついてから、トヨは自分でも独り言と見分けがつかない感じで言った。
「やばかったです」マリリンも言った。
「年って、訊いてもいいですか」トヨは言った。
「二十一です」
「おない年です……っていうか」
長い沈黙が流れ、トヨはもう一度、深いため息をついて言った。
「やばくなかったですか」
「やばかったです」
「マリリン……さんでいいんですかね。マリリンさん、こういう面接よく受けるんですか?」
「モエシャン界隈は、初めてです」
「なるほどです」
何がなるほどなのかトヨにもわからなかったけれど、そんなふうに相槌を打ちながら、もうひとくちビールをあおった。トヨには酒を飲む習慣はなかったし、弱いほうで、ソファに腰を下ろしてメニューにビールという文字を見るまで酒を飲もうとも思っていなかったけれど、冷えたビールは涙が出るほど美味しく感じられた。朝からまともに水も飲んでいなかったせいでトヨの血中アルコール濃度は急上昇し、額のうらにべったり張りついていたもやのようなものが、しゃきっと取り払われたような快感があった。
それからふたりは、それぞれスマートフォンを触った。
トヨは、チャンリイかモエシャンがさっきの面接のことを何かつぶやいたり、ストーリーズに上げていないかと思ってチェックしたけれど、何もなかった。ネットショップのダイレクトメールが何件か来ているだけで、ラインもなかった。ソファの毛羽立ちが太股の裏をちくちく刺激して、グラスのなかでは黄金色のビールが細かな気泡に揺れていて、その濃淡を見ていると自分が水の干上がった岩場にでも座っているような気持ちになった。
トヨはスマートフォンを触りながら、ちらちらと目をあげてマリリンの顔を見た。マリリンは普通にしててもびっくりしているような目を、何度もしばたたかせて画面に見入っていた。こうしてあらためて見ると、顔じゅうに何種類ものラメがぶつかるように飛び散っており、メイクのほうもすごかった。
でも、べつに長時間一緒にいるわけでもないのに、はじめてパウダールームでマリリンの顔を見たとき、そしてホテルの部屋の前で間近に見たときに受けた衝撃は不思議なことに薄らいでおり、さっきほどのどきどきは感じなくなっていた。
「……たいへんな女の子が、ふえてるから、ちょっと、たいへんになったのかも」
マリリンは困った顔で笑い、ビールをごくごく飲んだ。
「みんな、いま仕事がなくなってて……」
マリリンの話しかたは、ちょっとなんでなのかと思うくらい遅く、うーん、と相槌を打つときや、母音に、やわらかく間延びした独特の抑揚があった。顔は基本的に困ったような表情で、眉尻がぐんと下がって、ぶあつい唇が左右にきゅっと引っ張られ、濡れたような艶が表面をちらっと移動した。わたしはなんで今、このぜんぜん知らない子とビールを飲んでるんだろうとトヨはいっしゅん思ったけれど、しかしそのことじたいに嫌な感じはしなかった。とはいえ、ずっと緊張がつづいているせいでトヨの喉は飲んでも飲んでも潤わず、筒のような太いグラスになみなみと入っていたビールはすぐになくなった。マリリンのグラスもおなじタイミングで、空になった。ふたりはまたおなじものを注文して、それもまたすぐに空になった。
「酒飲めないと、そもそもギャラ飲みってきついですよね」
トヨは頭に浮かんだことをそのまま口にした。
「っていうか、わたし今すごく喉渇いてて一気にビールとか飲んでるけど、べつに強くないんですよね。っていうか、あんま飲めないし。さっきあそこで言われたのとべつの意味で、なんでおまえDMとか送ってんの、っていう。なにしに、っていう。なんか自分でも意味不明的な」
「いろんな子が、いるみたいだけど」
マリリンの声はどこか聞き覚えがあるというか、知ってる誰かの声に似ている気がしたけれど、それが誰なのかは思いだせなかった。
「でも、ブスはいないよね」
「うーん」
「っていうか、マリリンさんはメンタル削られないの。鬼スルーでしたけど」
トヨは訊いた。さっきホテルで、マリリンは名前を訊かれる以外はいっさい絡まれなかった。というか、名前だって、訊かれたというよりマリリンが勝手に名乗りをあげただけだ。あれこれ言われたのはわたしだけで、マリリンは彼女の目にまるで存在すらしないみたいな感じの扱いだった。あれはあれできついと思うんだけれど、そうでもないのか、どうなんだろう。
「削られは、あんまり……ないかなあ」
マリリンの整形にはかなりの金がかかってるはずだった。わたしとおない年なのに、いったいどうやって金を準備したんだろう。水商売なのか風俗か――トヨはネットで整形、美容アカウントを細かく追っているという自負から、彼女たちの生活や愚痴や交友や、人間関係に濃く触れているつもりで、色々なことに通じているような気になっていた。けれど、こうしてマリリンを目の前にすると、自分が現実的なことを何も知らないどころか、こういうときに適切な質問のひとつも思いつくことができなかった。水商売はともかく、風俗店で働いているかもしれないような友達も、マリリン級に整形をしている友人や知人だってひとりもおらず、これまでじっさいに会ったこともなければ話したことすらなかったのだ。
「……SNSとか見てると、頂き女子とかさ、キャバとかやりながらユーチューバーとかと絡んで、年商何億とかの社長もやってるとかって女の子、いるよね」トヨは言った。「あれ、ほんとだったら、なんか、すごいよね」
「すごい」
「でも、マリリンさんも、ちょっとすごい感じするけど」
「わたしは、べつに、すごくないよ」
マリリンのスマートフォンがブッと鳴って、それからまた、それぞれの画面に見入った。トヨは、インスタグラムで更新されているポストや、ストーリーズや、リールなんかを適当にスクロールしていった。
トヨのふだんの閲覧傾向から選ばれる関連動画や画像が次々に流れてくる。ぱんぱんに腫れたダウンタイム中の女の子の顔、TikTokの一問一答、ヴィトンのロゴいっぱいのセーターを着た女の子の笑顔、「顔短い女みると死にたくなる」、高級肉、三日したらすべての色が落ちてしまいそうな虹色にカラーリングされた髪、「しあわせに生きるために必要な20のこと」、「ブスな日本人
「マリリンさん、どういうの見てます?」
「わたしは、最近、骨のやつ、みてる」
「骨のやつ?」
「うーん。首の骨とかね、腰の骨とか、ぼきぼきやるの。ほねおと」
「あ、これっすかね」
トヨはインスタで検索して見つけたリールを見せた。
「あー、それー」
「うっわ、すごい音」
「はやってるの。いつか、やってもらえたら、いいなあって」
「でもこれ、今の時期、濃厚接触み、がんがんあるよね。でもマスクしてるからいけんのか」
「わたしも、いちおう持ってるよー、あんまりつけないけど」
マリリンは、ピンクのバッグからスヌーピーの柄のついたマスク入れを取りだして、トヨに見せた。
「スヌーピーじゃん、かわいい」
「かわいいー」
「でも、今どっこも売ってなくない? 買えた?」
「昔から、マスクは持ってるから」
「あー、ちゃんとしてる」
「うーん」
「あ、ここ、有名人も来てるね。うわ、すっごい鳴らされてる、えぐいね音。気持ちよさそう」
「これねえ、いっしゅんで顔がしゅって、小さくなるの」
「まじ」
「うーん」
ふたりは、いろんな美容整体師が、いろんな人の首や腰や背中の関節を、派手にぼきぼきと鳴らしまくる動画を見つづけた。体験したひとたちはみんな動画の中で興奮していて、すごーい、やばーい、うわまじ顔変わったあ、というような感嘆の声をあげていた。くりかえされる、ぼきぼき音。小さな画面のなかの誰かの体の関節が鳴らされているだけで、自分の体には何も起きてはいないのに、なぜここが、気持ちのいい感じになるんだろう。それがどこかも、誰の体かもわからないのに、あれとこれは、どこで、何で、繋がっているんだろう。トヨはそんなことをぼんやり思った。
「みてみて、銀座のさ、ここみたいに有名人はいないけど、千葉のここの人もやばい。店の手作り感もやばいけど、でもここがいちばん鳴らしてる」
「うわー、すごいかもー」
「これほんとの音かなあ。集音マイクとか使ってるのかなあ。あとから被せたりしてないのかな」
「うーん」
「っていうか、いくらすんだろ、高いのかな。でも有名人とかモデルとかは、どうせただでやってもらってるんだよね」
「うーん」
「見て、この人、これでビル建てたって書いてる。すごくない」
「うーん」
「骨でビルかあ、鳴らすだけなら一日二百人くらいさばけそう。ぼっろいなあ」
「うーん、骨切りとは、ちがうもんねえ」
ほかにも世界の色んな絶景や、額にカメラをくっつけて危険地帯を行く命知らずのインスタグラマーたちや、どじな子犬や子猫の動画をマリリンに見せて、あれこれおしゃべりをした。トヨが何か言うたびにマリリンは笑い、トヨも笑った。大きく見ひらかれたままで固定された目の形とは裏腹に、マリリンの視線じたいは柔らかで、そしてその話しぶりはぽやんとしていて、その感じや声の調子を聞いていると、どことなく懐かしいような、じれったいような感じがした。そしてトヨはふと、小学校の頃に仲良くしていたスミちゃんのことを思いだした。スミちゃんはトヨのことをヒデヨシと呼ばなかった数少ないクラスメイトで、冴えないトヨに負けず劣らず、誰からもさしたる注意を払われることのない、地味でおとなしい子どもだった。
トヨは小学生時代、派手で目立って弁の立つ女の子たちに使い走りをさせられたり、暇なときにどうでもいいことをふっかけられてはいじられるような存在だった。トヨはプライドが高く、そんな自分のことを恥ずかしいと思っていたけれど、スミちゃんだけはなぜかトヨを慕ってくれていた。女の子たちがトヨのことを無視したり、男子のまえで恥をかかせるようなことを言って笑い者にしたときも、スミちゃんはただひとり、変わらずおなじように接してくれた女の子だった。
でも、小学生の頃にはありがちな、そうした主導権を持つ女の子たちの気まぐれと風向きの変化によって、末端ではあるけれど、トヨがそちらの女の子たちの仲間入りを果たしたような感じになったとき、トヨはあっさり、スミちゃんのことを疎ましく感じるようになってしまった。自分の意見がなく、なぜかいつもくっついてきて、弱い感じがして、ださくて、ぱっとしなくて、何が好きなのかもわからなくて、人の話にいつも肯いてへらへら笑うだけのスミちゃんを見ていると、不安とも苛立ちともつかない気持ちになった。スミちゃんがそんなトヨの変化に気づいているのか、いないのか――いずれにせよ変わらずトヨに話しかけ、笑いかけてくるスミちゃんに、まるで足をひっぱられているような、そんな被害妄想まで抱くようになっていた。
それでいつだったか、これもありがちな顛末ではあるけれど、トヨが入れてもらった女子グループの、トヨよりもひとつかふたつ立場の強い位置にいる女の子が、スミちゃんが何か特別な行事のときに着てきた服を、こき下ろしたことがあった。そしてトヨはその女の子と一緒になって、スミちゃんが泣くまで笑って笑って追い詰めたことがあったのだ。
そのあと、スミちゃんがどんな感じでクラスで過ごしていたのか、そういうことは思いだせない。目の前のマリリンは、トヨにスミちゃんを思いださせた。スミちゃんてどうしてるんだろう。ぜんぜん知らない。中学校に上がってからは、道とか廊下とかを歩いてるのを見たことあるけど、けっきょく一回もしゃべらず終いだった。高校はどこへ行ったんだったっけ――とそこまで思いを巡らせたときに、トヨの頭に、ある突拍子もない考えが、ぽんと浮かんだ。
もしかして、このマリリンが、スミちゃんだってことは、ないよね?
まさかまさかと思いながら、トヨはマリリンの顔をじっと見た。
っていうか、スミちゃんって、どんな顔だった?――いや、ぜんぜんまったく、思いだせない。でも、マリリンはこんなに整形をしているわけだから、マリリンの本当の顔だって、わたしは知らないわけだよね。トヨは自分に問いかけた。ってことは、万が一、もしこの子がスミちゃんだったとしても、わたしにそれは、わからないよね。でももしも、この子がスミちゃんだったとしたら、スミちゃんには、わたしのことがわかるよね……だからここまで、ついて来たとか……?
いやいや、ないない、この子がスミちゃんだなんて、そんな阿呆みたいな可能性あるわけない。ないよね。ないでしょ。それは、ないない。確率っていうか、そんなふうにできてないでしょ、よくわからないけど、世界って。
トヨはため息をついて、自分のそんな馬鹿馬鹿しい思いつきを、頭の中から追いやった。そして、自分が、本当にきれいさっぱりスミちゃんの顔を忘れていることについて、考えた。
自分にはもう思いだせない顔。でも、当たり前だけど、スミちゃんは今もどこかで生きていて、そこにはスミちゃんの顔があるはずだった。ここにわたしの顔があるように。思いだすことはできないけれど、今もどこかに、スミちゃんの顔があるはずだった。わたしが思いだせないだけで。
たとえばマリリンは、もともとの自分の顔を覚えているんだろうか。目も鼻もこんなにいじって、唇や額をぱんぱんにして、顎も、ひょっとしたら頬骨だって削ってるかもしれないマリリンの顔は、元々は、こうではなかったはずだ。そんなマリリンの最初の顔は、本当の顔は、いったいどんなふうに記憶されているんだろうか。どこに、誰に、どんなふうに、残っているんだろうか。マリリンが、昔の自分の顔を思いだすとき、それは誰かべつの、ほかの誰かの顔を思い浮かべるのとは、違うのだろうか、どうなんだろうか。
でも、わたしだって昔と顔は変わったはずで、年をとって、色々なところが変わったはずで、これからだって変わるはずで。だったら手術して色んなところを変えた顔と、年をとって自然に変わってしまう顔っていうのは、いったいどこが違うのか、違わないのか――トヨの頭には、これまで思ってもみなかったいくつもの疑問が浮かび、それがまた、べつの疑問をつれてきた。
っていうか、そもそも、自分の顔って、考えてみたらやばくない? 自分で自分の顔って、そのまま直で見たことない。みんなが見てるのは、人の顔だ。自分の顔は、誰かがいるから存在するのだ。じゃあ、でも、たとえば、たとえばこの感染症がマックスに激烈にえぐい鬼展開になって、それはもう、とことんまでひどくなって、もう誰かに会うこともなくなって、あるいは無人島とかに送りこまれて自分以外の人がいなくなったなら、顔っていったいどうなるの? 誰も見る人がいなくなれば、顔だって足の裏とかひざの皮とかと、そんな変わらなくなるものなの? どうなの? いやいや、ひざと顔はちがうだろ。っていうか究極的にはおなじなの? そういうことなの? っていうか顔って、なんなの?
「――うちさあ、実家、しいたけ農家やってるんだよね」
あとからあとから湧いてくる、とりとめのない混乱を打ち消すように、トヨは言った。あ、覚えてる、水貯めてるとこで遊んで怒られたよねえ――なんてことをいっしゅんマリリンが言ったらどうしようとトヨは思ったけれど、そんなことは起きなかった。
「しいたけかあ。しいたけの味って、どんなだったっけ」
「しいたけの味って、説明しにくいよなあ」
「どうやって、作るの?」
「うちは色々やってたなあ。なんか、いっぱい木を並べてるとこがあって、そこにね、ぼこぼこ生えてくんの。子どもの頃びびったのがさ、電気みたいなの打つんだよね。流すっていうか」
「しいたけに?」
「そうそう、理屈はわかってないらしいんだけど、昔から雷が落ちたら、しいたけがなんか爆発的にふえるってのがあって。なんか数が倍くらいになるとかで。それで誰かが始めて、そっから何万ボルトとかの、電気を打つようになったの」
「人間みたいー」マリリンは笑った。
「どういうこと?」
「わたしも顔に、めっちゃ電気、打つよ、電気バリっていうの。めっちゃ刺して、めっちゃ流すよ、電気ー。やっぱり、意味あるんだねえ」
それぞれグラス三杯のビールを空にして、マリリンは少し、トヨはすっかり酔っていた。背もたれに体を預けたとき、紙袋のざらざらとした断面が肘をこすった。トヨは自分がお土産を持ってきていたことを思いだした。
けっきょく渡すこともできず、持ち帰ることになってしまった、駅前のフィナンシェ。悪い気持ちになる人はいないからね、という母の言葉を思いだして、トヨはなんとも言えない気持ちになった。気持ちどころか、渡すタイミングどころか、面接どころか――頭に浮かんでくる言葉をいちいち確認すると、なんだか胸が痛くなるので、あくびをしながら両手をのばして伸びをして、胸を広げ、そこにあるものを逃してやった。そして、マリリンが、もし友達だったらどうなんだろうと、そんなことを思った。新しい友達でもいい、懐かしい友達でもいい、なんだったらお互いに頭をぶつけるかなんかして激しい記憶喪失になったけど、ちょっとの巡りあわせでいまお互いに思いだし待ち、みたいな友達でも、なんでも。これからたまに連絡を取りあって、互いの部屋に泊まりにいったり、愚痴を言いあったり、今みたいに酒を飲んだり、どうでもいいことで笑いあうような友達とかでもなんでもいいけど、わたしたちがそういう友達だったなら、どうだったんだろう。そんな想像が、ふっとよぎった。でもそれはトヨの頭の中をいたずらに横切っただけで、自分がそんなことを求めていないことも、また、そんなふうにはならないことも、トヨにはわかっていた。
「ねえ、小腹すかない? フィナンシェあるよ」
「食べたいー」
トヨは持ち込んだ食べ物を店の中で食べるのはまずいと知っていたけれど、酔っていたので気が大きくなっていた。何か言われたら謝ればいいし、必要以上に失礼な態度をとられたら、言い返してやればいい。全然いける。全然よゆう。トヨは紙袋の中で包装紙をばりばり引き裂いて、そのまま小さな箱の蓋をあけ、中からフィナンシェをふたつ取りだして、ひとつをマリリンに渡してやった。おいしそー、とマリリンはフィナンシェの入った小さな透明の袋を指でつまんで、鼻のまえで小刻みに揺らし、にっこり笑った。白いアイシャドウを盛っていた涙袋が、上まぶたの黒いアイシャドウと混じりあって、見たことのないような銀色に光ってみえた。
やばいー、おいしー、と言いながらふたりはフィナンシェを齧りつづけ、おなじひとつの甘さがそれぞれの舌のうえに広がっていった。ほかに客の姿はなく、いい感じに酔いがまわったふたりの声は、大きく響き渡った。
いっぽう、さっきの店員はレジのカウンターの中で、ただでさえ長く美しく生えそろった睫毛をさらに長く美しくしようと念入りにマスカラを塗りながら、最近いい感じに距離がつまってきて、この数日に何かが起きそうな相手に送るラインの中身を考えている途中だった。もし寝ることになったなら、相手が自分に期待していたり想像している以上のものを、見せつけたいし、圧倒したいし、今まででいちばんすごいと言わせたい――小さな手鏡のなかの自分を見つめれば見つめるほど、その恍惚はいっそう高まる。客席から、女たちの笑い声が聞こえて顔をあげる。そのとき彼女はたしかにトヨとマリリンを見たけれど、ふたりの姿は目に映らない。