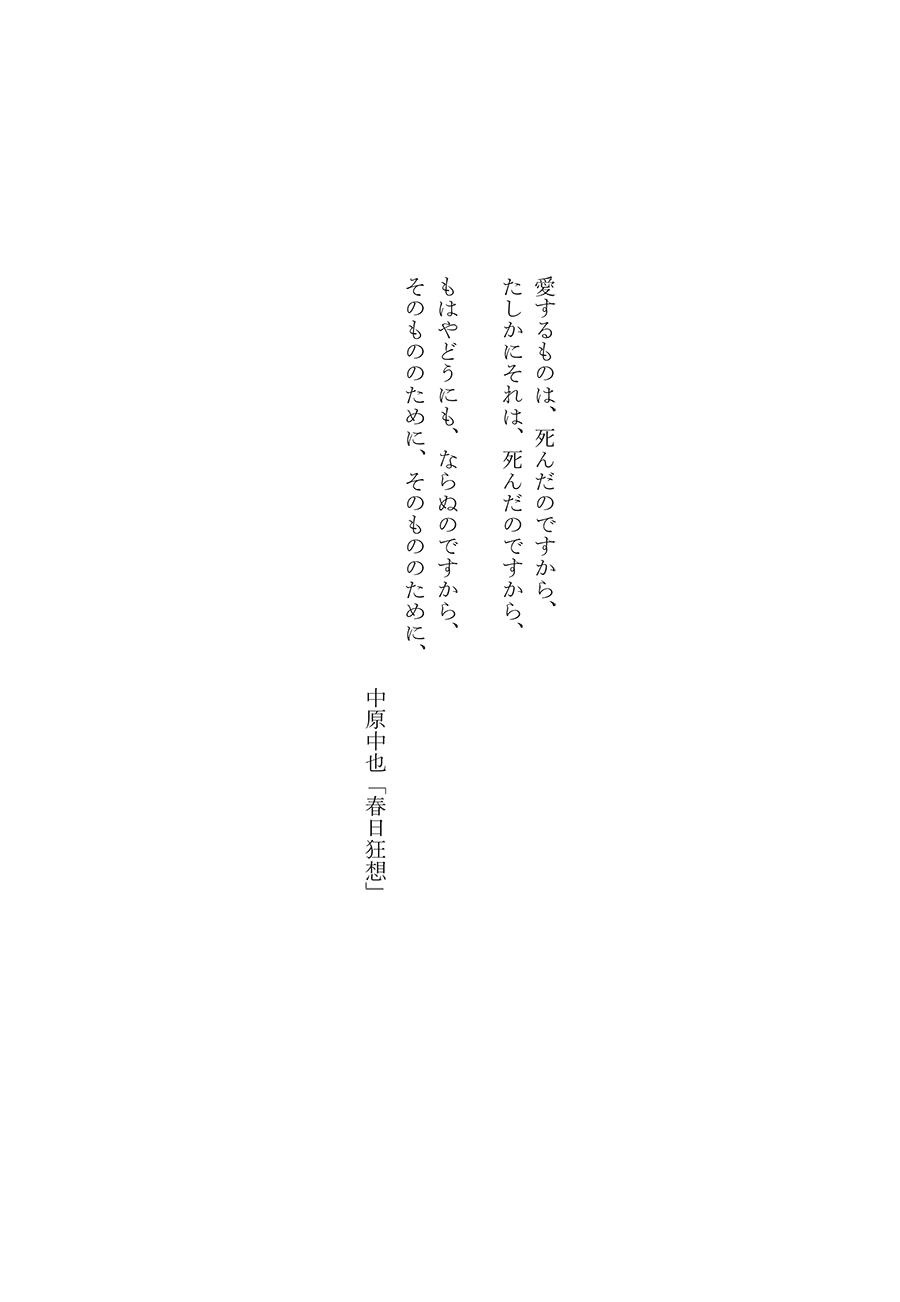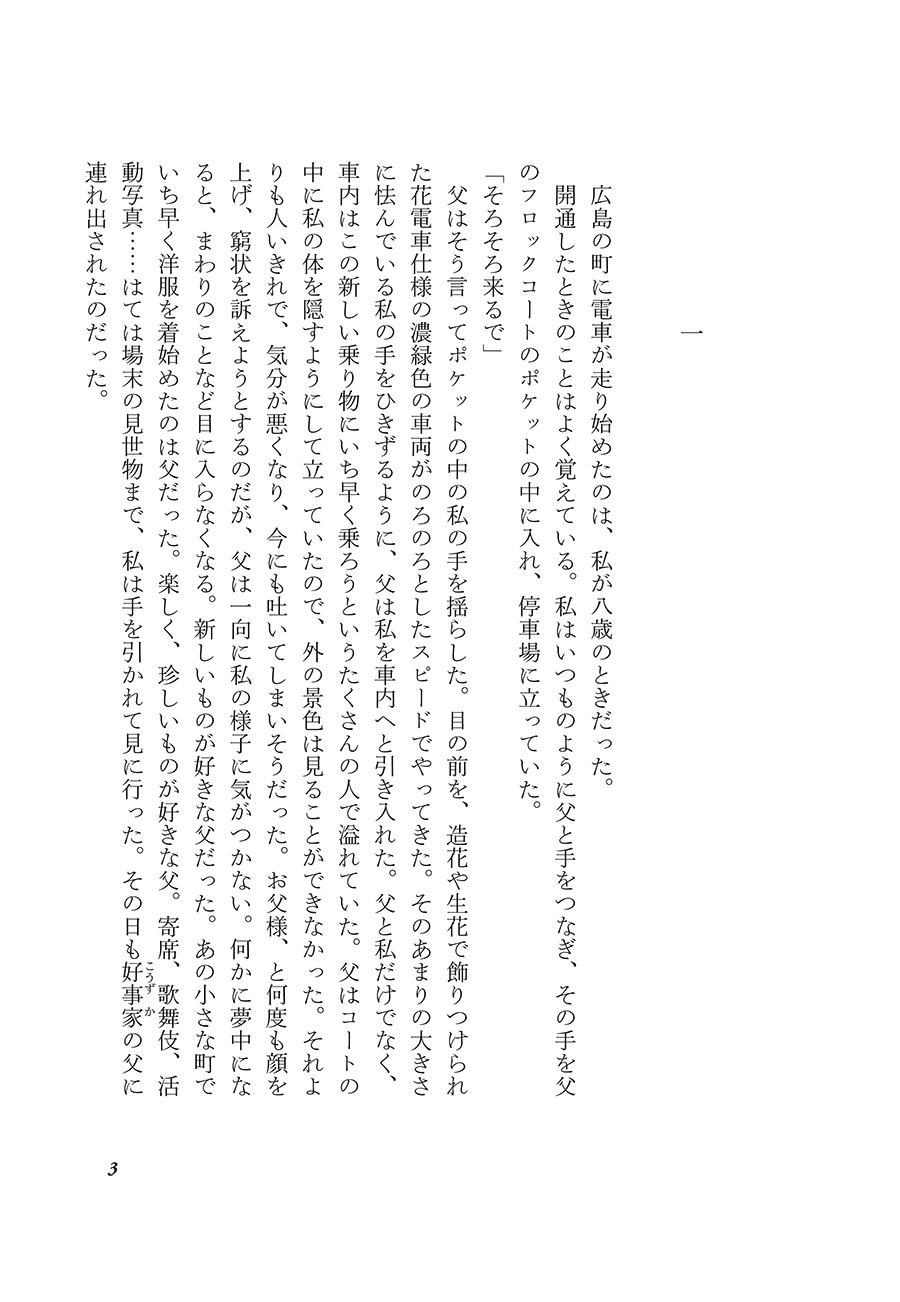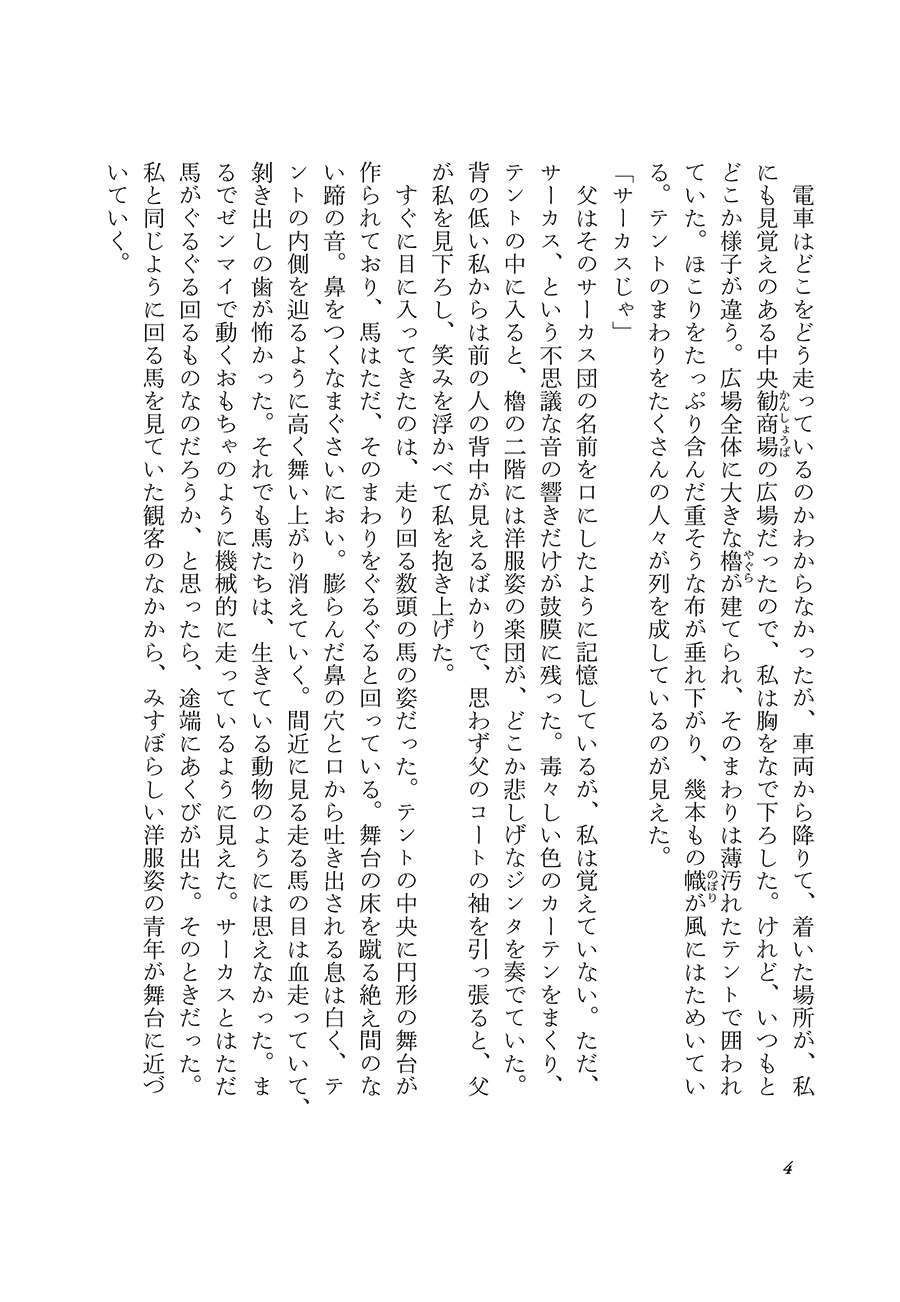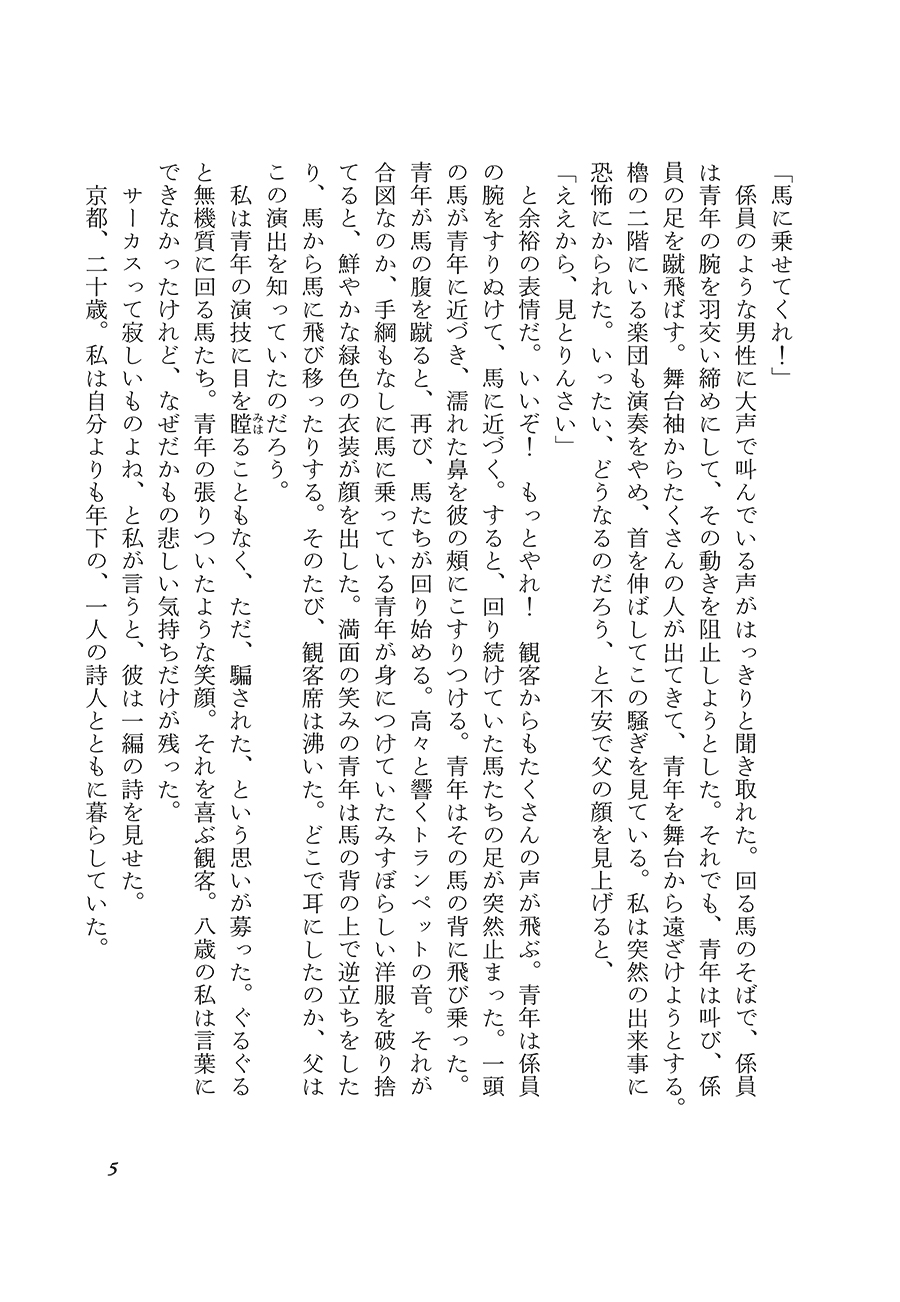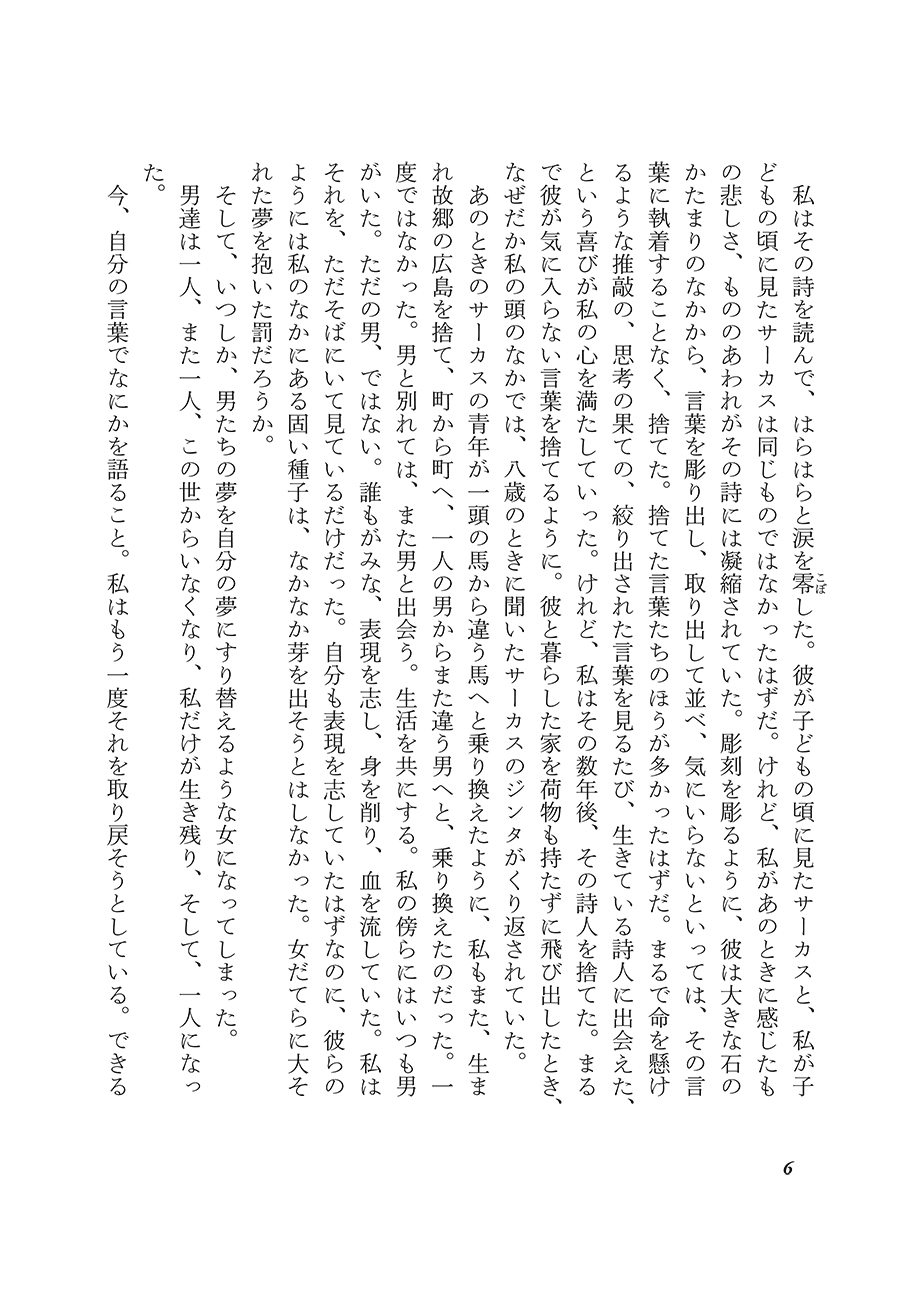夏日狂想人物相関図
愛するものは、死んだのですから、
たしかにそれは、死んだのですから、
もはやどうにも、ならぬのですから、
そのもののために、そのもののために、
中原中也「春日狂想」
一
広島の町に電車が走り始めたのは、私が八歳のときだった。
開通したときのことはよく覚えている。私はいつものように父と手をつなぎ、その手を父のフロックコートのポケットの中に入れ、停車場に立っていた。
「そろそろ来るで」
父はそう言ってポケットの中の私の手を揺らした。目の前を、造花や生花で飾りつけられた花電車仕様の濃緑色の車両がのろのろとしたスピードでやってきた。そのあまりの大きさに怯んでいる私の手をひきずるように、父は私を車内へと引き入れた。父と私だけでなく、車内はこの新しい乗り物にいち早く乗ろうというたくさんの人で溢れていた。父はコートの中に私の体を隠すようにして立っていたので、外の景色は見ることができなかった。それよりも人いきれで、気分が悪くなり、今にも吐いてしまいそうだった。お父様、と何度も顔を上げ、窮状を訴えようとするのだが、父は一向に私の様子に気がつかない。何かに夢中になると、まわりのことなど目に入らなくなる。新しいものが好きな父だった。あの小さな町でいち早く洋服を着始めたのは父だった。楽しく、珍しいものが好きな父。寄席、歌舞伎、活動写真……はては場末の見世物まで、私は手を引かれて見に行った。その日も
電車はどこをどう走っているのかわからなかったが、車両から降りて、着いた場所が、私にも見覚えのある中央
「サーカスじゃ」
父はそのサーカス団の名前を口にしたように記憶しているが、私は覚えていない。ただ、サーカス、という不思議な音の響きだけが鼓膜に残った。毒々しい色のカーテンをまくり、テントの中に入ると、櫓の二階には洋服姿の楽団が、どこか悲しげなジンタを奏でていた。背の低い私からは前の人の背中が見えるばかりで、思わず父のコートの袖を引っ張ると、父が私を見下ろし、笑みを浮かべて私を抱き上げた。
すぐに目に入ってきたのは、走り回る数頭の馬の姿だった。テントの中央に円形の舞台が作られており、馬はただ、そのまわりをぐるぐると回っている。舞台の床を蹴る絶え間のない蹄の音。鼻をつくなまぐさいにおい。膨らんだ鼻の穴と口から吐き出される息は白く、テントの内側を辿るように高く舞い上がり消えていく。間近に見る走る馬の目は血走っていて、剥き出しの歯が怖かった。それでも馬たちは、生きている動物のようには思えなかった。まるでゼンマイで動くおもちゃのように機械的に走っているように見えた。サーカスとはただ馬がぐるぐる回るものなのだろうか、と思ったら、途端にあくびが出た。そのときだった。私と同じように回る馬を見ていた観客のなかから、みすぼらしい洋服姿の青年が舞台に近づいていく。
「馬に乗せてくれ!」
係員のような男性に大声で叫んでいる声がはっきりと聞き取れた。回る馬のそばで、係員は青年の腕を羽交い締めにして、その動きを阻止しようとした。それでも、青年は叫び、係員の足を蹴飛ばす。舞台袖からたくさんの人が出てきて、青年を舞台から遠ざけようとする。櫓の二階にいる楽団も演奏をやめ、首を伸ばしてこの騒ぎを見ている。私は突然の出来事に恐怖にかられた。いったい、どうなるのだろう、と不安で父の顔を見上げると、
「ええから、見とりんさい」
と余裕の表情だ。いいぞ! もっとやれ! 観客からもたくさんの声が飛ぶ。青年は係員の腕をすりぬけて、馬に近づく。すると、回り続けていた馬たちの足が突然止まった。一頭の馬が青年に近づき、濡れた鼻を彼の頬にこすりつける。青年はその馬の背に飛び乗った。青年が馬の腹を蹴ると、再び、馬たちが回り始める。高々と響くトランペットの音。それが合図なのか、手綱もなしに馬に乗っている青年が身につけていたみすぼらしい洋服を破り捨てると、鮮やかな緑色の衣装が顔を出した。満面の笑みの青年は馬の背の上で逆立ちをしたり、馬から馬に飛び移ったりする。そのたび、観客席は沸いた。どこで耳にしたのか、父はこの演出を知っていたのだろう。

私は青年の演技に目を
サーカスって寂しいものよね、と私が言うと、彼は一編の詩を見せた。
京都、二十歳。私は自分よりも年下の、一人の詩人とともに暮らしていた。
私はその詩を読んで、はらはらと涙を
あのときのサーカスの青年が一頭の馬から違う馬へと乗り換えたように、私もまた、生まれ故郷の広島を捨て、町から町へ、一人の男からまた違う男へと、乗り換えたのだった。一度ではなかった。男と別れては、また男と出会う。生活を共にする。私の傍らにはいつも男がいた。ただの男、ではない。誰もがみな、表現を志し、身を削り、血を流していた。私はそれを、ただそばにいて見ているだけだった。自分も表現を志していたはずなのに、彼らのようには私のなかにある固い種子は、なかなか芽を出そうとはしなかった。女だてらに大それた夢を抱いた罰だろうか。
そして、いつしか、男たちの夢を自分の夢にすり替えるような女になってしまった。
男達は一人、また一人、この世からいなくなり、私だけが生き残り、そして、一人になった。
今、自分の言葉でなにかを語ること。私はもう一度それを取り戻そうとしている。できるかどうかはわからない。けれど、もうあまり時間がない。書き出さなければ、記憶も、指の間からこぼれ落ちていく砂のように私の頭のなかから消失してしまうだろう。だから、残った記憶をパッチワークのようにつなぎ合わせて、忘れないうちに書き留めておこうと思う。
それにどんな意味があるのかなんて、追求することはなしにしたい。
今の私にはただ、書きたいという純粋な気持ちだけが存在するのみである。
*
「お嬢様、こちらへどうぞ」
車夫に手を貸してもらい、
緋色の
「いってまいります」
礼子が父に頭を下げると、父はまるでそれが永遠の別れのような、悲しげな表情を浮かべる。その顔を見ると、礼子の胸のうちにもさざ波が立った。礼子を乗せた人力車がまだ人の少ない朝の道を進み出す。
礼子は明治三十七年、広島市
明治の終わりに生まれ、大正のはじめに多感な十代を過ごした礼子のそばには常に、次々にあらわれる近代の文化があった。それは急速に欧米の風俗や文化を取り入れていった明治維新後の日本の姿だったが、それ以上にハイカラ好みの父の存在が大きかった。
たくさんの本を読み、中島本町で初めて洋服を着、活動写真に目がなかった。母やまわりの家族の反対を押し切り、礼子を広島女学校の付属小学校に入れたのも父の望みだった。礼子はそのまま女学校に進み、十三の春を迎えていた。
人力車の上からふと礼子が目をやると、元安川の川面にミルク色の霞がかかり、帆掛け船が風に押されて、川下に向かっていく。はるか遠くには
ふいに、人力車が停まる。あの角を曲がれば女学校へ続く一本道。その手前で車から降りるのが礼子の常だった。女学校に向かう女学生たちの列に礼子は素知らぬ顔で紛れこむ。知った顔があれば、「ごきげんよう」と挨拶を交わした。
御影石の門柱の左には、太い筆で記された広島女学校という校名、左右の門柱に渡された鉄製の門をくぐると、両側に袖のあるコの字型の二階建ての白い建物が見えてきた。屋根は大屋根の
建物中央の玄関を入り、靴箱を開くと、まるで礼子が来るのを待っていたように、白い封筒が三つ、そこにあった。柔らな毛筆で「礼子様」と表に書かれている。
「また、お友達になりましょう、じゃろうか……」
礼子は小さなため息をつきながら、封筒を裏返して差出人の名を確かめることもなく、それを鞄の中にしまった。
礼子の通う広島女学校は、明治十九年、アメリカで洗礼を受けた
礼拝を終え、その日の一時間目は裁縫の時間だった。裁縫室に行くため、道具を包んだ風呂敷包みを手に、教室を出ようとすると、同級生の山下さんが礼子に駆け寄った。
「礼子さんの分もお持ちしますわ」
最初の頃はそのたびに断っていた礼子だったが、包みの引っ張り合いで一度裁縫道具を廊下にまき散らしてからは、何も言わずに山下さんに包みを渡すようになっていた。裁縫室までは渡り廊下を歩き、上級生の教室の前を歩いていく。授業の始まりを待つ上級生たちが廊下に立っている。この廊下でも礼子は、幾人もの年上の女学生の視線に晒される。この学校に入ったときからそうだった。礼子に微笑みかける生徒もいる。
ふり返れば幼い頃からそうだった。礼子の姿を視界の中に入れた人たちは皆、まるで朝露のなかに一粒のダイヤを見つけたような顔をする。それがどうしてなのかを幼い礼子もわかっていた。礼子が物心ついてから数多く投げられた言葉は「器量よし」だった。それは父が幾度も礼子の顔を見てはつぶやいた言葉でもあり、礼子が初めて覚えた言葉でもあった。まだよくまわらない舌で幼い礼子がその言葉を口にすると、仕事相手の人間や母にはかすかな笑顔すら見せない父も忽ち表情を崩し、礼子の口に金平糖を入れた。だから、自分が人よりも、器量がいい、ということに礼子は自覚があった。
だからといって、それを鼻にかけるようなことは絶対にしなかった。いつか校長先生が生徒に話してくれたこの言葉、
「髪を編んだり、装身具を身につけたり、着飾ったりしてうわべだけの人になるのではなく、思いやりのある柔和で平穏な精神の清廉な装い、それこそが神の前にとても価値のあることである」
礼子はこの言葉を帳面に記し、うわべだけの人には決してなるまい、清廉な装いを身につけるのだ、と心に誓った。とはいえ、神、というものが礼子にはよく理解できていなかった。家には仏壇も神棚もある。父は毎朝、仏壇の前に座り、長い念仏を唱え、母は暗い台所の神棚に手を合わせている。娘である礼子は、西洋の神に祈りを捧げる。神とは磔にされたイエス様なのか、それとも六日間で世界を造りあげた方なのか、礼子にはわからなかった。先生たち、なかでも外国からやってきた先生たちに聞くことにもためらいがあった。「身もたまも 主にささげ」と毎朝聖歌を口にしているが、主という存在に体も魂も捧げられるかどうかもわからない。
神さまとは誰なんじゃろう……。そんなことをぼんやり考えながら、礼子は先生に言われるまま、
「いたっ!」
針が礼子の左手の人さし指を深く突いた。指先の赤いふくらみがみるみるうちに大きくなっていく。思わず礼子は人さし指を口に入れた。山下さんをはじめ、数人の生徒が礼子の元に駆け寄る。
「先生、
山下さんがそう言ったものの、
「それくらいのことでなんです」と先生はそう言って相手にはしてくれなかった。礼子は指の痛みを我慢しながら授業を終えた。
「大丈夫? 先生はひどいねえ。でも黴菌が入ったら大変。消毒をしてもらいましょう」と山下さんが礼子の腕を引っ張り、保健室に連れて行く。二人のあとを数人の生徒も追いかける。この学校では私はまるで大きな赤ちゃんみたい。そう思いながらも礼子はされるがままになっていた。
午後の国語の時間、また礼子の作文が授業で読まれた。それは元安川のほとりの四季の移ろいを描いた文章だった。風景を思い浮かべながら筆をすすめる。自分の脳裏に浮かんだとおりの文章が書けると、胸がはずんだ。
先生と言ってもまるで女学生のような佐藤先生は、
「情景が目に浮かぶような文章ですね。皆さんも野中さんを見習うように」と礼子の文章を褒めそやした。生徒たちの視線が礼子に集まる。礼子の白磁のような頬に赤みがさす。何度ほめられても慣れなかった。
授業が終わると、佐藤先生は礼子一人を教室に残し、『少女画報』に作文を投稿してはどうか、と話した。
『少女画報』と聞いて礼子の胸はときめいた。大好きな作家、吉屋信子が『花物語』を連載している雑誌だ。もちろん、礼子は毎月『少女画報』を読んでいたし、同級生でも読んでいる者は多かった。鈴蘭、水仙、あやめ、コスモスなど、毎回花の名前を冠した作品の舞台は、まさに礼子が今いる女学校で、少女同士の友情も礼子にとっては身近なテーマだった。
幼い頃から、新聞を読むあぐら姿の父の足の間に座り、自然に文字を覚え、文字が書いてあるものならなんでも読みたい、という礼子が望む本ならば、父はなんでも買い与えてくれた。父は礼子が何を読んでいるのかには興味がなく、礼子が本を読んでいる姿に満足しているだけだったから、夏目漱石や島崎藤村、有島武郎、ゲーテはもちろん、高級娼婦が主人公のエミール・ゾラの『ナナ』を読んでいても、礼子に小言を言ったことはなかった。
背伸びをして大人びた読書を好む礼子ではあったが、そんな本を読んでいても、どこか遠くの絵空事という思いは消えなかった。それに反して吉屋信子の物語は、まるで自分の生活をどこかで見聞きしているのではないかと思えるほど、自分の心の奥深くに迫ってくる。
「野中さんなら必ず入賞しますよ。今日から毎日作文を書いて私に提出するように」
私もいつか小説を書いたら吉屋信子さまのようになれるんじゃろうか。礼子の小さな胸は震え、先生の言葉に頷くしかなかった。
床から数センチ、足元が浮き上がるような気持ちを抑えながら、礼子は礼拝堂に急いだ。放課後、誰もいない礼拝堂で二学年上のお姉様、

いつかの朝礼の先生の言葉が浮かぶ。「自分を愛するように隣人を愛しなさい」。愛する、という言葉も礼子にはわからない。自分を愛しているか、と問われれば、それもわからない。けれど、お姉様に対する気持ちはもしかして愛に近いのかもしれない。礼子はそんなふうに考えるようになっていた。
小さな足音が近づく。礼子のお姉様、寿美子がそっと後ろの入口から礼拝堂に入ってきた。礼子の顔を見て優しく微笑み、礼子の隣に腰を下ろす。礼子は鞄の中から、朝、靴箱に入れられていた三通の封筒を寿美子に渡した。寿美子はいつものようにどこかもどかしげに封を開き、三つ折りにされた便箋に目を通した。礼子は寿美子の横顔を見た。どこまでも
「礼子さんは人気者なんじゃね。……あなたは学校でもいっつも人の輪の中心におってから」
「ううん、私はお姉様さえおってくれればいいんよ」
礼子がそう言うと、寿美子は静かに微笑み、礼子の手をそっと握った。
「そうじゃ。佐藤先生のお話はなんだったん?」
寿美子が便箋を再び封筒の中に収めながら尋ねる。昨日、佐藤先生に放課後教室に残りなさい、と言われたことが心配で思わず寿美子に話していたのだった。礼子は佐藤先生に言われたことを寿美子に話した。
「すごいじゃない。礼子さんの作文は必ず『少女画報』に載るよ。私にはわかる。あなたはすばらしいものを持って生まれてきたんよ。礼子さんなら女文士にだってなれるよ」
「そんな……」礼子は自分の頬が染まるのを感じていた。
「そうじゃ。未来の女文士さんに差し上げたいものがあったんよ」そう言って寿美子は鞄の中から小さな紙の包みを取り出し、礼子に差しだした。礼子はその包みをそっと開いた。中には薔薇色のリボンが入っていた。
「わあ、なんと綺麗なんじゃろう」
「礼子さんならきっとお似合いになると思うて」
寿美子は礼子の髪にあったリボンをほどき、薔薇色のリボンを結んだ。
「思ったとおりじゃ。礼子さん色白じゃから、とてもよくお似合い」
「ありがとうございます。お姉様、私、本当にうれしい」
礼子は寿美子の体に身を寄せた。香水などつけているはずもないのに、寿美子からは
「お友達になりましょう」
女学校に入学早々、廊下を歩いていた礼子の手をとり、こう告げたのが二学年上の寿美子だった。まわりの皆は礼子と寿美子のことをエスだと噂した。エス、つまりsisterの頭文字をとったもので、上級生と下級生が仲良くなると、そんなふうに言われるのが常だった。エスの女学生は礼子と寿美子だけではなかったが、礼子も寿美子も「器量よし」であったから、なおさらその存在は目立った。
礼子にはきょうだいがいない。長い間、子宝に恵まれなかった両親の一人娘であった。父はまるで甘い蜜を口に運ぶように礼子を愛で、育てた。一方の母は神経質で、一心同体のような父と礼子をどこか醒めた目で見ている。礼子は母に似ず、年齢を重ねるにつれ、美しい少女に育っていった。そう認めたくはなかったが、礼子も母とは心の距離があった。いちばん幼い頃の母との想い出は、息の詰まるほどぎゅうぎゅうと、帯を締め上げられたことだった。女学校に上がる前は、外から遊んで帰ると、熱湯を含ませかたく絞った手ぬぐいで、礼子の手や顔を赤くなるほどこするのが常だった。お母様は怖い人だ。その印象は礼子が成長しても変わらなかった。だから、二歳上の寿美子は礼子にとって母のようでもあり、姉のような存在でもあった。家では父に、女学校では寿美子に愛されていた。その二人がいれば、礼子の毎日は丸く膨らんで、どこにも欠けたところはなかった。
二階の部屋で、礼子が佐藤先生に言われた作文を書いていると、遠くから路面電車が走るヒューッヒューッという空気を裂くような音が聞こえた。そして、カタン、コトンと橋を渡る下駄の音。川が引き潮のときはどちらの音も鋭い反響を伴って礼子の鼓膜を震わせた。そんなことを書いてみようか……。思案にくれながら、礼子は机にあった手鏡で自分の顔を見る。その顔はどこか寿美子に似ているようにも思えた。ほくろなどひとつもない透き通るような肌に小ぶりの鼻。化粧などしていないのに、頬は薄紅色に染まっている。やや冷淡にも見えかねない薄い唇の口角は上がり、黙っていてもどこか微笑みを湛えているように見える。お姉様が本当の姉ならばよかったのに……。礼子がぼんやりそんなことを考えていると、階下から、
「散歩に行こうやあ」という父の声が聞こえた。
どこに行くわけでもないが、夕餉前、商店街をそぞろ歩くのは、礼子と父との日課になっていた。小さな体の礼子は大柄な父の腕にぶらさがるように歩く。父は毎日のように本屋に寄った。礼子も店先の雑誌や本に目をやる。一冊の演劇雑誌の表紙に松井須磨子の名を見つけ、礼子の胸は高鳴った。
十歳のときに寿座で見た松井須磨子の舞台『復活』のことを、礼子はまるで昨日のことのように思い出す。トルストイの原作を劇作家の
それまで礼子が見てきた芝居、歌舞伎や人形浄瑠璃などは、台詞も堅苦しく、女役も男の俳優が演じていた。大正になると、歌舞伎の近代化を目指した新国劇や、日本の現代劇を演じる新派、さらに西洋の演劇を模倣した新劇があらわれ始めた。新劇活動を始めたのは
礼子に影響を与えたのは、松井須磨子だけではない。
礼子は父が連れて行ってくれる歌舞伎や寄席には興味が持てなかったが、いちばん心を惹かれたのは活動写真だった。なかでも洋画が礼子のお気に入りだった。イプセンの戯曲を映画化し、松井須磨子も舞台で演じたことのある『人形の家』や、メトロポリタン・オペラのプリマ、ジェラルディン・ファーラー主演の『カルメン』が印象に残った。礼子の心に響いたのは、弁士がまくしたてる物語の筋ではなく、モノクロのスクリーンのなかで自由に動き、笑い、泣く、女優たちの姿であった。
いつか私も女優になれないだろうか。女優へのあこがれは、日々くすぶり始めてはいたが、十三歳の礼子にとって、それは随分と曖昧模糊としたものだった。俳優という職業は「河原乞食」という汚名こそ返上してはいたものの、女が演技をする、ということへの風当たりの強さを、そして、まわりの人びとが「女優」という言葉を口にするとき、どこか蔑む視線を伴うことを、礼子も自然に感じとっていた。だから、女優になりたいという思いが募るたび、女学校まで上げてもらった自分がする仕事ではない、と礼子は自分を制した。
松井須磨子の名が載った演劇雑誌を父に買ってもらい、礼子は父と共に散歩を続けた。父が橋の欄干にもたれかかり、煙草に火をつける。礼子は少し離れた場所でおいしそうに煙草を吸う父の姿を見ているのが好きだった。もし父に、女優になりたい、と言ったらどんな顔をするだろう……。礼子はひどく残酷な想像をしているような思いにかられた。
長い散歩の終わりは、商店街の外れにある菓子屋で菓子を買うことだった。父は甘いものにも目がなかった。夕餉に響かないものをと、飴や金平糖や舶来のジェリービーンズを買っては、「母さんには言うたらいけんど」と礼子の口に放り込むのだった。

季節は秋を迎えていた。
「私は東京に行きたいんよ。もっともっと勉強がしたいんよ」
いつもの放課後の礼拝堂で寿美子が遠い目をして言った。
優秀な男子であれば中学校を卒業したあと、ゆくゆくは大学に進み、晴れやかな将来が期待されていたが、広島にいては、女学校の先がない。東京に行けば東京女子医専、女子英学塾、日本女子大学校、東京女子大学がある。それに学力さえあれば、女子にも帝国大学の門戸が開かれるようになっていた。この女学校からも東京に進学した生徒はいたが、ほんの数える程度だった。ミッションスクールに通ってはいても、ほかの女学校と同様に、卒業すれば結婚をして良妻賢母になることが求められる。
「お姉様はなんの勉強がしたいん?」
礼子の問いにいつもははきはきとした寿美子が恥ずかしそうに俯く。
「笑わん?」
「絶対に笑わん」
「……お医者様になりたいんじゃ……」
「へえ! お医者様!」
「私の母は胸が悪いでしょう」
寿美子の母が肺を患ってサナトリウムにいることは礼子も知っていた。
「先生たちは幾度もおっしゃるじゃない、人のために生きろ、と。でも、卒業した生徒のほとんどは結婚をして家に閉じこもってしまう。家族のために生きるのも確かに人のためかもしれん。でもね、私はもっとたくさんの人のために生きたいんよ」
そう言う寿美子の顔が輝いている。綺麗だ、と礼子は思った。
「お姉様なら、きっときっとお医者様になれるよ」
寿美子の成績が学年で一、二を争うということは礼子だけでなく、生徒の多くが知っていることだった。
「礼子さんは、将来、何になりたいん?」
そう言われて言葉に詰まった。女優の仕事を恥ずかしいものだとは思わなかったが、寿美子の言うたくさんの人を救うものだとも思えなかった。女優になりたい、と無邪気に言えない自分にも腹がたった。黙ってしまった礼子を気遣ったのか、寿美子が話の矛先を変えた。
「今度のクリスマスの
クリスマスのミサの後、選ばれた最上級生だけで行われる降誕劇になぜだか礼子も駆り出されていた。しかも主役といってもいいマリアの役だった。自ら望んだわけではなく、上級生たちが、ぜひ礼子をマリア様に、と先生たちに直談判して決まったことだった。
「きっと素敵なマリア様になるんじゃろうね」夢見心地に寿美子が礼子を見つめる。
「私、舞台の下から礼子さんを見守っとくけんね」
寿美子が口にした舞台、という言葉に礼子は心が震えた。礼拝堂で行われる降誕劇が自分にとっての初めての舞台になるのだ。自分にそんなことができるのだろうか。すでに始まっている練習では、声が小さい、台詞が聞き取りにくい、と言って先生に叱られてばかりいる。時には泣きたくなることもあった。そんなときは松井須磨子の舞台を思い出した。須磨子と自分では天と地ほどに違うことはわかっているが、せめて『復活』の舞台のときのような松井須磨子の度胸をくださいと、毎朝の礼拝で祈るようになった。
クリスマス当日、間に合わせの粗末な衣装ではあったが、マリアに扮した礼子を見て、誰もが息を吞んだ。礼子の台詞は二つしかなかった。
「どうしてそんなことが起こるのでしょう。私はまだ結婚しておりませんのに」
「私は神様のしもべです。あなたの
覚えた台詞を礼子は舞台袖でくり返した。舞台がこんなに緊張するものだとは思わなかった。礼拝堂の椅子に座った生徒たちの顔がこんなに近くに見えるものだとは。足が震えた。急ごしらえのカーテンから覗くと、舞台から数列先に座った寿美子の顔が見えた。寿美子も礼子の姿に気づいたのか、そっと目配せを返す。二、三度深呼吸をくり返し、心を決めて、すっ、と舞台に向かって足を伸ばす。あとは無我夢中だった。台詞を口にするときは声が震えた。それでも自分はマリアなのだと、礼子は信じ、演じきった。舞台はあっという間に終わった。観客席の皆の上気した顔。割れるような拍手。一人の生徒が立ち上がると、ほかの生徒もそれに続いた。真っ赤な目をしている寿美子の顔を礼子は見た。お辞儀をする。舞台袖にはける。恥ずかしさよりも、舞台の自分に皆が注目しているという強い快感が礼子の体を貫いていった。
降誕劇以降、礼子の名前は学校内に知れわたった。その年の年末、『少女画報』に礼子の文章が掲載されたことも、学内での礼子の人気に拍車をかけていた。毎朝靴箱を開けると、大量の手紙と、ときには野の花を束ねたものが入っていることもあった。同級生の誰もが礼子と友だちになりたがったし、上級生の誰もが礼子を妹にしたがった。けれど、礼子が心を開いているのは、寿美子ただ一人だった。
佐藤先生から『少女画報』を手渡され、後ろのほうに、小さな自分の名前と自分が書いた作文を見つけたとき、舞台に上がったときのように心がうち震えた。礼子を甘やかす父とのやりとりを書いた短い作文ではあったが、選者の「瑞々しさを湛えた文章のなかに、書き手の思いが重なり、情景が目に浮かぶ」という言葉が礼子を有頂天にさせた。
書きたいことはたくさんあった。子どもの頃に見たサーカスの話、大水で橋が流され怖かった話……。創作でもなく、ましてや小説でもない。人が読めばそれは女学生の作文でしかなかったのかもしれないが、礼子の何かを書きたい、という気持ちには終わりがなかった。『少女画報』に作文が掲載されたことは、父や母には黙っていたが、ある日、礼子が学校から帰ると、店先に山積みの『少女画報』があり、礼子は顔から火が出るような思いをした。
「礼子は顔だけじゃのうて、頭もええけん」
店にやってくる人に、礼子の作文が載った場所を指で示しながら、父は上機嫌だった。母だけは礼子が文章を書いていることに渋い顔をした。夜遅くまで原稿用紙を広げていると、「いつまでがさがさ紙の音を立てよるんね。早う寝んさい」と言って、明かりを消してしまう。思えば、幼い頃から母にはほめられたことはなかった。いつもどこかきつい目で娘である礼子のことを睨んでいる。それでも礼子にとっては、父の愛がありさえすればよかった。
礼子はいつの間にか、広島女学校の小さな文士、と呼ばれるようになっていた。学校の中だけでなく、門のところで礼子の登下校を待ち構えている他校の女生徒や男子生徒もいた。礼子はその誰にも興味はなかった。寿美子に対する気持ち以上のものを誰かに抱いたことはない。芝居や活動写真や文学に登場する、恋、というものがどういうものかもよくわからなかった。
降誕劇でのマリア役、『少女画報』に自分の文章が載ったこと。礼子に憂鬱などあるはずもなかったが、小さな胸のうちは、寿美子が来年の三月にこの学校を去ってしまう、ということで濃い灰色の影に染め上げられていた。
「お姉様、来年になったら会えんようになるんじゃね……本当に東京に行ってしまうん?」
「…………」
幾度となく礼子がそう尋ねても、寿美子は黙ったまま曖昧に笑みを浮かべるだけだった。
「ごめんなさい……」
「ううん、いいんよ。……でも礼子さんは本当に素晴らしいわ。礼子さんには文章の才があるんよ。あなたなら、本当に女文士になれると思うよ」
そう寿美子に言われて礼子は戸惑った。文章を書くことは確かに人よりも上手だ。書け、と言われればいくらでも何枚でも書くことができた。けれど、本当に自分のなりたいものは……。日常生活の些細なことでも寿美子に話していた礼子だったが、女優になりたい、という夢のことはどうしても話すことができなかった。そのことが苦しかった。それ以外のことはどんなことでも寿美子に話した。それなのに、こんなにも心を開いている寿美子と離れる日がやがて来る。それを想像すると、礼子は子どものように泣きたくなった。そして、礼子の胸の内側だけにあった灰色の憂鬱が、礼子自身の人生にも影を落とすようになるまで、それほど時間はかからなかった。
凪だった礼子の人生に波乱が起こり始めたのは、礼子が十四の誕生日を迎え、年が明け、松飾りもとれぬうちのことだった。夕餉前のいつもの父との散歩。帰り道、いつもの菓子屋に寄った。
「これが大好きなんじゃ」そう言って菓子屋の店員からジェリービーンズの入った紙袋を受け取った父の体が大きく揺らいだ。礼子が支える隙もなく、父は天を仰いで、菓子屋の店内に倒れ込んだ。桃色や水色、黄色、色とりどりのジェリービーンズが父の体のまわりに散らばった。
「お父様! お父様!」
礼子が声をかけても父は目を見開いたまま返事をしない。
機転を利かした菓子屋の店員が礼子の家まで人を呼びに行ってくれた。そこから先の礼子の記憶は
不幸はそれだけで終わらなかった。ある日、礼子が女学校から帰り、仏壇のある部屋に行くと、畳から浮かびあがった足袋の裏が見えた。父の死を嘆き悲しんだ母が鴨居に着物のしごきを結び、首をつったのだった。
「誰か! 誰か!」
礼子のただならぬ声に、家の使用人たちがばたばたと足音をたててやってきて、母の体を引き摺り降ろした。
幸い、命に別状はなかったが、元々神経質だった母の精神状態が悪化した。夕餉の時間になると、そこにはいないはずの父に声をかけたり、酒の徳利を傾けたりする。どこだかわからない場所を見つめては、笑みを浮かべたり、涙を浮かべたりもした。そんな母の首に残った赤黒い紐の痕を見るたび、礼子の胸はきしんだ。
父亡き後、父が一代で築いた種苗問屋は、妻を亡くし、子どももいない父の兄が引き継ぐこととなった。礼子の保護者もこの伯父がとって代わった。母の精神の病状は日ごとに悪くなり、伯父の一存で母は実家に帰されることとなった。実家へ戻される日、人力車に乗せられた母は礼子の顔を見て、ただ笑っていた。その顔が礼子は怖かった。母と心が通じ合っていた、とは言えないが、同じ時期に父と母の二人を失った礼子の悲しみは深かった。伯父は父とは違い厳しい人だった。そして礼子を自らの所有物のように扱った。
「女学校だけは出しちゃるが……」
礼子の顔を見ればそう言った。
父は自由な好事家だったが伯父は違った。礼子が本を読んでいるのを見ると、「女だてらにそがあなものを」そう言って本を取りあげた。活動写真館に行くことなど夢のまた夢だった。人力車で学校に行くことも禁止された。家と女学校の往復。それが礼子の日常になった。伯父は常に礼子の生活に目を光らせていた。その執着ぶりが、伯父という存在を超えているようにも思えて怖しかった。伯父の目を盗んで行った本屋の店先で見た演劇雑誌で、松井須磨子が恋仲だった島村抱月のあとを追って自死したことを知った。母がはかったのと同じ縊死だった。あの大女優がなぜ、と思わずにはいられなかった。「悪魔! 悪魔!」とカチューシャになりきって叫んだあの人ももうこの世にはいない。自分のまわりの空気が、父が生きていた時代とは異なり、日々、重さを孕んでいくことを感じずにはいられなかった。
女学校に行けば、礼子はそれまでと変わらず人気者だったが、廊下を一人歩いていると、今まで感じたことのないような視線に気づくことも多くなった。靴箱に入っている手紙も、そのほとんどは父を亡くした礼子の悲しみを慰めるものだったが、どんな励ましの言葉も礼子の心には届かなかった。ある日、校門を抜けた礼子の耳に、どこからか「首つりの……」という言葉が聞こえてきて、その場にしゃがみ込んで泣きたくなった。
唯一、穏やかな気持ちで過ごせるのは、放課後の礼拝堂、寿美子との時間だった。礼子は寿美子の腕のなかでだけ、心おきなく泣くことができた。けれど、その寿美子も、もうすぐこの学校からいなくなってしまう。
寿美子が女学校を出たあと、結婚をして九州に行ってしまうことを礼子は生徒たちの噂話で耳にした。けれど、寿美子は礼子にそのことを話さなかったし、礼子も寿美子に尋ねようとはしなかった。事実を確かめて、それが本当のことになってしまうのが怖かった。礼子は寿美子に会えばその腕のなかで泣いた。寿美子は泣いている礼子の髪をただ黙って撫でてくれる。その優しい仕草に父を思い出し、礼子はまた泣いた。本も読めないし、活動写真も見られない、そう言って礼子は泣き続けた。
「礼子さん、けど、作文を忘れちゃあだめよ。あなたには才があるんじゃから。この先、どんなことがあってもそのことを忘れちゃあだめよ」
父が亡くなってからというもの作文など書く気にはなれなかった。一度、父が亡くなったときのことを書こうとしたことがあったが、涙が溢れるばかりで一文字も書き進めることができなかった。いままで体験したことのなかった憂鬱が礼子の胸を暗い色に染めていった。
ある日の礼拝堂で思わず礼子は尋ねた。
「礼子はお姉様と別れたくないんです。お姉様、女学校を出たらお嫁にいくんでしょう?」
「…………」
寿美子は目を伏せたまま何も言わない。礼子は寿美子の言葉を待った。言えない事情があるのだとわかってはいても、その問いが寿美子を困らせることになるとわかってはいても、礼子は言葉にせずにはいられなかった。寿美子が苦しげに口を開く。
「もう、そうするしか私には生きる道がないんよ。医者になるなんて、私には大きすぎる夢じゃった……私には最初から無理じゃったんよ……」
「そんな……」
寿美子が男だったら、寿美子が東京に生まれていれば、いくつもの「もし」が礼子の頭の中に浮かぶ。けれど、そんなことはすでに寿美子は何万回も考えたはずだ。悔しくはないのだろうか。いや、悔しくないわけがない。目の前の寿美子は泣き笑いのような顔で、礼子を見ている。そこには、どこか自分の夢をあきらめた者の恥の感覚も含まれているような気がして堪らなかった。
礼子は寿美子の手をとり、両手の手のひらで温めるように
「そうじゃ、礼子さん、私の父は物産陳列館に勤めとるでしょう。そこで今度、工芸品展覧会があるんよ。そこで食べたことのない舶来のお菓子も出るんよ。私と一緒に行ってみん? 礼子さんの伯父様には、外出できるように私から頼んであげる」
礼子の頭に陳列館の丸いドームが浮かんだ。陳列館は煉瓦と鉄筋コンクリートでできた三階建て、塔屋には楕円形のドームが乗っていて、その壁の白さから「白亜の摩天楼」と呼ばれていた。礼子も父と共に幾度か行ったことがある。陳列館に行くときにはいつも心が弾んだ。これからの広島には、これからの日本には、こんな西洋建築がいくつも建って、西洋の国にひけをとらない国になる。礼子は心からそう信じていた。
「えっ、ほんま? お姉様、ほんま?」
「礼子さんはお菓子がお好きでしょう?」
こくりと礼子は頷いた。
その日、寿美子は礼子と共に礼子の家に寄り、伯父に日曜日の外出許可をとってくれた。いつもは苦虫を噛み潰したような顔をしている伯父も、寿美子の丁重な物腰にあっさりと許可を出してくれた。
日曜日の午後、迎えにきた寿美子と共に礼子は陳列館に向かった。
「ドイツのおいしいお菓子があるんよ」
陳列館の内部はたくさんの人で溢れていた。礼子が迷子にならないように寿美子は手を繋いでくれる。寿美子に導かれるまま、礼子は足を進めた。どこからか漂ってくる甘い香りが礼子の鼻をくすぐる。棚には、
「ここよ」寿美子の足が止まる。
たくさんの人が列に並んでいる。すぐそばで、白い調理服を着た白人が(それは第一次世界大戦中に中国の
「外で食べましょうね」
やっと順番が来て、その不思議なお菓子が乗った皿を受け取ると、寿美子は礼子を陳列館の庭に誘った。庭のまわりには生け垣ではなくお茶の木が、その脇には松葉牡丹が植えられ、どこか日本ではないような雰囲気がその場所には漂っていた。
椅子を二つ見つけ、寿美子が礼子を座らせる。
「ほら、食べてみんちゃい」
寿美子は口をつけず、礼子がその不思議なお菓子を口に入れるのをじっと見守っている。焼き色をつけた部分が輪を作って、切り口はまるで年輪のように見えた。寿美子に言われるまま礼子はお菓子を一口、口に入れた。

「おいしい……」
思わず礼子は言った。バターの甘い香りが鼻に抜ける。もっとふわふわとした雲のようなお菓子だと思っていたのに、ずっしりとして食べ応えがある。それでも、礼子は瞬く間に一切れを食べてしまった。その様子がおかしいのか寿美子は言った。
「私の分も食べんちゃいや、ね」そう言いながら寿美子が自分の皿を差し出す。そんな寿美子を見つめる礼子の目にみるみるうちに涙が溜まった。父のことを思い出したからだ。こんなにおいしいお菓子を甘いものが好きだった父にも食べさせてあげたかった。それに、こんなふうに自分に優しくしてくれる寿美子も、もうすぐ自分のそばからいなくなってしまう。そう思ったら、涙が止まらなくなった。
「まあ、礼子さん……」
寿美子がハンカチを手に礼子の涙を拭った。
「お姉様、本当に遠くにお嫁に行ってしまうん?」思いきって礼子は尋ねた。
「もう会えんようになってしまうん、私たち……」
寿美子は礼子にとって姉であり母であり、いや、それ以上に大事な人だった。寿美子はしばらくの間、礼子の顔を見て黙っていたが、ゆっくりと口を開いた。
「親が決めたことじゃから仕方がないよね」
「でも、お姉様、本当はお医者様になりたいんでしょう? もっともっと勉強がしたいんでしょう?」
寿美子は黙ったまま礼子の顔を見つめている。もう夕暮れだわ……と礼子が思う間もなく、陳列館全体を飾る照明に灯りがついた。礼子と寿美子のまわりで談笑していた人たちも、家路を急いだのか、もう誰もいなかった。
「礼子さんは文士になりんさいね」
「いいえ、私、文士になんかなりたくない」
「じゃあ、何に?」
「…………」礼子は言い淀んだ。それでも言った。
「お姉様、私、女優になりたいんよ」
「まあ……」そう言う寿美子の瞳を礼子は見た。濡れた黒曜石のような瞳。この瞳に幾度助けられてきただろう。その寿美子の瞳に泣いている自分が映っている。父も母もいなくなった。そして、寿美子が遠くにお嫁に行ってしまえば、もう会えることもないだろう。だからこそ、誰にも言えない自分の秘密を寿美子に共有してほしかった。寿美子が礼子の手をとる。
「礼子さんならきっとなれると思うよ。……でもそれじゃあ広島におったらだめじゃね。東京に……そう礼子さん、東京にお行きなさい」
「でも、どうやって……」
「じっと待つんよ。機が熟すのをじっと待つんよ。自分は絶対に東京に行くんじゃと、心に決めるんよ。私のようにあきらめちゃだめよ。……親のため、とか、女だてらに、とか、そんな言葉に気持ちを挫かれちゃだめ」
そう言って寿美子は礼子の手を握った。親のため、という足かせはもう礼子にはないはずだが、自分にあれほど執着している伯父が礼子を易々と手放して、東京に行かせるなどということに納得するとは思えなかった。「女学校だけは出しちゃるが……」という言葉の続きを考えると礼子の胸は憂鬱で塞がれた。自分も、寿美子やほかの生徒と同じように、気に染まぬ結婚をし、良妻賢母を求められる日々がいつか来るのだろうか。それはそう遠くもない未来だった。結婚などまだ遠い出来事のように思えるが、女学校の卒業までにはあと二年しかない。瞬く間に時間は去ってしまうだろう。
むくむくと湧き上がる不安な気持ちが礼子の表情を暗くしていた。また、涙が湧いてくる。泣くまい、と思っても涙はとどまることを知らない。寿美子が礼子の顔を覗き込む。一筋、礼子の頬に流れた涙に、寿美子が指で触れた。礼子の胸は張り裂けてしまいそうだった。陳列館を飾る灯りが寿美子の白い頬を照らしている。お姉様、お姉様、そう言いながら、礼子は寿美子の胸に飛びこんだ。いつもと同じ菫の香りがする。もうこの香りからも遠く離れてしまう。そう思って礼子は泣いた。礼子の額のあたりがあたたかいもので濡れた。顔を上げると、寿美子も泣いていた。
「本当は……親の決めた相手と結婚なんかしとうはないんよ。顔だって見たことはないんよ。どんな人なんかもわからん」
そう言って子どものように寿美子は泣いた。寿美子が礼子の腕をとった。
「礼子さんは私のようになっちゃだめ。新しい時代の、新しい女におなりなさい」
「新しい、女……」
もちろん礼子はその言葉を知っていた。平塚らいてうや伊藤野枝らの女流文学者が主張した、近代的自我に目覚めた進歩的な女性のことであることを。らいてうが『
「自由に恋をして、やりたいことをなんでもやるんよ。男や親の目など気にせず、やりたいことをやりんさい。親に結婚なんか無理強いさせんと、あなたが男の人を選んだっていいんよ。礼子さん、あなたならできる」
「私はお姉様が好きなんです、お姉様のそばを離れとうない」
「そんな子どもみたいなことを言うてはだめよ。礼子さんは私にとって妹のような存在じゃった。私を姉のように慕ってくれて本当にうれしかった。これからどこに行っても私は礼子さんのことを忘れはせんからね」
礼子はその言葉に胸を切り刻まれるようだった。お姉様とはもう一生会えないかもしれない。自然に礼子の体は動いていた。立ち上がり、寿美子の頬を両手でそっと挟み、その唇を礼子は塞いだ。寿美子が両手で礼子の体を押し返そうとするが、礼子も負けてはいなかった。男の人のことなど、今の私には考えることができない。考えたくもなかった。この世に小説や活動写真で目にするような恋、というものが存在するのなら、それは今、寿美子に向かって奔流のように流れる気持ち、ただそれだけなのだ。
礼子が寿美子から体を離すと、寿美子が驚いた顔で礼子を見つめている。
「礼子さん……」
寿美子は立ち上がり、後ずさりした。
寿美子の膝から、小さく折り畳まれたハンカチが落ちた。
「私は、あなたが怖い……こんなことしちゃあいけん。あなたはなんと恐ろしい人なんじゃろうか」
寿美子は青ざめた顔でそう言い残し、礼子のそばを離れ、庭園を駆けだして行く。
礼子は寿美子から放たれた言葉に身動きがとれなくなった。寿美子の後ろ姿は段々と小さくなり、やがて闇に溶けて見えなくなった。
大好きなお姉様に嫌われてしまった。そう思ったらまた涙が溢れた。それ以上に、寿美子にくちづけをした自分自身に驚いていた。お姉様は生まれて初めて好きになった人だ。だから触れたかった。ただ、それだけの気持ちだった。寿美子を前にして、自分のなかから怪物のようなものが飛び出してきた、と礼子は思った。自分のしでかした事に足が震えた。恋をすると抑制がきかなくなる自分に、礼子は生まれて初めて対峙したのだ。それと同時に、なぜだかそんな自分に対して笑いがこみ上げてきた。
泣きながら、礼子は乾いた声で一人、笑った。
礼子は寿美子が落としていったハンカチを手に取り、それに鼻を埋めた。大好きなお姉様の菫の香り。お姉様のことが愛しい。けれど、私はお姉様のように、親の決めた相手と、ただ流されるように結婚などするものか。ハンカチを手に握りしめながら、礼子は心に誓った。さっき寿美子が口にした町の名が頭に浮かんだ。そう、東京。私はなんとしても東京に行かねばならない。広島のあの家にいたのでは、未来はない。
東京に行って女優になるのだ。礼子はそう心に決めた。
すっかり暗くなった元安川の川面に、一羽の

陳列館の形の白い照明が川面にうつる。てっぺんにあるドームの丸い形の灯が、波に揺られて、川面に不思議な模様を作っていた。寿美子がさっき放った、新しい女、恐ろしい人、という言葉が礼子の胸の奥深くに刺さっていた。その言葉は棘のように生涯、礼子の胸に刺さったままで、多くの男や女と出会うたび、皮膚の表面に顔を出したり、また、皮膚の奥深くに隠れたりした。何かをして誰かから
浜鷸は嘴でせわしなく身繕いをすると、再び、暗い空に飛び立っていった。
十四の礼子の人生はまだ始まったばかりだった。