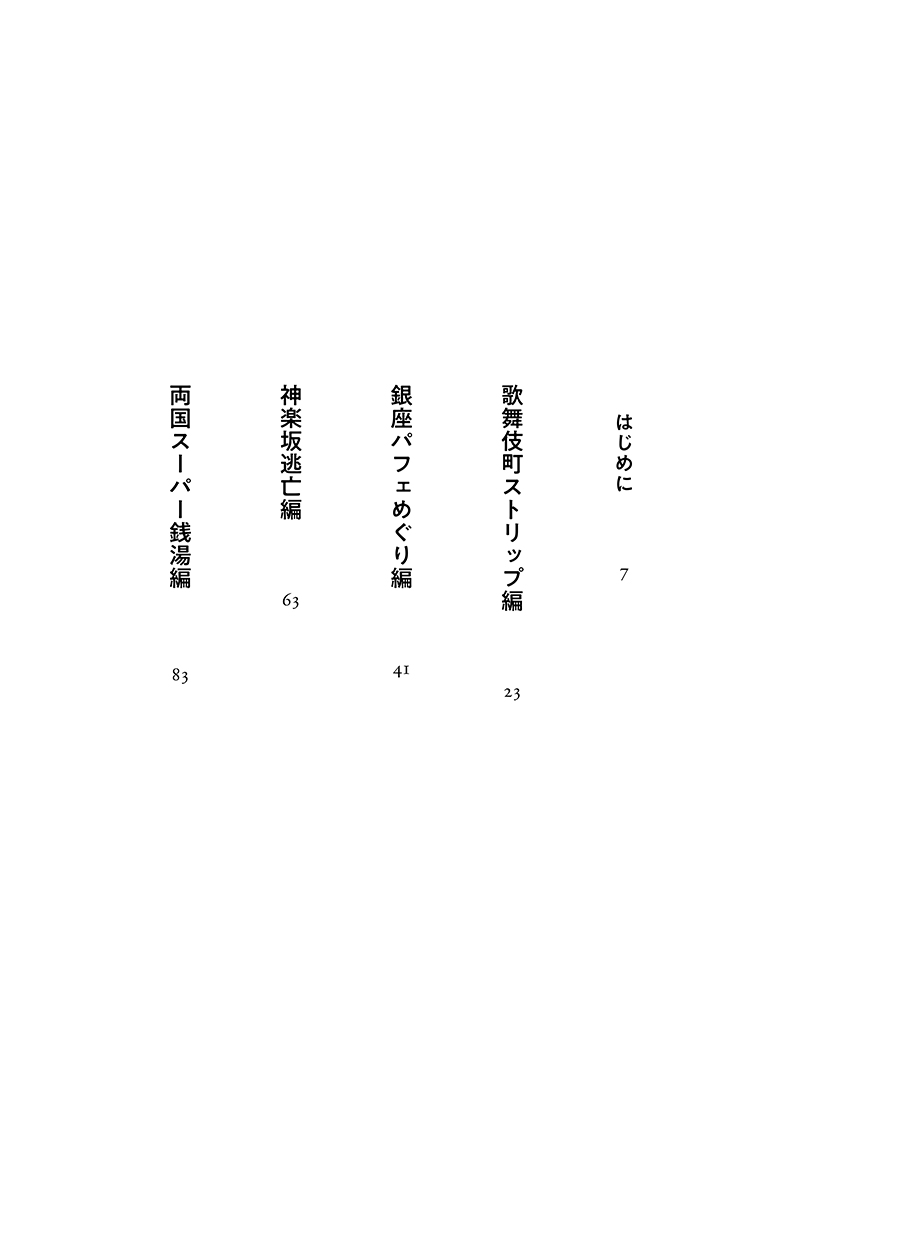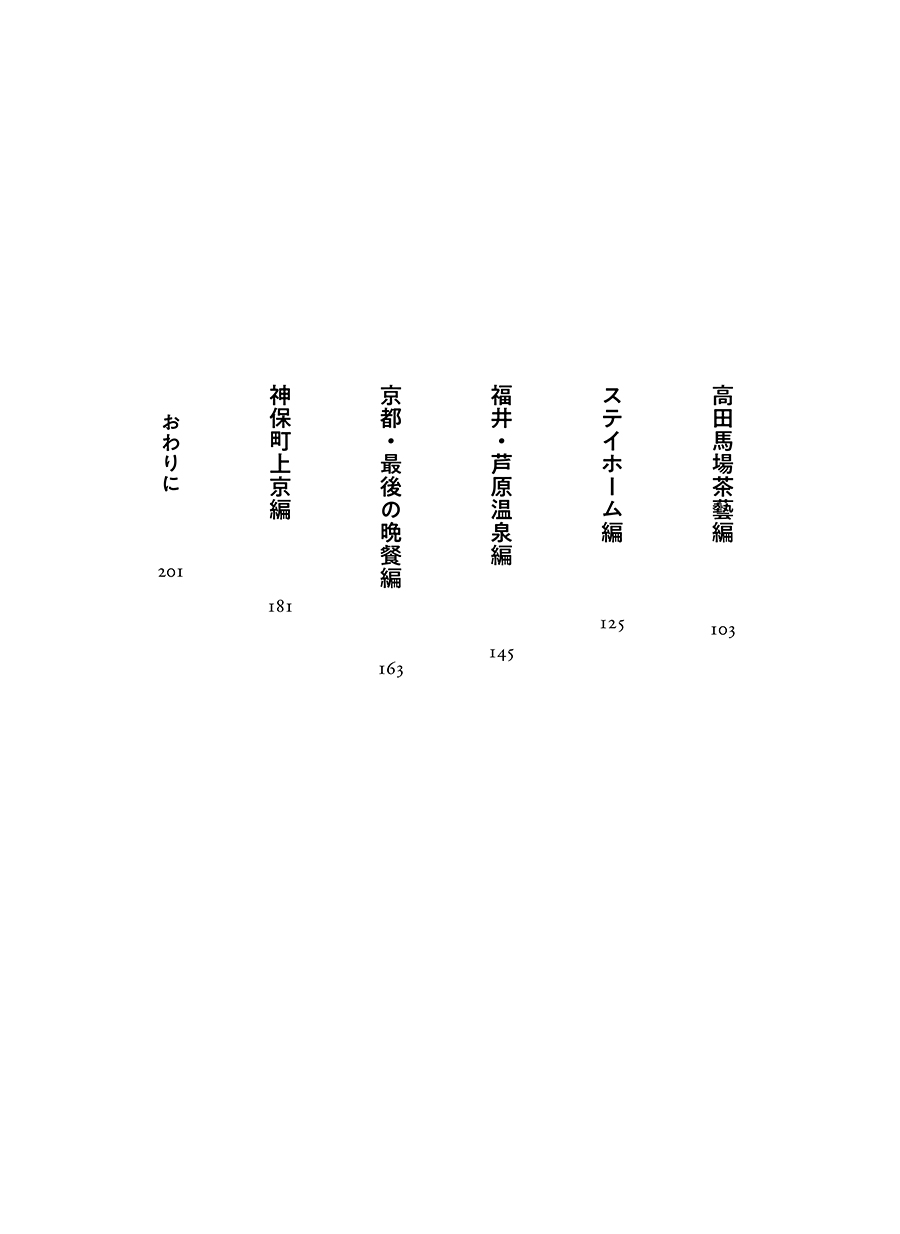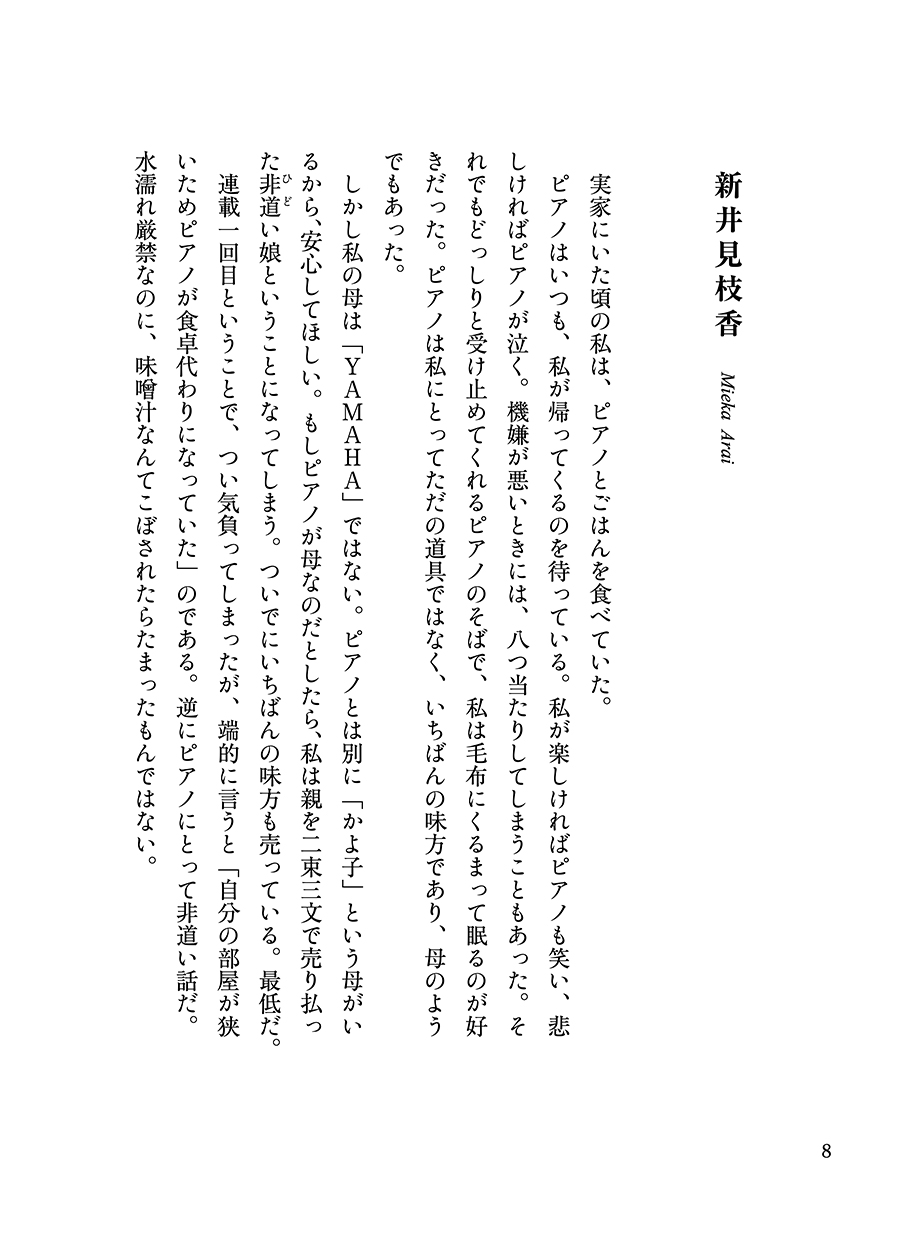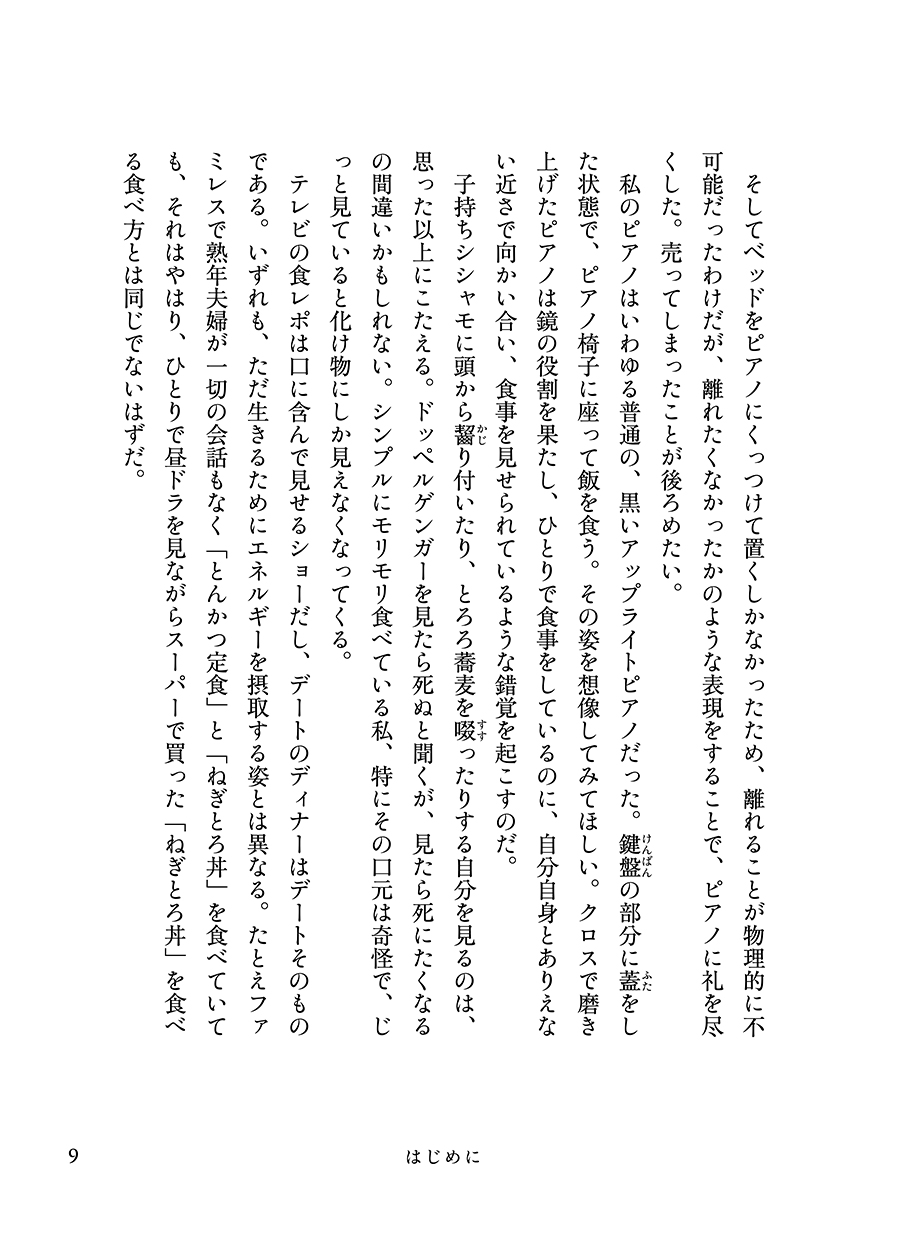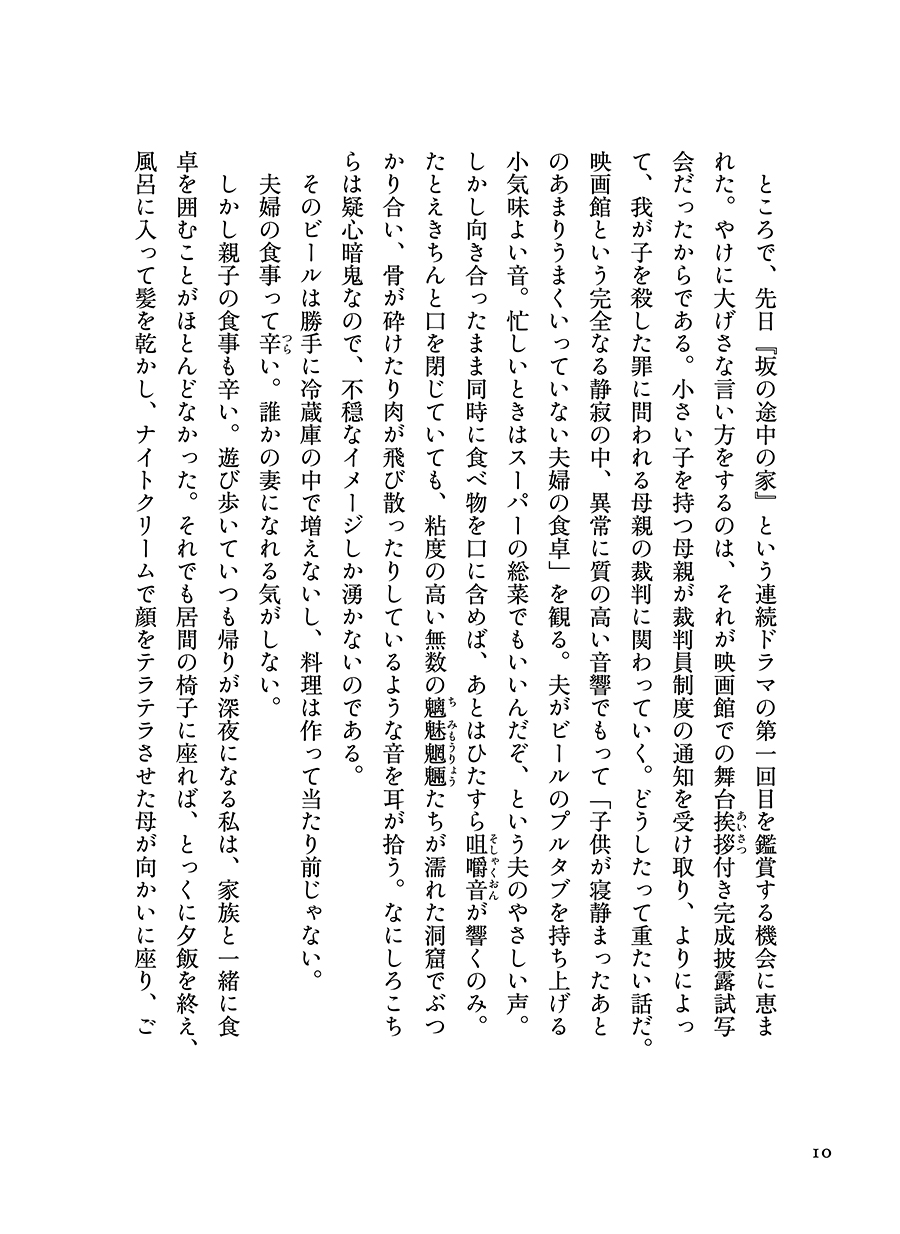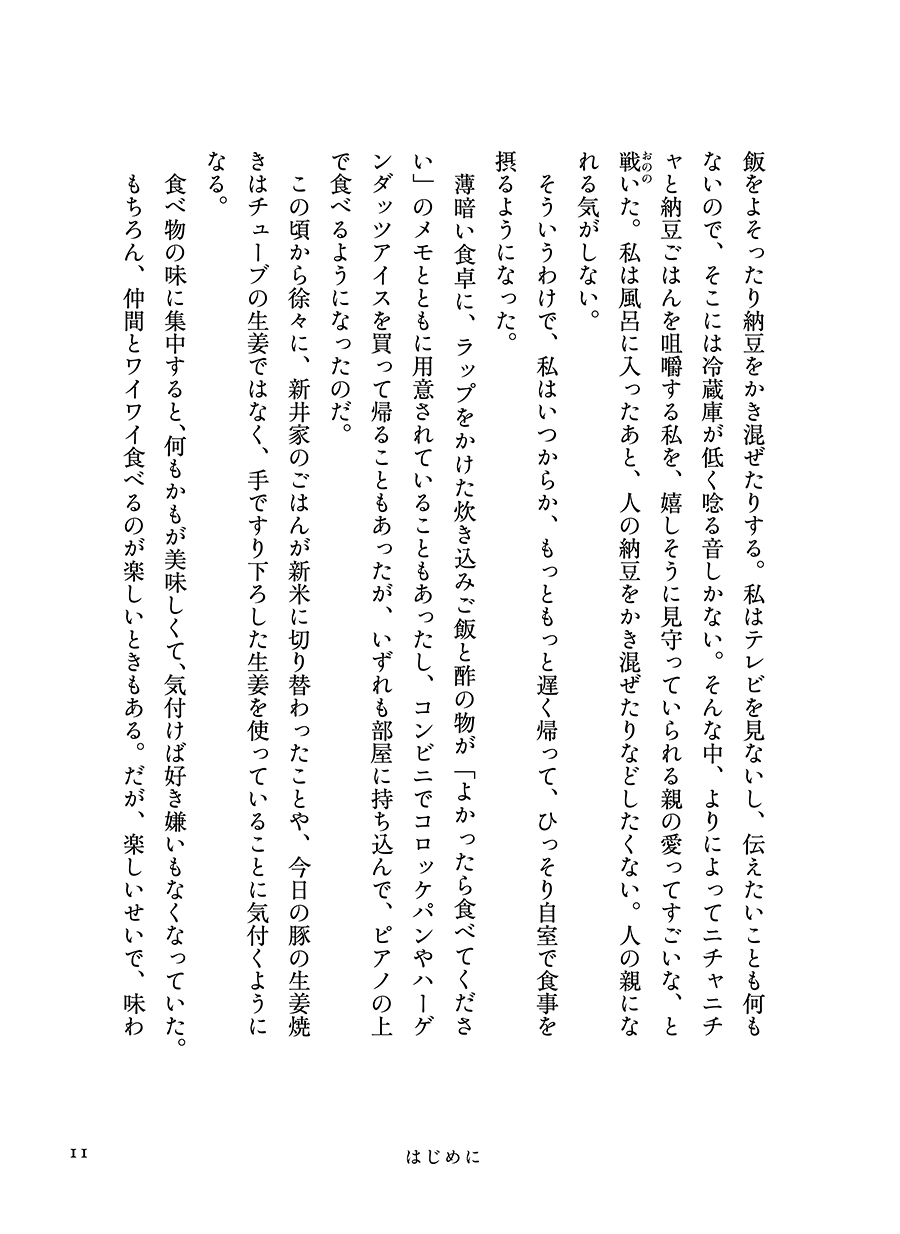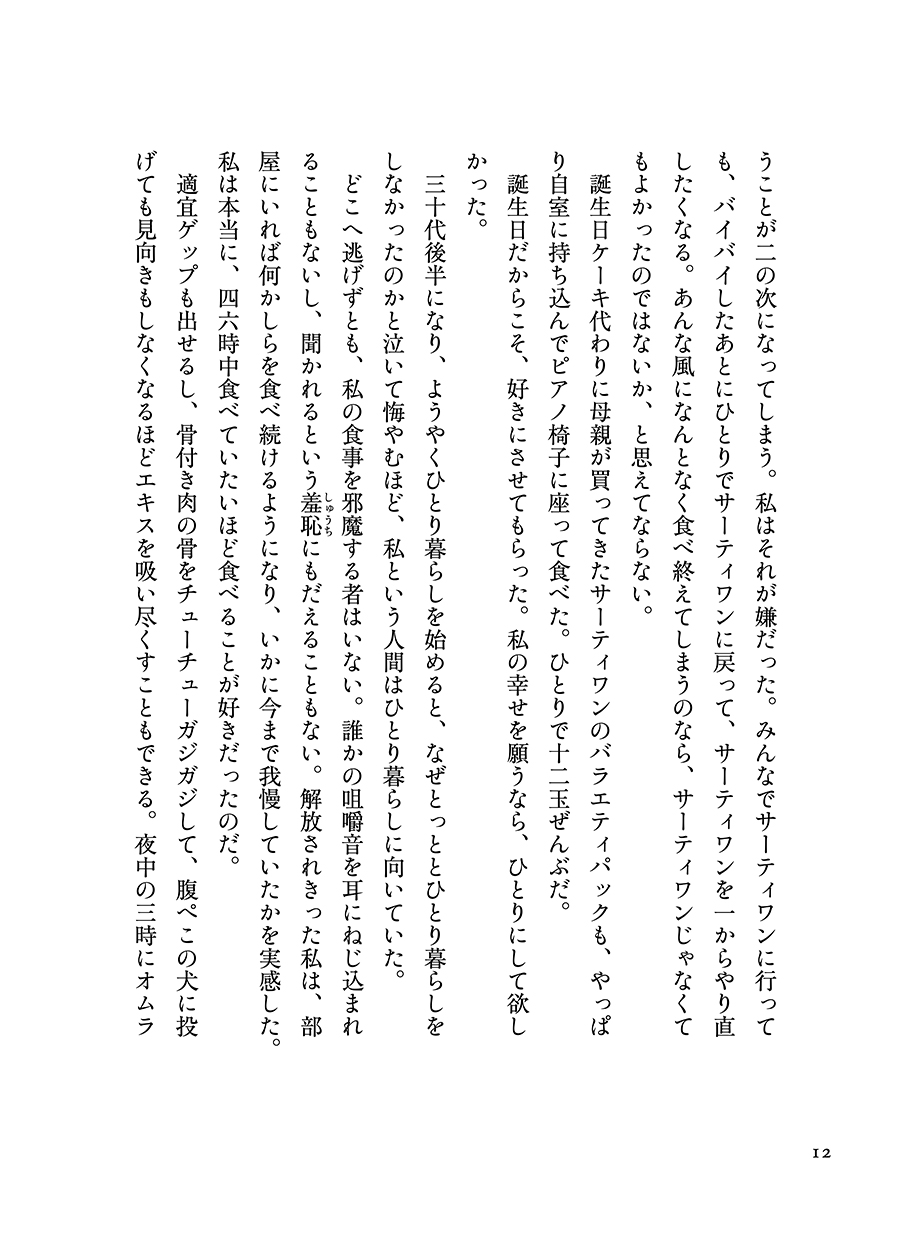はじめに
新井見枝香 Mieka Arai
実家にいた頃の私は、ピアノとごはんを食べていた。
ピアノはいつも、私が帰ってくるのを待っている。私が楽しければピアノも笑い、悲しければピアノが泣く。機嫌が悪いときには、八つ当たりしてしまうこともあった。それでもどっしりと受け止めてくれるピアノのそばで、私は毛布にくるまって眠るのが好きだった。ピアノは私にとってただの道具ではなく、いちばんの味方であり、母のようでもあった。
しかし私の母は「YAMAHA」ではない。ピアノとは別に「かよ子」という母がいるから、安心してほしい。もしピアノが母なのだとしたら、私は親を二束三文で売り払った非道い娘ということになってしまう。ついでにいちばんの味方も売っている。最低だ。
連載一回目ということで、つい気負ってしまったが、端的に言うと「自分の部屋が狭いためピアノが食卓代わりになっていた」のである。逆にピアノにとって非道い話だ。水濡れ厳禁なのに、味噌汁なんてこぼされたらたまったもんではない。
そしてベッドをピアノにくっつけて置くしかなかったため、離れることが物理的に不可能だったわけだが、離れたくなかったかのような表現をすることで、ピアノに礼を尽くした。売ってしまったことが後ろめたい。
私のピアノはいわゆる普通の、黒いアップライトピアノだった。鍵盤の部分に蓋をした状態で、ピアノ椅子に座って飯を食う。その姿を想像してみてほしい。クロスで磨き上げたピアノは鏡の役割を果たし、ひとりで食事をしているのに、自分自身とありえない近さで向かい合い、食事を見せられているような錯覚を起こすのだ。
子持ちシシャモに頭から齧り付いたり、とろろ蕎麦を啜ったりする自分を見るのは、思った以上にこたえる。ドッペルゲンガーを見たら死ぬと聞くが、見たら死にたくなるの間違いかもしれない。シンプルにモリモリ食べている私、特にその口元は奇怪で、じっと見ていると化け物にしか見えなくなってくる。
テレビの食レポは口に含んで見せるショーだし、デートのディナーはデートそのものである。いずれも、ただ生きるためにエネルギーを摂取する姿とは異なる。たとえファミレスで熟年夫婦が一切の会話もなく「とんかつ定食」と「ねぎとろ丼」を食べていても、それはやはり、ひとりで昼ドラを見ながらスーパーで買った「ねぎとろ丼」を食べる食べ方とは同じでないはずだ。
ところで、先日『坂の途中の家』という連続ドラマの第一回目を鑑賞する機会に恵まれた。やけに大げさな言い方をするのは、それが映画館での舞台挨拶付き完成披露試写会だったからである。小さい子を持つ母親が裁判員制度の通知を受け取り、よりによって、我が子を殺した罪に問われる母親の裁判に関わっていく。どうしたって重たい話だ。映画館という完全なる静寂の中、異常に質の高い音響でもって「子供が寝静まったあとのあまりうまくいっていない夫婦の食卓」を観る。夫がビールのプルタブを持ち上げる小気味よい音。忙しいときはスーパーの総菜でもいいんだぞ、という夫のやさしい声。しかし向き合ったまま同時に食べ物を口に含めば、あとはひたすら咀嚼音が響くのみ。たとえきちんと口を閉じていても、粘度の高い無数の魑魅魍魎たちが濡れた洞窟でぶつかり合い、骨が砕けたり肉が飛び散ったりしているような音を耳が拾う。なにしろこちらは疑心暗鬼なので、不穏なイメージしか湧かないのである。
そのビールは勝手に冷蔵庫の中で増えないし、料理は作って当たり前じゃない。
夫婦の食事って辛い。誰かの妻になれる気がしない。
しかし親子の食事も辛い。遊び歩いていつも帰りが深夜になる私は、家族と一緒に食卓を囲むことがほとんどなかった。それでも居間の椅子に座れば、とっくに夕飯を終え、風呂に入って髪を乾かし、ナイトクリームで顔をテラテラさせた母が向かいに座り、ご飯をよそったり納豆をかき混ぜたりする。私はテレビを見ないし、伝えたいことも何もないので、そこには冷蔵庫が低く唸る音しかない。そんな中、よりによってニチャニチャと納豆ごはんを咀嚼する私を、嬉しそうに見守っていられる親の愛ってすごいな、と戦いた。私は風呂に入ったあと、人の納豆をかき混ぜたりなどしたくない。人の親になれる気がしない。
そういうわけで、私はいつからか、もっともっと遅く帰って、ひっそり自室で食事を摂るようになった。
薄暗い食卓に、ラップをかけた炊き込みご飯と酢の物が「よかったら食べてください」のメモとともに用意されていることもあったし、コンビニでコロッケパンやハーゲンダッツアイスを買って帰ることもあったが、いずれも部屋に持ち込んで、ピアノの上で食べるようになったのだ。
この頃から徐々に、新井家のごはんが新米に切り替わったことや、今日の豚の生姜焼きはチューブの生姜ではなく、手ですり下ろした生姜を使っていることに気付くようになる。
食べ物の味に集中すると、何もかもが美味しくて、気付けば好き嫌いもなくなっていた。
もちろん、仲間とワイワイ食べるのが楽しいときもある。だが、楽しいせいで、味わうことが二の次になってしまう。私はそれが嫌だった。みんなでサーティワンに行っても、バイバイしたあとにひとりでサーティワンに戻って、サーティワンを一からやり直したくなる。あんな風になんとなく食べ終えてしまうのなら、サーティワンじゃなくてもよかったのではないか、と思えてならない。
誕生日ケーキ代わりに母親が買ってきたサーティワンのバラエティパックも、やっぱり自室に持ち込んでピアノ椅子に座って食べた。ひとりで十二玉ぜんぶだ。
誕生日だからこそ、好きにさせてもらった。私の幸せを願うなら、ひとりにして欲しかった。
三十代後半になり、ようやくひとり暮らしを始めると、なぜとっととひとり暮らしをしなかったのかと泣いて悔やむほど、私という人間はひとり暮らしに向いていた。
どこへ逃げずとも、私の食事を邪魔する者はいない。誰かの咀嚼音を耳にねじ込まれることもないし、聞かれるという羞恥にもだえることもない。解放されきった私は、部屋にいれば何かしらを食べ続けるようになり、いかに今まで我慢していたかを実感した。私は本当に、四六時中食べていたいほど食べることが好きだったのだ。
適宜ゲップも出せるし、骨付き肉の骨をチューチューガジガジして、腹ぺこの犬に投げても見向きもしなくなるほどエキスを吸い尽くすこともできる。夜中の三時にオムライスを作っても、目が覚めた五秒後にアイスを食べても、誰に言い訳する必要もない。
お行儀を抜きにすれば、いいことずくめである。この小さな塒で私は、魑魅魍魎を口内に飼い慣らす妖怪になったのだ。
そんな頃、私と良く似た妖怪がひょっこり視界に現れた。その感覚は、ドッペルゲンガーの時とはまるで違う。猫がテレビに映った猫から目が離せないように、ただ目が離せなかった。ウニャッニャ。
ふたりで食事をするようになった経緯は覚えていない。ただ、気が合う以上に、胃が合うことが印象的だった。「モンプチ」しか食べられない猫と、「モンプチ」でも猫まんまでも同じ勢いで頭を突っ込む猫とは、どうしたって仲良くはなれない。もちろん我々は、揃って後者だ。いい匂いがすれば、見境がない。
もう何度、一緒に食事をしただろう。彼女と違って、私は記録も記憶もしない。
それでも、確実にわかってきたことがある。
私は、誰かと食事をしているとき、その誰かにも自分と同じくらい、食事に集中してほしかっただけなのだ。同じようなタイミングで息を吐き、ゲフー、とはやらないが、一度くらいは目が合って、うまいね、うん、うまい、と無言で確認し合うくらいでコミュニケーションは十分だ。
こんな連載をするなんて、どれほどベタベタの仲良しなんだと思われるかもしれないが、食事をしているときは、大してお互い話を聞いていない。私も相当だが、彼女の聞いてなさっぷりには、時空が歪んだかと思えるほどだ。私がいることを忘れているような目をすることもある。
そして困ったことに、我々が会えば、ほとんど何かを食べている。なかなか会話ができない。
このエッセイでは、塊肉に興奮してうっかり聞き漏らした話や、パフェとの対話が忙しくてすっかり伝え忘れていた話を綴ってゆければと思っている。
ちはやん、よろしくね!
はじめに
Akane Chihaya 千早 茜
人との関係は食事からはじまることが多いように思う。
友情にしても恋愛にしても、相手を知りたいときはまず食事や飲みに誘うのが一般的なようだ。小説家という仕事のせいか、仕事の話の際も「一度、お茶かお食事でも」という感じで顔合わせをする。生活を共にしていない人との食事には「会いたい」とか「話したい」といった気持ちがもれなくついてきて、それらはときどき飲み物や食べ物の味をなくしてしまう。
私は食べることが好きだ。嗅ぎ、歯や舌でもって味わい、料理人が意図した通りに熱いものは熱いうちに冷たいものは冷たいうちに食べたい。宴会なんかで挨拶や乾杯合戦が続くうちに刺身や生野菜が乾き、鍋が煮つまり、揚げ物の輝きが失われていくのが非常につらい。
いままで一番つらかった外食はテレビ撮影中の飲食で、アナウンサーの女性と喋りながらケーキを食べるというものだった。ケーキは選ばせてもらえた。いつもの習慣通り私は二個選んだが、いざ集中して食べようとすると「質問に答えてください」とスタッフから指示が飛ぶ。自分の小説のインタビューだったので慎重に話していると「ケーキを食べてください」と言われる。ぱくり。「はいっ、目線ください。笑顔で感想を」「……おいしいです」チョコレート系を選んでしまったため、笑うとチョコまみれの前歯を晒してしまいそうでできない。「笑って」と追い打ちをかけてくる。アナウンサーの女性を見ると、切りやすく食べやすいフロマージュ系のムースをしずしずと食べている。なるほど、撮影のときはこういうケーキを選ぶべきなのかと思いつつ、そういう選択ってケーキに対する姿勢としてどうなのかと悩み、ますます混乱する。
結局、なにを選んでも一緒だった。あのときのケーキの味はまったく覚えていないから。ケーキに興味のない人々に囲まれ、指示されながら食べてもまったく美味しくない。ただただ虚しい食だった。ケーキにも職人さんにも失礼なことをした。もう二度とカメラの前で好物を食べないと心に誓った。
ケーキはひとりで食べるのが最良だ。私はメモを取り、一層一層確認しながら食べたいので、そんなときにケーキ以外の話題をふられても対応できない。しかし、人といて「ごめん、いまケーキ食べてるから」と話をさえぎるわけにもいかない。「ケーキと私(もしくは俺)どっちが大事なの!?」と面倒なことになるだろう。ならなくても、空気は悪くなる。
そんなとき、私はよくフロルのことを考えた。フロルとは萩尾望都の名作SF漫画『11人いる!』にでてくる可愛く勇敢な登場人物だ。私が持っている小学館文庫版には「スペース ストリート」という短いおまけ漫画がついていて、その中に「生きるべきか否か」という生存権について登場人物たちが語り合う回がある。極限状態において人肉を食べるか食べないかの議論になり、フロルが言う。
「オレは食わないだろな でもそんな時だれかが食ったとしても気にしないよ」
いいやつだな、とフロルを好きになった。こんな友人がいたら気持ちがいいだろうなと思った。他人の人肉食いを気にしないフロルだ、私がケーキに集中するくらいなんでもないだろう。お互い好きに食べて、好きに生きて、気にしない。それが尊重というものではないか。
そうは思ってもフロルみたいなタイプはなかなかいない。自分がフロルみたいになればいいと思っても、「気にしない」という姿勢は「冷たい」と捉えられることも多く、誤解を生んだ。
そうして、数年が経ち、フロルのような人がふらっと現れた。
彼女は朝の京都駅でアイスを食べていた。日記をつけているので、それが二〇一四年の六月十四日だったことがわかる。当時は彼女のことを「三省堂の新井さん(黒ずくめ)」と書いていた。黒ずくめとは服のことで、それは五年経った今もあまり変わらないが、呼び名は「新井どん」になった。
その日、私は八時半の待ち合わせに数分遅れてしまった。東京の書店員の子たちが京都に観光にくるので、京都在住の私が案内をする予定だった。これからモーニングに行くというのに、新井どんは数メートル離れた場所で『中村藤𠮷本店』のほうじ茶アイスを食べていた。「ちょっと目を離した隙に買いにいっちゃって」と他の書店員の子が説明してくれたが、新井どんは「オレのことは気にしないでくれ」オーラ全開でアイスに集中していた。別に構わない、と思った。行きたいところがあればどこへでも案内するから好きなものを食べて楽しんでくれたらいい。あなたの休日、あなたの胃袋だ。充実してくれることこそが案内役の喜びだ、と口にはださず念を送った。通じたと思う、たぶん。
『イノダコーヒ』でモーニングをして、夕方まで三軒の甘味処と二軒の喫茶店に行き、かき氷、団子、ホットケーキ、卵サンド、ナポリタン、プリン、フレンチトーストなどを食べまくった。移動中も新井どんはふらっと姿を消し、ドーナツやジェラートを買い食いしていた。手に食べ物がなくなると、派手な色の炭酸飲料を自動販売機でがこがこと買って飲みだす。涼しい顔をしてもくもくと飲み食べしている。フロルの精神性を体現している、と目が離せなくなった。
新井どんとは面識があったし、飲み会などで一緒になることもあった。けれど、はじめて意識をしたのがその日だったのだろう。あれから五年、ふたりでしょっちゅう食事に行くようになった今も、私は彼女と食べたものを記録し続けている。これは私の癖のようなもので、気になった人間ができるとその言動を記録してしまう。もちろん誰にも見せない、私だけのメモだ。
新井どんとの食事は楽しい。いつかのイベントで彼女と自分のことを「餌場が同じ野良猫」と言ったことがある。食べたいものや食への姿勢が似ていて、気がついたら同じ食卓を囲んでいる。延々と食べ続けられる。非常に、胃が合う。
けれど、もちろん違うところもある。彼女がなにより愛するかき氷を私の胃腸は受けつけないし、彼女は私のように茶愛好家ではない(じわじわ布教しているが)。
それを大きく実感したのは、一緒に行った台湾旅行でだった。地元の人で混雑した夜市のまんなかで私はフリーズした。わからない言語、嗅いだことのない匂い、人に揉まれながら逃げ場を求めて空を見あげれば、昼間は明るく見えた南国の樹木が夜闇でおどろおどろしく風に揺れていた。赤いランプで照らされた屋台には見たことのない食べ物があふれている。肉か魚か野菜といった大まかな分類しかわからない。なんの肉で、どの部位で、どんな調理がされているのか見当もつかない。お腹は減っているのに、なにも口に入れる気にならなかった。
一方、新井どんは目をきらきらさせて路地に入ったり、店の人と日本語で威勢よくやりとりをして惣菜を買ったりしている。私はあらかじめ調べていた「戚風蛋糕」(シフォンケーキのようなもの)と果物を買ってホテルに退散した。部屋に着くとソファに丸まって旅ノートをひらき、夜市の光景を書き記した。
やがて、「食べた、食べた」と新井どんが戻ってきた。その頃にはだいぶ気分が落ち着いていたので茶を淹れ、一緒におやつを食べた。自分はどうやら食べたいものしか食べられないようだと話した。つまりは知っているものや調べたものしか身体が受け入れない。しかし、彼女は「知らないものを食べたい」と言った。そこは大きな違いだ。
帰国してから、ふと思った。他人も未知の食材のようなものだ。自分とは違うその性質をすこしでも理解するために私は記録というかたちで言語化しようとしているのかもしれない。
そんなことを考えていると、パン大好き「小麦粉野郎」こと担当M嬢が「食いしん坊のおふたりで食エッセイを書きませんか」と声をかけてくれた。ふたりで食べにいったものについて書くという内容で、いくつか場所と食べ物の案をだし合った。担当M嬢の提案は若干、小麦粉方面へと誘導する傾向があったが、まだ行っていない場所や食べていないものがたくさんあがり、二つ返事で引き受けてしまった。
どんなに近くにいても、何千回食事を共にしても、当たり前のことだが同じ人間になるわけではない。それでも、わずかずつ私は彼女に食われているし、私も彼女を食っている気がする。
同じものを食べながら、どれだけ見ている景色が違うのか、またはどこが同じなのか、似てくるのか、変わらないのか、書いていくうちに見えてくれば面白いのではないかと思っている。
そうそう、私はもう彼女がフロルでなくともまったく気にならない。