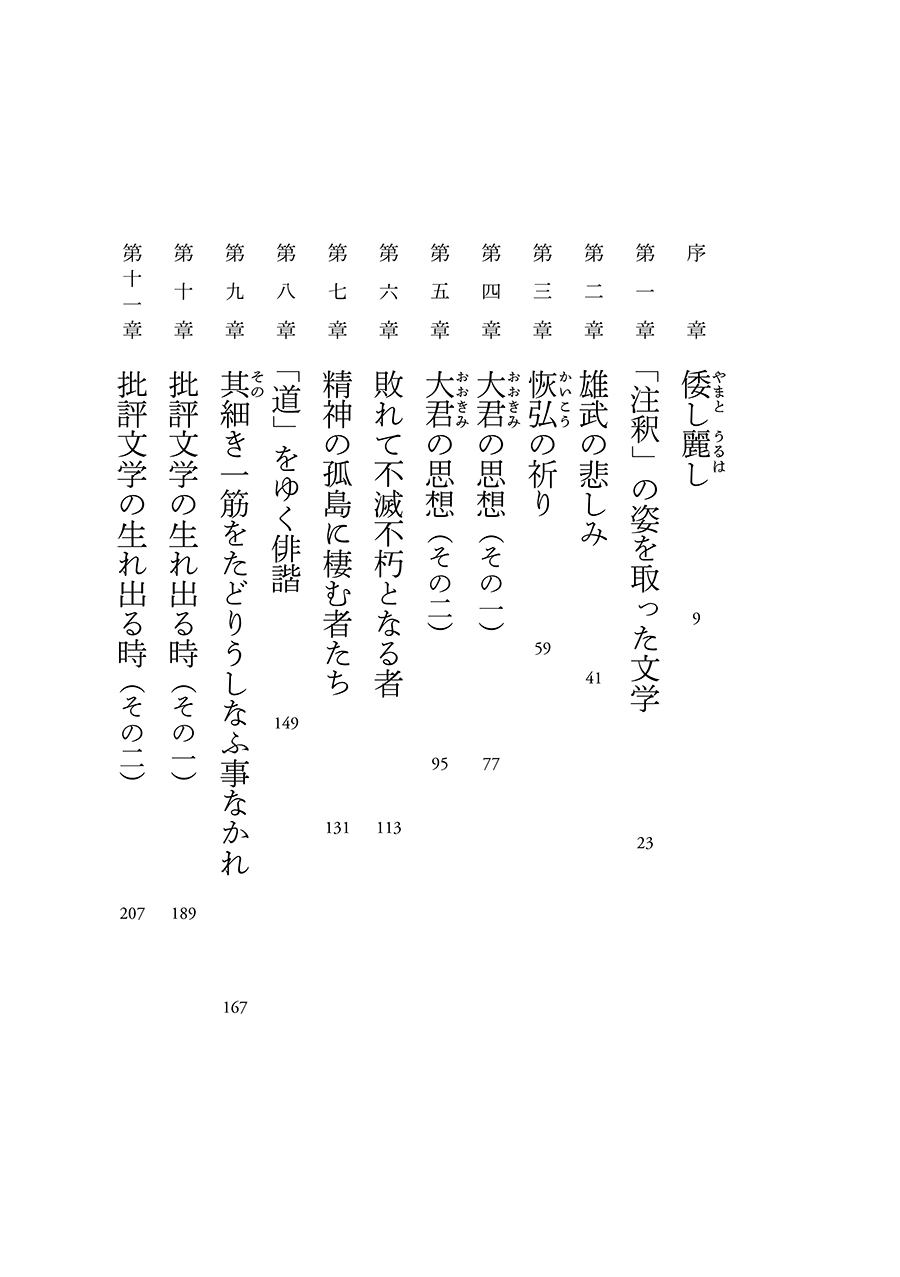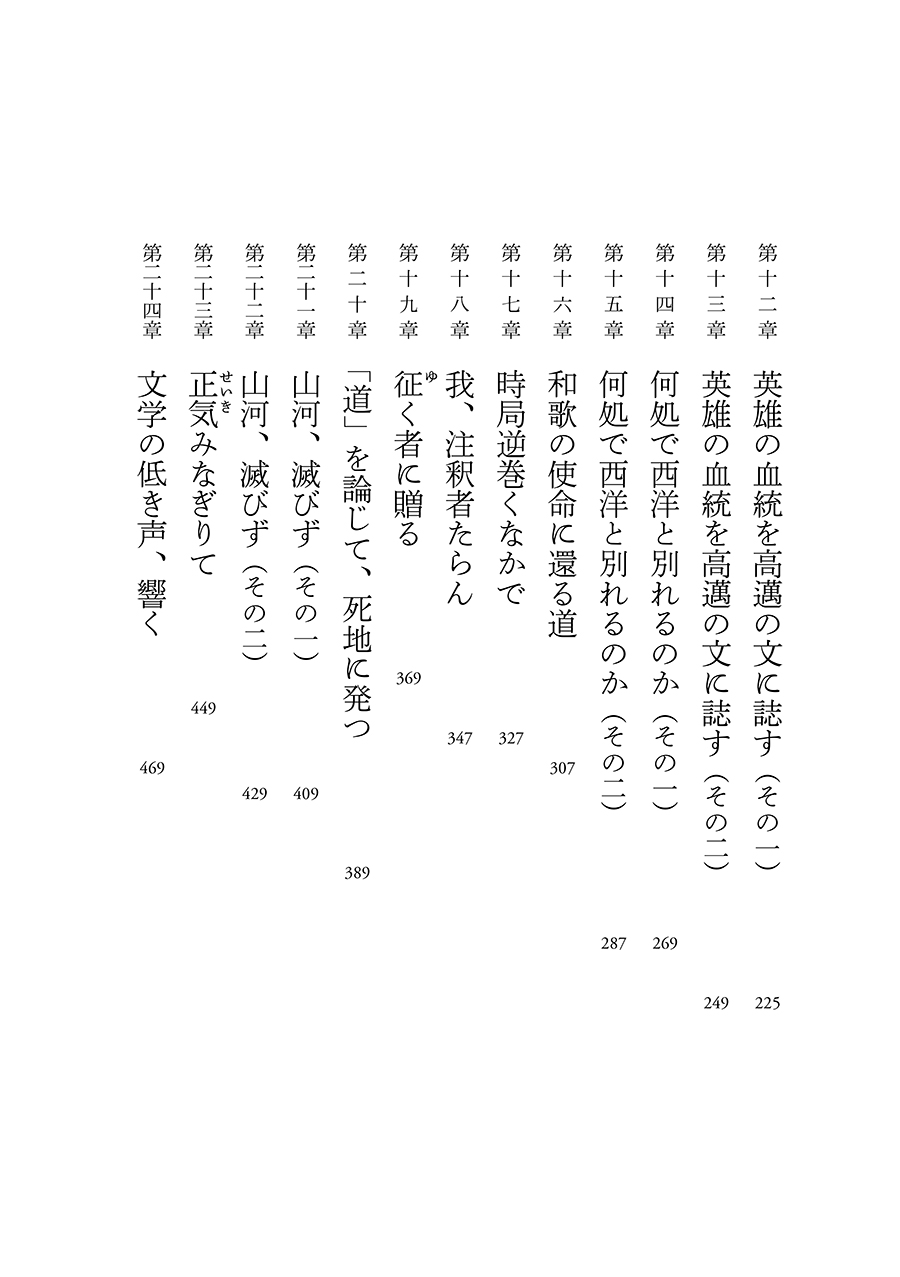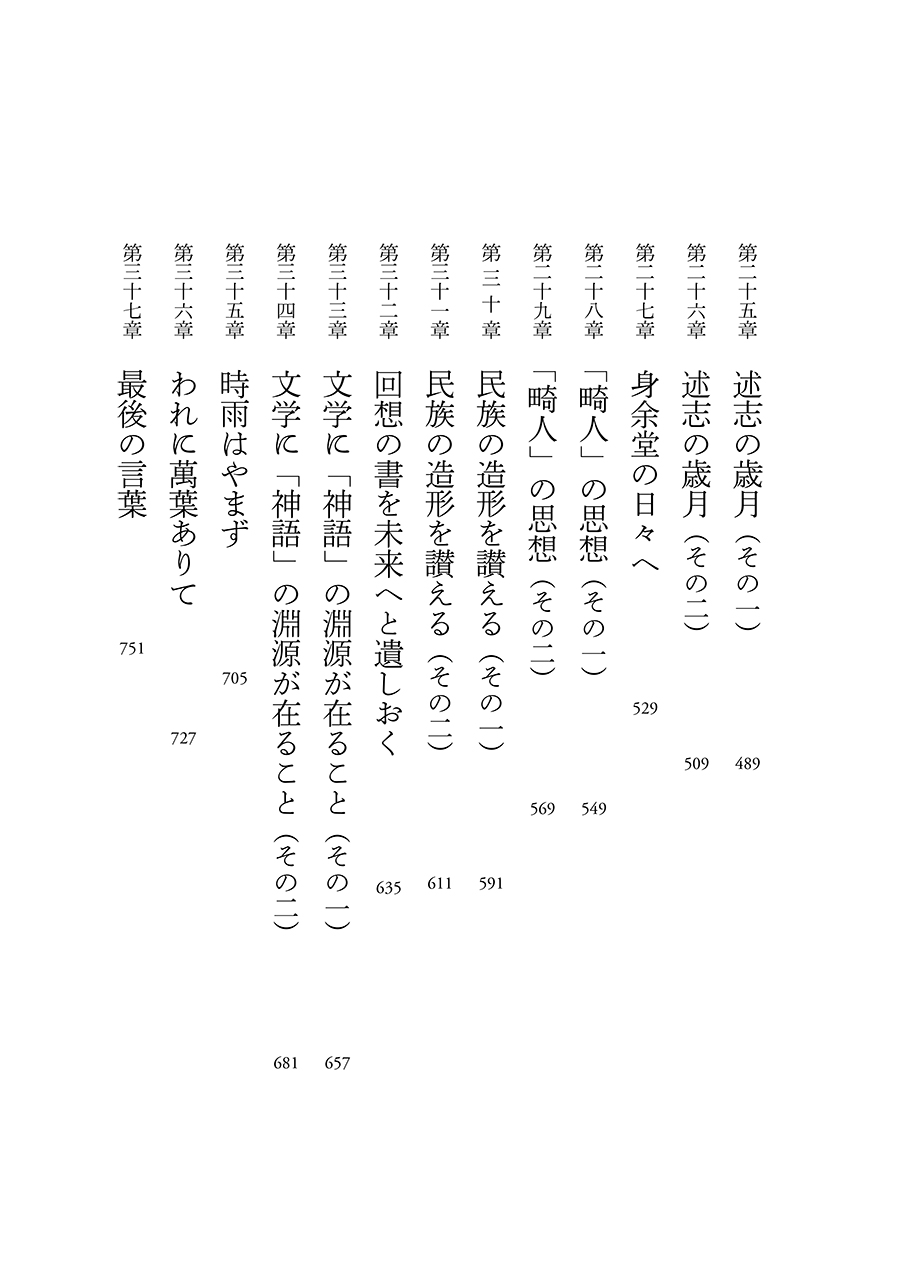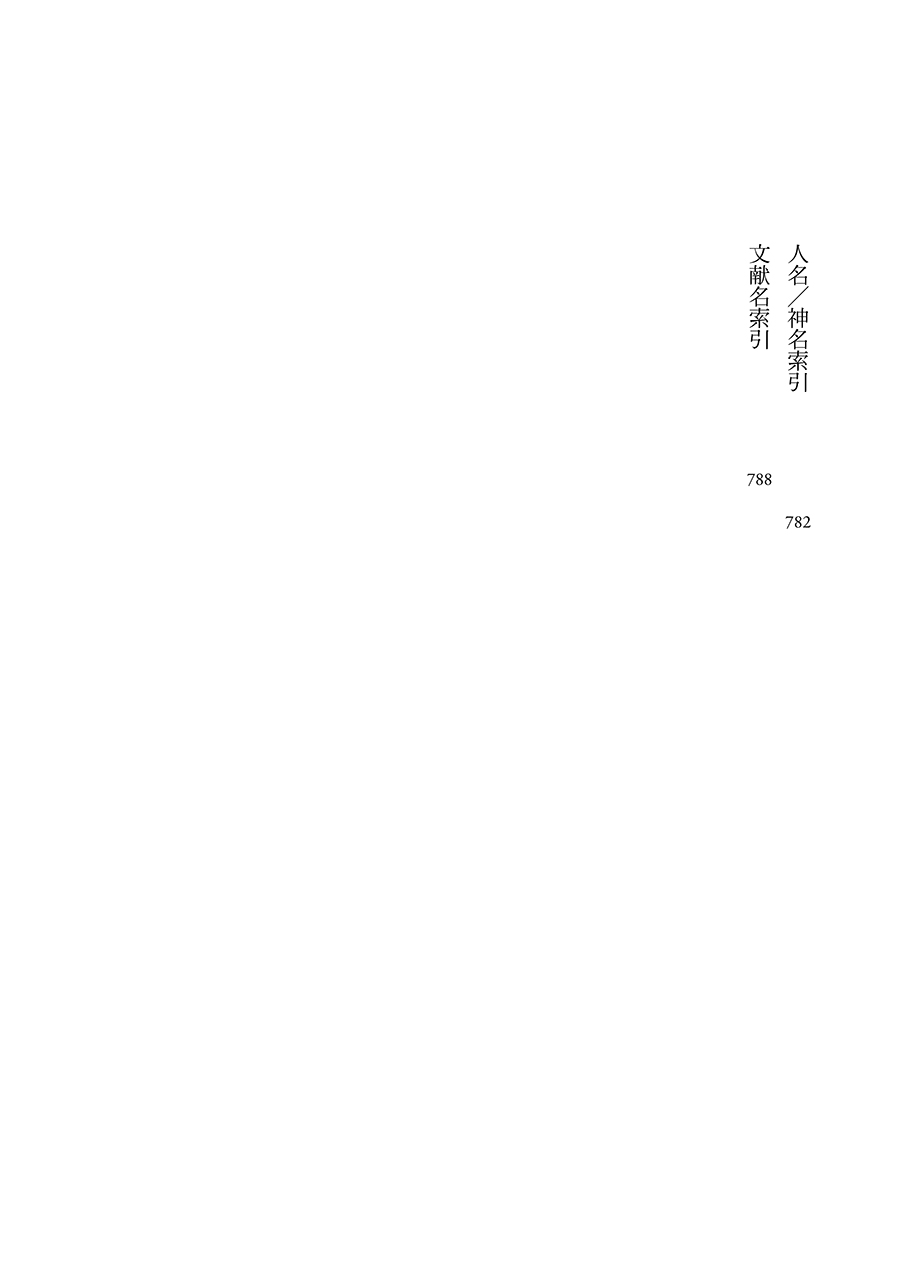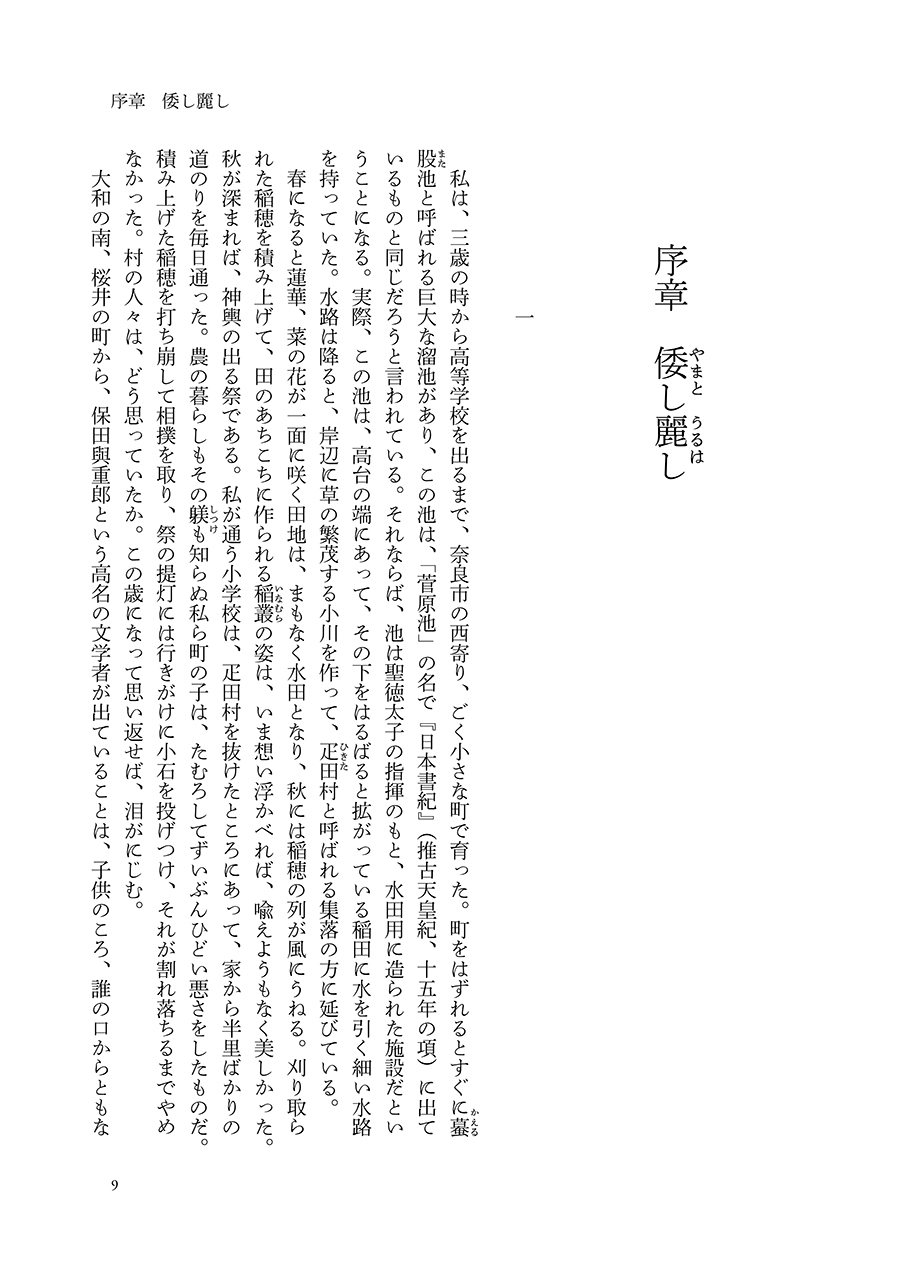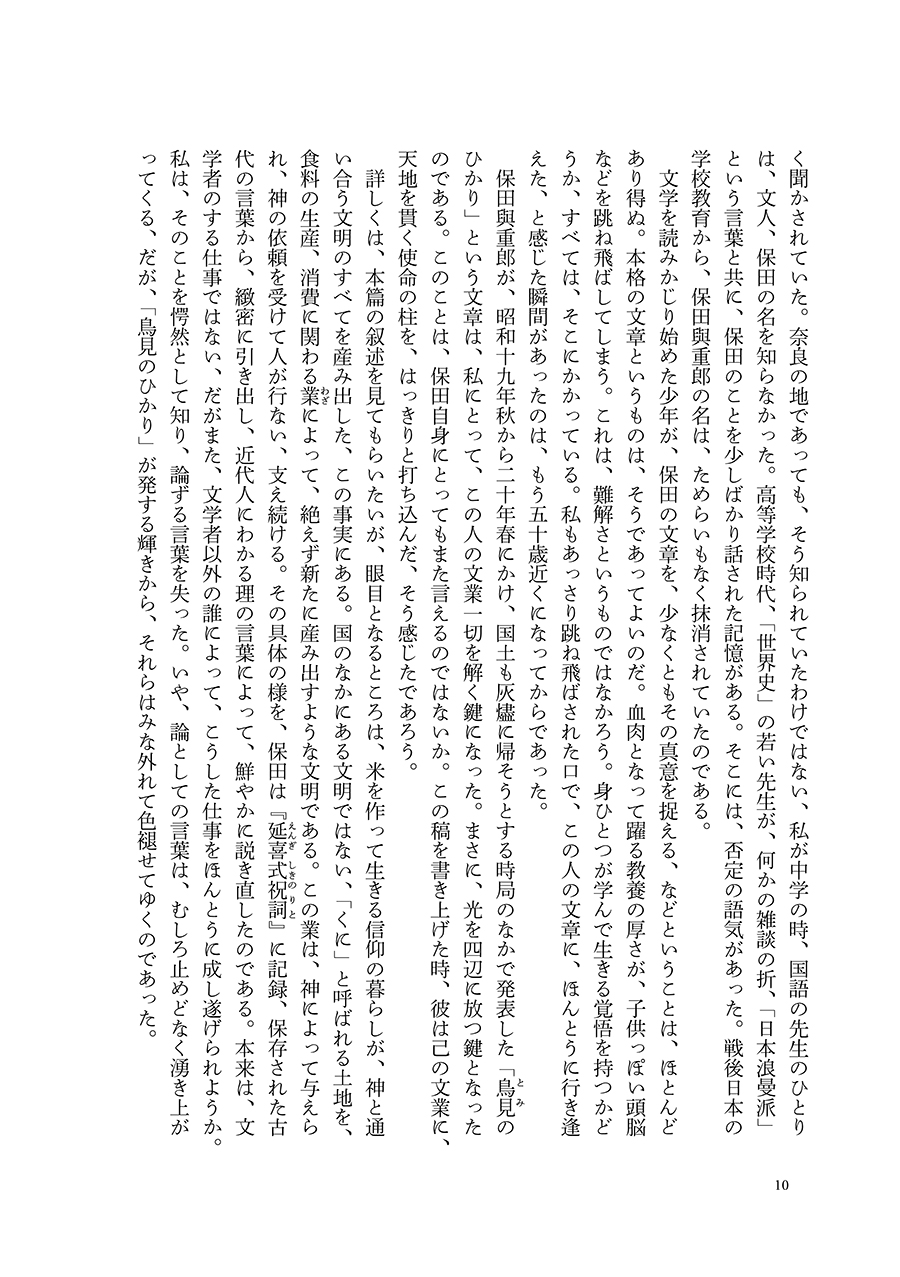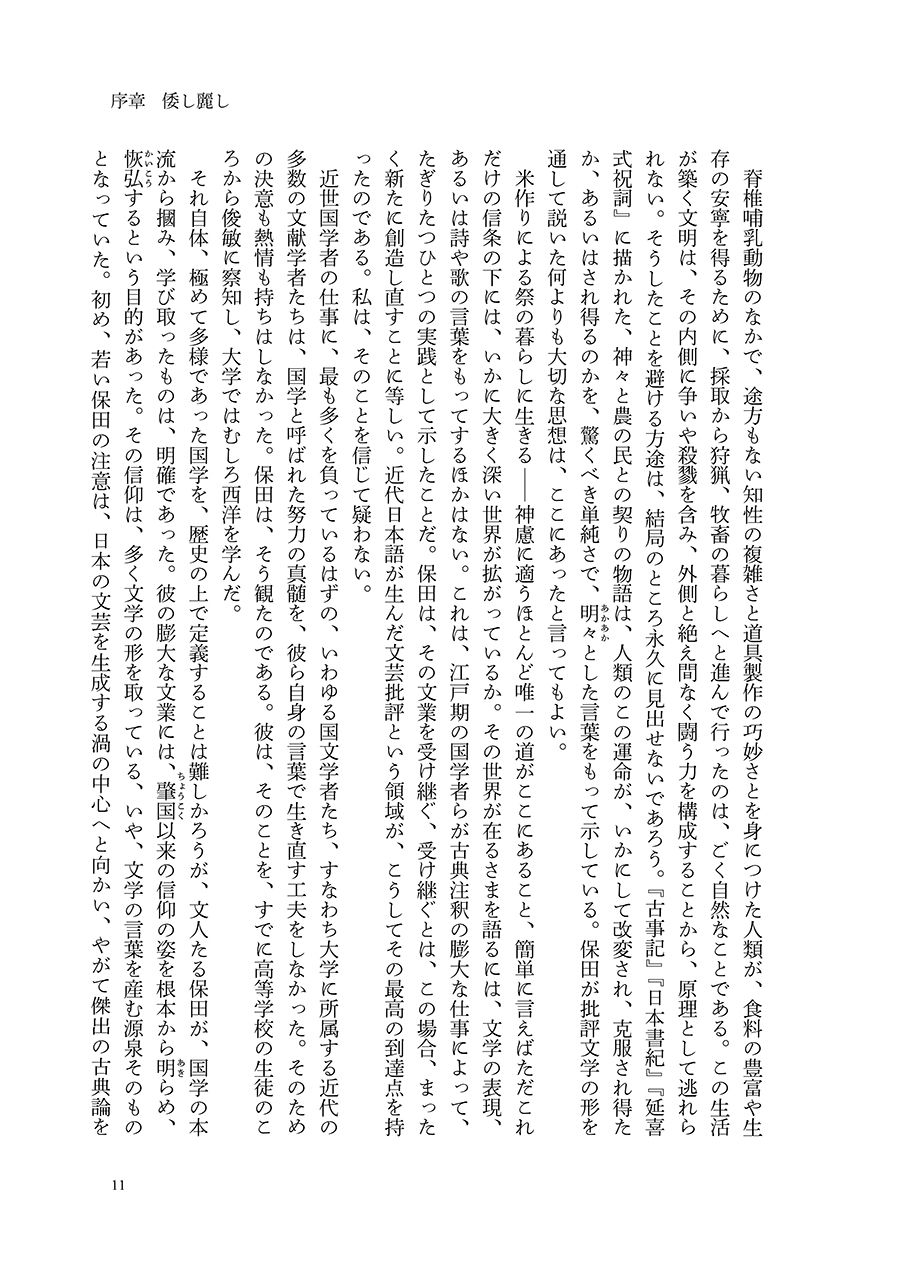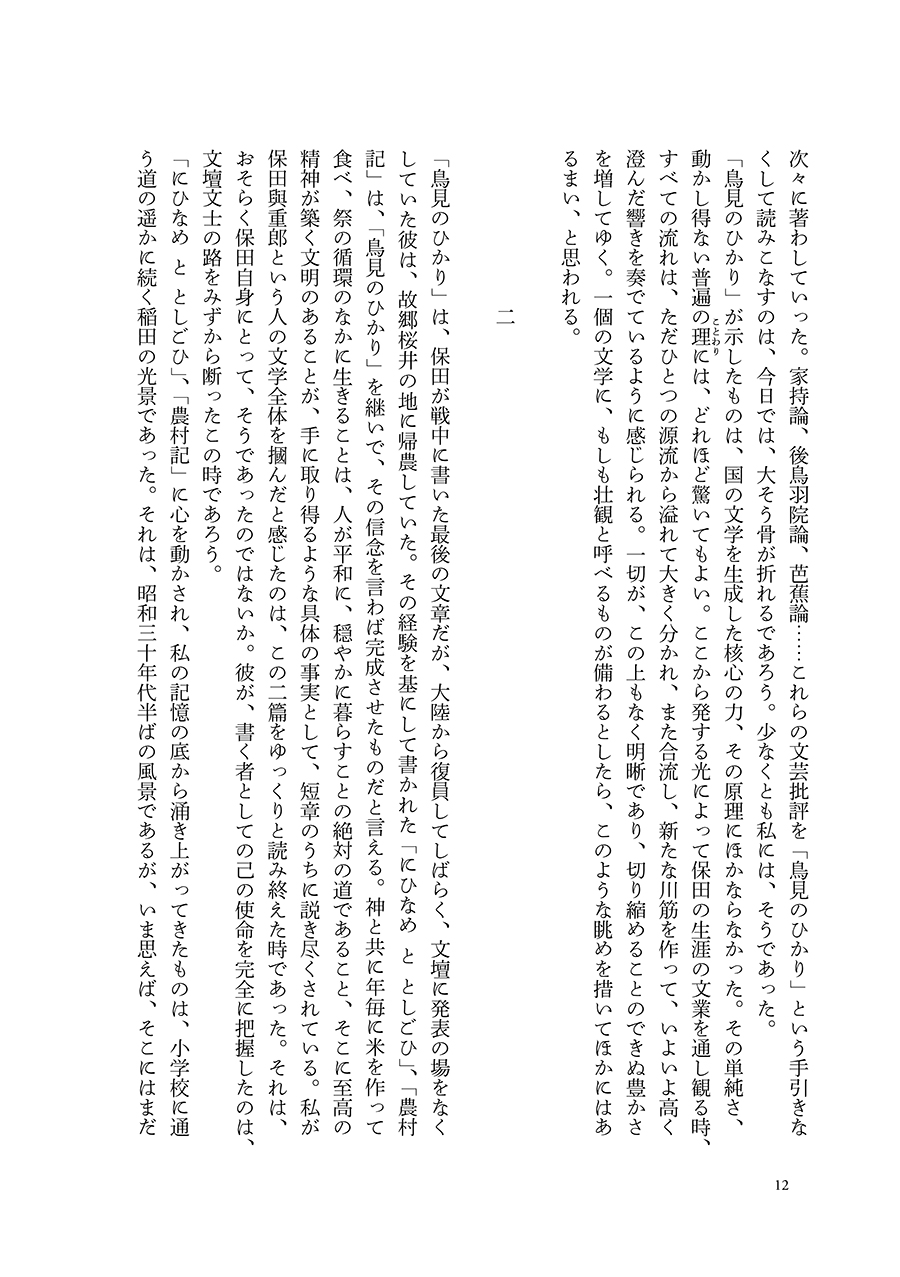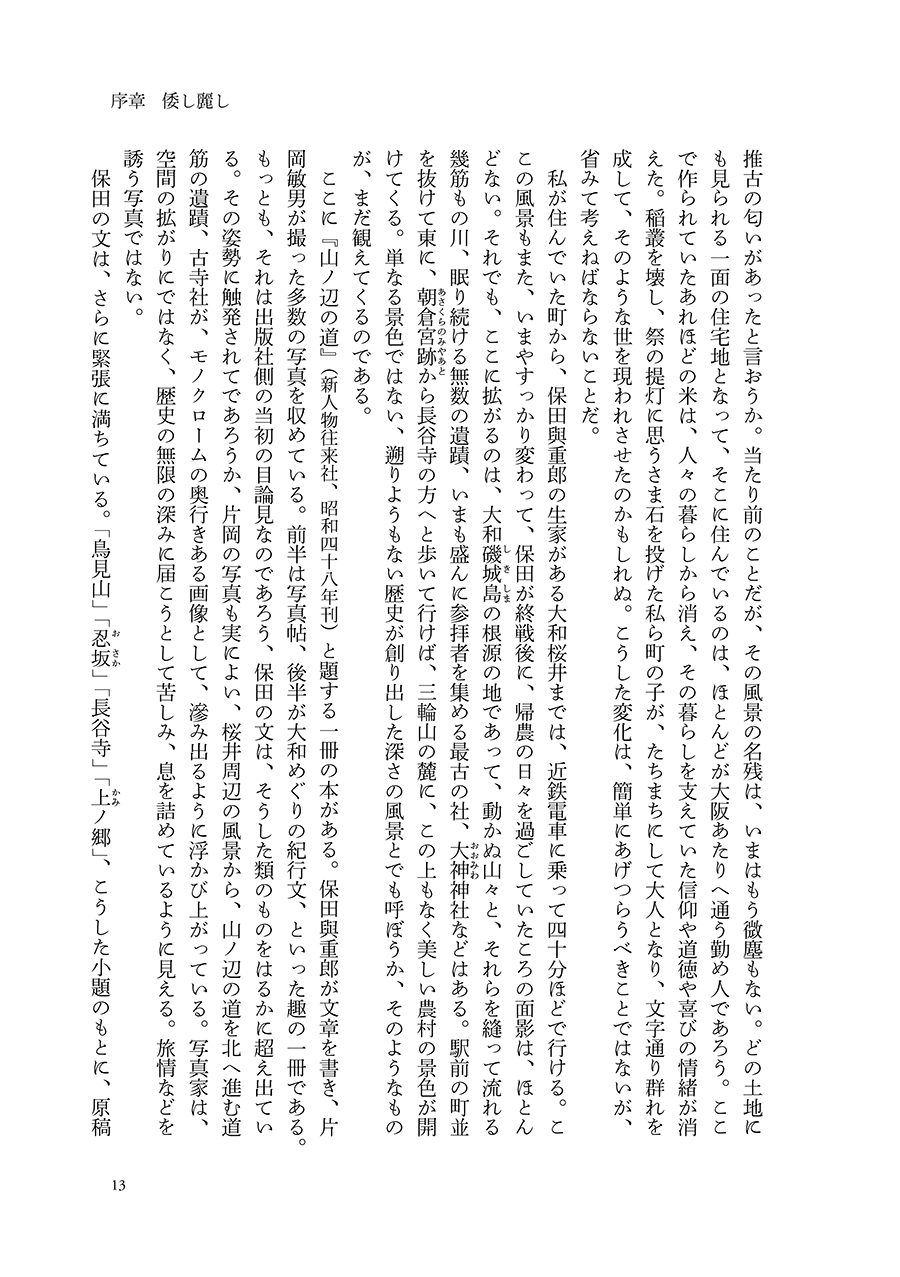序章 倭し麗し
一
私は、三歳の時から高等学校を出るまで、奈良市の西寄り、ごく小さな町で育った。町をはずれるとすぐに蟇股池と呼ばれる巨大な溜池があり、この池は、「菅原池」の名で『日本書紀』(推古天皇紀、十五年の項)に出ているものと同じだろうと言われている。それならば、池は聖徳太子の指揮のもと、水田用に造られた施設だということになる。実際、この池は、高台の端にあって、その下をはるばると拡がっている稲田に水を引く細い水路を持っていた。水路は降ると、岸辺に草の繁茂する小川を作って、疋田村と呼ばれる集落の方に延びている。
春になると蓮華、菜の花が一面に咲く田地は、まもなく水田となり、秋には稲穂の列が風にうねる。刈り取られた稲穂を積み上げて、田のあちこちに作られる稲叢の姿は、いま想い浮かべれば、喩えようもなく美しかった。秋が深まれば、神輿の出る祭である。私が通う小学校は、疋田村を抜けたところにあって、家から半里ばかりの道のりを毎日通った。農の暮らしもその躾も知らぬ私ら町の子は、たむろしてずいぶんひどい悪さをしたものだ。積み上げた稲穂を打ち崩して相撲を取り、祭の提灯には行きがけに小石を投げつけ、それが割れ落ちるまでやめなかった。村の人々は、どう思っていたか。この歳になって思い返せば、泪がにじむ。
大和の南、桜井の町から、保田與重郎という高名の文学者が出ていることは、子供のころ、誰の口からともなく聞かされていた。奈良の地であっても、そう知られていたわけではない、私が中学の時、国語の先生のひとりは、文人、保田の名を知らなかった。高等学校時代、「世界史」の若い先生が、何かの雑談の折、「日本浪曼派」という言葉と共に、保田のことを少しばかり話された記憶がある。そこには、否定の語気があった。戦後日本の学校教育から、保田與重郎の名は、ためらいもなく抹消されていたのである。
文学を読みかじり始めた少年が、保田の文章を、少なくともその真意を捉える、などということは、ほとんどあり得ぬ。本格の文章というものは、そうであってよいのだ。血肉となって躍る教養の厚さが、子供っぽい頭脳などを跳ね飛ばしてしまう。これは、難解さというものではなかろう。身ひとつが学んで生きる覚悟を持つかどうか、すべては、そこにかかっている。私もあっさり跳ね飛ばされた口で、この人の文章に、ほんとうに行き逢えた、と感じた瞬間があったのは、もう五十歳近くになってからであった。
保田與重郎が、昭和十九年秋から二十年春にかけ、国土も灰燼に帰そうとする時局のなかで発表した「鳥見のひかり」という文章は、私にとって、この人の文業一切を解く鍵になった。まさに、光を四辺に放つ鍵となったのである。このことは、保田自身にとってもまた言えるのではないか。この稿を書き上げた時、彼は己の文業に、天地を貫く使命の柱を、はっきりと打ち込んだ、そう感じたであろう。
詳しくは、本篇の叙述を見てもらいたいが、眼目となるところは、米を作って生きる信仰の暮らしが、神と通い合う文明のすべてを産み出した、この事実にある。国のなかにある文明ではない、「くに」と呼ばれる土地を、食料の生産、消費に関わる業によって、絶えず新たに産み出すような文明である。この業は、神によって与えられ、神の依頼を受けて人が行ない、支え続ける。その具体の様を、保田は『延喜式祝詞』に記録、保存された古代の言葉から、緻密に引き出し、近代人にわかる理の言葉によって、鮮やかに説き直したのである。本来は、文学者のする仕事ではない、だがまた、文学者以外の誰によって、こうした仕事をほんとうに成し遂げられようか。私は、そのことを愕然として知り、論ずる言葉を失った。いや、論としての言葉は、むしろ止めどなく湧き上がってくる、だが、「鳥見のひかり」が発する輝きから、それらはみな外れて色褪せてゆくのであった。
脊椎哺乳動物のなかで、途方もない知性の複雑さと道具製作の巧妙さとを身につけた人類が、食料の豊富や生存の安寧を得るために、採取から狩猟、牧畜の暮らしへと進んで行ったのは、ごく自然なことである。この生活が築く文明は、その内側に争いや殺戮を含み、外側と絶え間なく闘う力を構成することから、原理として逃れられない。そうしたことを避ける方途は、結局のところ永久に見出せないであろう。『古事記』『日本書紀』『延喜式祝詞』に描かれた、神々と農の民との契りの物語は、人類のこの運命が、いかにして改変され、克服され得たか、あるいはされ得るのかを、驚くべき単純さで、明々とした言葉をもって示している。保田が批評文学の形を通して説いた何よりも大切な思想は、ここにあったと言ってもよい。
米作りによる祭の暮らしに生きる――神慮に適うほとんど唯一の道がここにあること、簡単に言えばただこれだけの信条の下には、いかに大きく深い世界が拡がっているか。その世界が在るさまを語るには、文学の表現、あるいは詩や歌の言葉をもってするほかはない。これは、江戸期の国学者らが古典注釈の膨大な仕事によって、たぎりたつひとつの実践として示したことだ。保田は、その文業を受け継ぐ、受け継ぐとは、この場合、まったく新たに創造し直すことに等しい。近代日本語が生んだ文芸批評という領域が、こうしてその最高の到達点を持ったのである。私は、そのことを信じて疑わない。
近世国学者の仕事に、最も多くを負っているはずの、いわゆる国文学者たち、すなわち大学に所属する近代の多数の文献学者たちは、国学と呼ばれた努力の真髄を、彼ら自身の言葉で生き直す工夫をしなかった。そのための決意も熱情も持ちはしなかった。保田は、そう観たのである。彼は、そのことを、すでに高等学校の生徒のころから俊敏に察知し、大学ではむしろ西洋を学んだ。
それ自体、極めて多様であった国学を、歴史の上で定義することは難しかろうが、文人たる保田が、国学の本流から摑み、学び取ったものは、明確であった。彼の膨大な文業には、肇国以来の信仰の姿を根本から明らめ、恢弘するという目的があった。その信仰は、多く文学の形を取っている、いや、文学の言葉を産む源泉そのものとなっていた。初め、若い保田の注意は、日本の文芸を生成する渦の中心へと向かい、やがて傑出の古典論を次々に著わしていった。家持論、後鳥羽院論、芭蕉論……これらの文芸批評を「鳥見のひかり」という手引きなくして読みこなすのは、今日では、大そう骨が折れるであろう。少なくとも私には、そうであった。
「鳥見のひかり」が示したものは、国の文学を生成した核心の力、その原理にほかならなかった。その単純さ、動かし得ない普遍の理には、どれほど驚いてもよい。ここから発する光によって保田の生涯の文業を通し観る時、すべての流れは、ただひとつの源流から溢れて大きく分かれ、また合流し、新たな川筋を作って、いよいよ高く澄んだ響きを奏でているように感じられる。一切が、この上もなく明晰であり、切り縮めることのできぬ豊かさを増してゆく。一個の文学に、もしも壮観と呼べるものが備わるとしたら、このような眺めを措いてほかにはあるまい、と思われる。
二
「鳥見のひかり」は、保田が戦中に書いた最後の文章だが、大陸から復員してしばらく、文壇に発表の場をなくしていた彼は、故郷桜井の地に帰農していた。その経験を基にして書かれた「にひなめ と としごひ」、「農村記」は、「鳥見のひかり」を継いで、その信念を言わば完成させたものだと言える。神と共に年毎に米を作って食べ、祭の循環のなかに生きることは、人が平和に、穏やかに暮らすことの絶対の道であること、そこに至高の精神が築く文明のあることが、手に取り得るような具体の事実として、短章のうちに説き尽くされている。私が保田與重郎という人の文学全体を摑んだと感じたのは、この二篇をゆっくりと読み終えた時であった。それは、おそらく保田自身にとって、そうであったのではないか。彼が、書く者としての己の使命を完全に把握したのは、文壇文士の路をみずから断ったこの時であろう。
「にひなめ と としごひ」、「農村記」に心を動かされ、私の記憶の底から涌き上がってきたものは、小学校に通う道の遥かに続く稲田の光景であった。それは、昭和三十年代半ばの風景であるが、いま思えば、そこにはまだ推古の匂いがあったと言おうか。当たり前のことだが、その風景の名残は、いまはもう微塵もない。どの土地にも見られる一面の住宅地となって、そこに住んでいるのは、ほとんどが大阪あたりへ通う勤め人であろう。ここで作られていたあれほどの米は、人々の暮らしから消え、その暮らしを支えていた信仰や道徳や喜びの情緒が消えた。稲叢を壊し、祭の提灯に思うさま石を投げた私ら町の子が、たちまちにして大人となり、文字通り群れを成して、そのような世を現われさせたのかもしれぬ。こうした変化は、簡単にあげつらうべきことではないが、省みて考えねばならないことだ。
私が住んでいた町から、保田與重郎の生家がある大和桜井までは、近鉄電車に乗って四十分ほどで行ける。ここの風景もまた、いまやすっかり変わって、保田が終戦後に、帰農の日々を過ごしていたころの面影は、ほとんどない。それでも、ここに拡がるのは、大和磯城島の根源の地であって、動かぬ山々と、それらを縫って流れる幾筋もの川、眠り続ける無数の遺蹟、いまも盛んに参拝者を集める最古の社、大神神社などはある。駅前の町並を抜けて東に、朝倉宮跡から長谷寺の方へと歩いて行けば、三輪山の麓に、この上もなく美しい農村の景色が開けてくる。単なる景色ではない、遡りようもない歴史が創り出した深さの風景とでも呼ぼうか、そのようなものが、まだ観えてくるのである。
ここに『山ノ辺の道』(新人物往来社、昭和四十八年刊)と題する一冊の本がある。保田與重郎が文章を書き、片岡敏男が撮った多数の写真を収めている。前半は写真帖、後半が大和めぐりの紀行文、といった趣の一冊である。もっとも、それは出版社側の当初の目論見なのであろう、保田の文は、そうした類のものをはるかに超え出ている。その姿勢に触発されてであろうか、片岡の写真も実によい、桜井周辺の風景から、山ノ辺の道を北へ進む道筋の遺蹟、古寺社が、モノクロームの奥行きある画像として、滲み出るように浮かび上がっている。写真家は、空間の拡がりにではなく、歴史の無限の深みに届こうとして苦しみ、息を詰めているように見える。旅情などを誘う写真ではない。
保田の文は、さらに緊張に満ちている。「鳥見山」「忍坂」「長谷寺」「上ノ郷」、こうした小題のもとに、原稿用紙数枚程度の短い案内文が綴られるのだが、どれも保田の生涯の文業を、怖ろしいまで圧縮して弛みなく、気負いなく、思索の結晶体のように光る。ここで彼が語っている土地の範囲は、いたって狭い。南は飛鳥へと通じる磐余の道を挟んで左右にひしめく古墳、宮跡、古寺、そこから三輪山の麓を北上して「山ノ辺の道」をゆき、天理市に入って石上神宮に到る。距離にして、南北十数キロメートルであろう。朝のうち、桜井駅を出れば、夕方までには十分に歩き尽くせる。ここは、奈良の都よりはもちろん、飛鳥の里よりもはるかに古い、まさに極め得ない「くに」の根源である。
現われた土地は狭いが、潜んでいる「くに」は、ここでは広い。この広さは、そのまま、果てのない時間の深さである。その深さは、見聞きできるものとして、この場所に実際にある。きらきらと光る記憶の結晶体を集めるが如き『山ノ辺の道』は、私たちにそうした場所をありありと見させ、その声を聞かせる。
大神神社の御神体である三輪山の麓を、蛇行して北へ向かうこの道は、その中ほど、西側に、景行天皇陵と崇神天皇陵のふたつを配している。山ノ辺の道を代表する見事な風景が、ここに拡がる。保田が生きていた頃も、今もそうである。季節の移りに従い、むろん日差しも山の色合いも変わるが、天皇陵の壮麗な美しさは、道の風景とひとつになり切って、歩く者を包む。『山ノ辺の道』の開巻冒頭で、保田は書いている。「これら[ふたつ]の御陵は、造形が雄大だといふだけでなく、景観としての造園が、比べるものがない程に美しい。わが国の数ある庭園中の第一流のものは、修学院の上の庭であるが、それを念頭にすれば、崇神天皇御陵、景行天皇御陵の、比類ない大きい美しさがさらによくわかると思ふ」(「山ノ辺の道と磐余の道」)。
最も古い時代の御陵の造形は、人の意識をもって巧まれた美術作品の姿を大きく凌いで美しい。人為のみでは到底達し得ない美しさが、そこにはある。人の手の加わらぬただの自然ではない、むしろ造形であり、「我国で最もおほらかに美しい造園である」(同前)。神と人との協力のみが現われさせた上古の風景が、いまも厳然として在る。その協力は、米作りに関わるものだ。二陵を大きく取り巻く広大な濠を見よ。ここに満々と湛えられた水は、「長い年月、大和平野何万石の水田の、いのちの水だつたのである。御陵の濠の水は、百姓のものだつた。この御陵の景観の比類ない美しさには、さらに重い国がらの生産のくらしとの関係をもつてゐたのである」(同前)。
第十代崇神天皇、第十二代景行天皇には、神武以来、国の始めの歴史のなかで、取り分けて重い役割が課せられていたのだが、その目標は、詰まるところ、大和平野に拡がる米作りの暮らしの豊かな成就というものであっただろう。二陵の景観は、果たされたその使命の形を、「重い国がら」の明瞭なる表現として今も眼の前に拡がっている。もはやこれは、まったく人為を超えた造形だと、保田は言っているのである。
崇神天皇の都は磯城瑞籬宮、その址は、桜井から山ノ辺の道に入ってすぐのあたりにある。伝えによれば、神武以来、天皇と「同床共殿」にいました天照大御神を、神託に従い、すぐ近くの笠縫邑に遷し奉ったのは、崇神天皇六年のことである。誰も知るように、天照大御神は、やがてここから伊勢の五十鈴川上流に遷り、そこに鎮座される。このことは、人の治世が天上の神々から分かれ、言わば独立することを意味しよう。『古語拾遺』が伝えるとおり、この分離には当初よりの「幽契」があったと、保田は観る。それを為し遂げた人々の畏れは、いかばかりであったかと。
景行天皇の都は纏向日代宮、大神神社を過ぎて「山ノ辺の道」を少し北へ辿ったところに今も宮跡がある。倭建命は、この時代の皇子であり、皇子が父、景行天皇の命によって行なった西と東への征討の旅は、おそらく治世の完成に向けた大きな前進を目指すものであっただろう。旅の終わり、熱田よりの帰途、倭建命は荒ぶる山の神と気まぐれに試みた戦いがもとで、倒れて果てる。『古事記』中の最大の英雄が、このようにして亡くなるのだが、この出来事が意味するものは、またその悲傷は、語り尽くすことができない。人が、天上の祖たる神々から独立しなくてはならぬ、その避け得ない運命を、命の死は歌っている。この時、命が能煩野の地(三重県鈴鹿のあたり)で「国を思ひて」歌う絶唱が、『古事記』のなかに記されている。
倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山籠れる 倭し麗し
この「青垣」とは、命の故郷、「山ノ辺の道」を、深く抱く山々であろう。保田與重郎の生涯の文業は、倭建命のこの絶唱、「倭し麗し」の一句を、無限に変奏しては、縦横に走らせ、日本に潜み流れる文学の歴史を、明々とした光の下に浮かび上がらせたものである。私は、次第にはっきりと、そう断言し得るようになった。
三
「山ノ辺の道」と書かれるその「山」は、道から仰げば遠く聳える峰の連なりであるが、登ってみれば、そこは広々とした高原である。山上の地の途方もない広さは、一望するだけでわかる。この高台は、大和盆地の全体に匹敵する面積を持っていよう。近ごろは、ここ一帯を「大和高原」と名づけているようだが、地元の人は「上ノ郷」と呼び慣わしてきた。「上ノ郷」は、滝倉、笠、小夫の地を一括して呼ぶときの名であるが、「上」の字は、やはり「神」の意に通じていよう。そう考えるほかない。この地からは、八、九千年前のものと推定される押型縄文式土器の破片が出土している。これは、驚愕すべき事実ではないか。
桜井一帯から「山ノ辺の道」に沿い次々と都が開かれた時代よりはるか以前、伝える言葉もすでになくなり果てた遠い記憶の底で、「上ノ郷」は畏怖される根源の地、神々の住んだ故郷であったのだろう。神話の伝える「高天原」が、「上ノ郷」を指している、という考えに憑かれた郷土史家が近代にいたことを、保田は楽しげに記している。この考えは、想像でも仮説でもない、大和の地に、ひとつの歴史事実として流れ続けていた明瞭な感情であった。保田の心に芯まで染み込んでいたのは、そのようにして伝わり、現存していた信仰である。記紀、萬葉を語り、古美術を評して微塵も誤ることがなかった彼の批評の秘密は、そこにこそあった。
「高天原」が大和盆地の東側に拡がる広大な高原だとすれば、記紀が伝える「天孫降臨」の神話は、一体どのようなことになるか。高原よりは、谷川の水流に恵まれた低地が、稲作に適していることは言うまでもない。米作りの高原の民が、その信仰を携えて、草木生い茂る未開の低地を伐り開き、伐り開き、祭の暮らしを完成させていった具体の過程が思い浮かぶ。「皇孫」とは、この暮らしが、一年にわたる祭それ自体として、天上の暮らしに通じて離れないための、ただひとつの中心を表わす言葉である。人としての帝が何代続き、いつまで代り続けようと、米作りの暮らしと信仰のなかで「皇孫」たる神の子はただひとり――文人、保田のこの思想は、語って尽きない生動のなかにあって、しかも不動のものであった。
通常の感覚を超えた「上ノ郷」の神威は、都の平地人にとっては、畏怖の極みにあって、また限りもなくなつかしい故地となっていった。今日でも、その感じ方は、無言のうちに残っている。三輪山の少し北側に位置する巻向山は、登れば「上ノ郷」の一部に入るが、そこにある水源から流れ落ちる谷川を巻向川と呼び、穴師の村に入って穴師川となる。「山ノ辺の道」はこの村を南北に通う。村の家並みは、今でも目を洗われるばかりに美しい。穴師の集落を語る保田の言葉は、このような地を庭の如くに持って生まれ、育った者のみの比類ない詩心を示している。
大和路では、誰もが古い社寺を語るが、見事な美しい民家も見るべきである。しかしそれ以上に心して見て欲しいのは、村の美しさである。一つの村として、おのづからに出来上つたものの構成の美しさである。世界のどこに、かういふ美しい村をつくれる造園師がゐるだらうか。いづこの国に、これに劣らぬものの作れる都市計画家や設計師がゐるだらうか。村は人々各々の思ひで、勝手につくりつゝ、見事に調和し、統一の品格がある。その上で美しいのだ。この原因は彼らのくらしの中に、その共通の原理があつたからだ。それは強制や干渉をしない。これが道徳だつたのである。(『山ノ辺の道』「巻向」)
こうした村は、人が小知をもって成したものではない、むろん単なる自然の結果でもない、人と神との協力による米作りの暮らしが、おのずからに開いているものだ。川の流れと土地の高低に従った農家の配置、山を背負って拡がる田野の春の花々、秋の稲穂……刻々に移る日差しが、村に無限の巡り行きをもたらす。ここに現われる美しさは、近代が芸術美などと呼んだものとは何の関わりもなく、そうした観念が生む作品をどこまでも凌駕している。それは、人類が帰るべきところを、強制もなく、干渉もなく、静かに示し、教えていると言ってもよい。
『萬葉集』最大の歌人、柿本人麻呂は、土地では穴師の人と伝えられている。穴師の風景を詠んだ人麻呂の歌は、そのほとんどが集中最高峰の傑作である。
ぬば玉の夜さり来れば巻向の川音高しも嵐かも疾き
巻向の山辺響みて往く水の水沫のごとし世の人われは
あしひきの山かも高き巻向の岸の小松にみ雪降りけり
後に、日本語詩歌の根柢となってゆく心緒の調べが、ここに川音のようにはっきりと聞こえる。それは、なぜであろうか。この問いに、保田ほどはっきりと、その文章をもって答え得た人は、彼の前にも後にもいない。
穴師の山を登ったところに大兵主神社があった。いま山下に残る兵主神社は、それを平地に移したもので、穴師の山は神人の故地として記憶された。都は纏向から磯城島へ、さらにまた磐余、飛鳥浄御原、奈良へと移り続ける。その間も、穴師の山は「遠い祖先の聖地」、穴師の山人は、「一種の心遠い神秘感」をもたらす人々だったと、保田は言う。天武朝に生きた人麻呂の身のうちには、穴師のその山人、いや神人の血が流れるのであろうか。彼が歌ったものは、里に降った上ノ郷の神々の歎き、その願いや喜びに近い。「どの歌も格調高く、また人生永劫の寂寥感のふかく心にひゞくものがある」とは、保田の言葉だが、「人生永劫」の限りもない温かさは、人が神から分かれる悲しみとひとつになって離れぬ。
人麻呂が穴師の里で生まれたという言い伝えは、この地の人々にとっては、証明の要なき事実であった。保田はこの言い伝えを「一種の絶対感をふくめてうべなひたい」と書く、「五十年以前には、人麻呂の屋敷の址と称した場所もあつたほどである」(同前)と。千三百年以上前に生きた歌神の屋敷址を、あたりまえのことと信じて暮らす、これを迷信と笑う近代人の知性こそが、迷いのなかでさまよっているのである。
「山ノ辺の道」を穴師から少しばかり北に行ったところ、倭大国魂を祭った大和神社の旧地を過ぎると、道は衾道と呼ばれる地帯に入ってゆく。このあたりから、「山ノ辺の道」の呼称はやや曖昧になって、やがて天理市の石上神宮に至るのである。衾道の東には巻向山から連なって延びる引手山が聳えている。ある日、人麻呂は、この山にひとりの女性を葬ったようである。その時の歌が、まるで今の日に詠まれたかのように、『萬葉集』にある。
衾路を引出の山に妹を置きて山路を行けば生けりともなし
「人生永劫」の懐に抱かれた寂しさが、ここにも響いている。保田與重郎が生まれ、育ち、不世出の文人となったのは、このような土地に在る神の力によってである。私には、そう信じられる。
四
これは、ことのついでに言っておくのであるが、本書では保田與重郎の発言と行動とをめぐって、戦中、戦後に激しく起こった種々の論争めいた文章には、ほとんどいっさい触れていない。そうしたものを日本近代史の一様相として分析したい人は、ほかにいるであろう。また、さらに、そうした分析を、今日の時務論争にまで引き延ばし、保田の言葉を右翼、国粋主義、反動として深刻に批判したい人は、いくらでもいるであろう。
ここでの私の文章は、そういうものに関わり合うなら、すっかりその色合いと意味とを変える性質のものである。その性質を作っているものは、私の生まれつきというものであろうか。いや、それだけではない。五十歳も近くなってから始まった、保田與重郎愛読の容易に言葉にはしがたい経験が、おのずからに私を、そのような論争から遠ざけ、無関心にさせてきたのである。文学の力とは、そういうものではないか――と、こう言えばまた、あちこちから反論が起きよう。しかし、これは論などではない。現に、私が生き生きと受け続けてきた実際の力である。これを離れて、私には何を書くことも決してできなかった。それだけの話であって、あえて言うほどのこともない、まことに簡単明瞭ないきさつである。
政治思想史家、橋川文三が、一九六〇年に刊行した『日本浪曼派批判序説』(未来社)は、保田批判で名高い書物であるが、これについては何を言えばよいか。この本を、いま読み返してみて、改めて深々と感じるのは、保田の孤独である。いかなる鋭敏な批判者、また、どれほどに熱烈な崇拝者のなかにあっても、保田與重郎の常に開いたままなる魂は、孤独であった。
橋川の保田批判は、それ自体として読めば、多くの傾聴すべき点を持っている。それは、政治上の立場から為される単調な否定とは全く異なっていて、この人自身の保田熱読に根差した経験の響きをあちこちで顕わにしている。そこでは、最も強い否定は、最も高い称賛と表裏になって切り離せぬと言ってもよい。保田に対しての、青年時代の強い傾倒、進行する戦局のなかでの静かな疑いの芽生え、戦後期を迎えての内省と批判、みずからが責任を負うべき方途への苦渋の思索、こうしたものすべてがひとつになった論旨に熱く説得され、共感した読者は、おそらく多かろう。私の場合は、そうではなかった。
実際、橋川の思考法、それを運ぶ文体は、保田與重郎が創り上げた文学とは、ほとんど無縁のもののように、私には思われる。保田の文学は、彼自身が歴史の深所に掘り当て、創造し直した遠大な系譜の潜在する内側から爆発し、噴出している。その運動がやむを得ず巻き上げ、撒き散らした同時代の粉塵を、あれこれと執拗に分析したところで、噴き上がったその力の本体に入り込むことはできない。橋川が、そのことを直覚していなかったはずはない。だからこそ、彼の文章は、何か独特な政治上の留保と自問とに渦巻くのである。
橋川は知っている。保田こそが、第二次大戦中にあってナチスを終始明確に批判し、「日本主義者」「東亜協同体論者」「世界史の哲学論者」に「もっとも根本的ないみで批判的であった」(『日本浪曼派批判序説』)ことを。さらに、大学の体制に囲われた学問体系から、青年たちを解放し、「日本の古典にみちびいた唯一の運動」が、保田の率いた日本浪曼派であり、「それはともかく私たちの失われた根柢に対する熱烈な郷愁をかきたてた存在であったこと」(同前)を。
「熱烈な郷愁」と、橋川は言う。しかし、そこに動き、現に働いていた力は、はたしてそういうものであっただろうか。いかに「熱烈」であろうと、「郷愁」とはありふれた弱い想念であって、人の生きる方向を、それが秘める生の曲率を決定づけるに足るものではない。保田が当時の青年らに引き起こしたものは、そんな想念ではなかった。人の命を悠久に貫いて流れるひとつの明瞭な実在への感触、地の底から吹き上げる火柱のように、人の魂を燃え上がらせてやまない力であった。
昭和十八年以降、保田が繰り返し、繰り返し説き続けることになる「米作り」という原理の重みも、橋川は、ほんとうには、よく感じ取っている。ただ、それを「国学的農本主義」などというイデオロギーの範疇に置く時、橋川の論旨は、いたって曖昧になる。彼は言う。保田の「農本主義」は、「一個の世界理念の形態であり」、これを他のどのような農本政策とも連接させることはできない。
それは、権藤成卿のように制度学的農本主義でもなく、横井時敬のように官僚エリート的な重農主義でもなく、橘孝三郎のように人道主義的農本思想でもない。それは[本居]宣長の「みち」の思想の延長線上に立つことによってテオクラシー[神政]の理念を表現し、その非政治的構成の徹底によって無政府主義の相貌をおびるものであった。(同前)
その通りかもしれない。だが、どうであろう、この種の概念を用いた思想史上の整理や位置づけは、それが的を射ていようがいまいが、保田が為した言葉の懸命の努力(それをして彼は「文学」と呼ぶのであるが)、それとは始めから無関係な場所に置かれているように思う。厄介なのは、橋川がそのことを十分に知っていることである。
米作りによる祭の暮らし、これは制度でも思想ですらもなく、宣長が生涯をかけて説いたあの「道」に潜在する原理なのだ。そこに「美」を観るかどうかは、第一義のことではない。とりわけて論ずる必要のあることでもない。「しかし、また、その『美』が、一種の根源的実在として提示されたものである限り、それが現在もなお、ある隠された原理として作用していることは否定できないのである」(同前)。このように書かれて、橋川の「日本浪曼派批判序説」の本文は閉じられる。
あえて言うとすれば、これから始まる私の文章は、政治思想史とは永遠に無関係であるような一個の批評文学を、それが在り、かつ躍動したままの姿に戻して、みずから生き直すことを目指したものである。そのために、いささか長い道のりを歩くこととなったが、読者がまたその道筋を、ゆっくりと歩いてくれるよう、心底から願っている。
続きは本書でお楽しみください。