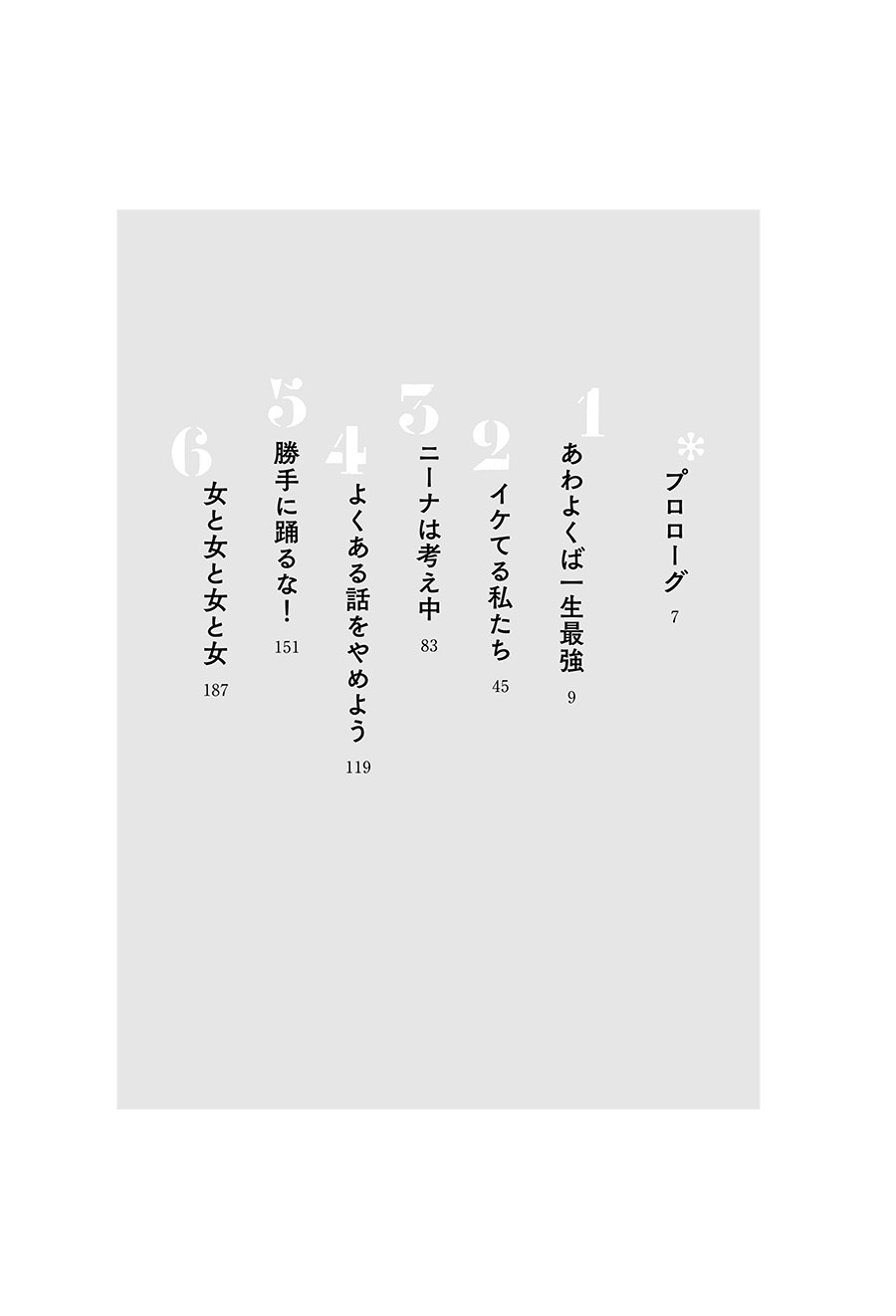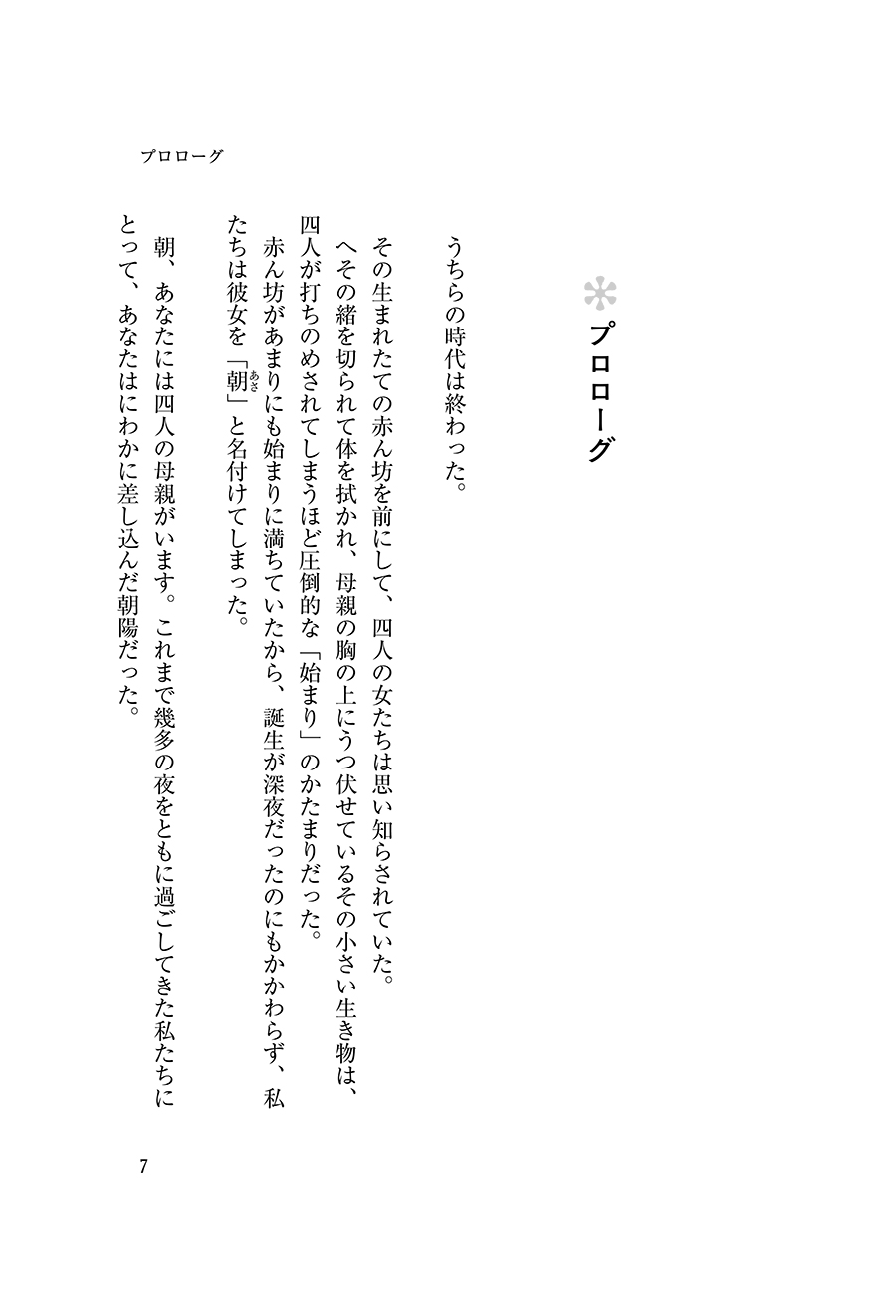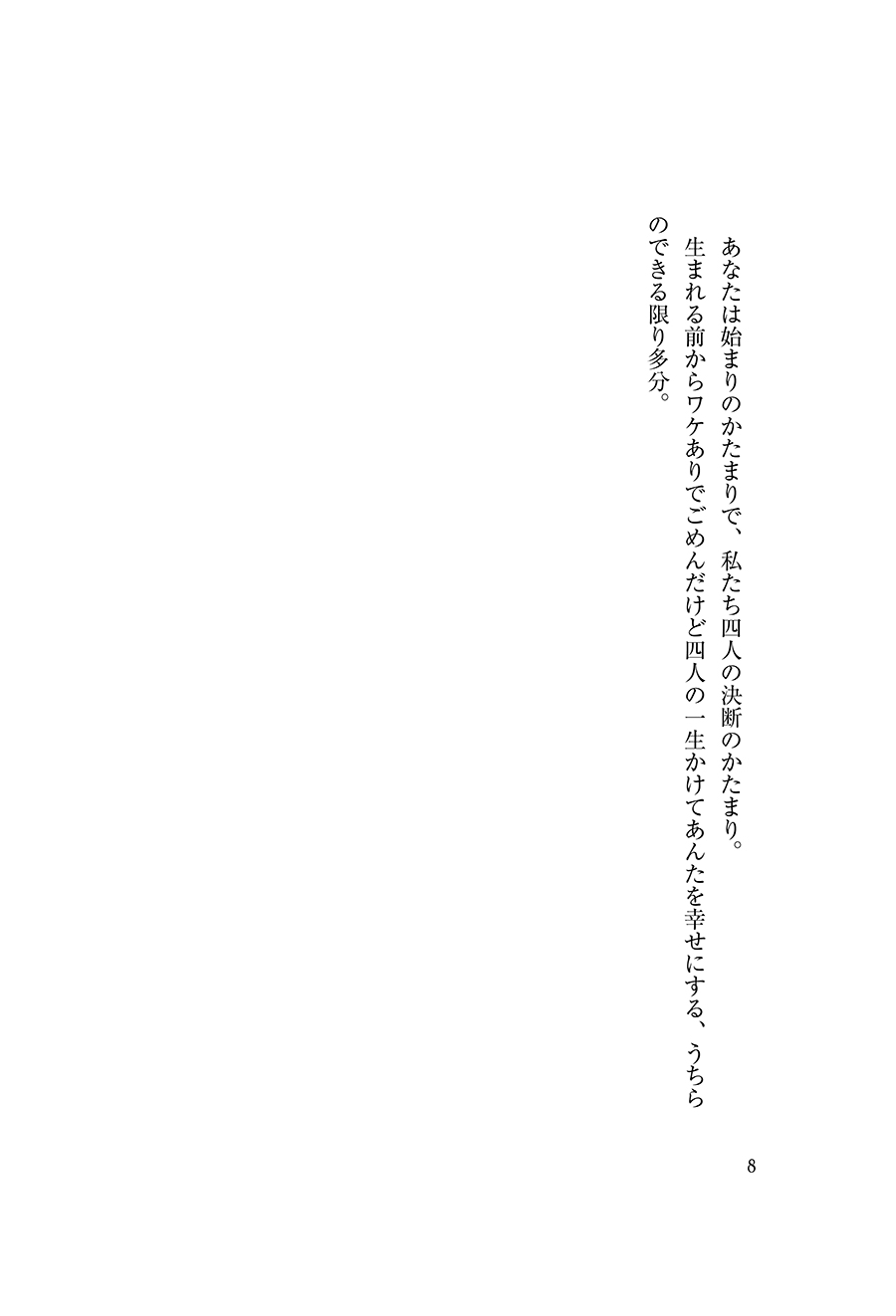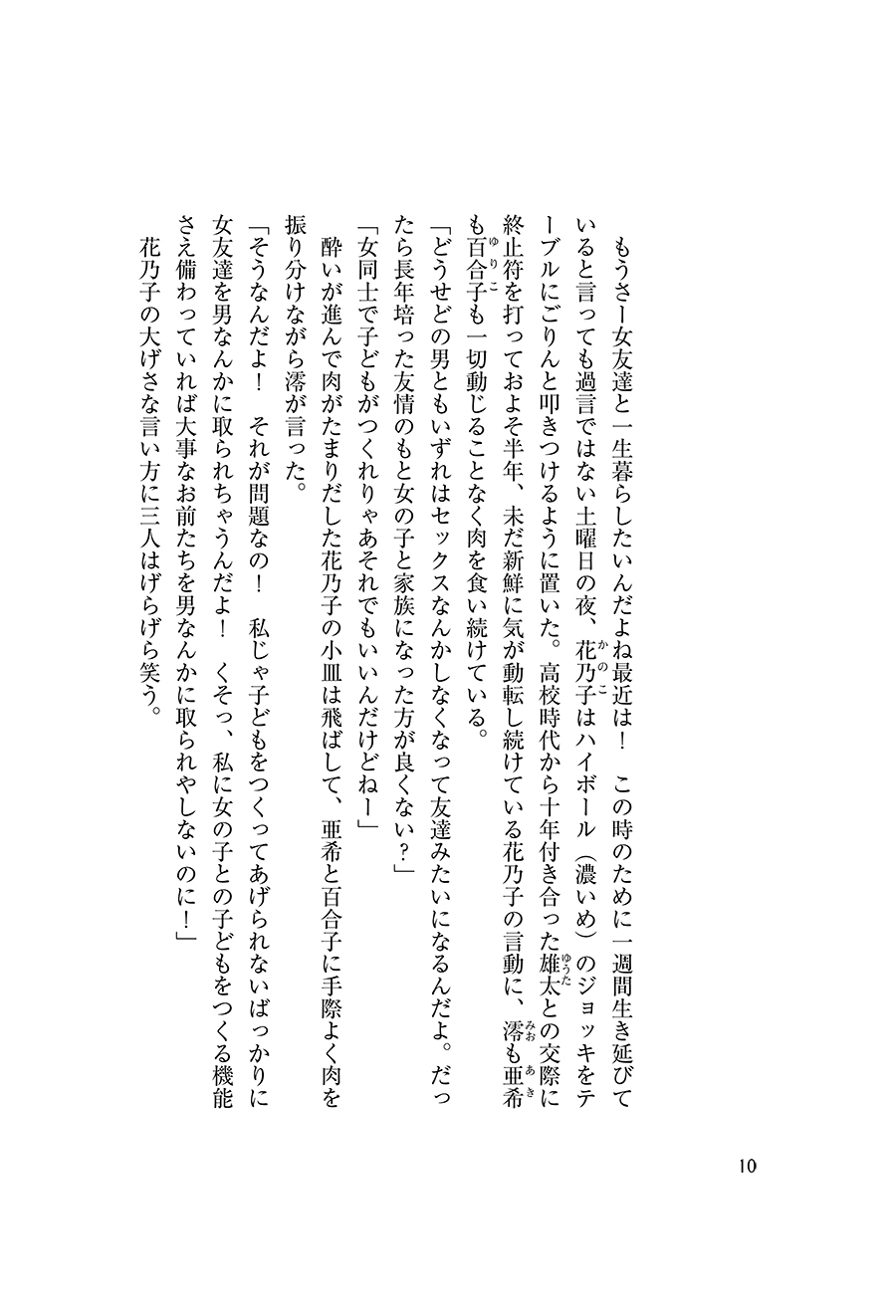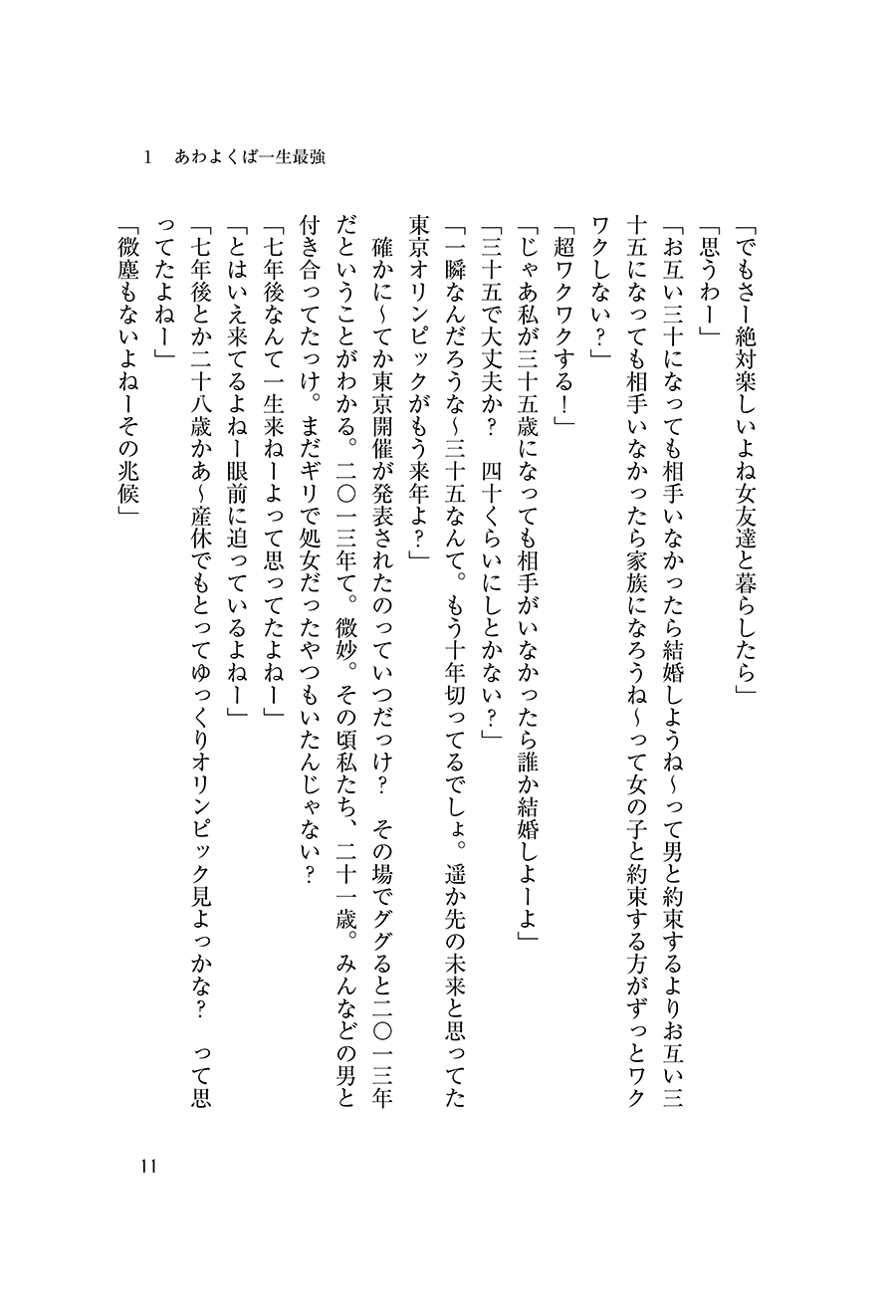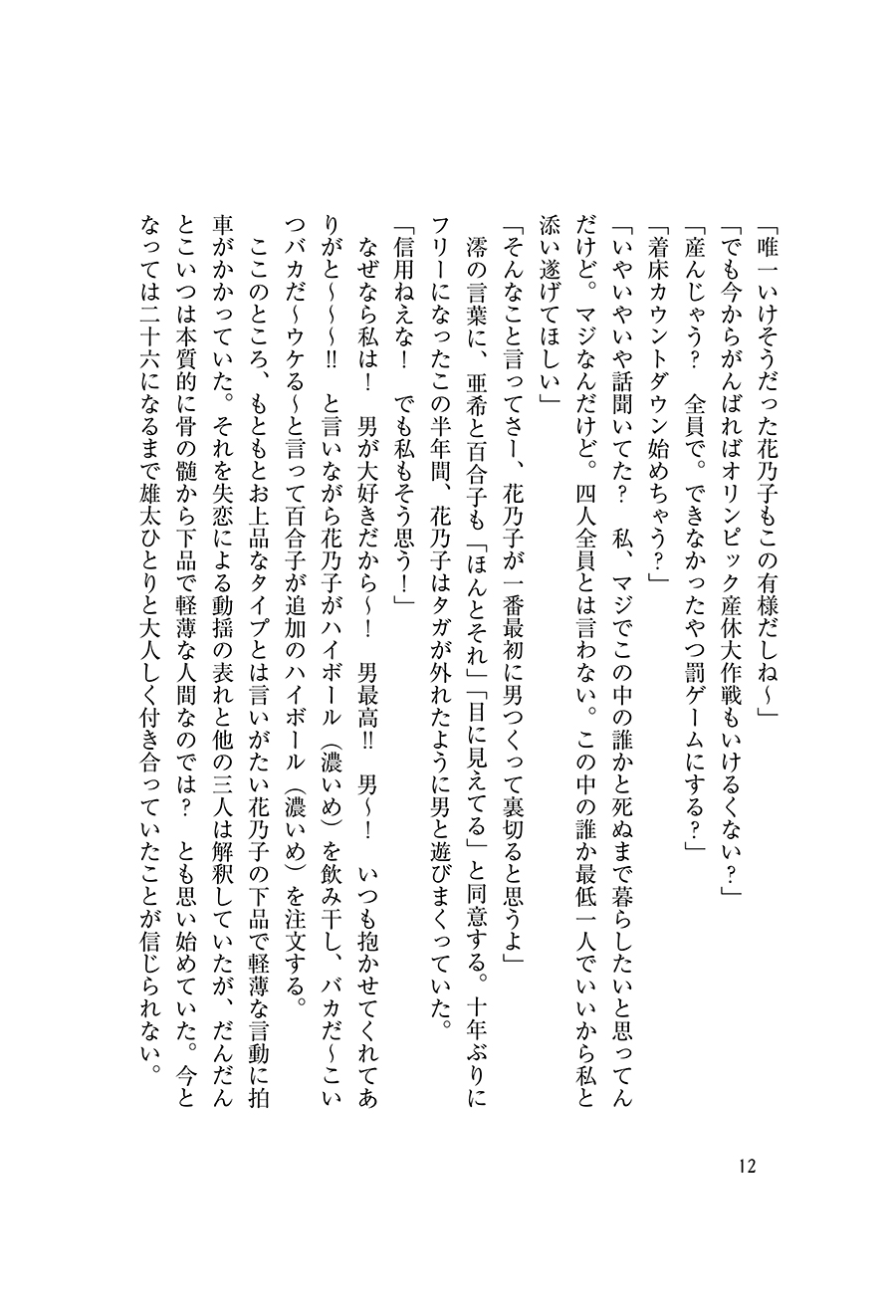プロローグ
うちらの時代は終わった。
その生まれたての赤ん坊を前にして、四人の女たちは思い知らされていた。
へその緒を切られて体を拭かれ、母親の胸の上にうつ伏せているその小さい生き物は、四人が打ちのめされてしまうほど圧倒的な「始まり」のかたまりだった。
赤ん坊があまりにも始まりに満ちていたから、誕生が深夜だったのにもかかわらず、私たちは彼女を「
朝、あなたには四人の母親がいます。これまで幾多の夜をともに過ごしてきた私たちにとって、あなたはにわかに差し込んだ朝陽だった。
あなたは始まりのかたまりで、私たち四人の決断のかたまり。
生まれる前からワケありでごめんだけど四人の一生かけてあんたを幸せにする、うちらのできる限り多分。
1 あわよくば一生最強
もうさー女友達と一生暮らしたいんだよね最近は! この時のために一週間生き延びていると言っても過言ではない土曜日の夜、
「どうせどの男ともいずれはセックスなんかしなくなって友達みたいになるんだよ。だったら長年培った友情のもと女の子と家族になった方が良くない?」
「女同士で子どもがつくれりゃあそれでもいいんだけどねー」
酔いが進んで肉がたまりだした花乃子の小皿は飛ばして、亜希と百合子に手際よく肉を振り分けながら澪が言った。
「そうなんだよ! それが問題なの! 私じゃ子どもをつくってあげられないばっかりに女友達を男なんかに取られちゃうんだよ! くそっ、私に女の子との子どもをつくる機能さえ備わっていれば大事なお前たちを男なんかに取られやしないのに!」
花乃子の大げさな言い方に三人はげらげら笑う。
「でもさー絶対楽しいよね女友達と暮らしたら」
「思うわー」
「お互い三十になっても相手いなかったら結婚しようね~って男と約束するよりお互い三十五になっても相手いなかったら家族になろうね~って女の子と約束する方がずっとワクワクしない?」
「超ワクワクする!」
「じゃあ私が三十五歳になっても相手がいなかったら誰か結婚しよーよ」
「三十五で大丈夫か? 四十くらいにしとかない?」
「一瞬なんだろうな~三十五なんて。もう十年切ってるでしょ。遥か先の未来と思ってた東京オリンピックがもう来年よ?」
確かに~てか東京開催が発表されたのっていつだっけ? その場でググると二〇一三年だということがわかる。二〇一三年て。微妙。その頃私たち、二十一歳。みんなどの男と付き合ってたっけ。まだギリで処女だったやつもいたんじゃない?
「七年後なんて一生来ねーよって思ってたよねー」
「とはいえ来てるよねー眼前に迫っているよねー」
「七年後とか二十八歳かあ~産休でもとってゆっくりオリンピック見よっかな? って思ってたよねー」
「微塵もないよねーその兆候」
「唯一いけそうだった花乃子もこの有様だしね~」
「でも今からがんばればオリンピック産休大作戦もいけるくない?」
「産んじゃう? 全員で。できなかったやつ罰ゲームにする?」
「着床カウントダウン始めちゃう?」
「いやいやいや話聞いてた? 私、マジでこの中の誰かと死ぬまで暮らしたいと思ってんだけど。マジなんだけど。四人全員とは言わない。この中の誰か最低一人でいいから私と添い遂げてほしい」
「そんなこと言ってさー、花乃子が一番最初に男つくって裏切ると思うよ」
澪の言葉に、亜希と百合子も「ほんとそれ」「目に見えてる」と同意する。十年ぶりにフリーになったこの半年間、花乃子はタガが外れたように男と遊びまくっていた。
「信用ねえな! でも私もそう思う!」
なぜなら私は! 男が大好きだから~! 男最高!! 男~! いつも抱かせてくれてありがと~~~!! と言いながら花乃子がハイボール(濃いめ)を飲み干し、バカだ~こいつバカだ~ウケる~と言って百合子が追加のハイボール(濃いめ)を注文する。
ここのところ、もともとお上品なタイプとは言いがたい花乃子の下品で軽薄な言動に拍車がかかっていた。それを失恋による動揺の表れと他の三人は解釈していたが、だんだんとこいつは本質的に骨の髄から下品で軽薄な人間なのでは? とも思い始めていた。今となっては二十六になるまで雄太ひとりと大人しく付き合っていたことが信じられない。
高校の同級生だった四人は、それぞれ微妙に疎遠になった時期もあるけれど――百合子がノリで申し込んだ交換留学プログラムにあっさり合格して一年間カナダに留学したり、花乃子が漫研の幹部になってサークル運営と自身の創作に夢中になっていたり、澪が優良JTCに新卒入社したかと思いきや社内随一の激務部署へ配属され毎週のように休日出勤を余儀なくされていたり、亜希が供給過剰なジャンルの沼にハマってネットパトロールとチケットの手配に心血を注いでいたり――これといって大きな
ピンボールのようにあらゆる角にガンガンぶつかりながらトイレから戻ってきた花乃子を見て「マジこいつすげー酔ってるじゃんおもしろ~」と百合子が笑った。
「当たり前じゃん今日は誰よりも酔いたいからわざわざ献血してから来てんだよこっちは」
「花乃子、男いない時の方がおもしろいから一生男つくんない方がいいよ」
「あ? だから男抜きで一生一緒に暮らそーって何度も言ってんだろが。ちゃんと話聞けって。マジさ~私と暮らしたら一生楽しませっから。見とけよ。私と暮らすのがどんだけ楽しいか思い知らせてやるよ」
「でも確かに、この四人で住んだら絶対超楽しいよね。毎日」
去年、いちばんでかいテレビのある澪の家で酒飲みながらM-1グランプリ見たの超楽しかったよね、という話で盛り上がる。ちょうど同い年の霜降り明星が優勝して、全然関係ない花乃子たちもなんとなく優勝したみたいな気持ちになったのだった。家に一人でいるとついついネットの動画ばっか見ちゃうけど友達と見るテレビってめっちゃ楽しくて、あれ? テレビってもしかして結構おもしろいんじゃね? って新鮮に思えた。ああいうのが毎日できるってことでしょ。最高じゃない? みんなでMステとかゴッドタンとかさー、リアタイしようよ。会社のつまんねえ飲み会なんか全部ブッチしてさあ。
そんなことを話していると、一刻も早く四人で一緒に暮らすべきなんじゃないのかという思いが花乃子の中にむくむくと湧き上がってきた。「じゃあさじゃあさ、とりあえず二年くらいルームシェアでもしてみない? 試しに」という提案は、亜希と百合子には「悪くないね、一人で住むより経済的だし」「今しかできないし実際アリかも」と好感触で受け入れられ、澪に至っては筆記具まで取り出して全員の家の契約期間を確認し始めた。頭を寄せ合って最適な立地を考えたり、家賃はいくらまでなら出せるか、4LDKを探すならいっそ一軒家を借りるのはどうかなどと検索しまくっているうちに、いよいよ全員スマホを繰る目がマジになってくる。やろうと思えばできちゃうんだから大人って楽しい。
とりあえず転職したいが口癖となっている亜希の転職先が決まり次第四人の勤務地を加味して具体的に物件を絞り込もう、と議長の澪が宣言すると、「えーやばーてかそもそも選考のための有休とれるかなー」とかへらへらしてる亜希のスマホを百合子が奪い取り、希望条件をヒアリングしながら素早く企業を見繕いその場で二社エントリーさせて焼肉屋を出た。アルコールで
最寄り駅につくと、コンビニに吸い込まれてあれこれ買い込む。四人とももう感情と声量のコントロールができなくなって、道端でつまずいて転んだ亜希を囲んで息ができなくなるくらい笑った。家に入ってからはもう大声でお喋りするわけにはいかないので、くすくす笑いをこらえながらかわりばんこに風呂に入る。ベッドとその脇の床に敷かれた布団に二人ずつ寝そべって半時間も経つ頃、やっと会話が途切れがちになってきた。いつもはバカ話で笑い転げている四人だけど、とろみのある眠気の中でこうして近い距離に寝そべっていると空気が甘ったるくなり、何だか普段言えない大事なことが言えそうな気がしてくる。
とはいえ、普段言えないようなことで、みんなに知っていてほしい大事なことって一体なんだろう。何か大事なことを言いたいもどかしさはあるけれども、具体的に何を言いたいのか酔った四人には判断がつかない。
それぞれ仕事や男の愚痴を冗談めかして話すことはあっても、自分たちにとって本当に切実なあれこれを四人で話し合うことはあまりなかった。抗いがたい感情の波に襲われて身を縮め息を潜めている一人の夜には、みんなにこの苦しみをわかってほしい、次にみんなに会ったら絶対に話を聞いてもらわなければと強く思うのだけど、いざ顔を合わせると、伝えたかった重たい言葉はたちまち霧消し、しんどかったことがどうでもよくなって流れる楽しさに身を任せてしまう。四人でいると親しさが高じて自分たちだけに共通するノリとニュアンスで寸劇めいた会話を永遠に続けることができるから、結局意味のない話で何時間も潰してしまい毎回大事なことを伝えそびれる。別の友人に、そういえば澪ちゃん後輩の指導に苦労してるって言ってたねー大丈夫かな? とか当然あなたは知ってるでしょうってふうに伝えられたけどこっちはまるで初耳だというようなことがままあり、ひょっとして、私たちはお互いのことを実際はよく知らないのではないか? という懸念を抱くこともある。たとえば澪と亜希と百合子は、自分の失恋を茶化して笑う花乃子も内心では傷ついているのだろうと漠然とは感じていても、彼女が雄太との交際中にセックスレスに悩んでいたこともそのさなかに浮気されたことも知らないし、ましてやその事実に未だ苦しみ続けているなんてことは知る由もないのだった。悩みを打ち明けて慰めあったり遊ぶたびにいちいちインスタに投稿したりしない四人がともに過ごしてきたこの十数年でいったい何か積み重なるものはあったのだろうか。でも私たちは四人でバカ笑いしながら寸劇できてればそれでいいから。
誰かが口火を切るのを待つような、
花乃子たちは、そういう人生の大きなことを一切話し合ってこなかったから、他の三人がそれぞれ結婚したいのか子どもを持ちたいのかを知らない。親友に結婚および出産願望があるか、把握しているのがフツウ? みんな、別の友達とはそういうこと話してる? そもそも、四人とも自分自身がどう思っているのかすらよくわかっていないのだった。
うーん、と考えあぐねたまま花乃子が言う。
「雄太と付き合ってた時はいつか結婚して子どもつくるもんだと思ってたけど。別れてから、自分がどうしたいのかわかんなくなっちゃった」
「私も結婚したいかはわかんないけど……夫も子どもも持たずに、何十年もひとりで楽しく老いてく自信がない」
「今は楽しいんだけどねー」
「自分に飽きちゃいそう」
「ネットで見たんだけど、金、仕事、愛のうち二つに満足できてれば幸せな人生なんだって」
「二つってむずいでしょ!」
「私今んとこいっこも満たされてないんだけど」
「愛の部分がさ、友情じゃだめなのかな。友情って恋愛より弱いのかな」
「友愛でもいいんじゃない? 愛は愛だし。家族愛とかさ」
「友愛でいいんだったら私らとりあえず一つは全員クリアしてるじゃん!」
「うちら、愛情溢れる四人組だもんね」
「これから二年間、愛に溢れる家庭をつくってこうね」
亜希が軽い調子でそう言って、四人はそれぞれにめくるめく二年間を想像する。
「二年も一緒にいたらさ、一生一緒にいたくなっちゃうんじゃない?」
「なっちゃうよー絶対!」
どうしよう! と百合子は枕を抱える。
「ねえほんとにさ、私たち、家族になることにしようか。一生一緒に暮らそうか。そういう人生も悪くなさそうじゃない?」
花乃子の言葉に、床で寝ていた亜希と百合子もがばっと体を起こす。ベッドの上の花乃子と澪もいつの間にかうつ伏せの姿勢で上体を起こしていて、四人で顔を見合わせてにやっと笑った。
「悪くない!」
「むしろ良い!」
それは四人にとって、まだ見ぬ男と好き合って結婚し子どもをつくることよりもずっと実現可能性が高く、確かな幸せが約束されているように思えるプランだった。
「二年なんて言わずに、四人でずっと一緒に住み続けようよ。誰かが適当につくってきた子ども、みんなで育てたっていいしさ」
花乃子が言い、澪も同意する。
「そもそもさー、年齢も性別もバラバラの人間たちが血が繋がってるってだけで家族やるより、同年代の同性が寄り集まって暮らす方が効率いいに決まってんだよな。色んなもんシェアできるし」
「出た~澪の合理性至上主義」
「効率で家族やるなよ~」
「花乃子がやっぱ男の方がいいから出ていくって言い出したらしょうがないけど、その時は三日三晩送別会しようね。脱出ふざけんなパーティー」
「そんなもん脱出じゃねえ! 脱落だ脱落!」
「なめんな! 私は絶対に脱落しない! 絶対に全員看取ってやるから不穏なデータの削除ちゃんとしとけよ!」
あははっと笑って、また全員布団に潜り込めば、ようやく本格的な眠気が四人に降りかかり、全員似たような夢を見ながら眠った。そして翌日の昼頃のろのろと起き出して、ダル着のままスーパー行って食材買い込んでホットサンドをつくって食べて、食べ過ぎて、もう一生腹減んない気がすると言いながらNintendo Switchでマリオパーティと大乱闘スマッシュブラザーズを交互にやってたらあっという間に日が暮れて、じきに来る月曜の重たさが四人に徐々にのしかかる。死ぬまでこうしてたいな、と思う一方で、もし本当に私たちが家族になれたら、死ぬまでこうしていられちゃうのかーと思って、幸福の予感にちょっと
遊びの時間が終わって四人にも平等に月曜日がやってくる。澪が稟議承認スタンプラリーの段取りと根回しのテクニックを課の後輩に伝授したり、百合子が確認を急いでいる案件のレイアウトよりもまず容姿を誉めてくるプロジェクトマネジャーを強めに諫めたり、亜希が独り言なのか話しかけられているのか微妙に判断つかない先輩のぼやきを失礼にならない程度にやり過ごしながら虚無顔で弁当を食べたりしている時、花乃子はまだ自宅のベッドで横たわっていた。
花乃子は昨年電子部品メーカーの総務の仕事を辞め、専業少女漫画家として活動していた。いい加減に起き上がって原稿に着手しないといけない時間になっていたが、楽しかった週末の揺り戻しの死にたさに襲われ、午後になってもベッドから出られずにいるのだった。
四人でいる時はとにかくひたすら楽しくて、踊り狂いながら街を歩いたりして、この先私何にでもなれるじゃん! 男と別れたなんて些細なこと! 漫画だってそのうち売れるっしょ! って根拠なく無敵で楽観的になれるんだけど、その分翌日の揺り戻しがひどい。目覚めた瞬間から、ゆうべの万能感は何だったんだってくらい何もかもが不安になる。
死にてえな。とぼんやりと思う。
花乃子は、雄太と別れて初めて死にたいという感情を知った。
「死にたい」というのは正確ではなく、より言葉を尽くすならば、「五年後か二十年後かは知らないが遅かれ早かれ心から死にたいと感じる日が来ることへの恐怖」が花乃子を襲うようになったのだった。今はまだ、目先の楽しいこともあるし。若いし。セックスする相手もいるし。心から死にたいわけではなく、いろんなことが深刻じゃないけど。でも十五年後の自分はどうなの? 男も寄り付かず、漫画の売り上げもぱっとせず、友人たちも家庭を持って今みたいにつるんでられなくなったら私はいったいどうするの? いつか本当に深刻に死にたいと感じる日が来そうで怖い。要約すると死にたい。
花乃子は布団の中で目を閉じたまま、ゆうべ四人で交わした会話をひとつひとつ思い出すことで少しずつ死にたさを払拭し、机に向かう力を蓄えていった。早くみんなと住んで、揺り戻しに襲われる隙なんてないくらい毎日最強になりたい。
焼肉屋でシェアハウスについて話し合った日から二週間後の夜、澪と亜希と百合子は上野の韓国料理屋でチーズタッカルビを食べていた。花乃子が欠けていてもそれなりに盛り上がるが、それは四人揃った時のぴったりと満ち足りたような快感とは程遠く、普段の75%程度の盛り上がりでしかない。今日のように誰かが欠席したり遅れてきたりすることはもちろんあるけど、ホットなトピックは全員揃っていないと何となく切り出さない暗黙の了解がある。人生の進捗をみんなにリアルタイムで把握してほしいから、みんなに聞いてもらいたい話題がある時に四人揃わないと歯がゆい気持ちになる。
その頃花乃子は、三人が食事をしている店にほど近いタイ料理屋で、マッチングアプリでマッチングした男と会っていた。ときめきもないが不快な男でもない。つまり決め手がない。何か決定的なマイナスポイントがあればソッコー店を出て三人と合流しようとそわそわするが男は尻尾を出さない。何を話していいかわからず酒ばかり進む。メコンハイボールを飲みまくって酔いが回って、どうせ私は孤独に死ぬ、孤独に死ぬんですよとうわごとのように繰り返せば、あなたはまだ若いしじゅうぶん魅力的だから大丈夫ですよと慰められる。これは傷心ハラスメントといって過剰に自虐することで相手に無理やり自分の人生を肯定させる花乃子の常套手段である。タチが悪い。本気で思ってるわけじゃないのに口に出すことで本当に孤独に死ぬ未来を手繰り寄せているような気がして末恐ろしくなる。ふざけんじゃねえ! いいか、絶対に私は孤独に死なねえからな。
「解散した。今どこ?」と花乃子からグループLINEに連絡が入ったのを合図に、三人も会計を済ませて店を移動する。二次会の居酒屋にやや遅れて到着した花乃子はガンガン壁にぶつかりながらこちらにたどり着き、あ~くそ気持ちわりい、と吐き捨ててドスンと腰を下ろした。
「よくわかんないけど気に入られたっぽい。次は寿司食わせてくれるらしい」と呻くように花乃子は言った。
「マジ? 初デートでこんな泥酔しちゃってんのに? どんな男?」興味津々の様子で百合子が尋ねる。
「えーなんか人畜無害にちんこついて歩いてるみたいな男だった」
花乃子が言うと、百合子が即座に「ちんこついてんだったらいいだろうが!」と言い、そうだよな! ちんこついてんだったらいいよな! と二人が笑い合う中で澪の表情はかたく、「てゆーか、まだマッチングアプリなんかやってたんだ?」と冷めた目で花乃子を見た。
「え? まあそんなに熱心にはやってないけど」
花乃子が利用しているマッチングアプリは雄太に浮気された際に半ば当て付けの気持ちで登録したもので、ばからしくなって一度は退会したものの彼と別れてから再登録していた。
「相手の男のプロフィール、見せてよ」
ただならぬ雰囲気に
「……なんでこんな男にいいね押したわけ? 全然おもしろそうじゃないじゃん」
「いや別に、なんとなくだよ」
花乃子はこれまでどうせなら話のネタになりそうな男と出会いたいと言って、自己紹介文をモールス信号で書いてるやつとか(モテる気あんのか?)、趣味の欄に「正夢」って書いてるやつとか(どういうことだよ)、淫売狩りがマイブームです! って書いてるやつとか(よく見たら「渓流下り」だったから頭おかしいのは花乃子の方だった)、そういうオモシロ要素のある男にばかりいいね! を押していて、それによるオモシロハプニングが起こるたび嬉々として三人に共有していたのだった。
「だいたい世田谷区役所勤務って。遊びの男じゃないじゃん。完全に生涯を共にする前提の男にいいねしてるじゃん! 何がなんとなくだよ! こいつの顔だって全然好みじゃないでしょ。お前が好きなのは顔が可愛くって肌が汚い男だって知ってるんだよ!」
「いや男って写真下手だから、基本的にプロフィール写真の印象よりだいぶマシなのが来るんだって」
「そんなこと聞いてないんだよ。やっぱ花乃子さー、女友達と一生暮らしたいとかさ、口だけだよね」
「え、澪なんか怒ってる?」
不安そうに瞳を揺らして花乃子が言う。対角線の位置に座っている亜希と百合子は一度ちらりと目を合わせ、口を出さずに花乃子と澪の会話を見守っている。
「別に怒ってはない。ただ、男と別れて頭おかしくなってる花乃子の言葉を真に受けてちょっとでもマジになっちゃった自分にがっかりしてるだけ」
「ほんとに私、みんなと一生一緒に暮らせたらいいと思ってるよ」
「でも現に結婚相手探してるじゃん、アプリで」
「別に結婚相手探してたわけじゃないけど、安定した職業の男にぐっと来たのは認めるよ。私はさー、不安定な仕事してるから不安なんだって。もう毎日毎日ほんとに不安なの。不安で泣けてくんの」
「不安なのは私だってそうだよ」
「大企業勤めの澪と私とじゃわけが違うよ!」
「何それ。漫画家が不安定なのわかってて会社員辞めたのは花乃子だし、私が大企業に就職したから人生不安じゃないって思ってる? 結局花乃子はさー、何だかんだ言って男の方が好きなんだよ。精神的にも経済的にも、女より罪悪感なく甘えさせてくれるから! 女友達と支え合って生きていくのはやっぱ花乃子には難しいんだよ。あんたは支え合いたいんじゃなくてただ甘えたいだけなんだからさあ。もう女友達と住むなんて夢見てないで、潔く甘えさせてくれる男探せばいいよ、それも一種の就活だよ。若くて有利なうちに結婚目指せば?」
とはいえそう花乃子に言い募っている澪自身も、現時点で本当に四人で一生一緒に暮らしていく覚悟があるわけではないのだった。それを他の三人もわかっていた。
普段の四人ではありえないたっぷりした沈黙のあと、澪は「ごめん、言いすぎたね。最近仕事忙しくて、なんかイラついてたのかも」と決まり悪そうに謝った。「私もごめん」と花乃子も小声で謝る。
花乃子たちは高校入学時から十年以上の付き合いになるけれども、喧嘩や言い合いのようなことをした経験はかつてなかった。それは仲の良さの裏打ちというよりは、これまでいかに深刻な、切実な話題にまともに取り合ってこなかったかの証明で、四人はいまそのツケを払わされていた。
亜希がためらいがちに口を開く。
「私たち、どうやったら不安じゃなくなるんだろうね。下手に選択肢があるから迷うのかな」
東京在住二十六歳大卒の四人には選択肢がありすぎて、心もとないほど自由だった。何を選んだって構わないはずなのに、いちばん大勢の人が乗ってて声がでかい「男と結婚して出産」ってプランがベタに幸せっぽいせいで迷うし苛立つ。女友達と暮らす人生! ってパッケージがAmazonで売ってて、☆5のレビューが百万件ついてたら安心できるのだろうか。幸せっぽさ、ぽさ、ぽさ。ぽさこそが全て。私たちには幸せと幸せっぽいものの区別がつかない。
「本当に、私たちの間に子どもができちゃえばもう迷わないのかもね」と花乃子がぽつりと呟いた。
「私、娘ができたら竹下通り行きたいなー一緒に」
花乃子たちは、いま直面している重要事項について、しっかり話し合うべき局面なのかもしれなかった。ただ、慣れない口論をしたばかりの花乃子と澪には気力がなく、臆病な亜希には蒸し返す勇気がなく、揺らぎの少ない百合子は切実さの輪郭をつかみかねていた。四人とも、意味のないことにばっかり口がまわって、深刻さを保つ能力がなかった。ふざける以外に場の雰囲気をまとめる手段を知らない四人は、花乃子と澪が言い合ったことを帳消しにするように酒を多めに飲み、架空の子どもの話で盛り上がってまた例のノリに身を委ね、意味のない寸劇で大笑いして夜を更かしていった。
亜希の転職活動は遅々として進まず、ルームシェア計画も動かない。現在OA機器を扱う会社の営業事務として働いている亜希は「結局自分が次どんな仕事したいかわかんないんだよね~」と軽い調子で言うが、全員にとってそれが切実な問いであることも、答えが出せないことも明白で、誰からともなく、よっしゃじゃあ四人でキッザニアでも行くか~ってふざけてしまう。すぐさまググるとキッザニア東京は三歳から十五歳までしか職業体験できないが大人も付き添いというかたちならオッケーだということがわかり、亜希が今推してるアイドル研修生は十四歳であるので、おい! 一緒に行ってくれってお願いしろよ! とひと盛り上がりする。
亜希の勤務先が決まるまで具体的に動き出さない段階にあるからこそ仮想シェアハウスの話は弾む。花乃子がグループLINEに「それぞれの個室に東西南北で名前つけようよ。四神的な。澪ってなんか北の玄武っぽくない?」と送れば「玄武って咬ませ犬っぽくね? 嫌です」「私は朱雀がいい。譲れない」「ハリー・ポッターの寮の名前にするのはどう?」などと返事が来る。またある日は「シェアハウスでハリネズミを飼い始めました」と亜希が写真を送ってくる。「リビングにシロクマの椅子をおくことにしました」と澪が楽天のURLを送ってくる。「今日ノー残業デーだからシェアハウスそばの区民プールでひと泳ぎしてくるわ」と百合子が報告してくる。実際には何も動き出さないままイマジナリーシェアハウスのディテールは着々と充実していく。ついには百合子が「シェアハウスを引き払う前日の夜、床で酒を飲みながら全員で大泣きしました」と送ってきた時はさすがにいや勝手に完結さすなや! と三人で怒ってやった。
花乃子と澪が口論した日から、マジレス無用のノリに拍車がかかっていた。言い合いなんてらしくないことしちゃったから、私たちらしさを取り戻すために誰からともなく過剰にふざけているようだった。しかし、話が弾めば弾むほどにルームシェア計画はどこかフィクションめいてきて、四人の手から遠のいていくような心細さがあった。
よく晴れた土曜日の午後、四人はそれぞれに髪を結い上げてパーティードレスに身を包み、白いクロスがぴっちりと引かれた丸テーブルに着席していた。この八名席には、花乃子たち四人と、その反対側には雄太を含む男子四名が腰かけている。式場受付で席次表を受け取って自席を確認した瞬間、花乃子以外の三人は肝を冷やした。四人の高校の同級生である新郎新婦は、花乃子と雄太が十年の交際に終止符を打ったことを知らず、(おそらく)善意で二人を隣り合わせの席に配置したのだった。三人が遠慮がちに花乃子の表情を窺うと、花乃子は席次表で顔をぱたぱた
丸テーブルに置かれている花乃子の席札には「花乃子ちゃん♡今日は来てくれてありがとう♡花乃子ちゃんも雄太くんと幸せになってね♡」と書かれた新婦直筆のメッセージがあり、隣の雄太の席を見るとだいたい同じようなメッセージが添えられていた。(「雄太くんも花乃子ちゃんを幸せにしてあげてね♡」)
お前が新郎かってくらい緊張の面持ちで現れた雄太に花乃子の方から歩み寄り、お互いの席札を指差して「ねえねえ見てよこのメッセージ~」と笑いかけた。雄太および連れの男子たちはその一見和やかな態度に安堵した様子を見せたが、澪と亜希と百合子は内心舌打ちをする。花乃子はこういう場で条件反射的にピエロを演じてしまうタチなのである。内面に住まわせているピエロを飼い慣らせていないのである。つまり私たちの花乃子が割を食っているのである! 花乃子は「これほんと高度なジョークだよね~写メ撮ろう写メ」と言って雄太と顔を寄せ合い、お互いの席札を顔の横に掲げて満面の笑みで自撮りを始めた。シャッターを切る瞬間の雄太のちょけた表情が腹立たしい。花乃子はスマホで画像を確認しながら「は~まじでうける。これインスタにあげよ~」とフリック入力を駆使して「しげくん桃ちゃんおめでとう! 言い忘れてたけど私たちは音楽性の違いで解散したのでした! 私たちの分まで幸せになってくれよな! #しげももwedding #このテーブルは戦場になる #再結成の余地ナシ」とコメントをつけてツーショットをインスタグラムに投稿した。ついさっきロビーで「Please tag your photos with #しげももwedding」という文言が記載されているハンドメイドのウェルカムボードに深い感銘を受けていた花乃子の瞬発力に感嘆しながら三人も素早くいいね!のハートマークを押した(結果的にこのタグで投稿された写真のうち最もいいね!数を獲得したのが花乃子と雄太の破局報告となる)。男子たちは、この光景を笑っていいものか迷って終始苦笑いしながら目をぱちぱちさせていた。
披露宴が始まってからも花乃子は快活に喋りまくり、進行に合わせて笑い声を上げたり大きく拍手したりと式を満喫している
そんな中、男子のうちのひとりが当たり障りのない会話でお茶を濁そうとして「四人は今でもよく会ってるんだ?」と尋ねてきた。「よく会うどころかこれから一緒に住むんだよね私たち四人で。亜希の転職先決まり次第物件探し始めるの」と澪がにこにこと答える。
「え! そうなの? 相変わらず仲良いねー」
雄太が目を丸くして言い、花乃子が笑顔で答える。
「うんそうなの! めっちゃ楽しみ」
「でもさーそれって婚期逃しそうじゃない? 大丈夫?」
雄太の発言ににわかにテーブルが緊迫するが、花乃子は表情を変えずに赤ワインを呷って言った。
「いや、一生四人で暮らすから関係ないから婚期とか」
「一生? どういうこと?」
「ルームメイトじゃなくて、家族になんの。私たち」
家族? と怪訝そうにする雄太を尻目に花乃子はワインをお代わりし、披露宴は順調に進んでいく。新郎新婦の中座中に会場の照明が落とされ、新郎の手による二人の生い立ちやなれそめをまとめたムービーが映し出される。BGMが流れ始めた段階で、ああこれはまずいな、と四人は反射的に身構えた。二人で行ったイタリア旅行の様子やパジャマ姿で微笑む新婦の画像。四人とも新郎新婦が恋人時代に起こしたしょうもないゴタゴタのいくつかを知っているが、それでもこうして幸せの上澄みを抽出した幸せっぽさ一番搾りを見せつけられると否応なく泣けてくる。この涙、何の感情? スクリーンに映し出されている二人のストーリーは、取り立ててインパクトのないよくある話だ。でもそのよくある話を私たちは誰も手にしていないし、BGMにキリンジを使用されたら泣くしかないし、キリンジを流すために著作権料をいくら払ったのかを考えるとさらに泣けてくるのだった。
その後、新婦友人による余興ダンスや両親に宛てた手紙の朗読などが行われ、感動的で非の打ちどころのない披露宴はつつがなく終わり、ひとつの正解のかたちを目の当たりにした花乃子たちはずっしりとした疲労を感じていた。新婦が妊娠中のため二次会は設定されておらず、四人は幸福な夫婦に見送られて会場を出る。
幸せっぽい披露宴の余韻で全員著しく口数が減っていた。つむじからつま先まで綺麗に整えられたこの体とその中のめまぐるしい感情を自分たちだけで正しく処理して、一刻も早く最強になる必要があった。
「もういいよ」
澪の家に向かう電車の中で、ドアに体を預けた亜希が言った。
「転職できんのいつになるかわかんないからさー、もうルームシェア計画進めよう。私、ルームシェア始めてから本腰入れて転職活動するよ」
「マジで!?」
亜希の宣言に四人は活気付いた。今日の式で捻出された感情をシェアハウス計画の推進に充てるのは、考えうる限り最ものぞましい発散の仕方のように思われた。引き出物の重たさもむくんだ足の痛みもたちまち消え去った。
澪の家の狭い玄関にサイズの異なるハイヒールが四足並ぶ。おおよそ十センチ背の低くなった四人は、めいめいベッドやクッションに腰を下ろして乾杯した。今後の具体的なスケジュールおよび役割分担を澪が熱心に提案している中、花乃子が顔色を変えてスマホを気にし始めたので、亜希が「どうかした? なんか仕事の連絡?」と尋ねると、花乃子は「雄太からメッセージ来てる」と早口で答えた。
「何て?」
「話がしたいって」
四人で顔を寄せ合って花乃子のスマホを覗き込むと、雄太から「今どこにいる?」「ちょっと会って話せないかな」などとメッセージが届いていた。
どうしよう? どうしたらいいかな? と動揺する花乃子に、澪は「呼んだらいいじゃん。ここに」と言った。
「でも」
「いいから。呼べ」
澪は有無を言わさぬ口調で言った。亜希と百合子は思わず顔を見合わせるが、花乃子はそれに従ってメッセージを打ち込んだ。
数十分後、澪の家にインターホンの呼び出し音が鳴り響く。四足の華奢なハイヒールの中に丈夫そうな黒のストレートチップシューズが鎮座して、狭い玄関がさらに窮屈そうになる。
花乃子の隣に腰を下ろした雄太が居心地悪そうに、「えっと、ちょっと花乃子と二人にしてもらってもいい?」と切り出すと、「無理」と澪が間髪容れずに断った。
「ここでできない話だったら帰ってください。私たちこれから物件決めの話し合いをしなきゃいけないので。なるべく長く住める良い家に決めたいし」
「
「マジで? 本当に一生四人で住む気でいるの? 花乃ちゃん、やっぱり考え直した方がいいって。俺たちもうすぐ二十七歳じゃん。もう子どもいる同級生だっているわけだしさあ。もっとちゃんとよく考えなよ」
雄太は花乃子を見つめて、切羽詰まったように話し出す。
「シェアハウスも、更新しないで二年とかでやめるんだったらまだいいよ。でもそれだって終わる頃には二十九歳だよ。ほとんど三十歳だよ。こんなこと言いたくないけど、男の三十と女の三十はわけが違うでしょ。ルームシェアはいつでもできるけど子どもはいつでも産めるわけじゃないんだよ。結婚適齢期の二年間をわざわざ捨てなくてもさあ、どうしてもみんなで一緒に住みたいんだったら老後だっていいじゃん! 今日の式だってさー、二人、すごい幸せそうだったでしょ。花乃ちゃんなら今からでも絶対良い男つかまえられるって!」
花乃子の方だけを向いて話していた雄太ははっと顔をあげ、三人に向けて取り繕うように言った。
「みんな良い子なんだから絶対結婚できると思うし、家族じゃなくてもママ友目指せばいいじゃんか! それにほら、さっきの式でも百合子ちゃん見ていいなーって言ってるやついたんだよ? シェアハウスとか言ってるから引いちゃったみたいだけど」
謎に少し得意げな雄太の表情に、百合子は露骨にオエッという顔をし、澪と亜希はそれぞれ苦笑した。雄太は花乃子に向き直って話を続ける。
「俺はさー、別れた今でも、花乃ちゃんのこときょうだいみたいに大事に思ってるから言うんだよ。どうでもいい子が一生女友達と暮らすって言っても止めないよ。わかってよ。漫画の仕事だっていつまであるかわかんないんだし、俺は花乃ちゃんに普通に幸せになってほしくて言ってるんだよ。花乃ちゃんによその男と幸せになれなんて死んでも言いたくないんだよ本当は。ねえ、俺がどんな気持ちでこんなこと言ってるかわかる?」
雄太は大事な話をする時いつも手を握るのを、花乃子はよく知っていた。
その高い体温が、花乃子を今追い詰めている。
「別れる時さ、花乃ちゃん俺に言ったじゃん。俺たち、長く付き合って、きょうだいみたいな関係になっちゃったのが嫌だったって。俺ときょうだいみたいになったのは嫌だったけど、女友達と家族になるのはいいの? ごめんだけど、俺それ全然わかんないよ。ねえ、それって逃避じゃない? だったら俺たちってなんで別れたの?」
真剣に話をする雄太の手には、目のくらみそうな幸せっぽさがつまっていた。この人といつか結婚したいと無邪気に思っていた時もあった。仲が良いと評判の二人で、共通の友人も多くいる。家族も雄太を気に入っていた。花乃子は、雄太自身ももちろん好きだったけれど、一緒にいることで多くの人から祝福されそうな雄太と花乃子というカップリング、二人のストーリーの幸せっぽさも愛おしく思っていた。雄太と花乃子には、うさんくささのない幸せっぽさがつまっていた。でもその幸せっぽさではやり過ごせない幾多の夜の重たさを、花乃子は乗り越える自信がなかったのだ。
「俺が、本当に花乃ちゃんのこと幸せにできればよかったのにね」
雄太が何かをぎゅっと我慢するような表情で言い、花乃子の目から涙がこぼれ落ちると、それまで静観していた澪が花乃子を引き寄せ、雄太をきっと睨んで言った。
「男がいないと幸せになれないと思わないでくんない」
亜希と百合子も即座に加勢する。
「そもそもお前が花乃子を幸せにできなかったんだろ」
「マジで白けること言うんじゃねーよ頼むから」
「むしろありがとう花乃子を返してくれて!」
「つか、私たちを考えなしみたいに言うけどさー、自分はどうなの? ちゃんとしっかり考えた上で花乃子は既存のレールに乗るべきだと思ってるわけ?」
澪は、亜希と百合子とともに雄太に向かって矢継ぎ早に言葉を投げかけながら、やっぱり花乃子を一人で行かせないでよかったと実感していた。でも、これから四人で一緒に暮らし始めたら、ましてや家族になったら、いま花乃子が雄太に言われたようなことを、私たちはどのくらいの頻度で、どのくらいの熱量で周囲から言われ続けることになるんだろう。そのたびに私たちは迷うんだろうか。今日みたいに四人で団結できればいい、でも私たちが打ちのめされるのはだいたいひとりの時だから。
楽しそうだから一緒に住むんだ! って手放しに言いたい。幸せっぽい誰かに怯えたくない。私たちだって祝福されたい!
俯いて沈黙していた花乃子がついに口を開いた。
「ねえ、でもやっぱり私、子どもがほしいかもしれない」
「そうだよね?」
雄太が勢いよく花乃子の手を取る。花乃子は、その手を握り返しも振り払いもしないまま淡々と言った。
「私たち、雄太との間に一人ずつ子どもつくって八人家族になるのはどうだろう。そうすれば子どもどうしに血の繋がりもできるし、本当の家族になれるよね」
雄太の表情につかの間表れた期待はすぐに失せ、色濃い困惑へと変わる。
「花乃ちゃん、自分が何言ってるかわかってる?」
澪と亜希と百合子は、息を飲んで考える。どっちだ? これは花乃子が真剣に言っているのか、それともいつものふざけたノリ、マジレス無用の寸劇の一環か? 三人とも判断しかねて言葉が出ない。
「なんかもう、私、ほんとにみんなとの子どもほしくなっちゃったんだよ。四人で本当の家族になりたいよ。もう一秒も迷いたくないの」
花乃子が真剣だということが語尾の震え方でわかったが、わかったからこそ澪も亜希も百合子も何も言えない。意味のないふざけた会話なら何時間でも続けられるのに、肝心なところで言葉が出ない。切実な響きを感じ取った瞬間怖気付いてしまう。
静寂の数分間が過ぎ、得体の知れない何かに背中を押されるようにして百合子がおずおずと喋り出した。
「花乃子の前衛的な提案を尊重するとなると、ここで気になるのは受精方法ですが……」
一瞬部屋の時が止まった。
「着床するまで全員と寝るってこと?」
亜希がそれに続く。
「それはさすがに恐怖政治すぎ」
澪が笑い混じりに言う。
「産む順番どうやって決めよっか? 殴り合う?」
「そこはうちらの鉄砲玉こと百合子からいくっしょ」
「いいけど、お前ら第一子からめっちゃ可愛がれよ。愛も財も全力注げよ」
「つうか同じ男の子を産むにしても、私は普通に精子バンクから選んだ方がいいと思う」と言う澪に、花乃子は「なんで? 雄太、ちょっとバカだし背も低いけど顔は可愛いし人は好いし良くない!?」と反論する。
ぐっと踏み込まれたアクセルで普段のリズムを取り戻した四人は、口々に推しの精子をほしがったりSF的解決を提案したりと会話が急速に大喜利めいてきて収拾がつかなくなる。露骨に嫌悪感を示していた雄太もつられてちょっと笑ってしまっている。
よおしわかったわかった、と言って澪はすっくと立ち上がり、テレビの方に近寄ってNintendo Switchを起動させ「ひとまずスマブラで勝った人がどの男に精子もらうか決められることにしよう」と言い放った。
かくして、花乃子たち四人と雄太はテレビの前に並んで座っている。「ねえ、さっきからほんとみんなして何言ってんの? 四人ともちょっとおかしいよ!」と抵抗していた雄太も、Switchのコントローラーを手渡されると、
私たちは、なんでいまこんなことになっているんだっけ? スマブラで決着をつけることを提案した澪でさえもがそう感じていた。四人はひとたびふざけ始めると、自分たちでもコントロール不可能な大きな流れみたいなものが出現し、もう自分の意思でどうこうできなくなってひたすらそのノリに身をまかせるしかなくなる。澪がスマブラを起動させたのも、百合子が花乃子の提案を茶化したのも、決してそうするのが最善と思ったわけではなく、得体の知れないグルーヴに支配されていてそうせざるを得なかったのだ。私たちは、それに抗わないことで今日まで楽しくやってきた。
とはいえ、私たちは、花乃子の真剣な提案を、もっと真剣に受け止めるべきだったんじゃないか? もしかして、私たちは今、ものすご~く、間違えているんじゃないだろうか?
私たち、な~にやってんだろ? 幸せってな~~んだろ?
押し黙ってプレイする中で、雄太が「ちなみにこれ俺が勝ったらどうなんの? シェアハウス計画、いったん白紙にしてくれる?」と問いかけるが揃って黙殺する。五人のダメージ量を示すパーセンテージがそれぞれどんどん上がっていく。その数字の高まりに合わせて、花乃子たちの内なる何かも切迫していく。
ドレスアップした四人は、床にぺたりと座ってコントローラーを握り、一様にテレビ画面と向き合っている。打ち合わせることなく選んだドレスの色は見事にばらばらで、赤青黄緑の鮮やかなスカートのすそがふわりと床に広がって、上から見れば四輪の花のようだった。瞬きをするたびに、丁寧にマスカラを塗られたまつげがぱしぱしと音を立てるけど、ゲーム音量が大きくて誰の耳にも届かない。ベージュのストッキングのつま先から透けて見える爪すらも、それぞれ今日のために鮮やかに彩られているのだった。
部屋には、ゲームBGMと、コントローラーのちゃかちゃか言う音だけが響き、五人は完全に無言だった。その沈黙を破ったのは、現状雄太の次に優勢な澪だった。意を決したように話し出す。
「迷わないための手段として子どもを持とうとするのは違うと思う」
花乃子と亜希と百合子は黙ったまま、目線と体勢は動かさずひたすらピカチュウをボコボコにしている。
「無理に子どもつくらなくても、私たちは一生一緒にいられると思う」
澪は、言い終わるのとほとんど同時に手をすべらせてコントローラーを取り落としたが、素早く持ち直した。百合子は狙い通りにコンボ攻撃をピカチュウに決めて、っし、と小さく声を漏らし、「花乃子が雄太と別れた時さー」と続けて言った。
「すぐ私たちにLINEくれたじゃん。その時さー、『十年分のセーブデータが消えた気分だわ(笑)』って送ってきたの覚えてる?」
三人は、その瞬間のことを鮮明に覚えている。その時澪は休日出勤していて、いつもより静かなオフィスで捨て鉢な気持ちで資料作成をしていた。亜希はよく行く喫茶店の気に入りのソファでネットサーフィンをしていた。百合子はあと一本でやめようと思いながら海外ドラマを三時間近く見ていた。
「私たちだってさー、高一の時からの仲だから、もう十年分以上セーブデータ持ってるわけじゃん、花乃子の。雄太が持ってた分が消えたくらいで悲しまないでよ。これからあとまだ何十年もあんだよ。あんたのセーブデータ、死ぬまで持っててやるからさあ」
戦いは終盤に入っていた。いつ脱落してもおかしくないダメージを負っている亜希も「私思うんだけど」と忙しない指の動きとは対照的に、ゆっくりと言葉を紡ぐ。
「もう十年も二十年も経てばさ、今時男女で結婚とか古くない? って感じの社会になってると思うんだよね。なんかこう、制度も整ってさー、今よりずっと、私たちが明るく仲良く暮らしやすい感じになってるよ、わかんないけど」
澪の攻撃をかわしたピカチュウが、手際よく亜希にかみなりを食らわせた。
「わかんないけど……絶対そうなると思うんだよ、わかんないけど」
花乃子は、コントローラーを操作しながら、どこか気の抜けた表情で三人の言葉を聞いていた。
画面の中では、一進一退の攻防が続いている。
「今日の式さあ」
テレビ画面から片時も目を離すことなく花乃子が言う。「うん」と私たちは相槌を打つ。
「すごい良かったよね」
「うん」
「超良かった」
「綺麗だったね」
「ほんと、幸せそうだった」
表情を変えずに口だけを動かして花乃子が言う。
「私たちの結婚式もさ、今日みたいに天気のいい土曜日がいいよね」
私たちは想像していた、四人で挙げる結婚式の光景を。普段ならそれは、すぐさま口に出して共有して、何時間だって寸劇できるような詳細な想像だった。今夜だけは私たちは無言で、その式の様子を思い描いていた。よく晴れた涼しい土曜日の午後、四人とも真っ白なドレス着て、大口開けて笑って踊り狂って、金に糸目つけずに好き勝手なBGM流して、参列した全員が、こんな幸せで楽しい結婚式ないよって言い合うような、誰もが祝福せずにいられないような、ぴったりと満ち足りた非の打ちどころのない結婚式の想像だった。お色直しでは今日みたいにさ、みんなばらばらの色のドレス着よう。それぞれいちばん好きな色。ハッシュタグの名前なんにしよ? 世界中にシェアして、いいよ。