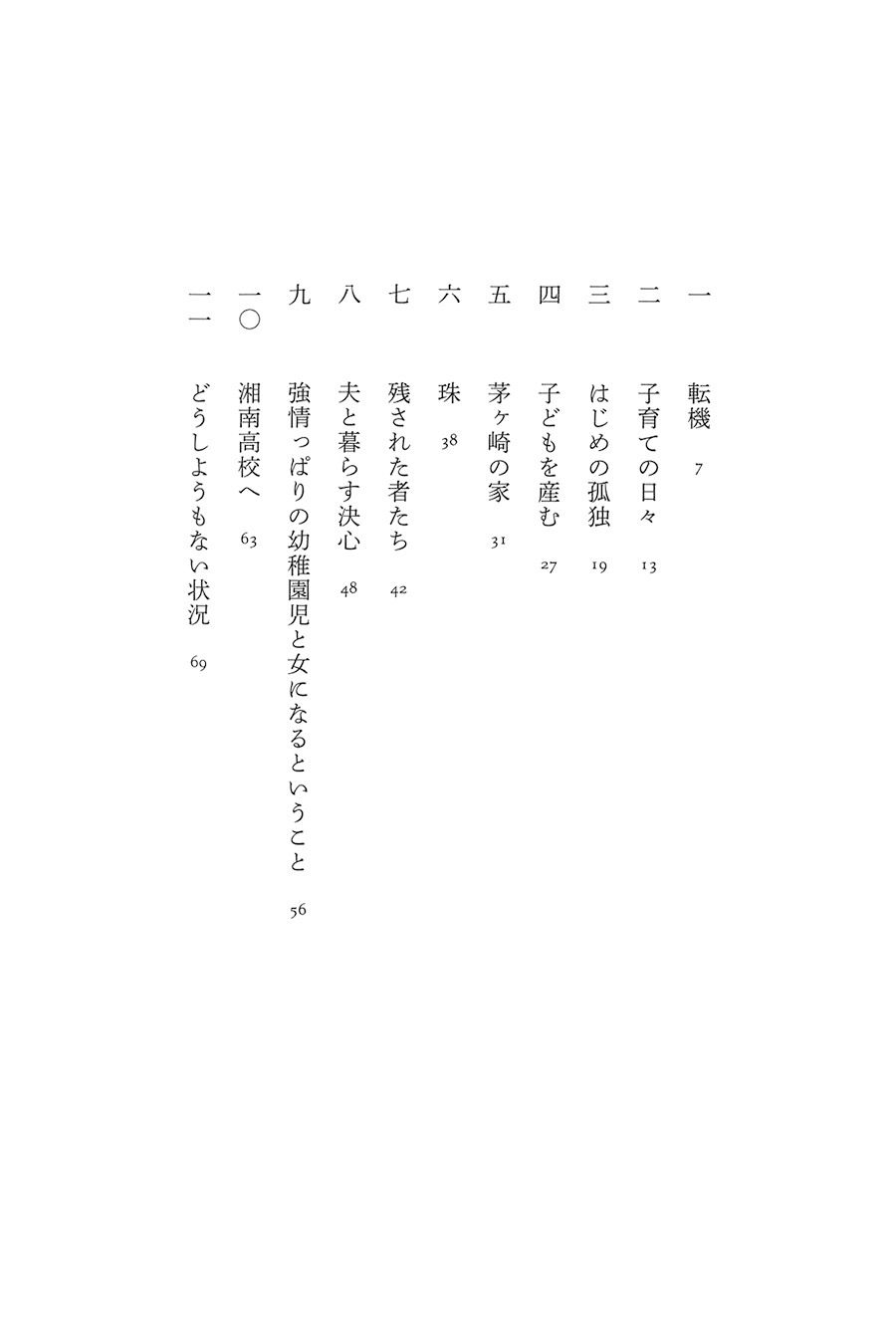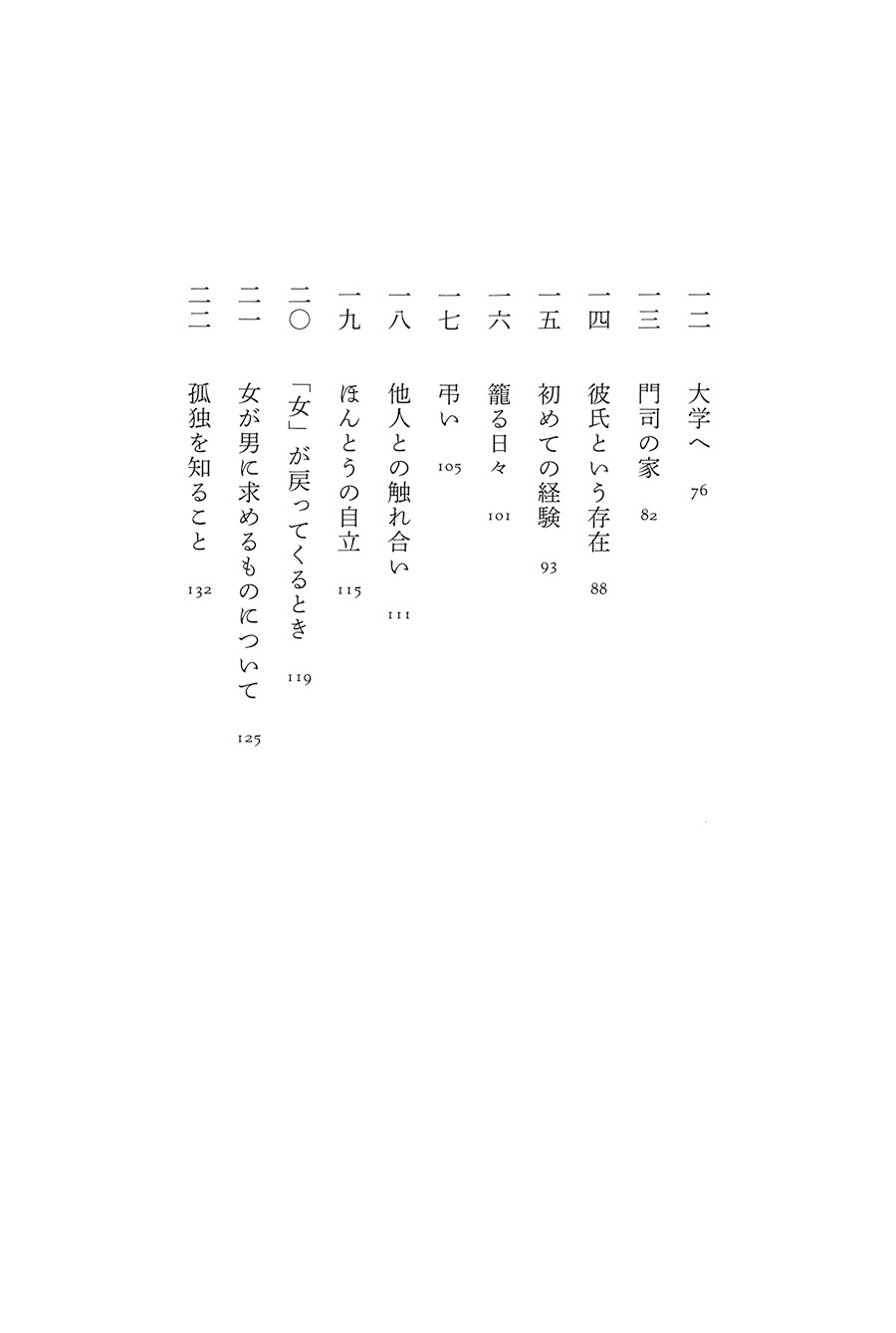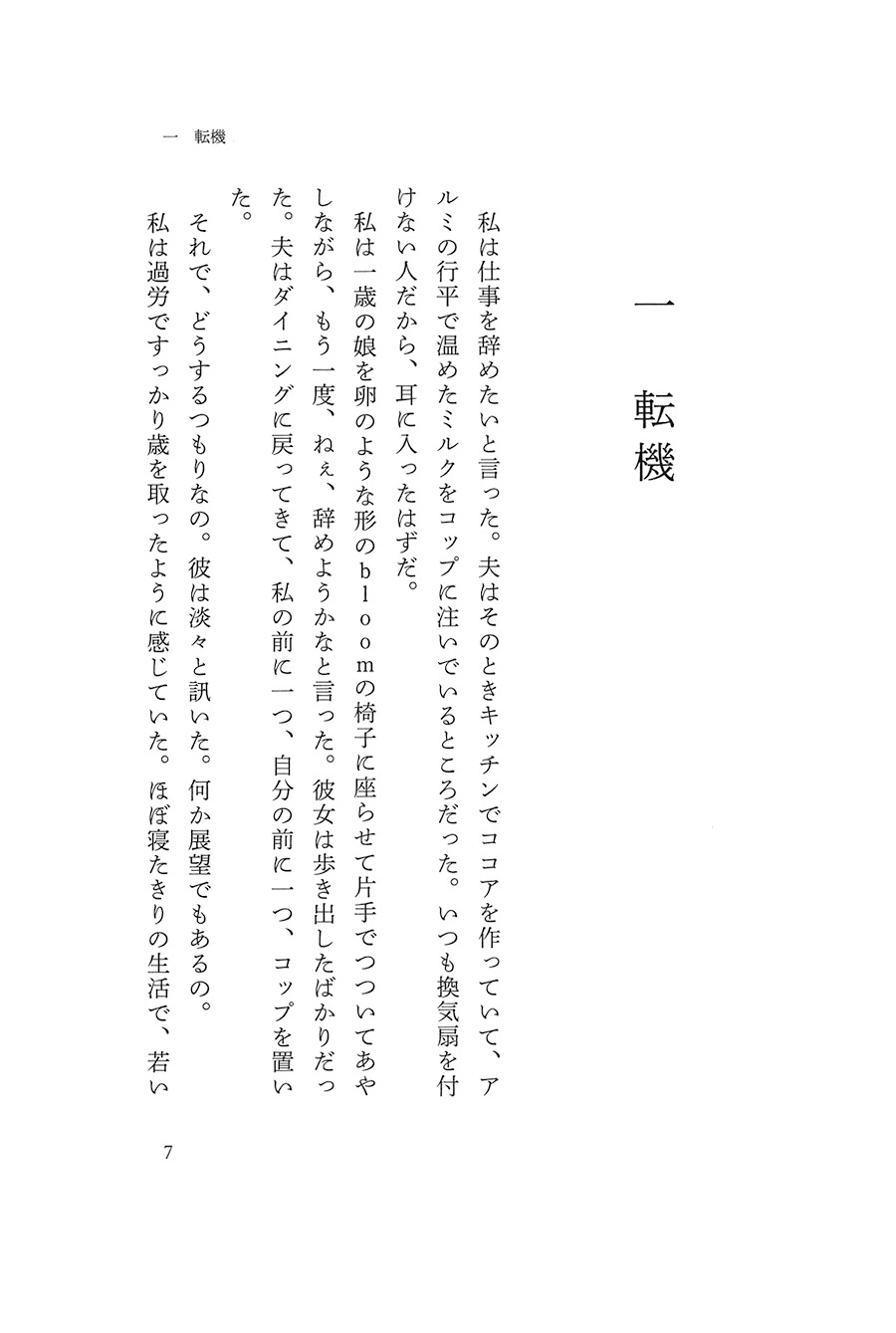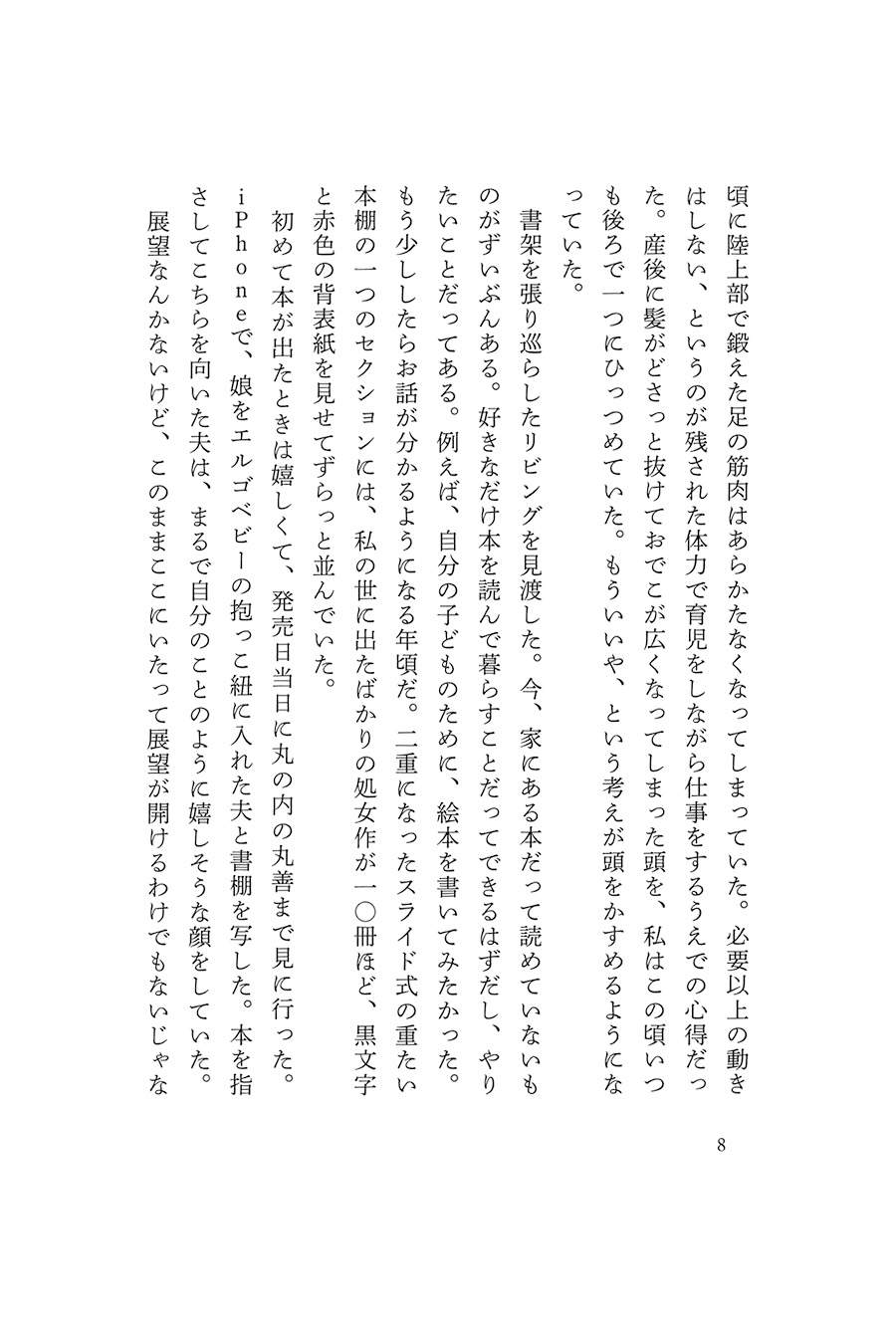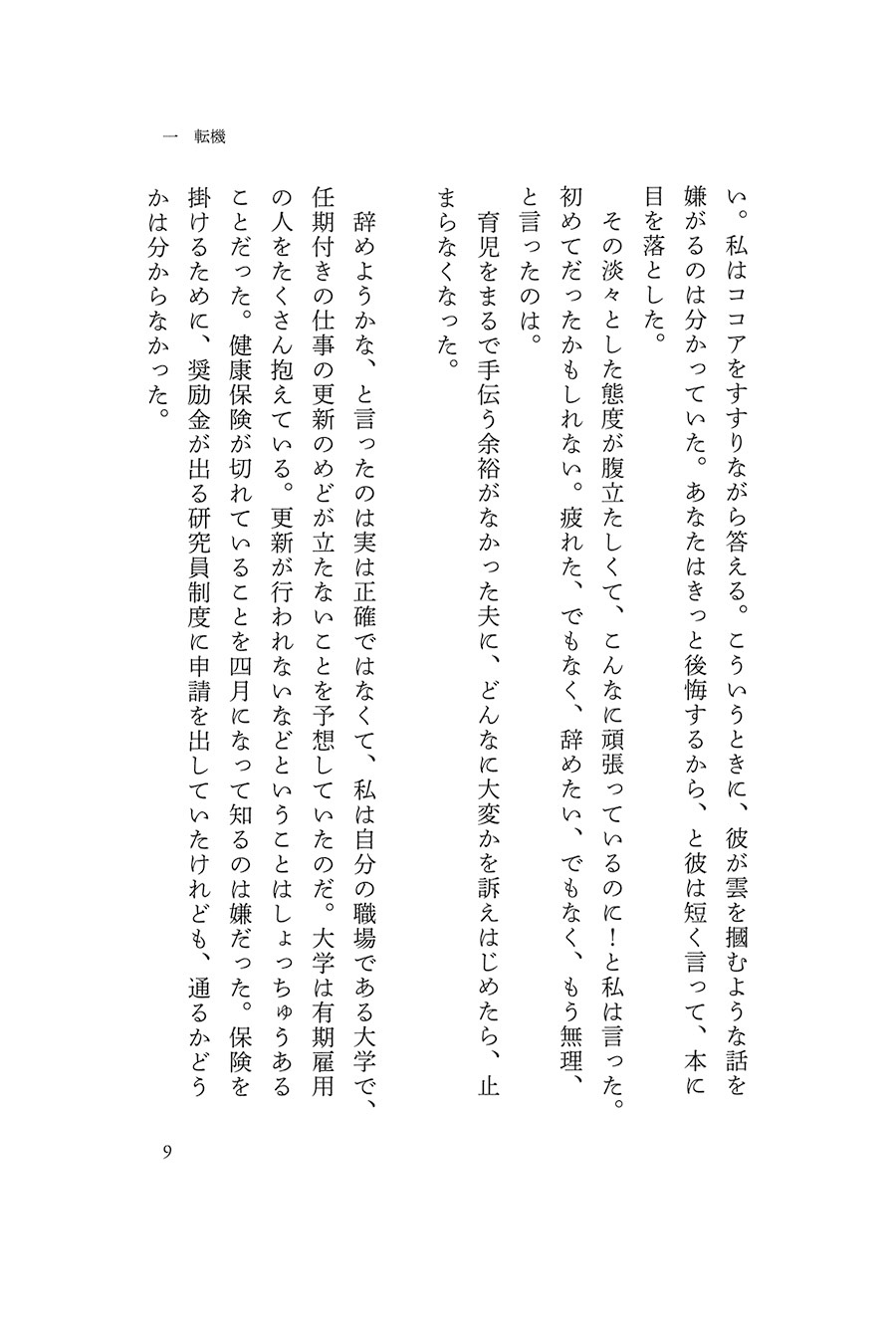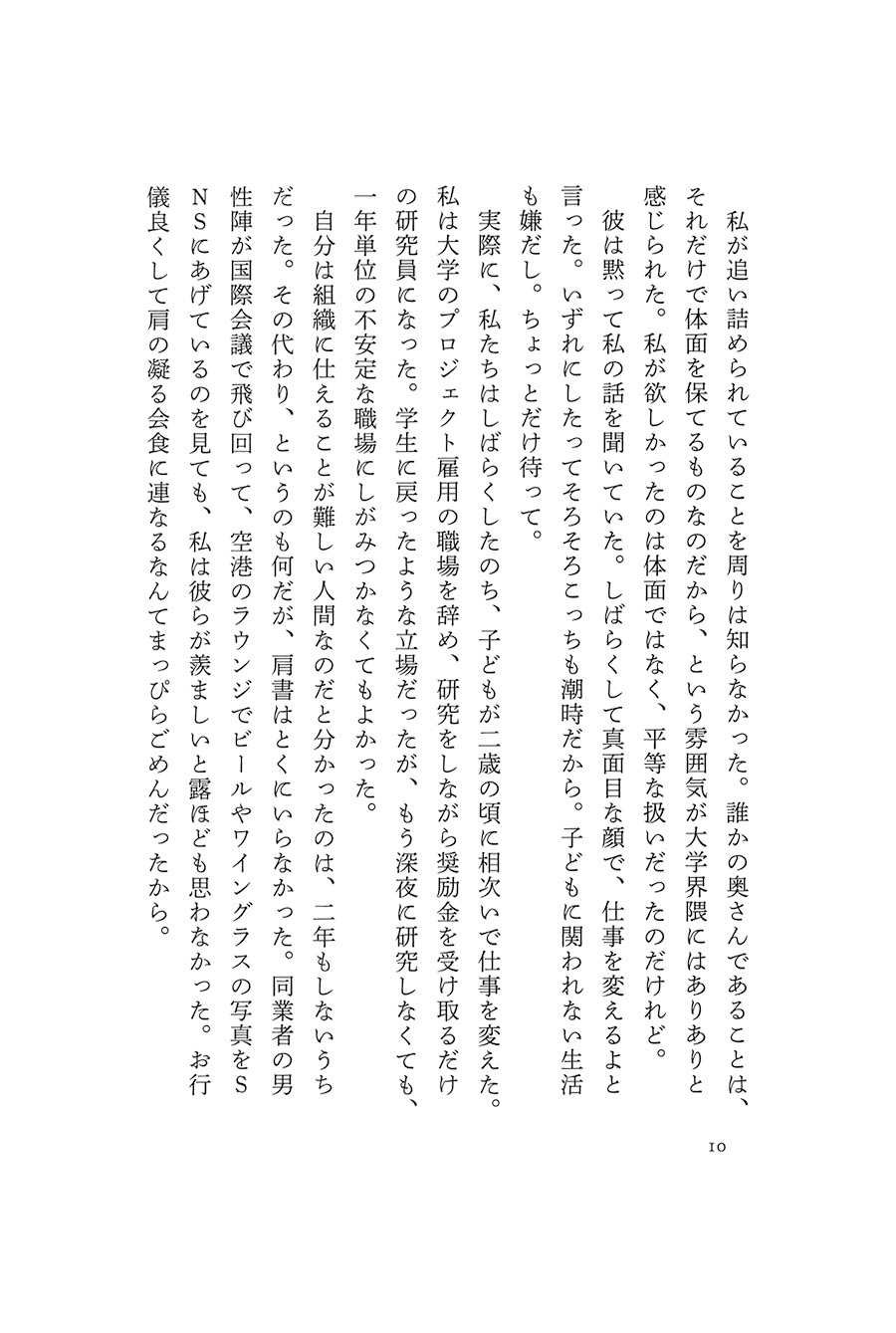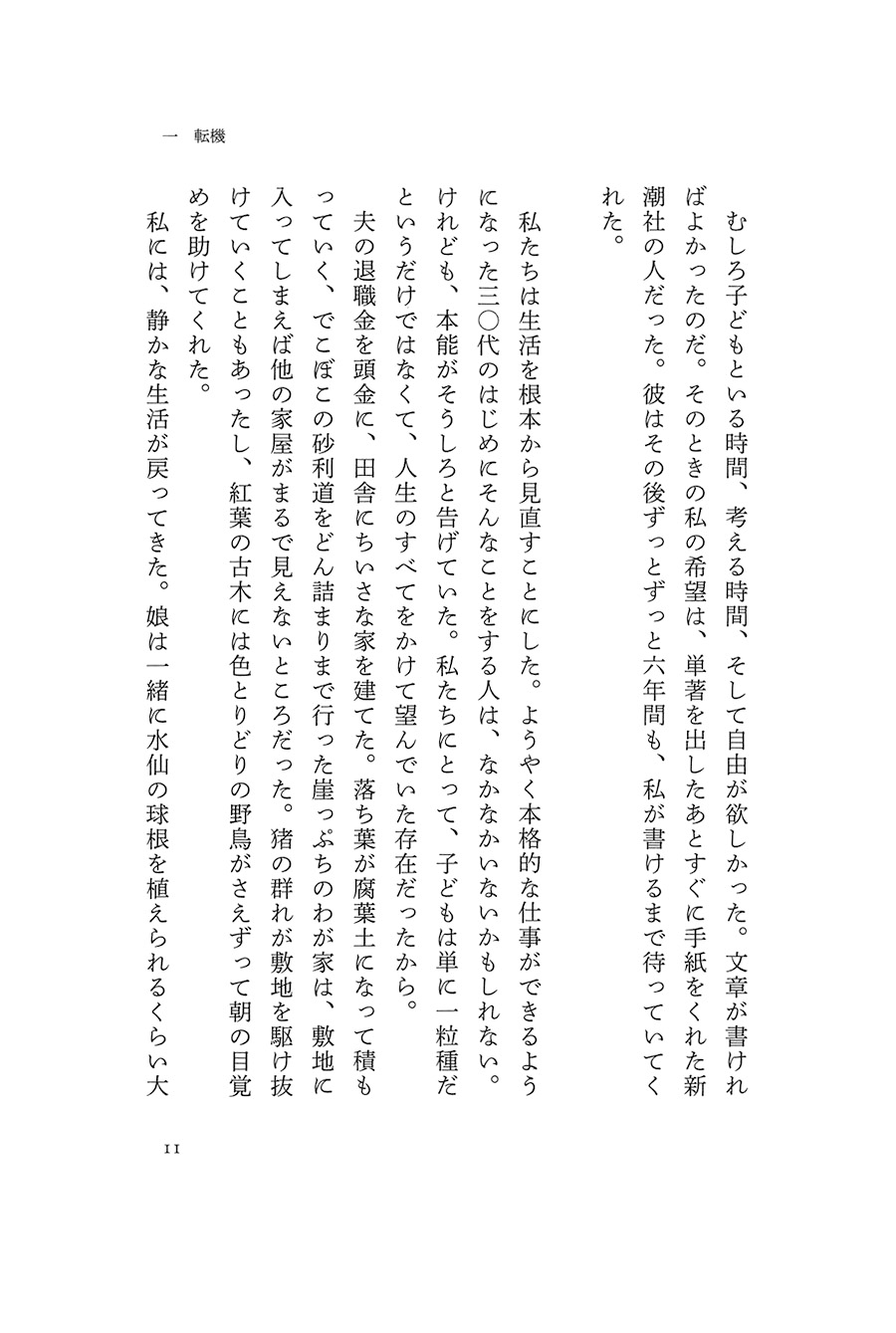一 転機
私は仕事を辞めたいと言った。夫はそのときキッチンでココアを作っていて、アルミの行平で温めたミルクをコップに注いでいるところだった。いつも換気扇を付けない人だから、耳に入ったはずだ。
私は一歳の娘を卵のような形のbloomの椅子に座らせて片手でつついてあやしながら、もう一度、ねぇ、辞めようかなと言った。彼女は歩き出したばかりだった。夫はダイニングに戻ってきて、私の前に一つ、自分の前に一つ、コップを置いた。
それで、どうするつもりなの。彼は淡々と訊いた。何か展望でもあるの。
私は過労ですっかり歳を取ったように感じていた。ほぼ寝たきりの生活で、若い頃に陸上部で鍛えた足の筋肉はあらかたなくなってしまっていた。必要以上の動きはしない、というのが残された体力で育児をしながら仕事をするうえでの心得だった。産後に髪がどさっと抜けておでこが広くなってしまった頭を、私はこの頃いつも後ろで一つにひっつめていた。もういいや、という考えが頭をかすめるようになっていた。
書架を張り巡らしたリビングを見渡した。今、家にある本だって読めていないものがずいぶんある。好きなだけ本を読んで暮らすことだってできるはずだし、やりたいことだってある。例えば、自分の子どものために、絵本を書いてみたかった。もう少ししたらお話が分かるようになる年頃だ。二重になったスライド式の重たい本棚の一つのセクションには、私の世に出たばかりの処女作が一〇冊ほど、黒文字と赤色の背表紙を見せてずらっと並んでいた。
初めて本が出たときは嬉しくて、発売日当日に丸の内の丸善まで見に行った。iPhoneで、娘をエルゴベビーの抱っこ紐に入れた夫と書棚を写した。本を指さしてこちらを向いた夫は、まるで自分のことのように嬉しそうな顔をしていた。
展望なんかないけど、このままここにいたって展望が開けるわけでもないじゃない。私はココアをすすりながら答える。こういうときに、彼が雲を掴むような話を嫌がるのは分かっていた。あなたはきっと後悔するから、と彼は短く言って、本に目を落とした。
その淡々とした態度が腹立たしくて、こんなに頑張っているのに!と私は言った。初めてだったかもしれない。疲れた、でもなく、辞めたい、でもなく、もう無理、と言ったのは。
育児をまるで手伝う余裕がなかった夫に、どんなに大変かを訴えはじめたら、止まらなくなった。
辞めようかな、と言ったのは実は正確ではなくて、私は自分の職場である大学で、任期付きの仕事の更新のめどが立たないことを予想していたのだ。大学は有期雇用の人をたくさん抱えている。更新が行われないなどということはしょっちゅうあることだった。健康保険が切れていることを四月になって知るのは嫌だった。保険を掛けるために、奨励金が出る研究員制度に申請を出していたけれども、通るかどうかは分からなかった。
私が追い詰められていることを周りは知らなかった。誰かの奥さんであることは、それだけで体面を保てるものなのだから、という雰囲気が大学界隈にはありありと感じられた。私が欲しかったのは体面ではなく、平等な扱いだったのだけれど。
彼は黙って私の話を聞いていた。しばらくして真面目な顔で、仕事を変えるよと言った。いずれにしたってそろそろこっちも潮時だから。子どもに関われない生活も嫌だし。ちょっとだけ待って。
実際に、私たちはしばらくしたのち、子どもが二歳の頃に相次いで仕事を変えた。私は大学のプロジェクト雇用の職場を辞め、研究をしながら奨励金を受け取るだけの研究員になった。学生に戻ったような立場だったが、もう深夜に研究しなくても、一年単位の不安定な職場にしがみつかなくてもよかった。
自分は組織に仕えることが難しい人間なのだと分かったのは、二年もしないうちだった。その代わり、というのも何だが、肩書はとくにいらなかった。同業者の男性陣が国際会議で飛び回って、空港のラウンジでビールやワイングラスの写真をSNSにあげているのを見ても、私は彼らが羨ましいと露ほども思わなかった。お行儀良くして肩の凝る会食に連なるなんてまっぴらごめんだったから。
むしろ子どもといる時間、考える時間、そして自由が欲しかった。文章が書ければよかったのだ。そのときの私の希望は、単著を出したあとすぐに手紙をくれた新潮社の人だった。彼はその後ずっとずっと六年間も、私が書けるまで待っていてくれた。
私たちは生活を根本から見直すことにした。ようやく本格的な仕事ができるようになった三〇代のはじめにそんなことをする人は、なかなかいないかもしれない。けれども、本能がそうしろと告げていた。私たちにとって、子どもは単に一粒種だというだけではなくて、人生のすべてをかけて望んでいた存在だったから。
夫の退職金を頭金に、田舎にちいさな家を建てた。落ち葉が腐葉土になって積もっていく、でこぼこの砂利道をどん詰まりまで行った崖っぷちのわが家は、敷地に入ってしまえば他の家屋がまるで見えないところだった。猪の群れが敷地を駆け抜けていくこともあったし、紅葉の古木には色とりどりの野鳥がさえずって朝の目覚めを助けてくれた。
私には、静かな生活が戻ってきた。娘は一緒に水仙の球根を植えられるくらい大きくなっていた。彼女は色がごちゃ混ぜのフリースや長ズボン、ミトンを賑やかにまとって、苗にかぶせるふわふわした腐葉土に喜んで触った。わずかに湿って確かな感触を手にもたらす土を、彼女は握っては離し、握っては離した。自然に触れたいという彼女の欲望は、私の欲望そのものだった。
職場を去る三カ月前の、二〇一四年の正月のことだった。宮沢賢治の『注文の多い料理店』からとって「山猫日記」と名付けたブログを始めた。書きはじめたら、筆はまるで止まらなかった。
私は、途中から奨励金も返上して、ひとり立ちした。そうこうして発信者、という場所に辿りついたとき、自分にそれがしっくりくるのを感じた。
これまで、自由でありたいという思いは、私を世間からどんどん切り離す作用を持っていたのだが、おかしなことに、今度は、孤独が逆に仕事を連れてきた。
二 子育ての日々
娘はどんどん、どんどん大きくなる。おっぱいをたくさん飲み、一日五〇グラム以上のペースで成長する。一日ずつ、自分の手が自分自身のものだということを発見したり、キックが強くなったり、親指しゃぶりを始めたり、ゆりかごの上のメリーを触ろうとしはじめたり。この子の中で流れている時間は、私たちよりよほど早いか、それともよほどゆっくりとしたものなのか。
夏の強い日差しを避けて夕方にベビーカーで散歩すると、風が気持ちよいのか目を細めたり、すぐに眠ってしまう。いかにも満足そうな顔をして、うーんと伸びをする。
眺めても眺めても、あきなかった。匂いを嗅ぐだけで、あの子に寄り添うだけで、満たされた。節ごとにぷっくりと膨らんだやわらかな肌。ぽやぽやとしたおでこの生え際の、甘いミルクのような匂い。そっと持ち上げて枕の上に載せると、彼女のちいさな身体がその分だけの静かなくぼみを作った。このちいさな赤ちゃんを肥えさせて、背中が痒かったり眠かったりするそのちいさな思いを汲みとってやることが、私の日々の主な仕事になった。
そんな光に溢れたような日々の中で、しかし、お産からしばらくのあいだ私は睡眠不足と疲労とで廃人のようだった。誰にも助けてもらえなかったからだ。仕事で疲れている夫が安眠できるように、夜中に娘が泣き出すと私は授乳したあとにベビーベッドの傍の床で寝転がったまま目を閉じた。
働き出したばかりの非正規雇用の私に育休はなかったから、仕事はひと月もすればやってきた。昼は授乳しながら片手でパソコンのキーボードを叩いて、自宅で仕事をした。髪はめったに洗えず、毎日が三時間睡眠だった。髪は触るたびに、掴めるほど抜けていった。哺乳瓶を拒否した娘は、どうしても二時間おきにはお腹が空く。授乳しながら気が遠くなるように寝入ってしまうこともあった。
けれども、私の目の中には娘しかいなかった。誰の助けもないあの最初の半年に耐えられたのは、まず無事に生まれてくれたことへの感謝があったからだ。早産が危ぶまれたこの子がただ息をしているだけで、元気に泣きわめくだけで嬉しかった。あの頃の私にのしかかっていたのは、耐え切れなくても当然、というくらいの負荷だった。忍耐を可能にする母親のホルモンの作用に加えて、私はさらに限界まで無理をしていた。どうしても子どもが欲しかったから。
とにかく、あの子が傍にいればよかった。一度だけ一時託児所に預けたとき、身体の一部がなくなったようで不安で仕方なくて、ようやく保育士さんの手から抱き取ったときに思わず匂いを嗅いで抱きしめた。娘と一緒になると心から満たされた。
半年が過ぎると、私はどこへでも娘を背負って連れて行った。イスラエルの死海のほとりにも、ボストンの街中にも。おぶい紐に入っているあいだのあの子は
一〇カ月になると、大学構内にある保育園に入ることができた。車の後部座席のベビーシートに娘を乗せて運転しながら、娘がむずかり出すと大声で歌を歌ってなだめる。
出勤して仕事をし、キャンパス内を歩いて授乳に立ち寄り、昼ご飯を食べながら仕事をし、授乳に行き、仕事をし、お迎えに行き、研究室で授乳し、おむつを替えて机や床におもちゃのついたマットを敷いて遊ばせながら残業し、買い物をし、帰宅し、授乳し、お風呂に入れ、寝かせ、起き出して仕事をする。この繰り返しだった。土曜日は保育園に栄養士さんがいないので、お弁当を作って子どもを預け、研究室へ行って今度は自分のためだけの研究をした。
家から徒歩五分のところにある便利な二四時間スーパーに買い出しに行くたび、抱っこ紐の中で娘はすやすやと寝たり、起きているときは声を出して甘えたりした。両手に持てる量は限られているのに、何度も往復できない私は歯を食いしばって大量の荷物を持って歩いた。住宅街で夜に赤ちゃんを連れて歩いていると、よく人がこちらを怪訝そうに見ることがあった。
ビニール袋の取っ手が破れそうに細くなって掌に食い込み、何キロもある娘の身体が私の重心を下げた。私は道すがら歩数を数えるようになった。踵が舗道にめり込み、歩幅を刻んでいく。次の電柱まで、次の街灯まであと少し。一方通行の狭い道路に面した家々からは夕飯の匂いが漂い、だんらんの気配をさせている。
ごめんね、と私はなぜか声に出して娘に言った。こんな生活でごめんね。娘はくうくうと喜んで私の頬をぴしゃぴしゃと叩いた。もう一度、ごめんね、と言うと彼女はもっと声を出してはしゃいだ。ごめんね、ぴしゃ、ごめんね、ぴしゃ、ごめんね、ぴしゃ。帰り道、私は視界がぼやけるのを感じながら、手で拭うこともできずに歩いていたのだった。
悲しかったのではない、働いていることを後悔しているのでもない、でもひとりぼっちで育児をしながら、私は娘にひとり言を言うようになった。私はとても幸福で、とてもさみしかったのだ。
なぜ、誰にも助けを求めなかったのだろうか。なぜ、あそこまで完璧に離乳食を作らなければいけなかったのだろうか。なぜ、仕事をもっとサボれなかったのだろうか。帰りついてダイニングのカーペットの上に
たぶん、私が八方美人だったからだ。夫に育休を取ってもらうことは無理そうだった。彼も生き馬の目を抜く業界で競争に晒されている身。命がかかっていないのに、わがままを言うことはできない、と私は思った。所詮、非正規雇用にすぎない私の仕事なんか大したことないんだから、と。
けれども、黙っているあいだに察してくれという思いは伝わらなかった。育児を一手に担わない人は、実際にやってみない限りそれがどれだけ大変なことなのかを理解できない。しかも、オフィス以外でも自分の研究をしなければならない私は、赤ちゃんが寝ているときにも休息はなかった。
自分に寄り添ってくれ、と思いながら黙っている時間が、私たち夫婦のあいだの溝となった。
つづきは書籍版『孤独の意味も、女であることの味わいも』で。購入はコチラ