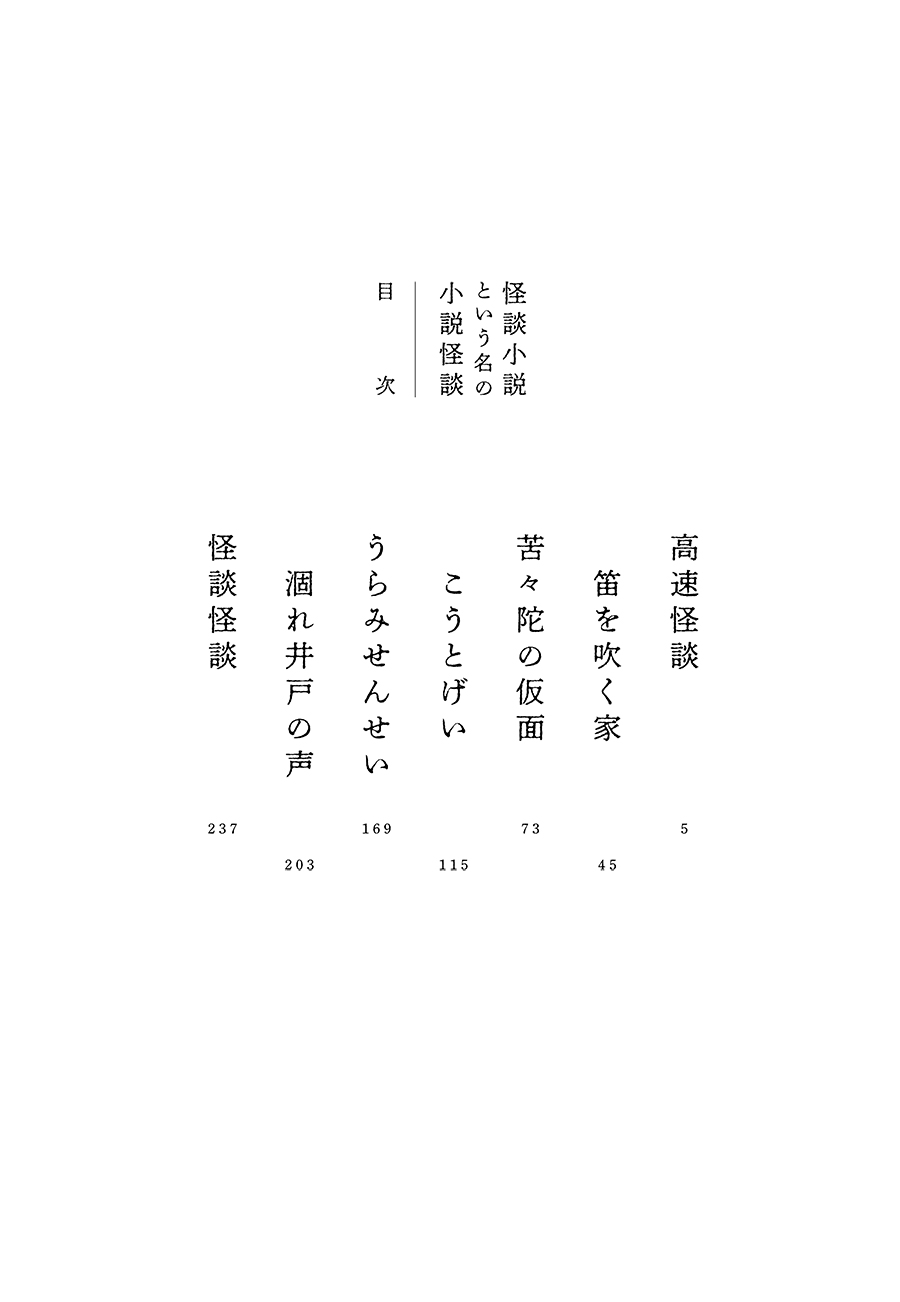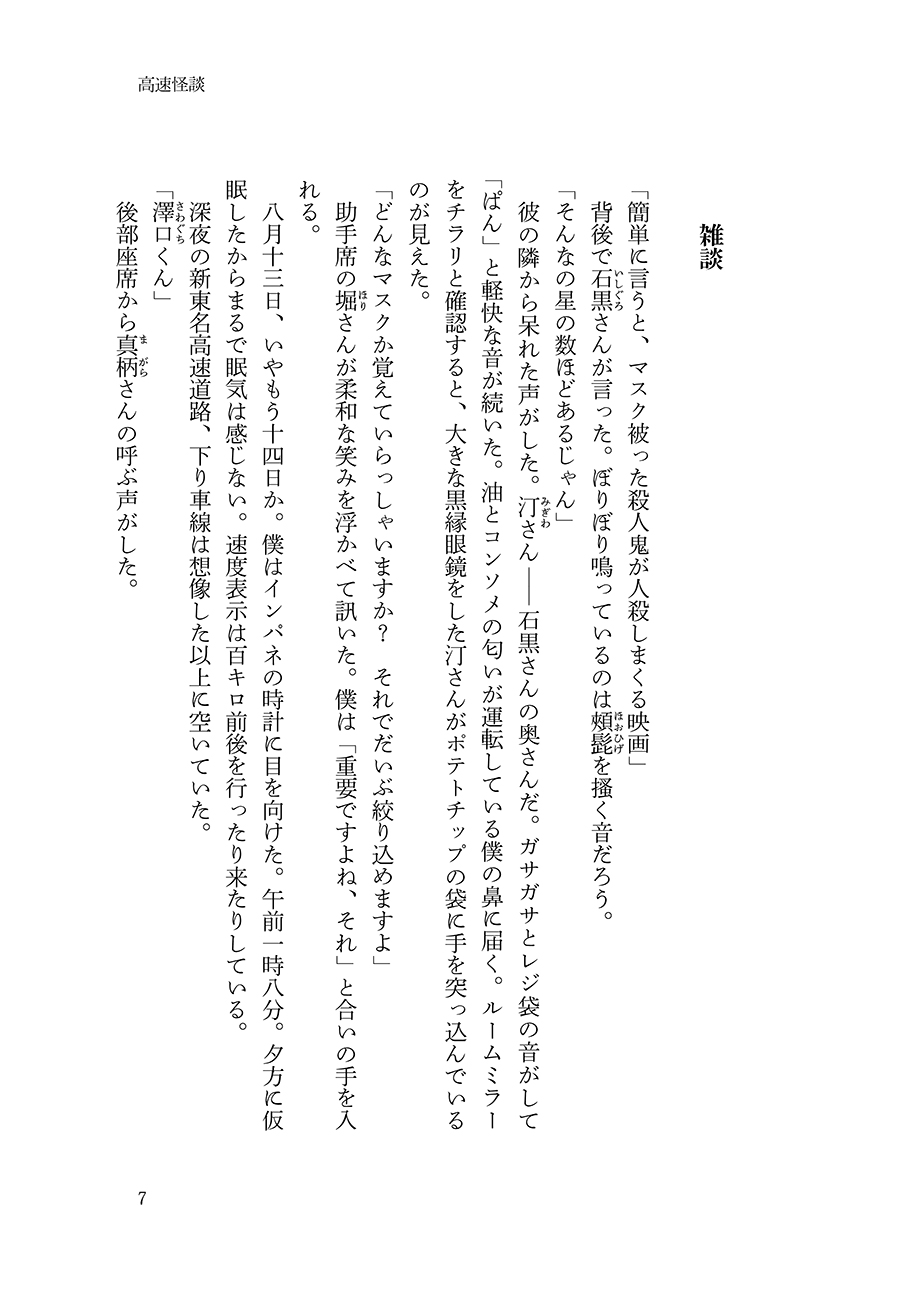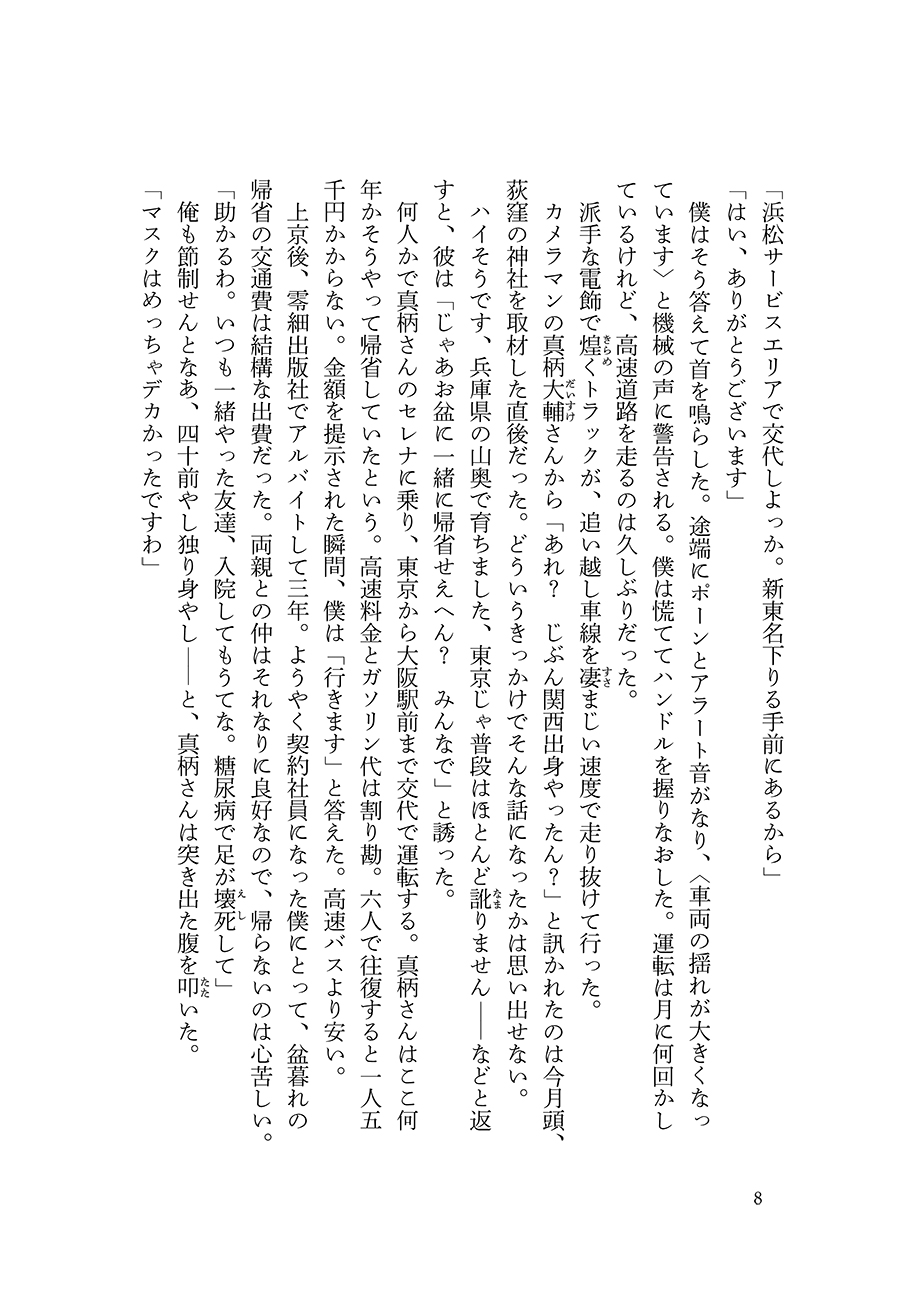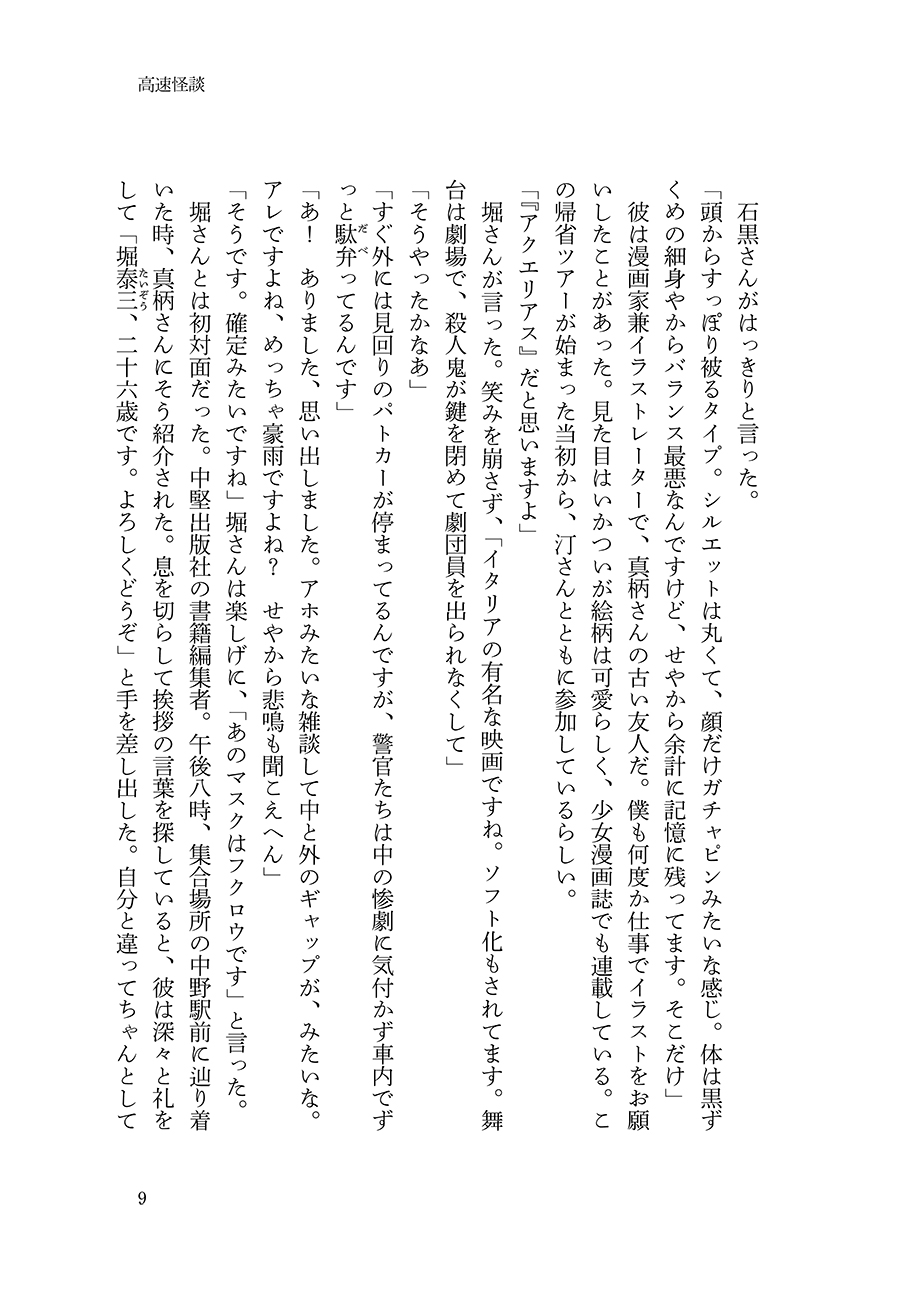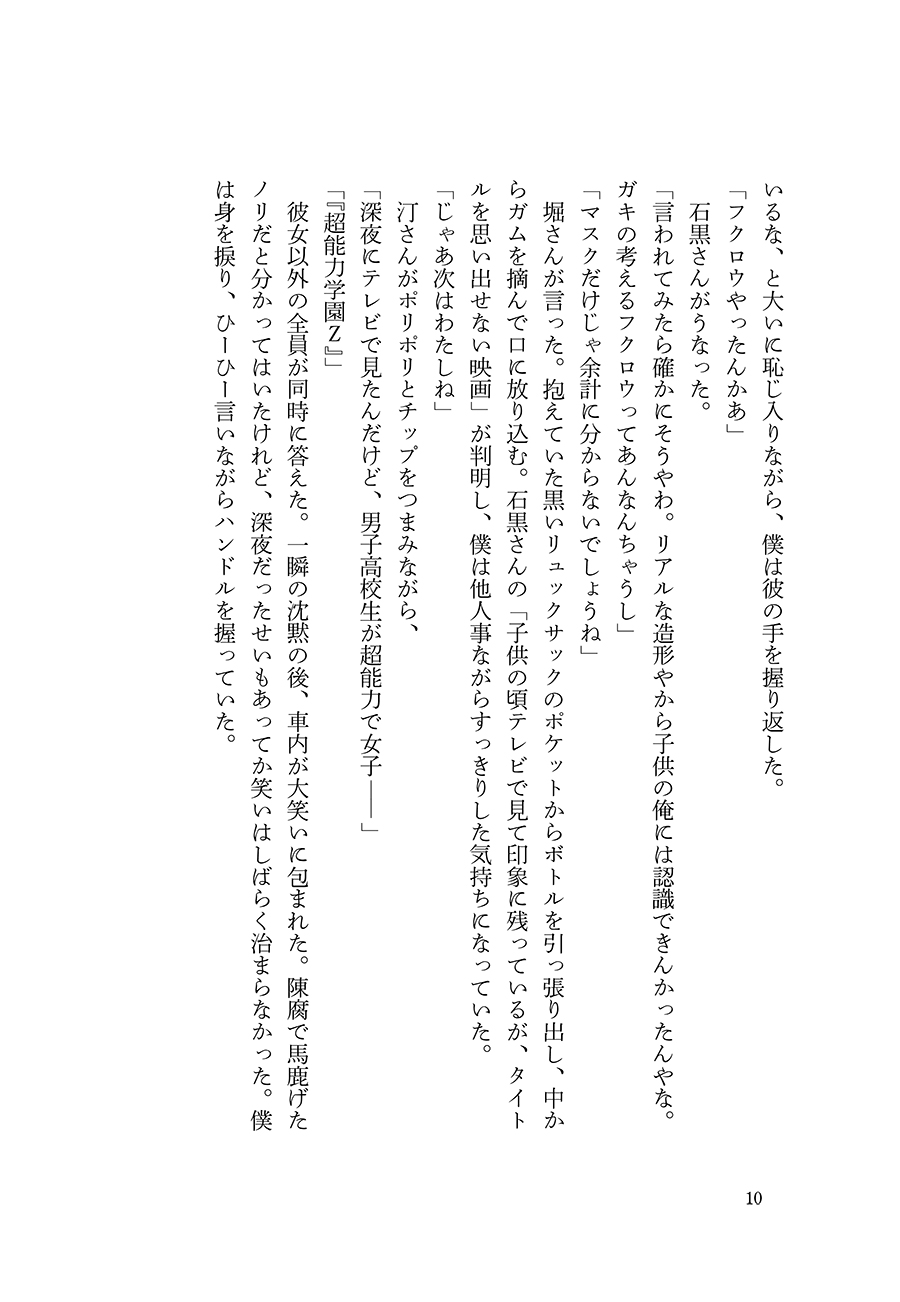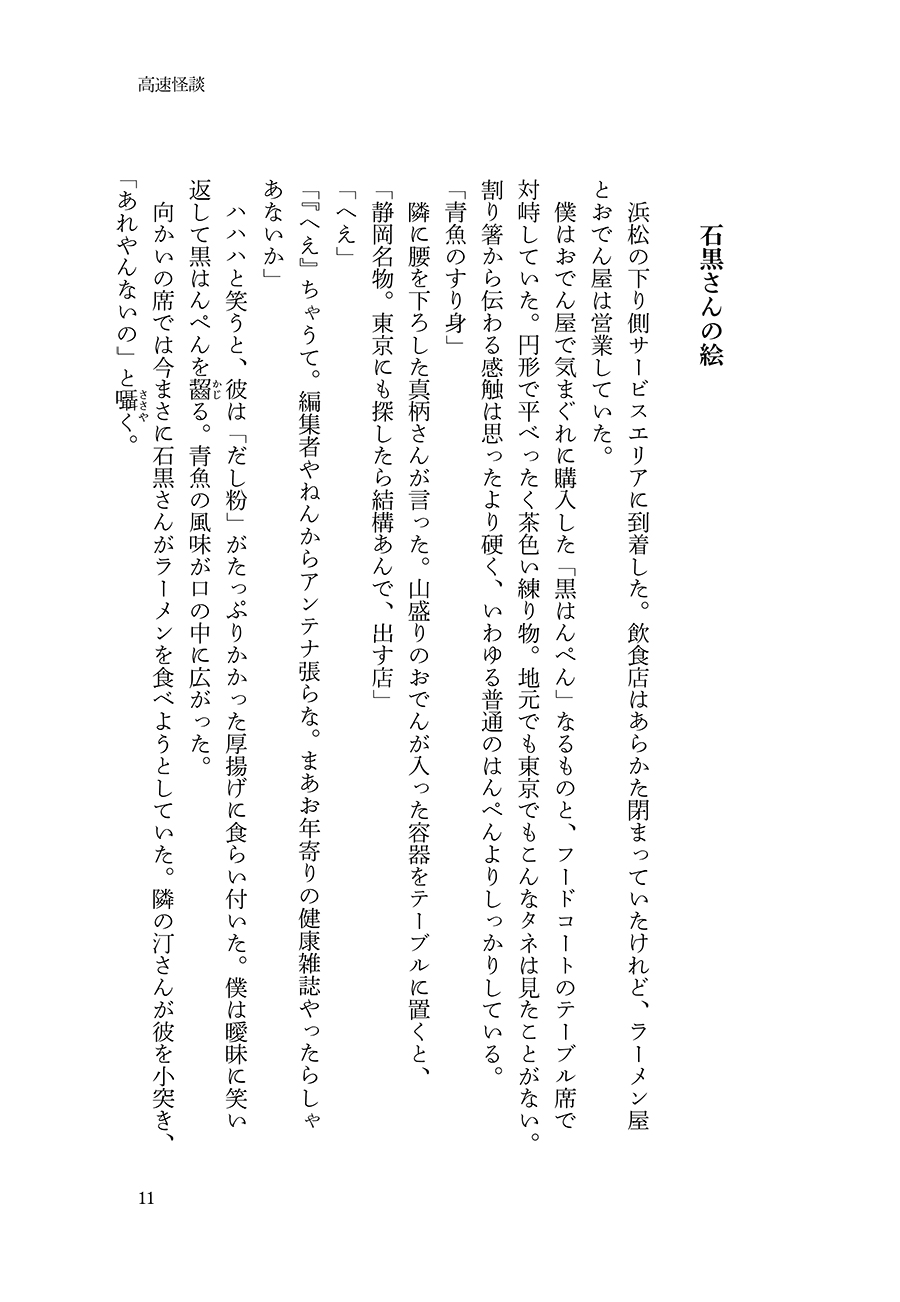涸れ井戸の声
この原稿の大半は、小説家の先輩が書いたものだ。仮に
過去形にしたのは、彼女はもう小説を書くことはないからだ。公式に断筆なり引退なりのアナウンスはしていないが、ぼくは彼女から直接「小説家は辞めた」と聞いている。三ヶ月前のことだ。彼女はその後すぐ東京は三鷹の自宅を引き払い、現在はパートナーである男性の実家で暮らしている。
ぼくは少しばかり引越しの手伝いをしたが、別れ際に彼女からUSBメモリを受け取った。長いこと使っていたのだろう。本体部分の緑色の塗装が半分ほど剥げていた。
「未発表の原稿です」
西村さんはそう言って、結んでいた髪をほどいた。がらんとした明るいリビング。パートナー氏は小さな庭の掃除をしていた。
「差し上げます。ネタが切れたら使ってください。
後輩のぼくにも彼女は敬語で話す。そしてぼくのことを本名で呼ぶ。穏やかではあるが掴みどころがなく、賑やかなところにもあまり顔を出さない。ぼくと彼女が交流するようになったのは、とある官能小説誌の編集者の披露宴で、席が隣だったことがきっかけだった。
「よくご存知ですね」
ぼくは笑った。ものの弾みでデビューした人間だ。生活のために小説を書いているだけで、作家の
「著作権は放棄します。香川くんの作品ということにしてもらって構わない。あと、下手に気を遣って中途半端に改変なんかしないでください」
ぼくは首をかしげた。「発表してくれ」という意味にも受け取れたからだ。単なるネタ提供ではない、そんな含みを感じた。
こちらの気持ちを読み取ったのか、彼女は小さく笑った。
「使う使わないはお任せしますけど――香川くんには読んでほしいな」
わずかに口調が砕けていた。
小説家を辞める理由を訊くなら今しかない。そう思ったが訊けなかった。度胸も勇気もない自分が改めて
ここからの文章は、USBメモリに入っていた彼女の原稿から引き写したものだ。もちろん彼女の名義は「西村亜樹」に書き換えてある。タイトルは記載されていなかったが、文書ファイルには「例の小説に関して」という名前が付いていた。
※ ※
西村亜樹先生
はじめまして。去年、近くの書店で偶然先生の作品に出会い、すぐに全て拝読しました。最新作の書き下ろし長編『喪われた島』、とても怖くて布団の中で震えながら読みました。
大学のゼミの人たちと、アルバイト先の居酒屋で、先生の作品の布教に努めています。読んだ人はみんなとても怖がっていますよ。
雑誌(文芸誌って言うんでしょうか)掲載の短編も、お金に余裕がある時は買って読むようにしています。
今年のはじめ『S-Fマガジン』に載っていた「ジェミノイドの見る夢」も怖くて面白かったです。人間とアンドロイドの区別はどこにあるのか、分からないのが特によかったと思いました。
でも、一番怖かったのは『小説新潮』の特集にご寄稿された「涸れ井戸の声」です。思い出すだけで冷や汗が出てきました。特に主人公が井戸を覗き込むところが……駄目です。これ以上書けません。いずれ短編集にまとまると思いますが、怖すぎるので買わないかもしれません(ごめんなさい)。
これからもますますのご健筆をお祈り申し上げます。
『小説新潮』編集部の担当、
わたしは「涸れ井戸の声」などという小説を書いたことはない。
文面から察するに短編だろうけれど、パソコンにもバックアップの外付けHDDにもそんなタイトルの原稿はない。念のためこれまで寄稿し献本された『小説新潮』すべてを確認したが、「涸れ井戸の声」なる短編は載っていなかった。つまり別の作家が書いたものを、わたしの作品だと勘違いしたわけでもないらしい。
三井さんもメールに「変ですね」と書いていた。編集部に配属されて八年になるそうだが、その間、同タイトルの短編を掲載した記憶はないという。
「お手すきの時で結構ですので、バックナンバーを確かめていただけますでしょうか」
わたしは返信にそんな一文を付け加えていた。
気になっていたからだ。
というより「悔しかったから」と書いた方が正しいのかもしれない。
もちろん読者さんからの応援はありがたい。ネットレビューやSNSでの感想を見る習慣はないから尚更だ。これからも頑張ろうと思える。
だが、今回のメールを読む限り、わたしのどの小説より「涸れ井戸の声」の方が面白かった、ということになる。
わたしの小説より怖かった、ということになる。
やはり「悔しい」と言語化した方が誠実だろう。わたしは悔しかった。「そんなに怖いなら読んでみたい」とも思っていた。単なる興味、好奇心だけではない。確かめてみたいだけでもない。読者さんが感じた恐怖を推し量って、自分まで少し怖くなっていた。
三井さんからメールが届いたのは二日後のことだった。
「涸れ井戸の声」などという作品は掲載されていなかった。井戸が出てくる話すら見つからなかった。おそらく他の雑誌に載った、別の方の作品でしょう――
簡潔な報告を読んで、わたしはこう返信した。
「大変お手数ですが、読者の方に下記転送していただけますでしょうか」
“下記”はお礼と問い合わせだった。メールありがとうございます、とても励みになります。差し支えなければ「涸れ井戸の声」について詳細を教えてください。どの媒体に何を寄稿したか忘れることがあり、また納品した原稿を消去してしまうことも稀にあります。内容も書き終われば頭の中から消えてしまいます。今回もきっとそのケースだと思います……
言い訳がましい、回りくどいのは百も承知だった。それでも知りたくなっていた。
西村亜樹先生
お返事ありがとうございます。先日編集部宛にメールをお送りした者です。
本当にごめんなさい。
「涸れ井戸の声」ですが、あれから調べたら、持っている『小説新潮』には載っていませんでした。先生の「ロードサイド怪談」は載っていました(後半で幼馴染みが豹変するところが怖かったです!)。
他の雑誌にもなかったので、記憶違いだと思います。
でも不思議です。たしかに先生の名前で「涸れ井戸の声」という小説が載っていたのです。
内容もはっきり覚えています。
主人公の男性が妻に先立たれ、失意の中で訪れた地方の寒村で、古い井戸を見つけるというものです。そこを覗き込んだ時(これ以上は書けません)。
読んだその日は眠れませんでした。久しぶりに母親と一緒の部屋で布団に入りました。
先生はどうしてこんな恐ろしい話を考え付いたのだろう、形にしたのだろうと思いました。こんな怖い思いをさせられたことに対して、ちょっと怒ってもいました。もちろん尊敬の念はありましたし、今もそれは変わりません。
混乱させてしまって申し訳ありません。
先生の更なるご活躍をお祈り申し上げます。
読者さんはまた名前を書き漏らしていた。女子大生であること、母親と同居していることはこれまでの文面で分かったが、だからといってどうにもならない。
「あまり勘繰りたくはないですが、いたずらかもしれませんね」
転送されたメールの末尾に、三井さんはそう書き加えていた。わたしもその可能性を疑っていた。
読者を名乗る人物からの投書は、好意的なものばかりではない。
知識では知っていた。誹謗中傷、卑猥な文言、何度読み返しても意味が分からない支離滅裂な妄言。ネットが普及して激減したものの、小説家や編集部宛にそうした文書が届くことは未だにあるという。最近はとある文学賞を受賞した大御所女性作家に、殺害予告のメールが数十通も届いたことがあったらしい。逮捕された送り主は「デビュー当初から愛読していたファン」の男性で、失業した四十代半ば頃から、女性作家に憎しみを抱くようになったそうだ。
表沙汰になっていないのは男性が出版関係者だからだ、いや政治家の息子だからだ、と憶測が業界内で飛び交っているが、本当のところは知らない。
このメールも規模は違えど似たようなものかもしれない。パッとしないホラー作家と、編集部をからかう目的で送ったものかもしれない。軽い気持ちで書いたものではあるのだろう。少し調べればすぐばれる嘘だ。身の危険を感じるような内容でもない。
「そうかもしれませんね。お手を煩わせてしまい申し訳ありませんでした」
三井さんに返信してわたしは仕事に戻った。再来年刊行予定の書き下ろし長編のプロットだ。来週には担当に送らなければならない。高校を舞台にした学園ホラーで、わたしとしては新機軸に当たる。
夕食を取らず深夜まで粘っても、ほとんど進まなかった。夫の
頭の中で「涸れ井戸の声」のことがずっと巡っていたからだ。
そして「怖い話」全般のことも。
残念だよ、『シェラ・デ・コブレの幽霊』はそんなに怖くなかった――
カナザワ映画祭で特別上映された伝説のホラー映画を観た、ホラー系のライターさんの感想だ。彼はとても落胆していた。長い間とても楽しみにしていたのに、と肩を落としていた。他の人の感想も似たり寄ったりで、総じて「期待したほどではなかった」というものだった。
『シェラ・デ・コブレの幽霊』はアメリカの怪奇映画だ。テレビシリーズのパイロット版として製作され一九六四年に放映される予定だったが、本国ではお蔵入りになった。そして日本を含む海外に貸し出され、各国でひっそりとテレビ放映された。それが六十年代後半のことだ。
時を経てこの映画は伝説化する。「子供の頃にテレビで見てトラウマになった怪奇映画」「今は観ることができない映画」として、好事家の間で噂になり、少しずつ広まっていったのだ。多くの人が知ることになった契機は二〇〇九年、テレビ番組『探偵!ナイトスクープ』で取り上げられたことだ。映画ライターの添野知生氏がフィルムを所有しているが、権利問題でソフト化することは難しく、限られた形でしか観ることができない。
放映では出演者たちが、上映されたフィルムを鑑賞し慄く姿が映し出されていた。
映画監督であり脚本家である高橋洋氏は、この作品の予告編をテレビで観た時の衝撃を忘れられず、映画『女優霊』の脚本を執筆した。Jホラーの草分けと評価される作品の一つだ。
主人公である若き映画監督は、撮影したフィルムに奇妙な映像が紛れ込んでいることに気付く。役者の服装から察するに、大昔の日本映画の一部らしい。
彼はこの映画に見覚えがあった。子供の頃に一度テレビで観た記憶があった。だが真相を調べていくうちに、彼は意外な事実に突き当たる。
高橋洋氏は自身が『シェラ・デ・コブレの幽霊』に触れた体験を、そのまま作品に織り込んだわけだ。『女優霊』を監督したのは中田秀夫氏。この監督と脚本家コンビが後に手がけたのが、あの『リング』だ。この二作の映像表現には一部共通するところがある。そういう意味で、『シェラ・デ・コブレの幽霊』はJホラーの遠いご先祖様、という言い方もできるだろう。
だが肝心の内容は伝説を耳にして胸躍らせた人々を、満足させるものではなかったらしい。
だから、と言っていいのか分からないが、もし今後何かで鑑賞できる機会があったとしても、わたしは観ないでおこうと思っている。観ないまま想像して怖がる方を選ぶつもりでいる。
ホラーや怪談、大まかに言うなら「怖い話」にはそういう側面がある。
内容ではなく、怖いという触れ込みそのものが恐怖を喚起することがある。
小説でこの側面を扱ったのが、巨匠・小松左京の掌編「牛の首」だ。「あんなに怖い話は聞いたことがない」と噂される怪談「牛の首」の内容を知ろうとした語り手は、終盤で真実を知り戦慄する。愛好家でなくても知っている有名な作品だ。ネットには「牛の首」の内容を知っている、という書き込みが散見されるし、その内容とされるテキストもたまに見つかるが、投稿者は重大な勘違いをしているとしか思えない。
中島らもの短編「コルトナの亡霊」は明らかに『シェラ・デ・コブレの幽霊』を下敷きにしたものだ。試写会の後半、あまりの恐ろしさに観客がみな劇場から逃げ出した――そんな逸話があるスペイン製ホラー映画『コルトナの亡霊』を、ライターが調べる話。
いずれも「怖い」という証言、噂話、喧伝を扱っている。
自分ではない誰かが怖がっている、そうした傍証こそが「怖い」――そんな物語だ。
この「怖さ」はホラーについて怪談について、少しばかり掘り下げれば誰でも気付くものだ。それに煎じ詰めればあらゆるものに当てはまる。
祭りは準備をしている時が、遠足は前日が一番楽しい。そうした言い回しはよく聞くし、生きていれば何らかの局面で、誰もが実感するだろう。体験している最中より期待している間の方が、気持ちは盛り上がる。そのものを目の当たりにする時より、予想したり予感したりしている時の方が心は激しく動く。感情が掻き立てられ気分は高揚する。
名も知れぬ女子大生からのメールは、それを踏まえたものに違いない。
いたずらだとしても、ホラー作家に送りつける内容としては「正しい」。少なくともわたしは気分を害してはいない。むしろ楽しませてくれたことに感謝の念すら抱いている。仕事が捗らないのはマルチタスクが苦手なせいで、送り主のせいではない。
わたしは自然とそう思うようになっていた。
やがて日々の慌しさの中、少しずつメールのこと、「涸れ井戸の声」のことを忘れていった。
とある季刊誌の企画でSさんと対談した時のことだ。
小説家の大先輩であり、同じ賞の出身でもある。厳密には彼女は再デビューだが、いずれにしろ輝かしい経歴も実績もお持ちで「雲の上の人」と言っていい。ここ十年はテレビ番組にもよく出演している。ホラー作品も多いが、最近はもっぱら所謂「実話怪談」の著作が多い。実際に人から聞いた話、という体の掌編集だ。
対談したのは夕方の出版社の会議室で、その後すぐ彼女の希望で飲み会をすることとなった。ほとんど聞き役、相槌係になってしまったわたしは申し訳ない気持ちで参加した。
Sさんは
「そういえば」
同席していた編集者二人が、立て続けに電話を受けて席を外した時。Sさんが何杯目かのハイボールを飲み干すなり訊いた。
「西村さん、スランプってないの?」
「いつもそうです」
わたしは正直に答えた。謙遜ではなかった。すらすら書けたことなど一度もない。デビュー作になった応募原稿すら難航した。
「にしては順調じゃない?」
「食事と睡眠以外は全部執筆に当ててるからです。読書も最近はなかなか」
「あらあ、そう」
Sさんはテーブルの呼び出しボタンを押した。自分の気の利かなさに情けなくなりながら、わたしは縮こまる。
「わたしは一回だけある。十五年くらい前かな」
「そう……でしたか」
合点がいった。Sさんの刊行ペースが一度だけ、大幅に落ちたことがある。ブランクと言っていい。年に一冊出るか出ないか、それが何年か続いた。彼女の言ったとおり十五年前のことだ。ちょうど就職したばかりの頃で、慌しさの合間に新刊を待ち侘びていた記憶がある。
「どうしてスランプになったんですか」
これは訊いても構わない流れだろう。
「めちゃくちゃ怖い小説を書いてやろうって、悪戦苦闘してたの」彼女は顔をしかめて、「何かのアンソロジーでとんでもなく怖い小説を読んだって知り合いの子から訊いて、負けるかって思ったのがきっかけ。またその子が自分の手柄みたいに言うわけよ。それが余計にカチンと来て」
「なんて小説ですか」
「涸れ井戸の声」
「え?」
変な声が出ていた。
心がざわざわと
やって来た店員にハイボールのお替わりを注文すると、Sさんは話を再開した。
「その小説は結局見つからなかったんだけどね。読んだ子も本無くしたとか書名も覚えてないとか言ってたし、直後に夜の仕事が親バレして東京からいなくなっちゃったし。でもそういうの気になるでしょ。普段小説なんか滅多に読まない子が、夢に見てうなされるって怯えてたんだよ? どんだけ怖いのって思うし、自分も書いてみたいってなるのは当然だよね」
「ええ」
「で、取材とかいっぱいやって何回も書き直したりして、そしたら訳分かんなくなって……何とか書き終えたやつもボツにされた。考え過ぎて散らかってるって。何回書き直してもダメだった。で、あきらめて素直に書いて今に至る。遠回りだったね、結果的に」
Sさんはハハハと笑った。わたしは愛想笑いを返しながら必死で考え、
「どんな話だったんですか? その、『涸れ井戸の声』」
と訊ねた。
「忘れちゃったなあ」彼女はそっけなく答えた。思い出そうとする仕草すら見せない。
「気になりますよ」わたしは作り笑顔で促す。
「そお? うーんとね……ああ」Sさんは退屈そうに、「しょぼくれたおっさんが旅先の村の外れで、井戸を覗き込んでどうとかいう話」
心臓がどくんと鳴る。
「そ、そこから先は?」
「欲しがるねえ」Sさんはわざとらしく抑揚をつけて驚く。今思えばタメ口が気に障ったのかもしれないが、その時は気付かなかった。
「分からない。教えてもらってないの。その子、口つぐんじゃった。思い出すだけで怖い、話そうとしただけで震えるって」
明るかった表情が不意に曇る。
「……その子の怖がりようがまたね」
遠い目でハイボールのジョッキをあおる。それまでとは打って変わって、不味そうな顔をしていた。
個室に初めて沈黙が訪れた。
「きっと、声が聞こえるんでしょうね」
わたしは思い付いた推論をそのまま口にした。タイトルがタイトルだ。そんな展開になる以外に考えられない。
きっと主人公の男性は聞いてしまうのだ。
井戸の底から響く何者かの声を。おそらくはとっくに水が出なくなった、涸れ井戸にこだまする声を。
どんな声だろう。何を言うのだろう。
話すのを拒否するほど、メールに書くことができないほど恐ろしい声とは一体。
Sさんは答えず、黙って壁を見つめていた。
編集者のうち一人が戻って来た瞬間、彼女は喋り出した。知り合いのキャバクラ嬢から聞いたという、大物芸能人のアブノーマルな趣味を暴露する。個室に笑いが湧き起こる。
わたしはもう聞いていなかった。そこから飲むことも食べることもしなかった。どうやって別れて、どう帰ったのかも覚えていない。
気が付けばここ、自室兼書斎にいた。
そしてこのファイルに今までのことを書き綴っていた。
これまで「涸れ井戸」と聞いて最初に思い出すのは、泡坂妻夫の長編ミステリ『乱れからくり』だった。いや、あちらの表記は「枯れ井戸」だったか。
今は作者も掲載媒体も分からず、内容もはっきりしない謎の短編だ。
ネットで検索してますます謎は深まった。
「涸れ井戸の声」という作品を読んだことのある人は、少なからずいるらしい。SNS、ブログ、掲示板、個人サイトに、タイトルと「とても怖かった」という感想が幾つも上がっている。
だが――作者がすべて異なっていた。
クトゥルー神話作品や、一休宗純を主人公にした伝奇ホラーに定評のあるKさん。ショートショートの賞出身でホラーアンソロジーの監修もしていたMさん。多作でカルト映画収集家としても知られるHさんに、新本格ミステリの草分けであるところのYさん。
Sさんの短編集で読んだ、と書かれたブログもあった。
都筑道夫の晩年の作品だというつぶやきも、ロバート・ブロックの初期作品だ、いや違うジャック・フィニイのだ、と言い争いになっている掲示板もあった。もっとも古い文章は一九九八年、とある個人サイトの読書記録だった。
掲載媒体、収録媒体もことごとく違っていた。一方、短編であることはどのテキストでも共通している。主人公の男性が役所勤めであり車を所有していること、妻の顎に小さな
「『怪奇礼讃』で一番怖かった」と書かれたブログを読んだ時は目を疑った。創元推理文庫から二〇〇四年に出た、十九世紀末頃の英国怪奇小説をまとめたものだ。勤めていた頃に購入して読んでいる。最も印象的だったのはマーティン・アームストロングなる作家の「メアリー・アンセル」という切ない作品だった。ホラー系のアンソロジーではこうしたことがままある。想定していなかった悲しい話や泣ける話に不意打ちを食らい、記憶に刻み込まれてしまうのだ。
慌てて『怪奇礼讃』を書棚から引っ張り出して確認したが、「涸れ井戸の声」なる作品は存在しなかった。それらしいタイトルの作品も見当たらなかった。もう一度目次で、続いてぱらぱら捲って確かめる。やはり載っていない。
わたしはブログ主に問い合わせてみようと、記事のコメント欄を見た。
〈管理人様。
はじめまして。『怪奇礼讃』購入しましたが、「涸れ井戸の声」なんて掲載されていませんよ。勘違いじゃないですか?〉
「特命鬼ボウ」を名乗る人物からそんなコメントがあった。同じことに気付いた人が既にいたわけだ。管理人の回答はこんなものだった。
〈コメントありがとうございます。
載っていませんでしたね。ご指摘の通りです。
すみません。
おかしいなあ。じゃあ、どこで読んだんだろう〉
回答にさらに返信する形で、特命鬼ボウが「作り話をするな」「謝罪しろ」という意味のコメントをしていたが、管理人は放置していた。
頭の中で奇妙な仮説が組み立てられていた。理屈に合わないと思いつつ妄想せずにはいられなかった。
「涸れ井戸の声」なる物語は、この世の本の中を彷徨っているのではないか。そして読んだ人々をひとしきり怖がらせ慄かせると、また別の本へ移動するのではないか。
あるいは――人々の記憶の中にしか「涸れ井戸の声」は存在しないのではないか。現実世界にはどこにもなく、ただ「読んだ」「怖かった」という記憶だけが一部の人にあるのでは。
作者不在の恐怖譚。もしくは存在しない「怖い話」。
どちらも馬鹿げている。SFじみている。
だが魅力的ではあった。
読めるものなら読みたい、という気持ちが膨らんでいた。
考えた末に相談した相手は三井さんだった。もちろん自分の仮説など打ち明けたりはしなかった。ただ「涸れ井戸の声」という恐ろしい短編があること、ネットに複数の証言があることを伝えただけだ。それも新作小説の打ち合わせのついでに、雑談の延長のような流れで。
「鮫島事件みたいですねえ」
新潮社の会議室。三井さんはネットユーザーらしい反応をした。かなり早い段階から巨大掲示板2ちゃんねる、現5ちゃんねるに親しんでいるという。同世代ながらこの点はわたしと大きく異なっている。
鮫島事件とは旧2ちゃんねるで大勢のユーザーによって創り上げられた「絶対に明かしてはいけない事件」のことだ。無数のディテールが有志によって構築されているが、肝心の事件そのものは語られない。
「だから大勢で作った冗談ってことも考えられますよ。というか理性的に考えれば、それ以外に有り得ない」
「だとしても、Sさんが参加するとは思えません」
「たしかに。流行には敏いけどそういう趣味はないんだよなあ、Sさん」
彼は腕を組んだ。
「リアルの知り合いに一人でもいればいいんですけどね、読んだことあるって人。そしたら話が進む」
「それか……自分が読むか」
「ですね」
三井さんはニッと歯を見せると、
「とりあえず社内で聞いてみます。知っている人間がいればめっけものですし、手に入れることもできるかもしれない。そしたらご連絡差し上げます。なんか俄然興味が湧いてきましたよ」
嬉しそうに言った。
その翌週のこと。
取材から帰宅したのは午後六時を少し回った頃だった。夫の良平は仕事で泊まりだと言っていた。冷蔵庫にあるもので簡単に夕食を作って数分で食べ終え、書斎で締め切りの迫っているコラムに取り掛かる。とある料理雑誌から依頼されたもので、テーマは「私と缶詰」。枚数は原稿用紙換算で二枚。
五分ほど構想してわたしはモニタに向き直り、キーボードを叩き始めた。小学校の修学旅行で鰯の缶詰を自作した経験を簡潔に紹介し、そこから話を広げる。
詰まることもなく書き進められる。指先から勝手に言葉が、文章が紡ぎ出される。小説もこれくらいスムーズに書ければいいのに、と心の片隅で思っていると、マウスの傍ら、所定の位置に置いていた携帯が鳴った。
ショートメールだった。液晶画面には「新潮社 三井さん」と表示されていた。
進展があったのだろうか。
「涸れ井戸の声」が見つかったのだろうか。
はやる気持ちを抑えながら、わたしは暗証コードを入力してショートメールを開いた。
〈お疲れ様です。大至急こちらのライブ動画を見てください〉
文末には動画配信サイト「YouTube」のアドレスが貼られていた。
文面からは焦りが感じられた。どういうことだろうと首を傾げる。
パソコンで見るか携帯で見るか。一瞬だけ考えて、わたしはパソコンで閲覧することにした。
モニタに映し出されたのは、ヒラメのような顔をした黒髪ツインテールの少女だった。
色白だが頬が少し荒れている。顎の一箇所だけ不自然に平坦なのは、吹き出物をファンデーションで隠しているせいだろう。ぬいぐるみのようにモコモコした「ジェラートピケ」のパジャマを着て、こちらに上目遣いの視線を向けている。手元にはステッカーだらけのタブレット。背後には白い壁と無機質なスチールシェルフ。
ライブ配信動画のタイトルは「ぽこりんアイドル★むめたん文豪を目指す」だった。地下アイドルだろうか。それともユーチューバーという職業の人だろうか。
「ヤバイ、もうテンションあがってきましたよぉ、これ大当たりかもしれませんね。むめたんドキドキ」
少女――むめたんは八重歯を見せてタブレットに目をやる。再び三井さんからショートメールが届いた。
〈彼女は青空文庫を朗読しています〉
青空文庫。著作権の切れた文学作品や評論を公開しているサイトだ。横書きの小説を読むことに馴染まないので頻繁には閲覧しないが、急ぎで参照したい時には重宝している。
だがそれが何だというのか。
〈さっきから読んでいるのが「涸れ井戸の声」です。本人がそう説明しました。作者は分かりません〉
続けて届いた文面を読んだ瞬間、わたしの背筋がぴんと伸びた。
むめたんは笑みを浮かべながら朗読していた。
「――男が辿り着いたのは、小さな村だった。色あせた郵便ポストは傾き、伸び放題の草に半ば埋もれている」
わたしはキーボードを叩いて青空文庫のトップページを開く。検索ボックスに「涸れ井戸の声」と打ち込む。
そんな作品は見つからなかった。検索結果の一覧が表示されたが、公開作品の本文から「枯れ」「井戸」「声」の文字を拾い上げただけだった。
三井さんに簡潔に状況を送信すると、すぐに返事が届いた。
〈自分もです。でも彼女は読めています〉
「――老婆は何も答えず歩き去った。丸くなった背、痩せさらばえた手足、前屈みで歩く様は秋口の甲虫を思わせた……」
わたしや三井さんには読めないテキストを、むめたんはすらすらと読み上げている。閲覧人数は「851」。多いのか少ないのか判断できない。
分かるのは今この瞬間、どこかで「涸れ井戸の声」を読んでいる少女が、確かに存在することだけだった。
「――井戸が、あった」
むめたんは抑揚をつけて言った。わざとらしく間を空ける。タブレットを見つめる目が左右に小刻みに動いている。
すっ、と顔から笑みが消えた。
口を中途半端に開いたままで固まっている。タブレットから目を離さないでいる。
「あっ、ご、ごめんね」
引き攣った顔で彼女はこちらに詫びた。笑おうとしても笑えない。そんな風に見える。
「面白くて入り込んじゃいました。じゃあ、続き読みますね」
姿勢を正し、深呼吸をすると、むめたんはタブレットを両手でしっかりと持って、
「男は……井戸の縁に手を掛け、て」
すぐ言葉に詰まる。
白い顔が真っ青になっているのが映像でも分かった。唇まで血の気が引いて紫色になっている。
何度か言いよどむと、彼女は決意したようにコクリとうなずき、
「真っ暗な」
はっ、と息を呑んですぐさま振り返る。「えっ、なに……」と狭い部屋を見回している。
後頭部の白い分け目が酷く目立った。
しばらくして、彼女はこちらに向き直った。
目が真っ赤に充血していた。
ぐす、と洟を啜る。
「そ、底を、覗き込ん……だ」
彼女の目から、ぽろりと涙が零れ落ちた。
左目から一粒。右目から二粒。
瞬きすればするほど溢れ出し、次々と頬を伝う。
むめたんは震えていた。音が聞こえそうなほど全身を
わたしは固唾を呑んで彼女を見守っていた。またしてもここから先を知ることができないのか、という落胆が少し。さっさと続きを読めと急かす気持ちが少し。
残りの感情は間違いなく恐怖だった。
読もうとするだけで泣いてしまうほどの記述とは。注目を浴びたくて自らカメラの前に立っているのに、取り乱してしまう内容とは。
勝手に想像を逞しくしてしまう。
妄想すればするほど恐れてしまう。
鳥肌が首筋から背中へ、腕へと広がっていく。そして治まらない。
「……やだ」
タブレットを投げるように床に置くと、むめたんは近くにあったクッションを掴んだ。そのまま勢いよくタブレットを覆い隠す。ぼすんと大きな音がした。
「やだやだやだ! やだっ!」
むめたんは立ち上がった。猛然と走り出して画面の外に消える。ドアを激しく開け閉めする音が響いた。くぐもった足音が遠ざかる。
寒々しい部屋だけが画面に映っていた。
わたしは椅子に縮こまり、ほとんど呼吸を止めてパソコンを見つめていた。部屋に何らかの変化が起こるのでは、と思って目を逸らすことができなかった。
突然ぶつりと中継が途絶えた。真っ暗な画面から顔を上げ、時計を確認すると日付が変わっていた。
三井さんから何通もショートメールが届いていた。
〈ご覧になりました? どういうことですか?〉
〈こんなことってあるんですか?〉
〈お休みでしたら申し訳ありません。混乱しているので、ここで失礼させていただきます〉
読み終えたのと同時に、自分が独りであることに気付いた。この部屋で独り。この家で独り。むめたんなる少女は逃げ出した。三井さんはとっくに寝ただろう。
泣いて怯えるむめたんの姿が脳裏に浮かんだ。そして消えなかった。彼女はいつまで経っても頭の中に居座り続けた。
居間でテレビを観て過ごし、昼過ぎに良平が帰宅してから布団に入った。
書きかけのコラムのことを思い出したのは、締め切り当日の夕方だった。
むめたんのウェブアカウントがすべて消えたのは翌月のことだった。YouTube、ブログ、各種SNS。事前に告知は一切なかった。ファンらしき人々はあれこれ憶測を投稿していたが、以前から心身ともに調子が悪かったそうで、「涸れ井戸の声」と関連付けたものは一つもなかった。
わたしは夢を見るようになった。夢でうなされ、夜中に飛び起きるようになった。そのまま朝まで眠れず鬱々と一日を過ごす。そんな日が確実に増えていった。
夢の内容は呆れるほど陳腐だったが、それ以上に不吉だった。
曇り空の下、良平とドライブして寒村に行き当たる。荒れ放題の村を二人で歩き回る。いつの間にか前を行く良平が、村外れで井戸を見つけて走り寄る。
不安に思うわたしをよそに、彼は子供のような笑みをこちらに向け、そして井戸を覗き込み、すると中から、底から――
声がしたのは何となく覚えている。
良平が「あっ」と後ずさったことも、うっすら覚えている。だが、どんな声だったか、その後で何が起こったのかは、どれだけ頭を捻っても断片すら思い出せなかった。目覚めた瞬間にきれいさっぱり忘却し、拾い集めることは決してできなかった。
鮮明なのは感情だけだった。
凄まじいまでの恐怖に襲われたことだけ、記憶と胸の内に克明に刻み込まれていた。
「どうしたの最近?」
何回目か忘れたが、うなされて布団で目を覚ました時、隣で寝ていた良平がわたしの頬を撫でて訊ねた。暗い中で彼の目が光っていた。
わたしは大雑把に打ち明けた。彼は黙って聞いていたが、話が終わるなり「亜樹は真剣すぎるんだよ」と溜息を吐いた。
「恐怖とか怖いとかについて考えすぎて、気が滅入ってるんじゃないかな。よく聞くよ、ギャグについて考えすぎて精神を病んじゃうギャグ漫画家。あとほら、噺家の誰だっけ。上方の有名な、何でか『ドグラ・マグラ』映画版で大役を演ってる、禿頭の……」
「桂枝雀?」
「そう。あの人も鬱で自殺だろ。笑いを体系化しようと頑張り過ぎたからだ、なんて話もある」
良平は真剣な顔で「初心に帰りなよ。伸び伸び書くのが一番いい」と言った。何から何まで説明すれば、余計に頭がおかしくなっていると心配するだろう。わたしは「ありがとう」と笑った。夫の気持ちも助言も単純に嬉しかったし、迷惑をかけてはいけないと心の底から思った。
もう「涸れ井戸の声」について考えるのはやめよう。そう決意した。
このテキストも機を見て消去しよう。
信じられないことが起こっている。
目の前に「涸れ井戸の声」があるのだ。
短編を寄稿した『小説NON』の最新号。自分の作品を確認しようとページを捲ったところ、巻末に掲載されているのを見つけた。
作者はわたしだった。
扉ページ、「涸れ井戸の声」と大きく書かれたすぐ下に、「西村亜樹」とあった。
考えてはいけない。読みたいなどと思ってはいけない。つい先月に決めたばかりだ。ここで雑誌を閉じるのが賢明だ。
でも読みたい。読み進めたい。
男が井戸を覗き込んだらどうなるのか、一刻も早く知りたい。
理性が止めろと告げる。感情が読めと勧める。
こうして書くのがもどかしい。小説ですよと言わんばかりの文体を維持するのが辛い。馬鹿馬鹿しい。
読みたい。駄目だ。読みたい。駄目だ。どうしよう。どうもするな。少しだけなら。一行たりとも読むな。良平はいない。三井さんに電話しようか。いやそんな悠長なことをしている場合ではない。いや、している場合だ。
何をしているのだろう。無意味なことばかり書いている。そもそもこのファイルは消すはずではなかったのか。でももう消せない。むしろ書き足す。
そうだ。
わたしはこれから「涸れ井戸の声」を読む。
そしてここに書き写す。
読んだらどこかに消えてしまい、二度と会えない小説だとしても写せば何度でも読めるだろう。多くの人をあれだけ怖がらせた短編が、手元に残るのだ。読み返して何度も怖がることができるのだ。参考にもできる。模倣もできる。
考えただけで高揚する。そして恐ろしい。
そうだ、早くもわたしは恐怖している。読む前から、読もうと思っただけで、読めると期待しただけで。こんなにも手が震える。座っていられない。背後が気になる。
深呼吸を二度繰り返した。
キッチンで水を飲んで顔を洗った。
家の中は静かだ。聞こえるのは高鳴る鼓動だけ。
準備は整った。読もう。
「涸れ井戸の声」
※ ※
西村さんから受け取ったファイルの文章は、ここで終わっている。厳密にはここから原稿用紙にして五十三枚分の空白があるのだが、再現はしない。
読み終わって最初に思ったのは、「冗談だろう」というものだった。つまりこのテキストすべてが作り話、彼女の創作というわけだ。
実際、ネットで検索しても「涸れ井戸の声」なる小説はまったく出てこない。『小説新潮』の三井さんに訊いても「いや、分からないです」という答えが返ってきた。
「限界を感じたから、と仰ってました」
彼女が引退した理由も、三井さんはあっさり明かしてくれた。残念そうではあったが、同時に「よくある話だ」と受け入れているようでもあった。書きたい小説が自分の技量では書けない。理想と現実が
ぼくも同じように考えていた。
つい先日までは。
池袋でサイン会をした時のことだ。ありがたいことに閑古鳥が鳴くことはなく、ぼくは胸を撫で下ろしながら書店の一角で、新作の短編集にサインをしていた。
単行本の「扉」に筆ペンで名前を記し、左下に落款を捺す。右上にお客さんの名前を、希望があれば日付も書き加える。お客さんの質問にはできるだけ真面目に答えた。穏やかな老人に「この世界の真実を知っている。教えて欲しいか」と訊かれた時は困ったけれど、書店員さんは慣れているのか、老人と何事か話し合うと連れ立って出て行った。
「いつも読んでます」
母親ほどの年齢と思しき、上品な女性が微笑を浮かべる。ぼくはお礼を言いながら彼女の購入した本を開く。サラサラとサインしていると、
「雑誌でもよくお書きになってますね」
「ええ、目先の原稿料に目が眩んだので」
ははは、と笑い合う。
「この前『小説推理』に載ってた短編も読みましたよ。読み切りっていうんですかねえ、とっても怖かったです」
「ありがとうございます」
そう言いながらぼくは疑問を覚えた。『小説推理』は今年に入ってから一度も寄稿していない。連載していたのは去年のことだ。彼女にとっての「この前」は数年単位なのかもしれないが、読み切りというのが不可解ではある。
「あんな怖い話、どうやったら考え付くんですか?」
彼女は言うなり全身を震わせた。顔色まで少し悪くなっている。
「いや……捻り出しますよ。ウンウン言いながら」
落款を掴んだまま、ぼくは半笑いで答えた。胸の内で不安がざわざわと無数の枝を伸ばしている。落款を握る手が瞬時に汗ばみ、一方で口の中はからからに乾く。
「一番好きかもしれない。今までの先生の小説で。長編も短編も全部含めて」
女性は寒さを堪えるように身を縮めると、声を潜めて言った。
「本当に怖かったですから――涸れ井戸の声」