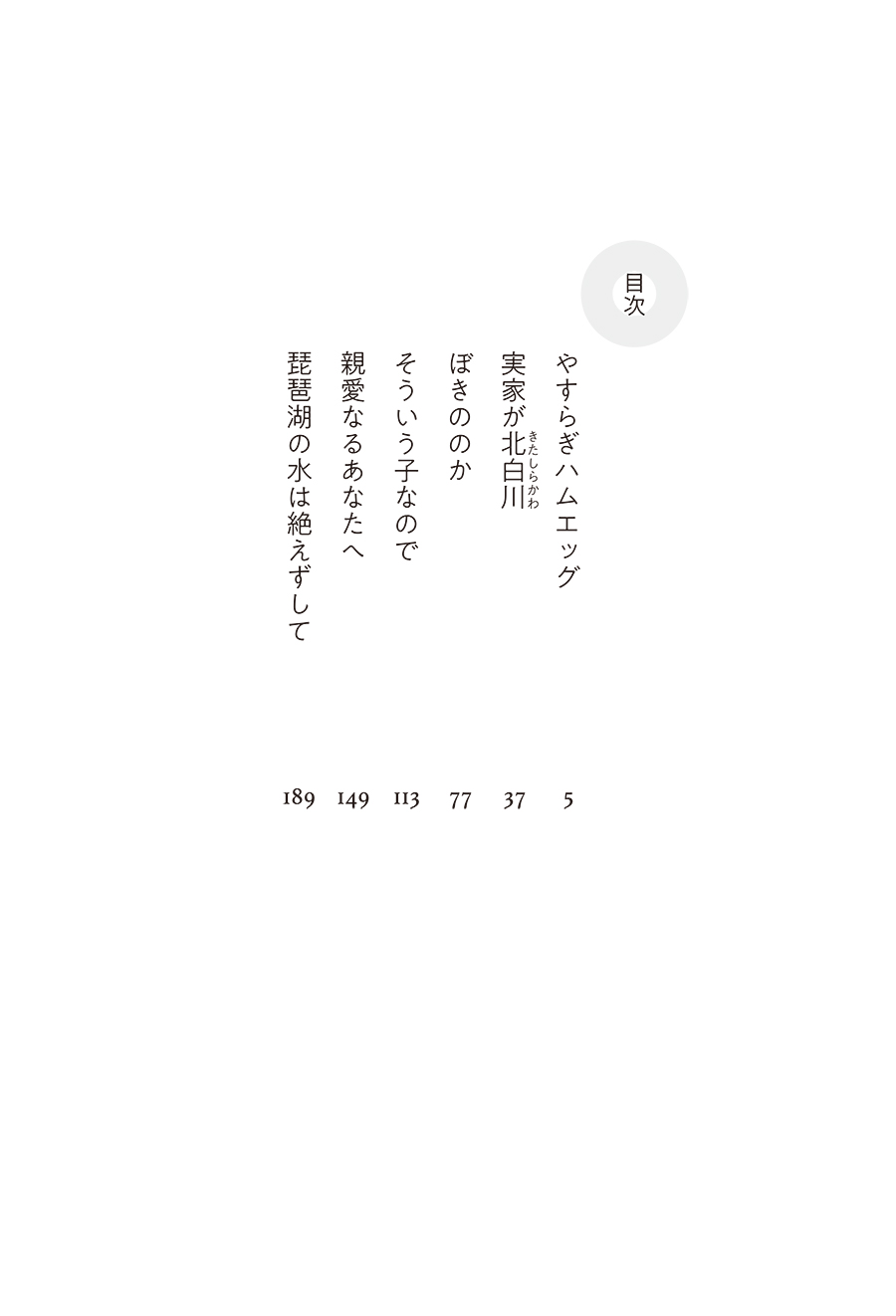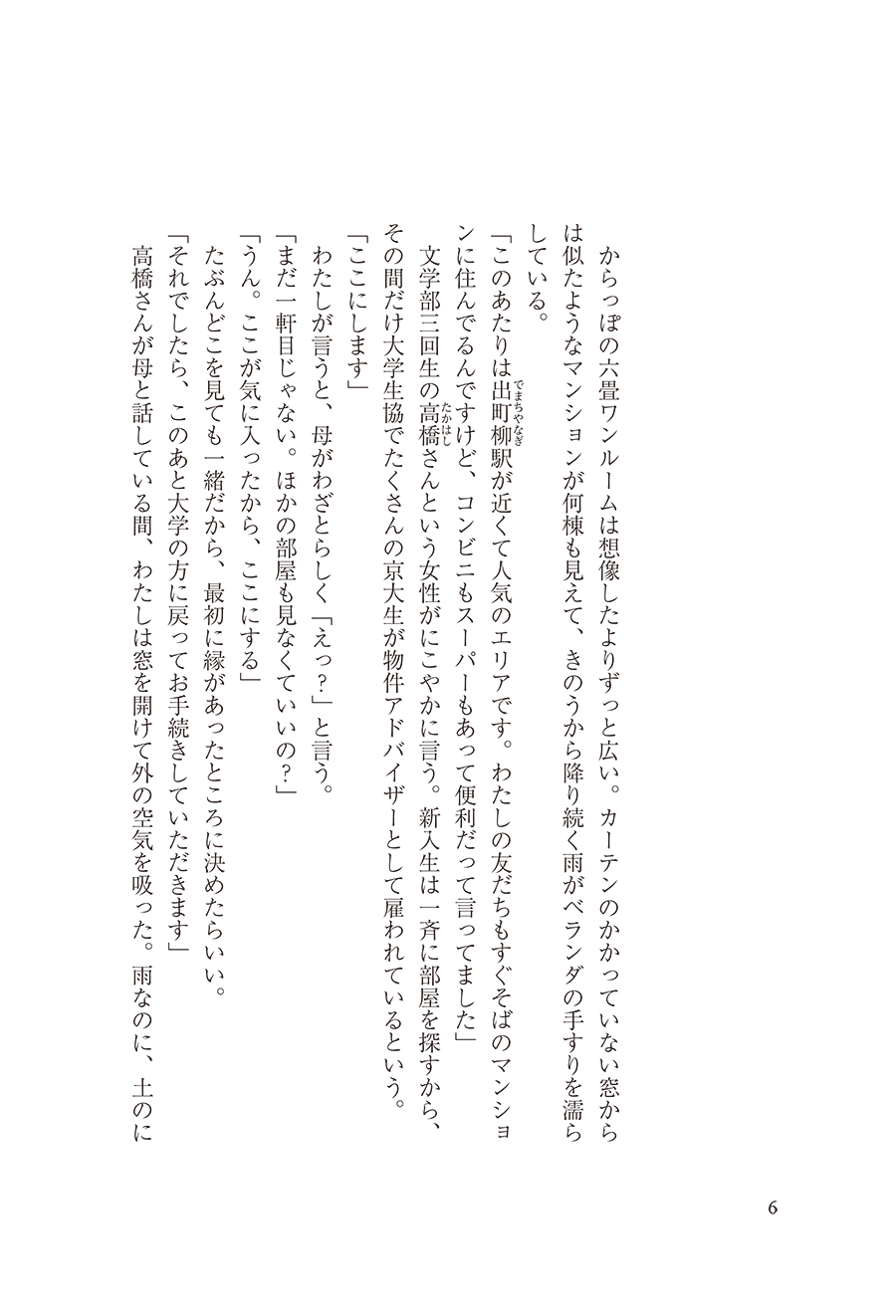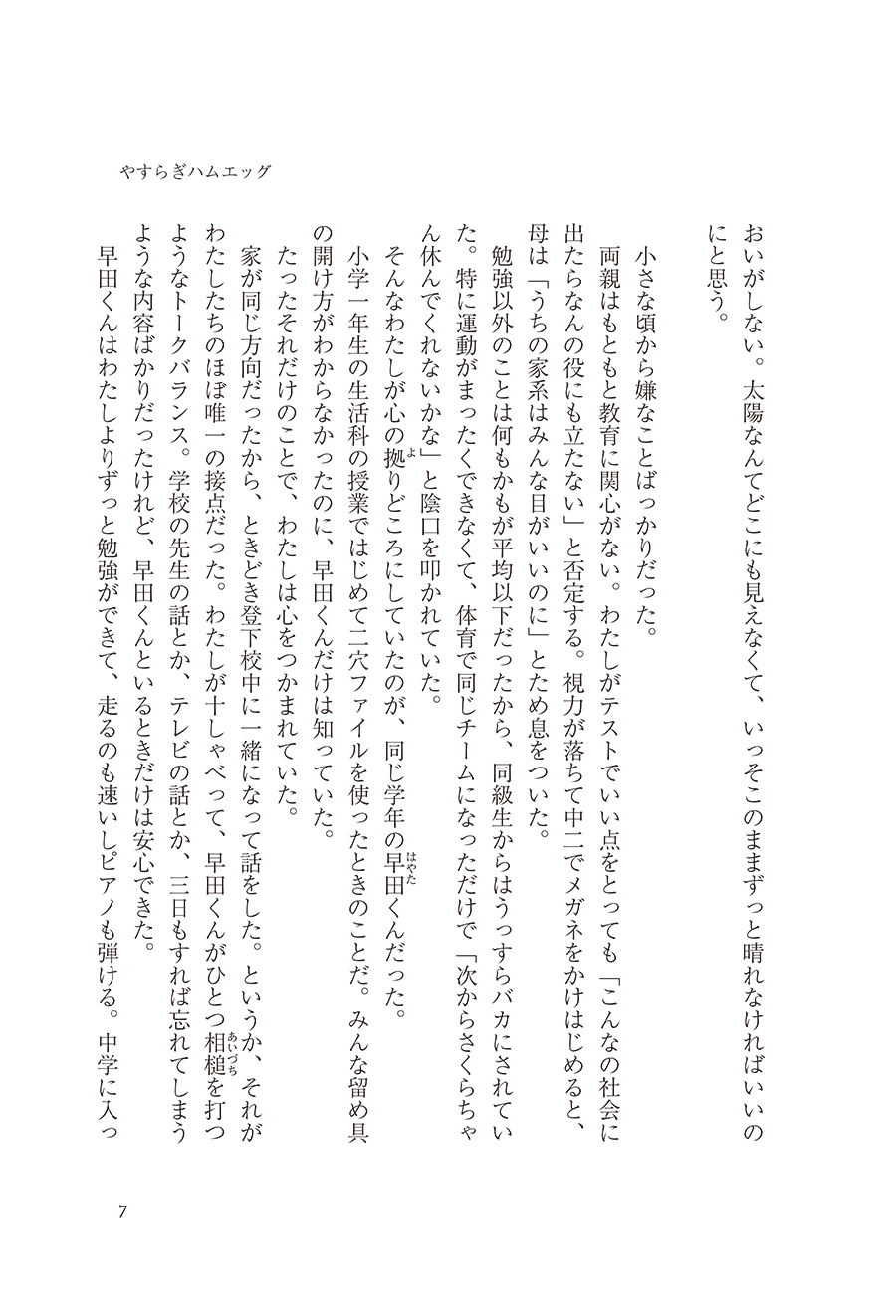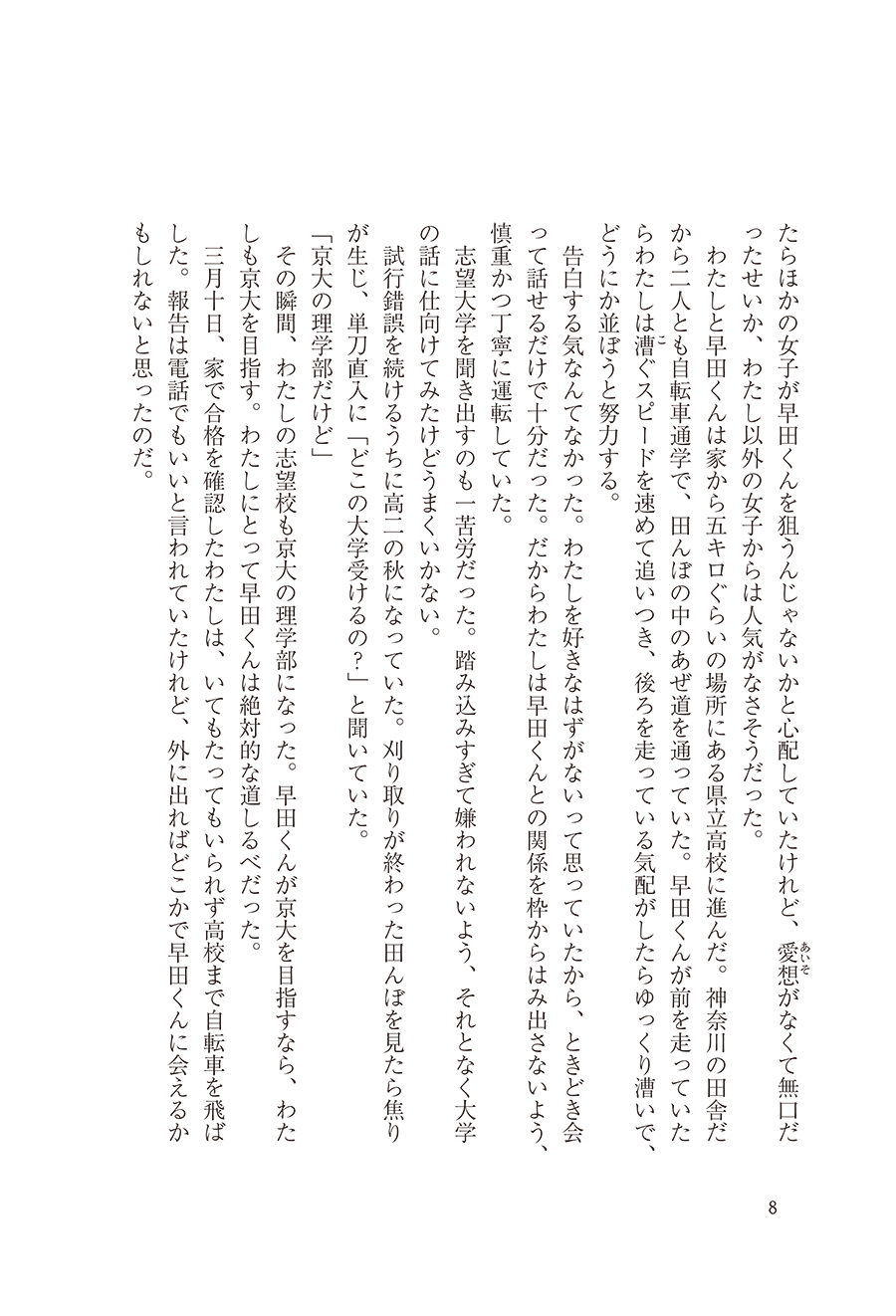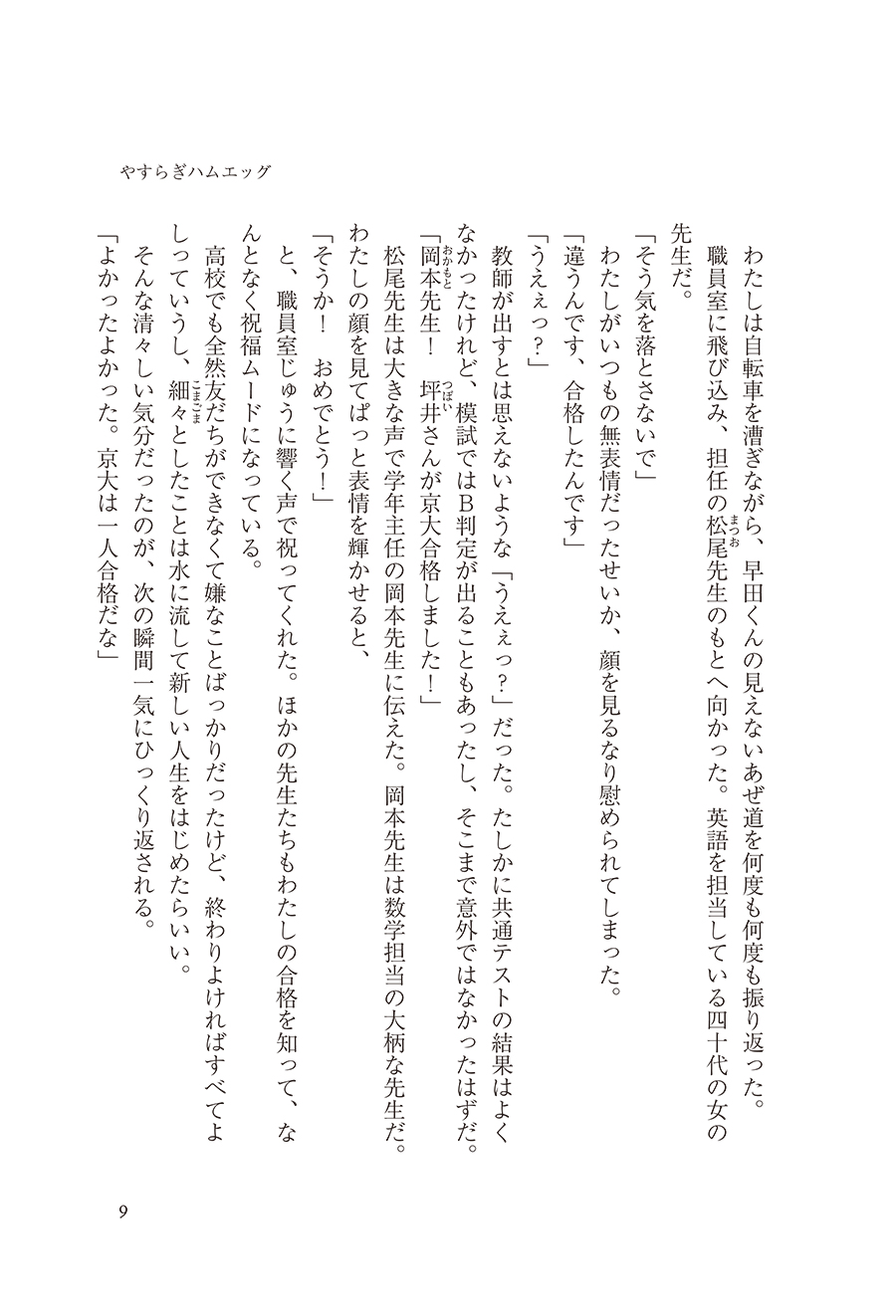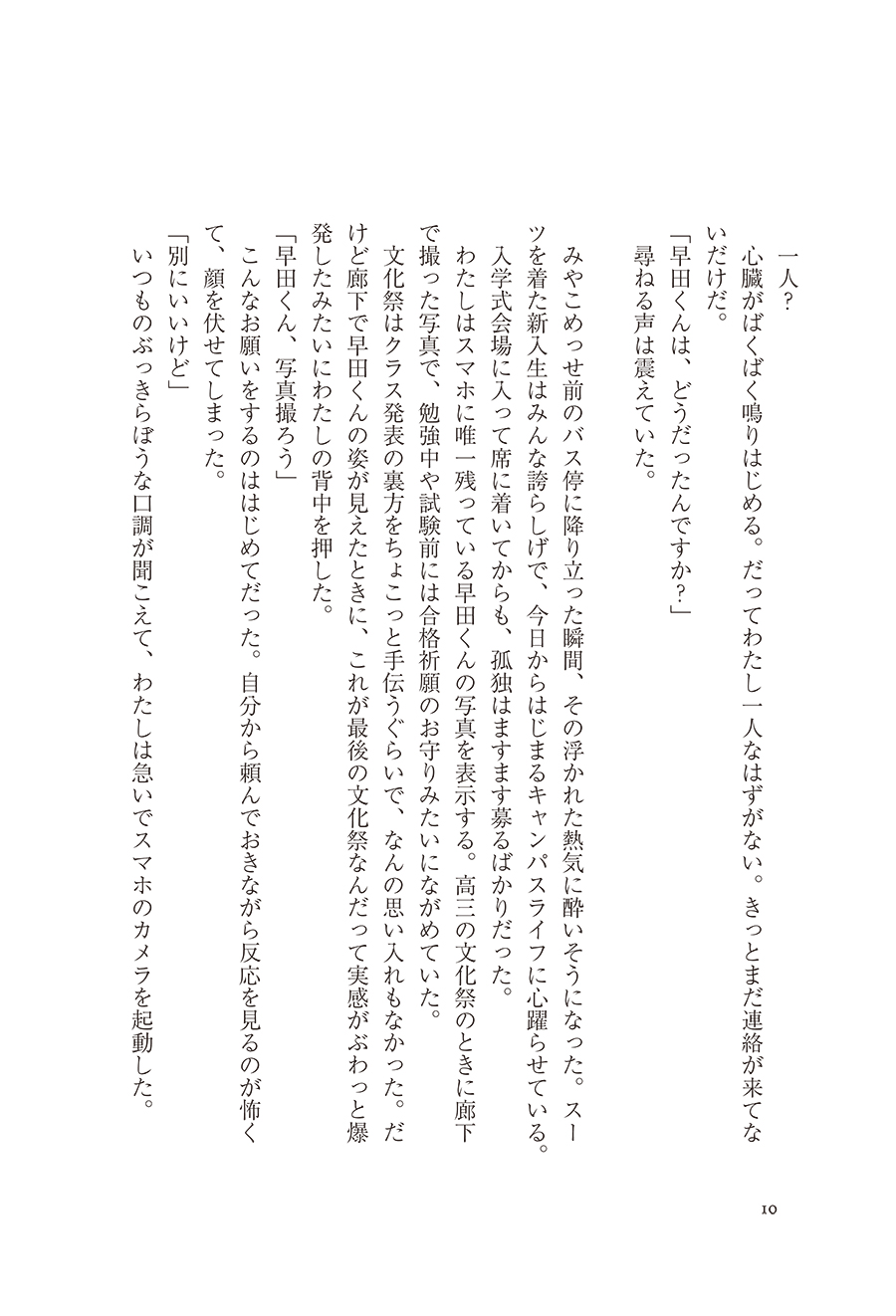やすらぎハムエッグ
からっぽの六畳ワンルームは想像したよりずっと広い。カーテンのかかっていない窓からは似たようなマンションが何棟も見えて、きのうから降り続く雨がベランダの手すりを濡らしている。
「このあたりは出町柳駅が近くて人気のエリアです。わたしの友だちもすぐそばのマンションに住んでるんですけど、コンビニもスーパーもあって便利だって言ってました」
文学部三回生の高橋さんという女性がにこやかに言う。新入生は一斉に部屋を探すから、その間だけ大学生協でたくさんの京大生が物件アドバイザーとして雇われているという。
「ここにします」
わたしが言うと、母がわざとらしく「えっ?」と言う。
「まだ一軒目じゃない。ほかの部屋も見なくていいの?」
「うん。ここが気に入ったから、ここにする」
たぶんどこを見ても一緒だから、最初に縁があったところに決めたらいい。
「それでしたら、このあと大学の方に戻ってお手続きしていただきます」
高橋さんが母と話している間、わたしは窓を開けて外の空気を吸った。雨なのに、土のにおいがしない。太陽なんてどこにも見えなくて、いっそこのままずっと晴れなければいいのにと思う。
小さな頃から嫌なことばっかりだった。
両親はもともと教育に関心がない。わたしがテストでいい点をとっても「こんなの社会に出たらなんの役にも立たない」と否定する。視力が落ちて中二でメガネをかけはじめると、母は「うちの家系はみんな目がいいのに」とため息をついた。
勉強以外のことは何もかもが平均以下だったから、同級生からはうっすらバカにされていた。特に運動がまったくできなくて、体育で同じチームになっただけで「次からさくらちゃん休んでくれないかな」と陰口を叩かれていた。
そんなわたしが心の拠りどころにしていたのが、同じ学年の早田くんだった。
小学一年生の生活科の授業ではじめて二穴ファイルを使ったときのことだ。みんな留め具の開け方がわからなかったのに、早田くんだけは知っていた。
たったそれだけのことで、わたしは心をつかまれていた。
家が同じ方向だったから、ときどき登下校中に一緒になって話をした。というか、それがわたしたちのほぼ唯一の接点だった。わたしが十しゃべって、早田くんがひとつ相槌を打つようなトークバランス。学校の先生の話とか、テレビの話とか、三日もすれば忘れてしまうような内容ばかりだったけれど、早田くんといるときだけは安心できた。
早田くんはわたしよりずっと勉強ができて、走るのも速いしピアノも弾ける。中学に入ったらほかの女子が早田くんを狙うんじゃないかと心配していたけれど、愛想がなくて無口だったせいか、わたし以外の女子からは人気がなさそうだった。
わたしと早田くんは家から五キロぐらいの場所にある県立高校に進んだ。神奈川の田舎だから二人とも自転車通学で、田んぼの中のあぜ道を通っていた。早田くんが前を走っていたらわたしは漕ぐスピードを速めて追いつき、後ろを走っている気配がしたらゆっくり漕いで、どうにか並ぼうと努力する。
告白する気なんてなかった。わたしを好きなはずがないって思っていたから、ときどき会って話せるだけで十分だった。だからわたしは早田くんとの関係を枠からはみ出さないよう、慎重かつ丁寧に運転していた。
志望大学を聞き出すのも一苦労だった。踏み込みすぎて嫌われないよう、それとなく大学の話に仕向けてみたけどうまくいかない。
試行錯誤を続けるうちに高二の秋になっていた。刈り取りが終わった田んぼを見たら焦りが生じ、単刀直入に「どこの大学受けるの?」と聞いていた。
「京大の理学部だけど」
その瞬間、わたしの志望校も京大の理学部になった。早田くんが京大を目指すなら、わたしも京大を目指す。わたしにとって早田くんは絶対的な道しるべだった。
三月十日、家で合格を確認したわたしは、いてもたってもいられず高校まで自転車を飛ばした。報告は電話でもいいと言われていたけれど、外に出ればどこかで早田くんに会えるかもしれないと思ったのだ。
わたしは自転車を漕ぎながら、早田くんの見えないあぜ道を何度も何度も振り返った。
職員室に飛び込み、担任の松尾先生のもとへ向かった。英語を担当している四十代の女の先生だ。
「そう気を落とさないで」
わたしがいつもの無表情だったせいか、顔を見るなり慰められてしまった。
「違うんです、合格したんです」
「うえぇっ?」
教師が出すとは思えないような「うえぇっ?」だった。たしかに共通テストの結果はよくなかったけれど、模試ではB判定が出ることもあったし、そこまで意外ではなかったはずだ。
「岡本先生! 坪井さんが京大合格しました!」
松尾先生は大きな声で学年主任の岡本先生に伝えた。岡本先生は数学担当の大柄な先生だ。わたしの顔を見てぱっと表情を輝かせると、
「そうか! おめでとう!」
と、職員室じゅうに響く声で祝ってくれた。ほかの先生たちもわたしの合格を知って、なんとなく祝福ムードになっている。
高校でも全然友だちができなくて嫌なことばっかりだったけど、終わりよければすべてよしっていうし、細々としたことは水に流して新しい人生をはじめたらいい。
そんな清々しい気分だったのが、次の瞬間一気にひっくり返される。
「よかったよかった。京大は一人合格だな」
一人?
心臓がばくばく鳴りはじめる。だってわたし一人なはずがない。きっとまだ連絡が来てないだけだ。
「早田くんは、どうだったんですか?」
尋ねる声は震えていた。
みやこめっせ前のバス停に降り立った瞬間、その浮かれた熱気に酔いそうになった。スーツを着た新入生はみんな誇らしげで、今日からはじまるキャンパスライフに心躍らせている。
入学式会場に入って席に着いてからも、孤独はますます募るばかりだった。
わたしはスマホに唯一残っている早田くんの写真を表示する。高三の文化祭のときに廊下で撮った写真で、勉強中や試験前には合格祈願のお守りみたいにながめていた。
文化祭はクラス発表の裏方をちょこっと手伝うぐらいで、なんの思い入れもなかった。だけど廊下で早田くんの姿が見えたときに、これが最後の文化祭なんだって実感がぶわっと爆発したみたいにわたしの背中を押した。
「早田くん、写真撮ろう」
こんなお願いをするのははじめてだった。自分から頼んでおきながら反応を見るのが怖くて、顔を伏せてしまった。
「別にいいけど」
いつものぶっきらぼうな口調が聞こえて、わたしは急いでスマホのカメラを起動した。
撮ってくれたのは名前も知らない早田くんの友だちだ。写真のわたしはうれしすぎたらしく、見たことのないような笑顔を浮かべて両手でピースしている。一方で早田くんは笑顔の下限みたいな表情で、やる気のなさそうなピースをしていた。
気付けば頰に涙が伝っていた。ここに来るまで何度「おめでとう」と言われただろう。そのたびわたしは自分の気持ちとの乖離を嘆かずにはいられなかった。早田くんのいない世界なんてわたしにとっては太陽のない世界で、どっちが上でどっちが下かもわからない。
わたしはたまらず席を立った。もう入学式なんてどうでもいい。隣の男子の足を踏みそうになりながら通路に出て、逃げるように会場を出る。水路沿いの桜並木まで走ったところで履き慣れないパンプスが滑って、危ないと思ったときにはもう転んでいた。
涙がコンクリートの地面に落ちる。ここに早田くんが現れて、わたしを起こしてくれたらいいのに。三月十日から今日までのことはすべて悪い夢で、早田くんもわたしと一緒に京大に受かっていて……。
「大丈夫か」
幻聴かと思った。おそるおそる視線を上げると、紺色の振袖を着た女子がこっちを見下ろしている。背後では満開の桜が花びらを散らしていて、わたしは何も言えずに見とれてしまった。
「立てるか?」
女はわたしの手を引き、近くのベンチに座らせてくれた。自分の膝をのぞきこむと、ストッキングがやぶれて血がにじんでいる。まだ一回しかはいてないのにもったいない。
「これは脱いだほうがいいが、ここで脱ぐのは問題があるな。中に行けば救護担当がいるのではないか」
「あっ、わたしは、もう大丈夫です」
「大丈夫じゃないだろう」
女は和装に不似合いな大きな鞄をさぐり、ウェットティッシュを取り出した。
「しみるかもしれないが、ひとまずこれで拭くといい」
わたしは言われたとおり膝ににじんだ血を拭いた。血の量はたいしたことがないが、強く打ったせいかじんじん熱く痛む。
「えっと、あなたは……」
わたしが尋ねた瞬間、風が強く吹いて女の後れ毛を揺らした。
「理学部一回生、成瀬あかりだ」
どこからか舞ってきた桜の花びらが、成瀬さんの頭にくっつく。
「君は受験番号一一〇番だっただろう」
迷いなく言い当てられて、心臓が止まりそうになった。
「えっ?」
「わたしは一〇八番で、君の二つ前の席に座っていたんだ」
「すごい記憶力ですね」
入試の日、わたしは理学部の大教室で早田くんの姿をきょろきょろ探していたけれど、まわりの人の顔なんて覚えていない。
「京大生から見ても珍しいのか」
成瀬さんは表情を変えないが、声のトーンはなぜか少し悲しそうだ。
「えっと、わたしは坪井さくらっていいます」
あわてて名乗ると、成瀬さんは「よろしく」とうなずいた。
「……その着物、素敵ですね」
とりあえず隙間を埋めるみたいな言葉を発する。
「五年前に死んだ祖母の形見だ。母は地味すぎるのではないかと懸念していたが、桜が入っているから今の時期にぴったりだと思ったんだ」
言われてみれば天の川みたいに桜が描かれている。わたしはさくらという名前なのに十月生まれで、あんまりしっくりきていなかった。だけど早田くんがごくまれにわたしを「さくら」と呼ぶ瞬間があって、そのときだけは桜になれた気がした。
「顔色がよくない。具合が悪いのか?」
成瀬さんがわたしの顔をまじまじと見つめて尋ねる。具合が悪いのは間違いないが、「大丈夫です」と言うしかない。
「ちょっと待っててくれ」
成瀬さんは道の向かいの自動販売機でほうじ茶を買ってきてくれた。
「えっ、そんな、お金払います」
「気にしなくていい」
ペットボトルのふたを開けて一口飲むと、冷たいほうじ茶がすっとのどを通っていくのがわかった。ほうじ茶ってこんなにおいしかったんだ。一人暮らしをはじめてから食欲が湧かず、食パンと水道水だけで生きていた。
成瀬さんはわたしの前に立ったまま腕組みをしてこっちを見ている。
「あ、もう入学式はじまっちゃいますよ。成瀬さんだけでも戻ってください」
「君は出なくていいのか」
「もう少し休んでから行きます」
「そうか」
成瀬さんは頭に桜の花びらをつけたまま、会場へと入っていった。
わたしはもう一口お茶を飲んでから、スマホを出して桜の写真を撮った。友だちもいないし、インスタもやってないし、ただわたしのスマホに残るだけの桜。
早田くんがわたしを「さくら」と呼ぶ声も、残しておけたらよかったのに。
あの日、早田くんの合否を尋ねたわたしに岡本先生は笑顔のまま答えた。
「早田なら、東大受かったぞ」
「東大?」
なにかの間違いだと思った。岡本先生の言い間違いか、早田くんの言い間違い。いや、わたしが京大を受けちゃったのが間違いだったのかもしれない。
「あぁ。今年は東大二人、京大一人だ。坪井、本当によかったな」
よかったって、何がよかったんだろう。何も言えずに立ち尽くしていると、岡本先生が「どうした?」と尋ねる。
「早田くんも、京大受けると思ってました」
「いや、あいつは夏ぐらいに東大に変えたんだ」
泣きながら自転車を漕いで家に帰った。いつも胸を高鳴らせて通ったあぜ道は、魔法が解けたみたいにごつごつしていた。
ぼんやり桜をながめているうちに、入学式は終わっていた。午後は京大の北部キャンパスで理学部ガイダンスがある。だけど新入生で混み合うバスには乗る気になれなくて、わたしは徒歩で三十分かけて移動することにした。
さっきもらったほうじ茶で水分補給しながら、東大路通を北上する。交通量が多く、歩道にも自転車が行き交っていて騒々しい。もしもこのあたりに生まれていたら、登下校中の会話を楽しむことなどできなかったかもしれない。
ガイダンスの会場は入試を受けた大教室だった。一番うしろの席から教室内を見渡すと、見事に男子ばっかりだ。一割ぐらいしかいない女子はすでにグループで固まっていて、わたしはさっそく出遅れているらしい。今から話しかけて仲間に入れてもらうなんて小器用なことはできそうになかった。
それでもなんとか話しかけられそうな相手がいないか視線をさまよわせていると、教室の前の入口から明らかに様子の違う女子が入ってきた。白い帽子に白い衣装、たすきには赤い文字で「びわ湖大津観光大使」と書いてある。何者だろうと思ったのも一瞬で、左肩からさげている黒い大きな荷物が目に留まる。
間違いない、成瀬さんだ。
「びわ湖大津観光大使だって」
「何者?」
同じ列に座っている男子二人の会話が聞こえて、あれは同じ理学部の成瀬さんだと心のなかで教えてあげる。
成瀬さんは最前列のセンターに座ると、帽子をはずして膝に載せた。さっきまでハーフアップにしていた髪は下ろしている。わたしがみやこめっせから北部キャンパスまでふらふら歩いている間に、衣装のみならず髪型まで直していたらしい。
「目立ちたくてやってるのかな?」
「ていうか本物?」
男子がくすくす笑っている。やっぱりあれはちょっと変、ということでいいらしい。京大は変な人が多いっていうイメージがあったけれど、みんながみんな変なわけじゃなくて、変じゃない人が多数派なのだ。さっきわたしに話しかけてくれたことはありがたかったけれど、正直ちょっと近寄りがたい。
スマホで「びわ湖大津観光大使」を検索すると、びわ湖大津観光協会のホームページが出てきた。令和七年度の観光大使が篠原かれんさんと成瀬あかりさんに決まりましたというニュースは三月三十日付で、おそろいの観光大使の衣装を身につけた二人がカメラ目線で微笑んでいる。
わたしが打ちひしがれながら引っ越しの準備を進めていた頃、成瀬さんは新たなステップを踏み出していたのだと思うと、その落差にむなしくなる。
それにしても、観光大使なんてよっぽど容姿に自信がないとできないはずだ。まあまあかわいいけど、超美人って感じでもない。見た目よりも意欲で選ばれたのだろうか。
「定刻になりましたので、これより理学部新入生ガイダンスをはじめます」
気付けば壇上に教員らしき人が立っていた。わたしはスマホをしまい、ペンを手に取る。
ガイダンスを終えたら、久しぶりにお腹が空く感覚があった。いつも食パンを買っているセブンイレブンで、のり弁を買って帰宅する。
あんなにがらんとしていた六畳一間も、家具を運び込んだ途端に空き容量がぐっと減った。鞄からは捨てそびれたストッキングと空のペットボトルが出てきて、振袖姿の成瀬さんを思い出す。
わたしはのり弁を食べながら、スマホで「成瀬あかり」を検索した。滋賀県立膳所高校かるた班の主将だったとか、ゼゼカラというコンビでM-1グランプリに出場したとか、大津市民短歌コンクールで入賞したとか、華々しい経歴が世界中に発信されている。
観光大使の写真を除いてはほぼ無表情で、何を考えているのかわからない。思えば早田くんもポーカーフェイスで、どんな感情を抱いているのかわかりづらかった。
ためしに「坪井さくら」で検索してみたら、小学生のときに入選した税の作文コンクールのページが出てくるだけで、全然手応えがない。
やっぱり京大でも目立つような人は入学前から仕上がっている。わたしなんてたまたま勉強ができただけで、誇れるものがひとつもない。
半分以上残ったのり弁はすっかり冷めている。きっともう食べないんだろうなと思いつつ、ふたを閉めて冷蔵庫にしまった。
翌日は一限からさっそく線形代数学の授業があった。はじまる五分前に教室に着くと、成瀬さんがまた一番前のセンターに座っているのが見えた。今日は白い長袖の服に紺のズボンというシンプルな装いで、髪はひとつにまとめている。
今なら話しかけられそうだけど、成瀬さんに近寄ったら変な人だと思われてしまうだろうか。わたしが逡巡していると、不意に成瀬さんがこっちを向いた。
「おう、坪井。おはよう」
「お、おはよう」
わたしは階段状になった教室内を見渡す。空席はぱらぱらあるけれど、さしあたって座りたい席はないし、誰もこっちなんて見ていない。
わたしは流れでそうなりましたという顔で、成瀬さんからひとつ空けた席に座った。
「きのう、お茶ありがとうございました」
「礼には及ばない」
成瀬さんは基本無表情だけど、それを誰かに言われたことってないのかな。
「どうかしたか?」
成瀬さんの顔を凝視していたことに気付き、あわてて目を逸らす。
「成瀬さんは、実家から通ってるの?」
同級生なのに敬語なのも変かと思い、タメ口で聞いてみる。
「そうだ。大津市の膳所というところに住んでいる」
「ぜぜ?」
わたしが聞き返すと、成瀬さんは定期券を取り出し「膳所」の文字を指した。
「こう書いて『ぜぜ』と読む」
きのう見た「膳所高校」と「ゼゼカラ」がつながる。
「『ぜんしょ』かと思ってた」
「難読地名だからな」
わたしも自分のことを話すべきか迷っているうちに、黒いスーツを着た五十代ぐらいの男の先生が入ってきた。成瀬さんが姿勢を正して前を向いたので、わたしも合わせて前を向いた。
わたしは愛想のない人に心惹かれるのかもしれない。生協食堂で成瀬さんと向き合って、そんな考えが浮かんできた。
「さっきもわたしの顔を見ていたが、なにか気になる点があるのか」
「ごめん。なんか、見ちゃうの」
成瀬さんは「それなら仕方ないな」と言いながら箸を持って味噌汁をすすった。成瀬さんのトレイにはライス大と味噌汁と鮭の塩焼きとほうれん草のおひたしが載っている。栄養バランスが考えられた見事な献立だ。
わたしは相変わらず何を食べたらいいかわからなくて、無難にきつねうどんにした。関西の出汁は薄いっていうけど、そんなに変わらない気がする。
「坪井は標準語だな。関東の出身か?」
「うん。神奈川の田舎のほう」
そういう成瀬さんは滋賀に住んでいるのに、全然関西弁っぽくない。
「わたしの幼なじみの母親が横浜の出身で、関東と関西ではネギが違うと話していた」
言われてみると、浮かんでいるネギが鮮やかな緑色をしている。
「ほんとだ。関東では白いネギだよ」
「そうか」
ここで成瀬さんと一緒にお昼を食べることになったのはたまたまだ。二限も同じ英語の授業だったからなんとなく隣同士で受けて、そのあと成り行きで生協食堂にやってきたという流れである。
「坪井は京都に関心があるか」
「全然ないけど、なんで?」
京都には高校の修学旅行で一度来ただけだ。清水寺とか金閣寺といったメジャーなスポットを巡ったけれど、どこも観光客がいっぱいで疲れてしまった。
「せっかく京都の大学に来たことだし、あちこち見て回りたいと思っているんだ」
「へぇ」
なんだかやる気のかたまりみたいな人だ。そのわりに表情は一定で、何を考えているかわからない。
「成瀬さんってずっとそんな感じなの?」
「そんな感じ、とは」
ぎろりと睨まれた気がしたけれど、ただ単に目力が強いだけかもしれない。
「あんまり表情が変わらないというか」
「あぁ、それは幼少期から言われているな。わたしだって内心では喜んだり悲しんだりしているのだが、表面からは気付かれにくいらしい」
成瀬さんはごはんを一口食べた。さっきから少しずつ口に入れ、丁寧に咀嚼している。
「親はなんにも言わない?」
「たとえばどんなことだ?」
成瀬さんは首をかしげた。この時点でわたしのように口うるさく言われていないのは見て取れる。
「もっと愛想よくしなさいとか」
「ないな。そういうものだと思われているらしい」
あぁ、わたしもそんな家に生まれたかった。
「わたしは愛嬌のあるお姉ちゃんといつも比べられて、あんたは愛想がないとか、もっとニコニコしなさいっていつも言われてたの。だから成瀬さんがうらやましい」
「えぇっ」
成瀬さんは表情を変えずに驚きの声だけ上げる。
「わたしは坪井に愛想がないなんて思っていなかった。十分笑顔だし、感じよく話しかけてくれるじゃないか」
「えぇっ」
今度はわたしが驚いた。京都に来てから一度も笑顔なんて作っているつもりがなかった。
「きっとそういう姿勢が身についているんだな。わたしは観光大使になって、口角を上げる練習をしているところだ」
成瀬さんは箸とお茶碗を置くと、両手の人差し指で口角を引き上げた。笑顔というより変顔に近い気がするが、表情を付加しようとする心意気は感じる。
「そうそう、なんで観光大使になったの?」
「わたし以上の適任者はいないと思ったからだ」
「それはすごいね」
成瀬さんってこういう人なんだって、はっきりわかった。きっと誰からも否定されず、自分の思うままに生きてきたのだろう。人生におけるすべてのガチャで大当たりを引いていることに、本人は気付いているのだろうか。
「でも、観光大使って笑顔でやるものでしょ? 自分には向いてないって思わなかった?」
あまりに恵まれている成瀬さんに、少し意地悪な質問をしてみた。成瀬さんは視線を斜め上に向けて考えてから、口をひらいた。
「向いているかどうかなんて、やってみないとわからないじゃないか」
完敗だった。わたしは「そうだね」と言って、きつねうどんの汁をすする。
「そういえば、なんでガイダンスのとき観光大使の衣装着てたの?」
ふと浮かんだ疑問を口にすると、「まぁあれが今年の衣装だからな」と要領を得ない答えが返ってきた。
「みんなに笑われたらいやだなとか思わない?」
「注目を集めることはいいことだ。わたしがたすきを着けていたことで、少なからず琵琶湖や大津に関心を持ってもらえただろう。それがわたしの役目なんだ」
「役目かぁ」
わたしの役目なんて、考えたこともなかった。きっと成瀬さんは役目を見つけるだけの余裕があるんだろう。
「わたしには役目なんてないよ」
「そんな気負わずとも、生きてるだけでいいんだ」
わたしは小さくため息をつく。そんなふうに思えるのは成瀬さんが肯定されてきたからだ。わたしは家でも学校でもうまくいかなくて、生きているのがつらかった。
中学の体育でバレーボールをやったとき、わたしのせいで負けたと責められた。家に帰って死にたいとうっかり漏らしたら、母は「そんなこと言うもんじゃない」と頭ごなしに怒鳴った。だからわたしはその思いを心のうちに秘めていて、生きてる「だけ」がすごく重い。
そんな物思いにふけっている間も、成瀬さんはまだもぐもぐと白米を食べ続けている。わたしはとっくにうどんを食べ終わったのに、成瀬さんのお茶碗には白米が半分ぐらい残っていた。
「すまない。わたしは食べるのが遅いんだ。先に出てもらっていい」
「いや、別にいいよ」
食べるのが遅いことも、成瀬さんは否定されなかったんだろう。どうしてわたしのそばにはまるごと肯定してくれる人がいなかったのかな。
不意に早田くんの顔が思い浮かぶ。早田くんはわたしを否定しなかった。それだけで親やほかの同級生とは違っていた。
早田くんすらいなかったら、わたしはどうなっていたんだろう。
食器を置いた成瀬さんがポケットティッシュを差し出したのを見て、自分が泣いていることに気付いた。
「あぁっ、ごめん」
わたしはあわててポケットティッシュを受け取る。
「別に謝らなくていい」
成瀬さんに言われてはっとする。わたしはほうじ茶もティッシュもすんなり受け取れない。もっと相手を信じてみてもいいのかもしれない。
「失恋したの」
ちょっとニュアンスが違う気がするけれど、端的に伝えるには都合のいい言葉だった。成瀬さんは「なるほど」とうなずいて腕を組む。
「それはつらかっただろうな」
「つらい」
声に出したら少しだけ楽になった。考えてみれば、わたしはこれまで早田くんへの思いを誰にも話していない。本人にはもちろん、母にもバレないよう注意していたし、恋バナができる友だちなんて一人もいなかった。
成瀬さんは無表情のままだけど、そのうなずき方には慈悲が感じられた。早田くんと長年過ごしてきて、微妙な感情の揺れへのセンサーが鋭くなったのかもしれない。
「さしあたり、ほかのことに打ち込んで気を紛らわすほかないだろうな」
そんなに簡単に気持ちを切り替えられたらどんなにいいだろう。これまでわたしが夢中になった対象は早田くんだけだ。新しく夢中になれるものなんて、見当がつかない。
「じゃあ成瀬さんが決めて」
これまでひとつもガチャを外さなかった人ならきっと間違いない。成瀬さんは特に気負った様子もなく、「料理はどうだ」と提案した。
帰り道、わたしは今出川通沿いにあるスーパーコレモにはじめて立ち寄った。
地元のスーパーにはどこも大きな駐車場があったから、駐輪場しかないなんてカルチャーショックだ。売り場の通路も狭くて、コンビニみたいに見える。
これまで料理なんて家庭科の調理実習でしかやったことがない。成瀬さんに何を作ったらいいかわからないとこぼすと、ハムエッグ丼をすすめられた。中学生の頃から毎朝自分で作って食べているという。半熟の黄身と熱々のごはんを絡めて食べるのが至高だそうで、話を聞いているうちにわたしも食べたくなってきた。
卵売り場に向かうと、さっそく選択を迫られた。実家の冷蔵庫には当たり前のように十個パックが入っていたけれど、一人暮らしで十個は多すぎるかもしれない。だけど四個パックや六個パックは割高だ。
わたしが悩んでいる間も、ほかの客は迷いなく十個パックを手に取っていく。考えてみれば、ハムエッグ丼以外にもゆで卵やスクランブルエッグに使えるだろう。わたしは十個パックで一番安いものを買い物かごの底にそっと置いた。
次はハムをチェックする。三枚入りパックが四つつながったものと、四枚入りパックが三つつながったものが目立つ位置にあった。同じ十二枚でも一パックは偶数のほうが落ち着くので、四枚×三のほうにした。
肝心のお米もいろんな大きさがある。さすがに十キロの袋は自転車のかごに入らなそうなので、二キロのこしひかりを選んだ。
フライパンをコンロにかけるところを想像して、油も必要だと気付く。それに塩こしょうやしょうゆも要るだろう。ソース売り場には実家で使っていたオレンジ色のラベルの中濃ソースがなくて、とんかつソースとウスターソースが並んでいる。
売り場を見ているうちにしばらく飲んでいなかった牛乳が飲みたくなって、だったら久しぶりにきのこの山も食べたくなり、買い物かごがしんどい重さになってきた。
レジ袋に五円払って、今後はエコバッグを持ってこようと心に誓う。買ったものをかごに入れて自転車を漕ぐと、生活している実感が湧いた。
部屋さがしのときにはキッチンのことなんて全然考えていなかったけれど、一応新しめのIHコンロが一口ある。まな板、包丁、フライパンといった基本的な調理器具は買ってあったので、なんとかなりそうだ。
使っていなかった炊飯器の説明書を開いてみる。お米なんて三十分もあれば炊けると思っていたが、標準コースでは五十三分かかるという。早炊きコースなら二十八分と書いてあって、最初から本気出せよと突っ込みたくなる。
研いだお米を早炊きコースでセットして、スマホでハムエッグの作り方を検索した。卵とハムをフライパンで焼けばいいって見当はつくけれど、IHコンロの使い方がわからないし、できれば失敗したくない。
見つけたレシピサイトに書いてあるとおりにフライパンを温めて、適当に油を引いて、ハムを敷き、卵を割り落とす。じゅうっという音とともに透明な白身が白く色づいて、わたし料理してるって思う。
ハムエッグを作りはじめるのが早すぎたせいでお米が炊けるタイミングと全然合ってなかったけど、どうにかごはんの上にハムエッグを載せたものが完成した。買ってきたウスターソースをかけて、成瀬さんが言っていたように黄身を崩してごはんと一緒に口に入れたら思わず「おふっ」と声が出た。すでにひんやりしている黄身をあつあつごはんが抱き締めるかのようにカバーしていて、冷えていた指先まで血が通うような感覚がある。これまで食欲がなかったのが噓のように、二口三口と食べたくなる。
わたしは半分ぐらい食べてしまったハムエッグ丼を写真に収めた。成瀬さんのLINEを聞いておけばよかった。残りのハムエッグ丼をかきこみながら、余った卵で何を作ろうかと考えていた。
その日以来、わたしは料理に傾倒した。自分で作って自分で食べるものだから、誰からも否定されないのがいい。たとえおいしくなくてもお腹に収めてしまえばわたしの栄養になる。
カレーは箱に書いてあるとおりに作っただけでもおいしかった。餃子は焼き加減が難しくて焦げてしまった。そんな試行錯誤を一ヶ月繰り返しているうちに、早田くんのことよりも次に作る料理に関心が向くようになった。
「京都を見て回りたいって言ってたけど、どこか見てきた?」
線形代数学と英語がある火曜日は、成瀬さんと一緒にお昼を食べる日だ。成瀬さんはいつもライス大をとってもぐもぐ食べている。長生きするために健康に気を遣っているそうで、急激な血糖値の上昇を防ぐために三十回以上嚙むようにしているらしい。どうりで食べるのが遅いわけだ。
「ああ、手始めにすぐそこの吉田神社を見てきた。厄除と開運の神がいるというので念入りに参拝した」
「へぇ、わたしも行ってみようかな」
成瀬さんは箸を置いてわたしの顔をじっと見た。
「最近調子良さそうだな」
「うん。料理するようになったからかも。成瀬さんのおかげだよ」
自炊をするようになってから、生協食堂では自分が作れないものを食べようという意識になった。特に揚げ物は家で作る気になれないから、今日はチキンカツ柚子胡椒マヨを食べている。
「ほう」
今のはうれしいときに出る「ほう」で、いつもより語尾が軽い。
「それは光栄だ。入学式のときの坪井はこの世の終わりみたいな顔をしていた」
「うん、あのときはそうだったね」
成瀬さんから排出された「やることガチャ」は当たりだった。わたしの生活を確実に彩り、わたしの体調まで救ってくれた。
「そうだ、成瀬さんにもなにか作るよ。食べに来ない?」
「それは願ってもない申し出だ」
成瀬さんは明日の夕方、わたしの部屋に来てくれることになった。母以外がうちに来るのははじめてだ。
「成瀬さんの好きな食べ物って何?」
「白いご飯だ」
「料理じゃないじゃん」
いつもは早炊きにするけれど、明日は標準コースでじっくり炊こうと思った。
翌日、成瀬さんは五限まであるというので、四限で終わったわたしはコレモで買い物をして一足早く家に帰った。
何を作るか迷ったけれど、練習の成果を見せるためにもハムエッグ丼は欠かせない。さらに豆腐の味噌汁と、いつも成瀬さんが生協食堂で食べているほうれん草のおひたしを作ることにした。
炊飯器を標準コースでセットして、一息つく。六時近くになってもカーテンの向こうはまだ昼間みたいに明るくて、いつのまにか日がのびているのを感じる。
この一ヶ月でわたしのキッチンは格段に充実した。調味料を買いそろえ、計量スプーンやピーラーも調達し、簡単なものなら一通り作れるようになっている。早田くんの幻を追い続けていた頃がもはや懐かしい。
早田くんってどんな顔してたっけ。ふと写真を見たくなってスマホのカメラロールをスクロールしてみると、どうも様子がおかしい。いつもあったはずの場所にあの写真がない。何かのバグかもしれないと写真の並び替えをしてみたものの結果は変わらず、高校時代の写真が断片的に消えている。
心臓がずきずきして、手が震えはじめた。もはやハムエッグ丼なんて作っている場合ではない。カメラロールの写真が突然消えたときにはどうしたらいいか検索して、複数の解説サイトを見比べる。
そんなことをしているうちにインターフォンが鳴って、モニターには真顔で手を振る成瀬さんが映し出された。
「はーい」
心ここにあらずで返事する。自分で誘ったくせに、なんでいま来るんだろうと疎ましく感じてしまった。
早田くんのことはもうだいぶ落ち着いていたはずだ。写真が消えただけでこんなに動揺するなんて、自分が情けなくなってくる。
「一人暮らしの部屋ってこんな感じなんだな」
入ってきた成瀬さんは興味深そうに部屋の中を見渡した。
「成瀬さんはスマホに詳しい?」
「いや、スマホは三月に持ったばかりだからわからない」
「そうなの?」
「ああ。マップのナビの機能も今日はじめて使った。いつも紙の地図を持ち歩いていたのだが、スマホだと現在地が自動的にわかるから便利だな」
あまりにのんきな感想にイライラしてきた。
「スマホに入ってた大事な写真が消えちゃったの」
「それは大変だ」
成瀬さんが表情を変えずに言うのと同時に、床に置いた炊飯器がぼこぼこいいはじめた。本当ならもう今ぐらいにはほうれん草をゆでて、味噌汁に取り掛かっておきたかった。
「落ち着いて作業したらいい。料理はわたしが代わりに作ろう」
成瀬さんは荷物を床に置き、キッチンに向かおうとする。どうしてこの人は何事にも迷いがないんだろう。胸の奥から熱いものがせり上がってくる。
「成瀬さんにわたしの気持ちなんてわかるわけない!」
わたしは思わず大声を上げた。完全な八つ当たりだってわかっているけれど、止められなかった。
「他人の気持ちがわかる人間がいたらエスパーだ」
冗談で言ったのかもしれないけれど、ひとつも笑えない。いや、成瀬さんのことだから本気で言ってるのかもしれない。こんな人と仲良くできる人っているんだろうか。またひどいことを言ってしまいそうになり、成瀬さんから顔を背ける。
「しかし、坪井はまだ失恋から立ち直れていないのだと推測できる。わたしだって大事な人間と離れ離れになるつらさは知っているからな」
口調に切実さが混じっているのを感じて、わたしは成瀬さんに向き直った。
「どういうこと?」
「小さい頃からそばにいてくれた幼なじみが、この春東京に引っ越したんだ」
成瀬さんは視線を遠くに向けて言った。沈黙が下りた部屋に、炊飯器からごはんのにおいが漂う。
「そうなんだ……」
なんでも持っている成瀬さんでも、きっとその別れは苦しかったに違いない。本当に大事な人とそばにいられるのは奇跡だって、わたしが一番よく知っている。
「近所で似た後ろ姿を見てはっとしたあとに、ここにいるはずがないって認識する、あの瞬間が寂しいな」
成瀬さんが照れたようにふっと息を吐く。
「めっちゃ感情揺れてんじゃん」
「島崎のことになると弱いんだ」
「しまざき」の響きが優しくて、特別な存在だったことがうかがい知れる。成瀬さんにもそういう相手がいたんだって思ったら、急に親近感が湧いてきた。
結局わたしの計画はぐだぐだで、ハムエッグ丼しか作れなかった。それでも成瀬さんは「この黄身の感じがちょうどいい」とか「ハムの火の通し方にセンスを感じる」などと褒めてくれた。
「それに、この米の炊き具合も抜群だ」
「ありがとう」
成瀬さんが米を嚙み締めている間に、早田くんの写真は無事復元できた。クラウドとの同期がうまくいっていなかったとかなんとかで、スマホを再起動してログインし直したらあっさり画像が戻ってきた。
「ほら、この写真」
戻ってきたのがうれしくて、全然興味がないであろう成瀬さんにも写真を見せる。
「坪井が幸せそうだ」
成瀬さんの言うとおり、わたしがこんなに笑顔の写真はほかにない。早田くんとばらばらになる未来なんて見えてなくて、京大を目指してまっすぐ勉強していた。このときのわたしは確実に幸せだった。
「そうだ、わたしもこの表情をまねしよう」
成瀬さんが写真を見ながら不自然なほどに口角を上げてダブルピースする。
「いや、わたしそんな顔してる?」
あまりに似てなくて、声を上げて笑ったら涙があふれてきた。
「わたしは、早田くんがいたから生きてこられたの」
こんなことを言ったらみんな大げさだって笑うだろう。だけど、わたしにとってはまぎれもない事実だ。わたしの歩いてきた道を振り返れば、どこにだって早田くんとの思い出が残っている。
成瀬さんはピースをやめ、笑みを残した穏やかな顔でうなずく。
「きっと、それが彼の役目だったんだ」
「役目」
わたしは思わず声に出していた。こっちに向かって静かに手を振り、脇道にそれていく早田くんの姿が見える。投げ出したのでも逃げ出したのでもなく、役目を終えた。そう思ったら早田くんへの感謝がこみ上げてくる。せめてひとこと「ありがとう」と伝えて別れたかった。
「まだまだ人生長いんだ。いつか再びめぐり逢うこともある」
わたしの思いを見透かしたように成瀬さんが言う。
「そうかなぁ」
ティッシュで涙を拭いていると、突然成瀬さんが荷物を持って立ち上がった。
「そういえば行きたい場所があったんだ。坪井、ついてきてくれるか」
「えっ?」
鍵とスマホだけ持って外に出ると、すっかり日が落ちていた。早足で歩く成瀬さんに導かれるまま出町柳駅を越え、鴨川デルタにたどり着く。橋や道からながめたことはあったけれど、降り立つのははじめてだ。
「いつも明るいうちに帰ってしまうから、夜の鴨川に来てみたかったんだ」
これも京都を見て回る一環なのだろう。鴨川デルタは夜でもまわりの灯りに照らされて、そこそこ明るい。サークルの新歓で来ているような男女がわいわい騒いでいる。
「坪井はサークルには入らないのか」
「出遅れちゃった。成瀬さんは?」
「わたしもやりたいことがいろいろあって、手が回らないんだ」
ふと成瀬さんに目を向けると、頭の上に何か光るものが見えた。
「えっ、蛍じゃない?」
「うわっ、ほんとだ」
成瀬さんが珍しく取り乱した声を出した。蛍らしきものはふわふわ浮かんで下流の方へと消えていく。
「今日はわたしの誕生日なんだ」
衝撃の新事実である。
「えっ、そんな日にここにいていいの?」
「別に誕生日だからといって祝う必要はない」
あぁ、たしかにそうだ。入学おめでとうと言われるのがあんなに嫌だったくせに、誕生日は祝うものだと思いこんでしまっている。
「誕生日に蛍が見られるなんて、来た甲斐があったな」
成瀬さんの声が弾んでいて、家に呼んだわたしもうれしくなる。
「ごはん、リベンジするからまた食べにきてよ」
今日はうまくいかなかったけれど、肉汁たっぷりハンバーグとか、ふわとろオムライスとか、挑戦してみたいメニューはたくさんある。
「ああ。いつでも誘ってくれ」
わたしは黙って川面に目をやる。幻の早田くんを追いかけてたどり着いた京都。今は何の思い入れもないけれど、それならこれから作ればいい。
「わたしも成瀬と一緒に京都をめぐってもいい?」
「もちろんだ」
うなずく成瀬の背後に白い月が浮かんでいる。その光を頼りにどこまでも歩いていける、そんな気がした。