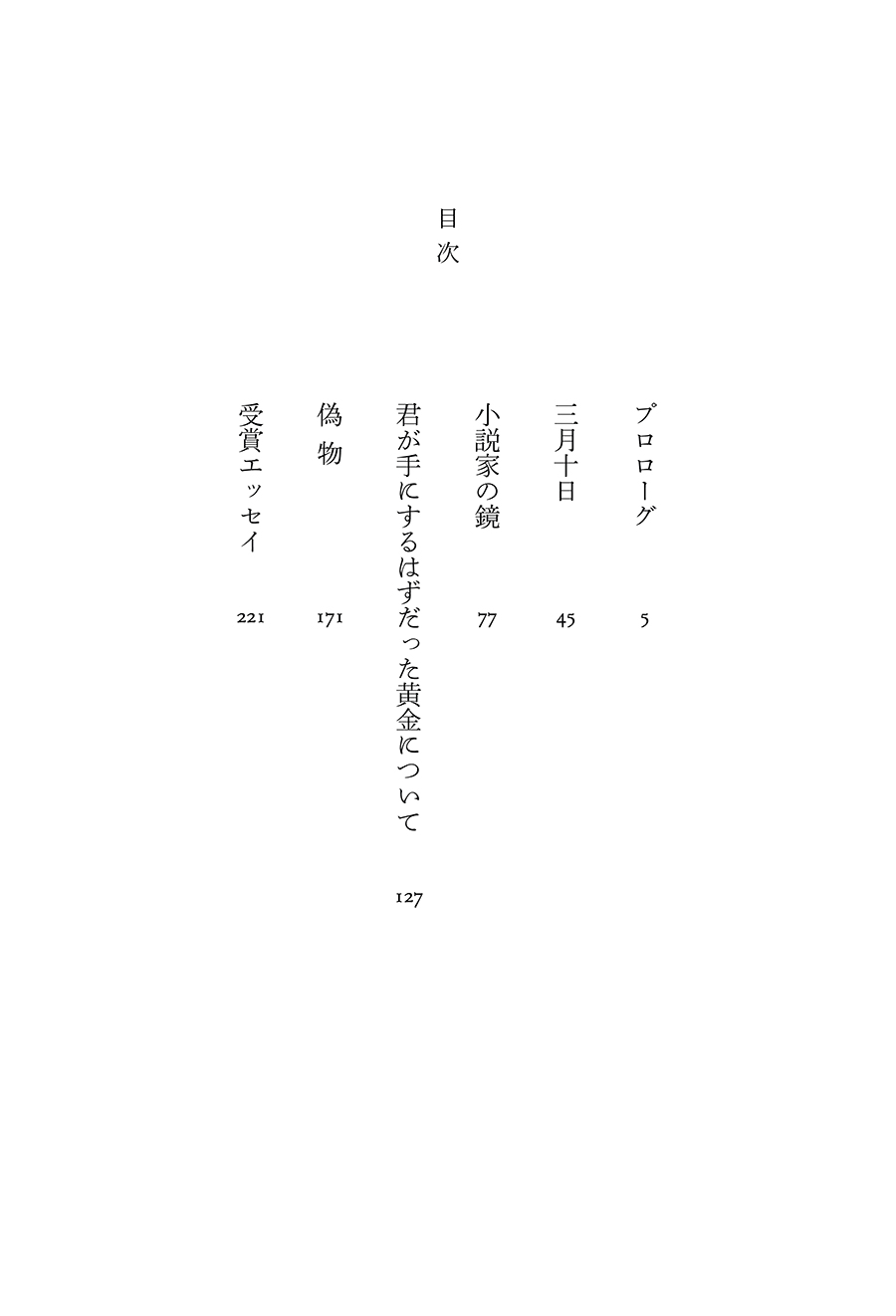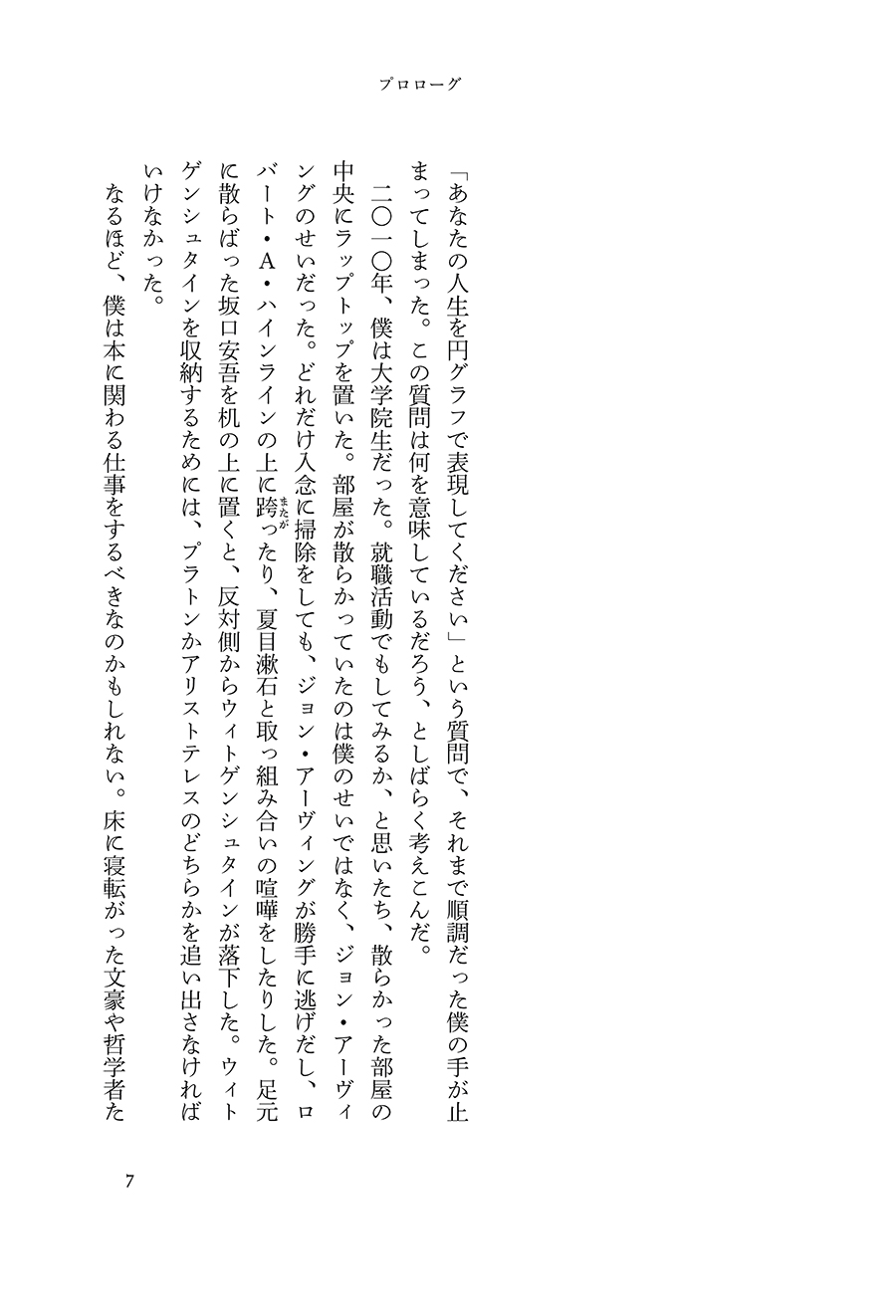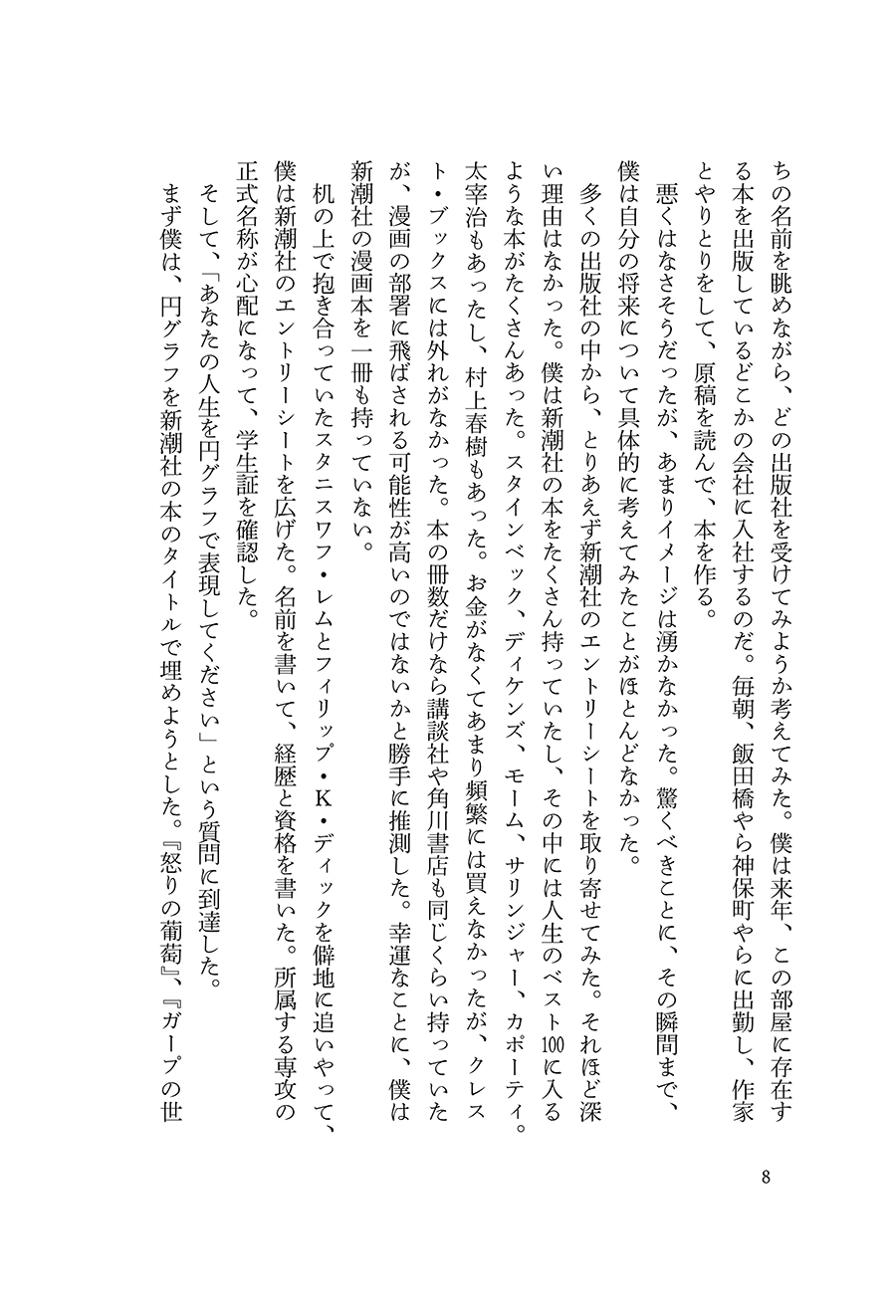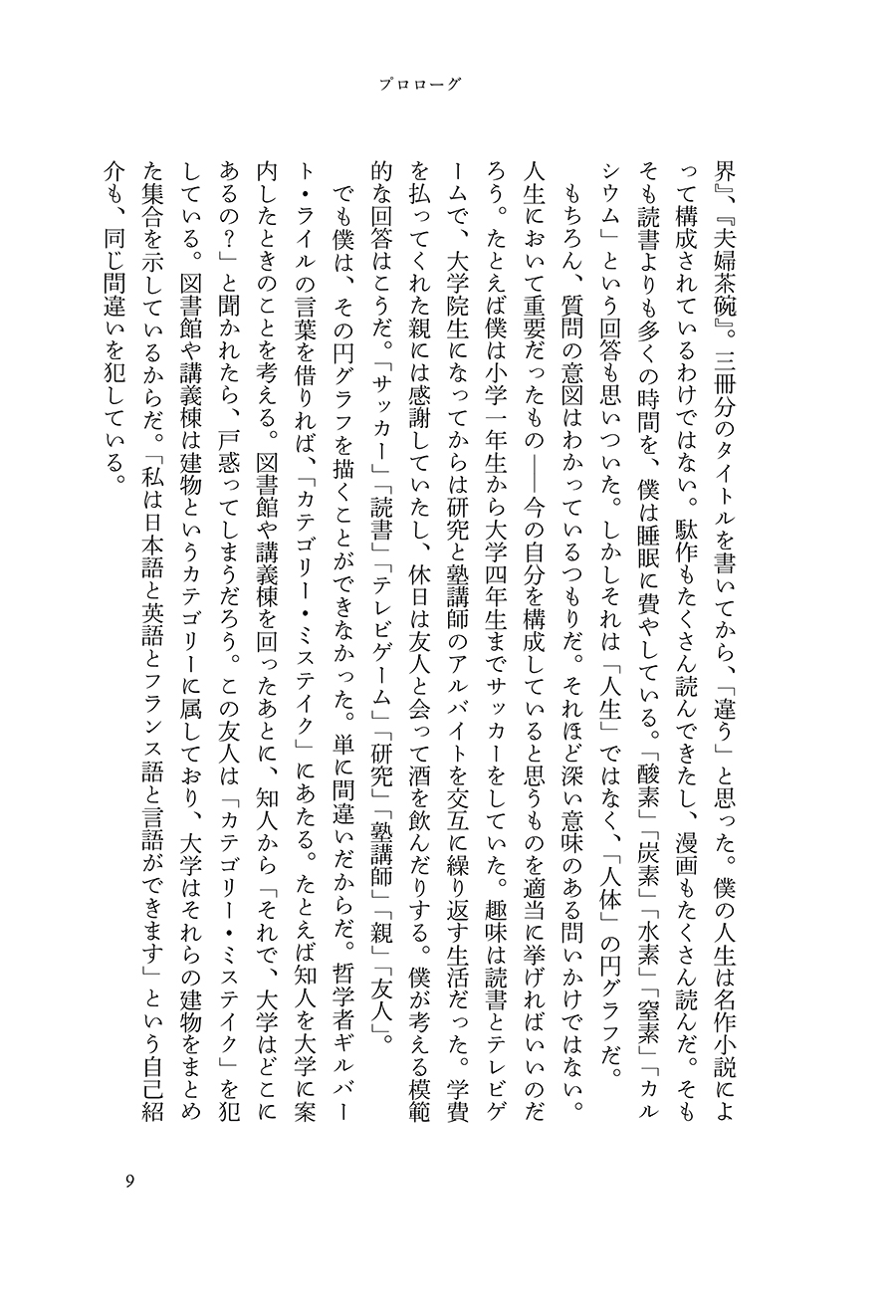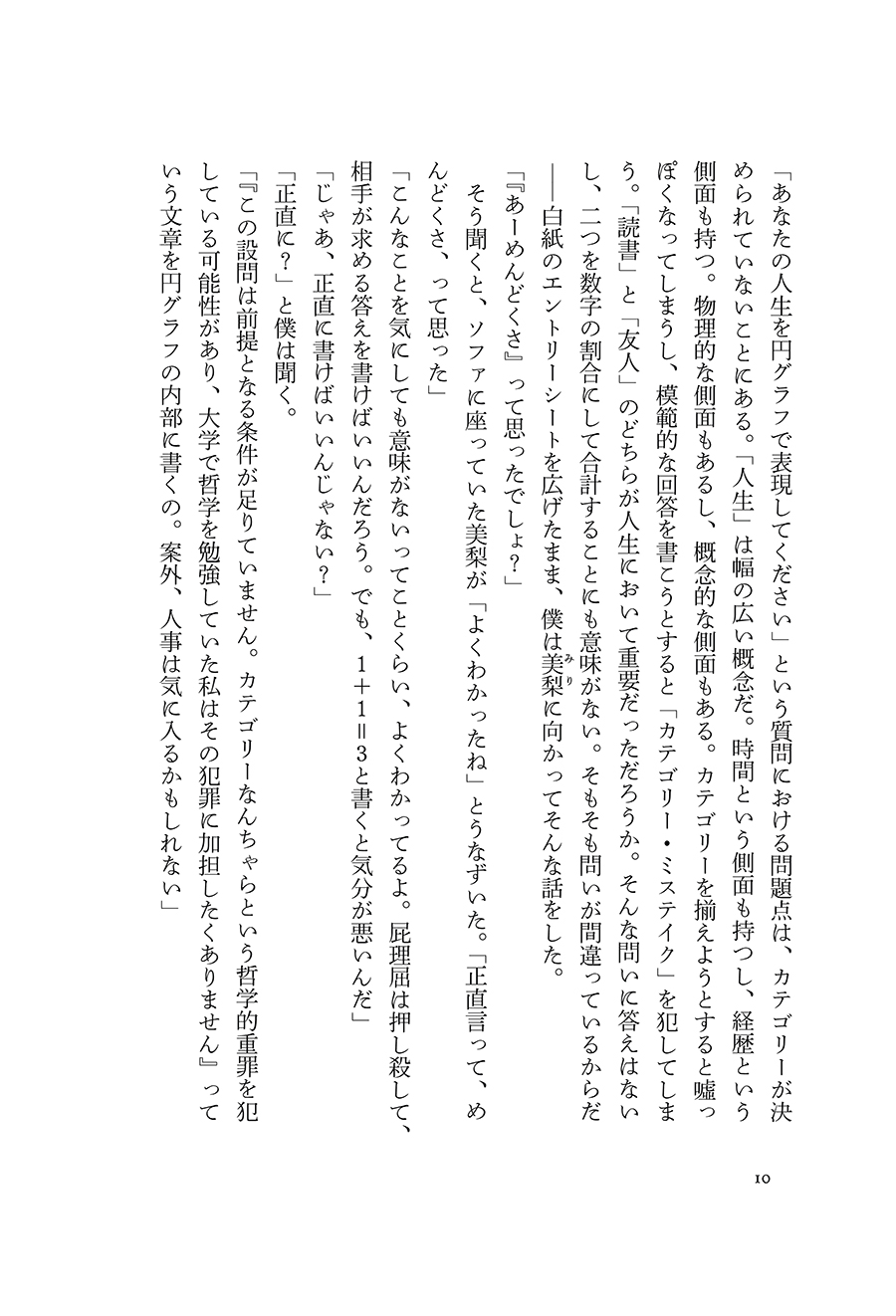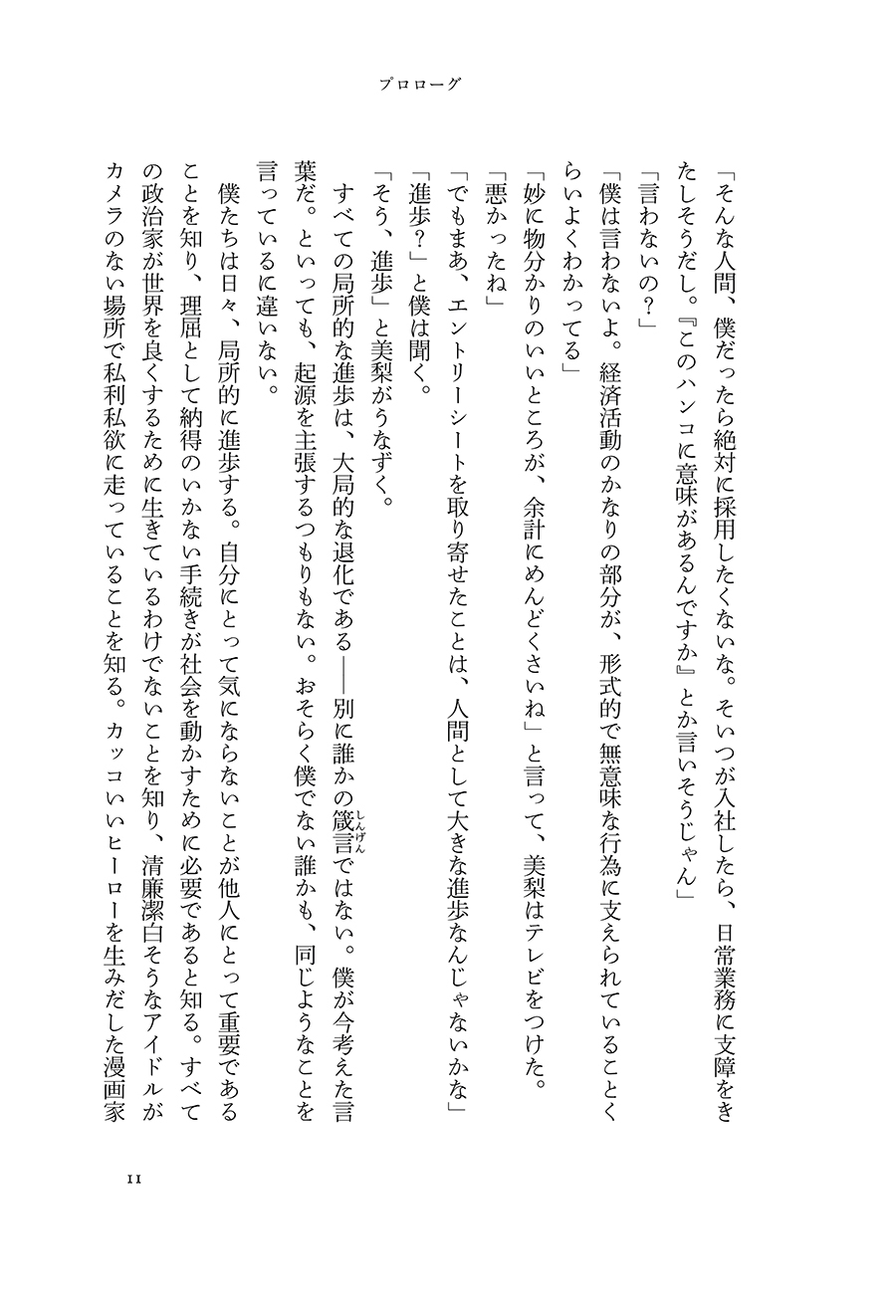プロローグ
「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問で、それまで順調だった僕の手が止まってしまった。この質問は何を意味しているだろう、としばらく考えこんだ。
二〇一〇年、僕は大学院生だった。就職活動でもしてみるか、と思いたち、散らかった部屋の中央にラップトップを置いた。部屋が散らかっていたのは僕のせいではなく、ジョン・アーヴィングのせいだった。どれだけ入念に掃除をしても、ジョン・アーヴィングが勝手に逃げだし、ロバート・A・ハインラインの上に跨ったり、夏目漱石と取っ組み合いの喧嘩をしたりした。足元に散らばった坂口安吾を机の上に置くと、反対側からウィトゲンシュタインが落下した。ウィトゲンシュタインを収納するためには、プラトンかアリストテレスのどちらかを追い出さなければいけなかった。
なるほど、僕は本に関わる仕事をするべきなのかもしれない。床に寝転がった文豪や哲学者たちの名前を眺めながら、どの出版社を受けてみようか考えてみた。僕は来年、この部屋に存在する本を出版しているどこかの会社に入社するのだ。毎朝、飯田橋やら神保町やらに出勤し、作家とやりとりをして、原稿を読んで、本を作る。
悪くはなさそうだったが、あまりイメージは湧かなかった。驚くべきことに、その瞬間まで、僕は自分の将来について具体的に考えてみたことがほとんどなかった。
多くの出版社の中から、とりあえず新潮社のエントリーシートを取り寄せてみた。それほど深い理由はなかった。僕は新潮社の本をたくさん持っていたし、その中には人生のベスト100に入るような本がたくさんあった。スタインベック、ディケンズ、モーム、サリンジャー、カポーティ。太宰治もあったし、村上春樹もあった。お金がなくてあまり頻繁には買えなかったが、クレスト・ブックスには外れがなかった。本の冊数だけなら講談社や角川書店も同じくらい持っていたが、漫画の部署に飛ばされる可能性が高いのではないかと勝手に推測した。幸運なことに、僕は新潮社の漫画本を一冊も持っていない。
机の上で抱き合っていたスタニスワフ・レムとフィリップ・K・ディックを僻地に追いやって、僕は新潮社のエントリーシートを広げた。名前を書いて、経歴と資格を書いた。所属する専攻の正式名称が心配になって、学生証を確認した。
そして、「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問に到達した。
まず僕は、円グラフを新潮社の本のタイトルで埋めようとした。『怒りの葡萄』、『ガープの世界』、『夫婦茶碗』。三冊分のタイトルを書いてから、「違う」と思った。僕の人生は名作小説によって構成されているわけではない。駄作もたくさん読んできたし、漫画もたくさん読んだ。そもそも読書よりも多くの時間を、僕は睡眠に費やしている。「酸素」「炭素」「水素」「窒素」「カルシウム」という回答も思いついた。しかしそれは「人生」ではなく、「人体」の円グラフだ。
もちろん、質問の意図はわかっているつもりだ。それほど深い意味のある問いかけではない。人生において重要だったもの――今の自分を構成していると思うものを適当に挙げればいいのだろう。たとえば僕は小学一年生から大学四年生までサッカーをしていた。趣味は読書とテレビゲームで、大学院生になってからは研究と塾講師のアルバイトを交互に繰り返す生活だった。学費を払ってくれた親には感謝していたし、休日は友人と会って酒を飲んだりする。僕が考える模範的な回答はこうだ。「サッカー」「読書」「テレビゲーム」「研究」「塾講師」「親」「友人」。
でも僕は、その円グラフを描くことができなかった。単に間違いだからだ。哲学者ギルバート・ライルの言葉を借りれば、「カテゴリー・ミステイク」にあたる。たとえば知人を大学に案内したときのことを考える。図書館や講義棟を回ったあとに、知人から「それで、大学はどこにあるの?」と聞かれたら、戸惑ってしまうだろう。この友人は「カテゴリー・ミステイク」を犯している。図書館や講義棟は建物というカテゴリーに属しており、大学はそれらの建物をまとめた集合を示しているからだ。「私は日本語と英語とフランス語と言語ができます」という自己紹介も、同じ間違いを犯している。
「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問における問題点は、カテゴリーが決められていないことにある。「人生」は幅の広い概念だ。時間という側面も持つし、経歴という側面も持つ。物理的な側面もあるし、概念的な側面もある。カテゴリーを揃えようとすると噓っぽくなってしまうし、模範的な回答を書こうとすると「カテゴリー・ミステイク」を犯してしまう。「読書」と「友人」のどちらが人生において重要だっただろうか。そんな問いに答えはないし、二つを数字の割合にして合計することにも意味がない。そもそも問いが間違っているからだ――白紙のエントリーシートを広げたまま、僕は美梨に向かってそんな話をした。
「『あーめんどくさ』って思ったでしょ?」
そう聞くと、ソファに座っていた美梨が「よくわかったね」とうなずいた。「正直言って、めんどくさ、って思った」
「こんなことを気にしても意味がないってことくらい、よくわかってるよ。屁理屈は押し殺して、相手が求める答えを書けばいいんだろう。でも、1+1=3と書くと気分が悪いんだ」
「じゃあ、正直に書けばいいんじゃない?」
「正直に?」と僕は聞く。
「『この設問は前提となる条件が足りていません。カテゴリーなんちゃらという哲学的重罪を犯している可能性があり、大学で哲学を勉強していた私はその犯罪に加担したくありません』っていう文章を円グラフの内部に書くの。案外、人事は気に入るかもしれない」
「そんな人間、僕だったら絶対に採用したくないな。そいつが入社したら、日常業務に支障をきたしそうだし。『このハンコに意味があるんですか』とか言いそうじゃん」
「言わないの?」
「僕は言わないよ。経済活動のかなりの部分が、形式的で無意味な行為に支えられていることくらいよくわかってる」
「妙に物分かりのいいところが、余計にめんどくさいね」と言って、美梨はテレビをつけた。
「悪かったね」
「でもまあ、エントリーシートを取り寄せたことは、人間として大きな進歩なんじゃないかな」
「進歩?」と僕は聞く。
「そう、進歩」と美梨がうなずく。
すべての局所的な進歩は、大局的な退化である――別に誰かの箴言ではない。僕が今考えた言葉だ。といっても、起源を主張するつもりもない。おそらく僕でない誰かも、同じようなことを言っているに違いない。
僕たちは日々、局所的に進歩する。自分にとって気にならないことが他人にとって重要であることを知り、理屈として納得のいかない手続きが社会を動かすために必要であると知る。すべての政治家が世界を良くするために生きているわけでないことを知り、清廉潔白そうなアイドルがカメラのない場所で私利私欲に走っていることを知る。カッコいいヒーローを生みだした漫画家はカッコいいヒーローではないと知り、慈善事業が税金対策として行われていることもあると知る。生きることとは、そういった不純さを受け入れ、その一部となり、他の大人たちと一緒に世界を汚すことだと知る。それでもなお、自分に何ができるかを探すしかないし、かといって何もできない人を責め立てても仕方がないと知る。
そういった知識を蓄えていくことは、たしかに局所的な進歩ではある。でも、結局のところ人間という不完全な存在が、社会という不完全なシステムを動かすために生みだされた必要悪や建前であり、必要ではあるけれども結局悪は悪で、噓は噓だ。僕たちは局所的な進歩の過程で悪と噓を内面化していく。それが大人になるということの一部なのは間違いないが、同時に人間としての退化でもある。僕は成長し、進歩して、これまで理解できなかったことが理解できるようになった。許せなかったことが許せるようになった。エントリーシートを取り寄せることができるようになった。その代わりに、いくつもの怒りや悲しみや喜びを失ってしまった。
僕にとって就職活動とは、人生を受け入れることを意味していた。社会という犯罪に加担することを意味していた。しかし、それでもやはり、僕たちは大人にならなければならない。
哲学者のバートランド・ラッセルは、あらゆる固有名が短縮された確定記述であると考えた。簡単に言えば、「名前とはさまざまな記述を束ねたものである」という主張だ。たとえば「アリストテレス」という固有名は「プラトンの弟子」「アレクサンダー大王の家庭教師」「人間の本性は知を愛することにある、と考えた人物」のような、いくつもの記述の束として存在している。そういった記述を無数に積み重ねることで、「アリストテレス」という人物を「アリストテレス」という言葉を使わずに特定することができる。
就職活動において僕は、自分の固有名をいくつもの記述に分解していく行為を強いられている。僕という人間と同義になるまで、僕の特徴を列挙していく。そうして生まれた大量の記述のうち、どれが「企業が求める人材」という要素と重なるかを検討する。
僕の人生は再構成を余儀なくされる。これまで並列していた記述に強弱が生まれ、「企業が求める人材」にそぐわない記述が、僕という人間から削ぎ落とされていく。
「『あーめんどくさ』って思ったでしょ?」
ソファでぼんやりとバラエティ番組を見ていた美梨に向かってそんな話をした。エントリーシートはもちろん白紙のままだった。
「いや、その通りだと思ったけど」
「え?」と僕は思わず聞き返す。
「いや、ちゃんと話を聞いてたわけじゃないからわかんないけど」と言って、美梨はテレビを消した。「社会が悪と噓だらけっていうのもそうだし、就職活動がその適性試験であることもそうだし。自分の特徴を会社に合わせて都合よく組み合わせるっていうのも、その通りじゃない?」
「意外な反応だね。テレビはいいの?」
「ああ、うん。別にそんなに面白くなかったし。少なくとも哲学の話の方が面白かった」
それから僕は、美梨に向かって分析哲学の話をした。ラッセルの話をして、クワインの話をして、クリプキの話をした。
「ラッセルさんによれば、私という人間が、『千葉県船橋市出身の女性』『中川敏也と中川加奈子の間に生まれた』『一九八六年五月二十一日に生まれた』『伊藤忠に勤めている』『さまぁ~ずとアンタッチャブルが好き』みたいに分解できるってこと?」
「そう。分解できるし、分解してできた記述を足し合わせたものと、中川美梨という固有名はイコールで結ばれると主張したわけ。でも、クリプキはそれが間違っていると考えた。たとえば、新たな歴史的史料が発掘されて、アリストテレスがアレクサンダー大王の家庭教師ではなかったことが判明したとする。ラッセルの記述理論が正しいとすると、少々困ったことになる。もし固有名が確定記述であれば、その確定記述に間違いがあったとき、アリストテレスという固有名自体が矛盾してしまうことになるからね。でもそれは直観に反する。仮にアレクサンダー大王の家庭教師でなかったとしても、アリストテレスはアリストテレスだ」
「なんとなくわかるような」
「クリプキはラッセルと違い、現実とは無数の可能世界のうちの一つにすぎないと考えた。ある可能世界では、アリストテレスはアレクサンダー大王を教えていなかったかもしれないし、美梨は伊藤忠に勤めていなかったかもしれない。人々はそういうシチュエーションを想像することができる」
「もし私が伊藤忠に勤めていなかったとしても、私という存在に矛盾が生じるわけではない」
「その通り。クリプキは、固有名には確定記述を超えた何かが存在すると考えた」
「何?」
「長くなるけど、時間は大丈夫なの?」と僕は時計を指さした。午前零時過ぎだった。
「ああ、明日も仕事だった」と言って、美梨は立ちあがった。「じゃあ、今度の楽しみにしておく」
「うん」
僕は彼女を代田橋駅まで送った。駅まで走らなかったせいで終電を逃してしまって、甲州街道でタクシーを捕まえ、彼女を乗せた。タクシーを見送ってから、近くの自販機で缶コーヒーを買い、すっかり寒くなった帰り道を一人で歩いた。
終電が行ってしまって開きっぱなしになった踏切を渡りながら、美梨の「今度の楽しみにしておく」という言葉を思い出した。僕は「今度の楽しみにしておく」が苦手だった。興味のある事柄を知ると、すぐに飽きるまで調べ尽くした。わからないことがあれば、わかったつもりになるまで他の話は一切頭に入らなかった。なんとなく読みはじめた漫画を夜通しで読み耽り、続きが気になって深夜も開いている書店まで行った。僕と美梨の一番の違いは、「今度の楽しみにしておく」ことができるかできないか、にあるのかもしれない。だから僕は、老後の生活を楽しみにしながら会社勤めをする、とか、週末を楽しみにして平日を過ごす、という考えがしっくりこない。今、この瞬間、僕は何かを我慢したくない。
美梨とは付き合って三年くらいになる。決して一目惚れではなかった。百目惚れですらなかった。そもそも彼女は僕の好みの見た目ではなかったし、同様に、僕も彼女の好みの見た目ではなかったはずだ。
最初に彼女の名前を知ったのは十三年前だった。当時の僕は小学五年生で、近所の小さな学習塾に通っていた。その学習塾は僕の家の近くと西船橋の二箇所にあって、僕は二つの校舎を合わせた定期テストでいつも一位を取っていた。五年生の途中で西船橋の教室に中川美梨が入ってきて、僕は初めて一位を逃した。悔しかった、というわけではない。当時の僕は、テストに一位以外の順位が存在することに対して純粋に驚いていた。それからはずっと彼女が一位で、僕が二位だった。次第に、僕はテストとは二位を取るものだと考えるようになった。
いろんな事情があって、僕は中学受験をしなかった。美梨も同じだった。どんな事情があったのか、あるいは別に事情があったわけでもないのか、一度も聞いたことはなかったけれど、とにかく彼女も中学受験をしなかった。そうして僕たちは高校生になり、同じ高校に進学した。
僕たちは教室でお互いの存在を認識すると、かつての塾の話で盛りあがり、すぐに仲良くなった――というようなことは起こらなかった。高校時代は一度も同じクラスになったことはなかったし、ほとんど喋ったこともなかった。高校二年生のときに、一度だけ文化祭の委員会で事務的な話をする機会があり、その流れで塾の話をした。「いつも一位だったよね?」と僕が聞くと、彼女は「そうだっけ?」と答えた。それだけだった。
僕はマクドナルドでアルバイトを始め、そこで知り合った他校の女の子と付き合ったけれど、高校三年生の八月に受験を理由にフラれた。逆に、美梨は部活を引退した野球部の四番と八月から付き合いはじめた。よく、予備校で二人を見た。坊主から解放された短い髪をワックスで固めた四番と、いつもと違ってやけに静かな中川美梨。二人はいつも自習室の隣同士に座り、バンプ・オブ・チキンのアルバムが入ったMDを片耳ずつ分け合いながら勉強していた。昼休みになると手を繫いで出ていって、手を繫いで自習室に戻ってきた。僕は最初から最後まで、机にかじりついて一人で勉強していた。そうして僕は東大に合格し、彼女は東大に落ちて早稲田に進学した(ちなみに、野球部の四番は浪人した)。
僕と美梨の関係は、知人以上、友人未満といったところだろうか。ミクシィという当時流行っていたSNSで、ぎりぎりマイミクの仲だった。彼女はときどき日記を書いていた。どこどこに旅行したとか、誰々と久しぶりに食事したとか、サークルの飲み会があったとか、そういうありふれた内容だった。僕は日記を書かず、読んだ本のリストを更新し続けていた。本の感想を書くこともなかった。ただひたすら、自分が読んだ本のリストを作っていた。
大学一年生のある日、美梨からダイレクトメッセージが届いた。彼女は「読書を趣味にしたいから、面白い本を貸してほしい」と言ってきた。僕が「どんなジャンルが読みたいの?」と聞くと、彼女は「読書家から一番趣味がいいと思われるジャンル」と答えた。
僕はしばらく考えた。「好きなサッカー選手は誰か?」と聞かれて「ロナウジーニョ」と答えると、たしかにミーハーだと思われるかもしれない。ロナウジーニョは素晴らしい選手だが、あまりにも有名すぎる。そこで「パベル・ネドベド」と答えたら、趣味が良さそうな気がする。
僕は正解に確信が持てないまま、ポール・オースターの『ムーン・パレス』を持って、SHIBUYA TSUTAYA内のスタバで彼女と会った。僕は疑問を二つぶつけた。一つは「どうして『読書家から一番趣味がいいと思われるジャンル』の本を読みたいのか」で、もう一つは「どうして僕から借りようと思ったのか」だった。
美梨は二つ目の質問には簡単に答えてくれた。「知り合いの中で、一番本を読んでそうだったから」らしい。一つ目の質問にはなかなか答えてくれなかったが、僕が「本を借りる目的がわからないと『ムーン・パレス』がふさわしい本かどうかわからない」と言うと、少しずつ真相を教えてくれた。気になっているサークルの先輩が読書家なので、話を合わせるために小説を読みたいと思ったが、趣味の悪い本の話をして幻滅されたくなかったから、だそうだ。
「その先輩が普段どんな本を読んでいるかわからないけど」と僕は言った。「『ムーン・パレス』を読んでいる人に幻滅するような男なら、そもそも付き合わない方がいい」
美梨は僕のその言葉に満足したようだった。帰り際、僕は彼女に「そういえば、野球部の四番とはどうなったの?」と聞いた。
「夏に振られたよ」と彼女は答えた。「今でもあんまり納得してないけど」
「なんで?」
「私と一緒にいると、勉強に集中できないんだって。受験の邪魔をしないように付き合ってたのに」
「なるほど、それは悲しいね」
「うん、悲しかった。ようやく立ち直ったところ」
僕は彼女に『ムーン・パレス』を渡し、そのまま解散した。それ以来僕たちは会わなかったし、連絡を取り合うこともなかった。
それから、僕たちの間には何もないまま一年が経った。
僕は相変わらず、読んだ本のリストを更新していた。リストが二百冊を超えたとき、僕は唐突に「自分はなんのためにこのリストを更新しているのだろうか」という実存的な問いを抱いてしまった。僕の友達に、読書が趣味の人間はいなかった。正確には、僕のように読書をしている人間は一人もいなかった。僕は一人で粛々と本を読み、そこで得た知識や感情を何かに活かすこともなく、ひたすら内側に溜めこんでいた。ミクシィに公開していた読書リストは、孤独に読書をしている僕が世界と接続している唯一の場所だった。しかしその場所だって、別に誰かが熱心に見てくれているわけでもない。
「僕はなんのために、こんなに本を読んでいるのだろう」
今にして思えばくだらない問いだが、当時の僕はかなり真剣だった。それくらい真剣に本を読んでいた(こういった感情を抱かなくなってしまったことも、ある種の進歩と退化だ)。
不安とも虚無ともとれる無能感の中で、僕は中川美梨に「『ムーン・パレス』を返してほしい」というダイレクトメッセージを送っていた。正直言って、貸した本を返してもらいたいという気持ちはなかった。もう一冊買った方が安いし早い。ただ、少なくとも彼女は、僕の読書リストを見ていた。僕は自分の読書経験を参照して『ムーン・パレス』を貸したのだ。今や、彼女は僕の読書が外の世界と繫がっている世界で唯一の証だった。
「忘れてた! ごめん、すぐに返す!」と彼女は返信してきた。「あと、『ムーン・パレス』、面白かった」
こうして僕たちは高田馬場のサンマルクで一年ぶりに会った。美梨は『ムーン・パレス』の感想を述べてから、オースターの他の小説も読んでしまったと言った。『ミスター・ヴァーティゴ』が一番だと言っていた。僕は『ムーン・パレス』がやはり一番だと言った。それもわかる、と言われた。
夕方になると、少しだけ勇気を出して夕食に誘った。彼女は「いいよ」とうなずいた。うろうろ歩いて見つけたガストで食事をした。僕たちはほとんど生まれて初めて、お互いについて話した。例の、読書好きの先輩への片想いは成就しなかったらしい。ドイツ語のクラスにオダギリジョーに少しだけ似ている人がいて、今はその人のことが気になっているという。彼の写真を見せてもらったが、どこがどう似ているのか一切理解できなかった。
僕は入学してすぐ付き合ったバイト先の女の子と別れたばかりだった。
「何が理由で別れたの?」と美梨に聞かれ、僕は「付き合う理由がなくなったから」と答えた。
「うわ、冷酷」と美梨は言った。
食後に美梨が「何か新しい本が読みたい」と言ったので、僕たちは書店へ向かった。本棚の前を歩きながらカート・ヴォネガット・ジュニアの『タイタンの妖女』を選び、彼女が購入するところを見届けた。携帯の電話番号を交換して、夜の十時ごろに僕たちは解散した。
それから美梨とは、一ヶ月に一度くらい会って食事をした。美梨に頼まれ、船橋の彼女の実家まで、良治くんという弟に勉強を教えにいったこともあった。良治くんは東大受験を控えていた。美梨のお母さんは関西弁の明るい人で、いつも晩御飯をご馳走してくれた。
「良治はどうなん? 見込みある? 遠慮しないで言って」
食事が終わったあと、美梨のお母さんにそう聞かれたとき、僕は「浪人すれば、確実に受かります」と答えた。「現役だと、私大は大丈夫ですが、東大は難しいかもしれません」
「やんなあ。私もそう思ってたわ。よりによって高三の夏に彼女作りよって。美梨と同じなんよ」
「でもまあ、長い目で見れば、人生において恋愛の方が大学受験より重要ですよ」
「小川くん、いいこと言うなあ」
冬が過ぎ、年が明け、春が来た。良治くんは東大に落ち、早稲田に進学した。美梨と同じだった。美梨はオダギリジョー似の男と付き合い、うまくいかずに三ヶ月で別れた。美梨の誕生日プレゼントとして、僕はライブチケットをあげた。NHKホールでくるりのライブを観てから、渋谷で食事をした。
その日をきっかけに、僕たちは月に二回くらい会うようになった。僕の誕生日も一緒に過ごした。表参道のいつもより少し高いレストランで、美梨は谷崎潤一郎の『瘋癲老人日記』の初版本をプレゼントしてくれた。僕は嬉しかったが、それ以上に「どうやってこのプレゼントを選んだのだろう」と気になった。それほど本に詳しくない人が選ぶにしては、渋すぎるチョイスだった。
美梨はなかなか教えてくれなかったけれど、執拗に粘ると最終的に白状した。
「前に、読書好きの先輩の話をしたよね?」と彼女が言った。
「うん。サークルの先輩でしょ。当時片想いしていた」
「そう。その人に選んでもらったの。『谷崎の初版本を渡されて喜ばない人とは付き合う価値がないよ』って言われた」
僕はどう応えるべきか少し迷ってから、「それはそうかもしれない」とうなずいた。
今にして思えば、その言葉が「告白」にあたるものだったのかもしれない。帰り道、初めて入った表参道ヒルズの中で、大学の友人と会った。友人は美梨を指さして「彼女?」と聞いてきた。僕は少し迷いながら「うん」と答えた。美梨は何も反論しなかった。
翌年、美梨は就職活動を本格的に始めた。大学院に進学する予定だった僕は、卒業論文の準備をしたり、好きな本を読んだりして過ごした。美梨は二つのメーカーとテレビ局と伊藤忠から内定をもらい、もっとも給料の高かった伊藤忠を選んだ。春からは社会人になって、森下で一人暮らしを始めた。彼女の実家と会社と僕の家を線で結んだとき、三角形のちょうど中心にあたる場所だったらしい。
休日にはよく二人で旅行をした。僕はいつも本を二冊持っていった。そのうちの一冊を美梨が選び、残った方を僕が読んだ。行きの電車や飛行機で読書をして、読み終わると交換した。年に何度か、彼女の実家へ一緒に行くこともあった。彼女のお父さんに有楽町へ呼びだされ、二人で酒を飲んだこともあった。
「君は、何かやりたいことがあるのか?」
かなり酒を飲んでから、美梨のお父さんはそう聞いてきた。美梨のお父さんは銀行員で、新卒からずっと同じ会社に勤め続けているらしい。僕はどう答えるべきか真剣に考えてみたけれど、しっくりくる答えを見つけることができなかった。
困ったときは正直に答えるべきである――これも誰かの箴言ではない。自分で考えたことだ。僕は正直に「あまり思いつきません」と答えた。
「じゃあ、やりたくないことはあるか?」
「それならたくさんあります」
「たとえば?」
通勤のために満員電車に乗るのは嫌だったし、無能な人間に偉そうな態度をとられるのも嫌だった。目覚ましで起きるのも嫌だったし、眠たいまま一日を過ごすのも嫌だった。お金のために噓をつくのも嫌だったし、誰かに気に入られるために持論を曲げるのも嫌だった。でも、それらの言葉を口に出すと、美梨のお父さんの人生を傷つけるかもしれないとも思った。目の前の相手は、僕がやりたくないことをやってお金を稼ぎ、二人の子どもを私立大学に通わせたのかもしれない。
「満員電車に乗りたくないです」
僕は慎重にそう答えた。僕は困っていたが、正直に答えるしかないと腹を括った。
「満員電車は最低だね」と美梨のお父さんは言った。「俺も大嫌いだ。他には?」
「無能な人間に偉そうな態度をとられるのも嫌です」
それを聞くと、美梨のお父さんは声を出して笑った。「それもそうだ。俺も自分が偉そうな態度をとってないか、気をつけないといけないね」
話の最後に、美梨のお父さんは「何があっても、電話口で怒鳴る人間と、猫舌の人間は信用してはいけない」と言った。
「なるほど」と僕はうなずいた。
こうして僕は就職について考えはじめた。
「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問は、おそらくその問いが設定された事情を超えて、僕にさまざまな問題を投げかけてきた。この問いに答えようと、僕は自分の人生を思い返した。一人で更新し続けた読書リストのことや、読書リストを見て僕に連絡した美梨のこと。
読書とは本質的に、とても孤独な作業だ。映画や演劇みたいに、誰かと同時に楽しむことはできない。最初から最後まで、たった一人で経験する。それに加えて、本は読者にかなりの能動性を要求する。目の前で何か行われていることを受けとればいい、というわけではない。読者は自分の意志で本に向きあい、自分の力で言葉を手に入れなければいけない。そんな拷問を、場合によっては数時間、十数時間も要求する。僕はときどき、本というものが、わがままな子どもや、面倒臭い恋人のように見える。
「僕だけを見て。私だけにずっと構って」
本が、そう喚いているように感じられるのだ。実に傲慢だと思う。
しかしその傲慢さのおかげで、僕たちは一冊の本と深い部分で接続することができる。誰かによって書かれたテキストと、たった一人の孤独な読者。二人きりの時間をたっぷり過ごしたからこそ、可能になる繫がりだ。
僕は今、就職活動をしている。他人に伝わる言葉で、可能な限り僕という人間を表現しなければならない。しかし、読書という行為の本質的な孤独さと、読書が僕たちに求める傲慢さのせいで、適切な言葉が出てこない。適切な円グラフを描くことができない。
エントリーシートのために、僕は僕という人間を記述しようとする。元サッカー部員で、読書が好き。しかしそれではまだ足りない。まだ、僕という人間を表現しきれていない。千葉県千葉市出身で、『H2』を二十回くらい読んでいて、映画『グッドフェローズ』を四回観ている。それでもまだ足りない。ラッセルの記述理論によれば、そうやって僕の特徴を挙げ続けると、いつかは僕という人間の固有名と同義になるという。それに対してクリプキは、どれだけ記述を続けても、固有名と同義にはならないと主張した。
クリプキは「名前」を「固定指示子」と呼んだ。「固定指示子」とは、あらゆる可能世界において、その「名前」が不変なものであると固定する機能を持ったものだ。僕が『H2』を読んでいなくても、僕は僕のままだ。僕という固有名は形而上学的に同一だ、とクリプキは指摘する。
「出た、形而上学」と美梨が言う。
僕たちは城崎温泉へ向かう特急の車内にいる。美梨が忙しくなったこともあり、旅行の回数はずいぶん減った。今回の旅行は久しぶりだった。
「形而上学の話題を出したのは僕じゃなくて、クリプキだよ」
「私は哲学に詳しいわけでもないけど、クリプキさんの言ってることは正しいと思う」
「どういう点において?」
「固有名には、記述で回収できない何かがあるっていう点。私という人間を、なんらかの記述で完全に説明できるとは思えない」
「つまり、対象の性質によって名前が決まるわけではなく、名付けそのものが名前の本質だという立場だね」
「自分がその立場に属するのかはわかんないけど」
「名前の本質を担保しているのは、名前が付けられてからその名前を共有してきた社会の因果的連鎖ということになる。言い換えると、言語や知識は個人の頭の中にはなく、共同体によって決定されるということだ」
「ねえ、哲学者ってなんでそんなに極端なの?」
「突き詰めて考える必要があるからだよ。クリプキの名指しに関する議論には、さまざまな批判があった。言語が本質的に外在的であるという主張も、いろいろな哲学者からかなり攻撃された」
「よくわかんないけど、簡単じゃないんだね」
「そう。簡単じゃない。直観的に正しそうなことを言うと、突き詰めて考えたときに矛盾が発生する。哲学者は何千年もそんなことを繰り返している」
僕は旅行鞄から二冊の本を出した。ケリー・リンクの『マジック・フォー・ビギナーズ』と、志賀直哉の『小僧の神様・城の崎にて』だ。
美梨は本を選ぶ前に「もう少し寝る」と言った。まだ仕事の疲れがとれていないようだった。結局、美梨は城崎温泉に到着するまでずっと寝ていたし、帰りの電車でもずっと寝ていた。僕は一人で二冊とも読んだ。
僕は「あなたの人生を円グラフで表現してください」という質問を飛ばして、他の項目を埋めることにした。志望する部署のことや、最近気になったニュースなどを書いていく。思ったよりすんなり埋まっていった。
文章を書いている間、僕は常に孤独だった。そこに他人が介在する余地はなく、世界は僕と紙とペンだけによって構成されている。読書という行為が本質的に孤独であるならば、本を執筆するという行為もまた、本質的に孤独だ。本は多くの場合、一人の人間によって書かれ、一人の人間によって読まれる。その一対一の関係性の中に、なんらかの奇跡が宿る。
僕は本棚を見る。数々の文豪の名前がある。床にも、同じくらいの数の文豪が散らばっている。すべての文豪も、この孤独の中で執筆作業をしたはずだ。彼らが有名だったかどうか、彼らが金持ちだったかどうかは関係ない。ディケンズも僕も同じだ。文章を書いている間は、誰であれ同じことをしている。そこには書き手と紙とペンしか存在しない。読者も同じだ。読書をしている間は、時代や国も超えて、貧富の差も超えて、本と読者だけが存在している。
誰かが本を書き、誰かが本を読む。もちろん、両者の間には多くの人間が関与する。編集者や出版社がいて、取次や書店がいる。でも、その始まりと終わりは究極的に孤独で、究極的に公平だった。だからこそ、僕は本を読んでいた。孤独で構わない。そういう人間がこの世界にいることを、誰にも知られなくても構わないと思っていた。そうやって、いろんな物語を内側に溜めこんできた。
僕はクリプキのことを思い出す。固有名には、記述の束では回収できない剰余が存在するらしい。本とはつまり、記述の束だ。豊かな世界を、言葉に閉じこめる作業だ。「よく晴れた春の朝にカーテンを開けたときの陽光」という文章は、よく晴れた春の朝にカーテンを開けたときの、本物の陽光ではない。どれだけ努力しても、本物の陽光には敵わない。
クリプキの主張を置き換えてみる。本物の世界には、小説では回収できない剰余が存在する。でも、と僕は反論したくなる。小説には、本物の世界では味わうことのできない奇跡が存在する。いつもその奇跡に出会うとは言えないが、特別な本に出会ったときは、言語で説明できない類の感動をおぼえる。百パーセント言語によって構成された本という物体が、どうして言語を超えることがあるのだろうか――少なくとも、言語を超えたような錯覚を得ることができるのは、どうしてだろうか。
その秘密はきっと、読書という行為の孤独さの中にある。
僕はエントリーシートを机の上に置いたまま立ちあがった。
ソファに美梨はいない。本当なら今日も一緒に食事をするはずだったが、仕事で会社から出られなくなったらしい。僕は「あなたの人生を円グラフで表現してください」という文章を見つめる。
僕の人生には、円グラフで表現することのできない剰余がある。僕はエントリーシートの空白に向かって、そう反論する。
僕たちは岩本町にあるイタリアンレストランにいる。この前ドタキャンしたときの埋め合わせのつもりらしく、珍しく美梨が予約をした。注文した料理が来るまでの間、美梨はウーロン茶を飲みながら僕が書きかけたエントリーシートを読んでいた。
「悪くない。でも、ちょっと弱い」と彼女は言った。「小川くんの文章の弱点、教えてあげようか?」
「何?」と赤ワインを飲みながら僕は聞いた。
「文章がかならず『たぶん』や『もしかしたら』で始まって、『と思う』や『かもしれない』で終わるところ」
「たしかにそうかもしれない」
「出た。『かもしれない』」
「あ」と僕は声を出す。自分でも意識したことはなかったけれど、きっとそうなのだろう。
「断言恐怖症だね」と美梨が言う。
「先生、どうやったら治りますか?」と僕は聞く。
「十分な睡眠と、規則正しい生活、最低限の運動、バランスの取れた食事――では治らないですね」
「じゃあ、どうすればいいんですか? 治療する方法はないんですか?」
「あなたは、どうして自分が断言恐怖症にかかってしまったと思いますか?」
「季節の変わり目に、お腹を出したまま寝てしまったからですか?」
「違います」と美梨が首を振る。「真実を話そうとしすぎなのです」
「真実を話すことは悪いことですか?」
「悪いことではありませんが、就職はできません」
「どうやったら就職できますか?」
「小川さんの趣味を活かせばいいのではないでしょうか」
「趣味、ですか?」
「小説です。これまでたくさん読んできたでしょう。エントリーシートに小説を書けばいいのです。就職活動はフィクションです。あなたはフィクションの登場人物です。話が面白ければ、別に噓でもいいのです。真実を書こうとする必要はありません」
「中川先生、たいへん勉強になります」
「それでは練習をしてみましょう」
「練習?」
「何か噓を言ってみてください」
「ミッキーマウスはネズミ年に生まれた」
僕はそう口にする。
「それは本当に噓ですか?」と美梨が聞く。
「調べたことはありませんが、十二分の十一の確率で噓です」と僕は言う。
「その調子」と美梨が言う。
僕は生まれて初めて、小説を書こうと試みる。主人公は就活を控えた大学院生だ。新代田と代田橋の中間にある月七万円のワンルームマンションに住んでいて、アルバイトと奨学金で生活している。両親はどちらも健在で、金持ちではないけれど貧乏でもない。付き合って三年の、商社に勤める彼女がいる。本を読むのが好きだという理由で、出版社を受けようとしている。
小説の主人公にするには面白みに欠ける人間だ、と僕は思う。葛藤がないし、わかりやすい屈折もない。これでは読者の共感が得られない。
この主人公の最終的な目標は、就職することにある。物語を成立させるためには、主人公には何かが欠けていて、就職することが必然的にその欠損を満たさなければいけない。しかし、この主人公は「就職する」という動機に欠けている。貧しい実家を支える必要もないし、多額の借金を返さなければならないわけでもない。偉くなって誰かを見返したいと願っているわけでもないし、実存的な不能感に晒されているわけでもない。
本が好きだから、出版社を受けようと思いました――オーケー、それはわかった。でも君は、そもそもどうして就職しようと思ったんだ? 本が好きなら、ただ本を読めばいいだろう。君がどうして就職したいと考えているのか、その理由はなんなのか、しっかり説明してくれよ。そうでないと、物語が生まれないじゃないか。
そもそも僕はどうして就職をしようとしているのだろうか。僕は自分に問いかける。
金のためだろうか。もちろん生きていく上で金は必要だ。だが、就職は金を稼ぐことの十分条件ではあるけれど、必要条件ではない。別に企業に就職をしなくても、金を稼ぐことならできる。事実として、僕は週四回の塾講師のバイトで、大卒の初任給と同程度の金を稼いでいる。
親のためだろうか。もちろん僕が就職すれば親は喜ぶだろう。親が喜べば、もちろん僕も嬉しい。でも別に、僕は親を喜ばせるために生きているわけではない。
なんのためなんだろう、と僕は腕を組む。エントリーシートに小説を書くため、僕は真剣に考える。
翌日、僕はスーツを着てホワイトボードの前に立っている。二十一人の生徒が、僕の授業を聞くためにこちらを見ている。僕は授業の冒頭で、先週出した仮定法過去に関する宿題を集める。それぞれの列ごとに宿題のプリントが重ねられていく。僕はそれらを集めて枚数を確認する。二十一枚ある。つまり、生徒全員が宿題を提出したということだ。
「今、僕の気持ちを率直に述べていいですか?」と僕は生徒たちに問いかける。何人かの生徒がうなずき、残りの生徒は少し戸惑っている。
「驚いています」と僕は口にする。教室内に、少しだけ重い空気が漂う。生徒たちが、今からなんらかの理由で怒られるのではないか、と警戒しているからだろう。普段、僕は授業に関係のない話をあまりしない。
「なんと、二十一人全員が宿題を提出しました。これは驚くべきことです」
だって僕は自分が学生のころ、記憶の限り、一度も宿題を提出したことがないからです――そう続けそうになって我慢した。塾講師として、適切な言葉ではない。
「早乙女くん、どうして宿題をやろうと思いましたか?」
僕は最前列に座っていた男の子に聞く。サッカー部のフォワードで、父親が不動産会社の役員をしている生徒だった。
「先生から宿題が出されたからです」と早乙女くんが答える。
「たしかに僕は宿題を出しました。でも、宿題をやらないという選択肢もあったはずです」
「宿題はやるべきだと思います」
そう言ってから、早乙女くんは困惑した表情を浮かべている。僕に責められていると感じているのだろうか。さすがに、宿題をやってきた生徒に対し、「宿題をやった動機に問題がある」などと怒るわけにもいかない。
「いい心がけだと思います」と僕は口にする。「では、真中さんはどうして宿題をやってきたのですか?」
別の生徒に話を振る。早乙女くんが安堵したような表情を浮かべている様子が視界の端に映る。真中さんは近所の女子高に通っている女の子で、小学校までは北海道に住んでいた。
「志望校に合格するためです」と真中さんが答える。まっすぐこちらを見ている。
「志望校に合格するのは、誰のためですか?」
僕は少し意地悪な質問をする。真中さんは少し考えてから「自分のためです」と答える。
「いい心がけだと思います」と言って、僕は授業を始める。生徒たちは、しばらく啞然としている。
宿題とは、自分のためにやるものである――真中さんの言葉だ。
僕はその言葉を置き換える。就活とは、自分のためにやるものである。
僕はラップトップを開き、自分という人間の記述を可能な限り列挙していった。ひとつひとつの記述を検討し、就職の動機となる根拠を探した。なかなか見つからなかったので、僕は記述自体に手を加えることにした。元サッカー部という設定を、元文芸部という設定に変えてみた。それだけで、物語が広がったような感覚があった。元文芸部の僕は、学生時代に同人誌を出版したことがあった。一から企画を考えた。締め切りを守ろうとしない部員に発破をかけ、徹夜で校正作業をした。印刷所とやりとりをして、なんとか文化祭の当日に間に合わせた。当日売り切ることができなかった同人誌の在庫を解消するために、さまざまなPR戦略を立てた。結局、そのときの戦略はうまくいかず、今でも家には同人誌の在庫が残っている。僕が出版社を受けるのは、この経験が元になっている。いろんな人と関わりながら、本という一つの作品を作り、多くの読者に届ける。その喜びを、もっと深い部分で感じたい。
月並みな話かもしれないが、筋は通っている。主人公には明確な動機があって、それを満たしたいと思っている。彼のような人間こそ、出版社に就職するべきだろう。
そこで僕は気がつく。この世界の僕には就職する動機がないかもしれないが、可能世界の僕には動機がある。可能世界の僕の動機を集めていけば、何か答えが見えるのではないか。
僕は自分の出身地を変えてみる。家庭環境を変え、年齢を変えてみる。趣味を変え、大学に通っていなかったことにする。性別を変えようと思ったところで、同時に名前も変える必要があることに気づく。
名前とは固定指示子だ、と言ったクリプキを思い出す。可能世界に散らばったさまざまな僕の可能性を束ねるものだ。僕は心の中でクリプキに許可を得て、自分の名前を捨てる。僕はアメリカ人女性のジェシカ・バートンという人物のことを考えている。ジェシカは結婚して夫もいるが、自分の平凡な生活に退屈しきっている。彼女は何かが起きて、世界が突然大きく変わることを心のどこかで祈っている。
僕はジェシカの人生について文章を書く。彼女がどこで生まれ、何が重要だと思って生きてきたか。何を信じ、何に裏切られたか。
その瞬間、僕は他の誰でもなく、自分のために文章を書いている。
真中さんの言葉を置き換える。文章とは、自分のために書くものである。
美梨と僕は、伊香保温泉にいる。
岩本町のイタリアンレストランで食事をしてから、かなり経っていた。
付き合いはじめて以来、こんなに会わなかったのはおそらく初めてだろう。彼女の仕事が忙しかったというのもあるが、基本的には僕のせいだった。
その間僕はずっと小説を書いていた。小説を書きはじめてから、どういうわけか美梨と会う気にならなくなっていた。もしかしたら、僕にとって小説を書くことと、美梨と会うことは、人生において同じ部分に存在しているのかもしれない。そんなことを考えた。だからこそ、うまく両立することができなかったのだ。
この旅行には、美梨の誕生日祝いという側面もあった。誕生日当日は、彼女の仕事のせいで一緒に過ごすことができなかった。旅館で食事をとり、すでに過ぎてしまった彼女の誕生日を祝った。美梨が以前から欲しがっていたボッテガ・ヴェネタの財布をプレゼントした。美梨は珍しく酒を飲んだ。ビールをグラス一杯飲んだだけで、新鮮な挽肉のように顔が真っ赤になっていた。
「一杯だけ飲めるようになったの」と彼女は言った。「ここ最近、飲み会ばっかで」
「無理しなくていいよ」
「一杯だけなら大丈夫。これ以上は飲まないけど」
僕と美梨は、完成することのないエントリーシートの話をした。美梨のアドバイスに従って、フィクションを書こうとしたんだ――僕はそう説明した。でも、僕という人間は、どうやらエントリーシートという物語の主人公に相応しくないみたいで。
「どうして?」と美梨が聞く。
「簡潔に言えば、動機がないんだ」と僕は答える。「僕は自分でも、自分がどうして就職しようとしているのか、満足に説明できない」
「それってたぶん――」
美梨は何かを言いかけて、「――やっぱなんでもない」と途中でやめる。
なんだよ、教えてよ、と言いかけて、美梨と目が合う。
目が合った瞬間、奇跡のような何かが降り注ぎ、僕は唐突に答えにたどり着く。そうか、君か、と僕は思う。そう、私だよ、と美梨も思っているに違いない。僕は目を伏せて、自分のグラスにビールを注ぐ。
僕は無意識のうちに、一人前の人間になろうとしている。もっと具体的に言うと、美梨と結婚するためには、きちんと就職しなければならないと思っている。だから僕は、就職しようとしている。
僕は不意に、泣きそうになってしまう。どうして泣きそうになったのか、自分でもまだよくわかっていない。
顔をあげると、美梨が泣いている。ビールのせいで顔が赤く、号泣しているように見えるけれど、たぶんそうではない。静かに、しっとりと泣いている。
「前に、小川くんが私のお父さんと二人で飲みにいったことがあるでしょ?」
美梨が洟をすすりながら言った。
「有楽町で」
「そう。あのあとお父さんと会ったとき、なんて言われたと思う?」
「想像もつかないな」
「『俺は美梨のことを世界一甘やかして育ててきたつもりだったが、世界二位だった』って。『もっと甘やかされて育ったやつがいた』って」
「それは褒め言葉なのかな」
「わかんない。たぶん褒めても、貶してもないと思う。どうしてだろう、そのことを思い出して、涙が止まらなくなって。別にお父さんが死んだわけでもないのに。今も毎朝元気に出勤してるのに」
僕の喉で、言葉が詰まっている。その言葉は、必死に外の世界へ出たがっていた。でも僕は、本能的に「出てはいけない」と命じている。一度外に飛びだせば、もう二度と同じ場所に戻ってくることができないような気がしていた。
「最近ずっと会えなかったじゃん?」と美梨が言う。僕は「うん」とうなずく。
「その間に、いろいろ考えたの。昔のこととか、将来のこととか」
「うん」と僕は繰り返す。
「完成しないエントリーシートのことも、少し考えた」
「何か妙案は浮かんだ?」
「浮かばなかった」と美梨は答えた。「いや、正確には違うかな。あの質問に、小川くんは答えるべきじゃないと思った。無理に埋める必要はないって」
「どっちにしろ、もうとっくに締め切りが過ぎちゃったけどね」
「知ってる」と美梨がうなずく。無理に笑おうとしているみたいに、ぎこちない表情をこちらに向ける。
「僕も――」と言いかけて、喉に詰まっていた言葉が飛びだすような感覚に陥る。「――僕もここ最近、いろんなことを考えた」
「どんなこと?」
「小説のこと」
「エントリーシートというフィクションのこと?」
「いや、そうじゃない」と僕は首を振る。「エントリーシートはすでに締め切られているし、何より僕という人間は小説に相応しくない。僕の人生には、心の躍る物語がないんだ」
「じゃあ、そうではない小説について考えていたの?」
「うん。初めは、僕という人間の記述を書き換えていった。クリプキ的に言えば、可能世界の僕について考えたんだ。でもそれじゃ物足りなくなって、僕は自分の名前を捨てた。まったく新しい人格を作りだして、その人格が世界と衝突する物語を考えた」
「なんとなく、そうじゃないかって気がしていた」
美梨の頰を伝った涙が、顎の先から机の上に落ちた。
「それで――」と言いかけた僕を、美梨が「――私に言わせて」と制した。
「うん」とうなずきながら、僕は自分がこれから何を言おうとしていたのか、自分でもよくわかっていなかったことに気づいた。
「私と一緒にいると、小説に集中できないんでしょ? 前にも同じようなことを言われたことがあるから、よくわかるの」
「野球部の四番に」
「そう」
それから、僕はなんと口にするべきか、必死になって言葉を探した。世界中を探しまわっても、何も見つからなかった。
「ごめん」と僕は口にした。「そうかもしれない」
翌日、僕たちは予定通りいくつかの温泉を回り、水沢うどんを食べてからレンタカーで東京へ帰った。多少のぎこちなさはあったけれど、悲愴感のようなものは出さないように気をつけていた。車中で何を話したかは、まったく覚えていない。ボーズ・オブ・カナダの同じアルバムが無限に繰り返されていた。高速を降りてから「家まで送ろうか」と僕は提案したけれど、美梨は「大丈夫」と言った。僕たちは新宿のレンタカー屋で解散した。最後に交わした言葉は「じゃあ」だった。
自宅に帰り、旅行鞄の中身を整理しながら、僕は一文字も読むことのなかったバルガス=リョサの『緑の家』と伊藤計劃の『ハーモニー』を手にとった。それでもやっぱり読むことができなくて、部屋にあった美梨の荷物を集めていった。いつかまとめて送ろうと思いながら、いつまでもできなかった。
こうして僕は小説を書いた。エントリーシートのときとは大きく違っていた。何もかも自分のせいだったけれど、少なくとも僕には欠損があり、その欠損を埋めるための動機があった。僕は小説を書かざるを得なかった。
新宿のレンタカー屋で解散してから六年後に、高校の同級生から「美梨が結婚した」という話を聞いた。相手はオダギリジョー似の男でも、サークルの先輩でもなく、会社の同期らしい。僕はすでに小説家としてデビューしていた。お祝いの言葉を贈ろうか一時間くらい悩んで、結局何も贈らなかった。
部屋は以前よりも散らかっていた。毎日のように文豪の数が増えていたからだった。カズオ・イシグロが暴れまわり、チェーホフとカーヴァーが机の上からその様子を見守っている。
今でもときどき、僕は可能世界の自分について考える。無数の可能世界のどこかには、人生を円グラフで表現することに成功して、エントリーシートを提出した自分もいるだろう。
一度、新潮社の編集者に「新潮社を受けようとしたことがあったんです」と言ったことがある。編集者は「僕も昔、小説を書こうとしたことがありました」と答えた。
僕はエントリーシートを書くことに失敗して、小説家になった。編集者は小説を書くことに失敗して、新潮社に入社した。もしかしたら、僕たちが逆の立場になっていた可能世界も存在するのかもしれない。
しかし、それでも僕は僕だし、編集者は編集者なのだ。クリプキによれば、僕たちの名前には、記述では回収しきれない剰余がある。その剰余とは、さまざまな可能性を繫ぎとめる楔のことだ。僕たちは手に入れることのできなかった無数の可能世界に想いを巡らせながら、日々局所的に進歩し、大局的に退化して生きている。きっと、そうすることでしか生きていけないのだと思う。
「プロローグ」 了
続きは本書でお楽しみください。