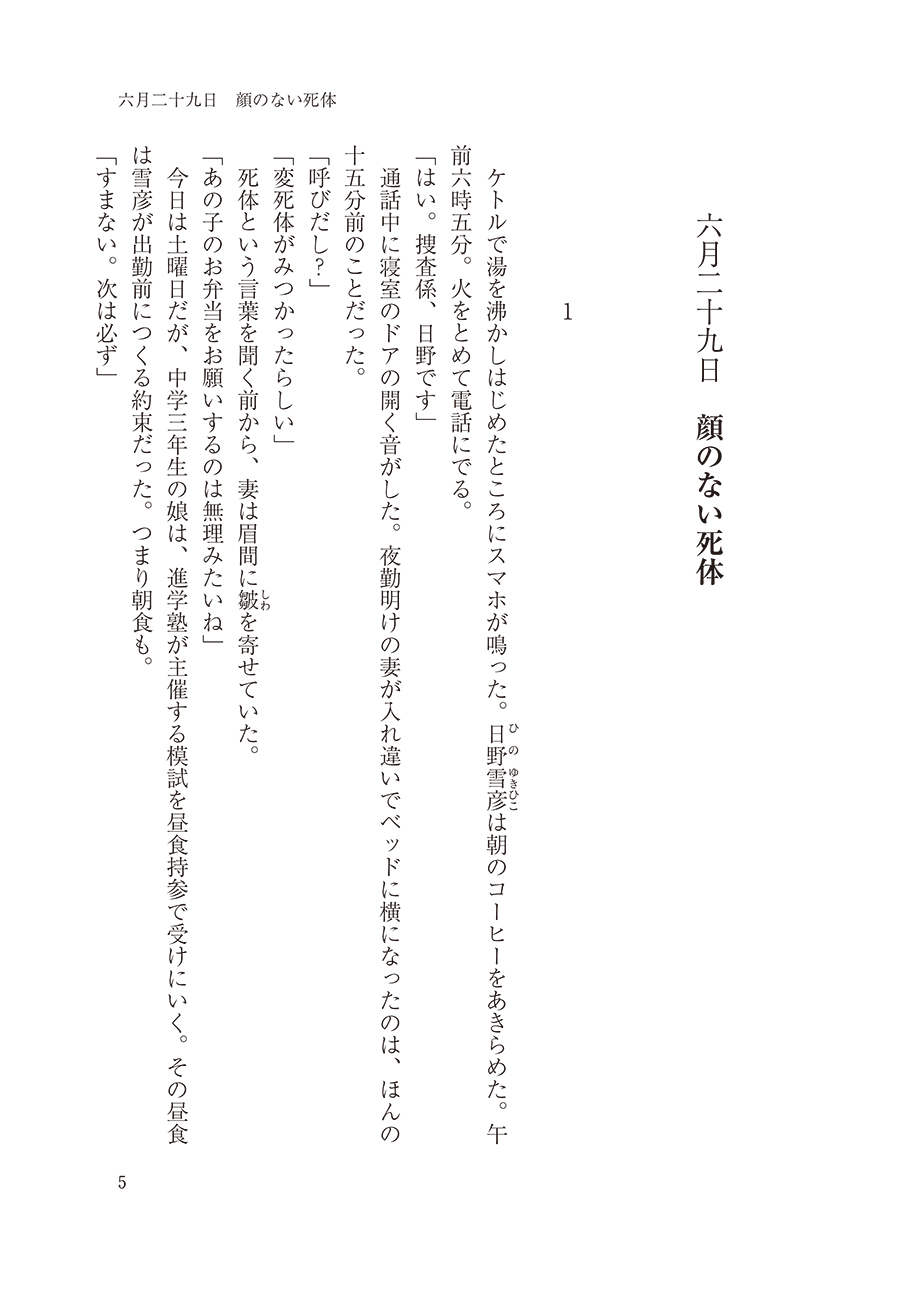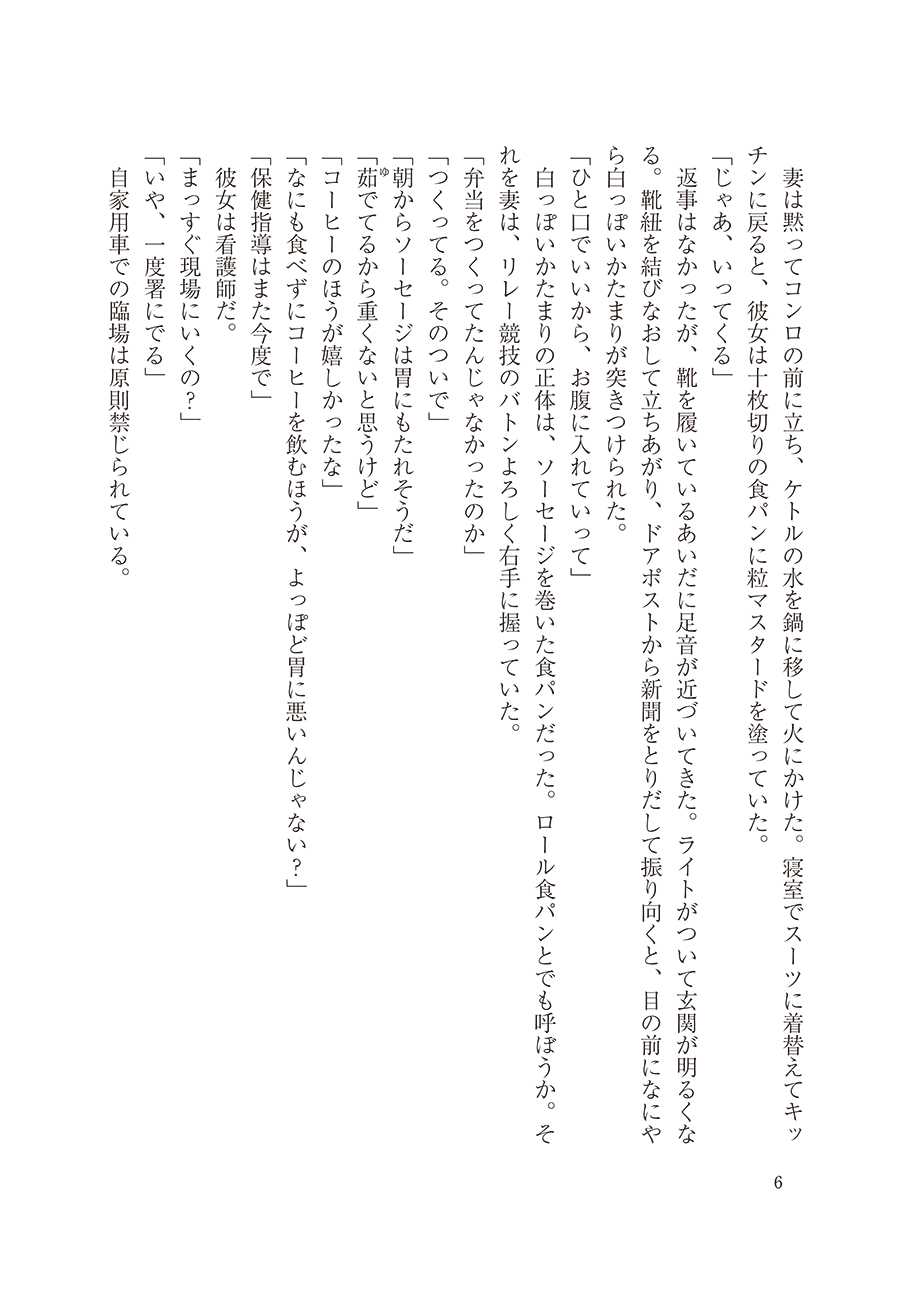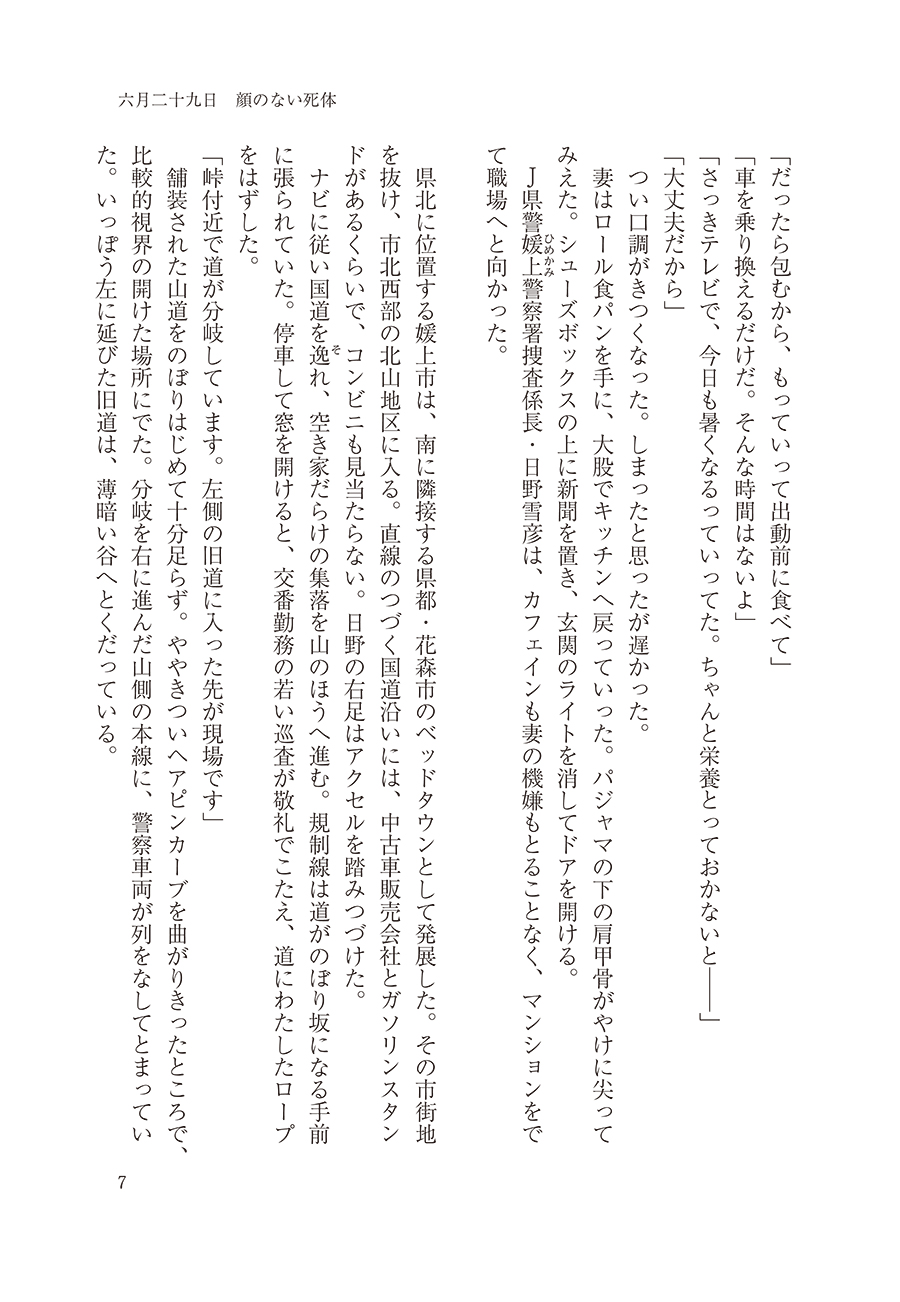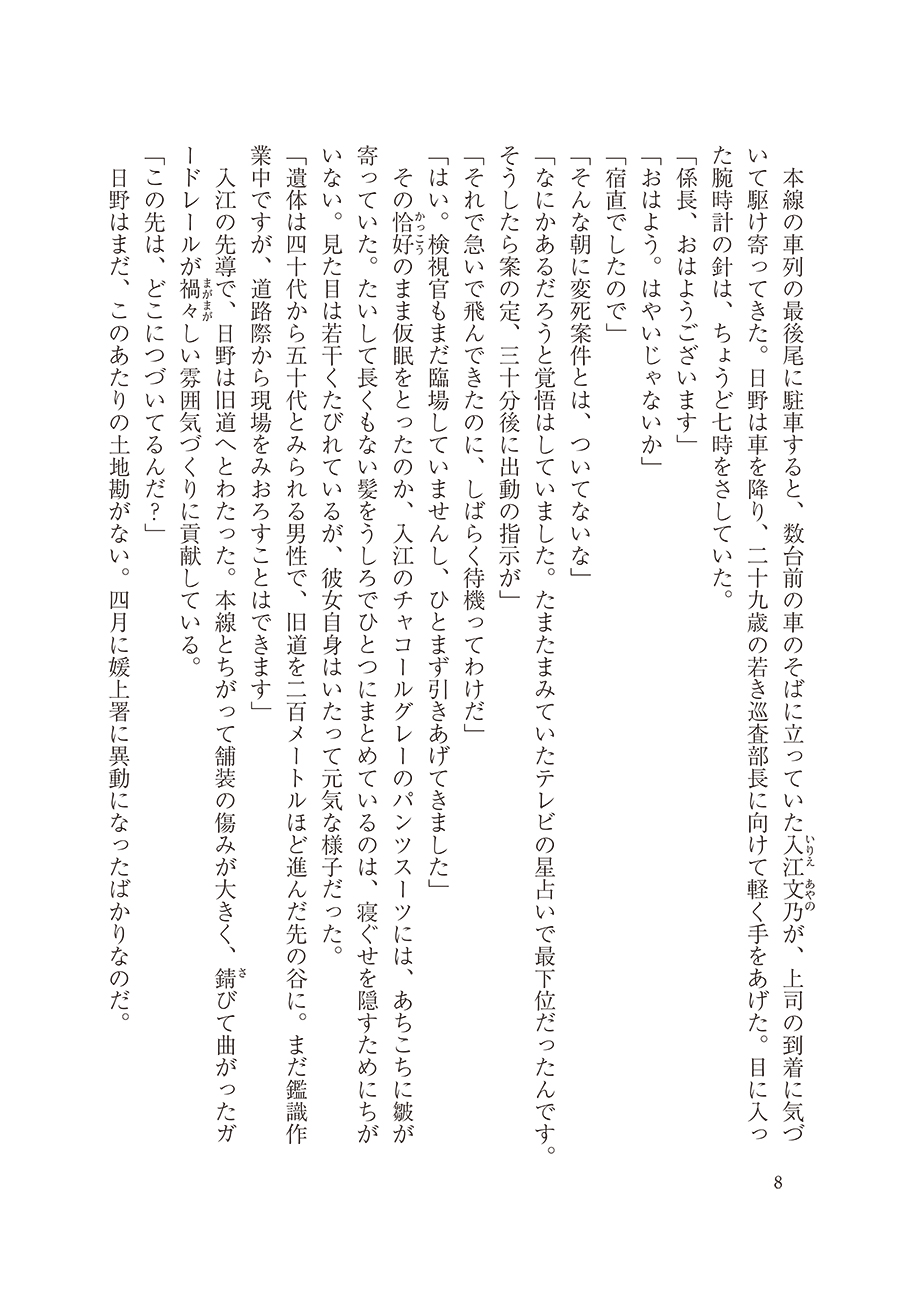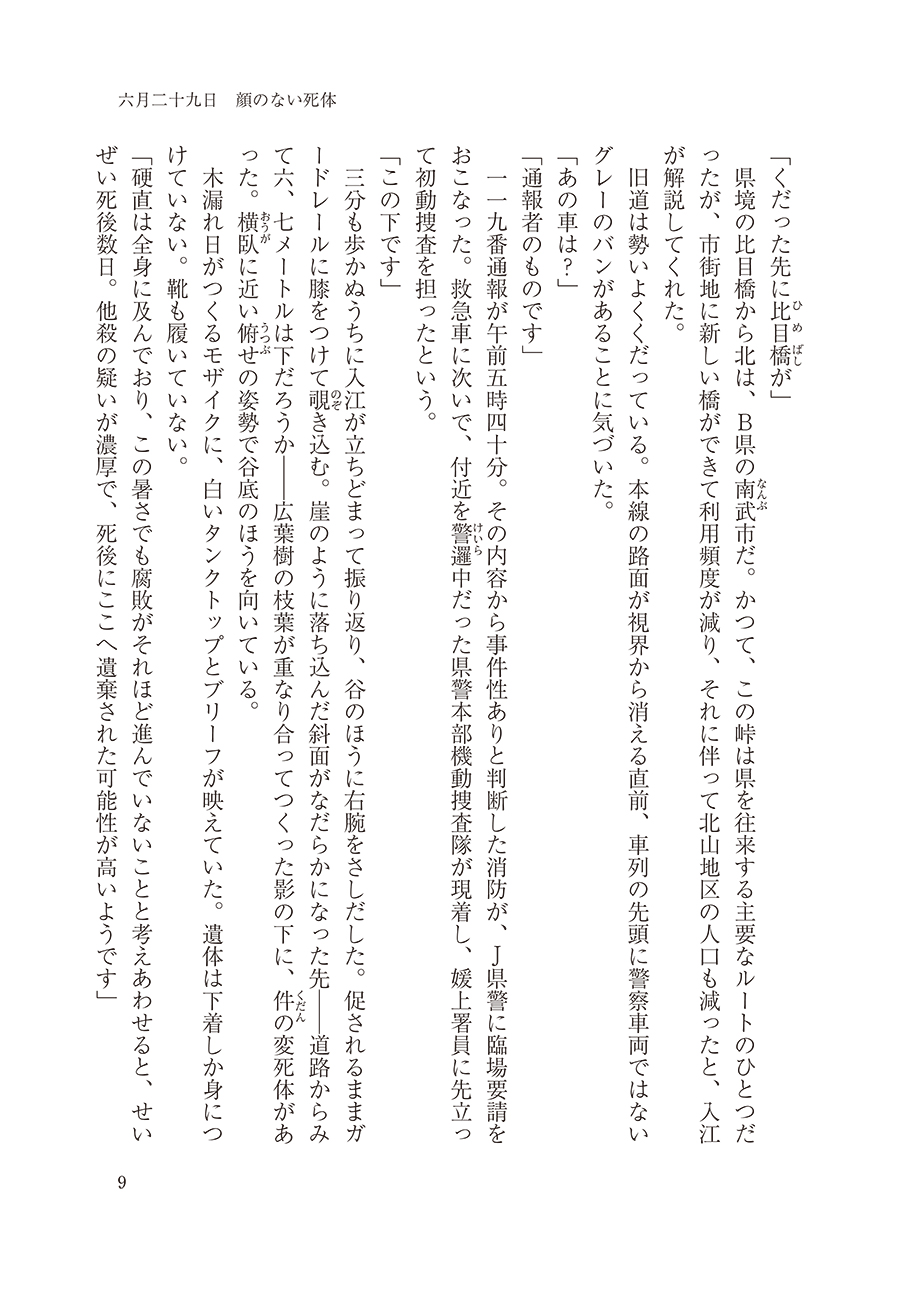六月二十九日 顔のない死体
1
ケトルで湯を沸かしはじめたところにスマホが鳴った。日野雪彦は朝のコーヒーをあきらめた。午前六時五分。火をとめて電話にでる。
「はい。捜査係、日野です」
通話中に寝室のドアの開く音がした。夜勤明けの妻が入れ違いでベッドに横になったのは、ほんの十五分前のことだった。
「呼びだし?」
「変死体がみつかったらしい」
死体という言葉を聞く前から、妻は眉間に皺を寄せていた。
「あの子のお弁当をお願いするのは無理みたいね」
今日は土曜日だが、中学三年生の娘は、進学塾が主催する模試を昼食持参で受けにいく。その昼食は雪彦が出勤前につくる約束だった。つまり朝食も。
「すまない。次は必ず」
妻は黙ってコンロの前に立ち、ケトルの水を鍋に移して火にかけた。寝室でスーツに着替えてキッチンに戻ると、彼女は十枚切りの食パンに粒マスタードを塗っていた。
「じゃあ、いってくる」
返事はなかったが、靴を履いているあいだに足音が近づいてきた。ライトがついて玄関が明るくなる。靴紐を結びなおして立ちあがり、ドアポストから新聞をとりだして振り向くと、目の前になにやら白っぽいかたまりが突きつけられた。
「ひと口でいいから、お腹に入れていって」
白っぽいかたまりの正体は、ソーセージを巻いた食パンだった。ロール食パンとでも呼ぼうか。それを妻は、リレー競技のバトンよろしく右手に握っていた。
「弁当をつくってたんじゃなかったのか」
「つくってる。そのついで」
「朝からソーセージは胃にもたれそうだ」
「茹でてるから重くないと思うけど」
「コーヒーのほうが嬉しかったな」
「なにも食べずにコーヒーを飲むほうが、よっぽど胃に悪いんじゃない?」
「保健指導はまた今度で」
彼女は看護師だ。
「まっすぐ現場にいくの?」
「いや、一度署にでる」
自家用車での臨場は原則禁じられている。
「だったら包むから、もっていって出動前に食べて」
「車を乗り換えるだけだ。そんな時間はないよ」
「さっきテレビで、今日も暑くなるっていってた。ちゃんと栄養とっておかないと──」
「大丈夫だから」
つい口調がきつくなった。しまったと思ったが遅かった。
妻はロール食パンを手に、大股でキッチンへ戻っていった。パジャマの下の肩甲骨がやけに尖ってみえた。シューズボックスの上に新聞を置き、玄関のライトを消してドアを開ける。
J県警媛上警察署捜査係長・日野雪彦は、カフェインも妻の機嫌もとることなく、マンションをでて職場へと向かった。
県北に位置する媛上市は、南に隣接する県都・花森市のベッドタウンとして発展した。その市街地を抜け、市北西部の北山地区に入る。直線のつづく国道沿いには、中古車販売会社とガソリンスタンドがあるくらいで、コンビニも見当たらない。日野の右足はアクセルを踏みつづけた。
ナビに従い国道を逸れ、空き家だらけの集落を山のほうへ進む。規制線は道がのぼり坂になる手前に張られていた。停車して窓を開けると、交番勤務の若い巡査が敬礼でこたえ、道にわたしたロープをはずした。
「峠付近で道が分岐しています。左側の旧道に入った先が現場です」
舗装された山道をのぼりはじめて十分足らず。ややきついヘアピンカーブを曲がりきったところで、比較的視界の開けた場所にでた。分岐を右に進んだ山側の本線に、警察車両が列をなしてとまっていた。いっぽう左に延びた旧道は、薄暗い谷へとくだっている。
本線の車列の最後尾に駐車すると、数台前の車のそばに立っていた入江文乃が、上司の到着に気づいて駆け寄ってきた。日野は車を降り、二十九歳の若き巡査部長に向けて軽く手をあげた。目に入った腕時計の針は、ちょうど七時をさしていた。
「係長、おはようございます」
「おはよう。はやいじゃないか」
「宿直でしたので」
「そんな朝に変死案件とは、ついてないな」
「なにかあるだろうと覚悟はしていました。たまたまみていたテレビの星占いで最下位だったんです。そうしたら案の定、三十分後に出動の指示が」
「それで急いで飛んできたのに、しばらく待機ってわけだ」
「はい。検視官もまだ臨場していませんし、ひとまず引きあげてきました」
その恰好のまま仮眠をとったのか、入江のチャコールグレーのパンツスーツには、あちこちに皺が寄っていた。たいして長くもない髪をうしろでひとつにまとめているのは、寝ぐせを隠すためにちがいない。見た目は若干くたびれているが、彼女自身はいたって元気な様子だった。
「遺体は四十代から五十代とみられる男性で、旧道を二百メートルほど進んだ先の谷に。まだ鑑識作業中ですが、道路際から現場をみおろすことはできます」
入江の先導で、日野は旧道へとわたった。本線とちがって舗装の傷みが大きく、錆びて曲がったガードレールが禍々しい雰囲気づくりに貢献している。
「この先は、どこにつづいてるんだ?」
日野はまだ、このあたりの土地勘がない。四月に媛上署に異動になったばかりなのだ。
「くだった先に比目橋が」
県境の比目橋から北は、B県の南武市だ。かつて、この峠は県を往来する主要なルートのひとつだったが、市街地に新しい橋ができて利用頻度が減り、それに伴って北山地区の人口も減ったと、入江が解説してくれた。
旧道は勢いよくくだっている。本線の路面が視界から消える直前、車列の先頭に警察車両ではないグレーのバンがあることに気づいた。
「あの車は?」
「通報者のものです」
一一九番通報が午前五時四十分。その内容から事件性ありと判断した消防が、J県警に臨場要請をおこなった。救急車に次いで、付近を警邏中だった県警本部機動捜査隊が現着し、媛上署員に先立って初動捜査を担ったという。
「この下です」
三分も歩かぬうちに入江が立ちどまって振り返り、谷のほうに右腕をさしだした。促されるままガードレールに膝をつけて覗き込む。崖のように落ち込んだ斜面がなだらかになった先──道路からみて六、七メートルは下だろうか──広葉樹の枝葉が重なり合ってつくった影の下に、件の変死体があった。横臥に近い俯せの姿勢で谷底のほうを向いている。
木漏れ日がつくるモザイクに、白いタンクトップとブリーフが映えていた。遺体は下着しか身につけていない。靴も履いていない。
「硬直は全身に及んでおり、この暑さでも腐敗がそれほど進んでいないことと考えあわせると、せいぜい死後数日。他殺の疑いが濃厚で、死後にここへ遺棄された可能性が高いようです」
「殺害後、谷の下まで運んだということか」
「運んだというより、道路際から投げ入れたのではないかと」
入江が、ちょうど斜面がなだらかになりはじめるあたりを指さした。幅数十センチにわたり土の崩れた痕がある。遺体はまずそこに落下し、さらに数メートル転がるか滑り落ちるかして、現在の位置にとどまったようだ。
「斜面に何者かが踏み入った痕跡は、捜査員と救急隊員のものを除いて確認できていません。ガードレールの高さは六十センチ程度。谷側に傾いていますから投げ込むにあたり大きな障害にはなりませんし、むしろ支えにつかえます」
複数犯のほうが当然遺棄は容易だろうが、単独犯でも不可能ではなさそうだ。
「後頭部に傷がみえるな」
「鈍器で殴打されたとの見立てですが、いまのところ該当する器物はみつかっていません」
「身元を示すものは?」
「それもみつかっていません」
「下着に名前が入っていたり──」
「しません。簡易検査で血液型だけは判明しています。B型でした」
「身元特定につながりそうな身体的特徴は?」
「つながらなさそうな特徴なら、いくつか」
その回答に、日野はあからさまに眉をひそめてみせた。
「なんの謎かけだ」
「べつに謎かけじゃありません。遺体は顔が叩きつぶされ、人相の判別ができない状態です。加えて、両腕とも手首から先が切断されて欠損しています。下着に血液による汚れはなく、遺体損壊後に着衣を脱がされたものと思われます」
「気に入らないな」
「髪もかなり乱雑に切られています。自分で散髪した結果かもしれませんが、そうだとしたらあまりに不器用で無頓着です」
「それも隠蔽工作か」
「そこまで手間をかけたということは、逆に身元さえわかれば、すぐ犯人に辿りつけるかもしれませんね」
入江の前向きな意見を否定する理由もなかったので、日野はとりあえずうなずいた。うなずきながら、いまいち頭が回っていないことに気づく。理由なら明白だ。脳がカフェインを欲している。斜面の土がコーヒーにみえてきたところで、入江が通報者について説明をはじめた。
「佐竹亘という三十三歳の男性で、市内の卸売業者で事務職をしているそうです」
住所は、ここから車で三十分ほどのマンションだという。
「事務職のサラリーマンが、どうして朝の谷を覗き込む必要があったんだ?」
「ゴミを捨てにきたようです。バンの後部には、冷蔵庫に金庫に自転車、自転車の空気入れ、ラジカセ、テレビにビデオデッキ……」
「未遂だったのか」
「いえ。遺体の数メートル向こうに扇風機が。手始めにそれを放り投げたあとで視線が下に向いて、遺体に気づいたと話しています」
「たとえ不法投棄が発覚したとしても、谷底に倒れている人を無視できなかったわけだ」
「感心するようなことじゃありません。常習でしょうか?」
「さあな。不法投棄の調べは生活安全課にまかせるさ。このあたりに監視カメラは?」
「機動捜査隊によれば、付近に設置はないようです。比目橋には道路情報用のライブカメラがありますが、南武市の管理なので、確認にはB県警の協力を仰ぐ必要が」
国道沿いには媛上市が設置する路上カメラもあるが、そちらは交通量が多すぎて、追跡対象が不明確な状態では、おそらく役立てることができない。タイヤ痕含め、車両特定につながるような手がかりは、みつかっていなかった。
そんなことを検討していると、機動捜査隊の班長が旧道をくだってやってきた。日野の挨拶に「課長は元気か?」と返事をよこす。班長と、日野の上司である刑事課長は同期の間柄なのだ。
「一帯に不審な車両は見当たらなかった。というわけで、うちはそろそろ引きあげるよ」
機動捜査隊としては、これ以上自分たちが動き回らねばならぬ緊急性は、ないと結論したようだ。
「いやに帰りを急ぐじゃないですか」
「嘱託の警察医と連絡がつかなかったとかで出発が遅れたらしいが、もうじき検視官が到着する。俺、あの人苦手なんだよ」
「どんなところがです?」
「年下のくせに横柄なところ」
午前七時三十分。一旦現場から引き返し、本線との分岐点がみえるあたりまで戻ったとき、一台のセダンがあらわれて車列の最後尾にとまった。入江がジャケットの裾を下に引っぱった。急に皺が気になりだしたらしい。思わず日野も頰を撫で、剃り忘れたひげの具合をたしかめた。
ドアが開き、運転席から鷹宮検視官がおりた。所属は県警本部刑事部鑑識課。四十一歳の日野より六年先輩で、階級はふたつ上の警視であり、身長も相手のほうが二十センチ近く高い。正式な役職は課長職級の管理官だ。
鷹宮につづいて、助手席から小柄な警察医がでてきた。ふたりは各種用具をしまいこんだケースを手に、日野たちのほうへ向かってくる。
日野は入江に、自分が検視に立ち会っているあいだの指示をだした。
「まずは署に戻って、佐竹亘の調書をとってくれ。彼については、ここ数日の行動をきっちり洗ってほしい。積荷と車両についても、できるかぎり詳しく調べたい。とくに血痕の有無を。任意でどこまでできるか微妙なところだが、相手は不法投棄を認めてるんだ、より協力的な態度を引きだせ」
「……第一発見者の線ですか? あり得ますかね」
入江の目が訝しげに細くなる。
「佐竹がここにきたのは、ほんとうはもっとはやい時間だったのかもしれない。あるいは数日前にもきたことがあったのかもしれない。たとえば彼は、数日前に遺体を棄てにやってきた。その際、現場になにか重大なもの──遺体の身元や自分自身につながり得る手がかりを残してしまい、今朝になってそのことに気づいた。佐竹はそれを慌てて回収にやってきたが、そうすることによって、またべつの痕跡が現場に残ってしまった」
「だから佐竹は発見者を装って通報することにした。そうすれば、現場に残った自身の痕跡に正当性を与えることができる……そういうことですか?」
「もしかしたら積荷のうちのいくつかは、捨てるために持参したものじゃなく、さっき谷底から回収した品かもしれない」
思いつきを口にしながら、日野は自分がみるみるうちに真相に近づいているような感覚になった。
「それ以外のゴミは、回収品をカムフラージュするために持参したと?」
「ゴミはゴミに隠せ、だ」
「でも鑑識は、救急隊と捜査員以外の足跡は確認できないといっていました」
「佐竹が谷底へとおりたルートを、救急隊員が踏み荒らさなかったとはいえまい」
「たしかに佐竹自身が隊員を誘導することもできたとは思いますが……」
カフェインの欠乏した脳に、入江の賛同──それがたとえ控え目なものだったとしても──が心地よい刺激となって、日野をますます調子づかせる。
「どうやら消防にも聴取をする必要があるな。あとは、ここに至る市内主要道のカメラを数日分おさえてくれ。比目橋のライブカメラについては、B県警への協力要請を課長に相談しておく。それと、この付近に防犯カメラの類がほんとうにないのか、あらためて確認してほしい。運がよければ機動捜査隊の見落としに気づける可能性もある。もっとも、占い最下位の人間にまかせるのは多少心許ないが……」
「その点は大丈夫です。コンビニでシュークリームを買いますので」
「……今度はどういう謎かけだ」
「今日のラッキーフードです」
「それもテレビの占いか」
「はい。ちなみに双子座は──」
「いわなくていい」
「九位でした」
最高にぱっとしない。
「ラッキーフードは──」
「もういい。はやくいけ」
「では、署へ戻ります」
入江は、くだってきた検視官に敬礼をすると、八百メートル走でインターハイにでたという自慢の脚力で、旧道を駆けのぼっていった。
遺体の確認を終えた鷹宮検視官が、立ちあがって日野に顔を向けた。
「致命傷は頭部および顔面への打撃のいずれか。手首の切断も含め、現場はここ以外の場所だ。現時点での死後経過時間は二十四時間から四十八時間」
日野は腕時計をみた。つまり死亡推定日時は、六月二十七日の午前八時から二十八日の同時刻まで。ざっくりいえば、一昨日の朝から昨日の朝までだ。
「歯型による鑑定はできそうですか」
この質問には、赤ら顔の医師のほうが、「むずかしいだろうな」とこたえた。
「歯も砕けてしまった?」
「いや、そもそも歯がない。死後にかなりの数が抜かれている」
「死後だと推定できる根拠が?」
「生きてる人間相手に、素人がこれだけの歯を抜くのは、ある意味殺すより難儀だと思うからさ」
医師はそういって、乾いた笑い声をたてた。
指紋、掌紋、面相、歯型──身元につながりそうな情報が、いずれも消失している。白髪まじりの頭髪についても、近くでみれば、たしかに乱雑な切りかただった。てきとうにハサミを入れて全体を短くしたような印象。それでもなお、遺体に残された髪にはきつめのウェーブがみてとれた。
「検視は以上。鑑識さえよければ遺体は搬送してかまわない。先生、お忙しいところ、朝からお付き合いいただきありがとうございました。先に車に戻っていてもらえますか」
医師は「そうか」といって、よろけながら斜面をのぼっていった。
遺体のそばに鷹宮とふたり。日野はなんとなく厭な予感がした。
「ところで日野係長。媛上署に異動後、殺人事件を扱うのは今回がはじめてでは?」
相手の声のトーンが変わった。星占い九位が頭をよぎる。気持ちで負けないようにと、日野は少しだけ斜面をのぼって身長差を補った。
「プレッシャーを与えるわけではないが、今日の〈北光ウィークリー〉の投書欄に、媛上署への苦情が掲載された」
北光ウィークリーは、花森市に本社を置く同名新聞社が発行する週刊の地方紙だ。歴史的につながりの深いB県南部の話題もとりあげるため、その地域にもシェアを有している。日刊紙とはべつに購読する家庭もいまだ多く、日野家もその例に漏れない。政財界や司法に対する姿勢は批判寄りの是々非々で、長年のキャッチコピーは〈市民の拡声器〉。
「苦情というのは、刑事課に対してですか」
今朝は非番予定でのんびりしていたため、新聞に目をとおしてこなかった。
「担当でいえば生活安全課になる。先月発生した、不審者による声かけ事案に、適切な対応がとられなかったそうだ」
「……それが、この事件となにか関係が?」
日野の発言に、鷹宮が目を見開いた。
「市民にとっては、署内の部署がどうとか誰が担当していたとか、そんなことは関係ないし、理解のしようがない。警察は警察。ひとつの組織の問題としてみられる」
どうやら自分は失言をしたらしいと気づく。
「仮に身元隠しという目的があったにしろ、遺体の一部を切断し、顔までつぶしたという表面的な猟奇性は世間の注目を集める。そんな事件の解決が遅れたとなれば、北光ウィークリーは今日の読者投稿をあらためてもちだし、怠慢こそ媛上署の体質だなどと書き立てるだろう。そうなれば合わせ技で向こうに一本だ。くれぐれも慎重かつ迅速に」
「肝に銘じます」
「媛上署の生活安全課長は羽幌警部だな。きみの同期だろう?」
「よくご存じで」
「本部にも、きみたちの同期はいる。警察学校時代から、彼は規律を重んじる警察官だったと聞いていたが……あれは卒業試験の話だったか?」
日野にそう訊ねながら、鷹宮が口もとに笑みを浮かべる。
「……いいえ。定期試験です」
「教官と深い仲になった生徒がいて、事前に問題用紙の提供を受けたんだったな」
「そうではありません。教官の一方的な好意でした。彼女の気を引きたいがために、そのような行動に」
彼女はそのことを誰にもいわなかった。しかし試験勉強期間中に、寮で同室だった生徒が用紙の存在に気づいた。彼女は「先輩からもらった過去問」だと誤魔化したが、そのせいでクラスに回覧せざるを得なくなった。試験後、内容が完全に一致していた〈過去問〉に疑惑の目が向けられ、耐えられなくなった彼女は事実を打ち明けた。
「もう二度と受けとらないと誓って、同期全員に謝罪をしたそうじゃないか」
同期の多くが、彼女の恩恵を受け試験を容易にパスしていた。ほかの教官に知られないかぎり、今回だけのこととして黙っておけばよいという意見が大勢を占めた。日野もまた、同じ考えだった。
「だが、当時の羽幌巡査だけは、その幕引きを是としなかったわけだな?」
それは質問ではなかった。すでに細部まで知っている話を、鷹宮はおもしろがって喋っているだけなのだ。日野はしかたなくうなずいた。
羽幌だけが、彼女に「不正を申告すべきだ」と迫った。「そうでなければ俺が告発する」と。
誰も羽幌を翻意させることができなかった。正論を懇願で覆すことはできなかった。彼女は学校側に問題提供を受けた事実を伝え、処分がくだる前に退校した。教官は懲戒処分を受けて、その後退職。ほかの生徒については、過去問と信じ込んだうえでの回覧であるとして不問とされた。
滲むようにひろがりだした追憶──しかし鷹宮の声が日野を現実に引き戻す。
「不審者案件については定められた手順に則った対応が各署に求められている。そこからの逸脱があったとすれば、羽幌警部にしては、めずらしく大きな失点だ」
揶揄する調子でそういうと、鷹宮は歩きだした。
2
午前九時二十分。媛上警察署に戻った日野は、一階の奥にある生活安全課にまっすぐ向かった。土曜で非番が多く、部屋には今期配属されたばかりの新人ひとりだった。
「羽幌は休みか?」
「署長室に呼ばれたみたいです」
羽幌が呼ばれた理由は北光ウィークリーの件にちがいない。非難の投書に殺人事件、署長も休日返上というわけだ。
「なにかあったんでしょうか。もしかして自分がミスを……」
留守番をまかされた新人は、まだ事情を把握していないらしい。
「心配するな。新人だろうがベテランだろうがミスは等しく起こす」
新人は「はあ」といって、わかったような、わからないような顔で首を傾げた。
「いないなら失礼するよ」
「課長に伝言は」
「いや。俺の用件は済んだ。俺がきたことも羽幌にはいわなくていい」
すでに上役に絞られているなら、自分の口からいうことはなにもない。でていこうとした日野を、新人が「あの……」と呼びとめた。
「課長が夕方どこにでかけているのか、ご存じですか?」
「いや、知らない。頻繁にいなくなるのか」
「五月の半ばくらいから、けっこうな頻度で。夕方四時から五時とか……電話はつながるんですけど、どこでなにをしているのか、先輩がたも知らないみたいで」
「俺も四月に異動してきたばかりで他部署の事情には疎い。羽幌と同じ署で働くのも十年以上ぶりでな。すまないが、あいつのルーティンについてはなにもわからない」
「そうですか……」
「タバコじゃないのか?」
「一時間もかけてですか?」
「喫茶店に入れば、なにも飲まずにでてくるわけにもいかない」
「それって、ただのサボりじゃないですか」
「怒るな。たんなる推測だ」
「もしかして、サボりがバレて署長に呼びだされたんじゃ」
「かもしれない。戻ってきたら問い詰めてみることだ」
生活安全課をでて、目の前の階段で二階にあがり、捜査係の自分のデスクに向かう。そこは媛上署におけるペーパーレス化の取り組み失敗を象徴する場所でもあった。机の上にバックパックを置くと、書類の束が落ちて派手な音を立てながら床に散らばり、よけいな仕事が増えた。
給湯室に置いた自前のマシンでコーヒーを淹れる。濃く熱い液体が喉を落ちると、気分がよくなる前に胃が痛みだした。デスクの抽斗を開けるが薬はない。とはいえ警務課までとりにいくのは面倒だ。先期の薬の消費量がとんでもなかったとかで、いちいち常備薬使用申請書なるものを書かねばならないのだ。
日野はそのまま刑事課長のところへ報告に赴いた。場合によっては、上司の小言で胃痛が紛れるという僥倖に恵まれないともかぎらない。
日野の報告を、相槌もうなずきも表情の変化もないまま聞き終えた課長は、
「つまり司法解剖が済むまでは、なんの手がかりも得られなそうだということですね」
といった。薄くなりつつある髪をオールバックで頭頂部に盛りあげ、そのせいでよけいに細長くみえる顔の真ん中に鋭い鼻がある。デスクの上はきれいなもので、書類をためないという一点だけでも、彼はきわめて有能な上司だった。
「比目橋のカメラについては本部を介してB県警に協力依頼をしておきました。南武署の捜査員が映像をおさえてくれる手筈です。ちょうど向こうからも、別件でJ県警に協力の打診があったらしく貸し借りなし。よいタイミングでした」
「ありがとうございます」
「ところで北光ウィークリーの件ですが──」
課長が椅子の上でわずかに身を反らした。天井の照明を反射して、銀縁メガネのレンズが磨りガラスのような白さを帯びる。
「本部から署長に、治安上の問題を放置したことに対する懸念と遺憾が寄せられたそうです。刑事課の問題ではない……というわけにはいきません」
「はい。市民にとっては、署内の部署がどうとか、そんなことは関係ありません。警察は警察。ひとつの組織です」
「よい認識ですね」
「おそれいります」
「司法解剖は明日の午前に県立医大でおこないます。即日実施とはいきませんでしたが朝一番で対応してくれるそうです。結果がでるまで、どう動きますか?」
「まずは通報者である佐竹亘の身辺から攻めようかと」
「不審な点が?」
「不法投棄目的で現場を訪れたという供述を、すぐには信用できませんので」
「実際は、現状ほかにアテがないという感じですかね」
「おそれいります」
「いずれにせよ早期解決。いいですね? 北光ウィークリーのほうは──」
「すぐに読んでおきます」
「まだ確認していない?」
メガネの奥で、課長の細い目が一層細くなった。
「付箋まで貼ってデスクに置いておきましたが」
「素どおりしてきたもので」
噓をつくときはためらうな──。
「少し前に、書類の崩れる音が聞こえたように思いましたが」
「おそらく入江の机でしょう」
胃痛を悪化させて上司の部屋をでると、お決まりのベージュのスーツに身を包んだ羽幌が、捜査係室の窓辺に立っていた。学生時代にラグビーで鍛えた巨体を揺らし、途中のデスクに何度も太腿のあたりをぶつけながら日野に近づいてくる。窓際で幾分か日射しを遮ってくれているほうが、よっぽどありがたいのだが。
「よう。署長に呼ばれてたんだって?」
「ふん。そっちこそ朝から忙しかったそうじゃないか」
「まあな。それはそうと、胃薬をもってないか」
「そんなものはないが、こいつなら床に落ちてたから拾っておいた」
羽幌がわたしてきたのは、水色の付箋が貼られた北光ウィークリーだった。日野は、目に入った記事を読みあげた。
「妻を刺した疑いで夫を逮捕。B県警南武署は二十八日夜、南武市棚井町に住む辻晴一容疑者三十九歳を、妻の加奈さん三十七歳を刺した傷害容疑で逮捕した──」
「おい」
「自ら通報し逮捕された夫は『口論がもつれて妻に包丁を向けられ、揉み合ううちに刺さってしまった』と供述しているそうだ」
「日野、もしかしてふざけてるのか」
「ふざけているものか。俺も今朝、妻と言い合いをしたばかりで他人事じゃない」
「知るか」
羽幌をからかうのはそれくらいにして、付箋の貼られた問題の投稿に目をとおす。
〈市民の不安に寄り添う警察に〉
5月13日、媛上市の鉄南地区で、小学生が不審な人物に声をかけられるという出来事があった。公園で遊んでいた男子児童に、マスクとサングラスで顔を隠した中年男性が話しかけてきたのだ。
届出を受けた媛上警察署は〈声かけ事案の発生〉として情報発信をおこない、周辺住民や店舗に防犯カメラ映像の提供を要請するなど、当初は捜査に前向きな姿勢をみせた。しかしながら、その後は重点的なパトロールの実施もなく、防犯ボランティア団体と連携を強める動きもなかった。明確な前兆事案があったにもかかわらず、犯罪抑止に積極的に取り組む意思が感じられないのは誠に残念であり、この件に関し、住民の不安はいまだ払拭されていないと感じている。
働き方改革の波は警察組織にも及んでいるのかもしれないが、市民に寄り添う気持ちだけは、常に忘れないでいてほしい。
媛上市・上村杏子(41)
「最後は皮肉も利かせていて、なかなか達者な文章だな」
感想を伝え、新聞のコピーをデスクに置いた。右の肩がこった気がしたので、首を曲げて揉んでみる。羽幌は目の前に立ったまま動かない。日野は訊ねた。
「どうした。なにか用か」
「死体がでたんだって?」
「ああ。せっかく仏の顔を拝みにいったのに、その顔がなかった」
「顔のない死体か。気に入らん」
「同感だ。めずらしく気が合うな」
そういって、日野は脱いだジャケットを椅子の背凭れにかけた。デスクのいちばん大きな抽斗を開けてコーヒーの在庫を確認し、納得して抽斗を閉める。羽幌はまだそこにいた。
「なんだ? 話があるならさっさといえ」
「あのな、日野。おまえが俺を訪ねてきたというから、わざわざ出向いてやったんだ」
先輩のいったことを鵜呑みにせず些細な報告を怠らない。じつに困った新人だ。
「どうせ、その投書の件で、おちょくりにきたんだろ?」
「そっちのおかげで、とばっちりを受けたと、ひとこと文句をいいたかっただけだ。現場で検視官から投書の話がでた」
日野がそうこたえると、羽幌は一瞬渋い顔をみせ、
「死体の身元はすぐわかりそうにないのか」
と、逃げるように話を変えた。
「その質問には黙秘する」
「ふざけるな。血液型くらいわかってるんだろ」
「簡易検査でB型だ」
顔の面積との比率でつぶらにみえる羽幌の目が、一瞬大きく見開かれた。
「……そうか」
「こっちの心配はいい。それより投書への対応を考えたらどうだ」
「地域の交番に巡回経路と頻度の変更を頼んだ。不審者の接触を受けた子どもの家に電話をかけて落ち度があったと謝罪した。その子がかよう学校の校長にも。投書をした上村杏子のスマホにもかけたが、そっちはつながらなかった」
「……スマホ? 投書人と知り合いなのか」
「放課後児童クラブで働き、地域の防犯ボランティアに十年以上従事している女性だ」
「なるほど。どうりで〈前兆事案〉なんて用語がでてくるはずだ」
おもに子どもや女性を対象とした〈声かけ〉や〈つきまとい〉などの発生を前兆事案と称し、この段階での対応が、凶悪事件の未然防止にはきわめて重要だ。媛上署管内で把握された前兆事案は、生活安全課に情報が集約され、そこで対応が検討される仕組みが構築されている──はずだった。
「どうして、いいかげんな対応をした」
「俺がじゅうぶんだと思う対応が、住民にとってはそうじゃなかったってことだ」
「おまえは徹底的にやる人間だと思っていたが、変わったのか?」
日野の言葉に、羽幌の眉がわずかに歪んだ。
「二十代の頃と比べるな」
「この上村という人物、防犯ボランティアをやっているくらいだから、生活安全課との関わりだって深いんだろ?」
「当然だ」
「それなのに新聞に投書か」
「北光ウィークリーと同じで、警察への態度は是々非々なのさ」
「立派じゃないか。そういう人物なら俺も会ってみたいよ」
「近いうちに署を訪ねてくるはずだ。会いたいなら、きたときに教えてやる」
「ありがたい。なんなら、おまえのかわりに頭をさげてやってもいいぞ」
鼻で笑うと羽幌の顔色が変わった。まさかとは思うが、胸ぐらに手が伸びてくるだろうか? 日野はデスクのカップにそっと指を伸ばした。向かってきたら、まずはコーヒーをかける──。
そのとき勢いよくドアが開いて入江が入ってきた。
「あ、羽幌課長」
入江は小柄なほうではないが、目の前の羽幌に対しては、さすがにみあげる恰好になる。
「もうすぐ佐竹亘を引きわたしますので、よろしくお願いします」
羽幌は少しバツが悪そうに首をすくめ、やはりデスクに体当たりを繰り返しながら部屋からでていった。その様子を興味深そうに見送った入江が、「怪獣みたい」と呟いてから日野を振り返った。
「すみません。変なタイミングで入ってきちゃいましたか?」
「いや、ちょうどよかった。おかげでコーヒーを無駄にしなくて済んだ。ところで──」
ありがたいことに、入江は胃薬をもっているという。
「悪いな。たすかる」
「気にしないでください。先期のうちにストックしたのが抽斗に残っているだけなので」
こういう輩がいるから薬の管理が厳しくなるのだ。感謝の気持ちを打ち消しつつ、薬はもらっておく。緑の顆粒の即効性を確認したところに報告がはじまった。
佐竹亘、三十三歳。媛上市出身。市内の卸売業者の事務所に勤めている。月曜から金曜までの勤務で今日は休日。実家近くの賃貸マンションに住んでおり、通勤時間は車で十五分ほど。実家には父親と姉が暮らしているらしい。
「つねづね実家の整理をしたいと考えていたそうです。ゴミの処分に困り、費用をかけずに捨てようと、あの山林へ」
「土地勘があったのか」
「下見をしたといってます。監視カメラもなさそうだし、ゴミを捨てるのにちょうどよいと思ったと。カメラについてはこちらでも調べましたが、やはり現場付近に設置はありませんでした」
供述によれば、佐竹は昨夜のうちにゴミを車に詰め込んでおいて、今朝は五時前に家をでた。夜ではなく朝にでかけたのは、もし山に入っていく車を目撃された場合、夜のほうがよっぽど怪しまれると考えたからだった。
計画性があり分別だってもち合わせていそうなのに、粗大ゴミを適正に処分することができない。人間というのは不思議なものだと日野は妙な感心をした。
「迂闊にも佐竹は、これから不法投棄にでかけようというのに、ドライブレコーダーの録画をとめていませんでした。カメラはフロントからの全方位タイプで、車両後方も撮影範囲に含まれます。通報直前の映像に、供述と異なる不審な点はありません。バックドアを開けて手前にあった扇風機をつかみ、谷のほうへ移動して一旦フレームアウト。その後、驚いた様子で再度フレームイン。このときすでに扇風機はもっていません。時刻は通報の二分前。不法投棄についてなら、じゅうぶんな証拠です」
佐竹のドラレコは、エンジンを切っても数分のあいだ録画がつづくのだという。メディアへの記録は、容量がいっぱいになると古い映像から順に消去・上書きされていく形式で、残っていたいちばん古いデータは、一昨日木曜の退勤時のものらしい。
「だが迂闊じゃなく狡猾という可能性もある。死体遺棄を疑われないための芝居をみせておいて、録画が切れたあと、なんらかの行為に及んだのかもしれん。罪は罪で隠せ、だ」
「念のため、不自然に欠落したデータがないか解析してもらってます。積荷と車内の確認については素直に応じました」
谷に落ちていた扇風機は、死体遺棄事件の押収品に含まれている。それとの照合という理由で、指紋と掌紋の採取も済んでいるという。
「車内の鑑識は午後の予定です。佐竹の身柄は一旦生活安全課に引きわたし、あらためて不法投棄関連の聴取を。なお、消防隊員が谷へくだるルートを彼が誘導したという事実はありませんでした」
入江の報告に、日野は納得してうなずいた。
あらためて彼女をみると、現場で会ったときに比べて目もとがくっきりとし、寝ぐせ隠しのヘアゴムは消えて、ボブの内巻きが完璧に決まっている。
「ずいぶん気合いを入れたじゃないか」
「当然です。はじめて係長と扱う殺人事件ですから。聞き込みにでかけるなら、係長も眉毛くらい描いたらどうですか?」
「これ以上濃くしてどうするんだ」
からかうつもりで逆にからかわれ、日野は小さく鼻を鳴らしてバックパックをもちあげた。
「現場周辺の聞き込みは、いまの人数でじゅうぶんだろう。俺たちは佐竹の自宅と実家を訪ねてみようじゃないか」
3
佐竹の実家は玄関先がゴミで溢れていた。
照れ笑いのような表情で、ハンカチを口もとにあてながらでてきた佐竹亘の姉は、警察と聞いて瞬時に表情を凍らせ、怯えた様子で「すみません、すみません」と繰り返した。家のなかから叫ぶような男性の声がした。「誰だ!」とか「追い払え!」とか、こちらも繰り返し喚いている。
「お父さん……ですか?」
入江の問いかけを、彼女はやはり「すみません」という言葉で肯定した。「向こうで少しお話を」という要請には、無言でうなずいた。
警察車両は、家から少し離れた場所にとめていた。運転席側の後部座席に座らせて話を聞く。入江が彼女の隣で質問役を担い、日野は助手席から様子を眺めることにした。
「母が去年のお正月に亡くなってから、父は急にゴミを捨てないようになってしまって。そのうえ、どこからか拾ってもくるように。わたしや亘が少しでも片づけようとすると、それはもう怒って手がつけられないんです。それで、いつの間にか、あんな状態に……すみません。ご近所さんにもご迷惑をおかけしていることは重々承知しています」
彼女は相変わらずハンカチを顔にあてながら、運転席の背凭れにひたいをぶつける勢いで──実際何度かぶつけていた──頭をさげつづけた。暑いなか厚手の長袖の服を着て、首を汗で光らせている。
「今日はゴミ屋……いや、ご自宅のことでうかがったわけではないんです」
入江がそういうと、姉は口もとのハンカチを握りしめ、
「そうですよね。私服の刑事さんがいらっしゃったってことは、きっと弟のことですよね? すみません。亘がゴミをどこかに捨てにいったのは、わかってました」
そういって大きく嘆息した。
「さすがにそれはどうだろうって、あの、父のものを勝手にもちだすことに対してじゃなく、それを違法に捨てるってことについて、さすがに一度はとめました。そうしたら亘は、『だったらどうするんだ!』って怒鳴るんです。もうわたし、誰にも怒られたくなくって。だから弟のいうとおりにさせました」
彼女の目と鼻が真っ赤に充血し、声が湿気を帯びる。
「それに……それにわたしも本心では、ゴミが少しでも減るなら、それもお金をかけずに捨てられるなら、そんなありがたいことはないと思って」
彼女はくしゃくしゃのハンカチで鼻のあたりを何度もこすった。
「父はゴミを捨てるといえば怒るけれど、勝手にもっていったとしても、たぶん気づかないんです。なにがどこに置いてあるかなんて、ちっともわかっちゃいないんです。父はやさしい人なんです。いまはちょっと心のバランスを崩しているだけなんです。ほんとうは父も、どうしたらいいのかわからなくて、途方に暮れてるはずなんです」
ときおりしゃくりあげては、彼女は言葉を詰まらせた。
「だからいつの間にかゴミがぜんぶなくなっていたら、『ああ、俺はなんて意味のないことに縋っていたんだろう』って気づいて、むかしの父に戻ってくれると思うんです。ぜったいぜったい、そう思うんです。だからわたし弟の、亘の、亘に、亘が、わたる……」
日野は彼女の涙も、拭いすぎて薄く皮の剝けた鼻の頭もみていられなくなり、しかたなく自分の丸い膝をみつめた。
佐竹の実家には、玄関先に防犯カメラがとりつけてあった。父親が設置を命じたのだという。しかし彼が映像を確認する姿を、亘の姉はみたことがないといった。彼女にお願いすると、過去一週間分のデータが入ったメディアを貸してくれた。父親は彼女に対し、容量がいっぱいになったら上書きせずにメディア自体を交換し、すべての録画記録を残すよう指示しているそうだ。
佐竹の実家をあとにし、そこから車で十分足らず。亘が借りているマンションに到着した。築年数はそれなりのようで、ベランダの鉄柵の形状と風合いに歴史を感じる。
駐車場に入るなり、入江が「ここにもカメラが」と嬉しそうにいった。エントランスに管理人室があり、防犯カメラについて訊ねると、近所で車上荒らしや空き巣が頻発した時期があったため設置したという。
「あのときは生活安全課の羽幌さんが、ずいぶん親身になってアドバイスをくれてね」
日野は市内で起きた事件について調べているとだけ伝え、ここ数日の映像をみせてもらえないかと頼んでみた。
「また窃盗でもあったのかい? せっかくあるんだから、役に立ててよ」
管理人は気安くいって、日野たちをパソコンが置いてある奥のデスクに座らせた。そしてアプリの操作を説明すると、「あとはご自由に」と、自身は窓口に戻っていった。
そこから一時間弱かけて、三日前からの映像を駆け足で確認した。
平日、佐竹亘の車が駐車場をでるのは午前八時十分頃。帰宅は遅くても午後七時で、その後に車の移動があったのは昨夜のみ。午後十一時すぎに駐車場をでて、日を跨いだ〇時十分に戻ってきている。そして今朝は、午前五時に駐車場を出発していた。
「係長。ここのカメラと佐竹の実家のカメラ、メーカーが同じです」
入江がそういったので、日野はパソコンに、亘の姉からあずかったメディアを差し込んでみた。アプリが認識してフォルダが展開される。
昨夜のデータを再生すると、佐竹亘の車が午後十一時十分に実家にあらわれた。玄関前の狭いスペースにどうにかバンを入れ、ゴミを次々と車内に積み込んでゆく。そのあいだ、姉はときどき通りに顔をだして周囲を気にしつつ、基本的にはおろおろするばかりだった。最後に扇風機を積んで作業が終わり、車が実家をでたのが午前〇時二分。
「死亡推定日時の範囲から今朝に至るまで、不自然な動きはなさそうですね」
「ああ。少なくとも遺体を運んだ様子はない」
日野たちは確認済みのメディアを返却するため、ふたたび佐竹の実家に赴いた。亘の姉はインターフォンから、「郵便受けに入れておいてください」と小声でいっただけで、もう顔をみせてはくれなかった。
「昼飯にするか」
小さな定食屋で、日野は天丼の海老に尻尾からかじりついた。ゲン担ぎでもないだろうが入江はカツ丼を食べている。苦い気持ちにはビールが似つかわしく、甘いタレの丼物にも然りである。午後二時五分。もちろん何時だろうと、職務中にアルコールを飲むわけにはいかない。鋭い尻尾が、喉を刺して胃に落ちた。
署に戻る車内で、入江が唐突に北光ウィークリーの投書に触れた。
「経緯は詳しくは知りませんけど、羽幌課長らしくないですね」
「まあな」
「係長と羽幌課長って同期なんですよね?」
「俺は警部補で係長。あいつは警部で課長。差はついたが同期だ。悪いか?」
「なんですか急に。べつにそんなつもりでいったわけじゃ……」
「……すまない。現場で検視官から同じことを訊かれてな。つい、またかと苛立った。捜査にプレッシャーをかけられたうえ……」
弁明が、つい愚痴っぽくなる。
「……むかしの忘れたい話まで蒸し返されたもんだから」
「それってもしかして、例の警察学校時代のエピソードですか」
「……知ってるのか」
「有名ですから」
日野はため息をついた。
「羽幌課長と衝突したとか」
「俺だけじゃない。全員があいつを説得しようとした」
「わたしが聞いた噂じゃ、係長は主要人物でしたけど」
「おもしろく切り抜かれてるだけだ」
「どちらの言い分も理解はできます。警察官として自らの不正を許すようであってはならない。だからといって一回の躓きがすべてを奪うことになってもいけない」
「わかりやすくまとめようとするな。まだなにもわかっちゃいない頃の話だ。あいつも年齢を重ねて変わった。規則と、それを守る正しさだけで社会は回らないと知った。折り合いをつけようとすれば、いつしか仕事のやりかたも変わっていく。その結果が市民の不満を招いた。そういうことだ」
「係長だって、勝手にまとめようとしてるじゃないですか」
「話は終わりだ。自分の事件に集中しろ」
「係長のほうも変わりましたか?」
「当然だ」
「異動が発表されたとき、あの羽幌課長につかみかかっていくような熱い人が上司になるんだって、楽しみにしてたんですけどね」
入江とのやりとりが、日野の心にふたたび追憶を呼んだ。
──彼女をあそこまで追い詰める必要がどこにあった。
彼女の退校を知った夜のことだった。
──ここでは教官は絶対の存在だ。拒むなんてできたはずがない。
寮の一室で、日野はそういいながら羽幌の胸ぐらをつかんだ。羽幌は少しも動じなかった。
──俺は不正を告白すべきだといっただけだ。警察官をやめたのは彼女自身の選択だ。
──おまえが彼女にそれを強いたんだ。彼女の人生をめちゃくちゃにしたんだ。
──自分の罪を認められない人間が、警察官として他人の罪に口をだせるのか?
──人の弱さを受け入れられない人間が力をもつよりは、よっぽどいいさ。
あんなものを熱さとは呼ばない。
ただ恥ずべき若さにすぎない。
「実物に会って落胆したか?」
「正直まだわかりません」
「そういうときは『そんなことありません』とこたえるもんだ」
「羽幌課長とは、いまだにギクシャクしてるんですか?」
「べつに。そうみえるか」
「おふたりのやりとりを聞いていると、互いにジャブで牽制しているだけのように感じることがあります」
「上司の観察をしている暇があったら一枚でも報告書を仕上げろ。あの件があろうとなかろうと、あいつとは、もともとウマが合わないんだ」
二十年近くが経ち、もはや曖昧になっている記憶を手繰り寄せる。羽幌との諍いの結末は、どうやってついたのだったか。まわりの仲間たちが、始末のつけかたを知らない自分を引きはがしてくれたのだろうか。
日野は入江が口にしたことを、心のなかで認めざるを得なかった。
あの夜を最後に、彼女の件について羽幌と語り合ったことは一度もない。
だから自分は、いまも羽幌との距離をはかりかね、向き合いきれずにいるのだと。
午後五時をすぎて、佐竹の車の鑑識結果が報告された。車内及び積載物から血液その他の体液は検出されていない。遺体のものと似た特徴の体毛も採取されていない。車内に歯は落ちていない。連続して録画されたドラレコの映像にデータの欠落は認められない。主要道のカメラに佐竹の車の不審な移動履歴はみつからない──。
「通報以外、佐竹亘は事件に関わっていませんね」
入江にきっぱりそういわれ、日野はコーヒーをつづけて二杯飲んだ。
デスクの電話が鳴り、生活安全課の新人から、佐竹亘を帰宅させてもよいかとの問い合わせがあった。日野は「かまわない」と返事をした。不法投棄に関しては微罪処分、すなわち厳重注意で済ませる方向で進んでいた。ふと思いだして「羽幌は?」と訊いてみる。「新聞の投書が効いたのか、今日は行先をいって巡回にでました」と、生意気なこたえが返ってきた。
現場周辺の聞き込みから有力な情報はあがってきていない。なにをすべきかと考え、やっぱり今日のうちに胃薬をもらっておこうと一階におりたところで、羽幌にでくわした。
「最近夕方になると、どこかにでかけてるんだって?」
「おまえには関係ない」
「じゃあ、関係あるかもしれない話をしよう」
日野は羽幌に佐竹の実家の様子を伝え、ゴミの放置について苦情が届いていないかを訊ねた。
「うちにはきていない。市役所に問い合わせてみろ」
「そういえばマンションの管理人が、以前窃盗が多発したときにアドバイスをもらってたすかったと、おまえに感謝していた。おかげで俺たちも仕事がしやすかった」
「ふん」
「佐竹亘には、なにかしてやれるアドバイスはないのか?」
「事情はどうあれ犯罪はよくない。俺がいえるのはそれだけだ」
捜査係の部屋に戻り、日野はデータベースを用いて、行方不明者リストに載っている人物の特徴を、身元不明遺体と照合しはじめた。県内から県外へと範囲をひろげるも、確実な情報が性別と血液型だけでは、絞り込みも捗らない。結局なんの収穫もないまま、気づけば午後十一時半をすぎていた。夕方に連絡を入れたきりだった娘に慌ててメッセージを送り、日野は帰り支度をはじめた。
一階におり、通用口から駐車場にでて、そういえば胃薬をもらい忘れたと気づいたとき、正面の空に月がみえた。月はちょうど半分で、けれど昨日のかたちを知らないから、それがこれから満ちてゆくのか、それとも欠けてゆくのかが、日野にはわからなかった。
帰宅すると、娘はリビングのソファーで仰向けになってスマホを眺めていた。
「おかえり。ママが、冷蔵庫の焼きうどん、チンして食べてって」
「模試はどうだった」
「うるさい」
「じゃあ、お弁当はなんだった」
「知らない」
「そのいいかた──」
「ナポリタン」
「ナポリタン?」
「ママって変わってるよね。お弁当にスパゲティ入れるときって、ふつう付け合わせじゃない?」
「急に当番を替わってもらったから、メニューを考える暇がなかったんだよ」
「パパは考えてたの?」
「玉子焼きとタコさんウインナーだ」
「やめてよ。子どもじゃないんだから」
「パパは大人だが、ウインナーはタコのかたちにしてほしい」
「わたしは恥ず……あ、そうだ。ウインナーっていえばさ、今日の朝ごはん、なんだったと思う?」
「クイズは嫌いだ」
「刑事なのに?」
「事件は遊びじゃない。で、なんだったんだ」
「なんかね、ソーセージを薄い食パンでぐるっと巻いた……」
「ああ、ロール食パン」
「そういう名前なの?」
「いや、パパが勝手につけた」
「でもさ、なんで巻く必要があるの? もしかして恵方巻に似てるから模試の朝に縁起がいいと思ったのかな? だったらウケるんですけど」
「そういうわけじゃない。もともとパパのだったんだ」
「あ、そうなの。ふうん……げっ!」
「今度はなんだ」
「もしかしてアレ、パパが一回握ったとか?」
「パパは握ってない。でもママは素手で握っていた」
「あっそ。ならいいや」
娘の返事に軽く傷つきながら、冷蔵庫から焼きうどんをだして電子レンジに入れた。あたたまるのを待つあいだ、気になっていたことを娘に訊いてみる。
「……第一志望は私立のままなのか」
「だって進学率がぜんぜんちがうんだもん。大学は国公立にするから許してよ」
「県外の大学か」
「県外にいきたいんじゃなく、獣医学部にいきたいの」
県内にも隣県にも、その隣の県にも、獣医学部を備えた国公立大学はない。
「イヤなの?」
「心配なんだ。パパは仕事柄、世のなかにいろんな事件があることを知っていて……」
もごもごと喋っているあいだに、娘がソファーからおりて、そばにやってきた。
「でもさ、パパ。夢も希望もある中学三年生の娘が、『わたしは一生故郷からでません』て宣言するほうが、よっぽど心配だと思わない?」
娘はそういって、あたため終わった焼きうどんをレンジからとりだすと、麺を一本つまんで、「しょっぱいね」と目を丸くした。
六月三十日 小さな来訪者
1
午前六時。コーヒーを飲みながら、日野は今朝の地元紙に目をとおした。身元不明遺体の件は、まだ小さな扱いだった。同じ社会面には、県境の街で起きたとあってB県南武市の事件も報じられていた。昨日の北光ウィークリーに速報のあった、夫との口論のはてに妻が包丁をもちだし、逆に刺されてしまったとされる一件だ。妻は死亡が確認されたという。
日野は、昨日の朝のロール食パンを巡るやりとりを思いだし、妻がつくった焼きうどんの味がやけに濃かったことが気になりだした。いつも口うるさく血圧のことを注意してくるというのに、どうして昨夜にかぎって……。
怖い想像はやめて新聞をたたみ、鷹宮検視官からかけられたプレッシャーについて考える。週刊紙である北光ウィークリーが、媛上の事件をはじめて報じるのは次の土曜日である七月六日。要するに彼は、その前日までに解決しろといっているのだ。
出勤後、日野は昨日の作業を再開したが、やはり成果はあがらない。そもそも死後数日しか経っていないのだから、被害者に家族がいたとしても、警察への相談に至っていない可能性がある。現場付近の聞き込みからも、依然として芳しい報告はあがっていなかった。
北光ウィークリーの件もあり、本来なら県警本部からのプレッシャーがもっとあってもよさそうだが、刑事課の電話は幸いにもおとなしい。
理由ならなんとなく察しがついている。今朝は同じJ県内の駒根市で変死体が発見されたらしく、やはり殺人の疑いが濃厚とのことで、そちらの初動に本部の人員が割かれているのだ。できればそのあいだに、こちらの捜査に進展があってほしいのだが……。
そんなことを思いながらディスプレイを睨みつづけていたら、そのうち刑事課長が日野のデスクにやってきて、うずたかく積もった書類の山に一瞥をくれてから、
「司法解剖が終わったと連絡がありました。検案書が届くまで、もう少し時間がかかるようです」
といった。日野はそれを、「すぐにこちらから問い合わせるように」という指示だと捉えて医大に電話をかけた。少し待たされてから、のんびりとした教授の声が耳に届く。
「急ぐのかい? いま検案書に添える資料をつくりはじめたところなんだが」
「先に概要を教えていただけるとたすかります」
教授は迷惑に感じているふうもなく、「あ、そう」といって説明を開始した。日野は慌ててデスクの上の書類を一枚裏返し、ペンをはしらせた。
「身長一六六センチ、体重六十八キロ。年齢は四十代もしくは五十代と推測。血液型はRhプラスのB型。栄養状態は悪くなく、脂肪肝で前立腺に軽度の肥大あり。頸椎の一部が変形し、椎間板ヘルニアの疑い。ほかにこれといった疾病は認められない。手術歴も骨折の痕もない」
特徴的なホクロや痣、刺青、火傷痕の類もみられなかったと、教授は付け加えた。
「死因は後頭部を殴打されたことによる脳挫傷。打撃によって意識は即時に失われたはずだ。危害を加えた人物は金槌のような器物を上から振りおろした可能性が高い」
金槌のサイズは、家庭の工具箱に入るような、ごく一般的な大きさだという。
「防御創はなし。不意の一撃だったようだ。頭部に三か所、傷が認められるが、これらはおそらく髪の毛を切った際に刃物が触れた結果だろう。死後の傷だ」
頭髪のウェーブは人工的なものではなく、天然の縮毛だという。
「胃と小腸の内容物はウイスキーとナッツ類、それにオリーブ。消化状況から、飲食は死亡の一時間ほど前まで、数時間にわたってなされている。つよい酒を飲むときには、もう少しなにか食べたほうが身体にやさしいんだがな。血液からは、アルコールを除いて薬物や毒物は検出されていない」
「死亡時刻はどのくらいの範囲で絞れそうですか」
「鷹宮くんの見立て以上には絞れそうにない。六月二十七日の午前八時から翌二十八日の同時刻まで。発見時の姿勢についても聞いたよ。俯せに近い恰好だったそうだが、薄い死斑が背面にも認められた。つまり死亡直後の数時間は、仰向けになっていたはずだ」
逆にいえば、死後それほど経たないうちに──せいぜい五、六時間以内には、斜面に遺棄されただろうというのが教授の見立てだった。
「遺体の損壊は死亡直後にはじまったと思われる。顔面の殴打は計十回。後頭部を殴ったのと同じ道具をつかったと思って間違いない。手首は関節部分で切断され、これには包丁と鋸の二種類の道具がつかわれている。同じ包丁が、髪を切るのにもつかわれたかもしれない。口内は全歯が欠損。もともと抜けていた歯も多かったようだが、少なくとも十八本が死後きわめて乱暴に抜かれている」
解剖が済んでも、身元につながる情報は乏しいままだった。もちろん遺体からDNAを採取することは可能だが、照合する対象が存在してこそのDNA鑑定であり、単独で遺伝子配列をみたところで個人の特定には至らない。
礼をいって電話を切り、これといって上司に報告すべき情報が得られていないことに気づく。日野は解剖所見のメモを手に、縋る思いで鑑識を訪ねてみることにした。すると廊下にでたところで鑑識係室のドアが開き、入江がでてきた。
「なにかみつかったのか?」
「遺体のタンクトップに、別人の体毛が付着していました」
みつかったのは一本だけ。一部を切りとって分析したところ、得られた血液型情報はAB型で、遺体のB型と合致しない。遺体の下着に血液の付着がないことから、着衣は遺棄直前に脱がされたと推測されるため、体毛の持ち主は遺棄に直接関わった人物である可能性が高い。
「十センチ以上ありますので、十中八九、頭髪です」
「佐竹亘の髪の毛という可能性は?」
「彼とは血液型が一致しません」
「性別は判断できそうか」
「形質的に女性の髪の特徴に近いそうですが、断定ではありません」
毛髪は自然脱落毛で、DNA鑑定に適するかは不明だが、それが無理であったとしても、髪質や髪色、血液型といった情報は、容疑者が浮かんだ際に役立つだろう。
「これで少しのあいだ課長の機嫌を保てそうだ」
「解剖のほうはどうでしたか?」
そう訊かれ、所見を伝える。すると入江が、
「ひとつ引っかかることがあります」
といった。
「どうして犯人は遺体の髪を切ったんでしょう」
「身元につながる手がかりを少しでも消そうとしたんだろう」
「であれば、いっそのこと丸刈りにしたほうがよかったんじゃありませんか? せっかく手間をかけたところで、ウェーブという特徴を遺体に残したままじゃ、あまり意味がないように感じます」
「たしかに特徴ではあるが、その情報だけで警察が身元にいきつくことは不可能だ」
「だったら逆に、そもそも切る必要がないのでは」
「それは残った根もとだけをみているから思うことだ。もしかしたら毛先のほうに大きな特徴があったのかもしれない。そんなことより、ひとつ意見を聞かせてほしい。遺体の身元を隠したいと思うなら、その存在自体を隠そうとしてもいいとは思わないか? 顔をつぶした。手首を切り落とした。歯まで抜いて山林に運んだ。だったらもうひとがんばり、死体を埋めようとは考えないものだろうか」
「わたしだったら考えません」
入江はきっぱりといった。
「なぜだ」
「新人だった頃に、現場検証の一環で、多少の雨では遺体が露出しない深さの穴を掘ったことがあります。正直、あんな重労働は二度とやりたくありません」
当時を思いだしたのか、入江が不機嫌そうな顔になる。それをみて、日野は思わず笑ってしまった。
「ありがとう、参考になるよ。さて、昼にするか」
気づけばとっくに正午をすぎていた。
入江は外へ食事にでた。そのまま午後は北山地区で聞き込みに参加するという。日野は出勤途中のコンビニでカツ丼を買っていた。温めもせず食べはじめたところで、床に置いたバックパックからスマホの振動音が聞こえた。デスクにカツ丼を安全に置ける余地がないため、箸だけ置いてバックパックに右手を突っ込む。未登録の番号からだった。
「はい、日野です」
「本部の鷹宮だ」
完全に想定外の相手だった。
「司法解剖の結果は聞いているか?」
「先ほど教授に問い合わせました」
「そうか。説明を省けるなら話がはやくてたすかる」
「というと、ほかに用件が……もしかして北光ウィークリーからなにかアプローチが?」
「ちがう。今朝、駒根市のアパートで変死体がみつかった件は知っているな?」
「はい。状況的に殺人の疑いが濃厚だと」
同じ県北地域にあって、媛上の東に位置する駒根市もまた、県都のベッドタウンとして発展した街だ。聞けば鷹宮は、今朝はやくに駒根の現場で検視を済ませたあと、司法解剖の立ち会いに向かったという。
「駒根の件がこちらとなにか……まさか向こうの遺体にも顔と手がなかったとか」
「先走るな。駒根の遺体にはどちらも揃っていて、身元も判明している。被害者は現場となったアパートのオーナーで、シラカワキヨシという六十八歳の男性だ」
机の書類を裏返してメモ用紙にする。
──被害者・白川清。現場アパートのオーナー。
「頭部に器物で殴られた痕があり、これが致命傷と思われる。殺害現場となった部屋に住んでいた男の名は、ヤギタツオ」
──八木辰夫。現場住人。
「その八木の行方が、現在わかっていない。当然、駒根署が重要参考人として彼を追っている」
「その男が、オーナーを殺害して逃走した可能性が?」
「まさに、そういうシナリオで駒根署は動いていた。だが、その後の調べで興味深い事実が浮かんできた。八木辰夫は年齢五十歳。血液型はRhプラスのB型。前立腺肥大と頸椎椎間板ヘルニアの既往歴があるが、外科的処置はなされていない。髪は天然の縮毛で、身長と体重はそれぞれ──」
「ちょっと待ってください。つまり……」
「八木の特徴は、身元不明遺体の所見に合致する」
日野は情報を書き加えた。
──八木辰夫。現場住人。行方不明。北山地区の死体?
「それにしても、短時間でよくそこまで調べがつきましたね」
「あらためて調べなくても、彼については警察に詳細なデータが残っている。八木には前科があった。すでに身元不明遺体から採取したサンプルと、駒根の現場から採取したサンプルとでDNA鑑定の準備を進めている。その結果、遺体が八木だと確認できれば、正式に駒根・媛上両署の合同捜査というかたちをとる」
ただし鑑定の結果がでるのは、どんなにはやくても明日だという。
「合同捜査に先立って、捜査協力という恰好で情報共有をおこなってもらうが、その通達をだすのにも多少の時間がかかる。それまでのあいだ、きみに駒根署との連携役を担ってほしい」
「承知しました。ただ、そういった用件であれば、うちの課長をとおして──」
「あの人は融通が利かない。それはきみにもわかるだろう?」
鷹宮の声が急に険しくなった。
「……わたしに単独で動けと?」
「繰り返させるな。そのほうが時間の節約になる。駒根署の捜査主任にも根回しはしておく。媛上署の担当者が隠密裏にうかがうかもしれないとな」
鷹宮が小さく笑った。
「よろしく頼んだ。きみには期待している」
日野がでかける準備をはじめたところに、今度はデスクの電話が鳴った。細長い液晶ディスプレイに表示されたのは、生活安全課の羽幌の内線番号だった。この忙しいときに──小さく舌打ちをして受話器をとる。
「なんだ?」
「きたぞ」
羽幌はそういったきり電話の向こうで黙り込んだ。驚くべきことに、それで用件が伝わった気になっているのだ。日野はさすがに呆れた。
「きた? 誰が? なんのために? おまえんとこの新人が、おまえを手本に電話をかけるようになったらどう責任をとる。なにもいわないなら切るぞ」
「待て。昨日話したとおり上村杏子が窓口にきている」
上村杏子──北光ウィークリーへの投書人。日野は首を傾げた。
「それが俺となんの関係が……おい羽幌、まさか昨日、おまえのかわりに頭をさげてやろうかといったのを、本気にしてるんじゃないだろうな」
「するわけないだろ。彼女は投書の件できたんじゃない」
「だったらなにを……」
「昨日みつかった身元不明遺体について話を聞きたいそうだ」
日野はますます混乱した。
「どういうことだ」
「彼女は、遺体の身元が、知り合いの夫かどうかを気にしている」
「なんだって?」
思わず大声がでた。
「騒ぐな日野。そして期待するな。たまにあることなんだ」
「たまにって……」
「管内に身元不明の遺体がでると、ここを訪ねてくる。それが殺人事件の被害者というケースは、はじめてだがな」
「知り合いの夫の名は?」
「オヌマケン。十年前に行方不明になった。生きていれば今年で四十二歳だ」
「羽幌。昨日、上村杏子が近いうちに訪ねてくるといったのは、このことか」
「ああ」
「どうして昨日のうちに話してくれなかったんだ」
「ずいぶん忙しそうだったからな。いう必要はないと思った」
日野は相手に聞こえるよう舌打ちをした。
「たしかに、いまとなってはもう必要のない情報だ。遺体の身元はすでに割れかけている。残念だが、こちらが握っている名前は、オヌマケンではない」
「そうか。なら、俺のほうで別人だと告げて引きとってもらう」
「ちょっと待て。冷たくあしらうつもりじゃないだろうな。投書が載って昨日の今日だぞ。市民が警察に求めているのは誠実な──」
「大丈夫だ。根拠を示す」
「根拠だと?」
「遺体はB型だといったな。間違いないか?」
「間違いない」
「だったらそれはオヌマケンじゃない」
そういうことかと、日野はようやく気づいた。羽幌が昨日、たいした意味もなく捜査係の部屋へやってきた理由に。
羽幌は、身元不明遺体がオヌマケンである可能性について知りたかったのだ。だから日野から遺体の血液型を聞きだした。「たまにある」という上村杏子の来訪にそなえて──。
腹立ちをおぼえながらも、結局は羽幌に対応を委ね、日野は受話器を置いた。
駒根署までは車で約三十分。食べかけのカツ丼を冷蔵庫にしまい、廊下にでる。薄暗い階段を一階におりる途中、踊り場からみおろした生活安全課のドアの前に、職員に案内されて、ひとりの女性が姿をみせた。
「なかへどうぞ」
職員がドアを開けると、女性は少し右足を引きずるようにして、生活安全課の室内へと消えた。
2
「どうもどうも。鷹宮検視官から話は聞いてます」
午後一時五十分。駒根署に到着すると、刑事課の柿本主任に迎えられた。たしか年齢は向こうがひと回り上。若い頃から物腰が落ちついていて、それゆえ〈渋柿〉のあだ名で呼ばれていたと聞いたことがある。小柄ながら柔道の達人として知られた人物でもあった。会議室にとおされ、情報交換がはじまる。
「被害者である白川清・六十八歳は、彼が所有する駒根市内のアパート〈ホワイトハウス〉の二〇一号室で、何者かに頭部を殴打され遺体となって発見されました。二〇一号室の住人の名は八木辰夫。現在行方不明です」
現場の間取りは1Kで、玄関の先にキッチンを兼ねた短い廊下が延び、奥にクローゼット付きの六帖の部屋。遺体はそのクローゼットに押し込まれていた。飛び散った血痕から、被害者は奥の部屋に入ってすぐに襲われたと考えられている。
「凶器は、もともとクローゼット内にあったと思しき小型金庫。中身は空でした」
白川は現場から徒歩十分ほどのところに住んでおり、ひとり暮らしだったという。車は自宅にとめられたままだった。大家である彼が、八木の部屋を訪ねた経緯については不明。遺体のポケットからは財布と自宅の鍵、現場のスペアキーがみつかったが、もっていたはずのスマホは所在がわからなくなっている。
「通報があったのは……?」
「今朝の六時です。通報者はアパートの前をとおりかかった七十歳の男性。妻と散歩の最中でした」
「なぜ散歩中の夫婦が二階の部屋を覗けたんです?」
「あ、そうではなく。歩いていたら急に悲鳴が聞こえて、なにかと思ってあたりを見回したら、アパートの外階段を落ちてくる女性が目に入ったと」
夫婦が驚いて駆け寄ってみると、女性は階段下に俯せで倒れていた。それで夫のほうが一一九番に通報したのだという。
「女性のそばでウイスキーの瓶が割れてたんで、最初は酔っぱらいが階段を踏みはずしたと思ったそうですよ」
「ウイスキー?」
「ええ、〈ダルマ〉です」
黒色のガラス瓶の独特な丸みから、ダルマの愛称で呼ばれる国産ウイスキーがある。女性の傍らには、砕けたダルマのほかにトートバッグも落ちていた。着地の際に身を守ろうと腕を伸ばし、抱えていたバッグが手から離れてしまったのだろうと推測されている。その際にウイスキーがバッグから飛びだしたのだろうとも。
「では、階段を落ちてきた女性が遺体の第一発見者ということですか?」
「おそらく。というのもその女性──幸田みつ子というんですが、入院中でしてね。夫婦が駆け寄った直後は呼びかけにも応答してたらしいんですが、救急車が到着したときには失神していました。現在は意識も回復しているんですが、まだ聴取の許可がおりず」
そういった事情により、現時点での遺体の発見者は、幸田みつ子の救助に駆けつけた救急隊員だった。外傷者は階段から落ちたと聞いた隊員が、状況確認のため二階の部屋を回った結果、無施錠だった二〇一号室に死体をみつけ、警察への連絡に至ったそうだ。それによってホワイトハウスは、事故現場から事件現場へと、にわかに様相を変えた。
救急隊の判断でトートバッグは現場に残され、その後駆けつけた駒根署の捜査員によって、ウイスキーボトルの破片とともに押収された。搬送された女性の身元は、財布に入っていた複数の身分証により判明した。
「ところで日野さん、八木が最近まで服役していたことは……?」
「検視官から前科があったとは聞きました」
日野の返事に柿本がうなずく。
「幸田みつ子は、駒根市内に事務所を置く〈カラン〉という出所者支援NPOの代表でしてね。いっぽう殺された白川清は、彼女の法人活動に共感して住居の提供……もちろん無償じゃありませんが、前科のある者を自分のアパートに積極的に住まわせていた人物でした。二〇一号室の契約はカランと白川のあいだで結ばれており、八木はカランの援助を受け、その部屋を提供されていた恰好です」
「そうだとしても幸田みつ子は、なぜそんな早朝に支援対象者の部屋を訪ねたんでしょう?」
「そこに関してはカランの職員も不思議がっていました。彼女は前日まで、県外で催されたワークショップに参加していたそうなんですが、その先で、なにかこの件に結びつくような連絡でも受けていたのか……」
職員が確認したところ、カランの事務所で管理していた二〇一号室の合鍵がなくなっており、それは幸田のものと思われるトートバッグからみつかっていた。
「白川の死亡推定日時は?」
「発見時からさかのぼること三十時間から四十時間。六月二十八日の午後二時から、日付の変わる深夜〇時までのあいだとなっています」
「二日前の午後ですか……少なくとも、幸田が犯行後に慌てて逃げようとして階段を踏みはずしたという可能性はないわけですね」
「もし彼女が犯人なら、第一発見者を装うためか、あるいはそれ以外の目的で、あらためて現場に戻ってきたことになりますな」
「アパートに防犯カメラは?」
「残念ながら。付近のカメラから手がかりが得られないかと期待しているんですが、なにしろ現場は住宅街のはずれで、いまのところはまだ……あ、そうそう。アパートから五百メートルほど離れた家のカメラに、幸田みつ子の車が映っているのは確認できました。今朝五時五十分頃のことで、ちょうど現場に向かっているところでしょう」
彼女が乗ってきた車はいまもアパートの駐車場にあるそうだ。
「駒根署では当初、部屋の住人である八木が、オーナーである白川を殺害し逃走したという見立てだったと聞きましたが」
「ええ。なにしろ状況的には、それがいちばん妥当でしたから。大家と住人のトラブル。しかも住人に最近の前科があるとなれば、疑ってかかりたくもなります。しかしその後の鑑識で、玄関と浴室から、白川のものではない血液の痕跡がみつかりましてね。血液型はB型で、これは八木と一致する。ところが白川の遺体に抵抗した形跡がないことから、犯人が出血するほどの深手を負ったとは思えない。だとしたら八木は加害者ではなく、彼もまた被害者であるという可能性がでてきたわけです」
そういったことを検討している最中に、鷹宮検視官から身元不明遺体の情報がもたらされたのだという。
「媛上の遺体の死亡推定日時はたしか……」
「遅くとも二十八日の午前中には殺害されています。その身元が八木辰夫なのだとしたら、時間的に白川の殺害は不可能です」
ふたりの刑事はそろってうなずきながら、テーブルの麦茶に手を伸ばした。そこへドアが開き、柿本の上司が顔を覗かせた。
「ちょっといいかい?」
「あ、はい」
柿本が部屋をでていくと、今度は日野がスマホに呼びだされた。
「おつかれさまです。入江です」
「おつかれさま。なにかあったか?」
「先ほど駒根署との捜査協力の通達がありました。今朝、駒根市のアパートでみつかった変死体に関連して、現場となった部屋の住人が行方不明になっているんですが──」
相槌を打ちながら説明を聞いていたら、急に入江が黙り込み、数秒の間をおいて、「もしかして、すでにご存じの話ですか?」と訊いてきた。どうやら応答が淡白すぎたようだ。
「係長。いま、どちらに?」
入江が、課長を思わせる冷淡な調子で訊ねてきた。
「いや、佐竹亘の件でちょっと気になることがあって……」
「駒根署にいるんですか?」
今度は日野が黙る番だった。
「駒根署にいるんですね?」
「……鋭い部下をもって嬉しいよ」
「どうして教えてくれなかったんですか」
入江の声がにわかに棘をもつ。
「鷹宮検視官からの直接の指示で動いている。課長にも話していない」
「わたしに話したら課長に伝わるとでも?」
「そうじゃない。単独で動けといわれていたし、あとで問題になったときに巻き込みたくなかった」
「上司に情報を伏せられるくらいなら、巻き込まれるほうがまだマシです」
「すまなかった。今回ばかりはわかってくれ」
納得したかは不明だが、入江はひとまず矛をおさめた。
「そちらはどんな状況なんですか。やはり、うちとの関連が?」
「関連があったとしたら、ふたつの遺体は同じアパートの一室で殺害されたにもかかわらず、殺害時刻に六時間以上の隔たりがあることになる。どうしてそんなことになったのか」
「どちらが先に?」
「うちの遺体だ」
「つまり八木ですね」
「カッコ仮だ」
「八木を恨んでいる人間なら、いくらでもいるでしょうね。なにしろ悪徳探偵の見本のような男だったわけですから」
「悪徳探偵だって?」
日野の反応に、入江が「それはご存じじゃないんですね」と、呆れたような声をだした。
「興信所の所長だったみたいですよ、八木辰夫は」
柿本もまた、捜査協力の件で上司に呼ばれていたらしい。麦茶のボトルを手に戻った彼に、日野は興信所の件をぶつけてみた。
「いやいや、べつにもったいぶったとか、情報を隠そうとしたとか、そういうわけじゃないんです」
相手は麦茶のおかわりをグラスにそそぎながら弁解した。ほんとうだろうかと、日野は多少訝った。もっとも八木の前科の中身くらいは、事前に調べてくるべきだった。彼は恐喝と詐欺で、過去に実刑を受けていた。
「たしかに、いまの時点であまり喋りすぎるなと、上役から釘を刺されていたことは認めます。ここからは腹を割りましょう」
「こちらはとっくに割ってたんですけどね」
日野のボヤキを柿本は笑い飛ばした。
「興信所の所長といっても所員は彼ひとり。恐喝の中身は、調査結果をネタに調査対象を脅して口止め料を巻きあげるという、ありふれた手口です。もちろん依頼人には虚偽の報告をして規定の料金をとるわけで、そっちで詐欺ならびに探偵業法違反」
逮捕は、六年前の二〇一八年のこと。八木は当時も駒根市に住み、自宅マンションの一部を事務所にしていたという。
「日野さん、ここはひとつ、媛上の遺体が八木辰夫だとして、ふたつの殺人を考えてみませんか」
柿本はそういって、柔道家らしく腫れた耳を指でつまんだ。
「六月二十八日の午前八時までに、ホワイトハウス二〇一号室に住む八木辰夫は、自室の玄関付近で何者かによって殺害された。犯人は浴室で遺体の顔をつぶして手首を切断、歯を抜いて髪まで切るといった身元隠蔽工作を実施」
その際に浴室と玄関を汚したのが、八木のB型の血液というわけだ。
「犯人は部屋の鍵を奪い、遺体を車で媛上市に運び、着衣を剝いで郊外の山林に遺棄した……遺棄の日時に関しては、いまのところ不明ですか?」
「わかっていません。司法解剖によれば斜面に放置されたのは死後六時間以内。そのあいだに一定の時間、平らな場所に置かれていた可能性が高いと」
「なるほど。浴室もしくは遺体を載せた車内が、その〈平らな場所〉だった可能性が高いでしょうな。であれば、やはり犯人は八木を遺棄したあとで、ふたたび二〇一号室に戻り、その際に白川を殺害したと考えられる。それが二十八日の午後二時から深夜〇時までのあいだ。この流れはいいとして、問題のひとつは、なぜ八木の遺体だけが念入りに損壊されたうえ殺害現場から遠く離れた場所に遺棄されたのか? 次に、犯人はなぜ現場に戻ってきたのか。さらには、白川がそこに居合わせた事情がなんだったのか」
「なにか思いつきますか」
日野は考える前に意見を求めた。なにしろ麦茶にはカフェインが含まれていない。柿本は耳たぶを引っぱりながら、
「犯人の狙いはあくまで八木だったと前提することで、解けていくように思います」
といった。
「白川殺害は本意ではなかった?」
「八木殺しの凶器は金槌。いっぽう白川につかわれたのは、たまたま部屋にあった金庫。すぐそばのキッチンには包丁という便利な道具があったにもかかわらず、です」
「となると考えられるのは、部屋に戻った犯人と、部屋を訪ねてきた白川が、たまたま鉢合わせてしまった可能性ですね」
「その場合は、白川のポケットに二〇一号室の鍵が入っていたという点が気になりますな。鍵をもっていたということは、無断で部屋に入るつもりがあったということです。習慣でもち歩いていたというなら、それ以外の部屋の鍵もないとおかしいでしょうし」
「白川が部屋を訪ねたのには、とくべつな理由があったはずだと」
「そのへんの事情を幸田みつ子が知ってるんじゃないかと期待してるんですが……まあいずれにせよ、犯人は八木を脅威と感じていたにちがいありません」
「脅威ですか。たんなる恨みではなく」
「もちろん恨みもあった。しかし恨みだけであれば、殺しておしまいでしょう。死体を損壊し、遺棄するまではわかる。しかし、そのあと部屋に戻ってくる理由がないじゃありませんか。そうしなければならなかったのは、現在進行形の脅威をとり除く必要があったからですよ」
日野はようやく、柿本のいいたいことがわかってきた。
「犯人が部屋に戻った目的は〈家捜し〉だったというわけですね」
「ええ。そして白川の遺体が損壊も遺棄もされず現場に残されたのは、彼まで身元不明遺体にしたところで、それに見合ったリターンは得られないと考えたからです」
「リターン?」
「出所者が支援団体のもとを逃げだし行方不明になるなんて話はザラにあります。だから八木の失踪だけでは、警察がただちに捜査をはじめることはないだろうと犯人は考えた。そして警察が失踪に興味をもたない以上、もし遺体がみつかったとしても、身元につながる手がかりさえ消しておけば、容易には八木に結びつかないだろうとも考えた。つまり八木の遺体を損壊することには、それに見合うだけのメリットがあると判断したわけです。しかし、アパートの大家まで同時に消えたとなれば話はべつです。警察が事件性を疑う確率は高くなり、そこに身元不明遺体がでたとなれば、すぐに八木や白川と結びつけられてしまう──そう思った犯人は、白川の遺体の処理に手間をかける意味はないと結論し、せいぜいスマホをもち去ることしかしなかった」
一気に捲し立てた柿本は、残っていた麦茶をぐいと飲み干し、
「いや、すみません。検討材料が少ない状態で推論を重ねても、たいして意味はありませんな」
そういって、六年前の捜査で判明している八木辰夫の経歴について話しはじめた。
八木は大学を卒業後、食品加工会社に営業職として就職。ところが三十二歳のときに、接待の場で取引先の担当者を殴り逮捕される。双方が酔ったうえでの諍いであり、警察の勧めに応じて示談が成立し起訴は免れたが、八木はこの件で閑職に追いやられ、その半年後に会社をやめた。それから二か月後、総務部長の不倫を告発する文書と証拠写真が、社長宛で会社に送られてきた。
「総務部長は人事権を握る人物であり、八木を閑職に追いやった当人でした」
会社は八木の関与を疑い警察に相談する。しかしながら、文書に具体的な要求が含まれないことから脅迫にはあたらず、あくまで社長個人に宛てていることから名誉毀損も成立しないだろうといわれ、被害届の提出には至らなかった。
その後どうなったかは、本来警察の与り知らぬところだが、総務部長から八木に相当額がわたったという話が、相談を受けた担当者の耳に聞こえてきたという。
「要するに若い頃から、八木は悪徳探偵の資質をもち合わせていました」
職を転々とした後、八木は三十七歳で県内大手の興信所である〈シリウス探偵社〉の職員となる。だがここでも、期間は三年あまりと長つづきしなかった。優秀と評価されるいっぽう、経費の水増しを疑われて上役との関係が悪化して退職。その直後、シリウスの顧客データが流出するという騒ぎが起こった。
「十年前の二〇一四年五月、北光ウィークリーに、依頼人や依頼内容を記したリストが届いたんです。もちろんリストそのものが紙面に掲載されることはありませんでしたが、大手興信所からの情報漏洩自体は記事になった。おそらく八木は退職前に、会社への復讐の準備をコツコツ進めていたんでしょう。信頼を失ったシリウス探偵社は一気に業務状況が悪化。あえなく廃業です」
いっぽう八木は、シリウスを退職した数か月後に個人事務所を設立。掲げた看板は〈浮気・不倫調査専門〉で、謳い文句は〈探偵はひとり。秘密が漏れる心配なし〉──大手への不信が募ったところで、滑りだしは上々だったらしい。
「それで満足すればよかったんですが、他人の秘密を握ることの旨みを、八木は忘れることができなかった」
六年前、ある男性の依頼で妻の浮気調査を請け負った八木は、彼女の不倫相手が県内で数軒のレストランを経営する既婚のシェフであることを突きとめた。そこでシェフをディナー営業前の店に訪ね、「相手の夫に報告されたくなければ」と恐喝行為に及んだ。
「ところが目論見どおりにいかず、その場でシェフに通報されましてね」
シェフのほうはすでに離婚を考えていて、不貞がバレてそれが叶うのなら、むしろのぞむところだと腹を括られたのだ。
「八木は一旦逃走するも翌日になって自ら出頭しました。店の防犯カメラ映像を証拠に、うちの捜査員が早々に自宅へ踏み込みましたから、それを悟って逃げきれないと思ったんでしょう。というわけで、過去にいろいろありすぎて、今回の殺人の動機が怨恨だとしたら、どこまで網をひろげて関係者をあさったらいいか悩むような小悪党でして」
「まあでも、今回はさすがに十年も二十年もさかのぼる必要はないんじゃありませんか? まずは八木の個人事務所に関わった人物にだけあたればじゅうぶんかと……依頼人や調査対象については、以前の捜査で洗いだしが済んでいるわけですし」
日野がそういうと、相手は困った顔で耳たぶを引っぱった。
「それがですねえ……情けないことに、六年前の捜査では、八木が所持していたはずの調査資料をみつけることができなかったんです。まったくもってコツコツ準備の男ですわ。いざというとき、かんたんには物証がでないよう、ペーパーレスでの業務を心がけていたフシがあります。むかしみたいに、ドラム缶に火を焚いてそこに書類を投げ込むなんて真似はできませんからな」
日野の頭に自分のデスクが浮かんだ。そんな真似ができたら、どれほど爽快だろう。
「押収したパソコンやスマホからも、これといった収穫はありませんでした。クラウドへのバックアップもなし。デジカメにはメディアが入っていなかった」
「しかし、調査資料をどこにも残していなかったとは、さすがに考えづらいのでは」
「複数の被害者が、八木がUSBメモリをつかっていたと証言しています。データは、すべて外付けのデバイスで管理していた可能性が高い。しかし結局それもみつけることができませんでした。出頭までの一日で、いくらでも処分できたでしょうからね」
「メールやアプリの通信履歴は?」
「通信秘匿性の高いアプリを依頼人や脅迫相手にダウンロードさせ、それでのやりとりを強いていました。調査期間終了後は履歴をすべて消去。サーバーにも履歴が残らないため、そこからの追跡も無理でした」
調査費の支払いは現金の手わたしが原則で、口座の入金記録から関係者を割りだすこともできなかったという。
「よく起訴にもち込めましたね」
「その点は八木の自供がありましたし、八木のほうからはでてこなくても、依頼人側の手もとには契約書類や費用の受領書、アプリの履歴などが残ります。他人の手にわたったものまでは、八木も処分できません」
余罪については、照会可能だった半年分の八木の通話履歴から、総あたりをかけるなかで数件の被害が確認された。八木も最初の相談だけは電話で受けざるを得ず、その履歴が残っていたのだ。
いずれにせよ、被害者が申告さえすれば立証は容易だったのだと日野は納得した。しかし、それによって知られたくない秘密が公になるリスクがあり、捜査への協力を拒んだ被害者も多かったにちがいない。
逮捕後、八木は示談交渉に臨まない姿勢を示し、違法行為で入手した金銭の返還を拒否した。恐喝二件と恐喝未遂一件に詐欺一件が加わり、執行猶予のない懲役五年六か月の実刑判決がくだる。さらに探偵業法違反で、罰金五十万円と営業廃止命令といった行政処分を受けた。
「当初被害者たちは、民事で賠償金をとろうという考えだったようですが、捜査による私生活への影響は大きく、刑事裁判の段階で疲弊して訴訟を断念しました。八木は罰金以外の金銭的損失がないまま、この一月まで服役。出所後は、事前にやりとりを重ねていた幸田みつ子のNPOをたよった」
「話をうかがうかぎり、六年前の捜査線上に一切浮かんでこなかった人物が、今回の事件に関連している可能性も……」
「ええ。大いにあり得るということです」
ふたりの刑事は同時にため息をついた。
「まあ、すべては媛上の遺体が八木だと仮定したうえでの話ですが……そうだ日野さん、NPOから借りた写真をみてもらえますか」
柿本がそういって写真をテーブルに置いた。屋外に立てたイベント用テントのなかに立つTシャツ姿の男性。それが八木辰夫なのだという。
「どうです? そちらの遺体と比べた印象は」
写真の八木はこれ以上なく不機嫌そうな表情をしていた。どうですといわれたところで、日野が知る遺体には、その仏頂面と比較すべき顔がない。
「なんともいえません」
そうこたえるしかなかった。
「そうでしょうな。まあ、焦らずとも間もなくわかることです」
「DNA鑑定には、まだ時間がかかりそうでしたが」
「ええ。ですがその前に足紋の照合が済むはずです」
「足紋?」
足の裏の皮膚文様が生涯不変のものであることは日野も知っていたが、指紋や掌紋のようなデータベースが存在しないことから、これまで捜査に活用した経験がなかった。
「なるほど。八木の部屋から採取された足紋と、遺体のそれが合致すれば」
「それもそうなんですが、今回はもっとダイレクトにいけるんですよ。じつは六年前にも、逃走中の八木の家宅捜索において足紋がとられていましてね……」
その際、室内からは複数名の足紋が採取された。それらを容疑者のものと容疑者以外のものに区別して記録するために、逮捕後の八木本人からも直接足紋がとられたという。
「というわけで、そこから身元がわかれば、DNA鑑定自体が不要になります」
そう話す柿本主任の顔は、どこか勝ち誇ってみえた。
3
午後四時。媛上署に戻ると、すぐ課長に呼ばれた。
「駒根署にでかけるのが少し早過ぎはしませんか」
日野のフライングに気づいているのかいないのか、上司の軽い厭味を曖昧にかわし、柿本から得た情報を報告する。黙って聞き終えた課長は、
「このぶんだと捜査の主導権は向こうに移りそうですね」
といってメガネをはずした。
「今後、両署での合同捜査の恰好になるでしょうが、大規模な捜査本部が立つという話はまだないようです」
予算や人員確保の問題に加え、捜査も会議もデジタル技術の利用が進み、管内の捜査本部設置件数はここ数年減少傾向にある。
「とはいえ連続殺人の可能性もある事件ですから、実際には駒根署のバックで県警本部が指揮をとっています。なんでも鷹宮検視官が担当しているとか」
鷹宮の名を口にするとき、課長がデスクに伏せていた目を日野に向けた。やはりなにか察しているようだ。
「どうやら次の異動で、彼を駒根署の署長にという話がでているらしい」
「そのための布石を県警本部が打ったということですか」
「上手くいけば駒根署の鷹宮体制に向けて弾みがつく。彼は、あくまで駒根署が中心となって事件を解決に導いたという構図をのぞむでしょう。うちはそのためのコマとして便利につかわれることになりかねない……日野係長にとっては着任後最初の大きな事件だというのに、がっかりしましたか?」
たしかに少し気は抜けたが、それは落胆とはちがっていた。
「そんなことはありません。県警本部がのぞむように動きます」
「ずいぶん聞き分けがいいですね」
課長はそういって、薄いレンズを布で丁寧に拭きはじめた。それが「もう用はない」という合図であることに、日野は最近気づいた。
課長室をでると、すぐに入江が近寄ってきて、睨むような目を日野に向けた。
「できればわたしを信頼してください」
開口一番、そんなことをいう。
「もちろん、している」
「生活安全課の新人くんみたいに、上司の行動を疑う部下にはなりたくありませんので」
「わかったよ」
そうこたえ、入江と壁のあいだをすり抜ける。腕と腕がわずかにぶつかったが、どちらもなにもいわなかった。
胃が痛みだす予感がして、いいかげん警務課で胃薬を仕入れておこうと部屋をでる。階段を折り返しの踊り場までおりたとき、一階の生活安全課のドアが開き、そこから少年が飛びだしてきた。日野に気づいて急ブレーキで立ちどまる。
はて、媛上中央小学校の職場体験でも入っていただろうか? そんなことを考えながら黙っていたら、少年のほうがパタパタと靴底を鳴らし階段をのぼってきた。たすきがけにしたバッグのストラップが長すぎるせいで、足をあげるたび膝がバッグを蹴りあげた。
「もしかして刑事さんですか? 殺人とか捜査する」
こちらをみあげ、ずいぶんと穏やかでない質問を繰りだしてくる。
「そうだけど、きみは……」
そのとき一階の廊下に重たい足音が響いた。少年は慌てた様子で踊り場まで駆けあがってきて、折り返した先をさらに二段のぼって身を隠した。通用口のほうから羽幌が姿をあらわし、日野に気づかない様子で生活安全課に入っていった。
しゃがんで膝を抱えている少年をみる。
「きみは、いまのおじさんを知ってるのかい?」
「そんなことよりこたえてよ。殺人課の刑事さん?」
「うちに殺人課はない。そういった事件に関しては刑事課の捜査係という部署が──」
大きな音をたて、みおろす先のドアが開いた。今度は羽幌としっかり目が合った。
「日野、子どもがうろちょろしてなかったか?」
日野は黙っていたが、つい視線が横を向いた。
「そこにいるんだな?」
「すまない、バレた」
「もう! どうしてこっちみるのさ」
少年は立ちあがって、踊り場にジャンプでおりた。
「こら。部屋で待ってるようにいわれたはずだぞ」
「だって羽幌さんじゃなく、殺人事件を調べてる人から話を聞きたいんだもん」
「俺を信用できないのか」
「羽幌さんが捜査してるわけじゃないでしょ? 又聞きの情報なら間違ってることもあるよ」
「記憶については、そっちの男のほうがもっと信用ならないぞ。なにしろ昇任試験に四年も落ちつづけてるんだ」
「子どもの前で他人の中傷はやめろ。いいか少年、テストの成績だけがすべてじゃ──」
「死体はほんとにぼくのお父さんじゃないんですか?」
まっすぐな目と質問に、日野はうろたえつつも背筋を伸ばした。
「……ちょっと待ってもらえるかな……おい羽幌、この子はいったい……」
羽幌が無言で階段をのぼってきた。日野を肩で押し退けて少年のそばにしゃがみ、
「いま、この刑事さんに時間をつくってもらうから、部屋のなかで待っていてくれ。いうことを聞いてくれないと、今後ここには入れてあげられなくなる」
そう諭した。少年は返事のかわりに、羽幌のひたいにゴンと頭突きをくらわせると、階段を飛ぶようにおりて生活安全課の部屋に入り、勢いよくドアを閉めた。
立ちあがった羽幌が、右手にもっていたペンの尻でひたいをかく。
「ずいぶん元気な子じゃないか」
「……日野、忙しいところ悪いが、相手をしてやってくれないか。決して聞き分けが悪いわけじゃないんだ」
「まず教えてくれ。あの子はいったい誰なんだ」
「オヌマケンの息子だ」
「オヌマ……ああ、上村杏子の知り合いの夫の……」
「名前はハヤト。小学四年生だ」
羽幌はポケットから手帳をだすとページを一枚破り、そこに〈小沼憲〉〈小沼隼斗〉と書いた。
「上村杏子の知り合いというのが、隼斗の母親で、小沼クミ」
名前がもうひとつ書き足された。〈小沼久美〉。
「小沼憲は〈ハヤ宅〉という配送請負業者の営業担当だったが、十年前の三月、会社をでたあと行方がわからなくなった。退勤の少し前に届いたメールが、彼から小沼久美への最後の連絡だった」
「行方不明者届は」
「消息を絶った二日後に小沼久美が提出し、俺の前任者が受理した」
羽幌の媛上署着任は三年前のことだ。
「蒸発の原因と思えるものはあったのか」
「消費者金融四社からの借金が約二百万」
「貸付期間は」
「行方不明になった時点で、最後の借り入れからは数か月」
仮に返済が滞っていたとしても、命に危険が及ぶほどの金額や期間には思えない。
「夫が消えて、返済はどうしたんだ」
「妻の久美と、憲の母親とで完済している。母親は当時、介護施設に入居していたが、孫の隼斗が小学校にあがる前に亡くなったと聞いた。憲の父親は、すでに他界していた」
「小沼憲……生きていれば四十二歳だといったな」
「ああ。そうだ」
その返事に、日野は首を横に二度振った。
「いいか羽幌、そんな名前の人間は県警の行方不明者リストには載っていない。俺は遺体の身元調べのため、データベース上の四十代から五十代の男性をあたったばかりなんだ」
「そりゃあ、そうだろうさ。届はとりさげられている」
「なぜ」
「なぜって、少しは頭を回せ。十年だぞ?」
いわれたとおり少し考えて、気づく。
「……失踪宣告を受けたということか」
ある人物の行方がわからなくなり、生死不明のまま七年が経過すると、家族は失踪宣告の申し立てをおこなうことができるようになる。家庭裁判所によって失踪宣告の審判がなされ、それに応じて失踪届を提出すれば、行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、家族は遺族となる。
「失踪宣告がなされ、妻のほうは、それでようやく気持ちの整理をつけることができた。ところが子どものほうは、遺体もないのに『父親は今日で死にました』といわれても、そうですかとは納得できなかった。市内で身元不明の男の死体がみつかったと報じられるたび、自分の父親じゃないかと気になって、しかたなくなるのさ」
「いつもひとりでくるのか」
「最初は二年前の十一月だった。そのときは隼斗がひとりできた。ホームレスの男性が公園で凍死してな。発見の二日後に八歳の子どもがあらわれて、『死体がぼくのお父さんかたしかめにきました』なんていうもんだから面食らったよ。ただ名前を聞けば、すぐに事情が飲み込めた。失踪宣告の申し立てと行方不明者届のとりさげについて、母親である小沼久美の相談にのったのは俺だったからな」
そのときの遺体は、推定年齢からして、明らかに小沼憲とは別人だった。
「母親に連絡して隼斗を迎えにきてもらったんだが、目の前で子どもがこっぴどく叱られるのをみるのは、他人であってもつらいもんだな。次が約一年前。上村杏子が『小沼隼斗くんの代理です』といって、交通事故死体の確認にやってきた。最初はなにをいっているのかわからなかった。どうやら隼斗は、警察署にいって自分の名前をだせば俺に話がとおるはずだと、彼女に伝えたらしい」
「たった一回の対応で、ずいぶん子どもの信頼を勝ち得たじゃないか。俺は娘ができてだいぶ経つが、いまだに疑いの目を向けられている」
「茶々を入れるな。彼女が放課後児童クラブで働いていることはいったな? クラブにきていた隼斗の様子がおかしいんで、どうしたのかと訊いてみたら、事故の被害者が身元不明だというニュースを知って警察署にいきたいけれど、母親には知られたくないというジレンマで落ちつかなくなっていたそうだ。そこで上村杏子が力になった」
この件も被害者は高齢男性だったので、彼女はすぐに納得して帰った。
「三度目は約半年前。そのときは上村杏子が隼斗をつれてやってきた。いや、逆か。隼斗が上村杏子を引っぱってきたんだ。それまでとちがい、遺体の年齢は四十代から五十代と発表されていたから、隼斗も今度こそはと緊張したんだろう。しかし、ふたりが窓口に顔をだす十五分前に指名手配中の強盗犯と指紋が一致し、逃走の末の自殺だとわかった。そして今日が四度目というわけだ」
「上村杏子にはきちんと説明して帰ってもらったんだろう?」
「ああ、隼斗も彼女から結果は伝えられている」
「それなのに、なぜ。血液型がちがうというだけでは納得しなかったのか」
「隼斗曰く、父親の血液型がAB型というのは、母親からそう聞かされただけだから、もしかしたら間違っているかもしれないと。あとは、俺が被害者の血液型を聞き間違えた可能性も疑っていた。だから担当の刑事に直接話を聞きたいそうだ」
「実際のところ、父親の血液型がAB型じゃない可能性が?」
「それはない。行方不明者届には小沼憲が過去に献血した際の検査通知も添付されていた。たしかにAB型だ」
「……しかたないな」
子どもの相手をしても、警務課の退勤までには間に合うだろう──そう思ったとき、自分を呼ぶ入江の大声が階段の上から聞こえてきた。
「どうやら急ぎらしい。悪いが、もう少しだけあの子を待たせておいてくれ。なるべくはやくいく。……ところで日曜なのに出勤しているのは、この事態を予見していたからか」
「うちの近所の北光ウィークリー購読率は高いんだ。昨日の今日でのんびりしていたら、なにをいわれるかわからん」
羽幌は媛上の生まれだ。亡くなった両親の建てた家に、彼はひとりで住んでいる。
午後四時半。捜査係室に戻ると、入江が書類を手に駆け寄ってきた。
「足紋が一致したそうです! 遺体の身元は八木辰夫です」
入江の声が興奮を隠しきれずに上擦る。
「八木が容疑者候補から完全にはずれたとなれば、いよいよ捜査本部が立ちますかね」
「立つとしても駒根署にだ。俺たちは、お手伝い要員に決定だよ」
「どうしてそんないいかたするんですか。遺体のひとつは媛上でみつかったんです。どこに本部が立とうと、わたしたちの事件であることに変わりありません。係長がそういうつもりでいてくれないと、ほんとうに駒根署に主導権を──」
「そうだ入江、いちおう写真をわたしておく」
話を遮られたせいか、入江は唇を嚙んで写真を受けとった。
「駒根署からコピーをもらった。それが最近の八木辰夫だ」
十秒ほどだろうか、それをみつめていた入江が、
「……とくに毛先に特徴があるわけじゃありませんね」
そんなことをいった。
「係長がおっしゃったじゃないですか。犯人が遺体を丸刈りにしなかったのは、毛先に特徴があって、そこだけとり除きたかったからだと」
「決めつけたわけじゃない。そういうケースもあり得るという話だ」
写真の八木は、ウェーブのかかった髪を、耳が隠れる長さまで無造作に伸ばしているだけだった。
「遺体の印象を少しでも変えたかった。その解釈じゃ満足できないのか?」
「……いえ、そういうわけじゃないんですけど」
「会議は何時からだ」
「六時半です」
「資料をまとめておいてくれ。ちょっと羽幌のところへいってくる」
「こんなときにですか? 事件に集中してください」
「集中してるさ。すぐに戻る」
最後は互いに声を荒らげていた。
午後四時四十分。生活安全課の応接室に入ると、羽幌と小沼隼斗が、テーブルの上の十円玉を指で弾いてぶつけ合っていた。
「まさか勝敗にコインを賭けてないだろうな? 場合によっては賭博罪が成立する」
ふたりは日野のジョークに微塵も反応しなかった。隼斗の鋭いショットが決まり、羽幌の十円玉がテーブルの外に弾き飛ばされた。
「まいった。これで十連敗だ」
羽幌が床からコインを拾って天を仰いだ。その芝居がかった仕草に、隼斗は両手のガッツポーズでこたえた。
「十回勝ったらジュースをおごってくれる約束だよ」
「なにがいい?」
「コーラ」
「歯が溶けるぞ」
隼斗は「お母さんみたいなこといった!」と、二人掛けのソファーの上で足をバタバタさせた。
「買ってくるから、話していてくれ」
羽幌がいなくなり部屋がだいぶひろくなった。日野もソファーに座り、「お待たせしました」と、わざとかしこまって挨拶する。
「とんでもないです」
少年は膝に手を置き、背中をピシリと伸ばした。
「小学四年生ってことは、十歳かな」
「誕生日が九月だから、まだ九歳です」
やや長めの髪は汗に濡れて、ところどころに小さな束をつくっては、頰やひたいにはりついている。瞳は日野を中心に部屋のあちこちへ忙しく動き回っていた。
「上村杏子さんがやってきて、羽幌のおじさんから、遺体がきみのお父さんではないと聞いて帰ったはずなんだけど、それでは納得できないわけだね?」
「はい。今日の新聞に、四十代か五十代の男性って書いてあって」
「隼斗くんのお父さんはたしか……」
「今年で四十二歳です。お母さんより三つ上で、羽幌さんよりはひとつ年上。そういえば日野さんも羽幌さんと同い年なんでしょ? さっき聞きました」
屈託なく訊ねてくる。娘が小学四年生だった頃も、こんな感じだったろうか。
「死体の一部が切断されてたって、そう書いてありました」
「まあ、うん、そうだね」
「だから誰の死体なのか、すぐにわからないんでしょ?」
「そういうことになるね」
「逆にいえば、その人がぼくのお父さんじゃないって決めつけるのも簡単じゃないってことだと思うんです」
ところどころに、かしこまった口調。
「それなのに杏子先生、すぐに納得して帰ってきたみたいだから、それが不思議で」
「たしかに、そんな簡単に済ませていい話じゃないね」
「もちろん血液型がちがうのは聞きました。でもほら、血液型をずっと間違えて憶えてたとか、そういうこともあるって聞くし」
「ただね、隼斗くん。お父さんの場合は検査で血液型がちゃんとわかっている。お父さんはたしかにAB型で、みつかったご遺体は間違いなくB型だ」
そう告げると、動き回っていた少年の瞳が、日野の顔にピタリととまった。
「……そうなんですか」
少年は膝の手をグーのかたちに握った。
「それに、ついさっき遺体の身元がべつの人だと判明した。残念だけれど……いや、ご遺体になってお父さんがみつかったわけじゃないんだから、決して残念なことではないんだけれど……」
こんなとき、法律上の死者の生死を、刑事はどのように扱うべきなのだろう。
「お父さんが生きてるなら、べつにどこでなにをしててもいいんです」
グーに視線を落としたまま、隼斗がそんなことをいう。
「だって、ぼくはお父さんのこと知らないし、お母さんとふたりだけでずっと楽しく暮らしてきたわけだし。でも、もしどこかで死んじゃって、誰かわからないまま放っておかれるとしたら、やっぱりみつけて、うちのお墓に入れてあげたいと思う。そりゃ、突然いなくなったことに、ひとことくらい文句はいいたいけど」
「なんて文句をいうのかな?」
つい口にしてしまった質問に、隼斗は少し考えるフリをしてから、
「どうしてお母さんを悲しませることしたの?」
といって照れたように笑い、また自分のグーをみた。
ふたりとも黙ってしまう。気をつかったわけでもないだろうが、エアコンの唸りが大きくなった。ドアが開き、羽幌が紙コップを手に戻ってきた。どうにも胡散臭いタイミングだ。おそらく聞き耳を立てていたにちがいない。
「ほら、コーラだ。砂糖とクリームを多めにしてやったぞ」
日野は思う。羽幌の冗談は、なぜこうもおもしろくないのか。
「おまえはブラックでよかったよな」
日野の前にも紙コップが置かれた。隼斗が尻を滑らせてソファーの奥にずれ、空いたスペースに羽幌が腰をおろした。
「あれ? 羽幌さんのジュースがないじゃん」
「俺はいいんだ。このところ糖分過多でな」
「そういえばタバコもやめたっていってたよね。健康気にしてるんだ」
「初耳だな。タバコから栄養を摂取していたようなおまえが、いつからだ? どこか悪いのか」
羽幌は日野の追及を嫌うように身体ごと隼斗のほうを向き、
「今日は、お母さんには、なんていってでてきたんだ?」
と訊ねた。
「なんにもいってない。仕事でいないから」
「じゃあ杏子先生には?」
「内緒。だって、先生のこと信用してないみたいで悪いもん」
隼斗は彼なりに悩んだ末、ここにくることを決めたようだ。
「そうだ! 杏子先生っていえば、北光ウィークリーに手紙をだしてたね」
「読んだのか」
羽幌の唇が歪む。
「ぼくの詩も少し前に載ったんだよ」
「ああ。上手だったぞ」
「羽幌さん、読んでくれたの?」
「読んだ。びっくりしたよ」
「授業で書いた詩を杏子先生にみせたら、新聞に送ってみたらって、いってくれたの」
顔を赤らめながら、信じがたい角度に紙コップを傾けてコーラを飲む少年の小さな喉仏が、生意気に上下した。
「……で、どうなんだ? こいつ……この刑事さんの説明に、納得はできたのか」
「うん」
「そうか。ならよかった」
「羽幌さんと日野さんは何型?」
「O型だ」
と羽幌。
「A型」
と日野。
「やっぱり、ふたりは相性バツグンだね」
「冗談だろ?」
と羽幌。
「気持ちの悪いことをいうんじゃない」
と日野。
「お母さんは羽幌さんとおんなじO型で、お父さんとの相性は最悪」
やれやれ、星占いの次は血液型占いか──。
「隼斗は何型なんだ?」
羽幌が訊ねる。
「B型。羽幌さんとは相性いいけど、日野さんとは悪い」
これには到底うなずけない。日野の妻も娘もB型なのだ。なにか反論をと思ったところで、隼斗が話題の矛先を変えた。
「ねえ。血液型って一生おんなじ? 突然アレルギーになるみたいに、変わったりしない?」
納得できたとこたえたのは、どうやら噓だったらしい。
「そりゃ、絶対だとは思うが……なあ?」
曖昧にこたえた羽幌が、うかがうような目を日野に向ける。日野は以前受けた法医学研修で得た知識を引っぱりだした。
「小さい頃……それこそ赤ちゃんのときに調べた血液型がちがっていたという話は、あるみたいだね。ただそれも、血液型そのものが途中で変わったわけじゃなく、検査の正確さの問題で、生まれた直後は免疫が弱いことが理由らしい。免疫ってわかるかな? いまきみがいったアレルギーの原因にもなる、身体を異物から守るための仕組み」
「コロナのときにさんざん聞いたからわかるよ」
「血液型を調べるのに、その免疫反応を用いる。だから小さい頃に調べた血液型が、あとで調べたら間違っていたということが起こり得るらしい。ただ、きみのお父さんの場合は、大人になってから調べた結果だから、誤りの可能性はない。ほかに聞いたことがあるのは、たとえば白血病の治療で骨髄移植……骨髄っていうのは血液をつくる場所だけど、その組織をちがう血液型の人からもらった場合、血液型が変わってしまうそうだ」
「そんなことがあるの?」
興奮して腰を浮かせた隼斗を落ちつかせるべく、日野は早口で説明を追加した。
「ただし今回みつかった身元不明のご遺体には、そういった治療の痕はない」
隼斗の尻がくたびれたソファーに沈む。
「輸血とかでも変わる?」
「それでは変わらない」
「じゃあ、死体が入れ替わってる可能性はゼロってこと?」
「入れ替わってる?」
「うん。ドラマでみたことあるんだ。首を切られちゃった死体があって、みんなそれを佐々木さんだと思ってたけど、ほんとうは鈴木さんだった──みたいな話」
「……それ、犯人は誰だったんだい?」
「殺されたと思ってた佐々木さん」
まあ、そうだろうな。
「今回にかぎっては、きみのお父さんのご遺体が、他人のご遺体に偽装された可能性はゼロだ」
「じゃあさ、日野さん。DNA鑑定とかって、むかしからあった?」
「むかしというと」
「お父さんがいなくなった十年前とか」
十年前といえば、自分と妻が三十一歳で娘が五歳。はじめて家族で北海道旅行にいき、小樽で観光船に乗ったら妻がレンタカーの鍵を海に落とした。あれがむかしだって? ついこのあいだのことじゃないか。
「その頃なら、もうちゃんとあった」
「でも〈事件性〉っていうの? ただ行方不明になっただけだと、警察ってそんなに真剣に調べてくれないんでしょ? それもドラマでいってたよ」
なんともこたえづらい質問だった。羽幌と視線を交わし互いに回答権を譲り合う。そうしているうちに、隼斗がバッグのなかをあさりだした。
「このメモ、みてください」
日野は、ふたつ折りの紙を受けとった。
「お父さんが法律で死んだって決まったとき、お母さん、ものをたくさん捨てたの。気持ちの整理だ……って。それをぼくも手伝ったんだけど」
「えらいな」
「えらいとかじゃなく。そのときにこれをみつけて、こっそり抜きとったの。はじめてみるメモだったから。まだ漢字とか読めなかったけど、そのうちわかるようになると思って。ここにある〈ハヤ宅〉って、お父さんがいた会社だよね?」
「お母さんが書いたものを勝手に読むわけにはいかないな」
「だって捨てたんだもん、もうぼくのものだよ」
「警察に拾得物の届出をだしてないだろう?」
「むずかしいこといわないで、いいからみてよ!」
子どもに叱られ、日野は紙を開いた。
2014年
3月21日 ハヤ宅からTEL 横領疑いで調査中 被害約220万
3月24日 ハヤ宅からTEL ローン会社から夫宛に連絡ありとのこと
4月3日 消費者金融4社 元本計190万
4月11日 夫の休職手続き 着服額224万 毎月5万以上の返済
相談とりさげ被害届提出は見送るとのこと
4月23日 義母より200万入金
4月25日 借金清算
「お父さんが行方不明になったのは十年前の三月六日だから、その直後のメモだよね?」
日野は黙って羽幌に紙をわたした。
「お父さんは、会社のお金を盗んだってことだよね。横領って、そういうことでしょ?」
メモに目を落としながら、羽幌は困った顔をしていた。
「お父さんは、盗んだお金を借金で返そうとしたのかな? それでも許してもらえないと思ったから逃げたのかな? でも、そんなかんたんに逃げられると思う?」
小沼憲に借金があったことは羽幌から聞いていた。つまり、妻の久美が警察にそれを話したということだ。しかし横領については初耳だった。羽幌の困惑の表情からは、彼もその件を知らなかったことがうかがえた。
「ねえ日野さん」
思考は隼斗の声に遮られた。
「何年も前にみつかった身元不明の死体を、もう一回いまの科学で調べなおしたら、じつはお父さんでしたって、わかったりしないかな?」
少年の黒い瞳は、刑事をまっすぐみつめていた。
「ほんとは、お母さんだって、お父さんのこと、あきらめられてないんじゃないかな。だって、ぼくにとっては知らない男の人でも、お母さんにとっては──」
「隼斗、そこまでだ」
羽幌がそういって少年の髪に手を置いた。その仕草のあまりのやさしさに、日野はみてはいけないものをみたような気がした。
「警察の仕事は、そんなにいいかげんなものじゃない」
「……ごめんなさい」
「怒ってるんじゃない。お母さんの仕事が終わるのは何時だ?」
「七時」
すでに五時半を回っていた。
「よし。俺が車で送っていってやる」
「ありがとう。でも自転車できちゃった」
「それくらい積んでいくさ」
「ひゃっほう!」
三人同時に立ちあがる。日野はほっとしつつ、ちょっと寂しいような気にもなった。
「ちょっと待ってて羽幌さん! おしっこいってくる」
ずっとがまんしていたのか、隼斗はとんでもない勢いで廊下に飛びだしていった。
エアコンを切った羽幌がこちらをみて、「たすかったよ」といった。娘がいる日野は、自分が子どもに甘いことをよく知っている。だが独身の羽幌までそうだとは意外だった。
「べつに。警察官として、やれることをやっただけさ」
「気どりやがって。こっちが下手にでたからって、急に調子にのるんじゃねえ」
羽幌は靴の底で、エアコンの下にできた小さな水たまりを散らした。
4
日野は署内の倉庫にいき、資源回収用に束ねられた古紙のなかから、最近の北光ウィークリーをさがして抜きとった。羽幌が「上手だった」といった隼斗の詩は、五月十一日の紙面にみつかった。日野は俳句や短歌、詩にイラストといった投稿コーナーに関して熱心な読者ではなく、その詩もやはり読んだ記憶がなかった。
〈うどん屋さん〉
きつねうどんに月見うどん
ぼくの注文は天ぷらうどん
カウンターのおくのちゅうぼうで
あげものをしている男の人と
洗いものをしている女の人が
ずっとおしゃべりをしている
しゃべってばかりいないで
さっさとかきあげをつくってほしいなあ
そう思っていたら
うどんをゆでていたおじさんが
口じゃなくて手を動かすんだ!
とふたりをしかった
ぼくは心のなかでおじさんに
いいぞいいぞとはくしゅをした
ふたりはすぐにあやまったけど
おじさんがうどんを洗いはじめたら
またすぐにしゃべりだした
ぼくはお母さんに
あの人たち反省してないね
といった
そしたらお母さんが
しかたないね
と笑った
どうしてしかたないの?
ときいたら
恋ってそういうものなのよ
といって
お母さんはまた笑った
ようやくあがったかきあげは
えびがたくさんだったのに
ふしぎととってもふわふわだった
小沼隼斗(媛上東小4年)
日野は詩を書くこともなければ、詩について語ることもない。ただ確実にいえるのは、小学四年当時の自分には、たとえ文字の上だろうと恋について口にするなんて、とてもじゃないが恥ずかしくてできなかったということだ。
日野は新聞を捜査係にもって帰り、デスクの上に置いた。ふと気になって、はやくも書類に埋もれかけている昨日の北光ウィークリーを手にとり、上村杏子の投書を読み返す。それによれば、声かけ事案の発生日は五月十三日。隼斗の詩が掲載された二日後のことだ。
日付が近いことに加え、隼斗がかよっているのが媛上東小という点も気になった。不審者のあらわれた鉄南地区にある学校なのだ。
日野は生活安全課に電話をかけた。やや間延びした新人の声が応答する。
「ひとつ訊きたいんだが、例の声かけ事案で被害に遭った児童の名を知っているか?」
「ナカヤマダイヤくんです」
間延びしつつも回答は迅速だった。ダイヤくんには申し訳ないが、日野は隼斗が被害者でなかったことに安堵して受話器を置いた。
北光ウィークリーをデスクに戻し、なおも隼斗のことをぼんやり思い返しているうち、日野はまたべつの不安に襲われた。ふたたび受話器をあげて、今度は医大の法医学教室に電話をかける。幸い教授は、まだ在室していた。
「日野です。解剖いただいた遺体について、ちょっとうかがいたいことがありまして」
「ああ、かまわないよ。きみのは……どっちだったかな」
「どっち……あ、駒根署の遺体も先生のところに?」
「鷹宮くんに無理やりねじ込まれたよ。少し前に済んだばかりだ。そうか、きみのは顔のないほうだったな。で、なにかな?」
「あらためて、いちおう、念のため、失礼を承知で確認したいんですが、たとえば遺体に、骨髄移植を受けたなんて痕跡は、なかったですよね?」
「うん。ない」
「見落とした可能性は」
「そこは信じてくれというしかない」
とくに気を悪くしたふうもなく、医師はそう返事をよこした。
「なんだい急に。血液型が途中で変わった可能性でも検討してるのか?」
「あ、さすがですね。まさかとは思ったのですが、気になってしまって」
「遺体の身元がわかりそうだと聞いたが、もしかして血液型が合致しないなんて話に?」
「いえいえ。そんな面倒なことじゃないんです」
礼をいって電話を切り、大きく息をつく。なんだって俺は、よけいなことに頭を回してるんだ──?
カフェインのとりすぎかもしれないと考え、日野は少しコーヒーを控えようと決めた。とはいえ、すでに気になってしまったものを放っておくことはできず、結局身元不明遺体の検索をはじめてしまう。とりあえず県内に範囲を絞り、二〇一四年三月以降に発見されたものについてデータをさかのぼった。
最初に気になったのは、〈16A〉というコードがつけられた、二〇一六年の五月に発見された遺体だった。
みつかったのは駒根市北部の山中。一部が白骨化した遺体は、深さ一メートルほどの人の手で掘られた楕円形の穴に、全裸の状態で埋められていたという。発見者は山菜とりにきた入山者。年月を経て穴の覆土の土嵩が著しく減少し、骨の一部が露出したらしい。肋骨に刃物の傷があったことから刺殺の可能性が考えられ、死後数年が経過していると推定された。
遺体は、頭蓋骨の顔面部分が陥没していた。おそらくは死後、幾度も顔を叩きつぶされたと考えられている。残っていた頭髪は、耳が隠れる程度の長さだったと推定され、天然の縮毛であることが確認されていた。このタイミングで、八木の遺体と似た特徴をもつ亡骸に出会ったことが、日野をなんとなく落ちつかない気分にさせた。
性別ならびに推定年齢は小沼憲と合致。しかしながら〈16A〉は、彼ではあり得なかった。血液型が一致しないのだ。小沼憲はAB型だが、遺体はO型だった。
日野はさらにデータをさかのぼり、もう一体、引っかかりをおぼえる遺体をみつけた。
二〇一四年の六月に媛上市内の河川敷の叢で発見された〈14B〉は、性別・推定年齢・血液型のいずれもが小沼憲と合致した。全裸の腐乱遺体で、こちらも一部が白骨化し、死因は後頭部の損傷。他殺の可能性も含め捜査したが事件性は未確定のままだった。
小沼憲が行方不明になった三か月後にみつかった遺体であり、当然、彼である可能性は取り沙汰されたはずだ。空気に触れる状態で放置されたほうが、土に埋められたり水に沈められたりした場合より腐敗ははやく進む。短期間で白骨化に至っても不思議はない。
日野は、この〈14B〉と小沼憲との照合が確実になされたのかが気になり、そこまで確認したい衝動に駆られたが、すでに会議の時間が迫っていた。
予定より少し遅れて、六時四十分からテレビ会議が催された。
連続して起きた二件の殺人に関し、いまだ捜査本部が立つという話がないことが不思議ではあった。県警本部から捜査上の指示はあるようだが、実際に人員が派遣されてくることはなく、ふたつの所轄署のみでの合同捜査という恰好がつづいている。
駒根署の柿本主任が、白川清の司法解剖と現場の鑑識結果を報告した。死因は脳挫傷。凶器は室内にあった重さ八キロ弱の小型金庫。白川は比較的小柄であり、犯人は彼の右前頭部めがけ、両手で掲げた金庫を真上から振りおろしたとみられる。
金庫から採取された指紋群は、過去の逮捕時に採取されている八木辰夫の指紋と一致した。死亡時刻の前後から、八木が白川を殺した可能性はないため、殺害犯は手袋等をつけた状態で犯行に及んだと推測される。
柿本が作成した資料には、ごく簡単な時系列が記されていた。
6月27日午前8時~28日午前8時 八木辰夫死亡
? 八木の死体遺棄
? 白川清が八木の部屋を訪問
6月28日午後2時~深夜0時 白川死亡
29日午前5時40分頃 八木の死体発見(佐竹亘)
30日午前6時頃 白川の死体発見(幸田みつ子?)
柿本は、すでに日野が聞いているところの、現時点での読みを披露した。本件は連続殺人だが、犯人の狙いはあくまで八木であり、白川殺害は偶発的あるいは付随的なものだった──。
つづいて日野が、八木の死体遺棄について捜査状況を説明した。現場付近で不審な目撃情報は依然としてあがらず、この点で唯一進展といえるのは、比目橋の道路カメラのデータが南武署経由で取り寄せられたことだった。目下、媛上署の捜査係内に専従班を設けて映像解析を進めている。とはいえ交通量はそれなりに多く、総あたりでの車両追跡は現状無意味かつ不可能に等しい。
そこに柿本が情報を付け加えた。
「足紋から遺体の身元が確定したため、八木の部屋の備品を用いたDNA鑑定は、すでに中止となっています。媛上署から提供のあった、八木の下着に付着していた頭髪についてですが、こちらの現場から特徴の似たものはみつかっていません。浴室の排水管から大量に採取された毛は、死後に切られた八木の頭髪と思われます。あとはそちらの通報者……ええと、佐竹亘ですか。彼は死体遺棄には無関係との見解でしたが、家族含め、過去に八木との接点がなかったかは再度確認いただきたいところです。とはいえこちらの関係者も含め、そのへんをどう確認するかが難儀な部分なんですが」
八木のスマホの通信履歴については、携帯電話会社に照会申請中。ただし有力な情報が得られるかについては見込み薄というのが、柿本の考えだった。彼は手もとの資料をめくりながら、さらに発言をつづけた。
「こちらの現場の近隣住民から、事件に関わる目撃情報は、いまのところあがっておりません。ただ一点、二キロほど離れた個人商店に、二十八日の午後四時頃、不審な挙動の女性が来店しています」
それを聞いた入江が、うかがうような視線を向けてきたので、日野は首を横に振りながら、「聞いていない話だ」と伝えた。マスクをつけたその女性は、会計時にも不自然に顔を逸らし、それゆえ店主の記憶に残ったらしい。
「……この店に防犯カメラはなく、よって人相や来店手段などもわかっていませんが、少なくとも常連客ではなかったとのことです。店主の印象では年齢三、四十代」
ここで入江が挙手して、
「その女性に着目したのには、とくべつな理由があったんでしょうか?」
と質問した。柿本は両隣の捜査員に目配せをしてから、
「現場の浴室および廊下に、塩素系漂白剤を使用して血痕等を除去しようとした痕跡がみつかりました。しかし該当する洗剤の類は室内にみあたらず、犯人が使用後にもち去った、あるいは持参してもち帰った可能性を検討していたのですが、いま申しあげた女性客の購入品というのが、まさに漂白剤だったことから関連を調べています」
そう回答して、話を先に進めた。
「最後に現場アパートの階段下から回収した、ダルマのボトルに関してですが……」
入江がダルマという呼称を知らなかったので、ウイスキーのことだと伝える。
「……瓶はキャップシールが剝がれた状態、要は開封済みでした。こぼれていた液体の量を鑑識で見積もった結果、中身はほとんど減っていなかったようです。状況からして、ボトルは幸田みつ子が所持していたものであり、階段から落ちた際にトートバッグから飛びでて割れてしまったと推察されます。興味深いことに、割れたガラスの表面から、鮮明な指紋が二種類採取されました。一点は当然幸田のものと思われますが、問題はもう一点で、八木辰夫の指紋と一致しました」
入江がまたこちらをみてきたので、先ほど同様首を横に振った。
「ぜんぜんうちに情報が流れてきてません」
彼女が小声で訴えてくる。
「向こうには向こうなりの進めかたがあるんだろう」
「係長も少しは腹を立ててくださいよ」
「いいから聞け。まだ話はつづいている」
「……このあたりの事情も含め、幸田の話を聞くことで事件の経緯がある程度明らかになるのではないかと期待しているところです。医師によれば明日の朝には事情聴取が可能ということで……日野係長、午前九時に現地集合でお願いできますか?」
「わかりました」
課長のいったとおり、捜査の主導権は完全に駒根署に移っていた。
会議後、とりあえずは佐竹亘に、「八木辰夫という人物に心あたりがあるか」を直接訊ねてみようと電話をしたが、何度かけても彼はでなかった。
「明日にするか」
午後九時。入江が先に部屋をでていき、日野も帰り支度を終えて立ちあがった。部屋のライトを消して回り、肩を落として廊下にでたところへ、入江が走って戻ってきた。
「どうした、忘れものか」
「羽幌課長が佐竹亘を引っぱったみたいです」
「なんだって?」
「係長は、ご存じなかったんですか」
部下から不信の目が向けられる。
「知らない。ほんとうだ。不法投棄は厳重注意で済ませたんじゃなかったのか」
「わたしだってそう思ってました。しかも任意じゃなく逮捕みたいで」
「逮捕……誰から聞いた?」
「新人くんです。生活安全課から大声がしたんで覗いてみたら、デスクの新人くんと目が合って。『なんの騒ぎ?』って訊いたら『逮捕した佐竹の聴取中です』って。『まだしばらく帰れないのかなあ』って。バカみたいな顔して」
「入江、発言に気をつけろ」
会議以降、彼女の機嫌はすこぶる悪かった。
「とにかく俺もいってみよう」
一階に駆けおり、入江につづいて生活安全課に入る。眠そうな新人の席の背後に取調室があり、そこから男ふたりの怒声が漏れ聞こえた。
「なにがあったんだ。どうして佐竹を逮捕する必要が──」
新人を問い詰めようとしたとき、さっき日野が閉めたばかりのドアが開いた。振り返ると、ひとりの男が震えながら廊下に立っていた。
「佐竹亘!」
入江がめずらしく叫んだ。
「ど、どうして?」
「どうしてだと? おまえらが呼んだんじゃないか!」
佐竹亘も叫んだ。すると今度は取調室のドアが開き、なかから羽幌がでてきた。
「よう。騒々しいな。どうした」
羽幌だけが、いつもと変わらぬ顔をしている。腹が立って日野は思わず詰め寄った。
「佐竹が逮捕されて聴取中だと聞いたから飛んできたんだ。新人と口裏を合わせて噓をつくとは、どういうつもりだ」
「なにが噓だ。こっちは間違いなく佐竹シチロウの聴取中だ」
「……シチロウ?」
「そいつの父親だ」
そいつと呼ばれた佐竹亘は、まだ若干震えながら部屋に足を踏み入れた。まっすぐ羽幌に近づき、少しみあげて睨みつける。
「なんで父さんを逮捕したんだ」
「理由なら伝えたはずだ」
「どうせすぐ釈放するくせに」
「それはわからん」
「帰ってきたら父さんはもっと乱暴になる。おまえのせいだといって姉さんにどんな仕打ちをするかわからない」
「そうしたら、また逮捕するさ」
「姉さんは、ぎりぎり耐えてたんだ。まだ耐えられる範囲だったんだ。ゴミ集めに文句をいわなければ、俺たちが従順でさえあれば、父さんはむかしのやさしい父さんだった。でも、これでもうおしまいだ。父さんをひとりにするわけにはいかない。姉さんはこの先も父さんと暮らすしかない。それなのに、なんてことしてくれたんだ」
「犯罪はよくない。俺がいえるのはそれだけだ」
羽幌はそういい残し、取調室に戻った。新人が佐竹亘に近づき、
「あっちの応接室で待っていてもらえますか。このあと、お話をうかがいたいので」
そういって、なお怒りに震えつづける佐竹亘を奥の部屋にとおした。いったん戻ってきて、冷蔵庫からお茶のペットボトルをとりだした新人に、入江が訊ねる。
「ちょっと、どういうことなの?」
両手にボトルをもった新人が、振り向くついでに二の腕で冷蔵庫の扉を閉め、質問にこたえた。
「佐竹シチロウは、娘に暴力をふるっていました。佐竹亘の姉に、です。隼斗くんを家に送った帰りに、課長は佐竹の実家に寄ることにしました。日野係長からゴミ屋敷だと聞いて、その状況を確認するためにです。なにしろそれが不法投棄の原因でもあったわけですから、放っておくわけにいかなかったんだと思います」
日野は、自分が羽幌に、佐竹亘にしてやれるアドバイスはないのかと訊ねたことを思いだした。
羽幌の訪ねに応じて玄関先にでたのは、やはり亘の姉だったという。
「顔をずっとハンカチで隠しているのが気になったそうです。とってもらうと、唇にまだ生々しい傷があって。彼女は、ついさっき転んでぶつけたんだと弁解したようですが、課長は家のなかに踏み込みました。酒に酔った父親の右手の指の甲に血がついているのをみつけ、その場で緊急逮捕に」
「姉はいま?」
「課長に呼ばれて、ぼくが病院へつれていきました。顔以外にも何か所か痣があり……」
昨日会った姉の恰好を思いだす。暑いなか、彼女は厚手の長袖で腕を隠し──。
「父親は課長が連行し、亘には電話で署にくるよう求めて、それで先ほどのひと幕です」
そのとき取調室のドアが開いて、また羽幌がでてきた。ドアが閉まる直前、「親が子どもに罰を与えてなにが悪い!」と、気の滅入るセリフが聞こえた。新人は、お茶のペットボトルを手に、亘のいる応接室へ入っていった。
日野と羽幌の目が合った。
「俺から佐竹の実家の様子を聞いた時点で気づいてたのか?」
「会いもせずに、わかるわけがないだろ」
「わたしは彼女と話したのに、なにも気づけませんでした」
入江がそういった。その声は少し震えていた。
「おまえらは殺人事件の捜査にでかけたんだ。俺は、こういうのをみつけるのが仕事だ」
「羽幌。佐竹亘がいったとおり、このあとがたいへんだぞ」
「ああ。しかし見過ごすわけにはいかない。警察官として、やれることをやるしかないんだからな」
返し技をくらった日野は、羽幌から目を逸らすと、応接室に入っていった。亘はソファーに腰掛けて足を開き、太腿に肘をついて両手をきつく握り合わせていた。
日野は彼に呼びかけた。
「俺からひとつだけ訊かせてほしい」
こちらを向いた亘の目に涙がたまっていた。こぼれ落ちそうで決してこぼれない。おまえたち警察の前で泣くものかと、彼は心に決めているのだ。
「八木辰夫という名前を知っているか」
「知らない」
「わかった」
日野と入江は生活安全課をあとにした。捜査係の六月が終わった。