

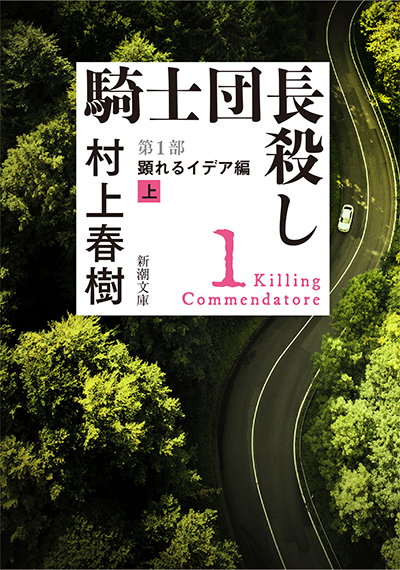 購入する
『騎士団長殺し』試し読み 第5回
購入する
『騎士団長殺し』試し読み 第5回
もうひとつ、肖像画を描くにあたって、私は最初から一貫して自分のやり方を貫いた。まずだいいちに、私は実物の人間をモデルにして絵を描くということをしなかった。依頼を受けると、最初にクライアント(肖像画に描かれる人物だ)と面談することにしていた。一時間ばかり時間をとってもらい、二人きりで差し向かいで話をする。ただ話をするだけだ。デッサンみたいなこともしない。私がいろんな質問をし、相手がそれに答える。いつどこでどんな家庭に生まれ、どんな少年時代を送り、どんな学校に行って、どんな仕事に就き、どんな家庭を持ち、どのようにして現在の地位にまでたどり着いたか、そういう話を聴く。日々の生活や趣味についても話をする。だいたいの人は進んで自分について語ってくれる。それもかなり熱心に(たぶんほかの誰もそんな話を聞きたがらないからだろう)。一時間の約束の面談が二時間になり、三時間になることもあった。そのあと本人の写ったスナップ写真を五、六枚借りる。普段の生活の中で自然に撮影された、普通のスナップ写真だ。それから場合によっては(いつもではない)自分の小型カメラを使って、いくつかの角度から何枚か顔の写真を撮らせてもらう。それだけでいい。
「ポーズをとって、じっと座っている必要はないのですか?」と多くの人は心配そうに私に尋ねる。彼らは誰しも肖像画を描かれると決まった時点から、そういう目に遭わされることを覚悟していたのだ。画家が――まさか今どきベレー帽まではかぶっていないだろうが――むずかしい顔つきで絵筆を手にキャンバスに向かい、その前でモデルがじっとかしこまっている。身動きしてはならない。そういう映画なんかでお
「あなたはそういうことをなさりたいのですか?」と私は逆に質問する。「絵のモデルになるのは、馴れない方にはかなりの重労働になります。長い時間ひとつの姿勢を保たなくてはならないから、退屈もしますし、けっこう肩だって凝ります。もしそれがお望みであるのなら、もちろんそうさせていただきますが」
当たり前の話だが、九十九パーセントのクライアントはそんなことをしたいとは望んではいない。彼らはほとんどみんな働き盛りの多忙な人たちだ。あるいは引退した高齢の人々だ。できることならそんな無意味な苦行は抜きにしたい。
「こうしてお会いしてお話をうかがうだけでもう十分です」と私は言って相手を安心させた。「生身のモデルになっていただいても、いただかなくても、作品の出来映えにはまったく変わりありません。もしご不満があれば、責任を持って描き直させていただきます」
それから二週間ほどで肖像画は仕上がる(絵の具が乾ききるまでに数ヶ月はかかるが)。私が必要とするのは目の前の本人よりは、その鮮やかな記憶だった(本人の存在はむしろ画作の邪魔になることさえあった)。立体的なたたずまいとしての記憶だ。それをそのまま画面に移行していくだけでよかった。どうやら私にはそのような視覚的記憶能力が生まれつきかなり豊かに
そのような作業の中でひとつ大事なのは、私がクライアントに対して少しなりとも親愛の情を持つということだった。だから私は一時間ほどの最初の面談の中で、自分が共感を抱けそうな要素を、クライアントの中にひとつでも多く見いだすように努めた。もちろん中にはとてもそんなものを抱けそうにない人物もいる。これからずっと個人的につきあえと言われたら、
そのようにして私はいつの間にか、肖像画を専門とする画家になっていた。その特殊な狭い世界ではいくらか名前を知られるようにもなった。私は結婚するのを機に、その四谷の会社との専属契約を打ち切って独立し、絵画ビジネスを専門とするエージェンシーを介し、より有利な条件で肖像画の依頼を引き受けるようになった。担当者は私より十歳ほど上で、有能で意欲的な人物だった。独立して、もっと大事に仕事をするようにと彼が私に勧めてくれたのだ。以来、私は多くの人の肖像画を描き(多くは財界と政界の人々だった。その分野では著名人だということだが、私はほとんど誰の名前も知らなかった)、悪くない収入を得るようになった。しかしその分野における「大家」になったというわけではない。肖像画の世界はいわゆる「芸術絵画」の世界とは成り立ちがまるで違う。写真家の世界とも違う。ポートレイト専門の写真家が世間的な評価を受け、名前を知られることは少なからずあるが、肖像画家にはそんなことは起こらない。描いた作品が外の世界に出ていくこともきわめて
ときどき自分が、絵画界における高級
自ら望んでそのようなタイプの画家になったわけではないし、そのようなタイプの人間になったわけでもない。私はただ様々な事情に流されるままに、いつの間にか自分のための絵画を描くことをやめてしまった。結婚して、生活の安定を考慮しなくてはならなかったことが、そのひとつのきっかけになったわけだが、そればかりではない。実際にはその前から既に私は「自分のための絵画」を描くことに、それほど強い意欲を抱けなくなってしまっていたのだと思う。私は結婚生活をその口実にしていただけかもしれない。私はもう若者とは言えない年齢になっていたし、何かが――胸の中に燃えていた炎のようなものが――私の中から失われつつあるようだった。その熱で身体を温める感触を私は次第に忘れつつあった。
そんな自分自身に対して、どこかで私は見切りをつけるべきだったのだろう。何かしらの手を打つべきだったのだろう。しかし私はそれを先送りにし続けていた。そして私より先に見切りをつけたのは妻の方だった。私はそのとき三十六歳になっていた。
村上春樹メールマガジン登録