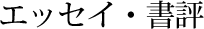ジョン・ラッセルは無口な奴
私には小説を書くうえでどうしてもふり払えない作家が数人いる。彼らは折に触れて私の仕事に口を出し、ときに冷笑を浮かべ、ときに拳骨をふりまわし、唾を飛ばしてわめき散らす。私はいつもまるで一兵卒のように気を付けの姿勢を崩せない。そのような存在をおそらく神と呼ぶのだろうが、それとも少しちがう。なぜなら、作家なんて死ねばどうせ地獄へ堕ちるのだから、彼らが神であるはずがない。
私にとってのエルモア・レナードは、やはり鬼軍曹のような立ち位置かもしれない。新兵時代にレナード軍曹にさんざんしごかれたおかげで、どうにかこうにか今日まで作家業という戦場を生き抜くことができた。意表を突くユーモアや緊迫した場面でのはぐらかし方、愛嬌ある人物像、清濁併せ呑む生き様など、すべてレナードの現代犯罪小説から学んだ。もちろん、めいっぱい楽しみながら。そのうちのいくつかは苦労しつつ原文でも読んだ。もしもレナードの小説に出会わなければ、そもそも作家になることすらおぼつかなかった。
そんな敬愛するレナード先生の作品群のなかで、これまで手を出せずにいたのが初期の西部小説だ。理由は簡単。邦訳されていなかったから。私は本書『オンブレ』のみならず、彼の他の西部小説もペーパーバックでちゃんと持っている。しかし英語が不如意なので、それらを原書で読むのに必要なだけの覚悟をかき集めることができなかった。そんなわけで、このたびの翻訳刊行は私にとって望外の喜びだ。ぶったまげてしまった。村上印のエルモア・レナードを読める日がくるなんて、いったい誰に想像できただろう。
西部劇ではよく見られることだが、本書も時代の節目を舞台にとっている。時は19世紀後半のアリゾナ、まさに蒸気機関車が駅馬車にとってかわろうという歴史的過渡期だ。古い価値観がすたれ、合理的で殺伐とした新たな価値観が台頭している。西部劇的英雄が産まれ落ちるのは、いつだってこうした新旧価値観がせめぎ合う狭間なのだ。ジョン・ラッセルも例外ではない。けっして言い訳を口にせず、軽々しく打ち解けたりもしない。しかも、彼の世界の崩壊はもうとっくに始まっている。アパッチ族に育てられた白人のジョン・ラッセルは、滅びゆく部族のアイデンティティを胸に、それでもどうにか白人社会に適応しようとしている。
遺産として相続した土地を売り払うために、ジョン・ラッセルは駅馬車に乗り込む。クセもウラもある他の乗客たちは、彼の非白人的な部分に眉をひそめる。アパッチ族なんかと同道したくないと騒ぎ立てる。そこへならず者の一味が襲いかかってくるという筋立てだ。馬を奪われ、人質を取られ、水を奪われた乗客たちは、灼熱の荒野に放り出される。それだけでも絶体絶命なのに、いったん立ち去ったならず者どもは、とある事情によって彼らの追殺をはじめる。生き残る術、戦う術を知っているのはジョン・ラッセルただひとり。さあ、駅馬車御一行の運命や如何に。
若い頃のレナード先生はこんなふうだったのか。私を魅了してやまない彼の現代犯罪小説ほど軽妙でも洒脱でもない。彼が師と仰ぐのはヘミングウェイだけど、たしかにヘミングウェイ的な悲壮感がそこかしこに漂っている。無理もない。この本に描かれているのは、これまた多くの西部劇がそうであるように、滅びゆく古い価値観の美学なのだから。ありていに言えば、笑いどころはほとんどない。ジョン・ラッセルはあまりしゃべらないし、他の登場人物たちも読者の神経を逆撫でするようなことばかり吐きまくる。
嗚呼、それでもやはりレナードはレナードなのだ! いつ読んでも、潔く、揺るぎなくエンターテインメントに徹してくれる。読者の鼻面を掴まえて引きずりまわすあの台詞回しの妙は、このころから冴えわたっていたのだな。ジョン・ラッセルは、そう、カントリー歌手がノスタルジックに歌いあげるようなタフガイだった。ボブ・ディランに歌われたジョン・ウェズリー・ハーディングのように。
さて、本書には「三時十分発ユマ行き」という短編も併録されている。こちらは刑務所行きの汽車に囚人を乗せようとする保安官補の物語だ。短いながらこれまで2度も映画化されている、いぶし銀の1本。最後にもうひと言だけ――ゴッド・ブレス・エルモア・レナード。
(ひがしやま・あきら 作家)
波 2018年2月号より

文庫
オンブレ
エルモア・レナード/著、村上春樹/訳
発売日 2018年2月 1日
605円(定価)