第9回 受賞作品
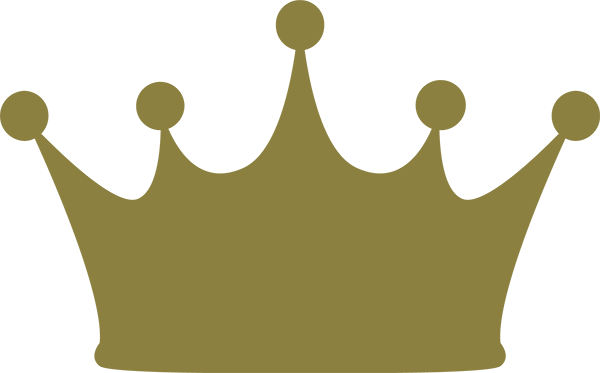 読者賞受賞
読者賞受賞

――受賞おめでとうございます。24歳という非常に若い年齢での受賞ですが、いつごろから小説を書いていらしたのでしょうか。
最初に書いたのは中学2年生、14歳の時です。ファンタジーで、人の身体に生まれながらに身分階級を定める痣(あざ)がある世界が舞台でした。上位の身分にいる主人公が自分の階級に居心地の悪さを感じ、国を出奔していろんな身分の人と交わるうちに、最終的に王である父親を殺してしまうというお話だったのですが、中学生には難しいテーマで、結局未完に終わってしまいました……。父の古いワープロで、300枚ぐらい書いたでしょうか。友達がおもしろがって読んでくれたのがただうれしくて毎日のように書いていました。
――そのころから小説家になりたかったですか。
あこがれはありましたが、親が現実的なほうだったので、実際にそれで食べていこうとは思っていませんでした。父親の仕事の関係でアメリカやスーダンで暮らしたこともあったので、外国と関わる仕事に就きたいとはぼんやりと思っていましたが。その後は女性を主人公にした日常的な短編や童話をぽつぽつ書いていましたが、本格的に書こうと思ったのは大学2年のときです。就職を意識したときに自分の将来に閉塞感を覚え、自分の人生の中で一番のばくちって何だろうと思ったのがきっかけでした。私の母は42歳で他界したのですが、たとえば自分が42歳で亡くなったとしても後悔しないためにはどうしたらいいだろうと考えたのです。それからはすばる新人賞や文学界新人賞、そしてこの賞に応募しはじめました。大学生って暇なので思い定めるとどんどん書けるんです。
――最初に応募された「かたばみ荘の猫たち」が第6回の最終選考に残りましたね。
選考に残るとも、受賞するとも思っていませんでした。もうそのころには友達に読ませるわけでもなく、パソコンの中だけで自分の小説世界が完結していたので、最終選考に残ったときも、選評をいただいたときも現実感のない不思議な感じでした。そのときの選評で山本文緒先生が「文章に安定感がある」と書いてくださったのがうれしかったです。自分ではそんなに安定した文章が書けているとは思っていなかったので。
――最初の選評では「既存の作家の影響が目立つ」「現代の女性作家のものとよく似ている」などと指摘されていました。川上弘美さんをはじめとする現代作家のことを指していたのではと思いますが、その指摘についてはどうお考えですか。
川上さん、実は短編の「おめでとう」を暗記しそうになるくらい大好きなんです。このままではまずいな、と思いました。けれど書き方や文体を変えるというよりは、自分の内面を掘り下げることで別のものにたどりつこうと努めました。それからはわざと川上さんの小説は読まないようにしていたのですが、どうしても我慢できなくて「風花」だけは手にとってしまいました。
――それから今回まで、ずっと応募し続けてくださいました。
作家になれるのではという期待値がもともと低かったので、何度賞を逃してもまったくへこたれませんでした(笑)。ただ、ちゃんと書き続けて、高い水準まで持っていけたら、どこかで届くだろうと思っていました。努力が報われる世界ではないかと思います。いくつになっても書き続けているつもりだったので、あせりなどはなかったです。
――小さい頃からこれまで、どういうものを読まれていますか。
記憶にあるなかで一番最初に印象に残った本は灰谷健次郎さんの『太陽の子』です。それからミヒャエル・エンデの『はてしない物語』も。海外だと気軽に外に遊びに行けないので、家にひとりでいることが多かったんですね。それに自分がなにか選んで読むというより、帰任した日本人の方が置いていったものを読むパターンが多かったです。
ここ数年は少し前の小説を読むことが多くて、寺山修司や坂口安吾、開高健さんなどをよく読んでいます。最近では沢木耕太郎さんのノンフィクション全集を父の本棚から借りっ放しにしています。
――これからどういう作品を書いていきたいですか。
家族や恋愛など、大きなテーマも書きたいのですが、それより一段階手前の、皮膚感覚や物を食べている感覚、死に対する感情など、原始的なものを強く描けるようになりたいです。それらと向き合い続けることで、人間の内側ってこういうものなのではないか、という一つの像を作ることができるようになればと願います。

