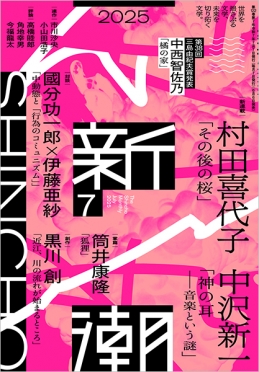【創作】松浦理英子「今度は異性愛」
【対談】奥泉 光×円城 塔「嘘はつかぬが、ほらは吹く──『虚傳集』と『去年、本能寺で』をめぐって」
新潮 2025年10月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2025/09/05 |
|---|---|
| JANコード | 4910049011058 |
| 定価 | 1,200円(税込) |
【創作】
◆今度は異性愛(250枚)/松浦理英子
還暦を過ぎて新しいことを始めてみよう──BL作家の宮内祐子はコロナ禍で、初の「男女物」に挑戦する。多数派の欲望をあえて描くことの困難と野心。老いのユーモアとペーソスが滲む、前作から三年ぶりの待望作!
◆生真面目な時/小野正嗣
小型犬のコジローは、この海沿いの集落での出来事に気づいていた。吠え声とともによみがえる過去の記憶。
【掌篇】
◆父/筒井康隆
ひとり息子がダイビング事故でしばらく浮かんで来ない。おれは素潜りで飛び込んだ。垂直に、海の底へ。
【連作】
◆からの旅 4/小山田浩子
私の政治的態度が理由で、予定されていた仕事が急遠キャンセルに。異国の地で不意にバカンスが訪れた。
◆ルンタ・ホース/高山羽根子
クーデターの影響か、今回の登山許可は下りず。シマモリは頭痛を抱えつつ、旗の意味について考える。
【連載小説】
◆山吹散るか ほろほろと(第3回)/辻原 登
学校法人中根学園の理事長が発作で倒れ、病院に突然、愛人とその娘が押しかける。物語の舞台が整った。
【対談】
◆嘘はつかぬが、ほらは吹く──『虚傳集』と『去年、本能寺で』をめぐって/奥泉 光×円城 塔
史談のスタイルを破壊するのか、模倣するのか。似ているようで違う特異な小説家による二つのアプローチ。
【鼎談】
◆書くという営為とサバイバル(前篇)/石川直樹×角幡唯介×服部文祥
俗世間を離れ、いかに世界に自らを曝せるか──社会の閾値と対峙してきた三人が、冒険の現在を語る。
【批評】
◆小説の死後──(にも書かれる散文のために)──保坂和志、私、青木淳悟/町屋良平
「小説のことは小説家にしかわからない」発言から20年。媒体横断の批評プロジェクト最終篇にして集大成!
【報告】
◆今年、ヴェネチア・ビエンナーレの日本館で/青木 淳
「穴」を介して彼岸と此岸、実と虚とが入れ替わる。建築家が展示によって問う、人間と生成AIの未来。
【リレーコラム 街の気分と思考】
◆北海道で精霊に出会う/マーサ・ナカムラ
◆私にヴァカンスは難しい(まだ)/ゆっきゅん
【新潮】
◆ストリートアートの資料室「ラグサ バイ エイオス」開室によせて/大山エンリコイサム
◆青潮のこと/栗原知子
◆『僕には鳥の言葉がわかる』を出版して/鈴木俊貴
【追悼 田川建三】
◆厳しさと寛容と/松家仁之
【書評委員による 私の書棚の現在地】
◆京都新聞取材班『自分は「底辺の人間」です──京都アニメーション放火殺人事件』/九段理江
◆佐々木 敦『「書くこと」の哲学──ことばの再履修』/山下澄人
【本】
◆グレゴリー・ケズナジャット『トラジェクトリー』/いしいしんじ
◆中西智佐乃『橘の家』/小川公代
◆島口大樹『ソロ・エコー』/川崎 祐
◆平野啓一郎『文学は何の役に立つのか?』/鈴木結生
◆小池水音『あなたの名』/長瀬 海
◆石井遊佳『ティータイム』/古舘佑太郎
◆柴崎友香『帰れない探偵』/松永K三蔵
【連載評論】
◆雅とまねび──日本クラシック音楽史(第10回)/片山杜秀
◆独りの椅子──石垣りんのために(第16回)/梯 久美子
◆小林秀雄(第121回)/大澤信亮
【連載小説】
◆マイネームイズフューチャー(第6回)/千葉雅也
◆湾(第16回)/宮本 輝
◆荒れ野にて(第90回)/重松 清
第57回新潮新人賞 予選通過作品発表
第58回新潮新人賞 応募規定
執筆者紹介
この号の誌面
編集長から
松浦理英子「今度は異性愛」
筒井康隆「父」
◎なんと挑発的なタイトルだろう! 松浦理英子氏による前作以来三年ぶりの小説は、「今度は異性愛」という。コロナ禍の日記形式で展開する本作の語り手は、BL作家の宮内祐子。還暦を過ぎ、初めての「男女物」を書いてみようと意気込んでいる。そして過去の男性との交際を回想し、自分なりのアプローチを試みるのだが、性行為の場面を作るべきか否かという問題が立ちはだかる。彼女が重視するのは、肝心の作品が面白くなるか、そこに緊張感が宿るかだ。やがて日記は、作中作である異性愛小説へと離陸していく──この二重の物語からは、いわばマイナー文学の手つきでマジョリティの描写に取り組む著者の姿が浮かんでくる。身体性への鋭敏さはそのままに、新たな関係に光を当てる傑作が誕生した◎老いのユーモアとペーソスを込めたのが松浦作品だとすれば、筒井康隆氏の掌篇「父」はさらにその向こう側へ手を伸ばしたと言えるだろうか。海で溺れたひとり息子をめぐる神との交渉が、胸を打つ。
編集長・杉山達哉
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?

文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

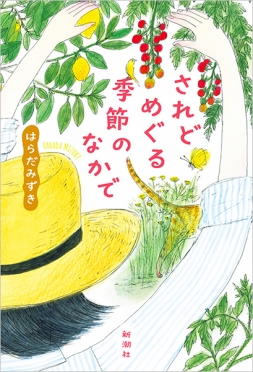

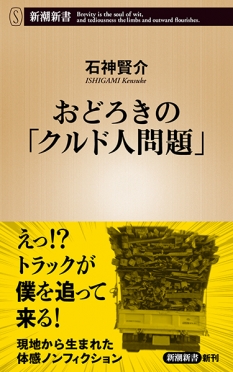




























 公式X
公式X