第16回 受賞作品
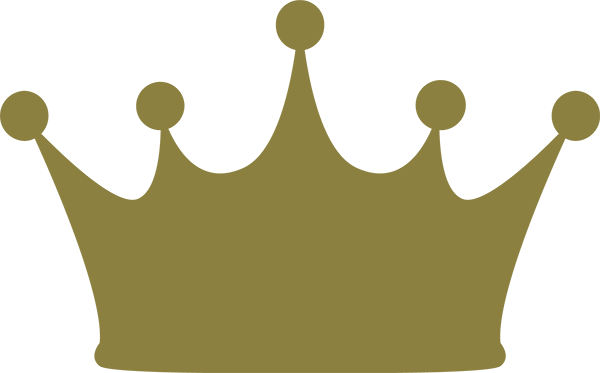 大賞・読者賞受賞
大賞・読者賞受賞

――大賞と読者賞のダブル受賞、おめでとうございます。受賞の知らせを聞いていかがでしたか。
第一声で「嘘!」と叫んでしまいました。選ばれなかったときのショックを考えて、小学生の甥っ子と一緒に映画に出かけていたほどでした。
――R-18文学賞に2014年から3年連続で応募され、初回は三次選考、前回は最終選考に残りました。特に前回の作品については選考委員のお二人から「例年だったら受賞できていた」というお言葉もありました。今回の応募時に何か意識されたことはありますか。
前回の選評は一言一句覚えてしまうくらい繰り返し読みました。三浦しをん先生には「(テーマにした)チェーホフもあの世で喜んでいる」と、辻村深月先生には「この話を必要とする人がいる」と仰っていただいて、とても嬉しかったです。また、三浦先生には「ラストが説教くさいので、読者に委ねるところがあってもいい」という点、辻村先生には「ひねりがなく話の展開が見える」という点をご指摘頂き、今回の応募作では特にそこを意識しました。
――今回は2作応募頂きました。一つは五十代女性、そしてもう一つが受賞した「アクロス・ザ・ユニバース」の女子高生2人の物語です。実は最終候補を選ぶ社内選考で、どちらを残すか票が割れました。全くタイプの違う作品で、またそれぞれの年代の物語がきちんと描ける幅の広さにも驚きました。
ありがとうございます。今回、本当は3本応募しようと思っていたんです。十代、五十代と、あとは仕上がらなかったのですが三十代の女性の物語です。このうち、十代の物語の「アクロス・ザ・ユニバース」を書いたきっかけは、“バスの中で、友達ではない女の子2人が出会う”というシーンが頭に浮かんだことでした。彼女たちはどこに、何をしに行くのだろうと、2人のキャラクターを膨らませていきました。若さゆえに良い・悪いの価値基準が固定化されがちで、打破するのが困難な狭い世界で、必死に立とうとする少女たちを書こうと思いました。
――主人公の智佳はホラー映画が大好きで、妄想の中では様々に残虐な手段で人を殺し復讐をします。その光景が実にリアルに浮かび、また痛快でした。
あんな風に殺しはしませんが、私自身、何か悔しい思いをした時に妄想の中でやり返す、ということがあります(笑)。
小学生の時クラシックホラー映画が好きで、妄想の中の殺人シーンは「13日の金曜日」や「キャリー」などへのオマージュも込めました。それらは小さい頃に見たからか、とても強烈に印象に残っています。
――映画がお好きということですが、小説を書こうと思われたのはいつごろから、またきっかけは何でしょうか。
三十歳を超えてからです。もともと映画業界で、出来上がった作品をデジタル・コンテンツとして展開していく仕事などを担当していました。でも映画製作に携わる方とやりとりをするうちに、「私もゼロから作品を作りたい」、「私も物語を創りたいんだ」と、自分の本心に気が付きました。
ただ、すぐに書けるわけもなく、最初は通信の小説講座を受けたのですが、原稿用紙十枚を書くのもやっとで。小説という形にできたかなと思ったのは、2011年に地方の短編の賞に応募して予選まで通ったときです。それから、2014年に初めてR-18文学賞に応募し選考に残ってからは、長編を書き上げようと小説教室にも通いました。
“小さい頃から本が好きで作家を目指していた”わけではなかったのですが、就学前の数年間は母が自宅で地域の子供たちのための小さな図書室を開いていたので、本に囲まれた環境にいて、また読書家の姉から勧められたものを読んでいました。自主的によく読むようになったのは、アメリカの大学に進学することが決まってからです。有名な文学作品は教養として読んでおこう、と。留学中には日本語に飢えて、膨大な宿題の合間に時々図書館にあった日本文学を読んでいました。実際に書き始めるまでは、自分が小説を書けるなんて少しも思っていなかったのですが、今は書くことがとても楽しいです。
――読者賞を受賞したとおり「アクロス・ザ・ユニバース」には読者からの熱い感想がたくさん届きました。世代を問わず、いろんな人の背中を押す作品だと思います。今後、どういった小説を書いていきたいですか。
書いては捨ててきた沢山のものをきちんと形にしていきたいと思います。また、留学先はリベラルアーツカレッジで、人類学と政治学を専攻していたのですが、自由主義の急先鋒の大学でした。人種、文化、社会階層、性的指向、ジェンダーなど、様々なマイノリティに属する学生たちのるつぼだったんです。この「マイノリティ/マジョリティ」もテーマの一つとして、様々な人たちの価値観が揺さぶられるような物語を書いていきたいと思います。読者の皆さんには是非、本の形でまたお会いできるように頑張ります。

