第13回 受賞作品
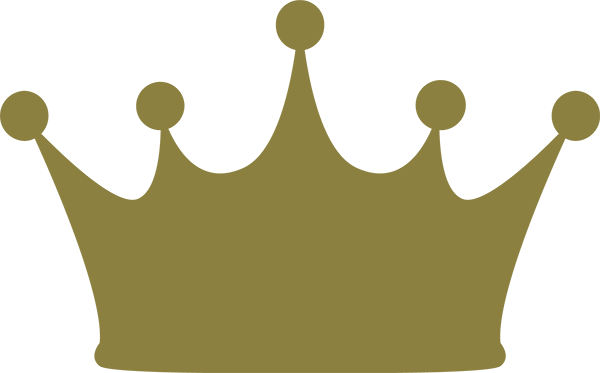 読者賞受賞
読者賞受賞

――このたびは読者賞の受賞、おめでとうございます。受賞と聞いてどう思われましたか。
受賞したときは本当に飛び上がるほど嬉しかったです。でも、2、3日ぐらいすると、今回受賞させていただいた「ただしくないひと、桜井さん」の後にも読むに値するものが書いていけるのだろうかと不安になりました。今は正直、受賞の喜びというものが吹き飛んでしまっていますね。大学の合格発表とか就活で内定が決まったときとかもそうだったのですが、決まった瞬間は喜べても、すぐその後の生活のことを考えて暗くなってしまう性質なんです。大学の入学式の帰り道に泣いてしまったこともあるんですよ。すぐに先が不安になるからこそ、書くことが私にとって一番の精神安定法です。書かないと落ち着かない。
――では、昔から小説を書いていらっしゃったのでしょうか。
つらつらと文章を連ねるということは小学生の頃から行なっていました。教科書の書写でもなんでもいいからひたすら文章を書いていると落ち着く。小説を完結させる形で書いたのは10年ぐらい前で、第2回か第3回のR-18文学賞に応募させていただきました。さらにもう一度応募し、そして今回の3度目で受賞に至りました。
――受賞作を読ませていただいて、どの登場人物にもとてもいきいきした個性が感じられました。例えば性的なことに興味津々で、桜井さんを誘惑しにかかる妖艶なぽっちゃり系女子の星野さん。彼女のキャラクターはどのようにして生まれたのでしょうか。
彼女の体型は私の中高時代の体型とほぼ一緒なのですが(笑)。それはさておき、世の中では、性的なことに関心をもってしまうことが忌避されるような風潮がありますよね。でも、それはなにか違うんじゃないかと。それこそ、痴漢をされた女性は嫌がらなければいけないということだって、決めつけではないかと思うのです。もし、そこで少しでも性的な快楽を感じてしまったら、その子は後ろ指をさされなければいけないのでしょうか。痴漢は犯罪だし、犯罪者側の詭弁に使われるのは論外ですが、たとえ悪いことであったとしても、性的な快楽を感じてしまったことは事実であって、その子にだって救いがあってほしい。酷いことをされたと思わなかったが故に人には言えない苦しみを抱える人だっているんじゃないでしょうか。そういう疑問から生まれたんじゃないかと思います。
――桜井さんは作品の中でちゃらんぽらんな人という風に描かれていますが、藤崎さんが星野さんに対して行なったようなことはしない人のように思えます。だから、タイトルのように、彼は本当に「ただしくないひと」なのかと疑問に思いました。
三浦しをん先生が選評の中で、正しくないって言っているお前は誰なんだ、というとても大切なことを指摘してくださったのですが、このタイトルに込めた気持ちがすごく強くて、掲載のときもこのままのタイトルにしました。
この話では、自分が正しくないことを知っている人間である桜井さん、ということが書きたかったんです。それこそ、藤崎さんは、自分がまさか正しくない人間であるなんてことには思いも至らない。私の友人が藤崎さんについて「空回りの正義感」と表してくれたのですが、まさにその通りで、彼女は自分が正義の意見を持っていると信じて疑わない人です。
大学生だった当時、私は三浦綾子先生のある作品の中で、聖書の一文を抜いて「義人なし、一人だになし」、ただしいひとなどいない、ひとりもいないという口語訳になる言葉に出会いました。正しいひとなんて誰一人として存在しない。正しくないという点において人はみな平等である。それ以来ずっと、そのことが私の中にあります。別段私はクリスチャンではないのですが、そうした特定の宗教とか神とかと切り離されたところであっても、自分は正しくないかも知れない、間違っているかも知れないと自己認識することは、すごく大事なことだと思っています。
――それはとても重要なテーマですし、辛い状況にいる人たちがたくさん出てくる物語なのにも拘わらず、コミカルな要素もありつつ、様々な人に読みやすいような語り口で書いてあったと思います。
普遍的すぎるテーマを念頭に置いて書きましたが、私たちが生きている世界というのは、本当にちょっとした出来事の積み重ねでできていますよね。そういう細かいところを仕草であったり、コメントであったりで、丁寧に書いておきたいという意識がありました。そこをコミカルな要素としても捉えていただけたなら嬉しいです。
――「ぽかぽかハウス」という舞台を設定したのはなぜですか。
この物語を書くとき、私は最初に物語の最後に出てくる手紙を書きました。こういう手紙を母親が子供に向けて書くにはどういう物語の内容にしようか、というところからの発想です。放課後の子供達の居場所として、裕福な家の子だったら塾に行かせられるし、習い事に行かせてあげられるのだろうけれど、そうではない子たちも集える場を舞台にしようと思いました。私も桜井さんのように、塾で先生として教えていたこともあるんですが、子供達から好かれるような先生ではなくて、本当に勉強を厳格に教えるだけのつまらない先生でした。あんまり厳しいので生徒が辞めてしまったことすらあります。でもそれが塾では正しいことだと思い込んでいました。同時期に、HIVの陽性者のサポート団体に属して感染不安の方を対象とした電話相談のボランティアをやっていたのですが、恐らくお金稼ぎの塾という業務とは離れて、相手の話をただただ聞くという自分自身のパーソナリティが必要とされる場所で、心のバランスをとろうとしたのでしょうね。こういうところは、今考えると、桜井さんと通じるところがあるかもしれません。
――桜井さんのバランス感覚の良さはこの物語の魅力ですね。
桜井さんは自分の母親すらもただしくないひとだったことを知っている人。心の奥底に罪悪感にも似た、ものすごく悲しいものを抱えていて、それによっていろんなことを抑圧しながら生きている人だと思って書いていました。私自身は、そういうバランスがとれないんですけどね(笑)。だからこそ、法律とか常識とかで正しくないとされることを、どうしようもなく、正しくないとわかりながらもやってしまうような人のことをこれからも書いていきたいのだと思います。

