第15回 受賞作品
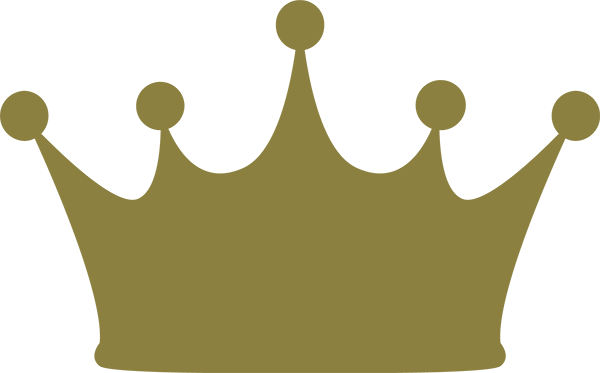 友近賞
友近賞

――このたびは友近賞受賞おめでとうございます。受賞の連絡があった瞬間はどのように過ごされていましたか。
まさにその瞬間は、部屋のソファーでだらっとしていました(笑)。でも応募してからは、祈るように毎日ホームページを見ていました。
夢にまで何度も出てきたんです。今回、受賞作と合わせて2作応募したんですが、私自身はもう1作のほうが気に入っていました。だけどある日、「県民には〜」が受賞するという夢を見て、あれ? って思いました。その後、別の日に、船に乗っている夢を見ました。夢占いによれば、船の夢は現実の物事が上手く行くという意味で、しかも船が大きいほど良いとのこと。でも私が乗ったのは琵琶湖の「うみのこ」という、滋賀の子がみんな小学5年生で乗る学習船だったんです(笑)。これはどう判断したらいいのか……と思っていました。
――さっそく滋賀の話が出てきましたね。受賞作の「県民には買うものがある」は、自分の暮らす場所や囲まれている物のつまらなさに倦んでいる女子高生たちの物語で、滋賀県が舞台です。作中に何度も登場する琵琶湖は、自然にあふれた環境の象徴でありながら、地方の閉塞感にほんの少し、さわやかな風を吹き込んでいました。
私もこの作品の主人公と同じように、滋賀で生まれ育ちました。いまも実家に住んでいます。その家は琵琶湖からは少し離れていて、自転車でも、ましてや歩いてもたどりつけない。車の免許を持たない高校生にとって、家から離れるには車に乗ってる男の人をつかまえるしかないんです。今作にはもともと「移動はセックスで買う」という仮題をつけていました。たとえ付き合っていても、その男の人が単純に好きなんじゃなく、どこかに連れていってくれる装置のように思える瞬間もあるんじゃないかと思います。
ただ、主人公と近いかといえばそうでもありません。私よりも彼女のほうがおしゃれで、現実に適応していると思います。主人公はできるだけ味が薄い感じにしたかった。自分と似ると雑味が入ると思いました。
私自身は場所に対する執着が強い方だと思います。「今は近江八幡みたいな気分」というような感じで、気持ちを地名で表したりすることもあります。
だけど、こうして賞をいただいた時、プロフィールに堂々と「私はこういう人間です」と書ける人と書けない人がいると思うんです。私は人並みにお笑いが好きですが、それだけで「友近さんのファンです」と胸を張っては言えない。言葉にできない人や、名前を付けられない関係性が、なんとなく滋賀には多いような気がします(笑)。
――ではご自身はどんな生活を送ってこられたのか、創作との関わりを交えて教えていただけますか。
中学のときは完全にオタクで、少年漫画の『BLEACH』にはまっていました。いわゆる「夢小説」を書いてホームページで公開したりもしました。ヒロインの名前を閲覧者が自由に設定できる、二次創作の恋愛小説です。内容は激甘でしたね……。高校生になると打って変わって、純文学を読むようになりました。授業をさぼって、学校の裏の土手で川上弘美さんの本を広げていました。そういうことをしている自分がカッコいいと思っていたんですね。友達も全然いなくて、休み時間も机につっぷしているような子でした。
大学に入ったら、今度は周りに個性的な人が多くて、自分以上のオタクもたくさんいる。他大学の映画研究会に入ってみたりもしたのですが、やっぱり知識という面ではかなわないし、なじめなかった。昨年休学してから『BLEACH』を読み返して、やっぱり面白い! と今は思っているところです。
――そこからどうしてR−18文学賞に応募することになったのでしょうか。
書くことはもともと好きでした。と言っても、作文程度でしたけれど。ただ大学1回生(1年生)の時、2週に1回2000字のエッセイを書く授業があって、そこで先生に褒められて自信がついたんです。「文章を書いていくつもりなら、もっと自分自身を突き詰めないと」と言われて、え、私書くの? ってその気になりました。次の年、川上弘美さんがゲストとして登壇される10代だけの読書会が京都であったんです。そこで、短編集『おめでとう』の中の一編「冷たいのがすき」が好きですと話したら、川上さんに「大人向けの話を書いたら?」と言っていただけた。その言葉が身体の中にずっと残っていました。
そして3回生の夏、「ユリイカ」の「女子とエロ」という特集で、窪美澄さんと山内マリコさんの対談を読みました(2013年7月号)。それまでこの賞のことは知りませんでしたが、お二人がとにかく「すごくいい賞です」とおっしゃっていたのが印象的で。それまで、文章を書くのは好きだけれど小説は書いたことがなかった。でもとりあえず応募してみようと思って、その年の秋に初めて応募しました。短篇の賞なので、心理的ハードルも低かったですし。
――2回目の応募での受賞でした。受賞作はどのように書かれましたか。
最初はあまり考えずに書き始めました。主人公の友人は、ミクシィの地元トピに登録して男の人を探している実在の友人がモデルです。あとは2ちゃんねるの滋賀の不倫スレッドをぼんやりと眺めたり。「堅田はダブル不倫が多い」とか書いてあるんです(笑)。でも途中、1か月ぐらい放置した時期もありました。その間にラストの展開を考えていました。そのころのメモを見ると「マック 女子高生 ツイート バズる」などと書いてあって、そこからラストを思いつきました。
タイトルは、藤子・F・不二雄先生のSF短編「女には売るものがある」からもじって付けました。藤子先生は小さい頃から大好きで、「チンプイ」や「ドラえもん」、そしてSF短編もよく読んでいました。「女には売るものがある」もその1つで、女性上位社会を皮肉るというか、あえて男性に身体だけを消費させる女性を描いたとても短い作品です。なんとなく、この物語と通じるものがある気がして。
――これからはどのような物語を書いていきたいですか。
平成生まれの「なつかしさ」を書いていきたいです。昭和のなつかしさについてはある程度類型化されているし、語る方もたくさんいますが、平成のなつかしさを書く方はまだあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
先日、京都鉄道博物館オープンのニュースで、入場列の先頭にいたのが10歳ぐらいの男の子だったんです。それを見て「あ、30年後のこの子は40歳の鉄オタなんやな」と思いました。今起こっている出来事が、いつか彼にとっての「なつかしさ」になる。そういう、自分より若い人や同じくらいの年の人たちの物語をこれからも書いていきたいです。
今回の受賞で、友近さんの選評がとてもとてもうれしかった。こんなにも丁寧に読んでくださって、自分以外の人に読んでもらう喜びを初めて知りました。今は世界の扉がバンと開いたような、そんな気持ちです。

