第19回 受賞作品
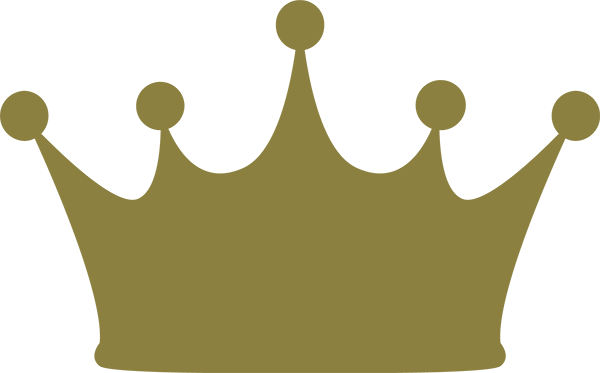 読者賞・友近賞受賞
読者賞・友近賞受賞

――受賞が決まった時のお気持ちはいかがでしたか? 一報が入った時はどんな状況だったのでしょう。
「受賞できたらラッキー」という気持ちと、「ここまできたら大賞がいいな」という気持ちが両方あったので、「ほっとした」が半分、「悔しい」が半分でした。
それでも、多くの読者の皆さまと、友近さんというひとりの読者に響いた事実が、純粋に嬉しかったです。
ご連絡をいただいた時は、都内のホステルに滞在していました。そこがちょっと面白くて。外国のお客さんに喜んでもらうためなのか、ロビーに甲冑が飾られていたり、部屋中にブラックライトで光る忍者が描かれていたりするホステルだったんですね。で、私が宿泊していた個室には、真っ黄色の壁に真っ赤な富士山が聳えておりまして。一報を受けたあとに真っ赤な富士山を眺めて「こりゃ景気が良いや」と思いました。
――数ある文学賞の中で、R-18文学賞に応募して下さったのは何か理由がありますか。
応募するなら、ご恩のある出版社の賞に送ろうと決めていました。
生まれて初めて自分だけの意思で、自分のお小遣いで買ったハードカバーの本が、新潮社さんのご本だったんです。佐藤ラギさんの『人形(ギニョル)』という作品で、その装幀を目にした瞬間、この世にこんなに美しく、禍々しいモノが存在するのかと衝撃を受けました。大人になった現在でも思い入れのある一冊です。
そういった背景があり、新潮社さんの文学賞で、かつ短編の賞を探していた中でR-18文学賞に行きつきました。また、選考委員が辻村深月先生と三浦しをん先生であることを知り、「ここしかない」と強く惹かれました。
――ほかに影響を受けた作家や表現者の方がいたら、ぜひ教えて下さい。
挙げたらきりがないので、ふたりだけ紹介させていただきます。
ひとりは、服部まゆみさんです。10代の頃に服部さんの『この闇と光』を読んで以来、今もずっと楔のように心の深い場所に打ち込まれています。私にとって、一生の宿題のような作品です。
もうひとりは、雨宮慶太監督です。雨宮監督からは、脚本で参加させていただいた『牙狼
――元々脚本家としてお仕事をされていた中で、小説を書き始めたのはどんなきっかけがあったのでしょうか。
一番の理由は、自分自身に「納得したかったから」です。
この10年間、ご縁あって数々の素晴らしい作品に携わらせていただきました。そのことに誇りを持ち、幸せを感じてきました。しかしそれは、一緒に仕事をしてきた監督や、スタッフとキャスト、作品そのものが素晴らしいのであって、当たり前ですが、私個人が優れているわけでは決してありません。20代の頃は目の前の仕事に必死で、そのことについて深く考える余裕がありませんでした。
30代に突入し、これからどんな作家になってゆきたいかを考えた時に、「とにかくいっぺん納得したい」という気持ちが強くなりました。
そのためには、誰の力も借りず、自分ひとりの力で、言葉で、ゼロから作品を創り上げる必要がありました。どんなに短い作品でも、自分が心から良いと言えるものを完成させて、結果を出すことが不可欠だと思いました。そうして自分を納得させなければ、このさき物書きとして生きてゆけないと感じたんです。
――受賞作は選考委員だけでなく、読者からも熱烈に支持された作品でした。カラダカシのユニークな設定はどこから思いつかれたのでしょうか。
「カラダを貸し借りする」というアイデア自体は、子供の頃に母から言われた言葉が根っこにあるのだと思います。あるとき母が「トイレ行きたいけどめんどくさいから代わりに行ってきて」と言ったんです。めちゃくちゃですよね。でもわかるなぁって。寒い冬の日なんかは、ちょっとやそっとの尿意で布団から出たくないじゃないですか。そんな時、一瞬だけカラダを貸し借りできたら便利だろうなと思ったのがきっかけだった気がします。
ちなみに、カラダカシは元々、別に構想していた作品のキャラクターでした。その物語には、不思議な生業を営む人たちがたくさん登場するのですが、カラダカシもそんな登場人物のひとりに過ぎませんでした。性別もおじさんでしたし。
それから、カラダカシ単独でひとつの作品にすることを思い付き、女性の店長と青年の助手とのおはなしを考えました。
更に、応募先をR-18文学賞に定めてからは、もっと「女性ならでは」の方向で設定を活かせないかと探り、現在のかたちに落ち着きました。
――梅田さんが贈呈式でお話しになっていた、子供時代に見た不思議な鳥のエピソードがとても面白かったです! この場でもう一度、何があったのか聞かせていただけませんか。
これは私が4歳か5歳の頃、実際に体験したおはなしです。
私が通っていた保育園では、週に何度かおさんぽの時間がありました。コースは日によって様々でしたが、いずれにしても保育園の近所を数十分かけて回るというものでした。
いつものおさんぽの時間、私たち園児が列をなして歩いていた時のことです。
誰かが「あっ」と空を指さしました。つられてひとりふたりと空を見上げ、さざ波のように連鎖して、園児も先生も皆一様に空を仰ぎ始めました。もちろん私もです。次の瞬間、私は息を呑みました。
炎のような、あるいは、天女の羽衣がゆらめくような光を全身に纏った、巨大な鳥が飛んでいたんです。その鳥は尾がとても長く、金色と桃色が混ざったような輝きをたずさえて、優雅に空を漂っていました。私は反射的に「火の鳥だ」と思いました。それから一瞬目を離した隙に、鳥は消えていました。
保育園に帰ってから、私はおともだちに話しかけました。
「さっきのやつ、すごかったねぇ。火の鳥って、ホントにいるんだねぇ」
すると、おともだちはポカンとした顔で言いました。
「え、なんのこと?」
今度は私がポカンとしました。慌てて他の子や先生にも鳥のことを尋ねましたが、ほとんどが「そんな鳥は見ていない」といった反応でした。
私の妄想や白昼夢だったのかもしれません。でも、もしもそうでなければ、あれはきっと、鳳凰とか不死鳥とか呼ばれる存在だったんじゃないかと思うんです。本当のところはわかりませんし、私は未だに「あれは一体なんだったんだろう」と思い続けています。
なぜこんな話をしたのかと言えば、私にとって理想の作家/作品とは、あの日見た鳥のような存在のことだからです。脳裏に焼き付いて離れない一瞬の光景と、「あれは一体なんだったんだろう」という永遠の疑問を投げかけてくる存在。佐藤ラギさんの『人形(ギニョル)』のように、服部まゆみさんの『この闇と光』のように。
そういう作品を書きたいですし、そういう存在に私もなりたいです。
――コロナ禍のために贈呈式の規模は縮小されましたが、その分選考委員のお二方とはゆっくりお話ができたかと思います。お二方とお話しされて、印象に残ったことがあれば教えて下さい。
辻村先生から「気が強い」と仰っていただいたことと、元彼のことを「昔の方」と表現したら三浦先生に「その表現いいね」と笑っていただいたことです。もっと他にあるだろうって感じなのですが、あの日はお二方のオーラやその場の雰囲気に溺れてしまいそうなところを必死にしがみ付いていたので、正直、あまりよく思い出せないんです。それこそ、伝説の存在だと思っていた人物が、目の前に現れた心地でした。
――これからどんなものを書いていきたいか、目標などがあれば教えていただけますか。
先ほどの鳳凰の話はふわっとした夢ですが、具体的な目標としては、いつか自分の小説を自分の脚本で映像化できたら良いなと思っています。
そのために、どんなに時間がかかっても、どんなに自分がダメに思えても、書き続けてゆきたいです。

