第23回 受賞作品
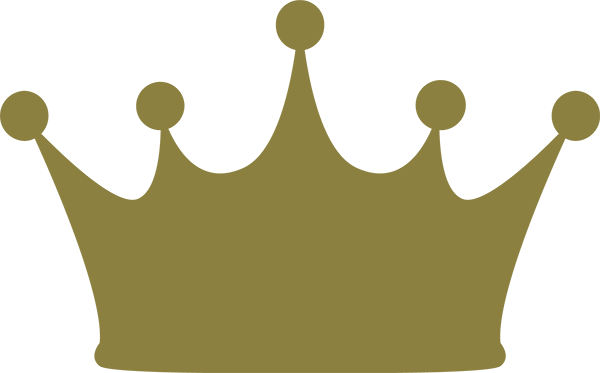 大賞受賞
大賞受賞

――この度は大賞受賞、おめでとうございます。受賞の知らせはどんなふうにお聞きになりましたか。
ありがとうございます。作品を書きあげたあとは、「どうせ駄目でしょ」と選考の結果を追っていなくて、一次選考も二次選考も結果を知りませんでした。いきなり知らない番号から電話がかかってきて「最終候補に残った」と聞いたときは、すごく驚きました。正直、詐欺かと思ったくらいです(笑)。最終選考の日も、子どもを歯医者に連れて行ったりして、受賞のお電話をいただいたのは、夕飯に焼きそばを作ろうとしていたところでした。すぐには信じられなかったです。
――執筆活動のきっかけは?
もともと文章を読むのが好きでした。小学生から中学生の頃に読んでいたのは、野中柊さん、栗本薫さんの作品など。谷崎潤一郎さんの「小さな王国」にも幼いながらに感動しました。高校生になってから読んで印象に残っているのは、ヘルマン・ヘッセの「デミアン」。読み終えた瞬間、足元がぐらつくような衝撃を受けたのを覚えています。
ただ、大学に入った頃から読書量が減り、さらに妊娠してからはぱたりと本が読めなくなりました。本の世界で巻き起こるドラマの刺激が、どうしても受け入れられなくなってしまったんです。唯一読めたのが、よしもとばななさんの作品で、特に『デッドエンドの思い出』は印象深いです。重いテーマでも透明感がある文章で、すごいなあと。
自分でも創作をしようと思うようになったのは、出産してしばらくしてから、東日本大震災がきっかけでした。当時、福島に住んでいたのですが、放射線量の高い地域だったので避難することになり、実家、あるいは受け入れてくださる地域などを転々とする生活をしていました。ただ、知らない土地にいきなり住むと、知り合いもいないし出かける場所もよくわからない。することが見つけられなくて、時間を持て余してしまうんですね。それで、書く練習をしてみよう、と。もとから文章を書くのも好きで、学生時代にレポートを書いたりするのも楽しかったから、ちょっとやってみようか、とパソコンに向かうようになりました。
――執筆を始めてからはどんなご苦労がありましたか。
当初は長いファンタジーを書いて、ネット上の投稿サイトにアップしていました。ですが、自分の書くものはどうやら、ネット上で需要のあるライトノベルでもないようでした。同じく需要のある悪役令嬢も異世界転生も私には書けませんでした。
そんななか、pixivという投稿サイトで、幸運にも長編で賞をいただくことができて、じゃあ次は短編を書く練習を始めようと決めた、これが2022年のことです。ちょうど開催されていたコンテストに投稿したところ、いくつか出したうちの一作で賞をいただけて、おお、よかったな、と。
昨年は、知識や語彙が圧倒的に足りないと感じて、とにかくたくさん本を読む、を目標にしていました。書くなら読むべき作品をまだ読んでいない、という思いもありました。長編はともかく、短編は読まないと書けない、とも。特に決められた枚数のなかでしっかりと物語を締めくくる手法は、イタリアの作家、ブッツァーティの短編がどれも素晴らしくて、『神を見た犬』という短編集にはとても感銘を受けたし、こんな終わり方があるのか、とびっくりしっぱなしでした。
――受賞作「息子の自立」は、障碍を持った息子と母親との関係がつぶさに描かれています。どのような思いで、書かれた作品なのでしょう。
私には障碍を持った子どもがいます。その子が成長するところをみていて、この経験を無駄にしたくない、と感じていて、いつか、このテーマを形にできたらいいと思っていました。
だけどすぐには書けなかった。受賞作のもととなる作品を書き始めたのは2年ほど前のことでしたが、最後まで書き切ることができませんでした。途中でどうしても手が止まってしまう。「今は書くべきときじゃないな」と一旦隅に置いて、しばらく別の作品を書いていました。
それが昨年、もう一度この作品を書き始めてみたら、1週間ほどで書き切ることができた。1行書いたら次の行が浮かぶ、というふうに、止まらずに手が動いてくれて、あれはとても不思議な感覚でした。
とはいえ、最初に書き始めてから時間を置いたことに、なにより意味があったのだろうと思います。書いていたのは1週間ほどでも、かけた時間はもっと長いように感じます。
――今後はどんなふうに創作の道を歩んでいきたいですか。
自分がこれからどんなものを書くのか、まだ想像できていません。受賞作の続きも、考えたことがありませんでした。支援学校に行くと、そこには様々な個性を持った子どもたちがいます。喋りつづける子、何も喋らない子、動き回る子、一歩も動かない子……、本当に多様です。彼らを一括りに語ることは決してできないし、「障碍のある人のために」というような気負いが自分のなかに今後生まれるとはあまり思いません。
ただ、受賞した今気づくのは、自分は書くことがどうやら好きらしい、ということです。これからもいろいろなテーマに向き合って、何が書けるかを考えていきたい。それが「障碍」というテーマに繋がるのかもしれないし、全く別の何かになるのかもしれない。
恩田陸さんの作品の一節ですが、「いいものを読むことは書くことよ」という台詞がずっと心に残っています。いろいろな本を読んで感じたことが降り積もり、ある日ふと物語の種が浮かんでくる。これからもたくさんの物語を吸収して、その奥に自分が書くものを見つけていきたい。そんなふうに書くことに向き合っていけたらと思います。

