第23回 受賞作品
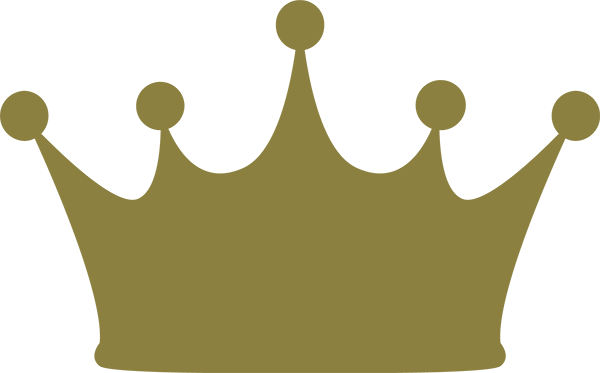 友近賞受賞
友近賞受賞

――この度はおめでとうございます。受賞の一報を聞いてどのように思われましたか。
電話が鳴った時、担当の編集者さんに申し訳ないなと思ったんです。受賞をせずともご連絡はいただけるとのことだったので、残念な結果を伝える仕事は気の毒だなと……。それくらい予想外でした。友近さんの作り込む世界にずっと魅了されていたので、賞をいただけたことより、本当に友近さんに読んでいただけたのだと、改めて驚いてしまいました。
ジャンルの分け隔てなく長編、短編といろいろな文学賞に応募して30年弱、100回くらい落選してきました。新潮社さんの主催する賞に応募したのは今回が初めてです。新潮社さんの本が大好き過ぎて、私は相手にしてもらえないだろうと。
しかし去年の今頃、人生も折り返し地点を過ぎたのに気づき「もう好きなものを書いて、好きな人に振られたい」と思ったんです。それが今回の結果に繋がったのですから、巡り合わせの不思議を感じました。
――去年の今頃、何かきっかけがあったのでしょうか。
フェムテックやフェムケアの商品を扱うお店を経営している友人に頼まれて、サイトのコラムを書き始めたんです。今までの人生で感じていた生きづらさや、もやもやした感情って私個人の問題ではなく、女性という性が関係していることに今更ながら気づきました。女性だから仕方ないと我慢してきたこと、受け入れてしまってきたことがたくさんあったんだなと。それでこの賞に応募しようと思いました。
それと同時に、ずっと世間に求められる小説を書こうとしてきたけれど、全然うまくいかなかったし、楽しくなかったと気づきました。これを機に、好きなものを書こうと決めました。
――小説を書き始めたのはいつ頃からでしょうか。
「書くこと」は物心ついた頃からしていました。好きというより、書くことしかできないという意識があったんです。作文コンクールで入賞したり、親から褒められたことも特になかったのですが、ぼんやりと書くしかないと思っていました。
幼い頃、空想癖があったんです。ある日母に幼稚園での出来事を話しているうちに止まらなくなり、あることないことごちゃ混ぜにして話してしまったら、翌日大騒ぎになってしまって。「子どもは夢の国に住んでいるのだから」と父が母に言ってくれたことを、ずっとあとになって知りましたが、お友達からは嘘つき呼ばわり、母や先生からも「なんでそんなことを言ったの」と𠮟られました。自分としては母を喜ばせたくてしただけだったのですが、周囲の反応は幼心にとてもショックで……。それからは思いついたあれこれをノートに書き留めるようになりました。
初めて小説らしきものを書いたのは、小学6年生の時でした。クラスの女子の間で小説を書くのが流行っていて、私は風を操る女の子が旅に出るというファンタジーを書きました。当時一緒に書いていた子は今でも友人で、書いたものを読んでもらっています。
その後もずっと書き続けてきましたが、結果が出ないことにくたびれて悩んでいるような時に、「何か書いたほうがいいよ」と意外な人から突然言ってもらうことが多くて。ご神託だなと幸せな勘違いをしながら今に至ります。
幼い頃の経験から、自分のお話は人を傷つけるんだという感覚がどこかありました。だからこそ今回賞をいただけたことで、書くことを許してもらえたような気がしたんです。
――書き続けてきた人生の隣にあった本を教えてください。
幼い頃から読書は大好きで、高校生の頃は江國香織さんの新刊が出るたびに、お小遣いを握りしめて書店に行っていました。町田康さんの『告白』や又吉直樹さんの『劇場』、上橋菜穂子さんの「守り人」シリーズなど、ジャンルも関係なく読みます。
小中高と演劇部だったので、別役実さんや如月小春さんの戯曲も読み漁りました。野田秀樹さんの戯曲も大好きですが、何度読んでも分からないところがあって。そういう時は声に出して読むようにしています。言葉のリズムを感じるのも好きなので、音読するうちに「もっと真剣にものごとを考えろよ」と言われている気になってきて……。自分の至らなさに反省します。
――受賞作は主人公の最後の長台詞が印象的でした。どのように書かれたのでしょうか。
真正面から、ひねりのないシスターフッドを書きたかったんです。世の中にしつこく蔓延る家父長制や、権力を振りかざす大人に私は立ち向かうことなく、やり過ごしてきてしまったけれど、それを未来には残したくないと思いました。
これについては象徴的な出来事がありました。あるニュース動画を見たんです。高校生が窮状を申し出て、政治家と面談をしている様子を映した映像だったのですが、その政治家が、面談を勝ち負けの場だと思っているのか、高圧的で。高校生に対して、彼らがいかに甘えていて、努力が足りないかをあげつらい、貧困家庭に生まれたのは自己責任だと断じていました。政治家の言葉に肩を落とす彼ら彼女らに対して「世の中はそんなに悪いものじゃないよ。大丈夫だよ」と言いたかったんです。私自身3人子どもがいるので、特にそう思うのかもしれません。
だからお話の中では主人公に、父親に対して言いたいことを思う存分、余すところなく言わせてあげたかった。最後の長台詞は意図的ではなくて、結果的に長くなってしまいました。音読に耐えうる文章ではないと読んでいても頭に入らないと思うので、リズムは意識しました。
――これからどんな作品を書いていきたいですか。
日常生活の中で抱く違和感を突き詰めていきたいです。なかったことにされてしまう人々やその感情を見逃さない人でありたいなと思います。
今までは子どもが寝ている間など隙間時間にこっそり書いてきました。賞をいただけたことで、編集者さんと、もしかしたら読者さんも一緒にいてくださるかもしれない。一人じゃないってありがたいなと思います。愚直に書き続けていきたいです。

