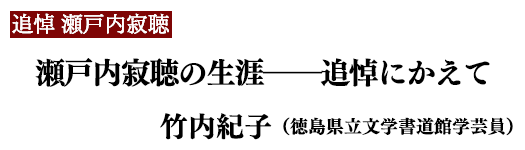敬愛する先輩、年長の友人たちが一人、また一人と身罷ってゆくのを、見送ることすらできず、恨めしい。この世を楽しく賑わせ、かき回してくれた人が退場すると、その分だけこの世が退屈になってゆくようで辛い。残された者が奮起し、穴を埋め合わせるしかないのだが、反知性主義と新自由主義が増長する中、「ぼっち感」を噛み締めている。「めげちゃダメ」といってくれる人がいなくなるだけで、人はたちまち無気力になってしまうものだ。かくして、この世を呪い始めた人は、楽しげに見えるあの世の方に惹かれ、死者との絆をいっそう深めてゆくことになる。
最晩年、寂聴さんは折に触れ、自分は死ぬ気がしないと語っていた。私は彼女の執筆欲や食欲を確認するたびに、不滅を信じたくなった。百歳超の人は日本だけで八万人いるが、百五歳以上は世界で百数十人しかいないので、あと六年はこの世にいてほしいと漠然と思っていた。京都の錦市場にご一緒した際、遠くから通行人が寂聴さんに合掌しているのを見て、この人を活仏と思う信者が少なくないことを知ったが、本当に活仏なら、生死を超え、この世とあの世を往還しているような存在だから、寿命には何ほどの意味もないことになる。
今夏発表の掌編『星座のひとつ』は、飛行機であの世に到着した設定になっている。書き死にするほど書きまくったこと、病に倒れたこと、名医との付き合い、岡本かの子の情欲などを思い出しながら、荷物を持って空港の外に出ると、そこは通い慣れた天台寺のある町に似ていて、何処に行けば、甥や両親や姉に会えるかな、恋のひとつもしてやろうかなと思っていると秘書とその幼子が現れ、軽口を交わすが、いつの間にかその姿も消え、たそがれてくる。
これを読む限り、晩年の寂聴さんの意識の中では、この世とあの世は相互に干渉し合い、入り交じっていたことがわかる。死者は生きている者と分断されることなく、いつも身近にいる。詩人や老人、僧侶はしばしば、この世にいながら、死者と対話する。あるいはあの世に片足を踏み入れ、平然と死者に会ってくる。源氏物語に登場する女たちを、同時代に生きる自分の知り合いのように語っていた寂聴さんの感覚は、おそらく近代以前の人々には普通に共有されていた。その意識は時間に縛られておらず、現在時制に若い頃の記憶や百年前の人の意識、平安時代の紫式部や清少納言の思いまでもが流れ込んでくる。意識は自在に様々な年代に飛び、絵巻物のように異なる時空が同一平面上に並列している。過去、現在、未来が直線的に並ぶ時間軸に従って生きる人の感覚からすれば、狂っているが、江戸時代や平安時代の人々にとっては、過去から現在を経由して未来に向かう時系列も、原因と結果を関連づける因果律も、生きていた時代の違いも、出来事が起きた順番などもどうでもよかったと思われる。
寂聴さんのあの自由闊達ぶり、神出鬼没ぶりは時系列や因果律から解放されていたことに由来するのではないかと思う。彼女は最も多くの戦死者を出した世代に属するが、現在の世相は若かりし頃に味わった嫌な感じを思い出させ、反射的に命を守る行動に繋がったと思われる。彼女が震災の被災地やイラクを訪れたのは、自発的にというより、そこに行けという声が聞こえたのだろう。イラクではジーンズにキャップという出で立ちだったので、僧侶とは思われず、「老人か、白血病の子供か」と訝られたという。彼女はローマ法王やダライ・ラマ一四世、あるいは天皇やフーテンの寅さん、源氏物語絵巻の光源氏のようにあらゆる場所に出没した。僧侶は鎮魂と平和のため世界に遍在していなければならないが、その使命を忠実に果たそうとすれば、自ずと神出鬼没になり、現世の地獄と歴史上の地獄を重ね合わせ、今ここにいる人々とあの世の人々を引き合わせることになる。
実際、寂聴さんが新旧文壇の渡し守り役をしてくれたので、文豪たちの記憶は後世に受け継がれた。私や山田詠美、平野啓一郎らに、過去の文豪たちの知られざる秘話を惜しげもなく披露し、長生きの役得は「復讐できること」とまでいって、微笑んだ。寂聴さんの態度には分別くささ、説教くささが一切なく、いつも赦しのオーラを放っていた。癒しよりも強く人の背中を押す赦しは、自らの情欲の深さを鎮め、かつ転化した末に獲得した法力なのである。
寂聴さんの自由闊達ぶりはとりわけ猥談の際に際立っていた。僧侶になったのは性的妄想を極限まで高める修行が目的だったのではないかと疑うほど熱心だったので、猥談に付き合うのは本当に楽しかった。ダンテの『神曲』でいえば、地獄の第二圏にいる人々、愛欲の罪を犯した者たちにとっては寂聴さんこそが仏だっただろう。この世にいるあいだに寂聴さんに赦しを授かれば、地獄落ちなんて怖くない。実際、私を含め多くの迷える羊を救ったのだから、宗派など問わず、愛と平和の使徒に列位すべきかと思う。