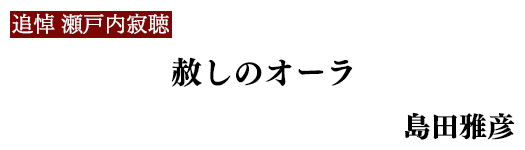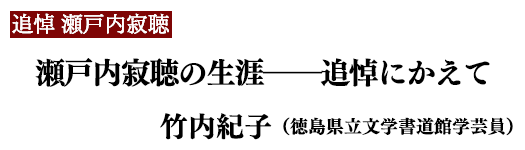瀬戸内寂聴さんとは、何度か対談をした。
一度だけ、対談以外でお話ししたことがある。
二〇〇〇年一月十七日に息子を産み、その三ヶ月後の四月二十日に十五年間連れ添った東由多加(劇団「東京キッドブラザース」主宰・劇作家・演出家)を亡くした。
わたしは渋谷のマンションで息子との二人暮らしをはじめていたが、東がこの世からいなくなったということに納得がいっていなかった。毎朝目覚めると同時に涙を流し、もう一度東と話したいという思いに捕らわれ、何人もの霊能者のもとを訪ねたりして、悲しみにすっぽりと嵌まり込んでいた。独りで子どもを育てていけるのだろうか、という不安も日毎に膨らんでいた。
どういう経緯だったのかはもはや憶えていないが、当時暮らしていた渋谷のマンションを瀬戸内さんが訪ねてくださった。
瀬戸内さんは「あら、まるまる太って、かわいい男の子ね」と、生後五ヶ月になる息子を抱きあげてくださった。
瀬戸内さんの顔に現れていたのは、喜びと祝福だけだった。
わたしは、東が闘病をしていた部屋に瀬戸内さんをご案内した。ベッドも枕も布団も机も灰皿もなにもかも、そのままにしてあった。赤ん坊を抱いていた瀬戸内さんは、東のベッドに祈るような沈黙を向けたが、祝福の微笑みが揺らぐことはなかった。
瀬戸内さんは、ティファニーのベビースプーンをくださった。ご自分でデパートに行って選んでくださった、とのことだった。ブルーの小箱を開けると持ち手が輪っかになった銀のスプーンが、これからの日々の道しるべのように輝いていた。ヨーロッパでは、幸福や富や繁栄を運ぶものとして銀のスプーンを子どもの誕生や洗礼のお祝いとして贈る習慣があるという。わたしは、ベビーベッドで寝ている息子の顔を見下ろした。瞼の閉じ目の柔らかい睫毛を
二〇一〇年の秋に瀬戸内さんと対談をした。瀬戸内さんは対談の冒頭から、泥酔をして階段から転落して顔面を打ちつけ、夜中に目覚めると血だらけの法衣が脱ぎ捨ててあった、と朗らかな笑い声を立てた。ボトルをキープしているゲイバーで、飲み過ぎですよ、と店の人に注意をされたが、「自分の酒を自分で飲んでなにが悪い!」とボトルを全部空けた、と、また笑った。
互いの近著の話が中心になり、瀬戸内晴美作品と初めて出遭った時のことを話そうと思っていたのに話すタイミングを見つけられなかった。
わたしが育った横浜のあばら家には、日本語の読み書きのできないパチンコ屋の釘師だった父親の本棚と、キャバレーのホステスだった母親の本棚があった。父の本棚に並べられていたのは世界文学全集と日本文学全集で、母の本棚に並べられていたのは瀬戸内晴美の小説だったのである。
最初に読んだ瀬戸内晴美作品は『花芯』だった。小学生のわたしは、こんなことまで言葉で捕まえられるのか――、と目を瞠った。そして、自分の心と体にさざなみが立つのを感じながら夢中になって読み耽った。子どもではあったものの、学校や家やその他の場所で、生きることが堪え難くなるような出来事が次々と起きていた。わたしは、瀬戸内晴美の小説によって、決して口にはできない思いや行いを物語に仕立て直す術を知ったのである。
対談の終盤、瀬戸内さんは赤ん坊だった息子を抱いて東のベッドを見ていた時に戻ったかのように、こう仰った。
「東さんの魂はいまだってずっと柳さんの側にきて、柳さんが新しい男と仲よくなっても、それを見守ってる。暖かな心で、あなたの幸福を見守ってる……そんなふうに自然に思えるようになっています。だからわたしも死ぬことはまったく怖くない。もう生き飽きたから早く死んで、なつかしい男たちに歓迎パーティしてもらいたいわ」
この対談の半年後に東日本大震災と原発事故が起きた。わたしは鎌倉から南相馬に移住することになった。この十年間は、他者にまみえることに自分を傾けてきた。癒しや贖いを奪われた苦しみと悲しみのための居場所を創ることに心と精神と力を尽くしてきた。それは、臨時災害放送局で六百人の住民の話を聴く、旧警戒区域でブックカフェを営むという具体的な行為のみならず、自分の小説に他者の苦しみと悲しみを迎え入れることでもあった。
昨年の十一月、徳島県立文学書道館で講演を行った。講演終了後に館内を見て歩いているうちに瀬戸内寂聴記念室に入り込み、瀬戸内さんが徳島出身だったことを思い出した。
年譜を辿っていって、あ!と小さな叫び声をあげた。
瀬戸内さんが天台宗の出家得度をして「寂聴」という法名を授けられたのも、わたしがカトリックの洗礼を受けて「テレサ・ベネディクタ」という霊名を授けられたのも、同じ五十一歳だった――。
また、十年ぶりに、瀬戸内さんとお話ししたい、と思った。
瀬戸内さんもわたしも、自己救抜のために宗教を希求したのではない。瀬戸内さんは対談の中で、「あまり深く考えてなくて、もっといい小説を書きたいという野心から出家した。ところが出家したらいやでも人間の
わたしの場合は、他者や出来事と決定的に出遭うと、その衝撃で自分の中から魂がはみ出す時がある。その魂が向かうところに従った結果、受洗があったのである。
五十一歳という年齢について、法名と霊名が作品に及ぼす影響についてなどお話ししたいことはたくさんあったのだが、もう、瀬戸内さんとお話しすることはできない。
八十八歳の瀬戸内さんが、四十二歳だったわたしにくださった言葉である。
「気が狂っても、自殺未遂をしてもいいから、八十八歳までは生きて、小説を書き続けてください。そして誰も書けないものを書く作家だということに誇りをもってください」
誰も、自分の死の日付は知らない。
八十八歳まで生きることになるのかどうかはわからないが、わたしは、有限な存在である「私」を出発点として、他者への気が触れたような共感という飛翔と不時着を繰り返しながら、これからも書いていくのだと思う。