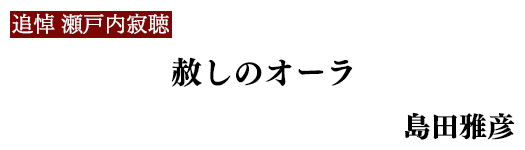瀬戸内寂聴(旧名・晴美)は一九二二(大正十一)年五月十五日、徳島市の中心部である塀裏町(現・幸町三丁目)で生まれた。父豊吉は腕のいい指物職人で、晴美が生まれた頃には十人あまりの住み込みの弟子がいて、母コハルは弟子たちの世話に明け暮れていた。五歳上に姉の艶がいて、その頃には父方の祖母もいた。
晴美は、生まれたとき、産婆が半年しか持つまいと予言したくらい体が弱く、滲出性体質で、年中おできに悩まされていた。薬や膿の匂いのする包帯だらけの子どもであったため、近所の子どもたちが遊んでくれず、一人遊びの癖がついた。
晴美が五歳の誕生日を迎えた頃、母が幼稚園に入れようとしてくれなかった。送り迎えをする祖母が亡くなったせいであったが、納得できない晴美は、迷いながら、姉の通っている寺島尋常小学校の校庭にある幼稚園にひとりで四十分歩いてたどりつき、驚いている教師に向かって、明日から通園したいと言ったのである。幼稚園の授業が終わった後、四年生の姉の教室で授業が終わるまで待っていていいと、姉の担任であった古島晴子先生が言ってくれたので、通園が決まった。「この子は何をしでかすかわからない」と母は父に報告しながら、大きな溜息をつく。姉の若い担任教師は、晴美のために教室の窓際の最前列に机を用意し、クレヨンや画用紙を与えてくれた。晴美は姉の四年生のクラスで一日の半分を過ごした。この古島先生の家に姉とともに遊びに行く習慣も生まれ、先生の書棚から新潮社の世界文学全集や改造社の日本文学全集などを借りていた。モーパッサンの『女の一生』も、フローベールの『ボヴァリー夫人』も、トルストイの『復活』もその全集から読んだという。
尋常小学校三年生の時の担任は新卒の広田シゲ先生で、子供の才能を伸ばそうと、意欲にあふれていた。放課後、晴美を一人だけ残し、白秋の詩や啄木の歌を暗誦させたり、藤村やアンデルセンの童話を読ませたりした。この時期、大きくなったら何になりたいかと問われると、晴美は「小説家になります」と書いている。
五年生になると高等女学校の入学試験のために、分厚い問題集を何冊も買い込み、猛勉強する毎日が続く。小説家の夢は忘れてしまい、何か強烈な生活をしたいという想いに憑かれ始める。満州に渡って女馬賊の頭目や、南極探検隊の女隊長になってみたいなど、荒唐無稽な夢を描いていた。
家では父のたくさんの弟子たちと生活を共にし、母親が応対する神仏具を商う店には絶えず見知らぬ客も来る。晴美はいわば人を見て育ったともいえる。そしてまた、この母は「聖人」とあだ名されるほど、人の話をよく聞き、人の面倒も見る、母性の強い人であった。父親は優秀な頭脳を持ち、発明が好きで、常に新案特許を申請していた。この両親の血を受け継いで、優秀な頭脳を持ち、面倒見のよい晴美になったのだろう。
県立徳島高等女学校には一番の成績で合格し、常に級長に任命された。陸上部に入り、三種競技の練習をするが、いい記録は出なかった。入学して早々、学校の図書館で与謝野晶子訳の『源氏物語』に出合い、これほど面白い物語があろうかと夢中になる。それまでに積み重ねた幅広い読書体験が、一三歳にして『源氏物語』を読ませたのだろう。後の『源氏物語』現代語訳を七五歳で成し遂げた、初めの一歩である。
ハンセン病療養所に勤めた経験を書いた『小島の春』がベストセラーとなった小川正子が女学校に講演に来たことがある。感銘を受け、自分も瀬戸内海の小島に渡り、不幸な宿命を背負った彼らの友となって生涯を送ろうかと考えこんだ。何にでもすぐ感動しやすく、たちまち身を挺して実践してしまいたくなる後年の性癖は、このとき自分の内部に生まれていたという。自分の中にも、もし才能があるなら、なんらかの形でこの世に刻み残したいという自己顕示欲をこの頃に自覚する。
東京女子大に進んだのは、学校の廊下に張りだされたポスターの白いチャペルに憧れたからである。勉強するなら小説家になるために役立つ勉強がしたいと国語専攻部を選んだ。田舎町の旧弊な女学校で過ごした日々に比べると、女子大の自由さや伸びやかさは新鮮だが物足りなさを覚え、単調で穏やかな女子大生活を続ける自信は次第になくなっていった。
そんな頃、外務省留学生として北京に渡り、中国古代音楽史の研究を続けている九歳上の学究との見合話が郷里で持ち上がり、学生生活から脱出できるチャンスと飛びついた。そして、突然、大阪の豊中にある断食寮にとびこんだ。貧乏な学者の妻となるには脆弱すぎるという診断を自ら下し、決行したのだった。二十日間の完全断食の後、自分の血がいれかわったような新鮮さが体中からわきあがってきた。婚約者は、この奇行を愛の証しと受けとめてくれた。
在学中に式だけを挙げ、二一歳の九月、大学を繰り上げ卒業して、北京に渡る。戦争末期、学徒動員が始まった時であった。当時日本は中国を占領下に置き、中国人に対してひどい仕打ちをする日本人も目にした。空襲はないものの、夫の重病、転職、引っ越し、出産、夫の現地召集と続く中、敗戦を迎える。夫が中国に骨を埋めたいというので、知人の家で身を潜めている時期、晴美はひどい肋膜炎にかかる。医者は、薬はなく、何もせずに寝ているしかないという。このときの心情を『いずこより』(七四年)に書いている。
国家の命令ひとつ、あるいは天皇の命令ひとつで虫けらのように、すべての意志を奪われ、すべての生活の根を切られ、奴隷のようにつれ去られ、生命を投げださなければならない人間の暮しというものに、どこに安住が得られるだろう。天皇のためにと、教えこまれてきた私の忠君愛国の純粋な感情は、もうなくなっていた。(中略)今の惨めな、敵国で敗戦の民として身をひそめ、病気を治す薬にも不自由し、いつ故国の土をふめるともわからず、明日の生活に何の保証もないこの不安定な暮し。こんなものが、物心ついて以来、心に刻みつけ守りつづけてきた天皇への忠誠と国家への忠義のおかえしだったのか。
やがて親子三人、着のみ着のままで日本に引き揚げる。四六年八月、船で佐世保に上陸し、身動きもできないほど引揚者がつめこまれた列車で徳島へ向かう。夜中、広島に停車したとき、ただ荒涼とした焼け野原が広がり、奇妙な形に折れ曲がった鉄骨や、半分しか残されていない樹々の不気味な姿が見えた。「原爆のあとだ」というささやきが広まり、その惨状を一目でも確かめようと人々は目を凝らしていた。故郷の徳島駅に着くと、幼なじみに会い、母と祖父が空襲で亡くなっていたことを知る。
夫は北京に渡る前、徳島で学校の教員をしたことがあり、その教え子たちが三日にあげず訪れてくるようになった。彼らは坂口安吾や織田作之助など戦後の新しい文学を晴美に紹介し、読書会を開き、同人雑誌めいたものを始めた。夫は職探しに上京していたが、ある日、目前に迫る参議院選挙に徳島から出馬する婦人代議士を、教え子たちと応援するようにと速達が届き、晴美を選挙中の秘書として推薦したという。
連日、徳島じゅうを駆け巡る中で、そのうちのひとりと恋におちてしまう。Rは晴美たち一家が北京にいた頃、上海の学校にいて、二度ほど訪ねてきたことがあった。晴美の初めての恋であった。選挙が終わり、しばらくして夫が帰郷したとき、晴美は泣きながら「Rさんを好きになってしまいました」とプラトニックであるにもかかわらず告白する。夫三五歳、晴美二五歳、相手は二一歳。夫は夫婦で上京することでRとの仲を引き裂こうとするが、晴美は、ノイローゼ状態になってしまう。二月の寒い日、娘を抱いた夫に「何もかも置いて行け」と言われ、オーバーもマフラーも手袋も財布も置いて、家を出てしまう。
東京から大学時代の友人がいる京都駅に着いたのは夜明けだった。徳島のRは駆けつけてきたが、家族の生活があって家は出られず、「あなたは自分の足でしっかり立ってみるべきだ」と言う。父は「お前はもうこうなった上は人の道を外れ、人非人になったのであるから、鬼の世界に入ったと思うよう。どうせ、鬼になったのだから、人間らしい情や涙にくもらされず、せいぜい大鬼になってくれ」と手紙に書いてくる。その年の夏の終わりに、徳島に帰り、結局、Rに別れを告げると、帰りの連絡船の中で、不思議な解放感がつきあげてきた。この船の中で、これからは、ひたすら小説を書いていくしかないと、心に決める。
京都では、貧しい暮らしで栄養失調になりながら、小さな出版社、京大附属病院の研究室、図書室で働く。その頃、三島由紀夫にファンレターを書いて、しばらく文通もしていた。ある日、少女小説を書いて編集部に送ると、雑誌に掲載され、生まれて初めての原稿料を手にする。これがきっかけとなり、作家をめざして上京する。それまでに父は亡くなり、夫との正式離婚が成立していた。
「ひまわり」や「少女世界」、小学館の学習雑誌に子供向けの読み物を書く一方、丹羽文雄の主宰する同人雑誌「文学者」に入り、中心メンバーの一人であった小田仁二郎と出会う。初めて持ち込んだ原稿を読んでくれたのが小田だった。あとで、自分の好きな詩人のボードレールに似ていると思い、幸先がいいように思った。次に会ったときは、「小説を本気で書くのは辛い。ずっと童話書いていったら、どうなの」と言われる。「可哀想すぎるよ、あんまり」と。その言葉で、自分が愛されているような気になり、読みはじめた彼の小説の虜になる。『触手』の新しさには衝撃を受けた。小田は新聞社に勤めたあと作家生活に入り、芥川賞候補二回、直木賞候補に一回挙がっていた。やがて小田と月の半分を共にする半同棲の生活が始まる。「文学者」が解散になったあと、小田が主宰して「Z」を始め、吉村昭、津村節子夫妻も参加した。小田が応募を勧めた新潮社同人雑誌賞で「女子大生・
六一年四月、『田村俊子』が文藝春秋新社から刊行され、第一回田村俊子賞を受賞する。この頃、離婚の原因となった年下の男Rが突然現れ、小田との三角関係となる。小田とは別れ、新しい住まいにはRが居着くようになる。この経緯を私小説の方法で書いたのが「夏の終り」で、これが五年ぶりに「新潮」に掲載され、第二回女流文学賞を受賞する。常にRは、晴美に文学上の転機を与えた男であった。
受賞後は注文が殺到し、寝る間を惜しんで書いた。週刊誌や新聞に同時に連載を数本持っている。六五年に連載された伝記小説『美は乱調にあり』、六八年『遠い声』、七一年『余白の春』は明治・大正の「冬の時代」を背景としている。歴史の闇を描こうとした勇気と知性に裏打ちされた仕事である。寂聴は、「彼女たちが、自分の生き方を、決して安易な妥協や習慣の中に埋没させないで、あくまで理想主義的な純粋な生命の燃焼をとげようとした、はりつめた生き方に魅せられたから書くのである」と執筆の理由を書いている。また、こうした伝記と同時に、職人を訪ねて書くルポルタージュ「一筋の道」を連載した。「書き中毒」ともいえる仕事中心の生活だったからか、共に暮らしていたRは会社の若い女性との結婚話を持ち出し、晴美は深く傷ついてノイローゼになり、精神療法を受ける。Rとはその後もやり直そうとしたが、元に戻らなかった。
六六年四月、高松市の講演に出かける車の中で、井上光晴と出会う。以後、出家まで関係は続いたが、寂聴が井上のことを「情人」とはっきり認めたのは、二〇一六年六月の朝日新聞の随筆が初めてである。
一年の中で、私の最も好きな五月がすでに終わってしまった。五月は私の誕生月であると同時に、月の終わりは、私の情人の命日でもあった。男には妻子があり、まだ六十六歳であった。(『寂聴 残された日々』)
井上との出会い以降発表した「蘭を焼く」「おだやかな部屋」「抱擁」などには、井上光晴を彷彿とさせる男が登場する。人間的に成熟した男女が深夜、女の部屋でだけ、純粋で濃密な時間を生きる。はかなく夢のような時間であり、魂の交歓が描かれる。出口のない愛ゆえに深い孤独を伴い、「死」も見え隠れする。
四九歳のとき、『余白の春』と半ば並行して書いた『京まんだら』は日本経済新聞に連載された。お茶屋の女将を中心に、その店の常連客や家族、仲居、舞妓や芸妓たちのドラマが、京都の伝統行事や四季の美しさとともに描かれる。この連載は評判を呼び、新聞の売上げを増大させた。
大逆罪で獄中で縊死した金子文子の生涯の暗さと、祇園の華やかさには何の共通点もないようだが、祇園の女たちを深く識るにつれ、女として生きる生涯の苦楽は、その両極端に生きながら、深い底で通じているとしか思えなくなった。(『瀬戸内寂聴全集』第七巻解説)
と書いている。伝記小説と純文学とエンターテインメントを三本の柱として、それぞれの雑誌に応じて、書き分けてきた。「女として生きる生涯の苦楽」を多面的に、多彩な手法で、多様な女たちを通して描いてきたといえる。しかし晩年になると、ジャンルを横断する、融通無碍な自由な書き方になっていった。
七三年十一月一四日、五一歳で、岩手県中尊寺で出家、得度。法名、寂聴となる。理由の一つとして、自らの文学のバックボーンとなるような思想や哲学が欲しかったと語っている。二ヶ月間の比叡山での修行のあと、京都嵯峨野に単立寺院「寂庵」を構える。
七五年二月、クモ膜下出血に見舞われ、命の危機を感じるが、自ら玄米菜食で治す。五一歳までの疲れが、ふと落ち着いた頃に出たのであろう。庭や畠作りに精を出し、今まで関心のなかった「自然」に開眼し、『遠い風近い風』『嵯峨野より』などの珠玉の随筆を発表し続ける。
出家以降の信条は「
八一年、徳島市で「寂聴塾」を開く。講師は寂聴ひとりで、文学を中心に、社会のこと、仏教のこと、旅のことなど、応募してきた六五人の老若男女の塾生に月一回、一年間語りかけた。続いて、寂聴が親しい作家や学者、芸術家を毎月招き、講演してもらう「徳島塾」を三年間開く。寂聴も同席してやりとりがあり、熱気にあふれた時間が生まれていた。筆者は二二歳のとき「寂聴塾」の塾生として寂聴と出会い、公私にわたって四〇年の親交を結んでいただいた。
八六年には連合赤軍裁判で永田洋子被告の証人として東京高裁の証言台に立つ。仏教者として死刑反対の立場もあるが、こんな事件が起きたことに、同時代を生きた者にも責任があるという考えだった。
八七年には岩手県天台寺の住職に就任する。月一回の法話に全国から一万人が集まるようになり、私財も投じて荒れた寺の復興を進めた。
翌年には敦賀女子短期大学の学長に就任。全国各地を飛び回る講演とあいまって、多忙な日々ながら、『花に問え』『手毬』『白道』で一遍、良寛、西行を描く連載を並行した。『花に問え』は谷崎潤一郎賞を、『白道』は芸術選奨文部大臣賞を受賞する。『夏の終り』からおよそ三〇年ぶりの文学賞受賞であった。
七〇歳からは、日本が世界に誇る唯一の文化遺産と言い続けてきた「源氏物語」現代語訳にとりかかり、九八年四月に全十巻刊行完結、各地で展覧会や講演が開催され、源氏ブームを巻き起こした。二〇〇〇年からは新作能・歌舞伎・狂言・オペラ・人形浄瑠璃などの台本を執筆し舞台を成功させる。〇一年には『瀬戸内寂聴全集』(第一期、全二〇巻)の刊行が始まり、両親の生まれた土地やかつて住んだ場所を訪れて半生を書いた『場所』が野間文芸賞を受賞した。故郷徳島市では〇二年に瀬戸内寂聴記念室を擁する県立文学書道館が開館し、〇四年から十年間館長も務める。〇六年に文化勲章受章。〇九年には徳島県鳴門市に寂庵の分院であるナルト・サンガを開庵し、月一回の法話に悩みをもつ人々が多く訪れた。
一方、平和を守るために身をもって社会に訴え、祈った。湾岸戦争やアフガン空爆の停戦祈願の断食、医薬品を携えてのイラク行き、原発反対のハンスト支援、車椅子での安保関連法案への反対スピーチ……。居ても立ってもいられず、命がけで自ら行動するという姿勢を貫いた。また、雲仙普賢岳火砕流、阪神大震災、東日本大震災など災害が起きる度に、義援金を携えて被災地を訪問した。
日中は講演や取材、人とかかわる仕事をし、夜中ひとりになって初めて、一番好きな書く仕事をしていたのだろう。誰にも邪魔されない、しずかな夜の時間。睡眠は削りに削って、独楽のように回り続ける生活は最晩年まで続いた。
八八歳まで病気知らずであったが、腰椎の圧迫骨折で半年間をベッドで過ごすことから始まり、胆嚢ガンや心臓のカテーテル手術も経験した。ドクターストップがかかっても、求められると出向いていった。寂庵での月一回の法話は二〇年一月が最後となった。新型コロナのため、ほぼ二年間、人との自由なコミュニケーションができなくなったことは、「人が好き」な寂聴にとって、どれほど刺激のない日常だったことだろう。
九〇歳代になっても「書くことがいのち」と、常に数本の連載を持っていた。「新潮」の連作「あこがれ」は連載中であった。最後の長編小説となった『いのち』は、盟友・河野多惠子、大庭みな子と自分の三人の生を描き、その最後は「七十年、小説一筋に生き通したわがいのちを、今更ながら、つくづくいとしいと思う。あの世から生れ変っても、私はまた小説家でありたい。それも女の。」と結ばれている。
二一年十一月九日午前六時三分。心不全のため京都市内の病院で死去。九九歳だった。
二二年五月十五日の百歳の誕生日には、こぞって盛大なお祝いをする予定だった。記念の展覧会も映画も計画されていた。二〇巻の全集の続きも一月より刊行される。数冊の著書も刊行を待っている。
「もう十分生きた」という声も聞こえてきそうであるが、もうちょっとこちらの世界にとどまっていてほしかった。「定命よ」という寂聴の声も聞こえてきそうだ。この世の無常を教えてくださった。笑顔で「切に生きる」ことも。何かに行き詰まったとき、「犀のようにただひとり歩め」の教えも。
不世出の作家、宗教者、社会活動家。小さな体に愛にあふれた底知れぬ生命エネルギーをたたえて、一世紀を駆け抜けた。自由と平和を求め、愛を書き続け、人の哀しみに寄り添った人。人間の可能性を示してくれた人。永い間、ありがとうございました。
(了)