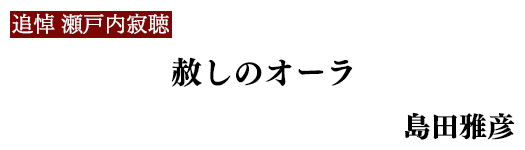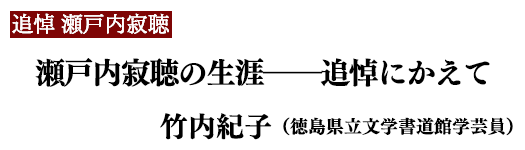瀬戸内寂聴さんに最初にお目に掛かったのは、一九九九年の年末である。ミレニアムの正月企画として、読売新聞が、瀬戸内さんと文化人類学者の青木保さん、それに私の三人の鼎談企画を組み、寂庵での初顔合わせとなった。
私は、前年に『日蝕』でデビューし、その年の初めに芥川賞を受賞していたが、その前後で、瀬戸内さんが私の『日蝕』や『一月物語』を高く評価されている、という話をちらほら耳にしていて、半信半疑ながら喜んでいた。母が瀬戸内さんの本を読んでいたので、実家には何冊かあったが、私自身が熱心に読み始めたのは、その頃からである。
初めて寂庵に伺った時には、さすがに緊張したが、瀬戸内さんは笑顔で迎えて下さった。庭でまず写真撮影をしたが、カメラマンが何カットも撮り続けていると、「もういいね、それだけ撮ったら。」と、さっと切り上げて歩き出された。私は、芥川賞受賞後の取材で、随分と写真を撮られたが、大家になるとこうなのかと、その振る舞いに目を瞠った。しかし、瀬戸内さんは必ずしも不機嫌になっていたわけでもなく、何十年も、撮られに撮られ続けてきただけに、本当にもういいはずだと判断されていたのだろう。今なら私にも、それが分かる。カメラマンも、ばつが悪そうに苦笑いしていた。
瀬戸内さんは、サッパリしていて、そういう意味では、最後まで京都人的な複雑さとは対極的だった。誰に対しても気づかいがあり、叱られた人も少なからずいるが、しかし、威張るというようなことは一切なかった。
鼎談は弾んだが、私は不思議なほど、その内容を覚えていない。ただ、その後、青木さんと一緒に初めて祇園のお茶屋に連れて行ってもらい、舞妓さん、芸子さんに囲まれて食事をしたことは、鮮明に覚えている。京都に既に五年間住んでいたとは言え、大学を出たての私は、祇園になど、それまで足を踏み入れたことがなかった。
瀬戸内さんは、お酒も食事もよく召し上がり、私もまた、よく飲み、よく食べた。とにかく、笑顔の絶えない楽しい夜だったが、谷崎潤一郎や川端康成といった嘗ての文豪だけでなく、甘粕正彦やイサム・ノグチといった人たちの名前までもが、知り合いだの、知り合いの知り合いだのといった調子で、ポンポン出てくる会話に圧倒された。
瀬戸内さんは、当時、河野多惠子さんとしょっちゅう電話をしていて、芥川賞の選考委員だった河野さんに、私については色々と尋ねていたらしい。
「受賞記者会見の時には、頼りない感じだったけど、それが、授賞式の日には、パッと見違えるほど変わったのよって、河野さんが言うのよ。」
そんな風に言われて、私は、そうだったのだろうか?とポカンとしつつ、二人の電話の会話で自分が話題になっていることの不思議さをつくづく感じた。
瀬戸内さんと河野さんとの関係は、決して単純ではなく、私はそのことにやがて気がついたが、この初対面の時には、半世紀も続く文学者同士の友情というものを、少し気が遠くなるような感じで想像した。
この最初の日の印象が良かったからか、当時京都に住んでいた私は、その後もちょくちょく瀬戸内さんから食事のお誘いを受けるようになり、こちらからもまた、お願いして寂庵にお邪魔するようになった。そのつきあいが、東京に転居し、結婚して家族ぐるみとなってからもずっと続いたが、最後の二年間は、コロナのせいでまったくお目にかかれないまま、お別れとなってしまった。何となく、虫が知らせたというわけでもないが、コロナも小康状態で、ワクチンも接種しており、十二月に京都に出張に行く予定があったので、PCR検査を受けて、何とか寂庵に伺えないものかと考えていた矢先だった。
瀬戸内さんは、私に新しい世界への扉を幾つも開いてくれた人だった。
祇園を始め、季節ごとに、京都のハイエンドのお店に随分と連れて行ってもらい、能や歌舞伎をご一緒したり、嵐山で鵜飼い見物の船に乗ったりと、自分一人ではまず経験出来なかったことをたくさん教えてくださった。徳島の阿波踊りに、横尾忠則さんデザインのドクロの浴衣で参加し、寂聴連に加わって一緒に踊ったこともある。
作家の思い出話は、殊に根掘り葉掘り質問して、後に『奇縁まんだら』シリーズで描かれるエピソードの数々を、直接、詳しく聞かせてもらった。そのために、私が本で読んで知っていただけの近代文学史には、生き生きと血が通うようになった。
瀬戸内さんも私も、漱石より鴎外が好きで、谷崎や三島に強い関心があり、最近書かれた色んな本の話をしても、基本的に趣味があった。
横尾忠則さんや美輪明宏さんなど、後に知遇を得た人たちも、本当なら畏れ入りつつ自己紹介から始めねばならなかったが、事前に瀬戸内さんがたっぷり私の話をしていたので、言わば最高の紹介状と共に受け容れられたのだった。
瀬戸内さんとの交流が深まっていったのが、丁度、全集の刊行が始まった時期だったので、私は、新しい巻が出る度に読んで、手紙でその感想を書き送った。
このことは、私の小説家としての成長にとっても良かったと思う。私は、高校時代までは典型的な田舎の文学少年で、読むのは専ら岩波文庫のような既に古典となった文学作品ばかりだったため、読書歴が男性作家にかなり偏っていた。その弱点を自分でも自覚し、大学に入ってからは、意識的に女性作家の本を読むようにしていたが、その関心の延長上で読んだ『田村俊子』に始まる中期の「青鞜」周辺の女性作家を描いた評伝は、それ故に、非常に刺激的に受け止められた。瀬戸内さんの多岐に亘る功績の中でも、この時期の作品は、やはり文学史的に格別の重みがあると思う。
また、宇野千代や円地文子といった「女流作家」たちとの交流の逸話は、やはり男性中心に偏しがちだった私の日本の近代文学史の理解を矯める教育的な意義があった。
瀬戸内さんの訃報の後、台湾の小説家の胡晴舫さんは、私のFBに追悼コメントを寄せてくれたが、彼女によると、瀬戸内作品は繁体字でも翻訳され、多くの読者を獲得しているという。そして、瀬戸内さんは、台湾の読者にとっては、女性の生き方を示した一つのロールモデルなのだという言葉にハッとさせられた。
瀬戸内さんの人生については、日本でも多くの人が知るところだが、その女性としての、或いは女性作家としての生き様が、小説を通じて、心情的な共感以上に「ロールモデル」として受け止められてきたかというと、微妙なところだろう。
寂庵に法話を聴きに来る人たちは、瀬戸内さんがご自身の経験に基づいて助言される言葉の一つ一つに大いに慰められ、励まされたと思うが、今日のフェミニズム文学の隆盛の中で、瀬戸内作品及び、瀬戸内さんと文壇との関わりが、適切な文脈の中で十分に議論されているかといえば、心許ない。しかしこれは、フェミニズムのみならず、一般的な文学史、文壇史そのものの問題である。
また、「青鞜」周辺の女性たちへの関心も、近年、また高まっているが、批評的に克服するにせよ、瀬戸内さんの仕事が十分に踏まえられているかどうかも気懸かりである。
出世作『女子大生・曲愛玲』は、第二次大戦中の内地と北京とのギャップなど、歴史的にも興味深いが、クイア小説の先駆けとしても今こそ注目すべきだろう。
女性の性に焦点化し、その自由と欲望とが、社会との間に生じさせる摩擦を描くスタイルは、『花芯』で一層洗練され、傑作と呼ぶに相応しい作品となっている。本作が被った酷評と、その後五年間、瀬戸内さんが文壇から「干されて」しまったという事件は、著しく差別的であり、ご本人が面白おかしくその怒りを回想されたために、つい笑って聞いてしまうが、日本の文壇の男性中心主義の典型的なスキャンダルとして、厳しく批判されるべき一件である。この作品の評価を巡っては、瀬戸内さんの生前に、何らかの名誉回復の機会を設けるべきだったと思う。
女性の性という主題は、『夏の終り』に於いては、愛そのものの不如意という問いへと昇華され、しかも私小説として自ら引き受けるという形で、見事に作品化されている。瀬戸内文学は、なるほど、数々の「恋愛」を描いているが、後の出家を予告するように、一貫して描かれているのは、寧ろ、近代以前から日本人のよく知っていた「愛欲」という言葉の方が似つかわしいようにも見える。
そこから、『田村俊子』以降の評伝へと進むに及んで、瀬戸内さんは、社会道徳と自由及び欲望との軋轢という主題を、制度的な次元で捉え直し、政治と文学という明確な問いの形式に発展的に整理している。その頂点が、『美は乱調にあり』であり、また『諧調は偽りなり』であろう。ここに文学者としての瀬戸内さんが、積極的な政治参加を行っていった思想的な立脚点が形成されたと言える。
他方、この自由と欲望の不如意という主題は、政治による社会化とは別の方向で、宗教による救済の可能性を通じ、新たに問い直される。自らの出家を経て書かれた『比叡』は、その代表作であり、ここに至って、個と社会変革、個と魂の救済という瀬戸内文学全体の骨格が完成し、更に『源氏物語』の現代語訳によって、それに歴史的なパースペクティヴが備わったというのが、晩年の仕事である。私たちは、瀬戸内さんのケータイ小説などの取り組みを、単なる新しもの好き、と見るのではなく、この枠組みを踏まえた上で評価する必要がある。
斯くの如く、一見、「書きたい」という衝動のままに、次々に作品を発表していったように見える瀬戸内さんの創作史は――事実、そうであったろうが――、論理的すぎるほどに整然とした歩みのようにも見える。それは、行き当たりばったりに物珍しい主題に飛びついていた、というのではなく、常に自身の実存に根差した問いに対する答えを求め続けていた結果であり、その意味では、政治と宗教という二つの大きな他者と直面することは、言わば必然であっただろう。
私は、ご本人の生前には、謹んで口に出さなかったが、瀬戸内さんの文学者としての功績は、過小評価されていると思う。理由は色々とあろうが、やはり、その社会的な存在感が大きすぎ、また、眩しすぎた故ではないか。
瀬戸内さんは、現実的な人で、今の作家は、死んだらもう読まれなくなる、と常々仰っていた。追悼文で、こんなことを幾ら書いても、「あなた、そんなこと今頃言っても、もう遅いわよ!」と呆れられそうだが、それでも、今は改めて、遺された著作とこそ静かに向き合うべき時だと思う。これを機に、瀬戸内文学が再発見され、再評価が進むことを切望している。
非常に多くのものを与えられ、しかも、貰いっぱなしのままの別離となってしまった。小説家としてデビューし、今日まで続いていた一つの幸福が、終わってしまった寂しさを感じている。