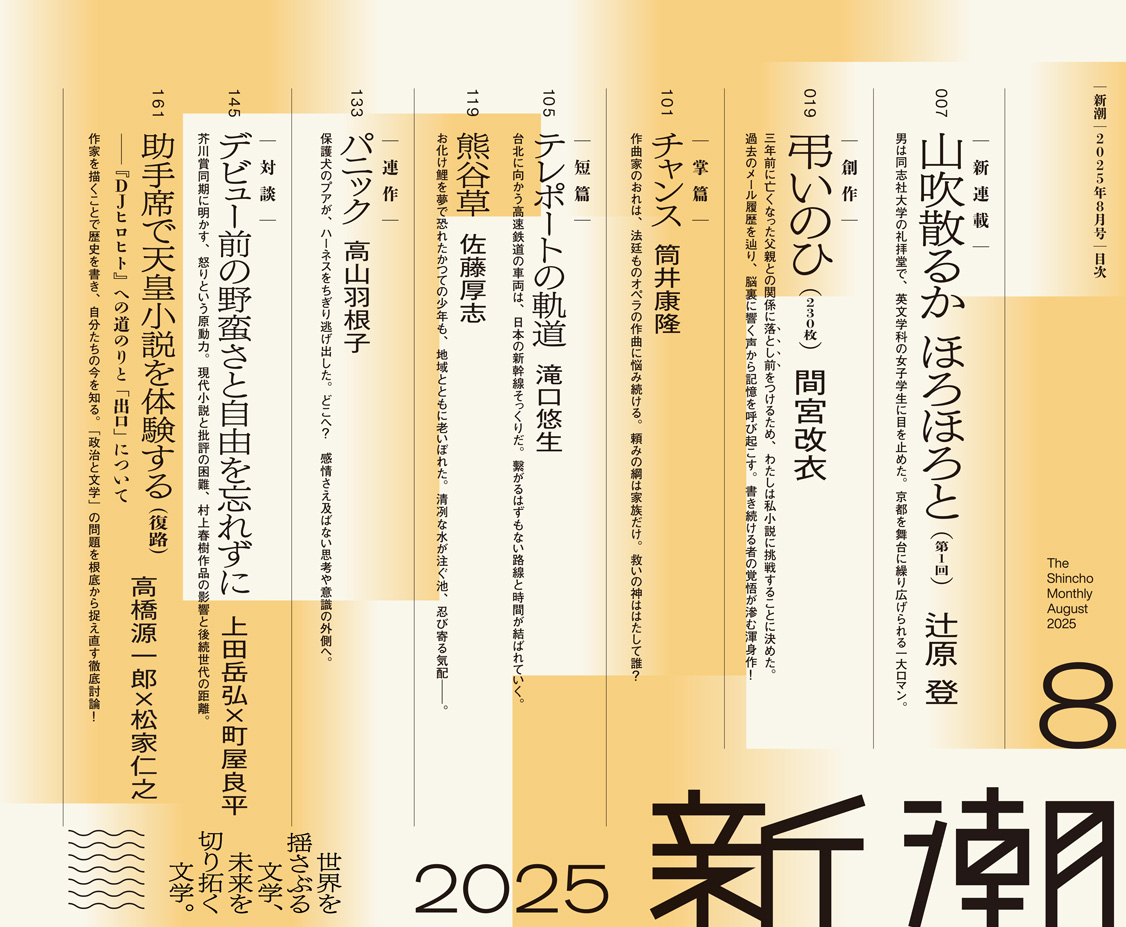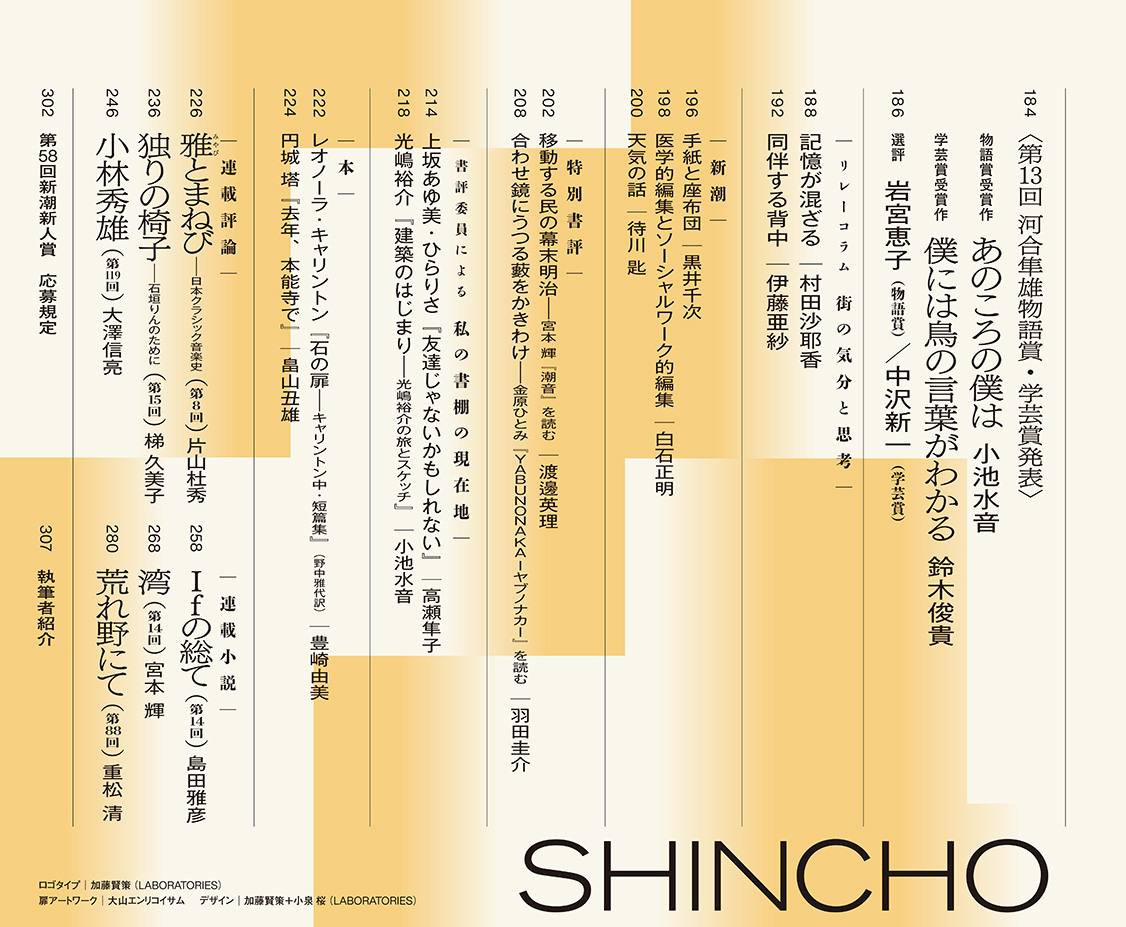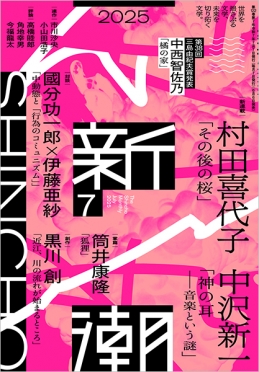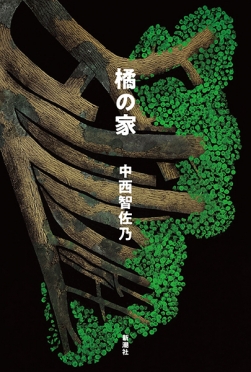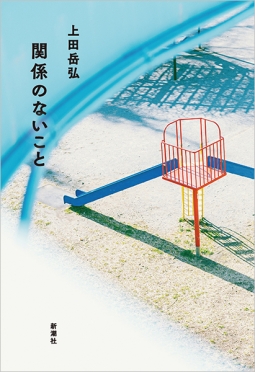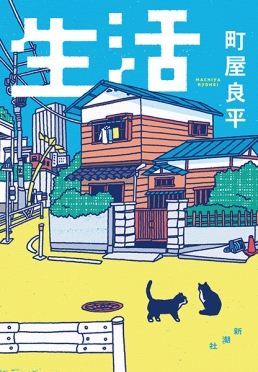【新連載】辻原 登「山吹散るか ほろほろと」
【創作】間宮改衣「弔いのひ」
新潮 2025年8月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2025/07/07 |
|---|---|
| JANコード | 4910049010853 |
| 定価 | 1,200円(税込) |
【新連載】
◆山吹散るか ほろほろと(第1回)/辻原 登
男は同志社大学の礼拝堂で、英文学科の女子学生に目を止めた。京都を舞台に繰り広げられる一大ロマン。
【創作】
◆弔いのひ(230枚)/間宮改衣
三年前に亡くなった父親との関係に落とし前をつけるため、わたしは私小説に挑戦することに決めた。過去のメール履歴を辿り、脳裏に響く声から記憶を呼び起こす。書き続ける者の覚悟が滲む渾身作!
【掌篇】
◆チャンス/筒井康隆
作曲家のおれは、法廷ものオペラの作曲に悩み続ける。頼みの綱は家族だけ。救いの神ははたして誰?
【短篇】
◆テレポートの軌道/滝口悠生
台北に向かう高速鉄道の車両は、日本の新幹線そっくりだ。繋がるはずもない路線と時間が結ばれていく。
◆熊谷草/佐藤厚志
お化け鯉を夢で恐れたかつての少年も、地域とともに老いぼれた。清冽な水が注ぐ池、忍び寄る気配――。
【連作】
◆パニック/高山羽根子
保護犬のプアが、ハーネスをちぎり逃げ出した。どこへ? 感情さえ及ばない思考や意識の外側へ。
【対談】
◆デビュー前の野蛮さと自由を忘れずに/上田岳弘×町屋良平
芥川賞同期に明かす、怒りという原動力。現代小説と批評の困難、村上春樹作品の影響と後続世代の距離。
◆助手席で天皇小説を体験する(復路)――『DJヒロヒト』への道のりと「出口」について/高橋源一郎×松家仁之
作家を描くことで歴史を書き、自分たちの今を知る。「政治と文学」の問題を根底から捉え直す徹底討論!
〈第13回 河合隼雄物語賞・学芸賞発表〉
【物語賞受賞作】あのころの僕は/小池水音
【学芸賞受賞作】僕には鳥の言葉がわかる/鈴木俊貴
【選評】岩宮恵子(物語賞)/中沢新一(学芸賞)
【リレーコラム 街の気分と思考】
◆記憶が混ざる/村田沙耶香
◆同伴する背中/伊藤亜紗
【新潮】
◆手紙と座布団/黒井千次
◆医学的編集とソーシャルワーク的編集/白石正明
◆天気の話/待川 匙
【特別書評】
◆移動する民の幕末明治――宮本 輝『潮音』を読む/渡邊英理
◆合わせ鏡にうつる藪をかきわけ――金原ひとみ『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』を読む/羽田圭介
【書評委員による 私の書棚の現在地】
◆上坂あゆ美・ひらりさ『友達じゃないかもしれない』/高瀬隼子
◆光嶋裕介『建築のはじまり――光嶋裕介の旅とスケッチ』/小池水音
【本】
◆レオノーラ・キャリントン『石の扉――キャリントン中・短綱集』(野中雅代 訳)/豊崎由美
◆円城 塔『去年、本能寺で』/畠山丑雄
【連載評論】
◆雅とまねび――日本クラシック音楽史(第8回)/片山杜秀
◆独りの椅子――石垣りんのために(第15回)/梯 久美子
◆小林秀雄(第119回)/大澤信亮
【連載小説】
◆Ifの総て(第14回)/島田雅彦
◆湾(第14回)/宮本 輝
◆荒れ野にて(第88回)/重松 清
第58回新潮新人賞 応募規定
執筆者紹介
この号の誌面
編集長から
辻原登「山吹散るか ほろほろと」
間宮改衣「弔いのひ」
◎辻原登氏の新連載「山吹散るか ほろほろと」の舞台は京都。室谷亮は同志社大学神学部の二回生として聖書の教えを真面目に学びながらも、礼拝堂で居合わせた女子学生の石原翠に一目惚れをし、半ばストーカーめいた片思いを募らせていく。亮の心のうちで起きる「はれやかな愛」と「暗い情欲」(アウグスティヌス)の相克。それを乗り越えるのが信仰の道だとすれば、葛藤を引き受けるところから文学が始まる◎昨年「ここはすべての夜明けまえ」で鮮烈なデビューを果たした間宮改衣氏による中篇第二作「弔いのひ」を発表する。コロナ禍の二〇二一年、作家は離れて暮らしていた父親を亡くした。あえて私小説と宣言して起筆される本作が見つめるのは、晩年まで没交渉であった父や家族との関係、そして書く行為それ自体の誠実さと残酷さだ。「私小説は過去に落とし前をつけること」という編集者から聞いた定義に適うものになっているかどうか。その成否をぜひ読んで確かめていただきたい。
編集長・杉山達哉
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?

文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
































 公式X
公式X