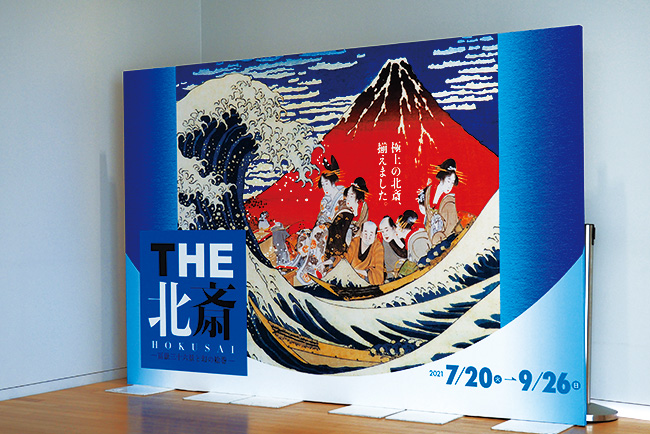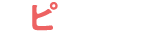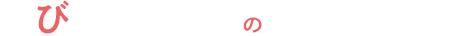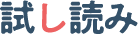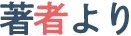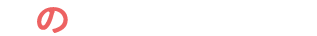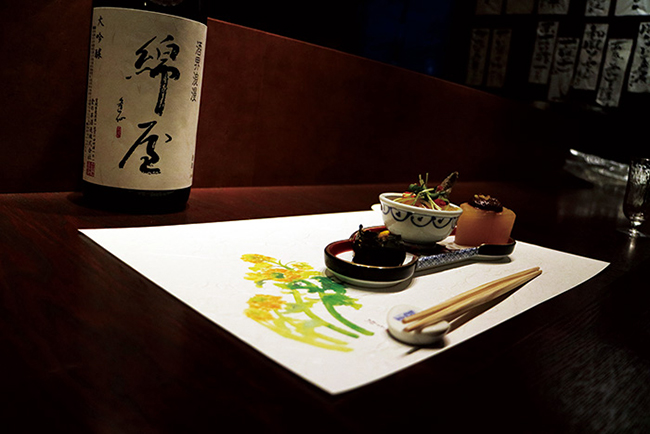「16歳の旅へ」
――この作品は、日本国内の、とりわけ北の地方を歩いて書いたエッセイ集ですが、沢木さんの「はじめての旅」をなぞるようなところがあるのが印象的です。16歳、高校1年生の春休み、国鉄の東北均一周遊券と3000円ほどのお金を持って出かけた旅でした。
沢木 当時ちょっとしたアルバイトをしていて少しお金が貯まっていたんです。それを使って、ザックに毛布を詰めて上野駅から奥羽本線に乗り込みました。でも、長い年月のあいだに、どこをどう歩いたのか、記憶が曖昧になっていたんです。いつかその旅を「再構築」してみたいという気持ちはずっと持っていたんですが、折よくJR東日本の「トランヴェール」という車内誌が、旅のエッセイを書いてくれないかと声をかけてくれました。
はじめての旅から50年以上がたった今、新たに北の土地を歩いてエッセイを書くことで、はじめての旅を再構築できるかもしれないと思いました。16歳のときの旅が蘇るかもしれない。あるいは全然蘇らないということがわかるかもしれない。はじめての旅の記憶がひとつの層としてあり、そこに新しい旅をして生まれる層を重ねて書いたら面白いんじゃないかと思ったんですね。
◆司馬遼太郎の旅
――旅を重層的に書くということですか?
沢木 司馬遼太郎さんが『街道をゆく』という一連の作品を書いていますよね。司馬さんの旅というのは、出版社が何もかもお膳立てして、記者や編集者、挿絵画家、その土地に詳しい人なんかがマイクロバスに乗って大勢同行するというものです。それじゃあ旅というよりは「大名行列」じゃないかなんて、ちょっと冷ややかに見ていた(笑)。だけどある機会があって、青森を歩いて書かれた『北のまほろば』を読み返してみて、印象が変わったんです。そんな単純な話ではないぞと思って。
この作品の一番の表層は、もちろんその大勢の同行者たちと土地を歩いて取材していくというものですが、そのすぐ下に司馬さんが産経新聞の記者だった頃に取材をしたり、会った人々の記憶の層が加わる。青森出身の棟方志功と一度だけ会った時の印象なんかが語られるわけです。さらに作家として生きてきた時間の中で交わった、作家や文化人とのかかわりから生まれてきた記憶の層がある。たとえば直木賞の選考委員だった今日出海やその長兄の今東光。2人も青森に縁の深い人で、素敵なお母さんの話が出てくる。そして司馬さんが小説を書くために取材をし、勉強もした、戦国時代から幕末、明治に至る歴史の層がある。最後に「仮説の証明」という層も加わってくる。縄文時代に青森を中心とする北の国に豊かさや美しさがあったという司馬さんの仮説がいろいろな形で明らかになっていく。あるいは自分自身で深く納得していく……。
『北のまほろば』という作品はこうした5つの層が豊かさを生んでいるんです。それに比べると、僕のこのエッセイ集は、たったの2層にしか過ぎません(笑)。まあ、僕が大学を卒業して、フリーランスのライターとして取材をし、人と出会い、触れ合ったり、付き合ったりしたという層が加わって、かろうじて3層ぐらいになっているかもしれませんが。
――就職した会社を1日で辞めて、フリーランスのライターになり、しかし先が見えないという時期のことも書かれています。永六輔さんや小澤征爾さんに取材したときのエピソードも印象深いですね。沢木さんにもこういう時代があったんだな、と。
沢木 でも、重層性ということでは司馬さんの足元にも及ばない。だから司馬さんには、心の中で密かに「生意気なことを思っていて、申し訳ありませんでした」と謝りました(笑)。
◆「旅の性善説」
――16歳のとき、はじめての旅の行き先に東北を選んだのはどうしてだったんですか?
沢木 それはごく単純な話で、東北には長い夜行列車の路線があったから。それに乗ることで宿泊代を浮かせることができるわけです。少年の僕には、1人でどこまで長く旅を続けられるかが大事でしたからね。
その旅の前年、つまり中学3年生の時、船に乗って大島まで行って、三原山に登ったんです。途中で親切なお兄さんに出会って、「このテントに一緒に泊まってもいいよ」と言われたんだけど、急に不安になってしまいましてね。どこかで罪を犯した逃亡者じゃないかと下らない妄想をしてしまって、三原山から下りたあと、まっすぐ波止場に戻って船に乗りこんで帰ってきちゃったということがあったんです。「あら、1週間は帰ってこないんじゃなかったの?」なんて、姉たちにからかわれました。よし、今度はちゃんと行くぞと思ったんでしょうね。いま思うと、よく親が出してくれたなと思うけど。
――宿を予約しているでもなく。
沢木 そう、まったく。車中泊と駅のベンチが大半で宿には2泊だけでした。なのに、帰ってきても「ああ、お帰り」というぐらいだった。でもそれが僕にとってはよかったんだろうと思います。あらゆることを任せてくれたということが……。いま思い出すと、僕は特別に早熟な子どもではなかったと思います。平凡な、ごく普通の高校生だった。ただ、1人で何でも決めて、1人で何でもやるということが、ほかの人よりほんの少しだけ早かったかもしれない。1人で何かをするという経験は、その後の僕にとって決定的に重要だったような気がします。
――旅ではいやな思いはしなかったんですか。
沢木 それが全然なかったんです。上野から奥羽本線に乗って、まず最初に秋田県の寒風山に行きました。そのときの僕の旅の基本的な方針は、かっこいい名前のところに行くという、ただそれだけだったもんだから(笑)。寒風山って、かっこいいじゃないですか。それで山から下りて道を歩いていると、トラックが止まって、「あんちゃん、乗んな」って言って乗せてくれた。運転席の前にリンゴが置いてあって、運転手さんが「そのリンゴ、1個持っていきな」と言ってくれました。
今はみんな、旅をするときにミネラルウォーターをザックに入れて歩くでしょう。昔はミネラルウォーターって高かったので、その代わりに僕はいつでもリンゴを1個用意していました。水分補給できるし、何かあったときにはお腹の足しにもなる。今でも旅していると、ホテルの朝食のビュッフェで必ずリンゴを1個失敬して、ザックに入れておきますが、あの旅のあの経験が原点だったんだなあと思います。寒風山のトラックの運転手さんにリンゴをもらう。あるいは北上の駅でベンチで寝ていたら、ホームレス風のおじさんが滑り落ちた毛布を掛け直してくれる。
僕は「旅における性善説」の信奉者ですが、その12日間の旅は、そういう親切に満ち満ちていたんです。まさに、旅の神様の「恩寵」に満ちていた。そもそも、最初の、上野からの奥羽本線でも、向かいに座った人にヤクザみたいなおじさんがいて、東京の裁判所から召喚状が来たから行ってきたんだとか意気がっていたんだけれど、僕が何も食べ物を持ってきてないということを知ると、バッグからあんパンを取り出して、「食べな」と言ってくれたりしてね。
◆長く旅を続ける方法
――そもそも(笑)、少し楽観的でないと、旅って楽しめないのかもしれませんね。
沢木 どちらかと言えば僕は楽天的な人間だと思う。文章を書く人間には向いてないのかもしれないんだけど(笑)。僕だってもちろん過去を回想して文章を書いたりします。けれど、行動においては、過去のことに拘泥するということはあまりないんですね。たとえ、うまくいかないことが起きたとしても、それを面白がるということが、とりわけ旅を続ける上では大事だと思います。家族の者には「一晩眠ると、みんな忘れちゃうだけでしょ」なんて言われるけど(笑)。実は、そうなんです(笑)。旅をしていく中で、それが強化されていったということはあるかもしれません。過ぎたことに拘泥すると前に進めなくなりますからね。
旅を続けていくにはフットワークを軽くしたい。だから可能なかぎり荷物を少なくする。それと同じように、生活もできるだけ簡素にしておくと、動きやすくなる。生活を大きくしなければ、無理にお金を稼がなくても済むし、借金もせず、贅沢もせず、軽やかに生きていくことができる。旅も人生も、きっと同じなんでしょうね。
――いつでも旅に出ることができるというのは素敵なことですよね。
沢木 僕はできるだけ予定を入れないで済む人生を歩みたいと思ってこれまで生きてきました。締め切りなんていうものをなるべく抱えないでね(笑)。もちろんたまには雑誌の連載を引き受けたりもするわけだけど、そんなものはその気になれば、全部書いて、編集者に渡しておくことだって可能なわけで、さほど行動を制約されるものでもない。手帳に先の予定が埋まっていないと心配だという人がいるけど、僕はどれだけ手帳を空白にしていられるかということに、人生を懸けてきたようなところがあります。
――長い空白があるとホッとする。
沢木 そう。今年なんか、本当の意味での約束なんて、2つぐらいしかないんじゃないかなぁ。それを除けば手帳は真っ白という感じですね。そういう人生を生きたいと思ってきました。そして、ほぼ、そういう人生を送ることができてきたと思います。
◆好きなものが1つあれば人生はOK
――若い人たちが旅に出ない、内向的になっていることを嘆く向きがありますが……。
沢木 よくそういうことについて意見を述べよと求められるんだけど、基本的には何も言わないで来ました。これからもたぶん言わないでしょう。誰かに何か偉そうなことを言われるの、やっぱりいやだなと僕は思うから。でも、単純に何かに興味を持てば人は動き出すというところがありますよね。人生にとって一番大事なことって、好きなものを1つ持つということだと思うんですよね。
――そうですね。
沢木 どんなことでもいいから、好きなことを1つ持っていればいい。それは何でもよくて、趣味であったり、あるいは好きな人であったり、ペットだったり、とにかく好きだというものが1つでもあれば、人生は一生、楽しく生きていけると思う。それはきっと巡り巡って、例えば外国に出かけるといったことに結びつく契機になるかもしれない。とにかく好きなものを1つ持てば、人生はそれでOKだと僕は思っています。
――内向的になって、外に向く目が弱くなるということは、好きになる気持ちが弱くなることなのかもしれません。
沢木 外に向かう感情、他者に向かう感情の架け橋がなくなっていくのはあまりよくないことですよね。好きになるということは、関心を持つということで、関心を持つということは、ほとんどもう好きであるということと同じことのはずですから。何かに関心を持ち、何かを好きになるという感情が痩せてしまうと、ちょっと困ったことになるとは思います。
(初出「波」2020年5月号)