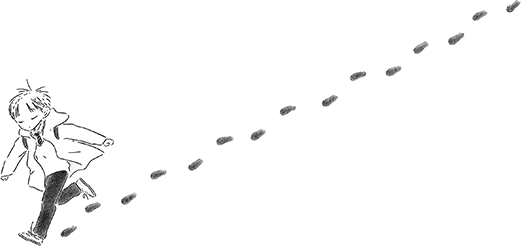書評
多様な社会での「親子物語」
池上彰
先日行きつけの書店の店頭に『タンタンタンゴはパパふたり』を見つけました。おお、ブレイディみかこさんが『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の中で紹介していた絵本ではないか。
これはニューヨークのセントラルパーク動物園で恋に落ちた二羽のオスのペンギンの話です。実話なんだそうです。
この絵本はイギリスの保育業界では「バイブル」のような扱いになっているとか。そうか、さすがイギリス。LGBTの人への差別意識を持たせないように、こういう絵本を読み聞かせているのか……と思っていたら、そうではないのですね。
〈子どもたちには、誰と誰が恋に落ちるのは多数派だが、誰と誰が恋に落ちるのは少数派、みたいな感覚はまったくない。「誰と誰」ではなく、「恋に落ちる」の部分が重要なのだ〉(『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』)
なるほどねえ。誰が誰と恋に落ちたっていいじゃないか。子どもたちは、それを本能的に悟っているのかしらん。
英国社会を取り上げたノンフィクション作品はいろいろありますが、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、格差社会に生きる子どもたちと、彼らをとりまく大人たちの生活ぶりを同じ視線の高さで描いているところが、ほかとは圧倒的に異なります。「上から目線」ではないのです。それは、著者の息子さんが「元底辺中学校」と作者が称する学校に入学したことによって、もたらされたものでしょう。
恵まれた上品な家庭の子弟が通う名門のカトリックの小学校を出たのに、そのままカトリックの中学校に進学せず、「元底辺中学校」に入学するとは。日本によくいる教育ママが聞いたら卒倒するような選択を、この親子はヒョイとしてしまったのです。さあ、ここからドラマの始まりです。
子どもたちが直面する「事件」のひとつひとつは、ぜひ本で読んでいただくとして、ここではその背景を説明しておきましょう。
イギリス社会は、私が子どもの頃は「ゆりかごから墓場まで」というスローガンに象徴されるように社会保障の充実した国でした。日本にとってお手本のような国として習いました。
その一方で、「福祉が行き届いていると、人々は働く意欲を失う」とも言われ、経済が停滞し、「英国病」と呼ばれました。
ここに大ナタを振るったのが、保守党の「鉄の女」サッチャー首相でした。新自由主義の立場から「小さな政府」を目指し、社会福祉を削減しました。その結果、経済は活性化しましたが、格差が拡大しました。
その後、労働党が政権を奪還しましたが、労働党のブレア首相も新自由主義と大差ない政策を取ったために格差は縮小しませんでした。では、いまはどうか。ブレイディみかこさんは、別の書籍で、次のように語っています。
〈英国では、保守党が緊縮財政をはじめた二〇一〇年から、実は平均寿命の伸びが横ばいになっています。一応、世界で一番リッチな国の一つだし、医療技術は進歩するわけですから、それまでは右肩上がりで伸びていたのに、二〇一〇年から恐ろしいことにパタッと止まっている。医療支出削減で国立病院も人員とインフラが不足して緊急救命室の待ち時間が史上最長になっているし、一日に一二〇人程度の患者を廊下で手当てしているという病院もある〉(『そろそろ左派は〈経済〉を語ろう』)
こんなイギリス社会で、貧しい家庭の子の様子を見ていられずに手を差し伸べる先生たち。先生の給料も上がっていないのに。人々の助け合いによって、かろうじて維持できている社会の実際が、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』では赤裸々に、活き活きと描かれます。
社会の底辺にも差別意識が何重にも積み重なっている。この本を読むと、そんな深刻な現状を知って気分が落ち込むのですが、著者の中学生の息子との会話によって、救われる。これが、この本の大きな魅力でしょう。
中学生の息子はどんどん大きくなる。格差と差別を目の当たりにしながらも精神的に成長する。その傍らには、息子の成長を喜び、息子と共に悩み、考え、成長する母親の姿がある。
そんな親子の成長記録を読むことで、読者の私たちもまた成長する。
そしてブレイディみかこさんは、イギリス社会の現実を日本の私たちに報告しながら警告を発しているのです。「これは、近未来の日本の姿かも知れないよ」と。
(いけがみ・あきら ジャーナリスト)